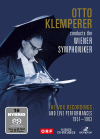| 品番 |
内容 |
演奏者 |
24-1121(5Bluray)
日本限定盤
数量限定盤
|
ベートーヴェン:交響曲全集
)
■BD1
交響曲第1番ハ長調Op.21
交響曲第3番変ホ長調Op.55「英雄」
■BD2
交響曲第4番変ロ長調Op.60
交響曲第5番ハ短調Op.67「運命」
■BD3
交響曲第2番ニ長調Op.36
交響曲第6番ヘ長調Op.68「田園」
■BD4
交響曲第8番ヘ長調Op.93
交響曲第7番イ長調Op.92
■BD5
交響曲第9番ニ短調Op.125「合唱つき」
◎ボーナス・オーディオ
オットー・クレンペラーについて/ガレス・モリスによる回想録(インタビューアー:ジョン・トランスキー) |
オットー・クレンペラー(指)
ニュー・フィルハーモニアO
■BD1
収録:1970年5月26日
放映(BBC TV):1970年6月19日(第1番)、6月21日(第2番)
■BD2
収録:1970年6月2日
放映(BBC TV):1970年6月26日
■BD3
収録:1970年6月9日
放映(BBC TV):1970年6月19日(第2番)、6月28日(第6番)
■BD4
収録:1970年6月21日
放映(BBC TV):1970年7月3日
■BD5
テレサ・ツィリス=ガラ(S)、ジャネット・ベイカー(Ms)、ジョージ・シャーリー(T) テオ・アダム(Br)、ニュー・フィルハーモニアcho
収録:1970年6月30日
放映(BBC TV):1970年7月5日
全て、ロンドン、ロイヤル・フェスティヴァル・ホール
音声:PCM Mono
画面:4:3 、リージョン:0
50GB
ドイツ語(第9のみ)、404'44 mins |
2019年にリリースされた、クレンペラー生涯最後のベートーヴェン・チクルス、1970年ベートーヴェン生誕200年記念演奏会のBlu-rayBOXが、この度シンプルな装丁で再登場します!!(普及版のため解説書は付属しません。なおオリジナルBOX(KKC-9476)は、現在在庫分で終了となります。)
以前クラシカ・ジャパンで放映され、神々しいばかりの『田園』などマニアのあいだで話題となっていたクレンペラー最後のベートーヴェン・サイクル。
新たにリマスターされて画質・音質共に大幅にアップ。演奏の様子をクリアな映像で見ることができるため、楽員たちの献身的というほかない真剣な様子がそれだけでも感動的。1970年のテレビ放映プログラムなので音声はモノラルですが、情報量も十分に多くたいへん聴きやすい音になっています。
このベートーヴェン・サイクルのライヴ映像は、1967年にデッカを退職してBBCテレビ音楽部門の責任者になっていたジョン・カルショーの尽力で制作されたものです。カルショーは米キャピトル時代の1953年にクレンペラーと契約しようとして、上層部に阻まれ断念した過去がありました。
クレンペラーは1966年8月に腰部を骨折して大きな手術を受け、療養のため約6か月間という予定外の空き時間を過ごすことになります。
その長い空き時間に、死や宗教の問題について思いを巡らせ、1967年1月には、47年間のカトリック信仰を終えてユダヤ教に改宗。背景には、イスラエル在住の妹マリアンネの危篤状態に、前年の姉レギーナの死、そしてなかなかうまくいかないイスラエルとの関わり方の問題などもありました。
1967年2月に現場復帰したクレンペラーは、マーラー交響曲第9番のリハーサルの際、近くにあった指揮棒を手に取って気に入り、楽員の意見も聞き入れて三十数年ぶりに指揮棒を使用することに決定。1971年9月の最後のコンサートまでの4年7か月、基本的には棒を使って指揮しています。クレンペラーの最晩年様式は、死や宗教への強い思いで始まり、指揮の方法も、楽員が見やすい指揮棒スタイルに変更。それが超低速化した演奏を崩壊寸前で食い止め、独自の世界を築き上げることに繋がったものと考えられます。 (Ki) |
|

KKC-4315(2SACD)
|
1947年ザルツブルク音楽祭ライヴ / クレンペラー&ウィーン・フィル
ラジオ・アナウンス
パーセル(1659〜1695):組曲「妖精の女王」(ハロルド・バーンズ編)
ロイ・ハリス(1898〜1979):交響曲第3番(1939)
マーラー:交響曲第4番ト長調
ラジオ・アナウンス |
オットー・クレンペラー(指)VPO
ヒルデ・ギューデン(S)
録音:1947年8月24日、ザルツブルク音楽祭、ライヴ |
当ディスクは、1973年 7月 6日に世を去ったクレンペラーの、没後
50年の記念として企画。1947年
8月24日、ザルツブルクの祝祭劇場でウィーン・フィ
ルを指揮したコンサートを収録したもので、これがクレンペラー唯一のザルツブルク音楽祭への出演。音源はオーストリア放送協会(ORF)の資料館で最近発見
され、スウェーデン放送のトランスクリプション・ディスク(放送用音源)を使用しリリースされます。これまでに、パーセルの組曲「妖精の女王」は発売されて
いましたが、その他の音源は初出となり、コンサート・プログラムすべてを聴くことができる、貴重な盤となります。
2020年に創立100周年を迎えたザルツブルク音楽祭ですが、その歴史は戦争の影が色濃く残ります。1938年オーストリアはナチス・ドイツに併合され、
反ナチやユダヤ系の音楽家たちは一掃されてしまいます。逆に戦後は、戦中に活躍した芸術家が活動停止処分を受け、戦争の爪痕も残る中、1945年8月12
日に音楽祭は開催。そして1947年からはフルトヴェングラー、ベーム、クレンペラーが活動を再開、当演奏会の記録は戦前の活況を取り戻してきたそんな中開
催されたものでした。特に演目には、クレンペラーが自らを導いてくれる人として生涯尊敬し、ナチ政権下で、禁じられていたユダヤ系の大作曲家マーラーの交
響曲第 4番をメイン・プログラムとし、パーセルの組曲「妖精の女王」、アメリカ人作曲家のロイ・ハリスの交響曲第
3番を演奏し、戦後を強く意識した内容となっ
ています。
1947年のクレンペラーは、アメリカへの亡命以降、2度目の欧州ツアーのために渡欧。8月にはこのザルツブルク音楽祭に出演しオーケストラ・コンサート
と「フィガロの結婚」を(指)その後ウィーン国立歌劇場で「ドン・ジョヴァンニ」を(指)そしてブダペスト国立歌劇場音楽監督に就任し、12月にはコンセル
トヘボウOに客演と多忙を極めていました。しかしその中でも、このザルツブルク音楽祭はこの年のハイライトであり、またその裏側にもドラマがありま
した。当時まだ知名度の低かったオーストリア人作曲家、ゴットフリート・フォン・アイネム(1918〜1996)の新作オペラ「ダントンの死」がクレンペラーの手
でザルツブルク音楽祭にて世界初演されるはずでした。しかしクレンペラーは一度は引き受けたものの、興味を失ってしまい指揮をキャンセルします。この件が
原因で以後クレンペラーはザルツブルク音楽祭への出演機会がなくなってしまいます。一方、代役とし登場したフリッチャイが指揮者として有名になる機会を得たというのも事実です。
一つの演奏会から歴史の裏側が見て取れる、非常に興味深い内容となっています。 (Ki) |
|
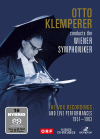
KKC-4317(16SACD)
|
クレンペラー&ウィーン響/ VOXレコーディング&ライヴ録音集1951〜1963
■Disc1
ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」
メンデルスゾーン:交響曲第4番「イタリア」
■Disc 2
ベートーヴェン:ミサ・ソレムニス
■Disc 3
ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」
■Disc 4
マーラー:交響曲第2番「復活」
■Disc 5
マーラー:交響曲第2番「復活」
■Disc 6
マーラー:大地の歌
■Disc 7
ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」
シューベルト:交響曲第4番「悲劇的」*
■Disc 8
メンデルスゾーン:交響曲第3番「スコットランド」
ショパン:ピアノ協奏曲第2番*
■Disc 9
シューマン:ピアノ協奏曲イ短調 Op.54
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番
■Disc 10、11
モーツァルト:交響曲第41番「ジュピター」
マーラー:交響曲第4番ト長調
■Disc 12、13
バッハ:管弦楽組曲第3番
ブラームス:交響曲第3番
ベートーヴェン:交響曲第7番
■Disc 14
録音:1958年2月26日(ライヴ)
ブルックナー:交響曲第7番
■Disc 15、16
ベートーヴェン:序曲「コリオラン」
交響曲第2番ニ長調 Op.36
ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 |
オットー・クレンペラー(指)ウィーンSO
■Disc1
録音:1951年3月8〜12&15日(VOX)
■Disc 2
イローナ・シュタイングルーバー(S)、エルゼ・シュールホフ(C.A)、エーリヒ・マイクート(T)、オットー・ヴィーナー(Bs)、ウィーン・アカデミーcho
録音:1951年3月8〜12&15日(VOX)
■Disc 3
録音:1951年3月8-12&15日(VOX)
■Disc 4
イローナ・シュタイングルーバー(S)、ヒルデ・レッセル=マイダン(Ms)、ウィーン・アカデミーcho、ウィーン楽友協会cho
録音:1951年5月14-16日(VOX)
■Disc 5
イローナ・シュタイングルーバー(S)、ヒルデ・レッセル=マイダン(Ms)、ウィーン・アカデミーcho ウィーン楽友協会cho
録音:1951年5月18日(ライヴ)
■Disc 6
エルザ・カヴェルティ(A)、アントン・デルモタ(T)
録音:1951年5月20-23日(VOX)
■Disc 7
録音:1951年5月20-23日(VOX)
プロ・ムジカO*
録音:1950年11月19-20日、パリ*
■Disc 8
ヘルベルト・ハフナー(指,第1楽章のみクレンペラーの指揮)
録音:1951年5月20-23日(VOX)
ギオマール・ノヴァエス(P)*
録音:1951年6月9-11日(VOX)*
■Disc 9
ギオマール・ノヴァエス(P)
録音:1951年6月9-11日(VOX)
■Disc 10、11
テレサ・シュティッヒ=ランダル(S)、録音:1955年6月21日(ライヴ)
※全コンサートCD初収録
■Disc 12、13
録音:1956年3月8日(ライヴ)
※全コンサートCD初収録
■Disc 14
録音:1958年2月26日(ライヴ)
■Disc 15、16
1963年6月16日(ライヴ)
※全コンサートCD初収録 |
アメリカに亡命したユダヤ系ハンガリー人であるジョージ・デ・メンデルスゾーン=バルトルディ(大作曲家メンデルスゾーンの子孫だと称していた)によって、
1945年に創設されたアメリカのレーベル、ヴォックス・レコード(VOX)。クレンペラーをはじめ、ホーレンシュタイン、ホルショフスキ、ブレンデル、ギトリス、といっ
た一流の演奏家の録音を多く残しています。
今回リリースされるセットは、クレンペラーとウィーンSOによる1951年のVOXレコーディングと1963年までのライヴ録音を、SACD用にリマスタリングし
た16枚組SACD Hybridのボックスです。リマスタリング&修復エンジニアのボリス=アレクサンダー・ボールズ氏は、「これらの芸術的な価値がきわめて高い歴史
的なスタジオ録音とコンサート録音を復刻するにあたって、私たちの主要な意図は、音楽の情報をできるだけ欠陥のない無傷な状態に保ち、劣化する要因を取り除
いて最大限に自然な音を提供することにあった。」と語っており、現在の基準に沿った実りあるリスニング体験が得られるよう、細心の注意が払われています。
最初にクレンペラーがVOXに録音したのは、1946年パリでプロ・ムジカOとのバッハの「ブランデンブルク協奏曲」、その後に1950年にはモーツァル
ト交響曲第25&36番を録音。そしてメンデルスゾーンが新たにクレンペラーに提案したのがウィーンSOとの録音シリーズです。1951年のVOXへの録音
は、クレンペラーの指揮者としてのキャリアのなかでもきわめて重要な年だったと捉えられています。クレンペラーは、戦後ヨーロッパに戻って行った演奏活動におけ
る第1期(1946〜51年)で、戦前の名声を再確立することができました。この時期は、アムステルダム・コンセルトヘボウOとの高水準な演奏の数々(伝説
的アムステルダム・コンサート1947-1961/KKC4258)と並ぶ魅力的な記録となっています。特にここに収録されているベートーヴェンの「ミサ・ソレムニス」
は、レコード化されたクレンペラーのその他の演奏と比べても類をみない演奏となっています。特に晩年クレンペラーは、楽曲の構造をより深く展開し、次第にテンポ
を遅くするようになります。1946〜51年頃のクレンペラーは戦前のスタイルを引き継いでおり、時として速めのテンポをとるなど、推進力のある演奏を展開してお
り、そういう意味でも1951年はクレンペラーの演奏の分水界でありました。特に7月に行われたオランダ音楽祭でのマーラーの「復活」はその頂点を極めている
といっても良いでしょう。
1951年のVOXレコーディングは3回に分かれて行われました。そして周知の通り3回目の録音の後、クレンペラーはVOXと決別することになります。クレンペ
ラーは6月9〜11日にかけて、メンデルスゾーンの「スコットランド」(すべて録り終えることはできなかった)、とピアニストのギオマール・ノヴァエスとのピアノ協
奏曲の録音を行い、6月14日からウィーンSOとともにギリシア・ツアーに出ています。その後クレンペラーの予定ではウィーンには戻らず、ロンドンへ行き、
南北アメリカ・ツアーを終えたのち、1952年はじめにウィーンに戻り、残りを録音するつもりでいました。しかし、1951年9月には、クレンペラーが録音したレコー
ドが発売されており、まだ録音してないはずの「スコットランド」はクレンペラー指揮として全曲リリースされていたのです。(未録音の楽章は、ヘルベルト・ハフナー
によって録音されていた)それを知ったクレンペラーはVOXと関係を断つことにします。
しかし、その間にクレンペラーにはさらなる災難が降りかかっていました。南米でのコンサートが成功を収め、ニューヨーク経由でモントリオールに戻ったクレンペラー
は、階段を踏み外し転倒、大腿骨骨折という大怪我を負います。予定されていた北米ツアーは中止、さらには長期にわたり国外に滞在したこと共産圏ハンガリーでの
滞在歴などが重なりパスポートが没収され、1954年1月までヨーロッパに渡ることが出来なくなりました。うつ状態の2年間を過ごすことになったクレンペラーで
すが、好機も到来します。レコード・プロデューサー、ウォルター・レッグの仲介によりEMIとの新しい契約が締結、後のレコード史に刻まれた名演の数々を生み出
すことになります。
また同時収録されているウィーンSOとのライヴ録音も注目。ウィーンSOとクレンペラーのはじめての共演は1920年12月18日のベートーヴェン音
楽祭でのコンサートでした。そして1958年10月1日未明の寝煙草による火災で負った大火傷など度々の災難を経て、1963年6月16日アン・デア・ウィーン
劇場でウィーンSOとのコンサートが行われました。偶然かそうでないかは定かではありませんが、クレンペラーが初めてウィーンSOと共演したコンサート
と同じく、両者最後の共演となったコンサートもまたオール・ベートーヴェン・プログラムとなりました。1920年の演目は、交響曲第2番、レオノーレ序曲、交響曲第
5番でしたが、1963年はコリオラン序曲、交響曲第2番、第3番という順で演奏されました。この演奏会を聴きに来ていたオーストリアの作家フランツ・タッシエが
このように書き残しています。「ウィーンSOは素晴らしかった。偉大な夜に、偉大な指揮者としか演奏しないかのように振る舞うやり方を、彼らが知っていた」 (Ki) |
|