| 湧々堂HOME | 新譜速報 | 交響曲 | 管弦楽曲 | 協奏曲 | 器楽曲 | 室内楽 | 声楽曲 | 歌劇 | バロック | 廉価盤 | シリーズ |
| 旧譜カタログ | チャイ5 | 殿堂入り | 交響曲 | 管弦楽 | 協奏曲 | 器楽曲 | 室内楽 | 声楽曲 | 歌劇 | バロック | |
| 協奏曲・新譜速報1 |
| ※発売済のアイテムも含めて、約3ヶ月間掲載しています。 ※新しい情報ほど上の段に記載しています。 ※表示価格は全て税込みです。 |
|
| EUROARTS 20-47344(Bluray) |
プレトニョフ/ラフマニノフのピアノ協奏曲全曲演奏 ピアノ協奏曲第2番ハ短調 Op.18 ピアノ協奏曲第3番ニ短調 Op.30 ピアノ協奏曲第1番嬰ヘ短調 Op.1 ピアノ協奏曲第4番ト短調 Op.40 パガニーニの主題による狂詩曲 Op.43 ラフマニノフ:ピアノ協奏曲全集、パガニーニの主題による狂詩曲 |
ミハイル・プレトニョフ(P) 使用楽器:Shigeru Kawai Grand Piano, SK-EX(調律師:山本有宗) ケント・ナガノ(指) ラフマニノフ国際O 録音:2023年10月、ロゼ・コンサート・ホール、ロール、スイス(ライヴ) 画面:1080i,Full HD,16:9 音声:PCMステレオ リージョンALL 164分 |
|
||
 Treasures TRE-326(1CDR) |
A.フィッシャー/モーツァルト&シューマン モーツァルト:ピアノ協奏曲第22番変ホ長調 K. 482* シューマン:ピアノ協奏曲イ短調Op.54# メンデルスゾーン:ロンド・カプリッチョーソ ホ長調 Op.14## |
アニー・フィッシャー(P) オットー・クレンペラー(指)* アムステルダム・コンセルトヘボウO* ヨゼフ・カイルベルト(指)# ケルンRSO# 録音:1956年7月12日コンセルトヘボウ*、1958年4月28日 ケルン放送 第1ホール#、1966年モスクワ## (全てモノラル・ライヴ) ※音源:Melodiya M10-44183#,##、Discocorp RR-527* ◎収録時間:70:15 |
| “造形美を確保しつつ確信を持って邁進し続けるA.フィッシャーのピアニズム!” | ||
|
||
| Forgotten Records fr-2308(1CDR) |
モーツァルト:協奏交響曲K.364 ハイドン:協奏交響曲Hob. I/105 |
ズザンネ・ラウテンバッハー(Vn) ウルリヒ・コッホ(Va) ペータ・シュヴァルツ(Vc) ヴィンフリート・リーベルマン(Ob) ハンス・ベール(Fg) イシュトヴァン・ケルテス(指)バンベルクSO 録音:1962年(ステレオ) ※音源:Opera ST1933 |
| Forgotten Records fr-2306(1CDR) |
ムソルグスキー:展覧会の絵* ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番 |
ジーナ・バッカウアー(P) ジョージ・セル(指)クリーヴランドO 録音:1957年*、1960年3月13日セヴェランスホール・ライヴ ※音源:His Master's Voice DLP1154* |
| Forgotten Records fr-2296(1CDR) |
ウェーバー:「オベロン」序曲 ブラームス:ヴァイオリン協奏曲* |
アイザック・スターン(Vn)* ポール・パレー(指)デトロイトSO 録音:1961年11月24日放送録音、1961年2月9日放送録音* |
| Forgotten Records fr-2285(1CDR) |
パガニーニ(クライスラー編):ヴァイオリン協奏曲第1番~第1楽章 メンデルスゾーン:「真夏の夜の夢」*~序曲/夜想曲/スケルツォ/結婚行進曲 |
イヴリー・ギトリス(Vn) クルト・ヴェス(指) ハイン・アーサー・ブラウン(指)* ニーダーエースターライヒ・トーンキュンストラーO 録音:1950年9月26-28日、1951年9月10-12日* ※音源:Remington RLP-149-20, Remington R-199-67 |
| Forgotten Records fr-2282(1CDR) |
リスト:ピアノ協奏曲第1番* マスネ:ピアノ協奏曲変ホ長調 ブロッホ:ピアノとオーケストラのための「協奏バレエ」 |
ソンドラ・ビアンカ(P) ジャン・マルティノン(指)ラムルーO* ハンス=ユルゲン・ワルター(指)ハンブルク室内O ※音源:Plymouth P12-38, MGM E3178 ※音源:Plymouth P12-38, MGM E3178 |
| Forgotten Records fr-2281(1CDR) |
モーツァルト:協奏交響曲 K.Anh.9 モーツァルト:交響第41番「ジュピター」 |
ブルノ・デールシュミット(Ob) オットカール・ドラパル(Cl) エルンスト・ミュールバッハー(Hrn) H・レルヒ(Fg) クルト・ヴェス(指) ニーダーエースターライヒ・トーンキュンストラーO 録音:1950年 ※音源:Remington R-199-54, Remington R-149-16 |
| Forgotten Records fr-2278(1CDR) |
ミルシテイン/チャイコフスキー&ドヴォルザーク チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲* |
ナタン・ミルシテイン(Vn) シャルル・ミュンシュ(指)ボストンSO アンタル・ドラティ(指)ミネアポリスSO* 録音:1953年、1951年* ※音源:RCA LM-1760 |
| Forgotten Records fr-2277(1CDR) |
ラロ:スペイン交響曲 ヴィエニャフスキ:ヴァイオリン協奏曲第2番 ポルムベスク (1853-1883):バラード(望郷のバラード) |
イオン・ヴォイク(Vn) イォシフ・コンタ(指) 録音:1956年 ※音源:Electrecord ECD73, Electrecord ECD83 |
| Forgotten Records fr-2275(1CDR) |
ブルメンタール/タヴァレス他 ヘケル・タヴァレス(1896-1969):ピアノと管弦楽のための 「ブラジルの様式による協奏曲」 第2番Op.105 ヴィラ=ロボス:ピアノ協奏曲第5番* パデレフスキ:幻想的ポロネーズ |
フェリシア・ブルメンタール(P) アナトール・フィストラーリ(指)LSO エイトール・ヴィラ=ロボス(指)ウィーンSO* 録音:1954年、1955年5月25日ウィーン・ムジークフェライン・ライヴ* ※音源:Decca LXT2975, Columbia FCX438 |
| Forgotten Records fr-2086(1CDR) |
アンセルメ&ジェルトレル バッハ:管弦楽組曲第2番 ヒンデミット:ヴァイオリン協奏曲 リャードフ:8つのロシア民謡 チャイコフスキー:「眠れる森の美女」組曲 |
アンドレ・ジェルトレル(Vn) エルネスト・アンセルメ(指) スイス・ロマンドO 録音:1959年5月13日ヴィクトリア・ホール・ライヴ |
| Forgotten Records fr-2083(1CDR) |
バッハ:ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 BWV.1041 バルトーク:ヴァイオリン協奏曲第2番* |
ヘンリク・シェリング(Vn) ジャン・マルティノン(指)フランス放送PO ヴィレム・ファン・オッテルロー(指)オランダ放送PO* 録音:1962年6月4日パリ、1962年6月25日アムステルダム(共に放送用ライヴ) |
| Forgotten Records fr-2080(1CDR) |
ヴューラー/ベートーヴェン:ピアノ協奏曲集 第2番変ロ長調 Op.19 第3番ハ短調 Op.37 |
/フリードリヒ・ヴューラー(P) ヴァルター・ダヴィソン(指)シュトゥットガルト・プロ・ムジカo 録音:1955年 ※音源:Vox PL9570 |
| Forgotten Records fr-2079(1CDR) |
ホルヴァート&オジム ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲* ヤコヴ・ゴトヴァツ:交響的コロ Op.12** コレダOp.11# |
イゴール・オジム(Vn)* ミラン・ホルヴァー(指)ザグレブPO*,** エミール・コッセット(指)男声合唱&器楽合奏# 録音:1961年*、1958年**,# ※音源:Fontana700154WGY, Jugoton LPY-33 |
| Goodies 78CDR-3957(1CDR) |
ハチャトゥリアン:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 | ダヴィッド・オイストラフ (Vn) アレクサンドル・ガウク(指) ロシア国立SO 米 MERCURY DM10(14000/14004) 1942年11月モスクワ録音 |
|
||
| Goodies 78CDR-3959(1CDR) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第14番変ホ長調 KV.449 | キャスリーン・ロング(P) ボイド・ニール(指) ボイド・ニールO 英 DECCA K.784/6 1935年7月19日ロンドン録音 |
|
||
 PARNASSUS PACD-96095(1CD) |
マイケル・レビン 未公開録音: ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61 ポール・クレストン:ヴァイオリン協奏曲第2番Op.78* |
マイケル・レビン(Vn)、 ナショナル・オーケストラル・アソシエーション、 ジョン・バーネット(指)、 アトランタSO*、 ヘンリー・ソプキン(指)* 録音:1960年頃/1961年1月27日* |
|
||
| SKARBO DSK-1245(1CD) |
モーツァルト:オーボエ協奏曲 ニ長調 K.314(原曲:ハ長調) フルートと管弦楽のためのアンダンテ K.315 フルート協奏曲第1番ト長調 K.313 ヴァイオリンと管弦楽のためのロンドK.373 ※すべてピッコロ版で演奏 |
ジャン=ルイ・ボーマディエ(ピッコロ) ウィーン・クラシカル・プレイヤーズ ヴァハン・マルディロシアン(指) 録音:2024年4月11~13日/ペンツィング、ウィーン(オーストリア) |
|
||
 Gramola GRAM-99286(9CD) |
ハンスイェルク・アンゲラーの芸術 - モーツァルトから現代作品まで 【CD1】 モーツァルト:ホルン協奏曲集 1-3. ホルン協奏曲第4番変ホ長調 K.495 4-5. ホルン協奏曲第1番ニ長調 K.412 6-8. ホルン協奏曲第3番変ホ長調 K.447 9-11. ホルン協奏曲第2番変ホ長調 K.417 K.495第1楽章&K.447第1楽章のカデンツァ…パウル・アンゲラー 【CD2】 ナチュラル・ホルンとオーケストラのための狩りの協奏曲集 1. オンジェイ・アントン(1754-1817):シュヴァルツェンベルクの狩りのためのファンファーレ Bei Ankunft der Herrschaft 2-4. ジョヴァンニ・プント(1746-1803):ホルンとオーケストラのための協奏曲 第5番ヘ長調* 5. 不詳:Aria Sancti Huberti 6-7. アントン:シュヴァルツェンベルクの狩りのためのファンファーレ 8-10. プント:ホルンとオーケストラのための協奏曲 ホ長調* *…カデンツァ:ハワード・アーマン 録音:1994年 【CD3】 ナチュラル・ホルンとフォルテピアノ 1-3. ベートーヴェン:ホルン・ソナタ ヘ長調 Op.17 4-6. ダンツィ(1763-1826):ホルン・ソナタ 変ホ長調 Op. 28 7-9. フェルディナント・リース(1784-1838):ホルン・ソナタ ヘ長調 Op.34 【CD4】 ホルンとピアノ 1-2. シューマン:アダージョとアレグロ Op.70 3. R・シュトラウス:序奏、主題と変奏TrV70 4. デュカス:ヴィラネル 5-8. ヴェルナー・ピルヒナー(1940-2001):Feld -, Wald - und Wiesen-Soli PWV53 9. ウジェーヌ・ボザ(1905-1991):森にて Op.40 10. ロッシーニ:前奏曲、主題と変奏 【CD5】 ホルンの哀歌 1. フランツ・シュトラウス(1822-1905):夜想曲 Op.7 2. R・シュトラウス:アンダンテ ハ長調 TrV 155 3. ボザ:森にて Op.40 4. オスカー・フランツ(1843-1886):無言歌 Op.2 5. シューベルト:流れにて D943 6. プーランク:エレジーFP168 【CD6】 クラシカル・ホルン 1-3. モーツァルト:五重奏曲 K.452 4-15. モーツァルト:2本のナチュラル・ホルンのための12の二重奏曲 K.487(K.496a) 16-18. テレマン:協奏曲 ヘ長調 TWV42/F14- リコーダー、バロック・ホルンと通奏低音のために 19-27. パウル・アンゲラー(1927-2017):17世紀の舞曲より「組曲」- リコーダー、バロック・ホルン、バロック・ファゴットとチェンバロのために 【CD7】 生まれついてのホルン吹き 1. ワーグナー:ジークフリートの角笛 2-7. ピルヒナー:ホルン四重奏曲「生まれついてのホルン吹き」 8-12. ピルヒナー:ホルンとトロンボーンのための二重奏曲 13. ヘルマン・バウマン(1934-):無伴奏ナチュラル・ホルンのための「哀歌」 14. リヒャルト・デュンサー(1959-):The Host of the Air - 無伴奏ホルンのために 15. パウル・アンゲラー:無伴奏狩猟ホルンのための「カプリッチョ」 16-22. パウル・アンゲラー:2本の狩猟ホルンのためのカノンによる「狩りの組曲」 23-27. パウル・アンゲラー:5つの狩りの歌 -4つの狩猟ホルンのために 28. パウル・アンゲラー:夜警の呼び声 -4つの狩猟ホルンのために 29. パウル・アンゲラー:葬送音楽 -4つの狩猟ホルンのために 30. ハンスイェルク・アンゲラー(1955-):DI Dieter Schramm Jagdfanfare 31. ハンスイェルク・アンゲラー:Klaus Stocker Jagdfanfare 32. ハンスイェルク・アンゲラー:Dr. Wolfgang Porsche Jagdfanfare 【CD8】 ホルン・コン・ブリオ&ロマンス 1. ベルンハルト・クロル(1920-2013):讃美 - 無伴奏ホルンのために 2-7. クロル:ホルン・ソナタ Op.1 8-10. クロル:3つの小品 Op.72 11. クロル:バーゼルのロマンス Op.114-4つのナチュラル・ホルンのために 12-14. パウル・ヴァルター・フュルスト(1926-2013):狩人の死 - アルメンラウシュ Op.80-4つの狩猟ホルンと4つのナチュラル・ホルンのための 15-17. フリッツ・ケル(1927-2018):4つのホルンのための小さなカッサシオン 18. ケル:ホルンとピアノのための「バルバラへのバラード」 19-22. ケル:ホルン・ソナタ 【CD9】 ザルツブルク・ウインド・フィルハーモニック 1-6. モーツァルト:歌劇「フィガロの結婚」 K.492による13の楽器のためのハルモニームジーク(アルフレード・ベルナルディーニ編) 7. ワーグナー:楽劇「神々の黄昏」 - ジークフリートの葬送行進曲* 8. エルンスト・ルートヴィヒ・ライトナー(1943-):交響曲第4番- 第4楽章「別れ」 …世界初演 9. ウェーバー:「魔弾の射手」 序曲* 10. フチーク(1872-1916):ワルツ「冬の嵐」 Op.184* 11. ホルスト:『惑星』 Op.32- 木星* 12. J・シュトラウス:ワルツ「美しく青きドナウ」 Op.314* *…アルベルト・シュヴァルツマンによる吹奏楽版 |
【CD1】 ハンスイェルク・アンゲラー(ナチュラルHrn) ザルツブルク・ホーフムジーク(古楽器使用) ヴォルフガング・ブルンナー(指) 録音:2006年4月10-12日 【CD2】 ハンスイェルク・アンゲラー(ナチュラルHrn) アンサンブル・ソ=ソ=ラ=ソハワード・アーマン(指) 録音:1994年 【CD3】 ハンスイェルク・アンゲラー(ナチュラルHrn) ノルベルト・リッカボナ(ハンマークラヴィーア) 録音:1991年 【CD4】 ハンスイェルク・アンゲラー(Hrn) ボジダル・ノエフ(P) 録音:1989年 【CD5】 ハンスイェルク・アンゲラー(Hrn) トーマス・ラルヒャー(P)…1-2 ボジダル・ノエフ(P)…3-4 ハンス・ゾーイエル(T)…5 ノルベルト・リッカボナ(ハンマークラヴィーア)…5 フローリアン・ポドゴレアヌ(P)…6 録音:オーストリア 1985年 ORF Innsbruck…3-4 1990年 ORF Innsbruck…1-2 1989年 Tiroler Landesmuseum -Ferdinandeum“, Innsbruck…5 2015年 Solitar der Universitat Mozarteum Salzburg…6 【CD6】 ハンスイェルク・アンゲラー(Hrn/ナチュラルHrn、バロックHrn) パヴェル・ギリロフ(P)…1-3 ホアン・カルロス・リヴァス・ペレッタ(Ob)…1-3 ダリオ・ジンガレス(Cl)…1-3 ミリアム・コフラー(Fg)…1-3 ダヴィッド・フリリ(ナチュラルHrn2)…4-7、12-15 スザンナ・ゲルトナー(ナチュラルHrn2)…8-11 イェレミアス・シュヴァルツァー(リコーダー)…16-27 エリザベート・カウフホールト(バロック・ファゴット)…19-27 ラルフ・ヴァルトナー(Cemb)…19-27 録音: 2017年 Solitar der Universitat Mozarteum Salzburg… 4-7、12-15 2018年 Solitar der Universitat Mozarteum Salzburg… 1-3、8-11 2002年 BR, Nurnberg…16-27 【CD7】 ハンスイェルク・アンゲラー(Hrn/ナチュラルHrn/狩猟Hrn…16-22) マルティン・ブラムベック(Hrn)…2-7 マルクス・プフェルシャー(Hrn)…2-7 クリストフ・ヴァルダー(Hrn)…2-7 リト・フォンタナ(Tb)…8-12 【狩猟ホルン】 クリストフ・ガップ…16-22、23-32 クラウス・デング…23-32 クリストフ・ヴァルダー…23-29 ガブリエル・クプジナー…30-32 アルベルト・シュヴァルツマン…30-32 エドゥアルド・ジュリアーニ…30-32 エリック・コシャク…30-32 トーマス・メヒトリンガー…23-32 トビアス・ツァンガール…30-32 ハンスイェルク・アンゲラー(指) 録音:1979年 Stadtsaal Innsbruck…1 2012年 Stadtsaal Innsbruck…15-32 1990年Konzertsaal ORF Tirol…14 1991年 Konzertsaal ORF Tirol…13 1999年 Konzertsaal ORF Tirol…2-12 【CD8】 ハンスイェルク・アンゲラー(Hrn/ナチュラルHrn) ボジダル・ノエフ(P) マルコ・トライアー(ナチュラルHrn…11)(狩猟Hrn…12-14) クリストフ・ガップ(ナチュラルHrn…11)(ホルン…15-17) クリストフ・ヴァルダー(ナチュラルHrn)…11 マルティン・ブラムベック(ナチュラルHrn)…12-14 マルクス・プフェルシャー(ナチュラルHrn)…12-14 クリストフ・ヴァルダー(ナチュラルHrn)…12-14 ヘルヴィヒ・モルシュアー(狩猟Hrn)…12-14 カリン・コラート(狩猟Hrn)…12-14 トーマス・メヒトリンガー(狩猟Hrn)…12-14 ミヒャエル・ペスコルデルング(Hrn)…15-17 ハンス・モーザー(Hrn)…15-17 録音:Stadtsaal Innsbruck 1994年…12-14 1999年…1-11 2003…15-22 【CD9】 ザルツブルク・ウインド・フィルハーモニック ダニエル・ヨハンセン(T) ハンスイェルク・アンゲラー(指) 録音:2016年 Grosser Saal der Stiftung Mozarteum Salzburg…1-6 2014年 Grosser Saal der Stiftung Mozarteum Salzburg…7 2009年 Saal Tirol des Congress Innsbruck…8 2018年Groses Festspielhaus Salzburg…9 2019年 Felsenreitschule Salzburg,2019…10、12 2023年 Groses Festspielhaus Salzburg…11 |
|
||
| Biddulph BIDD-85054(1CD) |
エルガー:ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 Op.61 ヴァイオリン・ソナタ ホ短調 Op.82# ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 Op.61(抜粋)* |
アルバート・サモンズ(Vn) ニュー・クイーンズホールO サー・ヘンリー・ウッド(指)管弦楽団* ウィリアム・マードック(P)# 録音/初出:1929年3月18日/Columbia L2346/50(Matrices WAX4785/94) 1935年2月2日/Columbia68392/94(Matrices CAX7421/26)# 1916年3月14日/ Columbia L107* |
|
||
| Hanssler HC-24047(1CD) |
マスネとラヴェルのピアノ協奏曲 (1)マスネ:ピアノ協奏曲 変ホ長調(1903) (2)ラヴェル:ピアノ協奏曲 ト長調(1929-31) |
エロイーズ・ベラ・コーン(P) ベルリンRSO、 クリストフ・コンツ(指) 録音:(1)2022年12月13~15日、(2)2023年4月4&5日/ハウス・デス・ルンドフンクス、RBB(ベルリン) 使用楽器:Yamaha CFX (2022) |
|
||
| Forgotten Records fr-1965(1CDR) |
ジャノリ&ホルヴァート/メンデルスゾーン メンデルスゾーン:ピアノ協奏曲第1番ト短調 Op.25 ピアノ協奏曲第2番ニ短調 Op.40 |
レーヌ・ジャノリ(P) ミラン・ホルヴァート(指) ウィーン国立歌劇場O 録音:1952年10月21日-26日 ※音源: Westminster XWN18043/ |
| Forgotten Records fr-1953(1CDR) |
ヘルマ・エルスナー他/Vox 録音のバッハ 2台のチェンバロの為の協奏曲第1番ハ短調 BWV.1060* ヴァイオリンとオーボエの為の協奏曲 ニ短調 BWV.1060# 2台のチェンバロの為の協奏曲第2番ハ長調 BWV.1061* 半音階的幻想曲とフーガ ニ短調 BWV.903+ /イタリア協奏曲 BWV.971+ |
ヘルマ・エルスナー(Cemb) ヴィル・べー(Vn)# フリードリヒ・ミルデ(Ob;#) ロルフ・ラインハルト(Cemb;*,指) シュトゥットガルト・プロ・ムジカO 録音:1955年3月、モノラル(+以外) /1958年1月、ステレオ+ ※音源:Vox, PL9580(+以外), STPL-510.770+ |
| Chandos CHSA-5339(1SACD) |
共鳴 - ヴァインベルク、シェーンベルガー:トランペット協奏曲
他 ヴァインベルク(1919-1996):トランペット協奏曲 Op.94(1966-67)* クリストフ・シェーンベルガー(1961-):トランペット協奏曲Op.94 (2016/2021-22)* ラフマニノフ:ヴォカリーズ 嬰ハ短調Op.34No.14(1915)** アレクサンドル・ゲディケ(1877-1957):演奏会用練習曲 ト短調 Op.49* (リー・レイノルズによる管弦楽伴奏版) |
マティルダ・ロイド(Tp) *…B♭管トランペット **…D管トランペット LSO 岩淵麻弥(リーダー) リー・レイノルズ(指) SACD層:Stereo, Multi-Channel5.0 録音:2023年11月17-19日ロンドン、ヘンリーウッド・ホール |
|
||
| IBS CLASSICAL IBS-132024(1CD) |
ミニマリスト~ピアノと管弦楽のための作品集 グラス(1937-):エチュード第4番 シモン・ネーリング(1995-):ブリッジ ヘンリク・ミコワイ・グレツキ:ピアノと弦楽オーケストラのための協奏曲 Op.40 シメオン・テン・ホルト(1923-2012):カント・オスティナート ギヤ・カンチェリ(1935-2019):ワルツ・ボストン -ピアノと弦楽のために ペルト(1935-):アリヌーシュカの癒しに基づく変奏曲 アンナ・マリアのために ヴォイチェフ・キラール(1932-2013):ピアノ協奏曲 |
シモン・ネーリング(P) ポーランド放送O ミハウ・クラウザ(指) 録音:2024年1月10、12日、31日、2月1日 |
|
||
| Orchid Classics ORC-100351(1CD) |
モーツァルト:フルートとハープのための協奏曲
他 1. 私はあなたに明かしたい、おお、神よ! K. 418(J=C.マルト&S.メノッツィ編) 2-4. フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299 2. I. Allegro カデンツァ…ハインツ・ホリガー 3. II. Andantino カデンツァ…ハインツ・ホリガー&ロバート・レヴィン 4. III. Rondeau カデンツァ…ハインツ・ホリガー 5. あなたは今は忠実ね K.217(J=C.マルト&S.メノッツィ編) 6-12. 「泉のほとりで」の主題による6つの変奏曲 ト短調 K360 13. アンダンテ ハ長調 K315 カデンツァ…ジュリアン・ボーディモン 14. ロンド ハ長調 K.373…原調での世界初録音 カデンツァ…ジュリアン・ボーディモン |
ジュリアン・ボーディモン(Fl) アナイス・ゴドゥマール(Hp) マッテオ・トレンティン(Ob) リヨン国立歌劇場O フィリップ・ベルノルド(指) 録音:2023年7月10-12日リヨン国立歌劇場 |
|
||
| CPO CPO-555563(2CD) |
フォルケル:4つのピアノ協奏曲 ヨハン・ニコラウス・フォルケル(1749-1818):ピアノ協奏曲 ト長調 ピアノ協奏曲 変ロ長調 ピアノ協奏曲 イ長調 ピアノ協奏曲 ハ長調 |
トビアス・コッホ(フォルテピアノ) アントン・ヴァルター製ハンマーフリューゲルによるフォルテピアノ (シュタウフェン・イム・ブライスガウ、クリストフ・カーンのピアノワーク ショップによる再現楽器、2007年製作) ケルン・アカデミー(古楽器使用) ミヒャエル・アレクサンダー・ヴィレンズ(指) 録音:2022年5月2-6日 ※全て世界初録音 |
|
||
| EVIDENCE EVCD-109(1CD) |
クリスティアン・シッテンヘルム:ピアノ協奏曲第4番「Air」 Dawn(夜明け)(交響詩) ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲 |
スヴェトラーナ・アンドレーエワ(P) ロイヤル・スコティッシュ・ナショナルO セルゲイ・ネラー(指) 録音:2023年1月5日、イギリス |
|
||
| CZECH RADIOSERVIS CR-1229(2CD) |
プラハの春音楽祭ゴールド・エディション Vol.5 ■CD1 (1)ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調Op.104 (2)ブラームス:ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 Op.102 ■CD2 (1)ハイドン:トランペット協奏曲変ホ長調 Hob. VIIe:1 (2)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番ハ短調Op.37 |
■CD1 (1)アントニオ・メネセス(Vc)、チェコPO、ズデニェク・コシュラー(指) 録音:1991年5月18日、プラハ、スメタナ・ホール(ライヴ) (2)ヨゼフ・スーク(Vn) 、インリヒ・シフ(Vc)、プラハSO、イルジー・ビエロフラーヴェク(指) 録音:1979年5月17日、プラハ、スメタナ・ホール(ライヴ) ■CD2 (1)モーリス・アンドレ(Tp) プラハSO、サー・チャールズ・マッケラス(指) 録音:1974年6月1日、プラハ、スメタナ・ホール(ライヴ) (2)ラドゥ・ルプー(P) プラハSO、ヘスス・ロペス=コボス(指) 録音:1977年5月23日プラハ、スメタナ・ホール(ライヴ) |
|
||
| LSO Live LSO-0886(1SACD) |
ミクロス・ローザ(1907-1995):ヴァイオリン協奏曲 op.24 バルトーク:ヴァイオリン協奏曲第2番* |
ロマン・シモヴィッチ(Vn) サー・サイモン・ラトル(指) ケヴィン・ジョン・エドゥセイ(指)* LSO 録音:2022年6月17日、2022年10月26日* |
|
||
| Goodies 78CDR-3957(1CDR) |
ハチャトゥリアン:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 | ダヴィッド・オイストラフ (Vn) アレクサンドル・ガウク指揮 ロシア国立SO 米 MERCURY DM10(14000/14004)1942年11月モスクワ録音 |
|
||
| SWR music SWR-19159CD(1CD) |
チェロのための作品集 カバレフスキー:チェロ協奏曲第2番 ハ短調 Op.77(1964) ショスタコーヴィチ:チェロ・ソナタ ニ短調 Op.40(1934) チャイコフスキー:ロココの主題による変奏曲* |
リオネル・マルティン(Vc) 南西ドイツRSO ギエドレ・シュレキーテ(指) デミアン・マルティン(P) カメラータ・シュヴァイツ* ハワード・グリフィス(指)* 録音:全てライヴ 2023年5月5日、6月30日、2024年7月9日 |
|
||
| Channel Classics CCS-45924(1CD) |
プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲 第1番ニ長調 Op.19 ショスタコーヴィチ:ヴァイオリン協奏曲 第1番イ短調 Op.77 |
ニン・フェン(Vn) ボーフムSO トンチエ・ツァン(指) 録音:2023年10月 アンネリーゼ・ブロスト・ムジークフォルム・ルール、ボーフム、ドイツ |
|
||
| Capriccio C-5528(1CD) |
ニコライ・カプースチン(1937-2020):変奏曲 Op.3ー ピアノ・ソロとビッグバンドのために(1961) トッカータ Op.8ー ピアノ・ソロとビッグバンドのために(1964) ピアノ協奏曲 第2番Op.14? ピアノと管弦楽のために(1972) 夜想曲 Op.16? ピアノと管弦楽のために(1972) コンサート・ラプソディ Op.25? ピアノと管弦楽のために(1976) ピアノ協奏曲 第6番Op.74- ピアノとビッグバンドのために(1993) |
フランク・デュプレー(P) ヤコブ・クルップ(ベース) マインハルト・OBI・イェンネ(ドラムセット) 南西ドイツ放送ビッグバンド 南西ドイツRSO ドミニク・ベイキルヒ(指) 録音:2023年7月12-14日、2024年2月14-16日 |
|
||
| Capriccio C-5534(1CD) |
ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104 エルガー:チェロ協奏曲 ホ短調 Op.85 |
ハリエット・クライフ(Vc) トーンキュンストラーO マルティン・ジークハルト(指) 録音:2024年5月6-11日 |
|
||
| GRAND SLAM GS-2329(2CD) 限定生産盤 ★ |
アーヨ&イ・ムジチの「四季」~ステレオ&モノラル2種セット ヴィヴァルディ: (1)協奏曲集、作品8「四季」 (2)協奏曲集、作品8「四季」 |
フェリックス・アーヨ(Vn) イ・ムジチ合奏団 録音:(1)1959年4月29日-5月6日ウィーン (2)1955年7月18日-21日アムステルダム、バッハザール 使用音源:(1) Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) (2)フィリップスPhilips(オランダ) A00301 L (LPレコード) 録音方式:(1)ステレオ(録音セッション) (2)モノラル(録音セッション) |
|
||
| Melodiya x Obsession SMELCD-1002698(2CD) 完全限定生産 |
ユリアン・シトコヴェツキー・コレクション ■CD1 1-3. シベリウス:ヴァイオリン協奏曲ニ短調 Op.47 4. パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第2番ロ短調 「ラ・カンパネッラ」 Op.7より 第3楽章 ロンド 5. パガニーニ(クライスラー編):魔女たちの踊り(フランツ・ジェスマイアーのバレエ 「ベネヴェントのくるみの木」の主題による変奏曲 Op.8) 6. パガニーニ:モーゼ幻想曲(ロッシーニの歌劇 「エジプトのモーゼ」より「汝の星をちりばめた王座に」による変奏曲 MS.23) 7-9. タルティーニ(クライスラー編):ヴァイオリン・ソナタ ト短調 「悪魔のトリル」 Bg.5 ■CD2 1-5. バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番 BWV1004 6. エルンストアイルランド民謡「夏の名残のバラ」による変奏曲(無伴奏ヴァイオリンのための練習曲第6番) 7. バッツィーニ:妖精の踊り(幻想的スケルツォ Op.25) 8. バルトーク(ゲルトレル編):ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ ニ長調 Sz.55より 第3楽章 フィナーレ 9. リピンスキ:無伴奏ヴァイオリンのためのカプリッチョ ニ長調 Op.29-3 10-11. サラサーテ:スペイン舞曲集 Op.21〔第1曲 マラゲーニャ、第2曲 ハバネラ〕 |
ユリアン・シトコヴェツキー(Vn)、ニコライ・アノーソフ(指揮/CD1:1-3)、チェコPO(CD1:1-3)、マルク・パヴェルマン(指揮/CD1:4)、モスクワRSO(CD1:4)、ベラ・ダヴィドヴィチ(P/CD1:5-6,
CD2:7,8,10,11)、ウラディーミル・ヤンポルスキー(P/CD1:7-9) 録音:1953年(CD1:1-3,6)、1955年(CD1:5)、1952年(CD1:7-9)、1954年(CD2:1-5, 9)、1951年(CD2:6)、1952年(CD2:10,11)/ADD |
|
||
| Bearton CDB-052(1SACD) |
ルトスワフスキ:チェロ協奏曲* ピアノ協奏曲** 交響曲第4番 |
ロバート・コーエン(Vc)*、エヴァ・ポブウォツカ(P)**、イェジ・マクシミウク(指)、シンフォニア・ヴァルソヴィア 録音:2013年1月、ポーランド放送ヴィトルト・ルトスワフスキ・コンサート・スタジオ(ワルシャワ) |
|
||
| Bearton CDB-049(1SACD) |
ショパン:ポーランド民謡による幻想曲イ長調 Op.13 ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 Op.21 アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 変ホ長調 Op.2 |
ヤヌシュ・オレイニチャク(P)、 マレク・モシ(指)、ティヒ市室内O 「AUKSO」 録音:2010年1月、カトヴィツェ音楽アカデミー・コンサート・ホール |
|
||
| Avie AV-2520(1CD) |
バッハのコーヒーハウス~バッハ、テレマン、ヴィヴァルディ バッハ:ブランデンブルク協奏曲第4番ト長調 BWV1049 テレマン:ドン・キホーテのブルレスク(ドン・キホーテ組曲) TWV55 バッハ:管弦楽組曲第3番ニ長調 BWV1068より エール(G線上のアリア) バッハ:オーボエとヴァイオリンのための二重協奏曲ニ長調 BWV1060 ヴィヴァルディ:ラ・フォリア(ソナタ Op.1-12からのコンチェルト・グロッソ) |
ジャネット・ソレル(ハープシコード、指揮)、 アポロズ・ファイア 録音:2023年11月(ブランデンブルク協奏曲第4番)、2002年10月(ドン・キホーテ組曲)、2021年4月(G線上のアリア)、2018年2月(オーボエとヴァイオリンのための協奏曲)、2021年4月(ラ・フォリア) |
|
||
| Chandos CHSA-5267(1SACD) |
シベリウス:ヴァイオリンと管弦楽のための作品全集 ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.47(1903-04/1905改訂) 2つのユモレ 4つのユモレスク Op.89(1917-18) 2つの小品(1914-15) 2つのセレナード Op.69(1912-13) ヴァイオリンとオーケストラのための組曲 ニ短調 Op.117JS185(1928-29) |
ジェイムズ・エーネス(Vn) ベルゲンPO メリナ・マンドッツィ(リーダー) エドワード・ガードナー(指) 録音:2023年8月14-18日 |
|
||
| TOCCATA TOCC-0728(1CD) NX-B06 |
モーセス・ペルガメント(1893-1977):作品集
第1集 1-3. ピアノ協奏曲(1951-52) 4. Sorrow 悲しみ Op.5- ピアノのために(1908-09) 5-7. 抒情的な舞曲集 - ピアノのために 8. 劇音楽『ソロモン王』:Sulamith’s Dance - ピアノのために(1915) 9. Chanson triste 悲しい歌-ヴァイオリン(オブリガートのヴィオリーノ)、チェロとピアノのために(1915) 10-11. 劇音楽『エステルの祝宴』(1936)よりI. Dance/ II. Adagio 12-14. 映画音楽『Med livet som insats』より 第1幕:The Mill (1939)(マルムグレン編)/. 第2幕:Minuet(1916)(マルムグレン編)/. 第3幕:ワルツ・レント(1939) 15. 祝祭ファンファーレ(ベルガメント編)(1961) 16. ニコルへ - ピアノのために(1974) 17. 瞑想曲 - チェロのために(1974) 18. 瞑想曲 - チェロとピアノのために(1969) 19. メロディア・ロマンティカ - チェロとピアノのために(1970) 20. ファンタジカ・ディフェレンテ「チェーロ・エ・テッラ」- チェロと弦楽九重奏のために(1969) |
ルティン・マルムグレン(P)…1-16、18、19 セバスティアン・シレン(Vn)…9 レア・トゥーリ(ヴィオリーノ・オブリガート)…9 マティアス・ホルトリング(Vc)…9 トーマス・ヌニェス(Vc)…17-20 ヘルシンキ・メトロポリタンO…1-3 サーシャ・マキラ(指)…1-3 ヘルシンキ室内O…20 アク・ソレンセン(指)…20 録音:2021年8月7-8日…1-3 2022年11月30日…17-19 Jarvenpaatalo, Jarvenpaa(フィンランド) 2022年3月20日…20 Organo, Music Centre, Helsinki(フィンランド) 2023年6月12日、11月29日、2024年3月17日…4-16 ※全て世界初録音 |
|
||
| ALPHA ALPHA-1090(1CD) |
バッハ:鍵盤楽器のための協奏曲 ニ短調 BWV1052 セルゲイ・アフノフ(1967-):スケッチ III 協奏曲「シャコンヌ」 バッハ:われ汝に呼ばわる、主イエス・キリストよ BWV639 ドブリンカ・タバコヴァ(1980-):II. Horizons 地平線 ~「The Quest 冒険」 ガブリエラ・モンテーロ(1970-)/ジョージ・モートン&クセーニャ・シドロワ編): Beyond Bach バッハを越えて |
クセーニャ・シドロワ(アコーディオン) シンフォニエッタ・リガ ノルムンズ・シュネー(指) 録音:2023年9月リガ・サウンド・レコーディング・スタジオ、ラトヴィア |
|
||
| ALPHA ALPHA-1047(1CD) ★ |
ヴィヴァルディ:『四季』と3つの協奏曲 2つのヴァイオリン、チェロ、弦楽と通奏低音のための協奏曲 ト短調RV578a(合奏協奏曲Op.3-2初期稿) ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 RV372「キアーラ夫人に」 ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 Op.8-1/RV269「春」 ヴァイオリン協奏曲 ト短調 Op.8-2/RV315「夏」 ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調 Op.8-3/RV293「秋」 ヴァイオリン協奏曲 ヘ短調 Op.8-4/RV297「冬」 ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 RV390 |
リ・インコーニティ(古楽器使用) アマンディーヌ・ベイエ(Vn独奏、指揮) アルバ・ロカ(Vn独奏2) マルコ・チェッカート(Vc独奏) 録音:2008年1月14-18日 ドイツ教会、パリ |
|
||
| ALPHA ALPHA-1087(1CD) |
モーツァルト:協奏曲集 ピアノ協奏曲 第10番変ホ長調 K.365(2台のピアノのための)*※カデンツァ…モーツァルト ヴァイオリンと管弦楽のためのロンド 変ロ長調 K.269※カデンツァ…ビラル・アルネムル、マーク・ナイクルグ ヴァイオリンと管弦楽のためのアダージョ ホ長調 K.261※カデンツァ…ビラル・アルネムル ヴァイオリンと管弦楽のためのロンド ハ長調 K.373※カデンツァ…ビラル・アルネムル、イツァーク・パールマン 協奏交響曲 変ホ長調 K.297b(オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルンのための) |
坂本彩・リサ(P/ベーゼンドルファー) ビラル・アルネムル(Vn) ガブリエル・ピドー(Ob) ブラーシュ・シュパロヴェツ(Cl) テオ・プラト(Fg) ニコラ・ラメズ(Hrn) ウィーンRSO ハワード・グリフィス(指) * トマス・ツェートマイヤー(指) 録音:オーストリア放送大ホール 2021年12月27-29日、2022年9月13-15日* |
|
||
| Linn CKD-757(1CD) |
クリスマスの季節のお楽しみ リスト:『クリスマス・ツリー』(4手ピアノ版) S.613より III. 飼葉桶のそばの羊飼たち 甘き歓びのうちに(もろびと声あげ) VII. 子守唄 IX. 夕べの鐘 ヘンデル(ツェルニー編):『メサイア』 HWV 56より ひとりのみどりごが我らのために生まれた ハレルヤ J・シュトラウス(ルノー・ド・ヴィルバク)&デュオ・プレイエル編):美しく青きドナウ Op.314 ヨハン・シュトラウス1世):ラデツキー行進曲 チャイコフスキー(エドゥアルド・ランゲル&デュオ・プレイエル編):『くるみ割り人形』 Op.71a |
デュオ・プレイエル アレクサンドラ・ネポムニャシチャヤ(第1ピアノ) リチャード・エガー(第2ピアノ) 使用楽器…クリス・マーネ製 平行弦コンサート・グランド・ピアノ 録音:2024年4月24-26日ルター派教会、ハールレム、オランダ |
|
||
| CPO CPO-555571(1CD) |
シャルヴェンカ(1850-1924):ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 Op.32 交響曲 ハ短調 Op.60 |
ジョナサン・パウエル(P) ポズナ二PO ウカシュ・ボロヴィチ(指) 録音:2022年6月4-6日、2022年9月27-30日 |
|
||
| Orchid Classics ORC-100339(1CD) |
Beethoven/5Vol.2 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 Op.15 サリー・ビーミッシュ(1956-):シティ・スタンザス(P協奏曲第3番) |
ジョナサン・ビス(P) スウェーデンRSO オメル・メイール・ヴェルバー(指) 録音:2018年12月13-15日(ライヴ) |
|
||
| SWR music SWR-19158CD(1CD) |
ヨーク・ボーエン(1884-1961):ヴィオラ協奏曲 ハ短調 Op.25(1907) ウォルトン:ヴィオラ協奏曲 イ短調(1929) |
ディヤン・メイ(Va) ザールブリュッケン・カイザースラウテルン・ドイツ放送PO ブレット・ディーン(指) 録音:2024年2月27日-3月1日 |
|
||
| Orchid Classics ORC-100325(1CD) |
モーツァルトとペルト モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第1番 変ロ長調 K.207 ロンド 変ロ長調(K.269) ヴァイオリン協奏曲第2番ニ長調 K.211 アルヴォ・ペルト(1935-):ピアノ三重奏曲「モーツァルト - アダージョ」 ※モーツァルト作品のカデンツァ…リール・ヴァギンスキー |
リール・ヴァギンスキー(Vn) ベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラ オハッド・ベン=アリ(P) ヒラ・カルニ(Vc) 録音:2023年2月27-28日、3月1日、2022年11月16日 |
|
||
| Orchid Classics ORC-100329(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番&第23番 ピアノ協奏曲 第20番ニ短調 K.466(1楽章カデンツァ:ヨハン・ネポムク・フンメル/3楽章カデンツァ:ロベール・カサドシュ) ピアノ協奏曲 第23番イ長調 K.488 |
チョ・ジェヒョク(P) ロイヤルPO ハンス・グラーフ(指) 録音:2020年8月24-26日 |
|
||
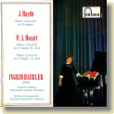 Treasures TRE-311(1CDR) |
ヘブラー~ソ連ライヴを含む3つの協奏曲 ハイドン:ピアノ協奏曲第11番ニ長調Op.21 Hob.XVIII : 11 モーツァルト:ピアノ協奏曲第12番 イ長調 K. 414 ピアノ協奏曲第17番 ト長調 K. 453* |
イングリット・ヘブラー(P) シモン・ゴールドベルク(指)オランダ室内O ベルンハルト・パウムガルトナー(指)ザルツブルク・モーツァルテウムO* 録音:1960年7月9&14-15日アムステルダム・コンセルトヘボウ、1965年モスクワ音楽院大ホール・ライヴ*(共にステレオ) ※音源:蘭PHILIPS 875-052FY、MELODIYA C90-13051-52* ◎収録時間:73:34 |
| “30代のヘブラーが織りなす気品と生命力溢れる理想のモーツァルト像!” | ||
|
||
| 299 MUSIC NIKU-9064(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
フィオリトゥーラ (1)ヴィヴァルディ:「調和の霊感」作品 3(1711) より ヴァイオリン協奏曲第9番ニ長調 ヴァイオリン協奏曲第6番イ短調 「ラ・ストラヴァガンツァ」作品4(1716) より ヴァイオリン協奏曲第4番イ短調 (2)ヴィヴァルディ:チェロ協奏曲 ニ短調 RV405(c.1720) チェロ協奏曲 ト短調 RV417(c.1720) (3)アルビノーニ:「6つのシンフォニアと 6つの五声の協奏曲」作品2(1700) より 5声のソナタ(シンフォニア)第1番ト長調op.2-1 5声のソナタ(シンフォニア)第2番 ハ長調op.2-3 |
古楽オーケストラ<ラ・ムジカ・コッラーナ
La Musica Collana> (1)丸山 韶(Vn・ソロ/Ⅰ)、佐々木梨花(Vn Ⅰ/Ⅱ)、廣海史帆/勝森菜々(Vn Ⅱ)、山本佳輝(Va)、島根朋史(Vc) 、諸岡典経(ヴィオローネ) 、石川友香理(チェンバロ/オルガン) 、西山まりえ(ハープ/チェンバロ/オルガン) (2)島根朋史(Vc・ソロ)、丸山 韶(Vn 1)、廣海史帆(Vn2)、佐々木梨花(Va)、懸田貴嗣(Vc) 、諸岡典経(ヴィオローネ)、石川友香理(チェンバロ/オルガン)、西山まりえ(Hp) (3)丸山 韶(Vn1)、廣海史帆(Vn 2) 、山本佳輝(アルト・ヴィオラ) 、佐々木梨花(テノール・ヴィオラ) 、島根朋史(Vc)、諸岡典経(ヴィオローネ)、石川友香理(Org)、西山まりえ(Hp) 録音:024年4月3-5日 五反田文化センター |
|
||
| LE PALAIS DES DEGUSTATEURS PDD-038(1CD) |
(1)グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調 Op.16 (2)ワーグナー=リスト:イゾルデの愛の死 (3)ショパン:夜想曲第8番変ニ長調 Op.27-2 (4)ドビュッシー:12の練習曲より第1集第6曲「8本の指のための」 (5)プロコフィエフ:10の小品 Op.12より第7曲「前奏曲」 (6)スクリャービン:8つの練習曲 Op.42より第3曲 嬰へ長調 (7)プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第2番ト短調 Op.16 |
ミハイル・ルディ(P) (1)(7)マリス・ヤンソンス(指)、 サンクトペテルブルクPO 録音:1990年代 |
|
||
| NIFC NIFCCD-157(1CD) |
ショパン:ピアノ協奏曲第2番(ギター版) ショパン:ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 Op.21(ギター版) モーツァルト:交響曲第5番変ロ長調 K.22 カロル・クルピンスキ/ゼバスティアン・ゴットシック(b1959):クラリネット協奏曲変ロ長調 |
マテウシュ・コヴァルスキ(G)、ロレンツォ・コッポラ(ピリオド・クラリネット、指揮)、マルティナ・パストゥシュカ(指)、{oh!}
オルキェストラ・ヒストリチナ 録音:2023年-2024年、ポーランド放送ヴィトルト・ルトスワフスキ・コンサート・スタジオ(ワルシャワ、ポーランド) |
|
||
| Nimbus Alliance NI-6446(1CDR) |
エルコック:交響曲第8番&ヴァイオリン協奏曲 スティーヴ・エルコック(b.1957):ヴァイオリン協奏曲(2006)* 交響曲第8番(1981/2021) |
ゾーイ・ベイヤーズ(Vn)*、 ケネス・ウッズ(指)イギリスSO 録音:2021年7月28日(交響曲第8番)&2022年5月26日(Vn協奏曲)、ワイアストン・コンサート・ホール |
|
||
| Lyrita SRCD-2421(2CDR) |
ジョージ・ロイド:ピアノ協奏曲全集 (1)プゴート(P協奏曲第1番) (2)ピアノ協奏曲第3番 (3)ピアノ協奏曲第2番 (4)ピアノ協奏曲第4番 |
(1)マーティン・ロスコー(P)、 BBCフィルハーモニック、ジョージ・ロイド(指) (2)キャスリン・ストット(P)、 BBCフィルハーモニック、ジョージ・ロイド(指) (3)マーティン・ロスコー(P)、 BBCフィルハーモニック、ジョージ・ロイド(指) (4)キャスリン・ストット(P)、LSO、ジョージ・ロイド(指) 録音:1984年~1990年、BBCスタジオ7(イギリス)/ヘンリー・ウッド・ホール(イギリス) |
|
||
| Lyrita SRCD-2422(2CDR) |
ジョージ・ロイド:ヴァイオリン&チェロ協奏曲集 (1)ヴァイオリンと管楽のための協奏曲 (2)ヴァイオリンと弦楽のための協奏曲 |
(1)クリスティーナ・アンゲレスク(Vn)、フィルハーモニアO、デイヴィッド・パリー(指) チェロ協奏曲 (2)アンソニー・ロス(Vc)、オールバニーSO、デイヴィッド・アラン・ミラー(指) 録音:1998年&2001年、ヘンリー・ウッド・ホール(イギリス)/トロイ貯蓄銀行音楽ホール(アメリカ)録音:1998年&2001年、ヘンリー・ウッド・ホール(イギリス)/トロイ貯蓄銀行音楽ホール(アメリカ) |
|
||
| Chandos CHAN-20323(1CD) NX-B09 |
モーツァルト:ピアノ協奏曲集 Vol.10 1. 歌劇「アポロとヒュアキントゥス」序曲 2. 歌劇「バスティアンとバスティエンヌ」序曲 3-5. ピアノ協奏曲 第1番ヘ長調 K.37(1767) 3. 第1楽章:Allegro 4. 第2楽章:Andante -Cadenza -[Tempo I] 5. 第3楽章:Rondo. [Allegro] -Cadenza -[Tempo I] カデンツァ…第2楽章:マレイ・ペライア/第3楽章:オリヴィエ・メシアン(?) 6-8. ピアノ協奏曲 第2番変ロ長調 K.39(1767) 6. 第1楽章:Allegro spiritoso -Cadenza -[Tempo I] 7. 第2楽章:Andante 8. 第3楽章:Molto allegro -Cadenza -[Tempo I] カデンツァ…ウラディーミル・アシュケナージ 9-11. ピアノ協奏曲 第3番ニ長調 K.40(1767) 9. 第1楽章:Allegro maestoso -Cadenza -[Tempo I] 10. 第2楽章:Andante 11. 第3楽章:Presto カデンツァ…モーツァルト 12-14. ピアノ協奏曲 第4番ト長調 K.41(1767) 12. 第1楽章:Allegro -Cadenza -[Tempo I] 13. 第2楽章:Andante 14. 第3楽章:Molto allegro -Cadenza -[Tempo I] カデンツァ…ウラディーミル・アシュケナージ |
ジャン=エフラム・バヴゼ(P:Yamaha CFX)…3-14 マンチェスター・カメラータ キャロライン・ペザー(リーダー) ガボール・タカーチ=ナジ(指) 録音:2023年10月7-9日 |
|
||
 Spectrum Sound CDSMBA-164(1CD) (UHQCD) 完全限定盤 |
ミルシテイン/ブラームスとチャイコフスキー (1)ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.77(カデンツァ:ミルシテイン) (2)チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35 |
ナタン・ミルシテイン(Vn) (1)フランス国立放送O、ルイ・フレモー(指) (2)フランス国立放送O、ジャン・マルティノン(指) ライヴ録音:(1)1967年6月13日(ステレオ)、(2)1969年6月4日/シャンゼリゼ劇場(ステレオ) |
|
||
| BIS BISSA-2635(1SACD) |
モーツァルト:ホルン協奏曲集 (1)ホルン協奏曲第1番ニ長調 【第1楽章:アレグロ K.412(1791)、第2楽章:アダージョK.211(1775)*、第3楽章:ロンド.アレグロ K.514(1791)#】 (2)ホルン協奏曲第2番変ホ長調 K.417(1783) (3)ホルン協奏曲第3番変ホ長調 K.447(1787) (4)ホルン協奏曲第4番変ホ長調 K.495(1786) (5)ホルン協奏曲第0番変ホ長調【第1楽章:[アレグロ]K.370b$、第2楽章:ロンドー.アレグロ K.371#】(1781) *= アレック・フランク=ゲミル&スティーヴン・ロバーツ編曲 #=スティーヴン・ロバーツ補筆完成版 $ = スティーヴン・ロバーツ復元版 |
アレック・フランク=ゲミル(Hrn) スウェーデン室内O、ニコラス・マギーガン(指) 録音:2023年5月22~26日/エレブルー・コンサートホール(スウェーデン) |
|
||
| Naive V-844[NA](1CD) |
ピアノとオーケストラのための作品集 (1)リムスキー=コルサコフ:ピアノ協奏曲嬰ハ短調Op.30 (2)プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第2番ト短調Op.16 (3)ツファスマン:ジャズ組曲 |
ズラータ・チョチエヴァ(P) カール=ハインツ・シュテフェンス(指) BBCスコティッシュSO 録音:2024年1月9-11日/グラスゴー市ホール |
|
||
| MSR MS-1844(1CD) |
ブラームス:ピアノ協奏曲第2番* フランク:交響詩「鬼神」# ウェーバー:コンチェルト・シュトゥック ヘ短調Op.79+ |
ジョシュア・ピアース(P) カーク・トレヴァー(指)ボフスラフ・マルティヌーPO*,# ビストリーク・レジュハ(指)スロヴァキア国立PO* 録音:1999年5月28-29日チェコ・BMFホール* 1999年12月10-11日、チェコ・BMFホール# 2003年9月18日スロヴァキア・ドム・ウメニア(コシツェ)+ *,#=MS1148で既発売 |
|
||
| Capriccio C-5537(2CD) ★ |
バルトーク:ピアノ協奏曲(全3曲) | ツィモン・バルト(P) ベルリン・ドイツSO クリストフ・エッシェンバッハ(指) 録音:2018年12月8日、2019年5月27-29日イエス・キリスト教会、ベルリン(ドイツ)、2019年6月2日 ベルリン・フィルハーモニー(ライヴ) |
|
||
| Biddulph BIDD-85052(1CD) |
HMVへの協奏曲録音全集 - チャイコフスキー、バッハ、ヴィヴァルディ
他 1-3. ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲 ト短調 Op.12No.1RV317 4-6. バッハ:ヴァイオリン協奏曲第2番 ホ長調 BWV1042 7-9. チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35(アウアー校訂版) 10. ベートーヴェン:ロマンス第1番 ト長調 11. ベートーヴェン:ロマンス第2番ヘ長調 |
ミッシャ・エルマン(Vn) 新SO…1-3、室内O…4-6 LSO…7-11 ローレンス・コリングウッド(指)…1-3、10-11 ジョン・バルビローリ(指)…4-9 録音:1-3.931年9月29日 初出:DB1595/96 (matrices2B1490/93) 4-6.1932年12月2日 初出:DB1871/73(matrices 2B4088/92) 7-9.1929年12月19、20日 初出:DB1405/08 (matrices BR2471/78) 10.1932年11月30日 初出:DB1846(matrices 2B4341/42) 11.1932年11月30日 初出:DB1847(matrices 2B4343/44) |
|
||
| Forgotten Records fr-1936(2CDR) |
ステンパルトのヘンデル1 12の合奏協奏曲 Op.6〔第1番-第8番〕 |
カール・リステンパルト(指) ザール室内O 録音:1953年-1955年 ※音源:Les Discophiles Français DF 89, DF 112, DF 157 |
| Forgotten Records fr-1938(1CDR) |
リステンパルトのヘンデル2 12の合奏協奏曲 Op.6,〔第9番-第12番〕 |
カール・リステンパルト(指) ザール室内O 録音:1953年-1955年 ※音源:Les Discophiles Français DF 89, DF 112, DF 157 |
|
Forgotten Records
fr-1946(1CDR) |
ハチャトゥリアン:ピアノ協奏曲* プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第1番* ラヴェル:「マ・メール・ロワ」~パゴダの女王レドロネット# エネスコ:組曲第2番ニ長調~#〔トッカータ Op.10-1/パヴァーヌ Op.10 -3/ブーレ Op.10-4〕 |
ミンドール・カッツ(P) エイドリアン・ボールト(指) LPO* 録音:1958年(ステレオ)* 、1960年(モノラル)# ※音源: Pye GSGC 14013他 |
| ALBANY TROY-1979(1CD) |
クリストファー・ラウズ(b.1949):協奏曲集 (1)ヘイムダールのトランペット (2)オーボエ協奏曲 (3)バスーン協奏曲 |
デヴィッド・アラン・ミラー(指) アルバニーSO (1)エリック・バーリン(Tp) (2)キャサリン・ニードルマン(Ob) (3)ピーター・コルケイ(Fg) 録音:(1)(3)2021年12月12日、(2)2016年10月24日、トロイ貯蓄銀行ミュージックホール |
|
||
| Albion Records ALBCD-061(1CD) |
グリンケ・レガシー~ヴォーン・ウィリアムズ:ヴァイオリン作品集
ヴォーン・ウィリアムズ:ヴァイオリン協奏曲ニ短調 揚げひばり 2つの讃美歌による前奏曲 より 第1番夕暮れ アーサー・ベンジャミン:ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ ヴォーン・ウィリアムズ:ヴァイオリン・ソナタ イ短調 |
フレデリック・グリンケ(Vn)、 ボイド・ニール(指)、 ボイド・ニールO、 アーサー・ベンジャミン(指)、 マイケル・マリナー(P) |
|
||
| Avie AV-2489(1CD) |
バッハ:ハープシコード協奏曲集 ハープシコード協奏曲 ニ短調 BWV1052 ハープシコード協奏曲 ヘ短調 BWV1056 ブランデンブルク協奏曲第5番ニ長調 BWV1050 |
ジャネット・ソレル(ハープシコード、指揮)、 アポロズ・ファイア 録音:1999年10月(BWV1050)、2002年10月(BWV1052)、2024年5月(BWV1056)、St. Paul’s Episcopal Church(クリーヴランド) |
|
||
| Channel Classics CCS-46724(1CD) NX-C04 |
シューマン:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 WoO1 ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 Op.26 |
ニーク・バール(Vn) ザールブリュッケン・カイザースラウテルン・ドイツ放送PO クリストフ・ポッペン(指) 録音:2023年5月30日-6月2日ザールラント放送ハルベルク放送局大スタジオ、ザールブリュッケン |
|
||
| Orchid Classics ORC-100335(1CD) NX-B06 |
プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第2番ト短調 Op.16 ピアノ協奏曲第3番ハ短調 Op.26 ピアノ・ソナタ第7番変ロ長調 Op.83* |
スチュワート・グッドイヤー(P) BBC響 アンドルー・リットン(指) 録音:2024年1月3-5日Maida Vale Studios、ロンドン(UK)、2024年1月7日Wyastone Concert Hall, Wyastone Leys(UK)* |
|
||
| CASCAVELLE VEL-1701(1CD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第0番変ホ長調 WoO.4【ヴィリー・ヘス
復元版(1943)】 交響曲第10番変ホ長調 【バリー・クーパー版】 |
カメラータ・ド・レマン フィリップ・ボアロン(P) |
|
||
| Hanssler HC-24035(1CD) |
20世紀ハンガリーの作品3篇 (1)ドラティ:ピアノ協奏曲(1974) (2)シェイベル:組曲「招待状」(1960) (3)シェイベル:組曲「ルネサンス舞曲」(1959) |
(1)オリヴァー・トリンドル(P) シュターツカペレ・ワイマール、 ドモンコシュ・ヘーヤ(指) 録音:2024年4月10~13日/オーケストラ練習ホール、ワイマール |
|
||
| Hanssler HC-24036(2CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲集 CD1 (1)ピアノ協奏曲第9番変ホ長調 K.271「ジュノーム」 (2)ピアノ協奏曲第13番ハ長調 K.415【ピアノと弦楽四重奏版】 CD2 (3)ピアノ協奏曲第8番ハ長調 K.246「リュッツォウ」 (4)ピアノ協奏曲第12番イ長調 K.414【ピアノと弦楽四重奏版】 |
ダナ・チョカルリエ(P) (1)(3)オープン・チェンバー・オーケストラ、ヤイール・ベナイム(指) (2)(4)ヤイール・ベナイム(Vn1)、ビン・ファム(Vn2)、テオドール・コマン(Va)、ディアナ・リゲティ(Vc) ライヴ録音:2022年9月29日&2023年3月13日/ベハーグ宮殿内ビザンティン・ホール(フランス) |
|
||
| Hanssler HC-23082(2CD) |
ブラームス:ピアノ協奏曲第1番ニ短調 Op.15 ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 Op.83 |
ミヒャエル・コルスティック(P) ベルリン・ドイツSO、 コンスタンティン・トリンクス(指) 録音:2023年9月13~18日/テルデックス・スタジオ(ベルリン) |
|
||
| Hanssler HC-24028(6CD) ★ |
ヘンデル、モーツァルト、バッハ、C.P.E.バッハ ■CD1 ヘンデル:6つの合奏協奏曲Op.3 (1)合奏協奏曲第1番変ロ長調Op.3-1HWV312 (2)合奏協奏曲第2番変ロ長調Op.3-2HWV313 (3)合奏協奏曲第3番ト長調Op.3-3HWV314 (4)合奏協奏曲第4番(b)ヘ長調Op.3-4HWV315 (5)合奏協奏曲第5番ニ短調Op.3-5HWV316 (6)合奏協奏曲第6番ニ長調Op.3-6HWV317 ■CD2 バッハ:ヴァイオリン協奏曲集 (1)ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調BWV1041 (2)ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調BWV1042 (3)ヴァイオリン協奏曲ニ短調BWV1052 (4)オーボエとヴァイオリンのための協奏曲ニ短調BWV1060(2つのヴァイオリンのための協奏曲編) ■CD3 モーツァルト: (1)セレナード第6番「セレナータ・ノットゥルナ」 (2)自動オルガンのためのアダージョとアレグロヘ短調K.594 (3)アダージョとフーガハ短調K.546 (4)セレナード第13番「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 ■CD4 バッハ:ホルン協奏曲 (1)ホルン、弦楽と通奏低音のための協奏曲変ホ長調BWV1053 (2)ホルン、弦楽と通奏低音のための協奏曲ニ短調BWV1059R(BWV974、BWV35からの再構築版) (3)ホルン、弦楽と通奏低音のための協奏曲変ロ長調BWV1055R ■CD5 「バッハ・ファミリーの交響曲集」 (1)ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハ:弦楽と通奏低音のための交響曲ニ長調BR-WFBCInc.1【世界初録音】 (2) C.P.E.バッハ:弦楽と通奏低音のための交響曲変ホ長調Wq/Hdeest【世界初録音】 (3) C.P.E.バッハ:弦楽と通奏低音のための交響曲ハ長調Wq/Hdeest【世界初録音】 (4) C.P.E.バッハ:弦楽と通奏低音のための交響曲ホ短調Wq177(1759) (5)ヨハン・クリストフ・フリードリヒ・バッハ:弦楽と通奏低音のための交響曲ニ短調 (6)ヨハン・エルンスト・バッハ:弦楽、2つのファゴットと通奏低音のための交響曲変ロ長調BR-JEBC1【世界初録音】 (7)ヨハン・ルートヴィヒ・バッハ:2つのヴァイオリン、2つのオーボエ、弦楽と通奏低音のための協奏曲ニ長調 (8)バッハ:ヴァイオリン、2つのオーボエ、3つのトランペット、弦楽、ティンパニと通奏低音のためのシンフォニアBWV1045 ■CD6 C.P.E.バッハ:鍵盤協奏曲集 (1)協奏曲イ短調Wq.1【第1&2楽章のカデンツァ:ミヒャエル・リシェ】 (2)協奏曲ニ長調Wq.45【第1楽章のカデンツァ:C.P.E.バッハ】 (3)協奏曲ホ短調Wq.15 |
ベルリン・バロック・ゾリステン ■CD1 マルティン・フンダ、アルバロ・パラ、ドリアン・ジョジ、マリー・ラーダウアー=プランク(Vn1)、町田琴和、ライマー・オルロフスキー、クリストフ・シュトロイリ、ラヘル・シュミット(Vn2)、ヴァルター・キュスナー、ユリア・ガルテマン(Va)、クリスティン・フォン・デル・ゴルツ、クレメンス・ヴァイゲル(Vc)、ウルリヒ・ヴォルフ(Cb)、ラファエル・アルパーマン((1)-(5)チェンバロ、(6)オルガン) (1)マリア・ホセ・ガルシア・サモラ(Fg) (2)-(6)ギヨーム・サンタナ(Fg) (3)マチュー・デュフォー(Fl) クリストフ・ハルトマン、ヴィオラ・オルロフスキー(Ob) (1)ザスキア・フィッケンッシャー(バロックフルート) (1)ケルスティン・ファール(バロックフルート) ラインハルト・ゲーベル(指) ■CD2 フランク・ペーター・ツィンマーマン(Vn) (4)セルゲ・ツィンマーマン(Vn) 町田琴和、リューディガー・リーバーマン、アレッサンドロ・カッポーネ(Vn1)、ライマー・オルロフスキー、エーファ=マリア・トマジ、ラヘル・シュミット(Vn2)、ヴァルター・キュスナー、クリストフ・シュトロイリ(Va)、ブリュノ・ドルプレール(Vc)、ウルリヒ・ヴォルフ(Cb)、ラファエル・アルパーマン(Cemb)、ダニエル・ゲーデ(Vn、指揮) ■CD3 ロベルト・ゴンザレス=モンハス(コンサートマスター)、町田琴和、ゾルタン・アルマージ、ハンデ・コデン(Vn1)、ドリアン・ジョジ、アンナ・ルイーザ・メーリン、ライマー・オルロフスキー、コルネリア・ガルテマン(Vn2)、ヴァルター・キュスナー、ユリア・ガルテマン(Va)、クリスティン・フォン・デル・ゴルツ、ジョアン・バシュ(Vc)、ウルリヒ・ヴォルフ(ヴィオローネ) (1)ライナー・ゼーガーズ(ティンパニ) ラインハルト・ゲーベル(指) ■CD4 ラデク・バボラーク(Hrn) マルティン・フンダ、ドリアン・ジョジ、ハンデ・コデン、ヘレーナ・オッテンリップス(Vn1) ライマー・オルロフスキー、アンナ・ルイーザ・メーリン、クリストフ・シュトロイリ(Vn2) ヴァルター・キュスナー、マシュー・ハンター(Va) クリスティン・フォン・デル・ゴルツ、ジョアン・バシュ(Vc) ウルリヒ・ヴォルフ(ヴィオローネ) ラファエル・アルパーマン(Cemb) ■CD5 クシシュトフ・ポロネク(コンサートマスター、(7)(8)独奏ヴァイオリン) (7)町田琴和(第2独奏ヴァイオリン)、ドリアン・ジョジ、ヘレーナ・オッテンリップス、クリストフ・シュトロイリ、ライマー・オルロフスキー、アンナ・ルイーザ・メーリン、マリー・ラーダウアー=プランク(Vn)、ヴァルター・キュスナー、ユリア・ガルテマン(Va)、ジョアン・バシュ、ファビアン・ボレック(Vc)、ウルリヒ・ヴォルフ(ヴィオローネ)、ラファエル・アルパーマン(Cemb) (7)(8)クリストフ・ハルトマン、アンドレーアス・ヴィットマン(Ob) (6)マルクス・ヴァイトマン、ルイーザ・スローザル(Fg) (8)ラインハルト・フリードリヒ、アンドレ・ショッホ、フェリックスビルデ(Tp) (8)ライナー・ゼーガーズ(ティンパニ)、ラインハルト・ゲーベル(指) ■CD6 ミヒャエル・リシェ(P&指揮)、ダニエル・ゲーデ(コンサートマスター)、町田琴和、アレッサンドロ・カッポーネ、ヘレナ・マドカ・ベルク(Vn1)、ライマー・オルロフスキー、アンナ・メーリン、アンナ・マッツ(Vn2) (1)(2)ヴァルター・キュスナー、(3)ウルリヒ・クネルツァー、クリストフ・シュトロイリ(Va) (1)(2)シュテファン・フォルク、(3)ジョアン・バックス(Vc) (3)クラウス・ヴァーレンドルフ、(3)アンドレイ・ジュースト(Hrn) 録音:(CD1)2019年1月8~11日、(CD2)2017年4月、(CD6(1)(2))2017年6月20&21日、 (CD6(3))2017年7月11&12日/イエス・キリスト教会(ベルリン) (CD3)2021年1月25~28日、(CD5)2021年4月11~15日/ベルリン・フィルハーモニー、カンマームジークザール(ベルリン) (CD4)2020年10月17~19日/ブラックバード音楽スタジオ、シャルロッテンブルク(ベルリン) |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00851(1SACD) 日本語解説付国内盤 税込定価 2024年8月28日発売 |
モーツァルト&ハイドン:協奏交響曲 モーツァルト:ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲変ホ長調K. 364 コンサートアリア「ああ、やさしい星よ、もし天に」K.538 ディヴェルティメント第11番ニ長調K.251より第3楽章 ハイドン:協奏交響曲変ロ長調Hob.I:105 |
アンサンブルof トウキョウ【青山聖樹(Ob)、ダーク・イェンセン
(Fg)、玉井菜採(Vn)、大野かおる(Va) 河野文昭(Vc)】 2022年5月11日東京文化会館小ホール、2023年10月27日紀尾井ホール・ライヴ |
|
||
| Solo Musica SM-398(1CD) NX-B06 |
オーロラ - グリーグ:ピアノ協奏曲、ペール・ギュント組曲(4手ピアノ版)
他 グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調 Op.16 ヒャウルマル・ヘルギ・ラグナルソン:スティッラ グリーグ:ペール・ギュント組曲第1番Op.46 (4手ピアノ版)* ペール・ギュント組曲第2番Op.55(4手ピアノ版)* |
マルガリータ・ヘーエンリーダー(P) 北西ドイツPO ジョナサン・ヘイウォード(指) アンティ・シーララ(P)* 録音:2022年1月 ドイツ・ヘルフォルト、2022年12月 ドイツ、ポリング |
|
||
| Etcetra KTC-1809(1CD) |
コンチェルト・グロッソ エリク・デシンペラーレ(b.1990):ノルウェー民謡の旋律による組曲より 第2曲「Aa Lensmand」 ピアソラ:天使の協奏曲より 第1曲「天使への序奏」* ピート・スヴェルツ(b.1960):Retro ピアソラ:天使の協奏曲より 第2曲「天使のミロンガ」* ピーテル・シュールマンス(b.1970):コンチェルト・エメルソ ピアソラ:天使の協奏曲より 第3曲「天使の死」* イェルン・ドー(b.1968):Prayer ピアソラ:天使の協奏曲より 第4曲「天使の復活」* (*=編曲:ロルフ・グプタ バンドネオン・パートのサクソフォンへのトランスクリプション:クルト・ベルテルス) |
アタネレス・アンサンブル、 クゴーニ・トリオ、 ピーテル・シュールマンス(指) |
|
||
| Ars Produktion ARS-38660S(1CD) |
モーツァルト&J.C.バッハ:OPUS V モーツァルト:協奏曲Ⅰ K.107(21b)-1(原曲:J.C.バッハのソナタ Op.5-2) J.C.バッハ:ソナタ Op.5-1 モーツァルト:協奏曲Ⅲ K.107(21b)-3(原曲:J.C.バッハのソナタ Op.5-4) J.C.バッハ:ソナタ Op.5-5、ソナタ Op.5-6 モーツァルト:協奏曲Ⅱ K.107(21b)-2(原曲:J.C.バッハのソナタ Op.5-3) |
イネス・モレノ・ウンシージャ(ハープシコード)、ミヌエ・アンサンブル〔吉田爽子(Vn)、阪永珠水(Vn)、ヨハネス・コフラー(Vc)〕 録音:2024年6月24日-28日、スイス |
|
||
| Ars Produktion ARS-38374S(1SACD) 日本語解説付き |
ヴィヴァルディ:ファゴット協奏曲集 Vol.3
ファゴット協奏曲イ短調 RV.500/歌劇 「ティートゥス・マンリウス」 RV.738より アリア「ローマがこのルチオの目に」/シンフォニア ハ長調 RV.112/歌劇 「ダリオの戴冠」 RV.719 より アリア「恋するあなたの心に」/ファゴット協奏曲ト長調 RV.494/歌劇 「エジプトの戦場のアルミーダ」 RV.699より アリア「いちど悪行の道へ踏み出した者は」/歌劇 「セミラーミデ」 RV.733より アリア「メガーラの松明を掲げ」/弦楽と通奏低音のための協奏曲ト長調 RV.157/歌劇 「ファルナーチェ」 RV.711より アリア「氷のように冷たい血が」/歌劇 「ティト・マンリオ」 RV.738より アリア「戦功にはやる心に」 |
福井美穂(バロック・ファゴット) ドミニク・ヴェルナー(Bs-Br)、アンサンブルF〔川原千真(Vn1)、三輪真樹(Vn2)、宮崎桃子(Va)、田崎瑞博(Vc)、菅間周子(ヴィオローネ)、タクミ・ヒラツカ(ヴィオローネ)、能登伊津子(Cemb)、佐藤亜希子(テオルボ)〕 録音:2022年11月8日-11日、三鷹市芸術文化センター(日本) |
|
||
| Anaklasis ANA-030(1CD) |
ヨアンナ・フヌク=ナザロワ:イル・テンポ・パッサ
ヨアンナ・フヌク=ナザロワ(b.1949):前奏曲と大フーガ 「カタストロフ」(大SO、ボーイ・ソプラノとフック・ハープのための)(2019)/Morze ?rodziemne, ?egnaj. Proba rekonstrukcji(2本のギターと室内オーケストラのための)(1986)/Nie odwracaj si?! Dyptyk(2本の独奏フルートと室内オーケストラのための)(2022)/イル・テンポ・パッサ. パッサカリア(大SOのための)(2020)/ひばり協奏曲(アンプリファイド・ハープシコードと室内オーケストラのための)(2023) |
バルトウォミエイ・ドゥダ(Boy-S)、アグニエシュカ・カチマレク=ビアリツ(フック・ハープ)、ヤクブ・モロジンスキ(G)、マレク・ノサル(G)、アガタ・キエラル=ドゥゴシュ(Fl)、ウカシュ・ドゥゴシュ(Fl)、フゴ・ドゥゴシュ(Tp)、アレクサンドラ・ガイェツカ=アントシエヴィチ(ハープシコード)、シレジア室内O、ピオトル・プワフネル(指)、シレジア・フィルハーモニーSO、ヤロスラフ・シェメト(指) 録音:2023年11月~2024年2月(カトヴィツェ、ポーランド) |
|
||
| Gramola GRAM-99328(1CD) NX-C05 |
シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.47 ヴァイオリンとピアノのための5つの小品 Op. 81 田園舞曲 Op.106- 第1曲 ヴァイオリンとピアノのための4つの小品 Op. 115 夜想曲 Op.51No.3 フランツ・フォン・ヴェチェイ(1893-1935):悲しきワルツ |
トーマス・アルベルトゥス・イルンベルガー(Vn) ロイヤルPO ドロン・サロモン(指) ミヒャエル・コルスティック(P) 録音:2022年7月7日、2023年2月27日 |
|
||
 Hanssler HC-23015(6CD) ★ |
「イン・メモリアム Vo.2」 ■CD1 (1)シューマン:チェロ協奏曲 イ短調 Op.129 (2)ブラームス:ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 Op.102 (3)チャイコフスキー:カプリッチョ風小品 ロ短調 Op.62 (4)ルトスワフスキ:チェロと弦楽オーケストラのためのメタモルフォーゼより「グラーヴェ」 ■CD2 (1)ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104 B.191 (2)ブロッホ:ヘブライ狂詩曲『シェロモ』 グバイドゥーリナ:チェロ、バヤンと弦楽合奏のための『7つの言葉』より第7曲「今日、あなたは私と共に楽園に入る」、第8曲「わが神,なんぞわれを見棄てし?」 ■CD3 (1)ショパン:チェロ・ソナタ ト短調 Op.65 (2)ショスタコーヴィチ:チェロ・ソナタ ニ短調 Op.40 シュニトケ:チェロ・ソナタ第1番 ■CD4 (1)メンデルスゾーン:ピアノ三重奏曲第1番 ニ短調 Op.49 シューベルト:ピアノ三重奏曲第2番変ホ長調 Op.100, D.929より第2楽章「アンダンテ・コン・モート」 (2)ツェムリンスキー:ピアノ三重奏曲 イ短調 (3)ドビュッシー:チェロ・ソナタ ニ短調 (4)ヤナーチェク:おとぎ話 (5)シェーンベルク:鉄の旅団 ■CD5 (1)ベートーヴェン:モーツァルトの「魔笛」の「恋を知る男たちは」の主題による7つの変奏曲 変ホ長調 WoO46 (2)シューマン:アダージョとアレグロ Op.70 (3)ブラームス:6つのリート Op.86より第2曲「野の寂しさ」 ブラームス:5つのリート Op.94より第4曲「サッフォー風頌歌」 ブラームス:5つのリート Op.105より第1曲「調べのように私を通り抜ける」 (4)チャイコフスキー:6つの小品 Op.19より第4曲「夜想曲」 (5)ドヴォルザーク:ピアノ三重奏曲第3番 ヘ短調 Op.65, B.130より第3楽章「ポーコ・アダージョ」 (6)ブルッフ:8つの小品 Op.83より第6曲 ト短調「夜想曲」 (7)フォーレ:悲歌 Op.24 (8)ドビュッシー:忘れられたアリエッタより第2曲「私の心に涙が落ちる」 エリセンダ・ファブレガス(1955~):アルハンブラの夜 (10)ヒラリー・タン(1947~):リーフ (11)カザルス:鳥の歌 ■CD6 (1)バッハ:無伴奏チェロ組曲第3番ハ長調 BWV1009 (2)クープラン(バズレール編):コンセールのための5つの小品より第4曲「嘆き」 (3)ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲第5番ニ長調「幽霊」 Op.70, No.1 (4)シューベルト:水の上で歌う Op.72D.774 シューベルト:白鳥の歌 D.957より第4曲「セレナード」 シューベルト:夜と夢 Op.43-2D.827 シューベルト:エレンの歌第3番「アヴェ・マリア」D.839 Op.52-6 (5)ポッパー:ハンガリー狂詩曲 Op.68 |
フランソワーズ・グローベン(Vc) ■CD1 (1)NHKSO、ウーヴェ・ムント(指) 録音:1996年8月26日(ライヴ)サントリーホール(東京) (2)カリン・アダム(Vn) ルクセンブルクRSO)、レオポルド・ハーガー(指) 録音:1995年11月9日(セッション)ルクセンブルク大劇場(ルクセンブルク) (3)ローザンヌ室内O、ニコラ・ブロシュ(指揮 録音:2003年10月10日(ライヴ)ヒポ・フェラインス銀行内ホール(ルクセンブルク) (4)ローザンヌ室内O、ニコラ・ブロシュ(指揮 録音:2011年3月12日(ライヴ)キューブ521、マルナッハ、クレルヴォー(ルクセンブルク) ■CD2 (1)ローザンヌ室内O、ニコラ・ブロシュ(指) 録音:2005年5月4日(ライヴ)メッツ・アルナセル(フランス) (2)ルクセンブルクPO、デヴィッド・シャローン(指) 【原盤:BGL(1999)】 ●マウリツィオ・スピリディリオッツィ(バヤン) ルクセンブルクPO、ヴェルナー・エールハルト(指) 録音:2006年4月2日(ライヴ)フィルハーモニー・ルクセンブルク(ルクセンブルク) ■CD3 (1)イヴァン・ガヤン(P) 録音:2000年10月8日(ライヴ)ヴィラ・ルヴィニー(ルクセンブルク) (2)イヴァン・ガヤン(P) 録音:1990年10月8日(ライヴ)ヴィラ・ルヴィニー(ルクセンブルク) ■CD4 (1)グラフ・ムーリャ(Vn)、ペーター・ラウル(P) 録音:2005年7月7日(ライヴ)カンブレー劇場(フランス) (2)マヤ・コッホ(Vn)、イラ・マリア・ヴィトシンスキ(P) 録音:1998年11月26日(ライヴ)カールスルーエ音楽大学(ドイツ) (3)イヴァン・ガヤン(P) 録音:2008年11月11日(ライヴ)キューブ521、マルナッハ、クレルヴォー(ルクセンブルク) (4)ライナー・ゲップ(P) 録音:2007年(ライヴ)ボーデン湖音楽祭(ドイツ) (5)トーマス・ブランディス(Vn)、マルコ・リッツィ(Vn)、ステファン・フェーラント(Va)、フリーデマン・リーガー(P) 録音:1999年7月29日(ライヴ)北ドイツ放送内スタジオ、ヒッツアッカー(ドイツ) ■CD5 (1)イヴァン・ガヤン(P) 録音:2000年10月8日(ライヴ)ヴィラ・ルヴィニー(ルクセンブルク) (2)小川典子(P) 録音:1996年8月(ライヴ)シューベルティアーデ、フォアアールベルク(オーストリア) (3)イラ・マリア・ヴィトシンスキ(P) 録音:2004年(ライヴ)カールスルーエ音楽大学(ドイツ)【原盤:ARS Produktion38435.(2004)】 (4)ローザンヌ室内O、ニコラ・ブロシュ(指揮 録音:2003年10月10日(ライヴ)ヒポ・フェラインス銀行内ホール(ルクセンブルク) (5)グラフ・ムーリャ(Vn)、ペーター・ラウル(P) 録音:2004年7月14日(ライヴ)カンブレー劇場、ユベントス(フランス) (6)ロナルド・ファン・スパンドンク(Cl)、ペーター・ラウル(P) 録音:2006年3月26日(ライヴ)シルダール(ルクセンブルク) (7)ライナー・ゲップ(P) 録音:2005年5月28日(ライヴ)マーブルタウン、ニューヨーク(アメリカ) (8)イラ・マリア・ヴィトシンスキ(P) 録音:2004年(ライヴ)カールスルーエ音楽大学(ドイツ) (9)マイニンガー・トリオ【クリストファー・マイニンガー(Fl)、フランソワーズ・グローベン(Vc)、ライナー・ゲップ(P)】 録音:2005年(セッション)ロンドン【原盤:Profil PH-05019】 (10)クリスティアーネ・マイニンガー(Fl) 録音:2005年(セッション)ロンドン【原盤:Profil PH-05019】 (11)小林由佳(P) 録音:1991年12月9日(ライヴ)カザルスホール(御茶ノ水) ■CD6 (1)録音:1991年12月9日(ライヴ)カザルスホール(御茶ノ水) (2)小林由佳(P) 録音:1991年2月3日(ライヴ)ブールリンシュター(ルクセンブルク) (3)グラフ・ムーリャ(Vn) ペーター・ラウル(P) 録音:2006年8月(ライヴ)カンブレー劇場、ユベントス(フランス) (4)小川典子(P) 録音:1996年8月28日(ライヴ)シューベルティアーデ、フォアアールベルク(オーストリア) (5)小林由佳(P) 録音:1991年11月28日(ライヴ)いずみホール(大阪) |
|
||
| ACCENT ACC-24403(1CD) |
バッハ:ヴァイオリン協奏曲集 2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043 ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 BWV1041(独奏:モニカ・ワイズマン) ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 BWV1042(独奏:フロリアン・ドイター) 2つのヴァイオリンのための協奏曲 ハ短調 BWV1060R |
フロリアン・ドイター(Vn 、指 揮 ) モニカ・ワイズマン(Vn 、指) アルモニー・ウニベルセル 録音:2022年5月30日-6月2日/ドイツ、ホンラート教会 |
|
||
 Treasures TRE-319(1CDR)  Branka Musulin |
ブランカ・ムスリン/ショパン:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲第1番ホ短調Op.11* ピアノ協奏曲第2番へ短調Op.21*# 練習曲Op.25-7/Op.25-3 |
ブランカ・ムスリン(P) ハインツ・ワルベルク(指)バンベルクSO* ウィルヘルム・シュヒター(指)ベルリンSO# 録音:1960年代初頭*、1963年7月4-5日#、1964年10月3日(全てステレオ) ※音源:日KING SH-5242*,#、日KING SR-5052# ◎収録時間:77:03 |
| “成熟した精神の昇華力で甘美なショパン像を打破!” | ||
|
||
| ONDINE ODE-1436(1CD) NX-B10 |
マグヌス・リンドベルイ(1958-):ヴィオラ協奏曲、他 ヴィオラ協奏曲(2023-24) 不在(2020) セレナード(2020) |
ローレンス・パワー(Va) フィンランドRSO ニコラス・コロン(指) 録音:2023年9月、2023年12月、2024年2、3月 |
|
||
| C Major 76-6508(DVD) 76-6604(Bluray) |
ブラームス:ヴァイオリン協奏曲ニ短調op.77 バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第1番ロ短調BWV1002~サラバンド(アンコール) ニールセン:交響曲第5番op.50 |
ヘルベルト・ブロムシュテット(指)VPO レオニダス・カヴァコス(Vn) 収録:2023年3月、ウィーン楽友協会大ホール(ライヴ) ◆DVD 画面:NTSC16:9 音声:PCMステレオ、DTS5、リージョン:All DVD9、93分 ◆Bluray 画面:1080i16:9FullHD 音声:PCMステレオ、DTS-HD MA5.1 リージョン:All BD25、93分 |
|
||
| ATMA ACD2-2885(1CD) |
アマデウスと皇妃 ~モンジュルーとモーツァルト エレーヌ・ド・モンジュルー(1764-1836):ピアノ協奏曲第1番変ホ長調 序曲『皇妃』(マテュー・ルシエによるモンジュルー作品の管弦楽編) モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番 ハ短調 K.491 エレーヌ・ド・モンジュルー:練習曲集『ピアノ教育のための完全教程』より 第19番ヘ長調 / 第107番ニ短調 / 第73番ニ長調 / 第26番ト長調 / 第111番ト短調 同曲集より 第26番『無言歌』(マテュー・ルシエによるピアノと弦楽合奏のための編曲版) |
エリザベート・ピオン(フォルテピアノ;1826年製ブロードウッド) マテュー・ルシエ(指) アリオン・バロックオーケストラ 録音:2023年10月9・10日/ケベック、ミラベル、聖オーギュスタン教会 |
|
||
| ATMA ACD2-2851(1CD) |
ハイドン:チェロ協奏曲第1&2番 ハイドン:チェロ協奏曲第1番ハ長調 Hob.VIIb:1 チェロ協奏曲第2番ニ長調 Hob. VIIb:2 ジャック・エテュ(1938-2010):チェロと弦楽合奏のためのロンド Op.9 |
キャメロン・クロズマン(Vc) ニコラス・エリス(指) レ・ヴィオロン・ドゥ・ロワ 録音:2023年6月13-15日/ケベック、パレ・モンカルム |
|
||
| Orlando Records OR-0054(1CD) |
コペル、シュミット、ベンソン:クラリネット協奏曲集
ヘアマン・D・コペル(1908-1998):クラリネットと室内オーケストラのための協奏曲 Op.35 オーレ・シュミット(1928-2010):クラリネットと室内オーケストラのための協奏曲 ニルス・ヴィゴ・ベンソン(1919-2000):独奏クラリネットと小器楽アンサンブルのための室内協奏曲 Op.578 |
ジョン・クルーゼ(Cl)、オールボーSO、フリードリク・ビューシュテット(指) 録音:2023年6月12日-16日、ミュージック・ハウス(オールボー、デンマーク) |
|
||
| Avie AV-2688(1CD) |
ジ・アイリッシュ・シーズンズ~マクドナー&ヴィヴァルディ ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集 「四季」 アルバ・マクドナー(b.1982):アイルランドの四季(世界初デジタル録音) |
リンダ・オコナー、 アナムス(オーケストラ)、 デイヴィッド・ブロフィー(指) 録音:2022年11月、ウィンドミル・レイン・スタジオ(ダブリン) |
|
||
| Fineline FL-72418(1CD) |
ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番ニ短調 Op.30 ピアノ協奏曲第4番ト短調 Op.40 |
ニコライ・ルガンスキー(P)、 ロシア国立SO、 イワン・シュピレル(指) 録音:1995年、モスクワ音楽院大ホール(ロシア) |
|
||
| IBS CLASSICAL IBS-72024(1CD) NX-B10 |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 Op.37 ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op.58 ※全てヴィンツェンツ・ラハナーによる弦楽オーケストラ伴奏版 |
ツ・ユー・ヤン(フォルテピアノ) ロバート A.ブラウンによる復元楽器 1806年 Michael Rosenberger製…第3番 1815年頃 Jacob Bertsche製…第4番 ヴァン・スヴィーテンス(古楽器使用) ティボー・バック・ド・スラニ(指) 録音:2022年10月22-23日、2022年2月24-25日 |
|
||
 Hanssler HC-24002(4CD) |
F・P・ツィンマーマン/ヘンスラー録音集成 ■CD1 モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲集Vol.1 ヴァイオリン協奏曲第1番変ロ長調K.207(カデンツァ コンスタンチン・モストラス) ヴァイオリンと管弦楽のためのアダージョホ長調K.261(カデンツァ フランツ・バイヤー) ヴァイオリンと管弦楽のためのロンドハ長調K.373 ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調K.216(カデンツァ フランツ・バイヤー) ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調K.218(カデンツァ ヨーゼフ・ヨアヒム) ■CD2 モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲集Vol.2 ヴァイオリン協奏曲第2番ニ長調K.211(カデンツァ 第1楽章:ピンカス・ズッカーマン/第2楽章:ロバート・D・レヴィン/第3楽章:ダヴィッド・オイストラフ) ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調K.219「トルコ風」(カデンツァ 第1楽章:フランツ・バイヤー/第2楽章:ロバート・D・レヴィン/第3楽章:ヨーゼフ・ヨアヒム) ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲変ホ長調K.364*(カデンツァ モーツァルト) ■CD3 バッハ:ヴァイオリン協奏曲集 ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調BWV1041 ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調BWV1042 ヴァイオリン協奏曲ニ短調BWV1052 オーボエとヴァイオリンのための協奏曲ニ短調BWV1060*(2つのヴァイオリンのための協奏曲編) ■CD4 ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.61(カデンツァ 第1楽章:フランク・ペーター・ツィンマーマン/第2楽章:フリッツ・クライスラー/第3楽章:フリッツ・クライスラー) |
■CD1 バイエルン放送室内O、ラドスラフ・スルク(指) セッション録音:2014年3月6~8日/ヘルクレスザール、ミュンヘン王宮内(ミュンヘン) ■CD2 アントワン・タメスティ(Va)* バイエルン放送室内O、ラドスラフ・スルク(指) セッション録音:2015年6月28~30日/ヘルクレスザール、ミュンヘン王宮内(ミュンヘン) ■CD3 セルゲ・ツィンマーマン(Vn)* ベルリン・バロック・ゾリステン 指揮&ヴァイオリン:ダニエル・ゲーデ 第1ヴァイオリン:町田琴和、リューディガー・リーバーマン、アレッサンドロ・カッポーネ 第2ヴァイオリン:ライマー・オルロフスキー、エーファ=マリア・トマジ、ラヘル・シュミット ヴィオラ:ヴァルター・キュスナー、クリストフ・シュトロイリ チェロ:ブリュノ・ドルプレール コントラバス:ウルリヒ・ヴォルフ チェンバロ:ラファエル・アルパーマン セッション録音:2017年4月/イエス・キリスト教会(ベルリン) ■CD4 シュターツカペレ・ドレスデン、ベルナルト・ハイティンク(指) ライヴ録音:2002年9月29日/ドレスデン文化宮殿(ドレスデン) |
|
||
| Biddulph BIDD-85040(1CD) NX-B06 |
ハイフェッツ コルンゴルト/カステルヌオーヴォ=テデスコ:ヴァイオリン協奏曲
他 1-3. コルンゴルト:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35 4-6. シンンディング:古風な様式の組曲 Op.10 7. ブラームス:ハンガリー舞曲第7番 イ長調(ヨアヒム編) 8. チャイコフスキー:憂鬱なセレナード Op.26 9. ラヴェル:ツィガーヌ 10-12. カステルヌオーヴォ=テデスコ:ヴァイオリン協奏曲第2番「予言者」 Op.66 |
ヤッシャ・ハイフェッツ(Vn) ロサンゼルスPO アルフレッド・ウォーレンスタイン(指) 録音/初出レコード番号: 1953年1月10日 RCA Victor LM1782…1-3 1953年12月9日 RCA Victor LM1832…4-6 1953年12月9日 RCA Victor LSC3232…7 1954年10月29日 RCA Victor LM2027…8 1953年12月8日 RCA Victor LM1832…9 1954年10月28&29日 RCA Victor LM2050…10-12 |
|
||
| Resonus RES-10335(1CD) NX-B08 |
フルート協奏曲集 イベール:フルート協奏曲(1934) ジョリヴェ(1905-1974):フルートと弦楽オーケストラのための協奏曲(1949) ロドリーゴ:田園協奏曲(1978) |
サミ・ユンノネン(Fl) ヘルシンキ室内O ジャームズ・S・カハーン(指) 録音:2023年10月11-14日 |
|
||
| H.M.F HMM-902392(1CD) |
アントニン・クラフト(1749-1820):チェロ協奏曲 ハ長調 op.4(1804) C.P.E.バッハ:チェロ協奏曲 変ロ長調 H436Wq171(1751) |
ジャン=ギアン・ケラス(Vc/Gioffredo Cappa,1696)
アンサンブル・レゾナンツ リッカルド・ミナージ(指) 録音:2023年9月、ハンブルク、フリードリヒ=エーベルト・ホール |
|
||
| Pentatone PTC-5187076(1CD) |
再発見~トーマス・ド・ハルトマン トーマス・ド・ハルトマン(1884-1956): (1)ヴァイオリン協奏曲 Op.66(1943) (2)チェロ協奏曲 Op.57(1935) |
(1)ジョシュア・ベル(Vn)、INSO-リヴィウSO、ダリア・スタセフスカ(指)
(2)マット・ハイモヴィッツ(Vc)、MDR響、デニス・ラッセル・デイヴィス(指) 録音:(1)2024年1月8~10日/ワルシャワ・フィルハーモニー・ホール(ポーランド) (2)2022年5月22日/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス大ホール(ドイツ) |
|
||
| Goodies 33CDR-3947(1CDR) |
モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第6番変ホ長調 K.268(365b) ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調 K.216 |
クリスチャン・フェラス(Vn) カール・ミュンヒンガー(指) シュトゥットガルト室内O 英DECCA LXT5044(FFRR録音) 1954年10月14日-11月11日、スイス、ジュネーヴ、ヴィクトリア・ホール録音 |
|
||
| Goodies 33CDR-3948(1CDR) |
チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲ニ長調作品35 | ナタン・ミルシテイン(Vn) シャルル・ミュンシュ(指)ボストンSO 米 RCA VICTOR LM1760 1953年3月23日ボストン・シンフォニー・ホール録音 |
|
||
| Melodiya x Obsession SMELCD-1002692(2CD) |
モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲全曲 ァイオリン協奏曲第1番変ロ長調 K.207 ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調 K.218 ヴァイオリン協奏曲第2番ニ長調 K.211* ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調 K.216 ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 K.219 アダージョ ホ長調 K.261* ロンド ハ長調 K.373* ロンド 変ロ長調 K.269* |
オレグ・カガン(Vn)、 ダヴィッド・オイストラフ(指)モスクワPO、 トヴィス・リフシッツ(指)ラトヴィア・フィルハーモニー室内O* 録音:1970年、1972年 |
|
||
| Melodiya x Obsession SMELCD-1001994(1CD) |
ショパン:ピアノ協奏曲第1番&第2番他 ピアノ協奏曲第1番ホ短調 Op.11*/ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 Op.21*/マズルカ ヘ短調 Op.63-2/マズルカ ヘ短調 Op.68-4/ワルツ ホ短調 Op.Posth |
エフゲニー・キーシン(P)、 モスクワPO*、 ドミトリー・キタエンコ(指)* 録音(ライヴ):1984年3月27日、モスクワ音楽院大ホール |
|
||
| PROSPERO CLASSICAL PROSP-010(1CD) |
ゲザ・アンダ&カール・ベーム完全初出! (1)スイス放送(DRS)のアナウンス (2)-(4)ブラームス:ピアノ協奏曲第1番ニ短調 Op.15 (5)オーストリア放送(ORF)のアナウンス (6)-(8)モーツァルト:ピアノ協奏曲第18番 変ロ長調 K.456 |
ゲザ・アンダ(P) カール・ベーム(指) (2)-(4)フィルハーモニアO (6)-(8)VPO 録音:(2)-(4)1963年9月14日/ルツェルン音楽祭(ライヴ・モノラル) (6)-(8)1974年8月25日/ザルツブルク音楽祭(ライヴ・ステレオ) |
|
||
| ALPHA ALPHA-1065(1CD) NX-C04 |
モーツァルト:フルート協奏曲集 フルート協奏曲 第2番ニ長調 K.314(カデンツァ:フランソワ・ラザレヴィチ) フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K. 299*(カデンツァ:ピエール・シェペロフ[1979-]) フルート協奏曲 第1番ト長調 K.313(カデンツァ:フランソワ・ラザレヴィチ) |
フランソワ・ラザレヴィチ(フラウト・トラヴェルソ、指揮) 使用楽器:1キーのバロック・モデル/ルドルフ・トゥッツ1790年代製作楽器に基づく8キー・モデル* サンドリーヌ・シャルトン(Hp) 使用楽器:フランソワ=ジョゼフ・ナーデルマン(1781-1835)製作のオリジナル楽器 レ・ミュジシャン・ド・サン・ジュリアン(古楽器使用) 録音:2023年6月 サル・コロンヌ、パリ |
|
||
| Biddulph BIDD-85049(1CD) NX-B06 |
協奏曲集と小品集 1-3. 伝モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第6番変ホ長調 K.268 4-5. ヴュータン:ヴァイオリン協奏曲第5番 イ短調 Op.37 6-9. ヘンデル:ヴァイオリン・ソナタ第6番 ホ長調 10. ピエトロ・ナルディーニ(1722-1793):ヴァイオリン・ソナタ ニ長調~アリア(イザイ編) 11. ルクレール:ヴァイオリン・ソナタ ニ長調 Op.9No.3-タンブーラン(ヘルマン編) 12. モーツァルト:ディヴェルティメント ニ長調 K.334-メヌエット(ヘルマン編) 13. ヴュータン:アルバムの綴り Op.40~ 第1番 ロマンス 14. イザイ:ヴァイオリン・ソナタ第3番 ニ短調「バラード」 15. クライスラー:レチタティーヴォとスケルツォ |
アルフレッド・デュボワ(Vn) ブリュッセル王立音楽院O…1-5 デジレ・デファウ(指)…1-5 ジェラルド・ムーア(P)…6-9 フェルナン・フイエンス(P)…10-13 14,15は無伴奏 録音/音源 1931年6月12日/LF X201/03(matrices LBX 83/87)…1-3 1929年9月27,28日/LFX14/16(matrices W 52031/36)…4-5 1947年10月27日/LCX103(matrices CLBX160/61)…6-9 1929年9月26日/LF2(matrices W33029)…10 1929年9月26日/LF2(matrices W33030)…11 1931年6月13日/LFX203(matrices LBX90)…12 1929年12月19日/D15144(matrices WLX700)…13 1947年10月27日/LCX104(matrices CLBX162/63)…14 199年9月26日/LF3(matrices W33031/32)…15 |
|
||
| Orchid Classics ORC-100315(1CD) NX-B06 |
モーツァルト:2台のピアノのための協奏曲とソナタ 2台のピアノと管弦楽のための協奏曲 第10番 変ホ長調 K.365/316a 2台のピアノと管弦楽のための協奏曲 第7番ヘ長調 K.242 2台のピアノのためのソナタ ニ長調 K.448/375a* |
フィアンメッタ・タルリ(P) イーヴォ・ヴァルバノフ(P) ムハイ・タン(指) イギリス室内O 録音:2018年7月13ー14日 Henry Wood Hall(UK) 2022年9月2日 Menuhin Concert Hall(UK)* |
|
||
| Queen Elisabeth Competition QEC-2024(4CD) NX-F06 |
エリザベート王妃国際音楽コンクール ヴァイオリン部門2024 ■CD1 ショスタコーヴィチ: 1-4. ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 Op.77 ブラームス: 5-7. ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.77 ■CD2 モーツァルト: 1-3. ヴァイオリン協奏曲第1番変ロ長調 K. 207 4-6. ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調 K.218 ベートーヴェン: 7-10. ヴァイオリン・ソナタ第7番ハ短調 Op. 30-2 ■CD3 チャイコフスキー: 1-3. ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35(1965-): 4. リタニー風変奏曲 シューベルト: 5. 幻想曲 D934 ■CD4 サン=サーンス: 1. 序奏とロンド・カプリチオーソ チャイコフスキー: 2. ワルツ・スケルツォ ハ長調 Op.34 シャーロット・ブレイ(1982-): 3. 太陽と彼女の花々 The Sun and Her Flowers シェーンベルク: 4. 幻想曲 Op.47 ルトスワフスキ: 5. スビト バルトーク: 6-7. ヴァイオリン・ソナタ第2番Sz.76 シュニトケ(1934-1998): 8-11ヴァイオリン・ソナタ第1番 |
■CD1 1-4. ドミトロ・ウドヴィチェンコ(Vn) 5-7. ジョシュア・ブラウン(Vn) ■CD2 1-3. 吉田南(MINAMI)(Vn) 4-6. ケヴィン・ジュー(Vn) ジョシュア・ブラウン(Vn) ■CD3 1-3. ジュリアン・リー(Vn) 4. ドミトロ・ウドヴィチェンコ(Vn) 5. エリー・チョイ(Vn) ■CD4 1. ルスラン・タラス(Vn) 2. カレン・スー(Vn) 3. ハナ・チャン(Vn) 4. ターユン・ユー(Vn) 5. アナ・イム(Vn) 6-7. ソンハ・チョイ(Vn) 8-11ドミトロ・ウドヴィチェンコ(Vn) ベルギー国立O アントニー・ヘルムス(指)…CD1& CD3/1-4 ワロニー王立室内O ヴァハン・マルディロシアン(指)…CD2/1-6 ピアノ:トマス・ホッペ…CD2/7-10& CD3/5 リーブレヒト・ファンベッケフォールト…CD4/1 クリスティア・フジー…CD4/2 ボリス・クズネツォフ…CD4/3 森川由佳子…CD4/4、6、7 エロディー・ヴィニョン…CD4/5 タティアナ・ビエリコヴァ…CD4/8-11 録音:2024年5月13-18日 フラジェ・スタジオ4、ブリュッセル 2024年5月27日-6月1日 ブリュッセル・ファイン・アーツ・センター、 全てライヴ |
|
||
| Queen Elisabeth Competition QECDUO-24(4CD) NX-E10 |
エリザベート王妃国際音楽コンクール ヴァイオリン部門2009-2012 ■CD1 チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35 フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調* サン=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 Op.28* ■CD2 パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ニ長調 Op.6 エネスコ:ヴァイオリン・ソナタ第3番* イザイ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第6番 ホ長調 Op.27-6* サン=サーンス:ハバネラ Op.83* ■CD3 モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番 イ長調 K.219「トルコ風」* エルガー:ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 Op.61* ■CD4 ショスタコーヴィチ:ヴァイオリン協奏曲第1番 イ短調 Op.77 モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調 K.216* チャイコフスキー:懐かしい土地の思い出(瞑想曲) Op.42-1* ワルツ・スケルツォ ハ長調 Op.34* |
■CD1 レイ・チェン(Vn) ベルギー国立O、ギルバート・ヴァルガ(指) トマス・ホッペ(P) 録音:2009年5月16日 ボザール(4-8)、5月30日 王立音楽院(1-3) *初出音源 ■CD2 ロレンツォ・ガット(Vn) ベルギー国立O、ギルバート・ヴァルガ(指) エリアーヌ・レイエス(P) 録音:2009年5月12日 ボザール(4-8)、5月26日 王立音楽院(1-3) *初出音源 ■CD3 ヴィネタ・サレイカ(Vn) ワロニー王立室内O、ポール・グッドウィン(指) ベルギー国立O、ギルバート・ヴァルガ(指) 録音:2009年5月14日 ボザール(1-3)、5月25日 王立音楽院(4-6) *初出音源 ■CD4 アンドレイ・バラノフ(Vn) ベルギー国立O、ギルバート・ヴァルガ(指) ワロニー王立室内O、ミヒャエル・ホフステッター(指) ダナ・プロトポペスク(P) 録音:2012年5月8日(5-7)、5月11日(8、9) フラジェ、スタジオ4、5月 24日 ボザール (1-4) *初出音源 録音場所:王立音楽院、フラジェ(スタジオ4)、ボザール(以上、ブリュッセル) 全てライヴ |
|
||
| APARTE AP-364(1CD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番ト長調Op.58 ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 |
リード・テツロフ(P) パヴェウ・カプワ(指)プラハ・フィル 録音:2023年3月/ドヴォルザーク・ホール(プラハ) |
|
||
| King International KKC-6874(2CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
フランス女性ピアニストたち~ブルショルリ他 ■CD1 (1)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 (2)ショパン:夜想曲集 第13番ハ短調、第7番ハ短調、第8番変ニ長調、第4番ヘ長調、第9番イ長調 ■CD2 (1)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番+ラヴェルについて語る(日本語訳なし) (2)サン=サーンス:ピアノ協奏曲第5番「エジプト風」+ショパンについて語る |
■CD1 (1)モニク・ド・ラ・ブルショルリ(P)、レオポルト・ルートヴィッヒ(指)BPO 録音:1948年6月20-21日ベルリン・ティタニア・パラストLive (2)ユーラ・ギュラー(P) 録音:1959年9月9日 ■CD2 (1)イヴォンヌ・ルフェビュール(P)、スタニスラフ・スクロヴァチェフスキー(指) フランス国立O 録音:1959年12月1日 (2)マグダ・タリアフェロ(P)、ポール・パレー(指) フランス国立O 録音:1958年4月21日Live |
|
||
| MELO CLASSIC MC-1078(2CD) |
アレクサンダー・ブライロフスキー/ライヴ・コンサート・イン・ヨーロッパ (1)チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 (2)ショパン:ピアノ協奏曲第1番 (3)ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 (4)シューマン:ピアノ協奏曲イ短調 (5)リスト:死の舞踏 |
アレクサンダー・ブライロフスキー(P) (1)カール・ガラグリー(指)ストックホルム・コンサート協会O (2)(4)ルイ・ド・フロマン(指)ルクセンブルク放送O (3)ユージン・オーマンディ(指)フィラデルフィアO (4)ルイ・ド・フロマン(指)ルクセンブルク放送O (5)アンドレ・クリュイタンス(指)フランス国立放送O 録音:(1)1951年9月19日スウェーデン放送局ストックホルム・コンサート・ホール、 (2)(4)1962年4月4日ルクセンブルク - オーディトリアム・ヴィラ・ルーヴィニーRTL、 (3)1958年6月30日ミュンヘン - コングレスホール ドイツ博物館、 (5)1958年10月16日パリ - シャンゼリゼ劇場 全てモノラル |
|
||
| MELO CLASSIC MC-2054(1CD) |
ヨハンナ・マルツィ/ライヴ・コンサート・パフォーマンス (1)ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第8 番ト長調 (2)メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調 (3)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調 |
ヨハンナ・マルツィ(Vn) (1)イシュトヴァン・ハイジュ(P) (2)ルチアーノ・ロサーダ(指)RAIミラノSO (3)ウルス・ヨーゼフ・フルーリー(指)ソロトゥルン室内O 録音:(1)1969年2月3日ヴェネツィア、フェニーチェ劇場(ライヴ・モノラル)、 (2)1961年6月6日ミラノ、スタジオRAI (ライヴ・モノラル)、 (3)1974年5月9日ソロトゥルン大ホール(ライヴ・モノラル) |
|
||
| MELO CLASSIC MC-2055(2CD) |
マックス・ロスタル/コンサート・ツアー1956-1965 (1)ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲イ短調Op.53 (2)ハチャトゥリアン:ヴァイオリン協奏曲ニ短調 (3)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調KV219 (4)ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調Op.26 (5)グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調Op.82 |
マックス・ロスタル(Vn) (1)(3)アンリ・ペンシス(指)ルクセンブルク放送O (2)ヤン・クーツィール(指)バイエルンRSO (4)カール・メレス(指)ルクセンブルク放送O (5)エーリヒ・シュミット(指)ベロミュンスター放送O 録音:(1)1957年11月23日ルクセンブルク、ヴィラ・ルーヴィニー(スタジオ録音・モノラル) (2)1957年3月15日ミュンヘン、ヘラクレスザール(スタジオ録音・モノラル) (3)1956年1月25日ルクセンブルク、ヴィラ・ルーヴィニー(スタジオ録音・モノラル) (4)1960年11月5日ルクセンブルク、ヴィラ・ルーヴィニー(スタジオ録音・モノラル) (5)1965年9月4日チューリッヒ、スタジオI-DRS(スタジオ録音・モノラル) |
|
||
| MELO CLASSIC MC-2056(2CD) |
アルテュール・グリュミオー/ライヴ・コンサート・パフォーマンス (1)パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第4番ニ短調MS60 (2)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調KV219 (3)バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲ニ短調BWV1043 (4)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調KV218 (5)サン=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソOp.28 (6)イザイ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ ニ短調「バラード」Op.27-3 (7)メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調Op.64 |
アルテュール・グリュミオー(Vn) (1)フランコ・ガリーニ(指)ウィーンSO (2)(4)(5)アンリ・ペンシス(指)ルクセンブルク放送O (3)ヘンリー・メルケル(2nd Vn)、ルイ・マルタン(指)ストラスブールRSO (7)カール・ミュンヒンガー(指)シュトゥットガルト・クラシッシェクPO 録音:(1)1954年12月9日ウィーン楽友協会ホールORF(ライヴ・モノラル)、 (2)1956年5月17日ルクセンブルク 、オーディトリアム・ヴィラ・ルーヴィニー(ライヴ・モノラル)、 (3)1958年6月19日ストラスブール、パレ・デ・フェット(ライヴ・モノラル)、 (4)(5)(6)1955年5月26日ルクセンブルク、オーディトリアム・ヴィラ・ルーヴィニー(ライヴ・モノラル)、 (7)1971年11月22日シュトゥットガルト、リートハレSDR(ライヴ・ステレオ) |
|
||
| MELO CLASSIC MC-2057(2CD) |
ピーナ・カルミレッリ/コンサート・ツアー1964-1971 (1)ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.61 (2)メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調Op.64 (3)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調KV216 (4)ショスタコーヴィチ:ヴァイオリン協奏曲第1 番イ短調Op.77 |
ピーナ・カルミレッリ(Vn) (1)(2)エーリッヒ・シュミット(指)ベロミュンスター放送O (3)ウィレム・ファン・オッテルロー(指)NDRハノーファー放送O (4)ウィリー・シュタイナー(指)NDRハノーファー放送O 録音:(1)1968年10月6日チューリッヒス、タジオ1-DRS(スタジオ録音・モノラル)、 (2)1964年2月2日チューリッヒ、スタジオ1-DRS(スタジオ録音・モノラル)、 (3)1971年2月12日ハノーファー、放送センターNDR(ライヴ・ステレオ)、 (4)1965年11月19日ゲッティンゲン、シュタットハレNDR(ライヴ・モノラル) |
|
||
| MELO CLASSIC MC-2058(1CD) |
グィラ・ブスターボ/発掘された放送音源集 (1)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第6番変ホ長調KV268 (2)ハチャトゥリアン:ヴァイオリン協奏曲ニ短調 |
グィラ・ブスターボ(Vn) (1)オトマール・ヌシオ(指)スイス・イタリアーナO (2)ヒューゴ・リグノルド(指)ラジオPO 録音:(1)1965年6月4日ルガーノ、テアトロ・クルサールRSI(スタジオ録音・モノラル)、 (2)1966年5月4日ヒルヴェルスム・スタジオAVRO(スタジオ録音・モノラル) |
|
||
| MELO CLASSIC MS-3018(2CD) |
ダニール・シャフラン/コンサート・ツアー・イン・ヨーロッパ (1)ドヴォルザーク:チェロ協奏曲ロ短調Op.104B 191 (2)シューマン:チェロ協奏曲イ短調Op.129 (3)シューマン:幻想小曲集Op.73 (4)シューベルト:アルペジオーネ・ソナタ イ短調D 821 (5)バッハ:無伴奏チェロ組曲第6番ニ長調BWV1012 (6)シュニトケ:古い様式の組曲 (7)ショスタコーヴィチ:チェロ・ソナタ ニ短調Op.40 |
ダニール・シャフラン(Vc) (1)アルヴィド・ヤンソンス(指)モスクワPO (2)ヤロスラフ・クロムホルツ(指)チェコRSO (3)(4)ハンス・アルトマン(P) (6)(7)アントン・ギンズブルグ(P) 録音:(1)1967年7月23日東ベルリン 、メトロポリタン・シアター、ドイツ放送協会(ライヴ・モノラル)、 (2)1973年5月22日プラハ、スメタナ・ホール(ライヴ・ステレオ)、 (3)(4)1959年11月09日ミュンヘン、スタジオBR(スタジオ録音・モノラル)、 (5)(6)(7)1982年5月20日プラハ、ドヴォルザーク・ホール(ライヴ・ステレオ) |
|
||
| Danacord DACOCD-888(2CDR) |
ラウニ・グランデールの遺産第8集 (1)ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲 イ短調 Op.53* (2)ヒンデミット:ウェーバーの主題による交響的変容 (3)ペーザー・グラム(1881-1956):ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op20(1919-20)** (4)グラム:序曲 ハ長調 Op.21(1935) (5)シベリウス:ヴァイオリン協奏曲(第1楽章に一部欠落あり)*** (6)シベリウス:交響曲第1番- 第1楽章・第3楽章・第4楽章 |
ヤロスラフ・スヒー(Vn)*、 ヴィリ・ケーア(Vn)*、 マックス・ロスタル(Vn)***、 ラウニ・グランデール(指)、 デンマークRSO (1)録音:952年12月11日 (ライヴ放送) (2)録音:1954年11月25日 ラジオ・オペラ 1952年12月11日 (ライヴ放送) (3)録音:1956年11月25日 (ライヴ放送) (4)録音:1950年9月28日 (ライヴ放送) (5)(6)録音:1950年12月7日 シベリウス85歳誕生日コンサート(ライヴ放送) |
|
||
| Signum Classics SIGCD-908(1CD) |
ヴィヴァルディ×22~フルート、オーボエ、ヴァイオリン、チェロのための二重協奏曲集 ヴィヴァルディ:協奏曲ハ長調 RV.557(2本のヴァイオリン、2本のオーボエ、2本のリコーダー、弦楽と通奏低音のための)/協奏曲ト短調 RV.531(2本のチェロ、弦楽と通奏低音のための)/協奏曲ハ長調 RV.533(2本のフルート、弦楽と通奏低音のための)/協奏曲ト長調 RV.516(2本のヴァイオリン、弦楽と通奏低音のための)/協奏曲ハ長調 RV.534(2本のオーボエ、弦楽と通奏低音のための)/協奏曲変ロ長調 RV.524(2本のヴァイオリン、弦楽と通奏低音のための)/協奏曲ヘ長調 RV.572「プロテウス、または、さかさまの世界」(Vn、チェロ、2本のフルート、2本のオーボエ、ハープシコード、弦楽と通奏低音のための |
ラ・セレニッシマ、 エイドリアン・チャンドラー(指,Vn) |
|
||
| BONGIOVANNI GB-5640(1CD) |
ヴィヴァルディ:ファゴット協奏曲全集 第2集 協奏曲 イ短調 RV500 協奏曲 ハ長調 RV469 協奏曲 ヘ長調 RV489 協奏曲 ニ短調 RV481 協奏曲 ハ長調 RV467 協奏曲 イ短調 RV497 協奏曲 ヘ長調 RV487 協奏曲 ハ長調 RV471 |
マウロ・モングッツィ(Fg)) スカラ座の弦楽奏者たち ジョヴァン ニ・ブロッロ(Cemb) 録音:2022年12月23日、2023年5月5日 |
|
||
 Treasures TRE-316(1CDR) |
ハンゼン/ベートーヴェン:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲第1番ハ長調 Op. 15* ピアノ協奏曲第3番ハ短調 Op. 37 |
コンラート・ハンゼン(P)、 ハインツ・ワルベルク*、イシュトヴァン・ケルテス(指) バンベルクSO、 録音:1960年頃(共にステレオ) ※音源:独OPERA St-3959*、St-3919 ◎収録時間:69:16 |
| “小手先の演出とは無縁のドイツ・ピアニズムの真髄!” | ||
|
||
| CPO CPO--555667(1CD) NX-C04 |
17-18世紀のホルン協奏曲集 ファッシュ:協奏曲 ニ長調 FWV L:D16 ハイニヒェン:シンフォニア ヘ長調 Seibel209 シュテルツェル(1690-1749):シンフォニア 変ホ長調 メルヒオール・ホフマン(1679頃-1715):協奏曲 変ホ長調 バッハ:われ心より至高なるものを愛する BWV174- シンフォニア グラウプナー(1683-1760):シンフォニア ニ長調 GWV511 ファッシュ:協奏曲 ニ長調 FWV L:D186番ニ短調 Op. 65No.6 |
シュテファン・カッテ(Hrn1/トロンバ・ダ・カッチャ) ゼバスティアン・フィッシャー(Hrn2/トロンバ・ダ・カッチャ) ラルパ・フェスタンテ(古楽器使用) シュテファン・カッテ(指) リーン・フォスカイレン(指) 録音:2021年1月11-13日 |
|
||
| ANTARCTICA AR-057(1CD) |
ロベール・グロロ:協奏曲集 ロベール・グロロ(b.1951):クラリネットと管弦楽のための協奏曲 Op.124 ピアノと管弦楽のための協奏曲 Op.35 ピアノと管弦楽のための協奏曲第2番 Op.125 |
ルーラント・ヘンドリックス(Cl)、 ヤン・ミヒールス(P) ブリュッセル・フィルハーモニック、 ロベール・グロロ(指) 録音:2014年-2023年(ベルギー) |
|
||
| DUX DUX-1796(1CD) |
アンビルド:ピアノ協奏曲 カロル・アンビルド(1925-2008):ピアノ協奏曲* ホーリークロス山脈のこだま ピアノと管弦楽のための狂詩曲* |
アルトゥル・ヤロン(P)*、 ヤツェク・ロガラ(指)、キエルツェSO |
|
||
| FONE FONE-2053(2CD) 完全数量限定盤 |
マダーマ宮殿のコンサート~クリスマス2000 ミケーレ・ノヴァーロ:イタリア国歌/ ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op.61 ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンス第2番ヘ長調 Op.50 交響曲第2番ニ長調 Op.36 コリオラン序曲 Op.62 |
サルヴァトーレ・アッカルド(Vn&指)、 イタリア室内O 録音:2000年12月、マダーマ宮殿(ローマ) |
|
||
| Eudora EUDSACD-2405(1SACD) |
故郷 グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調 Op.16 ファリャ:交響的印象「スペインの庭の夜」 |
ジュディット・ハウレギ(P)、 カスティーリャ・イ・レオンSO、 カスパール・ツェーンダー(指) 録音:2023年1月18日-20日、オーディトリオ・ミゲル・デリベス(バリャドリッド、スペイン) |
|
||
| BMC BMCCD-332(1CD) |
ペーテル・エトヴェシュ:フェルマータ、レスポンド、シフラ・プソディア ペーテル・エトヴェシュ(1944-2024):フェルマータ(アンサンブルのための)* レスポンド(独奏ヴィオラと32人の音楽家のための)** ピアノ協奏曲「シフラ・プソディア」*** |
ペーテル・エトヴェシュ(指)、 アンサンブル・コントルシャン*、 マーテー・スーチュ(Va)**、 コンチェルト・ブダペスト**、 ヤーノシュ・バラージュ(P)***、 ミクローシュ・ルカーチュ(ツィンバロム)***、 スイス・ロマンドO*** 録音:2022年4月6日(ジュネーヴ)&2023年3月24-25日(ブダペスト) |
|
||
| Audite AU-97816(1CD) |
バッハ・リコンストラクテッド 新ブランデンブルク協奏曲第1番~ソプラノ・リコーダー、オーボエ、ファゴット、弦楽合奏と通奏低音のための 1.Vivace(クリスマス・オラトリオ BWV248 第5部 冒頭の合唱曲より) 2-10.Aria with Variations1-8(イタリア風アリアと変奏 BWV989より) 11.Adagio ad libitum(即興演奏) 12.Presto(イタリア協奏曲 BWV971第3楽章より) 新ブランデンブルク協奏曲第2番~3つの弦楽三重奏と通奏低音のための 13.Allegro(3台のチェンバロのための協奏曲 BWV1064第1楽章より) 14.Adagio(3台のチェンバロのための協奏曲 BWV1064第2楽章より) 15.Allegro(3台のチェンバロのための協奏曲 BWV1064第3楽章より) 新ブランデンブルク協奏曲第3番~フラウトトラヴェルソ、変則調弦のヴァイオリン、リュート、弦楽合奏と通奏低音のための 16.Allegro(ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ BWV1029第1楽章より) 17.Adagio ma non tanto e dolce (三重協奏曲 BWV1044第2楽章、またはオルガンのためのトリオ・ソナタ BWV527の第2楽章より) 18.GavotteⅠ-GavotteⅡ(イギリス組曲第3番 第5楽章より) 19.Aria(アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳~「我が魂よ、とくと思いみよ」BWV509より) 20.Allegro(フランス風序曲 BWV831第8楽章より) |
ラ・フェスタ・ムジカーレ(ピリオド楽器オーケストラ) 録音:2022年10月18~21日/マリーエンミュンスター、シャフシュタール エグゼクティヴ・プロデューサー、レコーディング・プロデューサー:ルトガー・ベッケンホーフ(audite) |
|
||
| CLAVES 50-3080(1CD) |
ヴィスメール:ヴァイオリン協奏曲集 (1)ヴァイオリン協奏曲第1番(1942) (2)ヴァイオリン協奏曲第2番(1954) (3)ヴァイオリン協奏曲第3番(1987) |
オレグ・カスキフ(Vn/ジュゼッペ・グァルネリ・デル・ジェス製作)
シンフォニア・ヴァルソヴィア、アレクサンダー・マルコヴィチ(指) 録音:2023年9月/ポーランド放送局内第2スタジオ(ジュネーヴ) |
|
||
| Spectrum Sound CDSMBA-150(1CD) |
パリ国立高等音楽院の名教師たち (1)ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第9番「クロイツェル」 (2)パガニーニ:24のカプリス Op.1より第13~18番(6曲) (3)メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64 |
(1)ローラン・シャルミー(Vn)、フランソワー
ズ・ドロー(P) (2)ドゥヴィ・エルリー(Vn) (3)ジャン=ジャック・カントロフ(Vn)、 フランス国立O、 ポール・パレー(指) 録音:(1)1962年11月27日/フランス国立放送局内スタジオ(パリ)【モノラル】 (2)1967年5月12日/メゾン・ド・ラ・ラジオ内スタジオ120(パリ)【モノラル】 (3)1973年10月2日/オペラ=コミック座(パリ)【ステレオ/ライヴ】 |
|
||
| Solo Musica SM-458(1CD) NX-B06 |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第15番変ロ長調 K.450 ピアノ協奏曲第21番ハ長調 K.467 |
ツェン・ゼン(ピアン) トーマス・レスナー(指) マンハイム・プファルツ選帝侯室内O 録音:2023年7月21-22日 |
|
||
| Orchid Classics ORC-100301(1CD) NX-B06 |
ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲 イ短調 ニールセン(1845-1931):2つの幻想的小品 Op. 2FS8より - I. Andante con duolo ブルッフ:スコットランド幻想曲 Op.46 |
ボフダン・ルッツ(Vn) オーデンセSO アンナ・スクリレヴァ(指) 録音:2023年8月21-25日 |
|
||
| Orchid Classics ORC-100292(1CD) NX-B06 |
チャイコフスキー:ロココの主題による変奏曲 Op.33TH.57 ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104 |
ジョン=ヘンリー・クロフォード(Vc) サンフランシスコ・バレエO マーティン・ウェスト(指) 録音:2023年3月23-24日 |
|
||
| VOX VOXNX-3040CD(1CD) NX-B06 |
グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調 Op.16(1868)* 2つの抒情的小品 Op.68(1898-99) 古いノルウェーの歌と変奏 Op.51(1890/1900-05管弦楽編) 秋に Op.11(1866) |
グラント・ヨハネセン(P) ユタSO モーリス・アブラヴァネル(指) 録音:1975年2月-3月、1975年5月* |
|
||
| Pentatone PTC-5187230(1CD) |
(1)チェン・ガン/ヘ・チェンハオ:ヴァイオリン協奏曲「梁山伯と祝英台」(バタフライ・ラヴァーズ)(1959) (2)チェン・ガン(ヤン・リ・チン編):タシュクルガンの陽光(1976) (3)パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第1番ニ長調 Op.6(1815)【第1楽章のカデンツァ:エミール・ソー |
クロエ・チュア(Vn/グァダニーニ1753年製作)
(1)ジン・タ(Fl)、ウン・ペイ・シアン(Vc) (1)(2)ロドルフォ・バラーエツ(指)、(3)マリオ・ヴェンツァーゴ(指) シンガポールSO ライヴ録音:(1)(2)2023年9月9~11日/ヴィクトリア・コンサートホール(シンガポール)、 (3)2023年9月2日/エスパラネード・ホール(シンガポール) |
|
||
| Pentatone PTC-5187239(1CD) |
モーツァルト:フルート協奏曲第2番ニ長調 K.314 モーツァルト:フルート協奏曲第1番ト長調 K.313 ミスリヴェチェク:フルート協奏曲 ニ長調 |
アナ・デ・ラ・ヴェガ(Fl) イギリス室内O、ステファニー・ゴンリー(リーダー) 録音:2016年9月/ヘンリー・ウッド・ホール(ロンドン) |
|
||
| Linn CKD713(1CD) NX-C04 |
私たちの金継ぎ~管弦楽のための英国現代作品集 ジェイ・カッパーロールド(1989-):私たちの金継ぎ アンナ・クライン(1980-):彼女の腕の中で ジェイムズ・マクミラン(1959-):ゾエに捧ぐ オスカーの死 マーティン・サックリング(1981-):瞑想(ジョン・ダンに倣って) ピーター・マクスウェル・デイヴィス(1934-2016):ストロムネスへの別れ(ローズマリー・ファーニスによる弦楽合奏版) |
キャサリン・ブライアン(Fl) ヘンリー・クレイ(コーラングレ) ロイヤル・スコティッシュ・ナショナルO ロリー・マクドナルド(指) 録音:2022年1月18-20日、2024年2月9日スコットランド・スタジオ、UK |
|
||
| ALPHA ALPHA-942(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466(カデンツァ:オルガ・パシチェンコ) ピアノ協奏曲 第23番イ長調 K.488(カデンツァ: モーツァルト) |
オルガ・パシチェンコ(フォルテピアノ、リーダー) 使用楽器:ウィーンのアントン・ヴァルター1792年頃製作モデルに基づくポール・マクナルティ製作の再現楽器 イル・ガルデリーノ(古楽器使用) コンサートマスター:エフゲニー・スヴィリドフ(Vn) 録音:2021年6月6-9日コンセルトヘボウ、ブリュッヘ(ベルギー) |
|
||
| ALPHA ALPHA-1043(1CD) |
大家C.P.E.バッハと躍進期のモーツァルト C.P.E.バッハ:交響曲 ニ長調 Wq183-1/H663 チェンバロとフォルテピアノ〔と管弦楽〕のための協奏曲変ホ長調 Wq47/H479 モーツァルト:ディヴェルティメント ヘ長調 K.138(ザルツブルク交響曲第3番) ピアノ協奏曲 第17番ト長調 K.453 |
アレクサンドル・メルニコフ(フォルテピアノ) セリーヌ・フリッシュ(チェンバロ、フォルテピアノ) 「使用楽器」 フォルテピアノ:ウィーンのアントン・ヴァルター1795年製作モデルに基づくシュタウフェン・イン・ブレイスガウ(ドイツ)のクリストフ・ケルン2007年製作の再現楽器 チェンバロ:ベルリンのミヒャエル・ミートケ1710年製作モデルに基づくシュタウフェン・イン・ブレイスガウのクリストフ・ケルン2013年製作の再現楽器 カフェ・ツィマーマン(古楽器使用) パブロ・バレッティ(Vn&指揮) 録音:2023年1月 ベギン女子修道会教会、シント・トライデン(ベルギー東部リンブルフ州) |
|
||
| Dynamic CDS-8012(1CD) NX-B06 |
モーツァルト:アダージョとフーガ ハ短調 K. 546 協奏交響曲 変ホ長調 K.364 交響曲第27番ト長調 K.199 |
アレッサンドロ・ミラーニ(Vn) ルカ・ラニーエリ(Va) 新フェルッチョ・ブゾーニO マッシモ・ベッリ(指) 録音:2022年2月 Trieste(イタリア)、2022年5月 Sacile(イタリア)* |
|
||
| AAM Records AAM-45(1CD) NX-B10 NYCX-10475(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第25番ハ長調 K. 503 コンサートアリア「どうしてあなたを忘れられよう…心配しないで、愛する人よ」K. 505 ピアノ協奏曲第27番変ロ長調 K.595 ※K.503とK.595のカデンツァはロバート・レヴィンの即興による |
ルイーズ・オルダー(S) ロバート・レヴィン(フォルテピアノ) リチャード・エガー(指) アカデミー・オヴ・エンシェント・ミュージック ※使用楽器:フォルテピアノ:ウィーンのアントン・ヴァルター1795年製作をモデルとするベルギーのクリス・マーネの再現楽器。2018年製作 録音:2022年1月4-8日 St John’s Smith Square(UK) |
|
||
| Signum SIGCD-799(1CD) |
C.シューマン&グリーグ:ピアノ協奏曲集 クララ・シューマン:ピアノ協奏曲イ短調 Op.7 グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調 Op.16 |
アレクサンドラ・ダリエスク(P)、 ルー・ティエンイー(指)、フィルハーモニアO 録音:2023年9月11日-12日、セント・ジュード教会(ロンドン) |
|
||
| Glossa GCD-924703(1CD) XGCD-924703(1CD) 日本語解説付き国内盤 税込定価 |
SE4SONS~ヴィヴァルディ&ピアソラ:四季 1-12. ヴィヴァルディ:四季 Op.8Nos.1-4 13-16. ピアソラ:ブエノスアイレスの四季 |
リナ・トゥール・ボネ(バロックVn、指)、 ムジカ・アルケミカ(tr.1-12)、 クアルテート・アルケミコ(tr.13-16) 録音:2023年11月27日ー29日、ヴィラセカ音楽院(スペイン) |
|
||
| DUX DUX-2013(1CD) |
アダム・ヴェソウォフスキ:エンジェルズ アダム・ヴェソウォフスキ(b.1980):天体の踊り(シンフォニック・オーケストラのための) 天使たちの歌(弦楽オーケストラのための) 2本のフルートとシンフォニック・オーケストラのための協奏曲「大天使」* 天使たちと悪魔たち(シンフォニック・オーケストラのための) |
シレジアPO、ヤロスラフ・シェメト(指)、 アガタ・キエラル=ドゥウゴシュ(Fl)*、 ウカシュ・ドゥウゴシュ(Fl)* 録音:2023年8月29日-9月2日、シレジア・フィルハーモニック(ポーランド) |
|
||
| Eudora EUDSACD-2406(1SACD) |
神秘 フリアン・オルボーン(1925-1991):パルティータ第4番(Pと管弦楽のための交響的楽章) マヌエル・マルティネス・ブルゴス(b.1970):鐘(Pと管弦楽のための協奏曲)(世界初録音) |
ノエリア・ロディレス(P)、 ルーカス・マシアス(指)、オビエド・フィラルモニア 録音:2023年8月23日-25日&2024年1月31日-2月2日(スペイン) |
|
||
| BIS BISSA-2617(1SACD) |
プロコフィエフ:チェロ作品集 (1)チェロと管弦楽のための交響的協奏曲 ホ短調 Op.125 (2)無伴奏チェロ・ソナタ 嬰ハ短調 Op.134第1楽章「アンダンテ」(ヴラディーミル・ブロク補完) (3)チェロ・ソナタ ハ長調 Op.119 |
クリスチャン・ポルテラ(Vc) (1)ラハティSO、 アニヤ・ビールマイアー(指) (3)ユホ・ポホヨネン(P) 録音:(1)2021年3月12&13日シベリウスホール、ラハティ(フィンランド) (2)(3)2023年5月26~28日ライツターデル、ノイマルクト(ドイツ) |
|
||
| ONDINE ODE-1442(1CD) NX-B10 |
ガブリエル・エルコレカ(1969-):チェロ協奏曲、他 チェロ協奏曲「Ekaitza 嵐」(2012) 3つのミケランジェロのソネット(2009) ピアノ協奏曲「Piscis 魚」(2021-22) |
アシエル・ポロ(Vc) カルロス・メナ(C.T) フランソワ・カーディ(コルネット) ヌリア・サンロマ(コルネット) アルフォンソ・ゴメス(P) バスク国立O ファンホ・メナ(指) 録音:2023年9月4-8日 |
|
||
| TOCCATA TOCC-0708 NX-B06 |
マシュー・テイラー(1964-):管弦楽作品集 第2集 交響曲第6番Op.62(2021) オーボエ協奏曲 Op.60(2020-21) クラリネット協奏曲 Op.63(2021) ヴァイオリン小協奏曲 Op.52(2016) |
ジェイムズ・ターンブル(Ob) ポピー・ベドー(Cl) ミラ・マルトン(Vn) BBCウェールズ・ナショナルO マシュー・テイラー(指) 録音:2022年12月17-18日 ※全て世界初録音 |
|
||
| NoMadMusic NMM-119(1CD) |
スパーク・ライト マリー・ジャエル:ピアノ協奏曲第1番ニ短調 リスト:メフィスト・ワルツ第3番 ピアノ協奏曲第1番変ホ長調 |
セリア・オヌト・ベンサイド(P)、 デボラ・ワルドマン(指) アヴィニョン=プロヴァンスO 録音:2023年/アヴィニョン |
|
||
| Naive V-7957(1CD) |
バッハ:鍵盤協奏曲集 第1番ニ短調 BWV1052 第4番イ長調 BWV1055 曲第3番ニ長調 BWV1054 第5番ヘ短調 BWV1056 |
ティエンチ・ドゥ(P) ジョナサン・ブロックスハム(指) アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ(アカデミー室内O) 録音:2023年4月28-30日/LSO・セントルークス、イズリントン(ロンドン) |
|
||
| EUROARTS 30-73908(2DVD) 30-73904(Bluray) |
ドキュメンタリー:マルタ・アルゲリッチ『Bloody
Daughter』 【ボーナス】 ショパン:ピアノ協奏曲第1番ホ短調Op.11 ショパン:マズルカ ハ長調Op.24-2 シューマン:幻想小曲集Op.12-7『夢のもつれ』 |
【本編】(94分) マルタ・アルゲリッチ、リダ・チェン、アニー・デュトワ、ステファニー・アルゲリッチ、スティーヴン・コヴァセヴィッチ、ロバート・チェン、シャルル・デュトワ、ほか 監督:ステファニー・アルゲリッチ 製作:ピエール・オリヴィエ・バルデ、リュック・ピーター 【ボーナス】(54分) マルタ・アルゲリッチ(P) シンフォニア・ヴァルソヴィア ヤツェク・カスプシク(指) 収録:2010年8月27日、ワルシャワ・フィルハーモニー・コンサートホール 映像監督:ピエール=マルタン・ユバン ■DVD 画面:Full HD,16:9 音声:PCMステレオ、DD5.1、 DTS-HD MA5.1 リージョン:A l l BD50 字幕:英 仏 独 波 西 148分 ■Bluray 画面:N T S C ,16:9 音声:PCMステレオ、DD5.1、 DTS5.1 リージョン:A l l DVD9 字幕:英 仏 独 波 西 148分 |
|
||
| EUROARTS 20-68488(6DVD) |
マルタ・アルゲリッチBOX ■DVD1(94分) ドキュメンタリー:マルタ・アルゲリッチ『Bloody Daughter』 ■DVD2(54分) ショパン:ピアノ協奏曲第1番 ショパン:マズルカ ハ長調Op.24-2 シューマン:幻想小曲集Op.12-7『夢のもつれ』 ■DVD3(62分) (1)チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 (2)プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第3番 ■DVD4(120分) アルゲリッチ&バレンボイム/テアトロ・コロン凱旋公演 モーツァルト:2台ピアノのためのソナタ ニ長調K.448 シューベルト:創作主題による8つの変奏曲変イ長調D813 ストラヴィンスキー:春の祭典(2台ピアノ版) シューマン:2台ピアノのためのアンダンテと変奏Op.46 ラフマニノフ:組曲第2番Op.17~ワルツ カルロス・グアスタビーノ:バイレシート ミヨー:スカラムーシュ~ブラジレイラ ■DVD5(85分) シューマン:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第1番 イ短調 Op.105 プロコフィエフ:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第2番 ニ長調 Op.94 フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調 クライスラー:愛の悲しみ、美しきロスマリン ■DVD6(57分) 『プロメテウス』神話の様々な変奏~火の詩 監督:クリストファー・スワン ベートーヴェン:『プロメテウスの創造物』 Op.43より(導入部『嵐』/第1番/第9番/パストラーレ第10番) リスト:交響詩『プロメテウス』 スクリャービン:交響曲第5番『プロメテウス』 ノーノ:『プロメテオ』組曲 (1992)~ヘルダーリン |
マルタ・アルゲリッチ(P) ■DVD1(94分) 監督:ステファニー・アルゲリッチ ■DVD2(54分) シンフォニア・ヴァルソヴィア ヤツェク・カスプシク(指) 収録:2010年8月27日、ワルシャワ・フィルハーモニー・コンサートホール 映像監督:ピエール=マルタン・ユバン ■DVD3(62分) (1)マルタ・アルゲリッチ(P) ロイヤル・リヴァプールPO サー・チャールズ・グローヴス(指) 収録:1977年2月6日、プレストン、ギルド・ホール(ライヴ) (2)LSO アンドレ・プレヴィン(指) 収録:1977年5月3日、クロイドン、フェアフィールド・ホール(ライヴ) ■DVD4(120分) ウエスト=イースタン・ディヴァン・オーケストラ マルタ・アルゲリッチ(P) ダニエル・バレンボイム((指)ピアノ) 収録:2014年8月コロン劇場、ブエノスアイレス(ライヴ) ■DVD5(85分) ガイ・ブラウンシュタイン(Vn) マルタ・アルゲリッチ(P) 収録:2020年2月22日、ピエール・ブーレーズ・ホール、ベルリン(ライヴ) ■DVD6(57分) ベルリン・ジングアカデミー、 フライブルク・ゾリステンcho BPO、 クラウディオ・アバド(指) 収録:1992年5月23-25日、ベルリン、フィルハーモニー(ライヴ) 画面:NTSC,16:9(DVD3/4:3) 音声:PCM Stereo,DD5.1,DTS5.1 リージョン:All DVD9 字幕:英仏独波西 472分 |
|
||
| Goodies 78CDR-3941(1CDR) |
ドヴォルザーク:チェロ協奏曲ロ短調作品104 | ガスパール・カサド(Vc) ハンス・シュミット=イッセルシュテット(指) BPO 日TELEFUNKEN13622/26(独TELEFUNKEN1893/7 と同一録音) 1935年11月14日ベルリン録音 |
|
||
| Goodies 78CDR-3943(1CDR) |
ストラヴィンスキー:ピアノと管楽器のための協奏曲ニ長調(1923/4) | スリマ・ストラヴィンキー(P) フェルナン・ウーブラドゥ(指) パリ管楽器協会O 仏 DISQUES "GRAMOPHONE" DB11.105/6 1943年11月17日パリ、アルベール・スタジオ録音 |
|
||
| PARNASSUS PACL-95014(1CD) |
ウィリアム・プリムローズ~ヴィオラ・トレジャーズ (1)バルトーク:ヴィオラ協奏曲 (2)メンデルスゾーン:八重奏曲 変ホ長調 Op.20 (3)ウォルトン:ヴィオラ協奏曲 (4)パガニーニ(クライスラー編):「ヴァイオリン協奏曲第2番 ロ短調 Op.7第3楽章」より「カンパネラ」(プリムローズ編ヴィオラ版) (5)フォスター(ハイフェッツ編):金髪のジェニー(プリムローズ編ヴィオラ版) |
ウィリアム・プリムローズ(Va) (1)シェルイ・ティボール(指)、ニュー・シンフォニー・オーケストラ/録音:1951年 (2)ヤッシャ・ハイフェッツ(Vn)、イスラエル・ベイカー(Vn)、アーノルド・ベルニック(Vn)、ジョゼフ・ステパンスキー(Vn)、ヴァージニア・マジェフスキ(Va)、 グレゴール・ピアティゴルスキー(Vc)、ガーボル・レイト(Vc)/録音:1961年 (3)ウィリアム・ウォルトン(指)、フィルハーモニアO/録音:1946年 (4)ハリー・アイザックス(P)/録音:1937年 (5)不明(P) |
|
||
| Chandos CHSA-5346(1SACD) |
ブリッジ、フランシス=ホード、ウォルトン:チェロ協奏曲集 ブリッジ:悲歌的協奏曲 「祈り」 シェリル・フランシス=ホード(b.1980):チェロ協奏曲 「Earth, Sea, Air」(世界初録音) ウォルトン:チェロ協奏曲 |
ラウラ・ファン・デル・ハイデン(Vc) BBCスコティッシュSO、 ライアン・ウィグルスワース(指) 録音:2023年5月22日-24日、シティ・ホール(グラスゴー、スコットランド) |
|
||
| ALTO ALC-1483(1CD) |
クラシックス・フォー・クラリネット~クラリネット協奏曲集
モーツァルト:クラリネット協奏曲イ長調 K622* フランツ・クロンマー(1759-1831):クラリネット協奏曲変ホ長調 Op.36 ウェーバー:クラリネット小協奏曲ハ短調/変ホ長調 ハインリヒ・ヨーゼフ・ベールマン(1784-1847):クラリネットと弦楽のためのアダージョ ドビュッシー:第1狂詩曲 |
ジャック・ブライマー(Cl)、 ロイヤルPO*、 トーマス・ビーチャム(指)*、 ウィーン国立歌劇場O、 フェリックス・プロハスカ(指) 録音:1958年-1959年*&1966年 |
|
||
| ALPHA ALPHA-869(1CD) |
アビイ・ロード・コンチェルト ガイ・ブラウンシュタイン(1971-)作・編曲:アビイ・ロード・コンチェルト ヴォーン・ウィリアムズ: 揚げひばり ディーリアス:ヴァイオリン協奏曲 |
ガイ・ブラウンシュタイン(Vn) ベルギー王立リエージュPO アロンドラ・デ・ラ・パーラ(指) 録音:2021年11月 サル・フィラルモニーク、リエージュ、ベルギー |
|
||
| ALPHA ALPHA-1051(1CD) |
次世代ソリストたちによるモーツァルト Vol.
9 (1)協奏交響曲 変ホ長調 K.364(カデンツァ…モーツァルト) (2)ホルン協奏曲 第2番変ホ長調 K.417 (3) ピアノと管弦楽のためのロンド イ長調 K. 386(カデンツァ…アリエル・ラニ) (4) ピアノと管弦楽のためのロンド ニ長調 K. 382(カデンツァ…モーツァルト) |
(1)ユーハン・ダーレネ(Vn/ストラディヴァリウス1736年製「スペンサー・ダイク」) (1)アイヴィンド・リングスタッド(ヴィオラ/アンドレア・グァルネリ1676年製「コンテ・ヴィターレ」) (2)アレクサンドル・ザネッタ(ナチュラル・ホルン) (3)(4)アリエル・ラニ(P/ベーゼンドルファー) ザルツブルク・モーツァルテウムO ハワード・グリフィス(指) 録音:2021-2023年 オーストリア |
|
||
 APARTE AP-363(1CD) |
ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲【全楽章のカデンツァ:アンリ・ヴュータン】 ベートーヴェン(リスト編曲による管弦楽版):アンダンテ・カンタービレ(原曲:ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調 Op.97の第3楽章)* |
ベンヤミン・シュミット(Vn) マルティン・ハーゼルベック(指)、 ウィーン・アカデミーO ライヴ録音:2020年8月8日ブルックナーハウス、リンツ(オーストリア) 2022年10月24日ライディング・リスト音楽祭(オーストリア)* |
|
||
| Pentatone PTC-5187237(1CD) |
ベル・エポック ドビュッシー:第1狂詩曲 マンフレート・トロヤーン(1949-):ラプソディ~クラリネットとオーケストラのための(2002)【世界初録音】 ピエルネ:カンツォネッタ【イェーレ・タジンズ(1979-)編曲】 ブラームス:クラリネット・ソナタ第1番 ヘ短調 Op.120【ルチアーノ・ベリオ編曲】 ヴィドール:序奏とロンド Op.72【タジンズ編曲】 |
アンネリエン・ファン・ヴァウヴェ(Cl) アレクサンドル・ブロック(指)、 リール国立O 録音:2018年12月/ヌーヴォー・シエクル(リール) |
|
||
| CLAVES 50-307(1CD) |
フランツ・クサーヴァー・ヴォルフガング・モーツァルト(1791-1844):ピアノ協奏曲第1番(第3楽章のカデンツァ:アンドリー・ドラガン) ピアノ協奏曲第2番 |
アンドリー・ドラガン(P) ボグダン・ボジョヴィッチ(コンサートマスター)、 ヴィンタートゥール・ムジークコレギウム 録音:2023年10月/ヴィンタートゥール・シュタットハウス(スイス) |
|
||
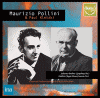 Spectrum Sound CDSMBA-010(1CD) |
マウリツィオ・ポリーニ追悼再発売 ブラームス:交響曲第3番ヘ長調 Op.90 ショパン:ピアノ協奏曲第1番ホ短調 Op.11 |
マウリツィオ・ポリーニ(P) フランス国立放送O、 パウル・クレツキ(指) ライヴ録音:1960年5月3日/シャンゼリゼ劇場(パリ) |
|
||
| BMOP SOUND BMOP-1095(1SACD) |
サミュエル・ジョーンズ(b.1935):協奏曲集
(1)フルート協奏曲(2018) (2)ヴァイオリン協奏曲(2014) (3)トロンボーン協奏曲「ヴィタ・アカデミカ」(2009) |
ギル・ローズ(指) ボストン・モダン・オーケストラ・プロジェクト (1)ジェフリー・ケーナー(Fl) (2)マイケル・リュドヴィッグ(Vn) (3)ジョセフ・アレッシ(Trb) 録音:(1)2021年11月29日、(2)(3)2020年1月12日 |
|
||
| BMOP SOUND BMOP-1096(1SACD) |
ナンシー・ガルブレイス(b.1951):協奏曲集 (1)フルート協奏曲(2019) (2)ヴァイオリン協奏曲第1番(2016) (3)打楽器協奏曲「万物は流れる」(2019) |
ギル・ローズ(指) ボストン・モダン・オーケストラ・プロジェクト (1)リンゼイ・グッドマン(Fl) (2)アリッサ・ワン(Vn) (3)アビー・ラングホースト(Perc) 録音:(1)2021年6月16日、(2)2021年11月29日、(3)2022年8月25日 |
|
||
| Orchid Classics ORC-100304(1CD) NX-B06 |
ベーラ・バルトーク:作品集 ヴィオラ協奏曲 Op. post(T. シェルイによる補筆完成版) ヴァイオリン協奏曲第1番Op. post ルーマニア民俗舞曲 Sz56、BB68(Y. ジスリンによるヴァイオリンと弦楽オーケストラ編) |
ユーリ・ジスリン(Vn/Va) ロシア国立シンフォニー・カペラ ヴァレリー・ポリャンスキー(指) 録音:2021年6月 |
|
||
| DUX DUX-2026(1CD) |
ペンデレツキ:協奏曲集 Vol.10 1. ヴァイオリン、ヴィオラ(Vc)と管弦楽のための二重協奏曲(ミシェル・ルティエクによるフルートとクラリネット版) 2. ホルン協奏曲 「冬の旅」(エヴァ・イェリンスカによるトロンボーン版) 3-8. フルート(Cl)と室内オーケストラのための協奏曲 |
パトリック・ガロワ(フルート/tr.1)、 ミシェル・ルティエク(クラリネット/tr.1)、 ヴォイチェフ・イェリンスキ(トロンボーン/tr.2)、 クシシュトフ・グジボフスキ(クラリネット/tr.3-8)、 イェジー・セムコフ・ポーランド・シンフォニア・ユヴェントゥスO、 マチェイ・トヴォレク(指) 録音:2023年12月9日ー10日&29日ー30日、ヴィトルト・ルトスワフスキ・ポーランド放送コンサート・スタジオ(ワルシャワ、ポーランド) |
|
||
| DUX DUX-20342035(2CD) |
マイ・ライフ...ショパン:ピアノ協奏曲集 ショパン:ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 Op.21 ピアノ協奏曲第1番ホ短調 Op.11 ※ユゼフ・ドムジャウ&ラドスワフ・ソプチャクによるオーケストレーション(2023) |
ラドスワフ・ソプチャク(P)、 ポドラシェ室内O、 カジミェシュ・ドンブロフスキ(指) 録音:2023年8月21日ー22日、イグナツィ・ヤン・パデレフスキ音楽学校コンサートホール、スタニスワフ・モニューシュコ・ポドラシェ歌劇場(ポーランド) |
|
||
| DUX DUX-2039(1CD) |
ポーリッシュ・ロマンティック・ワークス ~
ヴィエニャフスキ&ノスコフスキ ヴィエニャフスキ:ヴァイオリン協奏曲第1番嬰ヘ短調 Op.14(1853) ジグムント・ノスコフスキ(1846-1909):交響曲第2番ハ短調 「哀歌的」(1875-1879) |
ヴォイチェフ・ニェジュウカ(Vn)、 パヴェウ・プシトツキ(指)、 アルトゥール・ルービンシュタインPO 録音:2023年9月、クシシュトフ・ペンデレツキ・ヨーロッパ音楽センター・コンサート・ホール(ルスワヴィツェ、ポーランド) |
|
||
| NIFC NIFCCD-155156(2CD) |
ラスト・コンサート・イン・ポーランド ショパン:ピアノ協奏曲ヘ短調 Op.21 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 ショパン:ポロネーズ第6番変イ長調 Op.53「英雄」 |
アルトゥール・ルービンシュタイン(P)、 ウッチPO、ヘンリク・チシ(指) 録音:1975年5月30日、ウッチ・フィルハーモニック(ウッチ、ポーランド) ※レコーディング・スーパーヴィジョン:ポーランド放送(Polskie Radio) |
|
||
| ALIA VOX AVSA-9958(2SACD) |
ヴィヴァルディ:四季 [CD1] ・「四季」op.8~ソネットの朗読とともに〔協奏曲第1番「春」 ホ長調 RV269/協奏曲第2番「夏」 ト短調 RV 315 /協奏曲第3番「秋」 ヘ長調 RV293/協奏曲第4番「冬」 ヘ短調 RV297〕 ・ヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ヘ長調「プロメテウス、あるいは逆さまの世界」 RV544 ・海の嵐 RV253 [CD2] ・調和の霊感~4つのヴァイオリンのための協奏曲 ロ短調 RV580 ・ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 RV583より アンダンテ(第2楽章) ・「四季」 op.8~器楽のみ〔協奏曲第1番「春」 ホ長調 RV269/協奏曲第2番「夏」 ト短調 RV 315/協奏曲第3番 「秋」 ヘ長調 RV293/協奏曲第4番「冬」 ヘ短調 RV297〕 |
レ・ミュジシャン・デュ・コンセール・デ・ナシオン
ジョルディ・サヴァール(指) アルフィア・バキエヴァ(コンサートマスター/ヴァイオリン) オリヴィア・マネスカルキ(語り) 録音:2024年1月3-7日、カルドナ修道院 |
|
||
| EUROARTS 20-47347(2SACD) |
ラフマニノフ:ピアノ協奏曲全集、他 ピアノ協奏曲第2番ハ短調 Op.18 ピアノ協奏曲第3番ニ短調 Op.30 ピアノ協奏曲第1番嬰ヘ短調 Op.1 ピアノ協奏曲第4番ト短調 Op.40 パガニーニの主題による狂詩曲 |
ミハイル・プレトニョフ(P) ※使用楽器:Shigeru Kawai Grand Piano, SK-EX ケント・ナガノ(指) ラフマニノフ国際O アシスタント・コンダクター:ウラディスラ 録音:2023年10月、ロゼ・コンサート・ホール、ロール、スイス(ライヴ) |
|
||
| Profil PH-20055(4CD) |
エディション・シュターツカペレ・ドレスデンVol.48 カール・ベーム協奏曲集1938~1940 ■Disc1 (1)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調K.219「トルコ風」 (2)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番変ホ長調Op.73「皇帝」 ■Disc2 (1)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番ト長調Op.58 (2)同:ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.61 ■Disc3 (1)ブラームス:ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.77 (2)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番ハ短調Op.37 ■Disc4 (1)モーツァルト:ホルン協奏曲第3番変ホ長調K.447 (2)ブラームス:アノ協奏曲第2番変ロ長調Op.83 |
カール・ベーム(指) シュターツカペレ・ドレスデン ■Disc1 ヤン・ダーメン(Vn)(1)、 エドウィン・フィッシャー(P)(2) ■Disc2 ヴァルター・ギーゼキング(P)(1) 、 マックス・シュトループ(Vn)(2) ■Disc3 ヴォルフガング・シュナイダーハン(Vn)(1)、 リュプカ・コレッサ(P)(2) ■Disc4 マックス・ツィモロング(Hrn)(1)、 ヴィルヘルム・バックハウス(P)(2) 録音:Disc1:1938年6-7月(1)、1939年7-8月(2)、Disc2: 1939年(1)、1939年7-8月(2)、Disc3:1939年、Disc4: 1940年12月(1)、1939年5-6月(2)/ドレスデン・シュターツオーパー |
|
||
| H.M.F HMM-932075(1CD) |
ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 弦楽六重奏曲 第2番op.36 |
イザベル・ファウスト(Vn/'スリーピング・ビューティ'1704年ストラディヴァリウス)
[協奏曲]ダニエル・ハーディング(指)マーラー・チェンバー・オーケストラ [六重奏曲]イザベル・ファウスト、ユリア=マリア・クレッツ(Vn) ステファン・フェーラント、ポーリーヌ・ザクセ(Va)、クリストフ・リヒター 、シェニア・ヤンコビチ (Vc) 録音:[協奏曲]2010年2月(Sociedad Filarmonica(ビルバオ))、[六重奏曲]2010年9月(テルデックス・スタジオ(ベルリン)) |
|
||
| Capriccio C-5510(1CD) NX-B10 |
マリア・ヘルツ(1878-1950):ピアノ協奏曲/チェロ協奏曲/管弦楽作品集 ピアノ協奏曲 Op.4 大管弦楽のための4つの短い小品 Op.8 チェロ協奏曲 Op.10 管弦楽のための組曲 Op.13 |
オリヴァー・トリンドル(P) コンスタンツェ・フォン・グートツァイト(Vc) ベルリンRSO クリスティアーネ・ジルバー(指) 録音:2022年11月15-18日、2023年6月12-13日 全て世界初録音 |
|
||
| Channel Classics CCS-46624(1CD) NX-C04 |
ペルト、バッハ 作品集 バッハ:シンフォニア ~教会カンタータ「わが心に憂い多かりき」 BWV21 ペルト:タブラ・ラサ(1977) ペルト:B-A-C-Hの主題によるコラージュ(1964) バッハ:ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲 BWV1060R (2台のヴァイオリンによる) ペルト:シルーアンの歌(1991) |
シモーネ・ラムスマ(Vn) カンディダ・トンプソン(Vn、指) アムステルダム・シンフォニエッタ 録音:2020年-2023年 オランダ |
|
||
| Orchid Classics ORC-100291(1CD) NX-B06 |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 ブレット・ディーン(1961-):ピアノ協奏曲「グナイクセンドルフの音楽 - ある冬の旅」 |
ジョナサン・ビス(P) スウェーデンRSO ダーフィト・アフカム(指) 録音:2020年2月13-15日(ライヴ) |
|
||
| Pentatone PTC-5187202(1SACD) |
モーツァルト&プーランク:2台&3台ピアノのための協奏曲集 (1)モーツァルト:3台のピアノのための協奏曲ヘ長調K.242「ロードロン」 (2)モーツァルト:2台のピアノのための協奏曲変ホ長調K.365 (3)プーランク:2台のピアノのための協奏曲ニ短調 |
児玉麻里(第2ピアノ(1)(2)、第1ピアノ(3)) 児玉桃(第3ピアノ(1)、第1ピアノ(2)、第2ピアノ(3)) カリン・ケイ・ナガノ(第1ピアノ(1)) ケント・ナガノ(指)スイス・ロマンドO 録音:2023年3月/ヴィクトリア・ホール(ジュネーヴ) |
|
||
| DOREMI DHR-8231(2CD) |
ラドゥ・ルプーLIVE 第6集 (1)モーツァルト:ピアノ協奏曲第12番イ長調 K.414 (2)モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番ハ長調 K.467 (3)バッハ:平均律クラヴィーア曲集第1巻より 第22番変ロ短調 BWV867 (4)モーツァルト:ロンド イ短調 K.511 モーツァルト:ピアノ・ソナタ第10番ハ長調 K.330 モーツァルト:ピアノ・ソナタ第8番イ短調 K.310 ショパン:ピアノ・ソナタ第3番ロ短調 Op.58 ショパン:夜想曲 変ニ長調 Op.27-2 ショパン:夜想曲 嬰ハ短調 Op.27-1 |
ラドゥ・ルプー(P) (1)ガリー・ベルティーニ(指)ケルンRSO 録音:1976年5月ケルン (2)ガリー・ベルティーニ(指)北ドイツSO 録音:1977年1月17日ハンブルク (3)録音:1967年ブカレスト、エネスコ国際コンクール (4)録音:1987年10月16日東京 |
|
||
| Spectrum Sound CDSMBA-156(1CD) |
ORTFのステレオ技術 (1)サン=サーンス:ハバネラ Op.83 サン=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ (2)ラフマニノフ:チェロ・ソナタ ト短調 Op.19 (3)ラヴェル:左手のためのピアノ協奏曲 |
(1)ドゥヴィ・エルリー(Vn) ピエール・キャプドヴィエル(指)、フランス国立放送室内O 録音:1966年12月29日/メゾン・ド・ラ・ラジオ内スタジオ104【公開収録/ステレオ】 (2)ピエール・フルニエ(Vc)、ジャン・フォンダ(P) 録音:1980年3月17日/メゾン・ド・ラ・ラジオ内スタジオ124【セッション/ステレオ】 (3)ジャック・フェヴリエ(P) マニュエル・ロザンタール(指)、フランス国立放送O 録音:1960年1月26日/シャンゼリゼ劇場【ライヴ/ステレオ】 |
|
||
| Signum Classics SIGCD-791(1CD) |
シーズンズ・インタラプテッド シューベルト:4つの歌曲(トレイ・リー編曲/チェロとピアノ版)〔春に D.882、夏の夜 D.289、秋 D.945、凍った涙(冬の旅 D.911より)〕 ピアソラ:ブエノスアイレスの四季(トレイ・リー編曲/チェロと弦楽オーケストラ版) キルモ・リンティネン:チェロ協奏曲 |
トレイ・リー(Vc)、 ゲオルギー・チャイゼ(P)、 エミリア・ホーヴィング(指)、 イギリス室内O 録音:2023年5月、ロンドン&2023年8月、ベルリン |
|
||
| Hyperion CDA-68429(1CD) |
ロマンティック・ピアノ・コンチェルト・シリーズ
Vol.87~ライネッケ&ザウアー:ピアノ協奏曲集 ライネッケ(1824-1910):ピアノ協奏曲第3番ハ長調 Op.144、コンツェルトシュテュック Op.33 エミール・フォン・ザウアー(1862-1942):ピアノ協奏曲第2番ハ短調 Op.254 |
サイモン・キャラハン(P)、 ザンクト・ガレンSO、 モデスタス・ピトレナス(指) 録音:2023年5月22日-25日、トーンハレ・ザンクト・ガレン(スイス) |
|
||
| Avie AV-2662(1CD) |
イン・イヴニング・ライト ペーテリス・ヴァスクス(b.1946):ヴァイオリン協奏曲第2番「夕暮れの光の中で(イン・イヴニング・ライト)」(世界初録音) シューベルト(ポール・スーツ編):華麗なるロンド ロ短調 Op.70, D.895(Vnと弦楽版) ペーテリス・ヴァスクス:孤独な天使 |
セバスティアン・ボーレン(Vn)、 ミュンヘン室内O、 セルゲイ・ボルクホヴェツ(指) 録音:2023年9月27日-29日、昇天教会(ゼンドリンク、ミュンヘン) |
|
||
| Halle CDHLL-7562(1CDR) |
タバコヴァ:協奏曲集 ドブリンカ・タバコヴァ(b.1980):オルフェウスの彗星 ヴィオラと弦楽のための協奏曲* 組曲「地球」 チェロと弦楽のための協奏曲** |
デルヤナ・ラザロワ(指)ハレO、 マキシム・リザノフ(Va)*、 ガイ・ジョンストン(Vc)** 録音:2022年9月 |
|
||
| Lyrita SRCD-416(1CDR) |
イギリスのピアノ協奏曲集 ゴードン・ジェイコブ:ピアノ協奏曲第2番 変ホ長調(1957) ジョン・アディソン:ピアノと管弦楽のための変奏曲(1948) エドマンド・ラッブラ:ピアノ協奏曲 Op.30(1932)* |
サイモン・キャラハン(P)、 BBCウェールズ・ナショナルO、 スティーヴン・ベル(指)、ジョージ・ヴァス(指)* 録音:2022年4月&11月 |
|
||
| Ars Produktion ARS-38654(1CD) |
パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲集 (1)ヴァイオリン協奏曲第1番ニ長調 Op.6* (2)ヴァイオリン協奏曲第2番ロ短調 Op.7「ラ・カンパネラ」** (3)ヴァイグルの主題による変奏つきソナタ ホ長調 M.S.47*** |
マンリコ・パドヴァーニ(Vn) (1)オルテニアPO、ボリス・ペルノー(指) (2)ソウル・ギュリPO、ボリス・ペルノー(指) (3)スイス・イタリアーナO、ハワード・グリフィス(指) 録音(ライヴ):2012年10月(ルーマニア)*、2014年9月(韓国)**、録音日不詳(スイス)*** |
|
||
| ALPHA ALPHA-993(2CD) NX-E05 |
リゲティ作品集 【CD1】 1-5. ヴァイオリン協奏曲(1990-1992) 6-7. チェロ協奏曲(1966) 8-12. ピアノ協奏曲(1985) 【CD2】 1-4. 室内協奏曲 -13人の奏者のための(1969-1970) 5-6.2つの奇想曲 - ピアノのための(1947) 7-15.5つの小品 -4手ピアノのための(1942-1950) 16-21. 無伴奏ヴィオラのためのソナタ(1991-1994) 22-25. ホルン三重奏曲(1982) |
カン・ヘスン(Vn)…CD1/1-5 ルノー・デジャルダン(Vc)…CD1/6-7 ディミトリ・ヴァッシラキス(P)…CD1/8-12、CD 2/5-15 セバスティアン・ヴィシャール(P)…CD 2/7-15、22-25 ジョン・ストゥルツ(Va)…CD2/16-21 デイエゴ・トージ(Vn)…CD2/22-25 ジャン=クリストフ・ヴェルヴォワット(Hrn)…CD 2/22-25 アンサンブル・アンテルコンタンポラン ピエール・ブリューズ(指) 録音:2023年2月、6月 フィラルモニ・ド・パリ |
|
||
| ARCANA A-542(1CD+DVD) |
バッハ:ピアノ(Cemb)協奏曲 第1番-第5番 ピアノ協奏曲 第1番ニ短調 BWV1052 ピアノ協奏曲 第2番ホ長調 BWV1053 ピアノ協奏曲 第3番ニ長調 BWV1054 ピアノ協奏曲 第4番イ長調 BWV1055 ピアノ協奏曲 第5番ヘ短調 BWV1056 (以下、DVD及びデジタル配信のみ) イタリア協奏曲 ヘ長調 BWV971(アントニオ・ピオヴァーノ編曲/弦楽とピアノ版) |
ギル・ベ(P/ベーゼンドルファー) サンタ・チェチーリア音楽院弦楽合奏団 ルイジ・ピオヴァーノ(指) 録音:2021-2022年 CD…収録時間:80分 DVD…NTSC/All Region/16:9 リニアPCMステレオ 片面一層ディスク 収録時間:100分 |
|
||
| PROSPERO CLASSICAL PROSP-0083(1CD) |
モーツァルト:ホルン協奏曲集 第2番変ホ長調 K.417 第4番変ホ長調 K.495 第3番変ホ長調 K.447 第1番ニ長調 K.412 |
ジビュレ・マーニ(Hrn) アンドレアス・シュペリング(指) ブランデンブルクSO 録音:2023年 |
|
||
| Challenge Classics CC-72985(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第11~13番 協奏曲第11番ヘ長調 K.413 協奏曲第12番イ長調 K.414 協奏曲第13番ハ長調 K.415 |
ベン・キム(P;D584307) コンセルトヘボウ室内O 録音:2022年4月2日、2023年4月22-23日/ヒルフェルスム、MCO第1スタジオ |
|
||
| Pentatone PTC-5187325(1CD) |
メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64 チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35 |
アラベラ・美歩・シュタインバッハー(Vn/1716年製ストラディヴァリウス「ブース」)
シャルル・デュトワ(指) スイス・ロマンドO 録音:2014年9月22~24日/ヴィクトリア・ホール(ジュネーヴ) |
|
||
| Spectrum Sound CDSMBA-148(1CD) |
レジェンド・オブ・ザ・チェロ~フルニエ、シュタルケル、レヴィ (1)ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104 B.191 (2)ベートーヴェン:チェロ・ソナタ第2番 ト短調 Op.5-2 (3)チェレプニン:歌と踊り Op.74 |
(1)ヤーノシュ・シュタルケル(Vc)、シャルル・ブリュック(指)、フランス国立放送PO
(2)ピエール・フルニエ(Vc)、ジャン・フォンダ(P) (3) アンドレ・レヴィ(Vc)、エレーヌ・ボスキ(P) 録音:(1)1966年11月25日メゾン・ド・ラ・ラジオ内スタジオ104【ステレオ/公開収録】 (2)1980年3月17日メゾン・ド・ラ・ラジオ内スタジオ124【ステレオ/公開収録】 (3)1963年10月24日ブルダン・センター内スタジオ51【モノラル/セッション】 |
|
||
| Spectrum Sound CDSMBA-147(1CD) |
ドゥヴィ・エルリー~ザ・ライヴ・アーカイヴス・イン・フランス (1)ラロ:スペイン交響曲(第3楽章カット) (2)バッハ:ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ ホ短調 BWV1023 (3)ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」 |
ドゥヴィ・エ ルリー(Vn ) (1)マニュエル・ロザンタール(指)、フランス国立放送O (2)ロベール・ヴェイロン=ラクロワ(Cemb) (3)ブリジット・エンゲラー(P) 録音:(1)1956年5月10日、(2)1961年12月18日フランス国立放送局内スタジオ(パリ)【モノラル/公開収録】 (3)1981年3月5日メゾン・ド・ラ・ラジオ内スタジオ106【ステレオ/公開収録】 Previously unissued recordings Licensed by INA |
|
||
| Alba ABCD-477((1CD) |
フィンランドのアコーディオン協奏曲 ミンナ・レイノネン(1977-):Vyory(雪崩)(2021)(アコーディオンと弦楽オーケストラのための)* アウリス・サッリネン(1935-):協奏曲 Op.115(2つのアコーディオン、弦楽オーケストラと打楽器のための協奏曲)(2018-19)** ヴェリ・クヤラ(1976-):シェイプ=シフター(Shape-Shifter)(2018)(アコーディオンと弦楽オーケストラのための協奏曲)*** |
アンッティ・レイノネン(アコーディオン)* ソニヤ・ヴェルタイネン(アコーディオン)** ヤンネ・ヴァルケアヨキ(アコーディオン)** ペッテリ・ヴァリス(アコーディオン)*** オストロボスニア室内O トマス・ユープシェーバカ(指) |
|
||
| BIS BISSA-2715(1SACD) |
アドルフ・フォン・ヘンゼルト(1814-1889):ピアノ協奏曲 ヘ短調 Op.16 ハンス・ブロンサルト・フォン・シェレンドルフ(1830-1913):ピアノ協奏曲 嬰ヘ短調 Op.10 |
ポール・ウェー(P/Steinway D) スウェーデン室内O、 マイケル・コリンズ(指) 録音:2022年10月/エレブルー・コンサートホール(スウェーデン) |
|
||
| DOREMI DHR-8227(2CD) |
ラドゥ・ルプーLIVE 第5集 (1)ガーシュウィン:ピアノ協奏曲 ヘ長調 ラプソディ・イン・ブルー (2)アンドレ・チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第2番 Op.4 (3)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 Op.19 (4)ハイドン:ピアノ・ソナタ第50番ニ長調 Hob XVI:37 (5)ブラームス:ピアノ・ソナタ第3番へ短調 Op.5 シューベルト:ピアノ・ソナタ第13番 イ長調 D.664~第3楽章 アンダンテ |
ラドゥ・ルプー(P) (1)ディーン・ディクソン(指)フランクフルトRSO. 録音:1973年3月2日フランクフルト (2)ウリ・セガル(指)ロイヤルPO 録音:1975年10月28日ロンドン (3)エーリヒ・ラインスドルフ(指)CSO 録音:1978年1月12日シカゴ (4)録音:1988年9月ロンドン (5)録音:1980年10月新宿文化センター |
|
||
| MSR MS-1839(1CD) |
カゼッラ:ピアノと管弦楽のためのパルティータ レスピーギ:ピアノと管弦楽のためのトッカータ ラフマニノフ:パガニーニの主題によるラプソディ |
ジョシュア・ピアース(P) アントン・ナヌート(指) スロヴェニアRSO 録音:1991年4月9-11日 スロヴェニア |
|
||
| CPO CPO-555631(1CD) NX-C04 |
ウォルター・カウフマン(1907-1984):管弦楽作品集
第1集 ピアノ協奏曲第3番(1950)…第3楽章のカデンツァ:エリザヴェータ・ブルーミナ作 交響曲第3番(1936) インド交響曲(1943) 6つのインドの小品(1965) |
エリザヴェータ・ブルーミナ(P) ベルリンRSO デイヴィッド・ロバート・コールマン(指) 録音:2023年10月18-19日、2023年3月14-16日5 ※全て世界初録音 |
|
||
| Polskie Radio PRCD-22342235(2CD) 初紹介旧譜 |
ミェチスワフ・ホルショフスキ・イン・ポーランド
モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番ニ短調 KV466* バッハ:パルティータ第2番ハ短調 BWV826 モーツァルト:ピアノ・ソナタ第17番変ロ長調 KV570 シマノフスキ:20のマズルカ Op.50より 第13番~第16番 ショパン:ピアノ・ソナタ第3番ロ短調 Op.58 シューマン:子供の情景 より 「トロイメライ」 Op.15-7 メンデルスゾーン:無言歌集第6巻 より 「紡ぎ歌」 Op.67-4 アンナ・スクルスカによるミェチスワフ・ホルショフスキへのインタビュー** |
ミェチスワフ・ホルショフスキ(P)、 ポーランド国立RSO*、 ヤン・クレンツ(指)* 録音:1963年10月18日(カトヴィツェ)*、1984年5月6日/5月7日**(ワルシャワ) |
|
||
| NIFC NIFCCD-660(1CD) |
エリック・グオ~第2回ショパン国際ピリオド楽器コンクール・ライヴ
ショパン:ピアノ協奏曲第1番ホ短調 Op.11* 3つのマズルカ Op.59* ワルツ変イ長調 Op.42* |
エリック・グオ(ピリオド・ピアノ) {oh!} Orkiestra(オルキェストラ・ヒストリチナ)* ヴァーツラフ・ルクス(指)* ※使用楽器:プレイエル(1842年製) ※録音(ライヴ):2023年10月13日、ワルシャワ・フィルハーモニー・コンサート・ホール(/ファイナルステージ)、 2023年10月10日、ワルシャワ・フィルハーモニー・チェンバー・ホール(/第2ステージ)* |
|
||
| H.M.F HMM-902668(1CD) |
ブリテン:ヴァイオリン協奏曲&室内楽作品集 ヴァイオリン協奏曲 op.15(1939年、1958年改訂)* Reveille(起床ラッパ)(Vnとピアノ伴奏のためのコンサート・スタディ)(1937年) 組曲(1936年)# ヴァイオリン、ヴィオラとピアノのための2つの小品(1929年)【世界初録音】** |
全て、イザベル・ファウスト(Vn) ヤクブ・フルシャ(指)* バイエルンRSO* アレクサンドル・メルニコフ(P)#,** ボリス・ファウスト(Va)** 録音:2021年10月28-29日ライヴ*、 2022年4月、テルデックス・スタジオ(*以外) |
|
||
| PROSPERO CLASSICAL PROSP-0090(2CD) |
スイスの夢 ■CD1 ヨーゼフ・フランツ・クサーヴァー・ドミニク・スタルダー(1725-1765):交響曲 変ホ長調 ジャン・バティスト・エドゥアルド・デュピュイ(1770-1822):歌劇『若さと愚かさ』序曲 フランツ・クサヴァー・シュニーダー・フォン・ヴァルテンゼー(1786-1868):序曲 ハ短調 ハンス・フーバー(1852-1921):セレナード第2番『冬の夜』 ジョージ・テンプルトン・ストロング(1856-1948):組曲第3番『絵本』 ■CD2 ヘルマン・ズーター(1870-1926):ヴァイオリン協奏曲 イ長調 Op.23 パウル・フーバー(1918-2001):ダルシマーと弦楽合奏のための協奏曲 |
マイケル・バレンボイム(Vn) クリストフ・プフェンドラー(ダルシマー) レナ=リザ・ヴュステンドルファー(指) スイスO 録音:2019-2023年 |
|
||
 MELO CLASSIC MC-1076(9CD) ★ |
ヴィルヘルム・ケンプ/ライヴ・コンサート・エディション (1)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番ハ長調Op.15 ピアノ協奏曲第2番変ロ長調Op.19 ピアノ協奏曲第3番ハ短調Op.37 7つのバガテル―第1番変ホ長調Op.33-1 (2)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番ト長調Op.58 ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 シューベルト:即興曲変イ長調D.899-4,Op.90-41 (3)シューマン:ピアノ協奏曲イ短調Op.54 (4)モーツァルト:ピアノ協奏曲第27番 ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 ブラームス:間奏曲変ホ長調Op.117-1 (4)モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番 (5)モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番 (6)バッハ:フランス組曲第5番ト長調BWV816 モーツァルト:ピアノ・ソナタ第8番イ短調K.310 シューマン:交響的練習曲 シューベルト:4つの即興曲D.899,Op.90 ブラームス:ラプソディ第2番ト短調Op.79-2 ブラームス:カプリッチョロ短調Op.76-2 (7)モーツァルト:ピアノ協奏曲第15番 (8)モーツァルト:ピアノ四重奏曲第1番ト短調K.478 (9)ベートーヴェン:チェロ・ソナタ第5番ニ長調Op.102-2 ピアノ・ソナタ第32番ハ短調Op.111 6つのバガテルOp.126 (10)バッハ(ケンプ編):来なさい、異教徒の救い主よBWV659 ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第10番ト長調Op.96 ブラームス:ピアノ三重奏曲第1番ロ長調Op.8 |
全て、ヴィルヘルム・ケンプ(P) (1)ハインツ・レーグナー(指)シュターツカペレ・ベルリン 録音:1965年3月26日東ドイツベルリン(ステレオ) (2)ハインツ・レーグナー(指)シュターツカペレ・ベルリン 録音:1965年3月28日東ドイツベルリン(ステレオ) (3)ーリヒ・シュミット(指)ベロミュンスター放送O 録音:1962年1月24日スイスビール (4)ハインツ・レーグナー(指)シュターツカペレ・ベルリン 録音:1966年9月25日東ドイツベルリン(ステレオ) (5)ハンス・ミュラー=クライ(指)南ドイツRSO 録音:1955年7月21日西ドイツコスタンツ (6)カール・ミュンヒンガー(指)シュトゥットガルト・クラシッシェ・フィルハーモニー 録音:1969年11月21日西ドイツシュトゥットガルト(ステレオ) (7)録音:1963年10月7日東ドイツポツダム (8)オイゲン・ヨッフム(指)アムステルダム・コンセルトヘボウO 録音:1963年3月17日オランダアムステルダム (9)アマデウスQ 録音:フランスプロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏マントン (10)録音:1958年7月16日フランスピレネー=オリアンタル県プラド (11)シャンドール・ヴェーグ(Vn,Op.96,Op.8) パブロ・カザルス(Vc,Op.8) 録音:1958年7月17日フランスピレネー=オリアンタル県プラド ※ステレオ表記以外はモノラル 630'10 |
|
||
| ODRADEK RECORDS ODRCD-340(1CD) |
シェーンベルク:ピアノ協奏曲 Op.42(ライスによる室内オーケストラ伴奏編)
4つの歌曲 Op.22(グリースルによるピアノ五重奏伴奏編) 「グレの歌」―山鳩の歌(作曲者による室内オーケストラ伴奏編) 室内交響曲第1番Op.9 |
ミヒャエル・ツラビンガー(指) ヴィーナー・コンツェルト=フェライン ピーナ・ナポリターノ(P) イダ・アルドリアン(S)、クリストフ・フィラー(Br) 録音:2021年9月24-27日、2022年6月16-17 日、ウィーン |
|
||
| Orchid Classics ORC-100287(1CD) NX-B06 |
モーツァルト/ライネッケ/ニールセン:協奏曲集 モーツァルト:フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299 ライネッケ(1824-1910):フルート協奏曲 ニ長調 Op.283 ニールセン:フルート協奏曲 FS 119 |
アルベルト・ナヴァーラ(Fl) クラウディア・ルチア・ラマンナ(Hp) オーデンセSO ホリー・ヒョン・チェ(指) 録音:2023年1月16-20日 |
|
||
| Gramola GRAM-99287(1CD) |
モーツァルト:ホルン協奏曲全集 ホルン協奏曲第4番変ホ長調 K.495 ホルン協奏曲第1番ニ長調 K.412(386b)…第2楽章:フランツ・バイヤー編 ホルン協奏曲第3番変ホ長調 K.447 ホルン協奏曲第2番変ホ長調 K.417 ※K.495第1楽章&K.447第1楽章のカデンツァ…パウル・アンゲラー |
ハンスイェルク・アンゲラー(ナチュラルHrn) 使用楽器…1800年頃ボヘミア製 作者不詳 ザルツブルク・ホーフムジーク(古楽器オーケストラ) ヴォルフガング・ブルンナー(指) 録音:2006年4月10-12日 |
|
||
| ONDINE ODE-1429(1CD) NX-B10 |
ロルフ・ヴァリーン(1957-):作品集 Stride - オーケストラのために(2023) 2?5. Whirld - ヴァイオリンとオーケストラのために(2018) Spirit - エレクトリック・ベースギターと管弦楽のために(2017) .5つの季節 - 笙と管弦楽のために(2022) |
ウー・ウェイ(中国笙) エルドビョルク・ヘムシング(Vn) イダ・ニールセン(エレクトリック・ベースギター) スタヴァンゲルSO アンドリス・ポーガ(指) 録音:2022年6月15-17、2023年6月5-9日 |
|
||
| VOX VOXNX-3036CD(1CD) NX-B06 |
ショパン:ピアノと管弦楽のための作品全集
第2巻 ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 Op.21 モーツァルトの歌劇「ドン・ジョヴァンニ」の「お手をどうぞ」による変奏曲 変ロ長調 Op.2 演奏会用ロンド「クラコヴィアク」 Op.14 |
アビー・サイモン(P) ヘリベルト・バイセル(指) ハンブルクSO 録音:1972年ハンブルク(ドイツ) |
|
||
| BMOP SOUND BMOP-1093(1CD) |
ジョーン・タワー(b.1938):管弦楽作品集 ①ピアノ協奏曲「ベートーヴェンへのオマージュ」(1986) ②「ライジング」(2010)~フルートと管弦楽のための ③「赤いカエデ」(2013)~ファゴットと弦楽のための ④フルート協奏曲(1989) |
ギル・ローズ(指揮) ボストン・モダン・オーケストラ・プロジェクト ①マルク=アンドレ・アムラン(Pf) ②④キャロル・ウィンセンク(Fl) ③エイドリアン・モアジョン(Fg) 録音:①2021年9月10日、②2018年2月7日マサチューセッツ州 |
|
||
| Ars Produktion ARS-38647(1CD) |
ファビアン・ミュラー:協奏曲集 パン・フルート協奏曲(2017) ヘッケルフォーン協奏曲(2020)/大オーケストラのための「タラニス」 |
カスパール・ツェーンダー(指)、 ロイヤル・チェコ・シンフォニア・フラデツ・クラーロヴェー、 ハンスペーター・オジエ(パン・フルート)、 マルティン・フルティガー(ヘッケルフォーン) 録音:2023年2月 |
|
||
| Diapason DIAP-166(1CD) |
ヴァイオリン協奏曲集/ヤッシャ・ハイフェッツ (1)メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64 (2)ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 (3)ブルッフ:スコットランド幻想曲 Op.46 (4)サラサーテ:ツィゴイネルワイゼン |
ヤッシャ・ハイフェッツ(Vn) (1)シャルル・ミュンシュ(指)、ボストンSO 録音:1959年2月23日&25日 (2)マルコム・サージェント(指)、LSO 録音:1951年5月18日 (3)マルコム・サージェント(指)、オシアン・エリ録音:1961年5月15日&22日 (4)ウィリアム・スタインバーグ(指)、RCAビクターO 録音:1951年1月16日 |
|
||
| Danacord DACOCD-975(2CDR) |
バッハ:ブランデンブルク協奏曲集、他 (1)ブランデンブルク協奏曲第1番ヘ長調 BWV1046 (2)ブランデンブルク協奏曲第2番ヘ長調 BWV1047 (3)ブランデンブルク協奏曲第3番ト長調 BWV1048 より 第1楽章、第3楽章 (4)ブランデンブルク協奏曲第4番ト長調 BWV1049 (5)ブランデンブルク協奏曲第5番ニ長調 BWV1050 (6)ブランデンブルク協奏曲第6番変ロ長調 BWV1051 (7)ブランデンブルク協奏曲第3番ト長調 BWV1048 (8)ブランデンブルク協奏曲第3番ト長調 BWV1048 (9)トッカータとフーガ ニ短調 BWV565(アロイス・メリヒャル編) |
(1)BPO、アロイス・メリヒャル(指)、シモン・ゴールドベルク(Vn)、グスタフ・カーン(Ob) 録音:1932年 (2)BPO、アロイス・メリヒャル(指)、パウル・シュペッリ(Tp)、アルベルト・ハルツァー(Fl)、グスタフ・カーン(Ob)、シモン・ゴールドベルク(Vn)、ハンス・ボッタームント(Vc) 録音:1932年 (3)BPO、ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) 録音:1930年 (4)BPO、アロイス・メリヒャル(指)、ハインリヒ・ブライデン(Fl)、アルベルト・ハルツァー(Fl) 録音:1933年 (5)BPO、アロイス・メリヒャル(指)、ジークフリート・ボリース(Vn)、フリードリヒ・トーマス(Fl)、フランツ・ルップ(Cemb) 録音:1934年 (6)BPO、アロイス・メリヒャル(指)、ラインハルト・ヴォルフ(Va)、クルト・オーバーレンダー(Va)、パウル・グリュンマー(ヴィオラ・ダ・ガンバ)、シルヴィア・グリュンマー(ヴィオラ・ダ・ガンバ)、ヴォルフガング・クレーバー(Vc)、ヘルマン・メンツェル(Cb)、エータ・ハーリヒ=シュナイダー(Cemb) 録音:1934年 (7)ロイヤル・アルバート・ホールO、ユージン・グーセンス(指) 録音:1922or1923年 (8)ベルリン国立歌劇場O、ゲーオー・フベア(指) 録音:1924年 (9)BPO、アロイス・メリヒ |
|
||
| Melodiya x Obsession SMELCD-1002691(1CD) 初回生産限定 |
チャイコフスキー国際コンクールの優勝者たち
~諏訪内晶子、セルゲイ・スタドレル 1-3. パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第1番 4. ラヴェル:ツィガーヌ M.76 5. ショーソン:詩曲 Op.25 6. サン=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ |
諏訪内晶子(Vn/1-3) モスクワ国立SO(1-3) パヴェル・コーガン(指揮/1-3) セルゲイ・スタドレル(Vn/4-6) レニングラードPO(4-6) ウラディーミル・ポンキン(指揮/4-6) 録音:1-3.1990年7月4日、モスクワ音楽院大ホール(ライヴ録音/ADD/ステレオ) 4-6.1987年7月、レニングラード・フィルハーモニー協会大ホール(ADD/ステレオ) |
|
||
| Obsession CHSA-10078(2SACD) 初回生産限定 |
ラフマニノフ:ピアノ協奏曲全集&パガニーニの主題による狂詩曲
ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第1番嬰ヘ短調 Op.1/ピアノ協奏曲第2番ハ短調 Op.18 ピアノ協奏曲第3番ニ短調 Op.30 ピアノ協奏曲第4番ト短調 Op.40 パガニーニの主題による狂詩曲 Op.43 |
アール・ワイルド(P)、 ヤッシャ・ホーレンシュタイン(指)、 ロイヤルPO 録音:1965年 |
|
||
| Stradivarius STR-37258(1CD) |
カステルヌオーヴォ=テデスコ:ギター協奏曲第1番ニ長調Op.99(1039) モーゼス・イブン・エズラの詩集 Op.207~声とギターのためのソング・サイクル* |
ピエトロ・ロカット(G) ナディール・ガロファロ(指) エステSO ローニャ・ヴェイヘンマイヤー(S) * 録音:2023年2月8日フェラーラ、2022年3月12-13日ナポリ* |
|
||
| スロヴェニア放送 ZKP-118548(1CD) |
ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61 ロマンス第1番ト長調 Op.40 ロマンス第2番ヘ長調 Op.50 |
ジガ・ブランク(Vn) スラヴェン・クレノヴィチ(指) スロヴェニアRSO 録音:2023年9月 |
|
||
| CLAVES 50-3079(1CD) |
(1)ブロッホ:ヘブライ狂詩曲「シェロモ」 (2)ブルッフ:コル・ニドライ Op.47 (3)ドホナーニ:チェロと管弦楽のためのコンツェルトシュテュック ニ長調 Op.12 |
ティム・ポズナー(Vc) ベルンSO、カタリーナ・ミュルナー(指) 録音:2023年9月ディアコニアス教会(ベルン) |
|
||
| King International KKC-4341(1SACD) シングルレイヤー 日本語解説付国内盤 税込定価 |
プロムシュテット・ドレスデン・エテルナ・モーツァルト集成~モーツァルト:ホルン、フルート、オーボエ協奏曲集&ディヴェルティメント集 ホルン協奏曲第1番ニ長調 KV412(386b) ホルン協奏曲第2番変ホ長調KV417 ホルン協奏曲第3番変ホ長調KV447 ホルン協奏曲第4番変ホ長調KV495 ホルンと管弦楽のためのロンド変ホ長調KV371 フルート協奏曲第1番KV313(285c) フルート協奏曲第2番ニ長調KV314(285d) フルートと管弦楽のためのアンダンテハ長調KV315(285e) オーボエ協奏曲ハ長調KV314 ディヴェルティメント ニ長調KV136(125a) ディヴェルティメント 変ロ長調KV137(125b) ディヴェルティメント ヘ長調KV138(125c) アダージョとフーガ KV546 |
ペーター・ダム(Hrn) ヨハ ネス・ヴァルター(Fl) クルト・マーン(Ob) シュターツカペレ・ドレスデン ヘルベルト・ブロムシュテット(指) 録音日:[ホルン]1974年3月 [フルート&オーボエ]1973年2月、12月 [ディヴェルティメント]1976年11月 録音場所:ドレスデン・ルカ教会 |
|
||
| H.M.F HMX-2904104(2CD) ★ |
ロト&レ・シエクルのラヴェル ■CD1 (1)ピアノ協奏曲ト長調 (2)ドゥルシネア姫に思いを寄せるドン・キホーテ(全3曲) (3)2つのヘブライの歌 (4)なき王女のためのパヴァーヌ(P版) (5)マラルメの3つの詩 (6)左手のためのピアノ協奏曲 (7)聖女 ■CD2 (1)ムソルグスキー(ラヴェル編):展覧会の絵 (2)ラヴェル:ラ・ヴァルス |
フランソワ=グザヴィエ・ロト(指) レ・シエクル ■CD1(HMM902612) セドリック・ティベルギアン(P;1892年製プレイエル・グランパトロン)、 ステファーヌ・ドゥグー(Br) 録音:2020年12月/ピエール・ブーレーズ大ホール(1)(6)、2021年9月/フィラルモニ・ド・パリ(2)(3)(5)(7)、スタジオ(4) ■CD2(HMM905282) 録音:2019年11月フィルハーモニー・ド・パリ(ライヴ) |
|
||
| ALTO ALC-1488(1CD) |
ロージャ・ミクローシュ:ヴァイオリン協奏曲 ヴァイオリン協奏曲 Op.24 主題、変奏とフィナーレ Op.13A ハンガリー夜想曲 Op.28 ワイン醸造家の娘 Op.23A |
イゴール・グルップマン(Vn)、 ジェームズ・セダレス(指)、 ニュージーランドSO |
|
||
| ALPHA ALPHA-1005(1CD) NYCX-10456(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ヴィヴァルディ:四季、ラ・フォリア ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調 Op.8-3RV293「秋」 ヴァイオリン協奏曲 ヘ短調 Op.8-4RV297 「冬」 アリア 「太陽の強い輝きは」 ~歌劇「救われたアンドロメダ」 RV Anh.117* ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 Op.8-1RV269 「春」 ァイオリン協奏曲 ト短調 Op.8-2RV315「夏」 トリオ・ソナタ ニ短調 Op.1-12RV63「ラ・フォリア」 |
ポール=アントワーヌ・ベノス=ディアン(C.T)* ジュリアン・ショーヴァン(Vn) ル・コンセール・ド・ラ・ロージュ 録音:2023年2月 在仏イタリア大使館シチリア劇場、パリ ※国内仕様盤日本語解説…坂本龍右 |
|
||
| SWR music SWR-19141CD(1CD) NX-B09 |
ブゾーニ:ピアノ協奏曲 ハ長調 Op.39(1904) - ピアノと管弦楽、男声合唱のために | デイヴィッド・ライヴリー(P) バーデン=バーデン・フライブルクSWRSO フライブルク・ヴォーカルアンサンブル男声cho ミヒャエル・ギーレン(指) 録音:1990年2月13日ハンス・ロスバウト・スタジオ SWR、バーデン=バーデン(ドイツ) |
|
||
| ARCANA A-542(2CD+DVD) |
バッハ:ピアノ(Cemb)協奏曲 第1番-第5番 ピアノ協奏曲 第1番ニ短調 BWV1052 ピアノ協奏曲 第2番ホ長調 BWV1053 ピアノ協奏曲 第3番ニ長調 BWV1054 ピアノ協奏曲 第4番イ長調 BWV1055 ピアノ協奏曲 第5番ヘ短調 BWV1056 (以下、DVD及びデジタル配信のみ) イタリア協奏曲 ヘ長調 BWV971(A.ピオヴァーノ編曲/弦楽とピアノ版) |
ギル・ベ(P/ベーゼンドルファー) サンタ・チェチーリア音楽院弦楽合奏団 アントニオ・ピオヴァーノ(指) 録音:2021-2022年 CD…収録時間:80分 DVD…NTSC/All Region/16:9 リニアPCMステレオ 片面一層ディスク 収録時間:100分 |
|
||
| CPO CPO-555613(1CD) NX-C04 |
C. P. E. バッハ/J. G. グラウン:ヴィオラ協奏曲集 C.P.E.バッハ:チェロ協奏曲 変ロ長調 Wq171(マティス・ロシャによるヴィオラ編) ヨハン・ゴットリープ・グラウン(1703-1771):コンチェルタンテ ハ短調 Graun WV A:XIII:3- ヴァイオリン、ヴィオラと管弦楽のために グラウン:協奏曲 変ホ長調 Graun WV A:XIII:3- ヴィオラ、弦楽合奏と通奏低音のために |
マティス・ロシャ(Va) ステファン・ワーツ(Vn) カメラータ・シュヴァイツ ハワード・グリフィス(指) 録音:2022年7月7-9日 |
|
||
| CPO CPO-777975(1CD) NX-C04 |
フリードリヒ・エック(1767-1838):3つのヴァイオリン協奏曲 ヴァイオリン協奏曲第1番ホ長調 ヴァイオリン協奏曲第2番ト長調 ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 |
ターニャ・ベッカー=ベンダー(Vn) マンハイム・プファルツ選帝侯室内O ヨハネス・シュレーフリ(指) 録音:2016年11月15-18日 |
|
||
| AAM Records AAM-44(1CD) NX-B10 |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第6番 変ロ長調K.238 3台のピアノと管弦楽のための協奏曲第7番ヘ長調 K.242* ピアノ協奏曲第8番ハ長調 K.246 ※K.238とK.246のカデンツァはロバート・レヴィン作 |
ロバート・レヴィン(タンジェント・ピアノ) ヤ=フェイ・チュアン(フォルテピアノ)* ローレンス・カミングズ(Cemb/指)* ボヤン・チチッチ(指) アカデミー・オヴ・エンシェント・ミュージック ボヤン・チチッチ(リーダー) 録音:2022年5月3-7日 All Hallows, Gospel Oak 2022年7月2日 St Giles’ Cripplegate タンジェント・ピアノ:レーゲンスブルクのシュパート&シュマール1794年製作をモデルとするベルギーのクリス・マーネの再現楽器。2008年製作 フォルテピアノ:アウグスブルクのアントン・シュタイン1786年製作をモデルとするベルギーのクリス・マーネの再現楽器。2021年製作 チェンバロ:パリのパスカル・タスカン1769年製作をモデルとするマンチェスターのキース・ヒルの再現楽器。2010年製作 |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00842(1SACD) 税込定価 2024年2月21日発売 |
アンサンブルof トウキョウ ライヴ2023秋 (1)モーツァルト:セレナーデニ長調「セレナータ・ノットゥルナ」 (2)R.シュトラウス:オーボエ協奏曲ニ長調 (3)ウェーバー:ファゴット協奏曲ヘ長調 (Fg ダーク・イェンセン) |
アンサンブルof トウキョウ(指揮者無し)【青山聖樹(Ob)、ダーク・イェンセン
(Fg)、玉井菜採、戸原直(Vn)、大野かおる(Va)、渡邉玲雄(Cb)】 (1)玉井菜採(Vn)、戸原直(Vn)、大野かおる(Va)、渡邉玲雄(Cb) (2))青山聖樹(Ob) (3)ダーク・イェンセン(Fg) 録音:2023年10月27日東京、紀尾井ホール・ライヴ |
|
||
| Chandos CHAN-20286(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲集 Vol.9 モーツァルト:「後宮からの誘拐」序曲 ピアノ協奏曲 第11番ヘ長調 KV413* ピアノ協奏曲 第12番イ長調 KV414* ピアノ協奏曲 第13番 ハ長調 KV415* |
ジャン=エフラム・バヴゼ(P/YAMAHA CFX)*、 ガボル・タカーチ=ナジ(指)、 マンチェスター・カメラータ 録音:2023年4月4日-6日、ストーラー・ホール(ハンツ・バンク、マンチェスター) |
|
||
| Chandos CHSA-5333(1SACD) |
ブラームス&ブゾーニ:ヴァイオリン協奏曲集
ブゾーニ:ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op.35a, K243 ブラームス:ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op77 |
フランチェスカ・デゴ(Vn)、 ダリア・スタセフスカ(指)BBC響 録音:2023年7月4日-5日、フェニックス・コンサート・ホール(フェアフィールド・ホールズ、クロイドン、イギリス) |
|
||
| Spectrum Sound CDSMBA-149(1CD) 完全限定盤 |
ジャンヌ・ゴーティエ~フランス国営放送、未発表アーカイヴ (1)メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64 (2)クライスラー:パヴァーヌ (3)クライスラー:プニャーニのスタイルによる前奏曲とアレグロ (4)ヴィターリ:シャコンヌ (5)シューベルト:ピアノ三重奏曲第2番 変ホ長調 Op.100より第1&2楽章 |
ジャンヌ・ゴーティエ(Vn) (1)ピエール=ミシェル・ル・コント(指)リリック放送O (2)-(4)ユゲット・ドレフュス(Cemb) (5)フランス三重奏団【ジャンヌ・ゴーティエ(Vn)、アンドレ・レヴィ(Vc)、ジュヌヴィエーヴ・ジョワ(P)】 ライヴ録音:(1)1958年6月22日エラール・スタジオ31 (2)-(4)1956年7月7日モアザン・センター (5)1960年3月6日フランス・ラジオ・テレビ放送局内スタジオ(公開収録) |
|
||
| Spectrum Sound CDSMBA-161(1CD) 完全限定盤 |
フェリックス・アーヨに捧ぐ (1)ヴィヴァルディ:協奏曲集『四季』 (2)ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 RV210Op.8-11 (3)ロッシーニ:6つの四重奏のソナタより第3番 ハ長調 (4)バルトーク:ルーマニア民族舞曲 |
(1)(2)フェリックス・アーヨ(Vn独奏&コンサートマスター)、イ・ムジチ合奏団
(3)(4)フェリックス・アーヨ(コンサートマスター)、 イ・ムジチ合奏団 ライヴ録音:(1)1959年8月13日マントン【マントン音楽祭】 (2)(3)1958年7月9日ディボンヌ・レ・バン (4)1961年12月4日フランス・ラジオ・テレビ放送局内スタジオ(公開収録) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2312(1CD) |
(1)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 (2)マーラー:「さすらう若人の歌」 |
(1)エドウィン・フィッシャー(P) (2)ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(Br) ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)、 フィルハーモニアO 録音:(1)1951年2月19、20日アビーロード第1スタジオ(ロンドン) (2)1952年6月24、25日キングズウェイ・ホール(ロンドン) 使用音源:(1)Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) (2)Private archive (2トラック、19センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(セッション録音) |
|
||
| VOX VOXNX-3034CD(1CD) NX-B06 |
ドヴォルザーク:チェロ協奏曲、他 チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104B.191 森の静けさ Op.68No.5B.182)* ロンド ト短調 Op.94B.181* ロマンス ヘ短調 Op.11B.39# マズルカ ホ短調 Op.49B.90# |
ザラ・ネルソヴァ(Vc) ルッジェーロ・リッチ(Vn) セントルイスSO ヴァルター・ジュスキント(指) 録音:1974年5月15日、1974年5月*、1974年8月# |
|
||
| VOX VOXNX-3035CD(1CD) NX-B06 |
ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲、ピアノ協奏曲 ヴァイオリン協奏曲 イ短調 Op.53B. 108 ピアノ協奏曲 ト短調 Op.33B.63* |
ルッジェーロ・リッチ(Vn) ルドルフ・フィルクシュニー(P) セントルイスSO ヴァルター・ジュスキント(指) 録音:ミズーリ州セントルイス(USA) 1974年8月13日、1975年1月24日* |
|
||
| BIS BISSA-2665(1SACD) |
ヘンリク・ヘルステニウス(1963-):Public Behaviour(公的行動)(2020)(打楽器、6人の歌手と管弦楽のための協奏曲)* Together(ともに)(2021)(6人の歌手、ピアノ、サンプラーと打楽器のための)** |
ノルディック・ヴォイセズ トーネ・エリサベト・ブローテン(S)、イングリ・ハンケン(S)、エッバ・リュード(Ms)、ペール・クリスチャン・アムンドロー(T)、フランク・ハーヴロイ(Br)、ロルフ・マグネ・アッセル(Bs)、ハンス=クリスチャン・ショス・ソーレンセン(打楽器、ヴォイス)* エレン・ウゲルヴィーク(P)** ジェニファー・トレンス(打楽器、ヴォイス)** スタヴァンゲルSO * イラン・ヴォルコフ(指)* カイ・グリンデ・ミュラン(指)** |
|
||
| SUPRAPHON SU-4337(1CD) |
チェコのピアノ協奏曲3篇 (1)コヴァルジョヴィツ:ピアノ協奏曲 ヘ短調 Op.6(1887) (2)カプラーロヴァー:ピアノ協奏曲 ニ短調 Op.7(1935) (3)ボシュコヴェツ:ピアノ協奏曲第2番(1949) |
マレク・コザーク(P) プラハRSO、 ロベルト・インドラ(指) 録音:/(1)2022年1月4~6日、(2)2020年10月5&6日、(3)2022年11月9~11日/プラハ放送第1スタジオ |
|
||
| King International KKC-2717(1CD) 税込定価 |
外山雄三自作自演集Vol.2 (1)ヴァイオリン協奏曲第1番 (2)ヴァイオリン協奏曲第2番 (3)管弦楽のためのラプソディ |
森下幸路(Vn) 外山雄三(指)大阪SO 録音:2018年2月22日(1)、2019年11月21日(2)、2019年8月31日(3)/ザ・シンフォニーホール(すべてライヴ) |
|
||
| Avie AV-2650(1CD) |
夢~イザイ:ヴァイオリン作品集 ヴァイオリンと管弦楽のための協奏的詩曲(オーケストレーション:エリカ・ベガ/世界初録音) ヴァイオリン協奏曲ホ短調(第3楽章のオーケストレーション:グザヴィエ・ファルケス/全曲版世界初録音) ヴァイオリンとピアノのための2つのサロンのマズルカ Op.10 ヴァイオリンとピアノのための子供の夢 Op.14 |
フィリップ・グラファン(Vn)、 ロイヤル・リヴァプールPO、 ジャン=ジャック・カントロフ(指)、 マリサ・グプタ(P) 録音:2023年6月20日&21日、ザ・フライアリー(協奏曲)/2023年10月9日、ブリュッセル王立音楽院(デュオ) |
|
||
| Diapason DIAP-165(1CD) |
ラロ:チェロ協奏曲/スペイン交響曲 (1)チェロ協奏曲 ニ短調 (2)「ナムーナ」組曲第1番 (3)スペイン交響曲 |
(1)ピエール・フルニエ(Vc)、 ジャン・マルティノン(指)、ラムルーO 録音:1960年 (2)ポール・パレ―(指)デトロイトSO 録音:1958年 (3)レオニード・コーガン(Vn)、 キリル・コンドラシン(指)フィルハーモニアO 録音:1959年 |
|
||
| SUPRAPHON SU-4334(1CD) |
作曲家&指揮者ヴィクトル・カラビス (1)序曲「青春」 Op.7(1950)~大オーケストラのための (2)協奏曲「ストラヴィンスキーへのオマージュ」 Op.3(1948)~室内オーケストラのための (3)チェロ協奏曲 Op.8(1951/1956) |
(3)ミロスラフ・ペトラーシュ(Vc)) (1)(3)ヤナーチェクPO (2)ヤナーチェク室内O ヴィクトル・カラビス(指) 録音:(1)1984年1月16日、(2)1980年3月20&21日、(3)1979年2月23&24日/プラハ放送第1スタジオ |
|
||
| DOREMI DHR-8217(2CD) |
ラドゥ・ルプーLIVE 第3集 (1)モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番イ長調 K.488 (2)モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番ハ長調 K.467 (3)ベートーヴェン:合唱幻想曲 ハ短調 Op.80 (4)ショパン:夜想曲第7番嬰ハ短調 Op.27-1、夜想曲第8番 変ニ長調 Op.27-2、スケルツォ第1番ロ短調 Op.20 (5)ブラームス:間奏曲 変ロ短調 Op.117-2、イ短調 Op.118-1、イ長調 Op.118-2、変ホ短調Op.118-6 (6)ショスタコーヴィチ:ピアノ五重奏曲 ト短調 Op.57 (7)シチェドリン:フモレスケ |
ラドゥ・ルプー(P) (1)ルドルフ・ケンペ(指)ミュンヘンPO 録音:1974年3月6日ロンドン (2)ウリ・セガル(指)イギリス室内O 録音:1974年3月25日ロンドン (3)ローレンス・フォスター(指)ロイヤルPO 録音:1971年9月2日ロンドン (4)録音:1970年4月19日リーズ (5)録音:1973年3月5日ロンドン (6)ガブリエリSQ 録音:1973年3月5日ロンドン (7)録音:1974年12月9日ロンドン |
|
||
| King International KKC-116(1CD) 税込定価 |
菊池洋子&大阪SOのベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集Vol.1 ピアノ協奏曲第3番ハ短調Op.37(第1楽章カデンツァ=ライネッケ作) ピアノ協奏曲第4番ト長調Op.58(第1楽章カデンツァ=ベートーヴェン作、第3楽章カデンツァ=ブラームス作) |
菊池洋子(P) 山下一史(指)大阪SO 録音:2023年9月9日/ザ・シンフォニーホール(ライヴ) |
|
||
| ALBANY TROY-1948(1CD) |
「深淵の響き」~ジェフリー・マムフォード(b.1955):作品集 (1)「フィールドの展開・・・共鳴する光の深淵に響く」~チェロと管弦楽のための (2)「ビカミング・・・」~ピアノと管弦楽のための (3)ヴァイオリン協奏曲第2番「深まる春の青々とした斑点」 |
(1)クリスティーン・ランプレア(Vc) カゼム・アブドラ(指)デトロイトSO (2)ウィンストン・チョイ(P) マイケル・レワンスキー(指) アンサンブル・ダル・ニエンテ (3)クリスティーン・ウー(Vn) アレン・ティンカム(指) シカゴ・コンポーザーズ・オーケストラ 録音:(1)2017年3月4日デトロイト、(2)2021年6月 14日シカゴ、(3)2022年8月6日シカゴ |
|
||
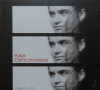 Polskie Radio PRCD-1721(7CD) ★ |
カヤ・ダンチョフスカ~アーカイヴァル・レコーディングズ
1974-2007 【CD1】 (1)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第1番変ロ長調 K.207* (2)メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調 Op.64* (3)ヴィエニャフスキ:ヴァイオリン協奏曲第2番ニ短調 Op.22* 【CD2】 (1)シマノフスキ:ヴァイオリン協奏曲第1番Op.35 シマノフスキ:ヴァイオリン協奏曲第2番Op.61 (2)カルウォヴィチ:ヴァイオリン協奏曲イ長調 Op.8 【CD3】 (1)ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第1番ト長調 Op.78 (2)ブラームス:クラリネット・ソナタ第2番変ホ長調 Op.120-2(Vn版) (3)パヌフニク:ヴァイオリン協奏曲 (4)ウェーベルン:ヴァイオリンとピアノのための4つの小品 Op.7* 【CD4】 (1)シマノフスキ:前奏曲ロ短調 Op.1-1(バツェヴィチ編曲/ヴァイオリンとピアノ版) シマノフスキ:ヴァイオリン・ソナタ ニ短調 Op.9 (2)シマノフスキ:バレエ 「ハルナシェ」Op.55より 舞曲(パヴェウ・コハンスキ編曲/ヴァイオリンとピアノ版) シマノフスキ:夜想曲とタランテッラ Op.28 シマノフスキ:アイタコ・エニアの子守歌 Op.52 (4)ショーソン:詩曲 Op.25(Vnとピアノ版)* (5)イザイ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番ニ短調 「バラード」 Op.27-3* 【CD5】 (1)ヴィエニャフスキ:ポロネーズ イ長調 Op.21* (2)ヴィエニャフスキ:伝説 Op.17* (3)イザイ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第4番ホ短調 Op.27-4* (4)イザイ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第5番ト長調 Op.27-5 (5)ショスタコーヴィチ:ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 Op.99* 【CD6】 (1)シューベルト:アヴェ・マリア D.839Op.52-6(ヴィルヘルミ編) エデ・ポルディーニ(1869-1957):踊る人形(クライスラー編) ブラームス:ワルツ 変イ長調 Op.39-15(デイヴィッド・ホクスタイン編) (2)アレクサンデル・ザジツキ(1834-1895):マズルカ ト長調 Op.26* (3)ラヴェル:ハバネラ形式の小品 (4)チャイコフスキー:「なつかしい土地の思い出」より メロディー変ホ長調 Op.42-3 (5)チャイコフスキー:ワルツ=スケルツォ ハ長調 Op.34* (6)ドビュッシー:レントより遅く(レオン・ロケ編) クライスラー:ウィーン奇想曲 Op.2 ドヴォルザーク:ユモレスク変ト長調 Op.101-7 フィビフ:詩曲 Op.41 (7)ヴィエニャフスキ:2つの性格的マズルカ Op.19* (8)グルック:歌劇 「オルフェオとエウリディーチェ」第2幕より メロディー(クライスラー編) (9)グラナドス:スペイン舞曲 ホ短調 Op.37-5(クライスラー編)* クライスラー:愛の悲しみ* クライスラー:美しきロスマリン* (10)バツェヴィチ:オベレク第1番* (11)ヴィエニャフスキ:クヤヴィアク イ短調* (12)ヴィエニャフスキ:スケルツォ=タランテッラ ト短調 Op.16* 【CD7】 フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調 シマノフスキ:神話 Op.30 シマノフスキ:歌劇 「ロジェ王」Op.46より ロクサナの歌(パヴェウ・コハンスキ編) シマノフスキ:クルピェの歌 Op.58 |
カヤ・ダンチョフスカ(Vn) 【CD1】 (1)カロル・テウチュ(指)、ワルシャワ国立フィルハーモニー室内O 録音:1974年4月7日、北ドイツ放送(ライヴ) (2)タデウシュ・ストルガワ(指)、ポーランド国立RSO 録音:1982年12月22日、ラジオ音楽館(カトヴィツェ) (3)アントニ・ヴィト(指)、ポーランド放送クラクフSO 録音:1981年2月27日、クラクフ・フィルハーモニー 【CD2】 (1)カジミエシュ・コルト(指)、ワルシャワ国立PO 録音:1996年2月21日、ワルシャワ・フィルハーモニー (2)アントニ・ヴィト(指)、ポーランド放送クラクフSO 録音:1978年12月22日、クラクフ・フィルハーモニー 【CD3】 (1)マヤ・ノソフスカ(P) 録音:1987年1月12日、ポーランド放送スタジオS-2(ワルシャワ) (2)マヤ・ノソフスカ(P) 録音:1987年1月13日、ポーランド放送スタジオS-2(ワルシャワ) (3)アグニェシュカ・ドゥチマル(指)、ポーランド放送ポズナン室内O(現ポーランド放送アマデウス室内O) 録音:1984年2月24日、アダム・ミツキェヴィチ大学講堂(ポズナン) (4)マヤ・ノソフスカ(P) 録音:1978年1月15日、ポーランド放送スタジオM-2(ワルシャワ) 【CD4】 (1)ユスティナ・ダンチョフスカ(P) 録音:2007年7月11日、ポーランド放送ヴィトルト・ルトスワフスキ・コンサート・スタジオ(ワルシャワ) (2)ユスティナ・ダンチョフスカ(P) 録音:2007年7月12日、ポーランド放送ヴィトルト・ルトスワフスキ・コンサート・スタジオ(ワルシャワ) (4)マヤ・ノソフスカ(P) 録音:1984年3月16日、RIAS(ベルリン) (5)録音:1975年12月13日、南ドイツ放送スタジオ(シュトゥットガルト) 【CD5】 (1)イェジ・サルヴァロフスキ(指)、ポーランド放送クラクフSO 録音:1978年1月24日、クラクフ・フィルハーモニー (2)イェジ・サルヴァロフスキ(指)、ポーランド放送クラクフSO 録音:1978年1月23日、クラクフ・フィルハーモニー (3)録音:1975年12月12日、南西ドイツ放送スタジオ(バーデン=バーデン) (4)録音:1977年1月12日、ワルシャワ (5)タデウシュ・ストルガワ(指)、ポーランド放送クラクフSO 録音:1981年1月12日-13日、クラクフ・フィルハーモニー 【CD6】 (1)ヤヌシュ・オレイニチャク(P) 録音:1980年6月15日、ワルシャワ・フィルハーモニー (2)マヤ・ノソフスカ(P) 録音:1976年6月27日、ポーランド放送スタジオ(ワルシャワ) (3)ヤヌシュ・オレイニチャク(P) 録音:1980年6月15日、ワルシャワ・フィルハーモニー (4)(5)ローター・ブロダック(P) 録音:1974年11月11日、RIAS(ベルリン) (6)ヤヌシュ・オレイニチャク(P) 録音:1980年6月15日、ワルシャワ・フィルハーモニー (7)マヤ・ノソフスカ(P) 録音:1978年1月15日、ポーランド放送スタジオM-1(ワルシャワ) (8)ヤヌシュ・オレイニチャク(P) 録音:1980年6月15日、ワルシャワ・フィルハーモニー (9)ユスティナ・ダンチョフスカ(P) 録音:2006年12月19日、ジェシュフ大学(ライヴ) (10)マヤ・ノソフスカ(P) 録音:1976年6月27日、ポーランド放送スタジオ(ワルシャワ) (11)ユスティナ・ダンチョフスカ(P) 録音:2006年12月19日、ジェシュフ大学(ライヴ) (12)マヤ・ノソフスカ(P) 録音:1976年6月27日、ポーランド放送スタジオ(ワルシャワ) 【CD7】 クリスチャン・ツィメルマン(P) 録音:1980年7月、ヘルクレス・ザール(ミュンヘン) *=初出音源 |
|
||
| Chandos CHSA-5340(1SACD) |
ストラヴィンスキー:ヴァイオリン協奏曲 ストラヴィンスキー:ヴァイオリン協奏曲 K053(1931)*/ロシア風スケルツォ K070(1945)/組曲第1番 K045(1925)/組曲第2番K038(1921)/ミューズを率いるアポロ K048(1927-28, revised1947) |
ジェームズ・エーネス(Vn)*、アンドルー・デイヴィス(指)、BBCフィルハーモニック 録音:2023年2月9日&13日、メディア・シティUK(サルフォード) |
|
||
| APR APRCD-5639(1CD) |
エリー・ナイ:プレイズ・ブラームス・アンド・シューベルト (1)ブラームス:ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 Op.83 (2)シューベルト:さすらい人幻想曲 D760 (3)シューベルト(エリー・ナイ編):「シューベルトの舞曲」より、 ドイツ舞曲 D783-1、ドイツ舞曲 D783-7、ドイツ舞曲 D783-10、グラーツのワルツ D924-6、感傷的なワルツ D779-13、ドイツ舞曲 D790-3、ワルツ D365-29、レントラー D734-14、ワルツ D365-36、ワルツ D365-33 |
エリー・ナイ(P) (1)マックス・フィードラー(指)、 アロイス・メリヒャル(指)*、BPO 録音:1939年6月1日-2日&5日&1940年4月29日* (2)録音:1942年5月21日 (3)録音:1942年5月21日 |
|
||
| Musikmuseum MMCD-13037(1CD) |
表彰台に立つ若きソリストたち~北チロルと南チロルの現代音楽作品集
マルティン・パチャイダー(b.1973):トランペットと管弦楽のための協奏曲(P無し) ミヒャエル・F.P.フーバー(b.1971): パーカッションと室内オーケストラのための小協奏曲 Op.56 ハンネス・ケルシュバウマー(b.1981):バセットホルンと室内オーケストラのための 「メラノキシロン」 フェリックス・レッシュ(b.1957):弦楽、パーカッションと独奏ツィターのための 「ラッジ」 マルティン・オアヴァルダー(b.1972):ゴー・ブロウ!4本のトランペットと室内オーケストラのための協奏曲 |
パトリック・ホーファー(Tp)、 ユリアン・グルーバー(パーカッション)、 ルカ・モランドゥッツォ(バセットホルン)、 アンドレアス・ヴェルクマイスター(ツィター)、 ガブリエル・グリッチュ(Tp)、 クレメンス・ネウ(Tp)、 ユリアン・リッチュ(Tp)、 マルクス・シュタイクスナー(Tp)、 チロル室内O、 ゲルハルト・ザマー(指) 録音:2012年-2015年 |
|
||
| Musikmuseum MMCD-13035(1CD) |
アル・カプリッチョ~ヤン・ツァハ:協奏曲&シンフォニア集 序曲ト短調/ハープシコード協奏曲ハ長調/フルート協奏曲ト長調/「主イエス・キリストの受難」 へのイントロドゥツィオーネ ホ長調/フルート協奏曲ニ長調/ハープシコード協奏曲ヘ長調/シンフォニア ト長調 |
ミュンヘン・バロックゾリステン、 ドロテア・ゼール(指) 録音:2016年 |
|
||
| Musikmuseum MMCD-13048(1CD) |
表彰台に立つ若きソリストたち Vol.2 マヌ・デラゴ(b.1984):Of Puppeteers and Marionettes(ジャズ・カルテットとオーケストラのための) ヨハンナ・ドーデラー(b.1969):アコーディオン協奏曲「大洋」 エリック・イウェイゼン(b.1954):Visions of Light(トロンボーンと室内オーケストラのための) マルティン・ライナー(b.1987):ハンガリー風変奏曲「Blickwinkel」(フルート、クラリネット、サクソフォンと室内オーケストラのための) アンドレア・オベルパーライター(b.1979):Egallopade(室内オーケストラのための) |
チロル室内O、 ゲルハルト・ザマー(指)、 HI5・ミニマル・ジャズ・チェンバー・ミュージック、 二コラ・ジョリチ(アコーディオン)、 ペーター・シュタイナー(Tb)、 サラ・ブブレグ(Fl)、 マルトン・ブブレグ(Sax)、 ベンセ・ブブレグ(Cl) 録音:2015年-2018年 |
|
||
| Musikmuseum MMCD-13047(1CD) |
ミヒャエル・F.P.フーバー:ピアノ協奏曲/交響曲第4番 ピアノ協奏曲 Op.61(ミヒャエル・ショッホに捧ぐ)* 交響曲第4番 Op.64** |
ミヒャエル・ショッホ(P)*、 マリア・ラドゥルナー(S)**、 カールハインツ・ジースル(指)、 聖ブラシウス・アカデミーO 録音:2016年&2017年、インスブルック |
|
||
| Obsession SMHQ-003(1CD) HQCD 完全限定生産 |
ヴィヴァルディ:リュート協奏曲&ソナタ集
リュート協奏曲ニ長調 RV93 ヴィオラ・ダモーレ協奏曲ニ短調 RV540 トリオ・ソナタ ト短調 RV85 トリオ・ソナタ ハ長調 RV82 |
ダーニエル・ベンケー(Lute)、ラースロー・バールソニ(ヴィオラ・ダモーレ)、ジュジャ・ペルティシュ(ハープシコード)、マリア・フランク(Vc)、ヤーノシュ・ロッラ(Vn)、ブダペスト・フランツ・リスト室内O フリジェシュ・シャーンドル(指) 録音:1978年/ADD |
|
||
| ALPHA ALPHA-1039(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲 第18番 変ロ長調 K.456 ピアノ協奏曲 第21番ハ長調 K.467(カデンツァ…ディヌ・リパッティ) |
ジョナタン・フルネル(P/ベーゼンドルファー) ザルツブルク・モーツァルテウムO ハワード・グリフィス(指) 録音:2023年2月22-24日アンジェラ・フェルストル・ザール、オルケスターハウス、ザルツブルク |
|
||
| Linn CKD742(1CD) |
イタリア組曲 ~ヴィヴァルディ、ソッリマ、ストラヴィンスキー ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 「ムガール大帝」 RV208 ジョヴァンニ・ソッリマ(1962-):ヴァイオリン、弦楽、リュートと打楽器のための協奏曲 「テュケー(運命の神)」 * ストラヴィンスキー(1882?1971):イタリア組曲(アンドレアス・フレックによる弦楽合奏、チェンバロ、ヴァイオリンのための編曲版) |
ヨニアン・イリアス・カデシャ(Vn) チャーツ・チェンバー・アーティスツ 録音:2022年12月8-11日 ボスヴィル旧教会、スイス |
|
||
| Linn CKD-736(1CD) |
トランペットによるヘンデル ~協奏曲とアリアによるトランペットのための再構成 ヘンデル/ジョナサン・フリーマン=アットウッド、ティモシー・ジョーンズ編曲:アリア「帰ってきて、私の愛しい大切な宝物」 ~歌劇「ロデリンダ」 HWV19 ソナタ 第1番ヘ長調 - 合奏協奏曲 ヘ長調 Op. 3-4HWV315による アリア「Nel passar da un laccio all’altro 罠から罠へ」~歌劇「アルゴスのジョーヴェ」 HWV A14 前奏曲、アルマンドとフーガ - クラヴサン組曲第1巻第3番 ニ短調 HWV428による ソナタ 第3番変ホ長調 - オルガン協奏曲 第13番 ヘ長調「カッコーとナイチンゲール」 HWV295 による アリア「あなたがどこを歩くとも」 ~オラトリオ『セメレ』 HWV58 アリア「愛らしさ、媚び、そして快活さ」 ~歌劇「アリオダンテ」 HWV33 二重唱「私の愛があなたの罪であるならば」~歌劇「エジプト王妃ベレニーチェ」 HWV38 ソナタ 第2番ヘ短調 - 合奏協奏曲 イ短調 Op. 6-4HWV322による アリア「あなたと一緒に、私は荒野を歩くだろう」 ~オラトリオ『ソロモン』 HMV67 二重唱「なにかしら、まだわからない」 ~歌劇「アレッサンドロ」 HWV21 ソナタ 第4番イ長調 - 二重協奏曲 HMV332 による 二重唱「汝、栄光に満ちた全能の息子よ」~オラトリオ『テオドーラ』 HWV68より アリア「なんてすてきな喜び」 ~歌劇「アグリッピーナ」 HWV6 |
ジョナサン・フリーマン=アットウッド(Tp) アンナ・シャウツカ(P) トム・フリーマン=アットウッド(Tp) 録音:2022年10月、2023年2月 英国王立音楽院、ロンドン |
|
||
| CD ACCORD ACD-329(1CD) NX-C09 |
モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第1番-第3番 ヴァイオリン協奏曲第1番変ロ長調 K.207 ヴァイオリン協奏曲第2番ニ長調 K.211 ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調 K.216 ※カデンツァは全てロベルト・クヴィアトコフスキ作 |
ロベルト・クヴィアトコフスキ(Vn/指揮) ポーランド・バルトPO 録音:2023年8月 |
|
||
| ORFEO C-220021(1CD) NX-C03 |
ブリテン:ヴァイオリン協奏曲/二重協奏曲 ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.15 二重協奏曲 ロ短調- ヴァイオリン、ヴィオラと管弦楽のための(1932)(C.マシューズによる完成版) |
バイバ・スクリデ(Vn) イヴァン・ヴクチェヴィチ(Va) ウィーンRSO マリン・オルソップ(指) 録音:2021年10月9-10日、2022年5月23日 |
|
||
| Capriccio C-5521(1CD) NX-B10 |
ヨーゼフ・ラーボア(1842-1924):左手のためのピアノ協奏曲集 小協奏曲 第1番(1915) - 左手ピアノとオーケストラのために 小協奏曲 第2番(1917) - 左手ピアノとオーケストラのために 小協奏曲 第3番(1923) - 左手ピアノとオーケストラのために |
オリヴァー・トリンドル(P) ラインラント=プファルツ州立PO ユージン・ツィガーン(指) 録音:2023年1月9-13日 |
|
||
| Solo Musica SM-425(1CD) NX-B03 |
ショパン:ピアノ協奏曲第1番ホ短調 Op.11 ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 Op.21* |
マルガリータ・ヘーエンリーダー(P…プレイエル
1848年製) ラ・シンティッラO リッカルド・ミナージ(指) ウィーン・アカデミーO* マルティン・ハーゼルベック(指)* 録音:2022年10月4-7日、2022年11月21-22日* ※SMLP431(LP)と同内容 |
|
||
| VOX VOXNX-3032CD(1CD) NX-B03 |
ショパン:ピアノ協奏曲第1番ホ短調 Op.11 ポーランドの歌による幻想曲 Op.13 アンダンテ・スピアナートと華麗な大ポロネーズ 変ホ長調 Op.2 |
アビー・サイモン(P) ハンブルクSO ヘリベルト・バイセル(指) 録音:1972年ハンブルク(ドイツ) |
|
||
| CPO CPO-555576(1CD) NX-B10 |
ウェーバー/クルーセル/ベルク:ファゴット協奏曲集 ウェーバー:ファゴット協奏曲 ヘ長調 Op.75 クルーセル(1775-1838):ファゴット協奏曲 変ロ長調 ウェーバー:アンダンテとハンガリー風ロンド Op.35 オラヴ・ベルク(1949-):ファゴット協奏曲 |
ダーグ・イェンセン(ファゴツト) カンマーアカデミー・ポツダム ダーグ・イェンセン(指) グレゴール・ビュール(指) 録音:2023年1月18-20日 |
|
||
| Gramola GRAM-99307(1CD) |
モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番-第5番 ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調 K.216 ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調 K.218 ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 K.219 ※カデンツァ…ベンヤミン・シュミット (K.216第2楽章のみダヴィッド・オイストラフ作) |
ベンヤミン・シュミット(指揮・ヴァイオリン) ムシカ・ヴィーテ室内O 録音:2022年8月31日-9月3日 |
|
||
| カメラータ CAMP-8022(1CD) 税込定価 2024年1月25日発売 |
パリとハープ~ハープ協奏曲集/シュース モーツァルト:フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299(297c)(カデンツァ:アンドレ・プレヴィン)* ドビュッシー:神聖な舞曲と世俗的な舞曲 ボイエルデュー:ハープ協奏曲 ハ長調[シングル・アクション・ハープ使用] サン=サーンス:演奏会用小品 作品154 |
マルギット=アナ・シュース(Hp) ※シングル・アクション・ハープ使用* カール=ハインツ・シュッツ(Fl)a ハンスイェルク・シェレンベルガー(指) ベルリンSO 録音:2021年9月 ほかベルリン(ドイツ) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2309(1CD) |
ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 「レオノーレ」序曲第2番* |
ジノ・フランチェスカッティ(Vn) ブルーノ・ワルター(指)コロンビアSO 録音:1961年1月23、26日、1960年7月1日*/ハリウッド、アメリカン・リージョン・ホール 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:ステレオ(録音セッション) |
|
||
| H.M.F HMX-2904095 (3CD+1BluRay) |
THE SCHUMANN TRILOGY~協奏曲&ピアノ三重奏全曲 ■CD シューマン: [CD1]ヴァイオリン協奏曲 WoO1ニ短調 ピアノ三重奏曲 第3番ト短調 op.110 [CD2]ピアノ協奏曲 イ短調 op.54 ピアノ三重奏曲 第2番ヘ長調 op.80 [CD3]チェロ協奏曲 イ短調 op.12 ピアノ三重奏曲第1番ニ短調op.63 ■Blu-Ray VIDEO~(120:41) シューマン:序奏、スケルツォと終曲 ホ長調 op.52 ピアノ協奏曲 イ短調 op.54 ヴァイオリン協奏曲 WoO1ニ短調 チェロ協奏曲 イ短調 op.12 |
イザベル・ファウスト(Vn/1704年製ストラディヴァリウス[スリーピング・ビューティー]) ジャン=ギアン・ケラス(Vc/ジョフレド・カッパ[1696年]) アレクサンドル・メルニコフ(フォルテピアノ/【協奏曲】1837年製エラール、 【ピアノ三重奏曲】ジャン=バティスト・シュトライヒャー(ウィーン,1847年)/いずれもエドヴィン・ボインク・コレクション) パブロ・エラス=カサド(指) フライブルク・バロック・オーケストラ(コンサートマスター:アンナ・カタリーナ・シュライバー) 録音:2014年5,8,9月、テルデックス・スタジオ・ベルリン/映像収録:2014年3月25日、ベルリン・フィルハーモニー |
|
||
| Hanssler HC-23057(1CD) |
ドヴォルザーク:ヴァイオリン作品集 ヴァイオリン協奏曲 イ短調 Op.53 ロマンス ヘ短調 Op.11~ヴァイオリンとオーケストラのための マズルカ ホ短調 Op.49~ヴァイオリンとオーケストラのための |
ミハイル・ポチェキン(Vn) スロヴァキアPO、 ダニエル・ライスキン(指) 録音:2023年5月2~5日/ブラチスラバ(スロヴァキア) |
|
||
| Challenge Classics CC-72983(1CD) |
ハイドン兄弟の協奏曲集 (1)ハイドン:ヴァイオリン協奏曲第4番 ト長調 Hob.VIIIa/4 (2)M・ハイドン:ヴィオラとチェンバロのための協奏曲 ハ長調 P55, MH41 ※カデンツァ作:寺神戸亮 |
寺神戸亮((1)Vn、(2)Va) 天野乃里子(Cemb、指) 「バロックの真珠たち」室内合奏団【[山縣さゆり(Vn)、迫間 野百合(Vn)、森田芳子(Va)、ルシア・スヴァルツ(Vc)、ロベルト・フラネンベルク(Cb)】 録音:2022年9月19-21日ハールレム、ドープスゲジンデ教会 |
|
||
| EDITION ABSEITS EDA-48(1CD) |
エコール・ド・パリ イベール:チェロと木管のための協奏曲(1925) マルセル・ミハロヴィチ:ピアノ、木管、チェレスタと打楽器のための2部のエチュード (1951) アンタイル:室内オーケストラのための協奏曲(1932) シモン・ラクス:ピアノ、木管と打楽器のための室内協奏曲(1963) |
アデ ル・ビッター(Vc) ホルガー・グロショップ(P) ヨハネス・ズール(指) ベルリン・ドイツSOのメンバー 録音:2021年4月3日/ベルリン放送 |
|
||
| Goodies 78CDR-3926(1CDR) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第22番変ホ長調 K.482 | エトヴィン・フィッシャー(P) ジョン・バルビローリ(指)管弦楽団 英HIS MASTER'S VOICE DB2681/4 1935年6月6日ロンドン、アビー・ロード EMI第1スタジオ録音 |
|
||
| Goodies 78CDR-3927(1CDR) |
サン=サーンス:チェロ協奏曲第1番イ短調 作品33 | ピエール・フルニエ(Vc) ワルター・ジュスキン(指) フィルハーモニアO 英 HIS MASTER'S VOICE DB6602/03 1947年9月29&30日ロンドン、アビーロード EMI第1スタジオ録音 |
|
||
| Goodies 78CDR-3928(1CDR) |
R.シュトラウス:オーボエ協奏曲ニ長調(1945-6) | レオン・グーセンス(Ob) アルチェオ・ガリエラ(指) フィルハーモニアO 英 COLUMBIA DX1444/6 1947年9月15&23日ロンドン、アビー・ロード EMI第1スタジオ録音 |
|
||
 Hanssler HC-23065(1CD) |
グレーテ・フォン・ツィーリッツ作品集 (1)日本の歌(1919)(全10曲) (2)死のヴァイオリン(死の舞踏)(1953/7)~ヴァイオリン、ピアノと管弦楽のための (3)2本のトランペットのための二重協奏曲(1975) |
ゾフィー・クルスマン(S)(1)、 ニーナ・カーモン(Vn)(2)、 オリヴァー・トリンドル(P)(2)、 イエルーン・ベルワルツ、アンドレ・ショッホ(Tp)(3) ヤーコプ・ブレンナー(指) シューマンPOー 録音:2023年7月12-14日/ヘムニッツ・シュターツハレ |
|
||
| BIS BISSA-2657(1SACD) |
ストラヴィンスキー、マルティヌー、バルトーク ストラヴィンスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 バルトーク:狂詩曲第1番BB94b 狂詩曲第2番BB96b マルティヌー:ヴァイオリンと管弦楽のための協奏的組曲 H276a(第2稿版) 瞑想曲~ヴァイオリンと管弦楽のための協奏的組曲 H276(初稿版)より第2楽章 |
フランク・ペーター・ツィンマーマン(Vn/ストラディヴァリウス「レディ・インチクイン」(1711年製))
バンベルクSO、 ヤクブ・フルシャ(指) 録音:(4)2021年6月30日~7月1日、(2)(3)(5)2021年12月20~22日、(1)2022年9月28&29日コンツェルトハレ・バンベルク(ヨーゼフ・カイルベルト・ザール) |
|
||
| DOREMI DHR-82(2CD) |
クリスチャン・フェラスLIVE 第3集 (1)シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.47 (2)ロドリーゴ:ヴァイオリン協奏曲『夏の協奏曲』 (3)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲 第4番 ニ長調 K.218 (4)ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第9番 イ長調 『クロイツェル』 Op.47 (5)エネスコ:ヴァイオリン・ソナタ第3番 イ短調 Op.25 シューマン:ヴァイオリン・ソナタ第2番 ニ短調 Op.121 |
クリスチャン・フェラス(Vn) (1)ズービン・メータ(指)フランス国立放送O 録音:1965年5月26日パリ (2)アタウルフォ・アルヘンタ(指)フランス国立O 録音:1951年4月4日パリ (3)ピエトロ・アルジェント(指)スカルラッティO 録音:1958年11月21日ナポリ(放送用ライヴ) (4)ピエール・バルビゼ(P) 録音:1961年5月24日パリ、シャンゼリゼ劇場 (5)ピエール・バルビゼ(P) 録音:1959年9月25日エットリンゲン城 |
|
||
| Biddulph BIDD-85040(1CD) |
ハイフェッツ コルンゴルト/カステルヌオーヴォ=テデスコ:ヴァイオリン協奏曲
他 (1)コルンゴルト:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35 (2)シンンディング:古風な様式の組曲 Op.10 (3)ブラームス:ハンガリー舞曲第7番(ヨアヒム編) (4)チャイコフスキー:憂鬱なセレナード Op.26 (5)ラヴェル:ツィガーヌ (6)カステルヌオーヴォ=テデスコ:ヴァイオリン協奏曲第2番「予言者」 Op.66 |
ヤッシャ・ハイフェッツ(Vn) ロサンゼルスPO アルフレッド・ウォーレンスタイン(指) 録音/初出レコード番号: 1953年1月10日 RCA Victor LM1782(1) 1953年12月9日 RCA Victor LM1832(2) 1953年12月9日 RCA Victor LSC3232(3) 1954年10月29日 RCA Victor LM2027(4) 1953年12月8日 RCA Victor LM1832(5) 1954年10月28&29日 RCA Victor LM2050(6)12 |
|
||
| Gramola GRAM-99308(1SACD) NX-C01 |
ハイドン:ヴァイオリン協奏曲集/二重協奏曲 ヴァイオリン協奏曲 ハ長調 Hob.VIIa:1 ヴァイオリン協奏曲 ト長調 Hob.VIIa:4 ヴァイオリン、鍵盤楽器と弦楽オーケストラのための二重協奏曲 ヘ長調 |
トーマス・アルベルトゥス・イルンベルガー(Vn) バルバラ・モーザー(フォルテピアノ) ミュンヘン・カンマーフィルハーモニー・ダカーポ フランツ・ショットキー(指) 録音:2022年3月15-17日、2022年5月31日-6月1日 |
|
||
| MPR MPR-006(1CD) |
ベンジャミン・エリン(1980-):トロンボーン作品集 パンドラ (トロンボーンと管弦楽のための) ストー・スケッチ (3本のトロンボーンのための) グレズリー(バス・トロンボーンと管弦楽のための) ウィンドウズ (3本のトロンボーンと管弦楽のための) |
ジョセフ・アレッシ(Tb) クリスチャン・ジョーンズ(トロンボーン、バス・トロンボーン) ブレア・シンクレア(Tb) オペラ・ノースO ベンジャミン・エリン(指) 録音:2022年11月22-24日 マントル・ミュージック・スタジオ、 ハワード・オペラ・センター、オペラ・ノース、リーズ、UK |
|
||
| Danacord DACOCD-929(2CDR) |
トマス・イェンセンの遺産 第19集 (1)ニールセン:フルート協奏曲 FS119CNW42 (2)ニールセン:ヴァイオリン協奏曲 FS61(Op.33) (3)ニールセン:サガの夢(Saga-Drom) FS46 CNW35(Op.39) (4)ニールセン:愛の賛歌 FS21CNW100(Op.12) (5)ヨハネス・フレゼリク・フレーリク(1806-1860):祝祭音楽「エーリク・メンヴェズの子供時代」 (6)ヨハン・ペーター・エミーリウス・ハートマン(1805-1900):序曲「ユルサ」 Op.78 (7)ニールセン:歌劇「仮面舞踏会」 FS39(抜粋) (8)アイナー・ヤコブセン(1897-1970):交響曲第1番「今」 (9)スヴェン・エーリク・タープ(1908-1994):季節の変わり目 Op.46 (10)ポウル・シアベク(1888-1949):ユラン(男声合唱と管弦楽のための) |
トマス・イェンセン(指)、デンマークRSO (1)ポウル・ビアケロン(Fl) 録音:1958年5月29日 ティボリ公園(コペンハーゲン)(ライヴ放送) (2)アーネ・カレツキ(Vn) 録音:1962年4月19日 (ライヴ放送) (3)録音:1961年1月12日 (ライヴ放送) (4)ルト・グルベク(S)、エレン・マグレーデ(Ms)、ニルス・ブリンカー(T)、ニルス・ムラー(T)、ホルガー・ヌアゴー(Bs)、ニルス・ユール・ボンド(Bs)、デンマーク放送児童cho、デンマーク放送cho 録音:1958年5月29日 ティボリ公園(コペンハーゲン)(ライヴ放送) (5)録音:1958年1月12日 (ライヴ放送) (6)録音:1958年1月12日 (ライヴ放送) (7)録音:1954年4月 スタジオ録音[Decca BR3111] (8)録音:1960年8月13日 (ライヴ放送) (9)録音:1958年1月12日 (ライヴ放送) (10)録音:1961年8月18日 (ライヴ放送) |
|
||
| Ars Produktion ARS-38365(1SACD) |
ラフマニノフ生誕150周年に捧ぐ~ピアノ作品集
ラフマニノフ:楽興の時 Op.16 リラの花 Op.21-5/ひなぎく Op.38-3 クライスラー(ラフマニノフ編):愛の悲しみ 前奏曲 Op.23-6 フランツ・べーア(ラフマニノフ編):W.R.のポルカ/前奏曲 Op.23-4 ピアノ協奏曲第2番Op.18 |
ショレナ・ツィンツァバーゼ(P)、 ヴァクタン・ジョルダニア(指)、 ロシア・フェデラル・オーケストラ 録音:2023年8月、インマヌエル教会(ヴッパータール、ドイツ) |
|
||
| Signum Classics SIGCD-789(2CD) |
アースサイクル 伝承曲(ジャッキー・オーツ&デイヴィッド・ル・ページ編):The Birds in the Spring デヴィッド・ゴードン:Windigo (or Gradually then Suddenly) ヴィヴァルディ:協奏曲第1番ホ長調 Op.8-1, RV269「春」 伝承曲(ジャッキー・オーツ&デイヴィッド・ル・ページ編):The Lark in the Morning デヴィッド・ゴードン:The Elephant and the Moth ヴィヴァルディ:協奏曲第2番ト短調 Op.8-2, RV315「夏」 伝承曲(ジャッキー・オーツ&デイヴィッド・ル・ページ編):Bright Phoebus デヴィッド・ゴードン:Feeling the Chill ヴィヴァルディ:協奏曲第3番ヘ長調 Op.8-3, RV293「秋」 伝承曲(ジャッキー・オーツ&デイヴィッド・ル・ページ編):The Robin’s Petition デヴィッド・ゴードン:The Water’s Tears ヴィヴァルディ:協奏曲第4番ヘ短調 Op.8-4, RV297「冬」 |
オーケストラ・オヴ・ザ・スワン、 デイヴィッド・ル・ページ(ディレクター、ヴァイオリン)、 デヴィッド・ゴードン(鍵盤楽器)、 ジャッキー・オーツ(ヴォーカル) 録音:2023年4月5日-7日、福音史家聖ヨハネ教会(オックスフォード、イギリス) |
|
||
 MIRARE MIR-686(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲 第20番ニ短調 KV466 ピアノ協奏曲 第27番変ロ長調 KV595 |
アンヌ・ケフェレック(P) リオ・クオクマン(指)パリ室内O 録音:2023年2月21-24日、フィルハーモニー・ド・パリ |
|
||
| CPO CPO-555372(1CD) NX-B10 |
フリードリヒ・フォン・フロトウ(1812-1883):ピアノ協奏曲集/序曲集 ピアノ協奏曲第1番ハ短調(1830) ピアノ協奏曲第2番イ短調(1831) ウィリアム・シェイクスピアによる序曲「冬物語」 Fackeltanz たいまつの踊り(1853) 喜歌劇「未亡人グラパン」- 序曲 歌劇「リューベツァール」 序曲 歌劇「アレッサンドロ・ストラデッラ」 序曲 |
マティアス・キルシュネライト(P) ミュンヘン放送O ウルフ・シルマー(指) 録音:2020年3月2日-5日ミュンヘン BR第1スタジオ(ドイツ) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2304(1CD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番変ホ長調 Op.73「皇帝」 | クリフォード・カーゾン (P) ハンス・クナッパーツブッシュ(指) VPO 録音:1957年6月10~15日ゾフィエンザール(ウィーン) 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:ステレオ(録音セッション) |
|
||
| Naive V-8120[NA](1CD) |
オー・ソレ・ミオ ヴィヴァルディ:2つのマンドリンのための協奏曲 ト長調 RV532 ディ・カプア(1865-1917)/マッツッキ(1878-1972)編)):オー・ソレ・ミオ タリアフェッリ(1889-1937)/ヴァレンテ(1880-1946):受難(Passione) カラーチェ(1863-1934):マンドリンとピアノのための協奏曲 ホ短調〔ティボー・ペリヌによるオーケストラ編曲版、世界初録音〕 パガニーニ:マンドリンとギターのための作品全曲 ロヴェーネのためのソナタ ホ短調(マンドリンとギターのための)MS 14 マンドリンとギターのためのソナタ ト短調 MS16 モーツァルト:カンツォネッタ~歌劇「ドン・ジョヴァンニ」第2幕第3場 フンメル:マンドリンとオーケストラのための協奏曲 ト長調 S28(第3楽章カデンツァ:マルティノー) |
ジュリアン・マルティノー(マンドリン) フロリアン・センペイ(バリトン/4-5, 13) エリック・フランスリー(ギター/4-5, 13) ヤン・ドゥボスト(コントラバス/4-5,13) アンナ・シヴァツァッパ(2ndマンドリン/1-3) フィリップ・ムラトグル(ギター/9-12) トゥールーズ・キャピトル国立O ウィルソン・ンー(指揮/1-3, 6-8&14-16) 録音:2022年9月1-4日 |
|
||
| DOREMI DHR-8223(2CD) |
クリスチャン・フェラスLIVE 第2集 (1)ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.77 (2)チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35 (3)ベルク:ヴァイオリン協奏曲『ある天使の思い出に』 (4)サン・サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ Op.28 モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ 変ロ長調 K.454 (5)モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ イ長調 K.526 |
全て、クリスチャン・フェラス(Vn) (1)シャルル・ミュンシュ(指)ボストンSO 録音:1959年3月7日ボストン (2)オイゲン・ヨッフム(指)フランス国立放送O 録音:1964年4月9日パリ (3)パウル・クレツキ(指)ベルリンRSO 録音:1956年4月23日ベルリン (4)ピエール・バルビゼ(P) 録音:1955年3月16日ハンブルク、NDR(放送用ライヴ) (5)ピエール・バルビゼ(P) 録音:1957年4月12日フランクフルト、ヘッセン放送(放送用ライヴ) |
|
||
| Da Vinci Classics C-00793(1CD) |
フィリッポ・デル・コルノ:作品集 フィリッポ・デル・コルノ(b.1970):ア・コーダ・ディ・ロンディーネ(オーケストラのための) クラリネット協奏曲 「パッセージ」 6つのメモ(オーケストラのための) ピアノ協奏曲 「ノット・イン・マイ・ネーム」 |
イ・ポメリッジ・ムジカーリO、 カルロ・ボッカドーロ(指)、 ディミトリ・アシュケナージ(Cl)、 エマニュエレ・アルチウリ(P) 録音:2023年4月4日-6日 |
|
||
| NovAntiqua Records NA-87(1CD) |
5つの季節 フランチェスコ・ヴェネルッチ(b.1968):オーボエ協奏曲 ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集 「四季」 Op.8 |
マリカ・ロンバルディ(Ob)、 ヴァディム・ツィジク(Vn&指揮)、 アンサンブル・レ・ヴィルトゥオーゼ 録音:2022年9月12日-14日(パリ、フランス) |
|
||
| FONE UHQ-190(1CD) UHQCD 初回完全限定生産 |
fone 創立40周年記念 (1)ヴィヴァルディ:2つのチェロのための協奏曲ト短調 RV531より アレグロ (2)バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第1番ト短調 より アダージョ (3)ヨハン・ゴットフリート・ヴァルター:トマゾ・アルビノーニ氏によるオルガンのための協奏曲 ヘ長調(アルビノーニの協奏曲Op.2-4による) より アレグロ (4)ビーバー:ソナタ第1番ニ短調「受胎告知」 (5)ロッシーニ:歌劇「アルジェのイタリア女」 序曲 (6)プッチーニ:歌劇「トスカ」より テ・デウム (7)ハロルド・アーレン/テッド・ケーラー:When The Sun Comes Out (8)ジュール・スタイン:Time after time (9)ファブリツィオ・デ・アンドレ/イヴァノ・フォッサーティ:Ho visto Nina volare (10)マイケル・ジャクソン/ビル・ボットレル:Black or White (11)ルー・リード:Perfect Day (12)コネ・セイドゥ:Jerusalem |
(1)イ・ムジチ合奏団 (2)サルヴァトーレ・アッカルド(Vn) (3)ステファノ・コンコルディア(Org) (4)マルコ・フォルナチャーリ(Vn)、fone アンサンブル (5)サンタ・チェチーリア国立アカデミーO、チョン・ミョンフン(指) (6)サンタ・チェチーリア国立アカデミーcho、チョン・ミョンフン(指) (7)スコット・ハミルトン(Sax)、パオロ・ビッロ(P)、アルド・ズニーノ(ダブル・ベース)、アルフレッド・クラーマー(ドラムス) (8)ジュリアン・オリヴァー・マッツァリエッロ(P)、エンツォ・ピエトロパオーリ(ダブル・ベース) (9)ペトラ・マゴーニ(ヴォイス)、フェルッチョ・スピネッティ(ダブル・ベース) (10)ファウスト・メゾレッラ(G) (11)ペトラ・マゴーニ(ヴォイス)、イラリア・ファンティン(アーチリュート) (12)ライズ&ラディカント(ヴォイス&インストゥルメンツ) |
|
||
| BMOP SOUND BMOP-1092(1SACD) |
アンソニー・ポール・デ・リティス(b.1968):作品集
(1)「中国ポップ(Zhongguo Pop)」(2021) ~中国伝統楽器四重奏と弦楽のための (2)琵琶協奏曲「ピン・ポン(卓球)」(2006) (3)打楽器協奏曲「牛飼いと織姫の伝説」(2018) (4)「梅の花」(2000)~ピパ(中国琵琶)のための (5)嫦娥と不老不死の薬(2022) ~中国伝統楽器アンサンブルのための |
ギル・ローズ(指) ボストン・モダン・オーケストラ・プロジェクト (1)(2)(4)ミン・シャオフェン(琵琶[ピパ]) (1)(5)ヤジ・グオ(笛子[ディズー]) (1)ヘ・タオ(二胡[アルフー]) (1)シンイー・ヤン(古箏[グーチェン]) (3)ベイベイ・ワン(Perc) (5)イーミン・ミャオ(笛子[ディズー]) ツジュイ・キャリー・チン(笙[シェン]) チェン・ジン・コー(揚琴[ヤンキン]) ジョウ・イー(琵琶[ピパ]) グオ・ジャオシュン(中阮[チョンルアン]) ウェイ・スン(古箏[グーチェン]) 録音:2021年9月8日、2019年9月11日、2018年4月22日、2017年2月11日、2022年3月16日 |
|
||
| Music&Arts M&ACD-1308(1CD) |
A.ルビンシテイン:ピアノ協奏曲第1番ホ短調 Op.25 ピアノ協奏曲第2番へ町長 Op.35 6つの性格的小品 Op.50~第3番「舟歌」,第5 番「子守歌」(レイトゥシュ編) |
アンナ・シェレスト(P) ネーメ・ヤルヴィ(指) エストニア国立SO 録音:2022年9月20,21,23日 エストニア タリン |
|
||
| VOX VOXNX-3030CD(1CD) NX-B03 |
ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第1番(1890-91/1919改訂) ピアノ協奏曲第4番(1926/1941改訂)* パガニーニの主題による狂詩曲# |
アビー・サイモン(P) セントルイスSO レナード・スラットキン(指) 録音:1977年9月30日、977年10月1日*、1976年8月13日# ミズーリ州セントルイス、パウエル・ホール |
|
||
| BRIDGE BCD-9583(1CD) |
ジャスティン・デロ・ジョイオ(b.1955):作品集 (1)ピアノ協奏曲「海を隔てて」(2022) (2)「デュー・パー・デュー」(2011) ~チェロとピアノのための (3)「青と黄金の音楽」(2009)~オルガンと金管五重奏のため |
(1)ギャリック・オールソン(P) アラン・ギルバート(指) ボストンSO (2)カーター・ブレイ(Vc) クリストファー・オライリー(P) (3)アメリカン・ブラス・クインテット 録音:(1)2023年1月12、14日、(2)2011年9 月4日、(3)2009年1月10日 |
|
||
| Goodies 78CDR-3923(1CDR) |
シューマン:ヴァイオリン協奏曲ニ短調 バッハ:無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番ホ長調 BWV.1006より ガヴォットとロンド |
ゲオルク・クーレンカンプ(Vn) ハンス・シュミット=イッセルシュテッ(指)BPO 日TELEFUNKEN23653/6(独TELEFUNKEN2395/8 と同一録音) 1937年12月20日ベルリン、ジングアカデミー録音 |
|
||
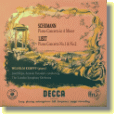 Treasures TRE-313(1CDR) |
ケンプ~シューマン&リスト:ピアノ協奏曲集 シューマン:ピアノ協奏曲イ短調Op.54* リスト:ピアノ協奏曲第1番変ホ長調 ピアノ協奏曲第2番イ長調 |
ウィルヘルム・ケンプ(P) ヨーゼフ・クリップス(指)LSO* アナトゥール・フィストラーリ(指)LSO 録音:1953年5月26-27日*、1964年6月2&4日(全てモノラル) ※音源:英DECCA LW-5337*、独DECCA MD-1043 ◎収録時間:73:03 |
| “芸術的表現に無関係なものを排斥するケンプのピアニズムを象徴!” | ||
|
||
| Spectrum Sound CDSMBA-1461CD) |
ダヴィド・オイストラフ&シルヴィア・マルコヴィチ
― ライヴ・レコーディングス・イン・パリ (1)ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.77 (2)シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.47 |
(1)ダヴィド・オイストラフ(Vn) ピエール・デルヴォー(指)フランス国営放送PO/ライヴ録音:1961年3月21日サル・プレイエル(パリ)【ステレオ】 (2)シルヴィア・マルコヴィチ(Vn) ジルベール・アミ(指)フランス放送新PO/ライヴ録音:1977年10月6日メゾン・ド・ラジオ・フランス、104スタジオ内大ホール(パリ)【ステレオ】 ※正規初CD化! |
|
||
| NIFC NIFCCD-152(1CD) |
ドゥラノフスキ&ヤニェヴィチ:ヴァイオリン協奏曲集
アウグスト・フレデリク・ドゥラノフスキ(1770-1834):ヴァイオリン協奏曲 イ長調 Op.8 フェリクス・ヤニェヴィチ(1762-1848):ヴァイオリン協奏曲第3番イ長調 モーツァルト:交響曲第14番イ長調 K.114 |
シュシャーヌ・シラノシアン(Vn)、 マルティナ・パストゥシカ(指) {oh!} オルキェストラ 録音:2022年6月2日-5日&2023年4月17日-20日(モーツァルト)、ポーランド放送ヴィトルト・ルトスワフスキ・コンサート・スタジオ(ワルシャワ、ポーランド) |
|
||
| Hyperion CDA-68345(1CD) |
ロマンティック・ピアノ・コンチェルト・シリーズ
Vol.86~テレフセン:ピアノ協奏曲集 トマス・テレフセン(1823-1874):ピアノ協奏曲第1番ト短調 Op.8、 ピアノ協奏曲第2番へ短調 Op.15 フリードリヒ・カルクブレンナー:嵐によって中断されポロネーズが後に続く大行進 Op.93 |
ハワード・シェリー(P&指揮)、 ニュルンベルクSO 録音:2022年12月14日-16日(ニュルンベルク、ドイツ) |
|
||
| ES-DUR ES-2091(1CD) JES-2091(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
CORE~トランペット協奏曲集 ヨハン・ヴィルヘルム・ヘルテル:トランペット、弦楽と通奏低音のための協奏曲第1番変ホ長調 レオポルト・モーツァルト:トランペット、2本のホルン、弦楽と通奏低音のための協奏曲ニ長調 ヨハン・メルヒオール・モルター:トランペット、2本のオーボエ、弦楽と通奏低音のための協奏曲ニ長調 MWV6.32 ヨハン・ミヒャエル・ハイドン:トランペット、2本のフルート、弦楽と通奏低音のための協奏曲第2番ハ長調 MH60 テレマン:トランペット、弦楽と通奏低音のための協奏曲ニ長調 TWV51:D7 |
アンドレ・ショッホ(Tp)、 スザンネ・フォン・グートツァイト(指)、 シュトゥットガルト室内O 録音:2023年2月3日&6月3日、シュトゥットガルト記念教会(ドイツ) |
|
||
| DUX DUX-1788(1CD) |
ブコフスキ:作品集 リシャルト・ブコフスキ(1916-1987):2台ピアノ、パーカッションと弦楽のための協奏曲 トランペット、ジャズ・リズム・セクションとオーケストラのための協奏曲 ピアノ協奏曲第1番 バリトンと13の楽器のための歌曲 |
キエルツェSO、 ヤツェク・ロガラ(指)、 マリア・マグダレナ・ヤノフスカ=ブコフスカ(P)、トマシュ・ルパ(P)、トマシュ・ヴォジニャク(Tp)、アダム・クルシェフスキ(Br) 録音:2022年6月20日-24日&8月24日-26日、キエルツェSOコンサート・ホール(ポーランド) |
|
||
| CAvi music 85-53539(1CD) |
ベルリン1923~ベートーヴェン&シュルホフ:ピアノ協奏曲集 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番ハ長調 Op.15 シュルホフ(1849-1942):ピアノ協奏曲 Op.43 「ジャズ風に」 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番ハ長調 Op.15より第1楽章(カデンツァ:シュルホフ) |
ヘルベルト・シュフ(P)、 ケルンWDRSO、 トンチエ・ツァン(指) 録音:2021年12月21日-23日、ケルン・フィルハーモニー(ドイツ) |
|
||
| ALTO ALC-1493(1CD) |
サクソフォン協奏曲&四重奏曲集 グラズノフ:アルト・サクソフォン協奏曲 Op.109 ヴィラ=ロボス:ソプラノ・サクソフォン、3本のホルンと弦楽のためのファンタジア マルタン:テナー・サクソフォンとオーケストラのためのバラード ジャン・リヴィエ:アルト・サクソフォンとトランペット協奏曲 グラズノフ:Canzona Variee(四重奏曲 変ロ長調 Op.109より) フランセ:小四重奏曲 ニコラウス・ショイブレ:デューク・エリントン・メドレー |
デトレフ・ベンスマン(Sax)、 デイヴィッド・シャローン(指)、 ベルリンRIASシンフォニエッタ、 ベルリン・サクソフォン四重奏団 録音:1984年、1991年 |
|
||
| Harp&Company CD-505051(1CD) |
オン・ザ・ルーフ~ハープとバスーンのための作品集
アンナ・シーガル:ユダヤ協奏曲/憧れ/バスーンとハープのための聖書のモザイク/フォークソングⅠ.キャラバン/フォークソングⅡ.恩赦-祈り/イエメンの愛の歌 |
ラシェル・タリトマン(Hp)、 マヴロウデス・トロウロス(Fg) ドロン・サロモン(指)、 イスラエル弦楽アンサンブル |
|
||
| Spectrum Sound CDSMBA-145(1CD) |
ヘンリク・シェリング・ライヴ・イン・パリ(バッハ、モーツァルト、ポンセ) バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043* モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調 K.216(カデンツァ:サム・フランコ) ポンセ:ヴァイオリン協奏曲# |
ヘンリク・シェリング(Vn) エルメロ・ノヴェロ(Vn2)* ヘンリク・シェリング(Vn&指)、 フランス公共放送室内O フランス国営放送PO#、 カルロス・チャベス(指)# ライヴ録音:1971年12月24日メゾン・ド・ラジオ・フランス、104スタジオ内大ホール(パリ)【ステレオ】 1960年10月4日シャンゼリゼ劇場(パリ)【ステレオ】# |
|
||
| IDIS IDIS-6751(1CD) |
カラヤン・スペクタキュラーVol.12 (1) ベートーヴェン:交響曲第2番ニ長調 Op.36 (2)ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61 |
ヘルベルト・フォン・カラヤン(指) (1)トリノRAI響 ライヴ録音:1953年4月10日 (2)ルツェルン祝祭O ライヴ録音:1955年8月27日 |
|
||
| Solo Musica SM-441(2CD) NX-C07 |
ブラームス:ピアノ協奏曲第1番/第2番 ピアノ協奏曲第1番ニ短調 Op.15 ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 Op.83 6つの小品 Op. 118 |
アンドレア・カウテン(P) ロイトリンゲン・ヴュルテンベルクPO ティモ・ハンドシュー(指) 録音:2022年12月12-14日、2023年6月22-25日 |
|
||
| Solo Musica SM-428(1CD) NX-B03 |
タイムトラベル~シッダールタ、マルコ・ポーロからバッハ&バードまで シルクロード - マルコ・ポーロ、東方へ - 笙と管弦楽のための協奏曲 シッダールタ- サクソフォンと管弦楽のための協奏曲 鐘-A Tribute to William Byrd ウィリアム・バード へのトリビュート- 管弦楽のために ブランデンブルガー・リミックスド(J.S. バッハのブランデンブルク協奏曲第2番作曲300年 バッハへのオマージュ)- トランペット、フルート、オーボエ、ヴァイオリン、弦楽とチェンバロのために ボーデン湖にて- 管弦楽のために |
ウー・ウェイ(笙) クリストフ・エンツェル(Sax) ラインホルト・フリードリヒ(ピッコロ・トランペット) コンスタンス・サニエ(Fl) ミヒャエル・キュッテンバウム(Ob) 谷野響子(Vn) クリスティアン・ナーゲル(Cemb) 南西ドイツPO ガブリエル・ヴェンツァーゴ(指) 録音:2023年3月9-15日、6月26-27日 |
|
||
| Linn CKD-732(2CD) NX-D09 |
ブラームス:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲 第1番ニ短調 Op.15 ピアノ協奏曲 第2番変ロ長調 Op.8* |
シモン・トルプチェスキ(P) ケルンWDRSO クリスティアン・マチェラル(指) 録音:2023年2月13-15、2023年3月7、8、10、11日(ライヴ)* ケルン・フィルハーモニー、ドイツ |
|
||
| ALPHA ALPHA-1001(1CD) |
モーツァルト:協奏曲集 ピアノ協奏曲 第19番ヘ長調 K.459(カデンツァ…モーツァルト) ホルン協奏曲 第1番ニ長調 K.412/514(386b)* フルートと管弦楽のためのアンダンテ ハ長調 K.315(カデンツァ…ディレン・ドゥラン) フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K. 299(カデンツァ…ハインツ・ホリガー) |
アーロン・ピルザン(P/ベーゼンドルファー) ニコラ・ラメズ(Hrn) ディレン・ドゥラン(Fl) エリーザベト・プランク(Hp) ウィーンRSO ハワード・グリフィス(指) トマス・ツェートマイヤー(指)* 録音:2021年3月、12月、2022年9月、2023年3月 オーストリア放送スタジオ6/大ホール、ウィーン |
|
||
| Chateau de Versailles Spectacles CVS-138(1CD) |
ヴィヴァルディ:『四季』、 オーボエ協奏曲 協奏曲集『四季』~『和声と創意への試み』Op.8より ヴァイオリン協奏曲 ホ長調「春」Op.8-1/RV 269 ヴァイオリン協奏曲 ト短調「夏」Op.8-2/RV 315 ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調「秋」Op.8-3/RV 293 ヴァイオリン協奏曲 ヘ短調「冬」Op.8-1/RV 297 オーボエ協奏曲 ハ長調 RV450 |
ヴェルサイユ王室歌劇場O(古楽器使用) ステファン・プレヴニャク(Vn、指) ミハエラ・フラバーンコヴァー(Ob) 録音:2023年7月14-16日 ヴェルサイユ宮殿王室歌劇場 |
|
||
| Orchid Classics ORC-100261(1CD) NX-B03 |
上岡敏之のR・シュトラウス オーボエ協奏曲 Trv292 ホルン協奏曲第1番 Op.11 組曲『町人貴族』 |
アンドレアス・フォスダル(Ob) ヤコブ・カイディング(Hrn) コペンハーゲンPO 上岡敏之(指) 録音:2019年2月18-21日、2021年3月23-27日 |
|
||
| CD ACCORD ACD-324(1CD) NX-C09 |
ミコワイ・グレツキ(1971-):作品集 序曲 Op.16-弦楽オーケストラのために(2000/2012) 3つの断片 Op.6- 弦楽オーケストラとチェレスタ(任意で)のために(1998) コンチェルト=ノットゥルノ Op.13- ヴァイオリンと弦楽オーケストラのために(2000) Concerto-Notturno, Op.13 アコーディオンと弦楽合奏のための協奏曲 Op. 61(2022)* ディヴェルティメント Op.32- 弦楽オーケストラのために(2009) |
ヤクブ・ヤコヴィツツ(Vn) マチェイ・フロンツキエヴィチ(アコーディオン) ワルシャワ・フィルハーモニー室内O ヤン・レウタク(音楽監督) 録音:2023年4月30日、5月1-2日ワルシャワ・フィルハーモニー・コンサートホール *=世界初録音 |
|
||
| DOREMI DHR-8213(2CD) |
ラドゥ・ルプーLIVE 第1集 (1)ブラームス:ピアノ協奏曲第1番ニ短調 Op.15 (2)フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調 (3)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番ハ短調 Op.37 (4)シューベルト:ピアノ・ソナタ第14番イ短調 D.784 シューベルト:4つの即興曲 Op.90D.899 |
ラドゥ・ルプー(P) (1)エド・デ・ワールト(指)BBC響 録音:1970年8月25日ロンドン (2)ストイカ・ミラノヴァ(Vn) 録音:1972年2月21日セント・ジョンズ、スミス・スクエア (3)アンドレ・プレヴィン(指)LSO 録音:1970年9月17日ブカレスト (4)録音:1969年9月19日リーズ |
|
||
| Goodies 78CDR-3921(1CDR) |
R・シュトラウス:ホルン協奏曲第1番変ホ長調作品11 | デニス・ブレイン(Hrn) アルチェオ・ガリエラ(指) フィルハーモニアO 英 COLUMBIA D.X.1397/8 1947年5月21日録音 |
|
||
| H.M.F HMM-902333(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲第6番変ロ長調 KV238〔カデンツァ:モーツァルト/アインガング:ベザイデンホウト〕 ピアノ協奏曲第25番ハ長調 KV503〔カデンツァ:ベザイデンホウト〕* |
クリスティアン・ベザイデンホウト(フォルテピアノ/2008年ポール・マクナルティ、1805年製ワルター&ゾーン・モデル)
フライブルク・バロック・オーケストラ 録音:2021年5月、2022年3月 * アンサンブルハウス・フライブルク |
|
||
 Melodiya x Obsession SMELCD-1000740(1CD) 完全限定生産 |
ダヴィド・オイストラフ・エディション Vol.1 チャイコフスキー:ヴィオリン協奏曲 シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 *、 2つのユモレスク Op.87* |
ダヴィド・オイストラフ(Vn) ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー(指揮、 モスクワPO、モスクワRSO* 録音:1968年(チャイコフスキー)、1965年(シベリウス) ステレオ |
|
||
| Gutman Records GUTMANCD-172(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲第13番ハ長調 KV415 ピアノ協奏曲第14番 変ホ長調 KV449 ピアノ協奏曲第23番イ長調 KV488 |
トーマス・ベイエル(P)、カメラータRCO ライヴ録音:2017年5月31日(アムステルダム、オランダ) |
|
||
| Gutman Records GUTMANCD-162(1CD) |
二つの月 ヴィヴァルディ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 イ短調 Op.3-8 ショスタコーヴィチ:2つのヴァイオリンとピアノのための4つの小品 バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043 モシュコフスキ:2つのヴァイオリンとピアノのための組曲 ト短調 Op.71 |
アナベス・ウェブ(Vn)、 ジョアンナ・ウェスターズ(Vn)、 カメラータRCO、他 録音:2015年2月22日-25日、MCO(ヒルフェルスム、オランダ) |
|
||
| Forgotten Records fr-1895(1CDR) |
ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲* ヴァイオリン・ソナタ第1番ニ長調 Op.12-1# |
アレクシ・ギャルペリーヌ(Vn) マニュエル・ロザンタール(指) パリ国立高等音楽・舞踊学校O* ジゼル・マニャン(P)# 録音:1970年12月13日* 、1978年4月14日、サル・ロッシーニ# ※初出 |
| Forgotten Records fr-1905(1CDR) |
シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 Op.54 フランク:交響的変奏曲 サン=サーンス:組曲「動物の謝肉祭」+ |
ベラ・シキ(P)、ゲザ・アンダ(P)+ ユージン・グーセンス(指)プロ・アルテO イーゴリ・マルケヴィチ(指)フィルハーモニアO+ 録音:1959年、1954年1月8日+ ※音源:Pye Records CCT31008、Columbia CX1175他 |
| Forgotten Records fr-1907(1CDR) |
ジャン・マルティノン:ヴァイオリン協奏曲第2番Op.51* ヒンデミット:ヴァイオリン・ソナタ 変ホ長調 Op.11-1# ラヴェル:ツィガーヌ |
ヘンリク・シェリング(Vn) タッソ・ヤノプーロ(P) ジャン・マルティノン(指)フランス放送PO* 録音:1961年9月8日ブザンソン音楽祭、1962年6月1日*(全て放送用ライヴ) |
| Forgotten Records fr-1914(1CDR) |
モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲集 第1番変ロ長調 K.207/第4番ニ長調 K.218 |
ヴィリー・ボスコフスキー(Vn,指) ウィーン・コンツェルトハウス室内O 録音:1955年 ※音源:Les Discophiles Français DF85 |
| AAM Records AAM-43(1CD) NYCX-10436(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第7番&第10番 他 ピアノ協奏曲 第7番ヘ長調 K.242-2台のピアノと管弦楽のための* ピアノ、ヴァイオリンと管弦楽のための協奏曲楽章 ニ長調 K. Anh56(315f)- 補筆完成:ロバート・レヴィン** ピアノ協奏曲 第10番変ホ長調 K.365-2台のピアノと管弦楽のための# |
ロバート・レヴィン(フォルテピアノ) ヤ=フェイ・チュアン(フォルテピアノ)*,# ボヤン・チチッチ(Vn)** ローレンス・カミングズ(指) アカデミー・オヴ・エンシェント・ミュージック ボヤン・チチッチ(リーダー) 録音:2022年7月5-10日 ロンドン、セント・ジュード・オン・ザ・ヒル教会 使用楽器:フォルテピアノ:アウグスブルクのアントン・シュタイン1786年製作をモデルとするベルギーのクリス・マーネの再現楽器。2016年製作及び2021年製作。 ヴァイオリン:ミラノのジョヴァンニ・グランチーノ1703年製作のオリジナル楽器。 |
|
||
| ARCANA A-555(3CD) NX-E02 |
バッハ:作品集 【CD1】 ブランデンブルク協奏曲 第1番ヘ長調 BWV 1046 ブランデンブルク協奏曲 第2番ヘ長調 BWV 1047 ブランデンブルク協奏曲 第3番ト長調 BWV 1048 ブランデンブルク協奏曲 第4番ト長調 BWV1049 【CD2】 ブランデンブルク協奏曲 第5番ニ長調 BWV 1050 ブランデンブルク協奏曲 第6番変ロ長調 BWV1051 序曲(管弦楽組曲)第2番ロ短調 BWV1067 ピッチ:A=398Hz 【CD3】 序曲 ハ長調 BWV119R 序曲(管弦楽組曲)第1番ハ長調 BWV1066 序曲(管弦楽組曲)第3番ニ長調 BWV1068 序曲 変ロ長調 BWV194R 序曲(管弦楽組曲)第4番ニ長調 BWV1069 ピッチ:A=415Hz |
ゼフィーロ・バロック・オーケストラ(古楽器使用) アルフレード・ベルナルディーニ(指) 「独奏」 ガブリエーレ・カッソーネ(Tp) ディレーノ・バルディン、フランチェスコ・メウッチ(Hrn) ドロテー・オーバーリンガー、ロレンツォ・カヴァサンティ(リコーダー) マルチェロ・ガッティ(フラウト・トラヴェルソ) アルフレード・ベルナルディーニ、パオロ・グラッツィ、 エミリアーノ・ルドルフィ(Ob) アルベルト・グラッツィ(Fg) チェチーリア・ベルナルディーニ(ヴィオリーノ・ピッコロ、ヴァイオリン) フランチェスコ・コルティ(Cemb) 録音:2017年9月27日-10月5日リストーリ歌劇場、ヴェローナ[CD 1-2] 2015年11月6-9日 マーラー・ホール(エウレジオ文化センター)、ドッビアーコ[CD 3] |
|
||
| ANALEKTA AN-29026(1CD) |
モーツァルト(1756-1791):ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466(カデンツァ…シャルル・リシャール=アムラン) ピアノ協奏曲 第23番イ長調 K.488(カデンツァ…モーツァルト) アダージョとフーガ ハ短調 K.546 |
シャルル・リシャール=アムラン(P) レ・ヴィオロン・デュ・ロワ ジョナサン・コーエン(指) 録音:2022年10月31日-11月2日ラウル・ジョバン・ホール、パレ・モンカルム、ケベック |
|
||
| ONDINE ODE-1423(1CD) NX-B07 NYCX-10424(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ブラームス:ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番 イ短調 ドヴォルザーク:森の静けさ Op. 68No.5 |
クリスティアン・テツラフ(Vn) ターニャ・テツラフ(Vc) ベルリン・ドイツSO パーヴォ・ヤルヴィ(指) 録音:2022年12月21-23日 |
|
||
| GENUIN GEN-23809(1CD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番(室内アンサンブル版)&第2番(室内アンサンブル版)
ベートーヴェン:ピアノと管弦楽のためのロンド 変ロ長調 WoO6(室内アンサンブル版) ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 Op.19(室内アンサンブル版) ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 Op.15 |
アリス・アレクサンダー・ブレッテンベルク(P、(指)編)、 ミュンヘン室内オペラO 録音:2023年4月12日-15日 |
|
||
| Gutman Records GUTMANCD-152(1CD) |
モーツァルト&メンデルスゾーン:協奏曲集 モーツァルト:ピアノ協奏曲第12番イ長調 K.414 メンデルスゾーン:ヴァイオリン、ピアノと弦楽のための協奏曲 ニ短調 |
ウェイイン・チェン(P)、 マルク・ダニエル・ファン・ビーメン(Vn)、 カメラータRCO 録音:2015年3月16日-18日、MCO(ヒルフェルスム、オランダ) |
|
||
| MDG MDG-10222942(4CD) |
バッハ:ブランデンブルク協奏曲、管弦楽組曲、ほか(レーガー編)):
ピアノ連弾版) ■CD1(47’54) ブランデンブルク協奏曲 ・第1番ヘ長調 BWV1046 ・第2番ヘ長調 BWV1047 ・第3番ト長調 BWV1048 ■CD2(56’42) ブランデンブルク協奏曲 ・第4番ト長調 BWV1049 ・第5番ニ長調 BWV1050 ・第6番変ロ長調 BWV1051 ■CD3(73’27) ・パッサカリア ハ短調 BWV582 管弦楽組曲 ・第1番ハ長調 BWV1066 ・第2番ロ短調 BWV1067 ■CD4(74’46) トッカータとフーガ ニ短調BWV565 管弦楽組曲 ・第3番ニ長調 BWVB1068 ・第4番ニ長調 BWV1069 ・前奏曲とフーガ 変ホ長調 BWV552 |
トレンクナー&シュパイデ ル・ピアノ・デュオ【エフェリン
デ・トレンクナー(P)、ゾントラウト・シュパイデル(P)】 録音:1995年6月(CD1&2),2000年3月27-29日(CD3&4),Furstliche Reitbahn Bad Arolsen |
|
||
| SWR music SWR-19140CD(1CD) NX-B06 |
グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調 Op. 16 シューベルト:幻想曲「さすらい人」 Op.15D760* |
オレグ・マイセンベルク(P) バーデン=バーデン・フライブルクSWR響 アダム・フィッシャー(指) 録音:2004年5月8日 ウィーン、コンツェルトハウス、大ホール(オーストリア)、1990年3月6日 Sparkassensaal Lorrach(ドイツ)* |
|
||
| CPO CPO-555467(1CD) NX-B10 |
カール・シュターミッツ(1745-1801):協奏交響曲集 協奏交響曲第9番ハ長調 協奏交響曲第12番変ロ長調 協奏交響曲 ニ長調 Op.2-2 |
ハンス=ペーター・ホフマン(Vn) ロベルト・コルン(Vn) クリストフ・エーベルル(Vc) ポール・メイエ(Cl) マンハイム・プファルツ選帝侯室内O ポール・メイエ(指) 録音:2021年2月18-20日 |
|
||
| N-crafts Sound NC-0002(1CD) 税込定価 |
Sixties Dialogue E. ボザ(1905-1991):2本のトランペットの為の「DIALOGUE」 W. ペリー(1930-):トランペットとオーケストラの為の協奏曲 J. ホロヴィッツ(1926-2022):コンチェルティーノ・クラシコ ヒンデミット:トランペットとピアノの為のソナタ Op.137 E. モラレス(1966-):2本のトランペットの為の協奏曲 |
井川明彦(Tp). 栃本浩規(Tp). 下田望(P) 大倉里美(パーカッション). 小林雅文(パーカッション). 小林奏人(パーカッション). 柳原正人(パーカッション). 録音:2023年5月3-4日 飛騨芸術堂 |
|
||
| CPO CPO-555523(1CD) NX-B10 |
ヴァイオリンと室内管弦楽の為の作品集 シモン・ラクス(1901-1983):詩曲- ヴァイオリンと室内Oの為の(E. ノヴィツカ編) 弦楽の為の交響曲 ミェチスワフ・ヴァインベルク(1919-1996):3つの小品 - ヴァイオリンと室内Oの為の(E. ノヴィツカ編) エヴェリナ・ノヴィツカ(1982-):カディッシュ1944- ヴァイオリンと室内Oの為の |
エヴェリナ・ノヴィツカ(Vn) ポーランド放送アマデウス室内O アニエスカ・ドゥチマル(指) アンナ・ドゥチマル=ムローズ(指) 録音:2012年2月8日、2013年1月18日 |
|
||
| Channel Classics CCSBOX-7723(3CD) NX-E02 |
ラフマニノフ:ピアノ協奏曲(全4曲) パガニーニの主題による狂詩曲 前奏曲 嬰へ短調 Op.23-1 前奏曲 嬰ト短調 Op.32-12 前奏曲 ト長調 Op.32-5 前奏曲 変ロ?調 Op.23-2 交響曲 ニ短調 「ユース・シンフォニー」 |
アンナ・フェドロヴァ(P) ザンクト・ガレンSO モデスタス・ピトレナス(指) 録音:2019年11月、2021年11月、2022年11月トーンハレ・シアター、ザンクト・ガレン、スイス |
|
||
| Willowhayne Records WHR-068(1CD) |
ホルン協奏曲集 アーノルド:ホルン協奏曲第2番Op.58 クリストフ・シェーンベルガー(1961-):ホルン協奏曲 ヘ長調 …世界初録音 ルース・ギップス(1921-1999):ホルン協奏曲 Op.58 |
ベン・ゴルトシャイダー(Hrn) フィルハーモニアO リー・レイノルズ(指) 録音:2021年3-5月 ヘンリー・ウッド・ホール、ロンドン |
|
||
| Glossa GCD-924702(1CD) |
ヒンメルスブルク~バッハ:ヴァイオリン協奏曲集
バッハ:ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 BWV.1042 ヴァイオリン協奏曲ニ短調 BWV.1052R〔復元版〕 ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 BWV.1041 ヴァイオリン協奏曲ト短調 BWV.1056R〔復元版〕 |
リナ・トゥール・ボネ(バロック・Vn、指) ムジカ・アルケミカ 録音:2022年11月15日-17日、ヴィラセカ音楽院(スペイン) |
|
||
| Challenge Classics CC-72945(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲集 第1集 モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番イ長調 K.488 モーツァルト(ラツィック編):「ロンド・コンチェルタンテ」-アレグレット・グラツィオーソ(P・ソナタ第13番 変ロ長調 K.333/315c 第3楽章からの編曲/世界初録音) モーツァルト:ピアノ協奏曲第14番変ホ長調 K.449 |
デヤン・ラツィック(P) ヤン・ヴィレム・デ・フリエンド(指) ベルゲンPO 録音:2022年2月14-17日/ノルウェー、ベルゲン、グリーグホール |
|
||
| Challenge Classics CC-72972(3CD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集 ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 Op.19 ピアノ協奏曲第1番ハ長調 Op.15 ピアノ協奏曲第3番ハ短調 Op.37 ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op.58 ピアノ協奏曲第5番『皇帝』 Op.73 ※カデンツァ:すべてベートーヴェン作 |
ハンネス・ミンナール(P) ヤン・ヴィレム・デ ・フリエンド(指) ネザーランドSO 録音:[CD1]2015年2月2-4日、[CD2]2016年9月23・27日、[CD3]2014年5月26-28日/オランダ、エンスヘデ、音楽センター |
|
||
| C Major 76-4908(DVD) 76-5004(Bluray) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.466* 交響曲第40番ト短調K.550 シューマン:ピアノ協奏曲イ短調Op.54* シルヴェストロフ:『使者』(Pと弦楽の為の)* |
エレーヌ・グリモー(P)* カメラータ・ザルツブルク ジョヴァンニ ・グッツォ(コンサートマスター) 収録:2022年3月、エルプフィルハーモニー・ハンブルク(ライヴ) ◆DVD 画面:NTSC16:9 音声:PCMステレオ、DTS5.1 リージョン:All DVD9、104分 ◆Bluray 画面:1080i16:9FullHD 音声:PCMステレオ、DTS-HD MA5.1 リージョン:All BD50、104分 |
|
||
| ALTO ALC-1480(1CD) |
レスピーギ:ヴァイオリン協奏曲集&組曲 ヴァイオリンと管弦楽の為の 「グレゴリオ風協奏曲」 ヴァイオリンと管弦楽の為の 「古風な協奏曲」 ヴァイオリンと管弦楽の為の 「秋の詩」 |
アンドレア・カッペレッティ(Vn)、 マティアス・バーメルト(指)、 フィルハーモニアO、 イゴール・グルップマン(Vn)*、 ドナルド・バッラ(指)*、 サン・ディエゴ室内O* 録音:1993年 |
|
||
| NORTHERN FLOWERS NFPM-A99151(1CD) |
ホルンの為のロシア音楽~協奏曲&四重奏曲集 グリエール:ホルン協奏曲変ロ長調 Op.91、 ホルンとピアノの為の4つの小品 グラズノフ:夢 Op.24、 セレナーデ Op.11-2、牧歌 シェバリーン(1902-1963):ホルンと管弦楽の為のコンチェルティーノ Op.14-2 ニコライ・ニコラエヴィチ・チェレプニン:6つのホルン四重奏曲 ヘ長調 |
マリー=ルイーズ・ノイネッカー(Hrn)、 バンベルクSO、 ヴェルナー・アンドレアス・アルベルト(指)、 ザルツブルク・モーツァルテウム・ホルン・アンサンブル、 パウル・リヴィニウス(P) |
|
||
| MUSICAL CONCEPTS MC-3111(1CDR) |
女性作曲家による管弦楽作品集 ファニー・メンデルスゾーン:序曲 クララ・シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 Op.7 タイユフェール:ハープ・コンチェルティーノ リリ・ブーランジェ:哀しみの夜に、春の朝に |
ジョアン・ファレッタ(指)、 ウィメンズPO、 アンジェラ・チェン(P)、 ジリアン・ベネット(Hp) |
|
||
| PARNASSUS PACD-96089(1CD) |
エマヌエル・フォイアマン・イン・コンサート (1)ドヴォルザーク:森の静けさOp.68、 ロンド ト短調 Op.94 ブロッホ:ヘブライ狂詩曲 「シェロモ」 B.39 (2)ダルベール:チェロ協奏曲ハ長調 Op.20 (3)ヨーゼフ・ライヒャ(レイハ):チェロ協奏曲イ長調 Op.4-1 |
エマヌエル・フォイアマン(Vc)、 レオン・バージン(指)、 ナショナル・オーケストラル・アソシエーション (1)録音:1941年11月10日 (2)録音:1940年4月22日 (3)録音:1940年1月27日 |
|
||
| Goodies 78CDR-3919(1CDR) |
ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲ニ長調作品61 | イゾルデ・メンゲス(Vn) サー・ランドン・ロナルド(指) ロイヤル・アルバート・ホールO 英HMV D767/71 1923年9月4、7&21日ロンドン録音 ※復刻に使用したSP盤のキズによるノイズがあります。 |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00828(1SACD) 税込定価 2023年9月27日発売 |
スメタナ:交響詩「モルダウ」 ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 B.191 歌劇《ルサルカ》より「月に寄せる歌」 |
笹沼樹(チェロ) ダニエル・ライスキン(指揮) スロヴァキア・フィルハーモニー管弦楽団 録音:2023年6月25日 東京・サントリーホール・ライヴ |
|
||
| Evil Penguin Records EPRC-0055(1CD) |
サンバ=バッハ バッハ:ヴァイオリン協奏曲第2番 ホ長調 BWV1042 ヴィラ=ロボス:Villa Cantilena & Melodia Sentimental アントニオ・カルロス・ジョビン(1927-1994):Desafinado / Garota de Ipanema 同:Samba de uma Nota So マルコス・ヴァーリ(1943-):Samba de Verao ノエル・ホーザ(1910-1937):Gago Apaixonado アリ・バホーゾ(1903-1964):Aquarela do Brasil アシス・ヴァレンテ(1911-1958):Brasil Pandeiro ヴァルジール・アゼヴェード(1923-1980)/ジャコー・ド・バンドリン(1918-1969):Brasileirinho / Assanhado ゼキーニャ・ジ・アブレウ(1880-1935):Tico-tico no Fuba ジョルジ・ベンジョール(1939-):Mas que nada ピシンギーニャ(1897-1973)&ベネヂート・ラセルダ(1903-1958):Um a zero |
リナス・ロス(Vn ) オルケストラ・ヨハン・セバスティアン・リオ 録音:2023年3月24・25・27・28日リオデジャネイロ、セシリア・メイレレス・ホール |
|
||
| Chandos CHAN-20246(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲集 Vol.8 歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」序曲 歌劇「魔笛」序曲 歌劇「皇帝ティートの慈悲」序曲 ピアノ協奏曲第26番KV537「戴冠式」* ピアノ協奏曲第27番 KV595* |
ジャン=エフラム・バヴゼ(P/YAMAHA CFX)* ガボル・タカーチ=ナジ(指)、 マンチェスター・カメラータ 録音:2022年9月24日-26日、ストーラー・ホール(ハンツ・バンク、マンチェスター) |
|
||
| CEDILLE CDR-90000221(1CD) NX-B04 |
リカルド・カストロ/マヌエル・ポンセ:ピアノ協奏曲 リカルド・カストロ(1864-1907):ピアノ協奏曲 Op. 22 子守歌 Op.36-1/愛の歌 嘆き Op.38-2 ポンセ:ピアノ協奏曲第1番「ロマンティコ」 メキシコの子守唄「ラ・ランチェリータ」 ガヴォット 愛のロマンス/間奏曲 |
ホルヘ・フェデリコ・オソリオ(P) ミネリアSO カルロス・ミゲル・プリエト(指) 録音:2022年8月1、8日 |
|
||
| CEDILLE CDR-90000223(1CD) NX-B04 |
ショスタコーヴィチ/メニーアン:ヴァイオリン協奏曲集 ショスタコーヴィチ:ヴァイオリン協奏曲第1番 イ短調 Op.77 アール・メニーアン(1976-):ヴァイオリンと管弦楽の為の協奏曲 |
レイチェル・バートン・パイン(Vn) ロイヤル・スコティッシュ・ナショナルO ティート・ムニョス(指) 録音:2022年1月7-8日 |
|
||
| SUPRAPHON SU-4331(1CD) |
ヤン・ノヴァーク(1921-1984):作品集 (1)4手ピアノと弦楽オーケストラのための「Concentus biiugis」(1977)【改訂版】 (2)フルート、弦楽オーケストラ、ハープとチェレスタのための「Choreae vernales」(1980) (3)2台のピアノとオーケストラのための協奏曲(1955) |
(1)(3)ドラ・ノヴァク=ウィルミントン(P)、 (1)(3)カレル・コシャーレク(P) (2)クララ・ノヴァーコヴァーー(Fl) プラハRSO、 トマーシュ・ネトピル(指) 録音:(1)(3)2022年3月7~12日、(2)2022年12月6&7日/チェコ放送第1スタジオ(プラハ) |
|
||
| CORO COR-16200(1CD) |
モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲集 Vol.2
ヴァイオリン協奏曲第2番 ニ長調 K.211 ヴァイオリン協奏曲第1番変ロ長調 K.207 ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 K.219 |
アイスリン・ノスキー(Vn)、 ヘンデル&ハイドン・ソサエティ 録音(ライヴ):2023年1月6日&8日(K.211)、2022年1月28日&30日(K.207)、2019年1月25日&27日(K.219)、シンフォニー・ホール(ボストン、アメリカ) |
|
||
| Goodies 78CDR-3915(1CDR) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第27番変ロ長調 K.595(カデンツァ:モーツァルト) | アルトゥール・シュナーベル(P) サー・ジョン・バルビローリ(指)LSO 米 VICTOR17053/56(英 HMV DB2249/52と同一録音) 1934年5月2日ロンドン、アビー・ロードEMI 第1スタジオ録音 |
|
||
| Goodies 78CDR-3916(1CDR) |
グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調作品16 | モウラ・リンパニー(P) シドニー・ビーア(指)ナショナルSO 英 DECCA AK1134/37 1945年5月14日ロンドン、キングスウェイ・ホール録音 |
|
||
| Gramola GRAM-99284(1CD) |
ジャズ・ヴァイオリン・コンチェルト - メイド・イン・オーストリア ヘルベルト・ベルガー(1969-):メトロポール組曲(Vnと弦楽オーケストラの為の協奏曲) フリードリヒ・グルダ(1930-2000):Wings ウィングス(独奏ヴァイオリン、弦楽オーケストラとパーカッション(リズム・セクション)の為の小協奏曲) ザビーナ・ハンク(1976-):見捨てられた天使の為の3つの歌(独奏ヴァイオリン、弦楽オーケストラとパーカッション(ドラムス)の為の協奏曲) |
ベンヤミン・シュミット(Vn&指揮) ムジカ・ヴィーテO クリスティアン・レットナー(ドラムス) 録音:2020年10月24-25日、2021年8月15-19日、2021年9月14日 |
|
||
 ARCANA A-550(3CD) NX-E02 |
ヴィヴァルディの三つの季節 ~ヴァイオリン協奏曲集~ 【Disc1】 春 ヴァイオリン協奏曲 イ長調 RV343「さまざまに異なる調弦のヴァイオリンを集めて」~アンナ・マリアの為の協奏曲 ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 RV240 ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 RV230(協奏曲集『調和の霊感』Op.3-9) ヴァイオリン協奏曲 ト短調 RV332(協奏曲集『和声と創意の試み』Op.8-8) ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 RV265(協奏曲集『調和の霊感』Op.3-12) ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 RV210(協奏曲集『和声と創意の試み』Op.8-11) 【Disc2】 夏 ヴァイオリン協奏曲 ハ長調 RV189~神聖ローマ皇帝カール6世の依頼による ヴァイオリン協奏曲 ト短調 RV333 ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調 RV289(世界初録音) ヴァイオリン協奏曲 ハ短調 RV197 ヴァイオリン協奏曲 ト短調 RV330 ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 RV380 【Disc3】 秋 ヴァイオリン協奏曲 ハ短調 RV201 ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 RV371 ヴァイオリン協奏曲 イ長調 RV353 ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 RV367(初期稿による世界初録音) ヴァイオリン協奏曲 ト短調 RV327 ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 RV390 |
ジュリアーノ・カルミニョーラ(Vn) 使用楽器:ピエトロ・グヮルネリ1733年製作のオリジナル楽器 アッカデーミア・デラヌンチアータ(古楽器使用) リッカルド・ドーニ(チェンバロ、ポジティフオルガン、指揮) 録音:2023年1月13-16日、2月1-4日、3月13-16日サン・ベルナルディーノ教会、アッビアーテグラッソ(イタリア北部ロンバルディア州ミラノ県) |
|
||
| Resonus RES-10319(1CD) NX-B05 |
マーク・デイヴィッド・ボーデン(1986-):クラリネット協奏曲(2017) ヒュー・ワトキンス(1976-):Four Fables4つの寓話 - クラリネットとピアノ・トリオのために(2018) ダイアナ・バレル(1948-):クラリネット協奏曲(1996) サラ・フランシス・ジェンキンス(1998-):木漏れ日(2020) |
ロバート・プレーン(Cl) グールド・ピアノ・トリオ【ルーシー・グールド(Vn)、リチャード・レスター(Vc)、ベンジャミン・フリス(P)】 BBCPO ジェフリー・パターソン(指) 録音:2022年12月13-14日 |
|
||
| Biddulph BIDD-85035(1CD) |
ナタン・ミルシテイン 1953年の協奏曲録音集 メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64 ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲* |
ナタン・ミルシテイン(Vn) ピッツバーグSO ウィリアム・スタインバーグ(指) ボストンSO* シャルル・ミュンシュ(指)* 録音:1953年11月28日 ボストン、シンフォニー・ホール、1953年3月23日 ピッツバーグ、シリア・モスク* 初出盤:Capitol P8243(1-6)、RCA LM1760(7-9) 復刻プロデューサー:Eric Wen 復刻エンジニア:David Hermann マスタリング:Rick Torres |
|
||
| BONGIOVANNI GB-5639(1CD) |
ヴィヴァルディ:ファゴット協奏曲全集 第1集 協奏曲 ト短調 RV495 協奏曲 ヘ長調 RV486 協奏曲 変ロ長調 RV502 協奏曲 ホ短調 RV484 協奏曲 ハ長調 RV476 協奏曲 ト短調 RV496 協奏曲 変ホ長調 RV483 協奏曲 ト長調 RV493 |
マウロ・モングッツィ(Fg) スカラ座の弦楽奏者たち ジョヴァン ニ・ブロッロ(Cemb) 録音:2021年11月12日、2022年5月30日イタリア、ブリオスコ |
|
||
| MELO CLASSIC MC-1071(2CD) |
ゲザ・アンダ/楽旅1951-1961 (1)シューマン:ピアノ協奏曲 (2)チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 (3)ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 (4)ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 |
ゲザ・アンダ(P) (1)アンリ・ペンシス(指)ルクセンブルクRSO 録音:1951年12月20日 ルクセンブルク (モノラル・ライヴ) (2)ルイ・ド・フロマン(指)ルクセンブルクRSO 録音:1961年10月2日 ルクセンブルク (モノラル・放送スタジオ録音) (3)ルドルフ・ミヒル(指)ザールブリュッケンRSO 録音:1956年5月26日 西ドイツ ザールラント州 ザールブリュッケン (モノラル・放送スタジオ録音) (4)フェレンツ・フリッチャイ(指)バイエルン国立O 録音:1958年5月12日 西ドイツ バイエルン州 ミュンヘン (モノラル・ライヴ) |
|
||
| MELO CLASSIC MC-1073(2CD) |
ジュリアス・カッチェン/楽旅1960-1968 (1)ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 (2)チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 (3)プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第1番 (4)ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 (5)バルトーク:ピアノ協奏曲第3番 (6)ラヴェル:左手のためのピアノ協奏曲 |
ジュリアス・カッチェン(P) (1)ルイ・ド・フロマン(指)ルクセンブルクRSO 録音:1964年3月25日 ルクセンブルク (モノラル・ライヴ) (2)ハンス・ミュラー=クライ(指)南ドイツRSO 録音:1964年4月3日 西ドイツ シュトゥットガルト (モノラル・放送スタジオ録音) (3)カール・ランドルフ(指)NDR SO 録音:1960年1月6日 西ドイツ ハンブルク (モノラル・放送スタジオ録音) (4)ハンス・シュミット=イッセルシュテット(指)NDR響 録音:1964年9月30日 西ドイツ ハンブルク (モノラル・ライヴ) (5)ゲオルク・ルートヴィヒ・ヨッフム(指)南ドイツRSO 録音:1967年12月8日 西ドイツ シュトゥットガルト (ステレオ・ライヴ) (6)シャルル・ブリュック(指)ORTF PO 録音:1968年12月10日 フランス パリ (ステレオ・ライヴ) |
|
||
| MELO CLASSIC MC-1074(2CD) |
ニキタ・マガロフ/演奏会楽旅1955-1973 (1)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番 (2)ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番 (3)チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 (4)ラヴェル:ピアノ協奏曲 (5)プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第3番 |
ニキタ・マガロフ(P) (1)モーリス・ル・ルー(指)フランス国立放送O 録音:1964年10月6日 フランス パリ (モノラル・ライヴ) (2)アンジェイ・マルコフスキ(指)ハノーファーNDRO 録音:1969年12月12日 西ドイツ ニーダーザクセン州 ハノーファー(ステレオ・ライヴ) (3)アンリ・ペンシス(指)ルクセンブルクRSO 録音:1955年10月20日 ルクセンブルク (モノラル・放送スタジオ録音) (4)ハンス・シュミット=イッセルシュテット(指)NDR響 録音:1963年10月23日 西ドイツ ハンブルク (モノラル・ライヴ) (5)ズデニェク・マーツァル(指)フランス国立放送O 録音:1973年11月28日 フランス パリ (ステレオ・ライヴ) |
|
||
| MELO CLASSIC MC-1075(2CD) |
ジョン・オグドン/演奏会楽旅1965-1970 (1)シューマン:ピアノ協奏曲 (2)リスト;ピアノ協奏曲第2番 (3)ブゾーニ:インディアン幻想曲 Op.44 (4)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番 (5)ラヴェル:左手のためのピアノ協奏曲 (6)ヒンデミット:ピアノ協奏曲 |
ジョン・オグドン(P) (1)ヴァーツラフ・ノイマン(指)南ドイツRSO 録音:1967年3月10日 西ドイツ シュトゥットガルト (ステレオ・ライヴ) (2)アンドレアス・フォン・ルカーチ(指)南西ドイツRSO 録音:1970年3月6日 西ドイツ バーデン=ヴュルテンベルク州 バーデン=バーデン (ステレオ・放送スタジオ) (3ルイ・ド・フロマン(指)ルクセンブルクRSO 録音:1965年10月27日 ルクセンブルク (モノラル・放送スタジオ録音) (4)ルイ・ド・フロマン(指)ルクセンブルクRSO 録音:1965年10月25日 ルクセンブルク (モノラル・放送スタジオ録音) (5)ラファエル・クーベリック(指)バイエルンRSO 録音:1968年5月24日 西ドイツ バイエルン州 ミュンヘン (ステレオ・放送スタジオ録音) (6)フェルディナント・ライトナー(指)バイエルンRSO 録音:1970年12月11日 西ドイツ バイエルン州 ミュンヘン (ステレオ・放送スタジオ) |
|
||
| MELO CLASSIC MC-2052(2CD) |
ヘンリク・シェリング/演奏会楽旅1952-1976 (1)サン=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ (2)メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 (3)シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 (4)プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲第2 番 (5)グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲 (6)ラロ:スペイン交響曲 |
ヘンリク・シェリング(Vn) (1)アンリ・ペンシス(指)ルクセンブルクRSO 録音:1952年1月17日 ルクセンブルク (モノラル・ライヴ) (2)カール・フォン・ガラグリ(指)ハルモニエン音楽協会(現 ベルゲン・フィル) 録音:1955年5月26日 ノルウェーベルゲン (モノラル・ライヴ) (3)ハンス・シュミット=イッセルシュテット(指)NDR響 録音:1962年9月24日 西ドイツ ハンブルク (モノラル・放送スタジオ録音) (4)ヴィルヘルム・シュヒター(指)NDR響 録音:1957年10月16日 西ドイツ ハンブルク (モノラル) (5)アンヘル・サウチェ(指)ヴェネズエラSO 録音:1958年4月11日 ヴェネズエラ カラカス(モノラル) (6)オイゲン・ヨッフム(指)ケルンRSO 録音:1976年9月7日 スイス ルツェルン (ステレオ・ライヴ) |
|
||
| MELO CLASSIC MC-3017(2CD) |
ジャクリーヌ・デュ・プレ/演奏会ライヴ1965-1969 (1)ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104 (2)シューマン:チェロ協奏曲 イ短調 (3)バッハ:チェロとピアノのためのソナタ第3 番ト短調 BWV1029 ベートーヴェン:チェロ・ソナタ第5番ニ長調 Op.102-2 シューマン:幻想曲集 Op.73 ブリテン:チェロ・ソナタ ハ長調 Op 65 |
ジャクリーヌ・デュ・プレ(Vc) (1)ズビン・メータ(指)BPO 録音:1968年8月4日 オーストリア ザルツブルク州 ザルツブルク (モノラル・ライヴ) (2)マルティン・トゥルノフスキー(指)NDR響 録音:1969年1月24日 西ドイツ ニーダーザクセン州 ハノーファー(モノラル・ライヴ) (3)スティーヴン・ビショップ(スティーヴン・コヴァセヴィッチ)(P) 録音:1965年6月11日 西ドイツ バーデン=ヴュルテンベルク州 エトリンゲン(モノラル・ライヴ録音) |
|
||
| Goodies 33CDR-3911(1CDR) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番ニ短調 K.466 ピアノ協奏曲第24番ハ短調 K.491 |
アルトゥール・シュナーベル(P) ウォルター・ジュスキント(指) フィルハーモニアO 米 VICTOR LHMV-1012 1948年6月17-18(K.466)&6月18-19日 ロンドン、アビー・ロードEMI第1スタジオ録音 |
|
||
| Goodies 78CDR-3913(1CDR) |
シューマン:チェロ協奏曲イ短調作品129 | ルートヴィヒ・ヘルシャー(Vc) ヨーゼフ・カイルベルト(指) ベルリン国立歌劇場O 日VICTOR JD-1599/601(英HMV DB4550/52と同一録音) 1938年6月8日ベルリン録音 ※一部に使用ディスクの傷によるノイズが入ります |
|
||
 Pentatone PTC-5187029(1CD) |
バルトーク:ピアノ協奏曲全集 ピアノ協奏曲第1番イ長調 Sz.83 ピアノ協奏曲第2番ト長調 Sz.95 ピアノ協奏曲第3番ホ長調 Sz.119 |
ピエール=ロラン・エマール(P) サンフランシスコSO、 エサ=ペッカ・サロネン(指) ライヴ録音:2022年6月16~19日&2023年2月17~19日デービス・シンフォニーホール(サンフランシスコ) |
|
||
| Linn CKD-729(1CD) |
ブリテン:歌劇「ピーター・グライムス」~4つの海の間奏曲
Op.33a エルガー:ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 Op.61 |
ミヒャエル・バレンボイム(Vn) フィルハーモニアO アレッサンドロ・クルデーレ(指) 録音:2022年9月7-8日 ブラックヒース・ホール、ロンドン、UK |
|
||
 ONDINE ODE-1414(1CD) NX-B07 NYCX-10416(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第9番変ホ長調「ジュノーム」
K.271…カデンツァ:W.A.モーツァルト ピアノ協奏曲第24番ハ短調 K.491 |
ラルス・フォークト(P&指) パリ室内O 録音:2021年4月25-28日 |
|
||
| Da Vinci Classics C-00755(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第12番&第14番(作曲者編曲によるピアノ五重奏版)
ピアノ協奏曲第12番イ長調 K.414 ピアノ協奏曲第14番変ホ長調 K.449 |
ピエロ・バルバレスキ(P)、 トリオ・ヘーゲル 〔ダヴィド・スカローニ(Vn1)、ダヴィデ・ブラーヴォ(Va)、アンドレア・マルコリーニ(Vc)、ジュリア・セッラ(Vn2)〕 録音:2022年5月、チーゴレ(イタリア) |
|
||
| Chopin University Press UMFCCD-126(1CD) |
21世紀のアコーディオン協奏曲集 ラファウ・ヤニャク(1986-):バンドネオンと室内オーケストラのための協奏曲「過去の追憶」(2015) ニコラ・コウォジェイチク(1986-):サクソフォン、バンドネオンと弦楽オーケストラのための協奏曲(2018) トマシュ・オパウカ(1983-):アコーディオンと弦楽オーケストラのための協奏曲「ブラック・ストリームズ」(2017 |
ラファウ・グジョンカ(バンドネオン、アコーディオン)、 パヴェウ・グスナル(Sax)、 ショパン音楽大学室内O、 ラファウ・ヤニャク(指) |
|
||
| DUX DUX-1873(1CD) |
ガスマン:ハープ協奏曲&トランペット協奏曲
ゲイリー・ガスマン(1952-):ロマンティックな協奏曲(ハープ協奏曲)(2018) トランペット協奏曲(2020)/マルガリータ(2022) |
マウゴジャタ・ザレフスカ(Hp)、 ゲイリー・ガスマン(Tp)、 ミロスワフ・ヤツェク・ブワシュチク(指)、 ポドラシェ歌劇場フィルハーモニーO 録音:2022年6月 |
|
||
| FONE 99F-16CD(1CD) 完全数量限定盤 |
マダーマ宮殿のコンサート バッハ:オーボエとヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1060 モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番 ト長調 K.216 プロコフィエフ:ピーターと狼 Op.67* |
サルヴァトーレ・アッカルド(Vn)、 ルカ・ヴィニャーリ(Ob)、イタリア室内O、 アルノルド・フォア(ナレーション)* 録音:1999年、マダーマ宮殿(ローマ) |
|
||
| BERLINER PHILHARMONIKER KKC-6741(1SACD) 税込定価 |
ラフマニノフ150 ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番* 「メロディー」~幻想的ピアノ小品集op.3より 3番 愛の悲しみ[クライスラー原曲] コレルリの主題による変奏曲 ニ短調 Op.42 「夜の静けさに」6つの歌 op.4ニ長調[ゲルシュタイン編曲] |
キリル・ゲルシュタイン(P) キリル・ペトレンコ(指)BPO* 録音:2022年6月25日、ヴァルトビューネ、ベルリン(協奏曲) 2023年2月6日、フィルハーモニー、ベルリン(独奏曲) |
|
||
| BIS BISSA-2646(1SACD) |
カレヴィ・アホ(1949-):協奏作品集 (1)リコーダーと室内管弦楽のための協奏曲(2020) (2)テナー・サクソフォーンと小管弦楽のための協奏曲(2015) (3)アコーディオンと弦楽のための協奏的ソナタ(1984/2019) |
(1)エーロ・サウナマキ(リコーダー) (2)エサ・ピエティラ(テナー・サクソフォーン) (3)ヤンネ・ヴァルケアヨキ(アコーディオン) サイマー・シンフォニエッタ、エルッキ・ラソンパロ(指) [楽器:Sopranino recorder in F:Kung (model: Superio), Eagle alto recorder in F:Adriana Breukink, Alto recorder in F:Thomas M. Prescott/Nikolaj Ronimus, Bass recorder in F:Yamaha moder YRB-61/Tenor saxophone:Selmer MK VI1958/Accordion: Pigini Nova, No.97] 録音:2022年4月19~22日、9月19&20日/ミカエリ・コンサート&コングレス・ホール(ミッケリ、フィンランド) |
|
||
| Goodies 33CDR-3911(1CDR) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番ニ短調 K.466 ピアノ協奏曲第24番ハ短調 K.491 |
アルトゥール・シュナーベル(P) ウォルター・ジュスキント(指) フィルハーモニアO 米 VCTOR LHMV-1012 1948年6月17-18(K.466)&6月18-19日 ロンドン、アビー・ロードEMI第1スタジオ録音 |
|
||
| Goodies 78CDR-3913(1CDR) |
シューマン:チェロ協奏曲イ短調作品129 | ルートヴィヒ・ヘルシャー(Vc) ヨーゼフ・カイルベルト(指) ベルリン国立歌劇場O 日VICTOR JD-1599/601(英HMV DB4550/52と同一録音) 1938年6月8日ベルリン録音 |
|
||
| Aulicus Classics FAB-0001(2CD) |
ヴィヴァルディ:「調和の霊感」 Op.3 | ロベルト・ジーニ(指) アンサンブル・コンチェルト 録音:1991年8月 イタリア ヴェネツィア |
|
||
| Resonus RES-10318(1CD) NX-B05 |
バッハ:チェンバロ協奏曲集 協奏曲 ニ短調 BWV1052 協奏曲 イ長調 BWV1055 協奏曲 ニ長調 BWV1054 協奏曲 ニ短調 BWV1059 (スティーヴン・デヴァインによる再構築版) |
スティーヴン・デヴァイン(チェンバロ&指揮) 使用楽器=ハンス・クリストフ・フライシャー(ハンブルク)が1710年に製作し た1段鍵盤のチェンバロを参考に、コリン・ブースが2000年に製作した2段 鍵盤チェンバロ エイジ・オブ・インライトゥメントO(古楽器使用)【Margaret Faultless(Vn)、Kati Debretzeni(Vn)、Max Mandel(Va)、Andrew Skidmore(Vc)、Christine Sticher(Cb)、Katharina Spreckelsen(Ob)(BWV 1059のみ)】 ピッチ a'=415Hz 録音:2022年3月1-3日 |
|
||
| ALPHA ALPHA-937(1CD) NYCX-10412(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
モーツァルトとマンボ3~美しきキューバ娘 モーツァルト:ホルン協奏曲 第4番 変ホ長調 K.495 エドガー・オリヴェロ(1985-):ルンバ風ロンド 協奏交響曲 変ホ長調 K.297b ホセ・ホワイト・ラフィット(ホルヘ・アラゴン編):美しきキューバ娘 ホセイト・フェルナンデス(アラゴン編):グァンタナメラ |
サラ・ウィリス(Hrn) ジョナサン・ケリー(Ob) ヴェンツェル・フックス(Cl) シュテファン・シュヴァイゲルト(Fg) ハロルド・マドリガル・フリアス(Tp) サラバンダ【サラ・ウィリス(Hrn)、ジュニエト・ロンビーダ(Sax)、ジャネル・ラスコン(P)、レオ・A. ルナ(ベース)、アレハンドロ・アギアル(カホン、マラカス)、アデル・ゴンサレス(コンガ)、エドゥアルド・ラモス(ティンバレス)】 ハバナ・リセウム・オーケストラ アデル・ゴンサレス(パーカッション/スペシャル・ゲスト) ホセ・アントニオ・メンデス・パドロン(指) 録音:2022年4月 ハバナ、キューバ 国内仕様盤日本語解説…今泉晃一 |
|
||
| ALPHA ALPHA-985(1CD) |
バッハ・ミニマリスト ~バッハ、グレツキ、アダムズ バッハ:チェンバロ協奏曲 第1番 ニ短調 BWV1052 1. I. Allegro ヘンリク・グレツキ:チェンバロ協奏曲 Op.40 2. I. Allegro molto クヌート・ニーステッド(1915-2014)/シモン=ピエール・ベスティオン編曲: 3. 不滅のバッハ(弦楽合奏) ジョン・アダムズ(1947-):シェーカー・ループス 4. I. Shaking and Trembling ジャン・アラン(1911-1940)/ベスティオン編曲: 5. リタニ アダムズ:シェーカー・ループス 6. II. Hymning Slews バッハ//ベスティオン編曲: 7. パッサカリア ハ短調 BWV582 ニーステッド/ベスティオン編曲: 8. 不滅のバッハ(無伴奏合唱) バッハ:チェンバロ協奏曲 第1番ニ短調 BWV 1052 9. III. Allegro グレツキ:チェンバロ協奏曲 Op.40 10. II. Vivace marcatissimo アダムズ:シェーカー・ループス 11. III. Loops and Verses 12. IV. A Final Shaking バッハ: 13. コラール「汝の御座の前に、われ進み出で」 BWV668(弦楽合奏) |
ルイ=ノエル・ベスティオン・ド・カンブラ(Cemb) ラ・タンペート(弦楽合奏、合唱…8) シモン=ピエール・ベスティオン((指)編) 録音:2022年4月 サン=ピエール・ルーテル教会、パリ |
|
||
| DACAPO MAR-8.224753(1CD) NX-B08 |
アウゴスト・エナ(1859-1939):ヴァイオリン協奏曲 ニ長調(1896) 交響曲第2番ホ長調(1907) |
アンナ・アガフィア(Vn) ボゴタPO ヨアキム・グスタフソン(指) 録音:2022年9月26-29日 |
|
||
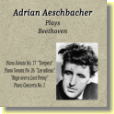 Treasures TRE-297(1CDR) |
エッシュバッハーのベートーヴェン ピアノ・ソナタ第17番Op.31-2「テンペスト」 ピアノ・ソナタ第26番Op.81a「告別」* ロンド・ア・カプリッチョ「なくした小銭への怒り」Op.129 ピアノ協奏曲第1番ハ長調Op.15# |
アドリアン・エッシュバッハー(P) ウィルヘルム・フルトヴェングラー(指)# ルツェルン祝祭O# 録音:1950年9月19日、1951年5月22日*、1947年8月27日# ※音源:独DG LPM-18220、米Discocorp RR-438# ◎収録時間:79:15 |
| “大指揮者と対等に音楽を紡ぎ合った美しき協奏!” | ||
|
||
| DOREMI DHR-8207(2CD) |
マルタ・アルゲリッチLIVE第16集 (1)ハイドン:ピアノ協奏曲 ニ長調 Hob.XVII:11 (2)プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第3番ハ長調 Op.26 (3)ラヴェル:ピアノ協奏曲 ト長調 (4)ショパン:ピアノ・ソナタ第3番ロ短調 Op.58 ヒナステラ:アルゼンチン舞曲 Op.2-2 スカルラッティ:ソナタ ニ短調 L.422, K.141 (5)ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 Op.60、夜想曲 ヘ長調 Op.15-1、マズルカ ハ長調 Op.24-2、マズルカ イ短調 Op.59-1、マズルカ 変 イ長調 Op.59-2、夜想曲 変ホ長調 Op.55-2、スケルツォ第3番 嬰ハ短調 Op.39、練習曲 嬰ハ短調 Op.10-4 (6)バルトーク:2台のピアノと打楽器のためのソナタ Sz.110 |
マルタ・アルゲリッチ(P) (1)ロンドン・シンフォニエッタ 録音:1980年6月6日ミラノ (2)クラウディオ・アバド(指)、フランス国立O 録音:1969年11月12日パリ (3)シャルル・デュトワ(指)、ローザンヌ室内O 録音:1959年1月19日ローザンヌ (4)録音:1979年4月22日アムステルダム・リサイタル (5)録音:1967年6月5日ベルガモ・リサイタル (6)スティーヴン・コヴァセヴィチ(P)、ウィリー・ハウドスワールト&ミカエル・デ・ルー(打楽器) 録音:1977年5月8日/アムステルダム・リサイタル |
|
||
| Naive OP-7368(1CD) |
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集XI~アンナ・マリアに捧ぐ~ ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 RV229、変ロ長調 RV363(Il corneto da posta/ポストホルン)、ニ長調 RV207、 変ホ長調 RV260、ハ長調 RV179a、変ホ長調 RV261、ラルゴ(RV179aより~オリジナルの装飾音で演奏) |
ファビオ・ビオンディ(Vn、指) エウローパ・ガランテ 録音:2020年10月9-13日、イタリア |
|
||
| H.M.F HMM-931833(1CD) |
ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲イ短調op. 53 ピアノ三重奏曲 第3番ヘ短調 op.65* |
イザ ベ ル・ファウスト(Vn) ジャン=ギアン・ケラス(Vc) アレクサンドル・メルニコフ(P)) イルジー・ビエロフラーヴェク(指) プラハ・フィルハーモニア 録音:2003年9月ルドルフィヌム、プラハ 2003年12月テルデックス・スタジオ、ベルリン* |
|
||
| H.M.F HMM-931816(1CD) |
ハイドン:チェロ協奏曲第1番ハ長調 Hob.VIIb-1 チェロ協奏曲第2番ニ長調 Hob.VIIb-2 モン(1717~50):チェロ協奏曲 ト短調 |
ジャン=ギアン・ケラス(Vc) ペトラ・ミュレ ヤンス (指&Vn) フライブルク・バロック・オーケストラ 録音:2003年3月、テルデックス・スタジオ・ベルリン |
|
||
| DUX DUX-1958(1CD) |
ポーランドの協奏曲集 Vol.1 マルセロ・ニシンマン(1970-):ポーランドの旋律による13の変奏曲(2018)~ヴァイオリン、チェロと室内オーケストラのための ミコワイ・グレツキ(1971-):セカンド・スペース(2010)~弦楽四重奏と弦楽オーケストラのための パヴェウ・ウカシェフスキ(1968-):ネオポリス・コンチェルト(2017)~ヴァイオリンと弦楽オーケストラのための エヴァ・ファビアンスカ=イェリンスカ(1989-):ヴィオラ協奏曲(2015)~ヴィオラと弦楽オーケストラのための* |
エマヌエル・サルヴァドール(Vn、指)、 アンドリー・ヴィトヴィッチ(Va)、 エミリア・ゴフ・サルヴァドール(Va)*、 コンスタンティン・ハイドリッヒ(Vc)、 バルティック・ネオポリスO 録音:2022年 |
|
||
| ANTARCTICA ANTAR-046(1CD) |
ロベール・グロスロ(1951-):ヴァイオリン協奏曲第2番Op.129 Now, Voyager, sail...(交響曲第1番) Op.130* |
リナス・ロス(Vn) ロベール・グロスロ(指) ブリュッセル・フィルハーモニック 録音:2020年4月19日、9月3日、2021年6月14・15日* |
|
||
| SWR music SWR-19129CD(1CD) NX-B02 |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第15番変ロ長調 K.450 ピアノ協奏曲第20番ニ短調 K.466(カデンツァ=ベートーヴェン) |
アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(P) シュトゥットガルトRSO アントワーヌ・ド・バヴィエ(指) 録音:1956年7月11日(モノラル・ライヴ) |
|
||
| Acte Prealable AP-0560(1CD) |
アルトゥル・チェシラク(b.1968):協奏曲集 クラリネット協奏曲 左手のためのピアノ協奏曲 管楽器と打楽器のための音楽(2人のドラマーと指揮者を伴うヴァージョン) クラリネット・ソナタ |
バルバラ・ハレツ(指)、 ミレナ・パルカイ(P)、 ボグスワフ・ヤクボフスキ(Cl)、 マルタ・ミクリンスカ(パーカッション)、 シモン・ガツェク(パーカッション)、 クシシュトフ・ソヴィンスキ(P)、 フィールハーモニー・クインテット(木管五重奏団)、 シュチェチン芸術アカデミーの器楽奏者たち |
|
||
| Chandos CHAN-20168(1CD) XCHAN-20168(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
シュトラウス、シューマン、ウェーバー:ホルン協奏曲集 シューマン:4本のホルンと管弦楽のためのコンツェルトシュテュック Op.86* ウェーバー:ホルン小協奏曲 ホ短調 Op.45, J188 R.シュトラウス:ホルン協奏曲第1番変ホ長調 Op.11, Trv117、 ホルン協奏曲第2番変ホ長調 Trv283 |
マーティン・オーウェン(Hrn) クリストファー・パークス(Hrn)* アレック・フランク=ゲミル(Hrn)* サラ・ウィリス(Hrn)* ジョン・ウィルソン(指)、 BBCフィルハーモニック 録音:2022年4月25日(コンツェルトシュテュック)、9月30日&10月10日(その他の作品)、メディア・シティUK(サルフォード、イギリス) |
|
||
| Signum Classics SIGCD-764(1CD) |
バッハ:ハープシコード協奏曲集 Vol.2 バッハ:ブランデンブルク協奏曲第5番 ニ長調 BWV1050 ハープシコード協奏曲 ホ長調 BWV1053 ハープシコード協奏曲 ヘ短調 BWV 1056 ハープシコード協奏曲 ヘ長調 BWV 1057 |
ハノーヴァー・バンド、 アンドルー・アーサー(指&ハープシコード) 録音:2019年5月&2022年3月、セント・ニコラス教会(アランデル、イギリス) |
|
||
| Chopin University Press UMFCCD-137(1CD) |
ル・クラヴサン・モデルヌ・プラス・パーカッション
Vol.1 ミコワイ・ヘルテル(b.1948):ハープシコード、弦楽と打楽器のための組曲「スペインの踊り子」* グラント・マクラクラン(b.1956):「アフリカの祝祭」 (ハープシコードとアフリカン・パーカッションのための) アンジェイ・カラウォフ(b.1991):「フェイタル・ミラーズ」 (打楽器とハープシコードのための) ミコワイ・ヘルテル:「アウト・オヴ・タイム」 (フルート、打楽器とハープシコードのための)* |
アリナ・ラトコフスカ(ハープシコード)、 レシェク・ロレント(パーカッション)、 アガタ・イグラス(Fl)、 ヤン・グララ(パーカッション)、 ショパン音楽大学室内O、 ラファウ・ヤニャク(指) 録音:2021年4月14日、6月28日、8月5日‐6日(ポーランド、ワルシャワ) *世界初録音 |
|
||
| NEOS NEOS-1231314(2CD) |
現代のヴィオラ協奏曲集 1. クリスティアン・ヨースト(b.1963):Mozarts 13097. Tag(2005)~ヴァイオリン、ヴィオラとオーケストラのための協奏交響曲* 2. ハンス・ウルリヒ・レーマン(1937-2013):Contradictions(2008)~独奏ヴィオラと室内オーケストラのための* 3. ナディア・ヴァッセナ(b.1970):D’oltremare(2012)~ヴィオラと小オーケストラのための* 4. ダーフィト・フィリップ・ヘフティ(b.1975):Cantabile(1975)~ヴィオラとオーケストラのための協奏曲* 5. モートン・フェルドマン(1926-1987):The Viola in My Life IV(1971)~ヴィオラとオーケストラのための 6. ギヤ・カンチェリ(1935-2019):Styx(1999)~ヴィオラ、混声合唱とオーケストラのためののための 7. ハインツ・ホリガー(b.1939):Recicanto(2001)~ヴィオラと小オーケストラのための |
ユルク・デーラー(Va)、 ウィリ・ツィンマーマン(Vn)、 コレギウム・ムジクム・ヴィンタートゥール、スイス室内cho ヤック・ファン・ステーン(指/1,6)、 ハインツ・ホリガー(指/2,7)、 ダグラス・ボイド(指/3)、 ダーフィト・フィリップ・ヘフティ(指揮/4)、ベアート・フラー(指/5) 録音:1999年~2021年(2を除きライヴ録音) *世界初録音 |
|
||
| Challenge Classics CC-72951(1CD) |
サン・サーンス:ヴァイオリン協奏曲第3番ロ短調 Op.61 グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲 イ短調 Op.82 |
ルドルフ・コエルマン(Vn) パウル・K・ハウク(指) シンフォニエッタ・シャフハウゼン 録音:2021年11月18・19日シャフハウゼン、聖ヨハネ教会 |
|
||
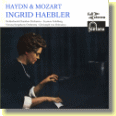 Treasures TRE-312(1CDR) |
ヘブラー~ステレオ初期の協奏曲録音集 ハイドン:ピアノ協奏曲 ニ長調Hob.18-11* モーツァルト:ピアノ協奏曲第18番変ロ長調K.456 ピアノ協奏曲第27番変ロ長調K.595 |
シモン・ゴールドベルク(指)オランダ室内O*
クリストフ・フォン・ドホナーニ(指)ウィーンSO 録音:1960年7月1-3日*、1959年5月9-11日 ※音源:蘭PHILIPS 802737DXY*、日Victor SFON-7508 ◎収録時間:79:52 |
| “穏やかなだけではないヘブラーの頑なにブレないピアニズム!” | ||
|
||
| Indesens Calliope Records IC-013(1CD) |
シャモー:協奏曲集 フィリップ・シャモー:ヴァイオリンと管弦楽のための小協奏曲 バスーンと管弦楽のための協 奏曲 トランペットと管弦楽のための夜想協奏曲 |
エリック・オービエ(Tp)、 スヴェトリン・ルセフ(Vn)、 ジョルジオ・マンドレージ(バスーン)、 ジャン=ジャック・カントロフ(指)ドゥエO 録音:2023年2月6日-7日(ドゥエ、フランス) |
|
||
| Chopin University Press UMFCCD-143(1CD) |
ニュー・ダブル・アコーディオン・コンチェルトズ
バッハ:2台のハープシコード協奏曲 ハ短調 BWV1060/2台のハープシコード協奏曲 ハ長調 BWV1061/2台のハープシコード協奏曲 ハ短調 BWV1062 |
デュオアコスフィア〔グジェゴシュ・パルス(第1アコーディオン)、アレナ・ブジニャーコヴァー(第2アコーディオン)〕、カペラ・クラコヴィエンシス弦楽五重奏団 録音:2019年 |
|
||
| MIRARE MIR-670(1CD) |
Momentum1 ウォルトン:ヴァイオリン協奏曲(ロ短調) レスピーギ:ヴァイオリン・ソナタ(ロ短調) |
リヤ・ペトロワ(Vn/Helios、1735年カルロ・ベルゴンツィ製) ロイヤルPO ダンカン・ウォード(指) アダム・ラルーム(P) 録音:[ウォルトン]2022年9月5日、ロンドン/[レスピーギ]2023年1月28-29日 |
|
||
| PROSPERO CLASSICAL PROSP-0071(1CD) |
旅へのいざない ~ラロの「ロシア協奏曲」とその原曲ほか (1)デュパルク:旅へのいざない(Vnと管弦楽のための編曲版) (2)ラロ:ヴァイオリン協奏曲第1番ヘ長調 Op.20 (3)サン・サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ (4)ラロ:ヴァイオリン協奏曲第4番ト短調 『ロシア協奏曲』 (5)リムスキー=コルサコフ:『100のロシア民謡』 Op.24より 「エヴラシェヴォ村の鐘が鳴る」(弦楽合奏のための編曲版) (6)ラロ:ヴァイオリン協奏曲第4番ト短調 『ロシア協奏曲』 Op.29第2~4楽章 (7)リムスキー=コルサコフ:『100のロシア民謡』 Op.24より 「ノヴゴロドに鳴り響く鐘」(Vn、バセットホルン、チェレスタ、ハープ、チェロのための編曲版) (8)ムソルグスキー:愛しいサーヴィシナ(Vn、チェロ、コントラバス、クラリネット、ホルン、ファゴットのための編曲版) |
ドミトリー・スミルノフ(Vn、編曲(5)(7)(8))
ハインツ・ホリガー(指) バーゼル室内O 録音:2022年2月23-25日/スイス、ドン・ボスコ・バーゼル |
|
||
| Pentatone PTC-5187110(1CD) |
ロシアン・コンチェルト集 ハチャトゥリアン:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲 イ短調 Op.82 |
ユリア・フィッシャー(Vn) ヤコフ・クライツベルク(指)、 ロシア・ナショナルO 録音:2004年5月12&13日DZZ第5スタジオ(モスクワ) |
|
||
| Goodies 78CDR-3909(1CDR) |
ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調作品26 | ユーディ・メニューイン(Vn) ピエール・モントゥー(指)サンフランシスコSO 米 VICTOR11-8951/53 1945年1月27日サンフランシスコ録音 |
|
||
| Goodies 78CDR-3910(1CDR) |
ショパン:ピアノ協奏曲第2番ヘ短調作品21 ワルツ第7番嬰ハ短調作品64-2 |
アルトゥール・ルービンシュタイン(P) ジョン・バルビローリ(指)LSO 英 HMV DB1494/7 1931年1月8-9日ロンドン、キングズウェイ・ホール(協奏曲) 1930年12月17日ロンドン、小クイーンズ・ホール内スタジオC録音 |
|
||
| MDG MDG-92622816(1SACD) |
ヴィルトゥオーゾの芸術 Vol.2~ソロ・コンチェルト集 モーツァルト:3つのピアノ協奏曲~第3番変ホ長調KV107(J.C. バッハのソナタ編) マルティン・ザイフェルト(1681-1745):オーボエ協奏曲ハ短調 ヨハン・ジギスムント・ヴァイス(1690-1737):リュートと弦楽のための協奏曲ト短調 フランティシェク・イラーネク(1698-1778):ヴァイオリン協奏曲イ長調 ヨハン・メルヒオール・モルター(1696-1765):ソナタ・グロッサ(3トランペット、2オーボエ、ティンパニ、弦楽、通奏低音)) ヨゼフ・ヘフナー(19世紀前半):キートランペットのための序奏とポロネーズ |
ソリスト; アダ・タニール(Cemb) ハンス・ハインリヒ・クリーゲル(Ob) 佐々木勇一(Lute) エルケ・ファブリ(Vn) ペドロ・H・デ・ソウザ・ローサ(キートランペット) カテルヴァ・ムジカ 録音:2022年6月2日、9月2,4日、10月27-29日、、マリエンミュンスター修道院コンツェルト |
|
||
| Challenge Classics CC-72942(1CD) |
『オルフェウスの降下』 ~ロビン・デ・ラーフ(1968-):作品集 (1)ピアノ協奏曲第2番『キルクルス』(2021-2022) (2)室内管弦楽のための『オルフェウスの降下』(2002-2003) (3)ヴァイオリン協奏曲第2番『北大西洋の光』(2002-2003) |
(1)ラルフ・ファン・ラート(P)、マティアス・ピンチャー(指)、ネーデルラント放送PO
(2)ローレンス・レネス(指)、ネーデルラント放送PO (3)トスカ・オプダム(Vn)、マルク・アルブレヒト(指)、ネーデルラントPO 録音:(1)2022年6月10日/アムステルダム、ヴェスターガスファブリーク (2)2020年11月21日アムステルダム、コンセルトヘボウ、 (3)2019年5月20日アムステルダム、コンセルトヘボウ" |
|
||
| Hanssler HC-23013(1CD) |
ライネッケ:フルート協奏曲 ニ長調 Op.283 ペンデレツキ:フルートと室内オーケストラのための協奏曲* |
クシシュトフ・カチカ(Fl) ヤナーチェクPO、 フェリペ・トリスタン(指) 録音:2022年6月21&22日、2022年6月30日~7月1日*/オストラバ(チェコ) |
|
||
 King International KKC-4336(1SACD) 限定発売 |
フルトヴェングラー&メニューイン ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 交響曲第1番ハ長調 作品21* |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) BPO、VPO* ユーディ・メニューイン(Vn) 録音:1947年9月28日ティタニア・パラスト、ベルリン(ライヴ)、1952年11月30日ムジークフェラインザール、ウィーン(ライヴ)* 解説:宇野功芳 |
|
||
| DOREMI DHR-8205(2CD) |
マルタ・アルゲリッチLIVE第15集 (1)ショパン:ピアノ協奏曲第1番ホ短調 Op.11 (2)ショパン:ピアノ協奏曲第2番へ短調 Op.21 (3)シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 Op.54 (4)モーツァルト:アンダンテと変奏曲 ト長調 K.501 (5)ドビュッシー:白と黒で (6)シューマン:アンダンテと変奏曲 Op.46a (7)リスト:3つの演奏会用練習曲 S.144より 第2番「軽やかさ」 ドビュッシー:『版画』より 第3曲 「雨の庭」 ラヴェル:水の戯れ |
マルタ・アルゲリッチ(P) (1)ルイ・マルタン(指)、スイス・ロマンドO ライヴ録音:1959年9月25日/ジェノヴァ (2)クラウス・テンシュテット(指)、北ドイツRSO ライヴ録音:1979年6月18日/キール (3)クラウス・テンシュテット(指)、北ドイツRSO ライヴ録音:1980年5月12日/シュトゥットガルト (4)(5)スティーヴン・コヴァセヴィチ(P)] (6)アレクサンドル・ラビノヴィチ(P)、フリードリヒ・ドレシャル(Vc)、ミッシャ・マイスキー(Vc)、マリー=ルイーズ・ノイネッカー(Hrn)] ライヴ録音:1977年5月8日/アムステルダム (7)ライヴ録音:1973年4月17日/ニューヨーク |
|
||
 Spectrum Sound CDSMBA-140(2CD) |
ダヴィド・オイストラフ・ライヴ・イン・パリ1958 (1)バッハ:ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 BWV1041 (2)ブラームス:ヴァイオリン協奏曲(カデンツァ:ヨアヒム) (3)ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲(カデンツァ:クライスラー) (4)ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第10番 ト長調 Op.96 |
ダヴィド・オイストラフ(Vn) (1)-(3)アンドレ・クリュイタンス(指)、 フランス国立放送O (4)レフ・オボーリン(P) 録音:(1)-(3)1958年10月27日シャイヨー国立劇場、パリ(ライヴ)(モノラル) (4)1962年6月18日フランス国営放送局内スタジオ(放送用収録)(モノラル) |
|
||
| Goodies 78CDR-3905(1CDR) |
牧神の午後への前奏曲-マルセル・モイーズの芸術 ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲 フェルー: 無伴奏フルートのための3つの小品 (1)恋する羊飼い (2)硬玉 (3)端陽 イベール:フルート協奏曲 |
マルセル・モイーズ(Fl) ワルテル・ストララム(指)ストララムO(ドビュッシー) ウジェーヌ・ビゴー(指)交響楽団(イベール) 仏COLUMBIA LFX30 1930年2月24日録音(ドビュッシー)、 仏COLUMBIA DFX194 1933年パリ録音(フェルー)、 仏DISQUE GRAMOPHONE L1013/4 1934年パリ録音(イベール) |
|
||
| Gramola GRAM-99268(1CD) |
リヒテンタール博士のモーツァルト ピアノ協奏曲第20番ニ短調 K.466(Pと弦楽四重奏版) 幻想曲第4番ハ短調 K.475(Pとチェロ版)* ピアノ・ソナタ第14番ハ短調 K.457(Pとチェロ版)* ※全てペーター・リヒテンタール(1779/80-1853)による編曲版 |
アウレリア・ヴィショヴァン(ハンマークラヴィーア) Johann Frenzel製作(1828年頃) パンドルフィス・コンソート(古楽器使用) ピッチ a=436Hz 録音:2022年5月5-7日 *…世界初録音 |
|
||
| Christophorus CHR-77471(1CD) |
ヴィヴァルディのサルテリオ ヴィヴァルディ:協奏曲 ハ長調 RV186、 協奏曲 ホ短調 RV275、 協奏曲 ヘ長調 RV294aよりアンダンテ、 協奏曲 ニ長調 RV84、 協奏曲 ト短調 RV156、 ソナタ ト長調 RV820、 ソナタ ロ短調 RV35a, RV37a、 協奏曲 ロ短調 RV388、 協奏曲 ニ長調 RV220、歌劇「ジュスティーノ」のアリア「Ho nel petto un cor si forte」による幻想曲 作曲家不詳(18世紀ヴェネツィア):ソナタホ短調よりアダージョ |
フランツィスカ・フライシャンデール(サルテリオ&指揮)、 イル・ドルチェ・コンフォルト 録音:2022年10月&11月、グレンザッハ=ヴィーレン福音教会(ドイツ) |
|
||
| Glossa GCD-P-31910(1CD) |
バッハ:リコーダー協奏曲集 協奏曲ニ長調 BWV1053(R) カンタータ第76番 「天は神の栄光を語る」 BWV.76より シンフォニア 協奏曲ト短調 BWV1056(R) 協奏曲イ長調 BWV1055(R) カンタータ第182番「天の王よ、ようこそ来ませ」 BWV.182よりソナタ 協奏曲ハ短調 BWV1060(R) |
ロレンツォ・カヴァサンティ(リコーダー)、リアナ・モスカ(Vn・ソロ/tr.5-7、11-14)ジュゼッペ・マレット(ディレクター)、カンティカ・シンフォニア〔リアナ・モスカ(Vn、ヴィオラ/BWV76)、エフィクス・プレオ(Vn、ヴィオラ/BWV182)、アレッサンドロ・コンラド(Vn/BWV1055&1060)、エレナ・サッコマンディ(Va)、二コラ・ブロヴェッリ(Vc)、フェデリコ・バニャスコ(ヴィオローネ)、キアラ・カッターニ(ハープシコード、オルガン)〕 録音:2021年1月2日-5日&2022年11月21日、サルッツォ(イタリア) |
|
||
| LAWO Classics LWC-1255(1CD) PLWC-1255(1CD) 国内盤仕様 税込定価 |
忍耐 フィリップ・グラス(b.1937):ヴァイオリン協奏曲第2番「アメリカの四季」〔プロローグ、第1楽章、ソング第1番、第2楽章、ソング第2番、第3楽章、ソング第3番、第4楽章〕 シェティル・ビェルケストラン(b.1955):ヴァイオリン協奏曲第1番「忍耐」〔命知らず、1と20、下りと上り、セブン、浮き沈み、忍耐〕 |
サラ・オーヴィンゲ(Vn)、 ノルウェー室内O、 エドワード・ガードナー(指) 録音:2021年8月2日-6日、ソフィエンベルグ教会(オスロ、ノルウェー) ※国内盤:解説日本語訳&日本語曲目表記オビ付き |
|
||
| GENUIN GEN-23842(1CD) |
ブローウェル、レムケ、モラ、ドックス:ギターとアコーディオンのための作品集
ブローウェル(1939-):ベートーヴェンによる協奏的変奏曲(2020)、Bomarzos Tales(2022) サーシャ・リノ・レムケ(1976-):Atemschaukel(2021)* エディー・モラ(1965-):ルクス・ノヴァ(2021) ヘクター・ドックス(1993-):3つの変容(2022) |
ルクス・ノヴァ・デュオ 〔リディア・シュミードル(アコーディオン)、ホルヘ・パス・ベラステギ(G)〕、 マルチア・レムケ=ケルン(S)*、 ハイルブロン・ヴュルテンベルク室内O、 エディー・モラ(指) 全て世界初録音 |
|
||
| Forgotten Records fr-1879(1CDR) |
チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番* 幻想序曲「ロメオとジュリエット」# リムスキー=コルサコフ:スペイン奇想曲 + |
アルトゥール・ルービンシュタイン(P)* ロリン・マゼール(指) フランス国立RSO*、BPO 録音:1959年9月22日モントルー音楽祭(ライヴ)*、1957年6月24日#、1958年12月10日+ ※音源:DG LPM 18382#、SLPM 138033 + |
| Forgotten Records fr-1887(1CDR) |
ヤコブ・ギンペル/シューマン&グリーグ シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調 |
ヤコブ・ギンペル(P) アルトゥール・ローター指揮 ベルリンSO 録音:1960年(ステレオ) ※音源: Opera 1184 |
| Forgotten Records fr-1889(1CDR) |
ヘブラー/モーツァルト:ピアノ協奏曲Vox録音集2 ピアノ協奏曲第5番ニ長調 K.175 ピアノ協奏曲第13番ハ長調 K.415 # ピアノ協奏曲第23番イ長調 K.488 |
イングリッド・ヘブラー(P) パウル・ヴァルター(指) ウィーン・プロ・ムジカO 録音:1956年、1956年5月7日-8日# ※音源: Vox PL 9830、PL 10080 |
| ALPHA ALPHA-991(1CD) |
次世代ソリストたちによるモーツァルト Vol.6 ピアノ協奏曲 第11番ヘ長調 K.413(カデンツァ…モーツァルト) ピアノ協奏曲 第13番ハ長調 K.415(カデンツァ…モーツァルト) オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314(カデンツァ…ガブリエル・ピドー)* |
ロマン・ボリソフ(P/ベーゼンドルファーVC280) ガブリエル・ピドー(Ob)* ウィーンRSO ザルツブルク・モーツァルテウムO* ハワード・グリフィス(指)* 録音:2022年9月 オーストリア放送スタジオ6/大ホール、ウィーン 2022年3月 オルケスターハウス、ザルツブルク* |
|
||
| DIVOX CDX-72201(1CD) NX-B03 |
ヴェニスのバッハ バッハ:協奏曲 ニ長調 BWV972(原曲:ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 RV230) 協奏曲 ト長調 BWV973(原曲 ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲 ト長調 RV299) 協奏曲 ハ長調 BWV976(原曲:ヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲 ホ長調 RV265) 協奏曲 ニ短調 BWV974(原曲:A. マルチェッロのオーボエ協奏曲) 協奏曲 ト長調 BWV980(原曲:ヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 RV381) 協奏曲 ヘ長調 BWV978(原曲:ヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲 ト長調 RV310) ※全てジューリオ・デ・ナルドによるチェンバロと室内アンサンブル編 |
ジューリオ・デ・ナルド(Cemb) セスティエール・アルモニコ(古楽器使用) 録音:2021年8月18-21日 全て世界初録音 |
|
||
| SOUPIR EDITIONS S-256(1CD) |
アルフレード・ダンブロージョ(1871-1914):ヴァイオリン作品集 (1)ヴァイオリン協奏曲第1番ロ短調 Op.29 (2)ヴァイオリン協奏曲第2番ト短調 Op.51 (3)カンツォネッタ ト長調 Op.28 (4)ロマンス ニ長調 Op.9 (5)導入とユモレスク イ短調 Op.25 (6)セレナード ニ長調 Op.4 (7)カンツォネッタ ト短調 Op.6 |
ジャン=ジャック・カントロフ(Vn) (1)(2)アリー・ファン・ベーク(指) オー・デ・フランス地域圏ドゥエーO (3)-(7)上田晴子(P) 録音:2021年10月22,24日,2022年7月27日 フランス オー・デ・フランス地域圏 ドゥエー |
|
||
| AAM Records AAM-42(1CD) NX-B08 NYCX-10404(1CD)「 国内盤仕様 税込定価 |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第5番/教会ソナタ
他 協奏曲の楽章 ト長調-『ナンネルの音楽帳』より(R. レヴィン復元) ピアノ協奏曲第5番ト長調 K.175* ピアノ協奏曲 ニ長調 K.107No.1 ピアノ協奏曲 ト長調 K.107No.2 ピアノ協奏曲 変ホ長調 K.107No.3 教会ソナタ第17番ハ長調 K.336* (カデンツァ:ロバート・レヴィンの即興演奏) |
ロバート・レヴィン(チェンバロ&オルガン*) 使用楽器 チェンバロ:ストラスブールのヨハン=ハインリヒ・ジルバーマン、1770年頃製モデルによる再現楽器、アラン・ゴット2013年製作 オルガン:ジョージ・イングランド1760年建造、 ウィリアム・ドレイク2009年レストア アカデミー・オヴ・エンシェント・ミュージック(古楽器使用) ボヤン・チチッチ(指) ローレンス・カミングス(指)* 録音:2021年12月8-9日、2022年8月18-20日 ※国内仕様盤には大津聡氏による日本語解説が付属します。 |
|
||
| CD ACCORD ACD-319(1CD) NX-C03 |
プーランク/ジョンゲン:オルガンとオーケストラのための協奏曲 プーランク:オルガンと弦楽合奏、ティンパニのための協奏曲 ジョンゲン:協奏交響曲 Op.81 |
カロル・モサコウスキ (Org) NFMヴロツワフPO ジャンカルロ・ゲレーロ(指) 録音:2021年6月8日、2022年10月21-24日 |
|
||
| GEGA NEW GD-418(1CD) |
「砂川晴彦の思い出に」~ヤッセン・ヴォデニチャロフ(b.1964):作品集 (1)ルバイヤット(ウマル・ハイヤームの詩による5つのワインの歌) (2)ピアノ協奏曲「水晶の森からの響きとささやき」 (3)アポクリファ(A.タルコフスキーに捧ぐ) (4)サクソフォン協奏曲「砂の歌」 (5)シンフォニア(リュドミラ・ヴィデニチャロフの詩による) |
(1)エメリ・ルフェーブル(Br) レオ・マルグ(指)アンサンブル・ラティネレール (2)デシスラヴァ・シュテレヴァ(P) イワン・ストヤノフ(指)ガヴロボ室内O (3)エレクトロアコースティック作品 (4)ニコラス・ケープランド(A.Sax) ヴセヴォロド・シュムイレヴィッチ(指) パリ・サクソフォーン・アンサンブル (5)テオドラ・ペトロヴァ(S) ナディヤ・パヴロヴァ(Ms) イワン・ストヤノフ(指)ブルガリア国立RSO |
|
||
 Spectrum Sound CDSMBA-137(1CD) |
フルノー&ケンプ (1)モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番ニ短調 K.466(31'29) (2)モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番ニ短調 K.466(29'25) |
(1)マリー=テレーズ・フルノー(P)、 ルネ・ジラール(指)フランス国立放送O (2)ヴィルヘルム・ケンプ(P)、 ゲオルク・ショルティ(指)パリ音楽院O 録音:(1)1967年5月22日メゾン・ド・ラジオ・フランス、105スタジオ(パリ)(モノラル)【初出音源】 (2)1959年9月3日/ブザンソン市民劇場(モノラル)【初出音源】 |
|
||
| REFERENCE FR-751SACD (3SACD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集 ピアノ協奏曲 第1番ハ長調 Op.15 ピアノ協奏曲 第2番変ロ長調 Op.19 ピアノ協奏曲 第3番ハ短調 Op.37 ピアノ協奏曲 第4番ト長調Op.58 ピアノ協奏曲 第5番『皇帝』 「プロメテウスの創造物」序曲 |
ギャリック・オールソン(P) サ-・ドナルド・ラニクルズ(指) グランド・ティトン音楽祭祝祭O 録音:2022年7月5日~9日 ウォーク・フェスティヴァル・ホール、ワイオミング州、アメリカ(グランドティトン音楽祭) |
|
||
| BIS BISSA-2532(1SACD) |
ラウタヴァーラ:ピアノ協奏曲第3番「夢の贈り物(Gift of Dreams)」(1998)
マルティヌー:ピアノ協奏曲第3番(1947-48) |
オッリ・ムストネン(P/スタインウェイD ) ラハティSO、 ダリア・スタセフスカ(指) 録音:2022年1月3-8日/シベリウスホール(ラハティ、フィンランド) |
|
||
| ANTARCTICA ANTAR-050(1CD) |
Overtones 細川俊夫:2つの日本民謡より さくら、散る(2008-2009) ケージ:イン・ア・ランドスケープ(1948) ジェフリー・ゴードン:ハープと管弦楽のための協奏曲『エオリアン』(2022)* マクミラン:ハープ独奏のための『ノックルーン・ワルツ』(2015)* 細川俊夫:2つの日本民謡より 五木の子守唄(2008-2009) |
エリーネ・グロスロ(Hp) カレン・カメンシェク(指)、 ブリュッセル・フィルハーモニック *=世界初録音 |
|
||
| Challenge Classics CC-72949(1CD) |
サン=サーンス&ラロ:チェロ協奏曲集 サン=サーンス:チェロ協奏曲第1番 『動物の謝肉祭』 R.125より 「白鳥」 アレグロ・アパッショナート Op.43 ラロ:チェロ協奏曲 ニ短調 |
マヤ・ボグダノヴィッチ(Vc) ボヤン・スジッチ(指)RTS響 録音:2022年3月-6月/ベオグラード、コララク・コンサートホール |
|
||
| Challenge Classics CC-72960(1CD) |
もっとバッハを C.P.E.バッハ:シンフォニア ハ長調 H.659Wq.182-3 バッハ:ブランデンブルク協奏曲第3番 ト長調 BWV1048/ 同第5番ニ長調 BWV1050 W.F.バッハ(1710-1784):シンフォニア ヘ長調『不協和音』 Fk67 |
ユルゲン・グロス(Vn 、指) エルビポリス・バロックオーケストラ 録音:2022年10月2-5日/ブレーメン、ゼンデザール |
|
||
| Chandos CHSA-5281(1SACD) |
イシュムラトフ:ピアノ協奏曲&ヴィオラ協奏曲第1番 アイラット・イシュムラトフ(1973-):ピアノ協奏曲 Op.40 ヴィオラ協奏曲第1番Op.7 |
ジャン=フィリップ・シルヴェストル(P)、 エルヴィラ・ミスバホヴァ(Va)、 アイラット・イシュムラトフ(指)LSO 録音:2022年4月&5月、LSOセント・ルークス(イギリス、ロンドン) |
|
||
| Danacord DACOCD-962963 (2CDR) |
デンマークの偉大なピアニスト~ヴィクト・シューラー
第6集 (1)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番ハ長調 Op.15 (2)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op.58 (3)メンデルスゾーン:無言歌 アレグレット・グラツィオーソ 「春の歌」 Op.62no.2 無言歌 アンダンテ・コン・モート 「甘い思い出」 Op.19b no.1 (4)リスト:愛の夢 S541no.3 (5)ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 (6)ヒンデミット:クラリネット・ソナタ変ロ長調 (7)サン=サーンス:ベートーヴェンの主題による変奏曲 Op.35(2台のピアノのための) |
ヴィクト・シューラー(P) (1)デンマークRSO、アルベール・ヴォルフ(指) 録音:1966年5月29日(ライヴ放送)] (2)デンマークRSO、エーリク・トゥクセン(指) 録音:1949年5月10日(ライヴ放送)] (3)録音:1957年][HMV7EGK1083] (4)ヴィクト・シューラー(P) 録音:1954年[TONO EP43025] (5)デンマークRSO、カール・フォン・ガラグリ(指) 録音:1952年3月14日(ライヴ放送) (6)イプ・エーリクソン(Cl) ラジオ放送プロダクション:1964年4月15日 (7)ペーター・ヴェステンホルス(P) テレビ放送:1966年2月6日、ヴィクト・シューラー宅(コペンハーゲン) |
|
||
| Avie AV-2598(1CD) |
エキゾチックな航海 ~クリストフ・クロワゼによる新しい音楽
クリストフ・クロワゼ(b.1993):1-4. チェロ協奏曲第1番Op.6 2本のチェロのための大二重奏曲 「エキゾチックな航海」 Op.2 クラリネット三重奏曲 Op.4 チェロ・ソナタ第1番Op.9 |
クリストフ・クロワゼ(Vc)、 ニーダーレンツ音楽祭室内O アネット・ヤコヴチッチ(Vc)、 ダミアン・バッハマン(Cl)、 オクサナ・シェフチェンコ(P) 録音:2022年4月&11月、スイス |
|
||
| Nimbus Alliance NI-6436(1CDR) |
ソーヤーズ:協奏曲集 フィリップ・ソーヤーズ(b.1951):ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 弦楽のための回想 ヴィオラ協奏曲/ 八重奏曲 |
ケネス・ウッズ(指)イギリスSO ダニエル・ローランド(Vn、Va)、 マーヤ・ボグダノヴィチ(Vc)、 イングリッシュ・シンフォニー・オーケストラ・ソロイツ 録音:2022年3月2日-3日(1-3&5-7)、2021年4月7日-8日(4,8) |
|
||
| CPO CPO-555597(1CD) NX-B10 |
フランツ・クロンマー(1759-1831):2つのクラリネットの為の協奏曲
Op.35 コンチェルティーノ Op.38 |
パオロ・ベルトラミーニ(Cl) コッラド・ジュフレディ(Cl) ブルーノ・グロッシ(Fl) マルコ・スキアヴォン(Ob) ロベルト・コヴァルスキ(Vn) スイス・イタリア語放送O ハワード・グリフィス(指) 録音:2017年1月30日、2018年11月13-14日 |
|
||
| DACAPO MAR-8.224744(1CD) NX-B07 |
パウル・フォン・クレナウ(1883-1946):ヴァイオリン協奏曲(1941) ピアノ協奏曲(1944) 交響曲第8番(1942) - 古風な形式による |
ヘ・ジユ(Vn) セーアン・ラストギ(P)… シンガポールSO ハンス・グラーフ(指) 録音:2021年10月14-15日、2022年3月1-3日 |
|
||
| BR KLASSIK BR-900332(1CD) NX-B07 |
イストリアン・ラプソディ デヤン・ラツィック(1977-):イストリアの様式によるピアノ協奏曲 Op.18(2014/2021) ナトゥコ・デヴシッチ(1914-1997):イストリア組曲(1948) イヴァン・マテティッチ・ロンジロフ(1880-1960):イストリア民族賛歌 2つのソピラによる演奏 重唱と合唱による演奏* デヤン・ラツィック:イストリア民族賛歌のオルタレーション Op. 29(2022)…世界初録音 |
デヤン・ラツィック(P) シュチェパン・ヴェチュコヴィッチ(ソピラ) クロアチア・ラジオ・テレビcho トミスラフ・ファチニ(指)* ミュンヘン放送O イヴァン・レプシッチ(指) 録音:2022年11月14-18日、2022年12月8日、2022年12月21日 |
|
||
| ALPHA ALPHA-886(1CD) |
デュティユー、デュサパン:チェロ協奏曲 デュティユー:チェロ協奏曲「遙かなる遠い国へ」 パスカル・デュサパン(1955-):チェロ協奏曲「アウトスケイプ」(改訂版)* |
ヴィクトル・ジュリアン=ラフェリエール(Vc) フランス国立O デイヴィッド・ロバートソン(指) クリスティーナ・ポスカ(指)* 録音2022年2月17日 オーディトリアム、:2021年2月4日* ラジオ・フランス、パリ (いずれもライヴ) *…世界初録音 |
|
||
| ALPHA ALPHA-928(1CD) |
次世代ソリストたちによるモーツァルト Vol.
5 モーツァルト:ピアノ協奏曲 第16番 ニ長調 K.451 ピアノ協奏曲 第15番変ロ長調 K.450 ピアノ協奏曲 第17番ト長調 K.453 ※カデンツァは全てモーツァルト作 |
クレア・フアンチ(P/スタインウェイ) ザルツブルク・モーツァルテウムO ハワード・グリフィス(指) 録音:2021年5月 オルケスターハウス、ザルツブルク |
|
||
| ALPHA ALPHA-946(1CD) |
ブリテン、ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲 ブリテン:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.15 ブルッフ:イン・メモリアム Op. 65 ヴァイオリン協奏曲 第1番ト短調 Op.26 |
カーソン・レオン(Vn) フィルハーモニアO パトリック・ハーン(指) 録音:2022年1月 フェアフィールド・ホール、クロイドン、UK |
|
||
| CEDILLE CDR-90000220(1CD) NX-B04 |
マレク・ジャンダリ(1972-):Concertos 協奏曲集 ヴァイオリン協奏曲 クラリネット協奏曲 |
レイチェル・バートン・パイン(Vn) アンソニー・マクギル(Cl) ウィーンRSO マリン・オルソップ(指) 録音:2022年5月27-29日 |
|
||
| ONDINE ODE-1427(1CD) NX-B07 NYCX-10398(1CD) 国内盤仕様 税込定価 |
グラジナ・バツェヴィチ:序曲、ピアノ協奏曲、2台のピアノとオーケストラのための協奏曲
他 序曲(1943) ピアノ協奏曲(1949) 2台のピアノとオーケストラのための協奏曲(1966) 弦楽,トランペットと打楽器のための音楽(1958) |
ペーテル・ヤブロンスキー(P) エリーザベト・ブラウス(第2ピアノ) フィンランドRSO ニコラス・コロン(指) 録音:2022年4月、2022年12月 |
|
||
| Sono Luminus DSL-92265 (1CD+BD-A) NX-B09 |
ボルダー・バッハ音楽祭 バッハ:2つのヴァイオリンと弦楽、通奏低音のための協奏曲 ニ短調 BWV1043 ヨハン・クリストフ・バッハ(1642-1703):ラメント「ああ、私の頭が水で満ちていたなら」 バッハ:チェンバロと弦楽のための協奏曲 ニ短調 BWV1052 J. C. バッハ:モテット「わが命、今やつき」 |
クレア・マッカハン (Ms) ジョゼフィーン・ストップレンバーグ(S) ダニエル・ハッチング(T) アダム・ ユーイング(Br) ザカリー・キャレッティン (Vn) キム・ユウン(Vn) ブルーン・マッカリー(Vn) マイケル・ローレンス・スミス(Vn) ポール・ミラー(Va) ヴィジャイ・チャラサニ(Va) コールマン・イツコフ(Vc) ジョセフ・ホー(Vc) ニコラス・レクバー(Cb) クリストファー・ホルマン(チェンバロ・オルガン) ミナ・ガイッチ(Cemb) 録音:2022年5月16-20日ボルダー・バッハ音楽祭, Boulder Colorado(USA) |
|
||
| Forgotten Records fr-1867(1CDR) |
ショパン&モーツァルト:協奏曲集 モーツァルト:ピアノ協奏曲第14番変ホ長調 K.449* ショパン:ピアノ協奏曲第1番ホ短調 Op.11# |
ミェチスワフ・ホルショフスキ(P) ルドルフ・バウムガルトナー(指)* ルツェルン祝祭弦楽合奏団* ハンス・スワロフフスキー(指)# ウィーン国立歌劇場O# 録音:1958年9月14日(ステレオ)*、1953年2月(モノラル)# ※音源: DG 133217*、 Vox PL 7870# |
| Forgotten Records fr-1868(1CDR) |
フランチェスカッティ&ライナーのブラームス ブラームス:ヴァイオリン協奏曲* 交響曲第3番ヘ長調 Op.90# |
ジノ・ フランチェスカッティ(Vn)* フリッツ・ライナー(指)CSO 録音:1957年12月12日、ライヴ*、1957年12月14日# ※音源:RCA LSC-2209#、 VICTROLA VICS 2043# |
| Forgotten Records fr-1870(1CDR) |
バルトーク:ヴァイオリン協奏曲第2番* ピアノ協奏曲第3番Sz.119# ギュンター・コーハン(1930-2009): ピアノ協奏曲 Op.16 |
ジョルジ・ガライ(Vn)* ディーター・ツェヒリン(P)# ヘルベルト・ケーゲル(指)ライプツィヒRSO 録音:1961年3月27日-29日#、6月26日-28日*(全てステレオ) ※音源: Eterna 825278、 825268他 |
| Forgotten Records fr-1873(1CDR) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op.58* ピアノ協奏曲第5番「皇帝」# |
ヤコブ・ギンペル(P) アルトゥール・ローター(指)ベルリンSO* ルドルフ・ケンペ(指)BPO # 録音:1960年*、1957年6月27日-28日#、(共にステレオ) ※音源: Opera 1183*、HMV SXLP 20004# |
| オクタヴィア OVCL-00810(1SACD) 税込定価 |
ラロ:スペイン交響曲作品21 ロシア協奏曲作品29 |
堀米ゆず子(Vn) マルコ・グイダリーニ(指) ニースPO 録音:2008年4月 |
|
||
| BIS BISSA-2655(1SACD) |
武満徹:ギターのためのコンチェルタンテ作品集 (1)スペクトラル・カンティクル(1995)~ヴァイオリン、ギター、オーケストラのための (2)夢の縁へ(1983)~ギターとオーケストラのための (3)虹へ向かって、パルマ(1984)~オーボエ・ダモーレ、ギターとオーケストラのための (4)トゥイル・バイ・トワイライト(1988)~オーケストラのための |
ヤコブ・ケッレルマン(G) ヴィヴィアン・ハグナー(Vn) ユリアナ・コッホ(オーボエ・ダモーレ) BBCフィルハーモニック、ゾエ・バイヤーズ(コンサートマスター) クリスチャン・カールセン(指) 録音:2022年3月7-9日/フィルハーモニック・スタジオ、メディア・シティUK(サルフォード) |
|
||
| BIS BISSA-2639(1SACD) |
『テラル』 セバスチャン・ファーゲルルンド(1972-): (1)テラル(Terral)(フルート協奏曲)(2020-21)* (2)骨の髄まで弦(Strings to the Bone)(2014-15)~弦楽オーケストラのための (3)室内交響曲(2020-21)~管弦楽のための |
タピオラ・シンフォニエッタ ヨン・ストゥールゴールズ(指) シャロン・ベザリー(フルート、アルトフルート)* 録音:2022年3月14-18日/タピオラホール(エスポー、フィンランド) [楽器 Flute:Muramatsu24carat gold with B foot joint/Alto flute:Muramatsu] |
|
||
 ACCENTUS Music ACC-10583BD (Bluray) ACC-20583DVD(DVD) |
ルツェルン音楽祭2022~ラフマニノフ/藤田真央&リッカルド・シャイー ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番* 交響曲第2番ホ短調Op.27 バッハ(ラフマニノフ編):無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第3番~ガヴォット* |
藤田真央(P)* リッカルド・シャイー(指) ルツェルン祝祭O 収録:2022年8月13日、ルツェルン・カルチャー・コングレスセンター、コンサート・ホール(ルツェルン音楽祭ライヴ) ◆DVD 画面:16:9、Full HD 音声:DTS HD MA5.1、 PCM STEREO BD25 リージョン:All 111’03 ◆Bluray 画面:16:9、NTSC 音声:DTS5.1、PCM STEREO DVD9 リージョン:All 111’03 |
|
||
| ACCENTUS Music ACC-70569DVD (4DVD) |
リッカルド・シャイー/ コンサート、オペラ、ドキュメンタリー映像集 ■DVD1 【ドキュメンタリー】 「音楽」~人生行路 / リッカルド・シャイー 【コンサート】 グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調 Op.16 ■DVD2 メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調Op.64 ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.61 バッハ:パルティータ第1番~サラバンド パルティータ第2番~サラバンド ■DVD3 プッチーニ:歌劇「ボエーム」 +特典映像 メイキング ■DVD4 ラヴェル:優雅で感傷的なワルツ ラ・ヴァルス 「ダフニスとクロエ」組曲 第1番&第2番 ボレロ |
全て、リッカルド・シャイー(指) ■DVD1 監督:パウル・スマチヌイ 制作:2013年4&5月 【コンサート】 ラルス・フォークト(P) ライプツィヒ・ゲヴァントハウスO 収録:2013年2月、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス(ライヴ) ■DVD2 ニコライ・ズナイダー(Vn) ライプツィヒ・ゲヴァントハウスO 収録:2012年9月、2014年10月、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス(ライヴ) ■DVD3 ガル・ジェイムズ(ソプラノ/ミミ) アキレス・マチャド(テノール/ロドルフォ) マッシモ・カヴァッレッティ(バリトン/マルチェッロ) カルメン・ロメウ(メゾソプラノ/ムゼッタ) ジャンルカ・ブラット(バス/コッリーネ) マッティア・オリヴィエーリ(バリトン/ショナール)他 バレンシア州立O バレンシア自治州cho 演出:ダヴィデ・リヴェルモーレ 収録:2012年12月12、15日、ソフィア王妃芸術宮殿(ライヴ) ■DVD4 ルツェルン祝祭O 収録:2018年8月、ルツェルン文化会議センター・コンサートホール、ライヴ 画面:NTSC,16:9 音声:PCM STEREO, DD5.1,DTS5.1 リージョン:ALL DVD9 字幕:独英伊仏韓,日本語 399'09 |
|
||
| CPO CPO-555415(1CD) NX-B10 |
C.シュターミッツ:クラリネット協奏曲集 第2集 クラリネット協奏曲第1番ヘ長調 クラリネット協奏曲第6番変ホ長調 クラリネット協奏曲第8番変ロ長調 |
ポール・メイエ(指・クラリネット) マンハイム・プファルツ選帝候室内O 録音:2020年9月2-5日 |
|
||
| Challenge Classics CC-72935(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番ハ短調 K491(カデンツァ:ベン・キム) ピアノ協奏曲第25番ハ長調 K503(カデンツァ:ユージン・イストミン / ベン・キム) |
ベン・キム(P;Steinway D584307) コンセルトヘボウ室内O 録音:2022年3月21-24日 |
|
||
| Evil Penguin Records EPRC-0053(1CD) |
クラリネットが主役のウェーバー作品集 クラリネット協奏曲第1番Op.73(カデンツァ:アンドレアス・タルクマン) 歌劇『魔弾の射手』より アリア「静かに、静かに、敬虔な調べよ」(アンドレアス・タルクマン編) クラリネット協奏曲第2番Op.74 歌劇『シルヴァーナ』の主題による変奏曲 Op.33(ライナー・ショットシュテット編) |
ルーラント・ヘンドリックス(Cl) ミシェル・ティルキン(指) ライン州立PO |
|
||
| KLANGLOGO KL-1521(1CD) |
ベートーヴェン・レアリティーズ ベートーヴェン:ピアノ協奏曲 ニ長調 Op.61a 騎士バレエのための音楽 WoO.1 ウェリントンの勝利(戦争交響曲) Op.91 |
クレア・フアンチ(P)、 ハワード・グリフィス(指)、 ブランデンブルク州立フランクフルトO 録音:2017年8月21日-23日、コンサートホール・“ C.P.E.バッハ”・フランクフルト(オーダー、ドイツ) |
|
||
| RUBICON RCD-1109(2CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲第20番ニ短調 K466 ピアノ協奏曲第21番ハ長調 K467 ピアノ協奏曲第23番イ長調 K488 ピアノ協奏曲第27番変ロ長調 K595 |
エリーザベト・ソンバール(P)、 ピエール・ヴァレー(指)、 ロイヤルPO |
|
||
| CAvi music 85-53524(1LP) |
レーガー:ピアノ協奏曲 ヘ短調 Op.114 綴じていないページ Op.13より 第7曲「コラール」 |
マルクス・ベッカー(P)、 ジョシュア・ワイラースタイン(指)、 ハノーファー北ドイツ放送PO 録音:2017年1月(協奏曲)ライヴ録音、2017年12月スタジオ録音(ドイツ、ハノーファー) |
|
||
| Channel Classics CCS-45023(1CD) |
ラフマニノフ:ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 Op.30 交響曲 ニ短調 「ユース・シンフォニー」* シルヴェストロフ(1937-):使者(P独奏版) |
アンナ・フェドロヴァ(P) ザンクト・ガレンSO モデスタス・ピトレナス(指) 録音:2022年11月 トーンハレ・シアター、ザンクト・ガレン、スイス |
|
||
 Biddulph BIDD-85025(1CD) NX-B04 |
アート・オヴ・ユーディス・シャピロ モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番 イ長調「トルコ風」 K.219# メンデルスゾーン:スケルツォ -弦楽四重奏曲 第4番ホ短調より チャイコフスキー:アンダンテ・カンタービレ~ 弦楽四重奏曲第1番ニ長調より ヴォルフ:イタリア風セレナード フォーレ:夢のあとに(ペーター・ヤッフェ編) トゥリーナ:la Oracion del Torero 闘牛士の祈り ラフマニノフ:セレナード -幻想的小品集 Op.3-5(ハルトマン編) ショスタコーヴィチ:ポルカ- バレエ組曲『黄金時代』より ブリッジ:ロンドンデリーの歌 グレインジャー:Molly on the Shore 岸辺のモリー ヴィクター・ヤング:Je vous adore* ヴィクター・ヤング:Stella by Starlight* |
ユーディス・シャピロ(Vn) NBC響# フランク・ブラック(指)# アメリカン・アートQ【ユーディス・シャピロ(Vn1)、ロバート・スーシェル(Vn2)、ヴァージニア・マジェフスキ(Va)、ヴィクター・ゴットリープ(Vc)】 ポール・ウェストン・アンド・ヒズ・オーケストラ* 録音及び初出盤:1944年8月20日 originally released on16-inch LP discs issued by the Armed Forces Radio Service(AFRS34)…1-3 1953年9月8日、14日 first released on an LP entitled “String Quartet Melodies” on RCA Victor Bluebird LBC1086…4-12 1958年 first appeared on an LP entitled “Hollywood” issued on Columbia CS8042* |
|
||
| Pentatone PTC-5187088(1CD) |
コルンゴルト:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35 ショーソン:詩曲 Op.25 ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調 Op.26 |
アラベラ・美歩・シュタインバッハー(Vn) ローレンス・フォスター(指)、 グルベンキアンO 録音:2012年7月/カルースト・グルベキアン財団大講堂(リスボン) |
|
||
| Hanssler HC-23008(1CD) |
C.P.E.バッハ:作品集 ピアノ協奏曲 ニ長調 Wq.43/2H.472 ソナチネ ニ長調 Wq.96H.449 ピアノ協奏曲 ホ長調 Wq.14H.417(1楽章、第2楽章のカデンツァ(即興):オラツィオ・ショルティーノ) ファンタジア第2番ハ長調 Wq.61/6 ラ・グライム、ロンドーWq.117/19 |
オラツィオ・ショルティーノ(P) パドヴァ・ヴェネトO 録音:2019年3月13&15日/オーディトリウム・ポリーニ、パドヴァ(イタリア) |
|
||
| BIS BISSA-2648(1SACD) |
アルメニアのチェロ協奏曲 ハチャトゥリヤンチェロ協奏曲ホ短調 ババジャニヤン:チェロ協奏曲 ペトロシヤン:チェロ協奏曲「8.4」* |
アレクサンドル・シャウシヤン(Vc) エドゥアルド・トプチヤン(指) アルメニア国立PO 録音:2022年1月24-27日、3月19-20日*/アラム・ハチャトゥリヤン・ホール(エレヴァン、アルメニア) |
|
||
| PROSPERO CLASSICAL PROSP-0064(1CD) |
ヴィヴァルディ:リコーダー協奏曲とアリア集 ソプラニーノリコーダー協奏曲 ハ長調 RV443 アルトリコーダー協奏曲 ハ短調 RV441 歌劇『救われたアンドロメダ』RV Anh.117より アリア「いつも太陽が」 ソプラニーノリコーダー協奏曲 ニ長調 『ごしきひわ』 Op.10-3, RV428 アルトリコーダー協奏曲 ト短調 『夜』 Op.10-2, RV439 歌劇『ジュスティーノ』 RV177より アリア「喜びをもって見よう」(アルトリコーダー編) ソプラニーノリコーダー協奏曲 イ短調 RV445 協奏曲 へ短調 『冬』 RV297より 第2楽章(ソプラノリコーダー編) |
イサーク・マクドゥーミ(リコーダー、編) アルノー・グルック(C.T) アンサンブル・ピッカンテ 録音:2022年7月/スイス、ゼーヴェン、聖ドイツ教会 |
|
||
| SCALA MUSIC SMU-007(1CD) |
BACH STAGE バッハ:ピアノ(Cemb)協奏曲 ト短調 BWV1058(第3楽章カデンツァ:小倉美春) ピアノ(Cemb)協奏曲 イ長調 BWV1055(第2楽章カデンツァ:ルドルフ・ブリュノー=ブルミエ) ピアノ(Cemb)協奏曲 ニ短調 BWV1052(第3楽章カデンツァ:フランチェスコ・トリスターノ) |
フラン チェスコ・トリスターノ(P) バッハ・ステージ・アンサンブル レオ・マルグ(指) 録音:2022年9月28-30日 |
|
||
| DUX DUX-1700(1CD) |
カジミェシュ・セロツキ(1922-1981):トロンボーンのための作品集 1-4. トロンボーン協奏曲 5-7. ソナチネ(管弦楽伴奏版) 8. スウィンギング・ミュージック(クラリネット、トロンボーン、チェロとピアノのための) 9-15. 組曲(トロンボーン四重奏のための) 16-18. ソナチネ(P伴奏版) |
ヴォイチェフ・イェリンスキ(Tb) ウカシュ・ボロヴィチ(指揮/tr.1-7) ポズナンPO(tr.1-7) セピア・アンサンブル・コンテンポラリー・ミュージシャンズ(tr.8) 〔シモン・ジュズヴィアク(Cl)、ヴォイチェフ・イェリンスキ(Tb)、アンナ・シュマトワ(Vc)、トマシュ・ソシニャク(P/tr,8, 16-18)〕 トロンブクァルテット(TROMBQUARTET/tr.9-15)〔ヴォイチェフ・イェリンスキ(Tb)、ピオトル・バニシ(Tb)、マルク・カチョル(Tb)、トマシュ・カチョル(バス・トロンボーン)〕 録音:2022年6月22日-23日&9月1日-2日、アダム・ミツキェヴィチ大学音楽堂、ポズナン・フィルハーモニー・コンサート・ホール(ポズナン、ポーランド) |
|
||
| DUX DUX-1883(1CD) |
ノヴォヴィエイスキ:ピアノ協奏曲&チェロ協奏曲
フェリクス・ノヴォヴィエイスキ(1877-1946):ピアノ協奏曲ニ短調 Op.60「スラヴ風」 チェロ協奏曲 Op.55 |
ヤツェク・コルトゥス(P)、 バルトシュ・コジャク(Vc)、 ウカシュ・ボロヴィチ(指)、ポズナンPO 録音:2022年9月、ポズナン・フィルハーモニー・コンサート・ホール(ポズナン、ポーランド) |
|
||
| SOREL CLASSICS SCCD-006(1CD) |
プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第1番ト短調 Op.16 ピアノ協奏曲第2番ハ長調 Op.26 |
アンナ・シェレスト(P) ニルス・ムース(指) ヤナーチェクPO 録音:2014年12月 チェコ オストラヴァ |
|
||
| Capriccio C-5469(1CD) NX-B07 NYCX-10393(1CD) 国内盤仕様 税込定価 |
ゲオルク・ゴルターマン(1824-1898):チェロ協奏曲第1番、他 チェロ協奏曲第1番イ短調 Op.14 ロマンス イ短調 Op.60No.1 バラード ト長調 Op.81 交響曲 イ短調 Op.20…世界初録音 |
ジャマル・アリエフ(Vc) ウィーンRSO ハワード・グリフィス(指) 録音:2022年6月7-10日 ※国内仕様盤には本田裕暉氏による日本語解説が付属 |
|
||
| Channel Classics CCSBOX-7423(7CD) NX-E07 |
ヴィヴァルディ協奏曲BOX 【DISC1&2】 協奏曲集 Op.4『ラ・ストラヴァガンツァ』(全12曲) 【DISC3&4】 協奏曲集 Op.9『ラ・チェトラ』(全12曲) 【DISC5&6】 協奏曲集 Op.3『調和の霊感』(全12曲) 【DISC7】 協奏曲集「四季」 ~『和声と創意への試み』 Op.8より ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 RV269Op.8-1「春」 ヴァイオリン協奏曲 ト短調 RV315Op.8-2「夏」 ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調 RV293Op.8-3「秋」 2. ヴァイオリン協奏曲 ヘ短調 RV297Op.8-4「冬」 ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 RV270「聖夜の休息」 ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 RV271「恋人」 ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 RV208「ムガール大帝」 |
レイチェル・ポッジャー(Vn) 【DISC1&2】 アルテ・デイ・スオナトーリ(古楽器使用) 録音:2002年9月 ゴシツィコヴォ=パラディシ・カトリック教会大学(ポーランド) 【DISC3&4】 オランダ・バロック(古楽器使用) ユディト・ステーンブリンク(第2ソロ・ヴァイオリン)…RV 530 録音:2011年9月 2012年1月、ワロン教会(Waalse Kerk)、アムステルダム 【DISC5&6】 ブレコン・バロック(古楽器使用) ボヤン・チチッチ、ヨハネス・プラムゾーラー(Vn) 録音:2014年2月&9月 セント・ジョン・エヴァンジェリスト教会、アッパー・ノーウッド、ロンドン 【DISC7】 ブレコン・バロック(古楽器使用) 録音:2017年10月 セント・ジュード教会、ロンドン |
|
||
| CONCERTO CLASSICS CC777-750(1CD) |
ヴィオラ・ダモーレ~ヴィヴァルディ&シュターミツ:3つの協奏曲とソナタ ヴィヴァルディ:ヴィオラ・ダモーレとオーケストラの為の3つの協奏曲(ニ短調 RV395、ニ短調 RV393、ニ短調 RV394) シュターミツ(1745-1801):ヴィオラ・ダモーレとヴァイオリンの為のソナタ イ長調 |
ピエール=アンリ・ゼレブ(ヴィオラ・ダモーレ)
クリストフ・ジョヴァニネッティ(Vn) アカデミー・ド・マンドリン・エ・ギタール・ド・マル セイユ(マンドリン&ギター・オーケストラ) ヴァンサン・ベール・ドゥマンデ(マンドリン・ソロ) 録音:2021年/マルセイユ、サン・ジョセフ教会(ヴィヴァルディ)、2022年/エポー=ベズ、シャトー・ド・リジエール(シュターミツ) |
|
||
| Naive V-7259[NA] |
Legacyレガシー (1)ハイドン:チェロ協奏曲第1番ハ長調 Hob. VIIb:1 (2)ポルポラ:ラルゴ~チェロ協奏曲 ト長調より (3)モーツァルト:協奏交響曲 イ長調 ~ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロの為の協奏曲 K320e / K.Anh.104(断片)〔ロバート・レヴィンによる補完版〕 (4)グルック(ラ・マルカ編):精霊の踊り(『オルフェオとエウリディーチェ』より) (5)ポルポラ:正しい愛、私を燃え上がらせた(『ヘスペロデスの園』より) (6)ハイドン:チェロ協奏曲第2番ニ長調 Hob.VIIb:2 |
クリスティアン=ピエール・ラ・マルカ(Vc) ジュリアン・ショヴァン((指)ヴァイオリン) アドリアン・ラ・マルカ(ヴィオラ((3))) ル・コンセール・ド・ラ・ローグ フィリップ・ジャルスキ(カウンターテナー((5))) 録音:2021年2月27-30日、パリ |
|
||
 King International KKC-095(2CD) |
野島稔~ベートーヴェン・ライヴ (1)ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 (2)ピアノ・ソナタ第19番ト短調Op.49の1 (3)ピアノ・ソナタ第11番変ロ長調Op.22 (4)ピアノ・ソナタ第13番変ホ長調Op.27の1 (5)ピアノ・ソナタ第32番ハ短調Op.111 |
野島稔(P) 山田一雄(指)札幌SO 録音:1989年11月20日北海道厚生年金会館大ホール(1)、2008年11月1日厚木文化会館(2)-(5)(ライヴ) |
|
||
| Dynamic CDS-7978(1CD) NX-B03 |
ショパン:ピアノ協奏曲第1番ホ短調 Op.11 ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 Op.22 |
ピエトロ・デ・マリア(P) トスカーナO ダニエーレ・ルスティオーニ(指) 録音:2021年4月8-10日 |
|
||
 Avanti Classic AVA-10662(1CD) NX-B10 |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲 第2番 ラヴェル:ピアノ協奏曲* |
マルタ・アルゲリッチ(P) イスラエルPO ラハフ・シャニ(指) 録音:2019年12月22日、24-27日* チャールズ・ブロンフマン・オーディトリアム、テルアビブ、イスラエル |
|
||
| SOMM SOMMCD-281(1CD) NX-B04 |
ニムロッド・ボーレンシュタイン(1969-):ピアノ協奏曲/光と闇/シリム ピアノ協奏曲 Op.91 光と闇 Op.80/シリム Op.94 |
クレリア・イルズン(P) ロイヤルPO ニムロッド・ボーレンシュタイン(指) イ・ムジカンティ(アンサンブル)【タマーシュ・アンドラーシュ(Vn)、ロベルト・スミセン(Va)、アーシュラ・スミス(Vc)、レオン・ボッシュ(Cb)】 録音:2022年5月9-10日 ヘンリー・ウッド・ホール、ロンドン(UK) 2022年6月26-27日 メニューイン・ホール、ストーク・ダバノン(UK) |
|
||
 Biddulph BIDD-85024(2CD) NX-C03 |
ブロニスワフ・ギンペル~ヴァイオリン協奏曲集 (1)ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲(カデンツァ:フリッツ・クライスラー。第2楽章から第3楽章への移行部のみ:カール・フレッシュ) (2)ラロ:スペイン交響曲 (全5楽章) (3)チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 (4)ヴィエニャフスキ:ヴァイオリン協奏曲第2番 (5)パガニーニ:1楽章の協奏曲 (原曲:ヴァイオリン協奏曲第1番 第1楽章:ヴィルヘルミ編) |
ブロニスワフ・ギンペル(Vn) (1)バンベルクSO ハインリヒ・ホルライザー(指) 録音:1955年2月18日/音源:Vox PL9340(MONO) (2)ミュンヘンSO フリッツ・リーガー(指) 録音:1956年4月4-6日/DGG19071(MONO) (3)バンベルクSO ヨハネス・シューラー(指) 録音:1960年/Opera1187(STEREO) (4)(5)バーデン=バーデン南西ドイツRSO ロルフ・ラインハルト(指) 録音:1956年/Vox PL10.450(MONO) 復刻プロデューサー:Eric Wen 復刻エンジニア:David Hermann マスタリング:Dennis Patterson |
|
||
| SWR music SWR-19433CD(10CD) NX-G09 |
偉大なピアニストたち ■CD1 (1)ハイドン:ピアノと弦楽のための協奏曲第11番 ニ長調Hob. XVIII (2)モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番 イ長調 K488 ■CD2 (1)モーツァルト:ピアノ協奏曲第9番変ホ長調「ジュノーム」 K271 (2)モーツァルト:ピアノ協奏曲第19番ヘ長調 K459 ■CD3 (1)モーツァルト:ピアノ協奏曲第27番 (2)モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番ハ短調 K491 ■CD4 (1)モーツァルト:ピアノ協奏曲第22番 (2)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番 ■CD5 (1)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第2番 (2)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5「皇帝」 ■CD6 (1)ショパン:ピアノ協奏曲第1番 (2)ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ■CD7 (1)ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 (2)シューマン:ピアノ協奏曲 ■CD8 (1)ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 (2)ラヴェル:左手のためのピアノ協奏曲 ■CD9 (1)バルトーク:ピアノ協奏曲第2番 (2)チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 ブラームス:間奏曲 変ホ長調 Op.117 No.1 ■CD10 (1)サン=サーンス:ピアノ協奏曲第5番 「エジプト風」 (2)ガーシュウィン:ピアノ協奏曲 へ調 |
■CD1 フリードリヒ・グルダ(P) ※2020年初出時のSWR19088CDにおいて、こちらの録音はMONOとご案内をいたしましたが、実際はSTEREOであることが判明いたしました。 (1)シュトゥットガルトRSO (1)ハンス・ミュラー=クライ(指) (2)バーデン=バーデン南西ドイツRSO (2)ハンス・ロスバウト(指) 録音:(1)1962年1月10日 リーダーハレ、シュトゥットガルト(ドイツ) (2)1962年1月15日 ハンス=ロスバウト・スタジオ、バーデン=バーデン(ドイツ) ■CD2 クララ・ハスキル(P) シュトゥットガルトRSO カール・シューリヒト(指) 録音:(1)1952年5月23日 Stuttgart-Degerloch,Waldheim(ドイツ)(MONO) (2)1956年4月7日(ライヴ) Schloss Ludwigsburg,Barock-Theater(ドイツ)(MONO) ■CD3 (1)イェルク・デームス(P) (2)パウル・バドゥラ=スコダ(P) シュトゥットガルトRSO (1)ハンス・ミュラー=クライ(指) (2)カール・シューリヒト(指) 録音:(1)1961年9月28日 ヴィラ・ベルク、シュトゥットガルト(MONO) (2)1962年10月18日(ライヴ) リーダーハレ、シュトゥットガルト(ドイツ)(MONO) ■CD4 アリシア・デ・ラローチャ(P) (1)シュトゥットガルトRSO (1)ガルシア・ナバロ(指) (2)バーデン・バーデン&フライブルク南西ドイツRSO (2)エルネスト・ブール(指) 録音:(1)1986年1月15日 リーダーハレ、シュトゥットガルト(ドイツ) (2)1977年1月17日 ハンス=ロスバウト・スタジオ、バーデン=バーデン(ドイツ) ■CD5 (1)ヴィルヘルム・ケンプ(P) (2)ヴィルヘルム・バックハウス(P) (1)シュトゥットガルトRSO (1)ハンス・ミュラー=クライ(指) (2)シュトゥットガルトRSO (2)ヨーゼフ・カイルベルト(指) 録音:(1)1957年11月7日 リーダーハレ、シュトゥットガルト(ドイツ)(MONO) (2)1962年3月15日 リーダーハレ、シュトゥットガルト(ドイツ)(MONO) ■CD6 ゲザ・アンダ(P) (1)エルネスト・ブール(指) (2)ハンス・ロスバウト(指) 録音:(1)1952年3月18日 ハンス=ロスバウト・スタジオ、バーデン=バーデン(ドイツ)(MONO) (2)1953年3月3日 ハンス=ロスバウト・スタジオ、バーデン=バーデン(ドイツ)(MONO) ■CD7 (1)ヴィルヘルム・バックハウス(P) (1)シュトゥットガルトRSO (1)ハンス・ミュラー=クライ(指) (2)アニー・フィッシャー(P) (2)バーデン=バーデン南西ドイツRSO (2)ハンス・ロスバウト(指) 録音:(1)1959年12月2日 リーダーハレ、シュトゥットガルト(ドイツ)(MONO)、(2)1959年2月25日 ハンス=ロスバウト・スタジオ、バーデン=バーデン(ドイツ)(MONO) ■CD8 (1)クラウディオ・アラウ(P) (1)シュトゥットガルトRSO (1)エリアフ・インバル(指) (2)ゲザ・アンダ(P) (2)バーデン・バーデン&フライブルク南西ドイツRSO (2)ハンス・ロスバウト(指) 録音:(1)1972年3月23日(ライヴ) リーダーハレ、シュトゥットガルト(ドイツ) (2)1952年3月15日 ハンス=ロスバウト・スタジオ、バーデン=バーデン(ドイツ)(MONO) ■CD9 ゲザ・アンダ(P) シュトゥットガルトRSO ハンス・ミュラー=クライ(指) フェルディナント・ライトナー(指) 録音:(1)1950年11月14日 Krone,Stuttgart Unterturkheim(ドイツ)(MONO) (2)1973年3月13日 リーダーハレ、シュトゥットガルト(ドイツ) ■CD10 スヴャトスラフ・リヒテル(P) シュトゥットガルトRSO クリストフ・エッシェンバッハ(指) 録音:1993年5月30日(ライヴ) Rokokotheather,Schwetzingen(ドイツ) |
|
||
| BIS BISSA-2554(1SACD) |
ニコス・スカルコッタス:協奏曲集 (1)ヴァイオリン協奏曲 A/K22(1937/38) (2)ヴァイオリン、ヴィオラとウィンドオーケストラのための協奏曲 A/K25(?1939-40) |
ジョージ・ザ カリアス(Vn ) (2)アレクサンドロス・コウスタス(Va) ロンドン・フィルハーモニックO、マーティン・ブラビンズ(指) 録音:(1)2022年4月19&20日、(2)2020年1月5&6日/ヘンリー・ウッド・ホール(ロンドン、イングランド) [楽器 Violin:‘Georgina Joshi’ by Sanctus Seraphin1719/Viola:Bohemian School, early 1900s] 制作:(1)マシュー・ベネット、(2)アレグザンダー・ヴァン・インゲン 録音エンジニア:(1)デーヴ・ローウェル、(2)アンドルー・メラー |
|
||
| DOREMI DHR-8201(2CD) |
マルタ・アルゲリッチLIVE第13集 (1)モーツァルト:ピアノ協奏曲第25番ハ長調 K.503 (2)ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番ニ短調 Op.30 (3)バッハ:パルティータ第2番ハ短調 BWV826 シューマン:ピアノ・ソナタ第2番ト短調 Op.22 ショパン:夜想曲第8番変ニ長調 Op.27-2 スケルツォ第3番嬰ハ短調 Op.39 ラヴェル:夜のガスパール |
マルタ・アルゲリッチ(P) (1)ラファエル・クーベリック(指)NYO 録音:1978年2月7日/ニューヨーク、リンカーン・センター、エイブリー・フィッシャー・ホール (2)ベルンハルト・クレー(指)ハノーファーRSO 録音:1979年6月14日/ハノーファー (3)録音:1972年4月14日/ザールブリュッケン・リサイタル |
|
||
| CLAVES 50-3057(1CD) |
ニールセン:ヴァイオリン協奏曲 Op.33FS.61 シマノフスキ:ヴァイオリン協奏曲第2番Op.61 |
アンナ・アガフィア(Vn/グァルネリウス「スフィンクス」(1730-33年製作)) アレクサンドル・マルコヴィチ(指)、シンフォニア・ヴァルソヴィア 録音:2022年11月/ポーランド放送、第2スタジオ(ワルシャワ) |
|
||
| Goodies 78CDR-3898(1CDR) |
プーランク:オーバード(Pと18の楽器のための舞踊協奏曲) | フランシス・プーランク(P) ワルテル・ストララム(指) コンセール・ストララム 仏 COLUMBIA LF33/35 1930年1月20&22日パリ、シャンゼリゼ劇場録音 |
|
||
| SOREL CLASSICS SCCD-013(1CD) 2023年2月10日までのご注文分は 税込¥2050!! |
ルビンシテイン:ピアノ協奏曲第4番ニ短調 Op.70 ロシア奇想曲 Op.102 |
アンナ・シェレスト(P) ネーメ・ヤルヴィ(指) ザ・オーケストラ・ナウ 録音:2017年10月15日ニューヨーク州 ニューヨーク・シティ(ライヴ) |
|
||
| SOREL CLASSICS SCCD-014(1CD) 2023年2月10日までのご注文分は 税込¥2050!! |
ルビンシテイン:ピアノ協奏曲第3番ト長調 Op.45 ピアノ協奏曲第5番変ホ長調 Op.94 |
アンナ・シェレスト(P) ネーメ・ヤルヴィ(指) エストニア国立SO 録音:2018年5月7日 エストニア・タリン |
|
||
| Anaklasis ANA-024(1CD) PANA-024(1CD) 国内盤仕様 税込定価 |
エルジュビエタ・シコラ:協奏曲集 (1)ピアノ協奏曲 「フレデリック・ショパンへのオマージュ」(2000) (2)ヴァイオリン協奏曲(2018) (3)オルガンと管弦楽のための 「オリヴァ協奏曲」(2007, rev.2020) |
(1)アダム・コシミェヤ(P)、シンフォニア・ヴァルソヴィア、バッセム・アキキ(指) (2)リヌス・ロート(Vn)、ポーランド国立放送O、ホセ・マリア・フロレンシオ(指) (3)福本茉莉(Org)、NFMヴロツワフPO、パスカル・ロフェ(指) 録音:2018年(P協奏曲)、2019年(Vn協奏曲)、2021年(オルガン協奏曲) 国内盤=解説の日本語訳:山根悟郎 |
|
||
| DUX DUX-1909(1CD) |
マルティヌー:チェロ協奏曲第2番H.304 チェロ・ソナタ第2番 H.286* |
バルトシュ・コジャク(Vc)、 ヤナーチェクPO、ペトル・ポペルカ(指)、 ラドスワフ・クレク(P)* 録音:2021年6月2日ー4日&2022年6月26日 |
|
||
| DUX DUX-1907(1CD) |
ポーランドの作曲家たちによるフルート作品集
ベネディクト・コノヴァウスキ(1928-2021):フルート協奏曲 フェリクス・リュビツキ(1899-1978):フルート協奏曲(小協奏曲)へ長調 Op.51 タデウシュ・シェリゴフスキ(1896-1963):フルート・ソナタ パヴェウ・シマンスキ(b.1954):アペンディックス ヤロスワフ・シヴィンスキ(b.1964):ミスティ・アイ・オヴ・ザ・アースワーム* |
グジェゴシュ・オルキエヴィチ(フルート、ピッコロ*)、 ポーランド放送アマデウス室内O、 アグニエシュカ・ドゥチマル(指)、他 録音:1987年-1990年(ポーランド) |
|
||
| H.M.F HMM-902618(1CD) |
エルガー:ヴィオラ協奏曲(原曲:チェロ協奏曲/ライオネル・ターティス
(1876-1975)によるヴィオラ編曲版に基づく) ブロッホ:ヴィオラとオーケストラのための組曲 B.41 |
ティモシー・リダウト(Va) BBC響、 マーティン・ブラビンス(指) 録音:2022年4月、ロンドン |
|
||
| H.M.F HMM-902718(1CD) |
ファウスト&ロトのストラヴィンスキー バレエ音楽「ミューズを率いるアポロ」~アポロのヴァリアシオン(1927-8) ヴァイオリン協奏曲ニ長調(1931) 弦楽四重奏のための3つの小品(1914) 弦楽四重奏のためのコンチェルティーノ(1920) パストラール~ヴァイオリン、オーボエ、イングリッシュホルン、クラリネット、バソンのための(1923) 弦楽四重奏のための二重カノン(1959) |
イザベル・ファウスト(Vn) フランソワ=グザヴィエ・ロト(指) レ・シエクル 録音:2021年9月、2022年3月、4月/セーヌ・ミュジカルRIFFXスタジオ1(ブローニュ・ビリヤンクール |
|
||
| SUPRAPHON SU-4323(2CD) |
ラフマニノフ:ピアノ協奏曲全集 (1)ピアノ協奏曲第1番嬰ヘ短調 Op.1 (2)ピアノ協奏曲第4番ト短調 Op.401926/rev.1928, 1941) (3)パガニーニの主題による狂詩曲 (4)ピアノ協奏曲第2番ハ短調 Op.18 (5)ピアノ協奏曲第3番ニ短調 Op.30 |
ルカーシュ・ヴォンドラーチェク(P) トマーシュ・ブラウネル(指)、 プラハSO 録音:(1)2021年4月22-24日、(2)2021年2月16-19日、(3)2021年6月14-16日、(4)2021年2月22&23日、(5)2021年10月18-20日/スメタナ・ホール(プラハ) |
|
||
 AAM Records AAM-41(1CD) NYCX-10383(1CD) 国内盤仕様 税込定価 |
プロジェクト再開! モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番ハ長調 K 467 ピアノ協奏曲第24番ハ短調 K 491 (共にカデンツァ:ロバート・レヴィン作) |
ロバート・レヴィン(フォルテピアノ) ウィーンのアントン・ヴァルター1795年頃製モデルによるフォルテピアノ (ベルギーのクリス・マーネによる再現楽器、2018年製作) ピッチ:A=430Hz/ヴァロッティ音律による調律 アカデミー・オヴ・エンシェント・ミュージック(古楽器使用) リチャード・エガー(指) 録音:2021年8月25-26日、28-29日 ロンドン、セント・ジョンズ・スミス・スクエア ※国内仕様盤には大津聡氏による日本語解説が付属します。 |
|
||
| CD ACCORD ACD-313(1CD) NX-C09 |
チェロとオーケストラのためのポーランドの音楽集 タンスマン:幻想曲- チェロとピアノのために グラジナ・バツェヴィチ:チェロ協奏曲第1番 ヘンリク・フベルトゥス・ヤブウォンスキ(1915-1989):C-67 ミウォシュ・マギン(1929-1999):チェロ協奏曲 |
マルチン・ズドゥニク(Vc) ワルシャワPO アンドレイ・ボレイコ(指) 録音:2021年9月1-3日、2021年6月2、4日 |
|
||
| Dynamic CDS-7977(1CD) NX-B03 |
ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 他 チェロ協奏曲 ロ短調 Op. 104 森の静けさ Op. 68No. 5 ロンド ト短調 Op. 94 4つの歌 第1番「私にかまわないで」 Op. 82 No. 1 (エンリコ・ディンドによるチェロと弦楽合奏編) |
エンリコ・ディンド(Vc) トスカーナO ダニエーレ・ルスティオーニ(指) 録音:2021年2月3-6日 |
|
||
| CPO CPO-555420(1CD) NX-B10 |
ニコライ・ミャスコフスキー:チェロ協奏曲とソナタ集 ミャスコフスキー:チェロ協奏曲 ハ短調 Op. 66 チェロ・ソナタ第1番ニ長調 Op. 12 リャードフ:前奏曲 Op. 11No. 1 マズルカ Op. 11No. 3 リムスキー=コルサコフ:セレナード Op. 37 ミャスコフスキー:チェロ・ソナタ第2番イ短調 Op. 81 |
ラファエル・ウォルフィッシュ(Vc) サイモン・キャラハン(P) ヤナーチェクPO ウカシュ・ボロヴィチ(指) 録音:2020年9月14-16日、2020年10月29-30日 |
|
||
 Pentatone PTC-5187062(1CD) |
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集『和声と創意の試み』Op.8より ヴァイオリン協奏曲第1番ホ長調 Op.8-1 RV 269「春」 ヴァイオリン協奏曲第2番ト短調 Op.8-2RV 315「夏」 ヴァイオリン協奏曲第3番ヘ長調 Op.8-3RV 293「秋」 ヴァイオリン協奏曲第4番ヘ短調 Op.8-4RV 297「冬」 ロカテッリ:独奏ヴァイオリン、弦楽器と通奏低音のための『ヴァイオリンの技法』Op.3~ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.3-12「和声の迷宮」 |
クロエ・チュア(Vn/グァダニーニ製作) シンガポールSO、 チャン・ユーン・ハン(コンサートマスター) 録音:2022年4月23&24日/エスパラネード・ホール(シンガポール) |
|
||
 Danacord DACOCD-887(2CDR) ★ |
ラウニ・グランデールの遺産 第7集 (1)ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op.61 (2)リムスキー=コルサコフ (デンマーク語版:テューイェ・テューイェセン):歌劇 「モーツァルトとサリエリ」 (3)ニールセン:歌劇 「仮面舞踏会」 序曲 (4)チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番変ロ短調 Op.23 (5)シューベルト:交響曲第9番(第8番)ハ長調 D.944「ザ・グレート」 - 第1楽章、第2楽章 |
(1)アドルフ・ブッシュ(Vn)、デンマークRSO、ラウニ・グランデール(指) 録音:1949年3月17日、デンマーク放送第1スタジオ(コペンハーゲン)(「木曜コンサート」ライヴ) (2)クリスチャン・ブランケ(テノール/モーツァルト)、ヘンリュ・スケーア(バリトン/サリエリ)、デンマークRSO、ラウニ・グランデール(指) 録音:1954年11月25日、デンマーク放送第1スタジオ(コペンハーゲン)(「ラジオ・オペラ」) (3)デンマークRSO、ラウニ・グランデール(指) 録音:1950年8月11日、フォーラム(コペンハーゲン)(「ラジオ・フェア」実況) (4)ヴィクト・シューラー(P)、デンマークRSO、ラウニ・グランデール(指) 録音:1951年9月24日、ロイヤル・フェスティヴァル・ホール(ロンドン)(ライヴ) (5)デンマークRSO、ラウニ・グランデール(指) 録音:1952年12月11日 デンマーク放送第1スタジオ(コペンハーゲン)(「木曜コンサート」ライヴ) |
|
||
| RUBICON RCD-1106(1CD) |
チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35 ラロ:スペイン交響曲 ニ長調 Op.21 |
エリノア・ディメロン(Vn)、 アイルランド国立SO、 ハイメ・マルティン(指) |
|
||
 Urania Records WS-121407(2CD) |
アシュケナージ・プレイズ・ピアノ・コンチェルト・ライヴ (1)グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調 Op.16 (2)ショパン:ピアノ協奏協奏曲第2番ヘ短調 Op.21 (3)ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番ニ短調 Op.30 (4)プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第2番ト短調 Op.16 |
ウラディーミル・アシュケナージ(P) (1)ベルゲンPO、カルステン・アンデルセン(指) (2)レニングラード・アカデミーSO、アルヴィド・ヤンソンス(指) (3)ロサンゼルスPO、ウィリアム・スタインバーグ(指) (4)ソビエト国立SO、ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー(指) 録音:1970年、ベルゲン(グリーグ)、1960年2月21日、レニングラード(ショパン)、1968年7月、ロサンゼルス(ラフマニノフ)、1961年、モスクワ(プロコフィエフ)/STEREO/ADD |
|
||
| GWK GWK-157(1CD) |
人間性~チェロと弦楽オーケストラのための作品集
ペール・ヘンリク・ノルドグレン(1944-2008):チェロと弦楽オーケストラのための協奏曲第1番 Op.50 バッハ:アリア(Vcと弦楽のための)(「パストラーレ ヘ長調」 BWV590より) ペーテリス・ヴァスクス(b.1946):チェロと弦楽オーケストラのための協奏曲第2番「存在すること」 バッハ:われを憐れみたまえ、おお主なる神よ BWV721(Vcと弦楽のための) |
ジモーネ・ドレッシャー(Vc)、 シンフォニエッタ・リガ、 ヤーニス・リエピンシュ(指) 録音:2022年1月11日-13日、改革派教会(リガ、ラトビア) |
|
||
| Avie AV-2601(1CD) ★ |
ミステリウム バッハ(サミュエル・アドラー編):主よ、人の望みの喜びよ バッハ(レン・ローズ編):羊は安らかに草を食み、目覚めよと呼ぶ声あり モーテン・ローリゼン(b.1943)(ガーション&ローリゼン編):おお、大いなる神秘 |
アン・アキコ・マイヤース(Vn)、 グラント・ガーション(指)、 ロサンゼルス・マスター・コラール 録音:2022年3月21日、ウォルト・ディズニー・コンサート・ホール(ロサンゼルス)/※収録時間:約18分(4曲) ※全曲世界初録音 |
|
||
| Urania Records WS-121408(2CD) |
ミルシテイン・プレイズ・ヴァイオリン・コンチェルト (1)ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op.61 (2)ブラームス:ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op.77 (3)メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調 Op.64 (5)チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op.35 (6)ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調 Op.26 |
ナタン・ミルシテイン(Vn) (1) ピッツバーグSO ウィリアム・スタインバーグ(指) 録音:1955年1月10日(モノラル) (2)フィルハーモニアO アナトール・フィストゥラーリ(指) 録音:1960年6月23日-24日(ステレオ) (3)フィルハーモニアO レオン・バージン(指) 録音:1959年10月1日-3日(ステレオ) (5)ピッツバーグSO ウィリアム・スタインバーグ(指) 録音:1959年4月6日(ステレオ) (6)フィルハーモニアO レオン・バージン(指) 録音:1959年10月1日-3日(ステレオ) STEREO/MONAURAL(ベートーヴェンのみ)/ADD |
|
||
| Indesens Calliope Records IC-004(2CD) OIC-004(2CD) 国内盤仕様 日本語解説&日本語曲目表記オビ付き 税込定価 |
バッハ:ブランデンブルク協奏曲(全曲) ブランデンブルク協奏曲第1番ヘ長調 BWV.1046 ブランデンブルク協奏曲第2番ヘ長調 BWV.1047 ブランデンブルク協奏曲第3番ト長調 BWV.1048 ブランデンブルク協奏曲第4番ト長調 BWV.1049 ブランデンブルク協奏曲第5番ニ長調 BWV.1050 ブランデンブルク協奏曲第6番変ロ長調 BWV.1051カンタータ第174番 「われ、いと高き者を心を尽くして愛しまつる」 BWV.174 |
ヴァンサン・ベルナール(ハープシコード、指揮) クライペダ室内O 録音:2021年、クライペダ・コンサートホール(リトアニア) ※国内盤:解説:ヴァンサン・ベルナール(日本語訳:白沢達生) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2285(1CD) |
ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104 | パブロ・カザルス(Vc)、 アレクサンダー・シュナイダー(指)、 プエルト・リコ・カザルス音楽祭O 録音:1960年6月14日/サン・フアン、プエルト・リコ大学講堂 使用音源:Private archive(2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:ステレオ(放送用録音) |
|
||
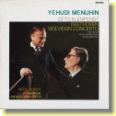 Treasures TRE-284(1CDR) |
超厳選!赤盤名演集Vol.9~_メニューイン/バルトーク&ベートーヴェン バルトーク(シェルイ編):ヴィオラ協奏曲 ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲* |
ユ-ディ・メニューイン(Vn) アンタル・ドラティ(指) オットー・クレンペラー(指)* ニュー フィルハーモニアO 録音:1966年9月28-29日、1966年1月22,22,24,25日*(共にステレオ) ※音源:TOSHIBA AA-8257、HA-1186* ◎収録時間:66:24 |
| “弱音のニュアンスに逃げず呼吸の持久力で作品の精神を徹底音化!” | ||
|
||
| H.M.F HMSA-0064(2SACD) シングルレイヤー 日本語帯・解説付 国内盤仕様 税込定価 |
バッハ:ブランデンブルク協奏曲(全6曲) | ベルリン古楽アカデミー イザベル・ファウスト(Vn/ヤコブス・シュタイナー(1658年製))、 アントワン・タメスティ(ヴィオラ/1672年製ストラディヴァリウス「マーラー」) 録音:2021年3,5月 録音場所:ベルリン、イエス・キリスト教会 |
|
||
| CANARY CLASSICS CC-22(1CD) |
スティーヴン・マッキー(1956-):作品集 「美しき終わり」~ヴァイオリンとオーケストラのための 「ムネーモシュネーの泉」~オーケストラのための* |
アントニー・マーウッド(Vn ) デイヴィッド・ロバートソン(指)シドニーSO 録音:2015年6月1-6日、2017年8月21-26日*/シドニー・オペラハウス・コンサートホール |
|
||
| DOREMI DHR-8195(2CD) |
アルトゥール・ルービンシュタインLIVE 第1集 (1)ブラームス:ピアノ協奏曲第1番ニ短調 Op.15 (2)ブラームス:ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 Op.83 (3)モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番 イ長調 K.488 (4)ショパン:ポロネーズ第6番変イ長調 Op.53 (5)ショパン:アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ Op.22 ショパン:マズルカ ハ短調 Op.56-3 |
アルトゥール・ルービンシュタイン(P) (1)ヘンリク・チシ(指)フランス国立O 録音:1974年3月13日パリ (2)クリストフ・フォン・ドホナーニ(指)、ケルンRSO 録音:1966年5月23日チューリッヒ (3)ポール・パレー(指)デトロイトSO 録音:1960年1月7日デトロイト (4)録音:1974年3月13日パリ (5)録音:1959年10月6日ロンドン |
|
||
| Chandos CHAN20192(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲集 Vol.7 歌劇「フィガロの結婚」序曲 ピアノ協奏曲第24番 ニ短調 KV 491* ピアノ協奏曲第25番ハ長調 KV 503* |
ジャン=エフラム・バヴゼ(P/YAMAHA CFX)*、 ガボル・タカーチ=ナジ(指)、 マンチェスター・カメラータ 録音:2022年3月27日-28日、ストーラー・ホール(ハンツ・バンク、マンチェスター) |
|
||
| Etcetra KTC-1697(1CD) |
テナー・トリビュート~テナーサックス、ピアノとオーケストラのための作品集
リチャード・ロドニー・ベネット:スタン・ゲッツのための協奏曲(1990)、 バラード - シャーリー・ホーンの追憶に(2005) デイヴ・ヒース:コルトレーン(1965) ヤコプ・テル・フェルトハウス(JacobTV):May This Bliss Never End(1996) アダム・ケアード:Out of Line(2007) |
イェロン・ファンベイファー(テナーサックス)、 ルーカス・ヘイテンス(P)、 カスコ・フィル |
|
||
| Goodies 78CDR-3893(1CDR) |
バッハ:ヴァイオリン協奏曲ニ短調 BWV1052 | ヨーゼフ・シゲティ(Vn) フリッツ・シュティードリー(指) ニュー・フレンズ・オブ・ミュージックO 米 COLUMBIA 11379/81-D 1940年4月24日ニューヨーク、リーダークランツ・ホール録音 |
|
||
| Capriccio NYCX-10375(1CD) 国内盤仕様 |
ニコライ・カプースチン(1937-2020):ピアノ協奏曲第4番 Op. 56(1989) ヴァイオリン、ピアノと弦楽オーケストラのための協奏曲 Op. 105(2002) 室内交響曲 Op. 57(1990) |
フランク・デュプレー(P) ロザンネ・フィリッペンス(Vn) ハイルブロン・ヴュルテンベルク室内O カーセ・スカリョーネ(指) 録音:2020年10月26-31日 Erlenbach, Sulmtalhalle(スイス)、2020年12月3、4日 Heilbronn, Harmonie(ドイツ) 同内容の既発輸入盤…C5437 |
|
||
| Capriccio C-5495(1CD) NX-B07 |
ニコライ・カプースチン(1937-2020):1. ピアノ協奏曲第5番 Op. 72(1993) 2台のピアノとパーカッションのための協奏曲 Op. 104(2002) シンフォニエッタ Op. 49- 4手ピアノのために(1986) |
フランク・デュプレー(P) アドリアン・ブレンドル(P) マインハルト・OBI・イェンネ(ドラムセット) フランツ・バッハ(パーカッション) ベルリンRSO ドミニク・ベイキルヒ(指) 録音:2022年1月5-7日、2022年8月4-5日 |
|
||
| ONDINE ODE-1420(1CD) NX-B07 |
ロッタ・ヴェンナコスキ(1970-):ハープ協奏曲「Sigla」
他 Flounce(2017) Sigla(2022) - ハープと管弦楽のための Sedecim(2016) |
シヴァン・マゲン(Hp) フィンランドRSO ニコラス・コロン(指) 録音:2021年12月、2022年5月、2022年10月 |
|
||
| WERGO WER-7389(1CD) |
SAX~現代サクソフォン協奏曲集 (1)ペーテル・エトヴェシュ(1944-):フォーカス ~サクソフォンと管弦楽のための協奏曲(2021) (2)ゲオルク・フリードリヒ・ハース(1953-):協奏曲 ~バリトンサックスと管弦楽のための(2008) (3)ヴィキンタス・バルタカス(1972-):サクソルディオンフォニクス ~ソプラノサックス、アコーディオンと室内オーケストラのための(2013) (4)ヨハネス・マリア・シュタウト(1974-):暴力的なできごと ブルース・ナウマンを讃えて ~サクソフォン、木管アンサンブルと打楽器のための(2005/06) |
マルクス・ヴァイス(各種サクソフォン) テオドロ・アンゼロッティ(アコーディオン(3)) ケルンWDRSO((1)-(3)) エレナ・シュヴァルツ(指揮(1)) エミリオ・ポメリコ(指揮(2)(3)) ウィンドクラフト・チロル((4)) カスパー・デ・ロー(指揮(4)) 録音:(1)2022年1月15日、(2)2008年4月21-30日、(3)2013年4月28日、(4)2007年2月8-10日 (1)(2)世界初録音 |
|
||
| APARTE AP-299(1CD) |
モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲 ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調K.216 ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調K.218 ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調K.219「トルコ風」 |
ゴットフリート・フォン・デア・ゴルツ(Vn)
クリスティアン・ベザイデンホウト((指)フォルテピアノ) フライブルク・バロック・オーケストラ 録音:2021年8月20-24日 フライブルク・アンサンブルハウス |
|
||
| PAN CLASSICS PC-10445(1CD) |
バッハ:復元版室内協奏曲集 6声の室内協奏曲 ニ短調 BWV1063R(原曲:3台のチェンバロのための協奏曲)~リコーダー、オーボエ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、通奏低音 協奏曲 変ロ長調 BWV525&1032による(原曲:オルガン独奏のためのトリオ・ソナタ、フルート・ソナタ)~リコーダー、オーボエ、ファゴット 室内協奏曲 ニ長調 BWV1064R(原曲:3台のチェンバロのための協奏曲)~3つのヴァイオリン、ヴィオラ、ファゴット 5声の室内協奏曲 ト長調 BWV592&592aによる(原曲:エルンスト公の作品を編曲したオルガン協奏曲)~リコーダー、ヴァイオリン、ヴィオラ、ファゴット、通奏低音 パッサカリア BWV78による(カンタータ『イエスよ、汝わが魂を』)~リコーダー、オーボエ、ヴァイオリン、ヴィオラ、通奏低音 6声の協奏曲 BWV1059R(原曲:チェンバロ協奏曲)~リコーダー、3つのヴァイオリン、ヴィオラ、通奏低音 5声の室内協奏曲 ヘ長調 BWV1047R(原曲:ブランデンブルク協奏曲第2番)~リコーダー、オーボエ、ホルン、ヴァイオリン、通奏低音 |
ミヒャエル・フォルム(リコーダー、指) オゥ・ピエ・ドゥ・ロワ 録音:2022年7月11-14日/スイス、聖パンタレオン教会 |
|
||
 Profil PH-22080(6CD) |
ヨハンナ・マルツィ~協奏曲とソナタ集 ■Disc1 (1) ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲イ短調Op.53 (2) ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ■Disc2 (1) モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調K.218 (2) 同:ヴァイオリン・ソナタ第24番ヘ長調K.376 (3) シューベルト:幻想曲ハ長調Op.159, D934 ■Disc3 (1) メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調Op.64 (2) ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第8番ト長調Op.30の3 (3) シューベルト:ヴァイオリン・ソナタ(二重奏曲)イ長調D574 ■Disc4 シューベルト: (1) ソナチネ第1番ニ長調D384 (2) ソナチネ第2番イ短調D385 (3) ソナチネ第3番ト短調D408 (4) 華麗なるロンド ロ短調 ■Disc5 バッハ: (1) 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番ト短調BWV1001 (2) 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第1番ロ短調BWV1002 (3) 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番イ短調BWV1003 ■Disc6 (1) 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ短調BWV1004 (2) 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番ハ長調BWV1005 (3) 無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番ホ長調BWV1006 |
ヨハンナ・マルツィ(Vn) ■Disc1 フェレンツ・フリッチャイ(指)RIASSO(1)、 パウル・クレツキ(指)フィルハーモニアO(2) ■Disc2 オイゲン・ヨッフム(指)バイエルン放送室内O(1)、 ジャン・アントニエッティ(P)(2)(3) ■Disc3 パウル・クレツキ(指)フィルハーモニアO(1)、 ジャン・アントニエッティ(P)(2)(3) ■Disc4 ジャン・アントニエッティ(P) 録音:Disc1:1953年6月10-12日イエス・キリスト教会(ベルリン)(1)、1954年2月15-17日キングズウェイ・ホール(ロンドン)(2) Disc2:1952年11月ミュンヘン(1)、 1952年7月9-10日ハノーファー、ベートーヴェン・ザール(2)、 1955年11月9-12日ベルリン(3) Disc3:1955年12月20-21日キングズウェイ・ホール(ロンドン)(1)、 1952年7月7-8日ハノーファー、ベートーヴェン・ザール(2)、 1955年9月26日、11月13日ベルリン(3) Disc4:1955年11月9-12日ベルリン Disc5:1955年3月26-27日(1)、 4月27-30日(2)、3月27-31、4月1-2日(3)アビーロード・スタジオ(ロンドン) Disc6:1954年7月24-26日(1)、 5月1、6月1-3日(2)、 1955年5月15-18日(3)アビーロード・スタジオ(ロンドン) |
|
||
| Forgotten Records fr-1854(1CDR) |
ブロニスワフ・ギンペル~ブラームス&クライスラー ブラームス:ヴァイオリン協奏曲* クルト・クレーメル編曲:クライスラー・トランスクリプションズ#[愛の喜び/愛の悲しみ/美しきロスマリン/セレナード「ポリシネル」/R=コルサコフ:「アラブの踊り」(「シェヘラザード」より)/ウィーン奇想曲/中国の太鼓/ラフマニノフ:「ひなぎく」 /ファリャ:「スペイン舞曲」] |
ブロニスワフ・ギンペル(Vn) アルトゥール・グリューバー(指)ベルリンSO* クルト・クレーメル(指)シュトゥットガルト・プロ・ムジカO# 録音:1958年頃#、1960年頃* ※音源:Opera 3238*、St-1932* 他 |
| Forgotten Records fr-1860(1CDR) |
ワーナー・ジャンセン カスキ:「ショウ・ボート」の主題によるオーケストラの為のシナリオ バーバー:演奏会用序曲「悪口学校」 Op.5 バーナード・ハーマン:ピアノ協奏曲(映画「戦慄の調べ」」より) デイヴィッド・ラクシン:映画「ローラ殺人事件」 ~ローラのテーマ タンスマン:映画「肉体と幻想」 ~スケルツォ |
マックス・ラビノヴィチ(P)* ワーナー・ジャンセン(指)ロサンゼルス・ジャンセンSO 録音:1942~1945年 ※音源:Camden CAL-205 |
| Channel Classics CCS-45223(1CD) |
プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲 第1番ニ長調 Op. 19 ヴァイオリン協奏曲 第2番ト短調 Op. 63 |
マリア・ミルシテイン(Vn) フィオン(ヘルダーラント&オーファーアイセルO オットー・タウスク(指) 録音:2022年5月 エンスヘデ音楽センターMCO、オランダ |
|
||
| CPO CPO-555151(2CD) NX-D11 |
ルイ・シュポア(1784-1859):クラリネットと管弦楽のための作品全集 クラリネット協奏曲第1番ハ短調 Op. 26 クラリネット協奏曲第2番変ホ長調 Op. 57 アルルーナの主題による変奏曲 WoO 15 ペーター・フォン・ヴィンターの歌劇「妨げられた奉献祭」の2つの主題によるポプリ Op. 80 ダンツィの主題による幻想曲と変奏曲 Op. 81-クラリネットと弦楽四重奏のために . クラリネット協奏曲第3番ヘ短調 WoO 19 クラリネット協奏曲第4番ホ短調 WoO 20 |
クリストファー・スンドクヴィスト(Cl) ハノーファー北ドイツ放送PO ジモン・ガウデンツ(指) 録音 2017年1月24-27日、2019年6月24-28日 |
|
||
| ONDINE ODE-1419(1CD) NX-B07 |
アルトゥルス・マスカツ(1957-):アコーディオン協奏曲/タンゴ
他 タンゴ(2002) アコーディオン協奏曲「What the Wind Told Over the Sea 海を渡る風が語るもの」(2021) カントゥス・ディアトニクス(1982) ” わたしの川はあなたへと流れる エミリー・ディキンソンへのオマージュ(2019) |
アルトゥルス・ノヴィクス(アコーディオン) クセーニャ・シドロワ(アコーディオン) ラトヴィア国立SO アンドリス・ポーガ(指) 録音:2022年3月11-12日、2022年9月2-3日 |
|
||
| FUGA LIBERA FUG-798(1CD) |
プロコフィエフ:ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 Op. 16 交響曲第2番ニ短調 Op. 40 |
アンドレイ・コロベイニコフ(P) ウラルPO ドミトリー・リス(指) 録音:2021年7月 スヴェルドロフスク・フィルハーモニック大ホール、エカテリンブルク、ロシア |
|
||
| Rondeau ROP-6219(1CD) |
コンチェルト・セッション ヨハン・ヴィルヘルム・ヘルテル(1727-1789):トランペット協奏曲 ニ長調 ヨハン・ミヒャエル・ハイドン:トランペット協奏曲 ニ長調 フランツ・クエルフルト(1715/1720-ca.1751):トランペット協奏曲 変ホ長調 ヨーゼフ・リーペル:トランペット協奏曲 ニ長調 ミヒャエル・ハイドン:トランペット協奏曲 ハ長調 フランツ・クサヴァー・リヒター:トランペット協奏曲 ニ長調 |
ヘルムート・フックス(Tp)、 マティアス・グリュナート(Org) 録音:2021年2月10日-12日 |
|
||
| Nimbus NI-8109(1CDR) |
ドリーム・キャッチャー~クラリッサ・ベヴィラックア・プレイズ・オーガスタ・リード・トーマス オーガスタ・リード・トーマス(b.1964):ラッシュ リア・エンチャンテッド/カプリス カプリシャス・トッカータ 「ダンデライオン・スカイ」 ドリーム・キャッチャー インカンテイション/パルサー ヴィーナス・エンチャンテッド レインボウ・ブリッジ・トゥ・パラダイス ヴァイオリン協奏曲第3番「ジャグラー・イン・パラダイス」 |
クラリッサ・ベヴィラックア(Vn)、 ヴィンバイイ・カズィボニ(指)、 BBCウェールズ・ナショナルO 録音:2021年9月1日-2日、シカゴ大学(ソロ作品)&、2022年4月25日、BBCホディノット・ホール(協奏曲) |
|
||
| Hyperion CDA-68397(1CD) |
ハープシコード協奏曲集 マルティヌー:ハープシコードと小オーケストラのための協奏曲 H246 ハンス・クラーサ:ハープシコードと7つの楽器のための室内楽曲 ヴィクトル・カラビス:ハープシコードと弦楽オーケストラのための協奏曲 Op.42 |
マハン・エスファハニ(ハープシコード)、 プラハRSO、 アレクサンダー・リープライヒ(指) 録音:2021年9月21日-22日&10月13日-14日、スタジオ・S1、チェコ放送(プラハ、チェコ) |
|
||
| Pentatone PTC-5187017(1CD) |
「バッハとペルト」 (1)ペルト:フラトレス~ヴァイオリン、弦楽オーケストラと打楽器のための (2)バッハ:ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 BWV1042 (3)バッハ:ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 BWV1041 (4)バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043 (5)ペルト:鏡の中の鏡 |
アラベラ・美歩・シュタインバッハー(Vn/グァルネリ・デル・ジェス(1744年製作))
(1)-(5)シュトゥットガルト室内O、ラヴァー・スコウ・ラーセン(コンサートマスター) (4)クリストフ・コンツ(Vn) (5)ピーター・フォン・ヴァイン ハ ルト(P) 録音:2022年6月21-24日聖ペーター&パウル教会、ロイトリンゲン・ゲニンゲン(ドイツ) |
|
||
| BIS BIS-2625(1CD) |
『織られた光』~ヴィート・パルンボ(1972-):作品集 (1)ヴァイオリン協奏曲(2015) (2)シャコンヌ(「織られた光」、「闇の中の輝き」)~エレクトリック・ヴァイオリンとエレクトロニクスのための(2019-20) |
フランチェスコ・ドラツィオ((1)ヴァイオリン
、 (2)エレクトリック・ヴァイオリン) LSO、 リー・レイノルズ(指) (2)フランチェスコ・アブレシア(ライヴ・エレクトロニクス) [楽器:ヴァイオリン:Giuseppe Guarneri, Cremona 1711、エレクトリック・ヴァイオリン(5弦):Alter Ego (2007)、 エレクトロニクス:Csound, Cycling ’74MaxMSP] 録音:(1)2016年9月17日/アビーロード・スタジオ 第1スタジオ(ロンドン)、(2)2021年1月19-20日/モーラ・ディ・バーリ(イタリア) |
|
||
| Stradivarius STR-37221(1CD) |
モーツァルト:オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314 ハイドン:オーボエ協奏曲 ハ長調 Hob.VIIg:C1 クロンマー:オーボエ協奏曲第1番ヘ長調 Op.37 |
クリスティアン・シュミット(Ob) ペルージャ室内O 録音:2021年11月16,17,18日 イタリア ウンブリア州 チッタ・デッラ・ピエーヴェ |
|
||
| BIS BISSA-2466(1SACD) |
カレヴィ・アホ(1949-):協奏曲集 (1)ヴァイオリン協奏曲第2番(2015) (2)チェロ協奏曲第2番(2013) |
(1)エリナ・ヴァハラ(Vn)、 (2)ヨナタン・ローゼマン(Vc) キュミ・シンフォニエッタ、 オラリ・エルツ(指) 録音:(1)2019年4月24-26日、(2)2021年12月2-4日/クーサンコスキ・ホール、コウヴォラ(フィンランド) |
|
||
| Altus ALTSA-503(1SACD) シングルレイヤー |
INA秘蔵音源・ハスキル&クリュイタンス・フランス国立管ライヴ モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番ハ短調 K.491 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番 |
クララ・ハスキル(P) アンドレ・クリュイタンス(指) フランス国立放送O ライヴ録音:1955年12月8日(モノラル) |
|
||
| DOREMI DHR-8193(2CD) |
マルタ・アルゲリッチLIVE第12集 (1)ショパン:ピアノ協奏曲第2番へ短調 Op.21 (2)シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 Op.54 (3)リスト:ピアノ協奏曲第1番変ホ長調 S.124 (4)バッハ:パルティータ第2番ハ短調 BWV826 プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第7番変ロ長調 Op.83 シューマン:幻想小曲集 Op.12 ショパン:スケルツォ第3番嬰ハ短調 Op.39 ショパン:アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ Op.22 D.スカルラッティ:ソナタ ニ短調 K.141, L.422 |
マルタ・アルゲリッチ(P) (1)クラウス・テンシュテット(指)デトロイトSO ライヴ録音:1978年2月9日デトロイト (2)シャルル・デュトワ(指)フランス国立O ライヴ録音:1973年9月6日パリ (3)ノーマン・デル・マー(指)エーテボリSO ライヴ録音:1971年3月18日エーテボリ (4)ライヴ録音:1978年11月3日トロント・リサイタル |
|
||
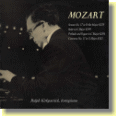 Treasures TreasuresTRE-283(1CDR) |
カークパトリック/フォルテピアノによるモーツァルト ピアノ・ソナタ第17番 変ロ長調 KV 570 組曲 ハ長調 KV 399 幻想曲とフーガ ハ長調 KV 394 ピアノ協奏曲第17番 ト長調 KV 453* |
ラルフ・カークパトリック(フォルテピアノ) アレクサンダー・シュナイダー(指)* ダンバートン・オークスCO* 録音:1952年、1951年3月* ※音源:W.R.C CM-30、日Victor LH-25* ◎収録時間:71:33 |
| “楽器へのこだわりが音楽表現と不可分であることを証明する最高の実例!” | ||
|
||
| フォンテック FOCD-9875(1CD) 2022年12月7日発売 |
第8回仙台国際音楽コンクール ヴァイオリン部門優勝
~中野りな モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」K219 バルトーク:ヴァイオリン協奏曲第2番 |
中野りな(Vn) 広上淳一(指)仙台PO 録音:2022年6月2・5日日立システムズホール仙台 ライヴ(コンクールのセミファイナルとファイナルの模様を収録) |
|
||
| フォンテック FOCD-9876(1CD) 2022年12月7日発売 |
第8回仙台国際音楽コンクール ピアノ部門優勝~ルゥォ・ジャチン モーツァルト:ピアノ協奏曲第25番 K503 プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第2番 |
ルゥォ・ジャチン(P) 高関健(指)仙台PO 録音:2022年6月23・26日日立システムズホール仙台 ライヴ(コンクールのセミファイナルとファイナルの模様を収録 ) |
|
||
| Goodies 78CDR-3885(1CDR) |
バッハ:ハープシコード協奏曲第1番ニ短調 BWV 1052 | ワンダ・ランドフスカ(ハープシコード) ウジェーヌ・ビゴー(指)O 仏 LA VOIX DE SON MAITRE DB 11229/31 1938年12月1日パリ、アルベール・スタジオ録音 |
|
||
| EUROARTS 20-56773F(Bluray) 20-56777F(2DVD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集 ピアノ協奏曲第1番ハ長調 作品15 ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 作品19 ピアノ協奏曲第3番ハ短調 作品37 ピアノ協奏曲第4番ト長調 作品58 ピアノ協奏曲第5番『皇帝』 |
シュターツカペレ・ベルリン ダニエル・バレンボイム(P、指 ) 収録:2007年5月、ルール・ピアノフェスティヴァル(ライヴ) ◆Bluray 画面:16:9、Full HD 音声:PCMステレオ、 DD 5.1、DTS-HD MA5.1 リージョン:A l l、198分 ◆DVD 画画面:16:9、NTSC 音声:PCMステレオ、DD 5.1、DTS5.1 リージョン:A l l |
|
||
| Hyperion CDA-68339(1CD) |
ロマンティック・ピアノ・コンチェルト・シリーズ
Vol.85~カール・ライネッケ:ピアノ協奏曲集
ライネッケ(1824-1910):ピアノ協奏曲第1番 嬰ヘ短調 Op.72(1860) ピアノ協奏曲第2番 ホ短調 Op.120(1872) ピアノ協奏曲第4番 ロ短調 Op.254(1900) |
サイモン・キャラハン(P)、 ザンクト・ガレンSO、 モデスタス・ピトレナス(指) 録音:2021年11月15日-18日、トーンハレ・ザンクト・ガレン(スイス) |
|
||
| Goodies 78CDR-3888(1CDR) |
マリユス・カザドシュ:モーツァルトのヴァイオリン協奏曲ニ長調 K.Anh.294a 「アデライデ」 | ユーディ・メニューイン(Vn) ピエール・モントゥー(指) パリSO 英 HMV DB 2268/70 1934年5月14日パリ、アルベール・スタジオ録音 |
|
||
| Goodies 78CDR-3889(1CDR) |
リスト:ピアノ協奏曲第1番変ホ長調 | エミール・フォン・ザウアー(P) フェリックス・ワインガルトナー(指) パリ音楽院O 英 COLUMBIA LX789/91 1938年12月1日パリ録音 |
|
||
| Forgotten Records fr-1852(1CDR) |
ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番* チャベス:ピアノ協奏曲# |
ダニエル・ワイエンベルク(P)* ユージン・リスト(P)# ディミトリ・ミトロプーロス(指)NYO 録音:1953年11月22日*、1942年1月2日#放送用録音 |
| Forgotten Records fr-1853(1CDR) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番ハ短調 K.491* ピアノ・ソナタ第18番二長調 K.576 # |
ルイス・ケントナー(P) ハリー・ブレック(指)フィルハーモニアO* 録音:1959年5月23日-24日*、1959年6月8日# ※音源: HMV XLP-20035 |
| Forgotten Records fr-1855(1CDR) |
フリードリヒ・ヴューラー/ウェーバー&メンデルスゾーン ウェーバー:ピアノ協奏曲(全2曲)* メンデルスゾーン:ピアノ協奏曲第2番# |
フリードリヒ・ヴューラー(P) ハンス・スワロフスキー(指)ウィーン・プロ・ムジカO* ルドルフ・モラルト(指)ウィーンSO# 録音:1950年8月31日#、9月2日#、1953年*、すべてウィーン ※音源: Vox PL 8140* 、PL 6570 # |
| ARCANA A-535(1CD) NYCX-10364(1CD) 国内盤仕様 税込定価 |
バッハ:チェロ・ピッコロによる協奏曲 6編 バッハ:チェロ・ピッコロ、弦楽と通奏低音のための協奏曲 ニ長調〔チェンバロ協奏曲 第3番ニ長調 BWV 1054(Vn協奏曲 第2番ホ長調 BWV 1042による)からの編曲〕 ェロ・ピッコロと通奏低音のための協奏曲 ニ長調〔チェンバロ独奏のための協奏曲 ニ長調 BWV 972(アントニオ・ヴィヴァルディ[1678-1741]:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.3-9RV 230による)からの編曲〕 チェロ・ピッコロ、弦楽と通奏低音のための協奏曲 ト短調〔ヴァイオリンあるいはオーボエ協奏曲 ト短調 BWV 1056R(チェンバロ協奏曲 第5番ヘ短調 BWV 1056から復元)からの編曲〕 チェロ・ピッコロと通奏低音のための協奏曲 ニ短調〔チェンバロ独奏のための協奏曲 ニ短調 BWV 974(アレッサンドロ・マルチェッロ[1678-1741]:オーボエ協奏曲 ニ短調 による)からの編曲〕 チェロ・ピッコロ、弦楽と通奏低音のための協奏曲 イ長調〔オーボエ・ダモーレ協奏曲 イ長調 BWV 1055R(チェンバロ協奏曲 第4番イ長調 BWV 1055 から復元)による〕 チェロ・ピッコロ、弦楽と通奏低音のための「イタリア協奏曲」 ヘ長調チェンバロ独奏のための協奏曲 ヘ長調 BWV 971「イタリア協奏曲」 から リッカルド・ドーニによるオーケストレーション〕 |
マリオ・ブルネロ(Vc・ピッコロ) アカデミア・デッラヌンチアータ(古楽器使用) 〔コンサートマスター:カルロ・ラッザローニ(Vn)〕 リッカルド・ドーニ((指)チェンバロ、ポジティフ・オルガン) 録音:2021年7月1-5日 サン・ベルナルディーノ教会、 アッビアーテグラッソ(イタリア北部ミラノ県) ※国内仕様盤解説日本語訳…白沢達生 |
|
||
| TUDOR TUD-7211(1CD) |
ピアノ協奏曲集 モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K. 466 マルティーニ:ピアノ協奏曲 ト長調 ヨハン・フランツ・クサヴァー・シュテルケル(1750-1817):ピアノ協奏曲 ニ長調 Op. 26No. 2 ※カデンツァ:ヨルク・クローネンベルク |
ヨルク・クローネンベルク(フォルテピアノ) Walter & Sohn 1805頃製作の楽器に基づく Paul McNultyによる復元楽器 カプリッチョ・バロックO ドミニク・キーファー(指) 録音:2021年10月5-7日 |
|
||
| Solo Musica SM-400(1CD) NX-B03 |
ショパン:ピアノ協奏曲第1番/マズルカ集 ピアノ協奏曲第1番ホ短調 Op. 11* マズルカ ト短調 Op. 24No. 1 マズルカ ハ長調 Op. 24No. 2 マズルカ イ短調 Op. 17No. 4 マズルカ ロ短調 Op. 33No. 4 マズルカ 嬰ハ短調 Op. 50No. 3 マズルカ ロ短調 Op. 30No. 2 マズルカ 嬰ヘ短調 Op. 6No. 1 マズルカ 変ロ長調 Op. 7No. 1 マズルカ ト短調 Op. 67No. 2 マズルカ 嬰ヘ短調 Op. 59No. 3 |
マルガリータ・ヘーエンリーダー(フォルテピアノ) プレイエル(19世紀半ば 制作年不詳)* プレイエル(1855年頃制作)の修復楽器 ラ・シンティッラO(ピリオド楽器使用) リッカルド・ミナージ(指) |
|
||
| ODRADEK RECORDS ODRCD-404(3CD) ★ |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集 + ピアノ小品集
ピアノ協奏曲第1番ハ長調 Op.15 ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 Op.19 ピアノ協奏曲第3番ハ短調 Op.37 ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op.58 ピアノ協奏曲第5番変ホ長調 Op.73「皇帝」 ロマンス第1番ト長調 Op.40(ピサロ編 独奏ピアノ) ロマンス第2番ヘ長調 Op.50(ピサロ編 独奏ピアノ) アンダンテ ヘ長調「アンダンテ・ファヴォリ」WoO.57 ロンド ハ長調 Op.51-1 ロンド ト長調 Op.51-2 |
アルトゥール・ピサロ(P) ジュリア・ジョーンズ(指)ヴッパータルSO 録音:2021年1月20,21,22,23日(Op.15,Op.19,Op.37) ドイツ ヴッパータル 2021年3月21,25,26日(Op.58,Op.73) ドイツ ヴッパータル 2021年8月10-12日 イタリア アブルッツォ州 モンテシルヴァーノ |
|
||
| Gramola GRAM-99267(1CD) |
ヴィヴァルディ:モテットと協奏曲集 弦楽のための協奏曲 ト短調 RV 157 4-7. モテット「いと公正なる怒りの激しさに」 RV 626 モテット「おお、天にても地にても清きもの」 RV 631 チェロ協奏曲 ニ短調 RV 405 モテット「まことの安らぎはこの世にはなく」 RV630 弦楽のための協奏曲 ハ短調 RV 119 モテット「色は紅」 RV 642 |
アレクサンドラ・ザモイスカ(S) ミハル・スターヘル(Vc) パンドルフィス・コンソート(古楽器アンサンブル)【マキシミリアン・ブラット(Vn1)、カタジナ・プジョザ(Vn2)、ルジュビエタ・サイカ=バフレル(Va)、ゲオルク・クロナイス(ヴィオローネ)、フーベルト・ホフマン(テオルボ)、マティアス・クランペ(Org)】 録音:2021年10月 |
|
||
| BIS BISSA-2576(1SACD) |
スウェーデンのピアノ協奏曲 ラウラ・ネーツェル(1839-1927):ピアノ協奏曲 Op.84 スヴェン=ダーヴィド・サンドストレム(1942-2019):ピアノと管弦楽のための5つの小品(2016) アンドレーア・タッロディ(1981-):ピアノ協奏曲第1番「星の雲(Stellar Clouds)(2015) |
ペーテル・フリース・ユーハンソン(P)、 ヨーテボリSO、 ライアン・バンクロフト(指) 録音:2021年10月4-7日/ヨーテボリ・コンサートホール(ヨーテボリ、スウェーデン) |
|
||
| DOREMI DHR-8187(2CD) |
マルタ・アルゲリッチLIVE第10集 (1)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 Op.19 (2)プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 Op.26 (3)ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第21番ハ長調『ワルトシュタイン』 Op.53 ショパン:ピアノ・ソナタ第3番ロ短調 Op.58 ドビュッシー:『版画』より 第3曲「雨の庭」 (4)ラヴェル:ピアノ協奏曲 ト長調 (5)シューマン:ピアノ・ソナタ第2番 ト短調 Op.22 |
マルタ・アルゲリッチ(P) (1)ロリン・マゼール(指)ベルリンRSO/録音:1972年ベルリン (2)クラウディオ・アバド(指)フランス国立放送O/録音:1967年12月7日フランス (3)録音:1970年2月4日東京厚生年金会館 (4)ペーター・マーク(指)シュトゥットガルトRSO/録音:1969年10月10日シュトゥットガルト (5)録音:1973年4月7日ニューヨーク |
|
||
| Da Vinci Classics C-00623(1CD) |
ヴィオラとオーケストラのための作品集 ブルッフ:クラリネット,ヴィオラとオーケストラのための協奏曲ホ短調 Op.88、 ロマンス Op.85、コル・ニドライ Op.47 ヒンデミット:葬送音楽 ロータ(ストラッキ編):インテルメッツォ |
ヴィットーリオ・ベナグリア(Va)、 ダニスタ・ラフキエヴァ(Cl)、 パザルジクSO、 アレクサンドル・ゴードン(指) 録音:2021年6月15日、パザルジク(ブルガリア) |
|
||
| DUX DUX-1834(1CD) |
ガリアーノ:オパール協奏曲~アコーディオン協奏曲集 リシャール・ガリアーノ(b.1950):オパール協奏曲(1994) ブロニスワフ・カジミエシュ・プシビルスキ(1941-2011):コンチェルト・クラシコ(1986) クシシュトフ・オルチャク (b.1956):協奏曲(1989) |
ミハウ・ガイダ(アコーディオン)、 コーオペラO、 アダム・ドムラット(指) 録音:2017年8月 |
|
||
| ALPHA ALPHA-883(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲 第23番イ長調 K. 488 カデンツァ…ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト ピアノ協奏曲 第24番ハ短調 K. 491 カデンツァ(第1楽章)…ヨハン・ネポムク・フンメル カデンツァ(第3楽章)…ジュリアン・トレヴェリアン |
ジュリアン・トレヴェリアン(P/ベーゼンドルファーVC
280) ウィーンRSO クリスティアン・ツァハリアス(指) 録音:2022年1月オーストリア放送スタジオ6/大ホール、ウィーン |
|
||
| CEDILLE CDR-90000214(1CD) NX-B04 |
黒人作曲家によるヴァイオリン協奏曲集 サン=ジョルジュ(1745-1799):ヴァイオリン協奏曲 イ長調 Op. 5No. 2 ホセ・ホワイト・ラフィット(1836-1918):ヴァイオリン協奏曲 嬰ヘ短調 コールリッジ=テイラー(1875-1912):ロマンス ト長調 Op. 39 フローレンス・ベアトリス・プライス(1887-1953):ヴァイオリン協奏曲第2番* |
レイチェル・バートン・パイン(Vn) アンコール室内O ダニエル・ヘギー(指) ロイヤル・スコティッシュ・ナショナルO* ジョナサン・ヘイウォード(指)* 録音:1997年6月3-5日、2022年1月7日* |
|
||
| オクタヴィア OVCC-00167(1SACD) 税込定価 2022年10月19日発売 |
R・シュトラウス:ホルン協奏曲 第1番* F・シュトラウス:ノクターンOp.7* R・シュトラウス:ホルン協奏曲 第2番 アンダンテ 遺作 |
日高剛 (Hrn) 粟辻聡(指)* カーチュン・ウォン(指) 日本センチュリーSO 録音:2021年1月7日 豊中市立文化芸術センター*、6月10日 大阪 ザ・シンフォニーホール・ライヴ |
|
||
| ATMA ACD2-2853(1CD) |
バッハ:協奏曲集 (1)2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043 (2)オーボエ・ダモーレ協奏曲 イ長調 BWV1055R (3)ヴァイオリン協奏曲 イ短調 BWV1041 (4)チェンバロ協奏曲 ニ長調 BWV1054 (5)ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲 ハ短調 BWV1060R |
ジュリア・ウェドマン(Vn(1) (3)(5)) ジェシー・デュベ(Vn(2) ) マシュー・ジェンジョン(オーボエ・ダモーレ(2)、オーボエ(5)) エリック・ミルンズ(指、Cemb(4) ) アルモニー・デ・セゾン 録音:2021年10月21、22日ケベック |
|
||
| Profil PH-22053(6CD) |
クララ・ハスキル/協奏曲とソナタ ■Disc1 モーツァルト: (1)ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.466 (2)ピアノ協奏曲第24番ハ短調K.491 (3)ピアノと管弦楽のためのロンドイ長調K.386 ■Disc2 モーツァルト: (1)ピアノ協奏曲第9番「ジュノム」 (2)ヴァイオリン・ソナタ変ロ長調K.454 (3)ヴァイオリン・ソナタイ長調K.526 ■Disc3 モーツァルト: (1)ピアノ協奏曲第13番ハ長調K.415 (2)ピアノ協奏曲第27番変ロ長調K.595 ■Disc4 ベートーヴェン: (1)ピアノ協奏曲第3番ハ短調Op.37 (2)ヴァイオリン・ソナタ第10番ト長調Op.96 ■Disc5 ベートーヴェン: (1)ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」 (2)ピアノ・ソナタ第17番「テンペスト」 (3)ピアノ・ソナタ第18番変ホ長調Op.31 ■Disc6 シューマン: (1)色とりどりの小品Op.99~3つの小品 (2)色とりどりの小品Op.99~5つのアルバムの綴り (3)子供の情景Op.15 (4)森の情景Op.82 (5)アベッグ変奏曲Op.1 |
クララ・ハスキル(P) ■Disc1 イーゴリ・マルケヴィチ(指)ラムルーO(1)(2) ベルンハルト・パウムガルトナー(指)ウィーンSO(3) 録音:1960年11月パリ(1)(2)、1954年10月ウィーン(3) ■Disc2 パウル・ザッハー(指)ウィーンSO(1)、アルテュール・グリュミオー(Vn)(2)(3) 録音:1954年10月ウィーン(1)、1956年1月2-5日アムステルダム(2)(3) ■Disc3 ルドルフ・バウムガルトナー(指)ルツェルン音楽祭弦楽合奏団(1) フェレンツ・フリッチャイ(指)バイエルン国立O(2) 録音:1960年5月ルツェルン(1)、1957年9月7日ミュンヘン(2) ■Disc4 イーゴリ・マルケヴィチ(指)ラムルーO(1)、アルテュール・グリュミオー(Vn)(2) 録音:1960年10月パリ(1)、1956年12月28-30日アムステルダム(2) ■Disc5 アルテュール・グリュミオー(Vn)(1) 録音:1957年1月2-5日(1)、1955年5月(2)(3)アムステルダム ■Disc6 録音:1952年4月9日(1)(2)、1955年5月(3)、1954年5月(4)、1951年10月(5)ヒルフェルスム(オランダ) |
|
||
| ALPHA ALPHA-882(1CD) |
次世代ソリストたちによるモーツァルト Vol.3 ヴァイオリン協奏曲 第4番ニ長調 K. 218(カデンツァ…ヨーゼフ・ヨアヒム) フルート協奏曲 第1番ト長調 K. 313(カデンツァ…ジョセフィーヌ・オレック) ピアノ協奏曲 第6番変ロ長調 K. 238(カデンツァ…スリマ・ストラヴィンスキー[第1楽章]、モーツァルト[第3楽章]) |
ルズヴィ・グディム(Vn) ジョセフィーヌ・オレック(Fl) ジェネバ・カネー=メイソン(P) ウィーンRSO ハワード・グリフィス(指) 録音:2022年3月 |
|
||
| REFERENCE FR-749(1CD) |
侵略~ウクライナへの音楽と美術 ルイス・スプラットランの作品 (1)侵略(2022) (2)ピアノ組曲第1番(2021) (3)6つのラグ(2018) (4)2つのソナタ(2021) (5)さすらい人(2005) |
ナージャ・シュパチェンコ(P) アンソニー・パーンサー(指)、パット・ポージー(Sax)、アイジャ・マットソン=ジョヴェル(Hrn)、フィル・キーン(Tb)、稲生由里(パーカッション)、ジョティ・ロックウェル(マンドリン)(以上(1)) 録音:2022年5月29日、6月22日-23日/サイレント・ズー・スタジオ(グレンデール、カリフォルニア) |
|
||
| PAN CLASSICS PC-10441(1CD) |
バッハ一族とフルート バッハ:管弦楽組曲第2番ロ短調 BWV1067 ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハ:フルート・ソナタ ホ短調 IWB58 C.P.E.バッハ:フルート協奏曲 ト長調 Wq169 ヨハン・クリストフ・フリードリヒ・バッハ:フルート、ヴィオラと通奏低音のための三重奏曲 ホ短調 BR B4 ヨハ ン・クリスティアン・バッハ:フルート、オーボ エ 、ヴァイオリン、ヴィオラ、通 奏 低 音 の ため の五 重 奏曲 ニ長調Op.11-6 |
ベニャミーノ・パガニーニフラウト・トラヴェルソ、指)
ムジカ・グローリア 録音:2021年5月5-7日/ベルギー、ヘクス教会 |
|
||
| Biddulph BIDD-85019(1CD) |
フリッツ・クライスラー/ベル・テレフォン・アワー録音集
第1集 (1)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番 ト長調 K. 216- I. Allegro (2)モーツァルト:2. ヴァイオリン協奏曲第4番 ニ長調 K. 218- I. Allegro (3)ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番(F. クライスラー編) (4)メンデルスゾーン: 6. ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op. 64- I. Allegro molto appassionato (5)ブラームス:ヴァイオリン協奏曲- II. Adagio (6)ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番-I. Vorspiel:Allegro moderato/ II. Adagio |
フリッツ・クライスラー(Vn) ベル・テレフォン・アワー・オーケストラ ドナルド・ヴォーヒーズ(指) (1)録音:1950年3月6日 (2)録音:1945年1月1日 (3)録音:1945年2月19日&1945年10月29日 (4)録音:1944年7月17日 (5)録音:1945年12月31日 (6)録音:1944年10月9日 復刻プロデューサー:Eric Wen マスタリング:Dennis Patterson |
|
||
| Piano21 P-21050N(1CD) |
ハイドン:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲 ニ長調 Hob. XVIII:11 ヴァイオリンとピアノのための協奏曲 ヘ長調 Hob. XVIII:6* ピアノ協奏曲 ト長調 Hob. XVIII:9 |
シプリアン・カツァリス(P)、 ステファニー・ゴンリー(Vn)*、 アカデミー室内O、 サー・ネヴィル・マリナー(指) 録音:2013年4月29日-30日、セント・ジョンズ・スミス・スクエア/使用楽器:ヤマハ CFX |
|
||
| La Dolce Volta LDV-106(1CD) |
オペラ作曲家モーツァルト 幻想曲 ハ短調 K.475 ピアノ協奏曲 変ホ長調 K.482 演奏会用アリア「どうしてあなたを忘れられよう」 K.505 4手のためのピアノ・ソナタ ヘ長調 K.497 |
フィリップ・カッサール(P&指) ナタリー・ドゥセ(S) セドリック・ ペ シ ャ(P) ブルターニュ国立O 録音:2022年4月16-20日、レンヌ |
|
||
| Hanssler HC-220651CD) |
「ヤン・クベリークへのオマージュ」 (1)ヤン・クベリーク:ヴァイオリン協奏曲第1番 ハ長調【世界初録音】 (2)メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64 |
パヴェル・シュポルツル(Vn) トマーシュ・ブラウネル(指)プラハSO 録音:(1)2022年1月8、10&11日、(2)2022年3月8&9日/スメタナ・ホール(プラハ) |
|
||
| CLAVES 50-3050(1CD) |
モーツァルト:管楽器のための協奏曲集 Vol.1 (1)フルート協奏曲第1番ト長調 K.313 (2)フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K.299 (3)フルート協奏曲第2番ハ長調 K.314 (4)アンダンテ ハ長調 K.315 カデンツァ: (1)(3)(4)レイチェル・ブラウンとコンラート・ヒュンテラーを基にアレクシス・コセンコが即興演奏、(2)シルヴァン・ブラッセル |
アレクシス・コセンコ(フルート) (2)ヴァレリア・カフェルニコフ(Hp) ステファン・マクラウド(指)、 リ・アンジェリ・ジュネーヴ(古楽器) ン録音:2021年6月/ランドガストホフ、リーエン(スイス) |
|
||
| BIS BISSA-2524(1SACD) |
ヨハン・ヴィルヘルム・ヴィルムス(1772-1847):ピアノ協奏曲集
Vol.2 協奏曲 ヘ長調 Op.32~ピアノとオーケストラのための 協奏曲 変ホ長調 Op.55~ピアノとオーケストラのための |
ロナルド・ブラウティハム(フォルテピアノ)
マイケル・アレクサンダー・ウィレンス(指)、ケルン・アカデミー 録音:2021年8月/イムマヌエル教会、ヴッパータール(ドイツ) |
|
||
| BAM International BAM-21603(1CD) |
黒のリスト ~ライヴ・レコーディング リスト:ピアノ協奏曲第1番S.124 哀しみのゴンドラ S.200/1 諦め S.187 メフィスト・ワルツ第4番S.216b 暗い雲 S.199 われらの主イエス・キリストの変容の祝日に S.188 死の舞踏 ~「怒りの日」によるパラフレーズ S.525 忘れられたロマンス S.132 |
ア ルド・シジッロ(指 ) ブラショフPO マルチェッロ・マッツォーニ(P) ライヴ録音:2020年1月(協奏曲)、2019年8月(独奏曲) 発売:2021年 |
|
||
| B RECORDS LBM0-451(1CD) |
ヴィヴァルディ:海の嵐、およびその他の室内協奏曲集 協奏曲 ニ長調 RV 95「羊飼いの娘」 協奏曲 ニ長調 RV 90「ごしきひわ」 協奏曲 ト短調 RV 107 リュート、ヴァイオリンと通奏低音のためのトリオ・ソナタ ハ長調 RV 82 協奏曲 ニ長調 RV 94 協奏曲 ヘ長調 RV 98「海の嵐」 |
レ・パラダン(古楽器使用)【フランソワーズ・ニコレ(リコーダー、フラウト・トラヴェルソ)、ティモテー・ウディノ(Ob)、ニルス・コッパル(バスーン)、クレール・ソッティヴィア(Vn)、ニコラ・クルニャンスキ(Vc)、バンジャマン・ナルヴェ(テオルボ、バロックギター)】 ジェローム・コレアス(チェンバロ、指揮) 録音:2021年5月25-28日 サントル・デュ・ボール・ド・マルヌ、ル・ペルー=シュル=マルヌ(パリ郊外)(ライヴ/最終トラックに拍手入り) |
|
||
 ICA CLASSICS ICAC-5168(1CD) NX-B03 |
サン=サーンス:ピアノ協奏曲 第2番 リスト:ピアノ協奏曲 第1番* ベートーヴェン:15の変奏曲とフーガ 「エロイカ変奏曲」# パデレフスキ:6つの演奏会用ユモレスク Op. 14~I. メヌエット ト長調# ショパン:ワルツ 第14番ホ短調 「遺作」# |
シューラ・チェルカスキー(P) サイモン・ラトル(指)バーミンガム市SO ノーマン・デル・マー(指)BBC響* 録音:1983年9月3日 アッシャー・ホール、エディンバラ 1983年10月5日 ロイヤル・フェスティバル・ホール、ロンドン* 1979年11月22日 クイーン# 全てステレオ・ライヴ録音:拍手入り 初CD化 |
|
||
| BIS BISSA-2586(1SACD) |
ハチャトゥリヤンピアノ協奏曲変ニ長調 「仮面舞踏会」組曲(ドルハニアン編ピアノ独奏版) ピアノと管弦楽のためのコンチェルト・ラプソディ |
イヤード・スギャエル(P) アンドルー・リットン(指) BBCウェールズSO 録音:2021年10月20-22日/BBCホディノット・ホール(カーディフ) |
|
||
 TRE-257 |
ノーマン・デロ=ジョイオ(1913-2008):ピアノと管弦楽のための幻想曲と変奏曲* プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第5番ト長調 Op.55# ラヴェル:ピアノ協奏曲ト長調 M.83 |
ロリン・ホランダー(P) エーリヒ・ラインスドルフ(指)ボストSO 録音:1963年2月17日(世界初録音)*、1964年3月28日#、1963年1月16日、ボストン、シンフォニー・ホール(全てステレオ) ※音源:米RCA_LSC-2667、日VICTOR_SHP-2370# ◎収録時間:65:55 |
| “洗練を極めたタッチから紡ぎ出される作品の本質!” | ||
|
||
| MSR MS-1789(1CD) |
マルティン・マタロン(b.1958):ピアノ作品集 (1)トレイムIV(2001)~ピアノと11楽器のための協奏曲 (2)策略(2014)~ピアノ独奏のための (3)二つの時間(2000)~ピアノ独奏のための (4)機械(2007)~2台のピアノ、二人の打楽器奏者とエレクトロニクスのための |
エレーナ・クリオンスキー(P) (1)ジョエル・サックス(指) ニュー・ジュリアード・アンサンブル (4)サロメ・ジョルダニア(P) イヴ・ペイヤー(Perc) ジュリアン・マセド(Perc) デイヴィッド・アダムシック(エレクトロニクス) |
|
||
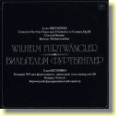 Treasures TRE-271(1CDR) |
ハンゼン~ベルリンでの協奏曲録音 チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番* ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番 |
コンラート・ハンゼン(P) ウィレム・メンゲルベルク(指)BPO* ウィルヘルム・フルトヴェングラー(指)BPO 録音:、1940年7月11日ベルリン*、1943年10月30(31)日(ライヴ)、 共にベルリン、フィルハーモニーホール ※音源:PAST MASTERS_PM-18*、Melodiya M10-460067 ◎収録時間:65:56 |
| “ハンゼンとフルトヴェングラー、双方の強烈なシンパシーが完全融合!” | ||
|
||
| ACCENT ACC-24385(1CD) |
バッハ:チェンバロ協奏曲集 第1集 チェンバロ協奏曲第4番イ長調 BWV1055 チェンバロ協奏曲第2番ホ長調 BWV1053 ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 BWV1041 2台のチェンバロのための協奏曲第3番ハ短調 BWV1062 |
【独奏者】マリオ・セラッチャ(Cemb) BWV1055/
1053/ 1062(第2) バルト・ナセンス(Cemb) BWV1062(第1) サラ・クイケン(Vn) BWV1041 【ラ・プティット・バンド】シギスヴァルト・クイケン((指)ヴァイオリン、BWV1062のみヴィオロンチェロ・ダ・スパッラ) サラ・クイケン、ユン・キム(Vn) マルレ ーン・ティー ルス(Va) エドゥアルド・カタラン(バスヴァイオリン) BWV1053/ 1041/ 1055 バルト・ナセンス(通奏低音チェンバロ) 録音:2021年10月2-5日/ベルギー、ティールト、ペーター教会 |
|
||
| DOREMI DHR-8181(2CD) |
マルタ・アルゲリッチLIVE第8集 (1)チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 (2)シューマン:ピアノ協奏曲 (3)ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第7番 ニ長調 Op.10-3 バルトーク:ピアノ・ソナタ Sz.80 ショパン:24の前奏曲 Op.28 スカルラッティ:ソナタ ニ短調 K.141, L.422 ショパン:マズルカ第40番へ短調 Op.63-2 |
マルタ・アルゲリッチ(P) (1)シャルル・デュトワ(指)エーテボリSO ライヴ録音:1972年10月27日エーテボリ (2)ヴァーツラフ・ノイマン(指)チェコPO 放送ライヴ録音:1971年3月29日ミュンヘン (3)ライヴ録音:1976年6月8日東京文化会館 |
|
||
| H.M.F HMM-902332(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲 第9番変ホ長調 K.271「ジュノーム」 ピアノ協奏曲 第18番変ロ長調 K.456 |
クリスティアン・ベザイデンホウト (フォルテピアノ/ヴァルター&ゾーン・ピアノ(ウィーン、1805年頃)のコピー(ポール・マクナルティ製、2008年)) フライブルク・バロック・オーケストラ(コンサートマスター:ゴットフリート・フォン・デア・ゴルツ) 録音:2021年5月、アンサンブルハウス、フライブルク |
|
||
| Chandos CHAN-20263(1CD) |
モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲集 Vol.2
ヴァイオリン協奏曲第1番変ロ長調 K.207 ヴァイオリン協奏曲第2番 ニ長調 K.211 ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 K.219「トルコ風」 |
フランチェスカ・デゴ(Vn)、 ロジャー・ノリントン(指)、 ロイヤル・スコティッシュ・ナショナルO 録音:2021年9月10日-12日、ロイヤル・コンサート・ホール(RSNOセンター、グラスゴー) |
|
||
 ONDINE ODE-1410(1CD) NX-B07 |
ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 ベルク:ヴァイオリン協奏曲 (ある天使の思い出に)* |
クリスティアン・テツラフ(Vn) ベルリン・ドイツSO ロビン・ティチアーティ(指) 録音:2022年3月25-26日(ライヴ) 2021年9月28-29日* |
|
||
| BIS BISSA-2581(3SACD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲(全5曲) ピアノ協奏曲第1番ハ長調 Op.15 ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 Op.19 ピアノ協奏曲第3番ハ短調 Op.37 ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op.58 ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 |
ハオチェン・チャン(P/Steinway D, No. 989)
ナタリー・シュトゥッツマン(指) フィラデルフィアO 録音:2021年10月26-29日/キンメル舞台芸術センター内ベライゾンホール(フィラデルフィア) |
|
||
|
Naive |
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集~ピゼンデルとその周辺 ト長調 RV 314、ニ長調 RV 226、変ロ長調 RV 369、ニ短調 RV 237、ニ長調 RV 225、イ長調 RV 340 |
ジュリアン・ショヴァン(Vn、指揮) コンセー ル・ド・ラ・ローグ 録音:2021年3月11-14日、フランス |
|
||
| GRAND SLAM GS-2274(1CD) |
ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.77 | ダヴィッド・オイストラフ(Vn) オットー・クレンペラー(指) フランス国立放送O 録音:1960年6月17-19日/パリ、サル・ワグラム 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:ステレオ(録音セッション) |
|
||
| H.M.F HMX-2904032 (8CD+1DVD) (NTSC) |
イザベル・ファウスト・プレイズ・バッハ ■CD1] ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 BWV 1052R カンタータ第174番「われいと高き者を心を尽して愛しまつる」 BWV 174よりシンフォニア(hrn2, ob2, オーボエ・ダ・カッチャ, vn3, vla3, vc3, 通奏低音) ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 BWV 1042 ・カンタータ第21番「わがうちに憂いは満ちぬ」BWV 21よりシンフォニア(ob, 弦, 通奏低音) トリオ・ソナタ ハ 長調 BWV 529(vn2と通奏低音) オーボエ、ヴァイオリン、弦と通奏低音のための協奏曲 ハ短調 BWV 1060R ■CD2] 管弦楽組曲第2番BWV 1067~ヴァイオリンと弦楽合奏、通奏低音の編成による(イ短調で演奏) トリオ・ソナタ ニ短調 BWV 527(ob, vn, 通奏低音) ヴァイオリン協奏曲 ト短調 BWV 1056R カンタータ第182番「天の王よ、汝 を迎えまつらん」BWV 182より 第1曲 ソナタ(rec, vn, 弦と通奏低音) ヴァイオリン協奏曲 イ短調 BWV 1041 シンフォニア BWV 1045(vn;trp3, tim, ob2, 弦、通低) 2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV 1043 ■CD3] 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ集 パルティータ第2番BWV 1004ニ短調 ・ソナタ第3番 BWV 1005ハ長調 パルティータ第3番BWV 1006ホ長調 ■CD4] 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ集 ソナタ 第1番ト短調 BWV 1001パルティータ 第1番ロ短調 BWV 1002 ソナタ 第2番イ短調 BWV 1003 ■CD5] バッハ:ヴァイオリン・ソナタ集(オブリガート・チェンバロとヴァイオリンのためのソナタ集) 第1番ロ短調 BWV 1014/第2番イ長調 BWV 1015/第3番 ホ長調 BWV 1016 ■CD6] バッハ:ヴァイオリン・ソナタ集(オブリガート・チェンバロとヴァイオリンのためのソナタ集) 第4番ハ短調 BWV 1017/第5番ヘ短調 BWV 1018/第6番 ト長調 BWV 1019 ■CD7] ブランデンブルク協奏曲 第1番ヘ長調 BWV1046/第2番ヘ長調 BWV1047/第3番 ト長調 BWV1048 ■CD8] ブランデンブルク協奏曲 ・第4番ト長調 BWV1049 ・第5番ニ長調 BWV1050 ・第6番 変ロ長調 BWV1051 ■DVD 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番ハ長調 BWV 1005、パルティータ第2番ニ短調 BWV 1004 収録:トーマス教会(ライプツィヒ)/映像監督:ウテ・フォイデル、プロデューサー:ポール・スマチヌィ |
[CD1-2]イザベル・ファウスト(Vn/ヤコブ・シュタイナー) ベルンハルト・フォルク(Vn/制作者不明(1725年))、クセニア・レフラー(オーボエ、リコーダー)、ヤン・フライハイト(Vc)、ラファエル・アルパーマン(Cemb)、ベルリン古楽アカデミー(コンサートマスター:ベルンハルト・フォルク) 録音:2017年12月、2018年9月/テルデックス・スタジオ・ベルリン [CD3]イザベル・ファウスト(Vn/1704年製ストラディヴァリウス「スリーピング・ビューティ」) 録音:2009年9月 [CD4]イザベル・ファウスト(Vn/1704年製ストラディヴァリウス「スリーピング・ビューティ」) 録音:2011年8,9月 [CD5-6]イザベル・ファウスト(Vn/ヤコブ・シュタイナー 1658年製)、クリスティアン・ベザイデンホウト(チェンバロ/ジョン・フィリップス、バークレー 2008年製(ヨハン・ハインリヒ・グレープナー(ジ・エルダー) ドレスデン 1722年製モデル/トレヴァー・ピノックより貸与) 録音時期:2016年8月18-24日 [CD7-8]ベルリン古楽アカデミー、イザベル・ファウスト(Vn/ヤコブス・シュタイナー(1658年製)/BWV1048、 1049) アントワン・タメスティ(ヴィオラ/1672年製ストラディヴァリウス「マーラー」/BWV 1048、1051) 録音:2021年3,5月 DVD 57'56 音声:PCM 2.0& 5.1 NTSC |
|
||
| H.M.F HMSA-0058 (2SACD) 日本独自企画 税込定価 |
バッハ:チェンバロ協奏曲集 [Disc1]協奏曲第1番ニ短調 BWV 1052、第2番 ホ長調 BWV 1053、第7番ト短調 BWV 1058 [Disc2]協奏曲第3番ニ長調 BWV 1054、第4番 イ長調 BWV 1055、第5番へ短調 BWV 1056、第6番 ヘ長調 BWV 1057 |
アンドレアス・シュタイアー(Cemb)、フライブルク・バロック・オーケストラ(音楽監督&ヴァイオリン:ペトラ・ミュレヤンス) 録音:2013年7月 |
|
||
| H.M.F HMSA-0057(1SACD) シングルレイヤー 日本独自企画 税込定価 |
ショスタコーヴィチ:ピアノ協奏曲 第2番ヘ長調 作品102 ヴァイオリン・ソナタ op.134 ピアノ協奏曲 第1番ハ短調 op.35 |
アレクサンドル・メルニコフ(P) イザベル・ファウスト(Vn) イエルーン・ベルワルツ(Tp) マーラー・チェンバー・オーケストラ テオドール・クルレンツィス(指) 録音:2010年10,11月&2011年3月 |
|
||
| DOREMI DHR-8183(2CD) |
レオン・フライシャーLIVE 第4集 (1)ブラームス:ピアノ協奏曲第1番ニ短調 Op.15 (2)モーツァルト:ピアノ協奏曲第25番 ハ長調 K.503 (3)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 Op.19 ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 Op.43 (4)フランク:ピアノと管弦楽のための交響的変奏曲 (5)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 Op.19より 第1楽章 |
レオン・フライシャー(P) (1)ピエール・モントゥー(指揮NYO ライヴ録音:1944年11月4日/カーネギーホール (2)エルネスト・ブール(指)南西ドイツRSO 放送用ライヴ録音:1960年3月19日 (3)ヘンリー・ソプキン(指)アトランタSO ライヴ録音:1963年頃 (4)エンリケ・ホルダ(指)サンフランシスコSO 録音:1955年2月6日 (5)フェレンツ・フリッチャイ(指)サンフランシスコSO 録音:1953年11月29日 |
|
||
| GENUIN GEN-22774(1CD) |
「深い高み」 ドニゼッティ:「ドン・パスクワーレ」~天使のように美しく ブージョワ:バス・トロンボーンとバンドのための協奏曲Op.239a チャイコフスキー:「エフゲニー・オネーギン」~誰でも一度は恋をして レベデフ:チューバ/バス・トロンボーンと管弦楽のための協奏曲第1 番 ヴェルディ:「ドン・カルロ」~彼女は私を愛してはいなかった ブルーベック:プラハ協奏曲~バス・トロンボーンと管弦楽のための ワーグナー:「タンホイザー」~ああお前よ、私の優しい夕星よ |
リザ・ホッホヴィンマー(Tb) ベンヤミン・ライナース(指) キールPO 録音:2021年3月24―26日 ドイツ キール |
|
||
 ALPHA ALPHA-878(1CD) NYCX-10336(1CD) 国内盤仕様 税込定価 |
『モーツァルトとマンボ 2- キューバン・ダンス』 モーツァルト:ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調 K. 417 『キューバン・ダンス』 ソロ・ホルン、弦楽合奏とパーカッションのための ペペ・ガビロンド(1989-)/ヤセル・ムニョス(1996-):I. Tamarindo Scherz-son ユニエト・ロンビーダ(1989-):II. Danzon de la Medianoche ウィルマ・アルバ・カール(1988-):III. Guaguanco Sencillo ホルヘ・アラゴン(1988-):IV. Un Bolero para Sarah ユニエト・ロンビーダ/エルネスト・オリバ(1988-):V. Sarahcha エルネスト・オリバ:VI. !Ay Comay! Un Changui pa´Sari モーツァルト:ホルン協奏曲 第1番ニ長調 K. 412 マリーア・テレーサ・ベラ(1895-1965)/ホルヘ・アラゴン編曲:20年 リチャード・エグエス(1924-2006)/ホルヘ・アラゴン編曲:エル・ボデゲーロ エドガー・オリヴェロ(1985-):パ・パ・パ (モーツァルト:「魔笛」パパゲーナとパパゲーノのデュエットによる) |
サラ・ウィリス(Hrn) カルロス・カルンガ(歌) エンリケ・ラサガ(ギロ) サラバンダ【サラ・ウィリス(Hrn)、ユニエト・ロンビーダ(Sax)、ジャネル・ラスコン(P)、レオ・A. ルナ(ベース)、アレハンドロ・アギアル(カホン、マラカス)、アデル・ゴンサレス(コンガ)、エドゥアルド・ラモス(ティンバレス)】 ハバナ・リセウム・オーケストラ アデル・ゴンサレス(パーカッション/スペシャル・ゲスト)、 セ・アントニオ・メンデス・パドロン(指) 録音:2022年1月、4月 オラトリオ・サン・フェリペ・ネリ教会、ハバナ、キューバ ※ 国内仕様盤 日本語解説…今泉晃一、歌詞日本語訳…原口昇平 |
|
||
 Channel Classics CCS-42522(1CD) |
ラフマニノフ:ピアノ協奏曲 第4番 ト短調 Op. 40 ピアノ協奏曲 第2番ハ短調 Op. 18 |
アンナ・フェドロヴァ(P) ザンクト・ガレンSO モデスタス・ピトレナス(指) 録音:2021年11月 トーンハレ・シアター、ザンクト・ガレン、スイス |
|
||
| CD ACCORD ACD-293(1CD) NX-C09 |
アンジェイ・チャイコフスキ/ギヤ・カンチェリ:
作品集 アンジェイ・チャイコフスキ(1935-1982):協奏曲「古典」 - ヴァイオリンと管弦楽のために ギヤ・カンチェリ(1935-2019):リベラ・メ(レクイエム風) |
イリア・グリンゴルツ(Vn) マグダレーナ・シャボフスカ(S) ワルシャワ・フィルハーモニー合唱団男声セクション ワルシャワPO アンドレイ・ボレイコ(指) 録音:2021年2月5日、2021年4月2日…4 |
|
||
| CD ACCORD ACD-295(1CD) NX-C05 |
サン=サーンス:ミューズと詩人たち Op. 132 マルティヌー:協奏曲 H.252 ヘンリク・クシェショヴィエツ(1946-):トリオ・コン・ブリオ(2017) |
シモン・クシェショヴィエツ(Vn) アダム・クシェショヴィエツ(Vc) ヤン・クシェショヴィエツ(Fl) イェジー・マクシミウク(指) NFMヴロツワフPO 録音:2021年3月19日(ライヴ) |
|
||
| MDG MDG-90122166 (1SACD) |
ベートーヴェン:献堂式序曲 ピアノ協奏曲第4番ト長調Op.58 創作主題による32の変奏曲 ハ短調 WoO.80 ●ボーナスCD:ペーター・ギュルケによるアルフレッド・ブレンデルの対談集の朗読 |
ラウマ・スクリデ(P) ブランデンブルクSO ペーター・ギュルケ(指) 録音:2020年11月10-14日、ブランデンブルク劇場 |
|
||
| MDG MDG-90322646 (1SACD) |
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」(Vnとオルガン版) 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」 協奏曲第3番ヘ長調 RV 293「秋」 協奏曲第4番ヘ短調 RV 297「冬」 ヴァイオリン協奏曲 イ短調 (すべてテオフィル・ハインケによるオルガン編) |
デヴィッド・ゴロル(Vn) テオフィル・ハインケ(Org)使用楽器:ヴァルタースハウゼン市教会、トロスト・オルガン 録音:2021年11月2-4日、ヴァルタースハウゼン市教会 |
|
||
| Etcetra KTC-1749(1CD) |
ピッコロ協奏曲集 レヴェンテ・ジェンジェシ(b.1975):ピッコロ協奏曲(2022) エリク・デシンペラーレ(b.1990):ピッコロ協奏曲(2016) ロベール・グロロー(b.1951):ピッコロ協奏曲(2012/2021) バート・ワッテ(b.1979):ピッコロ協奏曲(2016/2021) |
ペーター・フェルホーエン(ピッコロ)、 アタネレス・アンサンブル、他 |
|
||
| Avie AV-2555(1CD) |
クロイツェル・プロジェクト ベートーヴェン(コリン・ジェイコブセン編):クロイツェル協奏曲(Vn・ソナタ第9番 イ長調 Op.47より)* コリン・ジェイコブセン(b.1978):Kreutzings アンナ・クライン(b.1980):速記** ヤナーチェク(エリック・ジェイコブセン編、マイケル・P・アトキンソンによるオーケストレーション):クロイツェル・ソナタ(弦楽四重奏曲第1番 JW 7/8より) |
ザ・ナイツ、エリック・ジェイコブセン(指)、 コリン・ジェイコブセン(Vn)*、 カレン・ウズニアン(Vc)** 録音:2020年2月8日-10日&7月21日-23日 |
|
||
| Pentatone PTC-5187016(1CD) |
モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調 K.216 ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調 K.218 ヴァイオリンと管弦楽のためのアダージョ ホ長調 K.261(カデンツァ:ユリア・フィッシャー) ヴァイオリンと管弦楽のためのロンド 変ロ長調 K.269(カデンツァ:ユリア・フィッシャー) |
ユリア・フィッシャー(Vn/1750年製グァダニーニ) ヤコフ・クライツベルク(指)、 オランダ室内O ゴルタン・ニコリッチ(コンサートマスター) 録音:2005年ヴァールゼ教会(アムステルダム) |
|
||
| Hanssler HC-22039(1CD) |
C.P.E.バッハ:鍵盤協奏曲集 Vol.7 (1)協奏曲 ハ短調 Wq.5(1739)(第2楽章のカデンツァ;C.P.E.バッハ) (2)協奏曲 イ長調 Wq.8(1741)(第2&3楽章のカデンツァ;リシェ) (3)協奏曲 ロ短調 Wq.30(1753)(第1&2楽章のカデンツァ;C.P.E.バッハ) |
ミヒャエル・リシェ(P&指揮) ベルリン・バロック・ゾリステン 【マルティン・フンダ(Vn/コンサートマスター) 町田琴和、ハンデ・キューデン、ドリアン・ジョジ(1)(2)、ヨハンナ・ステムラー(3)(Vn1) アンナ・ルイーザ・メーリン、アレクサンダー・キッシュ、ライマー・オルロフスキー、ジョナサン・マサキ・シュワルツ(Vn2) ヴァルター・クシュナー、ユリア・ガルテマン(Va) クレメンス・ヴァイゲル、サヤカ・セリーナ・シュトゥーダー(Vc) ウルリッヒ・ウォルフ(1)(2)、エスコ・ライン(3)(ヴィオローネ)】 A'=442Hz 録音:2022年3月/テルデックス・スタジオ(ベルリン) |
|
||
| BRAVO RECORDS BRAVO-10009(1CD) 税込)定価 |
ショパン:ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 Op.21(ケヴィン・ケナー、クシシュトフ・ドンベク
室内楽版編) マズルカ第31番変イ長調 Op.50-2 |
實川風(P) (1)ハマのJACKメンバー(弦楽五重奏)【三又治彦(Vn)、白井篤(Vn)、村松龍(Va)、海野幹雄(Vc)、松井理史(Cb)】 ライヴ録音:2022年3月1日/横浜市港南区民文化センターひまわりの郷 |
|
||
| ORFEO DOR C-220081(1CD) NX-A13 |
ドヴォルザーク:序曲「フス教徒」 ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 |
ヘンリク・シェリング(Vn) ラファエル・クーベリック(指) バイエルンRSO 録音:1967年6月11日(ライヴ) Konzerthaus Wien(オーストリア) STEREO ※C719071DRの再発盤 |
|
||
| H.M.F HMM-902688(1CD) |
ヴィヴァルディ:作品集 協奏曲 ニ長調 RV 562「聖ロレンツォの祝日のために」 フルート協奏曲 ホ短調 RV 432 協奏曲 ハ長調 RV 556「聖ロレンツォの祝日のために」(1720年半ば) 協奏曲 ヘ長調 RV 571 ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲 ト短調 RV 576 ヴァイオリン協奏曲 イ長調 RV 344 2つのオーボエのための協奏曲 イ短調 RV 536 協奏曲 ヘ長調「プロテウス、あるいは逆さまの世界」RV 572 |
アマンディーヌ・ベイエ(Vn&指) 「リ・インコーニティ」 トラヴェルソ&リコーダー:エレオノーラ・ビシェビチ、マニュエル・グラナティエロ(ソロ:RV432) オーボエ:ネヴェン・ルサージュ(ソロ:RV 576)、ガブリエル・ピドゥ クラリネット:ロベ ル タ・クリスティ、ル ノー・ギィ= ルソ ー ファゴット:アレ ハンドロ・ペレス= マラン ホルン:テオ・スカネク、シリル・ヴィトコク ヴァイオリン:川久保洋子、フラヴィオ・ロスコ、ヴァディム・マカレンコ、アルバ・ロカ、カティア・ヴィエル、エレナ・ズマノヴァ ヴィオラ:マルタ・マラモ 、リカルド・ジ ル・サンチェス チェロ:レベカ・フェリ、カルラ・ロヴィロサ ヴィオローネ:バルドメロ・バルシエラ テオルボ&バロックギター:フランチェスコ・ロマノ チェンバロ&オルガン:アンナ・フォンタナ ティンパニ:クレ マン・ロスコ 録音:2021年4月、スペイン |
|
||
| DOREMI DHR-8168(2CD) |
ルドルフ・ゼルキンLIVE 第3集~モーツァルト (1)ピアノ協奏曲第21番ハ長調 K.467 (2)ピアノ協奏曲第24番ハ短調 K.491 (3)ピアノ協奏曲第20番ニ短調 K.466 (4)ピアノ協奏曲第12番イ長調 K.414 (5)ピアノとヴァイオリンのためのソナタ K.12 & K.13(任意のチェロつき) (6)前奏曲とフーガ ハ長調 K.394 |
ルドルフ・ゼルキン(P) (1)ユージン・オーマンディ(指)、VPO ライヴ録音:1963年6月9日ウィーン (2)ミシェル・シンガー(指)、オーバリン室内O ライヴ録音:1985年10月17日オーバリン (3)グイード・カンテッリ(指)、ニューヨーク・フィルハーモニック ライヴ録音:1953年3月26日カーネギーホール (4)アレクサンダー・シュナイダー(指)、カザルス祝祭O ライヴ録音:1963年カザルス音楽祭 (5)ピーナ・カルミレッリ(Vn)、ダヴィド・コール(Vc) ライヴ録音:1974年頃マールボロ (6)ライヴ録音:1968年5月13日ロンドン、ロイヤル・フェスティバル・ホール |
|
||
| DOREMI DHR-8177(2CD) |
ルドルフ・ゼルキンLIVE 第4集 (1)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番変ホ長調 『皇帝』 Op.73 (2)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番ハ短調 Op.37 (3)モーツァルト:ピアノ協奏曲第16番ニ長調 K.451、第25番ハ長調 K.503 (4)ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第1番 へ短調 Op.2-1 |
ルドルフ・ゼルキン(P) (1)ギュンター・ヴィッヒ(指)、NHKSO ライヴ録音:1979年10月4日東京 (2)ジェームズ・レヴァイン(指)セントルークスO ライヴ録音:1986年4月20日メトロポリタン美術館 (3)ディミトリ・ミトロプーロス(指)NYO ライヴ録音:1955年10月23日カーネギーホール (4)ライヴ録音:1977年6月6日トロント大学 |
|
||
| LAWO Classics LWC-1234(1CD) |
嘆きの跡 ギンゲ・アンヴィーク(b.1970):オスティナート(Vcと管弦楽のための)* ガウテ・ストロース(b.1959):別の側から(Vcと弦楽オーケストラのための) ヘンリク・スクラム(b.1973):晩餐(Vcと管弦楽のための)*、創発(Vcと管弦楽のための)* ガウテ・ストロース:北欧の年(Vcと弦楽オーケストラのための) |
アウドゥン・サンヴィーク(Vc)、 ノルウェー放送O *、トマス・クルーグ(指)*、ノルウェー室内O、 ペール・クリスチャン・スカルスタード(指) 2018年1月17日-19日、ノルウェー放送(NRK)コンサートホール(オスロ)*&2020年6月11日-12日、オスロ・コンサートホール「小ホール」(オスロ) |
|
||
| Nimbus Alliance NI-6429(1CDR) |
トーマス・ド・ハルトマン:管弦楽作品集 ピアノ協奏曲 Op.61(1939) 交響詩第3番Op.85(1953) 幻想的スケルツォ Op.25(1929) |
ウクライナ・リヴィウ国立フィルハーモニックO、 ティアン・ホイ・ウン(指)、 エラン・シクロフ(P) 録音:2021年9月18日-19日、国立フィルハーモニックホール、リヴィウ(ウクライナ) |
|
||
| Signum Classics SIGCD-704(1CD) |
ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61 ロマンス第1番ト長調 Op.40 ロマンス第2番 ヘ長調 Op.50 |
チャーリー・シーム(Vn)、 オレグ・カエターニ(指)フィルハーモニアO 録音:2021年11月22日-23日、オール・ハロウズ・ゴスペル・オーク(ロンドン、イギリス) |
|
||
 BRAVO RECORDS BRAVO-10008(1CD) 税込定価 |
ショパン:ピアノ協奏曲第1番ホ短調 Op.11(ケヴィン・ケナー、クシシュトフ・ドンベク
室内楽版編) 夜想曲第8番変ニ長調 Op.27-2 |
福間洸太朗(P) (1)日本フィル団員(弦楽五重奏)【田野倉雅秋(Vn)、竹歳夏鈴(Vn)、安達真理(Va)、石崎美雨(Vc)、高山智仁(Cb)】 ライヴ録音:2022年1月27日横浜市鶴見区民文化センター サルビアホール |
|
||
 CPO CPO-555447(4CD) NX-G11 |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集(第0番-第7番) ピアノ協奏曲第1番ハ長調 Op. 15 ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 Op. 19 ピアノ協奏曲第3番ハ短調 Op. 37 4-6. ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op. 58 ピアノ協奏曲(第7番) ニ長調 Op. 61a(原曲: ヴァイオリン協奏曲) ピアノ協奏曲第5番変ホ長調 Op. 73 ピアノ協奏曲第0番変ホ長調 WoO 4(オーケストレーション:ヘルマン・デヒャント) ロンド 変ロ長調 WoO 6 ピアノ協奏曲(第6番) ニ長調(1814/15) H15(ニコラス・クックによる補筆完成版に基づく) |
ミヒャエル・コルスティック(P) ウィーンRSO コンスタンティン・トリンクス(指) 録音:2020年12月21-23日、2021年1月4-5、7-8日、3月18-19、21-22日 |
|
||
| MClassics MYCL-00030(1CD) 税込定価 |
松村禎三:交響作品集 ピアノ協奏曲 第1番 ゲッセマネの夜に 交響曲第1番 |
渡邉康雄(P). 野平一郎(指) オーケストラ・ニッポニカ 録音:2021年7月18日 東京、紀尾井ホール |
|
||
| Forgotten Records fr-1836(1CDR) |
プレスラー&グリーンハウス ハイドン:協奏曲集 ピアノ協奏曲 ニ長調 Hob.XVIII:11* / チェロ協奏曲 ニ長調 Hob.VIIB:2# |
メナヘム・プレスラー(P)* バーナード・ グリーンハウス(Vc)# アイズラー・ソロモン(指)MGM管 録音:1950年代末 音源:MGM Records GC-30008 |
| Forgotten Records fr-1843(1CDR) |
ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調* バーバー:チェロ協奏曲 Op.22# |
エドマンド・クルツ(Vc)* ラヤー・ガールブゾヴァ(Vc)# ディミトリ・ミトロプーロス(指)NYO 録音:1950年11月12日*、1947年12月7日# カーネギーホール 、ライヴ |
| Forgotten Records fr-1845(1CDR) |
チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番変ロ短調 Op.23* 交響曲第4番ヘ短調 Op.36# |
マリーナ・ムディヴァニ(P)* ウジェーヌ・ビゴー(指)* フランス放送リリクO* ルドルフ・アルベルト(指)# セント・ソリO# 録音:1961年6月26日、ロン=ティボー国際コンクール、ライヴ 1958年5月10日(ステレオ)# ※音源:Le Club Français du Disque CFD 133#他 |
| Indesens INDE-018(1CD) |
バロックと古典派のトランペット協奏曲集 フンメル:トランペット協奏曲ホ長調 テレマン:トランペット協奏曲ニ長調 バッハ:ブランデンブルク協奏曲第2番ニ長調 BWV1047* L・モーツァルト:トランペット、2本のホルンと弦楽のための協奏曲ニ長調 フランツ・ハイドン:トランペット協奏曲変ホ長調 Hob.VIIe-1 |
エリック・オービエ(Tp) ヴァンサン・バルト(指)、 ブルターニュO、 トゥルーズ室内O* 、フランソワ・ルルー(Ob)*、 ブノワ・フロマンジェ(Fl)*、 アラン・モリア((指)ヴァイオリン)* |
|
||
| DUX DUX-1773(1CD) |
ジグムント・ストヨフスキ:ピアノ協奏曲集
ストヨフスキ(1870-1946):ピアノ協奏曲第1番嬰ヘ短調 Op.3 ピアノ協奏曲第2番変イ長調 Op.32「プロローグ、スケルツォと変奏曲」* |
マレク・シュレゼル(P)、 ヴィトルト・ヴィルチェク(P)*、ポーランド・シンフォニア・ユヴェントスO、マレク・ヴロニシェフスキ(指)、ゾフィア・グス((指)第1番第2楽章のみ) 録音:2021年5月17日-20日(ワルシャワ) |
|
||
| Signum Classics SIGCD-710(1CD) |
バッハ:ハープシコード協奏曲集 ハープシコード協奏曲 ニ短調 BWV 1052 ハープシコード協奏曲 ト短調 BWV 1058 ハープシコード協奏曲 ニ長調 BWV 1054 ハープシコード協奏曲 イ長調 BWV 1055 |
ハノーヴァー・バンド、 アンドルー・アーサー(指&ハープシコード) 録音:2019年5月、セント・ニコラス教会(アランデル、イギリス) |
|
||
| KLARTHE KLA-020(1CD) |
「Rencontre(S)~出会い(の数々)」 ジャン=セバスティアン・ベロー:「ジャイス」~ピアノとフルート・オーケストラのための(2003) 「黒人保護区」~フルートとピアノのための(1969) 「葉脈」~ピアノのための(1969) 「再生」~フルートとピアノのための(2011) |
ピエール=イヴ・アルトー (Fl)、 アナ・テレス(P) オルケストル・ド・フルート・フランセ、 ジャン=セバスチャン・ベロー(指) 録音:2011年9月13&14日/オーディトリアム・ヴィアナ・ダ・モッタ |
|
||
| BRIDGE BCD-9562(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第25番ハ長調K.503(カデンツァ:クリス・ロジャーソン)
ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.466(カデンツァ:ベートーヴェン) |
アン=マリー・マクダーモット(P) セバスチャン・ラング=レッシング(指) オーデンセSO 録音:2020年8月25-29日 デンマーク |
|
||
| BIS BISSA-2507(1SACD) |
ハイドン:チェロ協奏曲第1番ハ長調 Hob.VIIb:1 チェロ協奏曲第2番ニ長調 Hob.VIIb:2 「アダージョ」~交響曲第13番ニ長調 Hob.I:13より第2楽章 ヒンデミット:『葬送音楽』~チェロと弦楽オーケストラのための(1936) |
クリスチャン・ポルテラ(Vc&指) ミュンヘン室内O 録音:2021年4月6-9日/昇天教会、ゼンドリング(ミュンヘン) |
|
||
| CLAVES 50-3045(1CD) |
ヴィスメール:協奏曲と管弦楽曲集 (1)交響曲『子供とバラ』(サン=テグジュペリ原作『星の王子さま』に基づく) (2)オーボエ協奏曲 (3)ヴァイオリン協奏曲第3番 (4)交響的三部作『クラマヴィ』 |
ノラ・シスモンディ(Ob) オレグ・カスキフ(Vn) スイス・ロマンドO、 ジョン・フィオーレ(指) 録音:2021年6月ヴィクトリア・ホール(ジュネーヴ) (1)(2)(4)=世界初録音 |
|
||
| KLARTHE KLA-151(1CD) |
オデット・ガルテンロープ:生誕百年記念アルバム (1)フルート協奏曲 (2)ピアノ協奏曲 (3)交響的楽章 |
(1)レイモン・ギヨー(Fl)、マニュエル・ロザンタール(指)フランス放送フィル (2)オデット・ガルテンロープ(P)、デジレ=エミール・アンゲルブレシュト(指)フランス放送フィル (3)デジレ=エミール・アンゲルブレシュト(指)フランス放送フィル 録音:(1)1967年7月3日/パリ放送局104スタジオ (2)1958年6月19日シャンゼリゼ劇場(世界初演時ライヴ) (3)1955年7月17日シャンゼリゼ劇場(世界初演時ライヴ) |
|
||
| Goodies 78CDR-3874(1CDR) |
サン=サーンス:チェロ協奏曲第1番(単一楽章) | グレゴール・ピアティゴルスキー(Vc) フレデリック・ストック(指)CSO 米 COLUMBIA 11440/41 1940年3月6日シカゴ、シンフォニー・ホール録音 |
|
||
 ALPHA ALPHA-866(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲 第24番ハ短調 K. 491(第1楽章カデンツァ…ガブリエル・フォーレ) ピアノ協奏曲 第17番ト長調 K. 453 |
エリック・ル・サージュ(P) イェヴレSO フランソワ・ルルー(指) 録音:2021年9月 イェヴレ、スウェーデン |
|
||
| QUEEN ELISABETH COMPETITION QECDUO-22(4CD) NX-E02 |
エリザベート王妃国際コンクール2017・チェロ部門 ■ヴィクトル・ジュリアン=ラフェリエール (仏/第1位) (1)バッハ:無伴奏チェロ組曲 第2番 ニ短調 BWV 1008より プレリュード/ アルマンド/ジーグ (2)ボッケリーニ:2つのチェロのためのソナタ ハ短調 G. 2 (3)ブラームス:チェロ・ソナタ 第2番ヘ長調 Op. 99 (4)ショスタコーヴィチ:チェロ協奏曲 第1番 変ホ長調 Op.107 ■岡本侑也 (日本/第2位) (5)ハイドン:チェロ協奏曲 第2番 ニ長調 Hob.VIIb:2 (6)ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104 (7)ドヴォルザーク:ロンド ト短調 Op.94 ■サンティアゴ・カニョン=バレンシア (コロンビア/第3位) (8)ショスタコーヴィチ:チェロ・ソナタ ニ短調 Op. 40 (9)エルガー:チェロ協奏曲 ホ短調 Op. 85 (10)ハンス・ボッタームント(1892-1949)/ヤーノシュ・シュタルケル(1924-2013):パガニーニの主題による変奏曲 ■イヴァン・カリズナ (ベラルーシ/第5位) (11)ハイドン:チェロ協奏曲 第1番ハ長調 Hob.VIIb:1 (12)ボッケリーニ:2つのチェロのためのソナタ ハ長調 G. 17 (13)プロコフィエフ:チェロ・ソナタ ハ長調 Op. 119 (14)チャイコフスキー:ロココの主題による変奏曲 |
エリザベート王妃国際コンクール2017・チェロ部門 ■(2)リディ・ブライドルプ(Vc) (3)テオ・フシェンネレ(P) (4)ブリュッセル・フィルハーモニック、ステファヌ・ドゥネーヴ(指) (5)(6)ブリュッセル・フィルハーモニック、ステファヌ・ドゥネーヴ(指) (7)トマス・ホップ(P) (8)薗田奈緒子(P) (9)アントワープSO ムハイ・タン(湯沐海)(指) (11)ワロニー王立室内O、フランク・ブラレイ(指) (12)リディ・ブライドルプ(Vc) (13佐藤卓史(P) (14)ベルギー王立リエージュPO、クリスティアン・アルミンク(指) 録音(ライヴ):2017年5-6月フラジェ、スタジオ4/ファイン・アーツ・センター (ブリュッセル) |
|
||
| ARCANA A-530(2CD) NX-D09 |
『16シーズンズ』 ヴィヴァルディ:『四季』 ピアソラ(デシャトニコフ編):ブエノスアイレスの四季 マックス・リヒター(1966-):リコンポーズド:ヴィヴァルディ - フォー・シーズンズ フィリップ・グラス(1937-):ヴァイオリン協奏曲 第2番「アメリカの四季」 |
アレッサンドロ・クアルタ (Vn) ディーノ・デ・パルマ(Vn) コンチェルト・メディテラネオ ジャンナ・フラッタ(指) 録音:2021年5月21-29日 サンタ・キアーラ教会オーディトリアム、フォッジャ、イタリア |
|
||
 CZECH RADIOSERVIS CR-1141(2CD) |
プラハの春音楽祭ゴールド・エディション Vol.3 (1)ドヴォルザーク:劇的カンタータ「幽霊の花嫁」 Op. 69 (2)シューマン:ピアノ協奏曲イ短調Op.54 |
(1)チェコPO ヴォルフガング・サヴァリッシュ(指) ガブリエラ・ベニャチコヴァー(S) リハルト・ノヴァーク(Bs) ズデニェク・ヤンコフスキー(T) プラハ・フィルハーモニーcho 録音:1980年5月23日プラハ、スメタナ・ホール(ステレオ・ライヴ) (2)カルロス・クライバー(指) クリストフ・エッシェンバッハ(P) 録音:1968年5月25日プラハ、スメタナ・ホール(ステレオ・ライヴ) |
|
||
| SUPRAPHON SU-4298(1CD) |
ヨゼフ・ミスリヴェチェク:ヴァイオリン協奏曲全集 (1)ヴァイオリン協奏曲 ハ長調 (2)ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 (3)ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調 (4)ヴァイオリン協奏曲 イ長調 (5)ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 (6)ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 (7)ヴァイオリン協奏曲 ト長調「田園」 (8)ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 |
石川静(Vn) ドヴォルザーク室内O、 リボル・ペシェク(指) 録音:(1)(2)(3)(5)1983年9月8-10日、 (4)(6)(7)(8)1986年3月1-8日 ドヴォルザークホール、ルドルフィヌム(プラハ) |
|
||
| CLAVES 50-3046(1CD) |
フェルナンド・デュリュック(1896-1954):協奏的作品集 (1)サクソフォンとオーケストラのためのソナタ (2)「英雄の詩」~トランペット、ホルンとオーケストラのための* (3)ハープとオーケストラのための協奏曲 |
(1)キャリー・コフマン(Sax) (2) エ イミー・マッケイブ(トラン ペット)、リーラン エ・ステレット(Hrn) (3)チェンユー・ファン(Hp) ジャクソンSO、 マシュー・オービン(指) 録音:2022年1月ジョージ・E・ポッター・センター内ハロルド・シェファー音楽ホール、ジャクソン(ミシガン州) *=世界初録音 |
|
||
| Challenge Classics CC-72915(1SACD) |
ヨハネス・マティアス・シュペルガー(1750-1812):コントラバス協奏曲集 協奏曲第2番ニ長調(1778) 協奏曲第3番変ロ長調(1778)* 協奏曲第4番ヘ長調(1779)* |
ヤン・クリゴフスキー(Cb)[使用楽器]第2番:アントン・ポッシュ製、1736年、ウィーン
第3番:ヨハン・ヤコブス・エルトル製、1789年、プレスブルグ 第4番:制作者不明、1810年頃、ウィーン コレギウム・ヴァルトベルク430 録音:2021年10月29-31日/スロバキア、ブラスチヴァ宮殿、鏡の間 *=世界初録音 |
|
||
| BIS BISSA-2481(1CD) |
バッハ:チェンバロと弦楽のための協奏曲集
Vol.2 協奏曲第6番ヘ長調 BWV1057 協奏曲第4番イ長調 BWV1055 協奏曲第7番ト短調 BWV1058 協奏曲第3番ニ長調 BWV1054 |
鈴木優人(チェンバロ&指揮) バッハ・コレギウム・ジャパン 【オーケストラ】 アンドレアス・ベーレン、水内謙一(リコーダー)、若松夏美(Vn/コンサートマスター)、高田あずみ(Vn)、山口幸恵(Va) 【コンティヌオ】 山本徹(Vc)、西澤誠治(ヴィオローネ)、鈴木優人(Cemb) 録音:2019年7月22-26日ヤマハホール(銀座) 【チェンバロ:Willem Kroesbergen, Utrecht 1987after J. Couchet, 2manuals, 8', 8', 4', FF?f'''】 |
|
||
 Altus ALT-518(1CD) |
ケンプ&ミルシテイン、1956年モントルー音楽祭ライヴ (1)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番(カデンツァ:ヴィルヘルム・ケンプ) (2)ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲 |
(1)ヴィルヘルム・ケンプ(P)、ヨーゼフ・カイルベルト(指)
(2)ナタン・ミルシテイン(Vn)、パウル・クレツキ(指) ケルン・ギュルツェニヒO 録音:(1)1956年9月12日、(2)1956年9月14日(共にモノラル) 共に、モントルー音楽祭でのライヴ |
|
||
| Skani SKANI-091(2CD) |
クリスツ・アウズニエクス(b.1992):ギターを伴う作品集 ■Disc 1 心の大聖堂(2019)(サクソフォーン、エレクトリック・ギターと打楽器のための) ■Disc 2 エレクトリック・ギターと管弦楽のための協奏曲 「らせん巻きの地平線」(2020) |
■Disc 1 アウズィンシュ・チュダルス・アルチュニアン・トリオ〔カールリス・アウズィンシュ(サクソフォーン)、マティース・チュダルス(エレ クトリック・ギター)、イヴァルス・アルチュニアン(打楽器)〕 ■Disc 2 JIJI(エレクトリック・ギター) シンフォニエッタ・リガ、 ノルムンス・シュネー(指) 録音:2020年5月、ラトビア放送第1スタジオ(リガ)(Disc1)、2021年12月11日、GOR コンサートホール(レーゼクネ、ラトビア)(Disc2) |
|
||
 Hanssler HC-22021(6CD) |
「イン・メモリアム」 ■CD1 (1)エルガー:チェロ協奏曲 ホ短調 Op.85 (2)ショスタコーヴィチ:チェロ協奏曲第1番変ホ長調 Op.107 (3)ブルッフ:コル・ニドライ Op.47 ■CD2 (4)サン=サーンス:チェロ協奏曲第1番イ短調 Op.33 (5)チャイコフスキー:ロココの主題による変奏曲 Op.33 (6)マルティヌー:チェロ協奏曲第1番H.196 (7)ダンツィ:チェロ協奏曲第1番イ長調 ■CD3 (8)ハイドン:チェロ協奏曲第1番ハ長調 Hob VIIb.1 (9)ハイドン:チェロ協奏曲第2番ニ長調 Hob VIIb.2 (10)ボッケリーニ:チェロ協奏曲第2番ニ長調 G 479 ■CD4 (11)シューベルト:アルペジョーネ・ソナタ イ短調 D.821 (12)ドヴォルザーク(アンドレーアス・N・タルクマン編):ロンド Op.94【編曲版・世界初録音】 (13)アレクサンダー・ミュレンバッハ(1949-):チェロ協奏曲「光と影の連祷」【世界初録音】 (14)エリセンダ・ファブレガス(1955-):アンダルシアの色彩 ■CD5 (15)ラフマニノフ:チェロ・ソナタ ト短調 Op.19 (16)グリーグ:チェロ・ソナタ イ短調 Op.36 (17)ブゾーニ:セレナータ~チェロとピアノための ト短調 Op.34 (18)ヒラリー・タン(1947-):ザ・クレセット・ストーン(1993)~チェロ独奏のための ■CD6 (19)ブラームス:ピアノ三重奏曲第1番ロ短調 Op.8 (20)シューマン:弦楽四重奏曲第3番イ長調 Op.41 (21)タン:ガーデンズ・オブ・アンナ・マリア・ルイザ・デ・メディチ(2004)~フルート、チェロ、ピアノのための |
全て、フランソワーズ・グローベン(Vc) (1)(2)RTLSO、レオポルド・ハーゲル(指) (3)(6)ルクセンブルク室内O、ニコラ・ブロシュ(指) (4)(5)ルクセンブルクPO、デヴィッド・シャローン(指) (7)コレギウム・ムジクム・デア・ウニヴェルズィテート・カールスルーエ、フーベルト・ハイツ(指) (8)(10)ソロイスツ・ヨーロピアンズ・ルクセンブルク、ヤック・マルティン・ヘンドラー(指) (9)ハイデルベルクSO、トーマス・ファイ(指) (11)レ・ミュジシャン、ピエール・カオ(指) (12)PRISMA木管八重奏団 (13)ベルリン・フィル弦楽合奏団、アレクサンダー・ミュレンバッハ(指) (14)イヴァン・ガヤン(P) (15)(16)アルフレッド・パール(P) (17)マリア・ヴィトシンスキ(P) (19)グラフ・ムリャ(Vn)、ペーター・ラウル(P) (20)ツェートマイアー・クァルテット【トーマス・ツェートマイアー(Vn)、マティアス・メッツァー(Vn)、ルース・キリウス(Va)、フランソワーズ・グローベン(Vc)】 (21)マイニンガー・トリオ【クリストファー・マイニンガー(Fl)、フランソワーズ・グローベン(Vc)、ライナー・ゲップ(P)】 録音:(1)1994年5月2&5日(セッション)、(2)1994年7月12&13日(セッション)/ヴィラ・ルヴィニー、ルクセンブルク【原盤:BGL(1994)】 (3)2011年3月11日(ライヴ)、(6)2009年5月31日(ライヴ)/聖ジャン・バプティスト教会ルーヴェン、ルクセンブルク (4)1999年7月(セッション)、(5)1999年9月(セッション)/コンセルヴァトワール・ド・ルクセンブルク【原盤:BGL(1999)】 (7)2002年2月3日(ライヴ)/カールスルーエ音楽大学、ドイツ (8)1990年(セッション)/エッシュシュルアルゼット劇場、ルクセンブルク【原盤:SEL(1990)】 (9)2001年5月11日(ライヴ)、(13)1995年4月23日(ライヴ)/エヒテルナハ聖堂、ルクセンブルク (10)1993年(セッション)/ベットボーン、ルクセンブルク【原盤:SEL(1993)】 (11)1997年1月26日(ライヴ)/マルベルク、ルクセンブルク (12)2003年6月1日(ライヴ)/ハーゲンオーセン、ドイツ (14)2007年11月11日(ライヴ)/キューブ521、マルナッハ、ルクセンブルク (15)(16)1993年(セッション)/コンサート・スタジオ、ケルン、ドイツ【原盤:AUROPHON (1993)】 (17)1998年9月&12月(セッション)/ケルン・クントハウス、ドイツ【原盤:CAPRICCIO 10794】 (18)(21)2005年(セッション)/ドイチュラントラジオ・クルトゥーア、ベルリン、ドイツ【Profil PH-05019(2005)】 (19)2005年8月(ライヴ)/カンブレー劇場、フランス (20)2001年8月(セッション)/チューリヒ放送、スイス【原盤:ECM 1793】 |
|
||
| DOREMI DHR-8173(2CDR) |
マルタ・アルゲリッチLIVE第6集 (1)ショパン:ピアノ協奏曲第1番ホ短調 Op.11 (2)ショパン:ピアノ協奏曲第2番へ短調 Op.21 (3)モーツァルト:ピアノ・ソナタ ニ長調 K.576 (4)バッハ:パルティータ第2番ハ短調 BWV826 シューマン:ピアノ・ソナタ第2番ト短調 Op.22 ラヴェル:夜のガスパール プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第7番変ロ長調 Op.83 |
マルタ・アルゲリッチ(P) (1)岩城宏之(指)オランダ放送PO 録音:1968年10月19日アムステルダム (2)ヴァーツラフ・ノイマン(指)北ドイツRSO 録音:1969年3月3日ハンブルク (3)録音:1960年1月30日ミュンヘン (4)録音:1971年10月13日ブダペスト |
|
||
| MDG MDG-90122306(1SACD) |
エゴン・ガブラー(1876-1959):コンチェルト集 ホルン協奏曲変ロ長調(22'50) クラリネットのための演奏会用小品(14'33) クラリネット協奏曲第3番ニ短調(24'01) |
ロベルト・ラング バイン(Hrn) フリーデリケ・ロート(Cl) バーデン=バーデンPO パヴェル・バレフ(指) 録音:2021年3月16-20日、クアハウス・バーデン・バーデン、ヴァインブレナーホール |
|
||
| DOREMI DHR-8171(2CDR) |
レオン・フライシャーLIVE 第3集 (1)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 Op.15 (2)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 Op.19 (3)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 Op.37 (4)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番 ト長調 Op.58 (5)レオン・キルヒナー:ピアノ協奏曲第2番 |
レオン・フライシャー(P) (1)ジョージ・セル(指)NYO ライヴ録音:1963年3月14日リンカーン・センター、フィルハーモニックホール (2)ハンス・ロスバウト(指)ケルンRSO 放送用ライヴ録音:1957年11月18日 (3)フレデリック・ワルトマン(指)ムジカ・エテルナO ライヴ録音:1964年11月22日ニューヨーク (4)オットー・クレンペラー(指)ケルンRSO 放送用ライヴ録音:1956年2月27日 (5)レオン・キルヒナー(指)NYO ライヴ録音:1964年12月3日リンカーン・センター、フィルハーモニックホール |
|
||
| APARTE AP-291(1CD) |
18世紀ヴァイオリン協奏曲集 ベンダ:ヴァイオリン協奏曲イ長調L2.13 グラウン:ヴァイオリン協奏曲ハ短調GraunWV Av:ⅩⅡ:18 サン=ジョルジュ:ヴァイオリン協奏曲ニ長調 マッダレーナ・ロンバルディーニ=ジルメン:ヴァイオリン協奏曲第1番変ロ長調Op.3 モーツァルト:ロンド ハ長調K.373 |
ゼフィーラ・ヴァロヴァ(Vnと指) イル・ポモドーロ 録音:2021年2月/ヴィラ・サン=フェルモ(ロニーゴ) |
|
||
| Pentatone PTC-5186949 (1SACD) |
(1)ラヴェル:ピアノ協奏曲 ト長調(1932) (2)メシアン:「異国の鳥たち」(1956) (3)シェーンベルク:ピアノ協奏曲 Op.42(1942) |
フランチェスコ・ピエモンテージ(P) スイス・ロマンドO、 ジョナサン・ノット(指) 録音:(1)2020年11月、(2)2020年12月、(3)2021年2月 ヴィクトリア・ホ ー ル(ジュネーヴ ) |
|
||
| Pentatone PTC-5186966(1CD) |
バッハ:チェンバロ協奏曲集第3集 (1)2台のチェンバロのための協奏曲第3番ハ短調 BWV1062 (2)2台のチェンバロのための協奏曲第2番ハ長調 BWV1061 (3)チェンバロ、オーボエと弦楽のための協奏曲 ニ短調 BWV1059(フランチェスコ・コルティによる再構成版) (4)2台のチェンバロのための協奏曲第1番ハ短調 BWV1060 |
フランチェスコ・コルティ(Cemb独奏:BWV1059、第1チェンバロ:BWV1060-1062) (1)(2)(4)アンドレア・ブッカレッラ(第2チェンバロ) (3)エマニュエル・ラポルト(Ob) イル・ポモ・ドーロ【エフゲニー・スヴィリドフ(Vn1)、アンナ・ドミトリエヴァ(Vn2)、ステファノ・マルコッキ(Va)、キャサリン・ジョーンズ(Vc)、パオロ・ズッケリ(ヴィオローネ)】 録音:2021年4月17-21日/ヴィッラ・サン・フェルモ、ロニゴ(イタリア) |
|
||
| Ars Produktion ARS-38329(1SACD) |
モザイク ギィ=クロード・ルイパルツ:二重協奏曲第4番(フルートとハープのための)#、 ほおずき(ナサニエル・キャレ編/ピアノと管弦楽版)+、 古典協奏曲(Pと管弦楽のための)*、 ゴレ(P・ソロのための)$、 アダージョ(弦楽オーケストラのための)Ψ |
ギィ=クロード・ルイパルツ(Fl、指)#+*Ψ、 アンヌ=ソフィー・ベルトラン(Hp)#、 パスカル・ジャンドロ(指)#、 ナサニエル・キャレ(指)+、 ジャン・デュベ(P)*$、 フォクトラントPO 録音:2021年7月5日-8日 |
|
||
| ONDINE ODE-1403(1CD) NX-B07 |
ジブオクレ・マルティナイティーテ(1973-):
作品集 ぎ行く今、残る今(2020)- パーカッションと弦楽オーケストラのための 闇から光へ(2021)- 弦楽オーケストラのための 心の原風景(2019)- チェロと弦楽オーケストラのための |
パヴェル・ギュンテル(パーカッション) ロカス・ヴァイトケヴィチウス(Vc) リトアニア室内O カロリス・ヴァリアコイス(指) 録音:2021年6月8-12日 |
|
||
| PREISER PRCD-91557(1CD) |
モーツァルト:ホルン協奏曲集(室内楽版) 変ホ長調 K.417 変ホ長調 K.495 変ホ長調 K.447 ニ長調 K.412(2021年補完版) |
ペーター・ドルフマイヤ ー(Hrn) ウィーンSOのメンバー |
|
||
| DOREMI DHR-8163(2CDR) |
ブロニスラフ・ギンペルLive 第1集 (1)ラロ:スペイン交響曲~第1楽章 サラサーテ:マラゲーニャ イ長調 Op.21-1 (2)ヴィエニャフスキ:スケルツォ・タランテラ Op.16 サラサーテ:ホタ・ナバーラ Op.22-2 パガニーニ(アウアー編):カプリース第24番イ短調 (3)サラサーテ:ツィゴイネルワイゼン (4)クライスラー:中国の太鼓 プニャーニの様式による前奏曲とアレグロ (5)ディニク:ホラ・スタッカート (6)シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 (7)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番 (8)グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲 |
ブロニスラフ・ギンペル(Vn) (1)ブロニスラフ・ギンペル(指)ABCコンサート・オーケストラ 録音:1949年頃(放送用ライヴ) (2)リチャード・ベックマン(P) 録音:1953年8月29日(放送用ライヴ) (3)マルティン・クラウゼ(P) 録音:1955年2月13日(放送用ライヴ) (4)カロル・ギンペル(P) 録音:1930年代(放送用ライヴ) (5)ピアニスト不明 録音:1930年代(放送用ライヴ) (6)オイゲン・ヨッフム(指)、BPO 録音:1956年4月21日(放送用ライヴ) (7)ロベルト・ベンツィ(指)西ドイツRSO 録音:1967年頃(放送用ライヴ) (8)ジョセフ・ステパル(指)ABCコンサート・オーケストラ 録音:1949年頃(放送用ライヴ) |
|
||
| NIFC NIFCCD-078(1CD) PNIFCCD-078(1CD) 国内盤仕様 税込定価 |
ヴィエニャフスキ:ヴァイオリン協奏曲第2番# ドブジンスキ:演奏会用序曲 Op.1 クルピンスキ:クラリネット協奏曲 変ロ長調(1823)+ ドブジンスキ:交響曲第2番 ハ短調 「性格的」 Op.15(1831) |
18世紀オーケストラ、 アリョーナ・バーエワ(Vn)#、 エリック・ホープリッチ(Cl)+、 ホセ・マリア・フロレンシオ(指) 録音:2018年9月7日-9日、コンサート・ホール、クシシュトフ・ペンデレツキ・ヨーロッパ音楽センター(ルスワビツェ、ポーランド) |
|
||
| Diapason DIAP-144(1CD) |
グリーグ:作品集 (1)ピアノ協奏曲 イ短調 Op.16 (2)管弦楽伴奏付き歌曲集(最初の出会い Op.21-1 春 Op.33-2/若者 Op.33-1 ルンダルネにて Op.33-9 到着点 Op.33-12 モンテ・ピンチョから Op.39-1 希望 Op.26-1/白鳥 Op.25-2 エロス Op.70-1/君を愛す Op.5-3 (3)ピアノのための3つの小品(恋の曲 Op.43-5 ヨルスターの踊り Op.17-5 ゆりかごの歌 Op.68-5) |
(1)クリフォード・カーゾン(P)、LSO、エイフィン・フィエルスター(指) 録音:1959年 (2)キルステン・フラグスタート(S)、BBC響、マルコム・サージェント(指) 録音:1957年 (3)アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(P) 録音:1940年-1941年 |
|
||
| CALLIOPE CAL-2197(1CD) |
ショスタコーヴィチ&チャイコフスキー ショスタコーヴィチ:チェロ協奏曲第1番(Vc・アンサンブル版) チャイコフスキー:ロココ風の主題による変奏曲(Vc・アンサンブル版) |
クセニア・ヤンコヴィチ(Vc)、 アンサンブル・インスピリムス 録音:2021年7月8日-10日、マルティン・ルター教会(デトモルト、ドイツ) |
|
||
| MELO CLASSIC MC-1058(2CD) |
アレグザンダー・ユニンスキー/ピアノ欧州楽旅1951-1962年 (1)ショパン:ピアノ協奏曲第1番ホ短調Op.11 (2)ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 (3)ショパン:ピアノ・ソナタ第2番変ロ短調Op.35 (4)プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第3番ハ長調Op.26 (5)バッハ:パルティータ第2番ハ短調BWV826 (6)シューマン:謝肉祭Op.9 ラヴェル:夜のガスパール~オンディーヌ |
アレグザンダー・ユニンスキー(P) (1)カール・メレス(指)RTL響 録音:1958年11月19日ベルギールクセンブルク放送スタジオ(モノラル) (2)ヴィリ・シュタイナー(指)NDRハノーファーSO 録音:1961年4月11日西ドイツハノーファー放送スタジオ(モノラル) (3)録音:1961年4月10日西ドイツハノーファー放送スタジオ(モノラル) (4)アンドレ・リュー・シニア(指)リンブルフSO 録音:1951年6月29日オランダマーストリヒト放送スタジオ(モノラル) (5)録音:1961年4月16日西ドイツミュンヘン放送スタジオ(モノラル) (6)録音:1962年2月15日フランスパリ放送スタジオ(モノラル) |
|
||
| MELO CLASSIC MC-1060(2CD) |
ハリーナ・チェルニー=ステファンスカ/ドイツでの楽旅1958-1971年 (1)リスト:ピアノ協奏曲第1番変ホ長調 (2)グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調Op.16 (3)メンデルスゾーン:ピアノ協奏曲第1番ト短調Op.25 (4)ショパン:夜想曲ホ短調Op.72-1/ワルツロ短調Op.69-2/前奏曲変イ長調Op.28-17 (5)ショパン:ピアノ協奏曲第1番ホ短調Op.11 (6)ラモー:サラバンド/ガヴォット/タンブーラン/鳥の囀り/優しい訴え/メヌエット/雌鶏 D.スカルラッティ:ソナタニ短調K.9/ソナタニ長調K.430/ソナタハ長調K.159 マチェイェフスキ:三連作 |
ハリーナ・チェルニー=ステファンスカ(P) (1)ハインツ・フリッケ(指)シュターツカペレ・ベルリン 録音:1964年6月3日東ドイツベルリン放送スタジオ(モノラル) (2)オタカール・トルフリク(指)ベルリンRSO 録音:1962年4月7-8日東ドイツベルリン放送スタジオ(モノラル) (3)ハンス・シュミット=イッセルシュテット(指)NDRSO 録音:1963年2月24-25日西ドイツハンブルク放送スタジオ(モノラル) (4)録音:1958年9月25日西ドイツハノーファー放送スタジオ(モノラル) (5)ロルフ・クライネルト(指)ベルリンRSO 録音:1971年2月4-5日東ドイツベルリン放送スタジオ(モノラル) (6)録音:1963年2月27日西ドイツハンブルク放送スタジオ(モノラル) |
|
||
| MELO CLASSIC MC-1063(2CD) |
伝説的なポーランドのピアニストたち/ドイツでの演奏会1949-1959年 (1)ショパン:ピアノ協奏曲第1番ホ短調Op.11 (2)ショパン:ピアノ協奏曲第2番ヘ短調Op.21 (3)チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番変ロ短調Op.23 (4)プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第3番ハ長調Op.26 |
(1)バルバラ・ヘッセ=ブコフスカ(P) ヘルマン・アーベントロート(指)ベルリンRSO 録音:1955年2月20日東ドイツベルリン放送スタジオ(モノラル) (2ヘンリク・シュトンプカ(P) ヘルマン・アーベントロート(指)ライプツィヒRSO 録音:1952年5月5日東ドイツライプツィヒ放送スタジオ(モノラル) (3)マリアン・フィラー(P) ヴィンフリート・ツィリヒ(指)フランクフルトRSO 録音:1949年2月16日西ドイツフランクフルト放送スタジオ(モノラル) (4)レギナ・スメンジャンカ(P) ヘルベルト・ケーゲル(指)ライプツィヒRSO 録音:1959年4月20日東ドイツライプツィヒ放送スタジオ(モノラル) |
|
||
| MELO CLASSIC MC-2049(2CD) |
クリスティアン・フェラス/ヨーロッパでの楽旅1961-1974年 (1)ラロ:スペイン交響曲ニ短調Op.21(第3楽章省略) (2)メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調Op.64 (3)ショーソン:詩曲 (4)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調K.218 (5)バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第3番~ガヴォット・アン・ロンドー (6)ロベール・ド・フラニ:ダヌビアナ (7)ラヴェル:ツィガーヌ (8)シェーンベルク:ヴァイオリン協奏曲Op.36 |
クリスティアン・フェラス(Vn) (1)ルイ・ド・フロマン(指)RTLO(ルクセンブルクRSO) 録音:1961年3月22日ベルギールクセンブルク放送スタジオ(モノラル) (2)ボゴ・レスコヴィチ(指)WDRSO放送スタジオ録音 録音:1964年4月29日西ドイツケルン放送スタジオ(モノラル) (3)ジャン・クロード・アルトマン(指)ORTFリリックO 録音:1969年5月9日フランスパリ放送スタジオ(ステレオ) (4)ヘルムート・ミュラー=ブリュール(指)ケルン室内O (5)録音:1968年8月3日フランスマントンライヴ(モノラル) (6)ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴス(指)ORTF国立O 録音:1964年9月9日フランスブザンソンライヴ(モノラル) (7)ジャン・クロード・アルトマン(指)ORTFリリックO 録音:1969年5月16日フランスパリ放送スタジオ(ステレオ) (8)ミルティアデス・カリディス(指)ORFSO 録音:1974年オーストリアグラーツライヴ(モノラル) |
|
||
| MELO CLASSIC MC-2050(2CD) |
伝説的なソヴィエト連邦のヴァイオリニストたちヨーロッパでの楽旅1961-1974年 (1)ヴィエニャフスキ:ヴァイオリン協奏曲第1番嬰ヘ短調Op.14 (2)プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲第2番ト短調Op.63 (3)ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第3番ニ短調Op.108 ハチャトゥリアン:詩曲 ハチャトゥリアン(ハイフェッツ編):アイシャの踊り,剣の舞(「ガイーヌ」から) (4)ヘンデル:ヴァイオリン・ソナタホ長調Op.1-15HWV373 (5)カバレフスキー:ヴァイオリン協奏曲ハ長調Op.48 (6)パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第2番ロ短調Op.7 |
(1)ボリス・ゴリトシテイン(Vn) ズデネク・マーツァル(指)NDRハノーファー放送O 録音:1975年6月6日西ドイツハノーファーライヴ(ステレオ) (2)ボリス・ゴリトシテイン(Vn) ユーリ・アーロノヴィチ(指)NDR響 録音:1976年10月8日西ドイツハノーファーライヴ(ステレオ) (3)ボリス・ゴリトシテイン(Vn)、シシュティ・ヨルト(P) 録音:1977年6月3日西ドイツハノーファー放送スタジオ(ステレオ) (4イーゴリ・ベズロドニー(Vn)、フセヴォロド・ペトルシャンスキー(P) 録音:1968年6月8日東ドイツライプツィヒライヴ(モノラル) (5)イーゴリ・ベズロドニー(Vn) キリル・コンドラシン(指)ベルリンRSO 録音:1950年7月24日東ドイツベルリンライヴ(モノラル) (6)ユリアン・シトコヴェツキー(Vn) フランツ・ユング(指)ライプツィヒRSO 録音:1955年12月17日東ドイツライプツィヒ放送スタジオ(モノラル) |
|
||
| MELO CLASSIC MC-2051(2CD) |
ミハイル・ヴァイマン東ドイツでの演奏会1951-1963年 (1)チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.35 (2)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調K.219 (3)バッハ:ヴァイオリン協奏曲ホ長調BWV1042 (4)マチャヴァリアニ:ヴァイオリン協奏曲 (5)プロコフィエフ:ヴァイオリン・ソナタ第1番ヘ短調Op.80 バルトーク(Szekely編):ルーマニア民俗舞曲 ヴィヴァルディ:前奏曲ハ短調 バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番ト短調BWV1001 |
ミハイル・ヴァイマン(Vn) (1)ロルフ・クライネルト(指)ベルリンRSO 録音:1957年5月20日東ドイツベルリン放送スタジオ(モノラル) (2)ヘルマン・アーベントロート(指)ベルリンRSO 録音:1955年5月15日東ドイツベルリンライヴ(モノラル) (3)カール・エリアスベルク(指)ライプツィヒRSO 録音:1950年7月29日東ドイツライプツィヒライヴ(モノラル) (4)フランツ・コンヴィチュニー(指)ライプツィヒ・ゲヴァントハウスO 録音:1951年11月27日東ドイツライプツィヒライヴ(モノラル) (5)マリア・カランダショヴァ(P) 録音:1963年10月30日東ドイツベルリンライヴ(モノラル) |
|
||
| ODRADEK RECORDS ODRCD-413(1CD) |
ブラームス・ザ・プログレッシヴVol.2 ウェーベルン:9楽器のための協奏曲Op.24(1934) ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 |
ピナ・ナポリターノ(P) モデスタス・ピトレナス(指)リトアニア国立SO 録音:2021年6月10-11日リトアニア・ナショナル・フィルハーモニック・ホール、ヴィリニス ※日本語オビ・解説付き |
|
||
| Forgotten Records fr-1823(1CDR) |
カンポーリ~協奏曲録音集 ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲# |
アルフレッド・カンポーリ(Vn) ジョン・プリッチャード(指)ロイヤルPO アタウルフォ・アルヘンタ(指)LSO # 録音:1961年8月10日-12日、 EMI アビー・ロード第1スタジオ、ロンドン/1956年12月27日-28日、キングズウェイ・ホール#、ともにロンドン、ステレオ ※音源:HMV SXLP 20043、、 Decca SXL 2029 #他 |
| Forgotten Records fr-1822(1CDR) |
サイエ、パウムガルトナー~モーツァルト: オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314* ディヴェルティメント集【第12番変ホ長調 K.252/第13番ヘ長調 K.253/第14番変ホ長調 K.270/第16番変ホ長調 K.289]# |
マルセル・サイエ(Ob)* ベルンハルト・パウムガルトナー(指) ザルツブルク・モーツァルテウム・カメラータ・アカデミカ*、 ウィーンSO 木管アンサンブル# 録音:1950年*、953年12月10日-13日、ウィーン# ※音源:Period SPLP 519*、 Philips A 00211 L # |
| Forgotten Records fr-1824(1CDR) |
ブロニスワフ・ギンペル~協奏曲録音集 ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲 イ短調 Op.53+ ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調 Op.26* |
ブロニスワフ・ギンペル(Vn) ロルフ・ラインハルト(指) バーデン=バーデン南西ドイツ放送O 録音:1957年1月 ※音源:Opera Pantheon XP 2930+、XP 3060* |
| Forgotten Records fr-1827(1CDR) |
ウェーバー:クラリネット協奏曲第1番* ファゴット協奏曲 ヘ長調 Op.75#、 ピアノとクラリネットの為の変奏曲 Op.33+ |
ジャック・ランスロ(Cl) ポール・オンニュ(Fg)# ルイ・ド・フロマン(指) オワゾリール・アンサンブルO* アニー・ダルコ(P)+ 録音:1955年 ※音源:L'Oiseau-Lyre OL-LD 69、OL 50105 |
| Forgotten Records fr-1835(1CDR) |
ラロ:スペイン交響曲 (4楽章版)* フランク(ピエルネ編):前奏曲,コラールとフーガ# ラヴェル:道化師の朝の歌 「マ・メール・ロワ」組曲 |
ベティ=ジーン・ヘイガン(Vn)* ディミトリ・ミトロプーロス(指) NYO 録音:1950年11月26日、1951年10月28日#、1956年11月4日*、すべてカーネギー・ホール(放送用録音) |
| Indesens INDE-160(1CD) |
ローラン・ルフランソワ(b.1974):木管楽器のための協奏曲集 クラリネットと管弦楽のための協奏曲* シギリージャ~フルートと弦楽オーケストラのための Le nouveau Balneaire~管弦楽のための E♭クラリネットと弦楽オーケストラのための協奏曲** |
ポール・メイエ(Cl)*、 マガリ・モニエ(Fl)、 ピエール・ジェニソン(Cl)**、 ジャン=フランソワ・ヴェルディエ(指)、 ヴィクトル・ユーゴ・フランシュ=コンテO 録音:2020年12月17日-19日(フランス) |
|
||
| Indesens INDE-159(1CD) |
プロクラメーション~近現代のトランペット協奏曲集 ブロッホ:プロクラメーション アルチュニアン(1920-2012):トランペット協奏曲変イ長調 ジャック・エテュ(1938-2010):トランペット協奏曲 Op.45 ジョン・エスタシオ(b.1966):トランペット協奏曲(世界初録音) |
マルク・グージョン(Tp) ミュルーズSO、 ジャック・ラコンブ(指) ※使用楽器:Schilke SC4-MG(ブロッホ、エテュ、エスタシオ)、Schilke SB4-MG(アルチュニアン) 録音:2020年9月、ラ・フィラチュール(ミュルーズ、フランス) |
|
||
| Hyperion CDA-68389(1CD) |
ロマンティック・ピアノ・コンチェルト・シリーズ
Vol.84~アロイス・シュミット(1788-1866)::ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲第1番ハ短調 Op.14 ピアノ協奏曲第2番ニ短調 Op.34 華麗なるロンド Op.101 |
ハワード・シェリー(P&指)、 アルスターO 録音:2021年6月15日-17日、ウォーターフロント・ホール(ベルファスト) |
|
||
| Forgotten Records fr-1811(1CDR) |
ハイドン、ヴィヴァルディ、テレマン:協奏曲集 ハイドン:チェロ協奏曲 二長調 Op.101Hob.VIIb:2* ヴィヴァルディ:チェロ協奏曲 ハ短調 RV.401* テレマン:オーボエ協奏曲 ヘ短調# C.P.E.バッハ:オーボエ・ソナタ ト短調+ |
エアリング・ブロンダール・ベンクトソン(Vc)* ヴァルデマ・ヴォルシング(Ob;#/+) アルベルト・メディチ(Vc)+ モーエンス・ヴェルディケ(Cemb+,指) デンマーク放送室内O 録音:1956年5月12日-14日*、1956年10月12日#、1957年2月15日+ ※音源:HMV ALP 1501* XLP 30039* 他 |
| Forgotten Records fr-1812(1CDR) |
ヴィヴァルディ:協奏曲集 室内協奏曲 ト短調 RV.104「夜」 協奏曲 変ロ長調 RV.579「葬送」 合奏協奏曲 ハ長調 RV.555 合奏協奏曲 ハ長調 RV.569 2つのヴァイオリンの為の協奏曲 ハ短調 RV.510 # ヴァイオリン協奏曲 ト短調 RV.155# |
グイード・ノヴェッロ(Fl) レーノ・ファントゥッツィ(Vn) アンジェロ・エフリキアン(指) ヴェネツィア楽派室内O 録音:1950年#、1952年(#以外) ※音源:Stradivari Records STR-621他 |
| Forgotten Records fr-1815(1CDR) |
マシューズ&ジュスキントのベートーヴェン: ピアノ協奏曲第5番「皇帝」* ピアノ・ソナタ第17番「テンペスト」# |
デニス・マシューズ(P) ウォルター・ジュスキント(指)* フィルハーモニアO* 録音:1947年4月24日* 、1955年6月2日-3日# ※音源:Columbia RL-3037(US) * SX 10470 # |
| Forgotten Records fr-1818(1CDR) |
エドワード・キレニー モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番* リスト:ピアノ協奏曲第1番# ハンガリー幻想曲 + 死の舞踏 S.126# |
エドワード・キレニー(P) パウル・ワルター(指)ザルツブルク・モーツァルテウムO* ヨネル・ペルレア(指)ベルリン RIAS 響# フェリクス・プロハスカ(指)オーストリアSO+ 録音:1951年* 、1951年4月10日-11日、30日#、1953年8月、10月+ ※音源:Remington R-199-61、R-199-166 |
| Forgotten Records fr-1819(1CDR) |
ブラームス:ピアノ協奏曲第1番二短調 Op.15 | フリードリヒ・ヴューラー(P) ジョルジュ・セバスティアン(指) フランス国立放送O 録音:1961年2月26日、パリ(放送用録音) |
| ICA CLASSICS ICAC-5166(1CD) NX-B03 |
ハスキル、カラヤンのモーツァルト ピアノ協奏曲 第20番ニ短調 K. 466 交響曲第39番変ホ長調 K. 543 デュポールのメヌエットによる9つの変奏曲 K. 573* |
クララ・ハスキル(P) フィルハーモニアO ヘルベルト・フォン・カラヤン(指) 録音(ライヴ/モノラル/拍手入り):1956年1月28日 モーツァルテウム大ホール、ザルツブルク 1956年9月7日 ブザンソン音楽祭* |
|
||
| ALBANY TROY-1889(1CD) |
ダニエル・パルコフスキの音楽 (1)「夏の組曲」~ピアノのための (2)「さやえんどう」~中国琵琶のための (3)カノン的ベクトル (4)ピアノと室内管弦楽のためのコンチェルティーノ |
(1)(3)シリン・シー(P) (2)ウ・マン(中国琵琶) (4)エレーナ・アタナソフスカ(P) オレグ・コントラテンコ(指) F.A.M.E.スタジオO |
|
||
| CPO CPO-555461(1CD) NX-B10 |
ヴィヴァルディ:四季 Op.8(カルロス・ピノ=キンタナによる編曲) リュート,2つのヴァイオリンと通奏低音のための協奏曲 ニ長調 RV 93 |
アンドレーア・チラ(パンフルート) プフォルツハイム南西ドイツ室内O ダグラス・ボストック(指) 録音:2020年10月28-31日 |
|
||
| Profil PH-21039(2CD) |
グリーグとエネスコ ■Disc1 (1)グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調Op.16 (2)エネスコ:ピアノ協奏曲ニ短調(未完) (3)グリーグ:叙情小曲集~アリエッタOp.12の1/ノルウェーの旋律Op.12の6/民謡Op.38の2/蝶々Op.43の1/愛の歌Op.43の5/ハリングOp.47の4/跳びはね踊りOp.47の6/ノルウェーの農民行進曲Op.54の2/トロールの行進Op.54の3 ■Disc2 (1)グリーグ:叙情小曲集~夜想曲Op.54の4/過ぎ去った日々Op.57の1/郷愁Op.57の6/サロンOp.65の4/トロルドハウゲンの婚礼の日Op.65の6/あなたのおそばでOp.68の3/小妖精Op.71の3/ハリング Op.71の5 (2)エネスコ:ピアノ・ソナタ第3番ニ長調Op.24の3 (3)同:即興小品集Op.18~コラール/カリヨン・ノクチュルヌ |
ルイザ・ボラク(P) ニコラエ・モルドヴェアヌ(指)ブカレスト国立放送O(Disc1(1)(2)) 録音:2019年6月25-27日ブカレスト放送(Disc1(1)(2))、 2007年1月11日、6月29日ブレーメン放送(ライヴ)(Disc1(3), Disc2(1)(2))、 2003年6月1日ヴァイセナウ修道院広間(ライヴ)(Disc2(3))、 2004年10月25日シュタットシアター・リンダウ(ライヴ)(Disc2(1)の夜想曲のみ) |
|
||
| Hanssler HC-21042(1CD) |
シュルホフ:作品集 (1)ピアノ協奏曲 Op.11 (2)「町人貴族 |
ミヒャエル・リシェ(P) (1)イスラエル・イノン(指) ケルンWDRSO、 (2)ゲルト・アルブレヒト(指)ベルリン・ドイツSO、 録音:(1)1998年10月20-22日ケルン・フィルハーモニー (2)1999年11月21&22日イエス・キリスト教会(ベルリン) |
|
||
| Biddulph BIDD-85014(1CD) |
モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調 K. 216(カデンツァ:オスカー・シュムスキー) 協奏交響曲 変ホ長調 K. 364 |
オスカー・シュムスキー(Vn) エリック・シュムスキー(Va) スコットランド室内O ヤン・パスカル・トルトゥリエ(指) 録音:1985年1月13日&14日エジンバラ、クイーンズホール(UK) |
|
||
| Lyrita SRCD.407(1CDR) |
イギリスのピアノ協奏曲集 ジョン・アディスン(1920-98):ウェリントン組曲(1959) アーサー・ベンジャミン(1893-1960):ピアノとオーケストラのためのコンチェルティーノ(1927) エリザベス・マコンキー(1907-94):ピアノと弦楽合奏のためのコンチェルティーノ(1949) ハンフリー・サール(1915-82):ピアノ、パーカッションと弦楽のためのコンチェルタンテ(1954) エドマンド・ラッブラ(1901-86):自然の歌(1920) ジェフリー・ブッシュ(1920-98):トマス・アーンの主題によるピアノと弦楽のための小協奏曲(1939) |
サイモン・キャラハン(P) BBCウェールズ・ナショナルO、 マーティン・ブラビンズ(指) 録音:2021年6月29日-30日、ホディノット・ホール、カーディフ(イギリス) |
|
||
| RUBICON RCD-1057(1CD) |
リスト:ピアノ協奏曲第1番変ホ長調 S.124 ピアノ協奏曲第2番イ長調 S.125 ピアノ・ソナタ ロ短調 S.178 |
アレグザンダー・ウルマン(P) 、アンドルー・リットン(指)、 BBC響 |
|
||
| TRPTK TTK-0088(1SACD) |
レンブラント・フレリフス:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲第1番 ピアノ協奏曲第2番 「エターナル・ヴァリエイティング・オルタネイションズ」 |
レンブラント・フレリフス(P)、マルク・ダニエル・ファン・ビーメン(Vn1)、ベンジャミン・ペレド(Vn2)、イェルン・ヴァウトストラ(Va)、クレモン・ペニエ(Vc)、ドミニク・セルディス(Cb)、フィンセント・プラニエル(パーカッション) 録音:2021年12月10日-11日、ベツレヘム教会スタジオ150(アムステルダム) |
|
||
| BISCOITO FINO BC-251(1CD) |
ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104 ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番* |
アントニオ・メネセス(Vc) クラウディオ・クルス(Vn) ジョン・ネシリング(指)サンパウロSO 録音:2008年6月、 2008年10月*/文化芸術劇場(サンパウロ) |
|
||
| BISCOITO FINO BC-249(1CD) |
(1)ハイミ:ギター協奏曲 (2)アイレス:パーカッション協奏曲 |
(1)ファビオ・ザノン(G)、 アロンドラ・デ・ラ・パーラ(指)サンパウロSO (2)エリザベス・デル・グランデ、リカルド・ボローニャ、リカルド・リギーニ、アルフレド・リマ、アルマンド・ヤマダ、エドゥアルド・ヒアネセッラ(パーカッション)、ジョン・ネシリング(指)、サンパウロSO 録音:(2)2008年12月、(2) 2009年11月/文化芸術劇場(サンパウロ) |
|
||
| BIS BIS-2303(1CD) |
イェ・シャオガン(1955-):作品集 (1)交響的絵画「四川の映像(Sichuan Image)」Op.70~オーケストラのための(2013-14) (2)「命の協奏曲(Concerto of Life)」Op.23c~ピアノとオーケストラのための (2000) |
(1)シュエ・ヤン【楊雪】(二胡&中胡)、ユエ・リー【李楽】(笛&簫(ショウ))、ヤン・ジン【楊静】(中国琵琶)、レイ・ワン【王磊】(笙)
(2)小川典子(P) ロイヤル・スコティッシュ・ナショナルO ホセ・セレブリエール(指) 録音:2018年8月21-25日/RSNOセンター(グラスゴー、イギリス) |
|
||
| BIS BISSA-2523(1SACD) |
フランスのトランペット協奏曲集 トマジ:トランペット協奏曲(1944)(フランク・ヴィラール復元によるオリジナル版)【世界初録音】 ジョリヴェ:トランペット、弦楽とピアノのコンチェルティーノ(1948) シュミット:ランペットとオーケストラのための組曲 Op.133(1955) ジョラス:11の歌(1977)【カデンツァ:ホーカン・ハーデンベルガー】 ジョリヴェ:トランペット協奏曲第2番(1954) |
ホーカン・ハーデンベルガー(Tp) ロイヤル・ストックホルムPO、 ファビアン・ガベル(指) 録音:2021年8月23-27日/ストックホルム・コンサートホール(スウェーデン) |
|
||
| BIS BISSA-2504(1SACD) |
ヨハン・ヴィルヘルム・ヴィルムス(1772-1847):ピアノ協奏曲集
Vol.1 (1)協奏曲 ホ長調 Op.3~ピアノ(またはチェンバロ)とオーケストラのための (2)協奏曲 ハ長調 Op.12~ピアノとオーケストラのための (3)協奏曲 ニ長調 Op.26~ピアノとオーケストラのための |
ロナルド・ブラウティハム(フォルテピアノ)
マイケル・アレクサンダー・ウィレンス(指) ケルン・アカデミー 録音:(1)(3)2021年4月&5月、(2)2021年8月/イムマヌエル教会、ヴッパータール(ドイツ) |
|
||
| Pentatone PTC-5187005(1CD) |
チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 憂鬱なセレナード Op.26 ワルツ=スケルツォ Op.34 なつかしい土地の思い出 Op.42 |
ユリア・フィッシャー(Vn) ロシア・ナショナルO、 ヤコフ・クライツベルク(指、P) 録音:2006年4月 |
|
||
| H.M.F HMM-902612(1CD) |
ラヴェル:ピアノ協奏曲と歌曲 (1)ピアノ協奏曲ト長調 (2)ドゥルシネア姫に思いを寄せるドン・キホーテ(全3曲) (3)2つのヘブライの歌 (4)なき王女のためのパヴァーヌ(P版) (5)マラルメの3つの詩 (6)左手のためのピアノ協奏曲 (7)聖女 |
セドリック・ティベルギアン(P;1892年製プレイエル・グランパトロン)
ステファーヌ・ドグー(Br)(2)(3)(5)(7) フランソワ=グザヴィエ・ロト(指) レ・シエクル 録音:2020年12月ピエール・ブーレーズ大ホール(1)(6)、 2021年9月フィラルモニ・ド・パリ(2)(3)(5)(7)、スタジオ(4) |
|
||
| KLARTHE KLA-012(1CD) |
『四季』の創世記 ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集『和声と創意の試み』Op.8より ヴァイオリン協奏曲第1番~第4番『四季』 (1)ヴァイオリン協奏曲第1番ホ長調 Op.8-1 RV 269「春」* (2)ヴァイオリン協奏曲第2番ト短調 Op.8-2RV 315「夏」* (3)ヴァイオリン協奏曲第3番ヘ長調 Op.8-3RV 293「秋」* (4)ヴァイオリン協奏曲第4番ヘ短調 Op.8-4RV 297「冬」* (5)ヴァイオリン協奏曲第1番ホ長調 Op.8-1 RV 269「春」 (6)ヴァイオリン協奏曲第2番ト短調 Op.8-2RV 315「夏」 (7)ヴァイオリン協奏曲第3番ヘ長調 Op.8-3RV 293「秋」 (8)ヴァイオリン協奏曲第4番ヘ短調 Op.8-4RV 297「冬」 *=朗読付 |
(1)-(4)ネルソン・モンフォー(朗読) ジル・コリャール(Vn&指揮)、 バルセロナ・バロックO 録音:2015年5月サン=エスプリ教会(バルセロナ) |
|
||
| Naive OP-7367(2CD) |
VIVALDI BACH「調和の霊感」全曲&バッハによる編曲6作 [CD1] 1-3. ヴィヴァルディ:4つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ長調 RV 549(「調和の霊感」第1番) [4つのヴァイオリン・ソロ:アンドレア・ロニョーニ、ステファノ・バルネスキ、ボリス・ベゲルマン、エリザ・チッテリオ] 4-7. ヴィヴァルディ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ト短調 RV 578(「調和の霊感」第2番) [2つのヴァイオリン・ソロ:ステファノ・バルネスキ、ボリス・ベゲルマン] 8-10. ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲 ト長調 RV 310(「調和の霊感」第3番) [ヴァイオリン・ソロ:ステファノ・バルネスキ] 11-13. バッハ:チェンバロ協奏曲 ヘ長調BWV 978(原曲:RV 310) [チェンバロ:リナルド・アレッサンドリーニ] 14-16. ヴィヴァルディ:4つのヴァイオリンのための協奏曲 ロ短調 RV 580(「調和の霊感」第10番) [4つのヴァイオリン:ボリス・ベゲルマン、エリザ・チッテリオ、アンドレア・ロニョーニ、ステファノ・バルネスキ] 17-19. バッハ:4台のチェンバロのための協奏曲 イ短調 BWV 1065(原曲:RV 580) [チェンバロ:リナルド・アレッサンドリーニ、アンドレア・ブッカレッラ、イグナツィオ・シファーニ、サルヴァトーレ・カル キオーロ] 20-23. ヴィヴァルディ:2つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ニ短調 RV 565(「調和の霊感」第11番) [ヴァイオリン・ソロ:ボリス・ベゲルマン、エリザ・チッテリオ チェロ:マルコ・フレッツァート] 24-26. バッハ:オルガン協奏曲 ニ短調 BWV 596(原曲:RV 565) [オルガン・ソロ:ロレンツォ・ギエルミ] 27-29. ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲ホ長調 RV 265(「調和の霊感」第12番) [ヴァイオリン・ソロ:エリザ・チッテリオ] [CD2] 1-3. バッハ:チェンバロ協奏曲 ハ長調 BWV 976(原曲:RV 265) [チェンバロ:リナルド・アレッサンドリーニ] 4-7. ヴィヴァルディ:4つのヴァイオリンのための協奏曲 ホ短調 RV 550(「調和の霊感」第4番) [ヴァイオリン・ソロ:ステファノ・バルネスキ、ボリス・ベゲルマン、エリザ・チッテリオ、アンドレア・ロニョーニ] 8-10. ヴィヴァルディ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 イ長調 RV 519(「調和の霊感」第5番) [ヴァイオリン・ソロ:アンドレア・ロニョーニ、ステファノ・バルネスキ] 11-13. ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲 イ短調 RV 356(≪調和の霊感≫第6番) [ヴァイオリン・ソロ:アンドレア・ロニョーニ] 14-18. ヴィヴァルディ:4つのヴァイオリンのための協奏曲 ヘ長調 RV 567(「調和の霊感」第7番) [ヴァイオリン・ソロ:エリザ・チッテリオ、アンドレア・ロニョーニ、ステファノ・バルネスキ、ボリス・ベゲルマン] 19-21. ヴィヴァルディ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 イ短調 RV 522(「調和の霊感」第8番) [ヴァイオリン・ソロ:エリザ・チッテリオ、アンドレア・ロニョーニ] 22-24. バッハ:オルガン協奏曲 イ短調 BWV 593(原曲:RV 522) [オルガン:ロレンツォ・ギエルミ] 25-27. ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 RV 230(「調和の霊感」第9番) [ヴァイオリン・ソロ:ボリス・ベゲルマン] 28-30. バッハ:チェンバロ協奏曲 ニ長調 BWV 972(原曲:RV 230) [チェンバロ:リナルド・アレッサンドリーニ] |
オルガン:ロレンツォ・ギエルミ【使用楽器:マショーニ・オルガン(2001年)、サンタ・マリア奇跡の教区教会、モルビオ・インフェリオーレ州(スイス)】 ヴァイオリン:ステファノ・バルネスキ、ボリス・ベゲルマン、エリザ・チッテリオ、アンドレア・ロニョーニ チェンバロ:アンドレア・ブッカレッラ、サルヴァトーレ・カルキオーロ、イグナツィオ・シファニ コンチェルト・イタリアーノ リナルド・アレッサンドリーニ(チェンバロ、指揮 ) 録音:2020年12月14-20日ローマ(調和の霊感&チェンバロ編曲) 2021年7月スイス、モルビオ・インフェリオーレ(オルガン編曲) |
|
||
| BIS BISSA-2559(1SACD) |
イェスペル・ヌーディン(1971-):Emerging from Currents and Wave(潮流と波浪の間から出現する)~クラリネット、管弦楽とライヴ・エレクトロニクスのための(2018) (1)Currents(潮流)(第1部) (2)Emergng(出現する)(第2部)(クラリネット、管弦楽とジェストルメントのための) (3)Waves(波浪)(第3部)* |
マルティン・フレスト(クラリネット、ジェストルメント)
スウェーデンRSO、 エサ=ペッカ・サロネン((指)ジェストルメント) マグヌス・ホルマンデル(Clソロ)* ライヴ録音:2018年8月31日/ベールヴァルドホール(ストックホルム、スウェーデン) |
|
||
| CPO CPO-555390(1CD) NX-B10 |
ゲオルグ・アブラハム・シュナイダー(1770-1839):
3つのフルート協奏曲 フルート協奏曲 イ短調 Op. 53 フルート協奏曲 ト長調 Op. 12 フルート協奏曲 ホ短調 Op. 63 |
ギャビー・パス=ファン・リエ(Fl) ハイルブロン・ヴュルテンベルクCO ヨハネス・メーズス(指) 録音:2020年7月1-4日 |
|
||
| Forgotten Records fr-1754(1CDR) |
バルヒェットのバッハ ヴァイオリン協奏曲[第1番イ短調 BWV.1041 ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 BWV.1042 2つのヴァイオリンの為の協奏曲 ニ短調 BWV.1043 # |
ラインホルト・バルヒェット(Vn) グイド・ファン・デア・ミューレン(Vn)# フリードリヒ・ティーレガント(指) 南西ドイツCO 録音:1959年 ※音源:Berstelmann 11362 他 |
| Forgotten Records fr-1755(1CDR) |
ヘルムート・ロロフ/モーツァルト&ベートーヴェン モーツァルト:ピアノ協奏曲第27番変ロ長調 K.595* ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番ハ長調 Op.15 # |
ヘルムート・ロロフ(P) レオポルト・ルートヴィヒ(指)* ヴォルフガング・マルティン(指)# ベルリン RIAS響 録音:1953年-1954年* 、1954年# 、 ※音源:Bertelsmann 8019* 7008 # |
| Forgotten Records fr-1757(1CDR) |
コーガン&コンドラシン プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲第2番 ハチャトゥリアン:ヴァイオリン協奏曲 バレエ「仮面舞踏会」組曲+ |
レオニード・コーガン(Vn) キリル・コンドラシン(指)ソヴィエト国立SO* アラム・ハチャトゥリアン(指)ソヴィエト国立RSO# サムイル・サモスード(指)ソヴィエト国立RSO+ 録音:1956年* /1952年# /1953年+ ※音源:Melodiya D 3190/1* D 0548/9 # |
| Forgotten Records fr-1758(1CDR) |
ヴィクトー・ショアラー~ピアノ協奏曲録音集 チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番* グリーグ:ピアノ協奏曲# |
ヴィクトー・ショアラー(P) エーリク・トゥクセン(指) デンマーク国立RSO 録音:1950年9月-10月* 、1948年11月26日-27日# ※音源:Mercury MG 10094* MG 15012 # |
| Forgotten Records fr-1763(1CDR) |
カルロ・ヴァンヌッツィ&エンリコ・マイナルディ モーツァルト:フルート協奏曲第1番ト長調 K.313* ポコルニー:フルート協奏曲 二調調* ボッケリーニ:メヌエット 二調調# チェロ協奏曲第9番変ロ長調 G.482 + ラルゴ++ |
カルロ・ヴァンヌッツィ(Fl)* エスネスト・マティソン(指)ウィーン楽友協会O* フリードリヒ・ティレガント(指)南西ドイツCO# エンリコ・マイナルディ(Vc) ウィーン・フォルクスオーパー歌劇場CO+ パウル・アンゲラー(Cemb) 録音:1958年(*/#) 、1961年、#以外はステレオ ※音源:Bertelsmann 1104、14133他 |
| Forgotten Records fr-1765(1CDR) |
ブライロフスキー~ピアノ協奏曲集 ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番* リスト:死の舞踏# フランク:交響的変奏曲+ |
アレグザンダー・ブライロフスキー(P) アンドレ・クリュイタンス(指)フランス国立放送O* フリッツ・ライナー(指)RCA ビクターSO# ジャン・モレル(指)RCA ビクターSO 録音:1951年2月20日+、1951年3月6日# 1961年9月21日、ルツェルン音楽祭ライヴ ※音源:RCA LM-1195、 LA VOIX DE SON MAITRE FALP 172他 |
| Forgotten Records fr-1766(1CDR) |
タンスマン:弦楽オーケストラの為のパルティータ ドビュッシー:神聖な舞曲と世俗的な舞曲 * リヴィエ:弦楽オーケストラの為のアダージョ ダマーズ:ハープと弦楽オーケストラの為のコンチェルティーノ # |
リリー・ラスキーヌ(Hp) ピエール=ミシェル・ル・コント(指) フランス放送CO 録音:1958年12月24日放送用録音 |
| Forgotten Records fr-1768B(2CDR) |
ランパル&リステンパルト/フルート協奏曲集 ヴィヴァルディ:フルート協奏曲集 [第1番ヘ長調 RV.433 「海の嵐」/第2番 ト短調 RV.439 「夜」/第3番ニ長調 RV.428 「ごしきひわ」/第4番ト長調 RV.435 /第5番ヘ長調 RV.434 /第6番ト長調 RV.437]* フルート協奏曲集(第2集)#[ニ長調 RV.429 /ハ短調 RV.441 /ト長調 RV.436 /ニ長調 RV.427 /イ短調 RV.440 /ト長調 RV.438]# テレマン:フルート協奏曲[ト長調 TWV Anh.51:G1 ニ長調 TWV.51:F1 (D2?)]/ 組曲 イ短調 TWV.55:a2 |
ジャン=ピエール・ランパル(Fl) ロベール・ヴェイロン=ラクロワ(Cemb) カール・リステンパルト(指)ザールCO 録音:1954年*、1956年 ※音源:Les Discophiles Francais DF 129* DF 201 # |
| Forgotten Records fr-1771(1CDR) |
ブルショルリ~モーツァルト:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲第20番二短調 K.466 ピアノ協奏曲第23番イ長調 K.488 |
モニク・ド・ラ・ブルショルリ(P) ベルンハルト・パウムガルトナー(指) ザルツブルク・モーツァルテウムO 録音:1961年、1959年+、全てステレオ ※音源:Bertelsmann 14 383、Opera L 12430 他 |
| Forgotten Records fr-1774(1CDR) |
チェロ協奏曲集 ハイドン:チェロ協奏曲 ニ長調 Op.101 Hob.VII:B2 シューマン:チェロ協奏曲 イ短調 Op.129 # |
サシャ・ヴェチトモフ(Vc) ボフシュ・ヘラン(Vc)# ヴァーツラフ・スメターチェク(指) プラハSO 録音:1953年3月11日、1953年4月7日# ※音源:Supraphon DM 5156 DM 5154 #. D LPM-106 D-20107 # |
| Forgotten Records fr-1781(1CDR) |
ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 Op.97 * ブラームス:ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 Op.83 # |
イェフディ・メニューイン(Vn)* ルイス・ケントナー(P)# ディミトリ・ミトロプーロス(指)NYO 録音:1953年10月18日*、1957年4月28日#、ともにカーネギー・ホール、ライヴ、放送用録音 |
| Forgotten Records fr-1783(2CDR) ★ |
バッハ:ヴァイオリン・ソナタ全集 第1番ロ短調 BWV.1014 第2番イ長調 BWV.1015 第3番ホ長調 BWV.1016 第4番ハ短調 BWV.1017 第5番ヘ短調 BWV.1018 第6番ト長調 BWV.1019 |
ポール・マカノヴィツキー(Vn) ノエル・リー(P) 録音:1958年、パリ ※音源:Lumen LD 3.437-438、 JALONS DE LA MUSIQUE SACREE JM 901 |
| Forgotten Records fr-1789(1CDR) |
ワレリー・クリモフ チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲* フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調# |
ワレリー・クリモフ(Vn) カール・エリアスベルク(指)モスクワPO* ヴラジーミル・ヤンポリスキー(P)# 録音:1958年*、1959年# ※音源:Melodiya D 04302/3* D 05600/1 # |
| Forgotten Records fr-1801(2CDR) ★ |
バッハ:ブランデンブルク協奏曲集(全6曲) | ギュンター・ケール(指) マインツCO 録音:1958年12月 ※音源:Vox STPL 516.430 |
| Forgotten Records fr-1803(1CDR) |
ラウテンバッハー/バッハ:ヴァイオリン協奏曲集 ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 BWV.1041 ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調BWV.1042 2つのヴァイオリンの為の協奏曲 ニ短調 BWV.1043* |
ズザーネ・ラウテンバッハー(Vn) ディーター・フォアホルツ(Vn)* ギュンター・ケール(指)マインツCO 録音:1960年頃(ステレオ) ※音源:Vox STPL-511.540 PL 11540 |
 Altus ALT-506(1CD) |
INA秘蔵音源・クリュイタンス&フランス国立管ライヴ (1)ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 (2)メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 |
アイザック・スターン(Vn(1)) ヘンリク・シェリング(Vn(2) ) アンドレ・クリュイタンス(指) フランス国立放送O ライヴ録音:(1)1954年11月11日パリ、シャンゼリゼ劇場(モノラル) (2)1959年9月20日モントルー音楽祭(モノラル) |
|
||
| Skani SKANI-134(1CD) |
ヴェスタルズ・シムクス(b.1984):ピアノ作品集 ピアノ協奏曲第1番 「扱いにくい人に捧げる」(Pと弦楽オーケストラのための) 夢の情景(Pのための9つのエチュード) ~ 水門、蛇、Silverdark Trees、浮かぶ星、津波、忘れてしまった夢-ヨハン・ゼバスティアン・バッハに捧ぐ、平行する夢の時間、現実、弾丸 運命の門(PとSOのための) |
ヴェスタルズ・シムクス(P)、 アトヴァルス・ラクスティーガラ(指)、 リエパーヤSO |
|
||
| KAIROS 0015090KAI(1CD) |
ユン・イサン(尹 伊桑):チェロ協奏曲&チェロとピアノのための作品集
チェロ協奏曲(1976)/ピアノのための5つの小品(1958)/ノレ(Vcとピアノのための)(1964)/インテルルディウム A(Pのための)(1982)/エスパス I(Vcとピアノのための)(1992) |
ルイージ・ピオヴァーノ(Vc)、 アルド・オルヴィエート(P)、 日本フィルハーモニーSO、 下野竜也(指) 録音:チェロ協奏曲…2018年3月2日(ライヴ)、サントリーホール(東京) チェロとピアノのための作品…2021年3月28-29日(イタリア、トリノ) |
|
||
| Danacord DACOCD-920(2CDR) |
トマス・イェンセンの遺産 第10集 (1)ニルス・ヴィゴ・ベンソン (1919-2000):ヴァイオリン協奏曲第1番 Op.70(c.1952)* (2)フランス・シベア(1904-1955):交響曲(1940) (3)クヌーズオーウ・リスエーヤ(1897-1974):演奏会序曲 「春」 Op.31(1934) (4)弦楽のための小序曲(1934) (5)シークフリト・セーロモン(1885-1962):チェロ協奏曲 二短調 Op.34(1922)** (6)ライフ・テューボ(1922-2001):チェロ協奏曲(1959)** (7)ニルス・ヴィゴ・ベンソン:チェロ協奏曲第1番 Op.106(1956)** |
トマス・イェンセン(指)、 デンマークRSO、 チャーレス・センデローヴィツ(Vn)* エアリング・ブレンダール・ベンクトソン(Vc)** (1)録音:1957年9月26日、デンマーク放送コンサートホール(コペンハーゲン)(放送コンサート) (2)録音:1961年5月27日、デンマーク放送コンサートホール(コペンハーゲン)(スタジオ放送) (3)録音:1960年、スタジオ録音(コペンハーゲン)][Odeon MOAK 10 (4)録音:1949年1月27日-28日、スタジオ録音(コペンハーゲン)[Tono X 25146/DACOCD 523-524] (5)録音:1959年6月16日、スタジオ放送(コペンハーゲン)[DACOCD 727] (6)録音:1962年5月40日、デンマーク放送コンサートホール(コペンハーゲン)(放送コンサート)[DACOCD 846] (7)録音:1957年8月16日、ティヴォリ・コンサートホール(コペンハーゲン)(放送コンサート)[DACOCD 727] |
|
||
| CALLIOPE CAL-22100(1CD) |
モーツァルト、レイシェル:ピアノ協奏曲 モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番イ長調 K.488 ベルナール・レイシェル:ピアノ協奏曲(1949) モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番 ハ短調 K.491 |
クリスチャン・シャモレル(P)、 オーケストラ・ネクサス、 ギヨーム・バーニー(指) 録音:2021年8月16日-19日(スイス) |
|
||
| Signum Classics SIGCD-700(1CD) |
ショパン:ピアノ協奏曲集(室内楽版) ショパン:ピアノ協奏曲第1番ホ短調 Op.11(弦楽五重奏とピアノ版) ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 Op.21(弦楽五重奏とピアノ版) |
エマニュエル・デスパ(P/ファツィオリ)、チネケ!・チェンバー・アンサンブル 録音:2021年5月7日-9日、メニューイン・ホール(サリー、イギリス) ※使用楽器:Fazioli model 278 |
|
||
| Anaklasis ANA-018(3CD) |
ショパン:ピアノ協奏曲集、練習曲集、室内楽作品集
CD1~ピアノ協奏曲第1番ホ短調 Op.11* ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 Op.21* CD2~12の練習曲 Op.10+ 12の練習曲 Op.25+ CD3~ピアノ三重奏曲ト短調 Op.8$ 序奏と華麗なるポロネーズ ハ長調 Op.3# マイアベーアの歌劇「悪魔のロベール」の主題による協奏的大二重奏曲ホ長調# |
ハリーナ・チェルニー=ステファンスカ(P)*、 レギナ・スメンジャンカ(P)*、 ヴィトルト・ロヴィツキ(指)ワルシャワPO**、 ボレスワフ・ヴォイトヴィチ(P)+、 ウワディスワフ・シュピルマン(P)$#、 タデウシュ・ヴロンスキ(Vn)$、 アレクサンデル・チエチャンスキ(Vc)$、 ハリナ・コヴァルスカ(Vc)# 録音:1959年*+、1960年$、1961年#、ワルシャワ・フィルハーモニック ※サウンド・レストレーション&マスタリング:エヴァ・グジョウェク=トゥベレヴィチ(2021) |
|
||
| Urania Records WS-121386(2CD) |
バッハ:ブランデンブルク協奏曲集(全6曲) | イ・ムジチ合奏団、 エーリヒ・ペンツェル(Hrn)、ゲルト・ハウケ(Hrn)、ハインツ・ホリガー(Ob)、モーリス・ブルグ(Ob)、ハンス・クル(Ob)、カール・ヴァイス(Fg)、モーリス・アンドレ(Tp)、セヴェリーノ・ガッゼローニ(Fl)、マクサンス・ラリュー(Fl)、フランス・ブリュッヘン(Fl)、ジャネット・ファン・ビンゲルデン(Fl)、ヤーノシュ・ショルツ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)、マリア・テレサ・ガラッティ(ハープシコード) 録音:1963年 ※STEREO/ADD |
|
||
| Hyperion CDA-68357(1CD) |
ヴィヴァルディ&ピアソラ:四季(マンドリン版)
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲ヘ短調「冬」 RV297 ピアソラ:ブエノスアイレスの冬 ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲ホ長調「春」 RV269 ピアソラ:ブエノスアイレスの春 ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲ト短調「夏」 RV315 ピアソラ:ブエノスアイレスの夏 ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲ヘ長調「秋」 RV293 ピアソラ:ブエノスアイレスの秋 |
ディオン、ハープシコード、指揮)、 シンフォニエッタ・ライプツィヒ 録音:2021年3月24日-26日、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス 大ホール(ドイツ) |
|
||
| Centaur CRC-3904(1CDR) |
フレデリック・レセマン:歌曲&小協奏曲集 (1)フルートと混合五重奏のための小協奏曲 (2)アレルヤ...イン・ドーモ・ペル・セクラ (3)オーボエと6つの楽器のための小協奏曲 (4)李煜の3つの歌 (5)ファゴットと6つの楽器のための小協奏曲 |
(1)ジュリー・ロング(ソロ・フルート) エリック・ジェイコブス(Cl)、クララ・キム(Vn)、マイケル・カウ フマン(Vc)、イーサン・アーマッド(マリンバ)、サラ・ギブソン(P) (2)ハイデン・エバーハート(S)、ジョセフ・モリス(Cl)、マルコ・デ・アルメイダ(Hrn)、アンジェラ・ロメロ(Tp)、ブレント・アンダーソン(Tb) (3)ラシェル・ファン・アンバース(ソロ・オーボエ)、アシュリー・ハリス(Fl)、エリック・ジェイコブス(Cl)、カイル・ギルナー(Vn)、マイケル・カウフマン(Vc)、トーマス・コッチェフ(P) (4)ティムール・ベクボスノフ(T)、チャン・ルー(Fl)、エリッサ・ブラウン (Fl)、ミシェル・フアン(Fl)、ケルシ・ドゥーリトル(バスクラリネット)、 キャサリン・レドルス(Hp)、ケヴィン・シュー(Va) (5) ブリタニー・セイツ(ソロ・ファゴット)、キャサリン・スタンデファー(アルトフルート)、エリック・ジェイコブス(バスクラリネット)、カイル・ギルナー(Vn)、ディン・スン(Va)、ステラ・チョ(Vc)、タイラー・ステル(パーカッション) USCソーントンエッジ、ドナルド・クロケット(音楽監督) 録音:2012年-2015年(アメリカ) |
|
||
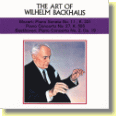 Treasures TRE-258(1CDR) |
バックハウス~珠玉の協奏曲録音 モーツァルト:ピアノ・ソナタ第11番「トルコ行進曲付き」 ピアノ協奏曲第27番変ロ長調Op.83* ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第2番# |
ウィルヘルム・バックハウス(P) カール・ベーム(指)VPO* ハンス・シュミット=イッセルシュテット(指)VPO# 録音:1955年5月-6月、1955年5月*、1959年6月29-30日#(全てステレオ) ※音源:日KING_SL-1029、SLC-1620# ◎収録時間:71:19 |
| “バックハウスによる協奏曲の二大筆頭名演!” | ||
|
||
| H.M.F HMM-902412(1CD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集 vol.3 ピアノ協奏曲第3番〔I. アレグロ・コン・ブリオ【カデンツァ:ベザイデンホウト/ベートーヴェン】 -II. ラルゴ-III. ロンド、アレグロ【ロンド主題への導入:ベザイデンホウト/ベートーヴェン】〕 ピアノ協奏曲第1番〔I. アレグロ・コン・ブリオ【カデンツァ:ベザイデンホウト/ベートーヴェン】-II. ラルゴ-III. ロンド.アレグロ・スケルツァンド〕 |
クリスティアン・ベザイデンホウト (フォルテピアノ/1824年コンラート・グラーフのコピー、1989年ロドニー・レジエ製作(フリーポート、メイン州、アメリカ)、 2002年エドウィン・ボインク&ホハン・ヴェンニクによる修復、エドウィン・ボインク・コレクション) パブロ・エラス=カサド(指) フライブルク・バロック・オーケストラ 録音:2017年12月、アンサンブルハウス・フライブルク |
|
||
| H.M.F HMSA-0045(1SACD) シングルレイヤー 日本独自企画 限定盤 税込定価 |
シェーンベルク:ヴァイオリン協奏曲 op.36 [1936年] 浄夜 op.4(弦楽六重奏曲版)[1899年] |
ヴァイオリン協奏曲:イザベル・ファウスト(Vn) スウェーデンRSO、 ダニエル・ハーディング(指) 浄夜:イザベル・ファウスト(Vn)、アンネ・カタリーナ・シュライバ ー(Vn)、アントワン・タメスティ(Va)、ダヌーシャ・ヴァスキエヴィチ(Va)、クリスティアン・ポルテラ(Vc)、ジャン=ギアン・ケラス(Vc) 録音:【ヴァイオリン協奏曲】2019年1月/ベルワルト・ホール(ストックホルム)、 【浄夜】2018年9月/テルデックス・スタジオ(ベルリン) |
|
||
| MDG MDG-90122296 (1SACD) |
ディミトリス・パパディミトリウ(1959-):作品集 ピアノ協奏曲第1番/不完全性 ポロック(Painting Soundtracksより抜粋) ミニチュア組曲 |
ティトス ・クベリス(P) アテネ国立O ジョージ・ペトロウ(指) |
|
||
| ATMA ACD2-2811(1CD) |
極光のヴィオラ ヴァスクス(1946-):ヴィオラ協奏曲 メロディ・マッキバー(1988-):Ningodwaaswi / Niizh テレマン:ヴィオラ協奏曲 ト長調 TWV51:G9 |
マリーナ・ティボ ー(Va) ニコラス・エリス(指) アゴラO 録音:2021年10月16-19日/ケベック) |
|
||
| スロヴェニア放送 ZKP-117152(2CD) |
イゴール・オジムが弾く名協奏曲集 (1)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第2 番 ニ長調 K.211 (2)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第4 番 ニ長調 K.218 (3)チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35 (4)メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64 (5)ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.77 |
イゴール・オジム(Vn) (1)(2)サモ・フバド(指)スロヴェニアPO 録音:(1)1972年9月20日、(2)1972年9月21日スロヴェニア リュブリャナ(ライヴ) (3)ユーリ・シモノフ(指)リュブリャナRSO 録音:1993 年3 月19 日 スロヴェニア リュブリャナ(ライヴ) (4)ネーメ・ヤルヴィ(指)スロヴェニアPO 録音:1978 年4 月12 日 スロヴェニア リュブリャナ(ライヴ) (5)ニコライ・アレクセーエフ(指)リュブリャナRSO 録音:1992 年1 月10 日 スロヴェニア リュブリャナ(ライヴ) 146'31 |
|
||
| スロヴェニア放送 ZKP-115752(1CD) |
ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61 ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1 番ト短調 Op.26 |
ステファン・ミレンコヴィッチ(Vn) ヴラディミル・クレノヴィッチ(指) スロヴェニアRSO 録音:2019年5月 スロヴェニア リュブリャナ 68'47 |
|
||
| PROSPERO CLASSICAL PROSP-0025(1CD) |
ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 ピアノ協奏曲第3番ニ短調 Op.30 |
イリーナ・ゲオルギエヴァ(P) サッシャ・ゲッツェル(指) パブロ・ゴンザレス(指)* バーゼルSO 録音:2020年12月21・28日スイス、スタッドカジノ・バーゼル |
|
||
| Evil Penguin Records EPRC-0045(1CD) |
ヴァインベルク(1919-1996):チェロ・コンチェルティーノ Op.43bis チェロとオーケストラのための幻想曲 Op.52 室内交響曲第4番Op.153 |
ピーター・ウィスペルウェイ(Vc) ジャン=ミシェル・シャルリエ(Cl) ラファエル・ファイユ(指) レ・メタモルフォーゼス 録音:2021年6月28日-7月1日ベルギー |
|
||
| FIRST HAND RECORDS FHR-82(1CD) |
初期ステレオ録音集 第5集 (1)ヴィヴァルディ:オーボエ協奏曲 イ短調 RV461 (2)チマローザ(アーサー・ベンジャミン編):オーボエ協奏曲 ハ長調 (3)ハイドン:チェロ協奏曲第2番ニ長調 Hob.VIIb:2, Op.101 (4)モーツァルト:ピアノ協奏曲第17番ハ長調 K453 |
(1)(2)レナート・ザンフィーニ(Ob)、レナート・ファザーノ(指)、ローマ合奏団
(3)アメデオ・バルドヴィーノ(Vc)、フェルナンド・プレヴィターリ(指)、プロ・アルテO (4)ジーナ・バッカウアー(P)、アレック・シャーマン(指))、ザ・ロンドン・オーケストラ 録音:(1)(2)1956年10月3-4日、(3)1956年10月17・19・25日、(4)1956年5月9-10日 すべてステレオ初出 |
|
||
| DOREMI DHR-8165(3CD) |
ルドルフ・ゼルキンLIVE 第2集 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲集(全5曲) 合唱幻想曲 Op.80 ピアノ・ソナタ第21番『ワルトシュタイン』* |
ルドルフ・ゼルキン(P) マックス・ルドルフ(指)ボストンSO ライヴ録音:1970年4月8-10日ボストン、シンフォニーホール 1974年トロント、マッセイ・ホール* |
|
||
| KLARTHE KLA-017(1CD) |
『四季』 ニコラ・バクリ(1962-):『四季』 (1)闇の協奏曲「冬」Op.80-3~オーボエ、ヴィオラとオーケストラのための協奏曲(2009) (2)愛の協奏曲「春」Op.80-2~オーボエ、ヴァイオリンとオーケストラのための協奏曲(2004-05) (3)光の協奏曲「夏」Op.80-4~オーボエ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロとオーケストラのための協奏曲(2010-11) (4)郷愁の協奏曲「秋」Op.80-1~オーボエ、チェロとオーケストラのための協奏曲(2000-02) |
(1)(3)アドリアン・ラ・マルカ(Va)、 (1)(2)(3)(4)フランソワ・ルルー(Ob)、 (2)(3)ヴァレリー・ソコロフ(Vn)、 (3)(4)セバスティアン・ヴァン・カイック(Vc) ヴィクトル・ユーゴー・フランシュ=コンテO、 ジャン=フランソワ・ヴェルディエ(指) 録音:2015年2月/ブザンソン地方音楽院、フランシュ=コンテ地域圏(フランス) |
|
||
| KLARTHE KLA-087(1CD) |
モダニズム (1)リャトシンスキー(チェスノコフ編):バラードOp.24 (2)ドミートリー・チェスノコフ:ヴァイオリン協奏曲Op.87「天地創造」 (3)ショスタコーヴィチ:交響曲第1番ヘ短調Op.10 |
サラ・ネムタヌ(Vn)(2)、 バスティアン・スティル(指) ウクライナ国立SO 録音:2016年12月4-5日/ウクライナ国営放送大コンサート・スタジオ |
|
||
| Hanssler HC-21058(1CD) |
(1)メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64 (2)ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第2番ニ短調 Op.44 |
ミハイル・ポチェキン(Vn) ロイトリンゲン・ヴュルテンベルクPO、 セバスチャン・テウィンケル(指) 録音:2021年5月27-29日/ロイトリンゲン・ヴュルテンベルク・フィルハーモニー・スタジオ(ドイツ) |
|
||
| Capriccio C-5438(1CD) NX-B05 |
イェネー・タカーチ(1902-2005):作品集 セレナード - 古いグラーツのコントルダンスより Op. 83b(1966) - 弦楽のために ラプソディ「ハンガリーの旋律」 Op. 49a(1941)- ヴァイオリンと弦楽オーケストラのために 協奏曲 - ピアノと弦楽オーケストラ、パーカッションのために Op. 60(1947-2000) パッサカリア Op. 73 - 弦楽オーケストラのために(1960) 3つの小品 - 弦楽オーケストラのために(1993) |
ニナ・カルモン(Vn) オリヴァー・トリンドル(P) インゴルシュタット・ジョージア室内O エヴァン・アレクシス・クリスト(指) 録音:2020年10月13-16日 |
|
||
| Chateau de Versailles Spectacles CVS-065(1CD) |
ヴィヴァルディ:弦楽と通奏低音のための12の協奏曲(「パリ協奏曲集」) 協奏曲 第5番ハ長調 RV 114 協奏曲 第4番ヘ長調 RV 136 協奏曲 第11番ト長調 RV 150 協奏曲 第1番ト短調 RV 157 協奏曲 第12番イ長調 RV 159 協奏曲 第10番二長調 RV 121 協奏曲 第6番ト短調 RV 154 協奏曲 第7番イ長調 RV 160 協奏曲 第3番ハ短調 RV 119 協奏曲 第9番変ロ長調 RV 164 協奏曲 第8番ニ短調 RV 127 協奏曲 第2番ホ短調 RV 133 |
ステファン・プレフニャク(Vn&指揮) ヴェルサイユ王室歌劇場O(古楽器使用) 録音:2020年12月2-6日、ヴェルサイユ宮殿「十字軍の広間」 |
|
||
| ONDINE ODE-1405(1CD) NX-B04 |
ラウタヴァーラ:『Lost Landscapes 失われた風景』 ファンタジア(2015) - ヴァイオリンと管弦楽のための イン・ザ・ビギニング(2015)- 管弦楽のための…世界初録音 2つのセレナード(2016/18)- ヴァイオリンと管弦楽のための(カレヴィ・アホによる補筆完成) 愛する人へのセレナード 人生のセレナード 失われた風景(2005/15)- ヴァイオリンと管弦楽のための…管弦楽伴奏版による世界初録音 |
シモーネ・ラムスマ(Vn) マルメSO ロバート・トレヴィーノ(指) 録音 2021年6月21日-23日マルメ・ライヴ・コンサートホール、マルメ(スウェーデン) |
|
||
| Challenge Classics CC-72820(1CD) |
「復活」 ~ベートーヴェン:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op.58 ピアノ協奏曲 ニ長調 Op.61a |
ニーノ・グヴェタッゼ(P) バンジャマン・レヴィ(指) フィオンO 録音:2021年6月15-18日オランダ、エンスヘデ音楽センター |
|
||
| Challenge Classics CC-72908(1CD) |
告げ口心臓 ~ヴィレム・イェツ(1959-):作品集 (1)永遠の死 Mors aeterna (2)ヴァイオリン協奏曲第2番『二連板の肖像』 Diptych portrait (3)告げ口心臓 The Tell-Tale Heart |
(1)ジェイムズ・ガフィガン(指) (2)タスミン・リトル(Vn)、ラインベルト・デ・レーウ(指) (3)ユリアーネ・バンゼ(S)、 ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン(指) オランダ放送PO 録音:(1)2015年11月14日、(2)2010年5月22日、(3)2018年4月14日 |
|
||
| DOREMI DHR-8160(1CD) |
レオン・フライシャーLIVE 第2集 (1)ブラームス:ピアノ協奏曲第1番ニ短調 Op.15 (2)モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番イ長調 K.488 |
レオン・フライシャー(P) (1)ピエール・モントゥー(指)コンセルトヘボウO (2)ブルーノ・ワルター(指)ロサンゼルスPO ライヴ録音:(1)1962年5月14日アムステルダム、 (2)1959年6月12日ロサンゼルス、ハリウッド・ボウル |
|
||
| KLARTHE KLA-050(1CD) |
「啓蒙時代」 ヴァーゲンザイル:トロンボーン協奏曲(カデンツァ:B.ガルツィア=ガプドヴィル) ベゾッツィ:トロンボーン・ソナタ 変ロ長調 アルブレヒツベルガー:トロンボーン協奏曲 変ロ長調(カデンツァ:B.ガルツィア=ガプドヴィル) ヘンデル:トロンボーン協奏曲 ヘ短調 エーベルリン:「イエス、流れよ、熱きトラネンバッハよ」 |
(5)ヴァンニーナ・サントーニ(S) アンリ=ミシェル・ガルツィア(Tb) アンサンブル・ネオフォニア 、 バンジャマン・ガルツィア(指) 録音:2016年10月13-16日/サン=ルイ (フランス) |
|
||
| フォンテック FOCD-9865(1SACD) 税込定価 2022年3月9日発売 |
ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 | 矢部達哉(Vn) 朝比奈隆(指) 新日本フィルハーモニーSO 録音:1996 年5 月3 日 サントリーホール・ライヴ |
|
||
| EUROARTS 20-56733(Bluray) 20-56739(DVD) |
バッハ:ブランデンブルク協奏曲(全6曲) 第1番ヘ長調 BWV.1046 第3番ト長調 BWV.1048 第5番ニ長調 BWV.1050 第6番変ロ長調 BWV.1051 第4番ト長調 BWV.1049 第2番ヘ長調 BWV.1047 アンコール: 第2番ヘ長調 BWV.1047より第3楽章アレグロ・アッサイ |
クラウディオ・アバド(指)モーツァルトO コンサートマスター:ジュリアーノ・カルミニョーラ(Vn) チェンバロ:オッターヴィオ・ダントーネ 第1&2ヴァイオリン:ラファエル・クリスト、ロレンツァ・ボッラーニ、ユナ・シェフチェンコ、ティモティ・フレグニ、 エティエンヌ・アブラン 、マヌエル・カストル 、ヤナ・クールマン ヴィオラ:ダニューシャ・ヴァスキエヴィチ、シモーネ・ヤンドル、ベーランク・ラシュキ、ラファエル・ザックス ヴィオラ・ダ・ガンバ:ライナー・ツィパーリング、サビナ・コロンナ・プレティ チェロ:マリオ・ブルネロ、エンリコ・ブロンツィ 、ブノワ・グルネ コントラバス:アロイス・ポッシュ フルート:ジャック・ズーン リコーダー:ミカラ・ペトリ、ニコライ・タラソフ オーボエ:ヴィクトール・アヴィアット、ルーカス・マシアス・ナヴァロ、グイド・グアランディ ファゴット:ギヨーム・サンタナ ホルン:アレッシオ・アレグリーニ、ジョナサン・ウィリアムズ トラン ペット:ラインホ ルト・フリードリヒ 収録:2007年4月21日 イタリア、レッジョ・エミリア、ヴァーリ市立劇場 ◆Bluray ★★ 画面:カラー 、16:9 、1080i Full HD 音声:PCMステレオ、 DTS-HD MA5.1 リージョン:All、100分 ◆DVD 画面:カラ ー 、16:9 、 1080i Full HD 音声:PCMステレオ、 DTS-HD MA5.1 リージョン:All、100分 |
|
||
| ALPHA ALPHA-825(1CD) |
18世紀ファゴット協奏曲集 バッハ(マティス・シュティーア編):1-3. ファゴット協奏曲 ト長調 BWV 1055R(オーボエ・ダモーレ協奏曲〔原曲: チェンバロ協奏曲第4番BWV 1055〕) ヘルテル(1727-1789):ファゴット協奏曲 イ短調 モーツァルト:ファゴット協奏曲 変ロ長調 K. 191 |
マティス・シュティーア(Fg) アンサンブル・レフレクトーア 録音:2021年8月、西部ドイツ放送(WDR)放送局、ケルン |
|
||
| ALPHA ALPHA-794(1CD) |
『次世代ソリストたちによるモーツァルト Vol.1』 ヴァイオリン協奏曲 第1番変ロ長調 K. 207 (カデンツァ: ステファン・ワーツ) ピアノ協奏曲 第8番ハ長調 K. 246 「リュッツォウ」(カデンツァ: ジャン・チャクムル) ホルン協奏曲 第4番変ホ長調 K. 495(カデンツァ: イヴォ・ドゥドラー) |
ステファン・ワーツ(Vn) ジャン・チャクムル(P) イヴォ・ドゥドラー(Hrn) カメラータ・シュヴァイツ ハワード・グリフィス(指) 録音:2021年3月 オーバーシュトラース教会、チューリヒ |
|
||
| ALPHA ALPHA-795(1CD) |
『次世代ソリストたちによるモーツァルト Vol.2』 ヴァイオリン協奏曲 第3番ト長調 K. 216(カデンツァ: サム・フランコ) ファゴット協奏曲 変ロ長調 K. 191(カデンツァ: テオ・プラート) ピアノ協奏曲 第5番ニ長調 K. 175(カデンツァ: メロディ・チャオ) |
ジユ・ヘ(何子毓) (Vn) テオ・プラート(Fg) メロディ・チャオ(趙梅笛) (P) ザルツブルク・モーツァルテウムO ハワード・グリフィス(指) 録音:2021年6月 オルケスターハウス、ザルツブルク |
|
||
| Centaur CRC-3844(1CD) |
ピアソラ~百年 ピアソラ:バンドネオン協奏曲「アコンカグア」 モサリーニ:トマ,トカ*、百年* ピアソラ(モサリーニ編):ブエノスアイレスの四季*、リベルタンゴ* (世界初録音*) |
ジゼル・ベン=ドール(指)、 フアンホ・モサリーニ(バンドネオン)、 ボストン・プロアルテ室内O、 クリスティーナ・ニルソン(Vn)、 アン・ブラック(Va)、 スティーヴン・レヴァン(Vc) 録音:2020年1月13日、サンダー・テアトル(アメリカ) |
|
||
| Centaur CRC-3879(1CD) |
ヴァーレーズ、ルトスワフスキ、リゲティ、バルディーニ
クリスティアン・バルディーニ(b.1978):Elapsing Twilight Shades(2008,rev.2012)# ルトスワフスキ:チェーン2(1985)+ リゲティ:ヴァイオリン協奏曲(1989,rev.1993)* ヴァーレーズ:アメリカ(1918-21,rev.1927)$ |
クリスティアン・バルディーニ(指)、 マクシミリアン・ハフト(Vn)+、 ミランダ・クックソン(Vn)*、 ミュンヘン放送O#、UC・デイヴィスSO+*$ 録音:2012年4月29日(バルディーニ)、2019年11月23日(ルトスワフスキ)、2018年5月5日(リゲティ)、2015年5月2日(ヴァーレーズ) |
|
||
| Chandos CHAN-20166(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲集 Vol.6 モーツァルト:歌劇「劇場支配人」序曲 ピアノ協奏曲第22番変ホ長調 KV 482* ピアノ協奏曲第23番ホ長調 KV 488* |
ジャン=エフラム・バヴゼ(P/YAMAHA CFX)*、 ガボル・タカーチ=ナジ(指) マンチェスター・カメラータ 録音:2020年10月9日-10日、ストーラー・ホール(ハンツ・バンク、マンチェスター) |
|
||
| APR APRCD-5519(1CD) |
ホロヴィッツ~チャイコフスキー&ラフマニノフ
(1)チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 (2)ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番 |
ヴラディーミル・ホロヴィッツ(P)、 ジョン・バルビローリ(指)NYO (1)録音:1940年3月31日、カーネギー・ホール (2)録音:1941年5月4日、カーネギー・ホール |
|
||
| DACAPO MAR-6.220702(1SACD) NX-C05 |
オーレ・シュミット(1928-2010):金管楽器のための協奏曲集 協奏的小品 Op. 19(1964) - トランペットとトロンボーン、弦楽、ハープ、パーカッションとチェレスタのために テューバ協奏曲(1975) ホルンと室内オーケストラのための協奏曲(1966) |
ガボール・タルケヴィ(Tp) イェスパー・ブスク・ソレンセン(Tb) イェンス・ビョルン=ラーセン(Tub) シュテファン・ドール(Hrn) オルボアSO ジョルダーノ・ベッリンカンピ(指) 録音:2021年5月17-21日 |
|
||
| CLAVES 50-3004(1CD) |
「原点回帰」 ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番ハ短調 Op.18 ババジャニャン:「英雄のバラード」(1950) |
ジャン=ポール・ガスパリアン(P) ベルンSO、 ステファン・ブルニエ(指) 録音:2021年9月ダイアコニス教会、ベルン(スイス) |
|
||
| Audite AU-97802(1CD) |
フレンチ・チェロ ボエルマン:交響的変奏曲 Op.23 サン=サーンス:チェロ協奏曲第1番イ短調 Op.33 フォーレ:悲歌 Op.24 ラロ:チェロ協奏曲 ニ短調 サン=サーンス:白鳥 |
マ ル ク・コッペイ(Vc) ジョン・ネルソン(指)、 ストラスブールPO、 本田早美花(コンサートマスター) 録音:2021年4月20-23日サル・エラスム、パレ・ド・ラ・ミュジク・エ・デ・コングレ(ストラスブール) |
|
||
| Goodies 78CDR-3859(1CDR) 税込定価 |
パガニーニ(ウィルヘルミ編):ヴァイオリン協奏曲第1番(単一楽章) | ラースロ・セントジェルジ(Vn) クレメンス・シュマルシュティッヒ(指) ベルリン国立歌劇場O 独 HMV EH418/19 1929年10月録音 |
|
||
| BIS BISSA-2400(1SACD) |
サン=サーンス:ピアノ協奏曲集 (1)ピアノ協奏曲第2番ト短調 Op.22(1868) (2)「ウェディング・ケーキ」(カプリース・ワルツ)Op.76(1886) (3)アレグロ・アパショナート 嬰ハ短調 Op.70(1884) (4)ピアノ協奏曲第1番ニ長調 Op.17(1858) (5)「オーベルニュ狂詩曲」Op.73(1884) (6)幻想曲「アフリカ」Op.89(1891) |
アレクサンドル・カントロフ(P;Steinway D)
ジャン=ジャック・カントロフ(指) タピオラ・シンフォニエッタ 録音:(2)(5)2018年1月28日-2月2日、(3)(4)(6)2020年1月13-17日、(1)2021年9月6-8日/タピオラ・コンサートホール(フィンランド) |
|
||
| BIS BISSA-2647 (1SACD) |
クラリネット協奏曲集 (1)モーツァルト:クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 (2)モーツァルト:クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581 (3)リチャード・バーチャル(1984-):バセット・クラリネット協奏曲“マイケル・コリンズのために”(2020) |
マイケル・コリンズ(バセット・クラリネット、(1)指揮) (1)(3)フィルハーモニアO、 (3)ロビン・オニール(指) (2)ウィグモア・ソロイスツ【アレクサンドル・シトコヴェツキー(Vn1)、アナベル・メアー(Vn2)、イザベル・ファン・クーレン(Va)、アドリアン・ブレンデル(Vc)】 録音:(1)(3)2021年4月8&9日ヘンリー・ウッド・ホール(ロンドン) (2)2021年8月21日メニューイン・ホール、メニューイン音楽学校(ストーク・ダバノン) |
|
||
| DOREMI DHR-8161(2CD) |
ルドルフ・ゼルキンLIVE 第1集 (1)ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 (2)ブラームス:アノ協奏曲第2番 (3)ブラームス:4つのピアノ小品 Op.119 (4)シューベルト:さすらい人幻想曲 |
ルドルフ・ゼルキン(P) (1)ジョージ・セル(指)クリーヴランドO (2)レナード・バーンスタイン(指)NYO、 ローン・マンロー(Vc独奏) ライヴ録音:(1)1968年4月18日セヴェランス・ホール (2)1966年1月25日リンカーンセンター、フィルハーモニックホール (3)(4)1974年トロント、マッセイホール |
|
||
| Pentatone PTC-5186973(1CD) |
『フロー』 モーツァルト:クラリネット協奏曲 イ長調 K.622 ヘンデリクス:協奏曲『経典(SUTRA)』~(バセット)クラリネット、オーケストラとエレクトロニクスのための【世界初録音】* |
アン ネリエン・ヴァン・ヴァウヴェ(バセット・クラリネット)
アンドルー・マンゼ(指) ハノーファー北ドイツ放送PO 録音:2021年4月13&14日、2021年11月16-18日*/ NDRハノーファー、放送局スタジオ大ホール |
|
||
| Solo Musica SM-394(1CD) NX-B03 |
アルベーナ・ペトロヴィチ:サクソフォンのための音楽 バリトン・サクソフォンのための協奏曲 Op. 204(2018) ポエム-マスク Op. 236(2021) 夢の恋人 Op. 189(2017) 2つの小品(2018) Gebet zum Nichterscheinen Op.102(2006) |
ジョアン=マルティ・フラスキエ(バリトン・サクソフォン,サクソフォン/アルト・サクソフォン) ロマン・ノスバウム(P) シンシア・ノック(ヴォーカル) ケビヤール・エンサンブレ 録音:2021年10月20-22日 |
|
||
| Linn CKD-680(1CD) NX-B09 |
モーツァルト:ファゴット協奏曲 変ロ長調 K. 191 ファゴットとチェロ(低音部)のためのソナタ 変ロ長調 K. 292 * セレナード 第12番ハ短調 「ナハトムジーク」 K. 388 ** |
ピーター・ウィラン(Fg) 使用楽器:ペーテル・デ・コニング2004年製作、J.H.グレンザーのモデルによる再現楽器 アンサンブル・マルシュアス(古楽器使用) クリスティアン・ベザイテンホウト(フォルテピアノ) エマニュエル・ラポルト、ロドリーゴ・グティエレス(Ob) ニコラ・ボウド、キャサリン・スペンサー(Cl) アレック・フランク=ジェミル、ジョゼフ・ウォルターズ(Hrn) ピーター・ウィラン、ジュリアン・ドボルド(Fg) クリスティーネ・シュティヒャー(Cb) 録音:2021年5月31日 サフロン・ホール、サフロン・ウォールデン(イングランド南東部エセックス州)、2014年7月4日 聖モナン教会、イースト・ニューク、スコットランド、2019年6月27日 ノース・リース教区教会、エディンバラ、スコットランド * 音源初出…CKD546 ** 音源初出…CKD654 |
|
||
| BR KLASSIK BR-900202(1CD) NX-B05 |
ショスタコーヴィチ:ピアノ協奏曲第1番* 交響曲第9番 変ホ長調 Op. 70 |
イェフィム・ブロンフマン(P)* ハンネス・ロイビン(Tp)* バイエルンRSO マリス・ヤンソンス(指) 録音:2012年10月15-19日ミュンヘン、ヘルクレスザール(ライヴ)* 2011年3月21日ウィーン、ムジークフェラインザール(ライヴ) |
|
||
| Da Vinci Classics C-00527(1CD) |
ダヴィド・フォンタネージ(b.1969):4つの金管楽器のための協奏曲集 B♭管トランペット,弦楽とパーカッションのための協奏曲 トロンボーン,弦楽とパーカッションのための協奏曲 F管ホルン,弦楽とパーカッションのための協奏曲 テューバ,弦楽とパーカッションのための協奏曲 |
マルコ・ピエロボン(Tp)、 ジャンルカ・スキピオ-ニ(Tb)、 ニロ・カラクリスティ(Hrn)、 ステファノ・アンマンナーティ(テューバ)、 イ・ヴィルトゥオージ・イタリアーニ、 アルベルト・マルティーニ(指) 録音:2021年2月28日-3月3日、テアトロ・リスト―リ(ヴェローナ、イタリア) |
|
||
| fra bernardo FB-2271745(1CD) |
ドン・アントニオ~ヴィヴァルディ:リコーダー協奏曲集 フラウティーノ協奏曲ハ長調 RV.443/室内協奏曲ト短調 RV.107(リコーダー、オーボエ、ヴァイオリン、ファゴット、通奏低音)/室内協奏曲ト長調 RV.101(リコーダー、オーボエ、ヴァイオリン、ファゴット、通奏低音)/フルート協奏曲ト短調 RV.439 「夜」/室内協奏曲ト短調 RV.103(リコーダー、オーボエ、ファゴット)/フルート協奏曲ニ長調 RV.428 「ごしきひわ」 |
ミヒャエル・オマン(リコーダー、ディレクター)、アマンディーヌ・ベイエ(バロック・ヴァイオリン)、パオロ・グラッツィ(バロック・オーボエ)、アルベルト・グラッツィ(バロック・ファゴット)、オーストリアン・バロック・カンパニー |
|
||
| DUX DUX-1805(1CD) |
フルーティッシマ~協奏曲集 ベンダ:フルート協奏曲ホ短調(カデンツァ:ミラン・ムンツリンゲル) メルカダンテ:フルート協奏曲ホ短調(カデンツァ:シルヴィア・クビアク=ドゥブロフスカ) |
シルヴィア・クビアク=ドゥブロフスカ(Fl)、 ウカシュ・ヴォヤコフスキ(指)、 シンフォニア・ノーヴァ・オーケストラ 録音:ヘンリク・デビク・コンサート・スタジオ(ヘンリク・デビク、ポーランド) |
|
||
| Phil.harmonie PHIL-06017(1CD) 【初紹介旧譜】 |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第9番&第19番 モーツァルト:ピアノ協奏曲第9番変ホ長調 KV 271 ピアノ協奏曲第19番ヘ長調 KV 459 |
クララ・ハスキル(P)、 カール・シューリヒト(指) シュトゥットガルトRSO 録音:1952年、1956年 |
|
||
| RUBICON RCD-1081(1CD) |
シンディング&メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 シンディング:ヴァイオリン協奏曲第1番イ長調 Op.45、 ロマンス ニ長調 Op.100 メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64 |
レア・ビリンガー(Vn)、 ヘルマン・ボイマー(指)ホーフSO |
|
||
| Goodies 78CDR-3858(1CDR) 税込定価 |
モーツァルト:ホルン協奏曲第2番変ホ長調 K.417 グラズノフ:夢 作品24 |
オーブリー・ブレイン(Hrn) ジョゼフ・バッテン(指) ロイヤルSO(モーツァルト) マリオン・ブレイン(P)(グラズノフ) 英 EDISON BELL X508/9 1926年頃録音 |
|
||
| Lyrita SRCD.405(1CDR) |
エレノア・アルベルガ(b.1949):ヴァイオリン協奏曲集 :ヴァイオリン協奏曲第2番「水仙」(2020)# ザ・ソウルズ・エクスプレッション(バリトンと弦楽オーケストラのための)(2017)* ヴァイオリン協奏曲第1番(2001)# |
BBCウェールズ・ナショナルO、 トーマス・ボウズ(Vn)#、 モーガン・パース(Br)*、 ジョセフ・スウェンセン(指) 録音:2021年2月19日-21日、ホディノット・ホール(イギリス) |
|
||
| DUX DUX-1690(1CD) |
モーツァルト:交響曲&二重奏曲集 協奏交響曲変ホ長調 K.364(Vc・パート編曲:マルチン・ズドゥニク) 二重奏曲第1番ト長調 K.423(Vc・パート編曲:マルチン・ズドゥニク) 交響曲第29番イ長調 K.201 |
マルチン・ズドゥニク(Vc)、 カロリナ・ノヴォトチンスカ(Vn)、 エルブロンク室内O、 マレク・モシュ(指) 録音:2020年10月3日-4日&2021年1月8日-10日、カジミエージュ・ヴィウコミルスキ国立音楽院コンサート・ホール(エルブロンク、ポーランド) |
|
||
| Signum Classics SIGCD-580(1CD) |
ガニング:協奏曲集 フルートとスモール・オーケストラのためのコンチェルティーノ クラリネットと弦楽オーケストラのための協奏曲 ギター協奏曲 「マヨルカの思い出」 |
クレイグ・オグデン(G)、 マイケル・ホワイト(Cl)、 キャスリン・ハンドリー(Fl)、 クリストファー・ガニング(指)ロイヤルPO 録音:2011年6月&2012年5月、イギリス |
|
||
| ONDINE ODE-1400(1CD) |
メンデルスゾーン:ピアノ協奏曲第1番 ト短調 Op. 25 ピアノ協奏曲第2番ニ短調 Op. 40 華麗なカプリッチョ ロ短調 Op. 22 |
ラルス・フォークト(P&指)パリ室内O 録音:2021年11月2-5日 |
|
||
| ORFEO C-220011(1CD) NX-B08 NYCX-10281(1CD) 日本語訳付国内盤 税込定価 |
トランペットとピアノのための協奏曲集 ショスタコーヴィチ:ピアノ協奏曲第1番ハ短調 Op. 35 ヴァインベルク:トランペット協奏曲 変ロ長調 Op. 94(1966-67) ジョリヴェ:トランペット、ピアノと弦楽のためのコンチェルティーノ ラフマニノフ:歌うなかれ、美しい人よ Op. 4 No. 4(トランペットとピアノ編) |
セリーナ・オット(Tp) マリア・ラドゥトゥ(P) ウィーンRSO ディルク・カフタン(指) 録音:2020年11月26-29日 |
|
||
| Altus ALT-503(1CD) |
INA秘蔵音源・ハスキル&クリュイタンス モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番ハ短調 K.491 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op.58 |
クララ・ハスキル(P) アンドレ・クリュイタンス(指) フランス国立放送O 録音:1955年12月8日(モノラル・ライヴ) |
|
||
| DOREMI DHR-8158(2CD) |
レオン・フライシャーLIVE 第1集 ブラームスの協奏曲 (1)ピアノ協奏曲第1番ニ短調 Op.15 (2)ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 Op.83 モーツァルトの協奏曲 (3)ピアノ協奏曲第23番イ長調 K.488 (4)ピアノ協奏曲第25番ハ長調 K.503 |
レオン・フライシャー(P) (1)82ピエール・モントゥー(指)ボストンSO (3)フレデリック・ワルトマン(指)ムジカ・エテルナO (4)ジョージ・セル(指)ベルリンPO ライヴ録音:(1)1958年7月20日タングルウッド (2)1962年8月11日タングルウッド (3)1964年11月22日ニューヨーク (4)1957年8月3日ザルツブルク音楽祭 |
|
||
| CPO CPO-555403(1CD) NX-B10 |
アウグスト・エベルハルト・ミュラー(1767-1817):
フルート協奏曲集 第2集 フルート協奏曲第5番ホ短調 Op. 19 フルート協奏曲第7番ニ短調 Op. 22 フルート協奏曲第8番ヘ長調 Op. 24 |
タチアーナ・ルーラント(Fl) 南西ドイツ・プフォルツハイム室内O ティーモ・ハンドシュ(指) 録音:2020年10月28-31日 |
|
||
| Channel Classics CCS-41222(1CD) |
『オランダ人の秘密の宝石』 ~20世紀オランダのヴィオラ作品 ヘンク・バディングス:ヴィオラ協奏曲 アルネ・ヴェークマン(1960-):パヴァーヌ ~ヴィオラと弦楽合奏のための ヤン・クーツィール(1911-2006):ヴィオラ協奏曲 バディングス:ヴィオラ・ソナタ ヘンリエッテ・ボスマンス(1895-1952):アリエッタ - ラルゴ |
ダナ・ゼムツォフ(Va) アンナ・フェドロヴァ(P) フィオンO(ヘルダーラント&オーファーアイセル) シズオ・Z・クワハラ(指) 録音:2021年3月エンスヘデ音楽センター&ヒルフェルスムMCO、オランダ |
|
||
| Coviello COV-92201(1CD) |
出発 ~モーツァルト作品集 歌劇『ルーチョ・シッラ』 序曲 K.135 ピアノ協奏曲第9番変ホ長調『ジュナミ』 K.271 交響曲第34番ハ長調 K.338 |
ヴァスコ・ダンタス(P) ダ グラス・ボ ストック(指) プフォルツハイム南西ドイツ室内O 録音:2021年 |
|
||
| Naive V-7422[NA] |
サン=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ ハバネラ Op.83 ヴァイオリン協奏曲第3番ロ短調 Op.61 ヴァイオリン協奏曲第1番イ長調 Op.20 ロマンス Op.48 「あなたの声にわが心は開く」~歌劇『サムソンとデリラ』より(ヘルツォーク編曲によるヴァイオリン、ヴィオラとオーケストラ版) |
チョ・ジンジョ(Vn)、 マテュー・ヘルツォーク(指) アパッショナ ート( オーケストラ) カロリーヌ・ドニン(Va) ン録音:2021年3月8-10日/RIFFXスタジオ、ブローニュ=ビヤンクール(フランス) |
|
||
| MIRARE MIR-590(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第14番変ホ長調K.449 ピアノと管弦楽のためのロンド ニ長調K.382 ピアノ協奏曲第12番イ長調K.414 |
セリム・マザリ(P) ポール・メイエ(指) マンハイム・プファルツ選帝侯室内O(マンハイム・チェンバー・オーケストラ) 録音:2021年3月16-19日/マンハイム・エピファニー教会 |
|
||
| DUX DUX-1791(1CD) |
シュテファン・ボレスワフ・ポラドフスキ(1902-1967):ヴァイオリン協奏曲 Op.70 コントラバス協奏曲 Op.26 交響曲第3番 Op.29 |
マルチン・スシツキ(Vn)、 ピオトル・チェルヴィンスキ(Cb)、 ウカシュ・ボロヴィチ(指)ポズナンPO |
|
||
| Etcetra KTC-1719(2CD) |
ユップ・フランセンス(b.1955):ピアノ作品集
CD1~ピアノ協奏曲 「ジャーニー・アンダー・ブリリアント・スカイズ(輝かしい空の下の旅)」(2020年版)* CD2 ~ 3つの練習曲(2019)、オールド・ソングズ, ニュー・ソングズ(1988) |
ラルフ・ファン・ラート(P)、 オットー・タウスク(指)*、 ヘルダーラント&オーファーアイセル・フィオン・オーケストラ* |
|
||
| ORFEO DOR C-220043(3CD) NX-C05 |
値下げ再発売! ベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集/合唱幻想曲 【CD1】 ピアノ協奏曲第1番ハ長調 Op. 15 ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 Op. 9 【CD2】 ピアノ協奏曲第3番ハ短調 Op. 37 ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op. 58 【CD3】 ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 Op. 73 合唱幻想曲 ハ短調 Op. 80 |
ルドルフ・ゼルキン(P) バイエルンRSO バイエルン放送cho ラファエル・クーベリック(指) 録音:ミュンヘン、ヘルクレスザール(ドイツ)…全てライヴ 1977年10月5日…CD1 1977年11月4日…CD2 1977年10月30日…CD3 ※旧品番:ORFEOR-647053 |
|
||
| Gramola GRAM-99245(1CD) |
ラプソディ・イン・ブルー ガーシュウィン:ラプソディ・イン・ブルー ピアノ協奏曲 へ調 ダニエル・ムック(1990-):ピアノ協奏曲(2020)…世界初録音 |
カール・アイヒンガー(P) ブルノPO ルーカス・ダンヘル(Cl) ヤン・ブローダ(Tp) カスパー・リヒター(指) 録音:2021年5月4-7日 |
|
||
| ALPHA ALPHA-627(1CD) NYCX-10279(1CD) 国内盤仕様 税込定価 |
エサ=ペッカ・サロネン(1958-):チェロ協奏曲 ラヴェル:ヴァイオリンとチェロのためのソナタ* |
ニコラ・アルトシュテット(Vc) ペッカ・クーシスト(Vn) ロッテルダムPO ディーマ・スロボデニューク(指) 録音:2018年12月、2019年10月* ロッテルダム・フィルハーモニック ※国内盤日本語解説…片桐卓也 |
|
||
| DB Productions DBCD-202(1CD) |
ブラームス/レントヘン/アマンダ・レントヘン=マイエル:
ヴァイオリン協奏曲集 アマンダ・レントヘン=マイエル(1853-1894):ヴァイオリン協奏曲 ニ短調* ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op. 77 ユリウス・レントヘン:ヴァイオリン協奏曲 嬰ヘ短調 |
セシリア・シリアクス(Vn) ヴェステロース・シンフォニエッタ* マルメSO クリスティーナ・ポスカ(指) 録音:2018年8月14-17日、2021年9月30日、10月1日 |
|
||
| BIS BISSA-2620(1SACD) |
ニールセン:ヴァイオリン協奏曲 Op.33 FS 61 シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.47 |
ユーハン・ダーレネ(Vn)、 ヨーン・ストルゴーズ(指)、 ロイヤル・ストックホルムPO 録音:2021年6月7-10日/ストックホルム・コンサートホール(スウェーデン) |
|
||
| Glossa GCD-923530(1CD) |
ヴィヴァルディ:フルート協奏曲集 協奏曲第2番ト短調 RV.439 「夜」/協奏曲第3番ニ長調 RV.428 「ごしきひわ(イル・ガルデッリーノ)」/協奏曲第1番ヘ長調 RV.433 「海の嵐」/協奏曲第6番ト長調 RV.437/協奏曲第5番ヘ長調 RV.434/協奏曲第4番ト長調 RV.435 |
カルロ・イパタ(Fl&指揮)、 アウセル・ムジチ 録音:2020年11月13日-17日、サン・ドメニコ教会(ピサ、イタリア) |
|
||
| CLAVES 50-3039(2CD) |
ベートーヴェン:「シュテファン王」序曲 ピアノ協奏曲第3番ハ短調Op.37 シチェドリン:カルメン組曲(ビゼーの原曲による) |
ミハイル・プレトニョフ(P) ※ Kawai SK-EX使用 ガーボル・タカーチ=ナジ(指) ジュネーヴ室内O 録音:2021年3月2日/ヴィクトリア・ホール(ジュネーヴ)(ライヴ) |
|
||
| Alba ABCD-463(1CD) |
ペーテリス・ヴァスクス(1946-):チェロ協奏曲第2番「存在すること」(2011-12) ヴィオラと弦楽オーケストラの為の協奏曲(2014-15) |
マルコ・ユロネン(Vc) リッリ・マイヤラ(Va) タリン室内O ユハ・カンガス(指) 録音:2020年1月17日?22日 ブラックヘッド会館ホワイト・ホール(Mustapeade Maja, Valge saal)(タリン、エストニア) |
|
||
| TCO TCO-0003(1CD) |
シュニトケ:ピアノと弦楽の為の協奏曲(1979) プロコフィエフ:交響曲第2番ニ短調 op.40 |
フランツ・ウェルザー=メスト(指) クリーヴランドO、 イェフィム・ブロンフマン(P) 録音:2020年10月15-17日クリーヴランド・セヴェランス・ホール(無観客ライヴ配信用録音) 2020年1月17,18日マイアミ・ナイト・コンサート・ホール*/ エイドリアン・アルシュト・センター・フォー・ザ・パフィーミング・アーツ(ライヴ録音) |
|
||
| SWR music SWR-19113CD(2CD) NX-C09 |
モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲全集 【CD1】 ヴァイオリン協奏曲第1番変ロ長調 K. 207 ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調 K. 216 ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調 K. 218 ヴァイオリン協奏曲第2番ニ長調 K. 211 アダージョ ホ長調 K. 261 ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 K. 219 ロンド ハ長調 K. 373 |
ギル・シャハム(Vn) 南西ドイツRSO ニコラス・マギーガン(指) 録音:2018年5月14、15日、2019年5月6-10日 |
|
||
| Capriccio C-5463(1CD) NX-B05 |
エルンスト・フォン・ドホナーニ: 童謡の主題による変奏曲
Op. 25 他 童謡の主題による変奏曲 Op. 25(1913/14) ハープと室内オーケストラのための小協奏曲Op. 45(1952) コンツェルトシュテュック Op. 12 - チェロとオーケストラのための(1903/04) |
ソフィア・ギュリバダモヴァ(P) シルケ・アイヒホルン(Hp) アンドレイ・イオニーツァ(Vc) ラインラント=プファルツ州立PO モデスタス・ピトレナス(指) 録音 2021年5月31日-6月2日、6月4日 |
|
||
| BR KLASSIK BR-900638(1CD) NX-B05 |
オンドレイ・アダーメク作品集 Follow me(2016/17) - ヴァイオリンと管弦楽のための協奏曲* バイエルン放送とヘルシンキPO、musica vivaの委嘱作品 WHERE ARE YOU?(2020) - メゾ・ソプラノとオーケストラのために バイエルン放送とロンドンSO、musica vivaの委嘱作品 |
イザベル・ファウスト(Vn)* バイエルンRSO* ペーター・ルンデル(指)* マグダレーナ・コジェナー(Ms) バイエルンRSO サイモン・ラトル(指) 録音(ライヴ):2017年12月15日ミュンヘン、ヘルクレスザール(ドイツ)*、2021年3月6日ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ドイツ) 共に、世界初演 |
|
||
| CD ACCORD ACD-281(1CD) NX-D01 |
パヴェウ・ミキェティン(1971-):チェロ協奏曲第2番 オスカル・ダヴィツキへのオマージュ |
マルチン・ズドゥニク(Vc) バセム・アキキ(指) ベンヤミン・シュヴァルツ(指) 録音:2020年8月19-20日、2016年4月13-14日 |
|
||
| ACCENTUS Music ACC-10555BD(Bluray) ACC-0555DVD(DVD) |
バッハ:ブランデンブルク協奏曲(全6曲)BWV 1046-1051 | ヴァーツラフ・ルクス(指) コレギウム1704 収録:2021年6月、ケーテン城「鏡の間」 ◆Bluray 画面:16:9、Full HD 音声:DTS HD MA5.1、PCM STEREO BD25 リージョン:All、96'28 ◆DVD 画面:16:9、NTSC 音声:DTS 5.1、DD5.1、PCM STEREO DVD9 リージョン:All、96'28 |
|
||
| DOREMI DHR-8156(2CD) |
アイザック・スターンLIVE 第11集 (1)ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 (2)ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 (3)「1985年トロント・リサイタル」 ブラームス:F.A.E.ソナタ 第3楽章 スケルツォ モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ ホ短調 K.304 バッハ:無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第1番 ロ短調 BWV1002 フォーレ:ヴァイオリン・ソナタ第1番イ長調 Op.13 バルトーク:ルーマニア民俗舞曲 シマノフスキ:詩曲『神話』~「アレトゥーサの泉」 Op.30-1 ラヴェル:ヴァイオリン・ソナタ ト長調より 第3楽章「無窮動」 |
アイザック・スターン(Vn) (1)ヴィトルト・ロヴィツキ(指) ◇ワルシャワPO ◇ライヴ録音:1966年6月3日 (2)ウィリアム・スタインバーグ(指) ◇フランス国立放送O ◇ライヴ録音:1960年6月28日シャンゼリゼ劇場 (3)ポール・オストロフスキー(P) ◇ライヴ録音:1985年3月5日トロント、ロイ・トムソン・ホール |
|
||
| NIFC NIFCCD-638(1CD) |
ブルース・リウ~第18回ショパン国際ピアノ・コンクール・ライヴ ショパン:バラード第2番ヘ長調 Op.38 マズルカ風ロンド Op.5 ピアノ・ソナタ第2番「葬送」 ピアノ協奏曲第1番ホ短調 Op.11* |
ブルース・リウ(P)、 アンドレイ・ボレイコ(指)ワルシャワPO* 録音(ライヴ):2021年10月3日-20日、ワルシャワ・フィルハーモニー・コンサート・ホール(ワルシャワ、ポーランド) |
|
||
| RUBICON RCD-1075(1CD) |
ベートーヴェン:三重協奏曲 ピアノ、ヴァイオリン、チェロの為の三重協奏曲 ハ長調 Op.56、「私は仕立屋カカドゥ」によるピアノ三重奏の為の変奏曲 Op.121a ヴォジーシェク:ピアノ、ヴァイオリン、チェロの為のグランド・ロンド・コンチェルタンテ Op.25 |
ロプコヴィッツ・トリオ〔ヤン・ムラーチェク(Vn)、イヴァン・ヴォカッチ(Vc)、ルーカス・クランスキー(P)〕、ヤナーチェクPO、ペトル・ポペルカ(指) |
|
||
 Altus ALT-507(1CD) |
INA秘蔵音源・ギレリス&クリュイタンス・フランス国立管ライヴ リール(ベルリオーズ編):ラ・マルセイエーズ チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 【アンコール】バッハ(シロティ編):前奏曲 ロ短調 BWV855a |
エミー ル・ギレリス(P) フランス放送cho アンドレ・クリュイタンス(指) フランス国立放送O ライヴ録音:1959年6月19日/パリ、シャンゼリゼ劇場(ステレオ) |
|
||
| Profil PH-21052(1CD) |
(1)チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.35 (2)グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調Op.82 |
イワン・ポチェーキン(Vn) ミハイル・プレトニョフ(指)ロシア・ナショナルO 録音:2020年8月29、30日/チャイコフスキー・コンサートホール(モスクワ) |
|
||
 Audite AU-95650(1CD) |
正規初出!ルツェルン・フェスティヴァル・シリーズ第17弾 (1)バッハ:2台のチェンバロの為の協奏曲第2番 ハ長調 BWV 1061 (2)バルトーク:ピアノ協奏曲第2番BB 101 (3)バルトーク:ピアノ協奏曲第3番BB 127 |
全て、ゲザ・アンダ(P)、ルツェルン祝祭O (1)クララ・ハスキル(P)、ヘルベルト・フォン・カラヤン(指) (2)フェレンツ・フリッチャイ(指) (3)エルネスト・アンセルメ(指) ライヴ録音:(1)1955年8月、(2)1956年8月22日、(3)1965年8月25日/クンストハウス、ルツェルン(モノラル) |
|
||
| ANIMAL MUSIC ANI-102(1CD) |
パウエル:ホルン協奏曲(1957) グリエール:ホルン協奏曲 変ロ長調 Op.91 |
ラデク・バボラーク(Hrn) トマーシュ・ブラウネル(指)プラハSO 録音:2021年4月14&15日/スメタナホール(プラハ市民会館) |
|
||
| スリーシェルズ 3SCD-0067(1CD) 税込定価 |
伊福部昭:ヴァイオリン協奏曲第2番 (1)初演 (2)試演 (3)ピアノリダクション版 【ボーナス・トラック】 (4)伊福部昭の完売の挨拶~第43 回芸術祭(文化庁芸術祭)賞(音楽部門)の受賞を祝う会より |
小林武史(Vn) (1)ズデニェック・コシュラー(指)チェコ国立ブルノPO (2)三石精一(指)オーケストラ不詳 (3)ピアニスト不詳 録音:(1)1979 年3 月8 日Besedni dum ホー ル(チェコ) (2)1979 年初頭(?)東京音楽大学内 (3)1979 年初頭(?) (4)1989 年2 月5 日高輪クラブ |
|
||
| ALBANY TROY-1880(1CD) |
「イルミネーション」~ヴィクトリア・ボンド(b.1945):ピアノ作品集
(1)「ビザンチンの歌による幻影」(2021) (2)「古代の鍵」(2002)~ピアノと管弦楽の為の (3)「黒い光」(1997)~ピアノと管弦楽の為の (4)「ビザンチンの歌」(伝承歌)~独唱 |
ポール・バーンズ(Pf、歌) (2)(3)カーク・トレバー指揮 (2)スロヴァキアRSO (3)ボフスラフ・マルティヌー・フィル 録音:(1)(4)2021年5月ネブラスカ、(2)1997年、(3)2003年 |
|
||
| Urania Records WS-121387(2CD) |
リヒテル~モーツァルト:ピアノ協奏曲集 (1)ピアノ協奏曲第9番変ホ長調 K.271「ジュノム」 (2)ピアノ協奏曲第20番ニ短調 K.466 (3)ピアノ協奏曲第22番変ホ長調 K.482 |
スヴャトスラフ・リヒテル(P)、 (1)フランス国立放送O、ロリン・マゼール(指) 録音:1966年7月3日 (2)ソヴィエト国立SO、カルル・エリアスベルク(指) 録音:1950年 (3)イギリス室内O、ブリテン 録音:1967年6月13日&1965年6月16日 ※STEREO録音/ADD ※リマスタリング:ノエミ・マンゾーニ&ウラニア・レコーズ |
|
||
| Urania Records LDV-14067(1CD) |
ヴィヴァルディ:協奏曲とソプラノのためのアリア集 ヴァイオリン協奏曲ニ長調 RV.208「ムガール大帝」 ヴァイオリン協奏曲ニ長調 RV.234「不安」 リュート協奏曲ニ長調 RV.93 ヴィオラ・ダモーレ協奏曲ニ長調 RV.392 ヴィオラ・ダモーレ協奏曲ニ短調 RV.394 オラトリオ「勝利のユディタ」RV.644より 歌劇「ユスティヌス」RV.717より |
トゥリア・ペデルソリ(S)、 ダヴィデ・ベロシオ(Vn)、 マウロ・リギーニ(ヴィオラ・ダモーレ)、 マッシモ・マルケーゼ(Lute)、 イ・ソリスティ・アンブロジアーニ 録音:2020年7月8日-10日、ブスト・アルシツィオ(イタリア) |
|
||
| フォンテック FOCD-9863(1CD) FOCD9863 税込定価 2021年12月22日発売 |
モーツァルト:ホルン協奏曲集 ホルン協奏曲第1番 ニ長調 K.412+K.51(386b) (ジュスマイヤー補筆版) ホルン協奏曲 第4番 変ホ長調 K.495 ホルン協奏曲 第2番 変ホ長調 K.417 ホルン協奏曲 第3番 変ホ長調 K.447 協奏風ロンド 変ホ長調 K.371(レヴィン補筆・校訂版) |
濵地宗(Hrn) 鈴木秀美(指)群馬SO 録音:2021 年7 月30 日 高崎芸術劇場 ライヴ |
|
||
| CPO CPO-555509(3CD) NX-D03 |
ブルッフ:ヴァイオリンとオーケストラの為の作品全集 【CD1】 ヴァイオリン協奏曲第2番ニ短調 Op. 44 スコットランド幻想曲 Op. 46 アダージョ・アパッショナート Op. 57 【CD2】 ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調 Op. 26 セレナード イ短調 Op. 75 イン・メモリアム Op. 65 【CD3】 ヴァイオリン協奏曲第3番ニ短調 Op. 58 コンツェルトシュテュック 嬰ヘ短調 Op. 84 ロマンス イ短調 Op. 42 |
アンチェ・ヴァイトハース(Vn) 北ドイツ放送PO ヘルマン・ボイマー(指) 録音:2013年6月24-28日…CD1 2014年3月31日-4月4日…CD2 2015年2月24-27日…CD3 |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00768(1SACD) 税込定価 2021年12月22日発売 |
バルトーク:ヴァイオリン協奏曲 第1番ニ長調 BB48a、Sz.36 ヴァイオリン協奏曲 第2番BB117、Sz.112* |
豊嶋 泰嗣 (Vn) 井上 道義(指)、 上岡敏之(指)* 新日本フィルハーモニーSO 録音:2021年4月16-17日、2018年3月30-31日*、東京・すみだトリフォニーホール ・ライヴ |
|
||
| KKE Records KKE-001(1CD) |
クルト・アルブレヒト(1895-1971):作品集 ヴァイオリンとピアノの為のシャコンヌ Op.33#(Dr. K. Kremersのモティーフに基づく)、 弦楽とティンパニの為の交響曲、 室内オーケストラの為のパルティータ(シュッツの「ルカ受難曲」のモティーフに基づく) |
グスタフ・フリーリングハウス(Vn#、指揮)、 ヤーン・オッツ(P)#、 ハンブルク・カメラータ 録音:2017年~2019年、ドイツ |
|
||
| La Dolce Volta LDV-94(1CD) |
ブラームス:ピアノ協奏曲第1番ニ短調 作品15 バッハ/ブラームス編)):左手のためのシャコンヌ(原曲/ バッハ:ヴァイオリン・パルティータ第2番 ニ短調 BWV 1004~「シャコンヌ」) |
ジョフロワ・クトー(P) ダヴィド・レイラン(指)メス国立O 録音:2020年12月2-5日(協奏曲)、2021年1月2-3日(シャコンヌ) 日本語帯・解説付 |
|
||
| LSO Live LSO-0855(2SACD) |
モーツァルト:管楽のための作品集 ホルン協奏曲 変ホ長調 K417 オーボエ協奏曲 ハ長調 K314 クラリネット協奏曲 イ長調 K622 協奏交響曲 変ホ長調 K297b セレナード第10番「グラン・パルティータ」 |
ハイメ・マルティン(指) ティモシー・ジョーンズ(Hrn)、 オリヴィエ・スタンキエヴィチ(Ob)、 アンドルー・マリナー(Cl)、 ジュリアナ・コッホ(Ob)、 クリス・リチャーズ(Cl)、 レイチェル・ゴフ(Fg)、 LSO木管アンサンブル、LSO 録音:2019年10月12-13日(K417,314,622,297b)、2015年10月31日(K361)/ジャーウッド・ホール(セント・ルークス) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2252(1CD) |
ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61 | ダヴィッド・オイストラフ(Vn) アンドレ・クリュイタンス(指)、 フランス国立放送局O 録音:1958年11月8-10日サル・ワグラム(パリ)【ステレオ】 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) |
|
||
| Da Vinci Classics C-00462(1CD) |
ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番ニ短調 Op.30* 舟歌ト短調 Op.10-3 クライスラーの「愛の悲しみ」に基づくパラフレーズ |
ピエトロ・ベルトラーニ(P)、 センツァスピーネO*、 トンマーゾ・ウッサルディ(指)* 録音:2019年12月5日(ライヴ)、テアトロ・アウディトリウム・マンゾーニ(ボローニャ、イタリア)*、2020年5月、ファビオ・アンジェレッティ・スタジオ(イモラ、イタリア) |
|
||
| Chandos CHSA-5298(1SACD) |
マリウス・ネセット(b.1985):マンメイド(人工の)(2019) ~ サクソフォンとシンフォニー・オーケストラの為の協奏曲*〔1.
創造、2. エジソン、3. アポロ、4. ノーベル、5.
新しい創造〕 ウインドレス(風がなくなる)(2017) ~ サクソフォンとオーケストラの為の# エヴリ・リトル・ステップ(すべての小さな一歩)(2020-21) ~ オーケストラの為の〔7. 認識する、8. 動き、9. 高く高く〕 ア・デイ・イン・ザ・スパロウズ・ライフ(スズメの一生における一日)(2016-17) ~ サクソフォンとオーケストラの為の+ |
マリウス・ネセット(ソプラノ・サクソフォン*+、テナー・サクソフォン*#+)、 エドワード・ガードナー(指)ベルゲンPO 録音:2021年6月14日-17日、グリーグホール(ベルゲン、ノルウェー) ※「ア・デイ・イン・ザ・スパロウズ・ライフ」はオーケストラ版世界初録音。残り3曲はすべて世界初録音。 |
|
||
| Paladino Music PMR-0089(1CD) |
ウェーバー&ブルッフ:クラリネット、ヴィオラと管弦楽の為の作品集 ウェーバー:クラリネット小協奏曲 Op.26、 ヴィオラと管弦楽の為の「アンダンテとハンガリー風ロンド」 Op.35 ブルッフ:クラリネット.ヴィオラと弦楽オーケストラの為の「ルーマニアの旋律とスケルツォ」 Op.83(「8つの小品」より、セルゲイ・エフトゥシェンコ編)、 ヴィオラと管弦楽の為のロマンス Op.85、 クラリネット,ヴィオラと管弦楽の為の二重協奏曲 Op.88 |
ディミトリ・アシュケナージ(Cl)、 アントン・ホロデンコ(Va)、 ロイヤル・バルテイック祝祭O、 マッツ・リリエフォシュ(指) 録音:1995年6月&8月、スウェーデン王立音楽大学コンサート・ホール(スウェーデン、ストックホルム) |
|
||
 NIFC NIFCCD-637(1CD) |
第7回ショパン国際ピアノ・コンクール・ライヴ
~ ショパン:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲第1番ホ短調 Op.11* ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 Op.21** |
マルタ・アルゲリッチ(P)*、 アルトゥール・モレイラ・リマ(P)** ヴィトルト・ロヴィツキ(指)、ワルシャワPO 録音:1965年3月13日、ワルシャワ・フィルハーモニー・コンサート・ホール(ポーランド) |
|
||
| Goodies 78CDR-3853(1CDR) 税込定価 |
モーツァルト:フルートとハープの為の協奏曲ハ長調 K.299(297c) | リリー・ラスキーヌ(Hp) ルネ・ル・ロワ(Fl) サー・トーマス・ビーチャム(指) ロイヤルPO 英 HMV DB6485/7 (1947年3月11-12日録音) |
|
||
| Ars Produktion ARS-38167(1SACD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲集 モーツァルト:ピアノ協奏曲第12番 イ長調 KV414 ホルツバウアー(1711-1783):交響曲 変ホ長調 Op.4-3 モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番 イ長調 KV488 |
マテア・レコ(P)、 プファルツ選帝候室内O、 ヨハネス・シュレーフリ(指) 録音:2014年3月3日-5日 |
|
||
| Aulicus Classics ALC-0011(1CD) |
フランツ・クサーヴァー・ヴォルフガング・モーツァルト:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲集第1番ハ長調 Op.14 ピアノ協奏曲第2番変ホ長調 Op.25 |
オルガ・ズドレンコ(P)、 コレギウム・ムジクム室内O、 イヴァン・オスタポヴィチ(指) 録音:2017年2月25日、レオポリー・ナショナル・フィラルモニア(ウクライナ) |
|
||
| Simax PSC-1371(1CD) |
チャイコフスキー:弦楽セレナードOp.48ハ長調 クラッゲルード:ラグナロク~太陽の娘 チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲Op.35ニ長調 |
ヘンニング・クラッゲルード(Vn) アークティック・フィルハーモニック クリスチャン・クルクセン(指) |
|
||
| Simax PSC-1363(1CD) |
チャイコフスキー:ロココ風の主題による変奏曲(オリジナル版) ドヴォルザーク:チェロ協奏曲ロ短調Op.104 |
サンドラ・リード・ハーガ(Vc) 使用楽器:Joannes Florenus Guidantus, Bologna, 1730(Dextra Musicaより貸与) ロシア国立SO(スヴェトラーノフ・オーケストラ) テリエ・ミケルセン(指) 録音:2019年2月20.21日、3月1日、モスクワ音楽院大ホール |
|
||
| GWK CLCL-129(1CD) |
C.P.E.バッハ:チェロ協奏曲集 チェロ協奏曲 イ長調 Wq172、 チェロ協奏曲 イ短調 Wq170、 チェロ協奏曲 変ロ長調 Wq171 |
コンスタンチン・マナーエフ(Vc)、 ベルリン・カメラータ 録音:2014年4月28日-5月1日 |
|
||
| Ars Produktion ARS-38158(1SACD) |
フルートとハープの為の協奏曲集 ヘンツェ:C.P.E.バッハへの想い(1982) C.P.E.バッハ:フルート協奏曲 ニ短調 Wq.22(1747) モーツァルト:フルートとハープの為の協奏曲 ハ長調 K.299(1778) |
マリア・セシリア・ムニョス(Fl)、 サラ・オブライエン(Hp)、 バーゼル室内O 録音:2014年3月7日-9日 |
|
||
| Ars Produktion ARS-38301(1SACD) |
チェロと管弦楽の為の作品集 ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104 カプレ:悟り Op.22 |
ナデージュ・ロシャ(Vc)、 ロイヤル・スコティッシュ・ナショナルO、 バンジャマン・レヴィ(指) 録音:2019年11月14日-16日 |
|
||
| RUBICON RCD-1053(1CD) |
インフィニット・バッハ~バッハ・リコンポーズド・バイ・ユーハン・ウッレン 原曲=バッハ:ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 BWV.1042 ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 BWV.1041 チェンバロ協奏曲ニ短調 BWV.1052 チェンバロ協奏曲ト短調 BWV.1056 |
クリスチャン・スヴァルヴァール(Vn) ユーハン・ウッレン(指)LPO |
|
||
| PHIL.harmonie PHIL-06003(1CD) |
ヴィヴァルディ:協奏曲集 オーボエとヴァイオリンの為の協奏曲 変ロ長調 RV548、 チェロ協奏曲 ロ短調 RV424、 ヴィオラ・ダモーレの為の協奏曲 イ短調 RV397、 協奏曲集「四季」Op.8 |
ヨナタン・ケリー(Ob)、 ライナー・クスマウル(Vn)、 ゲオルク・ファウスト(Vc)、 ヴォルフラム・クリスト(ヴィオラ・ダモーレ)、 ベルリン・バロック・ゾリステン 録音:1998年9月、2004年6月、2009年9月 |
|
||
| PHIL.harmonie PHIL-06008(1CD) |
コントラバス協奏曲集 ディッタースドルフ:ヴァイオリン協奏曲 第1番変ホ長調(コントラバス版) ホフマイスター:ヴァイオリン協奏曲 第1番変ホ長調(コントラバス版) ヴァンハル:コントラバス協奏曲 変ホ長調 |
エディクソン・ルイス(Cb)、 クリスティアン・ヴァスケス(指)、 シモン・ボリバルSO 録音:2009年10月 |
|
||
| LAWO Classics LWC-1222(1CD) |
ブルッフ、ヴォーン・ウィリアムズ、バーバー
ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番ト# ヴォーン・ウィリアムズ:揚げひばり# バーバー:ヴァイオリン協奏曲 Op.14* |
園子ミリアム・ヴェルデ(Vn)、 タビタ・ベルグルンド(指)#、 ジョシュア・ワイラースタイン(指)*、 オスロPO 録音:2019年2月14日-15日*&2020年10月26日-28日#、オスロ・コンサート・ホール(ノルウェー) |
|
||
| ACCENTUS Music ACC-70551DVD(3DVD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番~第5番 (1)ピアノ協奏曲第1番ハ長調op.15 (2)ピアノ協奏曲第2番変ロ長調op.19 (3)ピアノ協奏曲第3番ハ短調op.37 (4)ピアノ協奏曲第4番ト長調op.58 (5)ピアノ協奏曲第5番変ホ長調op.73「皇帝」 |
マルガリータ・ヘーエンリーダー(ピアノ) (1)ファビオ・ルイージ(指)シュターツカペレ・ドレスデン/収録:2008年、ミュンヘン、フィルハーモニー・ガスタイク (2)レオン・フライシャー(指)アマデ室内フィルハーモニー/収録:2014年9月9日、エッセン、ツォルフェアアイン炭鉱業遺産群 (3)レオン・フライシャー(指)ハイルブロン・ヴュルテンベルク室内O/収録:2015年10月14日、バート・キッシンゲン、マックス・リットマン・ザール (4)マルティン・ハーゼルベック(指)バンベルクSO/収録:2018年、コンツェルトハレ、バンベルク (5)ブルーノ・ヴァイル(指)バイエルン国立O/収録:2020年プリンツレーゲンテン劇場、ミュンヘン 画面:NTSC,16:9 音声:PCMステレオ、DD5.1、DTS5.1 字幕:独英仏西韓,日本語 |
|
||
| NAXOS NYCX-57416(1CD) 税込定価 |
大澤壽人(1906-1953):ピアノ協奏曲「神風協奏曲」 交響曲第3番 |
エカテリーナ・サランツェヴァ(P) ドミトリ・ヤブロンスキー(指)ロシアPO 録音:2003年10月モスクワ、TV&ラジオ・カンパニー「カルチャー」大コンサート・スタジオ第5 |
|
||
| GRAND SLAM GS-2250(1CD) |
(1)チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番変ロ短調 Op.23 (2)ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番ハ短調 Op.18 |
スヴャトスラフ・リヒテル(P) (1)ヘルベルト・フォン・カラヤン(指)ウィーンSO (2)スタニスワフ・ヴィスロツキ(指)ワルシャワPO 録音:(1)1962年9月24-26日ムジークエラインザール(ウィーン) (2)1959年4月26-28日フィルハーモニー(ワルシャワ) 使用音源:Private archive(2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:ステレオ(録音セッション) |
|
||
| H.M.F HMM-902422(1CD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番ト長調 op.58〔ウィーン楽友協会所有、手稿譜
A 82 b, 1808年〕 ピアノ協奏曲「第6番」 ニ長調 op.61a〔ベートーヴェン自身による、ヴァイオリン協奏曲 op.61のピアノ編曲版〕 |
ジャンルカ・カシオーリ(P) アンサンブル・レゾナンツ、リッカルド・ミナージ(指) 録音:2019年11月 |
|
||
| Avie AV-2485(1CD) |
ヴィヴァルディ:四季 協奏曲ホ長調 Op.8-1 「春」/協奏曲ト短調 Op.8-2 「夏」/協奏曲ヘ長調 Op.8-3 「秋」/協奏曲ヘ短調 Op.8-4 「冬」/合奏協奏曲 「ラ・フォリア」*(ジャネット・ソレル編曲/原曲:ソナタ ニ短調 RV.63) |
アポロズ・ファイア、ジャネット・ソレル(指)、 フランシスコ・フラナ(Vn)、 アラン・チュー(Vn)* 録音:2021年4月15日-17日、エイボン・レイク・キリスト合同教会(アメリカ |
|
||
| KAIROS 0013242KAI(1CD) |
チェルハ:打楽器協奏曲/インパルス* | マルティン・グルービンガー(打楽器)、 ペーター・エトヴェシュ(指)、 ピエール・ブーレーズ(指)* VPO 録音(ライヴ):2011年11月25日、ウィーン・コンツェルト・ハウス&1996年8月15日、ザルツブルク祝祭大劇場音楽祭 |
|
||
| Biddulph BIDD-85007(1CD) |
ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.77 | オスカー・シュムスキー(Vn) フィルハーモニア・フンガリカ ウリ・セガル(指) 録音:1984年、マール(ドイツ) デジタル録音 |
|
||
| DOREMI DHR-8120(1CD) |
オレク・カガン&ナターリヤ・グートマン
ライヴ集 (1)ブラームス:ヴァイオリンとチェロの為の二重協奏曲 (2)ショスタコーヴィチ:チェロ協奏曲第1番 |
(1)オレク・カガン(Vn)、ナターリヤ・グートマン(Vc)、 エフゲニー・スヴェトラーノフ(指)ロシア国立SO (2)ナターリヤ・グートマン(Vc)、 アレクサンドル・ラザレフ(指)オランダ放送PO 録音:(1)1986年10月12日トロント、ロイ・トムソン・ホール、 (2)1980年1月26日アムステルダム |
|
||
| BIS BISSA-2426 (1SACD) |
カレヴィ・アホ(1949-):コールアングレ、ハープと管弦楽の為の二重協奏曲(2014) ヴァイオリン、チェロ、ピアノと室内管弦楽の為の三重協奏曲(2018)* |
(1)ディミトリー・メストダグ(コールアングレ) (1)アンネレーン・レナエルツ(Hp) (2)ストリオーニ三重奏団*【ヴァウテル・フォッセン(Vn)、マルク・フォッセン(Vc)、バルト・ファン・デア・ルール(P)】 アントワープSO、オラリ・エルツ(指) 録音:2019年6月25?28日エリザベートホール(アントワープ、ベルギー) [使用楽器:Cor anglais:Buffet Crampon, semi-automatic,-12547/Harp:Camac, type Oriane/ |
|
||
| FUGA LIBERA FUG-790(1CD) |
ピアソラ:バンドネオン協奏曲 「アコンカグア」 タンガーソ 「ブエノスアイレス変奏曲」(ウィリアム・サバティエ編) バンドネオンとピアノの為の二重協奏曲 「リェージュに捧ぐ」 (エミリアーノ・グレコ ピアノ・パート編) オブリビオン(忘却) |
ウィリアム・サバティエ(バンドネオン) エミリー・アリドン=コチョウェク(P) ディジョン・ブルゴーニュO レオナルド・ガルシア・アラルコン(指) 録音:2021年5月17-20日 オーディトリアム・ド・ディジョン、フランス |
|
||
| ORFEO C-210041(1CD) NX-B08 |
ヒンデミット:クラリネットの為の作品集 クラリネット協奏曲(1947) クラリネット四重奏曲(1938) クラリネット・ソナタ(1939) |
シャロン・カム(Cl) アンチェ・ヴァイトハース(Vn) ユリアン・シュテッケル(Vc) エンリコ・パーチェ(P) フランクフルトRSO ダニエル・コーエン(指) 録音:2021年3月1-3日、2020年10月25-27日 |
|
||
| DACAPO MAR-6.220665 (1SACD) |
イブ・グリンデマン(1934-2019):協奏曲集 コンチェルト - トランペットとオーケストラの為の(1962) コンチェルト- トロンボーンとオーケストラの為の(2017)…世界初録音 メドレー(2020)…世界初録音 Stroget / The Little Mermaid / Adam’s Theme / Take Off (イブ・グリンデマン&ヴォルフガング・ケファー編) |
ペア・モーテン・ビー(Tp) ロベルト・ホルムステッド(Tb) オーデンセSO ジョルダーノ・ベッリンカンピ(指) 録音:2019年5月20-23日 |
|
||
| GRAND SLAM GS-2248(1CD) |
リスト:ピアノ協奏曲第1番 ピアノ協奏曲第2番 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番* |
スヴャトスラフ・リヒテル(P) キリル・コンドラシン(指)LSO シャルル・ミュンシュ(指)ボストンSO* 録音:1961年7月19-21日ウォルサムストウ・アセンブリー・ホール(ロンドン) 1960年11月2&3日シンフォニーホール(ボストン) * 録音方式:ステレオ(録音セッション) |
|
||
| MELODIYA MEL-1002662(2CD) NX-C01 |
マリス・ヤンソンス モスクワでのラスト・コンサート アレクサンドル・チャイコフスキー(1946-):ヴィオラ、独奏ピアノと管弦楽の為の協奏曲第2番 「シンプル・トーンによるエチュード」(ユーリ・バシュメットに捧げる) 2台ピアノと管弦楽の為の協奏曲 op.70 交響曲第4番- オーケストラ、合唱と独奏ヴィオラのために ティホン・フレンニコフの思い出の為のエレジー ワルツ |
ユーリ・バシュメット(Va) クセニア・バシュメット(P) ボリス・ベレゾフスキー(P) ダリア・チャイコフスカヤ(P) ユルロフ・カペラcho モスクワPO マリス・ヤンソンス(指) 録音:2016年3月29日 ライヴ収録 チャイコフスキー・コンサート・ホール(ロシア) |
|
||
| CPO CPO-555421(1CD) NX B02 |
ルドミル・ルジツキ:ヴァイオリン協奏曲 他 ヴァイオリン協奏曲 Op. 70(1944) 2つのメロディ Op. 5? ヴァイオリンとピアノの為の 2つの夜想曲 Op. 30 ? ヴァイオリンとピアノの為の バレエ「パン・トファルドフスキ」 Op. 45からのトランスクリプション集-ヴァイオリンとピアノの為の |
エヴェリナ・ノヴィツカ(Vn) ポーラ・ラザール(P) ミハウ・クレンジレフスキ(P) ポーランド国立RSOカトヴィツェ ジグムント・リヒェルト(指) 録音:2001年2月、2010年7月 |
|
||
| NCA NCA-9601815(1CD) 【初紹介旧譜】 |
ヘンツェ:ギター作品集 ハンス・ヴェルナー・ヘンツェ(1926-2012):王宮の冬の音楽(1979)、 カリヨン,レシタティーフ,マスク(1974)、 An eine Aolsharfe(1985/86) |
ザビーネ・エーリング(G)、 ブラッハー・アンサンブル、 フリードリヒ・ゴルトマン(指) 録音:1995年9月21日、11月16日-17日、SFBホールⅢ |
|
||
| Solo Musica SM-366(1CD) NX-B03 |
ピアソラとマッサのヌエボタンゴ協奏曲集 オマール・マッサ(1981-):バンドネオン協奏曲「ブエノスアイレス=ベルリン」 ブエノスアイレス・レゾナンス…世界初録音 ネグロ・リソ タンゴ・レガシー ピアソラ:バンドネオン協奏曲「アコンカグア」 Tangazo:Variations on Buenos Aires タンガーソ: ブエノスアイレス変奏曲 |
オマール・マッサ(バンドネオン) ベルリンSO マーク・レイコック(指) 録音:2021年2月15-19日 |
|
||
| アールアンフィニ MECO-1065(1SACD) 税込定価 |
新倉 瞳/11 月の夜想曲 ファジル・サイ:11月の夜想曲~チェロと管弦楽の為の 藤倉大:スパークラー~チェロの為の 挾間美帆:組曲「イントゥー・ジ・アイズ」 佐藤芳明:2つの楽器の為の2つのカノン 和田薫:巫~チェロと和太鼓の為の ニーグン(伝承曲) |
新倉 瞳(Vc) 飯森範親(指)東京SO 塚越慎子(マリンバ) 佐藤芳明(アコーディオン) 林 英哲(太鼓) 録音:2020年3月21日 東京歌劇シティ(ライブレコーディング) 2021年1月23日 ハクジュホール(ライブレコーディング |
|
||
| DIVINE ART DDA-25222(1CD) NX-B07 |
イザイ~ヴァイオリン・ディスカヴァリーズ 感傷的な情景(1885)~第3番/第5番 悲歌(1912頃) 3つのエチュード=ポエム(1924) ロマンティックな小幻想曲(1901頃)* ヴァイオリン協奏曲 ト短調(1910)(サビン・パウツァによる管弦楽編 2017) |
シェルバン・ルプー(Vn) アンリ・ボナミ(P) リエパーヤSO ポール・マン(指) 録音:2019年3月16日 ブラショフ(ルーマニア)、2020年3月29日 リエパーヤ(ラトヴィア ※*以外=世界初録音 |
|
||
| RUBICON RCD-1053(1CD) |
インフィニット・バッハ~バッハ・リコンポーズド・バイ・ユーハン・ウッレン
原曲=バッハ:ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 BWV.1042/ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 BWV.1041/チェンバロ協奏曲ニ短調 BWV.1052/チェンバロ協奏曲ト短調 BWV.1056 |
クリスチャン・スヴァルヴァール(Vn)、 ユーハン・ウッレン(指)LPO |
|
||
| Onyx ONYX-4235(1CD) |
レーガー:ピアノ協奏曲 へ短調 Op.114 6つの間奏曲 Op.45a |
ヨーゼフ・モーグ(P)、 ニコラス・ミルトン(指)、 ザールブリュッケン・カイザースラウテルン・ドイツ放送PO |
|
||
| EGEA SCA-172(1CD) |
タヴナー:チェロと弦楽オーケストラの為の「奇跡のヴェール」 ジュディス・ウィアー(1954-):無伴奏チェロの為の「アンロックト」 |
マリオ・ブルネロ(Vc)、 クレメラータ・バルティカ、 アイナルス・ルビキス(指) 録音(ライヴ):2010年7月16日、聖ニコラウス教会(ロッケンハウス、オーストリア) |
|
||
| Chateau de Versailles Spectacles CVS-049(1CD) |
ヘンデル:オルガン協奏曲とモテット オルガン協奏曲 ヘ長調 Op. 4-4 HWV 292 サルヴェ・レジーナ」 HWV 241 オルガン協奏曲 ニ短調 Op. 7-4 HWV 309 「たとえ暴虐の中に地は荒れ狂おうとも」 HWV 240 オルガン協奏曲 ト短調 Op. 4-1 HWV 289 |
キアラ・スケラート(S) ガエタン・ジャリ(独奏オルガン、指) アンサンブル・マルグリット・ルイーズ(古楽器使用) 録音:2020年6月11-14日ヴェルサイユ宮殿、王室礼拝堂、フランス |
|
||
| Goodies 78CDR-3846(1CDR) 税込定価 |
ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 | ゲオルク・クーレンカンプ(Vn) ヨーゼフ・カイルベルト(指)BPO 独 TELEFUNKEN SK3712/4(1941年ベルリン録音) |
|
||
| HUNGAROTON HCD-32799(1CD) |
ホフマイスター:ヴィオラ協奏曲 ニ長調 シュターミッツ:ヴィオラ協奏曲第1番ニ長調 モーツァルト:ヴィオラ協奏曲イ長調 K.622(原曲:クラリネット協奏曲) |
アニマ・ムジケ室内O、 マテ・スーチュ(Va) 録音:2021年フンガロトン・スタジオ(ハンガリー) |
|
||
| Challenge Classics CC-72871(1CD) |
シューマン:チェロ作品全集 (1)アダージョとアレグロ 変イ長調 Op.70 (2)幻想曲集 Op.73 (3)民謡風の5つの小品 Op.102 (4)チェロ協奏曲 イ短調 Op.129 |
エッラ・ファン・ポウケ(Vc) ジャン=クロード・ヴァンデン・エインデン(P(1)(2)(3)) ギュンター・ノイホルト(指(4)) フィオンO((4)) 録音:(1)-(3)2021年6月11-13日、(4)2021年1月26-29日 |
|
||
| DOREMI DHR-8153(2CD) |
アイザック・スターンLIVE 第10集 (1)バルトーク:ヴァイオリン協奏曲第2番 (2)ベルク:ヴァイオリン協奏曲 (3)ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第2番 シューベルト:ヴァイオリンとピアノの為のソナチネ第1番 ト短調 Op.137 ファーガソン:ヴァイオリン・ソナタ第2番Op.10 ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第10番 ト長調 Op.96 |
アイザック・スターン(Vn) (1)エルネスト・アンセルメ(指)、ルツェルン祝祭O ライヴ録音:1956年8月18日 (2)ジョン・プリッチャード(指)、ロイヤル・リヴァプールPO ライヴ録音:1960年/第14回エディンバラ国際フェスティバル (3)マイラ・ヘス(P) ライヴ録音:1960年8月28日/第14回エディンバラ国際フェスティバル |
|
||
| TOCCATA TOCN-0010(1CD) NX-B03 |
カタロニアの小協奏曲集と幻想曲集 マルク・ミゴ(1993-):Fantasia popular 人気の幻想曲(2016/2017改訂) フアン・マネン(1883-1971):ヴァイオリン小協奏曲 Op. A-49(作曲年不詳) ミゴ:ピアノ小協奏曲(2016) ハンス・ロットの墓碑銘 - 弦楽の為の(2015) マネン:Rapsodia catalana カタロニア・ラプソディ Op. A-50(1954) |
カリーナ・マクタ(Vn) セルジ・パチェコ(P) ダニエル・ブランチ(P) ウクライナ国立SO ヴォロディミール・シレンコ(指) 録音:2018年10月7-11日 Concert Hall of Ukrainian Radio, キエフ(ウクライナ) 世界初録音 |
|
||
| Gramola GRAM-98025(1CD) |
エルキン&ハチャトゥリアン:ピアノ協奏曲集 ウルヴィ・ジェマル・エルキン(1906-1972):ピアノ協奏曲(1942) ハチャトゥリアン:ピアノ協奏曲 変ニ長調 Op. 38(1936) |
ギュルスィン・オナイ(P) ビルケントSO ホセ・セレブリエール(指) 録音:2011年1月10-14日 ※アルバムの別品番Aldila Records ARCD025 |
|
||
| NIFC NIFCCD-201(1CD) |
ショパン:ピアノと管弦楽の為の作品集 モーツァルトの歌劇「ドン・ジョヴァンニ」の「お手をどうぞ」の主題による変奏曲変ロ長調 Op.2 ポーランドの歌による幻想曲 イ長調 Op.13 ロンド・クラコヴィアク ヘ長調 Op.14 アンダンテ・スピアナートと華麗なポロネーズ 変ホ長調 Op.22 |
ピオトル・アレクセヴィチ(P/スタインウェイ
D,578221)、 ハワード・シェリー(指)、 シンフォニア・ヴァルソヴィア 録音:2019年11月25日-28日、ポーランド放送ヴィトルト・ルトスワフスキ・コンサート・ホール(ポーランド、ワルシャワ) |
|
||
| MUSICAPHON M-56866(1SACD) |
ウィーンの室内セレナーデ シューベルト(アンドレアス・N・タルクマン編):イタリア風序曲第1番ニ長調 D.590 ハイドン(ウルフ=グイド・シェーファー編):交響曲第45番嬰ヘ短調 Hob.I:45「告別」 モーツァルト(アンドレアス・N・タルクマン編):セレナーデ第9番ニ長調 K.320 「ポストホルン」 |
エムスラント・アンサンブル 録音:2005年7月(ドイツ) |
|
||
| MUSICAPHON M-51809(1CD) |
ミヨー&ラダノヴィチ:管弦楽作品集 ミヨー:マリンバ、ヴィブラフォンと管弦楽の為の協奏曲、葬送の行列 ミヒャエル・ラダノヴィチ(b.1958):イントロヴァージョン ミヨー:シンフォニエッタ |
ネボシャ・ヨヴァン・ジヴコヴィッチ(マリンバ、ヴィブラフォン)、 オーストリア室内SO、 エルンスト・タイス(指) 録音:1995年6月(ウィーン) |
|
||
| MUSICAPHON M-56821(1CD) |
マルティヌー&シュタインメッツ:協奏曲集
マルティヌー:室内協奏曲(独奏ヴァイオリン、ピアノ、ティンパニ、打楽器、弦楽オーケストラの為の) ヴェルナー・シュタインメッツ(b.1959):ソロと室内楽(独奏ヴァイオリン、ピアノ、ティンパニ、弦楽オーケストラの為の) マルティヌー:チェロの為のコンチェルティーノ |
ザビーネ・ヴィントバッヒャー(Vn)、 マルティン・ランメル(Vc)、 オーストリア室内SO、 エルンスト・タイス(指) 録音:1994年5月(ウィーン |
|
||
| Biddulph BIDD-85006(1CD) |
オスカー・シュムスキー/モーツァルト他 (1)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番 イ長調「トルコ風」 K. 219 (2) バッハ:ミサ曲 ロ短調 - ラウダムス・テ (4)バッハ:ミサ曲 ロ短調 ? ベネディクトゥス (5)モーツァルト:歌劇「羊飼いの王様」 - 彼女を愛そう (6)ラフマニノフ:夜の静けさに Op. 4 No. 3 (7)ラフマニノフ:子供たちに Op. 26 No. 7 (8)ラフマニノフ:美しいひとよ、私のために歌わないで Op. 4 No. 4 (8). ラフマニノフ:私の窓辺に Op. 26 No. 10 (9)チャイコフスキー:『白鳥の湖』より第2幕-パ・ド・ドゥ (10)マスネ:歌劇「タイス」より「瞑想曲」 (11)ファイアストーン:Do You Recall? (12)シューマン:トロイメライ(グッドマン編) |
オスカー・シュムスキー(Vn) (1)録音:1955年 Music Appreciation Records 5613 リトル・オーケストラ・ソサエティ/トーマス・シェルマン(指) (2) 録音:1947年1月30日/RCA Victor 11-9712 in set M-1145(matrix D7-RC7228/29) (4)録音:1947年1月31日/RCA Victor 11-9725 in set M-1146(matrix D7-RC7255) ジューン・ガードナー(S) ルシウス・メッツ(T) RCAビクターO/ロバート・ショウ(指) (5)録音:1950年3月24日/RCA Victor 12-1317 in set DM-1423(matrix EO-RC830) エレナ・ベルガー(S)/ゲオルゲ・シック(P) (6)録音:1947年8月12日/RCA Victor 12-0499 in set MO-1251(matrix D7-RC8332) (7)録音:1947年8月12日/RCA Victor 12-0499 in set MO-1251(matrix D7-RC8334) (8)録音:1947年8月12日/RCA Victor 12-0500 in set MO-1251(matrix D7-RC8333) (8)録音:1947年8月12日/RCA Victor 12-0500 in set MO-1251(matrix D7-RC8335) ジェームズ・メルトン(T)/キャロル・ホリスター(P)…7-10 (9)録音:1953年プライヴェート録音 コロンビアSO/ヨゼフ・レヴィン(指) (10)録音:1950年 ART111 アメリカ放送O/アルフォンソ・ダルテガ(指) (11)録音:1947年以前 (matrix D7-CC7932) ヴォイス・オブ・ファイアストーン・オーケストラ ハワード・バルロウ(指) (12)録音:ーマン:トロイメライ(グッドマン編) 1947年1月6日 RCA Victor 46-0008 アル・グッドマンと彼のオーケストラ 復刻プロデューサー:Eric Wen 復刻エンジニア:David Hermann マスタリング:Dennis Patterson |
|
||
| SWR music SWR-19427CD(3CD) NX-B06 |
イダ・ヘンデル SWR録音集 1953-1967 【CD1】 (1)ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 (2)メンデルスゾーン: ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64 【CD2】 (1)チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 (2)ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲 【CD3】 (1)ハチャトゥリアン:ヴァイオリン協奏曲 (2)バルトーク:ヴァイオリン協奏曲第2番* |
イダ・ヘンデル(Vn) シュトゥットガルトRSO ハンス・ミュラー=クライ(指) 録音(全てライヴ) (1)1955年9月20日 ゼンデザール、ヴィラ・ベルク、シュトゥットガルト (2)1953年1月10日 ゼンデザール、ヴィラ・ベルク、シュトゥットガルト (31960年1月8日 リーダーハレ、シュトゥットガルト (4)1965年9月21日 リーダーハレ、シュトゥットガルト (5)1962年2月5日 ゼンデザール、ヴィラ・ベルク、シュトゥットガルト (6)1967年11月23日 リーダーハレ、シュトゥットガルト *のみステレオ |
|
||
| SUPRAPHON SU-4303(1CD) |
イングリッシュホルンの芸術 (1)バッハ(レンツ編):協奏曲 ト長調 (復活祭オラトリオ BWV249からの再構築) (2)ドヴォルザーク(レンツ編):「ラルゴ」より抜粋~交響曲第9番「新世界から」より (3)シューベルト(ブランドシュテッター編):即興曲第3番変ト長調 Op.90 (4)シベリウス:「トゥオネラの白鳥」 Op.22 (5)ジャン・フランセ:コール・アングレ、ヴァイオリン、ヴィオラとチェロの為の四重奏曲 (6)ワーグナー:「トリスタンとイゾルデ」第3幕前奏曲「嘆きの調べ」 |
ドミニク・ヴォレンウェーバー(イングリッシュホルン)
(4)サー・サイモン・ラトル(指)BPO (1)(2)(5)BPOのメンバー、 (3)(6)アンナ・キリチェンコ(P) 録音:(1)(2)2021年3月16日、(3)(6)2021年5月28日カンマームジークザール、フルハーモニー・ベルリン(セッション) (5)2020年6月5日、 (4)2014年12月14日グローサー・ザール(大ホール)、フルハーモニー・ベルリン(ライヴ) |
|
||
| MSR MS-1746(1CD) |
「クイックシルヴァー」~吹奏楽伴奏の協奏曲集 (1)ステーシー・ギャロップ(b.1969):クイックシルヴァー(2017) (2)デイヴィッド・マスランカ(1943-2017):ピアノとウィンド・アンサンブルの為の協奏曲第3 番(2016) (3)デイヴィッド・ビーデンベンダー(b.1984):葉の上に書かれたもの(2019) |
マシュー・ウェストゲイト(指) UMASSウィンド・アンサンブル (1)ジョナサン・ハルティング=コー エン(Sax) (2)ナディーン・シャンク(P) 録音:(1)(2)2018年4月18-19日、(3)2019年4月28日マサチューセッツ大学ファイン・アーツ・センター |
|
||
| BERLINER PHILHARMONIKER KKC-9695 (2CD+1Bluray) 税込定価 |
ベルリン・フィル&F.P.ツィンマーマン ■CD1 (1)ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 (カデンツァ=クライスラー) (2)ベルク:ヴァイオリン協奏曲 ■CD2 (1)バルトーク:ヴァイオリン協奏曲第1番 (2)バルトーク:ヴァイオリン協奏曲第2番 ■Bluray ・上記全曲のコンサート映像(すべてHD映像) ・インタビュー映像~F.P.ツィンマーマンとベルリン・フィル(45分) |
フランク・ペ ーター・ツィンマーマン(Vn) BPO ■CD1 (1)ダニエル・ハーディング(指) 録音:2019年12月21日、ベルリン、フィルハーモニー(ライヴ) (2)キリル・ペトレンコ(指) 録音:2020年9月19日、ベルリン、フィルハーモニー(ライヴ) ■CD2 (1)アラン・ギルバート(指) 録音:2016年11月29日、ベルリン、フィルハーモニー(ライヴ) (2)アラン・ギルバート(指) 録音:2016年12月4日、ベルリン、フィルハーモニー(ライヴ) ■Blu ray 画面:Full HD 1080/60i - 16:9 音声:2.0 PCMステレオ/5.1DTS-HD MA リージョン:ABC(worldwide) 総収録時間:135分 字幕:独、英、日本語 Audio:2.0PCM Stereo 24 bit/48kHz 5.1DTS-HD MA 24 bit/48kHz ■ダウンロード・コード この商品には、上記全曲のハイレゾ音源(24bit/192kHz)をダウンロードするためのURLとそのパスワードが封入されています。 ■デジタル・コンサートホール ベルリン・フィルの映像配信サービス「デジタル・コンサートホール」を7日間無料視聴できるチケット・コードが封入されています。 |
|
||
 Treasures TRE-268(1CDR) |
ワイエンベルク/R.シュトラウス&ガーシュイン R・シュトラウス:ブルレスケ* ガーシュウィン:ラプソディ・イン・ブルー ピアノ協奏曲ヘ調 |
ダニエル・ワイエンベルク(P) クリストフ・フォン・ドホナーニ(指)* フィルハーモニアO* ジョルジュ・プレートル(指) パリ音楽院O 録音:1963年6月16&19日*、1960年頃(全てステレオ) ※音源:蘭CNR SKLP-4145*、蘭EMI 5C045-11656 ◎収録時間:69:03 |
| “リズムと色彩が常に共存する驚異のガーシュウィン!” | ||
|
||
| Sono Luminus DSL-92243 NX-B05 |
アイスランドの近代音楽集 ダニエル・ビャルナソン(1980-):ヴァイオリン協奏曲 ヴェロニク・ヴァカ(1986-):土地 ヘイクル・トウマソン(1960-):第七の天国にて ソルディス・ゲルズル・ヨンスドッティル:フラッター マグヌス・ブロンダル・ヨハンソン(1925-2005):アダージョ |
ペッカ・クーシスト(Vn) マリオ・カローリ(Fl) アイスランドSO ダニエル・ビャルナソン(指) 録音:2019年12月17-20日、2020年3月4-8日、2018年2月19-22日 |
|
||
| 2L 2L-166SABD (Blu-ray Disc Audio+SACD Hybrid) |
ストーレ・クライベルグ(1958-):ヴァイオリン協奏曲第2番(2017) Dopo(1993)(Vcと弦楽オーケストラのための) ヴィオラ協奏曲(2019) ストーレ・クライベルグの協奏曲 |
マリアン ネ・トーシェン(Vn) フレードリク・シェーリン(Vc) アイヴィン・リングスタード(Va) トロンハイムSO ペーテル・シルヴァイ(指) [楽器 Violin:G. B. Guadagnini, 1745/Viola: “ex-Vieuxtemps” G. B. Guadagnini, 1768/Cello: F. Ruggieri, 1688] 録音:2020年6月、8月 オラヴホール(トロンハイム、ノルウェー) |
|
||
 Treasures TRE-255(1CDR) ★ |
モイセイヴィチの十八番協奏曲集 ディーリアス:ピアノ協奏曲 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」* |
ベンノ・モイセイヴィチ(P) マルコム・サージェント(指)BBC響 録音:1955年9月13日プロムス(モノラル・ライヴ)、1963年3月6日ロイヤル・フェスティヴァル・ホール(モノラル・ライヴ)* ※音源:米Discocorp BWS-725 ◎収録時間:56:09 |
| “死の影なし!溢れる生命力を惜しげもなく放射した輝かしい「皇帝」!” | ||
|
||
| NXN RECORDINGS NXN-4003(1CD) |
エレキ・ギターと管弦楽のための作品集 1. Undying-Dying 2. Entirety for Guitar, Electronics and Orchestra 3. Entirety for Piano and Electronics 4. Germinal 5. Beneath the Lilac 6. Time and Mass 7. The Always Juvenilia 8. State of Fruition |
ビョルン・チャールズ・ドレイヤー(エレキ・ギター、エレクトロニクス、作曲) クリスティアンサンSO ペール・クリスチャン・スカルスタード(指) |
|
||
| A Flock Ascending AFACD-001(1CD) |
ジョン・タヴナー:ピアノと管弦楽のための 「パリントロポス」(PALINTROPOS)(世界初録音)* マイケル・スチュワート:ピアノ、エレクトロニクスとキーボードのための 「ビヨンド・タイム・アンド・スペース」(イン・メモリアム・ジョン・タヴナー)** |
ARUHI(原綾佳)(P)、 ロナルド・コープ(指)*、 ニュー・ロンドン・オーケストラ*、 マイケル・スチュワート(キーボード、エレクトロニクス、プログラミング)** 録音(パリントロポス):2020年1月21日、セント・ジュード教会(ハムステッド、ロンドン) |
|
||
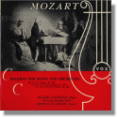 Treasures TRE-233(1CDR) |
ヘブラー&ホルライザー/モーツァルト:ピアノ協奏曲集Vol.1 ピアノ協奏曲第8番ハ長調 K. 246 ピアノ協奏曲第15番変ロ長調 K. 450* ピアノ協奏曲第18番変ロ長調 K. 456# |
イングリット・ヘブラー(P) ハインリヒ・ホルライザー(指) ウィーン・プロ・ムジカSO(ウィーンSO) 録音:1955年4月28.30日、1953年*,#(全てモノラル) ※音源:英VOX PL-9290、 PL-8300*,# ◎収録時間:76:48 |
| “「ヘブラーのモーツァルトは甘ったるい」というのは明らかに誤解です!” | ||
|
||
| Brana Records BR-0037(3CD) |
ブラーナ・レコーズ・コレクションVol.4 ~
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番ハ長調 Op.15 ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 Op.19 ピアノ協奏曲第3番ハ長調 Op.37 ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op.58 ピアノ協奏曲第5番変ホ長調 Op.73 「皇帝」 ピアノ協奏曲変ホ長調(1784) |
フェリシア・ブルメンタール(P) ロベルト・ワーグナー(指)、ウィーンSO 録音年月日不詳/ADD |
|
||
| Brana Records BR-0036(1CD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集 Vol.3 ピアノ協奏曲第5番変ホ長調 Op.73 「皇帝」 ピアノ協奏曲変ホ長調(1784) |
フェリシア・ブルメンタール(P)、 ロベルト・ワーグナー(指)ウィーンSO 録音年月日不詳/ADD |
|
||
| Brana Records BR-0035(1CD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集 Vol.2 ピアノ協奏曲第3番ハ長調 Op.37 ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op.58 |
フェリシア・ブルメンタール(P)、 ロベルト・ワーグナー(指)ウィーンSO 録音年月日不詳/ADD |
|
||
| FUGA LIBERA FUG-766(1CD) |
エリザベート王妃音楽大学ライヴ~モーツァルト:二重協奏曲と演奏会用アリア 2台のピアノと管弦楽のための協奏曲 変ホ長調 K. 365 演奏会用アリア 「どうしてあなたを忘れられよう…恐れないで、愛する人よ」-ソプラノ、オブリガート・ピアノと管弦楽のための K. 505 ヴァイオリン、ピアノと管弦楽のための協奏曲 ニ長調 K. Anh. 56 (フィリップ・ウィルビー補筆完成版) |
ルイ・ロルティ(P) ヴィクトリア・ヴァシレンコ(P) イリス・ファン・ウェイネン(Ms) フランク・ブラレイ(P)* ウラディスラヴァ・ルチェンコ(Vn) ビール・ゾロトゥルンSO カスパール・ツェーンダー(指) 録音:2019年3月20日、2020年3月11日 パレ・デ・コングレ、ビエンヌ(ビール)、ライヴ・拍手入り |
|
||
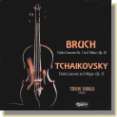 Treasures TRE-234(1CDR) |
ヴァルガ~ブルッフ&チャイコフスキー チャイコフスキー:「懐かしい土地の思い出」Op.42~瞑想曲(グラズノフ編)* ヴァイオリン協奏曲 ニ長調Op.35 ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番Op.26# |
ティボール・ヴァルガ(Vn) ジャン=マリー・オーバーソン(指) ボリス・マーソン(指)* ウィーン祝祭O 録音:1965年(ステレオ) ※音源:Comcert Hall SMS-24110、SMS-2587(TU)# ◎収録時間:74:10 |
| “潔癖かつ鉄壁!造形美への並々ならぬ執着がもたらす凛然たるニュアンス!” | ||
|
||
| JAN KUBELIK SOCIETY SJK-010(1CD) |
18世紀のヴァイオリン協奏曲 ジョゼフ・ブローニュ・シュヴァリエ・ド・サン・ジョルジュ (1745-1799):ヴァイオリン協奏曲 イ長調 Op.5-2 ルイジ・ボルギ(1745?-1806?):ヴァイオリン協奏曲 ハ長調 Op.3-4 フランチシェク・ベンダ(1709-1786):ヴァイオリン協奏曲 変ホ長調 ヤン・クーベリック(1880-1940):古い歌 (弦楽合奏の為の編曲版)* |
ミロスラフ・ヴィリーメツ(Vn*以外)) ハルモニア・プラーガ(管弦楽) シュテファン・ブリトヴィーク(指) 録音:2016-2017年、新市街市庁舎ホール、プラハ、チェコ |
| Velut Luna CVLD-292(1CD) |
モーツァルト:管楽器の為の協奏曲集 クラリネット協奏曲 イ長調 K.622* フルート協奏曲 第2番ニ長調 K.314 + ファゴット協奏曲 変ロ長調 K.191 # |
ルーカ・ルケッタ(クラリネット*) マリオ・フォレーナ(フルート+) パドヴァ・ヴェネトO(*/+) ジョルト・ハマル(指(*/+)) アリージ・ヴォルタン(ファゴット#) イ・ソリスティ・デロリンピコ# ジョヴァンニ・バッティスタ・リゴン(指揮#) 録音:2006年10月4日、ライヴ、ヴェルディ劇場、パドヴァ、イタリア(*/+) 2004年6月12日、ライヴ、オリンピコ劇場、ヴィチェンツァ、イタリア# |
|
||
| Velut Luna CVLD-293(1CD) |
フルート協奏曲集 サヴェリーノ・メルカダンテ(1795-1870):フルートと弦楽合奏の為の協奏曲 ホ短調 (アゴスティーノ・ジラール校訂版) ヨハン・ヨハヒム・クヴァンツ(1697-1773):フルート協奏曲 ト長調 カレル・シュターミッツ [カール・シュターミッツ] (1745-1801):フルート協奏曲 ト長調 Op.29 ジョヴァンニ・バッティスタ・ペルゴレージ :フルート、弦楽と通奏低音の為の協奏曲 ト長調 |
エンツォ・カローリ(Fl) オーケストラ GAV [ジョヴァーニ・アルキ・ヴェネティ] ルチア・ヴィゼンティン(第1ヴァイオリン & 指揮) 録音:2017年8月、アレア・マジステル・スタジオ、プレガンツィオル、イタリア |
 Treasures TRE-228(1CDR) |
ブライロフスキー/ショパン&サン・サーンス:ピアノ協奏曲、他 リスト:メフィスト・ワルツ第1番 愛の夢第3番 2つの演奏会用練習曲~小人の踊り サン・サーンス:ピアノ協奏曲第4番* ショパン:ピアノ協奏曲第2番# |
アレクサンダー・ブライロフスキー(P) シャルル・ミュンシュ(指)ボストンSO 録音:1953年4月18日、1954年11月24日*、1954年11月29日# ※音源:HMV ALP-1110、米RCA LM-1871*,# ◎収録時間:71:56 |
| “華麗な技巧だけで煽らないインスピレーション優先の芸の極み!” | ||
|
||
| SONOGRAFIC SG-15007(1CD) |
グスタボ・ベセラへのオマージュ~マルセロ・デ・ラ・プエブラ(1966-):ギターの為の作品集 ギターと打楽器アンサンブルの為の協奏曲 * ギター・ソナタ 第4番 3つの歌(声とギターの為の)+ 子守歌/労働者の手/汗と鞭 ギター・ソナタ 第2番 ギターとピアノの為のディヴェルティメント # |
マルセロ・デ・ラ・プエブラ(G) ドラマー・ドリーマー(打楽器アンサンブル*) イニャキ・マルティン(指*) カルメン・セラノ(ソプラノ+) イグナシオ・トルネル(P)# 録音:データ記載無し(2015年以前) |
 Treasures TRE-218(2CDR) ★ |
クルト・レーデルのバッハ バッハ:ブランデンブルク協奏曲BWV1046-1051(全6曲) |
クルト・レーデル ミュンヘン・プロ・アルテ室内O ラインホルト・バルヒェット(Vn) ピエール・ピエルロ、レオンハルト・ザイフェルト、ヴィルヘルム・グリム(Ob) クルト・リヒター、ヴィ・ベック(Hrn) カール・コルビンガー(Fg) モーリス・アンドレ(Tp) クルト・レーデル、パウル・マイゼン(Fl) ロベール・ヴェイロン=ラクロワ(クラヴサン) ゲオルク・シュミット、フランツ・ツェッスル(Va) イルミンギルト・ゼーマン、ロルフ・アレクザンダー(gmb) ヴィルヘルム・シュネッラー(Vc) ゲオルク・フェルトナーゲル(Cb) 録音:1962年5月1-6日(ステレオ) ※音源:日COLUMBIA OS-472、OS-473 ◎収録時間:101:20 |
| “親和的なアンサンブルから浮かび上がるバッハの温もり!” | ||
|
||
 BERLIN CLASSICS BC-0301304(4CD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集 ■CD 1 ピアノ協奏曲 第0番変ホ長調 WoO4 ピアノと管弦楽のためのロンド 変ロ長調 WoO6 創作主題による15の変奏曲とフーガ 変ホ長調(「エロイカ変奏曲」) Op.35 ■CD2 ピアノ協奏曲 第1番ハ長調 Op.15 ピアノ協奏曲 第2番変ロ長調 Op.19 ■CD3 ピアノ協奏曲 第3番ハ短調 Op.37 ピアノ、ヴァイオリン、チェロと管弦楽のための三重協奏曲 ハ長調 Op56 ■CD4 ピアノ協奏曲 第4番ト長調 Op.58 ピアノ協奏曲 第5番変ホ長調Op.73『皇帝』 |
児玉麻里(P) ケント・ナガノ(指) ベルリン・ドイツSO ■CD 1 録音:2019年5月9,10日、ベルリン、イエス・キリスト教会 ■CD2 録音:2006年6月23-24日、テルデックス・スタジオ・ベルリン ■CD3 コーリャ・ブラッハー(Vn) ヨハネス・モーザー(Vc) 録音:2006年11月9,10日、ベルリン、シーメンスヴィラ ■CD4 録音:2013 年3月5,6日(第4番)、2013年3月8,9日(第5番)、ベルリン、イエス・キリスト教会 |
|
||
| 2L 2L-159SABD (Blu-ray disc audio + SACD Hybrid) |
オーレ・ブル~人生の諸段階 オーレ・ブル(1810-1880):ラルゴ・ポザート・エ・ロンド・カプリッチョーソ(1841)(ヴァイオリンと管弦楽のための) ノルウェーの山々(ヴァイオリンと管弦楽のための)(ヴォルフガング・プラッゲ(1960-) 『リリー・デール』による幻想曲(1872)(ヴァイオリンとピアノのための) リオのヴィルスペル(1842 rev.1860)(ヴァイオリンと管弦楽のための) 最後のロマンス(1872)(ヴァイオリンとピアノのための) |
アンナル・フォレソー(Vn) ノルウェー放送O キム・ウンサン(指) ヴォルフガング・プラッゲ(P) [使用楽器:Violin: Enrico Rocca, 1870s/Piano: C. Bechstein Concert C234] 録音:2018年6月 ヤール教会(バールム、ノルウェー) [DXD(24bit/352.8kHz)録音] [Blu-ray: 5.1 DTS-HD MA(24bit/192kHz), 7.1.4. Auro-3D(96kHz), 7.1.4. Dolby Atmos(48kHz), 2.0 LPCM (24bit/192kHz), mShuttle: MQA + FLAC + MP3 Region ABC] [SACD hybrid(5.1 surround DSD/2.0 stereo DSD), MQA CD] |
|
||
| Printemps des Arts de Monaco PRI-034(3CD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集 (1)ピアノ協奏曲第1番ハ長調 Op.15 (2)ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 Op.19 [CD 2] (3)ピアノ協奏曲第3番ハ短調 Op.37 (4)ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op.58 (5)ピアノ協奏曲第5番変ホ長調 Op.73『皇帝』 ※カデンツァ:(1)(2)(3)(5)ベートーヴェン、(4)ブラームス |
フランソワ=フレデリック・ギィ(P&指) シンフォニア・ヴァルソヴィア 録音:2019年3月14-17日/ヤコフ・クライツベルク・ホール(モナコ) |
|
||
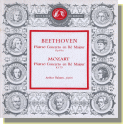 Treasures TRE-214(1CDR) |
バルサム~モーツァルト&ベートーヴェン モーツァルト:ピアノ協奏曲第5番ニ長調K.175* ベートーヴェン:ピアノ協奏曲ニ長調Op.61(原曲:ヴァイオリン協奏曲) |
アルトゥール・バルサム(P) ブロニスラフ・ギンペル(指)交響楽団* クレメンス・ダヒンデン(指)ヴィンタートゥールSO 録音:1951年*、1950年代初頭 ※音源:英NIXA PLP-229*、仏Guilde Internationale Du Disque MMS-3002 ◎収録時間:65:09 |
| “没入しないのに芯は熱い!2つのニ長調の名曲で見せるバルサムの凄い感性!” | ||
|
||
| TAFELMUSIK TMK-1039(1CD) NX-B07 |
ヴィヴァルディに愛を込めて .歌劇「離宮のオットー大帝」RV729-シンフォニア ヴァイオリン協奏曲 ハ短調 「アマート・ベネ」RV761 ファゴット協奏曲 ニ短調 RV481 2台のオーボエのための協奏曲 ハ長調 RV534 ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 RV271「恋人」 室内協奏曲 ニ長調 RV93 4台のヴァイオリンのための協奏曲 変ロ長調 RV553 2台のヴァイオリンと2台のオーボエ、ファゴットのための協奏曲 ニ長調 RV564a |
エリサ・チッテリオ(Vn) ドミニク・テレシ(Fg) ジョン・アッベーガー(Ob) マルコ・チェラ(Ob) ルーカス・ハリス(Lute) クリスティーナ・ツァハリアス(Vn) パトリシア・エイハン(Vn) ジェネヴィエーヴ・ジラルドー(Vn) ジョン・マルコ(Ob) ジュリア・ウェドマン(Vn) エリサ・チッテリオ(指) ターフェルムジーク・バロックO(ピリオド楽器使用) 録音:2018年10月30日-11月2日 |
|
||
| ヴァデメクム VMMM-1604(1CD) 税込定価 |
チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 懐かしい土地の想い出 Op.42 |
ステファニー=マリー・デガン(Vn) ヴァハン・マルディロシアン(指、P) カーンO 録音:(1)2012 年 6 月 21 日カエン(ライヴ録音) (2)2012 年8 月ジャン=ピエール・ドテール・オーディトリウム |
|
||
| Aurora ACD-5104(1CD) |
『Just for You(あなただけのために)』 ヤン・エーリク・ミカルセン(1979-):ヴァイオリン協奏曲(2017) Just for You(2017)(ソロ・ピアノと管弦楽のための) |
インゲリーネ・ダール(Vn) エレン・ウゲルヴィーク(P) スタヴァンゲルSO アイヴィン・グルベルグ・イェンセン(指) 録音:2018年8月13日-17日 スタヴァンゲル・コンサートホール(スタヴァンゲル、ノルウェー) |
|
||
| Aurora ACD-5093(1CD) |
ヘルゲ・イーベルグ(1954-):生命の惑星の歌(管弦楽、5人のソリスト、朗読のための合奏協奏曲) | エリセ・ボートネス(Vn) クリスチャン・イーレ・ハドラン(P) マリアンネ・ベアーテ・シェラン(Ms) フランク・ハーヴロイ(Br) トム・オッタル・アンドレーアセン(アルトフルート) リウ・ティエガン(朗読) シセル・エンドレーセン(朗読) イングリ・ブライエ・ニュフース(ピアノ・ソロ) ビョルン・ローケン(ゴング、クリスタル・サウンドボウル、クリスタル・サウンドピラミッド) ノルウェー放送O カイ・グリンデ・ミューラン(指) 録音:2018年3月19日-20日、5月7日-9日 NRK大スタジオ(オスロ) 録音(北京語朗読):首都師範大学音楽学院、中央戯劇学院(北京) 録音(打楽器、英語朗読):UrbanSoundStudios(オスロ) 制作:ハルドル・クローグ、ヘルゲ・イーベルグ 録音:オイスタイン・ハルヴォシェン、テリエ・へレム |
|
||
 SWR music SWR-19076CD(1CD) NX-B02 |
ショパン:ピアノ協奏曲集 .ピアノ協奏曲 第2番ヘ短調 Op.21 ピアノ協奏曲 第1番ホ短調 Op.11* |
ニキタ・マガロフ(P) ハンス・リヒター=ハーザー(P)* ハンス・ロスバウト(指) 南西ドイツRSO 録音:1951年10月10日バーデンバーデン音楽スタジオ(ハンス・ロスバウト・スタジオ)(モノラル)、 1961年4月28日バーデンバーデン音楽スタジオ(ハンス・ロスバウト・スタジオ)(モノラル)* |
| “自己の美学を貫徹しながら偏狭なショパンのイメージを一蹴!” | ||
|
||
| Tonar TONAR-31015(1CD) |
メデア~スペインのギター作品集 アルベニス:「スペイン」より 前奏曲、入江のざわめき、コルドバ、朱色の塔、タンゴ、マジョルカ グラナドス:ゴヤのマハ サンルーカル:ギターとオーケストラのための「メデア」 |
マヌエル・バルエコ(G)、 ビクトル・パブロ・ペレス(指)、 テネリフェSO |
|
||
| DOUBLE MOON BTLCHR-71246(1CD) |
イツハク・イエディッド(1971-):初演録音集 (1)祝福と呪い (2)ちいさなヤギ (3)ピアノと弦楽のための協奏曲 (4)ピアノのためのシャコンヌ『天使の反乱』 |
(1)クリスチャン・リンドベルイ(指)、イスラエル・ネタニヤ・キブツ・オーケストラ (2)ウィリアム・スタッフォード(Cl)、レイチェル・スミス(Vn)、ルイーズ・キング(Vc)、エイシャ・ゴーフ(P) (3)グレアム・ジェニングス(指)、マイケル・キーラン・ハーヴィ(P)、ディヴェルティメンティ・ストリング・アンサンブル (4)レイチェル・シパード(P) 録音:2016、2017年(すべて初演時の録音) |
|
||
| PAU KIYO-101(3CD) 税込定価 |
岡山潔の軌跡~第1巻 (1)ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 (2)シューマン:ヴァイオリン協奏曲 (3)バルトーク:2 つのヴァイオリンのための44 の二重奏曲 Sz.98 全曲 (4)モーツァルト:ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲(第1 番ト長調 K.423 & 第2 番変ロ長調 K.424) (5)ドヴォルザーク:テルツェット ハ長調 Op.74 B.148 (6)コダーイ:セレナード ヘ長調 Op.12 |
岡山 潔(Vn) (1)ゲルハルト・ボッセ(指)神戸市室内O (2)フォルカー・ヴァンゲンハイム(指)ボン・ベートーヴェンハレO (3)(5)(6)服部芳子(Vn)、 (4)(5)(6)深井硯章(Va) 録音:(1)2002 年10 月27 日東京藝術大学奏楽堂(ライヴ) (2)1975 年9 月ベートーヴェンハレ、ボン (3)1989 年10 月2、3、7 日バリオホール、東京 (4)1992 年9 月7~10 日府中の森芸術劇場 (5)(6)1990 年11 月22、23 日バリオホール、東京 |
|
||
| Willowhayne Records WHR-057(1CD) |
ロビン・A.スミス:LE WEEKEND (pour les amants) 組曲 「LE WEEKEND」 |
ロビン・A.スミス (P&指) チェコ国立SO 録音:2017年10月 |
|
||
| Aurora ACD-5091(1CD) |
『アクロスティック(Akrostikon)』 ビョルン・クルーセ(1946-):アクロスティック(2012)(オルガン、打楽器と弦楽オーケストラのための協奏曲) シェル・サムコフ(1952-):ヴィブラフォーンと弦楽のための協奏曲第2番(2008) シェル・ハッベスタ(1955-):アヴェ・マリアOp.11(1984)(オルガンと弦楽オーケストラのための協奏曲) |
ラーシュ・ノットー・ビルケラン(Org) アイリク・ラウデ(打楽器) ヴォクス・クラマンティス ノルウェー放送O カイ・グリンデ・ミューラン(指) 録音:2017年10月23日-24日 ファーゲルボルグ教会(オスロ) |
|
||
| DACAPO MAR-8.206004(6CD) NX-F01 |
ホルンボー(1909-1996):室内協奏曲とシンフォニア集 【CD1】…8.224038 1-2.室内協奏曲 第1番 Op.17(1939) 3-6.室内協奏曲 第2番 Op.20(1940) 7-8.室内協奏曲 第3番 Op.21(1940-1942) 【CD2】…8.224063 1-3.室内協奏曲 第4番 Op.30(1942-1945) 4-6.室内協奏曲 第5番 Op.31(1943) 7-9.室内協奏曲 第6番 Op.33(1943) 【CD3】…8.224086 1-2.室内協奏曲 第7番 Op.37(1944-1945) 3-4.室内協奏曲 第8番「シンフォニア・コンチェルタン テ」Op.38(1945) 5-7.室内協奏曲 第9番 Op.39(1945-1946) 【CD4】…8.224087 1-9.室内協奏曲 第10番 Op.40(1945-1946) 10-12.室内協奏曲 第11番 Op.44(1948) 13-15.室内協奏曲 第12番 Op.52(1950) 16-18.室内協奏曲 第13番 Op.67(1955- 1956) 【CD5】…8.226017-18 1.シンフォニア 第1番 Op.73a(1957) 2.シンフォニア 第2番 Op.73b(1957) 3.シンフォニア 第3番 Op.73c(1958-1959) 4-7.シンフォニア 第4番 Op.73d(1962) 【CD6】…8.226017-18 カイロス(時間) Op.73“シンフォニア 第1番-第4 番” 1.前奏曲(シンフォニア 第4番 Op.73dより) 2.シンフォニア 第1番 Op.73a 3.間奏曲 I(シンフォニア 第4番 Op.73dより) 4.シンフォニア 第2番 Op.73b 5.間奏曲 II(シンフォニア 第4番 Op.73dより) 6.シンフォニア 第3番 Op.73c 7.後奏曲(シンフォニア 第4番 Op.73dより) |
ハンヌ・コイヴラ(指) デンマーク国立室内O(デンマーク放送シンフォニエッタ) 【CD1】…8.224038 アンネ・エランド(P)…1-2 スタファン・ボルセマン(Vn) エヴァ・エステルゴー(Fl)…3-6 ミッケル・フットルプ(Vn)…3-6 ニルス・トムセン(Cl)…7-8 録音:1996年6月8-12日 Danish Radio Studio 2, Denmark 【CD2】…8.224063 アンネ・エランド(P)…1-3 ミッケル・フットルプ(Vn)…1-3.7-9 ニルス・ウルナー(Vc)…1-3 ティム・フレデリクセン(Va)…4-6 録音:1996年8月,10月 Danish Radio, Studio 2, Denmark 【CD3】…8.224086 マックス・アートヴェズ(Ob)…1-2 ミッケル・フットルプ(Vn)…5-7 ティム・フレデリクセン(Va)…5-7 録音:1997年1月6-11日,2月4-6日 Danish Radio, Studio 2, Denmark 【CD4】…8.224087 オーレ・エドヴァルド・アントンセン(Tp) ジャック・モージェ(トロンボーン)…13-15 ティム・フレデリクセン(Va)…16-18 マックス・アルトヴェド(Ob)…16-18 録音:1997年6月3-4日,8月20-21日, 11月5-6日 Danish Radio Studio 2, Denmark 【CD5】…8.226017-18 【CD6】…8.226017-18 セアン・エルビーク(Vn)・・・CD5.6 トレルス・スヴァネ(Vc)・・・CD5.6 録音:1997年 Danmarks Radio, Studio 2, Denmark |
|
||
| DACAPO MAR-8.226591(1CD) NX-A14 |
ペーター・ナバロ=アロンソ:作品集 合奏協奏曲「Le quattro stagioni 四季」(2014) 協奏曲 ロ短調(2017) |
アルファ(アンサンブル) 【メンバー】 ボレッテ・リード(リコーダー) ペーター・ナバロ=アロンソ(Sax) ダヴィッド・ヒルデブラント(パーカッション&ヴィヴラフォン) エッコゾーン(アンサンブル) マティアス・ロイメルト(指) 録音:コペンハーゲン 2015年12月14日、2017年6月19-20日 世界初録音 |
|
||
 Treasures TRE-198(1CDR) |
アラウ/ショパン:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲第1番ホ短調Op.11 ピアノ協奏曲第2番ヘ短調Op.21* |
クラウディオ・アラウ(P) オットー・クレンペラー(指)ケルンRSO マッシモ・プラデッラ(指)バイエルンRSO* 録音:1954年10月25日ケルン放送第1ホール、1960年4月12日ミュンヘン・ライヴ*(共にモノラル) ※音源:日KING SLF-5002、伊MOVIMENT MUSICA 01.064* ◎収録時間:73:08 |
| “甘美さ優先のショパンではに満足しない方は必聴!” | ||
|
||
| KLANGLOGO KL-1521(1CD) NX-B03 |
ベートーヴェン:秘曲作品集 ピアノ協奏曲 ニ長調 Op.61a 騎士のバレエ WoO1 交響曲「ウェリントンの勝利またはビトリアの戦い」(戦争交響曲) |
クレア・フアンチ(P) ハワード・グリフィス(指) フランクフルト・ブランデンブルク州立O 録音:2017年8月21-23日 |
|
||
| DACAPO MAR-8.226149(1CD) NX-B06 |
ポウル・ルーザス(1949-):ヴィオラ協奏曲/ヘンデル・ヴァリエーションズ ヴィオラ協奏曲(1993-1994/2013改訂) ヘンデル・ヴァリエーションズ(2009) ヘンデルの8小節の主題による90のシンフォニック・リフレクション* |
ラーシュ・アネルス・トムテル(Va)…1-3 マルク・スーストロ(指) アンドレアス・デルフス(指)* オーフスSO 録音:2015年12月11-12日、2017年3月18-20日* 世界初録音 |
|
||
| H.WIENIAWSKI MUSICAL SOCIETY (ヘンリク・ヴィエニャフスキ音楽協会) DUX-1395(2CD) |
第15回ヘンリク・ヴィエニャフスキ国際ヴァイオリン・コンクール(2016)実況録音! [CD 1] シマノフスキ:ロマンス ニ長調 Op.23* ミルシテイン:パガニーニアーナ ヴィエニャフスキ:新しい手法Op.10 から レ・スタッカート(No.4) スケルツォ=タランテッレ ト短調 Op.16* ヨアヒム:ロマンス変ロ長調 Op.2* フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調* クライスラー:ジプシー奇想曲* バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番ト短調 BWV 1001 から アダージョ モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 K.219 から 第1楽章+ [CD 2] モーツァルト:協奏交響曲変ホ長調 K.364(324d) から 第1楽章# ヴィエニャフスキ:ヴァイオリン協奏曲第2番ニ短調 Op.22** ショスタコーヴィチ:ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 Op.77++ |
ヴェリコ・チュムブリーゼ(Vn) ハンナ・ホレスカ(P)* カタジナ・ブドニク=ガウォンツカ(Va)# ポーランド放送アマデウス室内O(+/#) アグニェシュカ・ドゥチマル(指)+ ポズナンPO(**/++) マレク・ピヤロフスキ(指)** ウーカシュ・ボロヴィチ(指)++ 録音:2016年10月8-23日、ポズナン、ポーランド |
|
||
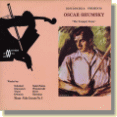 Treasures TRE-176(1CDR) |
若き日のオスカー・シュムスキー ヴィエニャフスキ:華麗なるポロネーズ第1番 ニ長調 Op. 4* シューベルト:華麗なるロンドOp.70** サン・サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ# ヴュータン:ヴァイオリン協奏曲第22番(ピアノ伴奏版)## モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」+ |
オスカー・シュムスキー(Vn) ピアニスト不明* レオニード・ハンブロ(P)** ミルトン・カティムズ(指)NBC響# ウラディミール・ソコロフ(P)## トーマス・シェルマン(指)小管弦楽協会O+ 録音:1940年8月15日*、1951年6月23日**、1950年4月22日#、1950年##、1956年頃+ (全てモノラル) ※音源:DISCOPEDIA MB-1040、Music Appreciation Records MAR-5613+ ◎収録時間:78:53 |
| “音楽を弄ばず、奉仕者に徹する信念が強固なニュアンスを形成!” | ||
|
||
 Treasures TRE-177(1CDR) |
ロベール・カサドシュ/ベートーヴェン:「皇帝」他 ウェーバー:コンツェルトシュテュック ヘ短調 Op. 79 フランク:交響的変奏曲 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」* |
ロベール・カサドシュ(P) キリル・コンドラシン(指)トリノ放送SO ハンス・ロスバウト(指)アムステルダム・コンセルトヘボウO* 録音:1960年5月6日ライヴ、1961年2月3日* (全てステレオ) ※音源:伊FONIT CETRA LAR-18、独FONO-RING SFGLP-77699* ◎収録時間:66:12 |
| “本質追求ヘの強い意志を分かち合ったカサドシュとロスバウトの強力タッグ!” | ||
|
||
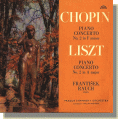 Treasures TRE-173(1CDR) |
フランティシェク・ラウフ/リスト&ショパン他 ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第30番 アンダンテ・ファヴォリ リスト:ピアノ協奏曲第2番* ショパン:ピアノ協奏曲第2番* |
フランティシェク・ラウフ(P) ヴァーツラフ・スメターチェク(指)プラハSO 録音:1965年11月15,18-19日、1964年6月17-18,20,22日&9月3日*(全てステレオ) ※音源:SUPRAPHON SUAST-50743、SUAST-50603* ◎収録時間:76:16 |
| “真心から紡ぎ出されるタッチに宿る幽玄のニュアンス!!!” | ||
|
||
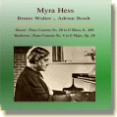 Treasures TRE-172(1CDR) |
マイラ・ヘス~モーツァルト&ベートーヴェン モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番* ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番** ショパン:ワルツOp.18# ブラームス:間奏曲Op.119-3# スカルラッティ:ソナタL.387# |
マイラ・ヘス(P) ブルーノ・ワルター(指)NYO* エイドリアン・ボールト(指)BBC響** 録音:1956年カーネギーホール* 、1953年1月ロンドン**、1949年3月17,18日イリノイ大学# (全てライヴ) ※音源:米 Bruno Walter Society PR-36*、加ROCOCO RR-2041**,# ◎収録時間:74:13 |
| “懐の深さをもって作品を捉えるヘスのピアニズムの大きさ!” | ||
|
||
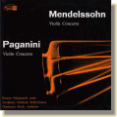 Treasures TRE-170(1CDR) |
オドノポゾフ~メンデルスゾーン&パガニーニ他 ショーソン:詩曲 メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調 パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第1番 |
リカルド・オドノポゾフ(Vn) ジャンフランコ・リヴォリ(指) ジュネーヴRSO 録音:1955年頃*、1962年(全てステレオ) ※音源:日Concert Hall SM-2250*、英SMS-2205 ◎収録時間:72:19 |
| “オドノポゾフの「美音の底力」をたっぷり堪能!” | ||
|
||
 Treasures TRE-166(1CDR) |
リンパニー/リスト&プロコフィエフ リスト:ピアノ協奏曲第2番* プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第1番 ピアノ協奏曲第3番 |
モーラ・リンパニー(P) マルコム・サージェント(指)ロイヤルPO* ワルター・ジュスキント(指)フィルハーモニアO 録音:1962年10月*、1956年5月2-3日(共にステレオ) ※音源:伊RCA GL-32526*、英WRC T-735 ◎収録時間:61:09 |
| “リンパニーの飾らない気品を堪能する協奏曲集!” | ||
|
||
 Treasures TRE-163(1CDR) |
リシャルト・バクスト~ベートーヴェン ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ピアノ・ソナタ第14番「月光」 ピアノ協奏曲第3番ハ短調* |
リシャルト・バクスト(P) スタニスワフ・ヴィスロッキ(指) ワルシャワ国立PO 録音:1963年頃(ステレオ) ※音源:MUZA SXL-0166、SX-0167* ◎収録時間:77:44 |
| “ベートーヴェン弾きとしてのバクストの芸術性を思い知るい一枚!” | ||
|
||
| ELOQUENTIA EL-0815(2CD) ★ |
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集 ヴァイオリン,弦楽と通奏低音の為の協奏曲ニ短調 RV.Anh.10 ヴァイオリン,弦楽と通奏低音の為の協奏曲変ロ長調 RV.381 ヴァイオリン,弦楽と通奏低音の為の協奏曲ニ長調 RV.220 ヴァイオリン,弦楽と通奏低音の為の協奏曲ヘ長調 RV.291 ヴァイオリン,弦楽と通奏低音の為の協奏曲ハ長調 RV.175 ヴァイオリン,弦楽と通奏低音の為の協奏曲イ短調 RV.355 ヴァイオリン,弦楽と通奏低音の為の協奏曲イ長調 RV.338 ヴァイオリン,弦楽と通奏低音の為の協奏曲ホ短調 RV.274 ヴァイオリン,弦楽と通奏低音の為の協奏曲ハ長調 RV.176 ヴァイオリン,弦楽と通奏低音の為の協奏曲ホ短調 RV.275 ヴァイオリン,弦楽と通奏低音の為の協奏曲変ロ長調 RV.377 ヴァイオリン,弦楽と通奏低音の為の協奏曲ヘ長調 RV Anh.130 |
フロリアン・ドイター(Vn) アルモニー・ウニヴェルセル 録音:2007年10月、西部ドイツ放送室内楽ホール、ケルン、ドイツ |
| DACAPO MAR-8.226134(1CD) NX-B06 |
セアンセン(1958-):ピアノと弦楽のための「ミニョン」(2013-2014) セレニッシマ(2014) 深い歌(1997-1998) シャロットの女(1987/1992改編) セレナード(2006) The Weeping White Room-嘆く白い部屋(2002) |
カトリーネ・ギスリンジェ(P) ジョン・ストゥールゴールズ(Vn) ラップランド室内O ジョン・ストゥールゴールズ(指) 録音:2014年12月16-17日 |
|
||
 Treasures TRE-142-143(2CDR) |
ジャンヌ=マリー・ダルレ/サン・サーンス:ピアノ協奏曲全集&七重奏曲 TRE-142とTRE-143をセット化したもの |
ジャンヌ=マリー・ダルレ(P) ルイ・フレスティエ(指) フランス国立放送局O ロジェ・デルモット(Tp)* ガストン・ロジェ(Cb)* パスカルQ団員* 録音:1955-1957年 ※音源:仏PATHE DTX-252、DTX-176、英HMV ALP-1593 ◎収録時間:68:14+74:45 |
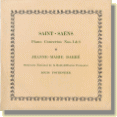 Treasures TRE-143(1CDR) |
ジャンヌ=マリー・ダルレ/サン・サーンス:ピアノ協奏曲集2 ピアノ協奏曲第1番 ピアノ協奏曲第3番 ピアノ協奏曲第4番## |
ジャンヌ=マリー・ダルレ(P) ルイ・フレスティエ(指) フランス国立放送局O 録音:1956年5月、1955年4月##(全てモノラル) ※音源:英HMV ALP-1593、仏PATHE DTX-176## ◎収録時間:74:45 |
|
||
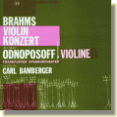 Treasures TRE-156(1CDR) |
オドノポゾフ~ブラームス、サン・サーンス他 サン・サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ ハバネラOp.83 サラサーテ:ツィゴイネルワイゼン ブラームス:ヴァイオリン協奏曲* |
リカルド・オドノポゾフ(Vn) ジャンフランコ・リヴォリ(指)ジュネーヴRSO カール・バンベルガー(指)フランクフルト歌劇場O* 録音:1955年頃、1954年頃*(全てステレオ) ※音源:日Concert Hall SM-2250、仏Prestige de la Musique SR-9653* ◎収録時間:65:49 |
| “甘美な音色と厳しい造形力を駆使した「語り」の妙味!!” | ||
|
||
| Lydia Music LYD-001(1CD) NX-B03 |
ショパン:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲 第1番 ピアノ協奏曲 第2番 |
エリザベス・ゾンバルト(P・・・Fazioli 278) ロイヤルPO ピエール・ヴァレー(指) 録音 2014年5月アビー・ロード・スタジオ |
|
||
 Treasures TRE-146(1CDR) |
カンポーリ~ブルッフ、サン・サーンス&ラロ ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 サン・サーンス:ハバネラ* 序奏とロンド・カプリチオーソ* ラロ:スペイン交響曲# |
アルフレッド・カンポーリ(Vn) ロイヤルトン・キッシュ(指)新交響楽団 アナトール・フィストラーリ(指)LSO* エドゥアルド・ヴァン・ベイヌム(指)LPO# 録音:1951年4月17日、1953年11月10日*、1953年3月3-4日# ※音源:英DECCA ACL-124、ACL-64# ◎収録時間:77:08 |
| “作品の様式美を踏み外さないカンポーリの芳しい歌心!” | ||
|
||
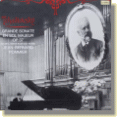 Treasures TRE-145(1CDR) |
J・B・ポミエ/チャイコフスキー&ベートーヴェン チャイコフスキー:ピアノ・ソナタ.ト長調Op.37 「ドゥムカ」-ロシアの農村風景Op.59* ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」# |
ジャン=ベルナール・ポミエ(P) ディミトリ・コラファス(指) ラムルーO 録音:1964年6月18-25日&10月20-22日&11月4日、1964年10月20-24日&11月4日*、1962年#(全てステレオ) ※音源:東芝 AA-8022、仏Club Francais 2300# ◎収録時間:79:53 |
| “10代から備わっていたポミエの美麗タッチと造形力!” | ||
|
||
 PODIUM POL-1053(1CD) |
シューマン:ヴァイオリン協奏曲集 シューマン:(1)ヴァイオリン協奏曲ニ短調 (2)ヴァイオリン協奏曲イ短調Op.127(原曲:チェロ協奏曲) (3)12 のピアノ小品~「夕べの歌」(ヴァイオリン版) (4)ブラームス:ハンガリー舞曲第1、2番 ヨアヒム:ロマンス |
全て、ゲオルグ・クーレンカンプ(Vn) (1)ゲオルグ・クーレンカンプ(Vn) カール・ベーム(指)BPO 録音:1937 年11 月26 日初演ライヴ (2)サシュコ・ガヴリロフ(Vn) ヴァルター・ギレッセン(指) ヴェストファーレンSO 録音:1987 年11 月29 日(ゲネプロ) (3)ゲオルグ・クーレンカンプ(Vn) ハンス・シュミット=イッセルシュテット(指)BPO 録音:1935 年 (4)ヨーゼフ・ヨアヒム(Vn) 録音:1903 年8 月27日 |
|
||
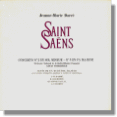 Treasures TRE-142(1CDR) |
ジャンヌ=マリー・ダルレ/サン・サーンス:ピアノ協奏曲集1 サン・サーンス:七重奏曲Op.65* ピアノ協奏曲第2番** ピアノ協奏曲第5番「エジプト風」# |
ジャンヌ=マリー・ダルレ(P) ルイ・フレスティエ(指) フランス国立放送局O ロジェ・デルモット(Tp)* ガストン・ロジェ(Cb)* パスカルQ団員* 録音:1957年6月*、1957年4月27-28日**、1957年4月15-17日# ※音源:仏PATHE DTX-252*、DTX-176 ◎収録時間:68:14 |
| “作曲家直伝という箔を超越したダルレの恐るべき色彩力!” | ||
|
||
 Treasures TRE-141(1CDR) |
マイラ・ヘス~モーツァルト&ブラームス モーツァルト:ピアノ協奏曲第14番K.449 ブラームス:ピアノ協奏曲第2番Op.83* |
マイラ・ヘス(P) ブルーノ・ワルター(指)NYO 録音:1954年1月7日、1951年2月11日*(共にライヴ ※音源:米 Bruno Walter Society PR-36、BWS-736* ◎収録時間:70:21 |
| “ヘスとワルターの親和性が最大に発揮された2大名演!” | ||
|
||
| KOKORO RECORDS KKR-009(1CD) 税込定価 |
GOLD-三味線協奏曲集 (1)川崎絵都夫:三味線協奏曲(2015) (2)江原大介:『魂の絃』 - 三味線と吹奏楽のための協奏曲(2010) (3)コリーン・シュムコー:『When the Waves Clash』 - 三味線協奏曲(2016) (4)三木稔:『三味線協奏曲』(2008) (5)杵屋正邦:『九重』-三絃九重奏曲-(1973) |
野澤徹也(三味線) (2)澤田由香(篠笛)、阿部大輔(尺八I)、本間豊堂(尺八 II)、大上茜(琵琶)、野澤佐保子(箏I)、吉澤延隆(箏 II)、松坂典子(十七絃筝)、吉川玄一郎(打楽器)、冨田晋平(打楽器) (3)野上博幸(指)ミュゼ・ダール吹奏楽団 (4)邦楽創造集団オーラJ (5)野澤徹也(三味線全9パート重ね録り) |
|
||
| AGLAE MUSICA AMC-104(1CD) |
ベートーヴェン:三重協奏曲ハ長調 Op.56* ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op.58 |
ルートヴィヒ三重奏団 [イム・ヒョスン(P) アベル・トマス(Vn)* アルナウ・トマス(Vc)*] ガリシアSO ビクトル・パブロ・ペレス(指) 録音:2013年3月22-23、25-26日、歌劇劇場、ア・コルーニャ、スペイン |
|
||
| Sono Luminus DSL-92204B05 |
Re:Imagined シューマン:チェロ協奏曲イ短調Op.129(チェロと弦楽四重奏版) ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第9番イ長調「クロイツェル」Op.47(チェロと弦楽四重奏版) |
ズィル・ベイリー(Vc) インSQ 録音:2014年10月12-16日 ヴァージニアボイス,ソノ・ルミナス・スタジオ |
|
||
| Sono Luminus SM-234(1CD) |
トランペット協奏曲集 アレクサンドル・アルチュニアン(1920-2012):トランペット協奏曲 ロベール・プラネル(1908-1994):トランペット協奏曲 トレッリ(1658-1709):トランペット協奏曲ニ長調G.28 ヨハン・バプティスト・ゲオルク・ネルーダ(1711-1776):トランペット協奏曲変ホ長調 ハイドン:トランペット協奏曲変ホ長調Hob.VIIe:1 ピアソラ:リベル・タンゴ(G.マンクーシによるトランペットと管弦楽編) エンニオ・モリコーネ(1928-):ミッション-ガブリエルのオーボエ(トランペットと管弦楽編)* |
ヨーゼフ・ホーフバウアー(Tp) クリスティーナ・ホイメッサー(Vc)* シェーンブルン祝祭O グイド・マンクーシ(指) 録音:2015年9月9日…1-3.13-17,2015年7月12日…4-12オーストリアウィーン,ヤマハ・コンサート・ホール |
|
||
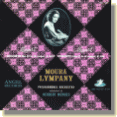 Treasures TRE-129(1CDR) |
リンパニー~モーツァルト:ピアノ協奏曲集 モーツァルト:ピアノ協奏曲第12番(カデンツァ=第1楽章:モーツァルト第2作、第2,3楽章:モーツァルト第1作) ピアノ協奏曲第21番(カデンツァ=第1楽章:ウィンディング作、第3楽章:クレンゲル作)* ブラームス:間奏曲Op.117-2** パガニーニの主題による変奏曲第2巻Op.35-2# ショパン:幻想即興曲Op.66## |
モーラ・リンパニー(P) ハーバート・メンゲス(指) フィルハーモニアO 録音:1954年4月28日、1953年2月17日*、1952年11月3日**、1947年12月19日#、1949年4月26日## ※音源:日Angel HC-1006(モーツァルト)、英Cambridge Records DIMP-2 ◎収録時間:73:33 |
| “英国風の端正さの中に光るリンパニー独自の華やぎ!” | ||
|
||
 Treasures TRE-126(1CDR) |
デニス・マシューズ~モーツァルト モーツァルト:ピアノ・ソナタ第8番K.310* ピアノ協奏曲第24番(カデンツァ=マシューズ作) ピアノ協奏曲第20番(カデンツァ=ベートーヴェン作) |
デニス・マシューズ(P) ハンス・スワロフスキー(指) ウィーン国立歌劇場O 録音:1959年頃*、1958年(全てステレオ) ※音源:米VANGUARD SRV-196SD*、SRV-142SD ◎収録時間:74:42 |
| “天国のモーツァルトに聴かせることだけを考えた唯一無二の感動作!” | ||
|
||
 Treasures TRE-122(1CDR) |
レギーナ・スメンジャンカ/ピアノ協奏曲集 バッハ:ピアノ協奏曲イ長調BWV.1055 モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番 ショパン:ピアノ協奏曲第2番* |
レギーナ・スメンジャンカ(P) スタニスラフ・ヴィスロッキ(指) ヴィトルド・ロヴィツキ(指)* ワルシャワ国立PO 録音:1960年頃、1959年*(全てステレオ) ※音源:独CNR FA-402、独TELEFUNKEN NT-459* ◎収録時間:77:28 |
| “タッチの変化の背後にドラマを添える独自のセンス!” | ||
|
||
| Velut Luna CVLD-241(1SACD) |
チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 瞑想曲 Op.42-1(懐かしい土地の思い出 より、ジョヴァンニ・アンジェレーリ編曲) |
ジョヴァンニ・アンジェレーリ(Vn、指) ヴェネツィアO |
|
||
| Velut Luna CVLD-246(1CD) |
ジョルジョ・ガスリーニ(1929-):シンフォニコ
4 クラリネット協奏曲変ロ長調(2010)* 管弦楽の為のラルゴ(2010)+ 永遠なるベロセットのオートバイ [Moto Velocetto perpetuo](管弦楽の為の;2006)# ビッグバン・ポエム [Big Bang Poema] (管弦楽の為の;1999)** |
アンジェロ・テオーラ(Cl)* ユピテルSO(*/+) キエーティ・マッルチーノ劇場O# フェデーレ・フェナローリ国際青年SO** ジョルジョ・ガスリーニ(指) 録音:2011年2月17日、ライヴ、エクセルシオール劇場、チェザーノ・マデルノ、イタリア(*/+) 2007年2月6日、ライヴ、マッルチーノ劇場、キエーティ、イタリア# 1999年8月22日、ライヴ、ランチアーノ、イタリア** |
|
||
| Hush Collection HUSH-011(1CD) |
ルミナス~インスパイアード・バイ・モーツァルト モーツァルト:クラリネット協奏曲イ長調 K.622より 第2楽章〔p〕 交響曲第40番ト短調 K.550より 第1楽章〔p, vn, vc, b, ds〕 アイネ・クライネ・ナハトムジークより 第1楽章〔p〕、第2楽章〔vc, p〕、第3楽章〔p, vn, vc〕、第4楽章〔p, vn, string quartet〕 ピアノ協奏曲変ロ長調 K.595より 第2楽章〔p, string quartet〕、第3楽章〔p〕 歌劇「魔笛」 より序曲〔p, b, ds, strings〕 ピアノ協奏曲第21番ハ長調 K.467より 第2楽章〔p, b, ds〕 ヴァイオリン・ソナタ変ロ長調 K.454より 第2楽章〔vn, p〕 ピアノ・ソナタイ長調 K.331より 第1楽章〔accordion, vn〕、第1楽章〔p〕 |
ジョー・チンダモ (ピアノ、アコーディオン)、ゾーイ・ブラック(Vn)、サラ・キュロー(Vn)、キャロライン・ヘンベスト(Va)、ジョセフィン・ヴェインズ(Vc)、ダニエル・ファルジア(パーカッション)、フィリップ・レックス(Cb) |
|
||
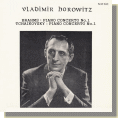 Treasures TRE-104(1CDR) |
ホロヴィッツ~2大激烈ライヴ集 ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番* |
ウラディミール・ホロヴィッツ(P) ブルーノ・ワルター(指)アムステルダム・コンセルトヘボウO ジョージ・セル(指)NYO* 録音:1936年2月20日アムステルダム・コンセルトヘボウ、1953年1月12日カーネギー・ホール(共にモノラル・ライヴ) ※音源:米BRUNO WALTER SOCIETY BWS-728 、Private EV-5007* ◎収録時間:68:53 |
| “似ているようで意味が異なる2つの激烈ライヴ!” | ||
|
||
| Resonus RES-10157(1CD) |
忘れられたウィーン ディッタースドルフ:2つのヴァイオリンのための協奏曲ハ長調 ヴァンハル:交響曲イ短調 オルドネツ:シンフォニア ハ長調 ヴァンハル:ヴァイオリン協奏曲変ロ長調、 レクイエム・ミサ.変ホ長調 |
アマデ・プレイヤーズ、 ニコラス・ニューランド(指) ジョージ・クリフォード(Vn)、 ドミニカ・フェヘール(Vn)、 ケンブリッジ・シドニー・サセックス・カレッジCho 録音:2015年1月26日、9月7日-10日、セント・ジョンズ・スミス・スクエア(ロンドン) |
|
||
| DACAPO MAR-6.220628(1SACD) |
ラース・グラウゴー:作品集 1.ヴィーナス(2013) 2.BookofThrows(2013) 3.レイヤーズ・オブ・アース(2011-2013) 4.3つの場所(2011) |
パッティ・キルロイ(Vn)…1 パトリック・スウォポダ(Cb)…1 ジャン=ミシェル・ピルク(P)…2 イアン・シェーファー(Ob)…3 ラーシュ・グラウゴー(コンピューター)…3 ニューヨーク大学SO…1 ニューヨーク大学現代音楽アンサンブル…2.4 ニューヨーク大学パーカッション・アンサンブル…3 イェンス・ゲオルク・バッハマン(指)…1.3 ジョナサン・ハース(指)…2.4 録音:2013年1月…1,2013年11-12月…2,2012年5月…3,2011年10月…4ニューヨーク |
|
||
| DACAPO MAR-8.226117(2CD) |
ラーシュ・メラー:春のリライト <CD1.春のリライト(スタジオ・ヴァージョン)>1.第1部:エヴォケーション/2.間奏曲/3.第2部:春の広場/4.第3部:プロセッション/<CD2.春のリライト(ライヴ・ヴァージョン)>1.第1部:エヴォケーション/2.間奏曲/3.第2部:春の広場/4.第3部:プロセッション |
デイヴィッド・リーブマン(Sax) マリリン・マズール(パーカッション) オーフス・ジャズ・オーケストラ ラーシュ・メラー(指) 録音:2013年9月26-27日デンマークオーフス,フィンランドスタジオ、2013年9月25日デンマークコペンハーゲン、ジャズハウスライヴ |
|
||
| Les Dissonances LD-006 (2CD+PAL-DVD) |
モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲集(全曲) [CD1] ヴァイオリン協奏曲第1番 変ロ長調 K.207 ヴァイオリン協奏曲第2番 ニ長調 K.211 ヴァイオリン協奏曲第3番 ト長調 K.216 [CD2] ヴァイオリン協奏曲第4番 ニ長調 K.218 ヴァイオリン協奏曲第5番 イ長調 K.219 [DVD] ヴァイオリン協奏曲第1~5番 |
ダヴィド・グリマル(Vn&コンサートマスター)、レ・ディソナンス 収録:2014年3月1日/シテ・ド・ラ・ミュジーク(ライヴ) |
|
||
| Les Dissonances LD-005 (1CD+PAL-DVD) 70ページブックレット付 |
ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 交響曲第4番 ホ短調 op.98 [DVD] ブラームス:交響曲第4番(全曲) |
ダヴィド・グリマル(Vnン&コンサートマスター)、レ・ディソナンス 収録:2012年10月27日(協奏曲)、2013年2月12日(交響曲) |
|
||
| Les Dissonances LD-004 (1CD+PAL-DVD) |
ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 交響曲第4番 ホ短調 op.98 [DVD] ブラームス:交響曲第4番(全曲) |
ダヴィド・グリマル(Vn&コンサートマスター)、レ・ディソナンス 収録:2012年10月27日(協奏曲)、2013年2月12日(交響曲) |
|
||
| Aurora ACD-5080(1CD) |
レーネ・グレナーゲル(1969-):3つの協奏曲 手術(2012)(打楽器とシンフォニエッタのための) スミロドン(2012)(コントラバスクラリネットとシンフォニエッタのための) チェロ協奏曲(2006)(チェロと17人のミュージシャンのための) |
ホーコン・ステーネ(打楽器) ロルフ・ボルク(コントラバスCl) ターニャ・オルニング(Vc) アークティック・フィルハーモニック・シンフォニエッタ ペーテル・シルヴァイ(指) 録音:2014年1月13日-17日 ストーレ・スタジオ(ボードー、ノルウェー) |
|
||
 Treasures TRE-081(1CDR) |
カール・エンゲル~モーツァルト:ピアノ協奏曲集 モーツァルト:ピアノ協奏曲第18番 ピアノ協奏曲第25番(カデンツァ:K.エンゲル) シューマン:子供の情景~トロイメライ* |
カール・エンゲル(P) フェリックス・プロハスカ(指) バイエルンRSO 録音:1963年、1963年頃*(全てステレオ) ※音源:独ELECTROLA STE-91-261、日KING RECORD SH-5043* ◎収録時間:62:35 |
| “モーツァルトの真心を伝える絶妙なタッチ!” | ||
|
||
| CANTABILE CCD-0019(1CD) |
メンデルスゾーン:ヴァイオリン、ピアノと弦楽合奏の為の協奏曲ニ短調(1823) ハイドン:ヴァイオリン,ピアノと弦楽合奏の為の協奏曲ヘ長調(1766) |
セルゲイ・テスリア(Vn) エレーナ・ノガエヴァ(P) ムジカ・ヴィーヴァ室内O アレクサンドル・ルージン(指) 発売:1998年 |
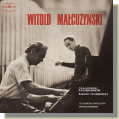 Treasures TRE-088(1CDR) |
マルクジンスキ~チャイコフスキー&ラフマニノフ チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番 |
ヴィトルド・マルクジンスキ(P) ヴィトルド・ロヴィツキ(指) ワルシャワ国立SO 録音:1961年(共にステレオ) ※音源:MUZA SX-0123、SX-0124* ◎収録時間:69:54 |
| “謙虚な燃焼が大きく羽ばたく、ラフマニノフの世紀の名演!” | ||
|
||
 SAKURA SAKURA-5(1CD) |
久成+功芳~宇和島ライヴ2015 チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ベートーヴェン:交響曲第7番 イ長調 Op.92 |
佐藤久成(Vn) 宇野功芳(指)仙台PO ライヴ収録:2015年4月11日宇和島市立南予文化会館 |
| “これ以上は不可能!命を削って奏で尽くすチャイコフスキー” | ||
|
||
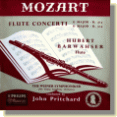 Treasures TRE-076(1CDR) |
バルワーザー~バッハ&モーツァルト バッハ:管弦楽組曲第2番BWV.1067* モーツァルト:アンダンテ.ハ長調K.315# フルート協奏曲第1番ト長調K.313 フルート協奏曲第2番ニ長調K.314 |
フーベルト・バルワーザー(Fl) エドゥアルト・ファン・ベイヌム(指)アムステルダム・コンセルトヘボウO* ベルンハルト・パウムガルトナー(指)ウィーンSO# ジョン・プリッチャード(指)ウィーンSO 録音:1955年5月31日-6月9日*、1954年2月21-22日#、1953年2月28-29日(全てモノラル) ※音源:仏PHILIPS 700064-700055*、仏FONTANA 698094FL ◎収録時間:69:07 |
| “音色美だけではない!愛で語るバルワーザーのフルートの魅力!” | ||
|
||
| CUBE BOHEMIA CBCD-2740(1CD) |
ベートーヴェン三重協奏曲Op.56(1804) ヤン・ヴァーツラフ・ヴォジーシェク(1791-1825):ピアノ,ヴァイオリン,チェロと管弦楽の為の協奏的大ロンド Op.25(1825) |
スメタナ三重奏団 [イトカ・チェホヴァー(P) ヤナ・ヴォナーシコヴァー=ノヴァーコヴァー(Vn) ヤン・パーレニーチェク(Vc)] オロモウツ・モラヴィアPO スタニスラフ・ヴァヴジーネク(指) 録音:2007年9月、オロモウツ、チェコ |
|
||
| TRIART TR-009(1CD) |
R・シューマン:ピアノ協奏曲イ短調 Op.54 C・シューマン:ピアノ協奏曲イ短調 Op.7 |
イトカ・チェホヴァー(P) オロノウツ・モラヴィアPO ペトル・ヴロンスキー(指) 録音:2009年11月5日、2010年11月18日、モラヴィアPOホール、オロモウツ、チェコ |
| Altus Records ALU-0002(1CD) |
ヴィヴァルディ:ヴィルトゥオーゾ・リコーダー協奏曲集 ヴィヴァルディ:協奏曲ハ長調 RV.443、 協奏曲ハ短調 RV.441、 協奏曲ヘ長調 RV.442、 協奏曲ハ長調 RV.444、 協奏曲イ短調 RV.108 サンマルティーニ:協奏曲ヘ長調 ノード:協奏曲ト長調 A・スカルラッティ:合奏協奏曲ニ短調 |
リチャード・ハーヴェイ(リコーダー)、 ロンドン・ヴィヴァルディ・オーケストラ |
|
||
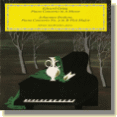 Treasures TRE-063(1CDR) |
エッシュバッハー/グリーグ&ブラームス グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調Op.16 ブラームス:ピアノ協奏曲第2番Op.83* |
アドリアン・エッシュバッハー(P) レオポルド・ルートヴィヒ(指)BPO ウィルヘルム・フルトヴェングラー(指)BPO* ティボール・デ・マヒュラ(Vcソロ)* 録音:1953年3月2-3日、1943年12月12-15日ベルリン・フィル定期公演ライヴ* ※音源:DGG LPE-17143、Melodiya M10-45921-009* ◎収録時間:74:22 |
| “爆撃の危機を乗り切った決死のブラームス!” | ||
|
||
| MUSEU DE VILAFRANCA BLF-005(1CD) |
前衛の声、記憶の声 パブロ・カザルス(1876-1973):チェロ・オーケストラの為のサルダーナ、または、ビラフランカの聖フェリクスの行列* エンリク・カザルス(1892-1986):不安(コブラの為の)+ |
バルセロナSO* フランツ・パウル・デッカー(指)* カタルーニャ室内コブラ+ マルセル・サバテ(指)+ 録音:1996年5月3日、カタルーニャ音楽堂、バルセロナ、スペイン* 2002年+ |
|
||
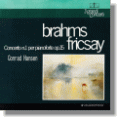 Treasures TRE-056(1CDR) |
コンラート・ハンゼン/モーツァルト&ブラームス モーツァルト:ピアノ・ソナタ第6番ニ長調K.284* ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 |
コンラート・ハンゼン(ハンマークラヴィア*、P) フェレンツ・フリッチャイ(指) ベルリンRIAS響 録音:1956~1957年*、1953年4月19日 ※音源:GRAMMOPHON LGM-1136(JP)*、LONGANESI PERIODICI GCL-50 ◎※収録時間:72:29 |
| “ブラームスの第2楽章は、同曲空前の大名演!” | ||
|
||
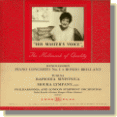 Treasures TRE-049(1CDR) |
メンデルスゾーン:華麗なるロンド ピアノ協奏曲第1番ト短調 Op.25* トゥリーナ:交響的狂詩曲Op.66** グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調Op.16# |
モーラ・リンパニー(P) ハーバート・メンゲス(指)LSO ラファエル・クーベリック(指)フィルハーモニアO* ワルター・ジュスキント(指)フィルハーモニアO** ハーバート・メンゲス(指)フィルハーモニアO# 録音:1952年6月3日、1948年10月3日*、1949年6月20日**、1954年11月4日# ※音源:RCA.HMV LHMV-1025、HMV CLP-1037# ◎※収録時間:64:34 |
| “リンパニーの十八番、グリーグにおける結晶化されたタッチ!” | ||
|
||
 Treasures TRE-048(1CDR) |
ベートーヴェン:三重協奏曲Op.56* ヴァイオリン協奏曲(カデンツァ;ヨアヒム作) |
マヌーグ・パリキアン(Vn) マッシモ・アンフィテアロフ(Vc)* オルネラ・サントリクイド(P)* ワルター・ゲール(指)ローマPO* アレキサンダー・クランハルス(指)フランクフルトRSO 録音:1950年代後半(モノラル) ※音源:Concert Hall MMS-2159*、MMS-2124 ◎※収録時間:79:57 |
| “個性をひけらかさない表現から漂う作品の魅力!” | ||
|
||
| ENCELADE ECL-1302(1CD) |
バッハ:シンフォニア&コンチェルト 2つのヴァイオリンの為の協奏曲ト長調(オルガン・ソナタ BWV530より復元)+ 組曲ホ短調 BWV996~サラバンド(チェンバロ独奏)** カンタータ「キリストは死の絆につきたまえり」BWV4~シンフォニア カンタータ「泣き、嘆き、憂い、怯え」BWV12~シンフォニア ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 BWV1041* カンタータ「主はわれらを思いたもう」BWV196~シンフォニア 3つのヴァイオリンの為の協奏曲ハ長調(3台のチェンバロの為の協奏曲 BWV1064より復元)# |
ダイアナ・リー(Vn)+ アリクス・ボワヴェール、シモン・ピエール(Vn)# ジャン=リュック・オー(Cemb)** アンサンブル・バロック・アトランティーク ギヨーム・ルバンゲ=シュドル(ヴァイオリン(*/+/#)、指揮) 録音:2013年11月18-23日、旧アノンシアード修道院礼拝堂、ボルドー、フランス |
|
||
| ARCO DIVA UP-0160-2(1CD) |
現代チェコのオーボエ音楽 イジー・テムル(1935-):オーボエと弦楽の為のコンチェルティーノ-ヴィヴァルディへのオマージュ* ヤロスラフ・クルチェク(1939-):オーボエと室内管弦楽の為の組曲+ 三重協奏曲 [Concerti per tre] # オーボエ・ダモーレと弦楽の為のコンチェルティーノ** ズデニェク・シェスタク(1925-):エウテルペ、アウレティカ [Euterpe, Auletica](イングリッシュホルンとピアノの為の)++ ヤン・マーレク(1938-):G.A.B.によるオーボエと弦楽の為のパストラーレとダンス## ■ボーナス・トラック リムスキー=コルサコフ(ヤロスラフ・クルチェク編):くまばちの飛行+ |
ガブリエラ・クルチコヴァー(Ob(**/++以外)、オーボエ・ダモーレ**、イングリッシュホルン++) カテジナ・ヤンソヴァー(Fl)# ハナ・ヨウゾヴァー(Hp)# ダニエル・ヴィエスネル(P)++ ムジカ・ボヘミカ・プラハ(++以外) ヤロスラフ・クルチェク(指(++以外)) 録音:1996年、チェコ放送*,1998年、チェコ放送##,2011年、聖ヴァヴジネツ教会++,2014年、福音教会(+/#/**),プラハ、チェコ |
|
||
| MILAN BLAHA 新規扱い BLAHA-6002036(1CD) |
アコーディオン協奏曲集 アントン・ライヒャ (1770-1836):グラスハーモニカと管弦楽の為の大独奏曲ヘ長調 +ヴァーツラフ・トロヤン(1907-1983):幻想曲風カデンツァ* エミル・フランチシェク・ブリアン(1904-1959):アコーディオン協奏曲+ ダリボル・ツィリル・ヴァーチカーシュ(1906-1984):ソプラノサクソフォン、アコーディオン、ギターと管弦楽の為の協奏曲# ヤン・トルフラーシュ(1928-2007): アコーディオンと弦楽合奏の為のスケルツォ** ミロシュ・ヴァツェク(1928-2012):年老いた道化師の思い出++ |
ミラン・ブラーハ(アコーディオン) ミロシュ・マヘク(指)ブルノ放送O* アントニーン・デ・ヴァーティー(指)プルゼニュ放送O+ ミロスラフ・ヤンダ(ソプラノサクソフォン#) ミラン・ゼレンカ(ギター#) イジー・スターレク(指)プラハRSO# ヴラディジミール・ヴァーレク(指)プラハSO** ヨセフ・フルンチーシュ(指)スメタナ劇場O++ 録音:1975年ステレオ*/1961年モノラル+/1968年モノラル#/1972年ステレオ**/1971年ステレオ++ |
|
||
| STUDIO MATOUS MK-0808-2(1CD) 高価格帯 |
ベートーヴェン:三重協奏曲ハ長調 Op.56* ピアノ三重奏曲第3番ハ短調 Op.1-3+ |
マルティヌー三重奏団 [ペトル・イジーコフスキー(P) パヴェル・シャーファジーク(Vn) ヤロスラフ・マチェイカ(Vc)] ムハイ・タン(指)プラハSO* 録音:2012年12月13-14日*、 2008年12月8日+ |
|
||
 Capriccio C-5210D(2CD) ★ |
ブラームス:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲第1番ニ短調Op.15* バラード第1番ニ短調Op.10-1 バラード第2番ニ長調Op.10-2 ピアノ協奏曲第2番変ロ長調Op.83# バラード第3番ロ短調Op.10-3 バラード第4番ロ長調Op.10-4 |
ツィモン・バルト(P) クリストフ・エッシェンバッハ(指) ベルリン・ドイツSO 録音:2012年*、2013年#、2014年 |
| “55分を超える低速で歌い抜く2つの協奏曲!” | ||
|
||
| AD VITAM AV-140315(1CD) |
左手のための作品集 VOL.4 ラヴェル:左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調 プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第4番 変ロ長調 op.53 ブリテン:ディヴァーションズ(左手のピアノと管弦楽のための協奏曲) |
マキシム・ゼッキーニ(P) ヤン・モリッツ・オンケン(指)ケープPO 録音:2013 年10月 |
|
||
| Sheva Collection SH-107(1CDR) |
モーツァルト&サリエリ:ピアノ協奏曲集 モーツァルト:ピアノ協奏曲第22番変ホ長調 K.482 サリエリ:ピアノ協奏曲ハ長調 |
ウィリアム・グラント・ナボレ(P)、 クリストフ・マイスター(指)ブリクシ室内O |
|
||
| OBSIDIAN OBSCD-713(1CD) |
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲ニ長調RV124 ヴァイオリン協奏曲集『四季』 Op.8-1~4 第1番ホ長調 Op.8-1, RV.269『春』 第2番ト短調 Op.8-2, RV.315『夏』 第3番ヘ長調 Op.8-3, RV.293『秋』 第4番ヘ短調 Op.8-4, RV.297『冬』 弦楽のための協奏曲ト短調RV157 |
ラース・ウルリク・モルテンセン(指&Cemb) ヨーロッパ・ユニオン・バロックO ヒュー・ダニエル(Vn:春) ボージャン・クルキッチ(Vn:夏) ヨハネス・プラムゾーラー(Vn:秋) ゼフィラ・ヴァロヴァー(Vn:冬) アントニ オ・デ・サルロ( 語り) 録音:2014年6月22、24日トリフォリオン・アトリウム、エヒタナハ、ルクセンブルク |
|
||
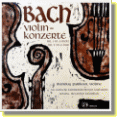 Treasures TRE-037(1CDR) |
パリキアン~バッハ&モーツァルト バッハ:ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 ヴァイオリン・ソナタ ホ短調 BWV 1023# モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」* |
マヌーグ・パリキアン(Vn) アレクサンダー・クランハルス(指)バーデン室内O ワルター・ゲール(指)アムステルダム・フィルハーモニー協会O* アレクサンダー・モルツァン(Vc)#、 ヘルベルト・ホフマン(Cemb)# 録音:1959年頃(全てモノラル) ※音源:独CONNCERT HALL MMS-2148、MMS-2206*、 ◎※収録時間:77:30 |
| “地味な佇まいから引き出される作品の様式美!” | ||
|
||
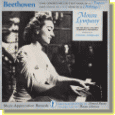 Treasures TRE-035(1CDR) |
モーラ・リンパニー~ベートーヴェン&フランク フランク:交響的変奏曲* ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」 ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 |
モーラ・リンパニー(P) ワルター・ジュスキント(指)フィルハーモニアO* トーマス・シャーマン(指)スタジアム・コンサートSO 録音:1947年*、1957年ニューヨーク(全てモノラル) ※音源:RCA LHMV-1013*、Music Appreciation Record MAR-5713 ◎※収録時間:69:42 |
| “気高い推進力!、リンパニー絶頂期の貴重なベートーヴェン!” | ||
|
||
 Treasures TRE-034(1CDR) |
ユージン・リスト~ショスタコーヴィチ&チャベス ショスタコーヴィチ:ピアノ協奏曲第1番* ピアノ協奏曲第2番** チャベス:ピアノ協奏曲(1940)# |
ユージン・リスト(P) フリッツ・ヴェゼニック(Tpソロ)* ゲオルク・ルートヴィヒ・ヨッフム(指)ベルリン歌劇場O* ヴィクトール・デザルツェンス(指)ウィーン国立歌劇場O** カルロス・チャベス(指)ウィーン国立歌劇場O# 録音:1960年、1962年#(全てステレオ)、 ※音源:Westminster WST-14141、WST-17030# ◎※収録時間:76:41 |
| “クールなピアニズムが冴え渡る、初演者ユージン・リストによる快演!” | ||
|
||
| UNIVERSAL MUSIC ITALY 476-5048(1CD) |
ヴィオッティ:祈りならがの瞑想(ヴァイオリンと管弦楽の為の) ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 W.I-22 ヴァイオリン協奏曲第24番ロ短調 W.I-24 |
グイード・リモンダ(Vn、指) カメラータ・ドゥカーレ |
|
||
| UNIVERSAL MUSIC ITALY 481-0343(1CD) |
ヴィオッティ:ヴァイオリンと管弦楽の為の主題と変奏曲* ヴァイオリン協奏曲第25番イ短調 W.I-25 G.124 ヴァイオリン協奏曲第12番変ロ長調 W.I-12 G.64 |
グイード・リモンダ(Vn、指) カメラータ・ドゥカーレ |
|
||
| UNIVERSAL MUSIC ITALY 481-1083(1CD) |
ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第30番イ短調 W.I-30(遺作)* ヴァイオリン協奏曲第4番イ短調 W.I-4 G.33 ヴァイオリン協奏曲第20番変ロ長調 W.I-20 G.92 |
グイード・リモンダ(Vn,指) カメラータ・ドゥカーレ *=世界初録音 |
| UNIVERSAL MUSIC ITALY 481-0070(1CD) |
C・P・E・バッハ:チェロ協奏曲イ短調 Wq.170 チェロ協奏曲変ロ長調 Wq.171 チェロ協奏曲イ長調 Wq.172 |
エンリコ・ディンド(Vc、指) イ・ソリスティ・ディ・パヴィア |
 UNIVERSAL MUSIC ITALY 481-0313(1CD) |
チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 |
アイマン・ムサハジャエヴァ(Vn) ウィーンSO マヌエル・エルナンデス・シルヴァ(指) |
|
||
| EM Records EMRCD-023(1CD) |
ミルフォード&スタンフォード:ヴァイオリン協奏曲集 ホルスト:ウォルト・ホイットマン序曲 スタンフォード:ヴァイオリン協奏曲第2番ト短調 Op.162(世界初録音) ミルフォード:ヴァイオリン協奏曲ト短調 Op.47(世界初録音) |
ルパート・マーシャル=ラック(Vn)、 オウェイン・アーウェル・ヒューズ(指) BBCコンサート・オーケストラ 録音:2014年1月7日-9日 |
|
||
| Intergroove IGC-009-2(1CD) |
チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.35 ロココ風の主題による変奏曲Op.33 |
リュドミラ・マリアン(Vn)、 スタニスラフ・ゴルコヴェンコ(指) サンクトペテルブルクRSO |
|
||
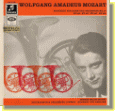 Treasures TRE-024(1CDR) |
デニス・ブレイン/モーツァルト&R・シュトラウス(ブライトクランク版) モーツァルト:ホルン協奏曲第1番~第4番 R・シュトラウス:ホルン協奏曲第1番* |
デニス・ブレイン(Hrn) ヘルベルト・フォン・カラヤン(指) ウォルフガング・サヴァリッシュ(指)* フィルハーモニアO 録音:1953年11月12-23日、1956年9月22日* ※音源:Electrola 1C 0663 00414、HMV HLS-7001*(以上,ブライトクランク擬似ステレオ盤) ◎※収録時間:69:50 |
| “ブライトクランク版で再認識する、D・ブレインの奇跡のニュアンス!” | ||
|
||
| DACAPO MAR-6.220595(1SACD) |
アナス・コッペル:マリンバ協奏曲集 マリンバとオーケストラのための協奏曲第1番(1995)* マリンバと弦楽オーケストラのための協奏曲第2番(2000) マリンバとオーケストラのための協奏曲第3番「リンツ」(2002/2003改訂) マリンバとオーケストラのための協奏曲第4番「変わり行く事象への思い出」(2006) マリンバ・ソロのための「P.S.toaConcerto-協奏曲への追伸」(1995)* |
マリアンナ・ベドナルスカ(マリンバ) オルボアSO ヘンリク・ヴァウン・クリステンセン(指) 録音:2012年6月26-29日.2013年6月24-28日アルボア・シンフォニエン *以外=世界初録音 |
|
||
 Altus ALT-300(1CD) |
アルゲリッチとチェリビダッケ シューマン:ピアノ協奏曲イ短調Op.54 プロコフィエフ:『ロメオとジュリエット』組曲第2 番Op.64よりモンタギュー家とキャピュレット家/少女ジュリエット/別れの前のロメオとジュリエット/アンティーユ諸島から来た娘たちの踊り/ジュリエットの墓の前のロメオ/タイボルトの死 |
マルタ・アルゲリッチ(P) セルジュ・チェリビダッケ(指) フランス国立放送O 録音:1974年5月19日/シャンゼリゼ劇場(ステレオ・ライヴ) |
| “強烈な個性を尊重し合った協調芸術の極み!” | ||
|
||
| LORELEY PRODUCTION LY-053(1CD) |
ヴィヴァルディ:四季 クライスラー:プニャーニの様式による前奏曲とアレグロ パッヘルベル:カノン |
フレデリック・ラロック(Vnソロ、指) ドリアーヌ・ギャーブル(Vn)、 セドリック・ラロック(Vn)、 ダニエル・ヴァグナー(Va)、 ジャン・フェリ(Vc)、アクセル・サル(Cb)、 ジル・ハーレ(Cemb) 録音:2013年5月4,6日(ライヴ)/サント・シャペル(パリ |
|
||
| PUREMUSIC 5414706-10432(1CD) |
チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 1. アレグロ・モデラート(カデンツァ:チャイコフスキー) 2. カンツォネッタ。アンダンテ 3. フィナーレ/アレグロ・ヴィヴァチッシモ(カデンツァ:チャイコフスキー) 4. フィナーレ/アレグロ・ヴィヴァチッシモ(カデンツァ:レオポルト・アウアー) アレンスキー:弦楽四重奏曲第2番 イ短調 op.35* |
フィリップ・クイント(Vn) マルティン・パンテレーエフ(指) ソフィアPO リリー・フランシス(Va) クラウディオ・ボルケス(Vc1)* ニコラ・アルトシュテット(Vc2)* 録音:2013 年 1 月 14‐17 日ブルガリア・ホール(ソフィア) 2013 年9月4-5日シーメンスヴィラ(ベルリン)* |
|
||
| スロヴァキア音楽財団 SF-0073-2(1CD) |
スロヴァキアのヴァイオリン協奏曲集 アレクサンデル・モイゼス(1906-1984):ヴァイオリン協奏曲 Op.53(1957-1958) アンドレイ・オチナーシュ(1911-1995):ヴァイオリン協奏曲 Op.47(1974-1975) デジデル・カルドシュ(1914-1991):ヴァイオリン協奏曲 Op.51(1980) |
ミラン・パリャ(Vn) マリオ・コシク(指)スロヴァキアRSO 録音:2009-2011年、スロヴァキア放送、ブラチスラヴァ、スロヴァキア ライセンサー:スロヴァキア放送 |
|
||
| スロヴァキア音楽財団 SF-0072-2(1CD) |
エフゲニー・イルシャイ(1951-):愛の場所で 消滅 [Uangamizi] (ヴァイオリン、チェロと管弦楽の為の協奏曲;2006)(*/+) サウンドクエイク・ゼロ [Soundquake Zero] (管弦楽の為の;2009) 引用 [Quotations] (ピアノと管弦楽の為の協奏曲;2005/2006)# 愛の場所で [In the Space of Love] (ヴァイオリン、ピアノと管弦楽の為の協奏曲;2004/2005)(*/**) |
ミラン・パリャ(Vn)* ヨゼフ・ルプターク(Vc)+ ラジスラフ・ファンチョヴィチ(P)# エフゲニー・イルシャイ(P)** マリオ・コシク(指)スロヴァキアRSO 録音:2009-2011年、スロヴァキア放送、ブラチスラヴァ、スロヴァキア ライセンサー:スロヴァキア放送 |
|
||
| HEVHETIA HC-10025(1CD) |
ヴァイオリン/ヴィオラと管弦楽の為の音楽 ユライ・ベネシュ(1940-2004): 冬の音楽 [Musica d'inverno] (ヴァイオリンと管弦楽の為の;1992)* エフゲニー・イルシャイ(1951-):アシラの歌 [Ashira Songs]* フランチシェク・グレゴル・エンメルト(1940-):ヤコブの戦い [Jacob's Fight] (ヴィオラと室内弦楽合奏の為の;2009)+ シュニトケ:モノローグ [Monologue] (ヴィオラと室内管弦楽の為の;1989)+ |
ミラン・パリャ(Vn*、Va+) チェコ・ヴィルトゥオージ オンドレイ・オロス(指) 録音:2009年10月18日、11月28日、スタディオン・ブルノ、ブルノ、チェコ |
|
||
.gif) Treasures TRE-011(1CD) |
モートン・グールド・プレイズ・ガーシュウィン 3つのプレリュード~第1番 ラプソディ・イン・ブルー 3つのプレリュード~第2番 ピアノ協奏曲へ調 「ポーギーとベス」組曲(M.グールド編) |
モートン・グールド(指,P) モートン・グールドO 録音:1955年(モノラル) ※音源:RCA LM-6033 ◎収録時間:79:04 |
| “ジャズ・テイストとクラシック様式との完全な調和!!” | ||
|
||
 Treasures TRE-018(1CDR) |
ハンス・リヒター=ハーザー/グリーグ&シューマン他 グリーグ:ピアノ協奏曲* シューマン:ピアノ協奏曲# リスト:愛の夢第3番# グリーグ:抒情小品集第6集~「過ぎ去った日々」Op.57-1 抒情小品集第8集~「トロールハウゲンの婚礼の日」Op.65-6 メンデルスゾーン:無言歌集~「春の歌」Op.62-6 シューマン:子供の情景~トロイメライ |
ハンス・リヒター=ハーザー(P) ルドルフ・モラルト(指)ウィーンSO 録音:1958年1月18-21日*,#(ステレオ)、1958年頃(モノラル) ※音源:蘭PHILIPS 835063*、fontana SFL-14093#、EPIC LC-3620 ◎※収録時間:79:25 |
| “楽想に応じてタッチを無限に変化させる奥義を凝縮!” | ||
|
||
 Treasures TRE-002(1CDR) |
メンデルスゾーン:華麗なカプリッチョ.ロ短調Op.22 ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第1番嬰ヘ短調Op.1* ピアノ協奏曲第2番ハ短調Op.18 |
モーラ・リンパニー(P) ニコライ・マルコ(指) フィルハーモニアO 録音:1953年2月2-3日、1954年4月30日* (全てモノラル) ※音源:MFP 2035、HMV CLP-1037* ◎収録時間:66:48 |
| “ラフマニノフの甘美さと一定の距離を保つことで生まれる気品!” | ||
|
||
| CLA XL HCD-0909(1CD) メーカー在庫限り |
ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 シューマン:花の曲Op.19* |
ヴィルヘルム・ケンプ(P) ピエトロ・アルジェント(指) イタリア放送A.スカルラッティO 録音:1958年1月21日イタリア放送ナポリ 1955年2月26日イタリア放送* 何れもステレオ、ライヴ録音(ライセンス:RAI TRADE) |
|
||
| DACAPO 8.226577(1CD) |
アナス・ノーエントフト:囚われた光 1-3.囚われた光-チェロと小管弦楽のための(1996/1998) 4.ダンス・オブ・セパレーション-弦楽六重奏のための(1998) 5.大聖堂-独奏チェロのための(1986) 6-11.ポインテッド・アウト-クラリネット,ヴァイオリン,チェロ,ピアノのための(2006) 12.アトラーニ-独奏ヴァイオリンのための(1991) 13.Hill Shapes-Wind Stillness-ヴィオラとピアノのための(2000) 14.その瞬間-クラリネット,ヴァイオリン,チェロとピアノのための(1989) |
ヘンリク・ブレンドシュロルプ(Vc) ヨハネス・セー・ハンセン(Vn) クラウス・ミルプ(Va) ジョン・クルーズ(Cl) クリスティーナ・ビェルケ(P) コペンハーゲン・クラシック・オーフス・シンフォニエッタ セアン.k.ハンセン(指) 録音:2008年6月14日オーフスロイヤル・アカデミー・オブ・ミュージック,室内楽ホール…1-3 2011年11月26日オーフス・ムジーク・フセットシンフォニック・ホール…5.14.6-11 2011年4月26日コペンハーゲン国立デンマーク歌劇場,リハーサル・ホール…4 2011年9月23日オーフス・ムジーク・フセットシンフォニック・ホール…12 2011年8月12日オーフス・ムジーク・フセットシンフォニック・ホール…13 ※世界初録音(5.12を除く) |
|
||
 Spectrum Sound CDSMLE-SIK004(1CD) |
ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104 ■ボーナス・トラック モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ第41番 変ホ長調 KV.481 |
ティボール・デ・マヒュラ(Vc) ルドルフ・モラルト(指)ウィーンSO 録音:1953年9 月13-15日、ウィーン 使用音源:独Philips A 00687 R ED 1 LP ■ボーナス・トラック ナップ・デ・クリーン(Vn)、 アリス・ヘクシュ(P) 録音:1951年7月、アムステルダム 使用音源:独Philips A 00691 R ED 1 LP |
| “甘美な囁きと決別した、男気満点のドヴォルザーク!” | ||
|
||
| TRIART TR-005(2CD) |
ブラームス:ヴァイオリンとチェロの為の二重協奏曲イ短調
Op.102* ピアノ協奏曲第1番ニ短調 Op.15+ |
イジー・ヴォディチカv* ヤン・パーレニーチェク(Vc)* イトカ・チェホヴァー(P)+ フラデツ・クラーロヴェーPO オンドジェイ・クカル(指) 録音:2013年11月、フラデツ・クラーロヴェーPOホール、 フラデツ・クラーロヴェー、チェコ |
|
||
| Capriccio C-5155D(1CD) |
ゴッフレード・ペトラッシ:ピアノ協奏曲他 ピアノ協奏曲(1936/1939) ピアノのためのパルティータ(1924) トッカータ(1933) ピアノのためのインベルツィオーニ(1942/1944) |
ピエトロ・マッサ(P) ゲッティンゲンSO クリストフ=マティアス・ミュラー(指) 録音:2011年11月1-2日ゲッティンゲンスタッドハレ 2012年3月31日-4月1日ベルリン,ゲルトナーシュトラッセ・スタジオ |
|
||
| Capriccio C-5197D(1CD) |
エルヴィン・シュルホフ:協奏曲集 ピアノと小管弦楽のための協奏曲Op.43WV66(1923) フルートとピアノ,弦楽合奏,2台のホルンのための二重協奏曲 弦楽四重奏と管楽アンサンブルのための協奏曲WV97(1930) ベートーヴェン:失われた小銭への怒り(シ ュルホフ編) |
フランク=インモ・ツィヒナー(P) ジャック・ズーン(Fl) ライプツィヒSQ ローランド・クルティヒ(指)ドイツSO 録音:2007年11月21-22日 2007年11月28-29日 |
|
||
| Cello Classics CC-1031(1CD) |
モール・ダブルス・ブラームス ブラームス:ヴァイオリンとヴィオラのための協奏曲イ短調Op.102 モール:2つのチェロのための協奏曲ニ長調Op.69 |
キン・リー・ウェイ(Vc)、 チェン・ジョウ(Vn)、 セバスチャン・コンベルティ(Vc)、 ジェイソン・ライ(指) ヨン・シュウトウ音楽院O 録音:2012年3月10日、2013年1月22日-24日 |
|
||
 DORON DRC-3065(1CD) |
サン=サーンス:ピアノ協奏曲第2番 ト短調 Op.22 ピアノ協奏曲第5番ヘ長調 Op.103「エジプト風」* |
ムーザ・ルバツキーテ(P) ハンス=マルティン・シュナイト(指) アラン・パリ(指)* リトアニア国立PO 録音:2001年12月1日、2013年3月16日*、ヴィリニュス、国立フィルハーモニック・ホール、ライヴ |
| “近年稀に見る、怖いもの知らずのスケール感と色彩の渦!” | ||
|
||
| BOMBA BOMB-033-854(1CD) |
ヤコフ・スロボトキン(1920-2009) ウェーバー:チェロ・ソナタ.イ長調* メンデルスゾーン:チェロとピアノの為の協奏的変奏曲ニ長調 Op.17+ グリーグ:チェロ・ソナタ.イ短調 Op.36# ハイドン::チェロ協奏曲第2番ニ長調 Hob.VII:b** |
ヤコフ・スロボトキン(Vc) ヤコフ・フリエール(P)* ナウム・ヴァリテル(P)+ グリゴリー・ギンズブルク(P)# ソヴィエト国立SO弦楽パート** アレクサンドル・ガウク(指)** 録音:データ記載なし、モノラル |
|
||
 ORFEO ORFER-855141(1CD) |
ダニエル・ミュラー=ショット/ドヴォルザーク作品集 4つのロマンティックな小品Op.75* チェロ協奏曲ロ短調Op.104 森の静けさOp.68-5 ロンド.ト短調Op.94 スラヴ舞曲第8番ト短調Op.46-8* わが母の教え給いし歌Op.55-4* |
ダニエル・ミュラー=ショット(Vc;1727年製マッテオ・ゴッフリラー) ミヒャエル・ザンデルリング(指) 北ドイツRSO ロベルト・クーレック(P)* 録音:2011年6月27日-7月1日ハンブルク、NDR、ロルフ・リーバーマン・スタジオ |
| “現代が誇る、最高に男前な「ドボチェロ」!” | ||
|
||
 CRQ Editions CRQCD-107(1CDR) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第17番K.453 ピアノ協奏曲第25番K.503 |
デニス・マシューズ(P) ハリー・ブレック(指) ロンドン・モーツァルト・プレーヤーズ 録音:1955年頃 ※音源:英Columbia 33SX1044 |
|
||
 Altus ALT-294(1CD) |
シューベルト:『ロザムンデ』序曲D.797 ドヴォルザーク:チェロ協奏曲ロ短調Op.104* デュティユー:メタボール |
ピエール・フルニエ(Vc)* セルジュ・チェリビダッケ(指) フランス国立放送O 録音:1974年10月2日、シャンゼリゼ劇場(ステレオ・ライヴ) 音源提供:フランス国立視聴覚研究所 |
| “チェリの冷静さをよそに、なぜか燃え盛るフルニエ!” | ||
|
||
 ALTO ALC-1255(1CD) |
ハチャトゥリアン:ヴァイオリン協奏曲ニ短調* ピアノ協奏曲変ニ長調+ |
ボリス・グートニコフ((Vn)* コンスタンチン・イヴァーノフ(指)ソヴィエト国立SO* アンネッテ・セルヴァデイ(P)+ ジョゼフ・ジュンタ(指)LPO+ 録音:1981年*/1987年10月+ 原盤:Melodiya* / Hyperion+ ライセンサー:A Tempo Prague, Aquarius Music* 前出:Regis, RRC 1300(廃盤) |
| “それぞれの個性が曲の魅力を倍加させた、好対照な2つの名演!” | ||
|
||
 DORON DRC-3064(1CD) |
パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第4番(第1楽章カデンツァ:マリオ・ホッセン) ヴァイオリン協奏曲第2番(第1楽章カデンツァ:フランソワ・ピエール・デカン) |
マリオ・ホッセン(Vn)、 ヴァレリー・ヴァチェフ(指) ブルガリアRSO 録音:2007年9 月、2008 年10 月、 |
|
||
 Hanssler(SWR) 94-226(1CD) |
ヨハンナ・マルツィ/メンデルスゾーン&ブラームス メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調 Op.64 ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.77* |
ヨハンナ・マルツィ(Vn) ハンス・ミュラー=クライ(指) ギュンター・ヴァント(指)* SWRシュトゥットガルトRSO 録音:1959年2月5日、1964年2月6日*、リーダーハレ・シュトゥットガルト(共にモノラル) |
| “無限に溢れる豊穣なニュアンス!EMIのセッション録音と並ぶ大名演!” | ||
|
||
 Hanssler(SWR) 94-225(1CD) |
ゲザ・アンダ~SWR放送録音集第5集 バルトーク:ピアノ協奏曲第2番* チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 ブラームス:間奏曲 ホ長調Op.117-1(アンコール) |
ゲザ・アンダ(P) ハンス・ミュラー=クライ(指)* フェルディナント・ライトナー(指) SWR シュトゥットガルトRSO 録音:1950年11月14日(モノラル)*、1973年3月13日(ステレオ)、リーダーハレ、シュトゥットガルト |
|
||
| King International KKC-2085(1CD) |
ケンプ~1965年のモーツァルト モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番ハ短調K.491 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」* |
ウィル ヘルム・ケンプ(P) アレクサンダー・ルンプフ(指) 外山雄三(指) 共に、NHK響* 録音:1965年6月8日東京文化会館、1967年11月3日(共に東京文化会館/ステレオ・ライヴ) |
|
||
 King International KKC-2086(1CD) |
最晩年のボレット ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番ニ短調Op.30 ショパン:夜想曲第5番嬰ヘ長調Op.15-2 |
ホルヘ・ボレット((P) デーヴィッド・アサートン(指)NHK響 録音:1988年11月9日NHKホール(デジタル・ライヴ) |
| “至上の歌とまろやかな音色に彩られた、感動必至のラフマニノフ!” | ||
|
||
| King International KKC-2088(2CD) ★ |
アニー・フィッシャー~生誕100年 シューマン:ピアノ協奏曲イ短調* ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番** モーツァルト:ピアノ協奏曲第22番# |
アニー・フィッシャー(P) クリストフ・ペリック(指)* ミルディアス・カリーディス(指)** フェルディナント・ライトナー(指)# NHK響 録音:1985年10月18*、1987年10月16日**、1983年6月22日*、 (全てNHKホール/デジタル・ライヴ) |
|
||
 Altus ALTSA-285(1SACD) シングルレイヤー ALT-285(1CD) |
ブラームス:悲劇的序曲 Op.81 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調『皇帝』 Op.73* |
セルジュ・チェリビダッケ(指) フランス国立放送O, アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(P)* 録音:1974年10月16日、シャンゼリゼ劇場(ステレオ・ライヴ) |
| “終楽章必聴!ミケランジェリだけが可能な驚異の「皇帝」!” | ||
|
||
 Spectrum Sound CDSMBA-002(2CD) |
スヴェトラーノフ&スタニスラフ・ネイガウス スヴィリドフ:「トリプティク」 ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番ハ短調Op.18 チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」 |
エフゲニー・スヴェトラーノフ(指) フランス国立放送O スタニスラフ・ネイガウス(P) 録音:1973年2月7日、シャンゼリゼ劇場 (ステレオ・ライヴ) |
|
||
 Altus ALT-285(1CD) |
ブラームス:悲劇的序曲 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 |
セルジュ・チェリビダッケ(指) フランス国立放送O アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(P) 録音:1974年10月16日、シャンゼリゼ劇場(ステレオ・ライヴ) ※正規初出 |
|
||
 Guild Historical GHCD-2405(1CD) |
ストコフスキーのモーツァルト1949-1969 (1)歌劇「フィガロの結婚」序曲 (2)ピアノ協奏曲第20番ニ短調 K.466* (3)そりすべり(ドイツ舞曲第3番 K.605)** (4)ピアノ協奏曲第24番ハ短調 K.491+ (5)トルコ行進曲(ストコフスキー編)++ |
レオポルド・ストコフスキー(指) フィラデルフィアO マリア・イザベラ・デ・カルリ(P)*、 インターナショナル・フェスティヴァル・ユースO*、 ヒズSO**、 エズラ・ラクリン(P)+、 ヒューストンSO+、NBC響++ 録音:(1)1960年12月12日(ステレオ) (2)1969年8月31日(ステレオ) (3)1949年3月2日、(4)1960年10月24日 (5)1955年2月9日(RCA音源) ※リマスタリング:ピーター・レイノルズ&レイノルズ・マスタリング ※マスター・ソーズ:エンノ・リエケーナ・コレクション |
|
||
 Signum Classics SIGCD-345(1CD) |
モーツァルト:ホルン協奏曲全集 ホルン協奏曲第2番変ホ長調 K.417 断章ホ長調 K.494a ホルン協奏曲第4番変ホ長調 K.495 ホルン協奏曲第3番変ホ長調 K.447 ホルン協奏曲第1番ニ長調 K.412/K.514 ホルン協奏曲楽章変ホ長調 K.370b & K.371 |
ロジャー・モンゴメリー(ナチュラルHrn)、 マーガレット・フォートレス(指&Vn) エイジ・オヴ・インライトゥメントO 録音:2012年10月25日、クイーン・エリザベス・ホール・ライヴ ※使用楽器:プラハのフランツ・シュトールのレプリカ・モデル |
| “遂に出た!ナチュラル・ホルンによるモーツァルトの最高峰!” | ||
|
||
 韓国Warner Classics PWC13D-0011(13CD) ★ |
クリスチャン・フェラス~The Art of Violin ■CD 1 フランク:ヴァイオリン・ソナタ.イ長調 フォーレ:ヴァイオリン・ソナタ第1番イ長調 Op.13 ■CD 2 チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調 ■CD 3 ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ラロ:スペイン交響曲 ■CD 4 ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第1番ニ長調 Op.12-1 ヴァイオリン・ソナタ第2番イ長調 Op.12-2 ヴァイオリン・ソナタ第3番変ホ長調 Op.12-3 ヴァイオリン・ソナタ第4番イ短調 Op.23 ■CD 5 ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第5番ヘ長調 Op.24 '春' ヴァイオリン・ソナタ第6番イ長調 Op.30-1 ヴァイオリン・ソナタ第7番ハ短調 Op.30-2 ■CD 6 ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第8番ト長調 Op.30-3 ヴァイオリン・ソナタ第9番イ長調 Op.47「クロイツェル」 ヴァイオリン・ソナタ第10番ト長調 Op.96 ■CD 7 バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲ニ短調 BWV.1043 ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲(カデンツァ:クライスラー)* ■CD 8 モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調 K.218 ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 K.219 「トルコ風」 ■CD 9 ドビュッシー:ヴァイオリン・ソナタ.ト短調 エネスコ:ヴァイオリン・ソナタ第3番イ短調 Op.25* ラヴェル:ツィガーヌ_9.05 ■CD 10 ブラームス:二重協奏曲Op.102 ■CD 11 ベルク:ヴァイオリン協奏曲 パリ音楽院O バンドー:ハンガリー風協奏曲 (1958)* ■CD 12 フォーレ:ヴァイオリン・ソナタ 第1番イ長調 Op.13 ヴァイオリン・ソナタ 第2番ロ短調 Op.108 ■CD 13 ショーソン:終わりなき歌 Op.37 (Charles Cros)*_7.05 ピアノ,ヴァイオリンと弦楽四重奏のための協奏曲ニ長調 Op.21+ |
全て、クリスチャン・フェラス(Vn) ■CD 1 ピエール・バルビゼ(P) 録音:1957年5月15-19日(モノラル) ■CD 2 コンスタンティン・シルヴェストリ(指) フィルハーモニアO 録音:1957年6月26-28日(ステレオ) ■CD 3 ワルター・ジェスキント(指) フィルハーモニアO 録音:1958年5月25~27日(ステレオ) ■CD 4~CD 6 ピエール・バルビゼ(P) 録音:1958年11月17-24日(モノラル) ■CD 7 ユーディ・メニューイン(Vn)、 バース・フェスティバルO マルコム・サージェント(指)* ロイヤルPO* 録音:1959年7月8日、1959年10月8-10日*(共にステレオ) ■CD 8 アンドレ・ヴァンデルノート(指) パリ音楽院O 録音:1960年9月20日(ステレオ) ■CD 9 ピエール・バルビゼ(P) 録音:1962年5月30日 1962年6月5日*(全てステレオ) ■CD 10 ポール・トルトゥリエ(Vc) パウル・クレツキ(指) フィルハーモニアO 録音:1962年6月22-23日(ステレオ) ■CD 11 ジョルジュ・プレートル(指) アラン・ロンバール(指)* パリ音楽院O 録音:1963年)(ステレオ) ■CD 12 ピエール・バルビゼ(P) 録音:1964年9月21-25(ステレオ) ■CD 13 アンドレ・エスポジート(S)+ ピエール・バルビゼ(P) パレナンSQ 録音:1966年、1968年+(ステレオ) |
|
||
| MUSIC VARS VA-0165(1CD) 未案内旧譜 |
ポッパー(1843-1913):チェロと管弦楽の為のヴィルトゥオーゾ作品集 小ロシアの歌による幻想曲 Op.43 スコットランド幻想曲 Op.71 スペイン舞曲集 Op.54 演奏会用ポロネーズ Op.14 |
ドミニカ・ホシュコヴァー(Vc) イジー・マラート(指) プルゼニュRSO 録音:2007年5月9-10日、11月5-6日、2008年2月11-13日 |
|
||
 BARTOK RECORDS BR-1928[BR](1CD) |
バルトーク:ピアノ協奏曲第1番 ロバート・マン:物語(TALES) ~アンデルセンとキプリングによる(ナイチンゲール/エンドウ豆の王女/クジラはどうして喉を持つようになったか/サイはどうして皮がシワシワか) |
レオニード・ハンブロ(P) ロバート・マン(Vn、指) ジンブラー・シンフォニエッタ ルーシー・ローワン(語り) 録音年不詳,モノラル(1950年代) ※ピーター・バルトークによるハイファイ録音 |
|
||
| Capriccio C-7172E(5CD) |
オルガン協奏曲集 <CD1.ヘンデル:作品集> オルガン協奏曲 第6 番 変ロ長調 Op.4-6 HWV294 オルガン協奏曲 第3番 ト長調 Op.4-3 HWV291 オルガン協奏曲 第4 番 ヘ長調 Op.4-4 HWV292 オルガン協奏曲 第2 番 変ロ長調 Op.4-2 HWV290 オルガン協奏曲 第5 番 ヘ長調 Op.4-5 HWV293 オルガン協奏曲 ヘ長調 HWV295「カッコウとナイチンゲール」 <CD2.J.S.バッハ&C.P.E.バッハ:作品集> バッハ:オルガン協奏曲 ニ短調 (BWV146 とBWV188 より) C.P.E.バッハ:オルガン協奏曲 ト長調 Wq.34 H444 C.P.E.バッハ:オルガン協奏曲 変ホ長調 Wq.35 H446 <CD3.J.ハイドン:作品集> オルガン協奏曲 ハ長調 Hob.XVIII:1 オルガン協奏曲 ハ長調 Hob.XVIII:5 オルガン協奏曲 ハ長調 Hob.XVIII:8 オルガン協奏曲 ハ長調 Hob.XIV:11 オルガン協奏曲 ハ長調 Hob.XIV:12 <CD4.M.ハイドン&J.ハイドン&モーツァルト:作品集> M.ハイドン:オルガンとヴィオラと弦楽のための協奏曲 ハ長調 P.55 ハイドン:オルガン協奏曲 ハ長調 Hob.XVIII:10 モーツァルト:教会コンチェルト 第17 番 ハ長調 K336 教会コンチェルト 第8 番 ヘ長調 K224 教会コンチェルト 第1 番 変ホ長調 K67 教会コンチェルト 第15 番 ハ長調 K328 <CD5.J.G.ラインベルガー:作品集> オルガン協奏曲 第1 番 ヘ長調 Op.137 オルガン協奏曲 第2 番 ト短調 Op.177 ヴァイオリンとオルガンのための組曲 ハ短調 Op.166 |
アキム・エルザベット(Org) クリスティーネ・ショルンスハイム(Org) マルティン・ハーゼルベック(Org) ローランド・ミュンヒ(Org) フランツ・レーンドルファー(Org) アンドレアス・ユフィンガー(Org) 他 ウィーン・アカデミー 新バッハ・コレギウム・ムジクム 「カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ」CO 他 |
|
||
| Aurora ACD-5069(1CD) |
ヨン・オイヴィン・ネス(1968?):獰猛なケンタッキーの運命の母たち ピアノ協奏曲《強烈な日の光(サンバースト)》 (2005?07) 増幅したギターと管弦楽のための協奏曲《私の心をカトノサに埋めてくれ》(2005) 2つのトロンボーンと2つのアンサンブルのための協奏曲《獰猛なケンタッキーの運命の母たち》(ロングバージョン)(2006) |
マグヌス・ロドガール(P) トマス・ヒェクスタ(G) スヴェッレ・リス(Tb) マリウス・ヘスビ(Tb) ノルウェー放送O トマス・リームル(指) 録音:2011年3月10日、14日-15日、21日-23日 ノルウェー放送 (NRK) 大スタジオ(オスロ) |
|
||
 Pavane ADW-7550(5CD) ★ |
オマージュ・トゥ・カルロ・ヴァン・ネスト
~ベルギーのヴァイオリン・スクール ド・ベリオ:ヴァイオリン協奏曲第7番ト長調Op.76、ヴァイオリン協奏曲第2番ロ短調Op.32 ブルギニョン:ヴァイオリン協奏曲Op.86(世界初録音) デヴリーゼ:ヴァイオリン協奏曲(世界初録音) ド・クロス:協奏曲第7番ハ短調 フェルブッシュ:ヴァイオリン協奏曲Op.37(世界初録音) ユイブレシュト:ヴァイオリン・ソナタ ブラームス:ワルツ変イ長調Op.39-15 フランツ・アントン・シューベルト:ミツバチOp.13-9 クライスラー:コレッリの主題による変奏曲 ヴュータン:ヴァイオリン協奏曲第2番嬰ヘ短調Op.19 イザイ:ヴァイオリンと管弦楽のための「悲劇的な詩」 Op.12 シュヴルイユ:ヴァイオリン協奏曲第2番Op.56 ブラームス:ピアノ三重奏曲第1番ロ長調Op.8、 ピアノ三重奏曲第2番ハ長調Op.87、 ピアノ三重奏曲第3番ハ短調Op.101、 ピアノ三重奏曲第4番イ長調Op.posth. |
カルロ・ヴァン・ネスト(Vn)、 エドガール・ドヌー(指)RTB室内O フランツ・アンドレ(指)INRSO、 ダニエル・スターンフェルド(指)INR大SO、 ルネ・ドフォッセ(指)ナウム・スルスニー(P)、 エリック・フェルブッシュ(Vc) 録音:1928年-1977年 |
|
||
| WERGO WER-6755 (1SACD) |
ロルフ・リーム:作品集 Hamamuth-天使の街 この子供たちは誰だ?* |
ニコラス・ホッジ(P) ビート・フラー(指) バーデンバーデン&フライブルクSWR響 録音:2012、2009* ※2作品とも世界初録音 |
|
||
 Alba ABCD-356 (1SACD) |
グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調 Op.16 シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 Op.54 |
ヤンネ・メルタネン(P) ハンヌ・コイヴラ(指)イェヴレSO 録音:2012年 |
| “豪放かつ繊細!!名手メルタネンのグリーグ&シューマン” | ||
|
||
 Hyperion CDA-67917(1CD) |
ドヴォルザーク:チェロ協奏曲ロ短調 Op.104 私にかまわないで Op.82-1(レオポルド編) チェロ協奏曲ロ短調 Op.104のオリジナル・エンディング チェロ協奏曲イ長調 B.10(ギュンター・ラファエル校訂) |
スティーヴン・イッサーリス(Vc) ダニエル・ハーディング(指) マーラー室内O 録音:2012年10月20日-21日、テアトロ・コムナーレ・ディ・フェラーラ(イタリア) |
| “民族色に頼らず、熱きロマンを爆発させた感動作!” | ||
|
||
 東武レコーディングズ TBRCD-0020(1CD) |
ゲルハルト・ヘッツェル/日本ライヴ ブラームス:ヴァオリン協奏曲* モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」 |
ゲルハルト・ヘッツェル(Vn) 渡邉曉雄(指)東京都SO* ハインツ・レークナー(指)読売日本SO 録音:1988年3月16日サントリーホール(デジタル・ライヴ)* 、1988年3月14日東京文化会館(ステレオ・ライヴ ) サウンド・マスタリング:WEITBLICK |
| “遂に出現!ヘッツェル極めつけのソロ録音!” | ||
|
||
 LAWO Classics LWC-1039(1CD) |
ミュージック・フォー・ブルー・デイズ~チューバのための作品集 フォン・コック:チューバ協奏曲 ヴォーン・ウィリアムズ:チューバ協奏曲 オーゴール=ニルセン:チューバ協奏曲「フェンリルの叫び」、 チューバとハープのための「ミュージック・フォー・ブルー・デイズ」 |
アイリク・イェルデヴィーク(Tub) ビョルン・ブライスタイン(指)プレヴェンPO アンネケ・ホドネット(Hp) 録音:2011年9月&2012年4月 |
|
||
| THE MASTERCLASS MEDIA FOUNDATION MMF4-044(DVD) |
ボリス・クシュニール/ヴェルビエ音楽祭アカデミー モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第4番K218(第1&2楽章) |
生徒:マイア・カベサ(Vn) アルブレヒト・メンツェル(Vn) |
|
||
| DACAPO MAR-6.220567(1SACD) |
アンディ・ペイプ:デンマークのアメリカ人 デンマークのアメリカ人(2003) 郊外のナイトメア(2006) 失われた時間の痕跡(1998/2011) |
カール・ボイエ・ハンセン(Tub) モルテン・エステルゴー(Fg) ヘンリク・ヴァウン・クリステンセン(指) オーデンセSO 録音:2011年10月3-7日オーデンセ・コンサート・ホール |
|
||
| DACAPO MAR-8.226076(1CD) |
マグヌス・リンドベルイ:オーケストラのための「EXPO」(2009) ピアノ協奏曲第2番(2011-2012)* オーケストラのための「アル・ラルゴ」 (2009-2010) |
イェフィム・ブロンフマン(P)* アラン・ギルバート(指)NYO 録音:2009年9月16日 2012年5月3日 2010年6月23日 |
|
||
| Laborie LC-07(1CD) |
リラ・オルガニザータ第2弾 ハイドン:ノットゥルノ第1番 Hob.II:25 ハ長調〔2 リラ、2Cl、2Hrn、2Vla、bc〕(1790) 作曲者不詳 ( 伝:モーツァルト):ふたつのリラ・オルガニザータのための協奏曲 ヘ長調〔2Hrn、弦〕 ハイドン:ノットゥルノ第2番 Hob.II: 26 ヘ長調〔2 リラ、2Cl、2Hrn、2Vla、BC〕(1788/90?) ヴィンチェンツォ・オルジターノ:シンフォニア第3番 ニ長調〔2Vn, 2Vla, 2Vc, Cb, Cem, Fg, 2リラ、2Ob, 2Cl, 2Hrn, BC〕(1786) ハイドン:リラ・オルガニザータのための協奏曲第3番 ト長調 Hob.VIIh:03〔2 リラ、2Vn, 2Vla, BC, 2Hrn〕(1786) プレイエル:2つのリラ・オルガニザータのためのノットゥルノ.ハ長調 B.202.5〔2 リラ, 2Cl, 2Hrn, 2Vla, BC〕(1785) |
クリストフ・コワン(Vc,指) リモージュ・バロック・アンサンブル マティアス・ロイプナー、 ティエリー・ヌア、トビーミラー 録音:2009年9月 |
|
||
| Capriccio C-5156D(2CD) |
カステルヌォーヴォ=テデスコ:ピアノ協奏曲・ピアノ作品集 ピアノ協奏曲第1番ト長調Op.46(1927) ピアノ協奏曲第2番ヘ長調Op.92(1936/37) マーメイドと脂っこい魚Op.18 仙人草と西洋山査子Op.21 船乗りOp.13/海藻Op.12 ダビデ王の舞曲Op.37/楽しみOp.54 2つの映像のための習作Op.67 波Op.86 パデレフスキーへのオマージュ |
ピエトロ・マッサ(P) シュテファン・マルツェフ(指) ノイブランデンブルクPO 録音:2010年11月11日ノイブランデンブルクコンチェルトキルヒェライブ |
|
||
| ELOQUENTIA EL-1340(1CD) |
ブリテン:ヴァイオリン協奏曲op.15 ヨナタン・ベルゲル(b.1954):Liyeh (ヴァイオリン、ツィンバロン、打楽器と弦楽オーケストラのための)* |
リヴィア・ゾーン(Vn) ルイジ・ピオヴァノ(指)マッルチーノ・ディ・キエーティ劇場O リヴィア・ゾーン(Vn)*、 ヤン・ロキタ(ツィンバロン)* ヘンク・ギッタルト(指)バンフ・センターCO* 録音:2010年5月(ライヴ、イタリア) 2007年2月(ライヴ、バンフ)* |
|
||
| MN RECORDS MNRCD-205(3CD) ★ |
マイケル・ナイマン~COLLABORATIONS ■CD1(MNRCD 116) 「The Glare」 デイヴィッド・マッカルモン&マイケル・ナイマンによるSongs 1. Take the Money and Run 2. Secrets, Accusations and Charges 3. City of Turin 4. Friendly Fire 5. In Rai Don Giovanni 6. In Laos 7. Going to America 8. Fever Stick and Bones 9. A Great Day in Kathmandu 10. Underneath the Hessian Bags 11. The Glare ■CD2 (MNRCD 117) (1)イン・Re ドン・ジョヴァンニ(+ナイジェル・バール) (2)Knowing the Ropes(+マイケル・ナイマン、ナイジェル・バール) (3)Trysting Fields (「数に溺れて」より) (4)ウェディング・タンゴ(+マイケル・ナイマン、ナイジェル・バール) (5)Come Unto These Yellow Sands (6)If(+マイケル・ナイマン) (7)羊飼いにまかせとけ(+マイケル・ナイマン) (8)悲しみを希う心(マイケル・ナイマン・ピアノソロ) (9)ミランダ(+マイケル・ナイマン、ナイジェル・バール) (10)サイレンス ■CD3(原盤:MNRCD 119) マイケル・ナイマン:サンガム (1)「雨を描写する3つの方法」~Sawant(ファースト・レイン)、Rang(自然の色)、Dhyant(瞑想) (2)Samhitha(色を集める) |
■CD1(MNRCD 116) マイケル・ナイマン・バンド&デイヴィッド・マッカルモン 録音:2008年 ■CD2 (MNRCD 117) モーション・トリオ,マイケル・ナイマン、ナイジェル・バール,録音:2009年9月 ■CD3(原盤:MNRCD 119) マイケル・ナイマン(指)、 マイケル・ナイマン・バンド,声/ラヤン・ミスラ、サヤン・ミスラ他,電子マンドリン/U.シュリニヴァス 録音:2002年 |
|
||
| ココロ・レコード KKR-005(1CD) |
三木稔:三味線協奏曲(2008) | 野澤徹也(三味線) 澤田由香(篠笛)、高橋聡子(笙) 山口賢治(尺八Ⅰ)、 阿部大輔(尺八Ⅱ)、 櫻木亜木子(琵琶)、 松村エリナ(二十絃筝Ⅰ)、 桑子裕子(二十絃筝Ⅱ)、 小林導恵(十七絃筝Ⅱ)、 若月宣宏(打楽器Ⅰ)、 片岡寛晶(打楽器Ⅱ) |
|
||
| DACAPO MAR-6.220599 (1SACD) |
ヴァーフン・ホルンボー:協奏曲集 ヴィオラ協奏曲Op.189(1992) 管弦楽のための協奏曲(1929)* ヴァイオリン協奏曲第2番Op.139(1979) |
エーリク・ヘイド(Vn) ラーシュ・アネルス・トムテル(Va) デマ・スロボデニューク(指) ノールショッピングSO 録音:2011年6月13-17日スウェーデンノールショッピングデ・ゲールハレン ※世界初録音(*は世界初演) |
|
||
| Discovery DMV-104(1CD) |
ガニング:協奏曲集 ギター協奏曲「マヨルカの思い出」 クラリネット協奏曲/フルート小協奏曲 |
クレイグ・オグデン(G)、 マイケル・ホワイト(Cl)、 キャスリン・ハンドリー(Fl)、 クリストファー・ガニング(指)ロイヤルPO 録音:2011年6月&2012年5月 |
|
||
 オクタヴィア DGY-001(1CD) |
ディーリアス:春初めてのカッコウの声を聴いて モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番ハ長調 K.467 ショパン:ピアノ協奏曲第1番~第2楽章 ドヴォルザーク:チェコ組曲Op.39 ■特典DVD メイキング オブCD(スペイン) |
イングリット・フジコ・ヘミング(P) トビアス・ゴスマン(指) スペイン・カメラータ21オーケストラ 録音:2012年/スペイン ※アーティストの希望により解説書は英文のみの掲載。 |
|
||
| Goodies 78CDR-3422(1CDR) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第15番変ロ長調 K.450 (カデンツァ: モーツァルト) |
キャスリーン・ロング(P) ボイド・ニール(指)ナショナルSO (1944年12月14日ロンドン、キングスウェイ・ホール録音) |
|
||
| Phono Suecia PSCD-188(1CD) |
スウェーデンのソプラノ・サクソフォン協奏曲集 マッティンソン:ソプラノ・サクソフォン協奏曲第1番「ゴールデン・ハーモニー」 スヴェン=ダーヴィド・サンドストレム:ソプラノ・サクソフォンとシンフォニック・バンドのための「4つの小品」* エリーアソン:ソプラノ・サクソフォンと弦楽オーケストラのための協奏曲** |
アンデシュ・パウルソン(ソプラノSax) クリストフ・アルトシュテット(指)ノールランド歌劇場SO、 トビアス・リングボリ(指)ヘルシンボリSO* ユハンネス・グスタフソン(指)ノールショピングSO** 録音:2011年-2012年 |
|
||
 オクタヴィア OVCL-00491 (1SACD) |
ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調Op.26 R.シュトラウス:ヴァイオリン・ソナタ 変ホ長調Op.18* |
小林美樹(Vn) 宮本文昭(指)東京シティPO 松本和将(P)* 録音 2012年5月26日 東京・ティアラこうとう・ライヴ 2012年12月12-13日 東京・稲城iプラザ* |
| “名作、R・シュトラウス:ヴァイオリン・ソナタに新たな光!” | ||
|
||
| Capriccio C-5139D(1CD) |
ハイドン:チェロ協奏曲第1番ハ長調Hob.VIIb:1 チェロ協奏曲第2番ニ長調Hob.VIIb:2 |
ハリエット・クリーフ(Vc) クラウディウス・トラウンフェルナー(指) ウィーン室内PO 録音:2012年3-4月ライディングリスト・コンチェルト・ホール |
|
||
| DUTTON CDLX-7284(1CD) |
ライオネル・センズベリー(1958-):チェロ協奏曲 Op.27(1999)* ジョン・フォウルズ(1880-1939):チェロ協奏曲ト長調 Op.17(1908-1909)+ |
ラファエル・ウォルフィッシュ(Vc) マーティン・イェーツ(指) ロイヤル・スコティッシュ・ナショナルO* ボーンマスSO+ 録音:2011年5月25日RSNOセンター・ヘンリー・ウッド・ホール・グラスゴー、イギリス* 2011年6月30日ライトハウス・プール、ドーセット、イギリス+ 世界初録音と表示されています。 |
| DUTTON CDLX-7286(1CD) |
クリストファー・ライト(1954-):モメントゥム(2008)* ヴァイリン協奏曲「そして静寂が訪れた…」(2010)+ ヴォーン・ウィリアムズ:交響曲第5番(ピーター・ホートン校訂新版;2008)# |
フェネッラ・ハンフリーズ(Vn)+ クリストファー・ワトソン(T)+ マーティン・イェーツ(指) ロイヤル・スコティッシュ・ナショナルO(*/+) ボーンマスSO# 録音:2011年5月24日RSNOセンター、ヘンリー・ウッド・ホール &2011年8月2日ロイヤル・コンサートホール、グラスゴー、イギリス(*/+) 2011年7月1日ライトハウス、プール、ドーセット、イギリス# (*/+)世界初録音、#新版による世界初録音と表示されています。 |
| DUTTON CDLX-7287(1CD) |
ゲオルギー・カトゥアール(1861-1926):ピアノ協奏曲 Op.21(1909) パーシー・シャーウッド(1866-1939):ピアノ協奏曲第2番変ホ長調(1932-1933) |
竹之内博明(P) マーティン・イェーツ(指) ロイヤル・スコティッシュ・ナショナルO 録音:2011年8月3-4日、ロイヤル・コンサートホール、グラスゴー、イギリス 世界初録音と表示されています。 |
| DUTTON CDLX-7290(1CD) |
ジョン・マッケイブ:あまつばめ(2つのヴァイオリンと弦楽合奏の為の協奏曲(2003) 多雨林 II(トランペットと弦楽の為の;1987)* 多雨林 I(室内アンサンブルの為の;1984)+ キャラバン(弦楽合奏の為の;1987-1988/改訂:2011) |
レトリカ* ハリエット・マッケンジー、フィリッパ・モー(Vn) アンジェラ・ウェラン(Tp)* オーケストラ・ノーヴァ(+以外) オーケストラ・ノーヴァ・アンサンブル+ ジョージ・ヴァス(指) 録音:2012年2月22-23日、ヘンリー・ウッド・ホール、ロンドン、イギリス 世界初録音と表示されています。 |
| DUTTON CDLX-7291(1CD) |
バンジャマン・ゴダール(1849-1882):ピアノ協奏曲第2番 Op.148(1893) ペルシャ幻想曲 Op.152(1893) 歌劇「ジョスラン」Op.100(1887)~組曲第1番[前奏曲,間奏曲「山の中で」,カリヨン] 組曲第2番[ 鷲の洞窟の前奏曲,子守歌+,舞踏会の場面] |
ヴィクター・サンジョルジョ(P)* アレクセイ・キセリョフ(Vc)+ マーティン・イェーツ(指) ロイヤル・スコティッシュ・ナショナルO 録音:2012年5月17-18日、ロイヤル・コンサートホール、グラスゴー、イギリス +以外世界初録音と表示されています。 |
| DUTTON CDLX-7292(1CD) |
セシリア・マクドウォール(1951-):グレート・ヒルズ(ヴァイオリン、2つのフルートと弦楽合奏の為のコンチェルタント;2007)* 橋を渡って(弦楽合奏の為の;2011)+ 海上予報(混声合唱、朗読と弦楽合奏の為の;2011)# パヴァーヌ(室内管弦楽の為の;1999/管弦楽版;2004)** 雨、蒸気、速度(室内管弦楽の為の;2006)** タンゴの劇場(バリトン、ヴァイオリンと室内管弦楽の為の;2011)++ |
マデリーン・イーストン(Vn)* キャスリン・トマス、ジョアンナ・ショー(Fl)* アンドルー・ホブデイ(朗読#) オックスフォード・マートン・カレッジ聖歌隊# オーケストラ・ノーヴァ(*/+/#) ジェレミー・ヒュー・ウィリアムズ(Br)++ タマーシュ・コチシュ(Vn)++ アルスターO(**/++) ジョージ・ヴァス(指) 録音:2011年9月15日、アルスター・ホール、ベルファスト、北アイルランド、イギリス(**/++) 2012年2月4日、殉教者聖サイラス教会、ケンティッシュ・タウン、ロンドン、イギリス(*/+/#) 世界初録音と表示されています。 |
| DUTTON CDLX-7296(1CD) |
ブライアン(1876-1972):ヴァイオリン協奏曲ハ長調(1934-1935)* 交響曲第13番ハ長調(1959)+ イギリス組曲第4番「幼稚園」(1921)# |
ロレイン・マクアスラン(Vn)* マーティン・ブラビンズ(指) ロイヤル・スコティッシュ・ナショナルO 録音:2012年5月31日、6月1日、RNSOセンター、ヘンリー・ウッド・ホール、グラスゴー、イギリス +世界初録音、#初デジタル録音と表示されています。 |
| SWEDISH SOCIETY SSACD-1145(2SACD) |
トビアス・ブルーストレム(1978-):管弦楽作品集 ピアノ協奏曲「ベル・エポック」(ピアノと弦楽合奏ための;2010-2011)* 万華鏡(管弦楽の為の;2008) ヴァイオリン協奏曲(2008)+ 地下鉄(管弦楽の為の;2007) ルチェルナリス(トランペット、ライヴエレクトロニクスと管弦楽の為の協奏曲;2009)# |
ペール・テングストランド(P)* 五明カレン(Vn)+ ホーカン・ハーデンベルガー(Tp)# ユハンネス・グスタフソン(指)イェヴレSO 録音:2010年10月18日-22日、2011年6月7日-10日、イェヴレ・ホール、イェヴレ、スウェーデン |
 ELECT ERT-1009(1CD) |
ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 バッハ:ヴァイオリン協奏曲第2番 シャコンヌ(BWV.1004より)* |
ヘンリク・シェリング(Vn) ヨシフ・コンタ(指)ルーマニア国立RSO 録音:1961年9月18日、1961年9月13日(共にジョルジュ・エネスコ国際音楽祭・ステレオ・ライヴ) ※CD日本プレス。英語、日本語によるライナーノート付。 |
| “途絶えない緊張と集中力!絶頂期のシェリングのステレオ・ライヴ!” | ||
|
||
| RPR RP-008(2CDR) ★ |
ヴィヴァルディ&ヘンデル ヴィヴァルディ:協奏曲ヘ長調RV.433「海の嵐」 協奏曲イ短調RV.445、 協奏曲ハ短調RV.441、 奏曲ニ長調RV.428「ごしきひわ」、 協奏曲ト短調RV.439「夜」、 協奏曲ハ長調RV.443 ヘンデル:ソナタ.ト長調Op.1-5*、 ソナタ.ト短調Op.1-2*、 ソナタ.ハ長調Op.1-7*、 調子のよい鍛冶屋*、 ソナタ.ニ長調HWV.378*、 ソナタ.ニ短調Op.1-1*、 ソナタ.ヘ長調Op.1-11*、 ソナタ.ニ短調HWV.367a「フィッツウィリアム」* |
ピアーズ・アダムズ(リコーダー)、 ロバート・キング(指&Cemb)、 ムジカ・ダ・カメラ、 ハワード・ビーチ(Cemb&Org )*、 デイヴィッド・ワトキン(Vc)* 録音:1988年11月&1989年11月* |
|
||
 LORELEY PRODUCTION LY-050(1CD) |
ロドリーゴ:アランフエス協奏曲 ある紳士のための幻想曲 |
エマニュエル・ロスフェルデル(G) アリー・ヴァン・ビーク(指) オーヴェルニュO 録音:2012年5月4-5日、ヴィシー・オペラ座 |
|
||
| IVM PMV-ACTUAL007 (1CD) |
ミゲル・ガルベス=タロンチェル(1974-):ヴァイオリン協奏曲「生ける愛の炎」* 管弦楽の為の協奏曲+ バスクラリネット協奏曲# |
アーヴィン・アルデッティ(Vn)* バレンシア自治州立青年O(*/+) マヌエル・ガルドゥフ(指(*/+)) カルロス・ガルベス=タロンチェル(バスCl)# ボロ・ガルシア(指)アンサンブル・エスパイ・ソノル# 録音:2008年3月26-28日、ビラ・ホヨサ劇場ホール、アリカンテ県、スペイン* 2008年7月17-19日、プリンシパル劇場、カステリョン、スペイン+ 2009年1月16-17日、リリア専門音楽院、バレンシア県、スペイン# |
|
||
| ARCO DIVA UP-0145-2(1CD) |
チャイコフスキー:アンダンテ・カンタービレ ロココ風の主題によるチェロと管弦楽の為の変奏曲 Op.33* 弦楽合奏の為の悲歌 チェロと管弦楽の為の奇想的小品 Op.62* プロコフィエフ:シンフォニエッタ.イ長調 Op.48 |
イジー・バールタ(Vc)* レオシュ・スヴァーロフスキー(指) パルドゥビツェ・チェコ室内PO |
| ARCO DIVA UP-0147-2(1CD) |
クラリネットと弦楽の為のクロスオーヴァー作品集 シルヴィエ・ボドロヴァー(1954-):Babadag(クラリネットと弦楽四重奏の為の) オンドジェイ・クカル(1964-):Clarinettino(クラリネットと弦楽の為の協奏曲)* ヤン・ドゥシェク(1985-):Meanwhile(クラリネットと弦楽の為の) トマーシュ・パールカ(1978-):Metafolkphoses(クラリネットと弦楽四重奏の為の) ヤン・クチェラ(1977-):Birth アラン・シュルマン(1915-2002):Rendezvous(クラリネットと弦楽の為の) ピアソラ:Oblivion* オリヴァー・エドワード・ネルソン(1932-):StolEN-Moments |
イルヴィン・ヴェニシュ(Cl) エポックSQ 【ダヴィド・ポコルニー、 ヴラディミール・クラーンスキー(Vn) ヴラディミール・クロウパ(Va) ヴィート・ペトラーシェク(Vc)】 ダヴィト・パヴェルカ(Cb)* 録音:2011年12月、プラハ音楽アカデミー、マルティヌー・ホール |
|
||
 Simax PSC-1323(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番ハ長調K467(カデンツァ:ハドランの自作) ピアノ協奏曲第22番変ホ長調K482 (カデンツァ:ベンジャミン・ブリテン) |
クリスチャン・イーレ・ハドラン(P) アルヴィド・エンゲゴール(指) オスロPO 録音:2011年5月18-20日 |
| “神の手”が導き出す、さり気なくも感動的なモーツァルト! | ||
|
||
 ABC Classics ABC-4764836(1CD) |
ショパン:ピアノ協奏曲第2番ヘ短調Op.21 ピアノ協奏曲第1番ホ短調Op.11* |
エヴァ・クピーク(P)、 セバスティアン・ラング=レッシング(指)タスマニアSO、 クリストファー・シーマン(指)メルボルンSO* 録音:2005年5月アーツ・センター(メルボルン)* 2011年3月10日-11日フェデレーション・コンサート・ホール(ホバート) |
| “ローカル色に安住せず、ショパンの内面に深く問い掛ける真摯さ!” | ||
|
||
 ORFEO DOR ORFEOR-867121(1CD) |
ロッシーニ:「セミラーミデ」序曲 シューマン:ピアノ協奏曲イ短調Op.54 モーツァルト:協奏交響曲変ホ長調K 364* |
スヴャトスラフ・リヒテル(P) ゲルハルト・ヘッツェル(Vn) ルドルフ・シュトレング(Va) リッカルド・ムーティ(指)VPO 録音:1972年8月17日ザルツブルク・祝祭大劇場(ライヴ・ステレオ) 1974年7月27日ザルツブルク・祝祭小劇場(ライヴ・ステレオ)* |
| “気品のヘッツェルと奥ゆかしさのシュトレングによる含蓄に富んだニュアンス!” | ||
|
||
| SUBITON SUB-0027-2(1CD) |
バッハ、ヴィヴァルディ:2つ&3つのヴァイオリンの為の協奏曲集 ヴィヴァルディ:2つのヴァイオリン,弦楽と通奏低音の為の協奏曲イ短調 Op.8-3 RV522+ バッハ:2つのヴァイオリン,弦楽と通奏低音の為の協奏曲ニ短調 BWV1060R+ ヴィヴァルディ:2つのヴァイオリン、弦楽と通奏低音の為の協奏曲変ロ長調 RV524* バッハ:3つのヴァイオリン,弦楽と通奏低音の為の協奏曲ヘ長調 RV551(*/+) |
ヤロスラフ・スヴィエチェニー(Vn) ダナ・ブラホヴァー(Vn)* ユリエ・スヴィエツェナー(Vn+) ヴィルトゥオージ・プラジェンセス(室内O) イトカ・ナヴラーチロヴァー(Cemb) トマーシュ・ストラシル(Vc) ミラン・ライチーク(アーティスティック・ディレクター) 録音:2010年、Fermata a.s.、チェコ |
|
||
| THURI THR-0001(1CD) 【未案内旧譜】 |
フランチシェク・クサヴェル・トゥリ(1939-):オーボエ協奏曲集 オーボエ,弦楽と通奏低音の為の協奏曲ニ短調 オーボエ,弦楽と通奏低音の為の協奏曲変ホ長調 オーボエ,2つのホルンと弦楽と通奏低音の為の協奏曲ヘ長調 オーボエ,オーボエ・ダモーレ,イングリッシュホルン,弦楽と通奏低音の為の三重協奏曲ニ長調 |
ヤン・トゥリ(Ob、オーボエ・ダモーレ、イングリッシュホルン) フランチシェク・クサヴェル・トゥリ(指) トゥリ室内O 録音:2005年3月5-13日、プラハ |
|
||
 DORON DRC-4020(1CD) |
~Legendary Artistsシリーズ~ グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調 Op.16 メンデルスゾーン:ピアノ協奏曲第1番* |
メナヘム・プレスナー(P) ジャン=マリー・オーベルソン(指)ウィーン祝祭O ハンス・スワロフスキー(指)ウィーン国立歌劇場O* 録音:1965年11月11日,1966年6月6日*,ADD(共にステレオ) ※コンサートホール原盤 |
|
||
| ORFEUS MUSIC OMCD-03(1CD) |
ヴィラ=ロボス:ギターの為の5つの前奏曲 ギター協奏曲+ 感傷的なメロディ(ギター、ヴァイオリンと管弦楽の為の)(*/+) |
クシシュトフ・メイシンゲル(G) アンドルー・ハヴァロン(Vn)* アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ ジョゼ・マリア・フロレンシオ(指) 録音:2011年11月、アビー・ロード・スタジオ1、ロンドン、イギリス |
|
||
| DACAPO MAR-558.226569(1CD) |
カスリーネ・リング:ハンド・フォー・ホルンボー すてきなお茶をください!(室内協奏曲第4番第2楽章) 笑うウサギ(室内協奏曲第4番第1楽章 ハリ、ハリ(室内協奏曲第1番第2楽章) ヘリコプター(室内協奏曲第8番第1楽章) 鳥たち(室内協奏曲第2番第1楽章) 道すがら(室内協奏曲第7番第2楽章) 熊が来るぞ(室内協奏曲第6番第1楽章) な、な、な、な、な(室内協奏曲第9番第3楽章) ヴァンとグンナーのパイプの煙 ヴァンとグンナーのパイプの煙(Basicjumpstyle) 〈ボーナスCD(ホルンボーのオリジナル)〉 1.室内協奏曲第4番Op.30第2楽章 2.室内協奏曲第4番Op.30第1楽章 3.室内協奏曲第1番Op.17第1楽章 4.室内協奏曲第8番Op.38第1楽章 5.室内協奏曲第2番Op.20第1楽章 6.室内協奏曲第7番Op.37第2楽章 7.室内協奏曲第6番Op.33第1楽章 8.室内協奏曲第9番Op.39第3楽章 |
ハンヌ・コイヴラ(指) デンマーク国立室内O 2011年8月マスタリング |
|
||
| Sono Luminus DSL-92161(1CD) |
ヴァイル、イベール、ベルク クルト・ヴァイル:ヴァイオリンと管楽オーケストラのための協奏曲Op.12 イベール:チェロと10の管楽器のための協奏曲 ベルク:ピアノとヴァイオリン,13の管楽器のための協奏曲 |
バトン・ルージュ・シンフォニー・チャンバー・プレイヤーズ |
|
||
| IVM PMV-010(1CD) |
マヌエル・パラウ(1893-1967):レバンテ協奏曲(ギターと管弦楽の為の;1947)* 劇的協奏曲(ピアノと管弦楽の為の;1946/1954頃改訂)+ |
ラファエル・セリャレト(G)* バルトメウ・ジャウメ(P)+ マヌエル・ガルドゥフ(指) バレンシア自治州立青年O 録音:2007年7月18日、ライヴ、アリカンテ大学講堂、スペイン* 2008年7月19日、ライヴ、プリンシパル劇場、カステリョン、スペイン* |
|
||
 Hanssler(SWR) HISTORIC Archive 94-219(1CD) |
ブラームス:ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op. 77 セレナード第2番イ長調Op. 16* |
ジノ・フランチェスカッティ(Vn) エルネスト・ブール(指)南西ドイツRSO 録音:1974年4月27日、1978年5月16日* バーデン=バーデン、ハンス・ロスバウト・スタジオ(放送用セッション・ステレオ) |
| “トロける美音と知的な造型制御バランスが完全融合!” | ||
|
||
 Hanssler(SWR) HISTORIC Archive 94-216(1CD) |
ゲザ・アンダSWR録音集Vol.3 モーツァルト:ピアノ協奏曲第17番ト長調KV 453 ピアノ協奏曲第23番イ長調KV 488* ラヴェル:左手のためのピアノ協奏曲 |
ゲザ・アンダ(P) ハンス・ロスバウト(指)、 エルネスト・ブール(指)*、南西ドイツRSO 録音:1952年3月15日、1963年3月13日* バーデン=バーデン、ハンス・ロスバウト・スタジオ(放送用セッション・モノラル) |
| ロスバウトとの相乗効果が生きた、モーツァルト「第17番」の驚愕の名演奏! | ||
|
||
 Hyperion CDA-67795(1CD) |
メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲集 ヴァイオリン協奏曲ホ短調Op.64 序曲「フィンガルの洞窟」Op.26 ヴァイオリン協奏曲ニ短調 |
アリーナ・イブラギモヴァ(Vn)、 ウラディミール・ユロフスキ(指) エイジ・オヴ・インライトゥメントO 録音:2011年9月2日-4日、ヘンリー・ウッド・ホール(ロンドン) |
|
||
| Capriccio C-5118D(1CD) |
ヨスト:ヴァイオリン協奏曲「深き陶酔」 コクーンシンフォニー~大オーケストラによる“中央への旅”の5楽章 |
ヴィヴィアン・ハグナー(Vn) クリスティアン・ヨスト(指) エッセン・フィルハーモニカー |
|
||
| Avanti Classics 5414706-10332 (1SACD+DVD) |
ピアソラ:ミケランジェロ70(F.フシド編) レヴィラド(P.シーグレル編) P.シーグレル:エル・エンペドラド サンドゥンガ/アスファルト? F.フシド:タンゴ・ラプソディー(2台のピアノとオーケストラのための)* シーグレル:ミロンゲータ ピアソラ(P.シーグレル編):天使の死 アディオス・ノニーノ フシド/コーデラー:「瞳の奥の秘密」 |
デュオ・レヒナー・ティエンポ 【カリン・レヒナー(P)&セルジオ・ティエンポ(P)】、 ヤシェク・カスプシク(指)スイス・イタリアーナO 録音:2011年1月オーディトリアム・ステリオ・モロ(ルガーノ、スイス) 2010年6月22-24日パラッツオ・デイ・コングレッシ(ルガーノ)* ライブ録音 |
|
||
| DACAPO MAR-8.226092(1CD) |
ペア・ノアゴー:パーカッションとアンサンブルのための「風景」 破壊への前奏曲(1986) O.サーヴィングの詩「この年」による4つのメディテーション(2010) パーカッション・ソロのための「アラベスク」(2010) パーカッションと6楽器のための「3つの情景」(2009) |
エスビェア・アンサンブル クリスティアン・マルツィネス(Perc) ペッテル・スンドクヴィスト(指) |
|
||
| Slovak Radio RB-0338-2(1CD) |
ミルコ・クライチ(1968-):ピエタ(2005) ヴァイオリン,チェロと室内管弦楽の為の二重協奏曲(2009)* 命の道(混声合唱と弦楽合奏の為の;2008)+ タンギッシモ(弦楽合奏の為の;2008)* |
フランチシェク・テレク(Vn)* オルソリャ・コヴァーチ(Vc)* テクニック混声cho+ イヴェタ・ヴィスクポヴァー(合唱指揮+) テクニック室内O ミルコ・クライチ(指) |
| スロヴァキア音楽財団 SF-0069-2(1CD) |
ミロ・バーズリク(1931-):ピアノ協奏曲(2003-2006)* オラトリオ「十二」(アレクサンドル・ブロークの詩による、6人の独唱者、朗読、合唱と管弦楽の為の;1967)+ |
ダニエル・ブラノフスキー(P)* マリオ・コシク(指)スロヴァキアRSO* フランチシェク・フサーク(朗読+) セルゲイ・コプチャーク(Bs)+ カタリーナ・ブラフシアコヴァー(S)+ ダグマル・ペツコヴァー(アルト+) リュドヴィート・ブフタ(T)+ マリアーン・ブッラ(Bs)+ スロヴァキア・フィルハーモニーcho+ ペテル・フラディル(合唱指揮+) ガブリエル・パトーチ(指)スロヴァキアPO+ |
|
||
| THE MASTERCLASS MEDIA FOUNDATION MMF3-042(DVD) |
ザハール・ブロン/ヴェルビエ音楽祭アカデミー ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 |
生徒:ヴィルデ・フラング、 ノア・ベンディックス=バルグレイ ヴェルビエ音楽祭アカデミー NTSC/16:9 音声:ステレオ/リージョン:All 162mm 言語:ドイツ語 字幕:英語 |
|
||
| Aurora ACD-5075(1CD) |
現代北欧協奏曲集 ネアゴー:チェロ協奏曲第2番《モーメンタム》 (2009) ヌールハイム:テネブレ(チェロと室内管弦楽のための協奏曲) (1982) サーリアホ:アメール (チェロ協奏曲第1番) (1992) |
ヤコブ・クルベア(Vc)、 シモン・ビヴァレツ(指) ニューミュージック・オーケストラ |
|
||
| Guild GMCD-7386(1CD) |
火の手 プーランク:オルガン,ティンパニと弦楽のための協奏曲ト短調 リュッティ:オルガン,弦楽と打楽器のための協奏曲、火の手 アレンスキー:チャイコフスキーの主題による変奏曲Op.35a |
マーティン・ヘイニ(Org)、 マリオ・シュービガー(打楽器&ティンパニ)、 ライナー・ヘルド(指) ノヴォシビルスク国立フィルハーモニー室内O |
|
||
 Inedita PI-2366(1SACD) |
ベートーヴェン・レアリティーズ Vol.7 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 Op.19(未出版の改訂版/カデンツァ:カフカ・スケッチブック所収、未出版) ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op.58(未出版の改訂版;1808) |
マウリツィオ・パチャリエッロ(P) ロベルト・ディエム・ティガーニ(指) サッサリSO 録音:2009年6月9-13日、ヴェルディ劇場、サッサリ、サルデーニャ、イタリア |
|
||
| WERGO WER-6750(1CD) |
ペトリス・ヴァスクス(b.1946):ヴァイオリンと弦楽オーケストラのための作品集 愛の声(ヴァイオリンと弦のためのファンタジア) 遠き光(ヴァイオリンと弦楽オーケストラのための協奏曲) 孤独な天使(ヴァイオリンと弦楽オーケストラのための瞑想曲) |
アリーナ・ポゴストキナ(Vn)、 ユハ・カンガス(指)シンフォニエッタ・リガ 録音:2011年 6月 |
|
||
| Classic Concert Records CCR-62020(1CD) |
ロベルト・ディ・マリノ(1956*):エレジア ピアノ協奏曲/オルガン協奏曲 ギター協奏曲/ロンド・ミロンガ |
ジェリカ・ヴォイヴォーダ(P)、 シモーネ・ヴェベル(Org)、 ロベルト・ベリニチ(G)、 ミラン・ヴァウポティチ((指) ロシアン・シンフォニー・オーケストラ・プロコフィエフ |
|
||
| Aurora ACD-5063(1CD) |
軌道に乗ったズヴェズドフカ~チェロとウィンドバンドのための作品集 ヨン・オイヴィン・ネス:軌道に乗ったズヴェズドフカ (2009)* フリードリヒ・グルダ:チェロとウィンドオーケストラのための協奏曲 (1980)# イベール:チェロとウィンドオーケストラのための協奏曲 (1925) オラヴ・アントン・トンメセン:チェロと2組の木管五重奏のための小協奏曲《光の幻影 (1990) |
エルンスト・シモン・グラーセル(Vc)、 ペーテル・シルヴァイ(指) ノルウェー軍西部音楽隊( ベルゲン) 録音:2010年4月/2010年11月* ライヴ/2011年12月#/(ベルゲン、ノルウェー) |
|
||
| 写影 SHHP-C008(DVD) |
ブラームス:ピアノ協奏曲第2番変ロ長調Op.83 ■特典映像 インタビュー「実相寺昭雄監督と朝比奈隆先生の思い出 出演:寺田農(俳優) 交響曲第4番ホ短調Op.98* |
園田高弘(P) 朝比奈 隆(指)新日本フィル 収録:1990年6月1日オーチャードホール(ライヴ)、1990年6月1日オーチャードホール(ライヴ)* リニアPCMステレオ 133’ カラーNTSC 4 : 3 Region All |
| ||
| DACAPO MAR-6.220592 (1SACD) |
アコーディオン協奏曲集 オーレ・シュミット(1928-2010):交響的幻想曲とアレグロOp.20 アナス・コッペル(1947-):アコーディオンと弦楽の為の「コンチェルト・ピッコロ」* マルティン・ローゼ(1971-):アコーディオンと管弦楽の為の「液体の中に」* ペア・ノアゴー(1932-):アコーディオンと管弦楽の為の「リコール」* |
ビャルケ・モーゲンセン(アコーディオン) ロルフ・グプタ(指)デンマーク国立室内O 録音:2011年4月12-15日コンチェルト・ハウス・スタジオ *=世界初録音 |
|
||
 ORFEO ORFEO-815121(1CD) |
グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調 ノルウェー舞曲集/抒情組曲Op.54 |
ミロフラフ・クルティシェフ(P) アイヴィン・グッルベルグ・イェンセン(指) ハノーファー北ドイツ放送PO 録音:2009年11月、2010年1月 |
| “アイヴィン・グッルベルグ・イェンセンの音楽性と統率力に唖然!” | ||
|
||
 DOREMI DHR-7984(1CD) |
ユリアン・フォン・カーロイの芸術 チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 シューマン:ピアノ協奏曲* リスト:ハンガリー幻想曲# |
ユリアン・フォン・カーロイ(P) ギカ・ズドラフコヴィチ(指)バイエルンRSO ロベルト・ヘーガー(指)バイエルンRSO* エドムント・ニック(指)ミュンヘンPO# 録音:1956年頃(ステレオ)、1948年頃# 原盤:独ELECTROLA、独DGG# |
| “まろやかなタッチから引き出される心あたたまる詩情!” | ||
|
||
 Lipkind Productions LP005-H01NE(1CD) |
チェロ・ヒロイックスⅠ シューマン:チェロ協奏曲イ短調Op.129 |
ガブリエル・リプキン(Vc) ミシャ・カッツ(指) シンフォニア・ヴァルソヴィア 録音:2009年2月21日ヴィトルト・ルトスワフスキ・コンサートホール(ポーランド、ワルシャワ) GLP-0300054と同演奏 |
 Lipkind Productions LP008-H02NE1CD) |
チェロ・ヒロイックスⅡ ショスタコーヴィチ:チェロ協奏曲第1番 |
ガブリエル・リプキン(Vc) ヴォイチェフ・ロデク(指) シンフォニア・ヴァルソヴィア 録音:2009年2月17日ヴィトルト・ルトスワフスキ・コンサートホール(ポーランド、ワルシャワ) GLP-0300055と同演奏 |
 Lipkind Productions LP011-H03NE(1CD) |
チェロ・ヒロイックスⅢ サン=サーンス:チェロ協奏曲第1番 |
ガブリエル・リプキン(Vc) アントニー・ヘルムス(指) シンフォニア・ヴァルソヴィア 録音:2009年2月18日ヴィトルト・ルトスワフスキ・コンサートホール(ポーランド、ワルシャワ) GLP-0300056と同演奏 |
 Lipkind Productions LP014-H04NE(1CD) |
チェロ・ヒロイックスⅣ ドホナーニ:チェロと管弦楽のためのコンツェルトシュテュックニ長調Op.12 |
ガブリエル・リプキン(Vc) イヴァン・メイレマンス(指)アーネムPO 録音:2009年11月25日ズットフェン市立劇場 GLP-0300057と同演奏 |
| Lipkind Productions LP006-H01ED(1CD+) |
チェロ・ヒロイックスⅠ シューマン:チェロ協奏曲イ短調Op.129 |
ガブリエル・リプキン(Vc) ミシャ・カッツ(指) シンフォニア・ヴァルソヴィア 録音:2009年2月21日ヴィトルト・ルトスワフスキ・コンサートホール(ポーランド、ワルシャワ) ※チェロ・パート譜付き |
| Lipkind Productions LP009-H02ED(1CD+) |
チェロ・ヒロイックスⅡ ショスタコーヴィチ:チェロ協奏曲第1番変ホ長調Op.107 |
ガブリエル・リプキン(Vc) ヴォイチェフ・ロデク(指) シンフォニア・ヴァルソヴィア 録音:2009年2月17日ヴィトルト・ルトスワフスキ・コンサートホール(ポーランド、ワルシャワ) ※チェロ・パート譜付き |
| Lipkind Productions LP012-H03ED(1CD+) |
チェロ・ヒロイックスⅢ サン=サーンス:チェロ協奏曲第1番イ短調Op.33 |
ガブリエル・リプキン(Vc) アントニー・ヘルムス(指) シンフォニア・ヴァルソヴィア 録音:2009年2月18日ヴィトルト・ルトスワフスキ・コンサートホール(ポーランド、ワルシャワ) ※チェロ・パート譜付き |
 Lipkind Productions LP015-H04ED(1CD+) |
チェロ・ヒロイックスⅣ ドホナーニ:チェロと管弦楽のためのコンツェルトシュテュックニ長調Op.12 |
ガブリエル・リプキン(Vc) イヴァン・メイレマンス(指)アーネムPO 録音:2009年11月25日ズットフェン市立劇場 ※チェロ・パート譜付き |
|
||
| Smekkleysa ISO-1(2CD) |
グヴズムンスドウッティル/ヴァイオリン協奏曲集 エルガー:ヴァイオリン協奏曲ロ短調* アウグーストソン(1926-):構造 II(1978-1979)+ ブリテン:ヴァイオリン協奏曲 Op.15# パウトル・P・パウルソン(1928-):ヴァイオリン協奏曲** |
グヴズニー・グヴズムンスドウッティル(Vn) ジェイムズ・ロッホラン(指)* リチャード・バーナス(指)+ シドニー・ハース(指)# ペトリ・サカリ(指)** アイスランドSO 録音:1992年11月10日*、 1994年10月28日+、1996年12月6日# 2001年6月12日**、 ハウスコウラビーオウ(大学映画館)、レイキャヴィーク、アイスランド |
|
||
 CLAVES 50-1010(1CD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲ニ長調Op.61a(ヴァイオリン協奏曲のピアノ編曲版) C.P.E.バッハ:協奏曲ハ短調Wq.43No.4 |
ドミトリー・バシキーロフ(P) (Steinway&Sons D-274)、 ペーテル・チャバ(指)ローザンヌCO 録音:2010年4月30日-5月2日、ローザンヌ |
|
||
 Altus ALT-227(2CD) ★ |
バッハ:ブランデンブルク協奏曲全曲 ブランデンブルク協奏曲第1番ヘ長調BWV1046 ブランデンブルク協奏曲第2番ヘ長調BWV1047 ブランデンブルク協奏曲第3番ト長調BWV1048 ブランデンブルク協奏曲第4番ト長調BWV1049 ブランデンブルク協奏曲第5番ニ長調BWV1050 ブランデンブルク協奏曲第6番変ロ長調BWV1051 |
ゲルハルト・ボッセ(指) 神戸市室内合奏団 [客演奏者:コンサートマスター:白井圭(vn)、平尾雅子&瀬田麗(ヴィオラ・ダ・ガンバ)、花崎薫(vc)、北谷直樹(チェンバロ)、白尾彰(fl)、古部賢一、森枝繭子&多田敦美(ob)、岩佐雅美(fg)、 太田光子&宇治川朝政(ブロックフレーテ)、垣本昌芳&永武靖子(hr)、高橋敦(tr)] 録音:2011年3月10日神戸文化ホール中ホール(ライヴ) |
| “先鋭的なバッハとは発する波動が全く別物!心に優しく宿るこの余韻!” | ||
|
||
 BRIDGE BCD-9339(1CD) |
モーツァルト:ピアノ協奏曲集Vol.2 ピアノ協奏曲第11番ヘ長調K.413(カデンツァ:モーツァルト作) ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.466(カデンツァ:第1楽章=ベートーヴェン作、第3楽章=クリスティアン・ツァハリス作) ピアノ協奏曲第21番ハ長調K.467(カデンツァ:ディヌ・リパッティ作) |
ヴァシリー・プリマコフ(P) ジモン・ガウデンツ(指)オーデンセSO 録音:2010年 |
|
||
| Aurora ACD-5066(1CD) |
ペーテル・ヘレスタール~キャッチ・ライト (1)ヨン・オイヴィン・ネス(1968-):マッド・キャップ・トゥートリング(ヴァイオリン協奏曲)(2003) (2)ヘンリク・ヘルステニウス(1963-):ヴァイオリン協奏曲「声のするところから微かな光が」(2001) (3)ギスレ・クヴェルンドク(1967-):イニシエーション(1992)(ヴァイオリンと管弦楽のための) (4)ニルス・ヘンリク・アスハイム(1960-):キャッチ・ライト(2009)(ヴァイオリン、打楽器と管弦楽のための) |
ペーテル・ヘレスタール(Vn) (1)ロルフ・グプタ(指)オスロPO 録音:2008年4月28日-30日オスロ・コンサートホール (2)ピエール=アンドレ・ヴァラード(指) BIT20アンサンブル 録音:2007年1月15日-17日グリーグ・ホール(ベルゲン、ノルウェー) (3)ペーテル・シルヴァイ(指)オスロPO 録音:2009年11月12日オスロ・コンサートホール(ライヴ) (4)ピーター・ケイツ(Perc) ペーテル・シルヴァイ(指)ベルゲンPO 録音:2009年3月28日グリーグ・ホール(ベルゲン、ノルウェー)(ライヴ) |
|
||
| Fabra FBRCD-04(1CD) |
ビョルン・H・クルーセ(1946-):Nostros(ヴァイオリンと弦楽の為の協奏曲;2002)* ギスレ・クヴェルンドク(1967-):Omriss(9人の弦楽器奏者と合唱の為の)+ ヘンリク・オーデゴール(1955-):Nyslatt(2つのハリングフェレと弦楽合奏の為の;2000)# |
ペール・アンデシュ・ビューエン・ガルノース、 トルゲイル・ストロン(ハリングフェレ)# Cor声楽アンサンブル+ テレマルク室内O ラーシュ=エーリク・テル・ユング(Vn*、指) 録音:2003年1月20-22日*、2005年2月8-11日(+/#)、ボー教会(ノルウェー) |
| KNS Classical KNS-A/009(1CD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番ハ長調 Op.15 ピアノ協奏曲第3番ハ短調 Op.37 |
マルコ・スキアヴォ(P) ワレーリー・ポリャンスキー(指) ロシア国立SO(ロシア国立シンフォニー・カペラ) 録音:1996年4月1-3日、モスクワ、モスフィルム・スタジオ |
| Tallpoppies TP-042(1CD) 【未案内旧譜】 |
ハイドン:ホルン協奏曲ニ長調HobVIId:3 クリストフ・フェルスター(1693-1745):ホルン協奏曲変ホ長調 テレマン:ホルン協奏曲ニ長調 アントン・タイバー:ホルン協奏曲変ホ長調 |
ヘクトル・マクドナルド(Hrn) ブレット・ケリー(指) アカデミー・オヴ・メルボルン |
|
||
| ELOQUENTIA EL-1024(2CD) |
サン=サーンス:チェロのための作品全集 [CD1]①チェロ協奏曲第1番op.33イ短調* ②チェロ協奏曲第2番op.119ニ短調 ③チェロ・ソナタ第2番op.123ヘ長調 [CD2「]白鳥」(1挺のチェロと2台ピアノ版)*、チェロ・ソナタ第1番ハ短調Op.32、チェロとピアノのための組曲 Op.16、ロマンスヘ長調Op.36、ロマンスニ長調Op.51、アレグロ・アッパシオナートOp.43、サッフォー風の歌Op.91、 ガヴォット(遺作)(ピアノ伴奏版世界初録音) |
ルイジ・ピオヴァーノ(Vc) 使用楽器:[CD1]①②マッテオ・ゴフリラー(1730頃)、③アレッサンドロ・ガリアーノ(1710頃) [CD2]アルトゥーロ・フラカッシ(1935年) ピエロ・ベッルーギ(指)テアトロ・マッルチーノO ピアノ:ナッツァレーノ・カルージ([CD1]/ヤマハ)、 ルイザ・プレイエル([CD2]/使用楽器:1883年製スタインウェイ・コンサート・グランド・Dモデル(ローズウッド材)、 1999年復元/「白鳥」はセカンド・ピアノ・パートを多重録音) *はライヴ録音 |
|
||
| Classic Concert Records CCR-62003(1CD) |
人生のリズム (1)ジョン・スローワー:2つのマリンバとソプラノのための「一つの世界」 (2)2つのマリンバとソプラノのための「ラヴ・ソングズ」 (3)独奏マリンバと管弦楽のための「人生のリズム」 |
ボグダン・バカヌ、神谷百子(Marimba) カッサンドラ・ディミポウロウ(Sp) ジョン・スロウワー(指) ザルツブルク・ゾリステン |
|
||
| Classic Concert Records CCR-62004(1CD) |
バッハ:無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番BWV1004~シャコンヌ ジョン・スローワー:真実の色彩、 人生のリズム(マリンバ独奏版) エマヌエル・セジュルネ:マリンバ協奏曲 |
ボグダン・バカヌ(Marimba) エヴァルド・ダンホッファー(指) ザルツブルク・ゾリステン |
|
||
| Classic Concert Records CCR-62006(1CD) |
バッハ:マリンバ協奏曲ハ短調BWV1060 マリンバ協奏曲ハ長調BWV1061 マリンバ協奏曲ハ短調BWV1062 |
ペーター・ザードロ(指) ウェイヴ・カルテット(ボグダン・バカヌ、内山詠美子、ヴラディーミル・ペトロフ、クリストフ・ズィーツェン~マリンバ) |
| Classic Concert Records CCR-62002(1CD) |
バッハ:マリンバ協奏曲ニ短調BWV1052 マリンバ協奏曲ニ長調BWV1054 マリンバ協奏曲ヘ短調BWV1056 |
ボグダン・バカヌ、 カテジナ・ミツカ(マリンバ) ブカレスト国立RSO |
| Classic Concert Records CCR-62006(1CD) |
バッハ:マリンバ協奏曲ハ短調BWV1060 マリンバ協奏曲ハ長調BWV1061 マリンバ協奏曲ハ短調BWV1062 |
ペーター・ザードロ(指) ウェイヴ・カルテット(ボグダン・バカヌ、内山詠美子、ヴラディーミル・ペトロフ、クリストフ・ズィーツェン~マリンバ) |
| Classic Concert Records CCR-62002(1CD) |
バッハ:マリンバ協奏曲ニ短調BWV1052 マリンバ協奏曲ニ長調BWV1054 マリンバ協奏曲ヘ短調BWV1056 |
ボグダン・バカヌ、 カテジナ・ミツカ(マリンバ) ブカレスト国立RSO |
|
|
| このサイト内の湧々堂オリジナル・コメントは、営利・非営利の目的の有無に関わらず、 これを複写・複製・転載・改変・引用等、一切の二次使用を固く禁じます。 万一、これと類似するものを他でお見かけになりましたら、メールでお知らせ頂ければ幸いです。 |
Copyright (C) 2004 WAKUWAKUDO All Rights
Reserved.