| 湧々堂HOME | 新譜速報 | 交響曲 | 管弦楽曲 | 協奏曲 | 器楽曲 | 室内楽 | 声楽曲 | 歌劇 | バロック | 廉価盤 | シリーズ |
| 旧譜カタログ | チャイ5 | 殿堂入り | 交響曲 | 管弦楽 | 協奏曲 | 器楽曲 | 室内楽 | 声楽曲 | 歌劇 | バロック | |
| 交響曲・新譜速報1 |
| ※発売済のアイテムも含めて、約3ヶ月間掲載しています。 ※新しい情報ほど上の段に記載しています。 ※表示価格は全て税込みです。 |
| ONDINE ODE-1465(1CD) NYCX-10526(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
フェルディナント・リース(1784-1838):交響曲(第8番) 変ホ長調 WoO30(1822) 交響曲第3番変ホ長調 Op.90(1816) |
タピオラ・シンフォニエッタ ヤンネ・ニソネン(指) 録音:2024年10月29日-11月1日エスポー(フィンランド)、タピオラ・ホール |
|
||
| CPO CPO-555615(1CD) |
エミーリエ・マイヤー(1812-1883):交響曲第4番、第6番 交響曲第4番ロ短調(A.N.タルクマンによる復元版) 交響曲第6番ホ長調 |
ハノーファー北ドイツ放送PO ヤン・ヴィレム・デ・フリーント(指) 録音:2023年2月13-17日 ハノーファー、NDRコンツェルトハウス、放送大ホール(ドイツ) |
|
||
| CPO CPO-555625(1CD) |
フェルディナント・ヒラー(1811-1885): 交響曲 ホ短調 Op.67「それでも春は来るはずだ」 .交響曲 ヘ短調 HWV2.4.4 |
フランクフルト・ブランデンブルク州立O ハワード・グリフィス(指) 録音:2023年4月28日-5月3日 |
|
||
| Capriccio C-5533(1CD) |
シャルル・ケクラン:交響詩「はるかに」 Op.20(1900) 交響曲第1番Op.57bis- 弦楽四重奏曲第2番からの編曲(1916/1926) 3つの歌曲 Op.17(1895-1900) |
パトリシア・プティボン((S) ロイトリンゲン・ヴュルテンベルクPO アリアーヌ・マティアク(指) 録音:2023年10月9-13日ロイトリンゲン、オーケストラ・スタジオ |
|
||
| ONDINE ODE-1449(1CD) |
レポ・スメラ(1950-2000):交響曲第1番(1981) 交響曲第6番(2000) |
エストニア国立SO オラリー・エルツ(指) 録音:2023年8月22-25日エストニア、タリン、エストニア・コンサート・ホール |
|
||
| Orchid Classics ORC-100371(1CD) |
ブルックナー:交響曲第9番ニ短調 WAB109 ノーヴァク版 | ノールショピングSO カール=ハインツ・シュテフェンス(指) 録音:2024年8月27-29日 ルイ・ド・イェール・コンサートホール、ノールショピング(スウェーデン) |
|
||
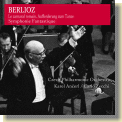 Treasures TRE-346(1CDR) |
カルロ・ゼッキの芸術Vol.1 ベルリオーズ:序曲「ローマの謝肉祭」 ウェーバー(ベルリオーズ編):舞踏への勧誘 ベルリオーズ:幻想交響曲* |
カレル・アンチェル(指) カルロ・ゼッキ(指)*、チェコPO 録音:1964年12月、1959年8月16-19日* (全てステレオ) ※音源:SUPRAPHON 10-8261-1 、SUAST-50103* ◎収録時間:69:57 |
| “やるべきことを全てやり尽くすカルロ・ゼッキの爆裂表現!” | ||
|
||
| TOCCATA TOCC-0727(1CD) |
リヒャルト・フルーリー:管弦楽作品集 第4集 リヒャルト・フルーリー:交響曲第2番「ティチーノ交響曲」(1936) 夜想詩(1939) |
BBC響 イーゴリ・ユゼフォヴィチ(リーダー) ポール・マン(指) 録音:2023年9月25-28日 ※全て世界初録音 |
|
||
 オクタヴィア OVCL-00868(1SACD) 税込定価 2025年5月21日発売 |
ファビオ・ルイージ、エクストン第1弾! ブルックナー:交響曲第8番ハ短調WAB108(初稿/1887年) |
ファビオ・ルイージ(指揮)NHK響 録音:2024年9月14-15日 NHKホール・ライヴ(N響第2016回定期公演Aプロ) |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00877(1SACD) 税込定価 2025年4月16日発売 |
ブルックナー:交響曲 第7番ホ長調(ノーヴァク版) | ジョナサン・ノット(指)東京SO 録音:2024年7月20日 東京・サントリーホール・ライヴ |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00858(1SACD) 税込定価 2025年4月16日発売 |
マーラー:交響曲第1番ニ長調「巨人」 | 小林研一郎(指)LPO 録音:2024年5月11-17日 ロンドン、アビー・ロード・スタジオ |
|
||
| Evil Penguin Records EPRC-0074(1CD) JEPRC-0074(1CD) 日本語解説付国内盤 税込み定価 |
スクリャービン:交響曲第3番ハ短調 Op.43「神聖な詩」 | ブリュッセルPO、 大野和士(指) 録音:2024年2月13日-16日、スタジオ4、フラジェ(ブリュッセル、ベルギー) |
|
||
| NIFC NIFCCD-160(3CD) XNIFCCD-160(3CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ハイドン:交響曲集(2004年ポーランド・ライヴ)
■CD1~交響曲第59番イ長調 Hob.I:59「火事」/アリア「あなたはご存じでいらっしゃる」 Hob.XXIVb:7*/アリア「私の一番いいところは」 Hob.XXIVb:17*/アリア「女房の機嫌がいい時は」 Hob.XXIVb:18*/交響曲第103番変ホ長調 Hob.I:103 「太鼓連打」 ■CD2~交響曲第83番ト短調 Hob.I:83「めんどり」/チェロ協奏曲第1番 ハ長調 Hob.VIIb:1**/交響曲第104番ニ長調 Hob.I:104「ロンドン」 ■CD3~交響曲第64番イ長調 Hob.I:64「時の移ろい」/シェーナ「ベレニーチェ、何をしているの?」 Hob.XXIVa:10***/交響曲第101番ニ長調 Hob.I:101 「時計」 【アンコール】 ベートーヴェン:交響曲第3番 変ホ長調 Op.55「英雄」 より 第3楽章(抜粋)/ヨーゼフ・シュトラウス:ポルカ・マズルカ「とんぼ」 Op.204**** |
18世紀オーケストラ、 フランス・ブリュッヘン(指) ヴィルケ・テ・ブルンメルストルテ(Ms)*、ロエル・ディールティエンス(バロック・チェロ)**、オルガ・パシェチュニク(S)*** 録音(ライヴ):2004年9月2日-4日、ワルシャワ・フィルハーモニー・コンサート・ホール(ポーランド)/2013年8月27日、ポーランド放送ヴィトルト・ルトスワフスキ・コンサート・スタジオ(ポーランド)**** |
|
||
| DUX DUX-2106(1CD) |
エミル・ムイナルスキ:交響曲 ヘ長調 Op.14 《ポーランド》 | ウカシュ・ボロヴィチ(指)、 ポズナンPO 録音:2024年10月11日、アダム・ミツキェヴィチ大学音楽堂、ポズナン・フィルハーモニー・コンサート・ホール(ポズナン、ポーランド) |
|
||
| Chandos CHAN-20319(1CD) |
ルース・ギップス(1921-1999):管弦楽作品集
第4集 ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 Op.24(1943)…世界初録音 リヴァイアサン Op.59- コントラファゴットと室内オーケストラのための(1969) 交響曲第5番Op.64(1982) Kyrie eleison. Largo - Christe eleison - Kyrie eleison Gloria in excelsis Deo. Allegro - Meno mosso - Et in terra pax hominibus bona voluntatis - Credo in unum Deum - Hosanna in excelsis. Allegro - Benedictus qui venit in nomine Domini. Meno mosso - Da capo dal Hosanna - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Meno mosso - Dona nobis pacem. Largo - Coda. Allegro moderato - Largo |
チャーリー・ラヴェル=ジョーンズ(Vn) ビル・アンダーソン(コントラファゴット) BBCフィルハーモニック ユーリ・トルチンスキー(リーダー) ラモン・ガンバ(指) 録音:2022年7月29日、2024年5月24日、2024年11月20日 |
|
||
| CPO CPO-555733(6CD) |
ペッテション=ベリエル:交響曲全集、他 【CD1】 1-4. 交響曲第1番変ロ長調「旗」 5-10. 組曲「過ぎし夏」(管弦楽版) 【CD2】 1-3. 交響曲第2番変ホ長調「旅は南風とともに」 4. ロマンス ニ短調(Vnと管弦楽版) 5. オリエンタル舞曲 6. カンタータ「スヴェーガルドラー」 - 前奏曲 【CD3】 1-4. 交響曲第3番ヘ短調「ラップランド」 5-9. 組曲「エリアナ」 - 管弦楽のための 10. 歌劇「最後の審判の予言者」 - コラールとフーガ 【CD4】 1-3. 交響曲第4番イ長調「ホルミア(ストックホルム)」 4-13. 組曲「眠りの森の美女」 14-18. 組曲「フレースエーの花々」第1巻より(管弦楽版) 夏の歌/フレースエーの教会で/バラに寄す/お祝い/挨拶 【CD5】 1-4. 交響曲第5番ロ短調「孤独」 5-7. ヴァイオリン協奏曲 嬰ヘ短調 【CD6】 1-4. ヴァイオリン・ソナタ第1番ホ短調 Op. 1 5-8. 組曲 Op.15 9. カンツォーネ 10. 民謡の調べ |
ザールブリュッケンRSO…CD1 ノールショピングSO…CD2-5 ミハイル・ユロフスキ(指)…CD1-5 ウルフ・ヴァリン(Vn)…CD:2-4、CD5:5-7、CD6 ルーヴェ・デルヴィンイェル(P)…CD6 録音:1997年11月18-19日…CD1 1998年2月9-13日…CD2 De Geer Hall, Norrkoping(スウェーデン) 1993年5月3-7日…CD3 1999年5月31-6月4日…CD4 2003年4月25-26日…CD5 Radiohuset, Swedish Radio, Stockholm(スウェーデン) 2001年10月9-11日、2002年1月22-24日…CD6 |
|
||
| CPO CPO-555738(9CD) |
ボッケリーニ:29の交響曲、他 【CD1】 1-3. 交響曲 ハ長調 Op.7G491 4-6. 交響曲 ハ長調 Op.10No.4G523 7-9. 交響曲 ニ長調 G490 【CD2】 1-4. 交響曲 ニ長調 Op.12No.1G503 5-7. 交響曲 変ホ長調 Op.12No.2G504 8-11. 交響曲 ハ長調 Op.12No.3G505 【CD3】 1-3. 交響曲 ニ短調 Op.12NO.4G506 4-7. 交響曲 変ロ長調 Op.12No.5G507 8-11. 交響曲 イ長調 Op.12No.6G508 【CD4】 1-3. 交響曲 変ロ長調 Op.21No.1G493 4-6. 交響曲 変ホ長調 Op.21No.2G494 7-9. 交響曲 ハ長調 Op.21No.3G495 10-12. 交響曲 ニ長調 Op.21No.4G496 13-15. 交響曲 変ロ長調 Op.21No.5G497 【CD5】 1-3. 交響曲 イ長調 Op.21No.6G498 4-6. 交響曲 ニ長調 Op.35No.1G509 7-9. 交響曲 変ホ長調 Op.35No.2G510 10-12. 交響曲 イ長調 Op.35No.3G511 【CD6】 1-3. 交響曲 へ長調 Op.35No.4G512 4-6. 交響曲 変ホ長調 Op.35No.5G513 7-9. 交響曲 変ロ長調 Op.35No.6G514 9-12. 交響曲 ハ長調 Op.37No.1G515 【CD7】 1-4. 交響曲 ニ短調 Op.37No.3G517 5-8. 交響曲 イ長調 Op.37No.4G518 9-12. 交響曲 ハ短調 Op.41G519 【CD8】 1-4. 交響曲 ニ長調 Op.42G520 5-8. 交響曲 ニ長調 Op.45G522 9-12. 交響曲 ニ長調 G500 【CD9】 1-3. 交響曲 ニ長調 G521 4-6. チェロ協奏曲 ハ長調 G477 7-9. 八重奏曲 ト長調 Op.38G470 10-12. チェロ協奏曲 ニ長調 G479 |
ドイツ・カンマーアカデミー…CD1-8 シュトゥットガルト室内O…CD9 ヨハネス・ゴリツキ(指,Vc…CD9) 録音:1990-1993年 Historisches Zeughaus, Neuss(ドイツ)…CD1-8 2005年Funkstudio im SWR Stuttgart(ドイツ)…CD9 |
|
||
| CPO CPO-555238(1CD) |
フランツ・ラハナー:交響曲第4番、アンダンテ 交響曲第4番ホ長調 アンダンテ 変イ長調 - ブラス・アンサンブルのための |
エヴァーグリーンSO ゲルノート・シュマルフス(指) 録音:2019年1月15-19日 |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00831(3SACD) 税込定価 2025年3月19日発売 |
メンデルスゾーン:交響曲全集 ■Disc1 交響曲第1番ハ短調作品11 交響曲第4番「イタリア」 序曲「静かな海と楽しい航海」 ■Disc2 交響曲第2番「讃歌」 序曲「ルイ・ブラス」 ■Disc3 交響曲第3番「スコットランド」 交響曲第5番「宗教改革」 序曲「フィンガルの洞窟」 |
尾高忠明(指) 大阪フィルハーモニーSO 盛田麻央(S)、隠岐彩夏(S)、吉田浩之(T) 大阪フィルハーモニーcho(指揮:福島章恭) 録音:2023年6月8日 (Disc1) 、8月25日(Disc1&3) 、11月9日(Disc3) 、2024年2月15日(Disc2) 大阪・ザ・シンフォニーホール |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00822(1SACD) 税込定価 2025年3月19日発売 |
ショスタコーヴィチ:交響曲第5番ニ短調 作品47 | 井上道義(指) 読売日本SO 録音:2022年2月10日 東京・サントリーホール |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00859(1SACD) 税込定価 2025年3月19日発売 |
マーラー:交響曲第5番嬰ハ短調 | 小林研一郎(指)LPO 録音:2024年5月11-17日 ロンドン、アビー・ロード・スタジオ |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00876(1SACD) 税込定価 2025年3月19日発売 |
ベートーヴェン:交響曲第6番ヘ長調 作品68 「田園」 交響曲第1番ハ長調 作品21 |
ジョナサン・ノット(指) 東京SO 録音:2019年7月27日 ミューザ川崎シンフォニーホール(第1 番)、2023年11月11日 東京・サントリーホール(第6番)・ライヴ |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00873(1SACD) 税込定価 2025年3月19日発売 |
ハイドン交響曲集Vol.27 交響曲第22番変ホ長調Hob.I:22「哲学者」 交響曲第24番ニ長調Hob.I:24 交響曲第80番ニ短調Hob.I:80 |
飯森範親(指) 日本センチュリーSO 録音:2023年3月31日(第22番)、 2024年3月1日(第80番)6月20日(第24番)大阪・ザ・シンフォニーホール |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00879(1SACD) 税込定価 2025年3月19日発売 |
ハイドン交響曲集Vol.28 交響曲第21番イ長調Hob.Ⅰ:21 交響曲第25番ハ長調Hob.Ⅰ:25 交響曲第98番変ロ長調Hob.Ⅰ:98 |
飯森範親(指) 日本センチュリーSO 録音:2023年3月31日(第21番)、5月18日(第25番)、12月 14日(第98番) 大阪・ザ・シンフォニーホール |
|
||
| SWR music SWR-19164CD(1CD) |
マーラー:交響曲第5番 | シュトゥットガルトRSO ガリー・ベルティーニ(指) 録音:1981年3月20日(ライヴ) シュトゥットガルト、リーダーハレ |
|
||
| Hyperion CDA-68464(1CD) |
ハヴァーガル・ブライアン(1876-1972):交響曲第6番「悲劇的交響曲」 交響曲第12番/歌劇「アガメムノーン」* |
イングリッシュ・ナショナル・オペラO、 マーティン・ブラビンズ(指)、 イングリッシュ・ナショナル・オペラcho*、 エレナー・デニス(S)*、 ステファニー・ウェイク=エドワーズ(Ms)*、 ジョン・フィンドン(T)*、ロバート・マレー(T)*、 クライヴ・ベイリー(Bs)* 録音:2023年12月1日-2日、セント・ジュード・オン・ザ・ヒル教会(ハムステッド、イギリス) |
|
||
| Danacord DACOCD-976(2CDR) ★ |
ランゴー:初期録音集1957-1981年~交響曲・管弦楽作品集 (1)交響曲第4番「落葉」 BVN124(1916rev.1920)(単一楽章による) (2)交響曲第6番「天を裂いて」 BVN165(1919-20 rev.1928-30) (3)交響曲第16番「太陽の氾濫」 BVN417(1950-51) (4)頌歌(エドヴァルド・グリーグの死にあたり) BVN20(1907rev.1909-13) (5)ヴィズビェア頌歌 BVN343(1948)(混声合唱、オルガンと管弦楽のための) (6)ヴァイオリン協奏曲 BVN289(1943-44)(単一楽章による) (7)「詩人の夢」への音楽 BVN181(1923-1925 Nyversion1926) (8)禁令 BVN335(1947-48)(オルガンと管弦楽のための) (9)天球の音楽 BVN128(1916-18)(ソプラノ、混声合唱、管弦楽とバンダのための) |
(1)デンマーク国立SO ジョン・フランセン(指) 録音:1981年4月2日、デンマーク放送スタジオ(コペンハーゲン) (2)デンマーク国立SO マーテリウス・ロンクヴィスト(指) 録音:1961年5月20日、デンマーク放送スタジオ(コペンハーゲン) (3)デンマーク国立SO フランセスコ・クリストフォリ(指) 録音:1966年3月16日、デンマーク放送コンサートホール(コペンハーゲン)(初演ライヴ) (4)デンマーク国立SO ラウニ・グランデール(指) 録音:1957年5月5日、デンマーク放送スタジオ(コペンハーゲン) (5)デンマーク国立SO エアンスト・ヒュー=クヌセン(指) 録音:1958年6月10日、デンマーク放送スタジオ(コペンハーゲン) (6)カイ・ラウアセン(Vn) オーゼンセSO アクセル・ヴェレユス(指) 録音:1968年2月8日、デンマーク放送スタジオ (7)オールボーSO アルフ・ショーエン(指) 録音:1969年10月21日、デンマーク放送スタジオ (8)グレーテ・クローウ(Org) オールボーSO アルフ・ショーエン(指) 録音:1970年4月17日、デンマーク放送スタジオ (9)マグレーデ・ダニエルセン(S) デンマーク国立SO デンマーク国立放送cho ジョン・フランセン(指) 録音:1971年1月21日、デンマーク放送スタジオ(コペンハーゲン) |
|
||
| Musikmuseum MMCD-13020(1CD) 初紹介旧譜 |
ヨハン・ルフィナッチャ(1812-1893):交響曲第3番ハ短調/演奏会用アリア「Ingeborgs Klage」*/演奏会用アリア「Der Schwur am Grabe der Mutter」**/演奏会用アリア「Erwartung」* | 聖ブラシウス・アカデミーO、 カールハインツ・ジースル(指)、 ベリンダ・ロウコタ(S)*、 アンドレアス・マッテルスベルガー(Bs-Br)** 録音:2012年11月23日-25日(インスブルック、オーストリア) |
|
||
| Musikmuseum MMCD-13019(1CD) 初紹介旧譜 |
ミヒャエル・F・P・フーバー:管弦楽作品集
Op.50-52 ハープ協奏曲 Op.50* ヴィオラ・ダモーレと室内オーケストラのための協奏曲 Op.51** 交響曲第3番Op.52 |
聖ブラシウス・アカデミーO、 カールハインツ・ジースル(指)、 マルティナ・リフェッサー(Hp)*、 アンドレアス・ティコッツィ(Va)** 録音:2012年~2013年 |
|
||
| フォンテック FOCD-9919(3CD) 税込定価 2025年3月5日発売 |
ブルックナー:初期交響曲集 交響曲第0番二短調 〈ノーヴァク版〉 交響曲第1番ハ短調 〈1865/66リンツ稿 ノーヴァク版〉 交響曲第2番ハ短調 〈1877第2稿 キャラガン版〉 |
尾高忠明(指) 大阪フィルハーモニーSO 録音:2024年6月13日(第0番) 、8月28 日(第2番)、11月14日(第1番) ザ・シンフォニーホール ライヴ録音: |
|
||
| CPO CPO-555589(1CD) |
エルフリーダ・アンドレー(1841-1929):フリチョフ組曲 交響曲第1番ハ長調 |
ノールショピングSO ヘルマン・ボイマー(指) 録音:2022年8月29日-9月1日 |
|
||
| Chandos CHSA-5354(1SACD) |
シューベルト:ます Op.32D550(B. ブリテンによるオーケストラ伴奏版) ロマンス 第3番ヘ短調 D797No.3b - 劇音楽『ロザムンデ』より 魔王 Op.1D328(ベルリオーズによるオーケストラ伴奏版) 秘めごと Op.14No.2D719(ブラームスによるオーケストラ伴奏版) 夕映えの中に D799(M. レーガーによるオーケストラ伴奏版) 交響曲第9番ハ長調「ザ・グレート」 |
メアリー・ベヴァン(S) バーミンガム市SO エドワード・ガードナー(指) 録音:2024年7月18,19日バーミンガム、タウン・ホール |
|
||
 ALPHA ALPHA-1082(1CD) ALPHA-1123(1LP) |
モレキュール:交響曲第1番「量子」 | モレキュール(エレクトロニクス) フランス国立リールO アレクサンドル・ブロック(指) 録音:2023年6月 リール新世紀音楽堂、フランス ※LP…180g重量盤、331/3rpm |
|
||
| ALTO ALC-1706(1CD) |
ポポフ:交響曲第2番&第5番 ガヴリール・ポポフ(1904-1972):交響曲第2番「祖国」 Op.39 交響曲第5番「田園」 Op.77* |
モスクワRSO、 ゲンナジー・プロヴァトロフ(指)、 ソ連国立SO*、 グルゲン・カラペチャン(指)* 録音:1961年5月(モスクワ)/1963年(モスクワ)* |
|
||
| GRAND SLAM GS-2337(1CD) |
ウラニアのエロイカ 〈ブラジル盤LPからの復刻〉 (1)ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 【ボーナス・トラック】 (2)ハイドン:交響曲第104番「ロンドン」 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指揮)
(1)VPO、(2)コロン劇場O 録音:(1)1944年12月19日、ウィーン、ムジークフェラインザール (2)1950年4月14日、ブエノスアイレス、コロン劇場 使用音源:(1)URANIA (Brazil) SLP 6530 (ULP-7095A/ULP-7095B) (2)Private archive (Akira Tanaka collection) 録音方式:モノラル(ラジオ放送用録音) |
|
||
| カメラータ CMCD-99089(2CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 2025年2月25日発売 |
池辺晋一郎:作品集 相聞 Ⅰ(1970)/ 相聞 Ⅱ(1970)/ 相聞 Ⅲ(2005) オペラ『死神』から「死神のアリア」(1971/Rev. 1978) オペラ『高野聖』(2011)から 夫婦滝/ 白桃の花 交響曲第11番「影を深くする忘却」(2023) [東京オペラシティ文化財団、オーケストラ・アンサンブル金沢 共同委嘱・世界初演] ピアノ協奏曲 Ⅰ(1967)[世界初演]* |
古瀬まきを(ソプラノ)、中鉢聡(テノール) 東京混声cho 上原興隆(ピアノ) オーケストラ・アンサンブル金沢 広上淳一(指揮) 学生有志オーケストラ 佐藤功太郎(指揮)* 録音:2023年9月,1967年3月 ほか東京[ライヴ録音] ※ 「ピアノ協奏曲 Ⅰ」の音源は、モノーラルで、オリジナル・テープに起因する音の混入等、お聞き苦しい個所がございます。予めご了承ください。 |
|
||
| Ars Produktion ARS-38667(1CD) |
モーツァルト:交響曲第35番ニ長調 K.385「ハフナー」 ピアノ協奏曲第24番ハ短調 K.491 |
ハンス=ユルク・シュトループ(P)、 クリスティアン・エルニー(指)、 ロイトリンゲン・ヴュルテンベルクPO 録音:2024年1月、ドイツ ※使用ピアノ:スタインウェイD |
|
||
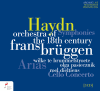 NIFC NIFCCD-160(3CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 XNIFCCD-160(3CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ハイドン:交響曲集(2004年ポーランド・ライヴ) 交響曲第59番イ長調 Hob.I:59「火事」/アリア「あなたはご存じでいらっしゃる」 Hob.XXIVb:7*/アリア「私の一番いいところは」 Hob.XXIVb:17*/アリア「女房の機嫌がいい時は」 Hob.XXIVb:18*/交響曲第103番変ホ長調 Hob.I:103 「太鼓連打」 交響曲第83番ト短調 Hob.I:83「めんどり」/チェロ協奏曲第1番 ハ長調 Hob.VIIb:1**/交響曲第104番ニ長調 Hob.I:104「ロンドン」 交響曲第64番イ長調 Hob.I:64「時の移ろい」/シェーナ「ベレニーチェ、何をしているの?」 Hob.XXIVa:10***/交響曲第101番ニ長調 Hob.I:101 「時計」 【アンコール】 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」~第3楽章(抜粋) ヨーゼフ・シュトラウス:ポルカ・マズルカ「とんぼ」 Op.204 |
18世紀オーケストラ、 フランス・ブリュッヘン(指)、 ヴィルケ・テ・ブルンメルストルテ(Ms)*、 ロエル・ディールティエンス(バロック・チェロ)** オルガ・パシェチュニク(S)*** 録音(ライヴ):2004年9月2日-4日、ワルシャワ・フィルハーモニー・コンサート・ホール(ポーランド)/2013年8月27日、ポーランド放送ヴィトルト・ルトスワフスキ・コンサート・スタジオ(ポーランド)*** |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00870(1SACD) 税込定価 2025年2月19日発売 |
ラウタヴァーラ:カントゥス・アルクティクス(鳥とオーケストラのための協奏曲)作品61 シベリウス:交響詩「ルオンノタル」作品70* ドヴォルザーク:交響曲第8番ト長調作品88 |
サカリ・オラモ(指) 東京SO アヌ・コムシ(S)* 録音:2024年4月20日 東京・サントリーホール、4月21日 ミューザ川崎シンフォニーホール・ライヴ |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00857(1SACD) 税込定価 2025年2月19日発売 |
ベルリオーズ:幻想交響曲作品14 | 小林研一郎(指)LPO 録音:2024年5月11-17日 ロンドン、アビー・ロード・スタジオ |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00872(1SACD) 税込定価 2025年2月19日発売 |
モーツァルト:交響曲第39番変ホ長調 K.543 交響曲第40番ト短調 K.550 交響曲第41番ハ長調 K.551「ジュピター」 |
上岡敏之(指)新日本PO 録音:2024年10月25-26日 東京・すみだトリフォニーホール・ライヴ |
|
||
 ALPHA ALPHA-1127(1CD) ALPHA-1154(2LP) |
マーラー:交響曲第5番嬰ハ短調 | チューリヒ・トーンハレO パーヴォ・ヤルヴィ(指) イヴォ・ガス(ホルン・ソロ) 録音:2024年1-2月 チューリヒ・トーンハレ ※LP…180g重量盤2枚組 331/3rpm |
|
||
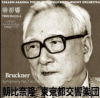 東武レコーディングズ TBRCD-0170(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
完全初出の幻の録音! ブルックナー:交響曲第7番(ハース版) |
朝比奈隆(指揮)東京都SO 録音:1978年5月5日都響特別演奏会、東京文化会館ステレオ・ライヴ |
|
||
| Linn CKD-778(3CD) |
ラフマニノフ:交響曲全集 ほか 交響曲第1番ニ短調 Op.13 ジプシーの主題による奇想曲Op.12 交響曲第2番ホ短調 Op.27 交響曲第3番イ短調 Op.44 死の島 Op.29 |
ケルンWDRSO クリスティアン・マチェラル(指) 録音:2021-2022年 ケルン・フィルハーモニー、ドイツ |
|
||
| Urania Records LDV-14122(1CD) |
マーラー:交響曲第1番「巨人」 | ヴラディーミル・デルマン(指)ミラノRAI響 録音:1991年(ミラノ、ステレオ録音、DDD) |
|
||
| GENUIN GEN-25909(1CD) |
モーツァルト:交響曲集4集 交響曲第4番 ニ長調 K.19/交響曲 ヘ長調 K. Anh. 223/19a/交響曲第5番 変ロ長調 K.22/交響曲第6番ヘ長調 K.43/交響曲第10番 ト長調 K.74/交響曲第12番ト長調 K.110/75b |
ヨハネス・クルンプ(指) エッセン・フォルクヴァング室内O 録音:2022年4月&9月 |
|
||
| NCPA Classics N-816202201(2CD) 高価格帯 限定生産 |
ブルックナー:交響曲第4番変ホ長調 WAB.104 「ロマンティック」(ノヴァーク版第2稿、1878/1880年) | 中国国家大劇院O(China NCPA Orchestra)、リュー・ジァ(指) 録音:2024年9月23日-9月24日中国国家大劇院(北京、中国) |
|
||
| NCPA Classics N-816202191(2CD) 高価格帯 限定生産 |
ブルックナー:交響曲第5変ロ長調 WAB.105(ノヴァーク版) | 中国国家大劇院O(China NCPA Orchestra)、リュー・ジァ(指) 録音:2024年7月11日-9月13日中国国家大劇院(北京、中国) |
|
||
| NCPA Classics N-816202081(1CD) 高価格帯 限定生産 |
ブルックナー:交響曲第6変ロ長調 WAB.105(ノヴァーク版) | 中国国家大劇院O(China NCPA Orchestra)、リュー・ジァ(指) 録音:2024年1月9日-1月11日中国国家大劇院(北京、中国) |
|
||
| Musikmuseum MMCD-13004(1CD) |
インスブルック・クラシック~インスブルック音楽協会のアーカイヴからの18世紀の交響曲集 レオポルト・モーツァルト:弦楽のための交響曲 ニ長調 ヨハン・クリスティアン・バッハ:複数の楽器のための交響曲変ホ長調 Op.3-3 ヨーゼフ・アントン・アウフマン(um 1720bis nach1773):交響曲ニ長調 カスパー・デムラー(um 1750bis nach1787):交響曲ヘ長調 ミュラー(おそらくヨーゼフ・シクストゥス・ミュラー, 1714-1783):交響曲変ホ長調 ヨハン・ミヒャエル・マルツァート(1749-1787):交響曲イ長調 |
コンチェルト・ステラ・マトゥティナ、 シルヴィア・シュヴァインベルガー(コンサートマスター) 録音:2009年4月25日 |
|
||
| ALPHA ALPHA-1130(1CD) |
ロウヴァリ&エーテボリ響のシベリウスここに完結! シベリウス:交響曲第6番ニ短調 Op.104 交響曲第7番ハ長調 Op.105 劇付随音楽『テンペスト』 Op.109(抜粋) |
エーテボリSO サントゥ=マティアス・ロウヴァリ(指) 録音:2022年5月、2024年 エーテボリ・コンサートホール、スウェーデン |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00866(1SACD) 税込定価 2025年1月22日発売 |
ブルックナー:交響曲第4番変ホ長調 「 ロマンティック」(1878/80年稿 ノヴァーク版) |
秋山和慶(指)東京SO 録音:2024年9月21日 東京・サントリーホール・てライヴ |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00869(1SACD) 税込定価 2025年1月22日発売 |
ハイドン交響曲集Vol.26 交響曲第13番ニ長調Hob.Ⅰ:13 交響曲第49番ヘ短調Hob.Ⅰ:49「受難」 交響曲第52番ハ短調Hob.Ⅰ:52 |
飯森範親(指) 日本センチュリーSO 録音:2017年12月8日(第52番)いずみホール、2023年3月31日(第13番)2023年5月18日(第49番) 大阪・ザ・シンフォニーホール・ライヴ |
|
||
| フォンテック FOCD-9918(1CD) 税込定価 2025年2月5日発売 |
ベートーヴェン:交響曲第7番 イ長調 作品92 交響曲第6番ヘ長調 作品68「田園」 |
高関(指) 富士山静岡SO 録音:2024年9月15日 静岡市清水文化会館マリナート 大ホール ライヴ録音: |
|
||
| BR KLASSIK BR-900225(1CD) |
マーラー:交響曲第7番ホ短調 | バイエルンRSO サー・サイモン・ラトル(指) 録音:2024年11月6-8日ミュンヘン、イザールフィルハーモニー・イン・ガスタイクHP8(ライヴ) |
|
||
| BR KLASSIK BR-900223(1CD) |
ドヴォルザーク:交響曲第7番ニ短調 Op.70 スケルツォ・カプリチオーソ Op.66* |
バイエルンRSO ベルナルト・ハイティンク(指) 録音:1981年3月26,27日(ライヴ)、1981年3月24日* ミュンヘン、ヘルクレス・ザール |
|
||
| Capriccio C-5540(2CD) |
シンディング:交響曲全集 交響曲第1番ニ短調Op.21(1894) 交響曲第2番ニ長調 Op.83(1907) 交響曲第3番ヘ長調 Op.121(1919) 交響曲第4番変ホ長調「冬と春」 Op.129(1936) |
ノールショピングSO カール=ハインツ・シュテフェンス(指) 録音:2023年6月12-15日、2024年6月17-21日 |
|
||
| PROSPERO CLASSICAL PROSP-0110(1CD) |
新世界 ~ドヴォルザーク&ドルマン (1)ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」 (2)アヴネル・ドルマン(1975-):打楽器協奏曲「凍てついた時」 |
セルゲイ・ミハイレンコ(打楽器) ニコラス・ミルトン(指) ゲッティンゲンSO 録音:(1)2020年8月、(2)2021年3月10-12日/ゲッティンゲン、ロックハレ |
|
||
| GRAND SLAM GS-2332(1CD) 日本語解説付国内盤 |
ワルター晩年の「未完成」「新世界」ステレオ録音 【オープンリール・テープ復刻】 (1)シューベルト:交響曲第8番「未完成」 (2)ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」 |
ブルーノ・ワルター(指) (1)NYO (2)コロンビアSO 録音:(1)1958年3月3日、ニューヨーク、セント・ジョージ・ホテル (2)1959年2月14、16、20日、カリフォルニア、アメリカン・リージョン・ホール 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:ステレオ(録音セッション) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2333(1CD) 日本語解説付国内盤 |
フルトヴェングラー&BPO~ウェーバー、ラヴェル、ベートーヴェン 【オープンリール・テープ復刻】 (1)ウェーバー:歌劇「魔弾の射手」序曲 (2)ラヴェル:「ダフニスとクロエ」、組曲第2番 (3)ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) BPO 録音:1944年3月20~21日/ベルリン国立歌劇場 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(ラジオ放送用録音) |
|
||
| King International KKC-4361(3CD) 日本語解説付国内盤 |
ワルター&ウィーン・フィル(HMV録音集成)(1936-1938)
■DISC1 (1)ハイドン:交響曲第100番ト長調「軍隊」 (2)ハイドン:交響曲第96番ニ長調「奇跡」 (3)モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番ニ短調 K.466* ■DISC2 (4)モーツァルト:交響曲第41番ハ長調 K.551「ジュピター」 (5)ベートーヴェン:交響曲第6番ヘ長調作品68「田園」 ■DISC3 (6)モーツァルト:アイネ・クライネ・ナハトムジークK. 525 (7)シューベルト:交響曲第8番ロ短調 D.759「未完成」 (8)ブラームス:交響曲第3番ヘ長調 作品90 |
ブルーノ・ワルター(指)VPO ブルーノ・ワルター(P)* 録音:1938年1月10日 原盤:英 HMV DB8445/7 (1) 録音:1937年5月5日 原盤:米 RCA VICTOR 13856/8(2) 録音:1937年5月7日 原盤:米VICTOR12151/4 (3) 録音:1938年1月11日 原盤:米 VICTOR 12471/4S (4) 録音:1936年12月5日 原盤:仏 LA VOIX DE SON MAITRE DB3051/5(5) 録音:1936年12月17日 原盤:英 HMV DB3075/6 (6) 録音:1936年5月19,21日 原盤:日本コロムビアJ8642/4 (7) 録音:1936年5月18,19日 原盤:米 VICTOR 12022/5(8) / 会場はすべて ウィーン、ムジークフェライン大ホール |
|
||
 Urania Records WS-121421(2CD) ★ |
アンチェルのシベリウス他 (1)シベリウス:交響曲第1番 交響詩「ポホヨラの娘」 (2)ヤナーチェク:狂詩曲「タラス・ブーリバ」 (3)マーラー:交響曲第9番 |
カレル・アンチェル(指)チェコPO 録音:(1)1962年6月7日-8日(プラハ) (2)1961年5月22日-24日(プラハ) (3)1965年(プラハ) |
|
||
| Signum Classics SIGCD-889(1CD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲第10番ホ短調 Op.93 | サントゥ=マティアス・ロウヴァリ(指) フィルハーモニアO 録音:2024年4月7日、サウスバンク・センターズ・ロイヤル・フェスティヴァル・ホール(ロンドン) |
|
||
 Melodiya x Obsession SMELCD-1002705(2CD) 完全限定生産 |
メロディアのフルトヴェングラー復活! ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」、第7番、第9番「合唱付き」 ベートーヴェン:交響曲第5番ハ短調 Op.67「運命」/交響曲第7番 イ長調 Op.92/交響曲第9番ニ短調 Op.125「合唱付き」* |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)、 BPO、ティラ・ブリーム(S)*、エリーザベト・ヘンゲン(Ms)*、ペーター・アンダース(T)*、ルドルフ・ヴァツケ(Bs-Br)*、ブルーノ・キッテルcho* 録音(ライヴ):1943年6月(第5番)/1943年10月(第7番)/1942年3月(第9番) ※リマスタリング:ヴァレリア・オボジンスカヤ |
|
||
| NCPA Classics 8162-02011(1CD) 高価格帯 限定生産 |
ブルックナー:交響曲第1番ハ短調 WAV-.101(ウィーン稿、1890/91年) | 中国国家大劇院O (China NCPA Orchestra)、リュー・ジァ(指) 録音:2023年8月31日-9月1日、中国国家大劇院(北京、中国)ステレオ・ライヴ |
|
||
| NCPA Classics 8162-01961(1CD) 高価格帯 限定生産 |
ブルックナー:交響曲第2番ハ短調 WAB.102(1877年版) | 中国国家大劇院O(China NCPA Orchestra) リュー・ジァ(指) 録音:2016年6月17日-18日、中国国家大劇院(北京、中国)ステレオ・ライヴ |
|
||
| NCPA Classics 81620-1871(2CD) 高価格帯 限定生産 |
ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 WAB.108 (ノヴァーク版第2稿、1890年) |
中国国家大劇院O(China NCPA Orchestra) リュー・ジァ(指) 録音:2023年6月11日-13日、中国国家大劇院(北京、中国) |
|
||
| NCPA Classics 81620-1681(1CD) 高価格帯 限定生産 |
ブルックナー:交響曲第7番ホ長調 WAB.10 | 中国国家大劇院O(China NCPA Orchestra) リュー・ジァ(指) 録音:2023年3月5日-7日、中国国家大劇院(北京、中国) |
|
||
| NCPA Classics 8162-01641(1CD) 高価格帯 限定生産 |
ブルックナー:交響曲第3番ニ短調 WAB.103 「ワーグナー」(ノヴァーク版第2稿、1889年) |
中国国家大劇院O(China NCPA Orchestra) リュー・ジァ(指) 録音:2023年1月9日-11日、中国国家大劇院(北京、中国) |
|
||
| NCPA Classics 8162-01341(1CD) 高価格帯 限定生産 |
ブルックナー:交響曲第9番ニ短調 WAV-.109 | 中国国家大劇院O(China NCPA Orchestra) リュー・ジァ(指) 録音:2022年3月14日-16日、中国国家大劇院(北京、中国) |
|
||
 東武レコーディングズ TBRCD-0162(8CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ハイドン&モーツァルト:交響曲名演集 ●ハイドン:交響曲集 第43番「マーキュリー」、第44番「悲しみ」*、 第48番「マリア・テレジア」、第55番「校長先生」、第60番「うかつ者」、第88番「V 字」、第92番「オックスフォード」、第94番「驚愕」、第100番「軍隊」、第101番「時計」、第103番「太鼓連打」、104番「ロンドン」 ●モーツァルト:交響曲集 第10番、第11番、第12番、第13番、第14番、第20番、第21番、第22番、第23番、第24番、第25番、第35番「ハフナー」、第38番「プラハ」、第39番、第40番、第41番「ジュピター」 |
秋山和慶(指)広島SO 録音:2006~09年アステール・プラザ大ホール(ライヴ) 、2000年2月26日広島厚生年金会館(ライヴ)* |
|
||
| QUERSTAND VKJK-2401(1CD) |
「エディション・バーディッシェ・シュターツカペレ03」
ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」(1936年、ハース版) |
ゲオルク・フリッチュ(指) バーディッシェ・シュターツカペレ(バーデン州立O) 録音:2022年3月6・7日ドイツ、カールスルーエ (ライヴ)D |
|
||
| BR KLASSIK BR-900210(1CD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲第15番 | バイエルンRSO ベルナルト・ハイティンク(指) 録音:2015年2月5-6日 ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ライヴ) |
|
||
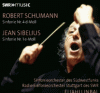 SWR music SWR-19151CD(1CD) NYCX-10505(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
インバル~若き日のシューマン&シベリウス シューマン:交響曲第4番ニ短調 Op.120(改訂版) シベリウス:交響曲第1番ホ短調 Op.39* |
エリアフ・インバル(指) 南西ドイツRSO シュトゥットガルトRSO* 録音:1971年4月21日(ライヴ)ハンス・ロスバウト・スタジオ、バーデン=バーデン 2012年7月12、13日(ライヴ) リーダーハレ、ベートーヴェンザール、シュトゥットガルト* |
|
||
| Spectrum Sound CDSMAC-029(1CD) |
ベーム&ケンペのブラームス (1)ブラームス:交響曲第1番ハ短調 Op.68 (2)ブラームス:交響曲第3番ヘ長調 Op.90 |
(1)カール・ベーム(指)BPO German DGG SLPM138113Alle Hersteller Big Tulip GY5STEREO ED1LP Record restoration (STEREO) (2)ルドルフ・ケンペ(指)BPO German EMI Electrola STE80582STEREO Sample Record restoration (STEREO) |
|
||
| LPO LPO-0129(1CD) |
マイケル・ティペット(1905-98):ピアノ協奏曲 交響曲第2番* |
エドワード・ガードナー(指) スティーヴン・オズボーン(P) 録音:2023年1月25日、2024年4月10日* いずれもロイヤル・フェスティヴァル・ホール(ライヴ) |
|
||
| Urania Records LDV-14122(1CD) |
マーラー:交響曲第1番「巨人」 | ヴラディーミル・デルマン(指)、 ミラノRAISO 録音:1991年(ミラノ、ステレオ録音、DDD) |
|
||
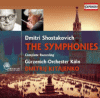 Capriccio C-7435(12CD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲全集(全15曲) | マリーナ・シャグチ(S) アルチュン・コチニャン(Bs) プラハ・フィルハーモニーcho ケルン・ギュルツェニヒO ドミートリー・キタエンコ(指) 録音:2002-2004年 |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00860(1SACD) 日本語解説付国内盤 税込定価 3850★★2024年12月18日発売 |
ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 | 川瀬賢太郎(指)名古屋PO 迫田美帆(S)、福原寿美枝(Ms)、清水徹太郎(T)、宮本益光(Br)、愛知県合唱連盟 録音:2023年12月16-17日日本特殊陶業市民会館フォレストホール(名古屋市民会館 大ホール) ライヴ |
|
||
| Capriccio C-5489(1CD) |
カール・ヴァイグル(1881-1949):交響曲第3番変ロ長調(1931) 悲劇への交響的前奏曲(1933) |
ラインラント=プファルツ州立PO ユルゲン・ブルーンス(指) 録音:2021年11月2-5日 ※全て世界初録音 |
|
||
| MSR MS-1816(1CD) |
バーバラ・ハーバック作品集VOL.18~ハーバック(b.1946):管弦楽曲集Vol.8
交響曲第12番「時は飛ぶ」(2002) 交響曲第14番「開拓者の女性達」(2002) |
デイヴィッド・アンガス(指)LPO 録音:2024年1月15-16日 ヘンリーウッドホール(ロンドン |
|
||
| SOMM ARIADNE-5034(2CD) |
ブルックナー:交響曲第8番、第9番、詩篇第150篇 ■CD1 1-4. 交響曲第8番ハ短調 WAB108(ノーヴァク版)・・・初CD化 ■CD2 1. 詩篇第150篇 WAB38 2-4. 交響曲第9番ニ短調 WAB109(ノーヴァク版)・・・初CD化 |
■CD1 バイエルンRSO オイゲン・ヨッフム(指) ■CD2 1.ヒルデ・チェスカ(S) ウィーン室内cho ウィーンSO ヘンリー・スヴォボダ(指) 2-4.ウィーンSO ヴォルフガング・サヴァリッシュ(指) 録音:全てモノラル 1957年11月21日(ライヴ) ミュンヘン、ヘルクレスザール(バイエルン放送のエア・チェック)...CD1 1950年10月、11月(セッション) ウィーン(Westminster LP, XWIN17075の復刻)...CD2:1 1966年5月22日(ライヴ) ウィーン、楽友協会大ホール(ORF収録、南ドイツ放送のエア・チェック)...CD2:2-4 |
|
||
| Chandos CHAN-20284(1CD) |
ルース・ギップス(1921-1999):管弦楽作品集
第3集 戴冠行進曲 Op.41(1953)* アンバルワリア Op.70(1988)* ホルン協奏曲 Op.58(1968)# グリングルマイア・ガーデン Op.39(1962) 交響曲第1番ヘ短調 Op.22(1942)* |
マーティン・オーウェン(Hrn)# BBCフィルハーモニック ユーリ・トルチンスキー(リーダー) ラモン・ガンバ(指) 録音:2022年1月7日、2023年9月14,15日 *…世界初録音 |
|
||
| CPO CPO-555482(1CD) |
パウル・ビュットナー(1870-1943):作品集 英雄的序曲 ハ長調 前奏曲、フーガとエピローグ 「幻影」 交響曲第2番ト長調 |
フランクフルト・ブランデンブルク州立O イェルク=ペーター・ヴァイグレ(指) 録音:2022年1月11-13日、2022年5月17日…1 |
|
||
| CPO CPO-555492(1CD) |
イグナツ・プレイエル(1757-1831):作品集 交響曲第18番変ホ長調 B139 ヴィオラ協奏曲 ニ長調 B105 交響曲第21番ニ長調 B124 |
ジョーダン・バク(Va) ロンドン・モーツァルト・プレイヤーズ ハワード・グリフィス(指) 録音:2022年4月4-5日 |
|
||
 BR KLASSIK BR-900228(1CD) |
バーンスタイン~アムネスティ・ライヴ ベートーヴェン:序曲「レオノーレ」 第3番 Op.72a 交響曲第5番ハ短調 作品67「運命」 |
バイエルンRSO レナード・バーンスタイン(指) 録音:1976年10月17日 ミュンヘン、 ドイツ博物館コングレスザール(ステレオ・ライヴ) |
|
||
| Altus ALT-535(1CD) |
マーラー:交響曲第10番嬰ヘ長調(カステレッティ編・室内オーケストラ版) | N響チェンバー・ソロイスツ 白井圭、大宮臨太郎、三又治彦、山岸努、横溝耕一(Vn) 中村翔太郎、中村洋乃理(Va) 辻本玲、宮坂拡志(Vc) 本間達朗(Cb) 梶川真歩(Fl) 吉村結実(Ob) 松本健司(Cl) 宇賀神広宣(Fg) 長谷川智之(Tp) 福川伸陽(Hrn) 竹島悟史(打楽器) 早川りさこ(Hp) 桑生美千佳(P/ハルモニウム) ライヴ録音:2021年11月30日/ハクジュホール ~N響メンバーによる室内楽シリーズ~より |
|
||
| ATMA ACD2-2867(1CD) |
シャンパーニュ:ガスペ交響曲 クロード・シャンパーニュ(1891-1965):ガスペ交響曲 バルトーク:舞踏組曲 Sz.77 コダーイ:ガランタ舞曲 アンドレ・プレヴォー(1934-2001):祝典 |
アラン・トゥルーデル(指) ラヴァルSO 録音:2021年6月19-21日 |
|
||
| NoMadMusic NMM-120(1CD) |
Symphonies Alpestres(アルプスの交響曲集) モーツァルト:交響曲第35番「ハフナー」、 交響曲第33番変ロ長調 K.319、 交響曲第36番ハ長調 K.425 |
オルケストル・デ・ペイ・ド・サヴォワ ピーター=ジェル・ド・ベール(指) |
|
||
| Urania Records LDV-14122(1CD) |
マーラー:交響曲第1番「巨人」 | ヴラディーミル・デルマン(指) ミラノRAIS響 録音:1991年(ミラノ、ステレオ録音、DDD) |
|
||
| NCM KLASSIK NCMK-9016(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第3番Op.55「英雄」 | オーケストラ・アンサンブル・ソウル イ・ギュソ(指) 録音:2021年8月31日ソウル・アーツ・センター(ソウル、韓国) |
|
||
| NCM KLASSIK NCMK-9002(1CD) |
モーツァルト:交響曲第29番イ長調 K.201 セレナード第13番ト長調 K.525「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 |
オーケストラ・アンサンブル・ソウル、 イ・ギュソ(指) 録音:2017年2月27日-28日スタジオ・パジュ(韓国) |
|
||
 東武レコーディングズ TBRCD-0157(5CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
Genius Naozumi ■CD1 ブラームス:交響曲第1番 ■CD2 ブラームス:二重協奏曲 ブラームス:ハンガリー舞曲第1番、第5番、第6番 ブラームス:子守歌 ■CD3 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付き」 ■CD4 山本直純の管弦楽入門“楽器の紹介” スッペ:「軽騎兵」序曲 楽器の紹介(打楽器、木管楽器、金管楽器、弦楽器) ■CD5 山本直純の管弦楽入門“オーケストラで世界をめぐる” エルガー:威風堂々 レハール:「金と銀」 ブラームス:ハンガリー舞曲第5番 モーツァルト(山本直純編):トルコ行進曲 楽器の紹介(サキソフォン、チェレエスタ、ハープ) ラヴェル:ボレロ マスカーニ:「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲 山本直純:「男はつらいよ」のテーマ音楽 ※山本直純の管弦楽入門で楽器紹介に使われている楽曲(一部断片) 前半(CD4):「ピーターと狼」(プロコフィエフ)、夕焼け小焼けの赤とんぼ(山田耕筰)、「剣の舞」(ハチャトゥリアン)、バディヌリ(バッハ:管弦楽組曲第2番)、五木の子守歌、クラリネットポルカ(作者不詳)、ぞうさん(團伊玖磨)、ガヴォット(ゴセック)、交響曲第5番~2楽章(チャイコフスキー)、魔弾の射手「狩人の合唱」(ウェーバー)、オブラディ・オブラダ(ビートルズ)、夢見る人(フォスター)、小象のエフィー(アレック・ワイルダー)、チャールダッシュ(モンティ)、荒城の月(滝廉太郎) 後半(CD5):TAKE5(ポール・デズモンド)、引き潮(マックスウェル)、くるみ割り人形 (チャイコフスキー) |
山本直純(指,お話) 新日本フィルハーモニーSO ■CD1&CD2 潮田益子(Vn)、 ローレンス・レッサー(Vc) 録音:1972年11月25日第3回定期演奏会東京文化会館(ステレオ) ■CD3 秋山恵美子(S)、大橋ゆり(A)、饗場智昭(T)、高橋啓三(Bs)、晋友会cho 録音:1990年12月24日オーチャードホール(ステレオ) ■CD4&5 録音:2000年7月4日静岡県、富士市文化会館 ロゼシアター(ステレオ) ※解説=柴田克彦 |
| “二重協奏曲の奇跡的な一体感が作品の地味なイメージを一掃!” | ||
|
||
| Pentatone PTC-5187232(1CD) |
ウィントン・マルサリス(1961-):ブルース・シンフォニー(2009) I. Born in Hope II. Swimming in Sorrow III. Reconstruction Rag IV. Southwestern Shakedown V. Big City Breaks VI. Danzon y Mambo, Choro y Samba VII. Dialogue In Democracy |
デトロイトSO、 ヤデル・ビニャミーニ(指) 録音:2023年12月1~3日/コンサートホール(デトロイト) |
|
||
| CLAVES 50-3099(1CD) |
モーツァルト:交響曲第40番ト短調 K.550 ディアナ・バルデス:ケツァルコアトル ハイドン:交響曲第49番ヘ短調 Hob I:49 J.C.バッハ:交響曲 ト短調 Op.6/6 |
ロベルト・ゴンザレス=モンハス(指) ヴィンタートゥール・ムジークコレ ギウム 録音:2023年9月/ヴィンタートゥール・シュタットハウス(スイス) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2323(2CD) 限定生産 ★ |
[疑似ステレオ版・オープンリール・テープ復刻] フルトヴェングラーVPO/ベートーヴェン:『英雄』、シューベルト:『未完成』、ほか (1)ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 (2)リスト:交響詩「前奏曲」 (3)シューベルト:交響曲第8番「未完成」 (4)ベートーヴェン:交響曲第7番 (5)ワーグナー:「ニュルンベルクのマイスタージンガ-」第1幕前奏曲 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) VPO 録音:(1)1952年11月26、27日、(2)1954年3月3、4日、(3)1950年1月19~21日、(4)1950年1月18、19日、 (5)1949年4月1~4日/以上、ウィーン、ムジークフェラインザール 使用音源:Angel(Japan) AXA-3043,3062,3060 (4トラック、19センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:ステレオ(セッション録音、疑似ステレオ) |
|
||
| Forgotten Records fr-2301(1CDR) |
R・シュトラウス:交響詩「死と変容」 ブラームス:交響曲第1番ハ短調Op.68 |
ポール・パレー(指)デトロイトSO 録音:1962年10月4日 放送録音 |
| Forgotten Records fr-2299(1CDR) |
ワルベルク&ケルテス/ハイドン 交響曲第101番「時計」 交響曲第104番「ロンドン」* |
ハインツ・ワルベルク(指) イシュトヴァン・ケルテス(指) バンベルクSO 録音:1961年 ※音源:Opera1202 |
| Forgotten Records fr-2295(1CDR) |
マーラー:交響曲第1番「巨人」 | ウィリアム・スタインバーグ(指) ボストンSO 録音:1960年1月8日 ボストン・シンフォニー・ホール放送録音 |
| Forgotten Records fr-2294(1CDR) |
メリヒャル/ハイドン:交響曲集 交響曲第45番「告別」 交響曲第94番驚愕」 |
アロイス・メリヒャル(指) ミュンヘンPO 録音:1949年 ※音源:Mercury MG15028, Mercury MG15023 |
| Forgotten Records fr-2288(1CDR) |
ドヴォルザーク:交響曲第8番* グリーグ:「ペール・ギュント」第1組曲&第2組曲 |
ヨネル・ペルレア(指) バンベルクSO 録音:1558年*、1957年(共にステレオ) ※音源:Vox STPL511.050, Vox STPL510.250 |
| Forgotten Records fr-2283(1CDR) |
ヨースタ・ニューストレム(1890-1966):交響曲第2番「シンフォニア・エスプレシーヴァ」 交響曲第3番「海の交響曲」* |
トゥール・マン(指) ストックホルムコンサート協会O イングリート・エクセル(S)* 録音:1950年 ※音源:His Master's Voice DB11030/33, Metronome CLP-504 |
| Forgotten Records fr-2085(1CDR) |
ハンニカイネンのシベリウス 交響曲第4番イ短調 Op.63 「カレリア」組曲* 交響詩「タピオラ」# |
ウノ・ハンニカイネン(指) ソヴィエト国立SO シンフォニア・オヴ・ロンドン* LSO# 録音:1958年、1959年1月7日*、1959年1月11日# ※音源:Melodiya4794/5, Everest SDBR3049, Everest SDBR3045 |
| Forgotten Records fr-2088C(2CDR) |
スクロヴァチェフスキのシューベルト 交響曲第9番「グレート」 交響曲第8番「未完成」 「ロザムンデ」~序曲 /間奏曲第2番/バレエ音楽第2番 |
スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ(指) ミネアポリスSO 録音:1961年 ※音源:Mercury SR90272, Mercury ST90218 |
| DOREMI DHR-8251(2CD) |
クラウス・テンシュテット LIVE 第5集 (1)ベートーヴェン:交響曲第1番ハ長調 Op.21 ベートーヴェン:交響曲第2番ニ長調 Op.36 (2)チャイコフスキー:ロココの主題による変奏曲 (3)ブルックナー:交響曲第7番ホ長調 |
クラウス・テンシュテット(指) (1)トロントSO 録音:1977年9月8日マッセイホール (2)ポール・トルトゥリエ(Vc)、フィラデルフィアO 録音:1988年1月8日フィラデルフィア (3)シカゴSO 録音:1984年5月31日、6月2日シカゴ |
|
||
| Goodies 78CDR-3956(1CDR) |
ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」から第4楽章「歓喜の頌」 (シラー原詩-尾崎喜八訳詞) |
橋本国彦(指)東京SO 国立音楽学校&玉川学園cho(岡本敏明指導) 香山淑子(S)(1910-) 四家文子(Ms)(1906-1981) 木下保(T)(1903-1982) 藤井典明(Br)(1915-1994) 日本ビクターJH232/4 1943年(昭和18年)5月13日日本青年館録音 |
|
||
| CPO CPO-555417(1CD) |
ホフマイスター:交響曲 ニ長調 「狩り」 Op.14 2つのホルンと管弦楽のための協奏曲 ホ長調…世界初録音 交響曲 ホ長調「ラ・プリマヴェーラ」…世界初録音 |
クリストフ・エス(Hrn) シュテファン・ショットシュテット(Hrn) プフォルツハイム南西ドイツ室内O ヨハネス・メーズス(指) 録音:2020年9月17-19日 |
|
||
| C Major 76-8508(DVD) |
フェニーチェ劇場ニューイヤー・コンサート2024 ブラームス:交響曲第2番ニ長調op.73 ヴェルディ:歌劇「二人のフォスカリ」~「風は凪ぎ、波は穏やか」 プッチーニ:歌劇「マノン・レスコー」~間奏曲 プッチーニ:歌劇「トスカ」~「星は光りぬ」、「歌に生き、愛に生き」 ヴェルディ:歌劇「椿姫」~「おれたちはマドリードのマタドール」 プッチーニ:歌劇「蝶々夫人」~ハミング・コーラス、「ある晴れた日に」 プッチーニ:歌劇「トゥーランドット」~「誰も寝てはならぬ」 ポンキエッリ:歌劇「ジョコンダ」~時の踊り ヴェルディ:歌劇「ナブッコ」~「行け、思いよ金色の翼に乗って」 プッチーニ:歌劇「トゥーランドット」~「おお神聖なる父君陛下よ」 ヴェルディ:歌劇「椿姫」~「乾杯の歌」 |
ファビオ・ルイージ(指) フェニーチェ歌劇場O&cho エレオノーラ・ブラット(S) ファビオ・サルトーリ(T) 収録:2024年1月1日 フェニーチェ歌劇場、ヴェネツィア(ライヴ) 画面:NTSC,16:9 音声:PCMステレオ、DTS5.1 DVD9 字幕:英独韓,日本語、112分 |
|
||
 BR KLASSIK BR-900225JP(1CD) 数量限定生産 初回盤のみ日本語訳解説付 |
マーラー:交響曲第7番ホ短調「夜の歌」 | バイエルンRSO サー・サイモン・ラトル(指) 録音:2024年11月6-8日 ミュンヘン、イザールフィルハーモニー・イン・ガスタイクHP8(ライヴ) |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00852(1SACD) 税込定価 2024年11月20日発 |
ブルックナー:交響曲第2番ハ短調(1877年ノーヴァク版第2稿) | ジョナサン・ノット(指)東京SO 録音:2022年10月22日 ミューザ川崎シンフォニーホール、10月23日 東京・サントリーホール・ライヴ |
|
||
| NIFC NIFCCD-158(1CD) |
ユゼフ・エルスネル(1769-1854):交響曲ハ長調 Op.11 ウェーバー:クラリネット協奏曲第2番変ホ長調 Op.74 モーツァルト:交響曲第21番イ長調 K.134 |
ロレンツォ・コッポラ(ピリオド・クラリネット) マルティナ・パストゥシュカ(Vn、指揮) {oh!} オルキェストラ・ヒストリチナ ※使用楽器:Clarinet in B flat with12keys, after Heinrich Grenser (c.1810, Dresden), made by Agnes Gueroult (Paris,1999) 録音:2023年10月10日-11日、3月4日ー5日、4月17日ー20日、ポーランド放送ヴィトルト・ルトスワフスキ・コンサート・スタジオ(ワルシャワ、ポーランド) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2321(2CD) 限定生産 ★ |
フルトヴェングラーVPO/ベートーヴェン:交響曲第1・4・5・6番 (1)交響曲第1番ハ長調、作品21 (2)交響曲第6番ヘ長調、作品68「田園」 (3)交響曲第4番変ロ長調、作品60 (4)交響曲第5番ハ短調、作品67「運命」 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) VPO 録音:(1)1952年11月24、27、28日 (2)1952年11月24、25日 (3)1952年11月1、2日 (4)1954年2月28日、3月1日 以上、ウィーン、ムジークフェラインザール 使用音源:EMI(Japan) AXA-3059,3060,3061 (4トラック、19センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:疑似ステレオ(録音セッション) |
|
||
| Forgotten Records fr-1957(1CDR) |
クレンペラー~Vox 録音集 シューベルト:交響曲第4番 「悲劇的」* ブルックナー:交響曲第4番調「ロマンティック」# |
オットー・クレンペラー(指) コンセール・ラムルーO*、ウィーンSO# 録音:1950年11月19日-20日* 1951年3月8日、12日、15日# ※音源:Vox PL6800*, PL5520# |
| Forgotten Records fr-1959(1CDR) |
ベートーヴェン&ウェーバー ベートーヴェン:交響曲第1番ハ長調 Op.21* 交響曲第8番ヘ長調 Op.93# ウェーバー:交響曲第1番ハ長調 Op.19+ |
ディミトリ・ミトロプーロス(指)NYO 録音:1951年4月1日+、1954年1月31日*、1957年5月5日#(ライヴ) |
| ANALEKTA AN-28890(1CD) |
2つのオーケストラ、1つの交響曲 ジャック・エテュ(1938-2010):交響曲第5番Op.81 |
ナショナル・アーツ・センターO ケベックSO トロント・メンデルスゾーンcho アレクサンダー・シェリー(指) 録音:2024年3月8、9日サウザム・ホール、カナダ・ナショナル・アーツ・センター |
|
||
| SOMM ARIADNE-5033(2CD) |
ブルックナー:交響曲第6&7番ほか 【CD1】 交響曲第6番イ長調 WAB106(ノーヴァク版) テ・デウム WAB45* 【CD2】 交響曲第7番ホ長調 WAB107(ノーヴァク版)# |
クリストフ・フォン・ドホナーニ(指) 北ドイツRSO ウィルマ・リップ(S)* エリーザベト・ヘンゲン(A)* ニコライ・ゲッダ(T)* ヴァルター・クレッペル(Bs)* VPO*、ウィーン楽友協会cho* ヘルベルト・フォン・カラヤン(指)* 南西ドイツRSO# ハンス・ミュラー・クライ(指)# 録音:全てモノラル 1961年11月18日(ライヴ)ハンブルク、ムジークハレ(北ドイツ放送のエア・チェック) 1962年5月26日(ライヴ)ウィーン、楽友協会大ホール(オーストリア放送のエア・チェック)* 1955年9月22日(放送用の非公開スタジオ・ライヴ)シュトゥットガルト、ヴィラ・ベルク、ゼンデザール(南ドイツ放送のエア・チェック)# ※2つの交響曲=初CD化 |
|
||
| FUGA LIBERA FUG-831(1CD) |
シテインベルク(1883-1946):交響曲第3番ト短調 Op.18* ショスタコーヴィチ:バレエ組曲「ボルト」 Op.27a |
ウラル・ユースSO ドミートリー・フィラトフ(指) 録音:2023年7月 スヴェルドロフスク・フィルハーモニック大ホール、エカテリンブルク、ロシア *=世界初録音 |
|
||
| CPO CPO-555661(1CD) |
グラジナ・バツェヴィチ:交響的作品全集 第3集 グラジナ・バツェヴィチ: 交響曲第1番…世界初録音 ポーランド序曲 オーケストラのためのパルティータ 大SOのための協奏曲 イン・ウナ・パルテ |
ケルンWDRSO ウカシュ・ボロヴィチ(指) 録音:2023年6月5-10日 |
|
||
| CPO CPO-555500(1CD) |
ポッター:交響曲全集 第2集 チプリアーニ・ポッター(1792-1871):交響曲 ハ短調(1826/1847) コンチェルタンテ ニ短調- ピアノ、ヴァイオリン、チェロ、コントラバスとオーケストラのために 交響曲 変ロ長調(1821)/序曲「嵐」 |
ミシュカ・ラシュディ・モーメン(P) ヨニアン・イリアス・カデシャ(Vn) ティム・ポズナー(Vc) フィリップ・ネルソン(Cb) BBCウェールズ・ナショナルO ハワード・グリフィス(指) 録音:2022年9月6-8日、2023年9月6日 |
|
||
| MDG MDG-91223306(1SACD) |
メンデルスゾーン・プロジェクトVOL.5 シンフォニア第11番ヘ短調 シンフォニア第12番ト短調 シンフォニア第13番ハ短調 |
ドグマ室内オーケストラ ミハイル・グレヴィチ(指) 録音:2023年6月24-26日、12月2-4日、マリエンミュンスター修道院コンサートホール |
|
||
 BPO RECORDINGS KKC-9891 (6CD+1Bluray) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ベルリン・フィルと小澤征爾 ■CD1-6 (1)ベートーヴェン:「レオノーレ」序曲 第2番 (2)ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲 第1番 (3)ラヴェル:ピアノ協奏曲ト長調 (4)バルトーク:ヴィオラ協奏曲Sz120 (5)ハイドン:交響曲 第60番『うかつ者』 (6)チャイコフスキー:交響曲第1番「冬の日の幻想」 (7)ブルックナー:交響曲第7番ホ長調 (8)マーラー:交響曲第1番 (9)ヒンデミット:シンフォニア・セレーナ (10)ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14 (11)R・シュトラウス:アルプス交響曲 作品64 (12)ワーグナー:楽劇「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死 ■ダウンロード・コード CD1-6に収録されているすべての音源をハイレゾリューション(24bit/48kHz)で聴くことのできるダウンロード・コードが封入されています。 ■Blu-ray Disc (1)ベートーヴェン:「エグモント」序曲 作品84 (2)合唱幻想曲 (3)メンデルスゾーン:オラトリオ「エリヤ」作品70 (4)ブルックナー:交響曲第1番 ハ短調(リンツ稿) ■ボーナス 小澤征爾、ベルリン・フィルの名誉団員の称号を授与 ■デジタル・コンサートホール ベルリン・フィルの映像配信サービス「デジタル・コンサートホール」を7日間無料視聴できるチケット・コードが封入されています。 [特別二大エッセイ掲載] 小澤征良 「父を想ってくださるみなさまへ」 村上春樹 「僕の夜明け前の同僚 ― 小澤征爾の死を悼んで」 |
小澤征爾(指)BPO ■CD1-6 (1)収録:1988年5月30日 (2ピエール・アモイヤル(Vn) 収録:1985年11月13日 (3)マルタ・アルゲリッチ(P) 収録:1982年6月22日 (4)ヴォルフラム・クリスト(Va) 収録:1988年5月30日 (5)収録:1987年6月25日 (6)収録:1992年11月12日 (7)収録:1988年6月22日 (8)収録:1980年2月3日 (9)収録:1987年6月28日 (10)収録:1982年6月27日 (11)収録:1996年5月31日 (12)収録:1979年11月10日 ■Blu-ray Disc (1)収録:2016年4月10日 (2)ピーター・ゼルキン(P)、ベルリン放送cho 収録:2016年4月10日 (3)アンネッテ・ダッシュ(S)、ガル・ジェイムズ(S)、ナタリー・シュトゥッツマン(A)、ナディーヌ・ヴァイスマン(A)、ポール・オニール(T)、アンソニー・ディーン・グリフィー(T)、マティアス・ゲルネ(Br)、フェルナンド・ハヴィエル・ラド(Bs)、ヴィクトール・ルード(Bs)、ベルリン放送cho 収録:2009年5月17日 (4)収録:2009年1月31日 ■ボーナス 収録:2016年4月 Blu-ray Disc (Concert videos) 画面:Full HD1080/60i,16:9 音声:2.0PCM Stereo24bit/48kHz 7.1.4Dolby Atmos24bit/48kHz リージョン:ABC(worldwide) 字幕:英、独、日本語 初回特典:L判写真×3種 |
|
||
| EUROARTS 20-67644(Bluray) |
ラフマニノフ:交響曲第2番+ドキュメンタリー ラフマニノフ:交響曲第2番ホ短調 Op.27 ドキュメンタリー『セルゲイ・ラフマニノフ・イン・ドレスデン』 |
シュターツカペレ・ドレスデン アントニオ・パッパーノ(指) 収録:2018年7月ドレスデン、ゼンパー・オーパー(ライヴ) 画面:16:9HD 音声:PCM ステレオ リージョン:All 字幕:英独韓,日本語 105分(本編62分 、ドキュメンタリー43分) |
|
||
| MELBOURNE SYMPHONY ORCHESTRA MSO-0002(1SACD) |
ドヴォルザーク:交響曲第5番ヘ長調 op.76, 交響曲第6番ニ長調 op.60 |
ハイメ・マルティン(指) メルボルンSO 録音:2023年11月17&18日(第5番)、2023年7月20&22日(第6番) |
|
||
| Aulicus Classics ALC-0113(1CD) |
アレッシオ・ミラーリア:交響曲第2番「オーラ(1、オーラ/2、霧の上昇/3、精霊の踊り/ 4、やまびこ/5、天空への旅) | アレッシオ・ミラーリア(作曲、コンピュータ、制作) |
|
||
| Goodies 78CDR-3956(1CDR) |
ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」から第4楽章「歓喜の頌」(シラー原詩-尾崎喜八訳詞) | 橋本国彦(指)東京SO 国立音楽学校&玉川学園cho(岡本敏明指導) 香山淑子(S)、四家文子(Ms)、木下保(T)、藤井典明(Br) 日本ビクターJH232/4 1943年(昭和18年)5月13日日本青年館録音 |
|
||
| CLAVES 50-3096(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第2番ニ長調 Op.36 ベートーヴェン:序曲「プロメテウスの創造物」Op.43 モーツァルト:交響曲第35番ニ長調 KV.385「ハフナー」 |
カメリスティ・デラ・スカラ ウィルソン・エルマント(指) 録音:2021年11月/ダル・ヴェルメ劇場、ミラノ(イタリア) |
|
||
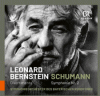 BR KLASSIK BR-900226(1CD) |
シューマン:交響曲第2番ハ長調 Op.61 バーンスタイン:オーケストラのためのディヴェルティメント |
バイエルンRSO レナード・バーンスタイン(指) 録音:1983年11月10-11日(ライヴ) ヘルクレスザール、ミュンヘン(ドイツ) |
|
||
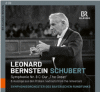 BR KLASSIK BR-900229(2CD) |
シューベルト:交響曲第8番ハ長調「グレート」 D944 コンダクターズ・イン・リハーサル 1. コンダクターズ・イン・リハーサル - フリードリヒ・シュロッフェルによる紹介 2-20. レナード・バーンスタインによるシューベルトの「グレート」のリハーサル風景 語り:フリードリヒ・シュロッフェル、 レナード・バーンスタイン、ヨハネス・リツコフスキー(ホルン奏者) 編集・原稿:ベルンハルト・ノイホフ リアリゼーション:カールハインツ・シュタインケラー |
レナード・バーンスタイン(指) バイエルンRSO 録音:1987年6月13-14日(ライヴ)ミュンヘン、ドイツ博物館 コングレスザール |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00863(1SACD) 税込定価 2024年10月23日発売 |
ハイドン交響曲集Vol.25 交響曲第57番ニ長調Hob. I:57 交響曲第44番ホ短調Hob. I:44「悲しみ」 交響曲第72番ニ長調Hob. I:72 |
飯森範親(指) 日本センチュリーSO 録音:2020年10月23日(第72番)、2022年9月18日(第44番、第57番) 大阪・ザ・シンフォニーホール・ライヴ |
|
||
| ALTO ALC-3147(10CD) 完全限定生産 |
チャイコフスキー:作品集 (1)交響曲第2番「小ロシア」 交響曲第3番 (2)交響曲第4番 交響曲第5番 交響曲第6番 (3)スラブ行進曲 Op.31 (4)交響曲第1番「冬の日の幻想」 (5)交響曲「ジーズニ」(セミヨン・ボガティレフによる補筆完成版) (6)マンフレッド交響曲 (7)ピアノ協奏曲第1番変ロ短調 Op.23 (8)カプリッチョ風小品 (9)ピアノ協奏曲第2番ト長調 Op.44 (10)ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.47 (11)・フランチェスカ・ダ・リミニ (12)ロココ風の主題による変奏曲 (13)「白鳥の湖」組曲 Op.20a 「くるみ割り人形」組曲 Op.71a 歌劇「チェレヴィチキ」よりポロネーズ 「眠れる森の美女」よりポロネーズ (14)組曲第3番ト調 Op.55 (15)幻想序曲「ロメオとジュリエット」 イタリア奇想曲 「エフゲニー・オネーギン」よりポロネーズ (16)弦楽セレナーデ ハ長調 Op.48 (17)「エフゲニー・オネーギン」よりワルツ 「眠れる森の美女」組曲 Op.66a (18)序曲「1812年」 |
(1)ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー(指)ソヴィエト国立文化省SO 録音:1988/9年 (2)エフゲニー・ムラヴィンスキー(指) レニングラードPO 録音:1960年-1961年 (3)アンタル・ドラティ(指)ミネアポリスSO 録音:1958年 (4)コンスタンティン・イワノフ(指)モスクワRSO 録音:1964年 (5)セルゲイ・スクリプカ(指)ロシア国立映画O 録音:1987年 (6)ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー(指)ソヴィエト国立文化省SO 録音:1989年 (7)スヴャトスラフ・リヒテル(P)、ヘルベルト・フォン・カラヤン(指)ウィーンSO 録音:1962年 (8)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(Vc)、 キリル・コンドラシン(指)モスクワ・ユースSO 録音:1950年 (9)エミール・ギレリス(P)、キリル・コンドラシン(指)ソヴィエト国立SO 録音:1962年 (10)ダヴィッド・オイストラフ(Vn)、ユージン・オーマンディ(指)フィラデルフィアO 録音:1959年 (11)パヴェル・コーガン(指)モスクワ国立SO 録音:1990年 (12)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(Vc)、 ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー(指)レニングラードPO 録音:1961年 (13)エフゲニー・スヴェトラーノフ(指)ソヴィエト国立SO 録音:1990年 (14)ウラディーミル・ユロフスキ(指)ロシア国立O 録音:2004年 (15)パヴェル・コーガン(指)モスクワ国立SO 録音:1990年 (16)ウラジーミル・フェドセーエフ(指)スクワRSO 録音:1992年 (17)ユージン・オーマンディ(指)フィラデルフィアO 録音:1959年 (18)アンタル・ドラティ(指)ミネアポリスSO、ミネソタ大学ブラス・バンド 録音:1958年 |
|
||
| ALTO ALC-3143(12CD) 完全限定生産 |
ショスタコーヴィチ:交響曲全集 (1)交響曲第1番ヘ短調 Op.10 交響曲第3番「メーデー」* (2)交響曲第2番「十月革命に捧ぐ」 (3)主題と変奏 変ロ長調 Op.3 (4)交響曲第12番ニ短調「1917年」 (5)交響曲第4番ハ短調 Op.43 (6)交響曲第5番ニ短調 Op.47 組曲「馬あぶ」 (抜粋) (7)交響曲第6番ロ短調 Op.54 交響曲第14番ト短調 Op.135* (8)交響曲第7番0「レニングラード」 (9)交響曲第8番ハ短調 Op.65 (10)祝典序曲 Op.96 スケルツォ 嬰ヘ短調 Op.1 (11)交響曲第9番変ホ長調 Op.70 (12)交響曲第15番イ長調 Op.141 (13)交響曲第10番ホ短調 Op.93 (14)交響曲第11番「1905年」 (15)劇音楽「リア王」 Op.58a (16)交響曲第13番「バビ・ヤール」 【ボーナス・ディスク】 交響曲第10番ホ短調 Op.93 |
(1)ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー(指)ソヴィエト国立文化省SO、ユルロフ・ロシアcho* 録音:1984年*、1985年 (2)ワレリー・ゲルギエフ(指)マリインスキー劇場O、マリインスキー劇場cho 録音:2009年&2010年 (3)ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー(指)ソヴィエト国立SO 録音:1970年 (4)エフゲニー・ムラヴィンスキー(指)レニングラードPO 録音:1962年~1963年 (5)ルドルフ・バルシャイ(指)ケルンRSO 録音:1996年 (6)マクシム・ショスタコーヴィチ(指)LSO 録音:1990年~1991年 (7)ウラディーミル・ユロフスキ(指)LPO、タチアナ・モノガロヴァ(S)*、セルゲイ・レイフェルクス(Br)* 録音(ライヴ):2006年*&2013年 (8)コンスタンティン・イワノフ(指)ソヴィエト国立SO 録音:1962年 (9)エフゲニー・ムラヴィンスキー(指)レニングラードPO 録音(ライヴ):1982年 (10)ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー(指)ソヴィエト国立SO 録音:1983年 (11)ワレリー・ゲルギエフ(指)マリインスキー劇場O 録音:2015年 (12)キリル・コンドラシン(指)モスクワPO 録音:1974年 (13)マクシム・ショスタコーヴィチ(指)LSO 録音:1990年 (14)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(指)LSO 録音:2002年 (15)エドワルド・セーロフ(指)サンクトペテルブルク室内O、ニーナ・ロマノワ(Ms) 録音:1984年 (16)キリル・コンドラシン(指)モスクワPO、ユルロフ・ロシア合唱団、ヴィタリー・グロマツキー(Bs) 録音:1962年 【ボーナス・ディスク】 エフゲニー・ムラヴィンスキー(指)レニングラードPO 録音(ライヴ):1954年 |
|
||
| ALPHA ALPHA-698(1CD) NYCX-10495(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
HAYDN2032Vol.16~驚き~ 交響曲第98番変ロ長調 Hob. I:98 交響曲第94番ト長調 Hob. I:94「驚愕」 交響曲第90番ハ長調 Hob. I:90 ロッシーニ:歌劇「絹のきざはし」序曲 |
イル・ジャルディーノ・アルモニコ バーゼル室内O (古楽器使用) ステファノ・バルネスキ(コンサートマスター) アンドレア・ブッカレッラ(Cemb) ジョヴァンニ・アントニーニ(指) 録音:2021年10月11-15日 ドン・ボスコ、バーゼル、スイス |
|
||
| Linn CKD-748(1CD) |
シューベルト:交響曲第5番変ロ長調 D485 交響曲第8番ロ短調 「未完成」 D759 ロンド イ長調 D438 |
スコットランド室内O ステファニー・ゴンリー(コンサートマスター/ソロ・ヴァイオリン) マキシム・エメリャニチェフ(指) 録音:2023年3月22-27日 カイヤード・ホール、ダンディー、UK |
|
||
| CPO CPO-777919(1CD) |
ハチャトゥリアン:交響曲第1番ホ短調 舞踏組曲 |
シューマン・フィルハーモニー フランク・ベールマン(指) 録音:2014年3月24-27日ドレスデン、ルカ教会(ドイツ) |
|
||
| CPO CPO-555472(1CD) |
ヨハン・ヴィルヘルム・ヴィルムス(1772-1847):交響曲第6番ニ短調 Op.58 演奏会用序曲 ホ長調 序曲 変ホ長調 序曲 ヘ短調 演奏会用序曲 変ホ長調 |
ミュンヘン放送O イヴァン・レプシッチ(指) 録音:2021年2月15-18日、6月9-11日 |
|
||
| VOX VOXNX-3047CD(1CD) |
メンデルスゾーン:交響曲第4番、第5番他(2024リマスター) 序曲「フィンガルの洞窟」 交響曲第4番イ長調「イタリア」 交響曲第5番ニ長調「宗教改革」 |
ボルティモアSO セルジュ・コミッショーナ(指) 録音:1974年6月26日、27日、11月7日 ボルティモア |
|
||
| GRAND SLAM GS-2327(2CD) 1枚分価格 |
フルトヴェングラー/3種のブラ1 ブラームス:交響曲第1番 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) VPO 録音:(1)1947年11月17~20、25日、ウィーン、ムジークフェラインザール (2)1947年(?) (3)1947年8月13日、ザルツブルク、フェストシュピールハウス 使用音源:(1)HMV (France, LA VOIX DE SON MAITRE) DB 6634/ 38, DBS 6639 (2VH7083-1/ 7084-2/ 7085-1/ 7086-2/ 7087-2/ 7088-2/ 7091-1/ 7092-1/ 7093-1/ 7099-1/ 7100-1) (2)日本コロムビア DXM-163 (3)Private archive 録音方式:モノラル(1)SP録音、(2)SPからの復刻、(3)ラジオ放送用録音 |
|
||
| Goodies 78CDR-3953(1CDR) |
ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 | フェリックス・ワインガルトナー(指)VPO 米 COLUBIA68855/68860-D(英 COLUMBIA LX532/7と同一録音) 1936年5月22&23日ウィーン録音 |
|
||
| フォンテック FOCD-9910(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 2024年10月9日発売 |
ブルックナー:交響曲第6番イ長調 <ノーヴァク版> | 尾高忠明(指) 大阪フィルハーモニーSO 録音:2024年1月22日 サントリーホール・ライヴ |
|
||
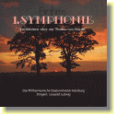 Treasures TRE-327(1CDR) |
ルートヴィヒ/モーツァルト&ブラームス モーツァルト:歌劇「魔笛」序曲* 歌劇「後宮からの逃走」* ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲# 交響曲第1番ハ短調Op.68+ |
レオポルド・ルートヴィヒ(指) ハンブルク国立歌劇場O*、ハンブルク国立PO#,+ 録音:1960年代中期*、1959年頃#,+(全てステレオ) ※音源:独EUROPA E-177*、日COLUMBIA MS-101-K#、独maritim KLASSIK 47473NK+ ◎収録時間:73:37 |
| “質実剛健一辺倒ではないルートヴィヒの人間味豊かな職人芸!” | ||
|
||
 オクタヴィア OVCL-00847(1SACD) 2024年9月25日発売 |
チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」 | 大友直人(指)東京SO 録音:2023年9月16日ミューザ川崎シンフォニーホール・ライヴ |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00861(1SACD) 2024年9月25日発売 |
ベルリオーズ:幻想交響曲 | 小林研一郎(指) コバケンとその仲間たちオーケストラ 録音:2024年6月1日東京・サントリーホール・ライヴ |
|
||
| ACCENTUS Music ACC-30652CD(1CD) |
ブルックナー:交響曲第2番ハ短調WAB102(1877) | バンベルクSO クリストフ・エッシェンバッハ(指) 録音:2024年3月、ヨーゼフ・カイルベルト・ザール、バンベルク |
|
||
 Hanssler HC-24039(4CD) KKC-6884(4CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ハイドン:交響曲全集 Vol.32~35 CD1 Vol.32 (1)交響曲第66番変ロ長調 Hob.I:66 (2)交響曲第71番変ロ長調 Hob.I:71 CD2 Vol.33 (3)交響曲第62番ニ長調 Hob.I:62 (4)交響曲第74番変ホ長調 Hob.I:74 (5)交響曲第76番変ホ長調 Hob.I:76 CD3 Vol.34 (6)交響曲第77番変ロ長調 Hob.I:77 (7)交響曲第78番ハ短調 Hob.I:78 (8)交響曲第81番ト長調 Hob.I:81 CD4 Vol.35 (9)交響曲第80番ニ短調 Hob.I:80 (10)交響曲第79番ヘ長調 Hob.I:79 (11)交響曲第91番変ホ長調 Hob.I:91 |
ハイデルベルクSO ヨハネス・クルンプ(指) 録音:(1)2022年6月30日&7月1日、(2)2022年7月2&4日、(3)2022年7月1&2日、4)2023年3月8&9日、(5)2022年10月10&11日、(6)2022年10月11~13日、(7)2022年10月13&14日、(8)2023年3月9~11日、(9)2023年5月19&20日、(10)2023年5月20&21日、(11)2023年5月22&23日 /ハイデルベルク=プファッフェングルント、ゲゼルシャフトハウス |
|
||
| EUROARTS 20-66504(Bluray) |
チェリビダッケ&ミュンヘンPOの芸術的遺産 (1)チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 (2)シューマン:ピアノ協奏曲 (3)ドヴォルザーク:交響曲第9番『新世界より』 (4)プロコフィエフ:古典交響曲 ラヴェル:スペイン狂詩曲 ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲 イベリア |
ミュンヘンPO セルジウ・チェリビダッケ(指揮 ) (1)ダニエル・バレンボイム(P) 収録:1991年10月ミュンヘン、ガスタイク(ライヴ) (2)ダニエル・バレンボイム(P) 収録:1991年7月エアランゲン・シュタットハレ(ライヴ) (3)収録:1991年 (4)収録:1988年 (5)収録:1994年ミュンヘン、ガスタイク(ライヴ) |
|
||
| BR KLASSIK BR-900720(9CD) |
ベルナルト・ハイティンク:ポートレート第2集 【CD1】 1-4. ベートーヴェン:交響曲第9番 ニ短調「合唱付き」 Op.125 【CD2】 ブルックナー:交響曲第4番 変ホ長調「ロマンティック」WAB 104(第2稿1878/80) 【CD3】 . ブルックナー:交響曲第7番ホ長調 WAB107 【CD4】 ブルックナー:テ・デウム WAB45 ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 WAB108(第1楽章-第2楽章)* 【CD5】 ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 WAB108(第3楽章-第4楽章) 【CD6】 ドヴォルザーク:交響曲第7番ニ短調 Op.70 スケルツォ・カプリチオーソ Op.66* 【CD7】 マーラー:交響曲第7番ホ短調 【CD8】 ショスタコーヴィチ:交響曲第8番 ハ短調 Op.65 【CD9】 ショスタコーヴィチ:交響曲第15番イ長調 Op. 141 |
全て、ベルナルト・ハイティンク(指)、バイエルンRSO 【CD1】 サリー・マシューズ(S)、ゲルヒルト・ロンベルガー(A)、マーク・パドモア(T)、ジェラルド・フィンリー (Bs)、バイエルン放送cho/録音:2019年2月20-23日ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ライヴ) 【CD2】 録音:2012年1月19-20日ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ライヴ) 【CD3】 録音:1981年11月19-20日ミュンヘン、ヘルクレスザール(ライヴ) 【CD4】 クラッシミラ・ストヤノヴァ(S)、イヴォンヌ・ナエフ(A)、クリストフ・シュトレール(T)、ギュンター・グロイスベック(Bs)、バイエルン放送cho/録音:2010年11月10-12日ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ライヴ)、1993年12月15-17日ミュンヘン、ヘルクレスザール(ライヴ)* 【CD5】 録音:1993年12月15-17日ミュンヘン、ヘルクレスザール(ライヴ) 【CD6】 初CD化 録音:1981年3月26-27日ミュンヘン、ヘルクレスザール(ライヴ)、1981年3月24日ミュンヘン、ヘルクレスザール(セッション)* 【CD7】 録音:2011年2月14-18日ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ライヴ) 【CD8】 録音:2006年9月23日ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ライヴ) 【CD9】 初CD化 録音:2015年2月5-6日ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ライヴ) |
|
||
| Channel Classics CCS-46924(1CD) |
神童フェリックス ~フェリックス・メンデルスゾーン初期作品集 キリエ ニ短調 MWV A3(1825) 弦楽のための交響曲第10番ロ短調 MWV N10(1823) めでたし、海の星(アヴェ・マリス・ステラ)(1828) 交響曲第1番ハ短調 Op.11(1824) (ミシャ・スポルクによる編曲版) カンタータ「ただ愛する神の摂理にまかす者」(1828) |
ナネッテ・マンス(S) アルス・ムジカO&cho パトリック・ファン・デル・リンデン(指) 録音:2023年11月 ワロン教会、アムステルダム |
|
||
| Pentatone PTC-5187353(4CD) |
シューベルト:交響曲全集 (1)交響曲第1番ニ長調 D.82(1813) (2)交響曲第6番ハ長調 D.589(1818) (3)交響曲第2番変ロ長調 D.125(1815) (4)交響曲第3番ニ長調 D.200(1815) (5)交響曲第4番ハ短調「悲劇的」D.417(1816) (6)交響曲第5番変ロ長調 D.485(1816) (7)交響曲第9番ハ長調「ザ・グレート」D.944(1825-26) (8)交響曲第8番ロ短調「未完成」D.759 【 「私の夢」第1部* / Ⅰ.アレグロ・モデラート / 「私の夢」第2部* / Ⅱ.アンダンテ・コン・モート】(1822) |
トビアス・モレッティ(朗読)* ビー・ロック・オーケストラ、 ルネ・ヤーコプス(指) 録音:(1)(2)2018年3月、 (4)(6)2020年2月ザール・インスブルック(インスブルック会議場内) (3)(5)2019年7月デ・スピル・コンサートホール(ルセラーレ) (7)(8)2020年12月デ・ジンゲル(アントワープ) |
|
||
| Forgotten Records fr-1930(1CDR) |
シューベルト:交響曲第9番「グレイト」 | ポール・パレー(指) デトロイトSO 録音:1962年12月8日、ヘンリー・フォード・ホール講堂〔フォード講堂〕、デトロイト、ライヴ |
| Forgotten Records fr-1932(1CDR) |
グーセンス~メンデルスゾーン:交響曲集 第4番「イタリア」/第5番「宗教改革」 |
ユージン・グーセンス(指) LPO 録音:1957年(ステレオ) ※音源: Classic Club X512他 |
| Forgotten Records fr-1939(1CDR) |
グラズノフ:交響曲第4番変ホ長調 Op.48* カバレフスキー:交響曲第2番Op.19# |
ジャック・ラフミローヴィチ(指) サンタ・チェチーリア音楽院O 録音:1949年3月 ※音源: Capitol P-8027他 |
| Forgotten Records fr-1943(1CDR) |
オスカー・フリート チャイコフスキー: 交響曲第6番「悲愴」* リスト:交響詩「マゼッパ」# |
オスカー・フリート(指) ロイヤルPO(旧)*、BPO # 録音:1929年1月2日、2月4日-5日 ※音源:英Columbia 9867/71他 |
| Forgotten Records fr-1945(1CDR) |
ストコフスキー&ニューヨークPO ヘンデル(ストコフスキー編): 組曲「水上の音楽」* モーツァルト:交響曲第40番# ショスタコーヴィチ:交響曲第1番+ |
レオポルド・ストコフスキー(指) NYO 録音:1960年3月5日、カーネギー・ホール、、ニューヨーク、 US 、ライヴ |
| Forgotten Records fr-1947(1CDR) |
ブラームス: 交響曲第2番ニ長調 Op.73* アルト・ラプソディ Op.53# |
グレース・ホフマン(A)# カール・バンベルガー(指)*,# フランクフルト歌劇場O*、 ハンブルク NDR響&cho# 録音:1956年、ステレオ ※音源:Concert Hall CHT/BN-23*, (オープン・リール) |
| ONDINE ODE-1454(1CD) NX-B10 NYCX-10490(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
フェルディナント・リース(1784-1838):交響曲第4番ヘ長調 Op.110(1818) 交響曲第5番ニ短調 Op.112(1813) |
タピオラ・シンフォニエッタ ヤンネ・ニソネン(指) 録音:2024年3月4日-7日エスポー(フィンランド)、タピオラ・ホール |
|
||
| CPO CPO-555115(1CD) NX-C04 |
カール・ライネッケ(1824-1910):管弦楽作品集第2集 交響曲第2番ハ短調 Op.134 序曲「ユーベルファイアー」 Op.166 荘厳なプロローグ Op.223 村の菩提樹の下での踊り Op161No.5 序曲「ダーメ・コボルト」 Op.51 ゼノビア序曲 Op.193 |
ミュンヘン放送O ヘンリー・ラウダレス(指) 録音:ミュンヘン、バイエルン放送 第1スタジオ2015年6月10-14日、2016年7月18-22日 |
|
||
| VOX VOXNX-3046CD(1CD) |
メンデルスゾーン:交響曲第3番「スコットランド」* 劇音楽『夏の夜の夢』~ 序曲/スケルツォ/夜想曲/結婚行進曲 |
ボルティモアSO セルジュ・コミッショーナ(指) 録音:1974年3月9日*、1977年6月 |
|
||
 Treasures TRE-328(1CDR) |
スワロフスキー~ベートーヴェン&シューベルト シューベルト:交響曲第8番「未完成」 ベートーヴェン:交響曲第7番イ長調* |
ハンス・スワロフスキー(指) ウィーン国立歌劇場O 録音:1957年(モノラル) ※音源:ORBIS 21224、仏VEGA 30MT-10.107* ◎収録時間:69:51 |
| “品格と内燃エネルギーを共存させるスワロフスキーの知られざる手腕!” | ||
|
||
 SOMM ARIADNE-5031(2CD) NX-D05 |
ブルックナー:交響曲第5番、他 【CD1】 交響曲第5番変ロ長調 WAB106・・・初CD化 【CD2】 弦楽五重奏曲 ヘ長調 WAB112 弦楽五重奏のための間奏曲 WAB113 |
【CD1】 クリストフ・フォン・ドホナーニ(指) ベルリンRSO(現ベルリン・ドイツSO) 【CD2】 ウィーン・コンツェルトハウスSQ フェルディナント・シュタングラー(第2ヴィオラ) 録音:【CD1】1963年12月8日 ベルリン、ケーペニック、放送会館(ステレオ、ライヴ/ベルリン放送のエア・チェック) 【CD2】1956年、ウィーン楽友協会ブラームスザール(MONO/初出LP:Vanguard VRS480による復刻) |
|
||
| Profil PH-20056(2CD) |
エディション・シュターツカペレ・ドレスデン
Vol.49 歴史的シェラック盤~ゼンパーオーパー録音 (1) ブラームス:交響曲第4番ホ短調Op.98 (2) レーガー:モーツァルトの主題による変奏曲とフーガOp.132 (3) ヘルベルト・ブロムシュテットへのインタビュー(2021年) (4) シューベルト:交響曲第5番変ロ長調D485 (5) ビゼー:歌劇「カルメン」抜粋(ドイツ語上演)【約53分】 |
カール・ベーム(指) シュターツカペレ・ドレスデン カルメン:エリーザベト・ヘンゲン(Ms)、ドン・ホセ:トルステン・ラルフ(T)、エスカミーリョ:ヨーゼフ・ヘルマン(Br)、ミカエラ:エルフリーデ・ヴァイトリヒ(S)ほか、 ドレスデン国立歌劇場cho 録音:1939年6-7月(1)、1937年6月(2)/ドレスデン・ゼンパーオーパー、 1942年6月(4)/ドレスデン衛生博物館、1942年12月4日(5)/ドレスデン・シュターツオーパー |
|
||
| Profil PH-23086(1CD) |
ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」(1888年版) | ゲルト・シャラー(指) フィルハーモニー・フェスティヴァ 録音:2023年8月20日/エーブラハ大修道院付属教会(ライヴ) |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00854(2SACD) 日本語解説付国内盤 税込定価 2024年8月28日発売 |
マーラー:交響曲第6番「悲劇的」 | ジョナサン・ノット(指) 東京SO 2023年5月20日東京・サントリーホール、5月21日ミューザ川崎シンフォニーホール・ライヴ |
|
||
| B RECORDS LBM-066(2CD) NX-E05 |
ベートーヴェン:交響曲全集 第1集 交響曲第1番ハ長調 Op.21 交響曲第2番ニ長調 Op.36 交響曲第4番変ロ長調 Op.60 |
オルケストル・コンスエロ ヴィクトル・ジュリアン=ラフェリエール(指) 録音:2023年8月22、23日サン・ロベール修道院(ラ・シェーズ=デュー音楽祭ライヴ) |
|
||
| FUGA LIBERA FUG-821(1CD) NX-C04 |
ラフマニノフ:交響曲 第3番イ短調 Op.44 ラヴェル:ラ・ヴァルス |
ウラルPO ドミトリー・リス(指) 録音:2022年9月 スヴェルドロフスク・フィルハーモニック大ホール、エカテリンブルク、ロシア |
|
||
| Avie AV-2713(1CD) |
エクソダス~タル、カウフマン、ルビン:管弦楽作品集 ヨセフ・タル(1910-2008):エクソダス ウォルター・カウフマン(1907-1984):インド交響曲 マルセル・ルビン(1905-1995):交響曲第4番「ディエス・イレ」 |
ジ・オーケストラ・ナウ、 レオン・ボットスタイン(指) 録音:2023年11月(ニューヨーク) |
|
||
| Signum Classics SIGCD-877(1CD) |
サントゥ・コンダクツ・ショスタコーヴィチ
ショスタコーヴィチ:交響曲第6番ロ短調 Op.54 交響曲第9番変ホ長調 Op.70 |
サントゥ=マティアス・ロウヴァリ(指) フィルハーモニアO 録音:2023年4月27日&9月24日、サウスバンク・センターズ・ロイヤル・フェスティヴァル・ホール(ロンドン) |
|
||
| GENUIN GEN-24903(1CD) |
クリスティアン・リディル:管弦楽のための音楽 フルート協奏曲 「パンの庭」(1999) 交響曲第1番「都市の風景」(1996-98) バスーン協奏曲 「フランスのブラームス」(1994) |
ロベルト・ファン・シュタイン(指) ライプツィヒSO、他 録音:2022年-2023年 |
|
||
| Gramola GRAM-99322(1CD) NX-C01 |
モーツァルト:セレナード第13番ト長調「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」
K.525 ディヴェルティメント ニ長調 K.136 交響曲第39番変ホ長調 K.543 |
ウィーン・コンツェルト・フェライン ミラン・トゥルコヴィチ(指) 録音:2023年9月6-8日 |
|
||
| LE PALAIS DES DEGUSTATEURS PDD-037(2CD) |
パイタのチャイコフスキー (1)交響曲第4番ヘ短調 Op.36(1877) (2)スラヴ行進曲 Op.31(1876) (3)幻想的序曲『ハムレット』Op.67a(1888) (4)イタリア奇想曲 Op.45(1880) (5)幻想的序曲『ロメオとジュリエット』(1869/70/80) (6)交響曲第6番ロ短調 Op.74『悲愴』(1893) |
カルロス・パイタ(指) (1)~(5)ロシアPO、 (6)ナショナルPO 録音:(1)~(5)1994年モスクワ音楽院大ホール(モスクワ) (6)1980年キングスウェイホール(ロンドン) |
|
||
| DACAPO MAR-8.224742(1CD) NX-B10 |
ヴィクトー・ベンディクス(1851-1926):交響曲第1番&第3番 交響曲第1番ハ長調「Ascension 昇天」 Op. 16(1877-78) 交響曲第3番イ短調 Op.25(1891-92) |
マルメSO ヨアキム・グスタフソン(指) 録音:2022年6月7-10日マルメ・ライヴ・コンサートホール(デンマーク) |
|
||
| ODRADEK RECORDS ODRCD-450(3CD) ★ |
マーラー:交響曲全集Vol.3 スカルタッツィーニ(b.1971):「オーメン」 マーラー:交響曲第6番「悲劇的」 スカルタッツィーニ:「オーメン-オルクス」* マーラー:交響曲第7番「夜の歌」* |
ジモン・ガウデンツ(指) イェナPO 録音:2023年3月21-24日、2023年5月9-13 日*、フォルクス・ハウス,イェナ・チューリンゲン・ドイツ |
|
||
| AfiA AFIA-9004(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
マーラー:交響曲第9番ニ長調 | 村中大祐(指) オーケストラ・アフィア 録音:2023年3月31日、横浜みなとみらいホールにおけるコンサート・ライヴ録音 |
|
||
| 大熱演!!ユーリ・アーロノヴィチの初出音源3タイトル一挙リリース! ※このレーベルは、初発売後早期に廃盤となる可能性が高いです。お早めにご注文されることをおすすめいたします。 |
||
 Spectrum Sound CDSMBA-165(1CD) |
(1)ストラヴィンスキー:組曲第2番~小オーケストラのための (2)チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」 (3)ショスタコーヴィチ:交響曲第7番「レニングラード」~第4楽章(第2部~第3部) |
全て、ユーリ・アーロノヴィチ(指) (1)(2)フランス国立O ライヴ録音:1977年10月19日サル・プレイエル(パリ)【ステレオ】 (3)フランス放送新PO ライヴ録音:1980年3月10日メゾン・ド・ラジオ・フランス内104スタジオ(パリ)【ステレオ】 |
|
||
| Spectrum Sound CDSMBA-166(1CD) |
(1)ドヴォルザーク:交響曲第8番 ト長調 Op.88 (2)ムソルグスキー(ラヴェル編):展覧会の絵 |
全て、ユーリ・アーロノヴィチ(指) (1)フランス国立O ライヴ録音:1976年4月7日サル・プレイエル(パリ)【ステレオ】 (2)フランス放送新フィルハーモニー管弦楽団 ライヴ録音:1978年10月5日メゾン・ド・ラジオ・フランス内104スタジオ(パリ)【ステレオ】 |
|
||
| Spectrum Sound CDSMBA-170(1CD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲第7番「レニングラード」 | ユーリ・アーロノヴィチ(指) フランス放送新PO ライヴ録音:1980年3月10日メゾン・ド・ラジオ・フランス内104スタジオ(パリ)【ステレオ】 |
|
||
| KLARTHE KLA-173(1CD) |
「新世界2.0」 ドヴォルザーク:交響曲第9番新世界より」 (コリャール編曲によるエレクトロニカ版) |
トゥールーズ室内O、 ジル・コリャール(指) 録音:2021年10月23~26日/エリクシール・スタジオ |
|
||
| REFERENCE FR-757SACD(1SACD) |
ブルックナー:交響曲第7番ホ長調(1883年ノヴァーク版) メイソン・ベイツ(1977-):レスルレクシト(2018) |
ピッツバーグSO マンフレート・ホーネック(指) 録音:2022年3月25-27日、ハインツホール、ピッツバーグ(ライヴ) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2319(2CD) ★ 限定生産 |
稀少音源つき限定盤/フルトヴェングラー/シューベルト:交響曲集 (1)交響曲第2番変ロ長調 D.125 (2)交響曲第3番ニ長調 D.200 (3)『ロザムンデ』序曲 D.644 (4)交響曲第8番ロ短調 D.759『未完成』 (5)交響曲第9番ハ長調 D.944『ザ・グレイト』 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) (1)(2)VPO ※指揮者不明、かつてフルトヴェングラー指揮とされていた音源 (3)-(5)BPO 録音:(1)(2)不明、(3)-(5)1953年9月15日/ベルリン、ティタニア・パラスト 使用音源:(1)(2)日本コロムビア DXM-165(非フルトヴェングラー録音) (3)-(5)Private archive(2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(ラジオ放送用録音) |
|
||
| Pentatone PTC-5187208(1CD) |
モーツァルト:交響曲第29番イ長調 K.201(1774) クラリネット協奏曲 イ長調 K.622(1791) 交響曲第33番変ロ長調 K.319(1779) |
エルンスト・シュラーダー(バセット・クラリネット) ベルリン古楽アカデミー(ベルンハルト・フォルク:コンサートマスター) 録音:2023年10月22~25日/テルデックス・スタジオ、ベルリン(ドイツ) |
|
||
| LSO Live LSO-0571(4SACD) ★ |
LSO Live25周年記念ボックス~ドヴォルザーク、スメタナ、ヤナーチェク (1)ドヴォルザーク:交響曲第6番ニ長調 op.60 (2)ヤナーチェク:シンフォニエッタ (3)ドヴォルザーク:交響曲第7番ニ短調 op.70 (4)ドヴォルザーク:交響曲第8番ト長調 op.88 (5)ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」 (6)スメタナ:我が祖国 |
全て、LSO (1)サー・コリン・デイヴィス(指)[録音:2004年9月] (2)サー・サイモン・ラトル(指)[録音:2018年9月] (3)サー・コリン・デイヴィス(指)[録音:2001年3月] (4)サー・コリン・デイヴィス(指)[録音:1999年10月] (5)/サー・コリン・デイヴィス(指)[録音:1999年9月] (6)サー・コリン・デイヴィス(指)[録音:2005年5月] |
|
||
| Challenge Classics CC-72959(1CD) |
シューマン:交響曲第3番「ライン」 交響曲第4番ニ短調 Op.120 |
スタヴァンゲルSO ヤン・ヴィレム・デ・フリエンド(指) 録音:2024年1月29日~2月1日スタヴァンゲル・コンサートホール(ノルウェー) |
|
||
| Challenge Classics CC-72997(4CD) ★ |
シューベルト:交響曲全集 CD1 (1)交響曲第2番ニ長調 D.125 (2)交響曲第4番ハ短調『悲劇的』 D.417 CD2 (3)交響曲第1番ニ長調 D.82 (4)交響曲第3番ニ長調 D.200 (5)交響曲第8番ロ短調 『未完成』 D.759 CD3 (6)交響曲第9番ハ長調 『グレイト』 D.944 CD4 (7)交響曲第5番変ロ長調 D.485 (8)交響曲第6番ハ長調 D.589 |
ハーグ・レジデンティO、 ヤン・ヴィレム・デ・フリエンド(指) 録音:(1)(2)2017年8月30日~9月1日、(4)(5)2018年6月5~8日、(6)2019年11月28~29日 アトリウム・メッペルヴェーグ 、ハーグ(オランダ) (3)2016年6月21~23日ザウダーストラント劇場、ハーグ(オランダ) (7)(8)2022年1月18~21日、2022年7月5~7日アマレ・コンサートホール、ハーグ(オランダ) |
|
||
| H.M.F HMM-902721(1CD) |
ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」(ノヴァーク版/第2稿) | パブロ・エラス=カサド(指) アニマ・エテルナ・ブリュッヘ(ピリオド楽器/コンサートマスター:アンネ・カタリーナ・シュライバー) 録音:2024年1月、コンセルトヘボウ・ブリュッヘ(ベルギー) |
|
||
| Myrios Classics MYR-035(2CD) |
ブルックナー:交響曲第1&2番 交響曲第1番ハ短調(1868年リンツ稿/トーマス・レーダー版、2016年出版) 交響曲第2番ハ短調(1872年第1稿/ウィリアム・キャラガン版、2005年出版) |
フランソワ=グザヴィエ・ロト(指) ケルン・ギュルツェニヒO 録音:2020年10・11月/シュトルベルガー・シュトラッセ・スタジオ(第1番)、ケルン・フィルハーモニー(第2番) |
|
||
| Audite AU-97832(1CD) |
ルツェルン・フェスティヴァル・シリーズ第20弾 (1)ドヴォルザーク:交響曲第8番 (2)ドヴォルザーク:交響詩「野鳩」 (3)スメタナ:歌劇「リブシェ」への前奏曲 |
チェコPO ヴァーツラフ・ノイマン(指) ライヴ録音:(1)1988年3月26日、(2)1984年8月25日、(3)1984年8月26日/クンストハウス(ルツェルン) |
|
||
| Simax PSC-1394(1CD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番ハ短調 Op.37(スティヤン・オーレスキョル
編)* ハイドン:交響曲第44番ホ短調「悲しみ(Trauer)」 Hob.I/44(スティヤン・オーレスキョル 編) |
クリスチャン・イーレ・ハドラン(P)* アイヴィン・オードラン(指) ノルウェー管楽アンサンブル[インゲル・ヨハンネ・ベルグ(Fl)、ローセ・エリン・アウスタ・ネス(Fl)、ダーヴィド・F・ストゥンク(Ob)、クリスティーナ・オールヴァイン(Ob)、エーリク・ヨルダル(Cl)、インゲ・ノストヴォル(Cl)、ローアル・アルネス・オールム(Cl)、トール=エギル・ハンセン(Cl)、クリステル・ベルグビュー(Fg)、リアン・カリー(Fg)、クリスティン・ホーゲンセン(サクソフォーン)、モッテン・ノールハイム(サクソフォーン)、スタイナル・グランモ・ニルセン(ナチュラル・ホルン)、ブリット・クリスティン・ラーシェン(ナチュラル・ホルン)、スティヤン・オーレスキョル(バロック・トランペット)トルゲイル・ホーラ(バロック・トランペット)、トリル・G・ベルグ(サックバット)、ミゲル・T・セビジャーノ(サックバット)、タリヤイ・グリムスビュー(サックバット)、ローゲル・フィエルデ(チンバッソ)、アレックス・ロルトン(Vc)、ローゲル・モルラン(Cb)、グンヒル・P・トンデル(Cemb)、ホーコン・シューベルグ(ティンパニ)] 録音:2021年8月、オストレ・フレドリクスタ教会(オストフォル、ノルウェー) |
|
||
| Polskie Radio PRCD-2345(2CD) ★ 初紹介旧譜 |
ダイアモンド・バトン賞 Vol.2 リスト:メフィスト・ワルツ第1番「村の居酒屋での踊り」 チャイコフスキー:交響曲第1番 ト短調「冬の日の幻想」Op.13 ヘンデル:歌劇「ソザルメ、メディアの王」HWV 30* |
アグニェシュカ・ドゥチマル(指)、 ワルシャワPO、ポーランド放送アマデウス室内O* 録音:1978年-1980年 |
|
||
| Dynamic CDS-8043(1CD) NX-B06 |
マーラー:交響曲第4番ト長調(エルヴィン・シュタインによる室内アンサンブル版) | ララ・マレッリ(S) アンサンブル・キャント・テル・イット アンドレア・カッペレーリ(指) 録音:2023年12月27-28日 |
|
||
| ALPHA ALPHA-1068(1CD) |
ブルックナー:交響曲第9番ニ短調 WAB109 (原典版) | チューリヒ・トーンハレO パーヴォ・ヤルヴィ(指) 録音:2023年9月 トーンハレ、チューリヒ |
|
||
 SWR music SWR-19155CD(8CD) ★ NX-G03 |
プレートル&シュトゥットガルト放送SO名演集 ■CD1 ベートーヴェン:「エグモント」序曲 交響曲第3番「英雄」* ■CD2 ブラームス:交響曲第1番* 4つのハンガリー舞曲[第1番ト短調/ 第3番ヘ長調/第4番 嬰へ短調/ 第5番ト短調] ■CD3 ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」(第2稿) ■CD4 ベルリオーズ:幻想交響曲* ファウストの劫罰~妖精の踊り/ラコッツィ行進曲 ■CD5 ラヴェル:『ダフニスとクロエ』 第2組曲 ラ・ヴァルス* ビゼー:交響曲第1番# ■CD6 ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」 マーラー:交響詩「葬礼」* ■CD7 レスピーギ:交響詩『ローマの噴水』 交響詩『ローマの松』 ストラヴィンスキー:バレエ音楽 『火の鳥』(1919年版)* ■CD8 R・シュトラウス:「ばらの騎士」組曲(1945) 交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」* 交響詩「ドン・ファン」# |
全て、シュトゥットガルトRSO ジョルジュ・プレートル(指) ■CD1 録音:1995年10月6日 ブラティスラヴァ、Slowakische Philharmonie、1995年9月28-29日 シュトゥットガルト、リーダーハレ* ■CD2 録音:2000年12月8日*、1997年10月29,31日 録音:1995年9月22-23日 ■CD4 録音:1994年3月24.25日*、2001年2月14,16日 ■CD5 録音:1997年10月29、31日、1995年12月22日*、1991年6月28日# ■CD6 録音:1996年10月14、28日、1998年6月24、26日* ■CD7 録音:2004年10月21,22日、2000年12月8日* ■CD8 録音:1998年10月2日 ウィーン、ムジークフェライン 1997年10月31日 シュトゥットガルト、リーダーハレ* 1995年9月29日 シュトゥットガルト、リーダーハレ# 全て、ステレオライヴ録音 |
|
||
| Resonus RES-10340(1CD) NX-B08 |
エリナー・アルベルガ(1949-):管弦楽作品集 Tower タワー(2017)* 交響曲第1番「ストラータ」(2022) Mythologies 神話(2000) |
カスタリアンQ* BBC響 トーマス・ケンプ(指) 録音:2023年9月20-22日 ※全て世界初録音 |
|
||
| GRAND SLAMGS-2317(2CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 1枚分価格 限定生産 |
バイロイトの第九[モノラル&疑似ステレオ] ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 |
エリザベート・シュワルツコップ(S)、エリザベート・ヘンゲン(A)、ハンス・ホップ(T)、オットー・エーデルマン(Bs)、ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) バイロイト祝祭O&cho 録音:1951年7月29日フェストシュピールハウス、バイロイト 使用音源:[Disc1]HMV(U.K.) ALP1286/7、[Disc2]EMI(Japan) AXA3044B(4トラック、19センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:[Disc1]モノラル、[Disc2]ステレオ(疑似ステレオ) |
|
||
| DOREMI DHR-8245(2CD) |
クラウス・テンシュテット LIVE 第3集 (1)ベートーヴェン:交響曲第3番変ホ長調 『英雄』 Op.55 (2)ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 WAB108 |
クラウス・テンシュテット(指) (1)ボストンSO 録音:1977年7月30日タングルウッド (2)NYO 録音:1992年4月14日ニューヨーク |
|
||
| DOREMI DHR-8247(2CD) |
クラウス・テンシュテット LIVE 第4集 (1)ベートーヴェン:交響曲第5番ハ短調 Op.67 (2)ベートーヴェン:交響曲第4番変ロ長調 Op.60 (3)R.シュトラウス:交響詩『ドン・キホーテ』 Op.35 (4)ブラッハー:パガニーニの主題による変奏曲 Op.26 (5)ブラッハー:協奏的音楽 Op.10 |
クラウス・テンシュテット(指) (1)NYO 録音:1985年1月17日ニューヨーク、エイヴリー・フィッシャー・ホール (2)NYO 録音:1980年5月29日ニューヨーク、エイヴリー・フィッシャー・ホール (3)ローン・マンロー(Vc)、ポール・ニューバウアー(Va)、NYO 録音:1985年1月17日ニューヨーク、エイヴリー・フィッシャー・ホール (4)録音:1985年4月11日ニューヨーク、エイヴリー・フィッシャー・ホール (5)シカゴSO 録音:1976年12月9日シカゴ |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00850(1SACD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
シューベルト:交響曲第7番「未完成」 交響曲第8番「ザ・グレイト」 劇音楽「キプロスの女王ロザムンデ」~間奏曲第3番 |
久石譲(指) フューチャー・オーケストラ・クラシックス 録音:2023年7月5日東京オペラシティコンサートホール、7月6日長野市芸術館メインホール・ライヴ |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00848(1SACD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ブルックナー:交響曲第1番ハ短調 (1877年リンツ稿、ノーヴァク版) |
ジョナサン・ノット(指) 東京SO 録音:2023年10月21日東京オペラシティ・コンサートホール・ライヴ |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00853(1SACD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ショスタコーヴィチ:祝典序曲イ長調作品96 交響曲第5番ニ短調作品47 |
太田弦(指)九州SO 録音:2024年4月11-12日アクロス福岡シンフォニーホール・ライヴ |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00849(1SACD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ハイドン交響曲集Vol.24 交響曲第82番ハ長調Hob.Ⅰ:82「熊」 交響曲第86番ニ長調Hob.Ⅰ:86 交響曲第87番イ長調Hob.Ⅰ:87 |
飯森範親(指) 日本センチュリーSO 録音:2022年3月31日大阪・ザ・シンフォニーホール・ライヴ |
|
||
| Orchid Classics ORC-100322(1CD) NX-B06 |
クリス・バワーズ(1989-):若き日の自分へ シェーンベルク:室内交響曲第1番(管弦楽版[1935]) |
チャールズ・ヤン(Vn) アメリカン・ユース・シンフォニー カルロス・イスカライ(指) 録音:2022年4月14日、2024年1月20日 |
|
||
| 東武レコーディングズ TBRCD-0156(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」(第1稿1874 年版) | 朝比奈千足(指)東京都SO 録音:1982年10月12日五反田簡易保険ホール・ライヴ(第1稿・日本初演ライヴ) |
|
||
| BIS BISSA-2510 (1SACD) |
リスト:ファウスト交響曲 S108(3人の人物描写による)(1854年版) 村の居酒屋での踊り(メフィスト・ワルツ第1番) S110/2~レーナウの「ファウスト」による2つのエピソードより第2曲(1859-62) |
リエージュ王立PO ゲルゲイ・マダラシュ(指) 録音:2023年8月29日~9月1日/サル・フィルハーモニック(リエージュ) |
|
||
| DOREMI DHR-824(2CD) |
クラウス・テンシュテット LIVE 第2集 (1)ベートーヴェン:交響曲第5番『運命』 (2)シューマン:交響曲第3番『ライン』 (3)ハイドン:協奏交響曲 変ロ長調 Op.84, Hob.I/105 (4)ハイドン:ェロ協奏曲 ハ長調 Hob.VIIb/1 (4)ハイドン:交響曲第64番イ長調 『時の移ろい』 Hob.I/64 |
クラウス・テンシュテット(指) (1)シカゴSO 録音:1976年12月9日/シカゴ (2)ニューヨーク・フィルハーモニック 録音:1985年4月11日/ニューヨーク (3)ジョゼフ・シルヴァースタイン(Vn) ジュール・エスキン(Vc) ラルフ・ゴンバーク(Ob) シャーマン・ウォルト(Fg) ボストンSO 録音:1979年7月20日/タングルウッド (4)ジュール・エスキン(Vc) ボストンSO 録音:1980年7月26日/タングルウッド (4)ボストンSO |
|
||
 Treasures TRE-321(1CDR) |
ラインスドルフ&ボストン響~厳選名演集Vol.6~ドヴォルザーク他 リムスキー=コルサコフ:組曲「金鶏」* ドヴォルザーク:交響曲第6番ニ長調 Op. 60 スラブ舞曲Op.72-2/Op.72-8 |
エーリヒ・ラインスドルフ(指) ボストンSO 録音:1965年4月23-24*、1967年(全てステレオ) ※音源:日ビクター SHP-2376*、SRA-2527、 ◎収録時間:77:30 |
| “ラインスドルフこだわりの「ドボ6」の比類なき昇華力!” | ||
|
||
| DOREMI DHR-8241(2CD) |
クラウス・テンシュテット LIVE 第1集 (1)ベートーヴェン:ヴァイオリン、チェロとピアノのための三重協奏曲 ハ長調 Op.56 (2)ベートーヴェン:交響曲第7番 (3)マーラー:交響曲第1番『巨人』 (4)ハイドン:交響曲第45番『告別』 |
クラウス・テンシュテット(指) (1)ジョゼフ・シルヴァースタイン(Vn)、ジュール・エスキン(Vc)、ピーター・ゼルキン(P) ボストンSO 録音:1977年7月30日タングルウッド (2)ボストンSO 録音:1977年7月29日タングルウッド (3)北ドイツRSO 録音:1977年11月14日 (4)ボストンSO 録音:1979年7月20日タングルウッド |
|
||
| Pentatone PTC-5187216(2CD) |
ドヴォルザーク:交響曲&序曲集 交響曲第7番ニ短調 Op.70 交響曲第8番ト長調 Op.88 交響曲第9番『新世界より』 序曲『自然と人生と愛』 「自然の中で」 「謝肉祭」/「オセロ」 |
チェコPO セミヨン・ビシュコフ(指) 録音:2023年9月27日~10月13日/ルドルフィヌム、ドヴォルザーク・ホール(プラハ) |
|
||
| BIS BISSA-2696(11SACD) ★ |
マーラー:交響曲全集 ■Disc1(56'45) 交響曲第1番ニ長調『巨人』 ■Disc2(84'38) 交響曲第2番ハ短調『復活』 ■Disc3&4(1h43'19) 交響曲第3番ニ短調 ■Disc5(59'25) 交響曲第4番ト長調 ■Disc6(75'30) 交響曲第5番嬰ハ短調 ■Disc7(86'48) 交響曲第6番イ短調 ■Disc8(77'30) 交響曲第7番ホ短調 ■Disc9(83'13) 交響曲第8番変ホ長調『千人の交響曲』 ■Disc10(81'32) 交響曲第9番ニ長調 ■Disc11(78'20) 交響曲第10番嬰ヘ長調(クック版第3稿(第2版)(1989)) |
ミネソタO&cho オスモ・ヴァンスカ(指) 交響曲第2番 ルビー・ヒューズ(S)、サーシャ・クック(Ms)、ミネソタO 交響曲第3番 ジェニファー・ジョンストン(Ms)、ミネソタcho、ミネソタ少年cho 交響曲第4番ト長調 キャロリン・サンプソン(S) 交響曲第8番 キャロリン・サンプソン(ソプラノI / いと罪深き女)、ジャクリン・ワーグナー(ソプラノII / 贖罪の女)、キャロリン・サンプソン(ソプラノIII / 栄光の聖母)、サーシャ・クック(アルトI / サマリアの女)、ジェス・ダンディ(アルトII / エジプトのマリア)、バリー・バンクス(テノール / マリア崇拝の博士)、ユリアン・オルリスハウゼン(バリトン / 法悦の教父)、クリスティアン・イムラー(バス / 瞑想の教父)、ミネソタcho(音楽監督:キャシー・サルツマン・ロメイ)、ナショナル・ルーテルcho、ミネソタ少年cho アンジェリカ・カンタンティ・ユースcho 録音:2018年3月(第1番)、2017年6月(第2番)、2022年11月(第3番)、2018年6月(第4番)、2016年6月(第5番)、2016年11月(第6番)、2018年11月(第7番)、2022年6月(第8番)、2022年3月(第9番)、2019年6月(第10番)/オーケストラ・ホール(ミネアポリス) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2316(1CD) |
ウラニアのエロイカ2024新復刻(ボーナス・トラック付) (1)交響曲第3番「英雄」 ボーナス・トラック (2)第1楽章 アレグロ・コン・ブリオ |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) VPO 録音:1944年12月19日/ウィーン、ムジークフェラインザール 録音方式:モノラル(ラジオ放送用録音) 【使用音源】(1)URANIA(U.S.A.) URLP7095(E3KP 4554-1A / E3KP4555-1B) (2)URANIA(U.S.A.) URLP7095(ULP7095A) |
|
||
| Goodies 78CDR-3946(1CDR) |
シューマン:交響曲第4番ニ短調作品120 | ハンス・プフィツナー(指) ベルリン国立歌劇場O 日POLYDOR40141/4A (独 POLYDOR66410/3と同一録音) 1926年ベルリン録音 |
|
||
| Urania Records LDV-14116(1CD) |
マーラー:交響曲第9番ニ長調 | ヴラディーミル・デルマン(指)、 ミラノRAI響 録音(ライヴ):1993年 |
|
||
| Urania Records WS-121419(2CD) |
レトロスペクティヴ (1)シューベルト:交響曲第9番「ザ・グレイト」 (2)R.シュトラウス:交響詩 「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」 「サロメ」 より7つのヴェールの踊り (3)ムソルグスキー:展覧会の絵 (4)ブラームス:交響曲第3番ヘ長調 Op.90 |
トーマス・シッパーズ(指) (1)シンシナティSO (2)シンシナティSO (3)NYO (4)トリノ・イタリアRSO 録音:1965年-1967年 |
|
||
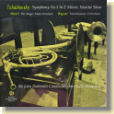 TreasuresTRT-023(1CDR) |
モーツァルト:歌劇「魔笛」序曲 ワーグナー:歌劇「タンホイザー」序曲 チャイコフスキー:スラブ行進曲* 交響曲第5番ホ短調Op.64# |
ジョン・バルビローリ(指)ハレO 録音:1959年3月30日&4月2,5-9日 1959年3月31日* 1959年3月30日-31日#マンチェスター・フリー・トラッド・ホール(全てステレオ) ※音源:Pye GSGC-2038、日TEICHIKU_UDL-3082-Y*,# ◎収録時間:73:42 |
| “敵なし!バルビローリならではの怒涛のロマン!!” | ||
|
||
 Spectrum Sound CDSMBA-158(1CD) |
マーラー:交響曲第10番(クック版) | フランス国立放送O、 ジャン・マルティノン(指) ライヴ録音:1970年5月27日/シャンゼリゼ劇場、パリ【ステレオ】 |
|
||
| Spectrum Sound CDSMBA-157(1CD) |
カサドシュ&マルティノン (1)ビゼー:「祖国」序曲 Op.19 (2)サン・サーンス:交響曲第3番ハ短調 Op.78 「オルガン付き」 (3)モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番イ長調 K.488 |
(2)ベルナール・ガヴォティ(Org) (3)ロベール・カサドシュ(P) (1)(2)フランス国立O、 (3)フランス国立放送O ジャン・マルティノン(指揮 ) ライヴ録音:(1)(2)1975年1月8日、(3)1969年6月18日/シャンゼリゼ劇場、パリ【ステレオ】 |
|
||
| Capriccio C-8096(2CD) NX-B10 NYCX-10477(2CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ブルックナー:交響曲第9番、他 【CD1】 交響曲第9番ニ短調 WAB109(ノーヴァク校訂 BSW9) 【CD2】 交響曲へ短調 WAB99(ノーヴァク校訂 BSW10) |
リンツ・ブルックナーO マルクス・ポシュナー(指) 録音:2021年11月9日&10日(CD1)、2022年2月23日&27日(CD2) リンツ、ムジークテアター・リハーサルホール |
|
||
| FUGA LIBERA FUG-813(1CD) |
パリの祭典 ミヨー:屋根の上の牛(カデンツァ…アルテュール・オネゲル) シャブリエ:気まぐれなブーレ(作曲者の未完のスケッチに基づくティボー・ペリーヌによる管弦楽版) ※世界初録音 ラヴェル:ツィガーヌ (ラヴェル・エディションによる新校訂版) 世界初録音 ビゼー:交響曲 ハ長調 |
アレクサンドラ・スム(Vn) ペレアス室内O バンジャマン・レヴィ(指) 録音:2021年5月5-8日 サル・コロンヌ、パリ |
|
||
| Altus ALTB-545(3SACD) シングルレイヤー 完全限定生産 |
ヴァント&N響ライヴ集成/SACD3タイトルセット(全3枚) 【ALTSA-258】 ベルリオーズ:「ローマの謝肉祭」序曲 シューマン:交響曲第4番ニ短調 【ALTSA-260】 ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」(ハース版) 【ALTSA-261】 シューベルト:交響曲第3番ニ長調 D.200 ブラームス:交響曲第1番ハ短調 Op.68 |
ギュン ター・ヴァント(指) NHK響 【ALTSA-258】 録音:1979年11月21日/NHKホール 【ALTSA-260】 録音:1982年4月14日/NHKホール 【ALTSA-261】 録音:1983年12月8日/NHKホール |
|
||
 オクタヴィア OVCL-00844(1SACD) 税込定価 2024年6月19日発売 |
ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 | ヤン・ヴィレム・デ・フリーント(指) 読売日本SO 森谷真理(S) 山下裕賀(Ms) アルヴァロ・ザンブラーノ(T) 加藤宏隆(Bs) 新国立劇場cho 録音:2023年12月23-24日東京芸術劇場コンサートホール・ライヴ |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00846(1SACD) 税込定価 2024年6月19日発売 |
ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 | 小林研一郎(指) コバケンとその仲間たちオーケストラ 市原愛(S) 山下牧子(Ms) 笛田博昭(T) 寺田功治(Br) 史上最高の第九に挑むcho 録音:2023年12月10日東京・サントリーホール・ライヴ |
|
||
 Capriccio C-5484(3CD) NX-D03 NYCX-10481(3CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
マーラー版ベートーヴェン:交響曲集 交響曲第5番「運命」 Op.67 交響曲第3番「英雄」 Op.55 序曲「コリオラン」ハ短調 Op.62 交響曲第7番イ長調 Op.92 弦楽四重奏曲第11番ヘ短調「セリオーソ」 Op. 95 序曲「レオノーレ」第2番Op.72 序曲「レオノーレ」第3番Op.72b 交響曲第9番「合唱」 Op.125 |
ラインラント=プファルツ州立PO マイケル・フランシス(指) マルガリータ・ヴィルソーネ(S) エヴリン・クラーエ(Ms) ミヒャエル・ミュラー=カステラン(T) デリック・バラード(Br) ブルノ・チェコ・フィルハーモニーcho 録音:2021年10月8-9日、18-22日…交響曲第5番、第7番 2022年7月5-8日…交響曲第3番、コリオラン 2023年11月6-8日…弦楽四重奏第11番 2022年11月4-5日(ライヴ)…交響曲第9番 ※マーラー研究家、前島良雄氏による日本語解説付き。 |
|
||
| BIS BISSA-2486(2SACD) |
マーラー:交響曲第3番ニ短調 | ジェニファー・ジョンストン(Ms) ミネソタcho(女声)、ミネソタ少年cho ミネソタO、 オスモ・ヴァンスカ(指) 録音:2022年11月14-18日/オーケストラ・ホール(ミネアポリス) プロデューサー:ロバート・サフ |
|
||
| B RECORDS LBM-063(1CD) NX-C04 |
ティエリー・エスケシュ(1965-):Vitrail(ステンドグラス) ショスタコーヴィチ(ヴィクトル・デレヴィアンコ編): 交響曲第15番Op.141(打楽器、チェレスタ、ピアノ、ヴァイオリンとチェロのための) |
トリオ・メシアン【ダヴィド・ペトルリク(Vn)、ヴォロディア・ファン・クーレン(Vc)、フィリップ・アタ(P)】 トリオ・クセナキス【エマニュエル・ジャケ、ロドルフ・テリー、ニコラ・ラモト(打楽器)】 録音:2023年8月1日 サル・エリー・ド・ブリニャック、アルカナ、ドーヴィル、フランス (ライヴ/拍手入り) |
|
||
| ALPHA ALPHA-1057(1CD) |
マーラー:交響曲第9番(ピリオド楽器による) | マーラー・アカデミーO フィリップ・フォン・シュタイネッカー(指) 録音:2022年9月 マーラー・ザール、トーブラッハ文化センター、イタリア |
|
||
| WERGO WER-7392(1CD) |
王西麟(ワン・シーリン Xilin Wang,1936-):交響曲第3番 Op.26(1989/90) | エマニュエル・シフェール(指) 中国国家SO 録音:2018年4月18日/北京コンサートホール(ライヴ) |
|
||
 SOMM ARIADNE-5028(2CD) NX-D05 |
ピエール・モントゥー/晩年のロンドン・ライヴ集 ■CD1 ウェーバー:祝典序曲 ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」 ラヴェル:スペイン狂詩曲 ダフニスとクロエ 第2組曲* ■CD2 ハイドン:交響曲第104番「ロンドン」* ストラヴィンスキー:春の祭典** 拍手とアナウンス** LSO員及び関係者へのインタビュー集# モントゥーへのインタビュー「ウィレム・ペイペルの交響曲第3番を語る」## ドヴォルザーク:交響曲第7番~第1楽章と第2楽章のリハーサルより+ |
ピエール・モントゥー(指) BBCノーザンO ロイヤルPO*、LSO**,+ 録音:1963年10月18日 マンチェスター・タウンホール(ライヴ)・・・CD1 1-10 1960年12月25日 ロンドン、BBCスタジオ(ライヴ)・* 1963年5月29日 ロイヤル・アルバート・ホール(ライヴ)** 1992年-1995年# 1955年 アムステルダム## 1959年10月+ #のみステレオ、他はすべてモノラル 音源:BBCラジオのエアチェック・・・CD1&*,** |
|
||
| BIS BISSA-2441(1SACD) |
ストラヴィンスキー:交響曲集 (1)3楽章の交響曲(1942-45) (2)管楽器のための交響曲(1918-20原典版) (3)交響曲 ハ調(1938-1940) |
ディーマ・スロボデニューク(指)、 ガリシアSO 録音:(1)(3)2019年2月11~15日、(2)2023年6月18&19日コルーニャ歌劇場(スペイン) |
|
||
| CPO CPO-555429(2CD) NX-E07 |
ディッタースドルフ:オウィディウスの『変 身物語』による交響曲集 交響曲第1番ハ長調「四つの時代」 交響曲第2番ニ長調「ファエトンの墜落」 交響曲第3番ト長調「鹿に変えられたアクタエオン」 交響曲第4番ヘ長調「ペルセウスによって救われたアンドロメダ」 交響曲第5番イ長調「蛙に変えられたリュキアの農夫たち」 交響曲第6番ニ長調「石にされたフィネウスと仲間たち」 |
ハイルブロン・ヴュルテンベルク室内O ケース・スカリオーン(指) 録音:2020年10月21-23日、11月19-21日 |
|
||
| CD ACCORD ACD-315(1CD) NX-D05 |
シマノフスキ:作品集 演奏会用序曲 ホ長調 Op.12(第2稿)(1912-13) おとぎ話の王女の歌 Op.31? ソプラノ独唱とオーケストラのために(1915) 交響曲第3番「夜の歌」 Op.27-ソプラノ独唱、合唱とオーケストラのために(1914-16) |
イヴォナ・ソボトカ(S) NMF合唱団 NFMヴロツワフPO ジャンカルロ・ゲレーロ(指) 録音:2022年7月17日 2021年6月9-10日 2022年6月13-15日 |
|
||
 LE PALAIS DES DEGUSTATEURS PDD-036(2CD) |
ショスタコーヴィチ&ブルックナー (1)ショスタコーヴィチ:交響曲第8番ハ短調 Op.65 (2)ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 WAB.108(ハース版) |
カルロス・パイタ(指)、 フィルハーモニックSO 録音:(1)1981年収録場所不明(未発表ライヴ録音)、(2)1982年5月/キングスウェイホール(ロンドン) |
|
||
| Urania Records LDV-14114(1CD) |
フランチェスコ・ザッパ:6つの交響曲 フランチェスコ・ザッパ(1717-1803):交響曲第1番変ホ長調/交響曲第2番ト長調/交響曲第3番変ロ長調/交響曲第4番ハ長調/交響曲第5番ニ長調/交響曲第6番変ホ長調 |
アタランタ・フーギエンスO、 ヴァンニ・モレット(指) 録音:2022年10月16日-17日 |
|
||
| Lyrita SRCD-2417(4CDR) |
ジョージ・ロイド:交響曲第1番~第6番 ジョージ・ロイド(1913-1998):交響曲第2番/交響曲イ長調(第1番)*/交響曲第3番ヘ長調/シャレード組曲/交響曲第4番「北極」*/歌劇「ジョン・ソックマン」序曲/交響曲第5番変ロ長調/交響曲第6番 |
ジョージ・ロイド(指)、 BBCフィルハーモニック、 オールバニーSO* 録音:1986年-1992年、BBCスタジオ7(マンチェスター)&トロイ貯蓄銀行音楽ホール(ニューヨーク)* |
|
||
| Lyrita SRCD-432(1CDR) |
リチャード・ブラックフォード(b.1954):サグラダ・ファミリア交響曲* カンタータ「バベル」 |
BBCウェールズ・ナショナルO*、リチャード・ブラックフォード(指)*、アイコン・シンガーズ&アンサンブル、デイヴィッド・ヒル(指)、レベッカ・ボットーネ(S)、アレッサンドロ・フィッシャー(T)、スティーヴン・ガッド(Br) 録音:2022年4月21日-22日*&2023年9月26日、ホディノット・ホール(カーディフ、イギリス)*&セント・ジョージズ・ヘッドストーン(イギリス) |
|
||
| Avie AV-2684(1CD) |
失われた世代 フーゴ・カウダー(1888-1972):交響曲第1番 ハンス・エーリヒ・アポステル(1901-1972):ハイドンの主題による変奏曲 アドルフ・ブッシュ(1891-1952)(ピーター・ゼルキン編):オリジナルの主題による変奏曲 |
レオン・ボットスタイン(指)、 ジ・オーケストラ・ナウ 録音:2022年11月 |
|
||
| ALTO ALC-1484(1CD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲第4番ハ短調 Op.43 劇付随音楽「ハムレット」組曲 Op.32a* |
キリル・コンドラシン(指)モスクワPO、 エドワルド・セーロフ(指)レニングラード室内O* |
|
||
 SWR music SWR-19152CD(2CD) NX-D05 |
ブルックナー:交響曲第7番ホ長調 WAB107 交響曲第8番ハ短調 WAB108(第1稿) |
エリアフ・インバル(指) シュトゥットガルトRSO 録音:2013年11月21&22日(第7番)、2015年10月1&2日(第8番) リーダーハレ(シュトゥットガルト)、ベートーヴェンザール(ライヴ収録) |
|
||
| Altus ALTB-542(3SACD) シングルレイヤー 限定生産 非圧縮SACD |
チェリビダッケ来日SACD傑作選 /SACD3タイトルセット 【ALTSA140】 シューマン:交響曲第4番 ムソルグスキー(ラヴェル編):組曲『展覧会の絵』 ドヴォルザーク:スラヴ舞曲第8番 【ALTSA141】 ロッシーニ:『どろぼうかささぎ』序曲 R.シュトラウス:交響詩『死と変容』 ブラームス:交響曲第4番 ブラームス:ハンガリー舞曲第1番 ヨハン&ヨーゼフ・シュトラウス:ピツィカートポルカ 【ALTSA183】 ブルックナー:交響曲第8番 |
セルジュ・チェリビダッケ(指) ミュンヘンPO 【ALTSA140】 録音:1986年10月14日/人見記念講堂(ライヴ) 【ALTSA141】 録音:1986年10月15日/東京文化会館(ライヴ) 【ALTSA183】 録音:1990年10月20日/サントリーホール(ライヴ) |
|
||
| Altus ALTB-543(6SACD) シングルレイヤー 限定生産 非圧縮SACD |
ウィーン・フィル ORF戦後ライヴSACD大集成
/SACD4タイトルセット (1)ベートーヴェン:交響曲第9番調 『合唱付き』 (2)ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 ヴァイオリン、チェロとオーケストラのための協奏曲 イ短調 作品102 ブラームス:交響曲第1番 (3)マーラー:さすらう若人の歌 ベートーヴェン:交響曲第3番『英雄』 (4)ブルックナー:交響曲第3番ニ短調 WAB103(1889年稿) (5)R・シュトラウス:交響詩『死と変容』 (6)R・シュトラウス:アルプス交響曲 (7)フランツ・シュミット:軽騎兵の歌による変奏曲 シューベルト:交響曲第9番ハ長調『ザ・グレイト』 (8)R・シュトラウス:交響詩『死と変容』 シューマン:交響曲第4番ニ短調 作品120 (9)ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 WAB.108 (10)シューベルト:交響曲第5番変ロ長調 D. 485 ブラームス:交響曲第4番 (11)ブルックナー:交響曲第9番 (12)ブルックナー:交響曲第8番 (13)ブルックナー:交響曲第5番 (14)ブルックナー:交響曲第7番 (15)モーツァルト:交響曲第38番ニ長調「プラハ」 (16)モーツァルト:交響曲第40番ト短調 K. 550 (17)モーツァルト:交響曲第35番ニ長調「ハフナー」 K.385 R. シュトラウス:交響詩「ドン・ファン」 ラヴェル:「マ・メール・ロワ」、「ダフニスとクロエ」第2組曲 (18)シューマン:ピアノ協奏曲 (19)ブラームス:交響曲第1番 |
全てVPO (1)イルムガルト・ゼーフリート(S)、ロゼッテ・アンダイ(A)、アントン・デルモータ(T)、パウル・シェフラー(Br)、ウィーン・ジングアカデミー (合唱)、録音:1953年5月30日/楽友協会 大ホール(ウィーン) ロートヴァイスロート(赤白赤)放送グループによるライヴ録音(モノラル) (2)ウィリー・ボスコフスキー(Vn)、エマヌエル・ブラベッツ(Vc)、録音:1952年1月27日/楽友協会 大ホール(ウィーン) ロートヴァイスロート(赤白赤)放送グループによるライヴ録音(モノラル) (3)アルフレート・ペル(Br)、録音:1952年11月30日/楽友協会 大ホール(ウィーン) ロートヴァイスロート(赤白赤)放送グループによるライヴ録音(モノラル) 以上、ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) (4)録音:1960年2月14日/楽友協会 大ホール(ウィーン) オーストリア放送協会によるライヴ録音 (5)録音:1958年11月9日/楽友協会 大ホール(ウィーン) オーストリア放送協会によるライヴ録音 (6)録音:1952年4月20日/楽友協会 大ホール(ウィーン) ロートヴァイスロート(赤白赤)放送グループによるライヴ録音 (7)録音:1957年10月27日/楽友協会 大ホール(ウィーン) オーストリア放送協会によるライヴ録音 (8)録音:1962年12月16日/ムジークフェラインザール オーストリア放送協会によるライヴ録音 (9)録音:1961年10月29日/ムジークフェラインザール オーストリア放送協会によるライヴ録音 以上、ハンス・クナッパーツブッシュ(指) (10)録音:1965年4月24日/楽友協会 大ホール(ウィーン)オーストリア放送協会によるライヴ録音(モノラル) (11録音:1955年3月17日/コンツェルトハウス 大ホール(ウィーン) ロートヴァイスロート(赤白赤)放送グループによるライヴ録音(モノラル) (12)録音:1963年12月7日/楽友協会 大ホール(ウィーン) オーストリア放送協会によるライヴ録音(モノラル) (13)録音:1963年2月24日/楽友協会 大ホール(ウィーン) オーストリア放送協会によるライヴ録音(モノラル) 以上、カール・シューリヒト(指) (14)カール・ベーム(指) 録音:1953年3月7日/楽友協会 大ホール(ウィーン) ロートヴァイスロート(赤白赤)放送グループによるライヴ録音(モノラル) (15)ブルーノ・ワルター(指) 録音:1955年11月6日/楽友協会 大ホール(ウィーン) ロートヴァイスロート(赤白赤)放送グループによるライヴ録音(モノラル) (16)ブルーノ・ワルター(指) 録音:1956年6月24日/楽友協会 大ホール(ウィーン) オーストリア放送協会によるライヴ録音(モノラル) (17)アンドレ・クリュイタンス(指) 録音:1955年5月15日/楽友協会 大ホール(ウィーン) ロートヴァイスロート(赤白赤)放送グループによるライヴ録音(モノラル) (18)ヴィルヘルム・バックハウス(P)、カール・ベーム(指) 録音:1963年3月17日/楽友協会 大ホール(ウィーン) オーストリア放送協会によるライヴ録音(モノラル) (19)ール・ベーム(指) 録音:1954年11月6日/楽友協会 大ホール(ウィーン) ロートヴァイスロート(赤白赤)放送グループ によるライヴ録音(モノラル) |
|
||
| Forgotten Records fr-2229E(1CDR) |
ベイヌム&クリーヴランドOライヴ ウェーバー:「魔弾の射手」序曲 ラヴェル:スペイン狂詩曲 ベルリオーズ:幻想交響曲 |
エドゥアルド・ヴァン・ベイヌム(指) クリーヴランドO 録音:1955年12月22日セヴェランス・ホール(ライヴ) |
| Forgotten Records fr-1922(1CDR) |
マーラー:交響曲第6番「悲劇的」 | ディミトリ・ミトロプーロス(指) VPO 録音:1957年9月22日(初出ライヴ) |
| Gramola GRAM-99306(1CD) NX-C01 |
ブルックナー:交響曲 ニ短調 WAB 100(1869) (2023年デイヴィッド・チャプマン校訂版) |
聖フローリアン・アルトモンテO レミ・バロー(指) 録音:2023年8月19日(ライヴ) 聖フローリアン修道院教会、ザンクト・フローリアン(オーストリア北部オーバーエスターライヒ地方) ※GRAM99311ブルックナー:交響曲全集より分売 |
|
||
| Capriccio C-8095(1CD) NX-B10 NYCX-10474(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ブルックナー:交響曲第3番ニ短調(第2稿)、 アダージョ(1876年/ノーヴァク校訂版)* |
ウィーンRSO リンツ・ブルックナーO* マルクス・ポシュナー(指) 録音:2023年11月22日 ウィーン、放送文化会館&11月24日 ウィーン、ムジークフェライン 2023年2月22日 リンツ、ムジーク* |
|
||
 ICA CLASSICS ICAC-5179(2CD) NX-D03 |
ボールト~初出ライヴ音源集 (1)ベートーヴェン::交響曲第3番「英雄」 (2) ベートーヴェン:『献堂式』 序曲 (3)ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 (4)シューベルト:交響曲第9番「ザ・グレート」 (5)ウェーバー:「オイリアンテ」 序曲 (6)ロッシーニ:「絹のはしご」 序曲 (7)ケルビーニ:「アナクレオン」 序曲 |
エイドリアン・ボールト(指) (1)LPO 録音:1972年5月10日 ロイヤル・フェスティバル・ホール、ロンドン (2) BBCウェールズO 録音:1973年6月19日 BBCカーディフ放送局コンサートホール (3)BBC響 録音:1976年10月3日 マイダ・ヴェール・スタジオ、ロンドン (4)BBC響 録音:1977年3月2日 ロイヤル・フェスティバル・ホール、ロンドン (5)BBCウェールズO 録音:1973年6月22日 BBCカーディフ放送局コンサートホール (6)BBCスコティッシュSO 録音:1973年8月4日 BBCグラスゴー放送局コンサートホール (7)ロイヤルPO 録音:1963年3月8日 ロイヤル・フェスティバル・ホール、ロンドン 全てライヴ録音(ステレオ) |
|
||
 ICA CLASSICS ICAB-5180(6CD) NX-G11 |
レオポルド・ストコフスキー/BBCレジェンズ・グレート・レコーディングス (1)マーラー:交響曲第2番ハ短調 「復活」 (2)ショスタコーヴィ:交響曲第5番ニ短調 Op.47「革命」 (3)ヴォーン・ウィリアムズ:交響曲第8番 ニ短調 (4)スクリャービン:法悦の詩 Op.54 (5)ベルリオーズ:幻想交響曲 Op.14 (6) レオポルド・ストコフスキーとデリック・クックの対話(インタビュー約9分) (7) ブリテン:青少年のための管弦楽入門 Op. 34 (8)ベートーヴェン:交響曲第7番イ長調 Op. 92 (9)ファリャ:恋は魔術師 (10) オットー・クレンペラー:メリー・ワルツ (11)ヴォーン・ウィリアムズ:トーマス・タリスの主題による幻想曲 (12)ラヴェル:スペイン奇想曲 (13)ブラームス:交響曲第4番ホ短調 Op.98 (14)ノヴァーチェク(ストコフスキー編):常動曲(無窮動) Op.5-4 ●ボーナス・ディスク(AVRO音源) (15) ラヴェル:ファンファーレ ~『ジャンヌの扇』 (16)フランク:交響曲 ニ短調 (17)プロコフィエフ:カンタータ「アレクサンドル・ネフスキー」 Op.78* |
レオポルド・ストコフスキー(指) (1)レイ・ウッドランド(S)、ジャネット・ベイカー(C.A)、BBC合唱団、BBCコーラル・ソサエティ、ゴールドスミス・コーラル・ユニオン、ハロー・コーラル・ソサエティ、LSO 録音:1963年7月30日 ロイヤル・アルバート・ホール、ロンドン (BBCプロムス) モノラル(ICA Ambient Mastering) (2)LSO 録音:1964年9月17日 ロイヤル・アルバート・ホール、ロンドン ステレオ (3)BBC響 録音:1964年9月15日 ロイヤル・アルバート・ホール、ロンドン ステレオ (4)(5)ニュー・フィルハーモニアO 録音:1968年6月18日 ロイヤル・フェスティバル・ホール、ロンドン ステレオ (7)(8)BBC響 録音:1963年7月23日 ロイヤル・アルバート・ホール、ロンドン(BBCプロムス) ステレオ (9)グロリア・レーン(Ms)、BBC響 録音:1964年9月15日 ロイヤル・アルバート・ホール、ロンドン(BBCプロムス) ステレオ (10) -(13)ニュー・フィルハーモニアO 録音:1974年5月14日 ロイヤル・アルバート・ホール、ロンドン ステレオ (14)LSO 録音:1964年9月21日 ロイヤル・アルバート・ホール、ロンドン ステレオ ●ボーナス・ディスク ソフィア・ヴァン・サンテ(Ms)*、オランダ放送合唱団*、オランダ放送PO 録音:1970年8月22日 デ・ドゥーレン、ロッテルダム ステレオ |
|
||
| DUX DUX-2022(1CD) |
グジェゴシュ・フィテルベルク:交響曲ホ短調 Op.16(世界初録音) | ウカシュ・ボロヴィチ(指)、 ポズナンPO 録音:2023年10月6日、アダム・ミツキェヴィチ大学講堂(ポズナン、ポーランド) |
|
||
| Danacord DACOCD-932(2CDR) |
トマス・イェンセンの遺産 第22集 (1)モーツァルト:交響曲第33番変ロ長調 K.319 (2)ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調 K.216* (3)交響曲第34番ハ長調 K.338 (4)交響曲第39番変ホ長調 K.543- 第3楽章「メヌエット」# (5)コレッリ:合奏協奏曲ハ短調 Op.6No.3 (6)J.C.バッハ:序曲(シンフォニア)変ロ長調 Op.18-2 (7)ハイドン:ノットゥルノ第7番ハ長調 Hob.II:31 (8)モーツァルト:セレナード第6番「セレナータ・ノットゥルナ」** (9)歌劇「フィガロの結婚」 序曲 (9)歌劇「魔笛」序曲 |
トマス・イェンセン(指)、 デンマークRSO、 ティヴォリSO#、 トゥター・ギウスコウ(Vn)* レーオ・ハンセン(Vn1)**、 アーネ・カレツキ(Vn2)**、 ゴナ・フレゼリクセン(Va)**、 ヘリエ・プロウ(Cb)** (1)録音:1961年10月23日、放送コンサートホール(ライヴ放送) (2)録音:1962年5月11日、カジノ・スレーイルセ(ライヴ放送) (3)録音:1958年5月7日、エスビェア(ライヴ放送) (4)録音:1942年秋 (5)録音:1962年11月19日(室内コンサート) (6)録音:1962年9月27日(火曜コンサート) (7)録音:1962年11月19日(室内コンサート) (8)録音:1961年10月23日、デンマーク放送コンサートホール(ライヴ放送) (9)録音:1962年5月11日、カジノ・スレーイルセ(ライヴ放送) (9)録音:1958年5月7日、エスビェア(ライヴ放送) |
|
||
| SOMM ARIADNE-5027(2CD) NX-D05 |
ブルックナー:交響曲ニ短調、第2番他 (1)ミサ曲第2番ホ短調 WAB27(1882) (2)交響曲ニ短調 WAV100(1869/ヴェス版)* (3)交響曲第2番ニ短調 WAB102(ハース版)* |
(1) カール・フォルスター(指)BPO、聖ヘトヴィヒ大聖堂が (2) エドゥアルト・ファン・ベイヌム(指) アムステルダム・コンセルトヘボウO (3)ゲオルク・ルートヴィヒ・ヨッフム(指) ケルンRSO 録音:(1)1956年6月24日-7月1日 ベルリン、ヴィンターガルテン【Electrola E80010】、 (2)1955年3月13日 アムステルダム、コンセルトヘボウ(ライヴ)・オランダ放送のエアチェック (3)1962年4月 ケルン、西部ドイツ放送局(WDR)ゼンデザール・西部ドイツ放送のエアチェック *=初出 |
|
||
| Goodies 78CDR-3939(1CDR) |
シューマン:交響曲第4番ニ短調作品120 | ブルーノ・ワルター(指)LSO 英 HMV DB3793/5 1939年4月26日ロンドン録音 |
|
||
| Altus OALTSA-002(1SACD) シングルレイヤー 完全限定生産 初SACD化 日本語帯・解説付 |
ブラームス:交響曲全集 | ラファエ ル・クーベリック(指) バイエルンRSO 録音:1983年4月26-29日、5月3-6日/ミュンヘン |
|
||
| Altus OALTSA-003(1SACD) シングルレイヤー 完全限定生産 初SACD化 日本語帯・解説付 |
モーツァルト:交響曲第39-41番、他 交響曲第39番変ホ長調 KV543 交響曲第40番ト短調 KV550 交響曲第41番ハ長調「ジュピター」 KV551 フリーメイソンのための葬送音楽 ハ短調 KV 477 |
オイゲン・ヨッフム(指) バンベルクSO 録音:1982年3月22-24日、11月18-20日/バンベルク、クルトゥーアラウム |
|
||
| ATMA ACD2-2453(1CD) |
シベリウス:交響曲第2番、第5番 交響曲第2番ニ長調 Op.43 交響曲第5番変ホ長調 Op.82 |
ヤニック・ネゼ = セガン(指) モントリオール・メトロポリタンO 録音:2023年9月16日(第2番)、2023年3月3日(第5番)/モントリオール・シンフォニー・ハウ |
|
||
| ACCENTUS Music ACC-30605CD(1CD) |
ブルックナー:交響曲第9番 ニ短調 WAB109 | ヤクブ・フルシャ(指) バンベルクSO 録音:2022年11月、ヨーゼフ・カイルベルト・ザール |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00839(1SACD) 税込定価 2024年4月24日発売 |
ショスタコーヴィチ:交響曲第10番ホ短調 作品93 | 井上道義(指)NHK響 録音:2022年11月12-13日NHKホール・ライヴ |
|
||
| Capriccio C-8094(1CD) NX-B10 NYCX-10469(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ブルックナー:交響曲第1番ハ短調(第2稿/ギュンター・ブロシェ校訂版) .スケルツォ(1865年/ヴォルフガング・グランジャン校訂版) |
リンツ・ブルックナーO マルクス・ポシュナー(指) 録音:2023年2月7-9日(交響曲)、2024年1月8日(スケルツォ) リンツ、ムジークテアター・リハーサルホール |
|
||
| FUGA LIBERA FUG-824(1CD) NX-C04 |
ルイーズ・ファランク(1804-1875):交響曲第3番ト短調 Op.36 シューマン:交響曲第3番「ライン」 |
南オランダPO ダンカン・ウォード(指) 録音:2022年11月、2023年5月 オランダ(ライヴ/拍手入り) |
|
||
| ONDINE ODE-1443(1CD) NX-B10 NYCX-10470(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
フェルディナント・リース(1784-1838):交響曲集 交響曲第1番ニ長調 Op.23(1809) 交響曲第2番ハ短調 Op.80(1814) |
タピオラ・シンフォニエッタ ヤンネ・ニソネン(指) 録音:2024年1月9日~11日 エスポー(フィンランド)、タピオラ・ホール |
|
||
| OEHMS OC-1730(1CD) NX-B10 |
エルガー:序曲「コケイン」Op.40 交響曲第1番Op.55 |
マンハイム国立劇場O アレクサンダー・ソディ(指) 録音:2023年6月5-6日、2021年10月18-19日 |
|
||
| SOMM ARIADNE-5026(2CD) NX-D05 |
フランツ・シュミット:交響曲第4番ハ長調(1933)* オラトリオ『7つの封印の書』 |
ウィーンSO* ルドルフ・モラルト(指)* ヨハネ…ユリウス・パツァーク(T) 主の声…オットー・ヴィーナー(Bs) 四重唱…ハンニー・シュテフェク(S)/ ヘルタ・テッパー(A)/ エーリヒ・マイクート(T)/ フレデリック・ガスリー(Bs) フランツ・イーレンベルガー(Org) グラーツ大聖堂聖歌隊 ミュンヘンPO アントン・リッペ(指) 録音:1954年9月7日 ウィーン・ムジークフェライン(オーストリア) MONO…* 1962年1月 シュテファニエンザール、グラーツ(オーストリア) STEREO 全て初CD化 |
|
||
| CPO CPO-777216(4CD) CPO-B4 NYCX-10471(4CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
フェルディナント・リース(1784-1838):交響曲全集 ■CD1 交響曲第1番ニ長調 Op.23(1809) 交響曲第2番ハ短調 Op.80(1814) ■CD2 交響曲第5番ニ短調 Op.112(1813) 交響曲第3番変ホ長調 Op.90(1815) ■CD3 交響曲第4番ヘ長調 Op.110(1818) 交響曲第6番ニ長調 Op.146(1822) ■CD4 交響曲第7番イ短調 Op.181(1835) 交響曲第8番変ホ長調 WoO30(1822) |
チューリヒ室内O ハワード・グリフィス(指) 録音:チューリヒ、ノイミュンスター教会、1999年9月(CD1)、2001年8月(CD3)、2002年5月(CD4) チューリヒ、ラジオスタジオ1、1997年9月(CD2) ※仕様変更:CD4がSACDハイブリッドから通常CDに、パッケージがマルチケースになりました。 |
|
||
 Altus ALT-544(2CD) |
ブルックナー:交響曲第9番ニ短調 WAB109 (石原勇太郎による第4楽章 新補筆完成版) |
坂入健司郎(指) タクティカート オーケストラ ライヴ録音:2023年10月11日東京芸術劇場 コンサートホール |
|
||
| BIS BISSA-2721(1SACD) |
ジョン・ピカード(1963-):作品集 交響曲第2番(1985-87) ヴェルレーヌ歌曲集(2019-20rev.2022)(室内管弦楽共演のための版)* 交響曲第6番(2021) |
エ マ・トリング(S)* BBCウェールズ・ナショナルO マーティン・ブラビンズ(指) 録音:2023年3月29~31日ホディノット・ホール(カーディフ、ウェールズ) |
|
||
| BIS BISSA-2757(1SACD) |
モーツァルト:交響曲集 交響曲第34番ハ長調 K.338 メヌエット ハ長調 K.409 交響曲第35番「ハフナー」 交響曲第36番「リンツ」 |
フィルハーモニアO、 マイケル・コリンズ(指) 録音:2023年3月4~6日フェアフィールド・ホールズ(クロイドン) |
|
||
| SILKROAD MUSIC SRM-055SACD (1SACD) |
マーラー:交響曲第1番ニ長調「巨人」 | ヤッシャ・ホーレンシュタイン(指)LSO 録音:1969年/クロイドン(ロンドン) |
|
||
| Chandos CHSA-5335(1SACD) |
アルヴォ・ペルト:深き淵より ショスタコーヴィチ:交響曲第13番 変ロ短調 Op.113「バビ・ヤール」 |
ヨン・ストゥールゴールズ(指)、 BBCフィルハーモニック、 アルベルト・ドーメン(Bs-Br)、 エストニア国立男声cho 録音:2023年3月19日-20日、メディア・シティUK(サルフォード) |
|
||
| Evil Penguin Records EPRC-0061(1CD) XEPRC-0061(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
スクリャービン:交響曲第2番ハ短調 Op.29 | ブリュッセルPO 大野和士(指) 録音:2023年6月5日-7日、スタジオ4、フラジェ(ブリュッセル、ベルギー) |
|
||
| ALPHA ALPHA-696(1CD) |
HAYDN2032Vol.15~王妃~ ハイドン:交響曲第85番変ロ長調 Hob. I:85「王妃」 交響曲第62番ニ長調 Hob. I:62 交響曲第50番ハ長調 Hob. I:50 |
バーゼル室内O(古楽器使用) ジョヴァンニ・アントニーニ(指) 録音:2021年3月16-18日&10月10-15日ドン・ボスコ、バーゼル、スイス |
|
||
| BR KLASSIK BR-900220(1CD) NX-B08 |
ベルリオーズ:幻想交響曲 | バイエルンRSO コリン・デイヴィス(指) 録音:1987年1月15、16日(ライヴ) ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ドイツ) |
|
||
| Myrios Classics MYR-034(1CD) |
ブルックナー:交響曲第9番ニ短調 WAB109(原典版/ノヴァーク校訂) | フランソワ=グザヴィエ・ロト(指) ケルン・ギュルツェニヒO 録音:2022年6月19-21日ケルン・フィルハーモニー(ライヴ) |
|
||
| BIS BISSA-2459(1SACD) |
C.P.E.バッハ:6つのシンフォニア『ハンブルク交響曲』とファンタジア集 シンフォニア第5番ロ短調 Wq.182-5(H.661)[Ⅰ.アレグレット / Ⅱ.ラルゲット / Ⅲ.プレスト]* ファンタジア ハ短調~ソナタ ヘ短調 Wq.63-6(H.75)よりフィナーレ* シンフォニア第3番ハ長調 Wq.182-3(H.659)[Ⅰ.アレグロ・アッサイ* / Ⅱ.アダージョ*# / Ⅲ.アレグレット*] ファンタジア ヘ長調 Wq.59-5(H.279)# シンフォニア第2番変ロ長調 Wq.182-2(H.658)[Ⅰ.アレグロ・ディ・モルト* / Ⅱ.ポコ・アダージョ / Ⅲ.プレスト#] シンフォニア第4番イ長調 Wq.182-4(H.660)[Ⅰ.アレグロ・ディ・モルト / Ⅱ. ラルゴ・エド・イノチェンテメンテ / Ⅲ.アレグロ・アッサイ]# ファンタジア(即興)* シンフォニア第6番ホ長調 Wq.182-6(H.662)[Ⅰ.アレグロ・ディ・モルト / Ⅱ.ポコ・アンダンテ / Ⅲ.アレグロ・スピリトゥオーソ]# ファンタジア ト短調 Wq.117-13(H.225)* シンフォニア第1番ト長調 Wq.182-1(H.657)[Ⅰ.アレグロ・ディ・モルト / Ⅱ.ポコ・アダージョ / Ⅲ.プレスト]# |
マルツィン・シヴィオントキエヴィチ(チェンバロ*、フォルテピアノ#、指揮)
アルテ・デイ・スオナトーリ 録音:2022年8月7~10日/ポーランド放送ルトスワフスキ・スタジオ(ワルシャワ) |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00767(2SACD) 税込定価 2024年3月20日発売 |
シューマン:交響曲全集 交響曲第1番変ロ長調作品38「春」 交響曲第2番ハ長調作品61 交響曲第3番変ホ長調作品97「ライン」 交響曲第4番ニ短調作品120 |
沼尻竜典(指) トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア 録音:2021年3月14日(第2番)、9月4日(第4番)、2022年3月19日(第3番)、7月30日(第1番) 東京・三鷹市芸術文化センター・ライヴ |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00841(1SACD) 税込定価 2024年3月20日発売 |
ハイドン交響曲集Vol.23 交響曲第29番ホ長調Hob.I:29 交響曲第55番変ホ長調Hob.I:55「校長先生」 交響曲第59番イ長調Hob.I:59「火事」 |
飯森範親(指) 日本センチュリーSO 録音:2022年12月9日(第59番)2023年8月4日(第29番、第55番) 大阪・ザ・シンフォニーホール・ライヴ |
|
||
 フォンテック FOCD-9897(1CD) 税込定価 2024年3月6日発売 |
ブルックナー:交響曲第4番変ホ長調「ロマンティック」<1878/80 年稿・ノーヴァク版> | 飯守泰次郎(指) 東京シティ・フィルハーモニックO 録音::2023年4月24日サントリーホール・ライヴ |
|
||
| CPO CPO-555580(1CD) NX-C04 |
エルンスト・アイヒナー(1740-1777):交響曲集 交響曲 ニ長調 Op.11No.3 交響曲 ヘ長調 Op.10No.3 交響曲 ニ長調 Op.1No.1 交響曲 変ロ長調 Op.7No.2 |
テレジアO(古楽器オーケストラ) ヴァンニ・モレット(指) 録音:2022年6月28日-7月1日 |
|
||
| BR KLASSIK BR-900194(2CD) NX-C03 |
マーラー:交響曲第3番ニ短調 | ナタリー・シュトゥッツマン(A) テルツ少年cho バイエルン放送女声cho バイエルンRSO マリス・ヤンソンス(指) 録音:2010年12月8-10日 ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ライヴ) ※既発のマーラー交響曲全集(900719)より分売 |
|
||
| Onyx ONYX-4244(1CD) |
ブルックナー:交響曲第4番変ホ長調 《ロマンティック》 (ノヴァーク版第2稿) | ドミンゴ・インドヤン(指) ロイヤル・リヴァプールPO |
|
||
| Polskie Radio PRCD-2366(1CD) 初紹介旧譜 |
レオポルド・ストコフスキー・イン・ポーランド 1. レオポルド・ストコフスキーのポーランドへの歓迎レポート 2. モニューシュコ:演奏会用序曲「おとぎ話」 【初出音源】 3-8. シマノフスキ:スターバト・マーテル Op.53 【初出音源】 9-12. ルトスワフスキ:交響曲第1番 13. レオポルド・ストコフスキーとヴィトルト・スタンコフスキの対話 |
1. 録音:1959年5月(ワルシャワ) 2. レオポルド・ストコフスキー(指)ポメラニアン・フィルハーモニーSO 録音:1960年5月19日-21日 3-8. レオポルド・ストコフスキー(指)ワルシャワPO&cho、アリナ・ボレホフスカ(S)、クリスティナ・シュチェパニスカ(A)、アンジェイ・ヒオルスキ(Br) 9-12. レオポルド・ストコフスキー(指)ワルシャワPO 録音:1959年5月22日&24日(ワルシャワ) 13.録音:1959年5月(ワルシャワ) |
|
||
| H.M.F HMM-902317(1CD) |
C.P.E.バッハ:交響曲集 ハ長調 H.649, Wq.174* ニ長調 H.651, Wq.176* ホ短調 H.652, Wq.177+ ト長調 H.657, Wq.182-1+ ハ長調 H.659, Wq.182-3+ イ長調 H.660, Wq.182-4* ロ短調 H.661, Wq.182-5+ |
ベルリン古楽アカデミー【コンサートマスター:平崎真弓*、ゲオルク・カッルヴァイト+】 録音:2023年1月、b-sharp |
|
||
| ALPHA ALPHA-1004(4CD) NX-F06 NYCX-10463(4CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
メンデルスゾーン:交響曲全集、劇音楽『夏の夜の夢』(抜粋) 【CD1】 交響曲第1番ハ短調 Op.11 交響曲第5番「宗教改革」 【CD2】 交響曲第2番「讃歌」 【CD3】 交響曲第3番「スコットランド」 交響曲第4番「イタリア」 【CD4】 劇音楽『夏の夜の夢』 Op.61(抜粋) 1. 序曲 2. No.1スケルツォ 3. No.3合唱付きの歌 4. No.5間奏曲 5. No.7夜想曲 6. No.9結婚行進曲 7. No.11道化師たちの踊り 8. フィナーレ |
チェン・レイス、マリー・ヘンリエッテ・ラインホルト(S) パトリック・グラール(T) チューリヒ・ジング・アカデミー カタリナ・コンラディ、ソフィア・ブルゴス(S) チューリヒ・ジング・アカデミー女声cho チューリヒ・トーンハレO パーヴォ・ヤルヴィ(指) 録音:2021年3月 トーンハレ・マーグ …CD 1&3 2021年5月 トーンハレ・マーグ …CD4 2023年1月 チューリヒ・トーンハレ …CD2 |
|
||
| ODRADEK RECORDS ODRCD-443(3CD) ★ |
マーラー:交響曲全集Vol.2 スカルタッツィーニ(b.1971):トルソ 墓碑銘 マーラー:交響曲第2番復活」* スカルタッツィーニ:精霊* マーラー:交響曲第3番ニ短調 |
ジモン・ガウデンツ(指) イェナ・フィルハーモニー イェナ・フィルハーモニー・フィルハーモニーcho イェナ・フィルハーモニー児童cho ヤナ・バウマイスター(S) エフェリン・クラーヘ(C.A) イダ・アルドリアン(C.A) 録音:2019年5月23-26日、2019年11月 5-8日*、イェナ・フォルクスハウス、 |
|
||
| Channel Classics CCSSA-46524(1SACD) NX-C07 |
ベートーヴェン:交響曲第3番変ホ長調 Op.55「英雄」 「コリオラン」序曲 Op.62 |
ブダペスト祝祭O イヴァン・フィッシャー(指) 録音:2023年8月ルンバッハ・ストリート・シナゴーグ、ブダペスト、ハンガリー |
|
||
| TOCCATA TOCC-0661(1CD) NX-B06 |
フリードリヒ・ブルク(1937-):管弦楽作品集
第5集 交響曲第13番「画家カジミール・マレーヴィチ[1878-1935]」(2014) 交響曲第14番「叫び」 |
リトアニア国立SO イマンツ・レスニス(指) 録音:2014年6月、2015年6月 全て世界初録音 |
|
||
| Capriccio C-8091(1CD) NX-B10 NYCX-10464(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ブルックナー:交響曲第7番ホ長調(ホークショー版) | ウィーンRSO マルクス・ポシュナー(指) 」録音:2023年12月5-8日ウィーン、放送文化会館及びコンツェルトハウス大ホール |
|
||
| ANALEKTA AN-28888(8CD) NX-E10 |
Living Art ~クララ・シューマン、シューマン、ヨハネス・ブラームス:
作品集 【CD1】 1-4. シューマン:交響曲 第1番変ロ長調 Op.38「春」 5. ガブリエラ・モンテーロ(1970-):即興曲 第1番 6-8. クララ・シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 Op.7 【CD2】 1-4. モンテーロ:即興曲 第2番-第5番 5-9. ブラームス:交響曲 第1番ハ短調 Op.68 【CD3】 1-4. シューマン:交響曲第2番ハ長調 Op. 61 5-11. C. シューマン:歌曲集 5. 彼はやってきた Op.12-1 6. 美しさゆえに愛するのなら Op.12-2 7. なぜ他の人たちに尋ねようとするの Op. 12-3 8. 私は暗い夢の中に立っていた Op.13-1 9. 彼らは愛し合っていた Op.13-2 10. 愛の魔法 Op.13-3 11. 私はあなたの瞳に Op.13-5 【CD4】 1-4. ブラームス:交響曲第2番ニ長調 Op. 73 5-9. C. シューマン:歌曲集 5.月は静かに昇った Op.13-4 6. 無言のハスの花 Op.13-6 7. 別れの時に 8. 私の星 9. おやすみなさいとあなたに言う 【CD5】 1-5. シューマン:交響曲第3番変ホ長調 「ライン」 Op.97 6-8. C. シューマン:歌曲集 6. 海辺にて 7. ある明るい朝に Op.23-2 8. ローレライ 9-11. C. シューマン:4つの束の間の小品 Op.15 (第4曲はピアノ・ソナタの第3楽章として収録 12-15. C. シューマン:ピアノ・ソナタ ト短調 【CD6】 1-4. ブラームス:交響曲第3番ヘ長調 Op. 90 5-8. C. シューマン:ピアノ三重奏曲 ト短調 Op.17 【CD7】 1-4. シューマン:交響曲第4番ニ短調 Op. 120 5-7. C. シューマン:3つのロマンス- ヴァイオリンとピアノのための Op.22 8-10. C. シューマン:3つのロマンス- ピアノのための Op.11 11. ロマンス ロ短調 【CD8】 1-4. ブラームス:交響曲第4番ホ短調 Op. 98 5-7. C. シューマン:ゼバスティアン・バッハの主題による3つのフーガ 8-9. C. シューマン:前奏曲とフーガ 嬰へ短調 10-15. C. シューマン:3つの前奏曲とフーガ Op.16 16. スチュワート・グッドイヤー(1978-):クララ・シューマンの主題による即興 |
ナショナル・アーツ・センターO アレクサンダー・シェリー(指) …CD11-4、6-8/CD 25-9/CD31-4/CD41-4/CD51-5/CD6 1-4/CD71-4/CD81-4 ガブリエラ・モンテーロ(P) …CD15-8/CD 21-4/CD512-15 アドリアンヌ・ピエチョンカ(S) …CD 35-11/CD45-9/CD56-8 リズ・アップチャーチ(P) …CD35-11/CD 45-9/CD56-8 スチュワート・グッドイヤー(P) …CD5 9-11/CD65-8/CD78-11/CD85-16 川崎洋介(Vn) …CD65-8/CD75-7 レイチェル・マーサー(Vc) …CD65-8 アンジェラ・ヒューイット(P) …CD 75-7 録音:2018-2023年 |
|
||
 SOMM ARIADNE-5025(2CD) NX-D05 |
ブルックナー:交響曲ヘ短調、交響曲第1番他(ブルックナー・フロム・アーカイヴ第1巻) アントン・ブルックナー ■CD1 (1)交響曲 ヘ短調 WAB99(1863)* (2) 行進曲 ニ短調 WAB96(1862)** (3) 管弦楽のための3つの小品(1862)** (4) 詩篇112WAB35(1863) ■CD2 (1) 序曲 ト短調 WAB98(1863年改訂版)* (2) 交響曲第1番ハ短調 WAB101(リンツ稿、ノーヴァク版)* (3)弦楽四重奏曲 WAB111(1862)* |
■CD1 (1)クルト・ヴェス(指) リンツ・ブルックナーO (2)(3)ハンス・ヴァイスバッハ(指) ウィーンSO (4) ヘンリー・スヴォボダ(指) ウィーンSO、ウィーン・アカデミー室内合唱団 ■CD2 (1) ディーン・ディクソン(指) ケルンWDRSO (2)オイゲン・ヨッフム(指) バイエルンRSO (3)ケッケルト四重奏団 録音/音源 ■CD1 (1)1974年6月11日/エアチェック (2)(3)1944年5月9日/Family Records, SFLP-541 (4)1950年/Westminster LP, XWN18075 ■CD2 (1)1959年/エアチェック (2)1959年1月1日/エアチェック (3)1951年5月9日/エアチェック 交響曲 へ短調のみステレオ *初出、**初CD化 |
|
||
| Challenge Classics CC-72958(1CD) |
シューマン:交響曲第1&2番 交響曲第1番変ロ長調 Op.38 |
ヤン・ヴィレム・デ・フリエンド(指) スタヴァンゲルSO 録音:2023年6月12-15日ノルウェー、スタヴァンゲル・コンサートホール |
|
||
| Melodiya x Obsession SMELCD-1002695(2CD) 初回生産限定 |
チャイコフスキー:後期三大交響曲集 ■CD1 1-4. 交響曲第4番ヘ短調 Op.36 5-6. 交響曲第5番ホ短調 Op.64第1楽章、第2楽章 ■CD2 1-2. 交響曲第5番ホ短調 Op.64第3楽章、第4楽章 3-6. 交響曲第6番ロ短調 Op.74「悲愴」 |
モスクワRSO ウラディーミル・フェドセーエフ(指) 録音:CD1/1-4,1984年、モスクワ放送大ホール(ADD/ステレオ) CD1/5-6, CD2,1981年、モスクワ放送大ホール(ADD/ステレオ) |
|
||
| GENUIN GEN-24853(2CD) |
ドヴォルザーク:ドヴォルザーク:交響詩「水の精」 Op.107 交響曲第3番変ホ長調 Op.10 交響詩「真昼の魔女」 Op.108 交響曲第9番ホ短調 Op.95「新世界より」 |
南ヴェストファーレン・フィルハーモニー、 ナビル・シェハタ(指) 録音:2021年5月18日-20日、ベッツドルフ市立ホール(ドイツ) |
|
||
| Chandos CHSA-5312(1SACD) |
ニールセン:パンとシランクス Op.49FS87(1917-18)、 フルート協奏曲 FS 119(1926)* 交響曲第3番Op.27FS60「広がりの交響曲」(1910-11)** |
エドワード・ガードナー(指)ベルゲンPO、 アダム・ウォーカー(Fl)*、 リナ・ジョンソン(S)**、 イングヴ・ソーバルグ(Br) 録音:2022年9月15日〔交響曲、ライヴ録音〕、2023年6月12日-16日〔その他の作品〕、グリーグホール(ベルゲン、ノルウェー) |
|
||
| Glossa GCD-921135(9CD) |
フランス・ブリュッヘン、モーツァルトとの人生
~グロッサ・コンプリート・レコーディング ■Disc1/2 交響曲第39番変ホ長調 K.543 交響曲第40番ト短調 K.550 交響曲第41番ハ長調 K.551「ジュピター」 ■Disc3 クラリネット協奏曲イ長調 K.622 歌劇「皇帝ティートの慈悲」K.621より 序曲、アリア「私は行くが、君は平和に」、アリア「夢に見し花嫁姿」 2つのクラリネットと3つのバセット・ホルンのための「アダージョ」変ロ長調 K.411 ■Disc4 「ホルンのための音楽」 ホルンのための12の二重奏曲 K.487より第8番アレグロ ホルン五重奏曲変ホ長調 K.407 ホルンのための12の二重奏曲 K.487より第7番アダージョ ホルンのための12の二重奏曲 K.487より第2番メヌエット(アレグレット) 歌劇「ポントの王ミトリダーテ」K.87よりアリア「あなたから遠く離れて」 ホルンのための12の二重奏曲 K.487より第3番アンダンテ ホルンのための12の二重奏曲 K.487より第12番アレグロ ホルン協奏曲第3番変ホ長調 K.447* ホルンのための12の二重奏曲 K.487より第9番メヌエット ホルンのための12の二重奏曲 K.487より第5番ラルゲット 音楽の冗談 K.522 ホルンのための12の二重奏曲 K.487より第4番ポロネーズ ■Disc5 オーボエ協奏曲ハ長調 K.314 オーボエ四重奏曲ヘ長調 K.370 2本のヴァイオリン、ヴィオラ、コントラバス、オーボエと2本のホルンのためのディヴェルティメント K.251 アリア「あなたに明かしたい、おお、神よ」K.418 ■Disc6 ヴァイオリン協奏曲第1番変ロ長調 K.207 ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調 K.218 ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調 K.219「トルコ風」 ■Disc7 ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲変ホ長調 K.364 ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調 K.216 ヴァイオリン協奏曲第2番ニ長調 K.211 ■Disc8 「アロイジア・ウェーバーのためのアリア集」 いえ、いえ、あなたにはできません K.419 アルカンドロよ、わたしは告白する ― どこから来るのかわたしにはわからない K.294 わたしはあなたに明かしたい、ああ! K.418 ああ、もし天に、恵み深い星たちよ K.538 わが憧れの希望よ-あなたにはどれほどの苦しみかわかるまい K.416 テッサーリアの民よ-わたしは求めはしません、永遠の神々よ K.316(K.300b) 私の感謝をお受け取り下さい、親切な後援者の皆様 K.383 ■Disc9 フリーメイソンのための葬送音楽 ハ短調 K.477 2つのクラリネットと3つのバセット・ホルンのためのアダージョ 変ロ長調 K.411 レクイエム ニ短調 K.626 |
■Disc1/2 18世紀オーケストラ フランス・ブリュッヘン(指) 録音:2010年3月、デ・ドゥーレン(ロッテルダム、オランダ) ステレオ(デジタル、ライヴ録音) ■Disc3 エリック・ホープリッチ(クラリネット&バセット・ホルン) ジョイス・ディドナート(Ms) トニ・サラール=ヴェルドゥ(クラリネット/K.411) ギィ・ファン・ワース(バセット・ホルン/K.411) アネッテ・トーマス(バセット・ホルン/K.411) ロレンツォ・コッポラ(バセット・ホルン/K.411) 18世紀オーケストラ フランス・ブリュッヘン(指) 録音:2001年2月(K.622)、1986年6月(K.621/序曲)、2001年11月(K.621/アリア)、2001年12月(K.411)、オランダ ステレオ(デジタル) トゥーニス・ファン・デァ・ズヴァールト(ナチュラルホルン) エルヴィン・ヴィーリンガ(ナチュラルホルン) マルク・デストリュベ(Vn) スタース・スヴィールストラ(Vn&ヴィオラ) エミリオ・モレーノ(Va) アルベルト・ブリュッヘン(Vc) ロベルト・フラネンベルク(Cb) クラロン・マクファデン(ソプラノ/K.87) 18世紀オーケストラ(K.447) フランス・ブリュッヘン(指揮/K.447) 録音:2006年6月、2007年11月、2008年7月、イタリア、スペイン、オランダ ステレオ(デジタル、ライヴ録音) ■Disc5 フランク・デ・ブライネ(Ob) 18世紀オーケストラ ケネス・モンゴメリー 録音:2015年1月&10月、アムステルダム ステレオ(デジタル) ■Disc6 トーマス・ツェートマイヤー(Vn&指揮) 18世紀オーケストラ 録音:2000年9月、ユトレヒト、オランダ(K.218&K.219)/2002年6月、クリチバ、ブラジル(K.207) ステレオ(デジタル、ライヴ録音) ■Disc7 トーマス・ツェートマイヤー(Vn) ルース・キリウス(ヴィオラ/K.364) 18世紀オーケストラ フランス・ブリュッヘン(指) 録音:2005年10月、ロッテルダム(K.364)、ユトレヒト(K.211&K.216) ステレオ(デジタル、ライヴ録音) ■Disc8 シンディア・ジーデン(S) 18世紀オーケストラ フランス・ブリュッヘン(指) 録音:1998年5月&9月、フレーデンブルフ音楽センター(ユトレヒト、オランダ) ステレオ(デジタル、ライヴ録音) ■Disc9 モーナ・ユルスルー(S) ヴィルケ・テ・ブルンメルストルテ(A) ゼーハー・ヴァンデルステイネ(T) イェレ・ドレイエル(Bs) ユーヘイン・リヴェン・ダベラルド(グレゴリオ聖歌指揮) オランダ室内cho 18世紀オーケストラ フランス・ブリュッヘン(指) 録音:1998年3月20日、東京芸術劇場 ステレオ(デジタル、ライヴ録音) |
|
||
| Pentatone PTC-5186989(2SACD) |
シューマン:交響曲全集 (1)交響曲第1番変ロ長調 Op.38「春」(1841) (2)交響曲第2番ハ長調 Op.61(1845-46) (3)交響曲第3番変ホ長調 Op.97「ライン」(1850) (4)交響曲第4番ニ短調 Op.120(1851年版/1841年作曲・1851年改訂) |
ドレスデンPO マレク・ヤノフスキ(指) コンサートマスター:ハンデ・コデン(ゲスト・コンサートマスター)(1)、 ハイケ・ヤニッケ(2)、 ヴォルフガング・ヘントリッヒ(3)(4) 録音:(2)(3)2021年5月、(4)2021年8月、(1)2023年5月&6月/ドレスデン、クルトゥーアパラスト(文化宮殿) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2313(1CD) |
マーラー:交響曲第9番ニ長調 | ブルーノ・ワルター(指)コロンビアSO 録音:1961年1月16、18、28、30、2月2、6日/ハリウッド、アメリカン・リージョン・ホール 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:ステレオ(録音セッション) |
|
||
| H.M.F HMX-2904102(2CD) ★ |
ロト&レ・シエクルのベルリオーズ ■CD1 (1)幻想交響曲Op.14 (2)序曲「宗教裁判官 ■CD2 (1)イタリアのハロルドOp.16 (2)歌曲集「夏の夜」Op.7 |
フランソワ=グザヴィエ・ロト(指) レ・シエクル ■CD1(HMM902644) 録音:2019年7月16、17日/アルフォールヴィル ■CD2(HMM902634) タベア・ツィンマーマン(Va/(1))、 ステファヌ・ドゥグー(Br/(2)) 録音:2018年3月2/3日フィルハーモニー・ド・パリ(1)、8月15/16日アルフォールヴィル、イル=ド=フランス国立オーケストラホール(2) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2314(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 | エミリア・クンダリ(S) ネル・ランキン(Ms) アルバート・ダ・コスタ(T) ウィリアム・ワイルダーマン(Br) ウェストミンスター交響cho ブルーノ・ワルター(指)、コロンビアSO 録音:1959年1月19、21、26、29、31日/アメリカン・リージョン・ホール(カリフォルニア)、1959年4月6、15日/セント・ジョージ・ホテル、ボールルーム(ニューヨーク) 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) |
|
||
 オクタヴィア OVCL-00772(2SACD) 税込定価 2024年2月21日発売 |
ブラームス:交響曲全集(全4曲) | 井上道義(指) 第1番:京都市SO 録音:2022年5月5日石川県立音楽堂〈いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭〉 第2番:新日本フィルハーモニーSO 録音:2021年3月6日愛知・東海市芸術劇場 第3番:広島SO 録音:2021年7月9日広島文化学園HBGホール 第4番:広島SO 録音:2021年8月1日呉信用金庫ホール(呉市文化ホール) 全てライヴ |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00838(1SACD) 税込定価 2024年2月21日発売 |
チャイコフスキー:交響曲第4番ニ長調作品29 | ジョナサン・ノット(指)東京SO 録音:2023年7月22日ミューザ川崎シンフォニーホール・ライヴ |
|
||
| Polskie Radio PRCD-22972299(3CD) 初紹介旧譜 |
ブラームス:交響曲全集(全4曲) | イェジ・セムコフ(指)、 ポーランド国立RSO 録音:2008年2月3日(第1番)、3月29日(第2番)、10月11日(第3番)、2009年5月21日(第4番)、NOSPRコンサート・ホール(カトヴィツェ、ポーランド) |
|
||
| Forgotten Records fr-2178(2CDR) |
ジョルジュ・ジョルジェスク/ベートーヴェン:交響曲集 交響曲第5番「運命」 交響曲第6番「田園」 交響曲第7番/交響曲第8番 序曲「レオノーレ」第3番 |
ジョルジュ・ジョルジェスク(指) ジョルジュ・エネスコPO 録音:1961年(ステレオ) ※音源:ELECTRECORD ECE-080他 |
 ICA CLASSICS ICAC-5177(2CD) NX-D03 |
A・ヤンソンス/チャイコフスキー&プロコフィエフ他 チャイコフスキー: (1)『眠れる森の美女』~序章: リラの精/ パ・ダクション: ローズ・アダージョ/パノラマ: アンダンティーノ/ワルツ (2)フランチェスカ・ダ・リミニ Op. 32 (3)プロコフィエフ:古典 交響曲* (4)チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調 Op. 64# |
レニングラードPO ソヴィエト国立SO* アルヴィド・ヤンソンス(指) 録音:1971年9月13日 ロイヤル・アルバート・ホール 1971年9月17日 ロイヤル・フェスティヴァル・ホール# 1983年11月17日 アルスター・ホール* 全てステレオ |
|
||
| BR KLASSIK BR-900217(1CD) NX-B08 |
マーラー:交響曲第6番「悲劇的」 | サイモン・ラトル(指) バイエルンRSO 録音:2023年9月28,29日(ライヴ) イザールフィルハーモニー・イン・ガスタイクHP8、ミュンヘン(ドイツ) |
|
||
| BR KLASSIK BR-900214(1CD) NX-B08 |
ショスタコーヴィチ:交響曲第8番ハ短調 Op.65 | ベルナルト・ハイティンク(指) バイエルンRSO 録音:2006年9月23日(ライヴ) フィルハーモニー・イン・ガスタイク、ミュンヘン(ドイツ) |
|
||
| Capriccio C-8088(1CD) NX-B10 NYCX-10454(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ブルックナー:交響曲第3番 ニ短調(第3稿 ノーヴァク版) | リンツ・ブルックナーO マルクス・ポシュナー(指) 録音:2023年2月2-3日、7-8日リンツ、ムジークテアター・リハーサルホール |
|
||
| Edition HST HST-122(1CD) 税込定価 |
J.B.ヴァンハル(1739-1813):交響曲集第28巻 交響曲ハ長調Bryan C14 交響曲へ長調Bryan F8 カッサシオン へ長調Weinmann III:F3 ~ウインナ・ヴィオロン(Cb)とヴァイオリン、ヴィオラとホルンのための |
ハイドン・シンフォ二エッタ トウキョウ リーダー;松井利世子(Vn)、ほか 録音:2023年6月、東京 文京シビック小ホール・ライヴ |
|
||
| Altus ALTL-018(2CD) |
東京ユヴェントス・フィルハーモニー第23回定期演奏会
パヌフニク:『平和への行列』 ゾンドイン・ハンガル(1948-1996):交響詩『海燕』~ショスタコーヴィチの思い出に捧げる詩?(日本初演) オグタイ・ズルファガロフ(1929-2016):ホリデー序曲(日本初演) モソロフ(1900-1973):交響的エピソード『鉄工場』 ショスタコーヴィチ:バレエ音楽『ボルト』より 「荷馬車引きの踊り」(アンコール) ショスタコーヴィチ:交響曲第7番ハ長調『レニングラード』 |
坂入健司郎(指) 東京ユヴェントス・フィルハーモニー/オーケストラ・リベルタとの合同演奏 録音:2023年1月7日/ミューザ川崎シンフォニーホール [東京ユヴェントス・フィルハーモニー創立15周年記念シリーズ] |
|
||
| Altus ALTB-540(4CD) 限定生産 |
アーベントロート集成・絶倒編 【TALT056】 (1)ハイドン:交響曲第103番『太鼓連打』 (2)モーツァルト:交響曲第39番変ホ長調 (3)メンデルスゾーン:『夏の夜の夢』序曲 (4)メンデルスゾーン:『フィンガルの洞窟』序曲 R.シュトラウス: (1)『ドン・ファン』/(2)『死と変容』 (3)『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら』 【TALT064】 モーツァルト: (1)セレナーデ第6番ニ長調『セレナータ・ノットゥルナ』 K.239 (2)ピアノ協奏曲第26番ニ長調『戴冠式』 【TALT069】 (1)カリンニコフ:交響曲第1番ト短調 (2)J.シュトラウス2世:『皇帝円舞曲』 、『美しく青きドナウ』 、『くるまば草』 序曲、『ジプシー男爵』 序曲 |
ヘルマン・アーベントロート(指 ) 【TALT056】 ライプツィヒ放送O 録音:(1)1951年10月29日、(2)1953年2月9日、(3)1950年8月13日、(4)1949年9月18日 【TALT063】 ライプツィヒ放送O 録音:(1)1952年2月11日、(2)1949年10月24日、(3)1950年11月14日 【TALT064】 ステファン・アスケナーゼ(P(2)) シュターツカペレ・ドレスデン 録音:1956年2月3日 【TALT069】 ライプツィヒRSO 録音:(1)1949年11月16日、(2)1950年11月18日 |
|
||
| Altus ALTB-541(6CD) 限定生産 |
アンチェル傑作ライヴ集・ステレオ有り 【TALT044】 (1)ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 (2)ドヴォルザーク:交響曲第8番 【TALT045/6】 [CD1] (1)ハイドン:交響曲第92番『オックスフォード』 (2)フランク:交響曲 ニ短調 [CD2] (3)ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 (4)プロコフィエフ:古典交響曲 (5)ハイドン:交響曲第104番『ロンドン』 (6)アンチェルのインタビュー(英語) 【TALT057/8】 [CD1] (1)モーツァルト:アイネ・クライネ・ナハトムジーク (2)メンデルスゾーン:交響曲第5番 『宗教改革』 (3)シューマン:交響曲第4番ニ短調 [CD2] (4)ベートーヴェン:交響曲第6番 『田園』 (5)ベートーヴェン:交響曲第8番ヘ長調 【TALT061】 マーラー:交響曲第5番嬰ハ短調 |
カレル・アンチェル(指 ) 【TALT044】 ヘルマン・クレバース((1)ヴァイオリン) アムステルダム・コンセルトヘボウO 録音:1970年1月28日(ステレオ、ライヴ録音) 【TALT045/6】 [CD1] ダニエル・ワイエンベルク((3)ピアノ) アムステルダム・コンセルトヘボウO(1)-(4) オランダ放送PO(5) 録音:(1)-(3)1970年1月21日、(4)1969年2月23日、(5)1970年7月6日(すべてステレオ、ライヴ録音) (6)1968年7月/プラハ(Document CBC) 【TALT057/8】 トロントSO ライヴ録音:(1)1968年11月10日(モノラル)、(2)1969年12月16・17日(モノラル)、(3)1969年12月9・10日(モノラル)、 (4)972年1月19日(ステレオ)、(5)1968年11月10日(モノラル) 【TALT061】 トロントSO ライヴ録音:1969年11月4日/CBC(モノラル) |
|
||
| EUROARTS 20-50443(Bluray) |
ベルリン・フィル2000年東京ライヴ ヒラリー・ハーン&ヤンソンス ウェーバー:「オベロン」序曲 ショスタコーヴィチ:ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 Op.77 バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第1番 BWV1001より プレスト(アンコール) ドヴォルザーク:交響曲第8番ト長調 Op.88、 スラヴ舞曲 ハ長調 Op.72の7 |
ヒラリー・ハーン(Vn) マリス・ヤンソンス(指)BPO 収録:2000年11月26日 サントリー・ホール、東京(ライヴ) 画面:16:9,1080/60i Full HD 音声:PCMステレオ, DTS-HS MA5.1 リージョン:All、99分 |
|
||
| GENUIN GEN-24864(1CD) |
モーツァルト:交響曲集第3集 交響曲第9番 ハ長調 K.73/75a 交響曲第14番イ長調 K.114 交響曲第20番 ニ長調 K.133 交響曲第24番変ロ長調 K.182/dA |
ヨハネス・クルンプ(指)、 エッセン・フォルクヴァング室内O |
|
||
| BIS BISSA-9062 (17SACD+4DVD) ★ |
アラン・ペッテション-コンプリート・エディション ■Disc1(77'54) (1)交響曲第1番(1951)(クリスチャン・リンドベルイ校訂版) (2)交響曲第2番(1952/3) ■Disc2(70'52) (3)交響曲第3番(1954-55) (4)交響曲第15番(1978) ■Disc3(65'13) (5)交響曲第4番(1959) (6)交響曲第16番(1979) (6)ユルゲン・ペッタション(アルト・サクソフォン) ■Disc4(68'53) (7)交響曲第5番(1960-62) (8)ヴィオラ協奏曲(1979)【独奏パートの補完:エレン・ニスベト】 ■Disc5(80'53) (9)交響曲第6番(1963-66) (10)弦楽のための協奏曲第1番(1949-50) ■Disc6(71'27) (11)交響曲第7番(1966-67) (12)交響曲第11番(1973) ■Disc7(71'31) (13)交響曲第8番(1968-69) (14)交響曲第10番(1972) ■Disc8(70'11) (15)交響曲第9番(1970) ■Disc9(79'45) (16)交響曲第12番「広場の死者」(1973-74)(詩:パブロ・ネルーダ) (17)8つの裸足の歌(1943-45)(オーケストレーション:アンタル・ドラティ) ■Disc10(66'46) (18)交響曲第13番(1976) ■Disc11(79'56) (19)交響曲第14番(1978) (20)弦楽のための協奏曲第2番(1956) ■Disc12(61'06) (21)ヴァイオリン協奏曲第2番(1977改訂稿) (22)交響曲第17番(1980)(断章)(1980)【マルクス・ブリルカ&クリスチャン・リンドベルイによる補完】 ■Disc13(54'00) (23)弦楽のための協奏曲第3番(1956-57) ■Disc14(59'30) (24)ヴァイオリンと弦楽四重奏のための協奏曲(1949) (25)2つの悲歌~ヴァイオリンとピアノための(1934) (26)アンダンテ・エスプレシーヴォ~ヴァイオリンとピアノのための(1938) (27)ロマンツァ~ヴァイオリンとピアノのための(1942) (28)ラメント~ピアノのための(1945) (29)4つの即興曲~弦楽三重奏のための(1936) ■Disc15(87'10) (30)2つのヴァイオリンのための7つのソナタ(1951) (31)フーガ ホ長調~オーボエ、クラリネット、ファゴットのための(1948) (32)交響的楽章(1973) (33)幻想曲~ヴィオラ独奏のための(1936) ■Disc16(50'33) (34)「人の声」~独唱者、混声合唱と弦楽オーケストラのための(1976) ■Disc17(71'35) (35)6つの歌~中声とピアノのための(1935) (36)裸足の歌(1943-45) ●特典DVD ■Disc1 「Allan Pettersson - The First Symphony(アラン・ペッテション-最初の交響曲)」 アラン・ペッテションの交響曲第1番について、作曲者の手稿から2010年の初演とその後の録音に至るまでの道のりを記録した1時間のドキュメンタリー ■Disc2 「The Voice of Man(人間の声)」 スウェーデン・テレビ放送1973~78年制作のペッテションについてのドキュメンタリー ■Disc3 「Who the hell is Allan Pettersson?(アラン・ペッテション、お前は一体何者?)」 1974年制作のペッテションのドキュメンタリー ■Disc4 「The Song of Life(いのちの歌)」 スウェーデン・テレビ放送1987年制作。ペッテションについてのドキュメンタリー |
■Disc1(77'54) (1)(2)クリスチャン・リンドベルイ(指)ノールショピングSO 録音:2010年5月~6月/ルイ・ド・イェール・コンサートホール、ノールショピング ■Disc2(70'52) (3)(4)レイフ・セーゲルスタム(指)ノールショッピングSO 録音:(3)1993年5月29日、(4)1994年3月24&25日/リンシェーピング・コンサートホール ■Disc3(65'13) (5)(6) (6)ユルゲン・ペッタション(アルト・サクソフォン) クリスチャン・リンドベルイ(指)ノールショピングSO 録音:2013年1月/ルイ・ド・イェール・コンサートホール、ノールショピング ■Disc4(68'53) (8)エレン・ニスベト(Va) クリスチャン・リンドベルイ(指)ノールショピングSO 録音:(7)2017年6月、(8)2020年1月13-17日/ルイ・ド・イェール・コンサートホール、ノールショピング ■Disc5(80'53) (9)クリスチャン・リンドベルイ(指)ノールショピングSO (10)クリスチャン・リンドベルイ(指)ノルディック室内O 録音:(9)2012年1月、(10)2007年3月/ルイ・ド・イェール・コンサートホール、ノールショピング ■Disc6(71'27) レイフ・セーゲルスタム(指)ノールショッピングSO 録音:(11)1992年4月29&30日、(12)1992年12月17日/リンシェーピング・コンサートホール ■Disc7(71'31) レイフ・セーゲルスタム(指)ノールショッピングSO 録音:1997年3月/ルイ・ド・イェール・コンサートホール、ノールショピング ■Disc8(70'11) (15)クリスチャン・リンドベルイ(指)ノールショピングSO 録音:2013年1月/ルイ・ド・イェール・コンサートホール、ノールショピング ■Disc9(79'45) (16)エリク・エリクソン室内合唱団、スウェーデン放送合唱団、クリスチャン・リンドベルイ(指)ノールショピングSO (17)アンデシュ・ラッション(Br)、クリスチャン・リンドベルイ(指)ノルディック室内O 録音:(16)2019年3月&2020年1月、(17)2007年3月/ルイ・ド・イェール・コンサートホール、ノールショピング ■Disc10(66'46) (18)クリスチャン・リンドベルイ(指)ノールショピングSO 録音:2015年1月/ルイ・ド・イェール・コンサートホール、ノールショピング ■Disc11(79'56) (19)クリスチャン・リンドベルイ(指)ノールショピングSO (20)クリスチャン・リンドベルイ(指)ノルディック室内O 録音:(19)2016年1月、(20)2007年3月/ルイ・ド・イェール・コンサートホール、ノールショピング ■Disc12(61'06) (21)ウルフ・ヴァリーン(Vn) クリスチャン・リンドベルイ(指)ノールショピングSO 録音:(21)2017年1月、(22)2018年1月/ルイ・ド・イェール・コンサートホール、ノールショピング ■Disc13(54'00) クリスチャン・リンドベルイ(指)ノルディック室内O 録音:2006年5月/ヘグドーンゲル教会、ハルノサンド ■Disc14(59'30) (24)ウルフ・ヴァリーン(Vn)、SQ【スーイエ・パク(Vn1)、ダニエル・ヴラシ・ルカヒ(Vn2)、ゲルマン・チャクロフ(Va)、アレクサンダー・ウォルハイム(Vc)】 (25)-(27)ウルフ・ヴァリーン(Vn)、トーマス・ホッペ(P) (28)トーマス・ホッペ(P) (29)ウルフ・ヴァリーン(Vn)、ゲルマン・チャクロフ(Va)、アレクサンダー・ウォルハイム(Vc) 録音:(25)-(27)2022年9月5&6日、(24)(28)(29)2022年11月28日~12月2日/聖ニコデモ教会、ノイケルン、ベルリン ■Disc15(87'10) (30)デュオ・ジュラン(2つのヴァイオリン)、レンナルト・ヴァリーン(P) (31)ノールショピングSOのメンバー【トマス・ブーディーン(Ob)、アルバロ・パストル・ヒメネス(Cl)、リヌス・ビョーンスタム(Fg)】 (32)クリスチャン・リンドベルイ(指)ノールショピングSO (33)エレン・ニスベト(Va) 録音:(30)1999年7月&8月/ダンデリード・グラマー学校 (31)2023年5月19日、(32)2023年1月13日/ルイ・ド・イェール・コンサートホール、ノールショピング (33)2020年5月29日/聖ペテロ教会、ダンデリード ■Disc16(50'33) マリアンネ・メルネス(S)、マルゴット・ローディン(Ms)、スヴェン=エーリク・アレクサンデション(T)、エルランド・ハーゲゴード(Br) スティーグ・ヴェステルベリ(指)スウェーデン放送合唱団、スウェーデンRSO 録音:1976年3月22日&1976年5月25日/王立スウェーデン音楽アカデミー、ストックホルム ■Disc17(71'35) ペーテル・マッテイ(Br)、ベンクト=オーケ・ルンディン(P) 録音:2021年3月11-14日/オレブルー・コンサートホール、オレブルー ●特典DVD ■Disc1 フォーマット:NTSC16:9、Dolby Digital、Stereo、Region code:0(Worldwide) 言語:スウェーデン語、字幕:英独仏 ■Disc2 フォーマット:NTSC16:9&4:3pillar box、Dolby Digital、Stereo Region code:0 (Worldwide) 言語:スウェーデン語、字幕:英 ■Disc3 フォーマット:NTSC16:9&4:3pillar box、Dolby Digital、Stereo Region code:0 (Worldwide) 言語:スウェーデン語、字幕:英 ■Disc4 フォーマット:NTSC16 |
|
||
| CLAVES 50-3104(2CD) |
ポシュナー/チャイコフスキー:2つの交響曲 (1)交響曲第5番ホ短調 Op.64 (2)交響曲第6番ロ短調 Op.74『悲愴』 |
スイス・イタリアーナO、 マルクス・ポシュナー(指) 録音:(1)2021年8月、(2)2022年10月 オーディトリオ・ステリオ・モロ・スタジオ( RSI )、ルガーノ |
|
||
| GRAND SLAM GS-2308(1CD) |
(1)ハイドン:交響曲第94番ト長調 「驚愕」 (2)チャイコフスキー:交響曲第4番ヘ短調 Op.36 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)、VPO 録音:(1)1951年1月11、12、17日、(2)1951年1月4、8、9、10日/ウィーン、ムジークフェライン 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(録音セッション) |
|
||
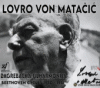 PROMINENT CLASSICS 2506-5618(5CD) |
マタチッチ最後のベートーヴェン:交響曲全曲演奏会 交響曲第1番ハ長調作品21 交響曲第3番「英雄」 交響曲第2番ニ長調作品36 交響曲第6番ヘ長調「田園」 交響曲第4番変ロ長調作品60 交響曲第5番「運命」 交響曲第8番ヘ長調作品93 交響曲第7番イ長調作品92 交響曲第9番「合唱」 |
ロヴロ・フォン・マタチッチ(指) ザグレブPO ラドミラ・スミッリャニチ(S)) マリヤ・クラシッチ(Ms) イーゴル・フィリポヴィチ(T) ネヴェン・ベレマリチ(Bs) ザグレブ・フィルcho 録音:(第1、2番)1980年12月19日 (第3、4番)1981年1月16日 (第5、6番)1981年2月27日 (第7,8番)1981年5月22日 (第9番)1981年6月5日 ヴァトロスラフ・リシンスキ・コンサートホール(ステレオ・ライヴ) HRTクロアチア放送による録音 *当時クロアチアはユーゴスラヴィアでした。 |
|
||
| Champs Hill Records CHRCD-167(1CD) |
マーラー:大地の歌(マーラーの自筆譜によるピアノ伴奏版) | クラウディア・ハックル(C.A)、 ニッキー・スペンス(T)、 ジャスティン・ブラウン(P) 録音:2021年8月9日-12日、チャンプス・ヒル・ミュージック・ルーム(イギリス) |
|
||
| NEOS NEOS-12315(1CD) |
グロリア・コーツ:室内オーケストラのための作品集 交響曲第1番「開放弦による音楽」(1972/1973) Wir tonen allein(ソプラノ、ティンパニ、パーカッションと弦楽オーケストラのための)(1988) Cette blanche agonie(ソプラノ、イングリッシュ・ホルン/オーボエ、ティンパニ、パーカッションと弦楽オーケストラのための)(1988) 交響曲第16番「時間の凍結」(1993) |
ミュンヘン室内O、 イラン・ヴォルコフ(指)、 ジェシカ・ナイルズ(S)、 トビアス・フォーゲルマン(イングリッシュ・ホルン、オーボエ) 録音:2022年10月21日-23日、ウトーピア・ホール(ミュンヘン) |
|
||
| Diapason DIAPCF-029(10CD) |
シューベルト:交響曲全集、合唱作品集、歌曲集 (1)交響曲第1番ニ長調 D82 (2)交響曲第2番変ロ長調 D125 (3)交響曲第3番ニ長調 D200 (4)交響曲第4番ハ短調 D417「悲劇的」 (5)交響曲第5番変ロ長調 D485 (6)交響曲第6番ハ長調 D589 (7)交響曲第8(7)番ロ短調 D759「未完成」 (8)交響曲第9(8)番ハ長調 D944「ザ・グレート」 (9)劇付随音楽「ロザムンデ」 D797全曲 (10)岩の上の羊飼い D965 (11)ミサ曲第6番変ホ長調 D950 (12)ミサ曲第2番ト長調 D167より クレド (13)水の上の霊の歌 D714 (14)詩篇第23番「主はわが羊飼い」 D706 15)ドイツ・ミサ曲 D872 (16)憂愁 D825 反抗 D865* 愛 D983a 16世紀の酒宴の歌 D847 愛の心 D747 永遠の愛 D825a (17)セレナード D920 (18)アヴェ・マリア D839 (19)アンゼルモの墓で D504 乙女の嘆き D191b (20)ガニュメート D544 (21)歌曲集「美しき水車小屋の娘」 D795全曲 (21)野ばら D257 スイスの歌 D559 ただあこがれを知る者だけが D877 子守歌 D498 夜咲きすみれ(花大根) D752 (22)ナイチンゲールに寄せて D497* (23)歌曲集「冬の旅」 D911全曲 (24)子守歌 D867 (25)魔王 D328 (26)歌曲集「白鳥の歌」 D957全曲 (27)月に寄す D193 (28)ズライカⅡ D717 (29)さすらい人の夜の歌 D224 (30)竪琴弾きの歌Ⅰ-Ⅲ (31)トゥーレの王 D367 糸を紡ぐグレートヒェン D118 (32)ます D550 水の上で歌う D774 (33)漁師の歌 D881 (34)糸を紡ぐグレートヒェン D118 (35)春の小川 D361 僕の挨拶を送ろう D741 録音:1949年 (36)春に D882 (37)死と乙女 D531* 音楽に寄せて D547** (38)憩いなき恋 D138 こびと D771 (39)シルヴィアに D891 若い尼僧 D828 恋人のそばに D162 (40)笑いと涙 D777 (41)それらがここにいたことは D775 (42)糸を紡ぐグレートヒェン D118 (43)アヴェ・マリア (44)君はわが憩い D776* ミューズの子 D764** (45)魔王 D328 |
(1)ロイヤルPO、トーマス・ビーチャム(指) 録音:1953年 (2)VPO、カール・ミュンヒンガー(指) 録音:1959年 (3)ロイヤルPO トーマス・ビーチャム(指) 録音:1958年-1959年 (4)ロンドン・モーツァルト・プレーヤーズ、ハリー・ブレック(指) 録音:1953年 (5)シカゴSO、フリッツ・ライナー(指) 録音:1960年 (6)アムステルダム・コンセルトヘボウO、エドゥアルト・ファン・ベイヌム(指) 録音:1957年 (7)レニングラードPO、エフゲニー・ムラヴィンスキー(指) 録音:1959年 (8)LSO、ヨーゼフ・クリップス(指) 録音:1958年 (9)ディアナ・エウストラーティ(Ms)、ベルリン・モテットcho、BPO、フリッツ・レーマン(指) 録音:1952-53年 (10)リタ・シュトライヒ(S)、ハインリヒ・ゴイザー(Cl)、エリック・ヴェルバ(P) 録音:1959年 (11)BPO ベルリン聖ヘドウィッヒcho、エーリッヒ・ラインスドルフ(指)、ピラール・ローレンガー(S)、ベティ・アレン(C.A)、フリッツ・ヴンダーリヒ(T)、マンフレッド・シュミット(T)、ヨーゼフ・グラインドル(Bs) 録音:1960年 (12)クリーヴランドcho、クリーヴランドOのメンバー、ロバート・ショウ(指) 録音:1961年 (13)ウィーン国立歌劇場cho、クレメンス・クラウス(指) 録音:1950年 (14)ベルリン・モテットcho、ミヒャエル・ラウハイゼン(P)、ギュンター・アルント(指) 録音:1952-53年 (15)ベルリン聖ヘドヴィヒ大聖堂cho、ヴォルフガング・マイヤー(Org)、ベルリンSO、カール・フォスター(指) 録音:1959年 (16)シュトゥットガルト・ヴォーカル・アンサンブル、ヴァルター・ベーレ(P)*、マルセル・クーロー(指) 録音:1955-56年 (17)ディアナ・オイストラティ(Ms)、ベルシン・モテットcho、ミヒャエル・ラウハイゼン(P)、ギュンター・アルント(指) 録音:1952-53年 (18)イルムガルト・ゼーフリート(S)、エリック・ヴェルバ(P) 録音:1957年 (19)キルステン・フラグスタート(S)、エドウィン・マッカーサー(P) 録音:1956年 (20)ヘルマン・プライ(Br)、ジェラルド・ムーア(P) 録音:1960年 (21)ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(Br)、ジェラルド・ムーア(P) 録音:1961年 (21リタ・シュトライヒ(S)、エリック・ヴェルバ(P) 録音:1959年 (22)エリーザベト・シューマン(S)、ジョージ・リーヴス(P)*、カール・アルヴィン(P)** 録音:1933年、1927年&1932年 (23)ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(Br)、ジェラルド・ムーア(P) 録音:1955年 (24)エリーザベト・グリュンマー(S)、ジェラルド・ムーア(P) 録音:1958年 (25)ヘルマン・プライ(Br)、カール・エンゲル(P) 録音:1962年 (26)ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(Br)、ジェラルド・ムーア(P) 録音:1951年、1955年&1957年 (27)リタ・シュトライヒ(S)、エリック・ヴェルバ(P) 録音:1959年 (28)エリーザベト・グリュンマー(S)、ジェラルド・ムーア(P) 録音:1958年 (29)ヘルマン・プライ(Br)、ジェラルド・ムーア(P) 録音:1960年 (30)ヘルマン・プライ(Br)、ジェラルド・ムーア(P) 録音:1960年 (31)イルムガルト・ゼーフリート(S)、エリック・ヴェルバ(P) 録音:1957年 (32)エリーザベト・グリュンマー(S)、ジェラルド・ムーア(P) 録音:1958年 (33)クリスタ・ルートヴィヒ(Ms)、ジェラルド・ムーア(P) 録音:1957年 (34)リーザ・デラ・カーザ(S)、カール・フーデッツ(P) 録音:1956年 (35)ハンス・ホッター(Br)、ジェラルド・ムーア(P) 録音:1949年 (36)ペーター・アンダース(T)、ミヒャエル・ラウハイゼン(P) 録音:1943年 (37)キャスリーン・フェリアー(C.A)、ブルーノ・ワルター(P)*、フィリス・スパー(P)** 録音:1949年 (38)ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(Br)、クラウス・ビリンク(P) 録音:1948年 (39)エリーザベト・シュヴァルツコップ(S)、エドウィン・フィッシャー(P) 録音:1952年 (40)イルムガルト・ゼーフリート(S)、エリック・ヴェルバ(P) 録音:1955年&1957年 (41)ゲルハルト・ヒュッシュ(T)、ハンス・ウード・ミュラー(P) 録音:1938年 (42)ロッテ・レーマン(S)、、エルネー・バログ(P) 録音:1937年 (43)マリアン・アンダーソン(S)、コスティ・ヴェハーネン(P) 録音:1936年 (44)エリーザベト・シューマン(S)、カール・アルヴィン(P)*、ジェラルド・ムーア(P)** 録音:1932年&1936年 (45)ハインリヒ・シュルスヌス(Br)、フランツ・ルップ(P) 録音:1933年 |
|
||
| Obsession SMHQ-002(1CD) HQCD 完全限定生産 |
マーラー:交響曲第1番「巨人」 | カルロス・パイタ(指)ロイヤルPO 録音:1976年、キングズウェイ・ホール(ロンドン)/ADD |
|
||
| ALPHA ALPHA-1008(1CD) |
シベリウス:交響曲第4番イ短調 Op.63 森の精 Op.15 悲しきワルツ Op.44 |
エーテボリSO サントゥ=マティアス・ロウヴァリ(指) 録音:2021年11月、2022年6月、2023年3月 エーテボリ・コンサート・ホール、スウェーデン |
|
||
| SWR music SWR-19130CD(1CD) NX-B09 |
ドヴォルザーク:交響曲第7番ニ短調 Op.7 交響曲第8番ト長調 Op.88 |
ピエタリ・インキネン(指) ドイツ放送PO 録音:2021年9月27-30日、2022年9月6-9日* |
|
||
| Capriccio C-8093(1CD) NX-B10 NYCX-10449(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ブルックナー:交響曲第2番ハ短調 | ウィーンRSO マルクス・ポシュナー(指) 録音:2023年4月11、12、14日ウィーン、放送文化会館(オーストリア) |
|
||
| CPO NYCX-10452(4CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
フェルディナント・リース(1784-1838):交響曲全集 ■CD1 交響曲第1番ニ長調 Op.23(1809) 交響曲第2番ハ短調 Op.80(1814) ■CD2 交響曲第5番ニ短調 Op.112(1813) 交響曲第3番変ホ長調 Op.90(1815) ■CD3 交響曲第4番ヘ長調 Op.110(1818) 交響曲第6番ニ長調 Op.146(1822) ■CD4 交響曲第7番イ短調 Op.181(1835) 交響曲第8番変ホ長調 WoO30(1822) |
チューリヒ室内O ハワード・グリフィス(指) 録音1999年9月(CD1)、2001年8月(CD3)、2002年5月(CD4)、1997年9月(CD2) CD4のみSACDハイブリッド・ディスク(Stereo/Surround) 輸入品番…777216 |
|
||
| CPO CPO-555660(1CD) NX-B02 |
グラジナ・バツェヴィチ:交響的作品全集 第2集 序曲(1943) 交響曲第2番(1951) 管弦楽のための変奏曲(1957) 3楽章の交響的音楽(1965) |
ケルンWDRSO ウカシュ・ボロヴィチ(指) 録音:2023年3月27-30日 |
|
||
| NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA NSO-0013 (5SACD+2Bluray) |
ベートーヴェン:交響曲全集 ■Disc1(SACD Hybrid) 交響曲第1番ハ長調 op.21 交響曲第3番変ホ長調 op.55「英雄」 ■Disc2(SACD Hybrid) 交響曲第2番ニ長調 op.36 交響曲第7番イ長調 op.92 ■Disc3(SACD Hybrid) 交響曲第4番変ロ長調 op.60 交響曲第5番ハ短調 op.67 ■Disc4(SACD Hybrid) 交響曲第6番ヘ長調 op.68「田園」 交響曲第8番ヘ長調 op.93 ■Disc5(SACD Hybrid) 交響曲第9番ニ短調 op.125「合唱」 ■Disc6(Blu-Ray/ pure audio/5.0DTS-HD MA24bit/192kHz2.0DTS-HD MA24bit/192kHz Dolby Atmos) 交響曲第1,2,3,4,5,6番 ■Disc7(Blu-Ray/ pure audio/5.0DTS-HD MA24bit/192kHz2.0DTS-HD MA24bit/192kHz Dolby Atmos) 交響曲第7,8,9番+交響曲第9番(収録:2023年6月3日)の映像 |
ジャナンドレア・ノセダ(指)、 ワシントン・ナショナルSO、 カミラ・ティリング(S)、 ケリー・オコーナー(Ms)、 イサハ・サベージ(T)、 ライアン・マッキニー(Bs-Br)、 ワシントンcho 録音:第1番&第5番:2022年1月13,15,16日、第2番:2023年5月24&25日 第3番:2022年1月27,28,29日、第4番:2022年1月20,21,22日 第6番:2023年5月19,20日、第7番&第8番:2023年5月12,13日 第9番:2023年6月1,2,3日(映像は6月3日の収録) |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00835(1SACD) 税込定価 |
チャイコフスキー:交響曲第3番「ポーランド」 | ジョナサン・ノット(指)東京SO 録音:2023年7月22日ミューザ川崎シンフォニーホール・ライヴ |
|
||
| フォンテック FOCD-895(1CD) 税込定価 2024年1月17日発売 |
ブルックナー:交響曲第7番ホ長調 <ハース版> | 尾高忠明(指) 大阪フィルハーモニーSO 録音:2023年1月24日 サントリーホール・ライヴ |
|
||
| BPO RECORDINGS KKC-9852 (2CD+Bluray) 初回限定特典付 2024年カレンダー 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ラフマニノフ生誕150周年第2弾 ■CD1 交響曲第2番 交響詩『死の島』* ■CD2 ピアノ協奏曲第2番 交響的舞曲* ■Blu ray Disc Concert videos 上記全曲のコンサート映像(すべてHD映像) ■Audio: 上記全曲のロスレス・スタジオ・マスター音源の音声トラック |
キリル・ペトレンコ(指)BPO ■CD1 収録:2021年3月20日、2021年1月16日* ■CD2 キリル・ゲルシュタイン(P) 収録:2022年6月25日、ヴァルトビューネ、ベルリン、2020年2月15日フィルハーモニー、ベルリン* ■Blu ray Disc 画面:Full HD1080/60i,16:9 音声:2.0PCM,7.1.4Dolby Atmos リージョン:ABC(worldwide) 総収録時間:161分 字幕:英、独、日本語 ■Audio: 2.0PCM Stereo24-bit /48-96kHz 7.1.4Dolby Atmos24-bit /48kHz ※ダウンロード・コード この商品には、上記全曲のハイレゾ音源(24-bit /192kHz迄)をダウンロードするためのURLとそのパスワードが封入されています。 ※デジタル・コンサートホール ベルリン・フィルの映像配信サービス「デジタル・コンサートホール」を7日間無料視聴できるチケット・コードが封入されています。 |
|
||
| King International KKC-4339(2SACD) シングルレイヤー 税込定価 |
ベートーヴェン:交響曲全集 (1)交響曲第1番ハ長調 作品21 (2)交響曲第2番ニ長調 作品36 (3)交響曲第3番「英雄」 (4)交響曲第4番変ロ長調 作品60 (5)交響曲第5番「運命」 (6)8交響曲第6番「田園」 (7)交響曲第7番イ長調 作品92 (8)交響曲第8番ヘ長調 作品93 (9)交響曲第9番「合唱」 (10)ドヴォルザーク:交響曲第8番ト長調 作品88 |
ヘルベルト・ブロムシュテット(指) シュターツカペレ・ドレスデン ヘレーナ・デーゼ(S)/マルガ・シムル(A)/ペーター・シュライヤー(T)/テーオ・アダム(Bs-Br)/ライプツィヒ放送cho ドレスデン国立歌劇場合cho 録音:(1)1979年12月19~21日 (2)1979年12月19~21日 (3)1976年3月17~21日 (4)1978年8月21~24日 (5)1977年3月14~18日 (6)1977年6月6~9日 (7)1975年2月24~26日 (8)1978年2月14~16日 (9)1979年4月9~11日、1980年3月31日) (10)1974年5月6~10日 |
|
||
| GRAND SLAM GS-2310(1CD) |
ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 交響曲第4番ホ短調 Op.98 |
ブルーノ・ワルター(指)コロンビアSO 録音:1960年1月18、27日(2)1959年1月2、4、6日、2月9、12、14日*/ハリウッド、アメリカン・リージョン・ホール 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:ステレオ(録音セッション) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2311(1CD) |
チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」 | ジャン・マルティノン(指)VPO 録音:1958年3月31~4月3日/ウィーン、ゾフィエンザール 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:ステレオ(録音セッション) |
|
||
| Altus PALTSA-1004(8SACD) 限定生産 |
ギュンター・ヴァント 不滅の名盤~ベルリン・ドイツSO編 【PALTSA001/2】 [Disc1] シューベルト:交響曲第7(8)番ロ短調「未完成」 D.759 [Disc2] ブルックナー:交響曲第9番(原典版) 【PALTSA003/4】 [Disc1] シューベルト:交響曲第8(9)番「ザ・グレート」 D.944 [Disc2] ストラヴィンスキー:バレエ組曲「火の鳥」(1945年版)、チャイコフスキー:交響曲第5番 【PALTSA005/6】 [Disc1] ベートーヴェン:(1)交響曲第1番ハ長調 作品21、交響曲第3番「英雄」 [Disc2] ベートーヴェン:(3)交響曲第4番、(4)序曲「コリオラン」 、序曲「エグモント」 【PALTSA007/8】 [Disc1] ベートーヴェン:(1)交響曲第6番「田園」、 (2)交響曲第5番「運命」 [Disc2] ベートーヴェン:(3)交響曲第6番「田園」 (4)交響曲第5番「運命」 |
ギュンター・ヴァント(指揮) ベルリン・ドイツSO 【PALTSA001/2】 録音:1993年3月20日/コンツェルトハウス・ベルリンにおけるライヴ 【PALTSA003/4】 録音:[Disc1]1993年6月14日、[Disc2]1987年4月5・6日/ベルリン・フィルハーモニーにおけるライヴ 【PALTSA005/6】 録音:(1)(2)1994年2月15日、(3)1996年4月9日、(4)(5)1994年11月28日/ベルリン・フィルハーモニーにおけるライヴ 【PALTSA007/8】 録音:(1)1992年9月26日、(2)1992年11月2日、(3)(4)1994年11月1・2日/コンツェルトハウス・ベルリンにおけるライヴ |
|
||
| Altus ALTB-536(3CD) 限定生産 |
アーベントロート集成・驚倒編 【TALT022】 (1)ブラームス:交響曲第1番ハ短調 (2)シューマン:交響曲第1番『春』 【TALT023】 ベートーヴェン:『エグモント』序曲 交響曲第3番『英雄』 【TALT053】 ベートーヴェン:交響曲第9番『合唱』 |
ヘルマン・アーベントロート(指) 【TALT022】 (1)バイエルン国立O、 (2)ベルリンRSO 録音:(1)1956年1月16日、(2)1955年9月18日(ライヴ、モノラル) 【TALT023】 ベルリンRSO 録音:1954年2月13日/ベルリン国立歌劇場(ライヴ、モノラル) 【TALT053】 ティッラ・ブリーム(S)、ディアナ・オイストラーティ(A)、ルートヴィヒ・ズートハウス(T)、 カール・パウル(Bs)、ベルリンRSO、ベルリン国立歌劇場cho 録音:1950年12月31日/ベルリン、放送局ホール1(ライヴ、モノラル) |
|
||
| Altus ALTB-538(3CD) 限定生産 |
スメターチェクの至芸 【ALT481】 (1)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 (2)シューマン:交響曲第1番「春」 【ALT489】 R=コルサコフ:(1)交響組曲「シェエラザード」 、 (2)「見えざる町キテージと聖女フェヴローニャの物語」組曲 【ALT490】 (1)ショスタコーヴィチ:交響曲第3番「メーデー」 (2)プロコフィエフ:交響曲第7番「青春」 |
ヴァーツラフ・スメターチェク(指) 【ALT481】 (1)アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(P)&プラハSO、 (2)プラハRSO 録音:(1)1957年5月29日(ライヴ、モノラル)、(2)1971年(セッション、ステレオ) 【ALT489】 (1)プラハRSO、(2)プラハSO 録音:(1)1975年6月3-5日、(2)1967年1月17日(ともにステレオ) 【ALT490】 (1)プラハRSO&プラハ放送cho(チェコ語歌唱)、(2)チェコPO 録音:(1)1974年9月、(2)1970年6月(ともにステレオ) |
|
||
 東武レコーディングズ TBRCD-0151(4CD) 税込定価 |
近衞秀麿 京都大学SOとの歴史的名演集 ■CD1 (1)リスト:交響詩「前奏曲」 (2)ベートーヴェン:交響曲第2番(ステレオ収録) (3)ベートーヴェン:「レオノーレ」序曲第3番 (4)ヨゼフ・シュトラウス:ポルカ「村の鍛冶屋」 (6)ベートーヴェン:「レオノーレ」序曲第3番 ■CD2 (1)シューマン:交響曲第3番「ライン」 (2)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番 ■CD3 (1)モーツァルト:交響曲第41番「ジュピター」 (2)R・シュトラウス:管楽セレナード (3)グリーグ:二つの悲しい旋律 (4)マーラー:さすらふ若人の歌 (5)ワーグナー:歌劇「タンホイザー」序曲 ■CD4 (1)グリンカ:歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲 (2)ドビュッシー:「小組曲」 (3)ブラームス:交響曲第1番 |
近衞秀麿(指) 京都大学SO ■CD1 録音:(1)1964年12月21日大阪公演 大阪サンケイホール (2)-(4)1964年12月16日京都公演・京都会館(ステレオ) (6)1964年12月21日大阪公演 大阪サンケイホール ■CD2 霧生トシ子(P) 録音:1968年12月9日大阪公演 大阪厚生年金会館中ホール ■CD3 録音:1970年12月21日大阪公演 大阪厚生年金会館大ホール 市来崎のり子(Ms) ■CD4 録音:1971年6月28日大阪公演 大阪厚生年金会館中ホール |
|
||
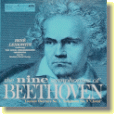 Treasures TRE-314(1CDR) |
レイボヴィッツ/ベートーヴェン名演集Vol.1 ベートーヴェン:序曲「レオノーレ」第3番* 交響曲第9番「合唱」 |
ルネ・レイボヴィッツ(指)ロイヤルPO インゲ・ボルク(S) 、ルート・ジーヴェルト(A)、リチャード・ルイス(T)、 ルートヴィヒ・ヴェーバー(Bs)、 ビーチャム・コーラル・ソサエティ 録音:1962年2月15日*、1961年5月2-3, 5,7日(共にステレオ) ※音源:英Readers Digest RDS-1013*、日ビクター RBS-6-7 ◎収録時間:74:37 |
| “響きの機能美に隠れがちな作曲家に寄り添ったレイボヴィッツの熱き魂!” | ||
|
||
 King International KKC-2714(3CD) 税込定価 |
The Last Symphonies シューベルト:交響曲第8番「ザ・グレイト」 ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」 シューベルト:交響曲第7番「未完成」 ショスタコーヴィチ:交響曲第15番 |
外山雄三(指)大阪SO 録音:2022年6月29日(Disc1)/2019年4月12日(Disc2)/11月21日(Disc3)/すべてザ・シンフォニーホール(ライヴ) |
|
||
| H.M.F HMM-905336 KKC-6787(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
メシアン:トゥーランガリラ交響曲 | マルク=アンドレ・アムラン(P) ナタリー・フォルジェ(オンド・マルトノ ) トロントSO グスターボ・ヒメノ(指) 録音:2023年5月、ロイ・トムソン・ホール、トロント(カナダ) |
|
||
| Hanssler HC-23081(4CD) KKC-6788(4CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ハイドン:交響曲全集 Vol.28~31 ■CD1 Vol.28(77'54) (1)交響曲第16番変ロ長調 Hob.I:16 (2)交響曲第72番ニ長調 Hob.I:72 (3)交響曲第12番ホ長調 Hob.I:12 (4)交響曲第13番ニ長調Hob.I:13 ■CD2 Vol.29(70'59) (5)交響曲第21番イ長調 Hob.I:21 (6)交響曲第22番変ホ長調 Hob.I:22「哲学者」 (7)交響曲第23番ト長調 Hob.I:23 (8)交響曲第24番ニ長調 Hob.I:24 ■CD3 Vol.30(73'01) (9)交響曲第28番イ長調 Hob.I:28 (10)交響曲第29番ホ長調 Hob.I:29 (11)交響曲第30番ハ長調 Hob.I:30「アレルヤ」 (12)交響曲 ニ長調 Hob.deest ■CD4 Vol.31(78'04) (13)交響曲第55番変ホ長調 Hob.I:55「学校の先生」 (14)交響曲第68番変ロ長調 Hob.I:68 (15)交響曲第67番ヘ長調 Hob.I:67 |
ハイデルベルクSO ヨハネス・クルンプ(指) 録音:(1)-(4)2021年3月ヴィースロッホ、パラティン (5)-(8)2021年11月バート・ヴィルトバート、トリンクハレ (9)-(12)2022年3月、(13)-(15)2022年6月ハイデルベルク=プファッフェングルント、ゲゼルシャフトハウス |
|
||
| Hanssler HC-23053(1CD) |
ピーター・ルジツカ(1948-):ベンヤミン交響曲~独唱、児童合唱とオーケストラのための エレジー |
リニ・ゴング(S)、 トーマス・バウアー(Br) フランクフルト歌劇場児童cho フランクフルトRSO、 ピーター・ルジツカ(指) 録音:(1)2019年3月29日、(2)2023年4月17日/hrゼンデザール(フランクフルト) |
|
||
 Treasures |
レオポルド・ルートヴィヒのマーラー マーラー:交響曲第9番 |
レオポルド・ルートヴィヒ(指)LSO 録音:1959年11月17-20日 ロンドン・ウォルサムストー・アセンブリー・ホール(ステレオ) ※音源:米EVEREST SDBR-3050-2 ◎収録時間:75:51 |
| “露骨な感情表現から開放した「マラ9」の世界初のステレオ録音!” | ||
|
||
| Altus ALTSA-1008(1SACD) シングルレイヤー 限定生産盤 |
フルトヴェングラー復帰三日目ライヴ ベートーヴェン:交響曲第5番『運命』 『エグモント』序曲 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) BPO ライヴ録音:1947年5月27日/ティタニア・パラスト(ベルリン) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2305(1CD) |
ブルックナー:交響曲第9番ニ短調(原典版) | カール・シューリヒト(指)VPO 録音:1961年11月20~22日/ウィーン、ムジークフェラインザール 使用音源:Private arvchive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:ステレオ(録音セッション) |
|
||
 SWR music SWR-19139CD(5CD) NX-F06 |
ガリー・ベルティーニ/SWR録音集~ハイドンからドビュッシーまで 【CD1】 (1)・モーツァルト:交響曲第40番 ト短調 K.550 (2)ハイドン:交響曲第53番ニ長調 「帝国」 Hob.I:53 (3)ハイドン:交響曲第95番ハ短調 Hob.I:95 【CD2】 (1)ベートーヴェン:交響曲第7番 イ長調 Op.92 (2)シューベルト:交響曲第8番「未完成」 【CD3】 ブラームス:交響曲集 (1)交響曲第1番ハ短調 Op.68 (2)交響曲第3番ヘ長調 Op.90 【CD4】 ベルリオーズ:作品集 (1)幻想交響曲 Op.14 (2)歌劇「ベンヴェヌート・チェッリーニ」 序曲 【CD5】 (1)ドビュッシー:選ばれた乙女 L.62 (2)ワーグナー:歌劇「さまよえるオランダ人」 序曲 楽劇「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死 |
シュトゥットガルトRSO ガリー・ベルティーニ(指) 【CD5】 (1)イレアナ・コトルバス(S) グレンダ・モーリス(A) シュトゥットガルト放送cho 録音:1996年12月1日(ライヴ) 東京芸術劇場…CD1(1) (2)1985年1月25日(ライヴ) Liederhalle Stuttgart…CD1(2)、CD3:(2) 1983年2月3日(ライヴ) Liederhalle Stuttgart…CD1:(3) 1995年4月13日(ライヴ)Liederhalle Stuttgart…CD2:(1) 1996年11月8日(ライヴ) Staatstheater Karlsruhe …CD2(2)、CD3:(1) 1978年4月14日(ライヴ) Liederhalle Stuttgart…CD4(1) 1978年9月28日 Liederhalle Stuttgart…CD4(2) 1984年9月 SDR Funkstudio Stuttgart…CD5:(1) 1996年11月28日(ライヴ) 東京芸術劇場…CD5:(2) |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00830(1SACD) 税込定価 2023年12月20日発売 |
モーツァルト:交響曲集 交響曲第31番ニ長調 K.297(300a)「パリ」* 交響曲第23番ニ長調 K.181(162b)# 交響曲第16番ハ長調 K.128 交響曲第17番ト長調 K.129 |
飯森範親(指) パシフィックフィルハーモニア東京 録音:2023年2月6-7日#、4月4-5日* 以上、埼玉・和光市民文化センターサンアゼリア、 7月10-11日 東京・タクトホームこもれびGRAFAREホール〈保谷こもれびホール〉 |
|
||
| Capriccio C-8092(1CD) NX-B07 NYCX-10443(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ブルックナー:交響曲第1番 (第1稿 レーダー版) |
リンツ・ブルックナーO マルクス・ポシュナー(指) 録音:2023年2月2-3日、7-8日 リンツ・ミュージックシアター ※国内仕様盤=石原勇太郎氏(音楽学/国際ブルックナー協会会員)による日本語解説付属 |
|
||
| BR KLASSIK BR-900218(1CD) NX-B07 |
ブルックナー:交響曲第7番ホ長調 WAB107 | バイエルンRSO ベルナルト・ハイティンク(指) 録音:1981年11月19&20日 ミュンヘン、ヘルクレスザール(ライヴ) |
|
||
| Profil PH-23085(1CD) |
ブルックナー:交響曲第2番ハ短調(1877年第2版) | ゲ ルト・シャラー(指) フィルハーモニー・フェスティヴァ 録音:2023年10月1日エーブラハ大修道院付属教会(ライヴ) |
|
||
| Altus PALTSA-1001(6SACD) 限定生産 |
ギュンター・ヴァント 不滅の名盤/ミュンヘン・フィル編~ブルックナー:交響曲第4・5・6・8・9番 【PALTSA009/10】 (1)ハイドン:交響曲第76番変ホ長調 Hob. I:76 ブルックナー:交響曲第6番イ長調 WAB.106(原典版) (2)ブルックナー:交響曲第9番ニ短調 WAB109(原典版) 【PALTSA011/2】 (3)ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 WAB.108(1884-90年、ハース版)/第1楽章~第3楽章 (4)ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 WAB. 108(1884-90年、ハース版)/第4楽章 シューベルト:交響曲第7(8)番ロ短調「未完成」 D.759 【PALTSA013/4】 (5)ブルックナー:交響曲第4番変ホ長調「ロマンティック」 WAB.104(1878-80年原典版) (6)ブルックナー:交響曲第5番変ロ長調 WAB. 105(原典版) |
ギュン ター・ヴァント(指) ミュンヘンPO (1)録音:1999年6月24日 (2)録音:1998年4月21日 (3)録音:2000年9月15日 (4)録音:1999年9月28日 (5)録音:2001年9月13~15日 (6)録音:1995年11月29日・12月1日 全てミュンヘン、ガスタイクにおけるライヴ |
|
||
| Altus PALTSA-1002(4SACD) 限定生産 |
ギュンター・ヴァント/不滅の名盤 北ドイツ放送響編I~ブラームス:交響曲全集
他 【PALTSA017/8】 (1).バッハ:ヴァイオリン協奏曲第1番 イ短調 BWV1041 (2)ブラームス:交響曲第1番ハ短調 作品68 (3)ハイドン:オーボエ協奏曲 ハ長調 Hob. VIIg: C1 (4)ブラームス:交響曲第2番ニ長調 作品73 【PALTSA019/20】 (5)モーツァルト:フルート協奏曲第1番 ト長調 K.313 (6)ブラームス:交響曲第3番へ長調 作品90 (7)リゲティ:ロンターノ (8)ブラームス:交響曲第4番ホ短調 作品98 |
ギュン ター・ヴァント(指) 北ドイツRSO (1).ロラント・グロイッター(Vn) ライヴ録音:1992年3月15-17日(場所記載なし) (2)ライヴ録音:1990年2月14日ケルン、フィルハーモニー (3)パウルス・ヴァン・デル・メルヴェ(Ob) ライヴ録音:1992年1月12-14日ハンブルク、ムジークハレ (4)ライヴ録音:1992年11月29-30日、12月1日ハンブルク、ムジークハレ (5)ヴォルフガング・リッター(Fl) ライヴ録音:1988年12月/ハンブルク (6)ライヴ録音:1990年2月14日ケルン、フィルハーモニー (7)ライヴ録音:1987年ハンブルク、ムジークハレ (8)ライヴ録音:1990年12月17日ハンブルク、ムジークハレ |
|
||
| Altus PALTSA-1003(6SACD) 限定生産 |
ギュンター・ヴァント/不滅の名盤 北ドイツ放送響編II~ブルックナー:交響曲第3・4・5・7・8・9番 【PALTSA023/4】 (1)ブルックナー:交響曲第3番ニ短調 WAB. 103(ノヴァーク第3稿/1889年) (2)交響曲第8番ハ短調 WAB.108(ハース版/1884-90年稿) 【PALTSA025/6】 (3)ブルックナー:交響曲第4番変ホ長調「ロマンティック」 WAB.104(1878-80年原典版) (4)交響曲第5番変ロ長調 WAB.105(原典版) 【PALTSA027/8】 (5)ブルックナー:交響曲第7番ホ長調 WAB. 107(1885年ハース原典版) (6)交響曲第9番ニ短調 WAB.109(原典版) |
ギュン ター・ヴァント(指) 北ドイツRSO (1)ライヴ録音:1985年12月23日 (2)ライヴ録音:2000年4月30日-5月3日 (3)ライヴ録音:1996年10月11-13日 (4)ライヴ録音:1995年10月8-10日 (5)ライヴ録音:1999年4月18-21日 (6)ライヴ録音:1998年4月5-7日 全てハンブルク、ムジークハレ |
|
||
 東武レコーディングズ TBRCD-0147(4CD) 税込定価 3850★★ |
ブリュッヘン+新日本フィルの音楽遺産2 (1)ラモー:歌劇「ナイス」序曲とシャコンヌ (2)シューマン:交響曲第2番 (3)シューマン:交響曲第4番 (4)モーツァルト:交響曲第31番「パリ」(四楽章版) (5)シューベルト:交響曲第9番「ザ・グレート」 (6)ハイドン:交響曲第102番、 (7)ハイドン:交響曲第103番「太鼓連打」 (8)ハイドン:交響曲第104番「ロンドン」 (9)アンコール(ハイドン:交響曲第104番~第4楽章) |
フランス・ブリュッヘン(指) 新日本フィルハーモニーSO 録音:(1)(2)(4)2005年2月18日すみだトリフォニーホール(第381回定期演奏会) (3)2007年1月26日すみだトリフォニーホール(第412回定期演奏会) (5)2005年2月25日サントリーホール(第382回定期演奏会) (6)-(9)2009年2月28日すみだトリフォニーホール(ハイドン特別演奏会) |
|
||
| Urania Records WS-121414(2CD) |
マーラー:交響曲第3番ニ短調* ワーグナー:楽劇「神々の黄昏」(抜粋) |
エーリヒ・ラインスドルフ(指)ボストンSO シャーリー・ヴァーレット(Ms)*、 ニューイングランド音楽院cho*、 ボストン少年cho* 録音:1966年10月(ボストン)*&1965年1月8日(ボストン、ライヴ録音) ※STEREO ADD |
|
||
| Urania Records WS-121415(2CD) |
チャイコフスキー:交響曲第1番&第6番ほか
チャイコフスキー:交響曲第1番1「冬の日の幻想」 交響曲第6番ロ短調 Op.74「悲愴」 スラヴ行進曲 Op.31/序曲「1812年」 ピアノ協奏曲第1番変ロ短調 Op.23* |
ニコライ・ゴロワノフ(指)、 モスクワRSO、エミール・ギレリス(P)* 録音:1944年(スラヴ行進曲)、1946年(P協奏曲)、1947年(交響曲)、1948年(序曲) ※MONO ADD |
|
||
 フォンテック FOCD-9894(1CD) 税込定価 2023年12月6日発売 |
ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 | 飯守泰次郎(指) 東京シティ・フィルハーモニックO 録音:2023年4月7日 サントリーホール ライヴ |
|
||
| Altus ALTSA-1005(6SACD) シングルレイヤー 限定生産 国内製作 日本語帯・解説付 |
ムラヴィンスキーレニングラード・フィル 来日公演集成/SACD5タイトルセット(全6枚) 【ALTSA001】 ベートーヴェン:交響曲第4番変ロ長調 リャードフ:バーバ・ヤーガ グラズノフ:バレエ「ライモンダ」第3幕間奏曲 【ALTSA002】 ショスタコーヴィチ:交響曲第5番 【ALTSA051/2】(2SACD) [DISC1] ワーグナー:楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より 第1幕へ の前奏曲 ブラームス:交響曲第2番ニ長調 チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調* [DISC2] (1)ワーグナー:歌劇「ローエングリン」 第1幕前奏曲/歌劇「タンホイザー」序曲 (2)ウェーバー:歌劇「オベロン」序曲 シューベルト:交響曲第8(7)番未完成」 (3)ウェーバー:歌劇「オベロン」序曲 シューベルト:交響曲第8(7)番「未完成」 チャイコフスキー:バレエ音楽「くるみ割り人形」より 抜粋(第6曲:客の退場、夜、ネズミの出現/第7曲:くるみ割り人形とネズミの戦闘、くるみ割りの勝利と王子への変身/第8曲:冬の森/第9曲:雪片のワルツ/第14曲:パ・ド・ドゥ/第15曲:終曲のワルツ) 【ALTSA054】 (1)シベリウス:交響曲第7番 チャイコフスキー:バレエ音楽「くるみ割り人形」より 抜粋(第6曲:客の退場、夜、ネズミの出現/第7曲:くるみ割り人形とネズミの戦闘、くるみ割りの勝利と王子への変身/第8曲:冬の森/第9曲:雪片のワルツ/第14曲:パ・ド・ドゥ/第15曲:終曲のワルツ) (2)モーツァルト:交響曲第39番 (3)チャイコフスキー:交響曲第5番 (4)チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」 【ALTSA063】 (1)ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」 ワーグナー:楽劇「トリスタンとイゾルデ」より 前奏曲と愛の死/楽劇「ジークフリート」より 森のささやき/楽劇「ワルキューレ」より ワルキューレの騎行 (2)グラズノフ:交響曲第5番変ロ長調 チャイコフスキー:バレエ音楽「眠りの森の美女」より 抜粋(序曲[プロローグ]、アダージョ、パノラマ、ワルツ) |
エフゲニー・ムラヴィンスキー(指) レニングラードPO 【ALTSA001】 ライヴ録音:1973年5月26日/東京文化会館 【ALTSA002】 ライヴ録音:1973年5月26日/東京文化会館 【ALTSA051/2】(2SACD) [DISC1] ライヴ録音:1977年9月27日/東京文化会館 ライヴ録音:1977年10月19日/NHKホール* [DISC2] (1)ライヴ録音:1977年9月27日/東京文化会館 (2)ライヴ録音:1977年10月12日/東京文化会館 (3)ライヴ録音:1977年10月8日/フェスティバルホール 【ALTSA054】 (1)ライヴ録音:1977年10月19日/NHKホール (2)ライヴ録音:1977年10月12日/東京文化会館 (3)ライヴ録音:1975年6月7日/東京文化会館 (4)ライヴ録音:1975年5月13日/東京文化会館 (5)ライヴ録音:1975年6月7日/東京文化会館 【ALTSA063】 (1)ライヴ録音:1979年5月21日/東京文化会館 (2)ライヴ録音:1979年6月8日/NHKホール |
|
||
| Altus ALTSA-1006(3SACD) シングルレイヤー 限定生産 国内製作 日本語帯・解説付 |
ムラヴィンスキーレニングラード・フィル ウィーンライブ集成/SACD3タイトルセット 【ALTSA287】 チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調 【ALTSA288】 ウェーバー:歌劇『オベロン』 序曲 ブラームス:交響曲第2番ニ長調 【ALTSA289】 シューベルト:交響曲第8番『 未完成』 ショスタコーヴィチ:交響曲第5番ニ短調 |
エフゲニー・ムラヴィンスキー(指) レニングラードPO 【ALTSA287】 ライヴ録音:1978年6月12、13日ウィーン楽友協会 大ホール 【ALTSA288】 ライヴ録音:1978年6月13日ウィーン楽友協会 大ホール 【ALTSA289】 録音:1978年6月12日(ショスタコーヴィチ)、13日(シューベルト)ウィーン楽友協会 大ホール |
|
||
| AltusALTSA-1007(4SACD) シングルレイヤー 限定生産 国内製作 日本語帯・解説付 |
若杉弘&N響/ブルックナー・チクルス&メシアン・管弦楽作品集 【ALTSA431/3】 (3SACD) ブルックナー:交響曲全集 [Disc1] (1)交響曲第1番ハ短調 WAB101 第1稿 (リンツ稿 )ノヴァーク版 (2)交響曲第2番ハ短調 WAB102 第2稿ノヴァーク版 (3)交響曲第3番ニ短調 WAB103 第3稿ノヴァーク版 [Disc2] (1)交響曲第4番変ホ長調『ロマンティック』 WAB104 1878・80年稿ノヴァーク版 (2)交響曲第5番変ロ長調 WAB105 原典版・ノヴァーク版 (3)交響曲第6番イ長調 WAB106 ノヴァーク版 [Disc3] (1)交響曲第7番ホ長調 WAB107 ノヴァーク版・第 2版 (2)交響曲第8番ハ短調 WAB108 第2稿ノヴァーク版 (3)交響曲第9番ニ短調 WAB109 ノヴァーク版 【ALTSA483】 メシアン:作品集 (1)忘れられた捧げもの(1930) (2)教会のステンドグラスと小鳥たち(1986)〈日本初演〉 (3)かの高みの都市(1987) (4)われら死者のよみがえりを待ち望む(1964) (5)聖体秘蹟への賛歌(1932) (6)キリストの昇天(1932-33) (7)天国の色彩(1963) (8)神の顕現の三つの小典礼 (9)輝ける墓(1931) |
木村かをり((2)(3)(7)(8)ピアノ) 原田 節((8)オンド・マルトノ) 東京混声cho((8)女声合唱) 大谷研二((8)合唱指揮) 若杉弘(指)NHK響 【ALTSA431/3】 [Disc1] (1)録音:1998年2月28日 (2)録音:1997年1月13日 (3)録音:1996年2月26日 [Disc2] (1)録音:1997年2月24日 (2)録音:1998年1月27日 (3)録音:1997年3月18日 [Disc3] (1)録音:1996年1月29日 (2)録音:1996年3月31日 (3)録音:1998年3月13日 【ALTSA483】 (1)録音:1996年1月29日 (2)録音:1996年2月26日 (3)録音:1996年3月31日 (4)録音:1997年1月13日 (5)録音:1997年2月24日 (6)録音:1997年3月18日 (7)録音:1998年1月27日 (8)録音:1998年2月28日 (9)録音:1998年3月13日 |
|
||
| CPO CPO-777665(1CD) NX-B10 |
ナタナエル・ベリ:交響曲第4番/第5番 交響曲第4番「交響的小品」 交響曲第5番「Triologia delle passioni 情熱=受難の三部作」 |
ノールショピングSO アリ・ラシライネン(指) 録音:2011年6月6-8日 |
|
||
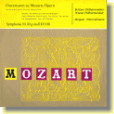 Treasures TRE-281(1CD) |
F.レーマン~モーツァルト:作品集1 オペラ序曲集* 後宮からの誘拐/フィガロの結婚、 ドン・ジョヴァンニ/コシ・ファン・トゥッテ、 劇場支配人/魔笛/イドメネオ 交響曲第40番ト短調K.550 |
フリッツ・レーマン(指) BPO*、ウィーンSO 録音:1952年7月9日*、1953年5月3-4日(共にモノラル) ※音源:DGG LPEM-19040*、29311 ◎収録時間:64:20 |
| “今こそ傾聴すべき、楽器や奏法を弄るではない真の原点回帰!” | ||
|
||
| LSO Live LSO-0572(4CD) |
エルガー:交響曲、エニグマ変奏曲、行進曲集、他 ■Disc1 (1)交響曲第1番変イ長調op.55 (2)行進曲「威風堂々」第3番ハ短調、第2番イ短調、第5番ハ長調 ■Disc2 (1)交響曲第2番変ホ長調op.63 (2)戴冠式行進曲op.65 帝国行進曲op.32/威風堂々第1番 ■Disc3 (1)交響曲第3番ハ短調op.88(A.ペイン(1936~2021)補筆) (2)ヴォーン・ウィリアムズ:トマス・タリスの主題によるファンタジア (3)行進曲「威風堂々」第4番 ■Disc4 (1)序奏とアレグロ (2)エニグマ変奏曲 (3)チェロ協奏曲 |
■Disc1 (1)サー・コリン・デイヴィス(指)/録音:2001年9月30&10月1日、バービカン・ホール (2)バリー・タックウェル(指)/録音:1988年4月26&27日/ウォルサムストー・タウン・ホール ■Disc2 (1)サー・コリン・デイヴィス(指)/録音:2001年10月4&5日、バービカン・ホール (2)バリー・タックウェル(指)/録音:1988年4月26&27日、ウォルサムストー・タウン・ホール(op.65とop.32は4月27日のみ録音) ■Disc3 (1)サー・コリン・デイヴィス(指)/録音:2001年12月13&14日、バービカン・ホール (2)サー・アントニオ・パッパーノ(指)/録音:2020年3月15日、バービカン・ホール】 (3)バリー・タックウェル(指)/録音:1988年4月26&27日、ウォルサムストー・タウン・ホール ■Disc4 (1)サー・コリン・デイヴィス(指)/録音:2005年9月2日3&12月9日、バービカン・ホール (2)サー・コリン・デイヴィス(指)/録音:2007年1月6&7日/バービカン・ホール (3)フェリックス・シュミット(Vc)、ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴス(指)/録音:1988年9月28&29日、ウォルサムストー・タウン・ホール |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00834(1SACD) 税込定価 2023年11月22日発売 |
ハイドン交響曲集Vol.22 交響曲 第67番 へ長調 Hob.I:67 交響曲 第68番 変ロ長調 Hob.I:68 交響曲 第11番 変ホ長調 Hob.I:11 |
飯森範親(指) 日本センチュリーSO 録音:2022年5月26日(第67番、第68番)、12月9日(第11番) 大阪、ザ・シンフォニーホール・ライヴ |
|
||
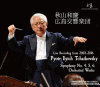 東武レコーディングズ TBRCD-0142(4CD) 税込定価 |
チャイコフスキー名演集~3大交響曲&管弦楽作品集 ■CD1 (1)交響曲第4番 (2)『白鳥の湖』抜粋 ■CD2 (3)交響曲第5番 (4)『エフゲニー・オネーギン』よりポロネーズ (5)幻想序曲『ロミオとジュリエット』 ■CD3 (6)交響曲第6番『悲愴』 (7)フランチェスカ・ダ・リミニ (8)『モーツァルティアーナ』より祈り ■CD4 (9)弦楽セレナーデ (10)フィレンツェの想い出 (11)デンマーク国家による祝典序曲 |
秋山和慶(指)広島SO 録音:(1)2012年2月17日アステールプラザ大ホール(ディスカバリー・シリーズ「ロマン派の旅路19~世紀を彩った作曲家」Ⅳ) (2)2011年9月16日アステールプラザ大ホール(ディスカバリー・シリーズ「ロマン派の旅路19~世紀を彩った作曲家」Ⅲ) (3)2012年1月7日広島市文化交流会館(YMFGもみじニューイヤーコンサート) (4)(5)2012年4月10日広島市文化交流会館(第318 回定期演奏会) (6)2003年8月6日広島国際会議場フェニックスホール(平和の夕べコンサート) (7)(8)2013年1月18日広島市文化交流会館(第325 回定期演奏会) (9)(11)2016年4月17日広島市文化交流会館(第359 回定期演奏会) (10)2013年2月28日アステールプラザ大ホール(ディスカバリー・シリーズ「音楽の街を訪ねて」4) |
|
||
| Myrios Classics MYR-033(1CD) KKC-6772(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ブルックナー:交響曲第3番ニ短調 WAB103(1873年第1稿/ノヴァーク版) | フランソワ=グザヴィエ・ロト(指) ケルン・ギュルツェニヒO 録音:2022年9月/ケルン・フィルハーモニー(ライヴ) |
|
||
| NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA NSO-0007(1SACD) |
ジョージ・ウォーカーシンフォニア集 :シンフォニア第1番(1984,1996改訂) (フロム財団委嘱) シンフォニア第2番(1990) (クーセヴィツキー財団委嘱) シンフォニア第3番(2002) シンフォニア第4番“Strands(糸)” (2011) (ナショナルSOほか共同委嘱) シンフォニア第5番“Visions” (2016) |
ジャナンドレア・ノセダ(指) ワシントン・ナショナルSO アーロン・ゴールドマン(Fl) シャナ・オシロ(S)、デ・マルクス・ボルズ(T)、ダニエル・J・スミス(Bs-Br)、V・サヴォイ・マクイルヴァン(Bs-Br) 録音:[第1番]2022年1月13,15,16日/[第2番]2023年5月24,25日/[第3番]2023年6月1,2,3日/[第4番]2022年1月27,28,29日/[第5番]2023年5月12,13日 |
|
||
| BIS BISSA-2701(1SACD) |
ヘルヴィ・レイヴィスカ(1902-1982):管弦楽作品集
第1集 シンフォニア・ブレヴィス(短い交響曲)(Sinfonia brevis) Op.30(1962rev.1972) 管弦楽組曲第2番Op.11(1937?38)(ニュルキ・タピオヴァアラの映画『ユハ(Juha)』の音楽から)* 交響曲第2番Op.27(1954) |
ラハティSO、 ダリア・スタセフスカ(指) 録音:2023年1月2~5&7日、2023年5月12&13日*/シベリウスホール、ラハティ(フィンランド) 制 作:インゴ・ペトリ |
|
||
| GRAND SLAM GS-2306(1CD) |
ベートーヴェン:序曲「コリオラン」* 交響曲第3番「英雄」 |
ブルーノ・ワルター(指) コロンビアSO 録音:1959年4月15日*、1958年1月20、23、25日/アメリカン・リージョン・ホール(カリフォルニア) 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:ステレオ |
|
||
| Glossa GCD-921134(1CD) |
C.P.E.バッハ:ハンブルク交響曲集 Wq182 シンフォニア第1番ト長調 シンフォニア第2番変ロ長調 シンフォニア第3番ハ長調 シンフォニア第4番イ長調 シンフォニア第5番ロ短調 シンフォニア第6番ホ長調 |
アレクサンダー・ヤニチェク(コンサートマスター)、 18世紀オーケストラ 録音:2021年5月&2022年9月、カイゼル運河教会(アムステルダム、オランダ) |
|
||
| ALTO ALC-1496(1CD) |
ジェローム・モロス:交響曲第1番他 交響曲第1番/最後の審判 オーケストラのためのワルツによる変奏曲 Biguine/オーケストラのための壮大な物語 |
ジョアン・ファレッタ(指)LSO 録音:1993年 |
|
||
| BIS BISSA-2496(1SACD) |
マーラー:交響曲第8番『千人の交響曲』 | キャロリン・サンプソン(ソプラノI / いと罪深き女)、ジャクリン・ワーグナー(ソプラノII
/ 贖罪の女)、キャロリン・サンプソン(ソプラノIII
/ 栄光の聖母)、サーシャ・クック(アルトI /
サマリアの女)、ジェス・ダンディ(アルトII
/ エジプトのマリア)、バリー・バンクス(テノール
/ マリア崇拝の博士)、ユリアン・オルリスハウゼン(バリトン
/ 法悦の教父)、クリスティアン・イムラー(バス
/ 瞑想の教父) ミネソタcho、ナショナル・ルーテルcho、ミネソタ少年cho、アンジェリカ・カンタンティ・ユースcho オスモ・ヴァンスカ(指)ミネソタO 録音:2022年6月10-12日(ライヴ)、2022年6月14-16日(セッション)/オーケストラ・ホール(ミネアポリス) |
|
||
| Cybele SC-832301(1CD) |
バッハ家の管弦楽作品集 ヨハン・ベルンハルト・バッハ:管弦楽組曲 ト短調 C.P.E.バッハ:ハンブルク交響曲第5番ロ短調 J.C.バッハ:交響曲 ト短調 バッハ:ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲 ハ短調 BWV1060 |
パヴェル・ストルガレフ(Ob) ベルンハルト・フォルク(Vn,指) ノイエ・フィルハーモニー・ヴェストファーレン |
|
||
 Gramola GRAM-99311(11CD) NX-K10 |
ブルックナー:交響曲全集(全10曲) 交響曲 ニ短調(通称第0番) WAB100(1869)(2023年デイヴィッド・チャプマン校訂版)…初出音源 交響曲第1番ハ短調 WAB101(1890/91年ウィーン稿) 交響曲第2番ハ短調 WAB1022(1872年初稿/2005年ウィリアム・キャラガン校訂版) 交響曲第3番ニ短調 WAB103(1873年第1稿) 交響曲第4番変ホ長調「ロマンティック」 WAB104(1888年第3稿/2004年ベンジャミン・コーストヴェット校訂版) 交響曲第5番変ロ長調 WAB105(1876-78) 交響曲第6番イ長調 WAB106(1881)* 交響曲第7番ホ長調 WAB107(1883-85)(1954年ノーヴァク版 2018/19年 ポール・ホークショー校訂版) 交響曲第8番ハ短調 WAB108(1890)(2014年 ポール・ホークショー校訂版)* 交響曲第9番ニ短調 WAB109(1887-96未完) |
レミ・バロー(指) 聖フローリアン・アルトモンテO オーバーエスターライヒ・ユースSO* 録音:2013-2023年聖フローリアン修道院教会、ザンクトフローリアン(オーストリア北部オーバーエスターライヒ地方) |
|
||
 ICA CLASSICS ICAC-5176(1CD) NX-B03 |
カバレフスキー:歌劇「コラ・ブルニョン」序曲 ショスタコーヴィチ:交響曲第8番ハ短調 Op. 65 |
ボーンマスSO コンスタンティン・シルヴェストリ(指) 録音:1961年4月27日ウィンター・ガーデンズ・パヴィリオン、ボーンマス(ライヴ/モノラル) |
|
||
| Phi LPH-040(1CD) |
シューマン:交響曲第1番変ロ長調 Op.38 「春」 交響曲第3番変ホ長調 Op.97「ライン」* |
アントワープSO フィリップ・ヘレヴェッヘ(指) 録音:2019年10月*、2022年10月エリザベート王妃記念ホール、アントワープ(アントウェルペン) |
|
||
| CD ACCORD ACD-266(3CD) NX-F01 |
スクロヴァチェフスキ生誕100年を記念して 【CD1】 スタニスワフ・スクロヴァチェフスキ:1. プレリュード、フーガとポストリュード(1946-1948) オネゲル:交響曲第2番(1941) 【CD2】 モーツァルト:レクイエム ニ短調 K.626(1791) 【CD3】 エンニオ・ポッリーノ(1910-1959):交響詩「サルデーニャ」(1933) ペトラッシ(1904-2003):管弦楽のための協奏曲 第1番(1934) ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 |
ステファニア・ヴォイトヴィチ(S) クリスティナ・シュチェパンスカ(Ms) ボグダン・パプロツキ(T) ヴィトルド・ピレウスキ(Bs) ワルシャワ・フィルハーモニーcho ワルシャワPO スタニスワフ・スクロヴァチェフスキ(指) 録音:全てモノラル 1956年2月11日(CD1&CD2)、6月22日(CD3) ワルシャワ・フィルハーモニーホール(ライヴ) |
|
||
| ONDINE ODE-1422(1CD) NX-B07 |
オッリ・ムストネン(1967-):交響曲第3番&第2番 交響曲第3番「Taivaanvalot 天空の光」(2020)- テノールと管弦楽のために 交響曲第2番「Johannes Angelos ヨハネス・アンジェロス」 (2013)* |
イアン・ボストリッジ(T) トゥルクPO オッリ・ムストネン(指) 録音:トゥルク・コンサート・ホール(フィンランド)、2022年11月24-26日、2023年5月29-30日* |
|
||
| FUGA LIBERA FUG-820(1CD) NX-B10 |
ミヤスコフスキー:交響曲集 交響曲第17番嬰ト短調 Op.41 交響曲第20番ホ長調 Op.50 |
ウラル・ユースSO アレクサンドル・ルーディン(指) 録音:2022年6月 スヴェルドロフスク・フィルハーモニック大ホール、エカテリンブルク、ロシア |
|
||
| BELVEDERE BELVED-08071(3CD) NX-D10 |
モーツァルト週間へのデビュー・コンサート 【CD1】 ●1980年 モーツァルト週間 歌劇「魔笛」 - 序曲 K.620 交響曲第34番ハ長調 K.338 オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314 交響曲第35番「ハフナー」 K.385 【CD2&3】 ●2006年 モーツァルト・イヤー オーケストラ・ワークショップ モーツァルト:交響曲第25番ト短調 K.183の公開リハーサル(ドイツ語) |
【CD1】 ヴェルナー・ヘルベルス(Ob) アムステルダム・コンセルトヘボウO ニコラウス・アーノンクール(指) 録音:1980年1月29日 ザルツブルク祝祭大劇場 【CD2&3】 カメラータ・ザルツブルク ニコラウス・アーノンクール(指) 録音:2006年6月10日 モーツァルテウム、大ホール |
|
||
| VOX VOXNX-3028CD(1CD) NX-B03 |
ラフマニノフ:交響曲第3番イ短調 Op.44 交響曲 ニ短調「ユース・シンフォニー」# 幻想曲「岩」 Op.7* |
セントルイスSO レナード・スラットキン(指) 録音:1977年10月1-2日、1979年*、1980年10月# |
|
||
| VOX VOXNX-3029CD(1CD) NX-B03 |
ラフマニノフ:交響曲第1番ニ短調 Op.13 交響詩「ロスティスラフ公」(1891)* |
セントルイスSO レナード・スラットキン(指) 録音:1976年12月3日、1980年10月* |
|
||
| ACCENTUS Music ACC-80544CD(4CD) |
フランツ・シュミット:交響曲全集 ■CD1(46'51) 交響曲第1番ホ長調 ■CD2(51'46) 交響曲第2番変ホ長調 ■CD3(50'43) 交響曲第3番イ長調 ■CD4(60'41) 交響曲第4番ハ長調 歌劇「ノートル・ダム」間奏曲&謝肉祭の音楽 |
BBCウェールズ・ナショナルO ジョナサン・バーマン(指) ■CD4 アリス・ニアリー(Vc)、フィリップ・シャルツ(Tp)、ティム・ソープ(Hrn)、サラ=ジェーン・ポルスモゲ(イングリッシュホルン) 録音:[第1番]2020年7月 [第2番]2021年10&11月 [第3番]2021年9月 [第4番&ノートルダム]2022年10月 |
|
||
| APARTE AP-328(1CD) |
モーツァルト:交響曲全集Vol.2 (1)交響曲第29番イ長調K.201 (2)オーボエ協奏曲ハ長調K.314 (3)交響曲第40番ト短調K.550 |
マキシム・エメリャニチェフ(指) イル・ポモ・ドーロ イワン・ポディヨーモフ(Ob)(2) 録音:2023年2月9-11日 サラ・デッラ・カリタ(パドヴァ) |
|
||
| MDG MDG-93822616(1SACD) |
エディション・ホーフカペレ2~宮廷コンサート アントン・ライヒャ(1770-1836):大序曲ニ長調 アンドレアス・ロンベルク:ヴァイオリン協奏曲第8番変ホ長調 パウル・ヴァインベルガー(1758-1821)交響曲ニ長調 |
ボン宮廷楽団(ボン・ベートーヴェンOのメンバー) ディルク・カフタン(指) ミハイル・オヴルツキ(Vn) 録音:2021年3月25,26日(ライヒャ、ロンベルク)、2023年1月9-12日(ヴァインベルガー)、ラ・レドゥーテ、ボン=バート・ゴーデスベルク |
|
||
| H.M.F HAF-8905371(2CD) |
ハイドン:パリ交響曲集+ヴァイオリン協奏曲 交響曲第84番変ホ長調 Hob.I:84 交響曲第85番変ロ長調 Hob.I:85「王妃」 ヴァイオリン協奏曲第1番ハ長調 Hob.VIIa:1* 交響曲第86番ニ長調 Hob.I:86 交響曲第87番イ長調 Hob.I:87 |
レザール・フロリサン ウィリアム・クリスティ(指) テオティム・ラングロワ・ド・スワルテ(Vn,指*) 録音:2020年10月(第84&87番)、2022年3月(第85,86番、協奏曲)/シテ・ド・ラ・ミュジーク(パリ) |
|
||
 Melodiya x Obsession SMELCO-1001087(2CD) 完全限定生産 |
ジャクリーヌ・デュ・プレ・イン・モスクワ ソビエト連邦国歌、イギリス国歌 ハイドン:交響曲第83番ト短調 《めんどり》 エルガー:チェロ協奏曲ホ短調 Op.85 シベリウス:交響曲第2番ニ長調 Op.43 ブリテン:青少年のための管弦楽入門 ~ XV.フーガ |
ジャクリーヌ・デュ・プレ(Vc) ジョン・バルビローリ(指)BBC響 録音(ライヴ):1967年1月7日、モスクワ音楽院大ホール/ステレオADD |
|
||
| Gutman Records GUTMANCD-231(1CD) JGUTMANCD-231(1CD) 日本語解説付き国内盤 税込定価 |
ブルックナー:交響曲第6番(ロルフ・フェルベーク編/アンサンブル版) | カメラータRCO、 ロルフ・フェルベーク(指) 録音:2022年9月2日、ワロン教会(アムステルダム、オランダ) |
| Gutman Recordsにブルックナーの交響曲第7番(JGUTMANCD211/GUTMANCD211)やマーラーの交響曲第4番(JGUTMANCD173/GUTMANCD173)、第9番(JGUTMANCD150/GUTMANCD150)を小編成アレンジでレコーディングしてきたカメラータRCOが、今度はブルックナーの交響曲第6番をリリース!カメラータRCOは世界最高峰のオーケストラ、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団(RCO)のメンバーで組織されるアンサンブル。今回演奏されるのは指揮を務めるロルフ・フェルベーク自身による編曲版で、前作の交響曲第7番同様、各1名の弦五部とクラリネット、ホルン、ティンパニにピアノとアコーディオンを加えた計10名の編成。ベイヌム、ヨッフム、ハイティンクらと共に長きにわたってブルックナー演奏の伝統を築いてきたRCOのメンバーが“ブル6”の演奏史に新たな1ページを刻みます。 今回指揮と編曲を担った1989年生まれのロルフ・フェルベークは2019年からカメラータRCOの常任客演指揮者として度々共演しており、彼らのための編曲もいくつも手掛けています。オランダ国内の多くの主要オーケストラを指揮しており、2023/24シーズンにはオランダ・フィルやロッテルダム・フィルにもデビューを予定しているほか、国外ではロンドン響、ミュンヘン・フィル、フランス放送フィルなど数々の一流オーケストラでアシスタント指揮者を歴任。またフリーのホルン奏者としても複数のオーケストラに客演し、エド・デ・ワールトやマルクス・シュテンツ、ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン、ネーメ・ヤルヴィといった著名な指揮者と共演しています。 |
||
| Forgotten Records fr-1894(1CDR) |
ベルワルド:交響曲集 第1番ト短調「厳粛」 第3番ハ長調「風変わりな」 |
ハンス・シュミット=イッセルシュテット(指) ストックホルムPO 録音:1962年2月19日、21日(ステレオ) ※音源:Opera 1211他 |
| Forgotten Records fr-1900(1CDR) |
シューマン:交響曲第3番「ライン」* ブラームス:交響曲第1番ハ短調 Op.68# |
ゲオルク・ショルティ(指) パリ音楽院O*、フランス国立放送O# 録音:1959年9月5日ブザンソン音楽祭*、1956年12月6日#(ともに放送用ライヴ音源) |
| Forgotten Records fr-1901(1CDR) |
ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」 スメタナ:交響詩「我が祖国」~モルダウ# 歌劇「売られた花嫁」~序曲/フリアント/道化師の踊り |
ディーン・ディクソン(指)ケルンRSO 録音:1959年、ステレオ ※音源:Bertelsmann 11331他 |
| Forgotten Records fr-1902(1CDR) |
マーラー:交響曲第1番「巨人」 ワーグナー:序曲「ファウスト」 # |
ジョルジュ・セバスティアン(指) フランス放送PO 録音:1960年4月28日 、1962年10月9日# (共に放送用音源) |
| Forgotten Records fr-1903(1CDR) |
シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 Op.54 ブラームス:交響曲第1番ハ短調 Op.68# |
ローズル・シュミット(P) ヨーゼフ・カイルベルト(指) バンベルクSO、BPO # 録音:1951年、バンベルク*、1951年3月9日、11日# ※音源:Mercury MG15020*、Telefunken SK7008# |
| Forgotten Records fr-1904(1CDR) |
チャイコフスキー:交響曲第4番ヘ短調 Op.36* ムソルグスキー(ラヴェル編):組曲「展覧会の絵」# |
ラファエル・クーベリック(指) フランス国立放送O 録音:1955年2月12日* 、1956年2月23日# 、(共に放送用ライヴ) |
| Forgotten Records fr-1906(1CDR) |
ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」 スメタナ:歌劇「売られた花嫁」序曲# |
ラファエル・クーベリック(指) フランス国立放送O 録音:1955年2月10日#、1958年3月13日*、(共に放送用ライヴ) |
| Forgotten Records fr-1909(1CDR) |
ドヴォルザーク:交響曲第4番ニ短調 Op.13* チャイコフスキー:フィレンツェの思い出 ニ短調 Op.70# |
ヘンリー・スヴォボダ(指) ウィーン国立歌劇場O*、 ウィーン国立歌劇場弦楽合奏団# 録音:1950年10月# 、1952年頃* ※音源:Concert Hall F-11*、Westminster WL5083# |
| Forgotten Records fr-1917(1CDR) |
バンベルガー/ブラームス&ワーグナー ブラームス:交響曲第1番ハ短調 ワーグナー:「タンホイザー」序曲# 「さまよえるオランダ人」序曲# |
カール・バンベルガー(指) フランクフルト歌劇場SO*、 バーデン国立歌劇場O# 録音:1956年*、1959年頃# ※音源:Musical Masterpiece Society MMS2096*, MMS2142# |
| QUERSTAND VKJK-2302(1CD) ハードカヴァーブック仕様 |
「エディション・バーディッシェ・シュターツカペレ01」 R.シュトラウス:アルプス交響曲 |
ゲオルク・フリッチュ(指) バーディッシェ・シュターツカペレ (バーデン州立O) 録音:2023年4月23,24日 ドイツ バーデン=ヴュルテンベルク州 カールスルーエ (ライヴ) |
|
||
| Capriccio C-8090(1CD) NX-B07 NYCX-10435(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ブルックナー:交響曲第5番(ノーヴァク版) | ウィーンRSO マルクス・ポシュナー(指) 録音:2023年2月15&16日ウィーン放送文化会館(オーストリア) |
|
||
| Gramola GRAM-99283(1SACD) NX-C01 |
ブルックナー:交響曲第1番ハ短調 WAB101ウィーン稿(1891) | 聖フローリアン・アルトモンテO レミ・バロー(指) 録音:2022年8月20日(ライヴ)聖フローリアン修道院教会、ザンクトフローリアン(オーストリア北部オーバーエスターライヒ地方) |
|
||
| Altus ALT-530(1CD) |
マーラー:交響曲『大地の歌』 | 藤村実穂子(Ms)、宮里直樹(T) 大野和士(指)東京都SO 録音:2021年4月26日/サントリーホール(無観客ライヴ) |
|
||
| ALPHA ALPHA-918(1CD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲第14番 「死者の歌」 Op.135 5つの断章 Op.42 |
アスミク・グリゴリアン(S) マティアス・ゲルネ(Br) フランス放送PO ミッコ・フランク(指) 録音:2021年6月、2022年8月 オーディトリアム、ラジオ・フランス、パリ |
|
||
| Linn CKD-667(1CD) |
メンデルスゾーン::交響曲第3番「スコットランド」 Op.56 交響曲第5番「宗教改革」 Op.107 |
スコットランド室内O マキシム・エメリャニチェフ(指) 録音:2022年2月 ケアード・ホール、ダンディー、UK |
|
||
| Urania Records LDV-14104(1CD) |
フランス革命後のミラノの交響曲集 ボニファツィオ・アジオーリ(1769-1832):交響曲へ短調、 交響曲ト長調「Azione teatrale campestre」 ジュゼッペ・ガッツァニーガ(1743-1818):交響曲ニ長調 アレッサンドロ・ロッラ(1757-1841):交響曲ニ長調 BI.533、交響曲ホ短調 BI.537 ジュゼッペ・ニコリーニ(1762-1842):交響曲変ロ長調 ステファノ・パヴェージ(1779-1850):交響曲変ロ長調 |
アタランタ・フーギエンスO、 ヴァンニ・モレット(指) ※全曲世界初録音 |
|
||
 ICA CLASSICS ICAB-5174(20CD) NX-L05 |
BBCレジェンズ グレート・レコーディングス
第4集 ■CD1&2 マーラー:交響曲第7番ホ短調 モーツァルト:交響曲第41番ハ長調 「ジュピター」* ■CD3 チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 レスピーギ:ローマの松 * ■CD4 シューベルト:ピアノ・ソナタ 第9番 ロ長調 Op.147D.575 ピアノ・ソナタ 第12番ヘ短調 D.625 ピアノ・ソナタ 第13番イ長調 Op.120D.664 楽興の時 Op.94D.780~第1番ハ長調 ■CD5 マーラー:交響曲第4番ト長調 ベルリオーズ:序曲「海賊」 ■CD6 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調「皇帝」 Op.73 モーツァルト:ピアノ協奏曲 第26番ニ長調「戴冠式」 K.537* ■CD7 リリ・ブーランジェ:詩篇 第24番 「全地は主のもの」 ピエ・イエズ 詩篇 第130番「深き淵より」 フォーレ:レクイエム Op.48 ■CD8 ブルックナー:交響曲第5番変ロ長調 WAB105 ■CD9 マーラー:さすらう若人の歌 若き日の歌 より* ドン・ファンの幻想/もう会えない!/春の朝/ 思い出 シュトラスブルクの砦に 10. 私は緑の野辺を楽しく歩いた 夏に小鳥はかわり(夏の歌い手交替す) いたずらっ子をしつけるために/うぬぼれ リュッケルト歌曲集 より 私は仄かな香りを吸い込んだ/私の歌を覗き見しないで 私はこの世に捨てられて/真夜中に ■CD10 グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調 Op.16 ドビュッシー:前奏曲集 第1巻 ■CD11 シューベルト:交響曲第8番ロ短調 「未完成」 ビゼー:小組曲 Op.22 ラヴェル:ダフニスとクロエ 第2組曲 シベリウス:交響曲第7番ハ長調 Op.105* ■CD12 ブリテン:戦争レクイエム ■CD13 リスト:ピアノ協奏曲 第1番** ピアノ協奏曲 第2番* メフィスト・ワルツ 第1番S.514a パガニーニの「鐘」による華麗な大幻想曲 S. 420# 超絶技巧練習曲集 S.139~XI. 「夕べの調べ」(1838年版)# ■CD14 リムスキー=コルサコフ:歌劇「ムラダ」 ~貴族の行進 交響組曲「シェエラザード」 スクリャービン:法悦の詩* ■CD15&16 ベートーヴェン:交響曲第8番ヘ長調 Op.93 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 ■CD17 モーツァルト:ホルン協奏曲 第3番変ホ長調 K.447 ブリテン:セレナーデ Op.31 シューマン:アダージョとアレグロ 変イ長調 Op.70# モーツァルト:ディヴェルティメント 第14番 変ロ長調 K.270(アンソニー・バインズ編曲 木管五重奏版) より* I. Allegro molto/ IV. Presto ミヨー:ルネ王の暖炉 ~VI. ヴァラブルでの狩り* ピーター・ラシーン・フリッカー(1920-1990):木管五重奏曲 Op.5## ■CD18 ティペット(1905-1998):二重弦楽合奏の為の協奏曲 ベルク:ヴァイオリン協奏曲「ある天使の想い出に」 ヤナーチェク:シンフォニエッタ* ■CD19 エルガー:チェロ協奏曲 ホ短調 Op.85* ブラームス:二重協奏曲 イ短調 Op.102** ドビュッシー:チェロ・ソナタ ニ短調 CD144 ■CD20 ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第29番「ハンマークラヴィーア」 ピアノ・ソナタ 第31番変イ長調 Op.110* |
■CD1&2 クラウス・テンシュテット(指)LPO 録音:1980年8月29日 アッシャー・ホール、エディンバラ 1985年9月13日 ロイヤル・アルバート・ホール*(STEREO ADD) ■CD3 コンスタンティン・シルヴェストリ(指)ボーンマスSO 録音:1963年2月22日 ウィンター・ガーデンズ、ボーンマス、1967年9月20日コルストン・ホール、ブリストル* (STEREO ADD) ■CD4 スヴャトスラフ・リヒテル(P) 録音:1979年3月31日 ロイヤル・フェスティバル・ホール(STEREO ADD) ■CD5 ヘザー・ハーパー(S)、ジョン・バルビローリ(指)BBC響 録音:1967年1月3日 スメタナ・ホール、プラハ(STEREO ADD) ■CD6 クリフォード・カーゾン(P)、ピエール・ブーレーズ(指)BBC響 録音:1971年2月17日 ロイヤル・フェスティバル・ホール 1974年8月14日 ロイヤル・アルバート・ホール*(STEREO ADD) ■CD7 ジャネット・プライス(S)、バーナデット・グリーヴィ(C.A)、イアン・パートリッジ(T)、ジョン・キャロル・ケース(Br)、BBC交響cho、BBC響、ナディア・ブーランジェ(指) 録音:1968年10月30日 フェアフィールド・ホールズ、クロイドン(STEREO ADD) ■CD8 ヤッシャ・ホーレンシュタイン(指)BBC響 録音:1971年9月15日 ロイヤル・アルバート・ホール(STEREO ADD) ■CD9 ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(Br)、カール・エンゲル(P)録音:1970年2月16日 ロイヤル・フェスティバル・ホール(STEREO ADD) ■CD10 アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(P)、ラファエル・ブリューベック・デ・ブルゴス(指)ニュー・フィルハーモニアO 録音:1965年6月17日(MONO ADD)*、1982年4月13日 (STEREO ADD) ■CD11 エイドリアン・ボールト(指)フィルハーモニアO、ロイヤルPO* 録音:1963年3月8日 ロイヤル・フェスティバル・ホール*、1964年7月30日 ロイヤル・アルバート・ホール・プロムナード・コンサート(STEREO ADD) ■CD12 ステファニア・ヴォイトヴィチ(S)、ピーター・ピアーズ(T)、ハンス・ヴィルブリンク(Br)、メロス・アンサンブル、ウォンズワース・スクール少年cho、ニュー・フィルハーモニアO&cho、 カルロ・マリア・ジュリーニ(指) 録音:1969年4月6日 ロイヤル・アルバート・ホール(STEREO ADD) ■CD13 ジョン・オグドン(P)、コンスタンティン・シルヴェストリ(指)ボーンマスSO**、コリン・デイヴィス(指)BBC響* 録音:1967年9月20日 コルストン・ホール、ブリストル**、1969年4月24日クイーン・エリザベス・ホール、1971年9月18日 ロイヤル・アルバート・ホール*(STEREO ADD) 1970年1月20日 BBCスタジオ#((MONO ADD)) ■CD14 ジョン・ジョージアディス(Vnソロ)、エフゲニー・スヴェトラーノフ(指)LSO、ソヴィエト国立SO* 録音:1968年8月22日 ロイヤル・アルバート・ホール*、1978年2月21日 ロイヤル・フェスティバル・ホール(STEREO ADD) ■CD15&16 ヘザー・ハーパー(S)、ジャネット・ベイカー(Ms)、ロナルド・ダウド(T)、フランツ・クラス(Bs)、ニュー・フィルハーモニアcho、ジョージ・セル(指)ニュー・フィルハーモニアO 録音:1968年11月12日 ロイヤル・フェスティバル・ホール(MONO ADD)※ポール・ベイリーによる新リマスター ■CD17 デニス・ブレイン(Hrn)、ピーター・ピアーズ(T)、ベンジャミン・ブリテン(P)、マルコム・サージェント(指)BBC響、ジョン・ホリングスワース(指)、デニス・ブレイン木管五重奏団 録音:1953年7月30日 ロイヤル・アルバート・ホール、1956年6月19日 BBCスタジオ*、1956年6月21日 オールドバラ教区教会、オールドバラ音楽祭#、1957年8月24日 フリーメイソン・ホール、エディンバラ音楽祭##(MONO ADD) ■CD18 エディト・パイネマン(Vn)、ルドルフ・ケンペ(指)BBC響 録音:1975年10月12日 フェアフィールド・ホールズ、クライドン*、1976年2月18日 ロイヤル・フェスティバル・ホール(STEREO ADD) ■CD19 ポール・トルトゥリエ(Vc)、ヤン・パスカル・トルトゥリエ(Vn)、アーネスト・ラッシュ(P)、エイドリアン・ボールト(指)*、ジョン・プリッチャード(指)BBC響 録音:1959年2月10日BBCスタジオ、1972年11月14日* 1974年4月17日** ロイヤル・フェスティバル・ホール(STEREO ADD) ■CD20 ルドルフ・ゼルキン(P) 録音:1968年5月13日(MONO ADD)、1971年6月16日(STEREO ADD)* ロイヤル・フェスティバル・ホール |
|
||
| Altus ALTL-016(2CD) |
アイヴズ:答えのない質問 ヴォーン・ウィリアムズ:トマス・タリスの主題による幻想曲 マーラー:交響曲第2番『復活』* |
中江早希(S)*、谷地畝晶子(A)* 東京ユヴェントス・フィルハーモニーcho* 坂入健司郎(指) 東京ユヴェントス・フィルハーモニー ライヴ録音:2022年1月15日/ミューザ川崎シンフォニーホール |
|
||
| MDG MDG-91222656(1SACD) |
メンデルスゾーン・プロジェクトVOL.4 シンフォニア第8番ニ長調 シンフォニア第9番ハ長調 シンフォニア第10番ロ短調 |
ドグマ室内オーケストラ ミハイル・グレヴィチ(指) 録音:2021年5月17-21日、マリエンミュンスター修道院コンツェルトハウス |
|
||
| BR KLASSIK BR-900212(2CD) NX-B09 |
ブルックナー:テ・デウム ハ長調 交響曲第8番(第2稿 ハース版) |
バイエルンRSO ベルナルト・ハイティンク(指) 録音:2010年11月10-12日 ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ライヴ)…テ・デウム 1993年12月15-17日 ミュンヘン、ヘルクレス・ザール(ライヴ)…交響曲第8番 |
|
||
| CPO CPO-555572(1CD) NX-B10 |
ヒューゴ・カウン(1863-1932):交響的作品集 交響詩「ミネハハ」 Op.43-1 交響詩「ハイアワサ」 Op.43-2 交響曲第3番ホ短調 Op.96 |
ベルリンRSO ジョナサン・シュトックハンマー(指) 録音:2022年5月31日-6月3日 |
|
||
| GENUIN GEN-23848(1CD) |
ベートーヴェン:「献堂式」序曲 チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調 Op.64 アンドレス・ロイカウフ(b.1972):南ヴェストファーレン=ファンファーレ(世界初録音) |
南ヴェストファーレン・フィルハーモニー、 ナビル・シェハタ(指) 録音:2021年5月18日-20日、ベッツドルフ市立ホール(ドイツ) |
|
||
| Onyx ONYX-4232(1CD) PONYX-4232(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ロベルト・シエッラ:交響曲第6番 シエッラ:交響曲第6番 弦楽オーケストラのためのシンフォニエッタアレグリア/ファンダンゴズ オーケストラのための2つの小品 |
ドミンゴ・インドヤン(指)、 ロイヤル・リヴァプールPO 録音:2021年10月14日&16日(交響曲第6番、ライヴ)&2022年5月20日(アレグリア、2つのオーケストラのための小品、ファンダンゴズ)、リヴァプール・フィルハーモニー・ホール(イギリス) 2022年6月10日(弦楽オーケストラのためのシンフォニエッタ)、フライアリー(イギリス) |
|
||
| Urania Records WS-121412(2CD) |
ドヴォルザーク:交響曲集 (1)交響曲第7番ニ短調 Op.70 (2)交響曲第8番ト長調 Op.88 (3)交響曲第9番「新世界より」 (4)スケルツォ・カプリチオーソ Op.66 (5)伝説 Op.59より第4番、第6番、第7番 |
ジョン・バルビローリ(指)ハレO (1)録音:1957年8月8日、マンチェスター (2)録音:1957年6月、マンチェスター (3)録音:1959年4月、マンチェスター (4)録音:1958年9月、マンチェスター (5)録音:1958年9月、マンチェスター |
|
||
| Signum Classics SIGCD-759(1CD) |
疾風怒濤 Vol.3 モーツァルト:アダージョとフーガ ハ短調 K.546 シュヴァイツァー:歌劇「アルチェステ」より「Er ist gekommen… Zwischen Angst und zwischen Hoffen」 コジェルフ:交響曲 ト短調 パイジェッロ:歌劇「トリノのハンニバル」より「Misera, ch’ei peri!... Smarrita, tremante」 ハイドン:交響曲第44番 ホ短調「悲しみ」 |
モーツァルティスツ、 イアン・ペイジ(指)、 エミリー・ポゴレルツ(S) 録音:2023年1月、セント・ジョンズ・スミス・スクエア(イギリス、ロンドン) |
|
||
| ALTO ALC-1491(1CD) |
バーナード・ハーマン:交響曲第1番 交響曲第1番* Concerto Macabre(Pと管弦楽の為の) 堕落者のために/組曲「The Devil and Daniel Webster」 |
ジェームズ・セダレス(指)、 フェニックスSO* 、ニュージーランドSO 録音:1992年-1995年 |
|
||
| ALTO ALC-1494(1CD) |
グレツキ:交響曲第3番「悲歌のシンフォニー」 古風な3つの小品/すべてあなたのもの |
ヴウォジミエシュ・カミルスキ(指) ベルリンRSO、 ステファニア・ヴォイトヴィチ(S)、他 録音:1982年&1996年 |
|
||
| LSO Live LSO-0887(1SACD) |
ブルックナー:交響曲第7番ホ長調 WAB107 (Version1881?83;
Cohrs A07) 〔ベンヤミン=グンナー・コールス校訂版(2015年)による世界初録音〕 |
サイモン・ラトル(指)LSO 録音:2022年9月18日&12月1日、バービカン・ホール |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00823(1SACD) 税込定価 2023年9月27日発売 |
ショスタコーヴィチ:交響曲第4番 ハ短調 作品43 | ジョナサン・ノット(指)東京SO 録音:2022年10月16日ミューザ川崎シンフォニーホール・ライヴ |
|
||
 オクタヴィア OVCL-00827(1SACD) 税込定価 2023年9月27日発売 |
チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 作品64 | 小林研一郎(指) コバケンとその仲間たちオーケストラ 録音:2023年6月25日 東京・サントリーホール・ライヴ |
|
||
| H.M.F HMM-902703(1CD) |
モーツァルト:交響曲第36番「リンツ」 交響曲第38番「プラハ」 |
アンサンブル・レゾナンツ、 リッカルド・ミナージ(指) 録音:2021年9月オトマールシェン・キリスト教会(ハンブルク) |
|
||
| H.M.F HAF-8932276(1CD) |
王妃のハープ~マリー・アントワネットの宮廷の音楽 ジャン=バティスト・クルムフォルツ(1747-1790):ハープ協奏曲 第5番op.7変ロ長調(1778) ハイドン:交響曲第85番「王妃」Hob.I:85(1785) ヨハン・ダヴィド・ヘルマン(1760?-1846):ハープとオーケストラの為の協奏曲第1番 op.9ヘ長調(1785-1789) グルック:「精霊の踊り」~オルフェオとエウリディーチェより(編):メストレ) |
グザヴィエ・ドゥ・メストレ(Hp) ウィリアム・クリスティ(指)、 レザール・フロリサン 録音:2016年6月27,28日、ヴェルサイユ宮殿王立歌劇場(ライヴ) |
|
||
| RCO Live RCO-23001(9CD) |
ブルックナー:交響曲全集 (1)交響曲第1番ハ短調 WAB101(1877年リンツ稿、ハース校訂1935年出版)※ (2)交響曲第2番ハ短調,WAB102(1872/1877年稿、ハース校訂1938年出版)※ (3)交響曲第3番ニ短調 WAB103(1889年稿、ノーヴァク校訂1959年出版) (4)交響曲第4番変ホ長調『ロマンティック』(1880年第2稿、ハース校訂1936年出版)※ (5)交響曲第5番変ロ長調WAB105(1878年稿、ノーヴァク校訂1951年出版) (6)交響曲第6番イ長調 WAB106(1881年稿、ノーヴァク校訂1952年出版) (7)交響曲第7番ホ長調 WAB107(1885年稿、ノーヴァク校訂1954年出版)※ (8)交響曲第8番ハ短調,WAB108(1890年稿、ノーヴァク校訂1955年出版) (9)交響曲第9番ニ短調 WAB109(1894年原典版、ノーヴァク校訂1951年出版)※ |
ロイヤル・コンセルトヘボウO 録音場所:すべてアムステルダム・コンセルトヘボウ (1)ベルナルド・ハイティンク(指) 録音:1972年2月10日(NOS) (2)リッカルド・シャイー(指) 録音:1990年4月29日(NSO & RNW) (3クルト・ザンデルリング(指) 録音:1996年11月8日(NOS) (4)クラウス・テンシュテット(指) 録音:1982年10月28日(NOS) (5)オイゲン・ヨッフム(指) 録音:1986年12月4日(NOS) (6)マリス・ヤンソンス(指) 録音:2012年3月7-9日(AVRO) (7)ベルナルド・ハイティンク(指) 録音:2006年4月2日(AVRO) (8)ズービン・メータ(指) 録音:2005年12月2日(AVRO) (9)リッカルド・シャイー(指) 録音:1996年6月6日(AVRO & RNW) ※初出 |
|
||
| ACCENT ACC-24394(1CD) |
アーベル(1723-1787):後期交響曲集 交響曲 ハ長調 WKO37* 交響曲 変ロ長調 WKO38* 協奏交響曲 ニ長調 WKO43(独奏:ヴァイオリン、オーボエ、チェロ) 交響曲 変ホ長調 WKO39* 交響曲 ニ長調 WKO41* |
マルティン・ヨップ(Vn 、指 ) マイン・バロックオーケストラ 録音:2022年10月1-4日ドイツ、イトシュタイン、ユニオン教会 *世界初録音 |
|
||
| Chandos CHAN-20165(1CD) XCHAN-20165(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ミェチスワフ・ヴァインベルク(1919-1996):夜明け Op.60(世界初録音) 交響曲第12番Op.114「ショスタコーヴィチの思い出に」 |
ヨン・ストゥールゴールズ(指)、 BBCフィルハーモニック 録音:2022年9月15日&11月24日-25日(第12番)、メディア・シティUK(サルフォード) |
|
||
 Epitagraph EPITA-042(1CD) (UHQCD) 限定発売 |
世界初!アセテート盤から復刻! ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 |
グレ・ブロウエンスタイン(S)、イーラ・マラニウク
(A)、ヴォルフガンク・ヴィントガッセン (T)、ルートヴィヒ・ウェーバー(Bs)
バイロイト祝祭O&cho ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) 録音:1954年8月9日、バイロイト祝祭劇場(ライヴ) |
|
||
| Pentatone PTC-5187059(1CD) |
モーツァルト:交響曲第35番「ハフナー」 .歌劇『後宮からの誘拐』K.384(作曲者自身によるハルモニームジーク版)より「序曲」 オーボエ協奏曲 ハ長調 K.271k/K.314* 交響曲第31番ニ長調 K.297/300a「パリ」 交響曲第31番より第2楽章「アンダンテ」の初稿版 |
クセニア・レフラー(Ob)* ベルリン古楽アカデミー ベルンハルト・フォルク(コンサートマスター) 録音:2022年9月27~29日アルト=ブリッツ、クルトゥーアシュタール(ベルリン) |
|
||
| Chateau de Versailles Spectacles CVS-094(1CD) |
ハイドン:交響曲「朝」「昼」「晩」 ハイドン:交響曲第6番ニ長調 「朝」Hob.I:6 交響曲第7番ハ長調 「昼」Hob.I:7 グルック:精霊の踊り(歌劇「オルフェとユリディス」〔「オルフェオとエウリディーチェ」パリ版〕より) ハイドン:交響曲第8番ト長調 「晩」Hob.I:8 |
ヴェルサイユ王室歌劇場O(古楽器使用) ステファン・プレフニャク(指) 録音:2022年6月1-6日ヴェルサイユ宮殿「十字軍の大広間」 |
|
||
| Orchid Classics ORC-100257(1CD) NX-B03 |
シューマン41/51 シューマン:交響曲第4番ニ短調 (1)初稿(1841) (2)改訂版 Op.120(1851) |
ブカレストSO ジョン・アクセルロッド(指) 録音:2023年3月18-21日 |
|
||
| Altus ALT-531(1CD) |
ブルックナー:交響曲第7番 ホ長調 WAB.107(ノヴァーク版) | ロー ター・ツァグロゼク(指) 読売日本SO ライヴ録音:2019年2月22日/サントリーホール |
|
||
| Altus ALT-532(1CD) |
モーツァルト:歌劇『フィガロの結婚』 序曲 ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 Op.68 |
坂入健司郎 (指) 読売日本SO ライヴ録音:2022年4月29日読響創立60周年記念・甲府特別演奏会 YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール) |
|
||
| Hanssler HC-23050(2CD) |
ヘルヴィ・レイヴィスカ(1902-1982):ピアノ協奏曲 ニ短調 Op.7(1935) 交響曲第1番変ロ長調 Op.23(1947) |
オリヴァー・トリンドル(P) シュターツカペレ・ワイマール 、 アリ・ラシライネン(指) ン録音:2023年4月24~27日/オーケストラ練習ホール、ワイマール(ドイツ) |
|
||
| Arte dellarco Japan ADJ-070(1CD) |
オーケストラ・リベラ・クラシカ(OLC)第41回定期演奏会 ハイドン:交響曲第3番ト長調 Hob.I:3 交響曲第102番変ロ長調 Hob.I:102 ベートーヴェン:交響曲第8番へ長調 Op.93 |
鈴木秀美(指) オーケストラ・リベラ・クラシカ ライヴ録音:2018年6月23日/三鷹市芸術文化センター 風のホール |
|
||
| Onyx ONYX-4243(1CD) 日本語解説付き限定盤 |
チャイコフスキー:交響曲第6番ロ短調 作品74 「悲愴」 | ドミンゴ・インドヤン(指)、 イヤル・リヴァプールPO 録音(ライヴ):2021年11月18日&21日 |
|
||
| ODRADEK RECORDS ODRCD-440(2CD) |
マーラー:交響曲全集Vol.1 (1)スカラタッツィーニ(b.1971):魔力 (2)マーラー:交響曲第4番ト長調 (3)スカラタッツィーニ:調和 (4)マーラー:交響曲第5番嬰ハ短調 |
ジモン・ガウデンツ(指) イェナ・フィルハーモニー (2)リナ・ジョンソン(S) 録音:(1)(2)2022年4月27-30日、 (3)(4)2022 年5月17-20日 |
|
||
| GRAND SLAM GS-2300(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 | イルムガルト・ゼーフリート(S) ロゼッテ・アンダイ(A) アントン・デルモータ(T) パウル・シェフラー(Bs) ウィーン・ジングアカデミーcho ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)VPO 録音:1953年5月31日/ムジークフェラインザール(ウィーン) 使用音源:Private archive(2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(ラジオ放送用録音) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2301(1CD) |
(1)シューマン:交響曲第4番ニ短調 Op.120 (2)バッハ:管弦楽組曲第3番ニ長調 BWV1068 (3)ベートーヴェン:交響曲第8番ヘ長調 Op.98 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)BPO 録音:(1)1953年5月14日ベルリン=ダーレム、イエス・キリスト教会 (2)1948年10月24日、(3)1953年4月14日/ベルリン、ティタニア・パラスト 使用音源:Private archive (1)(2)(2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) (3)(2トラック、19センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(録音セッション)(1)、(ラジオ放送用録音)(2)(3) |
|
||
| Goodies 78CDR-3914(1CDR) |
ブラームス:交響曲第2番ニ長調作品73 | ピエール・モントゥー(指) サン・フランシスコSO 米 VICTOR11-9237/40 1945年3月19日サン・フランシスコ録音 |
|
||
| MClassics MYCL-00045(1SACD) 税込定価 |
シベリウス:交響曲第3番ハ長調 カレリア組曲 交響詩「フィンランディア」 |
村川千秋(指)山形SO 録音:2022年4月16-17日 山形テルサホール、2023年1月15日 山形・やまぎん県民ホール 大ホール・ライヴ |
|
||
| Dynamic DYNDVD-37950(3DVD) NX-D05 DYNBRD-57950(2Bluray) NX-D05 |
ベートーヴェン:交響曲全集 【DVD】 Disc1…交響曲第1番-第3番 Disc2…交響曲第4番-第6番 Disc3…交響曲第7番-第9番 【Blu-ray】 Disc1…交響曲第1番-第5番 Disc2…交響曲第6番-第9番 |
フィレンツェ五月音楽祭O マンディ・フレドリッヒ(S) マリー・クロード・シャピュイ(Ms) AJ. グリュッカート(T) タレク・ナズミ(Bs) フィレンツェ五月音楽祭cho ズービン・メータ(指) 収録:2021年9月-10月、2022年9月フィレンツェ五月音楽祭歌劇場(イタリア) 収録時間:382分 音声:ドイツ語(交響曲第9番のみ) PCMステレオ2.0/DTS5.1(DVD) PCMステレオ2.0/DTS-HD Master Audio5.1(Blu-ray) 字幕:なし 画角:16/9 NTSC All Region DVD…片面ニ層ディスク×3 Blu-ray…片面ニ層ディスク×2 1080i High Definition |
|
||
| DynamicCDS-7950(5CD) NX-D05 |
ベートーヴェン:交響曲全集(全9曲) | フィレンツェ五月音楽祭O マンディ・フレドリッヒ(S) マリー・クロード・シャピュイ(Ms) AJ. グリュッカート(T) タレク・ナズミ(Bs) フィレンツェ五月音楽祭cho ズービン・メータ(指) 収録:2021年9月-10月、2022年9月フィレンツェ五月音楽祭歌劇場(イタリア) |
|
||
| ANALEKTA AN-28884(2CD) NX-D09 |
クララ、ロベルト、ヨハネス ~ロマンスと対位法 シューマン:交響曲第4番ニ短調 Op.120 クララ・シューマン:3つのロマンス ~ヴァイオリンとピアノの為の Op.22* 3つのロマンス ~ピアノの為の Op.11 ロマンス ロ短調 ブラームス:交響曲第4番ホ短調 Op.98 C.シューマン:ゼバスティアン・バッハの主題による3つのフーガ 前奏曲とフーガ 嬰へ短調 3つの前奏曲とフーガ Op.16 スチュワート・グッドイヤー(1978-):クララ・シューマンの主題による即興 |
ナショナル・アーツ・センターO アレクサンダー・シェリー(指) スチュワート・グッドイヤー(P) アンジェラ・ヒューイット(P) * 川崎洋介(Vn) * 録音:2019-2023年 |
|
||
| ICA CLASSICS ICAC-5172(1CD) NX-B03 |
ベルリオーズ:劇的交響曲「ロメオとジュリエット」 H.76より 争い - 騒動 - 領主の仲裁 ロメオ一人 - 哀しみ - 遠くから聞こえる音楽と舞踏会 - キャピュレット家の饗宴 愛の場面 - 夜 - キャピュレット家の庭 スケルツォ ~「女王マブ」 キャピュレット家の墓のロメオ - 祈り - ジュリエットの目覚め -忘我の喜び、絶望 - 最後の苦しみと恋人たちの死 スクリャービン:法悦の詩* |
BBC響&cho LSO* ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー(指) 録音:1976年1月24日 ロイヤル・フェスティバル・ホール* 1981年4月1日 ロイヤル・アルバート・ホール いずれもライヴ、ステレオ |
|
||
| DB Productions DBCD-210(1CD) NX-B07 |
メンデルスゾーン:交響曲第3番 イ短調 Op.56「スコットランド」 ヘレン・グライム(1981-):Elegiac Inflections ピーター・マックスウェル・デイヴィス(1934-2016):ストラスクライド協奏曲第10番 Op.179 |
ヴェステロース・シンフォニエッタ サイモン・クロフォード=フィリップス(指) 録音:2022年6月13-17日 |
|
||
| VOX VOXNX-3021CD(1CD) NX-B03 |
チャイコフスキー:交響曲第3番「ポーランド」 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」 |
ユタSO モーリス・アブラヴァネル(指) 録音:1972-73年 1974年LP初リリース |
|
||
| VOX VOXNX-3025CD(1CD) NX-B03 |
チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 スラヴ行進曲 |
ユタSO モーリス・アブラヴァネル(指) 録音:1972-73年 1974年LP初リリース |
|
||
| Signum Classics SIGCD-760(2CD) |
マーラー:交響曲第2番「復活」 | サントゥ=マティアス・ロウヴァリ(指) フィルハーモニアO、 マーリ・エーリクスモーエン(S)、 ジェニファー・ジョンストン(Ms)、 フィルハーモニアcho ライヴ録音:2022年6月8日、サウスバンク・センターズ・ロイヤル・フェスティヴァル・ホール |
|
||
| DUX DUX-1897(1CD) |
ジェジュン・リュウ(b.1970):交響曲第2番(世界初録音) | スンヘ・イム(S)、ミョンジュ・イ(S)、ジョンミ・キム(Ms)、オリヴァー・クック(T)、サミュエル・ユン(Bs-Br) ラルフ・ゴトーニ(指) 韓国国立cho、スウォン市cho、ソウル国際音楽祭O 録音:2021年10月22日 |
|
||
| Gutman Records GUTMANCD-173(1CD) JGUTMANCD-173(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
マーラー:交響曲第4番ト長調(エルヴィン・シュタイン編曲室内アンサンブル版) | カメラータRCO、 ルーカス・マシアス・ナバロ(指)、 ユディト・ファン・ヴァンロイ(S) 録音:2017年5月18日-20日、MCO(ヒルフェルスム、オランダ) |
|
||
| Gutman Records GUTMANCD-150(2CD) ★ JGUTMANCD-150(2CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 ★ |
マーラー:交響曲第9番ニ長調(クラウス・ジモン編曲室内アンサンブル版) | カメラータRCO、 グスターボ・ヒメノ(指) 録音:2014年6月27日-29日、MCO(ヒルフェルスム、オランダ) |
|
||
| Gutman Records GUTMANCD-211(1CD) JGUTMANCD-211(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ブルックナー:交響曲第7番ホ長調(アンサンブル版) | カメラータRCO、 オリヴィエ・パテイ(指) 録音:2019年10月6日、聖バーフ大聖堂(ハーレム、オランダ) |
|
||
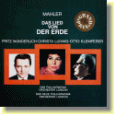 Treasures TRE-293(1CDR) |
超厳選!赤盤名演集Vol.11~クレンペラーの「大地の歌」 マーラー:大地の歌 |
フリッツ・ヴンダーリッヒ(T) クリスタ・ルートヴィッヒ(Ms) オットー・クレンペラー(指) フィルハーモニアO、ニュー・フィルハーモニアO 録音:1964年2月&1966年7月(ステレオ) ※音源:東芝 AA-8100 ◎収録時間:63:53 |
| “永遠に光り続ける普遍的芸術の象徴!” | ||
|
||
| ALIA VOX AVSA-9955(1SACD) |
メンデルスゾーン:交響曲第4番「イタリア」 1-4最終稿(1834年) 5-8初稿(1833年) |
ジョルディ・サヴァール(指) ル・コンセール・デ・ナシオン〈リナ・トゥール・ボネ(コンサートミストレス)〉 録音:2022年10月26-28日、カタルーニャ自治州カルドーナ城参事会教会 |
|
||
| GRAND SLAM GS-2297(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」 | ブルーノ・ワルター(指)コロンビアSO 録音:1958年1月13、15、17日/カリフォルニア、アメリカン・リージョン・ホール 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:ステレオ(録音セッション) |
|
||
| C Major 80-9504(5Bluray) |
ブルックナー:交響曲全集 ■BD1 交響曲ヘ短調WAB99(第00番「習作」) 交響曲ニ短調WAB100(第0番) 交響曲第5番変ロ長調WAB105 ■BD2 交響曲第1番ハ短調 WAB101(ウィーン稿) 交響曲第7番ホ長調 WAB107(ノーヴァク版) ■BD3 交響曲第2番ハ短調,WAB102(第2稿/1877年) 交響曲第8番ハ短調,WAB108(ハース版/1939年) ■BD4 交響曲第3番ニ短調 WAB103(1877年第2稿・ノーヴァク版) 交響曲第6番イ長調 WAB106 ■BD5 交響曲第4番変ホ長調『ロマンティック』(1880年第2稿 ハース校訂 1936年出版) 交響曲第9番ニ短調 WAB109(原典版 新全集IX、1951年出版 ノーヴァク校訂) ●ボーナス映像「ディスカヴァリング・ブルックナー」(日本語字幕付) 各交響曲について(ティーレマンと音楽学者ヨハネス=レオポルド・マイヤー氏による対話) |
クリスティアン・ティーレマン(指) VPO ■BD1 収録:2021年3月ウィーン楽友協会(無観客ライヴ) ■BD2 収録:2021年2月、ウィーン楽友協会(無観客ライヴ)(第1番)、8月、ザルツブルク音楽祭(ライヴ)(第7番) ・マルツァー(第7番) ■BD3 収録:2019年4月(第2番)、10月(第8番)、ウィーン楽友協会(ライヴ) ■BD4 収録:2020年11月(第3番)、2022年4月(第6番)、ウィーン楽友協会(ライヴ) ■BD5 収録:2020年8月、ザルツブルク祝祭大劇場、ライヴ(第4番)、2022年7月、ザルツブルク祝祭大劇場、ライヴ(第9番) 画面:16:9、1080i 音声:PCMステレオ、DTS-HD MA5.0 ■BD50 [ボーナス映像 ] 言語:ドイツ語、字幕:英韓,日本語 総収録時間:1018分 |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00824(1SACD) 税込定価 2023年8月23日発売 |
ハイドン:交響曲第69番ハ長調 Hob.I:69「ラウドン将軍」 交響曲第71番変ロ長調 Hob.I:71 交響曲第53番ニ長調 Hob. I:53「帝国」 |
飯森範親(指) 日本センチュリーSO 録音:2021年9月30日(第69番、第71番)、2022年5月26日(第53番) 大阪、ザ・シンフォニーホール・ライヴ |
|
||
| ALPHA ALPHA-694(1CD) NYCX-10417(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ハイドン交響曲全曲録音シリーズ Vol.14~帝国の響き 交響曲第53番ニ長調 Hob. I:53「帝国」 交響曲第54番ト長調 Hob. I:54 交響曲第33番ハ長調 Hob. I:33 序曲 ニ長調 Hob. Ia:7(人形音楽劇『ゲノフェーファ 第4部』〔本編は音楽消失〕の為の序曲、交響曲第53番の異版終楽章に転用) |
バーゼル室内O(古楽器使用) ジョヴァンニ・アントニーニ(指) 録音:2021年3月-10月ドン・ボスコ、バーゼル、スイス |
|
||
| Capriccio C-8089(1CD) NX-B07 NYCX-10414(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
ブルックナー:交響曲第2番ハ短調(第2稿/ホークショー版) | リンツ・ブルックナーO マルクス・ポシュナー(指) 録音:2022年2月1日リンツ・ミュージックシアター、リハーサル・ホール(オーストリア) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2298(1CD) |
モーツァルト:交響曲第39番変ホ長調 K.543 チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」* |
ヴイルヘルム・フルトヴェングラー(指)BPO 録音:1942年または1943年ベルリン、1951年4月19日または22日カイロ * 使用音源:Private archive(2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(ラジオ放送用録音) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2296(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 リハーサル風景(交響曲第7番の第2楽章より)* |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) BPO ルツェルン祝祭O* 録音:1952年12月7日ベルリン、ティタニア・パラスト、 1951年8月15日ルツェルン、クンストハウス * 使用音源:Private archive(2トラック、19センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(ラジオ放送用録音) |
|
||
| GENUIN GEN-23818(1CD) XGEN-23818(1CD) 日本語解説付国内盤 税込定価 |
マーラー:交響曲第2番「復活」(室内楽版)(ブルーノ・ワルターの4手ピアノ版を基にした、2台ピアノ、ソプラノ&アルト独唱、トランペットと合唱のための編曲版 | グレゴール・マイヤー(P)、ヴァルター・ツォラー(P)、アンニカ・シュタインバッハ(S)、ヘンリエッテ・ゲッデ(A)、エマヌエル・ミュッツェ(Tp)、ゲヴァントハウスcho、フランク=シュテッフェン・エルスター(指) 録音:2021年12月21日、2022年2月3日-4日&5月9日-10日、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス(ドイツ) |
|
||
| DUX DUX-1844(1CD) |
ウカシェフスキ:交響曲第1番&第2番 パヴェウ・ウカシェフスキ(1968-):交響曲第1番「摂理の交響曲」~ソプラノ、メゾソプラノ、バリトン、混声合唱と管弦楽のための 交響曲第2番「Festinemus amare homines」~ソプラノ、2台のピアノ、合唱と交響楽のための* |
マルチン・ナウェンチ=ニェショウォフスキ(指)、ピオトル・ボルコフスキ(指)*、ポドラシェ歌劇場PO、ポドラシェ歌劇場フィルハーモニーcho、アンナ・ミコワイチク=ニェヴィエジャウ(S)、ラヴェル・ピアノ・デュオほか 録音:2007年(第2番)、2009年12月(第1番) |
|
||
| Danacord DACOC-D-926(2CDR) ★ |
トマス・イェンセンの遺産 第16集 (1) シベリウス:交響曲第5番 (2)シベリウス:交響曲第6番 (3)シベリウス:抒情的なワルツ Op.96a、悲しきワルツ (4)スメタナ:モルダウ (5)ラウリツ・ラウリトセン(1882-1946):小組曲(弦楽オーケストラのための) エアリング・ブレーネ(1896-1980):コンチェルト・センツァ・ソレンニタ(厳粛さのない協奏曲) Op.20(フルートと管弦楽のための)* (6)ポウル・シアベク(1888-1949):ヴァイキングの歌 Op.22(テノールと管弦楽のための)**、 歌劇「華麗なる宴」 Op.25より「序曲」、 大学入学式のカンタータ Op.16、 大学入学式の大学祝典音楽 Op.17 (7)ニールセン:交響曲第2番「四つの気質」 |
トマス・イェンセン(指)、 デンマークRSO、 ヨハン・ベンソン(Fl)*、 ニルス・ムラー(T)** (1)録音:1957年5月14日(放送録音) (2)録音:1962年11月25日(放送) (3)録音:1947年6月25日(スタジオ録音 (4)録音:1947年6月25日(スタジオ録音)] (5)録音:1962年2月13日(ライヴ放送) (6)録音:1963年6月8日(ライヴ放送) (7)録音:1944年3月17日(スタジオ録音) |
|
||
| Danacord DACOC-D-927(2CDR) ★ |
トマス・イェンセンの遺産 第17集 (1)ベートーヴェン:交響曲第4番 (2)交響曲第6番ヘ長調 Op.68「田園」 (3)ハイドン:交響曲第104番「ロンドン」* (4ベートーヴェン:序曲「レオノーレ」第3番** (5ブラームス:ヴァイオリン協奏曲*** |
トマス・イェンセン(指)、 デンマークRSO、 オーフス市立O*、 ティヴォリ・コンサートホールSO**、 アイザック・スターン(Vn)*** (1)録音:1962年5月2日(ライヴ放送) (2)録音:1962年8月8日(ライヴ放送) (3)録音:1955年12月20日(ライヴ放送) (4)録音:1942年秋(スタジオ録音) (5)録音:1961年11月30日(ライヴ放送) |
|
||
| Onyx ONYX-4237(1CD) |
ミェチスワフ・ヴァインベルク(1919-1996):チェロ・コンチェルティーノ Op.43 ヴァイオリン・コンチェルティーノ Op.42 モルドバの主題によるラプソディ Op.47-3 交響曲第7番Op.81 |
ウェン=シン・ヤン(Vc)、 タッシロ・プロプスト(Vn)、 ミュンヘン・ユダヤ室内O、 ダニエル・グロスマン(指) |
|
||
 REFERENCE FR-752SACD(1SACD) |
チャイコフスキー:交響曲第5番 シュルホフ(1894?1942):弦楽四重奏のための5つの小品(ホーネック編) |
ピッツバーグSO マンフレート・ホーネック(指) 録音:2022年6月17-19、ハインツホール、ピッツバーグ(ライヴ) |
|
||
| ALPHA ALPHA-987(1CD) |
ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 WAB108 ノーヴァク版 第2稿(1890) | チューリヒ・トーンハレO パーヴォ・ヤルヴィ(指) 録音:2022年9月 トーンハレ、チューリヒ 収録時間:81分 |
|
||
| BR KLASSIK BR-900213(1CD) NX-B07 |
ブルックナー:交響曲第4番(第2稿1878/80) | バイエルンRSO ベルナルト・ハイティンク(指) 録音:2012年1月19日&20日 ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ライヴ) |
|
||
| VOX VOXNX-3020CD(1CD) NX-B03 |
チャイコフスキー:交響曲第1番 交響曲第2番ハ短調「小ロシア」 |
ユタSO モーリス・アブラヴァネル(指) 録音:1972-73年 1974年LP初リリース |
|
||
| VOX VOXNX-3024CD(1CD) NX-B03 |
チャイコフスキー:交響曲第6番ロ短調「悲愴」 5. 幻想序曲「ハムレット」 |
ユタSO モーリス・アブラヴァネル(指) 録音:1972-73年 1974年LP初リリース |
|
||
| Pentatone PTC-5187043(1CD) |
マーラー:交響曲第1番ニ長調「巨人」 | セミヨン・ビシュコフ(指) チェコPO 録音:2021年10月12~15日ルドルフィヌム、ドヴォルザーク・ホール(プラハ) |
|
||
 PROMINENT CLASSICS 2506-5616(3CD) |
ブラームス:交響曲全集 ■Disc1 交響曲第1番ハ短調Op.68 ハンガリー舞曲集(第1番、第3番、第4番、第5番) ■Disc2 交響曲第3番へ長調Op.90 交響曲第2番ニ長調Op.73 ■Disc3 ピアノ四重奏曲第1番(シェーンベルク編) 交響曲第4番ホ短調Op.98 |
ジョルジュ・プレートル(指) ■Disc1 シュトゥットガルトRSO 録音:2000年12月8日(第1番)、(2)1997 年10月29日~31日(ハンガリー舞曲) ■Disc2 ベルリン・ドイツSO 録音:2008年10月27日(第3番),2011年2 月6日(第2番)、 全て,フィルハーモニー・ベルリン ■Disc3 ローマ聖チェチリア音楽院O 録音:2009年3月17日(P四重奏)、2010 年5月31日(第4番) 全てデジタル、ライヴ録音 |
|
||
| GRAND SLAM GS-2295(1CD) |
ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 交響曲第4番ホ短調 Op.98 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指揮BPO 録音:1943年12月12~15日ベルリン、旧フィルハーモニー 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(ラジオ放送用録音) |
|
||
 Spectrum Sound CDSMBA-143(1CD) |
マルティノン&プレートル~ライヴ・イン・フランス
1968&1961 シューマン:交響曲第4番ニ短調 Op.120 ベルリオーズ:幻想交響曲* |
ジャン・マルティノン(指)、 ジョルジュ・プレートル(指)* フランス国立放送O ライヴ録音:1968年9月10日メゾン・デ・ザール・エ・ロワジール・ド・ラ・ヴィル・ド・ソショー(フランス) 1961年12月5シャンゼリゼ劇場 【共にステレオ・ライヴ】 |
|
||
 Audite AU-21464(3CD) KKC-6731(3CD) 日本語解説書付国内盤 税込定価 |
ヘルベルト・フォン・カラヤン/ルツェルン音楽祭初期録音集成(1952~1957) ■CD1 (1)ベートーヴェン:交響曲第8番 (2)モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番ハ短調 K.491 (3)バッハ:2台の鍵盤のための協奏曲第2番 ハ長調 BWV1061 ■CD2 (4)ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」 (5)ブラームス:交響曲第4番 ■CD3 (6)ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 (7)オネゲル:交響曲第3番「典礼風」 ■デジタルのボーナス・トラック バッハ:ミサ曲 ロ短調 BWV232(全曲) |
全て、ヘルベルト・フォン・カラヤン(指) (2)ロベール・カサドシュ(P) (3)ゲザ・アンダ(P)、クララ・ハスキル(P) (6)ナタン・ミルシテイン(Vn) (1)(2)(3)(6)(7)ルツェルン祝祭O (4)(5)フィルハーモニアO ライヴ録音:(1)(2)1952年8月16日、(3)(7)1955年8月10日、(4)(5)1956年9月6日、(6)1957年8月17日 クンストハウス、ルツェルン(モノラル) ■デジタルのボーナス・トラック ウィーンSO、ウィーン楽友協会cho エリーザベト・シュヴァルツコップ(S)、エルザ・カヴェルティ(A)、エルンスト・ヘフリガー(T)、ハンス・ブラウン(Bs) 録音:1951年9月1日 ※商品インレイに印字されたQRコードから聴くことができます |
|
||
| H.M.F HMSA-0069(1SACD) シングルレイヤー 日本語解説付国内盤 限定盤 税込定価 |
ベートーヴェン:交響曲第5番 ハ短調 op.67「運命」 ゴセック:17声の交響曲 ヘ長調 RH64 |
フランソワ=グザヴィエ・ロト(指) レ・シエクル(管弦楽/ピリオド楽器使用) 録音:2017年3月フィルハーモニー・ド・パリ(ベートーヴェン)、2020年2月ブローニュ=ビヤンクール、ラ・セーヌ(ゴセック) |
|
||
| H.M.F HMSA-0070(1SACD) シングルレイヤー 日本語解説付国内盤 限定盤 税込定価 |
ベートーヴェン:交響曲第3番 変ホ長調 作品55「英雄」 メユール(1763-1817):序曲~歌劇「アマゾネス、あるいはテーベの創生」より |
フランソワ=グザヴィエ・ロト(指) レ・シエクル(管弦楽/ピリオド楽器使用) 録音:2020年3月トゥルコアン市立劇場(グルノーブル)(ベートーヴェン)、 2020年2月セーヌ・ミュジカル、ブローニュ・ビリヤンクール(メユール) |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00820(3SACD) 税込定価 2023年7月19日発売 初回限定特別装丁BOXケース&紙ジャケット仕様 |
ブラームス:交響曲全集 交響曲第1番ハ短調 作品68 交響曲第2番ニ長調 作品73 交響曲第3番ヘ長調 作品90 交響曲第4番ホ短調 作品98 |
久石譲(指) フューチャー・オーケストラ・クラシックス 録音:第1番:2023年5月10-11日 長野市芸術館 メインホール(セッション) 第2番:2021年7月8日 東京オペラシティ コンサートホール、10日長野市芸術館 メインホール(ライヴ) 第3番:2022年2月9日 東京オペラシティ コンサートホール(ライヴ) 第4番:2022年7月14日 東京オペラシティ コンサートホール、16日長野市芸術館 メインホール(ライヴ) |
|
||
| Capriccio C-5509(1CD) NX-B07 |
ジグムント・ノスコフスキ(1846-1909)交響曲第2番ハ短調「エレジー風」(1875-79) 交響曲第1番イ長調(1874-75) |
ラインラント=プファルツ州立PO アントニ・ヴィト(指) 録音:2022年10月17-21日 |
|
||
| VOX VOXNX-3023CD(1CD) NX-B03 |
チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調 Op. 64 祝典序曲「1812年」 Op.49(1880) |
ユタSO モーリス・アブラヴァネル(指) 録音:1972-73年 1974年LP初リリース 総収録時間:61分 |
|
||
| SOMM ARIADNE-5022(2CD) NX-C09 |
マーラー演奏のパイオニアたち 【CD1】 1-2. マーラー:嘆きの歌 3. マーラー:アダージョ- 交響曲第10番より 4. レオポルド・ストコフスキーへのインタビュー(約23分) 【CD2】 1-4. マーラー:交響曲第4番ト長調 5. アルフレッド・フリーゼへのインタビュー(約18分) |
ジョーン・サザーランド(S)…CD1:1-2 ノーマ・プロクター(C.A)…CD1:1-2 ピーター・ピアーズ(T)…CD1:1-2 ゴールドスミス・コーラル・ユニオン…CD1:1-2 テレサ・シュティッヒ=ランダル(S)…CD2:4 LSO…CD1:1-2、CD2:1-4 ワルター・ゲール(指)…CD1:1-2、CD2:1-4 BBC響…CD1:3 ヘルマン・シェルヘン(指)…CD1:3 録音:1956年5月13日(ライヴ) ロイヤル・フェスティヴァル・ホール(UK)…CD1:1-2 1948年11月21日 BBCスタジオ(UK)…CD1:3 1960年2月9日 BBC Maida Vale Studios(UK)…CD2:1-4(全てMONO) インタビュー 1970年4月8日…レオポルド・ストコフスキー(指揮者) 1962年8月16日…アルフレッド・フリーゼ(ティンパニ奏者) |
|
||
| Spectrum Sound CDSMBA-141(1CD) |
モーツァルト:「フィガロの結婚」序曲 シューベルト:交響曲第9番「ザ・グレート」 |
カール・ミュンヒンガー(指) フランス国立放送O ライヴ録音:1966年5月18日シャンゼリゼ劇場(ステレオ)【初出音源】 |
|
||
| Spectrum Sound CDSMBA-142(1CD) |
(1)ブラームス:交響曲第1番ハ短調 Op.68 (2)ベートーヴェン:交響曲第5番ハ短調 Op.67「運命」 |
(1)サー・ゲオルク・ショルティ(指) (2)オイゲン・ヨッフム(指) フランス国立放送O ライヴ録音:(1)1956年12月6日シャンゼリゼ劇場、(2)1960年9月20日モントルー(モノラル)【初出音源】 |
|
||
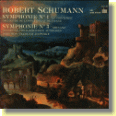 Treasures TRE-282(1CDR) |
スワロフスキー/シューマン&スメタナ スメタナ:歌劇「売られた花嫁」序曲 交響詩「モルダウ」 シューマン:交響曲第1番「春」* 交響曲第3番「ライン」# |
ハンス・スワロフスキー(指) ウィーン祝祭O、 ウィーン国立歌劇場O*、ウィーンSO#、 録音:1958年頃、1959年*、1955年1月19&21日#(全てモノラル) ※音源:W.R.C TT-17、仏ODEON XOC-819*,# ◎収録時間:75:27 |
| “模範解答的な佳演の域を超えるスワロフスキーの熱き表現!” | ||
|
||
| LSO Live LSO-0878(1SACD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲第15番イ長調 op.141 交響曲第6番ロ短調 op.54 |
ジャナンドレア・ノセダ(指)LSO 録音:2019年10月31日(第6番)、2022年2月6,13日(第15番) |
|
||
| LAWO Classics LWC-1258(1CD) |
モーツァルト:交響曲第39番&第40番交響曲第39番 変ホ長調 K.543 交響曲第40番ト短調 K.550 |
ノルウェー放送O、 ペトル・ポペルカ(指) 録音:2022年1月24日-28日&8月22日、NRKラジオ・コンサート・ホール(オスロ、ノルウェー) |
|
||
| ACO ACOJP-1(1CD) 日本語解説付き |
バッハ、ベートーヴェン、ブラームス バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 二短調 BWV1043* ベートーヴェン:弦楽四重奏曲 変ロ長調 作品130より 第5楽章 カヴァティーナ(弦楽オーケストラ編曲:リチャード・トネッティ)、 大フーガ 変ロ長調 作品133(弦楽オーケストラ編曲:リチャード・トネッティ) ブラームス:交響曲第3番 ヘ長調 作品90 |
リチャード・トネッティ(Vn1)*、 ヘレナ・ラスボーン(Vn2)* リチャード・トネッティ(芸術監督、ヴァイオリン)、 オーストラリア室内O 録音:2005年10月21日-24日、ABCユージン・グーセンス・ホール(バッハ)/2016年5月14日-20日、シドニー・シティ・リサイタル・ホール(ベートーヴェン/ライヴ)/2015年8月23日-24日、メルボルン・ハマー・ホール(ブラームス/ライヴ) |
|
||
| Diapason DIAP-159(2CD) |
マーラー:作品集 (1)交響曲第3番ニ短調 (2)「若き日の歌」より第1曲、第3曲、第6曲、第7曲 「少年の魔法の角笛」より第1曲、第4曲、第5曲、第6曲、第7曲、第9曲、第10曲 「リュッケルト歌曲集」より第2曲、第3曲、第4曲、第5曲 |
(1)レナード・バーンスタイン(指)NYO マーサ・リプトン(Ms) スコラ・カントルム女声cho トランスフィギュレーション教会少年cho 録音:1961年 (2)クリスタ・ルートヴィヒ(Ms) ジェラルド・ムーア(P) 録音:1957年&1959年 |
|
||
| Diapason DIAP-CF028((10CD) |
マーラー:交響曲全集 (1)交響曲第1番「巨人」 録音:1961年 (2)交響曲第2番「復活」 (3)交響曲第3番 (4)交響曲第4番 (5)交響曲第5番 (6)交響曲第6番「悲劇的」 (7)交響曲第7番 (8)交響曲第8番「千人の交響曲」 (9)交響曲第9番 (10)交響曲第10番(断章) |
(1)パウル・クレツキ(指)VPO 録音:1961年 (2)ブルーノ・ワルター(指)NYO、エミリア・クンダリ(S)、モーリン・フォレスター(A)、ウェストミンスターcho 録音:1958年 (3)レナード・バーンスタイン(指)、ニューヨーク・フィルハーモニック、マーサ・リプトン(Ms)、スコラ・カントルム女声合唱団、トランスフィギュレーション教会少年合唱団 録音:1961年 (4)フリッツ・ライナー(指)CSO、リーザ・デラ・カーザ(S) 録音:1958年 (5)ルドルフ・シュワルツ(指)LSO 録音:1958年 (6)ディミトリ・ミトロプーロス(指NYO 録音:1955年 (7)キリル・コンドラシン(指)モスクワPO 録音:1975年 (8) ヤッシャ・ホーレンシュタイン(指)LSO、他 録音:1958年 (9)ブルーノ・ワルター(指)コロンビアSO 録音:1961年 (10)ジョージ・セル(指)クリーヴランドO 録音:1958年 |
|
||
| MDG MDG-90122926 (1SACD) |
ヨーゼフ&ミヒャエル ハイドン「奇跡の兄弟」 ミヒャエル・ハイドン:交響曲第39番ハ長調 序曲「償われた罪人」 ハイドン:人形歌劇「フィレモンとバウチス」(神々の会議)への前奏曲 交響曲第96番「奇跡」ニ長調 |
ハイドン・フィルハーモニー エンリコ・オノフリ(指) 録音:2023年4月11-16日、ケルンテン州立音楽院、アルバン・ベルク・ザール、オシアッハ、オーストリア |
|
||
| GRAND SLAM GS-2294(1CD) |
ブルックナー:交響曲第5番(改訂版) | ハンス・クナッパーツブッシュ(指)VPO 録音:1956年6月3~6日ゾフィエンザール(ウィーン) 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:ステレオ(録音セッション) |
|
||
| CLAVES 50-3076(1CD) |
ベートーヴェン:献堂式 Op.124 (2)モーツァルト:交響曲第39番変ホ長調 K.543 タッローディ:啓蒙の断片【世界初録音】 (4)モーツァルト:フリーメイソンのための葬送音楽 K.477 |
ロベルト・ゴンザレス=モンハス(指) ヴィンタートゥール・ムジークコレギウム 録音:2022年9月/ヴィンタートゥール・シュタットハウス(スイス) |
|
||
| H.M.F HMSA-0067(1SACD) シングルレイヤー 日本独自企画・限定盤 税込)定価 |
マーラー:「巨人」~交響曲形式による音詩(交響曲第1番の1893年ハンブルク稿、2部から成る) 第1部 「青春の日々より」花、果実、そして茨の絵 1第1楽章:春、そして終わることなく(序奏とアレグロ・コモド) 2第2楽章:花の章(アンダンテ) 3第3楽章:順風満帆(スケルツォ) 第2部 「人間喜劇」 4第4楽章:難破!(カロ風の葬送行進曲) 5第5楽章:地獄から(アレグロ・フリオーソ) |
フランソワ=グザヴィエ・ロト(指) レ・シエクル(管弦楽) 録音:2018年2月、3月、10月 |
|
||
| H.M.F HMSA-0068(1SACD) シングルレイヤー 日本独自企画・限定盤 税込)定価 |
サン=サーンス:交響曲第3番「オルガン付き」 ピアノ協奏曲第4番ハ短調 作品44 |
フランソワ= グザヴィエ・ロト(指) レ・シエクル(管弦楽) ダニエル・ロト(Org/サン=シュルピス教会、1862年カヴァイエ=コル製) ジャン=フランソワ・エッセール(P/1874年製のエラール) 録音:2010年 |
|
||
| Goodies 78CDR-3908(1CDR) |
ベートーヴェン:交響曲第2番ニ長調作品36 | パウル・ファン・ケンペン(指) ドレスデンPO 独 GRAMMOPHON67608/12S 1941年ドレスデン録音 |
|
||
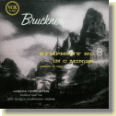 Treasures TRE-306(1CDR) |
ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 WAB 108 (1890年稿・ノヴァーク版) | ヤッシャ・ホーレンシュタイン(指) ウィーン・プロ・ムジカO(ウィーンSO) 録音:1955年(モノラル) ※音源:英VOX PL-9682 ◎収録時間:76:29 |
| “マーラーにもブルックナーにも適応できるホーレンシュタイン独自の音作り!” | ||
|
||
 King International KKC-4335(1SACD) 限定発売 |
「世界の調和」は真正ステレオ! フルトヴェングラーのヒンデミット 交響曲「世界の調和」 管弦楽のための協奏曲 作品38* |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) VPO、BPO* 録音:1953年8月30日 フェストシュピールハウス、ザルツブルク(ライヴ) 1950年6月20日 ティタニア・パラスト、ベルリン(ライヴ)* 解説:小石忠男 |
|
||
| GRAND SLAM GS-229(1CD) |
ハイドン:交響曲第88番ト長調Hob. I:88* シューベルト:交響曲第9番「ザ・グレイト」 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)BPO 録音:1951年12月4&5日*、1951年11月27&28日、12月2&4日/イエス・キリスト教会、ベルリン・ダーレム(ドイツ) 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2292(1CD) |
ベルリオーズ:幻想交響曲 Op.14a | シャルル・ミュンシュ(指)パリO 録音:1967年10月23~26日サル・ワグラム(パリ) 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:ステレオ(録音セッション) |
|
||
| Audite AU-97761(1CD) |
リスト:ファウスト交響曲 メフィスト・ワルツ第3番S.216(管弦楽編)(編曲:アルフレート・ライゼナウアー~キリル・カラビツ)【世界初録音】 |
アイラム・エルナンデス(T) ワイマール国民劇場cho、 イェンス・ペーターアイト(合唱指揮) テューリンゲン少年cho、 フランツィスカ・クバ(合唱指揮) キリル・カラビツ(指) シュターツカペレ・ワイマール 録音:2022年6月12&13日/ワイマール・ホール |
|
||
 Spectrum Sound CDSMBA-138(1CD) |
ベルリオーズ:幻想交響曲 Op.14 ドビュッシー:管弦楽のための3つの交響的素描『海』 |
シャルル・ミュンシュ(指) フランス国立放送O ライヴ録音:1966年1月10日バーデン=バーデン劇場、ドイツ(モノラル)【初出音源】 音源:フランス国立視聴覚研究所音源提供 |
|
||
 Spectrum Sound CDSMBA-139(1CD) |
ブラームス:交響曲第3番ヘ長調 Op.90 チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調 Op.64* |
ポール・パレー(指) フランス国立放送O ライヴ録音:1964年5月12日、1970年11月25日* シャンゼリゼ劇場(ステレオ)【初出音源】 |
|
||
| Goodies 78CDR-3906(1CDR) |
ダンディ:「フランス山人の歌による交響曲」 | マルグリット・ロン(P) ポール・パレー(指)コロンヌO 仏COLUMBIA LFX 332/4 1934年5月24-25日パリ録音 |
|
||
| Goodies 78CDR-3907(1CDR) |
ブラームス:交響曲第1番ハ短調 作品68 | レオポルド・ストコフスキー(指) ハリウッド・ボウルSO 米 VICTOR 18-0020/24 1945年8月1日ロサンジェルス録音 |
|
||
| Acte Prealable AP-0505(1CD) PAP-0505(1CD) 国内盤仕様 税込定価 |
ラウル・コチャルスキ(1885-1948):交響曲集
Vol.1 1-7. 愛より Op.99(ライナー・マリア・リルケによる7つの詩) 8-21. 交響的伝説 Op.53(管弦楽のための勇敢王ボレスラウスと聖司教スタニスラウスの交響的伝説) 22-31. 幻想交響曲 Op.73(エヴォカシオン) |
ヴォイチェフ・ロデク((指)8-31)、 フィルハルモニア・ルベルスカ(8-31)、 カタジナ・ドンダルスカ(ソプラノ、1-7)、 フィルハルモニア・ドルノシロンスカ(1-7)、 シモン・マコフスキ((指)1-7) 録音:2022年11月30日-12月1日、フィルハルモニア・ドルノシロンスカ(1-7)、2021年11月8日-10日、フィルハルモニア・ルベルスカ(8-31) ※国内盤:解説日本語訳&日本語曲目表記オビ付き |
|
||
| Forgotten Records fr-1882(1CDR) |
オネゲル:交響曲第2番「弦楽の為の」* マルティヌー:交響曲第3番H.299 # |
ブジェティスラフ・バカラ(指)ブルノPO 録音:1956年1月、1956年# ※音源: Muza L 0166*、L 0150 # |
| Forgotten Records fr-1881(1CDR) |
リスト:ダンテ交響曲 | アルフレッド・ウォーレンステイン(指) ロサンゼルスPO 録音:1953年2月 ※音源: 米Decca DL 9670 |
| Forgotten Records fr-1883(1CDR) |
ステンハンマル:交響曲第2番ト短調 Op.34* 感傷的なロマンス第1番 # |
フランチェスコ・アスティ(Vn)# トール・マン(指) ストックホルムPO*、イェーテボリSO# 録音:1930年3月13日# 1959年8月15日-16日、ストックホルム・コンサートホール(ステレオ)* ※音源: Swedish Society Discofil SLT 33198*、 HMV Z 206 |
| Forgotten Records fr-1884(1CDR) |
ウォーレンステイン/ラフマニノフ&チャイコフスキー ラフマニノフ:交響曲第2番* チャイコフスキー:ワルツ集# 眠れる森の美女 ~ワルツ 白鳥の湖 ~ワルツ くるみ割り人形 ~花のワルツ エフゲニー・オネーギン ~ワルツ 弦楽セレナード ~ワルツ 交響曲第5番 ~第3楽章 |
アルフレッド・ウォーレンステイン(指) ロサンゼルスPO 録音:1952年頃# 、1960年1月23日-24日(ステレオ)* ※音源:Capitol SP 8386*、Brunswick AXL 2012 # |
| Forgotten Records fr-1885(1CDR) |
スヴェンセン:交響曲第2番変ロ長調 Op.15* ハチャトゥリアン:交響曲第1番# |
アレクサンドル・ガウク(指)モスクワRSO 録音:1956年*、1959年# ※音源:Melodiya D 3048/9* D 4920/1 # |
| Forgotten Records fr-2111(1CDR) |
パレー、グリュミオー、ジャンドロン モーツァルト:「フィガロの結婚」序曲 ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」 ブラームス:二重協奏曲 イ短調 R・シュトラウス:交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」 |
アルテュール・グリュミオー(Vn) モーリス・ジャンドロン(Vc) ポール・パレー(指) モンテ・カルロ国立歌劇場O 録音:1959年8月19日(モナコ、モナコ公レーニエ3世&公妃グレース・ケリー夫妻臨席)・モノラル・ライヴ |
| GRAND SLAM GS-2291(1CD) |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op.58 交響曲第7番イ長調 Op.92 |
コンラート・ハンゼン(P) ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)BPO 録音:1943年10月31日~11月3日/旧フィルハーモニー、ベルリン 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(ラジオ放送用録音) |
|
||
| OEHMS OC1718(2CD) NX-C05 |
マーラー:交響曲第3番ニ短調 | ベッティナ・ランチ(A) エッセン・フィルハーモニー合唱団女声団員 アールト児童cho ベルリン・ドイツ・オペラ児童cho エッセンPO トマーシュ・ネトピル(指) 録音:2023年1月 |
|
||
| TOCCATA TOCC-0657(1CD) NX-B03 |
フリードリヒ・ブルク(1937-):管弦楽作品集
第4集 交響曲第15番「Reflections リフレクションズ」(2015) 交響曲第16番「The River Dnieper ドニプロ川」(2016) |
リトアニア国立SO イマンツ・レスニス(指) 録音:2015年9月、2016年6月 全て世界初録音 |
|
||
| Goodies 78CDR-3903(1CDR) |
モーツァルト:交響曲第40番ト短調 K.550 | アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC響 1938年3月7日&1939年2月27日ニューヨーク、NBC放送8Hスタジオ録音 英HMV DB 3790/2(米VICTOR 15733/5と同一録音) |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00813(1SACD) 税込定価 2023年5月24日発売 |
ハイドン:交響曲集Vol.20 交響曲第56番ハ長調Hob.Ⅰ:56 交響曲第40番ヘ長調Hob.Ⅰ:40 交響曲第74番変ホ長調Hob.Ⅰ:74 |
飯森範親(指) 日本センチュリーSO 録音:2020年10月23日(第40番)、2021年7月30日(第56番)、9月30日(第74番)大阪、ザ・シンフォニーホール・ライヴ |
|
||
 Biddulph BIDD-85027(1CD) NX-B04 |
初出音源~ビーチャム唯一のラフマニノフ!! ラフマニノフ:交響曲第3番イ短調 Op.44* 合唱交響曲「鐘」Op.35[英語による歌唱。第3楽章は1936年改訂版] |
サー・トーマス・ビーチャム(指)LPO* イソベル・ベイリー(S) パリー・ジョーンズ(T) ロイ・ヘンダーソン(Br) フィルハーモニックcho サー・ヘンリーウッド(指)BBC響* 録音:1937年11月18日 ロンドン、クイーンズ・ホール(ライヴ)* 1937年2月10日 ロンドン、クイーンズ・ホール(ライヴ) |
|
||
| BR KLASSIK BR-900209(1CD) NX-B07 |
マーラー::交響曲第7番「夜の歌」 | バイエルンRSO ベルナルト・ハイティンク(指) 録音:2011年2月14-18日ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ライヴ) 総収録時間:82分 |
|
||
| CZECH RADIOSERVIS CR-1179(2CD) |
プラハの春音楽祭ゴールド・エディション Vol.4 ■CD1 (1)マーラー:交響曲第1番「巨人」 (2)ブリテン:フランク・ブリッジの主題による変奏曲Op.10 ■CD2 (1)ドヴォルザーク:交響曲第7番ニ短調 (2)R.シュトラウス:交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」 |
■CD1(78‘43) (1)ジョン・バルビローリ(指)チェコPO 録音:1960年5月24日、プラハ、スメタナ・ホール(モノラル・ライヴ) (2)チャールズ・マッケラス(指)イギリス室内O 録音:1966年5月16日、プラハ、ドヴォルザーク・ホールモノラル・(ライヴ) ■CD2(74‘36) (1)カルロ・マリア・ジュリーニ(指)ウィーンSO 録音:1975年5月28日、プラハ、スメタナ・ホール(ステレオ・ライヴ) (2)ベルナルト・ハイティンク(指)ロイヤル・コンセルトヘボウO 録音:1980年5月18日、プラハ、スメタナ・ホール(ステレオ・ライヴ) |
|
||
 Spectrum Sound CDSMBA-134(1CD) |
(1)ブラームス:交響曲第2番ニ長調 Op.73 (2)ドビュッシー:「海」 |
シャルル・ミュンシュ(指)、 フランス国立放送O ライヴ録音(1)1965年11月16日/シャンゼリゼ劇場(ステレオ)、(2)1966年9月13日/ブザンソン市民劇場(ステレオ)【初出音源】 |
|
||
 Altus ALT-527(1CD) |
準・メルクル/台湾フィルハーモニック 2022年ライヴ メンデルスゾーン:序曲『フィンガルの洞窟』 メンデルスゾーン:交響曲第4番『イタリア』 ドビュッシー:夜想曲* ラヴェル:ラ・ヴァルス |
ラヴェル:ラ・ヴァルス 準・メルクル(指) 台湾フィルハーモニック(國家交響樂團) 台北室内cho* ライヴ録音:2022年11月4・10日(メンデルスゾーン)、11日(ドビュッシー、ラヴェル)/國家表演藝術中心 コンサートホール(台北) |
|
||
| C Major 80-7508(2DVD) 80-7604(Bluray) |
ブルックナー:交響曲第4&9番 交響曲第4番変ホ長調『ロマンティック』(1880年第2稿 ハース校訂 1936年出版) 交響曲第9番ニ短調 WAB109(原典版 新全集IX、1951年出版 ノーヴァク校訂) ■ボーナス映像「ディスカヴァリング・ブルックナー」 各交響曲について(ティーレマンと音楽学者ヨハネス=レオポルド・マイヤー氏による対話) |
クリスティアン・ティーレマン(指)VPO 収録:2020年8月、ザルツブルク祝祭大劇場、ライヴ(第4番) 2022年7月、ザルツブルク祝祭大劇場、ライヴ(第9番) ◆DVD 画面:16:9、1080i 音声:PCMステレオ、DTS5.0 DVD9 [ボーナス映像 ] 言語:ドイツ語 字幕:英韓,日本語 Total time:197分 交響曲:142分、ボーナス:55分 ◆Bluray 画面:16:9、1080i 音声:PCMステレオ、 DTS-HD MA5.0 BD50 [ボーナス映像] 言語:ドイツ語 字幕:英韓,日本語 Total time:197分 交響曲:142分、ボーナス:55分 |
|
||
| APARTE AP-315(1CD) |
メンデルスゾーン:ピリオド楽器による交響曲第4&5番 交響曲第4番イ長調「イタリア」 交響曲第5番ニ短調「宗教改革」 |
アレクシス・コセンコ(指) レ・ザンバサドゥール~ラ・グランド・エキュリ 録音:2022年5月7-9日イル・ド・フランス国立Oホール(アルフォールヴィル) |
|
||
| IDIS IDIS-6750(1CD) |
カラヤン・スペクタキュラーVol.11 ベートーヴェン:交響曲第5番『運命』 交響曲第8番ヘ長調 Op.93* |
ヘルベルト・フォン・カラヤン(指) BPO ライヴ録音:1957年11月3日東京(ステレオ)、 1961年4月8日ロンドン(モノラル)* |
|
||
| CPO CPO-777973(1CD) NX-B10 |
ハチャトゥリアン:交響曲第3番「交響詩曲」 ガイーヌより組曲第3番 |
シューマン・フィルハーモニー フランク・ベールマン(指) 録音:2015年12月8-10日(ライヴ) |
|
||
| DACAPO MAR-8.207002(7CD) NX-G05 |
ルーズ・ランゴー(1893-1952):交響曲全集 【CD1】 交響曲第1番「岩山の田園詩」 BVN32 【CD2】 交響曲第2番「春の目覚め」 BVN53(オリジナル版) . 交響曲第3番「青春のさざめき」 BVN96 【CD3】 交響曲第4番「落葉」 BVN124 交響曲第5番BVN191(第1版) 交響曲第5番「草原の自然」 BVN216(第2版) 【CD4】 交響曲第6番「引き裂かれた天国」 交響曲第7番BVN188(1926年版) 交響曲第8番「アメリエンボーの思い出」 BVN 193 【CD5】 交響曲第9番「ダウマー妃の町から」 BVN282 交響曲第10番「向こうに見える雷の住みか」 BVN298 交響曲第11番「イクシーオン」 BVN303 【CD6】 交響曲第12番「ヘルシングボリ」 BVN318 交響曲第13番「驚異の確信」 BVN319 交響曲第14番「朝」 BVN336 【CD7】 Drapa(On the Death of Edvard Grieg), BVN 20(1913最終版) Sfinx(Sphinx), BVN37(1913改訂版) Hvidbjerg-Drapa, BVN343…世界初録音 Danmarks Radio(Radio Denmark), BVN351…世界初録音 Res absurda!?, BVN354…世界初録音 交響曲第15番「海の嵐」 BVN375 交響曲第16番「太陽の氾濫」 BVN417 |
デンマーク国立SO&cho トーマス・ダウスゴー(指) 録音:1998年8月-2008年6月 |
|
||
 PROMINENT CLASSICS 2506-5612(2CD) UHQCD |
ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 | エフゲニ・スヴェトラーノフ(指) ハーグ・レジデンティO(ハーグPO) 録音:2000年3月25日アントン・フィリップザール,デジタル・ライヴ |
|
||
| フォンテック FOCD-9880(1CD) 税込定価 2023年5月10日発売 |
マーラー 交響曲第2番「復活」 | 小泉和裕(指揮)九州SO 安井陽子(S)、福原寿美枝(A)、 九響cho、RKB女声cho、九州大学男声合唱団コールアカデミー、九大混声cho 、久留米大学附設高等学校合唱部 、多目的混声cho"Chor Solfa!"、ちくしの混声cho、アクロス福岡公募メンバー 録音:2022 年10 月7・8 日 アクロス福岡シンフォニーホール(1LP)ライヴ) |
|
||
| Urania Records WS-121410(2CD) |
マーラー:交響曲第5番嬰ハ短調 交響曲第6番 イ短調「悲劇的」 |
エーリヒ・ラインスドルフ(指)ボストンSO レコーディング・プロデュース:1963年(第5番)、1966年(第6番)、ボストン(ステレオ、ADD) |
|
||
 BR KLASSIK BR-900207(1CD) NX-B07 |
チャイコフスキー:交響曲第5番 リスト:交響詩「マゼッパ」 |
バイエルンRSO ズービン・メータ(指) 録音:2013年2月25日-3月1日(ライヴ) ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ドイツ) |
|
||
| Capriccio C-8085(1CD) NX-B07 NYCX-10397(1CD) 国内盤仕様 税込定価 |
ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」(第3稿/コーストヴェット版) | ウィーンRSO マルクス・ポシュナー(指) 録音:2021年11月26-28日ウィーン放送文化会館(オーストリア) |
|
||
| J.S.Bach-Stiftung C-143CD(1CD) NX-E03 |
ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 | バッハ財団O(古楽器使用) ルドルフ・ルッツ(指) 録音:2022年8月17日 Tonhalle St. Gallen(スイス)ライヴ |
|
||
| Goodies 78CDR-3903(1CD) |
モーツァルト:交響曲第40番ト短調 K.550 | アルトゥーロ・トスカニーニ(指) NBC響 1938年3月7日&1939年2月27日ニューヨーク、NBC放送8Hスタジオ録音 英HMV DB3790/2(米VICTOR15733/5と同一録音) |
|
||
| Forgotten Records fr-1864(1CDR) |
ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」* ダンディ:交響詩「ヴァレンシュタイン」# |
ディミトリ・ミトロプーロス(指)NYO 録音:1949年12月11日*、1950年4月14日#、カーネギー・ホール・ライヴ |
| Forgotten Records fr-1871(1CDR) |
クリップスのベートーヴェン 交響曲第1番ハ長調 Op.21* 交響曲第8番ヘ長調 Op.93# |
ヨーゼフ・クリップス(指) アムステルダム・ コンセルトヘボウO 録音:1952年5月24日*、1952年9月5日#、コンセルトヘボウ(共にライヴ) |
| Forgotten Records fr-1875(1CDR) |
オーマンディ/シベリウス:交響曲集 交響曲第2番ニ長調 Op.43* 交響曲第4番イ短調 Op.63# |
ユージン・オーマンディ(指) フィラデルフィアO 録音:1947年10月31日*、1954年11月28日# ※音源: Columbia ML-4131*、ML-5045# |
| Forgotten Records fr-18761CDR) |
オーマンディ/シベリウス:交響曲集2 交響曲第2番ニ長調 Op.43* 交響曲第4番イ短調 Op.63# |
ユージン・オーマンディ(指) フィラデルフィアO 録音:1951年12月16日#、1954年12月19日* ※音源: Columbia ML-4672#、ML-5045* |
| Forgotten Records fr-1878(1CDR) |
アノーソフ/シベリウス&カバレフスキー シベリウス:交響曲第1番* カバレフスキー:交響曲第2番Op.19# |
ニコライ・アノーソフ(指) ソヴィエト国立RSO 録音:1956年#、1957年* ※音源: Melodiya D 02952/3*、D-03816# |
| オクタヴィア OVCL-00811(1SACD) 税込定価 |
エルガー:交響曲第2番変ホ長調作品63 | 大友直人(指) 東京SO 録音:2023年1月29日ミューザ川崎シンフォニーホール・ライヴ |
|
||
| GRAND SLAM GS-2264(2CD) ★ |
ブルックナー:交響曲集 (1)交響曲第4番変ホ長調「ロマンティック」(改訂版) (2)交響曲第8番ハ短調(改訂版) |
ブ ルーノ・ワルター(指) (1)NBC響、(2)NYO 録音:(1)1940年2月10日NBC、8Hスタジオ(ニューヨーク) (2)1941年1月26日カーネギー・ホール(ニューヨーク) 使用音源:Private archive 録音方式:モノラル(ラジオ放送用録音) |
|
||
| ACCENTUS Music ACC-60568BD(4Bluray) ACC-70568DVD(4DVD) |
アンドリス・ネルソンス~2つのオーケストラを振った映像集 ■(1)BD&DVD1(2014年ルツェルン音楽祭) ブラームス:セレナード第2番イ長調Op.16、 アルト・ラプソディOp.53、 交響曲第2番ニ長調Op.73 ■(2)BD&DVD2(2015年ルツェルン音楽祭) マーラー:「子供の不思議な角笛」より【ラインの伝説 / 美しくトランペットが鳴り響く所 / この世の生活 / 原光 /魚に説教するパドバの聖アントニオ / 起床合図 / 少年鼓笛兵】、 交響曲第5番 ■(3)BD&DVD3(2018年第21代カペルマイスター就任記念公演) シュテッフェン・シュライエルマッハー(1960-):オーケストラのためのレリーフ (世界初演、ライプツィヒ・ゲヴァントハウスOとボストンSOによる委嘱作品) ベルク:ヴァイオリン協奏曲 メンデルスゾーン:交響曲第3番「スコットランド」 ■(4)BD&DVD4(2017年ライプツィヒ・ライヴ) ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」、 序曲「オセロ」、 「ルサルカ」より“月に寄せる歌”、“ポロネーズ”、“ああ、無駄よ、無駄” わが母の教え給いし歌 スメタナ:「ダリボル」より“いいわ、彼に与えましょう” |
アンドリス・ネルソンス(指) ■(1)ルツェルン祝祭O サラ・ミンガルド(A) バイエルン放送cho 収録:2014年8月15、16日KKLルツェルン・コンサート・ホール(ライヴ) ■(2)ルツェルン祝祭O マティアス・ゲルネ(Br) 収録:2015年8月19&20日ルツェルン、文化会議センター(ライヴ) ■(3)バイバ・スクリデ(Vn) ライプツィヒ・ゲヴァントハウスO 収録:2018年2月22、23日ライプツィヒ、ゲヴァントハウス(ライヴ) ■(4)ライプツィヒ・ゲヴァントハウスO クリスティーネ・オポライス(S) 収録:2017年5月ライプツィヒ、ゲヴァントハウス(ライヴ) ■Bluray 画面:Full HD,16:9 音声:DTS HD MA5.0,PCM、ステレオ リージョン:All BD25 字幕:独英仏韓,日本語 425'01 ■DVD 画 面:NTSC ,16:9 音声:DTS、HD,PCMステレオ リージョン:All DVD9 字幕:独英仏韓,日本語 425'01 |
|
||
| H.M.F HMM-902694 (1SACD) |
シューベルト:交響曲第5番変ロ長調 D485 交響曲 ロ短調 「未完成」 |
パブロ・エラス=カサド(指) フライブルク・バロック・オーケストラ 録音:2021年11月 |
|
||
| Pentatone PTC-5187065(1SACD) |
シューベルト:交響曲第8番「未完成」 交響曲第9番「ザ・グレイト」 |
ドレスデンPO マレク・ヤノフスキ(指) コンサートマスター:ハイケ・ヤニッケ(未完成)、ラルフ=カルステン・ブレムゼル(ザ・グレイト) 録音:2020年11月ドレスデン、クルトゥーアパラスト(文化宮殿) |
|
||
| ACCENTUS Music ACC-70570DVD (4DVD) |
リッカルド・シャイー&ルツェルン祝祭O~第一期 ■DVD1 マーラー:交響曲第8番変ホ長調「千人の交響曲」 ■DVD2 メンデルスゾーン:「夏の夜の夢」~演奏会用序曲Op.21 劇付随音楽Op.61より抜粋 チャイコフスキー:マンフレッド交響曲Op.58 ■DVD3 ラヴェル:優雅で感傷的なワルツ ラ・ヴァルス 「ダフニスとクロエ」組曲 第1番 「ダフニスとクロエ」組曲 第2番 ボレロ ■DVD4 ラフマニノフ:ピアノ協奏曲 第3番二短調 Op.30* エチュード「音の絵」 第2番イ短調 Op.39-2(アンコール)* ヴォカリーズ(管弦楽版) 交響曲第3番イ短調 |
リッカルド・シャイー(指) ルツェルン祝祭O ■DVD1 リカルダ・メルベート(ソプラノ1/罪深き女)、ユリアーネ・バンセ(ソプラノ2/贖罪の女)、アンナ・ルチア・リヒター(ソプラノ3/栄光の聖母)、サラ・ミンガルド(メゾ・ソプラノ/サマリアの女)、藤村実穂子(アルト/エジプトのマリア)、アンドレアス・シャーガー(テノール/マリア崇拝の博士)、ペーター・マッティ(バリトン/法悦の神父)、サミュエル・ユン(バス/瞑想の神父)、バイエルン放送cho、ラトヴィア放送cho、オルフェオン・ドノスティアラ、テルツ少年cho 収録:2016年8月12日&13日 KKLコンサートホール、ルツェルン音楽祭2016(ライヴ) ■DVD2 収録:2017年8月、KKL コンサートホール、ルツェルン(ライヴ) ■DVD3 収録:2018年8月、ルツェルン文化会議センター・コンサートホール、ライヴ ■DVD4 デニス・マツーエフ(P)* 収録:2019年8月、ルツェルン音楽祭(ライヴ) 画面:NTSC,16:9 音声:PCM STEREO, DD5.1,DTS5.1 リージョン:ALL DVD9 字幕:独英仏韓,日本語 390'13 |
|
||
| CPO CPO-555462(1CD) NX-B10 |
ヴィルヘルム・ベルガー(1861-1911):小協奏曲/交響曲 小協奏曲 イ短調 Op.43a - ピアノとオーケストラの 交響曲 変ロ長調 Op.71 |
オリヴァー・トリンドル(P) ロイトリンゲン・ヴュルテンベルクPO クレメンス・シュルト(指) 録音:2021年3月11-12日、2020年11月2-5日 |
|
||
| Chandos CHSA-5311(1SACD) RCHSA-5311(1SACD) 国内盤仕様 税込定価 |
ニールセン:ヴァイオリン協奏曲 Op.33* 交響曲第4番「不滅」 |
エドワード・ガードナー(指)、 ベルゲンPO、 ジェームズ・エーネス(Vn)* 録音:2022年6月14日-17日、グリーグホール(ベルゲン、ノルウェー) 国内盤:解説日本語訳&日本語曲目表記オビ付き |
|
||
 BR KLASSIK BR-900196(2CD) NX-B09 |
モーツァルト:交響曲集 交響曲第39番変ホ長調 K.543 交響曲第40番ト短調 K.550* 交響曲第41番「ジュピター」 K.551# |
バイエルンRSO ヘルベルト・ブロムシュテット(指) 録音(ライヴ):2019年12月17-21日 ミュンヘン、フィルハモニー・イン・ガスタイク 2013年1月31日-2月1日 ミュンヘン、ヘルクレスザール* 2017年12月18-22日 ミュンヘン、ヘルクレスザール# |
|
||
| FUGA LIBERA FUG-816(1CD) |
ラフマニノフ:交響曲第2番ホ短調 Op.27 | ウラルPO ドミトリー・リス(指) 録音:2021年7月 スヴェルドロフスク・フィルハーモニック大ホール、エカテリンブルク、ロシア |
|
||
 Myrios Classics MYR-032(1CD) KKC-6696(1CD) 国内盤仕様 税込定価 |
ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」(1874年第1稿) | フランソワ=グザヴィエ・ロト(指) ケルン・ギュルツェニヒO 録音:2021年9月19-21日ケルン・フィルハーモニー(ライヴ) ※国内盤=日本語帯・解説付 |
|
||
| GRAND SLAM GS-2283(1CD) |
(1)フランク:交響曲 ニ短調 (2)ブラームス:第2番ニ長調 Op.73 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)VPO 録音:1945年1月28日ムジークフェラインザール(ウィーン) 使用音源:(1)Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) (2)Private archive(2トラック、19センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(放送用ライヴ録音) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2288(1CD) |
ブラームス:交響曲第2番ニ長調 Op.73 | ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)BPO 録音:1952年5月7日ドイツ博物館コングレスザール(ミュンヘン) 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(放送用ライヴ録音) |
|
||
| Hanssler HC-22078(1CD) |
モーツァルト:交響曲集 (1)交響曲第34番ハ長調 K.338 (2)交響曲第35番ニ長調 K.385「ハフナー」 (3)交響曲第36番ハ長調 K.425「リンツ」 |
マティアス・マナージ(指) ジリナ・スロヴァキア・シンフォニエッタ 録音:2022年11月17-19日/フィルハーモニー・ジリナ(スロヴァキア) |
|
||
| ATMA ACD2-2454(1CD) |
シベリウス:交響曲第3番ハ長調 Op.52 交響曲第4番イ短調 Op.63 |
ヤニック・ネゼ = セガン(指) モントリオール・メトロポリタンO 録音:2021年6月(第3番)、2022年2月(第4番) |
|
||
| BIS BISSA-2534(1SACD) |
ブルックナー:交響曲第4番『ロマンティック』(1878/80年稿ノヴァーク版) | トーマス・ダウスゴー(指) ベルゲンPO 録音:2020年1月20-22日グリーグ・ホール、ベルゲン(ノルウェー) |
|
||
 Altus ALT-523(1CD) |
ベルリオーズ:幻想交響曲 | 大野和士(指)東京都SO 録音:2019年4月20日/東京芸術劇場コンサートホール(第876回定期演奏会Cシリーズ) |
|
||
| Profil PH-23012(8CD) |
ギュンター・ヴァント~Profilブルックナー大集成 ■Disc1 交響曲第3番ニ短調(ノヴァーク第3稿) ■Disc2 交響曲第4番変ホ長調(1878/80年原典版) ■Disc3 交響曲第5番変ロ長調(原典版) ■Disc4 交響曲第6番イ長調(原典版) ■Disc5 交響曲第7番ホ長調(ハース原典版) ■Disc6 交響曲第8番ハ短調(ハース版) ■Disc8 交響曲第9番ニ短調(原典版) |
ギュンター・ヴァント(指) ■Disc1 53’59” 北ドイツRSO 録音:1985年12月23日ハンブルク、ムジークハレ ■Disc2 72’47” ミュンヘンPO 録音:2000年9月15日ミュンヘン、ガスタイク ■Disc3 75’41” ミュンヘンPO 録音:1995年11月29日、12月1日ミュンヘン、ガスタイク ■Disc4 57’37” ミュンヘンPO 録音:1999年6月24日ミュンヘン、ガスタイク ■Disc5 63’31” 北ドイツRSO 録音:1999年8月18-21日ハンブルク、ムジークハレ ■Disc6、7 33’39” 55’49” 北ドイツRSO 録音:2000年4月30日-5月3日ハンブルク、ムジークハレ ■Disc8 64’11” ミュンヘンPO 録音:1998年6月24日ミュンヘン、ガスタイク |
|
||
| DUX DUX-1901(1CD) |
ポーリッシュ・ロマンティック・シンフォニーズ フランチシェク・ミレツキ(1791-1862):交響曲 ハ短調(1855) ユゼフ・ヴィエニャフスキ(1837-1912):交響曲 ニ長調 Op.49(1890) |
パヴェウ・プシトツキ(指)、 アルトゥール・ルービンシュタインPO |
|
||
| DUX DUX-1898(1CD) |
クシシュトフ・メイエル(b.1943): ピアノ協奏曲 Op.46 交響曲第6番「ポーランド交響曲」* |
アントニ・ヴィト(指)、カトヴィツェ・ポーランドRSO、 クラクフ・ポーランド放送O* パヴェル・ギリロフ (P) 録音:1984年1月12日&19日-20日、1992年4月30日 |
|
||
| Urania Records WS-121409(2CD) |
マーラー:交響曲第1番&第2番 マーラー:交響曲第1番 「巨人」 交響曲第2番ハ短調「復活」* |
ヘルマン・シェルヘン(指)、 LPO、VPO&cho*、 ミミ・ケルツェ(S)*、 ルクレティア・ウェスト(A)* 録音:1954年、9月(第1番)、1958年10日-12日、ウィーン(第2番) |
|
||
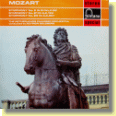 Treasures TRE-276(1CDR) |
S・ゴールドベルク指揮によるモーツァルト アイネ・クライネ・ナハトムジーク* 交響曲第5番K.22 交響曲第21番K.134 交響曲第29番K.201 |
シモン・ゴールドベルク(指) オランダ室内O 録音:1960年12月6-10*、1961年7月6-8日(全てステレオ) ※音源:日VICTOR SFON-10516*、FONTANA SFL-14073 ◎収録時間:65:02 |
|
| “高潔かつ清新!S.ゴールドベルクの美学がここに凝縮!” | |||
|
|||
 Treasures TRE-282(1CDR) |
スワロフスキー/シューマン:交響曲集他 スメタナ:歌劇「売られた花嫁」序曲 交響詩「モルダウ」 シューマン(マーラー編):交響曲第1番「春」* シューマン:交響曲第3番「ライン」# |
ハンス・スワロフスキー(指) オーストリアPO、 ウィーン国立歌劇場O*、ウィーンSO#、 録音:1958年頃、1959年*、1955年1月19&21日#(全てモノラル) ※音源:W.R.C TT-17、仏ODEON XOC-819*,# ◎収録時間:75:27 |
|
| “模範解答的な佳演に留まらないスワロフスキーの熱き表現意欲!” | |||
|
|||
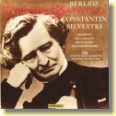 Treasures TRE-286(1CDR) |
超厳選!赤盤名演集Vol.10~シルヴェストリの「幻想」 ファリャ:「はかなき人生」~間奏曲&スペイン舞曲第1番 「恋は魔術師」~火祭りの踊り ベルリオーズ:幻想交響曲* |
コンスタンティン・シルヴェストリ(指) パリ音楽院O 録音:1961年1月31日&2月1日、1961年2月6-8&11日*(全てステレオ) ※音源:東芝 WS-23 、WS-10* ◎収録時間:64:26 |
|
| “伝統に阿らないシルヴェストリに必死に食らいつくパリ音楽院管!” | |||
|
|||
 Treasures TRE-293(1CDR) |
超厳選!赤盤名演集Vol.11~クレンペラーの「大地の歌」 マーラー:大地の歌 |
フリッツ・ヴンダーリッヒ(T) クリスタ・ルートヴィッヒ(Ms) オットー・クレンペラー(指) フィルハーモニアO、ニュー・フィルハーモニアO 録音:1964年2月&1966年7月 ※音源:東芝 AA-8100 ◎収録時間:63:53 |
|
| “永遠に光り続ける「大地の歌」の極北!” | |||
|
|||
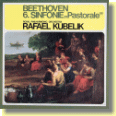 Treasures TRE-294(1CDR) |
超厳選!赤盤名演集Vol.12~クーベリック/田園&ハンガリー舞曲 ブラームス:ハンガリー舞曲集 第1&第3番(以上,ブラームス編) 第5&第6番(以上,シュメリング編) 第17~第21番(以上,ドヴォルザーク編) ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」* |
ラファエル・クーベリック(指) ロイヤルPO 録音:1958年11月20日、1959年1月21-23日*(全てステレオ) ※音源:東芝 ASC-5018、WS-19* ◎収録時間:62:41 |
|
| “40代半ばにしてクーベリックに備わっていた作品の本質を突く手腕!” | |||
|
|||
 Treasures TRE-295(1CDR) |
ライナーのモーツァルトVol.1 アイネ・クライネ・ナハトムジーク* ディヴェルティメント第17番K.334# 交響曲第40番K550 |
フリッツ・ライナー(指)CSO 録音:1954年12月4日*、1955年4月23&26日#、1955年4月24日(全てモノラル) ※音源:米RCA LM-1966*,#、米RCA LM-2114 * ◎収録時間:77:33 |
|
| “モーツァルトだからこそ浮上する強面ライナーの内面に宿る歌心!” | |||
|
|||
 Treasures TRE-296(1CDR) |
ライナーのモーツァルトVol.2 音楽の冗談K.522* ディヴェルティメント11番K.251# 交響曲第41番「ジュピター」 |
フリッツ・ライナー(指) NBC響団員*,#、CSO 録音:1954年9月16日*、1954年9月21日#、1954年4月26日(全てモノラル) ※音源:独RCA LM-1952-B、米RCA LM-2114 * ◎収録時間:75:36 |
|
| “モーツァルトだからこそ浮上する強面ライナーの内面に宿る歌心!” | |||
|
|||
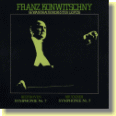 Treasures TRE-299(2CDR) |
コンヴィチュニー/ベートーヴェン&ブルックナー ベートーヴェン:交響曲第7番 ブルックナー:交響曲第5番* |
フランツ・コンヴィチュニー(指) ライプチヒ・ゲヴァントハウスO 録音:1959年6月11-19日、1961年6月26-28&30日*(全てステレオ) ※音源:日VICTOR SFON-5506、日COLUMBIA OP-7084* ◎収録時間:63:21+59:40 |
|
| “攻めの表現にも誇張に傾かない恐るべきバランス感覚!” | |||
|
|||
 Treasures TRE-303(1CDR) |
C.デイヴィスのハイドン&モーツァルト ハイドン:交響曲第84番変ホ長調 Hob.I:84* モーツァルト:交響曲第28番 ハ長調 K. 200 交響曲第38番 ニ長調 「プラハ」K.504 |
コリン・デイヴィス(指) イギリスCO 録音:1960年9月30日&10月2日*、1962年12月7-8日(全てステレオ) ※音源:LOISEAU LYRE SOL-60030*、SOL-266 ◎収録時間:74:23 |
|
| “最後のモーツァルト指揮者、コリン・デイヴィスの真骨頂!” | |||
|
|||
 Treasures TRE-304(1CDR) |
ラインスドルフ&ボストン響・厳選名演集Vol.5~ブラームス 交響曲第2番ニ長調 Op. 73 交響曲第4番 ホ短調 Op. 98* |
エーリッヒ・ラインスドルフ(指) ボストンSO 録音:1964年12月14&16日、1966年4月26-27日*(全てステレオ) ※音源:Victor SHP-2383、RCA LSC-3010* ◎収録時間:78:30 |
|
| “作品によって豹変するラインスドルフの底知れぬ魅力!” | |||
|
|||
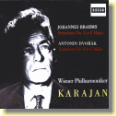 Treasures TRE-305(1CDR) |
カラヤン&VPO/デッカ録音名演集Vol.2 ブラームス:交響曲第3番 ドヴォルザーク:交響曲第8番* |
ヘルベルト・フォン・カラヤン(指)VPO 録音:1961年(ステレオ) ※音源:日KING SLC-1742、SLC-1751* ◎収録時間:69:53 |
|
| “カラヤンの芸術が「人工的」でも「嘘」でもないということの証明!” | |||
|
|||
|
|||
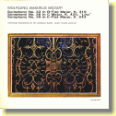 Treasures TRE-307(1CDR) |
ヨッフム&手兵バイエルン放送響とのモーツァルト 交響曲第33番変ロ長調 K. 319 交響曲第36番K.425「リンツ」* 交響曲第39番変ホ長調 K.543# |
オイゲン・ヨッフム(指) バイエルンRSO 録音:1954年11月29-30日*、1955年10月2日#、1954年6月1-2日(全てモノラル) ※音源:英HELIODOR 478-435*,#、DGG 29-307 ◎収録時間:78:52 |
|
| “おおらかなヨッフムと陽のモーツァルトとの幸福な出会い!” | |||
|
|||
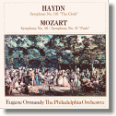 Treasures TRE-308(1CDR) |
オーマンディ~「古典」名演集Vol.1 ハイドン:交響曲第101番「時計」 モーツァルト:交響曲第30番* 交響曲第31番「パリ」# |
ユージン・オーマンディ(指) フィラデルフィアO 録音:1962年1月28日、1962年4月8日*、1961年1月29日#(全てステレオ) ※音源:米COLUMBIA MS-6812、MS-6122*,# ◎収録時間:62:17 |
|
| “オーマンディと古典的様式美との高い親和性を実証!” | |||
|
|||
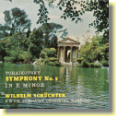 TRT-022(1CDR) |
シュヒター/チャイコフスキー&シベリウス チャイコフスキー:イタリア奇想曲* シベリウス:交響詩「フィンランディア」** 悲しきワルツ# チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調## |
ヴィルヘルム・シュヒター(指) 北西ドイツPO 録音:1954年11月25日*、1957年8月29日**、1955年2月22日#、1956年10月22-25日##(全てモノラル) ※音源:伊EMIL QUM-6361、HMV XLP-20009## ◎収録時間:72:31 |
|
| “シュヒターの厳しい制御が活きた品格漂う名演奏!” | |||
|
|||
 SWR music SWR-19123CD(6CD) NX-E10 |
カール・ベーム SWR録音集1951-1979年 ■CD1 (1)モーツァルト:交響曲第40番 ト短調 K.550 (2)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番 ト長調 Op.58 ■CD2 (1)ベートーヴェン:交響曲第2番ニ長調 Op. 36 (2)ベートーヴェン:交響曲第7番イ長調 Op. 92 ■CD3 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 ■CD4 (1)ブラームス:交響曲第1番ハ短調 Op.68 (2)シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 Op.54 ■CD5 (1)ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 Op.95 (2)ヒンデミット:ウェーバーの主題による交響的変容 ■CD6 ブルックナー:交響曲第7番ホ長調 |
全てカール・ベーム(指) シュトゥットガルト放 RSO ■CD1 ブランカ・ムスリン(P) 録音:(1)1974年9月18日ライヴ(STEREO)※SWR19432CD/93.014と同一音源 (2)1951年4月15日ライヴ(MONO)※93.014と同一音源 ■CD2 録音:1979年2月14日 ライヴ (STEREO) ■CD3 ルート=マルグレート・ピュッツ(S)、シビッラ・プラーテ(A)、ヴァルター・ガイスラー(T)、カール=クリスティアン・コーン(Bs)、シュトゥットガルト放送cho、シュトゥットガルトフィルハーモニーcho 録音:1959年11月12日 シラー生誕200周年記念演奏会のライヴ (MONO) ■CD4 ブランカ・ムスリン(P) 録音:(1)1951年4月15日 (スタジオ) (MONO) (2)1954年12月10日 (ライヴ)(MONO) ■CD5 録音:(1)1954年12月10日ライヴ (MONO) (2)1951年4月15日 ライヴ (MONO) ■CD6 録音:1974年9月18日ライヴi (STEREO) ※※第1楽章の冒頭にオリジナル・テープに由来する2小節の欠落があります。 |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00741(1SACD) 2023年3月22日発売 |
モーツァルト:交響曲第41番「ジュピター」 交響曲第39番変ホ長調 K.543 |
沼尻竜典(指) トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア 録音:2019年3月9日(第41番)、2020年8月1日(第39番) 東京・三鷹市芸術文化センター・ライヴ |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00806(1SACD) 2023年3月22日発売 |
ハイドン交響曲集Vol.19 交響曲第46番ロ長調 Hob.Ⅰ:46 交響曲第34番ニ短調 Hob.Ⅰ:34 交響曲第8番ト長調 Hob.Ⅰ:8「晩」 |
飯森範親(指) 日本センチュリーSO 録音:2020年1月17日(第8番) 大阪、いずみホール、 2020年10月23日(第34番)2021年7月30日(第46番) 大阪、ザ・シンフォニーホール |
|
||
| TOCCATA TOCC-0643(1CD) NX-B03 |
リヒャルト・フルーリー:管弦楽作品集 第3集 交響曲第1番ニ短調(1922-23) 交響曲第4番ハ長調「Liechtensteinische リヒテンシュタイン風」(1950-51) |
BBC響 ポール・マン(指) 録音:2022年1月11-12日 |
|
||
| SOMM ARIADNE-5020(1CD) NX-B04 |
ヴォーン・ウィリアムズ・ライヴ 第4集 (1)トマス・タリスの主題による幻想曲 (2)2台ピアノのための協奏曲 ハ長調(J. クーパー&R. ヴォーン・ウィリアムズ編) (3)交響曲第8番ニ短調 |
アーサー・ホイットモア(P) ジャック・ロウ(P) ディミトリ・ミトロプーロス(指)NYO (3)ジョン・バルビローリ(指)ハレO 録音(全てライヴ/MONO): (1)1943年8月29日 Carnegie Hall、ニューヨーク(USA) (2)1952年2月17日 Carnegie Hall、ニューヨーク(USA) (3)1964年5月15日 Free Trade Hall、 マンチェスター(UK) |
|
||
| GENUIN GEN-23818(1CD) |
マーラー:交響曲第2番「復活」(ブルーノ・ワルター編4手ピアノ版,声楽とトランペット入り) | グレゴール・マイヤー(P)、 ヴァルター・ツォラー(P)、 アンニカ・シュタインバッハ(S)、 ヘンリエッテ・ゲッデ(A) エマヌエル・ミュッツェ(Tp) ゲヴァントハウスcho 録音:2021年12月21日,2022年2月3-4日,5月9-10日 ドイツ ライプツィヒ |
|
||
| BIS BISSA-2476(1SACD) |
マーラー:交響曲第9番 | オスモ・ヴァンスカ(指) ミネソタO 録音:2022年3月21-25日/オーケストラ・ホール(ミネアポリス) |
|
||
| Chandos CHSA-5265(1SACD) |
シューベルト:交響曲集 Vol.3 交響曲第1番ニ長調 D.82 交響曲第4番ハ短調 D.417「悲劇的」 歌劇「フィエラブラス」序曲 Op.76D.796 |
エドワード・ガードナー(指)、 バーミンガム市SO 録音:2022年7月15日-16日、タウン・ホール、バーミンガム(イギリス) |
|
||
| Chandos CHSA-5309(1SACD) |
ラフマニノフ:「幻想的小品集」~前奏曲 Op.3-2(レオポルド・ストコフスキ編) 交響曲第2番ホ短調 Op.27 |
ジョン・ウィルソン(指)、 シンフォニア・オヴ・ロンドン |
|
||
| Sterling CDS-11282(1CDR) |
オーレ・イェッレモー(1873-1938):交響曲第2番 ヴァイオリン協奏曲(1933) ノルウェー・カプリース(Vnと管弦楽の為の)(1935) 交響曲第2番 ロ短調(1922-26) |
マクリスSO、 ヨルン・フォスハイム(指)、 クリストフェル・トゥン・アンデシェン(Vn) 録音:2022年4月22日-23日&25日、ザドゥジュビナ・イリエ・コラルカ(ベオグラード、セルビア) |
|
||
| Da Vinci Classics C-00667(1CD) |
リスト:ダンテ交響曲 S.648(2台ピアノ版) 悲愴協奏曲ホ短調 S.258-1(2台ピアノ版) ダンテ交響曲 S.648(2台ピアノ版) |
デュオ・ソッリーニ・バルバターノ〔マルコ・ソッリーニ(P)、サルヴァトーレ・バルバターノ(P)〕、 ボロメーオ大学cho、 マルコ・ベリーニ(指) 録音:2022年4月、ボロメオ大学(パヴィア、イタリア) |
|
||
| Pentatone PTC-5186992(1CD) |
マーラー:交響曲第2番「復活」 | クリスティアーネ・カルク(S)、エリーザベト・クールマン(A) プラハ・フィルハーモニックcho セミヨン・ビシュコフ(指) チェコPO 録音:2018年11月&12月/ルドルフィヌム、ドヴォルザーク・ホール(プラハ) |
|
||
| ATMA ACD2-2866(1CD) |
アイスストーム・シンフォニー マクシム・グーレ(1980-):アイスストーム・シンフォニー[I. 混乱 / II. あたたかさ / III. 暗黒 / IV. 光] なんて日だ [I. 陽気な朝 / II. 果てしない労働 / III.2人の夕べ / IV. 安らかな夜] 大げさな話 |
ジャック・ラコンブ(指) モントリオール・クラシカル・オーケストラ 録音:2022年8月14・15日/ケベック |
|
||
| VOX VOXNX-3002CD(1CDR) NX-B03 |
ベートーヴェン:交響曲第4番 | ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)BPO 録音:1943年(ライヴ) 収録時間:36分 |
|
||
| ANALEKTA AN-28882(2CD) NX-D09 |
クララ、ロベルト、ヨハネス~情感と構成力 【DISC1】 シューマン:交響曲第3番「ライン」 クララ・シューマン:海辺にて* ある明るい朝に Op.23-2* ローレライ* 4つの束の間の小品 Op.15(第4曲は ピアノ・ソナタの第3楽章として収録) ピアノ・ソナタ ト短調 【DISC2】 ブラームス:交響曲第3番 クララ・シューマン:ピアノ三重奏曲 ト短調 Op.17 |
ナショナル・アーツ・センターO アレクサンダー・シェリー(指) スチュワート・グッドイヤー(P) 川崎洋介(Vn) レイチェル・マーサー(Vc) ガブリエラ・モンテーロ(P) アドリアンヌ・ピエチョンカ(S) リズ・アップチャーチ(P)* 録音:2020年-2022年 収録時間:137分 |
|
||
| Profil PH-22069(1CD) |
ヴィルヘルム・ペーターゼン:交響曲第3番嬰ハ短調 | コンスタンチン・トリンクス(指) フランクフルトRSO 録音:2021年8月30日-9月3日 ヘッセン放送ゼンデザール |
|
||
| GRAND SLAM GS-2287(1CD) |
(1)ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」* (2)スメタナ:交響詩「モルダウ」 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)VPO 録音:1952年11月24&25日*、1951年1月24日ムジークフェラインザール(ウィーン) 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(録音セッション) |
|
||
| SOREL CLASSICS SCCD-003(1CD) 2023年2月10日までのご注文分は 税込¥2050!! |
ジュディス・ラング・ザイモント(b.1945):交響曲第4番「澄んだ、冷たい(水)」(2013)
ピアノ三重奏曲第 1番「ロシアの夏」(1989)* |
ニルス・ムース(指)ヤナーチェクPO ピーター・ウィノグラード(Vn)* ピーター・ウィリック(Vc)* ジョアン・ポーク(P)* 録音:2015年3月 チェコ オストラヴァ、1995 年10月 米国 ニューヨーク州 パーチェイ* |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00808(1SACD) 税込定価 2023年2月22日発売 |
マーラー:交響曲第5番嬰ハ短調 | ジョナサン・ノット(指)東京SO 録音:2022年7月16日 東京・サントリーホール、7月17日 りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 コンサートホール・ライヴ |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00803(1SACD) 税込定価 2023年2月22日発売 |
シューベルト:交響曲第8(9)番「ザ・グレイト」 | ヤン・ヴィレム・デ・フリーント(指) 京都市SO 録音:2022年5月20-21日 京都コンサートホール ・ライヴ |
|
||
| Chandos CHSA-5334(1SACD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲第12番&第15番 ショスタコーヴィチ:交響曲第12番ニ短調 Op.112「1917年」 交響曲第15番イ長調 Op.141 |
ヨン・ストゥールゴールズ(指)、 BBCフィルハーモニック 録音:2022年8月5日-6日(第15番)&9月15日-16日、メディア・シティUK(サルフォード) |
|
||
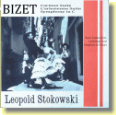 Treasures TRE-292(1CDR) |
ストコフスキーのビゼー 「カルメン」組曲【前奏曲/衛兵の交代/アルカラの竜騎兵/ジプシーの踊り/間奏曲/密輸入者たちの行進/アラゴネーズ】* 「アルルの女」組曲第1番【前奏曲/メヌエット/アダージェット/カリヨン】# 「アルルの女」組曲第2番【田園曲/間奏曲/メヌエット/ファランドール】 交響曲第1番ハ長調+ |
レオポルド・ストコフスキー(指) フィラデルフィアO*、ヒズ交響楽団#,+ 録音:1927年4月30日,5月2&10日*、1952年2月29日#、1952年3月20日+ ※音源:日RCA RVC1523*、英RCA VIC1008#,+ ◎収録時間:79:58 |
| “50年代のストコフスキーの本能的な美への執着と妥協なき表現!” | ||
|
||
 ACCENTUS Music ACC-80575CD(10CD) |
ブロムシュテット/ブルックナー:交響曲全集 ■CD1 交響曲第1番ハ短調 WAB 101[1865/66年リンツ稿,1955年ノヴァーク版] ■CD2 交響曲第2番ハ短調 WAB 102[1872年稿,キャラガン校訂版] ■CD3 交響曲第3番ニ短調 WAB 103[1873年第1稿,1977年ノヴァーク版] ■CD4 交響曲第4番変ホ長調『ロマンティック』 WAB 104[1878/80年,1953年ハース版] ■CD5 交響曲第5番変ロ長調 WAB 105[1875/77年,ノヴァーク版] ■CD6 交響曲第6番イ長調 WAB 106[1879/81年,ハース版] ■CD7 交響曲第7番ホ長調 WAB 107[1881/83年,ハース版] ■CD8&■CD9 交響曲第8番ハ短調 WAB 108[1890年,ハース版] ■CD10 交響曲第9番ニ短調 WAB 109(1887/96年,コールス校訂版2000年) |
ヘルベルト・ブロムシュテット(指) ライプツィヒ・ゲヴァントハウスO ■CD1 録音:2011年6月 ■CD2 録音:2012年3月 ■CD3 録音:2010年9月 ■CD4 録音:2010年10月 ■CD5 録音:2010年5月 ■CD6 録音:2008年9月 ■CD7 録音:2006年11月 ■CD8&CD9 録音:2005年7月 ■CD10 録音:2011年11月 |
|
||
 Altus ALTSA-055R(1SACD) シングルレイヤー 最新リマスター 限定生産 |
ケーゲル/ドレスデン・フィル 来日公演1989〈2023年新リマスター版〉 ベートーヴェン:「エグモント」序曲 交響曲第6番へ長調 「田園」 交響曲第5番「運命」 指揮者によるアンコール曲紹介 バッハ:管弦楽組曲第3番~エア |
ヘルベルト・ケーゲル(指) ドレスデンPO 録音:1989年10月18日サントリーホール(NHKによる実況録音) 収録時間:99分 |
|
||
| IDIS IDIS-6749(1CD) |
カラヤン・スペクタキュラーVol.10 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付き」 |
テレサ・シュティッヒ=ランダル(S) 、ヒルデ・レッセル=マイダン(A)、ヴァルデマール・クメント(T)、ゴットロープ・フリック(Bs) ヘルベルト・フォン・カラヤン(指) ローマRAISO&cho ライヴ録音:1954年12月4日/ローマ |
|
||
| FUGA LIBERA FUG-809(1CD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲第10番 | ウラルPO ドミトリー・リス(指) 録音:2021年11月22日(ライヴ) スヴェルドロフスク・フィルハーモニック大ホール、エカテリンブルク、ロシア |
|
||
 Altus ALTSA-1002(3SACD) シングルレイヤー |
チェリビダッケ&LSO/7つの演奏会1978~1982 (1)ヴェルディ:「運命の力」序曲 ヒンデミット:交響曲「画家マティス」 プロコフィエフ:組曲「ロメオとジュリエット」 (2)ブラームス:交響曲第3番 ブラームス:交響曲第1番 ブラームス:ハンガリー舞曲第1番 (3)シューマン:交響曲第2番 ラヴェル:スペイン狂詩曲 ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲 ワーグナー:「タンホイザー」序曲 (4)モーツァルト:交響曲第38番「プラハ」 シベリウス:「エン・サガ」 プロコフィエフ:交響曲第5番 (5)ティペット:「真夏の結婚」~祭典の踊り (6)ドビュッシー:管弦楽のための「映像」~イベリア ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」 (7)コダーイ:ガランタ舞曲 ラヴェル:組曲「マ・メール・ロア」 ブラームス:交響曲第1番 (8)デュカス:魔法使いの弟子 ラヴェル:ピアノ協奏曲 ト長調* フォーレ:レクイエム** |
アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(P)* マリー・マクローリン(S)s** グウィン・ハウエル(Bs)** リチャード・ヒコックス(合唱指揮)** ロンドン交響cho** セルジュ・チェリビダッケ(指)LSO (1)録音:1978年4月11日 (2)録音:1979年5月31日 (3録音:1979年9月18日 (4)録音:1979年9月21日 (5)録音:1980年4月10日 (6)録音:1980年4月10日 (7)録音:1980年4月13日 (8)録音:1982年4月8日 全てライヴ録音:ロンドン/ロイヤル・フェスティヴァル・ホール |
|
||
| Onyx ONYX-4232(1CD) PONYX-4232(1CD) 国内盤国内盤仕様 解説日本語訳&日本語曲目表記オビ付き 税込定価 |
ロベルト・シエッラ:交響曲第6番 弦楽オーケストラのためのシンフォニエッタ アレグリア/ファンダンゴズ オーケストラのための2つの小品 |
ドミンゴ・インドヤン(指)、 ロイヤル・リヴァプールPO |
|
||
 Pentatone PTC-5187067(1CD) |
マーラー:交響曲第5番嬰ハ短調 | ラファエル・パヤーレ(指)、 モントリオールSO 録音:2022年8月17&18日メゾン・サンフォニク・ド・モンレアル(ケベック) |
|
||
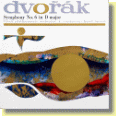 Treasures TRE-270(1CDR) |
アンチェル~ヤナーチェク&ドヴォルザーク ヤナーチェク:タラス・ブーリバ ドヴォルザーク:交響曲第6番* |
カレル・アンチェル(指)チェコPO 録音:1963年4月16-20日、1966年1月22-24日*(共にステレオ) ※音源:日COLUMBIA WS-3033、OS-2339* ◎収録時間:64:45 |
| “アンチェルが潔癖な響きに込めた強烈な共感と民族魂!” | ||
|
||
 Spectrum Sound CDSMBA-132(1CD) |
(1)フランク:交響曲 ニ短調 (2)ストラヴィンスキー:バレエ組曲「火の鳥」(1919年版) |
アンドレ・クリュイタンス(指)フランス国立放送O ライヴ録音:1959年6月19日パリ、シャンゼリゼ劇場(ステレオ) 音源:フランス国立視聴覚研究所音源提供 (24bit/192KHz digital restoration and remastering from the original master tapes) |
|
||
 Spectrum Sound CDSMBA-133(1CD) |
(1)ブラームス:交響曲第2番ニ長調 Op.73 (2)ブラームス:交響曲第4番ホ短調 Op.98 |
(1)ジョルジュ・プレートル(指) (2)アンドレ・クリュイタンス(指) フランス国立放送O (1)ライヴ録音:1968年2月28日シャンゼリゼ劇場(ステレオ) (2)ライヴ録音:1959年2月19日ジュネーヴ(モノラル) 音源:フランス国立視聴覚研究所音源提供 |
|
||
| Hanssler HC-22077(1CD) |
ハイドン:交響曲全集 Vol.27 交響曲第3番ト長調 Hob.I:3 交響曲第33番ハ長調 Hob.I:33 交響曲第108番「B」 変ロ長調 Hob.I:108 交響曲第14番イ長調 Hob.I:14 |
ハイデルベルクSO ヨハネス・クルンプ(指) 録音:2021年3月パラティン、ヴィースロッホ(ドイツ) |
|
||
| C Major 80-7308(2DVD) 80-7404(Bluray) |
ブルックナー:交響曲第3&6番 交響曲第3番ニ短調 WAB103(1877年第2稿・ノーヴァク版) 交響曲第6番イ長調 WAB106 ■ボーナス映像「ディスカヴァリング・ブルックナー」 各交響曲について(ティーレマンと音楽学者ヨハネス=レオポルド・マイヤー氏による対話) |
クリスティアン・ティーレマン(指)VPO 収録:2020年11月(第3番)、2022年4月(第6番)、ウィーン楽友協会(ライヴ) ◆DVD 画面:16:9、NTSC 音声:PCMステレオ、DTS5.0 DVD9 [ボーナス映像 ] 言語:ドイツ語、字幕:英韓,日本語 Total time:181分(交響曲:123分、ボーナス:58 分) ◆Bluray 画面:16:9、1080i 音声:PCMステレオ、 DTS-HD MA5.0 BD50 [ボーナス映像 ] 言語:ドイツ語、字幕:英韓,日本語 Total time:181分(交響曲:123分、ボーナス:58 分) |
|
||
| Hyperion CDA-68405(1CD) |
ヴォーン・ウィリアムズ:交響曲第7番&第9番
南極交響曲(交響曲第7番)* 交響曲第9番ホ短調 |
マーティン・ブラビンズ(指)、 BBC響、BBC交響cho*、 エリザベス・ワッツ(S)* 録音:2022年3月13日-14日、ワトフォード・コロシアム(ワトフォード、イギリス) |
|
||
 Capriccio C-8087(1CD) NX-B07 NYCX-10373(1CD) 国内盤仕様 税込定価 |
ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 WAB108(第1稿/ホークショー版) | リンツ・ブルックナーO マルクス・ポシュナー(指) 録音:2022年7月4-6日リンツ・ミュージックシアター、リハーサル・ホール(オーストリア) |
|
||
| IBS CLASSICAL IBS-142022(1CD) |
マーラー:交響曲第4番ト長調(カルロス・ドミンゲス=ニエトによる室内楽版) | ラケル・ロヘンディオ(S) カメラータ・ガラ(室内オーケストラ)【ゴンサロ・ボーテ(Vn1)、パトリシア・カバニージャス(Vn2)、カルメン・ペレス(Va)、ノーラ・プラット(Vc)、シャビエル・ボイシャデル(Cb)、サレタ・スアレス(Fl)、パウ・ロドリゲス(Ob)、マヌエル・ホダル(Cl)、マリアナ・モスケラ(Fg)、フランシスコ・ガルシア・ロメロ(Hrn)、マイテ・ガルシア(Hp)、カロリナ・アルカラス(パーカッション)、アレハンドロ・ムニョス(指)】 録音:2021年9月7-9日 世界初録音 |
|
||
 ICA CLASSICS ICAC-5170(1CD) NX-B03 |
ベートーヴェン:『プロメテウスの創造物』序曲 R・シュトラウス:交響詩「死と変容」 ドヴォルザーク: 交響曲第8番 |
ミュンヘンPO ロドルフ・ケンペ(指) 録音: 1972年9月9日 ロイヤル・アルバート・ホール BBCプロムスに於けるライヴ(ステレオ) |
|
||
 ICA CLASSICS ICAC-5171(1CD) NX-B03 |
ショスタコーヴィチ:交響曲第10番 バラキレフ(カゼッラ編):イスラメイ* |
クルト・ザンデルリンク(指)ニュー・フィルハーモニアO キリル・コンドラシン(指)ロイヤルPO* 録音: 1973年5月15日、1978年1月24日* ロイヤル・フェスティヴァル・ホール・ライヴ(ステレオ) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2284(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第1番ハ長調 Op.21 交響曲第5番ハ短調 Op.67「運命」* |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)VPO 録音:1952年11月24、27日、 1954年2月28日、3月1日*/ムジークフェラインザール(ウィーン) 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(録音セッション) |
|
||
| Goodies 78CDR-3890(1CDR) |
プロコフィエフ:交響曲第1番「古典交響曲」 | セルジュ・チェリビダッケ(指)BPO 仏 VSM SL141/42(英HMV C3729/30と同一録音) 1948年2月4,5,6日ベルリン録音 |
|
||
 Treasures TRE-269(1CDR) |
F.ブッシュのベートーヴェン「第9」 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付」 |
フリッツ・ブッシュ(指) デンマーク放送SO&cho シェシュティン・リンドベリ=トルリンド(S) エリセ・イェーナ(Ms) エリク・ショーベリ(T) ホルガー・ビルディン(Bs) 録音:1950年9月7日 ライヴ ※音源:MELODIA M10-46963-003 ◎収録時間:62:08 |
| “理性と直感で一時代先を見通すフリッツ・ブッシュのベートーヴェン!” | ||
|
||
| オクタヴィア OVCL-00801(1SACD) 税込定価 2023年1月25日発売 |
エルガー:交響曲第2番変ホ長調 作品63 | 尾高忠明(指) 大阪フィルハーモニーSO 録音:2022年4月8-9日、大阪・フェスティバルホール・ライヴ |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00804(1SACD) 税込定価 2023年1月25日発売 |
ハイドン交響曲集Vol.18 交響曲第3番ト長調 Hob.I:3 交響曲第15番二長調 Hob.I:15 交響曲第5番イ長調 Hob.I:5 |
飯森範親(指) 日本センチュリーSO 録音:2021年4月22日 大阪、ザ・シンフォニーホールにてライヴ |
|
||
| APARTE AP-307(1CD) |
モーツァルト~始まりと終わり 交響曲第1番変ホ長調K.16 ピアノ協奏曲第23番イ長調K.488 交響曲第41番ハ長調K.551「ジュピター」 |
マキシム・エメリャニチェフ(P,指) イル・ポモ・ドーロ 録音:2022年6月28-30日 ノートルダム・デュ・リバン(パリ) |
|
||
| Nimbus Alliance NI-6432(1CDR) |
エイドリアン・ウィリアムズ(b.1956):交響曲第1番(2020)、 室内協奏曲 「ネッド・ケリーのポートレイト」(1998) |
イギリスSO、 ケネス・ウッズ(指) 録音:2021年4月8日&12月1日-2日 |
|
||
| Forgotten Records fr-1856B(2CDR) |
モーツァルト:交響曲集 第28番ハ長調 K.200 /第29番イ長調 K.201 # /第30番二長調 K.202 /第31番 「パリ」/第32番ト長調 K.318 /第33番変ロ長調 K.319 + /第34番ハ長調 K.338 # /第35番「ハフナー」* |
オットー・アッカーマン(指) ワルター・ゲール(指)+ ヘンリー・スウォボダ(指)#,* オランダPO、ウィーン国立歌劇場O# 録音:1954年、1955年#,+ ※音源: Musical Masterpiece Society MMS 3027/29 他 |
| Forgotten Records fr-1862(1CDR) |
シューリヒト&アラウ~ベートーヴェン ピアノ協奏曲第3番ハ短調 Op.37* 交響曲第5番「運命」ハ短調 Op.67 # |
クラウディオ・アラウ(P) カール・シューリヒト(指) フランス国立放送O 録音:1959年3月24日、シャンゼリゼ劇場* 1956年9月23日、モントルー音楽祭#、共にライヴ |
| Altus ALTXR-1001(2XRCD) 新規リマスター 初XRCD化 完全限定生産 |
チェリビダッケ、幻のリスボン・ライヴ「XRCD」 ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 |
セルジュ・チェリビダッケ(指) ミュンヘンPO ライヴ録音:1994年4月23日コリセウ・リスボン(ステレオ) ポルトガル国営放送(RTP)によるデジタル録音 |
|
||
| Altus ALTXR-1003(XRCD) 新規リマスター 初XRCD化 |
チェリビダッケのシューマン&ブラームス
東京ライヴ「XRCD」 シューマン:交響曲第4番ニ短調 Op.120 ブラームス:交響曲第4番ホ短調 Op.98* |
セルジュ・チェリビダッケ(指) ミュンヘンPO ライヴ録音:1986年10月14日昭和女子大学 人見記念講堂 1986年10月15日東京文化会館* |
|
||
| ALPHA ALPHA-932(1CD) |
ブルックナー:交響曲第7番 | チューリヒ・トーンハレO パーヴォ・ヤルヴィ(指) 録音:2022年1月 チューリヒ・トーンハレ ※ 国内仕様盤日本語解説…舩木篤也 |
|
||
| ALPHA ALPHA-692(1CD) |
ハイドン交響曲全曲録音シリーズ Vol.13 1-4. 交響曲第31番ニ長調 Hob. I:31「ホルン信号」 5-8. 交響曲第59番イ長調 Hob. I:59「火事」 9-12. 交響曲第48番ハ長調 Hob. I:48「マリア・テレジア」 |
イル・ジャルディーノ・アルモニコ(古楽器使用) コンサートマスター:ステファノ・バルネスキ(Vn) ジョヴァンニ・アントニーニ(指) 録音:2021年4月10-16日、マーラー・ホール(エウレジ オ文化センター)、ドッビアーコ(イタリア北東部ボルツァーノ県) |
|
||
| BERLINER PHILHARMONIKER KKC-9784 (2CD+1Bluray) 初回封入特典付 税込定価 |
ショスタコーヴィチ:交響曲集 ■CD1:交響曲第8番Op.65 ■CD2:交響曲第9番Op.70、 交響曲第10番Op.93 ■Blu-ray Disc □Video 上記全曲のコンサート映像(すべてHD映像) インタビュー映像(キリル・ペトレンコ) □Audio: 上記全曲のロスレス・スタジオ・マスター音源の音声トラック 2.0PCM Stereo 24-bit / 96kHz 7.1.4Dolby Atmos 24-bit / 48kHz □ダウンロード・コード この商品には、上記全曲のハイレゾ音源(24-bit / 96kHz)をダウンロードするためのURLとそのパスワードが封入されています。 □デジタル・コンサートホールベルリン・フィルの映像配信サービス「デジタル・コンサートホール」を7日間無料視聴できるチケット・コードが封入されています。 |
キリル・ペトレンコ(指)BPO □Video 画面:Full HD 1080/60i,16:9 音声:2.0PCM,7.1.4Dolby Atmos リージョン:ABC(worldwide) 総収録時間(コンサート):152分 字幕:英、独、日本語 録音:2020年11月13日(第8番)、2020年10月31日(第9番)、2021年10月29日(第10番) すべてベルリン・フィルハーモニー |
|
||
 Altus ALT-522(1CD) |
マーラー:交響曲第1番「巨人」 | 大野和士(指)東京都SO ライヴ録音:2021年4月20日/東京文化会館(第924回定期演奏会Aシリーズ) |
|
||
 Altus ALTSA-1001(1SACD) シングルレイヤー 国内プレス 新規リマスター 初SACD化 500セット限定 日本語帯・解説付 |
チェリビダッケ、幻のリスボン・ライヴ「SACD」 ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 |
セルジュ・チェリビダッケ(指) ミュンヘンPO ライヴ録音:1994年4月23日/コリセウ・リスボン(ステレオ) ポルトガル国営放送 (RTP)によるデジタル録音 |
|
||
 Spectrum Sound CDSMBA-119(1CD) |
ポール・パレー・ライヴ録音集イン・パリ1966&1973 (1)シューマン:交響曲第3番「ライン」 (2)シューマン:交響曲第4番ニ短調 Op.120 (3)シャブリエ:狂詩曲「スペイン」 (4)ラヴェル:ラ・ヴァルス |
ポール・パレー(指) (1)(3)フランス国立放送PO、 (2)(4)フランス国立放送O ライヴ録音:(1)(3)1973年10月2日オペラ=コミック座(ステレオ)、 (2)(4)1966年6月28日シャンゼリゼ劇場(ステレオ) |
| “パレーが生涯持ち続けた瑞々しい表現へのこだわり” | ||
|
||
 Spectrum Sound CDSMBA-131(1CD) |
ブルックナー:交響曲第7番ホ長調 WAB107 | マリユス・コンスタン(指)、 フランス国立放送PO ライヴ録音:1971年3月16日メゾン・ド・ラジオ・フランス内オリヴィエ・メシアン・ホール、スタジオ104(ステレオ) |
|
||
| TCO TCO-0005(1SACD) |
ジョージ・ウォーカー:アンティフォニー シンフォニア第4番「Strands」 ライラック* シンフォニア第5番「Visions」 |
フランツ・ウェルザー=メスト(指) クリーヴランドO ラトニア・ムーア(S)* 録音:2020年10月、2021年10月、2022年3月 |
|
||
| BRIDGE BCD-9572(1CD) |
アメリカのロマンティシズムの古典 ブリストー(1825-98):交響曲第4番 「理想郷」 フライ(1813-64):ナイアガラ交響曲 |
レオン・ボツタイン(指) ザ・オーケストラ・ナウ 録音:2022年 1月 米国 ニューヨーク州 アナンデール=オン=ハドソン |
|
||
| ALPHA ALPHA-898(1CD) |
フランク:交響曲 ニ短調 交響詩「贖罪」 (管弦楽の断章) 第1版 交響詩「呪われた狩人」 |
フランクフルトRSO アラン・アルティノグル(指) 録音:2022年1月、2022年6月 HRゼンデザール、ヘッセン放送、フランクフルト |
|
||
| MClassics MYCL-00040(1SACD) 税込定価 |
シューマン:交響曲第2番 ブラームス:大学祝典序曲 |
山下一史(指) 愛知室内オーケストラ 録音:2022年4月16日 名古屋、三井住友海上しらかわホール(ライヴ) |
|
||
 Spectrum Sound CDSMBA-118(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第4番変ロ長調 OP.60 ドビュッシー:6つの古代のエピグラフ ドビュッシー:「海」 |
エルネスト・アンセルメ(指) フランス国立放送PO ライヴ録音:1967年1月11日メゾン・ド・ラジオ・フランス内オリヴィエ・メシアン・ホール、スタジオ104(ステレオ) 音源:フランス国立視聴覚研究所音源提供 |
|
||
 Spectrum Sound CDSMBA-117(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付き」 | マリア・ポーザ(S)、アルレット・シュデル(C.A)、ゲオルク・イェルデン(T)、ジャック・マルス(Bs) フランス国立放送O&cho ポール・パレー(指) ライヴ録音:1966年11月8日シャンゼリゼ劇場(ステレオ) 音源:フランス国立視聴覚研究所音源提供 |
|
||
| BIS BISSA-2669(3SACD) |
シューマン:交響曲&序曲集 (1)交響曲第1番「春」 (2)ツヴィッカウ交響曲 (3)序曲.スケルツォとフィナーレ (4)歌劇「ゲノヴェーヴァ」序曲 (5)序曲「メッシーナの花嫁 (6)交響曲第2番ハ長調 Op.61 (7)交響曲第4番ニ短調(原典版) (8)「ゲーテのファウストからの情景」序曲 (9)序曲「ジュリアス・シーザー」 (10)交響曲第3番「ライン」 (11)交響曲第4番ニ短調(現行版) (12)「マンフレッド」序曲 (13)序曲「ヘルマンとドロテア」 |
トーマス・ダウスゴー(指)、 スウェーデン室内O 録音:(3)(6)2005年3月、(7)(8)(9)2006年3月、(2)(12)2006年10月、(4)(5)2006年12月、(10)(11)2007年5月、(1)(11)(13)2007年8月/エレブルー・コンサートホール(スウェーデン) |
|
||
 King International KKC-4310(1SACD) シングルレイヤー 税込定価 |
モーツァルト:交響曲選集 (1)交響曲第32番ト長調KV318 (2)交響曲第33番変ロ長調KV319 (3)交響曲第34番ハ長調KV338 (4)交響曲第39番変ホ長調KV543 (5)交響曲第40番ト短調KV550 (6)交響曲第41番ハ長調KV551「ジュピター」 |
オトマール・スイトナー(指) シュターツカペレ・ドレスデン (1)録音:1974年1月4-7日、10月28日 (2)録音:1974年1月4-7日、10月28日 (3)録音:1974年1月4-7日、10月28日 (4)録音:1974年11月21、22日&1975年3月17、18日 (5)録音:1974年11月21、22日&1975年3月17、18日 (6)録音:1973年3月5、6日 |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00796(1SACD) 税込定価 2022年12月21日発売 |
ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」(1878/80年稿 ノーヴァク版) | ジョナサン・ノット(指) 東京SO 録音:k2021年10月16日 東京・サントリーホール・ライヴ |
|
||
| CD ACCORD ACD-299(1CD) NX-C09 |
ペンデレツキ:ピアノ協奏曲「復活」(2007年版) 交響曲第2番「クリスマス」 |
バリー・ダグラス(P) ワルシャワPO アンドレイ・ボレイコ(指) 録音:2022年3月11日&12日(1-3)、2021年11月27日(4-6) ワルシャワ・フィルハーモニー・ホール |
|
||
| CPO CPO-777898(1CD) NX-B10 |
ルイ・グラス(1864-1936):交響曲全集 第3集 交響曲第4番ホ短調 Op. 43 |
ライン州立PO ダニエル・ライスキン(指) 録音:2014年6月24日-7月1日 |
|
||
| CPO CPO-555556(1CD) NX-B10 |
グラジナ・バツェヴィチ:交響的作品全集 第1集 交響曲第3番(1952) 交響曲第4番(1953) |
ケルンWDRSO ウカシュ・ボロヴィチ(指) 録音:2021年11月20-26日 |
|
||
| SOMM ARIADNE-5019(2CD) NX-C09 |
ヴォーン・ウィリアムズ・ライヴ 第3集 【CD1】 1-9. 交響曲第2番「ロンドン交響曲」 10-17. 交響曲第5番 【CD2】 1-4. 交響曲第5 5-10. カンタータ「ドナ・ノビス・パーチェム」 |
LSO…CD1:1-9 LPO…CD1: 10-17、CD2:1-4 レニー・フリン(S)…CD2:5-10 ロイ・ヘンダーソン(Br)…CD2:5-10 BBC響&cho……CD2:5-10 レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ(指) 録音:全てライヴ 1946年7月31日…CD1:1-9 1943年7月31日…CD1:10-17 1952年9月3日…CD2:1-4 以上、BBCプロムス Royal Albert Hall,London(UK) 1936年11月 BBC Studios, England(UK)…CD2: 5-10 |
|
||
| philharmonia・rec PHR-0113(1CD) |
ドヴォルザーク:交響曲第8番ト長調Op.88 交響曲第7番ニ短調Op.70 |
フィルハーモニア・チューリッヒ ジャナンドレア・ノセダ(指) 録音:2021年10月(第8番)、2022年3月(第7番)、チューリッヒ歌劇場(ライヴ) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2282(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第4番変ロ長調 Op.60 交響曲第7番イ長調 Op.92 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)VPO 録音:1952年12月1&2日、1950年1月18&19日*/ムジークフェラインザール(ウィーン) 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) |
|
||
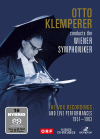 OTTO KLEMPERER FILM FOUNDATION KKC-4317(16SACD) |
クレンペラー&ウィーン響/ VOXレコーディング&ライヴ録音集1951~1963 ■Disc1 ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」 メンデルスゾーン:交響曲第4番「イタリア」 ■Disc 2 ベートーヴェン:ミサ・ソレムニス ■Disc 3 ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」 ■Disc 4 マーラー:交響曲第2番「復活」 ■Disc 5 マーラー:交響曲第2番「復活」 ■Disc 6 マーラー:大地の歌 ■Disc 7 ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」 シューベルト:交響曲第4番「悲劇的」* ■Disc 8 メンデルスゾーン:交響曲第3番「スコットランド」 ショパン:ピアノ協奏曲第2番* ■Disc 9 シューマン:ピアノ協奏曲イ短調 Op.54 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番 ■Disc 10、11 モーツァルト:交響曲第41番「ジュピター」 マーラー:交響曲第4番ト長調 ■Disc 12、13 バッハ:管弦楽組曲第3番 ブラームス:交響曲第3番 ベートーヴェン:交響曲第7番 ■Disc 14 録音:1958年2月26日(ライヴ) ブルックナー:交響曲第7番 ■Disc 15、16 ベートーヴェン:序曲「コリオラン」 交響曲第2番ニ長調 Op.36 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 |
オットー・クレンペラー(指)ウィーンSO ■Disc1 録音:1951年3月8~12&15日(VOX) ■Disc 2 イローナ・シュタイングルーバー(S)、エルゼ・シュールホフ(C.A)、エーリヒ・マイクート(T)、オットー・ヴィーナー(Bs)、ウィーン・アカデミーcho 録音:1951年3月8~12&15日(VOX) ■Disc 3 録音:1951年3月8-12&15日(VOX) ■Disc 4 イローナ・シュタイングルーバー(S)、ヒルデ・レッセル=マイダン(Ms)、ウィーン・アカデミーcho、ウィーン楽友協会cho 録音:1951年5月14-16日(VOX) ■Disc 5 イローナ・シュタイングルーバー(S)、ヒルデ・レッセル=マイダン(Ms)、ウィーン・アカデミーcho ウィーン楽友協会cho 録音:1951年5月18日(ライヴ) ■Disc 6 エルザ・カヴェルティ(A)、アントン・デルモタ(T) 録音:1951年5月20-23日(VOX) ■Disc 7 録音:1951年5月20-23日(VOX) プロ・ムジカO* 録音:1950年11月19-20日、パリ* ■Disc 8 ヘルベルト・ハフナー(指,第1楽章のみクレンペラーの指揮) 録音:1951年5月20-23日(VOX) ギオマール・ノヴァエス(P)* 録音:1951年6月9-11日(VOX)* ■Disc 9 ギオマール・ノヴァエス(P) 録音:1951年6月9-11日(VOX) ■Disc 10、11 テレサ・シュティッヒ=ランダル(S)、録音:1955年6月21日(ライヴ) ※全コンサートCD初収録 ■Disc 12、13 録音:1956年3月8日(ライヴ) ※全コンサートCD初収録 ■Disc 14 録音:1958年2月26日(ライヴ) ■Disc 15、16 1963年6月16日(ライヴ) ※全コンサートCD初収録 |
|
||
 Altus ALT-521(6CD) 限定生産 |
準・メルクル&N響/ライヴシリーズ・コレクション 【ALT006/7】(2CD) (1)ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲 (2)R.シュトラウス:死と変容 (3)ドビュッシー:交響詩『海』 (4)モーツァルト:『ドン・ジョヴァンニ』序曲 (5)ブラームス(シェーンベルク編):ピアノ四重奏曲第1番 ト短調 【ALT017】 (1)バルトーク:ルーマニア民俗舞曲 (2)ドヴォルザーク:交響曲第9番ホ短調『新世界より』 【ALT057】 (1)メンデルスゾーン:交響曲第3番イ短調『スコットランド』 (2)メンデルスゾーン:交響曲第4番イ長調『イタリア』 【ALT081/2】(2CD) マーラー:交響曲第2番『復活』 |
準・メルクル(指)NHK響 【ALT006/7】(2CD) ライヴ録音:(1)~(3)1997年6月23日サントリーホール、 (4)(5)1998年4月29日NHKホール 【ALT017】 ライヴ録音:(1)2001年1月17日サントリーホール、 (2)2001年1月27日NHKホール 【ALT057】 ライヴ録音:(1)2001年1月17日サントリーホール、 (2)2001年9月14日NHKホール 【ALT081/2】(2CD) ミカエラ・カウネ(S)、 リオバ・ブラウン(Ms)、 二期会cho ライヴ録音:2003年10月23日NHKホール |
|
||
| Profil PH-20038(2CD) |
ブルックナー:交響曲第4番『ロマンティック』(1878/80年稿) 交響曲第5番変ロ長調 |
ルドルフ・ケンペ(指) ミュンヘンPO 録音:1975、1976年ミュンヘン |
|
||
| Profil PH-20037(3CD) |
ブラームス:交響曲全集 交響曲第1番ハ短調 Op.68 交響曲第2番ニ長調 Op.73 交響曲第3番へ長調 Op.90 交響曲第4番ホ短調 Op.98 ハイドンの主題による変奏曲 |
ルドルフ・ケンペ(指) ミュンヘンPO 録音:1974、1975年ミュンヘン |
|
||
 OTTO KLEMPERER FILM FOUNDATION KKC-4315(2SACD) |
1947年ザルツブルク音楽祭ライヴ / クレンペラー&ウィーン・フィル ラジオ・アナウンス パーセル(1659~1695):組曲「妖精の女王」(ハロルド・バーンズ編) ロイ・ハリス(1898~1979):交響曲第3番(1939) マーラー:交響曲第4番ト長調 ラジオ・アナウンス |
オットー・クレンペラー(指)VPO ヒルデ・ギューデン(S) 録音:1947年8月24日、ザルツブルク音楽祭、ライヴ |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00798(1SACD) 税込定価 2022年11月23日発売 |
ハイドン交響曲集Vol.17 交響曲第33番ハ長調 Hob.Ⅰ:33 交響曲第48番ハ長調 Hob.Ⅰ:48「マリア・テレージア」 交響曲第36番変ホ長調 Hob.Ⅰ:36 |
飯森範親(指) 日本センチュリーSO 録音:2019年11月22日 大阪、いずみホール・ライヴ |
|
||
| LSO Live LSO-0570(4SACD) |
ブラームス:交響曲全曲他 交響曲第1番ハ短調 op.68 悲劇的序曲 op.81 ヴァイオリンとチェロのための協奏曲 イ短調 op.102(二重協奏曲) 交響曲第2番ニ長調 op.73 セレナード第2番イ長調 op.16 交響曲第3番ヘ長調 op.90 交響曲第4番ホ短調 op.98 |
ベルナルト・ハイティンク(指) LSO ゴルダン・ニコリッチ(Vn)、 ティム・ヒュー(Vc) 録音:2003-2004年/バービカン・センター |
|
||
| TUDOR TUD-1741(2SACD) NX-C07 |
ブラームス:交響曲第1番ハ短調 Op. 68 ブラームス:ハンガリー舞曲集 第1番/第3番/第10番 ドヴォルザーク:交響曲第6番 ニ長調 Op. 60 ブラームス:ハンガリー舞曲集 第17番/第18番/第19番 第20番/第21番 |
バンベルクSO ヤクブ・フルシャ(指) 録音:2020年9月21-24日、2021年1月25日、2021年1月22-25日、2020年9月24日、2020年10月1日 CD層…Stereo SACD…Stereo、マルチチャンネル5.1 |
|
||
| TUDOR TUD-1742(2SACD) NX-C07 |
ブラームス:交響曲第2番ニ長調 Op. 73 ドヴォルザーク::交響曲第7番ニ短調 Op. 70 |
バンベルクSO ヤクブ・フルシャ(指) 録音:2019年5月6-8日、2020年9月28日-10月1日 CD層…Stereo SACD…Stereo、マルチチャンネル5.1 |
|
||
| Epitagraph EPITA-029(1CD) (UHQCD) |
ブルックナー:交響曲第9番ニ短調 (原典版) | ブルーノ・ワルター(指)VPO 録音:1953年8月20日(ザルツブルク音楽祭) 祝祭劇場、ザルツブルク(ライヴ) |
|
||
| Edition HST HST-919(6CD) PP ケース入り 税込定価 |
ヴァンハル(1739-1813)&伝ヴァンハル;15 の交響曲集
(HST-919) ■CD1(第15巻;HST-095) ハ長調Bryan C8/ニ長調Bryan D6/ (伝)変ホ長調Bryan Es14=Grave Es15(ディッタース作?) ■CD2(第18巻;HST-106) ハ長調Bryan C27 (伝)ハ長調Bryan C24=Kimball C14, (ホフマン作?) (伝)ハ長調C25(シュテルケル作?) ■CD3(第21巻;HST-108) ハ長調「デ・シリー」 Bryan C4 ハ長調「混乱稿」C7a (伝)変ホ長調Bryan Es9(トウシュムラン作?) ■CD4(第22巻;HST-112) (伝)ニ長調Bryan D11(シュテルケル作?) (伝)イ長調Bryan A6(ディッタース作?) ■CD5(第23巻;HST-114) ハ長調Bryan C28 (伝)変ロ長調Bryan B8(ケルツル作?) ■CD6(第24巻;HST-117) ハ長調Bryan C18 (伝)変ホ長調Bryan Es11(ポコルニー作?) |
ハイドン・シンフォ二エッタ トウキョウ リーダー;松井利世子、 福本 牧(Vn)、 小原 圭(Vc)、他 録音:2010-19年、東京・三鷹、風のホール、近江楽堂(新宿)などにてライヴ収録 |
|
||
| Glossa GCD-921131(2CD) |
ボッケリーニ:6つの交響曲 Op.35 交響曲 ヘ長調 Op.35-4/交響曲 変ロ長調 Op.35-6/交響曲 変ホ長調 Op.35-2/交響曲 イ長調 Op.35-3/交響曲 ニ長調 Op.35-1/交響曲 変ホ長調 Op.35-5 |
マルク・デストリュベ(コンサートマスター)、 18世紀オーケストラ 録音:2021年5月&2022年5月、カイゼル運河教会(アムステルダム、オランダ) |
|
||
| TOCCATA TOCC-0676(1CD) NX-B03 |
トーマス・ド・ハルトマン(1885-1956):管弦楽作品集
第2集 交響詩第1番Op. 50(1934) 幻想的協奏曲 - コントラバスと管弦楽のために Op. 65(1942-44) |
レオン・ボッシュ(Cb) リヴィウ国立フィルハーモニーSO テオドレ・クチャル(指) 録音:2021年9月15、20、21、23日 ※全て世界初録音 |
|
||
| ICA CLASSICS ICAB-5167(20CD) NX-L05 |
BBCレジェンズ・グレート・レコーディングス
第3集 ■Disc 1 シューベルト:交響曲 第2番変ロ長調 D 125 ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 Op. 73 ■Disc 2 エルガー:序奏とアレグロ Op. 43 交響曲第1番変イ長調 Op. 55 ■Disc 3 R・シュトラウス:4つの最後の歌# マーラー:さすらう若者の歌 マーラー:リュッケルトの5つの歌 より私は快い香りを吸い込んだ/ 私はこの世に捨てられて/真夜中に R. シュトラウス:あなたは私の心の王冠 Op. 21-2* R. シュトラウス:憩え、わが心 Op. 27-1* R. シュトラウス:献呈 Op. 10-1* ブラームス:子守歌 Op. 49-4* ブラームス:セレナード Op. 106-1* ■Disc 4 (1)ケルビーニ:歌劇「アナクレオン」序曲 (2)ベートーヴェン: 交響曲第3番変ホ長調 Op. 55「英雄」 (3)R. シュトラウス:ドン・ファン Op. 20 (4)ベルリオーズ:『ファウストの劫罰』 Op. 24より ラコッツィ行進曲 ■Disc 5 バッハ:半音階的幻想曲とフーガ ニ短調 BWV 903 ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第22番ヘ長調 Op. 54 シューベルト:ピアノ・ソナタ 第11番ヘ短調 D 625 シューベルト:3つのピアノ曲(即興曲) D 946 シューベルト:4つの即興曲 D 899より 第3番/. 第4番 ■Disc 6 (1)シベリウス:交響曲第2番ニ長調 Op. 43 (2)チャイコフスキー:『眠れる森の美女』 組曲 (3)ベートーヴェン:エグモント序曲 ■Disc 7 リスト:ファウスト交響曲 S 108 ■Disc 8 モーツァルト:レクイエム K. 626 ニ短調 ブリテンとの対話(聞き手…ドナルド・ミッチェル)* ■Disc 9 ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第9番ホ長調 Op. 14-1 ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第10番ト長調 Op. 14-2 シューベルト:さすらい人幻想曲 シューマン:アベッグ変奏曲 Op. 1* シューマン:ウィーンの謝肉祭の道化 Op. 26* ショパン:練習曲 嬰ハ短調 Op. 10-4* ■Disc 10 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 ■Disc 11…BBCL4160 チャイコフスキー:ピアノ協奏曲 第1番* ムソルグスキー:展覧会の絵 シューラ・チェルカスキー(1909-1995):悲愴的前奏曲 リムスキー=コルサコフ(ラフマニノフ編):熊蜂の飛行 ■Disc 12 ハイドン:交響曲第100番「軍隊」 ハイドン:交響曲第101番「時計」 ヒンデミット:ウェバーの主題による交響的変容* ■Disc 13 バッハ:カプリッチョ ホ長調 BWV 993「ヨハン・クリストフ・バッハを讃えて」 レーガー:バッハの主題による変奏曲とフーガ Op. 81 ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第24番嬰へ長調 Op. 78「テレーゼ」 ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第21番ハ長調 Op. 53「ワルトシュタイン」 ■Disc 14 ショスタコーヴィチ:交響曲第8番 ハ短調 Op. 65 ■Disc 15 ウェーバー:歌劇「オベロン」 序曲 シューベルト:交響曲第9番「グレイト」 ブラームス:悲劇的序曲* ■Disc 16 ハイドン:チェロ協奏曲 第1番ハ長調 Hob. VIIb:I* サン=サーンス:チェロ協奏曲 第1番# エルガー:チェロ協奏曲 ホ短調 Op. 85 ■Disc 17 チャイコフスキー:バレエ『くるみ割り人形』 Op. 71第2幕 ショスタコーヴィチ:バレエ『ボルト』組曲~ 序曲/ 官僚の踊り/ 間奏曲/ 御者の踊り ストラヴィンスキー:バレエの情景* ■Disc 18…BBCL4210 モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲 第3番(カデンツァ…サム・フランコ) ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集 「四季」 Op. 8-1-4 ヴィヴァルディ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 イ短調 Op. 3-8RV 522より第3楽章 ■Disc 1 ヴォーン・ウィリアムズ:交響曲 第4番ヘ短調 シベリウス:交響曲第4番イ短調 Op. 63* ■Disc 20 スカルラッティ:ソナタ集~ ニ短調 K. 141/ヘ長調 K. 518/ニ短調 K. 32/ヘ短調 K. 466/イ長調 K. 533/ ロ短調 K. 27/ ト長調 K. 125 ドビュッシー:ピアノのために ドビュッシー:『映像』 第1集 より 水の反映 ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第27番ホ短調 Op. 90* スクリャービン:ピアノ・ソナタ 第4番嬰へ長調 Op. 30* プロコフィエフ:『つかの間の幻影』*~ 第1番、第3番、第5番、第10番、第11番、第17番 プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ 第3番イ短調 Op. 28* |
■Disc 1…BBCL4104 カール・ベーム(指)LSO 録音:1977年6月28日 ロイヤル・フェスティヴァル・ホール (ステレオ) ■Disc 2…BBCL4106 ジョン・バルビローリ(指)ハレO 録音:1970年7月24日 聖ニコラス教会(キングス・リン音楽祭) (ステレオ) ■Disc 3…BBCL4107 セーナ・ユリナッチ(S)、クリスタ・ルートヴィヒ(Ms)、マルコム・サージェント(指)BBC響# アンドレ・クリュイタンス(指)フィルハーモニアO ジェフリー・パーソンズ(P) 録音:1957年12月2日 ロイヤル・フェスティヴァル・ホール、1961年9月11日 ロイヤル・アルバート・ホール、1978年7月15日 ウィグモア・ホール *=(ステレオ) ■Disc 4…BBCL4112 ロイヤルPO(1)(2)、BBCノーザンSO(3)、LSO(4) ピエール・モントゥー(指) 録音:1960年1月25日 BBCスタジオ81、 1960年11月12日 BBCスタジオ(2)、1960年12月21日 ミルトン・ホール(3)、1961年12月15日 キングズウェイ・ホール(4) (モノラル) 録音:1969年6月5日 クイーン・エリザベス・ホール(ステレオ) ■Disc 5…BBCL4045 ウィルヘルム・ケンプ(P) 録音:1969年6月5日 クイーン・エリザベス・ホール(ステレオ) ■Disc 6…BBCL4115 BBC響*、ニュー・フィルハーモニアO、レオポルド・ストコフスキー(指) 録音:1964年9月15日 ロイヤル・アルバート・ホール(1) 1965年9月10日 キングズウェイ・ホール(2) 1973年7月7日 BBCスタジオ(3) *=ステレオ ■Disc 7…BBCL4118 ジョン・ミッチンソン(T) BBCノーザン・シンガーズ男声cho、BBCノーザンSO、ヤッシャ・ホーレンシュタイン(指) 録音:1972年4月23日 サルフォード大学 (ステレオ) ■Disc 8…BBCL4119 ヘザー・ハーパー(S)、アルフレーダ・ホジソン(C.A)、ーター・ピアーズ(T)、ジョン・シャーリー=カーク(Bs)、オlールドバラ祝祭cho、イギリス室内O、ブリテン(指) 録音:1971年7月20日 スネイプ・モルティングス・コンサート・ホール 録音:1969年2月 レッド・ハウス、オールドバラ* (モノラル) ■Disc 9…BBCL4126 スヴャトスラフ・リヒテル(P) 録音:1963年1月27日*、同年2月2日 ロイヤル・フェスティヴァル・ホール (モノラル) ■Disc 10…BBCL4131 マリアンネ・ヘッガンデル(S)、アルフレーダ・ホジソン(C.A)、ロバート・ティアー(T)、グウィン・ハウエル(Bs)、LPO&cho、クラウス・テンシュテット(指) 録音:1985年9月13日 ロイヤル・フェスティヴァル・ホール (ステレオ) ■Disc 11…BBCL4160 シューラ・チェルカスキー(P)、ゲオルグ・ショルティ(指)LSO* 録音:1968年1月30日 ロイヤル・フェスティヴァル・ホール* 1982年2月20日 ウィグモア・ホール (ステレオ) ■Disc 12…BBCL4176 オイゲン・ヨッフム(指)LPO、LSO* 録音:1973年1月30日、1977年6月23日* ロイヤル・フェスティヴァル・ホール (ステレオ) ■Disc 13…BBCL4177 ルドルフ・ゼルキン(P) 録音:1973年6月4日 ロイヤル・フェスティヴァル・ホール (ステレオ) ■Disc 14…BBCL4189 エフゲニー・スヴェトラーノフ(指)LSO 録音:1979年10月30日 ロイヤル・フェスティヴァル・ホール (ステレオ) ■Disc 15…BBCL4195 クラウス・テンシュテット(指)LPO 録音:1983年4月7日*、1984年10月7日 ロイヤル・フェスティヴァル・ホール (ステレオ) ■Disc 16…BBCL4198 ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(Vc、指)* LSO ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー(指) 録音:1965年7月1日*、5日、7日# ロイヤル・フェスティバル・ホール(モノラル) ■Disc 17…BBCL4204 BBC響 ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー(指) 録音:1981年4月29日*、1987年8月18日 ロイヤル・アルバート・ホール(ステレオ) ■Disc 18…BBCL4210 ヘンリク・シェリング(Vn、指)、ホセ・ルイス・ガルシア(Vn) イギリス室内O 録音:1972年2月26日 クイーン・エリザベス・ホール (ステレオ) ■Disc 19…BBCL4237 マルコム・サージェント(指)BBC響 録音:1963年8月16日4、1965年9月2日* ロイヤル・アルバート・ホール (ステレオ) ■Disc 20…BBCL4261 エミール・ギレリス(P) 録音:1957年4月22日 メモリアル・ホール、ファリンドン・ストリート (モノラル) 1984年10月15日 セント・ジョンズ教会、スミス・スクエア (ステレオ) |
|
||
| BR KLASSIK BR-9007191(12CD) NX-K03 |
マーラー:交響曲全集(第1番~第9番) ■CD1 交響曲第1番ニ長調 ■CD2 交響曲第2番ハ短調「復活」 ■CD3-4 交響曲第3番ニ短調 ■CD5 交響曲第4番ト長調 ■CD6 交響曲第5番嬰ハ短調 ■CD7 交響曲第6番イ短調「悲劇的」 ■CD9 交響曲第8番変ホ長調「千人の交響曲」 ■CD10 交響曲第9番ニ長調 ■CD11 (1)交響曲第3番リハーサル風景 (2)交響曲第4番のコンサートについてマリス・ヤンソンスとアンチェ・デルフナーの対談(ドイツ語) ■CD12 (1)交響曲第5番リハーサル風景 (2)交響曲第7番のコンサートについてマリス・ヤンソンスとハナー・ヴァイスの対談(ドイツ語) (3)ベルンハルト・ノイホフによる交響曲第7番のコンサート・ガイド(ドイツ語) |
マリス・ヤンソンス(指) バイエルンRSO ■CD1 録音:2007年3月1-2日 ミュンヘン、ヘルクレスザール(ライヴ) ■CD2 アニヤ・ハルテロス(S) ベルナルダ・フィンク (A) バイエルン放送cho 録音:2011年5月13-15日ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ライヴ) ■CD3-4 ナタリー・シュトゥッツマン(A) テルツ少年cho バイエルン放送女声cho 録音:2010年12月8-10日ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ライヴ) ■CD5 ミア・パーション(S) 録音:2010年12月15-17日ミュンヘン、ヘルクレスザール(ライヴ) ■CD6 録音:2016年3月10-11日 ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ライヴ) ■CD7 録音:2011年5月4-6日 ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ライヴ) ■CD9 トワイラ・ロビンソン(ソプラノ1)、クリスティーヌ・ブリューワー(ソプラノ2)、アンナ・プロハスカ(S)、ヤニーナ・ベヒレ(アルト1)、藤村実穂子(アルト2)、ヨハン・ボータ(T)、ミヒャエル・フォッレ(Br)、アイン・アンガー(Bs)、ラトヴィア国立cho、テルツ少年cho、バイエルン放送cho、 録音:2011年10月12-14日ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ライヴ) ■CD10 録音:2016年10月20日、21日 ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ライヴ) ■CD11 (1)録音:2010年12月8-10日 ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ライヴ) ※リハーサルはドイツ語。CD冒頭にバイエルン放送の解説者を務めたフリードリヒ・シュロッフェルによるイントロダクション(ドイツ語)が収録されています。 (2)録音:2010年12月17日 ■CD12 (1)録音:2006年3月9-10日 ミュンヘン、フィルハーモニー・イン・ガスタイク(ライヴ) ※リハーサルはドイツ語。CD冒頭にバイエルン放送の解説者を務めたフリードリヒ・シュロッフェルによるイントロダクション(ドイツ語)が収録されています。 (2)録音:2018年4月19、20日 (3)ベルンハルト・ノイホフによる交響曲第7番のコンサート・ガイド(ドイツ語) (語り)カルステン・ファビアン、マリス・ヤンソンス、ベルンハルト・ノイホフ 2007年3月9日 バイエルン放送ラジオ |
|
||
| C Major 80-7108(2DVD) 80-7204(Bluray) |
ブルックナー:交響曲第2&8番 交響曲第2番ハ短調,WAB102(第2稿/1877年) 交響曲第8番ハ短調,WAB108(ハース版/1939年) ◆ボーナス映像「ディスカヴァリング・ブルックナー」 各交響曲について(ティーレマンと音楽学者ヨハネス=レオポルド・マイヤー氏による対話) |
クリスティアン・ティーレマン(指) VPO 収録:2019年2月、ウィーン楽友協会(ライヴ) ◆DVD 画面:16:9、NTSC 音声:PCMステレオ、DTS5.1 DVD9 [ボーナス映像 ] 言語:ドイツ語 字幕:英韓,日本語 Total time:205分 交響曲:150分、ボーナス:55分 ◆Bluray 画面:16:9、1080i 音声:PCMステレオ、 DTS-HD MA5.1 BD50 [ボーナス映像 ] 言語:ドイツ語 字幕:英韓,日本語 Total time:205分 交響曲:150分、ボーナス:55分 |
|
||
| Danacord DACOCD-924(2CDR) ★ |
トマス・イェンセンの遺産 第14集 ■Disc 1 (1)オーレ・シュミット:交響曲第1番Op.14a(1956) (2)ヴァウン・ホルムボー(1909-1996):モノリス Op.76M207(交響的変容第2番) (3)ゴナ・ベアウ(1909-1989):聖歌(1946)(弦楽オーケストラのための) (4)ニルス・ヴィゴ・ベンソン(1919-2000):交響的変奏 Op.92(1953) (5)ニールセン:フルート協奏曲 FS119(1926)* ■Disc 2 (1)ヘンツェ:夜の小品とアリア(1957)(ソプラノと管弦楽のための)** 夜の小品 I アリア I「ばらの雷雨に変わるところ) 夜の小品 II アリア II「眠そうな鳥」 夜の小品 III (2)オネゲル:交響曲第5番「3つのレ」(1950) (3)ニールセン:歌劇「サウルとダヴィデ」 FS25(1898-1901)より 第2幕への前奏曲† 劇付随音楽「母」 FS94(Op.41)(1920)より 前奏曲 第7場† 歌劇「仮面舞踏会」 FS39(1904-06)より 若い雄鶏たちの踊り† (4)プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲第2番*** |
トマス・イェンセン(指)、 デンマークRSO、ティヴォリ・コンサートホールO†、 ホルガー・ギルバト=イェスパセン(Fl)*、 カーラ・ヘニウス(S)**、 ヴァンディ・トヴォレク(Vn)*** ■Disc 1 (1)録音:1957年5月27日(初演)(ライヴ放送) (2)録音:1961年5月26日(ライヴ放送) (3)録音:1962年1月20日(放送) (4)録音:1958年8月7日(ライヴ放送) (5)録音:1954年4月(スタジオ録音) ■Disc 2 (1)録音:1962年9月27日(ライヴ放送) (2)録音:1962年9月27日(ライヴ放送) (3)録音:1942年7月2日(スタジオ録音) 録音:1942年9月8日(スタジオ録音) (4)録音:1949年9月15日(ライヴ放送)(一部省略、欠落) |
|
||
| Danacord DACOCD-940(2CDR) ★ |
ヨン・フランセン~初期録音選集 モーツァルト:歌劇「フィガロの結婚」序曲 ブラームス:交響曲第4番 グリーグ:ピアノ協奏曲** シューベルト:交響曲第5番 ヨハン・ペーター・エミリウス・ハートマン(1805-1900):序曲「ヘーコン・ヤール」 Op.40* ゲーゼ:演奏会序曲「オシアンの余韻」 Op.1* フィン・フフディング(1899-1997):交響的幻想曲第1番「進化」 Op.32* スヴェン・エーリク・タープ(1908-1994):喜劇『わがマリオネット劇場』 序曲 Op.53、ジェリコの戦い Op.51 クヌーズオーウ・リスエーヤ(1897-1974):トルグートの踊り |
ヨン・フランセン(指)、 王立デンマークO、 デンマーク国立放送O*、 アイリーン・ジョイス(P)** 録音:1951年~1958年 |
|
||
| DACAPO MAR-6.220644(1SACD) NX-B08 NYCX-10355(1SACD) 国内盤仕様 税込定価 |
ルーズ・ランゴー(1893-1952):交響曲第1番「岩山の田園詩 岸壁の牧歌」BVN 32(1908-1911) ベント・ヴィルホルト・ニルセンの比較校訂版による世界初録音 |
サカリ・オラモ(指)BPO 録音:2022年6月16-18日 ライヴ |
|
||
| OEHMS OC-1717(1CD) NX-B03 |
マーラー:交響曲第2番ハ短調「復活」 | ジュリア・モンタナーリ(S) ベッティナ・ランチ(A) プラハ・フィルハーモニーcho エッセンPO トマーシュ・ネトピル(指) 録音:2022年5月26-27日 |
|
||
| CPO CPO-777943(1CD) NX-B10 |
パウル・ヴラニツキー(1756-1808):交響曲集 交響曲 ト長調 Op. 50 交響曲 ニ長調 Op. 37 交響曲 イ長調 Op. 51 |
ハノーファー北ドイツ放送PO ロルフ・グプタ(指) 録音:2014年6月16-20日、2016年2月23-25日 |
|
||
| GRAND SLAM GS-2281(1CD) |
マーラー:「大地の歌」 | キャスリーン・フェリアー(C.A) ユリウス・パツァーク(T) ブルーノ・ワルター(指)VPO 録音:1952年5月15&16日ムジークフェラインザール(ウィーン) 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(録音セッション) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2280(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 | ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)VPO 録音:1952年11月26&27日ムジークフェラインザール(ウィーン) 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(録音セッション) |
|
||
 PROMINENT CLASSICS 2506-5610(1CD) |
朝比奈+シュトゥットガルト放送響 イベール:『寄港地』 大栗裕:交響管弦楽のための組曲『雲水讃』 プロコフィエフ:交響曲第2番 |
朝比奈隆(指) シュトゥットガルトRSO 録音:1966年2月19日シュトウットガルト・フンクハウス、スタジオ(ステレオ) |
|
||
| GENUIN GEN-22783(1CD) |
モーツァルト:交響曲集第2集 交響曲第1番 変ホ長調K.16 交響曲第28番 ハ長調K.200 交響曲第41番「ジュピター」 |
ヨハネス・クルンプ(指) エッセン・フォルクヴァング室内O 録音:2019年9月20-23日(K.16,K.551),2021年6月24-27日(K.200) |
|
||
| Goodies 78CDR-3881(1CDR) |
モーツァルト:交響曲第25番ハ短調 K.183 | オットー・クレンペラー(指) パリ・プロ・ムジカO 仏 POLYDOR A6345/6 1950年2月パリ、プレイエル音楽堂録音 |
|
||
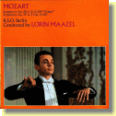 Treasures TRE-288(1CDR) |
若き日のマゼール/モーツァルト 交響曲第38番 ニ長調 「プラハ」 K. 504 交響曲第39番 変ホ長調 K. 543 |
ロリン・マゼール(指) ベルリンRSO 録音:1966年9月23日-9月1日(ステレオ) ※音源:英PHILIPS 6856019 ◎収録時間:62:10 |
| “モーツァルトで浮き彫りになるマゼールの「ケレン味のない」音作り!” | ||
|
||
| Signum Classics SIGC-D687JP(6CD) |
ベートーヴェン:交響曲全集&バリー ■CD1 ベートーヴェン:交響曲第1番 交響曲第2番ニ長調 Op.36 ジェラルド・バリー(b.1952):「ベートーヴェン」 ■CD2 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 バリー:ピアノ協奏曲 ■CD3 ベートーヴェン:交響曲第4番 交響曲第5番「運命」 バリー:ヴィオラ協奏曲 ■CD4 ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」 バリー:アイルランド侵略 ■CD5 ベートーヴェン:交響曲第7番 交響曲第8番ヘ長調 Op.93 ■CD6 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付き」 バリー:永劫回帰 |
トーマス・アデス(指)、 ブリテン・シンフォニア、 ニコラス・ホッジス(P)、 マーク・ストーン(Br)、 ローレンス・パワー(Va)、 ジョシュア・ブルーム(Bs)、 ジェニファー・フランス(S)、 クリスティアーネ・ストーティン(Ms)、 エド・ライオン(T)、 マシュー・ローズBs)、 ロイヤル・ホロウェイcho 録音:2017年~2019年、シアター・ロイヤル(ブライトン)&バービカン・センター(ロンドン) |
|
||
| Chandos CHSA-5315(1SACD) |
ストラヴィンスキー:交響曲集 グリーティング・プレリュード(1955) 交響曲 ハ調(1938-40) ディヴェルティメント(1934,1949改訂) サーカス・ポルカ(1942) 3楽章の交響曲(1942-45) |
アンドルー・デイヴィス(指) BBCフィルハーモニック 録音:2019年4月26日&2022年3月21日-22日、メディアシティUK(マンチェスター、イギリス) |
|
||
| Chandos CHSA-5297(1SACD) |
ラフマニノフ:交響詩「死の島」 Op.29 ヴォカリーズ Op.34-14(作曲者自身による管弦楽版) 交響曲第3番イ短調 Op.44 |
ジョン・ウィルソン(指)、 シンフォニア・オヴ・ロンドン 録音:2021年9月9日-11日、セント・オーガスティン教会(キルバーン、ロンドン) |
|
||
| Da Vinci Classics C-00618(1CD) |
マーラー:交響曲第4番(エルヴィン・シュタイン編曲による室内楽版) | アンサンブル・ジュリオ・ルスコーニ、 ダリオ・ガレニャーニ(指)、 マルコ・ピソーニ(芸術監督) 録音(ライヴ):2022年1月5日、ラ・カーサ・デッラ・ムジカ(チェザーノ・ボスコーネ、イタリア) |
|
||
| Channel Classics CCS-44722(1CD) |
ハイドン:交響曲「朝」「昼」「晩」 交響曲第6番ニ長調「朝」Hob. I:6 交響曲第7番ハ長調「昼」Hob. I:7 交響曲第8番ト長調「晩」Hob. I:8 |
フロリレジウム(古楽器使用) コンサートマスター:アガタ・ダラスカイテ(Vn) アシュリー・ソロモン(指揮・フルート) 録音:2021年11月セント・ジョーンズ教会、アッパー・ノーウッド、ロンドン |
|
||
 LSO Live LSO-0858(1SACD) KKC-6600(1SACD) 国内盤仕様 税込定価 |
ノセダ/ャイコフスキー:Sym#5 チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調Op.64 リムスキー=コルサコフ:「見えざる町キーテジと聖女フェヴローニャの物語」組曲 |
ジャナンドレア・ノセダ(指)LSO 録音:2019年11月3日、28日* ロンドン、バービカン・ホール(ライヴ) |
|
||
| EUROARTS 20-54388D(DVD) |
アバド&ポリーニ/ルツェルン音楽祭2004 マーラー:交響曲第5番嬰ハ短調 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲 第4番 |
マウリツィオ・ポリーニ(P) ルツェルン祝祭O、 クラウディオ・アバド(指) 収録:2004年8月18,19日 ルツェルン,コンサート・ホール(ライヴ) 画面:16:9、NTSC 音声:PCMステレオ、107分 |
|
||
| Challenge Classics CC-72803(1SACD) |
シューベルト:交響曲全集第4集 交響曲第5番変ロ長調 D.485 交響曲第6番ハ長調 D.589 |
ヤン・ヴィレム・デ・フリエンド(指) ハーグ・レジデンティO 録音:2022年1月18-21日/ハーグ、コンサートホール・アマーレ |
|
||
| Arte dellarco Japan ADJ-068(2CD) |
オーケストラ・リベラ・クラシカ/第44回定期演奏会 ハイドン:交響曲第4番ニ長調 Hob.I:4 ハイドン:交響曲第104番ニ長調 Hob.I:104「ロンドン」 モーツァルト:フルート協奏曲第1番ト長調 K.313 J.C.バッハ:フルート協奏曲 ニ長調 W.C79 |
バルトルド・クイケン(Fl)(3) 鈴木秀美(指)、 オーケストラ・リベラ・クラシカ ライヴ録音:2019年11月9日上野学園 石橋メモリアルホール |
|
||
 RCO Live RCO-19007(15CD) |
ニコラウス・アーノンクール& ロイヤル・コンセルトへボウO/ ライヴ放送録音集1981-2012 ■CD1&CD2 バッハ:ヨハネ受難曲BWV245(1724/1749) ■CD2(続き) メンデルスゾーン:詩篇第42「枯れた谷に鹿が水を求めるように」Op. 4 ■CD3&CD4 ハイドン:オラトリオ「天地創造」 Hob.XXI-2 ■CD4(続き) モーツァルト:演奏会用アリア「どうしてあなたを忘れられよう」 K. 505 ■CD5 モーツァルト:交響曲第39番変ホ長調 K. 543 交響曲第40番ト短調 K. 550 ■CD6 モーツァルト:交響曲第41番ハ長調 K.551「ジュピター」 ピアノ協奏曲第13番ハ長調K.415/387b ■CD7&CD8 ベートーヴェン:ミサ・ソレムニス ■CD8(続き) ベートーヴェン:交響曲第1番ハ長調Op.21 ああ不実なる人よ Op. 6 ■CD9 シューベルト:交響曲第8(9)番ハ長調「ザ・グレイト」 ■CD10 (1)シューベルト:交響曲第7(8)番ロ短調「未完成」 (2)ブラームス:交響曲第1番ハ短調Op.68 ■CD11 シューマン:マンフレッド序曲O 交響曲第1番変ロ長調 Op.38「春」 交響曲第3番変 ホ長調 Op.97「ライン」 ■CD12 (1)ブラームス:悲劇的序曲 交響曲第3番へ長調 Op.90 (2)ドヴォルザーク:聖書の歌 Op.99 ■CD13[66:32] ドヴォルザーク:交響曲第7番 リハーサル断片 ■CD14 (1)ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」 (2)J・シュトラウス:美しく青きドナウ 「こうもり」より 三重唱「ひとりになるのね」、「故郷の調べは」* ■CD15 メンデルスゾーン:「夏の夜の夢」 Op. 21&61 |
ニコラウス・アーノンクール(指) ロイヤル・コンセルトへボウO ■CD1&CD2 クルト・エクヴィルツ(テノール:福音史家)、ロベルト・ホル(バス:イエス)、ヨランタ・ラデック(S)、マルヤーナ・リポフシェク(A)、アントニー・ロルフ・ジョンソン(T)、アントン・シャリンガー(Bs) 録音:1984年4月15日 ■CD2(続き) 録音:2009年4月26日(メンデルスゾーン) ■CD3&CD4 録音:2000年10月22日 ■CD4(続き) シャルロット・マルジョーノ(S)、マリア・ボン(P) 録音:1992年1月9日 ■CD5[64:08] 録音:1991年1月27日 ■CD6 マルコム・フレイジャー(P) 録音:1981年9月18日 ■CD7&CD8 マルリス・ペーターゼン(S)、エリーザベト・クールマン(A)、ヴェルナー・ギューラ(T)、ジェラルド・フィンリー(Br)、オランダ放送cho 録音:2012年4月25日 ■CD8(続き) シャルロット・マルジョーノ(S) 録音:1998年3月19日 ■CD9 録音:1992年11月11日 ■CD10 (1)録音:1997年11月7日 (2)録音:1996年3月24日 ■CD11 録音:2004年11月28日 ■CD12 (1)録音:1996年1月20日 (2)クリスティアン・ゲルハーヘル(Br) 録音:2004年11月28日 ■CD13 (1)録音:1998年3月20日 (2)録音:1998年3月16-17日 ■CD14[80:40] (1))録音:1997年4月3日 (2)マグダ・ナドール(S)、アーリーン・オジェー(S)*、トーマス・ハンプソン(Br) 録音:1984年6月7日 ■CD15 ユリア・クライター(S)、エリーザベト・フォン・マグヌス(アルト、ゲルト・ベックマン(ナレーター) オランダ室内cho 録音:2009年4月26日 |
|
||
| ALPHA ALPHA-645(1CD) |
シベリウス:交響曲第3番ハ長調 Op. 52 交響曲第5番変ホ長調 Op. 82 ポヒョラの娘 Op. 49 |
イェーテボリSO サントゥ=マティアス・ロウヴァリ(指) 録音:2018年5月、2019年6月、2022年6月 イェーテボリ・コンサート・ホール、スウェーデン |
|
||
| ALPHA ALPHA-872(1CD) |
憧れ~ライヴ・イン・ロッテルダム ベルク:初期の7つの歌 (レインベルト・デ・レーウ編) 4つの歌曲 Op. 2(ヘンク・デ・フリーヘル編) マーラー:交響曲第4番ト長調 (エルヴィン・シュタイン編) |
バーバラ・ハンニガン(S) ラウル・ステファニ(Br) カメラータRCO ロルフ・フェルベーク(指) 録音:2021年4月30日 デ・ドゥーレン、ロッテルダム、オランダ (無観客ライヴ) |
|
||
| TOCCATA TOCC-0512(1CD) NX-B03 |
チャールズ・ローランド・ベリー(1957-):管弦楽作品集
第1集 序曲「オリンピック・マウンテン」(2003) 交響曲第4番(2017)* 交響曲第5番(2021)# |
モラヴィアPO リヴィウ国立PO* ポーランド・ヴィエニャフスキPO# ジョエル・エリック・スーベン(指) テオドレ・クチャル(指)*,# 録音:2003年6月8日、2020年11月17-20日 Philharmonic Hall, Lviv(ウクライナ)*、2022年5月15-18日 Philharmonic Hall, Lublin(ポーランド)# 全て世界初録音 |
|
||
| フォンテック FOCD-9873(1CD) 2022年10月5日発売 |
ブルックナー:交響曲第5番変ロ長調 <ノーヴァク版> | 尾高忠明(指) 大阪フィルハーモニーSO 録音:2022年2月 14日 第 54回東京定期演奏会 サントリーホール・ライブ |
|
||
| NIFC NIFCCD-143(1CD) |
リピンスキ:交響曲集 スタニスワフ・モニューシュコ:演奏会用序曲「おとぎ話」 カロル・リピンスキ:交響曲 ハ長調 Op.2-2、 交響曲 変ロ長調 Op.2-3 |
{oh!} オルキェストラ・ヒストリチナ、 ディルク・フェルミューレン(指) 録音:2019年9月&2021年8月(ポーランド) |
|
||
| Chandos CHAN-20161(1CD) |
ルース・ギップス:管弦楽作品集 Vol.2 序曲「シャンティクリア 」 Op.28 オーボエ協奏曲 ニ短調 Op.20 交響詩「青白い馬に乗った死」 Op.25 交響曲第3番Op.57(全曲世界初録音) |
ユリアナ・コッホ(Ob)、 ラモン・ガンバ(指)、 BBCフィルハーモニック 録音:2019年12月19日&2022年1月6日、メディアシティUK(イギリス、マンチェスター) |
|
||
| KLANGLOGO KL-1513(1CD) |
ブラームス:交響曲第1番&第2番 ブラームス:交響曲第1番ハ短調 Op.68 交響曲第2番ニ長調 Op.73 |
ハワード・グリフィス(指)、 フランクフルト・ブランデンブルク州立O 録音:2014年9月29日-10月2日、コンサートホール・“ C.P.E.バッハ”・フランクフルト(オーダー、ドイツ) |
|
||
| KLANGLOGO KL-1514(1CD) |
ブラームス:交響曲第3番&第4番 ブラームス:交響曲第3番ヘ長調 Op.90 交響曲第4番ホ短調 Op.98 |
ハワード・グリフィス(指)、 フランクフルト・ブランデンブルク州立O 録音:2015年6月22日-25日、コンサートホール・“ C.P.E.バッハ”・フランクフルト(オーダー、ドイツ) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2277(1CD) |
フランク:交響曲 ニ短調 | ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)VPO 録音:1953年12月14日、15日ウィーン、ムジークフェラインザール 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) モノラル(録音セッション) |
|
||
| SWR music SWR-19120CD(1CD) NX-B06 |
ニールセン:交響曲第2番ロ短調「四つの気質」 Op. 16FS
29 交響曲第4番「不滅」 Op. 29* |
シュトゥットガルトRSO ロジャー・ノリントン(指) 録音:2003年12月18-19日、2001年1月17-19日* ※初CD化 |
|
||
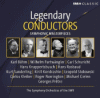 SWR music SWR-19432CD(10CD) NX-G09 |
偉大な指揮者たち - SWR録音集 【CD1】 (1)モーツァルト:交響曲第40番 (2)ベートーヴェン:交響曲第1番 【CD2】 (1) ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」 (2)シューベルト:交響曲第5番 【CD3】 ブラームス:交響曲第3番 ハイドンの主題による変奏曲 【CD4】 シューマン:交響曲第1番「春」 交響曲第4番ニ短調 Op. 120* 序曲「ジュリアス・シーザー」# 【CD5】 ブルックナー:交響曲第7番 【CD6】 マーラー:交響曲第6番「悲劇的」 【CD7】 (1)チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 Op. 64 (2)ボロディン:交響曲第2番 【CD8】 エルガー:序曲「南国にて」 序奏とアレグロ*/エニグマ変奏曲# 【CD9】 ストラヴィンスキー:バレエ音楽『プルチネッラ』 バレエ音楽『ミューズを率いるアポロ』* ロシア風スケルツォ# 【CD10】 R・シュトラウス:歌劇「ばらの騎士」演奏会組曲(1945年版) 交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」* 交響詩「ドン・ファン」# |
【CD1】 (1)カール・ベーム(指)シュトゥットガルトRSO 録音:1974年9月18日、 (2)ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)シュトゥットガルトRSO 1954年3月30日(モノラル) 【CD2】 カール・シューリヒト(指)シュトゥットガルトRSO 録音:(1)1957年2月14日 、(2)1960年4月11日 (全てモノラル) 【CD3】 ハンス・クナッパーツブッシュ(指)シュトゥットガルトRSO 録音:1963年11月15日 (全てモノラル) 【CD4】 ハンス・ロスバウト(指)バーデン・バーデン&フライブルク南西ドイツRSO 録音:1960年9月8日、1961年12月19日*、1961年12月18日#(全てモノラル) 【CD5】 クルト・ザンデルリンク(指)バーデン・バーデン&フライブルク南西ドイツRSO 録音:1999年12月15-17日 【CD6】 キリル・コンドラシン(指)バーデン・バーデン&フライブルク南西ドイツRSO 録音:1981年1月13-15日 【CD7】 (1)レオポルド・ストコフスキー(指)シュトゥットガルトRSO 録音:1955年5月20日 モノラル (2)カルロス・クライバー(指)シュトゥットガルトRSO 録音:1972年12月12日ステレオ 【CD8】 ロジャー・ノリントン((指)シュトゥットガルトRSO 録音:2010年9月30日-10月1日、2007年12月13-14日#、2010年10月4-5日 * 【CD9】 ミヒャエル・ギーレン(指)、エッダ・モーザー(S)、ヴェルナー・ヘルヴェヒ(T)、バリー・マクダニエル(Bs)、シュトゥットガルトRSO、バーデン・バーデン&フライブルク南西ドイツRSO# 録音:1973年2月12日(ライヴ)、1973年7月24日 *、1998年4月17日# 【CD10】 ジョルジュ・プレートル(指)、ディートヘルム・ヨナス(Ob)、シュトゥットガルトRSO 録音:1990年2月15-17日* 1997年10月31日# |
|
||
| Goodies 78CDR-3881(1CDR) |
モーツァルト:交響曲第25番ハ短調 K.183 | オットー・クレンペラー(指) パリ・プロ・ムジカO 仏 POLYDOR A6345/6 1950年2月パリ、プレイエル音楽堂録音 |
|
||
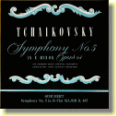 Treasures TreasuresTRT-019(1CDR) |
イッセルシュテット/シューベルト&チャイコフスキー シューベルト:交響曲第5番変ロ長調 チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調Op.64* |
ハンス・シュミット・イッセルシュテット(指) 北ドイツRSO 録音:1955年4月17-20日、1952年9-10月*(共にモノラル) ※音源:Capitol P-18021、DECCA ACL-3* ◎収録時間:72:34 |
| “ロシア的色彩とは無縁!無骨なカンタービレで真剣勝負!” | ||
|
||
| CPO CPO-555511(1CD) NX-B10 |
エミーリエ・マイヤー(1812-1883):交響曲第3番ハ長調 交響曲第7番ヘ短調 |
ハノーファー北ドイツ放送PO ヤン・ヴィレム・デ・フリエンド(指) 録音:2022年3月7-11日 |
|
||
| CPO CPO-555416(1CD) NX-B10 |
ゲオルク・ヴィルヘルム・ラウヒェネッカー(1844-1906):交序曲の形式による交響的作品 交響曲第1番 ヘ長調 東洋風幻想曲 |
ゼバスティアン・ボーレン(Vn) ザラストロ四重奏団 ヴィンタートゥーア・ムジークコレギウム ハワード・グリフィス(指) 録音:2020年10月26-29日、2020年9月21日 |
|
||
 King International KKC-4303(5CD) |
アーベントロート不滅の遺産(最新リマスター) ■CD 1 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 ■CD 2 ブラームス:交響曲第1番ハ短調 Op.68 交響曲第3番ヘ短調 Op.90* ■CD3 チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」 ■CD 4 モーツァルト:交響曲第41番「ジュピター」 ディヴェルティメント 第7番ニ長調 KV205 セレナード 第8番「ノットゥルノ」* ■CD 5 ハイドン:交響曲第88番ト長調「V字」 交響曲第97番ハ長調* ヘンデル:管弦楽のための二重協奏曲 第3番 ヘ長調* |
ヘルマン・アーベントロート(指) ■CD 1 ライプツィヒRSO エディット・ラウクス(S)/ディアナ・オイストラティ(A)/ルートヴィヒ・ズートハウス(T)/カール・パウル(Bs)/ライプツィヒ放送cho/ライプツィヒ音楽大学cho 録音:1951年6月29日* ■CD 2 ライプツィヒRSO 録音:1949年10月20日 / 1952年3月17日* ■CD3 ライプツィヒRSO 録音:1952年1月28日 ■CD 4 ライプツィヒRSO ベルリンRSO* 録音:1956年3月26日/ 1956年4月12日* ■CD 5 ライプツィヒRSO ベルリンRSO* 録音:1956年/ 1955年9月15日* 原盤:ドイツ・シャルプラッテン 国内製造品 日本語帯・解説付(解説:宇野功芳) |
|
||
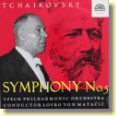 Treasures TRT-018(1CDR) |
マタチッチのロシア音楽1 ボロディン:「イーゴリ公」より 序曲/ダッタン人の行進/だったん人の踊り チャイコフスキー:交響曲第5番* |
ロヴロ・フォン・マタチッチ(指) フィルハーモニアO、チェコPO* 録音:1958年9月、1960年3月12-15日*(全てステレオ) ※音源:仏TRIANON TRI-33114 、独musicaphon BM30SL-1614* ◎収録時間:71:21 |
| ““マタチッチの強力なオーラでチェコ・フィル・サウンドが豹変!” | ||
|
||
 SOMM ARIADNE-5017(2CD) NX-C09 |
クーセヴィツキー/ロンドン・フィル、ライヴ録音集 【CD1】 チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 Op. 64 ドキュメンタリー「セルゲイ・クーセヴィツキーの思い出」 イントロダクションとボストンSO Part. I 【CD2】 ドキュメンタリー「セルゲイ・クーセヴィツキーの思い出」(続き) 1. ボストンSO Part. II 2. LPO シベリウス:交響曲第2番ニ長調 Op. 43* ●ドキュメンタリー「セルゲイ・クーセヴィツキーの思い出」使用曲 【CD1:5】 ベルリオーズ:ラコッツィ行進曲b…1、2、4 チャイコフスキー:交響曲第5番第1楽章(抜粋) a…1 R・シュトラウス:ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら(抜粋) b…3 チャイコフスキー:ロメオとジュリエット(抜粋) b…1 リスト:ファウスト交響曲のリハーサルよりb 【CD2:1】 シベリウス:タピオラよりb…1 ドビュッシー:海より第3楽章(抜粋) b…1 ベートーヴェン:交響曲第3番第4楽章(抜粋) b…3 シベリウス:交響曲第2番第2楽章(抜粋) b…3 コープランド:エル・サロン・メヒコ(抜粋) b…1、3 チャイコフスキー:交響曲第4番第4楽章(抜粋) b…2 チャイコフスキー:交響曲第4番第4楽章(抜粋) b…3 チャイコフスキー:交響曲第5番第2楽章(抜粋) a 【CD2:2】 シベリウス:交響曲第2番第1楽章(抜粋) a…4 ムソルグスキー:歌劇「ホヴァーンシチナ」前奏曲(抜粋) a チャイコフスキー:交響曲第5番第2楽章(抜粋) a チャイコフスキー:交響曲第5番第3楽章(抜粋) a…4 チャイコフスキー:交響曲第5番第3楽章(抜粋) a チャイコフスキー:交響曲第5番第4楽章(抜粋) a…4 |
セルゲイ・クーセヴィツキー(指) LPO 録音:すべてライヴ(モノラル) 1950年6月1日 Royal Albert Hall、London 1950年6月8日 Royal Albert Hall、London* ●ドキュメンタリー「セルゲイ・クーセヴィツキーの思い出」演奏者内訳(全て初CD化) LPO…a ボストンSO…b 語り手 ジョン・トランスキー(プロデューサー&インタビュアー) ハリー・エリス・ディクソン(ボストンSO 元ヴァイオリニスト)…1 エヴァレット・"ヴィック"・ファース(ボストンSO 元ティンパニスト)…2 ハリー・シャピロ(ボストンSO 元準首席ホルン奏者)…3 パトリック・ストレヴェンス(LPO 元準首席ホルン奏者)…4 |
|
||
| SOMM ARIADNE-5016(1CD) NX-B04 |
ヴォーン・ウィリアムズ・ライヴ 第1集 劇音楽「すずめばち」 アリストファネス組曲 - 序曲* 交響曲第6番ホ短調** 交響曲第9番ホ短調# |
マルコム・サージェント(指) BBC響*,**、ロイヤルPO# 録音:すべてライヴ(モノラル) 1957年9月12日 Royal Albert Hall、London* 1964年8月4日 Royal Albert Hall、London** 1958年4月2日 Royal Festival Hall、London# |
|
||
| Pentatone PTC-5187021(1CD) |
マーラー:交響曲第5番嬰ハ短調 | ヤン・ヴォボジル(ホルン独奏)、 スタニスラフ・マサリク(トランペット独奏) セミヨン・ビシュコフ(指)チェコPO 録音:2021年12月8-11日/ルドルフィヌム、ドヴォルザーク・ホール(プラハ) |
|
||
 Spectrum Sound CDSMBA-108(2CD) |
「オハン・ドゥリアンへのオマージュ」~1971・1980・1981年ライヴ音源集 (1)ワーグナー:「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕前奏曲 (2)ハイドン:交響曲第102番 (3)ストラヴィンスキー:バレエ組曲「火の鳥」(1919年版) (4)モーツァルト:「ドン・ジョヴァンニ」序曲 (5)ブルックナー:交響曲第9番ニ短調 |
オハン・ドゥリアン(指) (1)フランス国立O、(2)-(5)フランス放送ニューPO 録音:(1)1971年1月13日、 (4)(5)1981年5月8日シャンゼリゼ劇場(パリ)、 (2)(3)1980年5月22日メゾン・ドゥ・ラ・ラジオ・パリ104スタジオ(パリ) 録音方式:ステレオ(ライヴ) |
|
||
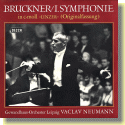 Treasures TRE-279(1CDR) |
ノイマンのブルックナー グリンカ:幻想曲「カマリンスカヤ」# リスト:交響詩「前奏曲」 ブルックナー:交響曲第1番* |
ヴァーツラフ・ノイマン(指) ライプチヒ・ゲヴァントハウスO 録音:1967年10月17日#、1965年12月13-14日ライプツィヒ救世主教会*、1968年2月22-23日 (全てステレオ) ※音源:独DECCA _SXL-20087*、ETERNA 8-25-847 ◎収録時間:74:34 |
| “ノイマンの端正な造形力にオケの魅力が完全バックアップ!” | ||
|
||
 ICA CLASSICS ICAC-5169(2CD) NX-C07 |
ショスタコーヴィチ:交響曲第4番ハ短調 Op. 43 交響曲第11番ト短調 Op. 103「1905年」* |
BBC響、BBCフィル* ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー(指) 録音:1978年9月9日 ロイヤル・アルバート・ホール、ロンドン(ステレオ/アナログ録音) 1997年10月4 ブリッジウォーター・ホール、マンチェスター2(ステレオ/デジタル録音)* ライヴ録音:拍手入り 全て初CD化 |
|
||
| BR KLASSIK BR-900205(1CD) NX-B07 |
マーラー:交響曲第9番 | バイエルンRSO サイモン・ラトル(指) 録音:2021年11月24-27日 イザールフィルハーモニー・イン・ガスタイクHP8(ライヴ) |
|
||
| PROSPERO CLASSICAL PROSP-0048(1CD) |
プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲第2番ト短調 Op.63 ミャスコフスキー:交響曲第25番変ニ長調 Op.69 プロコフィエフ:『ロメオとジュリエット』 Op.64より 仮面 |
ダーヴィト・ネベル(Vn) ダニエル・ユペール(指) ベルギッシュSO 録音:2021年8月/ケルン |
|
||
| Altus ALTSA-379(1SACD) シングルレイヤー 限定生産盤 |
ブルックナー:交響曲第3番ニ短調 交響曲第9番ニ短調 |
ロヴロ・フォン・マタチッチ(指) フランス国立O 録音:1965年1月26日、1963年1月29日*/シャンゼリゼ劇場(ステレオ・ライヴ) |
|
||
| Altus ALT-520(1CD) |
シューリヒト&スイス・ロマンド管 ブラームス:交響曲第4番ホ短調 Op.98 バッハ:管弦楽組曲第2番ロ短調 BWV1067 |
カール・シューリヒト(指) スイス・ロマンドO 録音:1952年5月3日、1955年8月4日* 共にスイス・ロマンド放送によるモノラル録音 |
|
||
| GRAND SLAM GS-2276(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 | ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)、BPO ティルラ・ブリーム(S)、エリーザベト・ヘンゲン(A)、ペーター・アンダース(T)、ルドルフ・ヴァツケ(Bs-Br)、ブルーノ・キッテルcho 録音:1942年3月22~24日/ベルリン、旧フィルハーモニー 使用音源:Private archive(2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(ラジオ放送用録音) |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00791(1SACD) 税込定価 2022年8月24日発売 |
ハイドン:交響曲集Vol.16 交響曲第51番変ロ長調 Hob.I:51 交響曲第28番 イ長調 Hob.I:28 交響曲第91番変ホ長調 Hob.I:91 |
飯森範親(指) 日本センチュリーSO 録音:2019年11月22日 大阪、いずみホール・ライヴ |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00789(1SACD) 税込定価 2022年8月24日発売 |
R.シュトラウス:アルプス交響曲 歌劇「ばらの騎士」~第1ワルツ集 |
ウラディーミル・アシュケナージ(指) チェコPO 録音:1999年3月21、22、27日 プラハ、ルドルフィヌム、ドヴォルザーク・ホール |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00792(1SACD) 税込定価 2022年8月24日発売 |
R.シュトラウス:家庭交響曲 交響詩「ドン・ファン」 |
ウラディーミル・アシュケナージ(指) チェコPO 録音:k1997年4月19日、20日 プラハ「芸術家の家」ドヴォルザーク・ホール |
|
||
| Goodies 78CDR-3878(1CDR) |
チャイコフスキー:交響曲第6番ロ短調作品74「悲愴」 | ブルーノ・ワルター指揮 ベルリン国立歌劇場O 独 POLYDOR 69771/5 1925年3月ベルリン録音 |
|
||
| ALPHA ALPHA-875(1CD) NYCX-10342(1CD) 国内盤仕様 税込定価 |
モーツァルト:歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲 ピアノ協奏曲 第23番イ長調 K. 488 交響曲第40番ト短調 K. 550「十二音技法」 |
アンドレアス・シュタイアー(フォルテピアノ) 使用楽器:ウィーンのアントン・ヴァルター1790年頃製作モデルに基づくクリストフ・ケルン製作の再現楽器 ル・コンセール・ド・ラ・ロージュ(古楽器使用) ジュリアン・ショーヴァン(Vn、指揮) 録音:2021年9月アルスナル、メス(フランス北東部ロレーヌ地方) ※ 国内盤仕様解説日本語訳…白沢達生 |
|
||
| TOCCATA TOCC-0636(1CD) NX-B03 |
エミール・タバコフ(1947-):交響曲全集 第7集 15の弦楽器のための協奏曲(1979) 交響曲第9番(2015)…世界初録音 |
ソフィア・ソロイスツ・チェンバー・アンサンブル ソフィアPO エミール・タバコフ(指) 録音:1980年2月3日、2018年3月18日(ライヴ) |
|
||
| Channel Classics CCSSA-42822(1SACD) NX-C03 |
ブルックナー:交響曲第9番 | ブダペスト祝祭O イヴァン・フィッシャー(指) 録音:2021年3月 コングレス・センター、ブダペスト、ハンガリー CD層…Stereo SACD層…Stereo、5.0マルチチャンネル |
|
||
| Channel Classics CCSBOX-7322(4CD) NX-F01 |
ブラームス:交響曲全集、管弦楽作品集 【DISC 1】 ハンガリー舞曲 第14番ニ短調 (イヴァン・フィッシャー編) ハイドンの主題による変奏曲 Op. 56a 交響曲第1番ハ短調 Op. 68 【DISC 2】 交響曲第2番ニ長調 Op. 73 悲劇的序曲/大学祝典序曲 【DISC 3】 交響曲第3番ヘ長調 Op. 90 セレナーデ 第2番 【DISC 4】 交響曲第4番ホ短調 Op. 98 ハンガリー舞曲 第11番ニ短調 シィク地方の民族音楽(Vn、ヴィオラ、コントラバスによる) ~ハンガリー舞曲 第3番に使われたオリジナル・メロディ ハンガリー舞曲 第3番ヘ長調 ハンガリー舞曲 第7番イ長調 |
ブダペスト祝祭O イヴァン・フィッシャー(指) 録音:2009年1月…DISC 1 2012年2月…DISC 2、 2013年4月…DISC 4 2020年8月30日-9月1日…DISC 3 ブダペスト芸術宮殿 ※DISC 3、トラック1の00'21''付近に小さなノイズが発生しますが、レーベルより電気的なノイズではなく収録時のものという回答を得ております。ご了承くださいませ。 |
|
||
 Pentatone PTC-5186978(3CD) |
ブロムシュテット/ブラームス:交響曲全集 ■CD1 (1)交響曲第1番ハ短調 Op.68 (2)悲劇的序曲 ニ短調 Op.81 ■CD2 (3)交響曲第2番ニ長調 Op.68 (4)大学祝典序曲 Op.80 ■CD3 (5)交響曲第3番ヘ長調 Op.90 (6)交響曲第4番ホ短調 Op.98 |
ヘルベルト・ブロムシュテット(指) ライプツィヒ・ゲヴァントハウスO 録音:(1)2019年9月、(2)(3)(4)2019年10月、(5)(6)2021年4月 ゲヴァントハウス(ライプツィヒ) (1)-(4)ライヴ、(5)(6)セッション |
|
||
| ALIA VOX AVSA-9950 (2SACD) ★ |
シューベルト:交響曲集~Transfiguration(変容) [Disc1] 交響曲 ロ短調「未完成」 [Disc2] 交響曲第9番ハ長調「ザ・グレイト」 |
ジョルディ・サヴァール(指) ル・コンセール・デ・ナシオン 録音:2021年9月26-29日、カタルーニャ |
|
||
| Skani SKANI-141(1CD) |
ヤーニス・イヴァノフス(1906-1983):交響曲第17番ハ長調(1976) 交響曲第18番ホ短調(1977) |
ラトビア国立SO、 グンティス・クズマ(指) 録音:2022年 |
|
||
| Prima Facie PFCD-181182(2CD) |
デイヴィッド・ゴライトリー(1948-2018):レターズ・オヴ・リグレット ムード/ピアノ・ソナタ第1番 交響曲第1番(ミドルスブラ交響曲) 海景/ウェアデールの肖像 |
ローソン・トリオ、 ギャヴィン・サザーランド(指)、 プラハ市PO、他 録音:1996年~2021年 |
|
||
| Hyperion CDA-68396(1CD) |
ヴォーン・ウィリアムズ:交響曲第6番、 イギリス民謡集(煤けたズボン*、The Carter*、Ward the Pirate*)、 交響曲第8番、イングランド・マイ・イングランド# |
マーティン・ブラビンズ(指)、 BBC響、BBC交響cho*#、 ロデリック・ウィリアムズ(Br)# 録音:2019年11月5日*#&2021年9月21日-22日、ワトフォード・コロシアム(ワトフォード、イギリス) |
|
||
| Danacord DACOCD-923(2CDR) |
トマス・イェンセンの遺産 第13集 ■CD 1 ニールセン: (1)交響曲第5番Op.50 (2)パンとシランクス Op.49 (3)交響曲第6番「素朴な交響曲」 (4)若き芸術家の棺の傍らで ■CD 2 シベリウス: (1)交響詩「フィンランディア」* (2)交響曲第1番ホ短調 Op.39 (3)交響曲第4番イ短調 Op.63 |
トマス・イェンセン(指)、 デンマークRSO、 ティヴォリ・コンサートホールO* ■CD 1 (1)録音:1954年4月7日(スタジオ録音) (2)録音:1956年2月1日(ライヴ放送) (3録音:1952年6月17日-19日(スタジオ録音) (4)録音:1958年1月12日(ライヴ放送) ■CD 2 (1)録音:1947年7月2日(スタジオ録音)]* (2)録音:1963年9月9日(ライヴ録音)] (3)録音:1961年11月30日(ライヴ放送)] ※復刻/デジタルマスタリング:クラウス・ビューリト |
|
||
| ONDINE ODE-1401(1CD) NX-B07 |
ターリヴァルディス・ケニンシュ(1919-2008):
交響曲第2番/第3番/第7番 交響曲第2番「Sinfonia concertante 協奏交響曲」(1967)- フルート、オーボエ、クラリネットと管弦楽のために 交響曲第3番(1970) 交響曲第7番(1980) - パッサカリアの形式による交響曲* |
トマーソ・プラトーラ(Fl) エギルス・ウパトニエクス(Ob) マールティンシュ・ツィルツェニス(Cl) ザンダ・シュヴェーデ(Ms) ラトヴィア国立SO アンドリス・ポーガ(指) 録音:2021年12月13-16日、2021年8月30日-9月2日* |
|
||
| Capriccio C-8086(1CD) NX-B05 NYCX-10332(1CD) 国内盤仕様 税込定価 |
ブルックナー:交響曲第3番ニ短調 WAB 103(1873年初稿/ノーヴァク版) | ウィーンRSO マルクス・ポシュナー(指) 録音:2022年1月23-24日Wien、Radio Kulturhaus(オーストリア) 2022年1月25日Konzerthaus(オーストリア) ※国内仕様盤には石原勇太郎氏(音楽学/国際ブルックナー協会会員)による日本語解説が付属 |
|
||
| C Major 76-2304(5Bluray) |
レナード・バーンスタイン・ボックスVol.2 ■BD1 シベリウス: (1)交響曲第1番ホ短調op.39 (2)交響曲第2番ニ長調op.43 (3)交響曲第5番変ホ長調op.82 (4)交響曲第7番ハ長調op.105 ■BD2 ベートーヴェン: (1)弦楽四重奏曲第16番ヘ長調op.135(弦(2)ハイドン:ミサ曲第7番ハ長調Hob.XXII:9『戦時のミサ』 ■BD3 ハイドン: (1)交響曲第94番ト長調Hob.Ⅰ-94「驚愕」 (2)交響曲第92番ト長調Hob.Ⅰ-92「オックスフォード」 (3)交響曲第88番ト長調作品56Hob.Ⅰ-88「V字」 (4)協奏交響曲 変ロ長調Hob.Ⅰ-105 ■BD4 (1)ベルリオーズ:幻想交響曲 (2)ルーセル:交響曲第3番ト短調作品42 サン=サーンス:交響詩「オンファールの糸車」 トマ:「レーモン」序曲 ■BD5 Bernsteinat100バーンスタイン生誕100周年記念~タングルウッド音楽祭 バーンスタイン: (1).『キャンディード』序曲 (2)プラトン「饗宴」によるセレナーデより第1楽章 (3).交響曲第3番「カディッシュ」より第2楽章第2部「カディッシュ2」 (4)「ミサ」よりチェロと管弦楽のための三つの瞑想曲 第3曲 (5)『ウェスト・サイド・ストーリー』よりプロローグ/ジェット・ソング/マリア/~あんな男に~私は愛している~/トゥナイト(クインテット) (6)マーラー:「子供の魔法の角笛」より“歩哨の夜の歌” (8)ジョン・ウィリアムズ:ハイウッドの幽霊(世界初演) (9)マーラー:交響曲第2番「復活」より終楽章 (アンコール) (10)バーンスタイン:『ウェスト・サイド・ストーリー』より“どこかに” ■ボーナス タングルウッドのバーンスタイン+ビデオ・メッセージ |
■BD1 シベリウス: (1)収録:1990年ウィーン、ムジークフェラインザール (2)収録:1986年ウィーン、ムジークフェラインザール (3)収録:1987年ウィーン、コンツェルトハウス (4)収録:1988年ウィーン、ムジークフェラインザール レナード・バーンスタイン(指)VPO 映像監督:ハンフリー・バートン 音声:PCM2.0,DTS5.1 画面:4:3 リージョン:All 収録時間:166:00 ■BD2 (1)レナード・バーンスタイン(指)VPO 収録:1989年ウィーン、ムジークフェラインザール (2)ジュディス・ブレゲン(S)、ブリギッテ・ファスベンダー(A)、クラエス・アーカン・アーンシェ(T)、ハンス・ゾーティン(Bs)、バイエルンRSO&cho、レナード・バーンスタイン(指) 収録:1984年ドイツ、オットーボイレン大聖堂バジリカ教会 音声:PCM2.0,DTS5.1 画面:4:3 リージョン:All 字幕(ミサ曲):英独仏西韓中 収録時間:93:00 ■BD3 (1収録:1985年10月ムジークフェラインザール(ウィーン) (2)収録:1983年ムジークフェラインザール(ウィーン) (3)収録:1983年11月ムジークフェラインザール(ウィーン) (4)ライナー・キュッヒル(Vn)、フランツ・バルトロメイ(Vc)、ヴァルター・レーマイヤー(Ob)、ミハエル・ヴェルバ(Fg) 収録:1984年10月ムジークフェラインザール(ウィーン) レナード・バーンスタイン(指)VPO 映像監督:ハンフリー・バートン 画面:4:3(デジタルリマスター) 音声:PCMステレオ 収録時間:111:00 ■BD4 (1)収録:1976年11月、パリ、シャンゼリゼ劇場 映像監督:ハンフリー・バートン、イヴ=アンドレ・ユベール (2)収録:1981年11月、パリ、シャンゼリゼ劇場 映像監督:ディルク・サンダース レナード・バーンスタイン(指)フランス国立O 画面:4:3new digital remastered in HD 音声:PCMステレオ リージョン:All 収録時間:108:00 ■BD5 (1)アンドリス・ネルソンス(指)ボストンSO (2)五嶋みどり(Vn)、クリストフ・エッシェンバッハ(指)ボストンSO (3).ナディーヌ・シエラ(S)、キース・ロックハート(指)ボストンSO タングルウッド祝祭女声cho (4)キアン・ソルタニ(Vc)、クリストフ・エッシェンバッハ(指)ボストンSO (5)イザベル・レナード、ジェシカ・ボスク、トニー・ヤスベック。マイケル・ティルソン・トーマス(指)ボストンSO (6)トーマス・ハンプソン(Br)。アンドリス・ネルソンス(指)ボストンSO (7)マイケル・ティルソン・トーマス(指)ボストンSO (8)ヨーヨー・マ(Vc)、ジェシカ・ジョウ(Hp)。ジョン・ウィリアムズ(指)ボストンSO (9)ナディーヌ・シエラ(S)、スーザン・グラハム(Ms)、アンドリス・ネルソンス(指)ボストンSO。タングルウッド祝祭cho (10)オードラ・マクドナルド アンドリス・ネルソンス(指) 全員参加 ■ボーナス タングルウッドのバーンスタイン+ビデオ・メッセージ 収録:2018年8月25日、タングルウッド音楽祭(ライヴ) 画面:16:9,HD,1080i 音声:PCMステレオ、DTS-HDMA5.1 字幕(ボーナス):英独韓,日本語 リージョン:All 収録時間:コンサート:127:00 ボーナス:14:00 |
|
||
| GRAND SLAM GS-2275(1CD) |
(1)ブラームス:交響曲第3番ヘ長調 Op.90 (2)ベートーヴェン:「レオノーレ」序曲第2番 ハ長調 Op.72 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)BPO 録音:(1)1954年4月27日ベルリン、ティタニア・パラスト (2)1954年4月4、5日ベルリン高等音楽院 使用音源:Private archive(2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(ラジオ放送用録音(1)、録音セッション(2)) |
|
||
| Naive V-7262[NA] |
メンデルスゾーン(1809-147):作品集 弦楽のためのシンフォニア第2番ニ長調(1821) ヴァイオリンと弦楽のための協奏曲 ニ短調(1822) ソプラノと弦楽のためのサルヴェ・レジーナ 変ロ長調(1824)* 弦楽四重奏のためのフーガ 変ホ長調(1827) 弦楽のためのシンフォニア第5番変ロ長調(1821) ピアノと弦楽のためのラルゴ ニ短調(1820) 3声のフーガ ト短調(1820) 3声のフーガ ニ短調(1820) |
ファビオ・ビオンディ(Vn、指揮) エウローパ・ガランテ パオラ・ポンチェット(フォルテピアノ) モニカ・ピッチニーニ(S)* 録音:2020年7月11-13日、サラ・ギスレリ(アッカデミア・モンティス・レガリス)、モンドヴィ(イタリア) |
|
||
| Edition HST HST-121(1CD) 税込定価 |
J.B.ヴァンハル(1739-1813);交響曲集第27巻
(HST-121) 交響曲変ホ長調「スヴィーテン男爵」 Bryan Es13(ca.1780) 交響曲ハ長調Bryan C5(1769-71?) 交響曲へ長調Bryan F5(1767-68?) (以下Bonus-) チェロ・ソナタ(バスを伴うチェロ独奏曲)イ長調 Weinmann VIId:A1(ca.1775) (*) |
ハイドン・シンフォ二エッタ トウキョウ リーダー;松井利世子、福本 牧(Vn)、他 (*)小原 圭(Vc独奏)、古庄正典(Cb) 録音:2022年4月26日、江東公会堂小ホール(東京)にて、ライヴ収録 ※Es13, A1は世界初録音! |
|
||
| DACAPO MAR-8.204002(4CD) NX-F10 |
ペア・ノアゴー(1932-):8つの交響曲 【CD1】 交響曲第3番(1972-1975) 交響曲第7番(2004-2006)…世界初録音 【CD2】 交響曲第1番「厳格」(1953-55/1956改訂) 交響曲第8番(2010-2011)…世界初録音 【CD3】 交響曲第6番「一日の終わりに」(1999) 交響曲第2番(1970/1971改訂) 【CD4】 交響曲第5番(1987-1990/1991改訂) 交響曲第4番(1981) |
ウッラ・ミュンシュ(A) デンマーク国立放送合唱団 デンマーク国立声楽アンサンブル デンマーク国立RSO トマス・ダウスゴー(指) VPO サカリ・オラモ(指) オスロPO ヨーン・ストルゴーズ(指) 録音:2007年12月20-22日 Danish Radio Concert Hall, Copenhagen(デンマーク) 2008年6月2-5日 Danish Radio Concert Hall, Copenhagen(デンマーク) 2013年5月16-17日 Konzerthaus Wien, Vienna(オーストリア) 2013年5月25-26日 Konzerthaus Wien, Vienna(オーストリア) 2015年5月25-28日 Oslo Konserthus(ノルウェー) 2015年6月1-5日 Orchestra Rehearsal Room, Oslo Opera House(ノルウェー) |
|
||
| CPO CPO-555319(1CD) NX-B10 |
カール・レーヴェ:交響曲 ニ短調/交響曲 ホ短調
他 交響曲 ニ短調(1835) 交響曲 ホ短調(1834) 序曲「テミスト」 |
イェナ・フィルハーモニー ジモン・ガウデンツ(指) 録音:2019年9月17-20日 |
|
||
 PROMINENT CLASSICS 2506-5600(10CD) |
チェリビダッケ+ロンドン交響楽団・伝説のコンサート集 ■CD1 ヴェルディ:「運命の力」序曲 ヒンデミット:交響曲「画家マティス」 プロコフィエフ:「ロメオとジュリエット」組曲[モンタギュー家とキャピュレット家/少女ジュリエット/仮面/別れの前のロメオとジュリエット/アンティル列島の娘たちの踊り/墓の前のロメオ/タイボルトの死] ■CD2 ブラームス:交響曲第3番 ■CD3 ブラームス:交響曲第1番 ブラームス:ハンガリー舞曲第1番 ■CD4 シューマン:交響曲第2番 ラヴェル:スペイン狂詩曲 ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲 ■CD5 ワーグナー:「タンホイザー」序曲 モーツァルト:交響曲第38番「プラハ」* シベリウス:交響詩「エン・サガ」* ■CD6 プロコフィエフ:交響曲第5番 ティペット:歌劇「真夏の結婚」~祭典の踊り* ■CD7 ドビュッシー:「映像」~イベリア ムソルグスキー(ラヴェル編):組曲「展覧会の絵」 ■CD8コダーイ:「ガランタ舞曲」 ラヴェル:組曲「マ・メール・ロア」 ■CD9 ブラームス:交響曲第1番 デュカス:交響詩「魔法使いの弟子」* ■CD10 ラヴェル:ピアノ協奏曲 フォーレ:レクイエム |
セルジュ・チェリビダッケ(指)LSO (以下CD10) アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(P) マリー・マクローリン(S) グウィン・ハウエル(Bs) リチャード・ヒコックス(指)ロンドン交響cho ■CD1 録音:1978年4月11日 ■CD2、CD3 録音:1979年5月31日 ■CD4 録音:1979年9月18日 ■CD5 録音:1979年9月18日 録音:1979年9月21日* ■CD6 録音:1979年9月21日 録音:1980年4月10日* ■CD7 録音:1980年4月10日 ■CD8 録音:1980年4月13日 ■CD9 録音:1980年4月13日 録音:1982年4月8日* ■CD10 録音:1982年4月8日 全てロンドン、ロイヤル・フェスティヴァル・ホールにおけるライヴ録音 ※英語、日本語によるライナーノート付 |
|
||
| H.M.F HMM-902448(2CD) |
ケルビーニ:『ロドイスカ』序曲 ベートーヴェン:交響曲第4番 変ロ長調 op.60 メユール:交響曲第1番ト短調(1808) ベートーヴェン:交響曲第8番 |
ベルリン古楽アカデミー【コンサートマスター:ベルンハルト・フォルク】 録音:2021年4,5月、テルデックス・スタジオ(ベリリン) |
|
||
| Epitagraph EPITA-026 (3UHQCD) |
マーラー:交響曲第1番「巨人」 交響曲第2番「復活」# 交響曲「大地の歌」* |
ブルーノ・ワルター(指)NYO マリア・シュターダー(S)# モーリン・フォレスター(A)# ウェストミンスター合唱団# キャスリーン・フェリアー(A)* セット・スヴァンホルム(T)* 録音:1950年2月12日(巨人)、1957年2月17日(復活)、1948年1月18日(大地の歌) カー ネギ ー・ホ ー ル 、ニューヨー ク(ライヴ ) Produced by Epitagraph(原盤:エピタグラフ) |
|
||
| MDG MDG-91222566 (1SACD) |
メンデルスゾーン・プロジェクトVOL.3 シンフォニア第7番ニ短調 ヴァイオリンとピアノのための二重協奏曲ニ短調 |
ドグマ室内オーケストラ ミハイル・グレヴィチ(指) ア ニ カ・トロイトラ ー(P) 録音:2021年8月8-11日マリエンミュンスター修道院コンツェルトハウス |
|
||
| MDG MDG-63222442 (3CD) |
ヨゼフ・ボフスラフ・フェルステル(1859-1951):交響曲全集 交響曲第2番Op.29 交響曲第1番Op9 交響曲第3番Op.36* 交響曲第4番Op.54* 組曲ト短調『イン・デン・ベルゲン』Op.7# 交響曲第5番Op.141# |
オスナブリュックSO ヘルマン・ボイマー(指) 録音:2007年3、5月、録音:2008年2月4-5,20,22日*、録音:2009年2月23~24日、5月4~5日# |
|
||
| RUBICON RCD-1073(1CD) |
シベリウス:交響曲第5番他 交響曲第5番変ホ長調 Op.82 交響曲第6番ニ短調 Op.104 交響曲第7番ハ長調 Op.105 |
オウェイン・アーウェル・ヒューズ(指) ロイヤルPO |
|
||
| CORO COR-16192(1CD) |
ハイドン:交響曲集 Vol.8 交響曲第103番「太鼓連打」 ミサ曲 変ロ長調 Hob.XXII:12「テレジア・ミサ」 |
メアリー・ベヴァン(S)、 キャスリン・ウィン=ロジャーズ(Ms)、 ジェレミー・バッド(T)、 サムナー・トンプソン(Br)、 ハリー・クリストファーズ(指)、 ヘンデル&ハイドン・ソサエティ 録音:2022年1月28日&30日、シンフォニー・ホール(ボストン) |
|
||
| Quartz QTZ-2146(1CD) |
ブラームス:悲劇的序曲 Op.81 ハイドンの主題による変奏曲 交響曲第2番ニ長調 Op.73 |
リマ・スシャンスカヤ(指)、 ロンドン・ナショナルSO 録音:2021年5月1日-2日 |
|
||
| Halle CDHLD-7558(2CDR) |
ヴォーン・ウィリアムズ:南極交響曲(交響曲第7番) ノーフォーク狂詩曲第1番 交響曲第9番ホ短調 揚げひばり |
マーク・エルダー(指)ハレO、 ソフィー・ベヴァン(第7番)、 ハレ合唱団のソプラノ&アルト歌手たち(第7番)、 マシュー・ハミルトン(合唱指揮)(第7番)、 リン・フレッチャー(Vn)(揚げひばり) 録音:2019年1月24日(第7番)、ブリッジウォーター・ホール(マンチェスター)/2021年11月15日-17日(第9番)、ハレ・セント・ピーターズ教会(マンチェスター)/2005年11月5日ー6日、BBCスタジオ7(マンチェスター) |
|
||
| APARTE AP-293(1CD) |
1773年モーツァルトとグレトリ 50-50 モーツァルト:交響曲第25番ト短調K.183 グレトリ:組曲「セファールとプロクリス」 モーツァルト:歌劇「エジプト王タモス」~組曲 |
マルティン・ヴァルベルグ(指) オルケルテル・ノルド 録音:2021年11月/セルブ教会(ノルウェー) |
|
||
| BIS BISSA-2362 (1SACD) |
シンガポール響のスクリャービン 法悦の詩Op.54 ピアノ・ソナタ第5番Op.53* プロメテウスOp.60 |
エフゲニー・スドビン(P) ラン・シュイ(指) シンガポールSO シンガポール響cho、 シンガポールSO青年cho 録音:2017年7/8月エスプラネード・コンサート・ホール(シンガポール)、 2006年8月ヴェステロース・コンサート・ホール* |
|
||
| ONDINE ODE-1391(1CD) NX-B07 |
ルードヴィグ・ヌールマン(1831-1885):交響曲第3番/序曲集 演奏会用序曲 変ホ長調 Op. 21(1856) 葬送行進曲「アウグスト・セーデルマンの思い出に」 Op. 46(1876) シェイクスピアの「アントニーとクレオパトラ」への序曲 Op. 57(1881) 交響曲第3番ニ短調 Op. 58(1881) |
オウルSO ヨハネス・グスタフソン(指) 録音:2021年5月27-31日 |
|
||
 Audite AU-95745(2CD) |
ルツェルン・フェスティヴァル・シリーズ第18弾 ハイドン:交響曲第99番 シェーンベルク:ピアノ協奏曲 Op.42 チャイコフスキー:交響曲第4番 |
ジョン・オグドン(P) ラファエル・クーベリック(指) ニュー・フィルハーモニアO ライヴ録音:1968年9月8日クンストハウス(ルツェルン)(モノラル) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2272(1CD) |
フルトヴェングラー/ハイドン&チャイコフスキー (1)チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調 Op.64 (2)ハイドン:交響曲第88番ト長調Hob. I:88『V字』 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) トリノ・イタリアRSO 録音:(1)1952年6月6日Sala del Conservatorio(トリノ) (2)1952年3月3日Auditorium A, via Montebello(トリノ) 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(ラジオ放送用録音) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2273(1CD) |
マーラー:交響曲第9番ニ長調 | ジョン・バルビローリ(指)BPO 録音:1964年1月10、11、14、18日ベルリン・ダーレム、イエス・キリスト教会 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:ステレオ(録音セッション) |
|
||
| Hanssler HC-22023(1CD) |
ペーター・ルジツカ(1948-):自作自演集 (1)「ヘルダーリン交響曲」~バリトン、室内合唱とオーケストラのための (2)「ムネーモシュネー~記憶と忘却」~ソプラノ、18の弦と打楽器のための |
(1)トーマス・E・バウアー(Br)、北ドイツ放送合唱団、ジェームズ・ウッド(合唱指揮)、ドイツ放送PO、ペーター・ルジツカ(指)
(2)サラ・マリア・サン(S)、ドイツ放送PO、ペーター・ルジツカ(指) 録音:(1)2012年6月17日コングレスザール、ザールブリュッケン(ライヴ) (2)2021年5月7&8日ザールラント放送大ホール、ザールブリュッケン |
|
||
| TOCCATA TOCC-0645(1CD) NX-B03 |
フリードリヒ・ブルク(1937-):管弦楽作品集
第3集 交響曲第22番「In the Ocean 海で」(2019) 交響曲第23番「In the Ingrian Mode イングリアの様式で」(2021) |
リトアニア国立SO マーリス・クプチス(指) 録音:2021年5月17-22日、2021年11月22-26日 世界初録音 |
|
||
| SWR music SWR-19119CD(1CD) NX-B06 |
マルティヌー:交響曲第5番 交響曲第6番「交響的幻想曲」* |
シュトゥットガルトRSO ロジャー・ノリントン(指) 録音:2008年2月16-18日、2003年9月25-26日* |
|
||
| SWR music SWR-19118CD(1CD) NX-B02 |
ハイドン:交響曲第102番変ロ長調 Hob. I:102 チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」 |
シュトゥットガルトRSO セルジュ・チェリビダッケ(指) 録音:1959年9月17日(ライヴ) |
|
||
| Goodies 78CDR-3875(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」 | ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)BPO 日POLYDOR 60024/28(独 POLYDOR 69855/9と同一録音) 1926年10月16日)、10月30日、1927年1月30日ベルリン録音 (古いコードのため雑音があります) |
|
||
| Pentatone PTC-5186894(1CD) |
シューベルト:交響曲第9番「グレート」 交響曲第8番「未完成」(「私の夢」第1部&第2部付き)* |
ルネ・ヤーコプス(指) ビー・ロック・オーケストラ トビアス・モレッティ(朗読)* 録音:2020年12月デ・ジンゲル(アントワープ) |
|
||
| KLARTHE KLA-057(1CD) |
ウェーバー:作品集 (1)交響曲第1番ハ長調 Op.19 (2)ホルン小協奏曲 ホ短調 Op.45 (3)アダージョとロンド J.115 (4)クラリネット協奏曲第2番変ホ長調 Op.74 |
(2)ダヴィド・ゲリエ(Hrn) (3)トマ・ブロシュ(グラス・ハーモニカ) (4)ニコラ・バルディルー(Cl) ヴィクトル・ユーゴー・フランシュ・コンテO ジャン=フランソワ・ヴェルディエ(指 録音:2015年12月CRR(フランス) |
|
||
| C Major 80-6908(2DVD) 80-7004(Bluray) |
ブルックナー:交響曲第1番ハ短調 WAB101(ウィーン稿) 交響曲第7番ホ長調 WAB107(ノーヴァク版) ■ボーナス映像「ディスカヴァリング・ブルックナー」 各交響曲について(ティーレマンと音楽学者ヨハネス=レオポルド・マイヤー氏による対話) |
クリスティアン・ティーレマン(指) VPO 収録:第1番:2021年2月、ウィーン楽友協会(無観客ライヴ) 第7番:2021年8月、ザルツブルク音楽祭(ライヴ) ◆DVD 画面:16:9、NTSC 音声:PCMステレオ、DTS5.1、DVD9 [ボーナス映像 ] 言語:ドイツ語、字幕:英韓,日本語 Total time:181分 交響曲:127分、ボーナス:54分 ◆Bluray 画面:16:9、1080i 音声:PCMステレオ、DTS-HD MA5.1 BD50 [ボーナス映像 ] 言語:ドイツ語、字幕:英韓,日本語 Total time:181分 交響曲:127分、ボーナス:54分 |
|
||
| GRAND SLAM GS-2271(1CD) |
(1)ブラームス:交響曲第1番ハ短調 Op.68 (2)ベートーヴェン:「レオノーレ」序曲第3番 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) トリノ・イタリアRSO 録音:(1)1952年3月7日トリノ、Sala del Conservatorio (2)1952年3月3日トリノ、Auditorium A, via Montebello 使用音源:Private archive (2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(ラジオ放送録音) |
|
||
| Halle CDHLD-7557JP(5CD) 日本向け限定生産 |
ヴォーン・ウィリアムズ:交響曲全集 CD1:海の交響曲(交響曲第1番) CD2:ロンドン交響曲(交響曲第2番)、 交響曲第8番 CD3:田園交響曲(交響曲第3番)、 交響曲第4番 CD4:交響曲第5番ニ長調、 交響曲第9番ホ短調 CD5:交響曲第6番ホ短調、 南極交響曲(交響曲第7番) |
マーク・エルダー(指)、ハレO、キャスリン・ブロデリック(S)(第1番)、ロデリック・ウィリアムズ(Br)(第1番)、ハレcho(第1番)、ハレ・ユース合唱団(第1番)、スコラ・カントルム(第1番)、アド・ソレム(第1番)、ジェイムズ・バートン(客演合唱指揮)(第1番)、サラ・フォックス(第3番)、ソフィー・ベヴァン(第7番)、ハレchoのソプラノ&アルト歌手たち(第7番)、マシュー・ハミルトン(合唱指揮)(第7番) 録音:2014年3月29日(第1番)、2010年10月14日(第2番)、2013年9月9日-10日(第3番)、2016年4月7日(第4番)、2011年11月9日(第5番)、2016年11月10日(第6番)、2019年1月24日(第7番)、2012年2月3日(第8番)、2021年11月15日-17日(第9番)、ブリッジウォーター・ホール(マンチェスター/第1番、第2番、第4番、第5番、第6番、第7番)、ハレ・セント・ピーターズ教会(マンチェスター/第3番、第9番)、BBCスタジオ(サルフォード/第8番) ☆日本向け500セット完全限定のSONY DADCプレス盤 ☆書き下ろし日本語解説(等松春夫)付き |
|
||
 ELECT ERT-1044(5CD) UHQCD |
ベートーヴェン:交響曲全集 (1)交響曲第1番/(2)交響曲第3番「英雄」 (3)交響曲第2番/(4)交響曲第6番「田園」 (5)交響曲第4番/(6)交響曲第5番「運命」 (7)「エグモント」序曲/(8)交響曲第8番 (9)交響曲第7番/(10)レオノーレ序曲第3番 (11)交響曲第9番「合唱」(ルーマニア語歌唱) (12)「コリオラン」序曲 |
ジョルジュ・ジョルジェスク(指) ブカレスト・ジョルジュ・エネスコPO エミリャ・ペトレスク(S),マルタ・ケスラー(Ms)、イオン・ピソ(T)、マリウス・リンツラー(Bs)、 ジョルジュ・エネスコ・フィルcho、ルーマニア放送cho 録音:(1)1961年5月、(2)1961年3月 (3)1961年4月20日、(4)1961年10月 (5)1962年1月、(6)1961年8月 (7)1962年1月11日、(8)1961年5月 (9)1962年1月、(10)1962年1月 (11)1961年7月、(12)1961年8月 全てルーマニア文化宮殿ホール(ステレオ) ※CD日本プレス。美麗夫婦箱5枚組。英語、日本語によるライナーノート付 |
|
||
 King International KKC-90006(2Bluray) |
朝比奈隆/ブルックナー交響曲選集 ■Disc1 (1)交響曲第4番変ホ長調「ロマンティック」(ハース版) (2)交響曲第5番変ロ長調(ハース版) (3)交響曲第7番ホ長調(ハース版) ■Disc2 (4)交響曲第8番ハ短調(ハース版) (5)交響曲第3番ニ短調(ハース版) (6)リハーサル(交響曲第3番) (7)実相寺昭雄監督インタビュー(2002年春収録) (8)鼎談(朝比奈隆×実相寺昭雄×松原千代繁)(1999年6月21日収録) |
朝比奈隆(指揮) 新日本フィルハーモニー交響楽団 映像演出:実相寺昭雄 収録:1992年5月13日東京文化会館(ライヴ)【第4番】、 9月2日サントリーホール(ライヴ)【第5番】 9月8日サントリーホール(ライヴ)【第7番】、 1993年2月16日サントリーホール(ライヴ)【第7番】 1996年12月12日東京文化会館(ライヴ)【第3番】 12月9日新日本フィルハーモニー交響楽団練習場【第3番のリハーサル】 |
|
||
| King International KKC-90008(2Bluray) |
朝比奈隆/ブラームス・チクルス ■Disc1 (1)交響曲第1番ハ短調Op.68 (2)ピアノ協奏曲第1番ニ短調Op.15 (3)ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.77 (4)交響曲第2番ニ長調Op.73 ■Disc2 (5)交響曲第3番ヘ長調Op.90 (6)ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲イ短調Op.102 (7)ピアノ協奏曲第2番変ロ長調Op.83 (8)特典映像:俳優・寺田農 実相寺昭雄監督と朝比奈隆先生の思い出 (9)交響曲第4番ホ短調Op.98 |
朝比奈隆(指揮) 新日本フィルハーモニー交響楽団 伊藤恵(ピアノ)(2)、 藤川真弓(ヴァイオリン)(3)、 豊嶋泰嗣(ヴァイオリン)(6)、 上村昇(チェロ)(6)、 園田高弘(ピアノ)(7) 映像演出:実相寺昭雄 収録:1990年2月5日(1)(6)、 5月1日(2)(5)、 4月3日(3)(4)、 6月1日(7)(9) オーチャードホール(ライヴ) |
|
||
| IDIS IDIS-6746(1CD) |
カラヤン・スペクタキュラー Vol.8 ベートーヴェン:交響曲第1番 交響曲第6番「田園」* |
NYO、RAIトリノSO* ヘルベルト・フォン・カラヤン(指) ライヴ録音:1958年11月22日、1954年2月12日* |
|
||
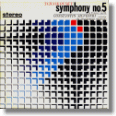 Treasures TRT-020(1CDR) |
超厳選!赤盤名演集Vol.7~シルヴェストリによるスラブ作品集 ボロディン:「イーゴリ公」~だったん人の踊り* ブラームス:ハンガリー舞曲第5番/第6番(シュメリンク編) ドヴォルザーク:スラブ舞曲第1番Op.46-1/第2番Op.46-2 チャイコフスキー:交響曲第5番# |
コンスタンティン・シルヴェストリ(指) パリ音楽院O、フィルハーモニアO# 録音:1961年1月30日-2月1日*、1961年2月2日、1957年2月21-22日#(全てステレオ) ※音源:TOSHIBA WS-23 、WS-20# ◎収録時間:75:31 |
| “実行すべきことをしたに過ぎないシルヴェストリの純粋な狂気!” | ||
|
||
| CPO CPO-555354(1CD) NX-B10 |
アルヴェーン(1872-1960):交響的作品集 第3集 交響曲第2番ニ長調 Op. 11 スウェーデン狂詩曲第3番「ダーラナ狂詩曲」 Op. 47 |
ベルリン・ドイツSO ウカシュ・ボロヴィチ(指) 録音:2019年5月21-24日 |
|
||
 LSO Live LSO-0875(2SACD) KKC-6557(2SACD) 国内盤仕様 (日本語解説付) 税込定価 |
2021年グンナー=コールス版「ブル4」の世界初録音! ■CD1 ブルックナー:交響曲第4番(1878-81年/Cohrs A04B) 第1楽章:Bewegt, nicht zu schnell(動いて、しかし速すぎずに)(作業段階B, 1881) 第2楽章:Andante quasi Allegretto(作業段階B, 1881) 第3楽章:Scherzo. Bewegt - Trio. Nicht zu schnell, Keinesfells schleppend-Scherzo da capo (スケルツォ。動いて/トリオ。速すぎず、遅くなりすぎず/スケルツォ・ダ・カーポ)(作業段階B, 1881) 第4楽章:Finale. Bewegt, nicht zu schnell(フィナーレ。動いて、しかし速すぎずに)(作業段階C, 1881年, カットあり版) ■CD2 ブルックナー:交響曲第4番 (1) Discarded Scherzo. Sehr schnell ? Trio. Im gleichen Tempo ? Scherzo da capo (1874/revised 1876;Cohrs A04B-1)(取り外されたスケルツォ-非常に速く/トリオ-同様のテンポで/スケルツォ・ダ・カーポ)(1874年/1876年改訂/Cohrs A04B-1) (2) Discarded Finale (‘Volksfest’). Allegro moderato 取り外されたフィナーレ(民衆の踊り)(1878; Cohrs A04B-2) (3) Andante quasi Allegretto (Work Phase A, 1878; extended initial version/1878年、作業段階A、第2楽章の当初の長いヴァージョン) (4) Finale. Bewegt; doch nicht zu schnell (Work Phase B, 1881; unabridged)(作業段階B, 1881年, カットなし版) |
サイモン・ラトル(指)LSO 録音:2021年10月、ジャーウッド・ホール、セント・ルークス、ロンドン |
|
||
 GRAND SLAM GS-2270(1CD) |
オスカー・フリート (1)ベルリオーズ:幻想交響曲 (2)チャイコフスキー:「くるみ割り人形」組曲 |
オスカー・フリート(指) (1)ソビエト国立SO (2)ロイヤルPO 録音:(1)1937年モスクワ、(2)1929年2月5、6日 使用音源:(1)Private archive(2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) (2)コロンビア L2318/20(SP盤/78回転) 録音方式:モノラル |
|
||
| GRAND SLAM GS-2268(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 | エリーザベト・シュワルツコップ(S)、エルザ・カヴェルティ(A)、エルンスト・ヘフリガー(T)、オットー・エーデルマン(Bs) ルツェルン祝祭cho ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) フィルハーモニアO 録音:1954年8月22日/ルツェルン、クンストハウス 使用音源:Privatearchive(2トラック、38センチ、オープンリール・テープ) 録音方式:モノラル(ラジオ放送用録音) |
|
||
| C Major 80-6708(2DVD) 80-6804(Bluray) |
ブルックナー:交響曲集 交響曲ヘ短調WAB99(第00番「習作」) 交響曲ニ短調WAB100(第0番) 交響曲第5番変ロ長調WAB105 ■ボーナス映像「ディスカヴァリング・ブルックナー」 各交響曲について(ティーレマンと音楽学者ヨハネス=レオポルド・マイヤー氏による対話) |
クリスティアン・ティーレマン(指) VPO 収録:2021年3月ウィーン楽友協会(無観客ライヴ) ◆DVD 画面:16:9、NTSC 音声:PCMステレオ、DTS5.1 DVD9 ボーナス映像 言語:ドイツ語、字幕:英、韓、日本語 Total time:254分 ◆Bluray 画面:16:9、1080i 音声:PCMステレオ、 DTS-HD MA5.1 BD50 ボーナス映像 言語:ドイツ語、字幕:英、韓、日本語 Total time:254分 |
|
||
| H.M.F HMM-905357(1CD) |
マーラー:交響曲第4番ト長調 | フランソワ=グザヴィエ・ロト(指) レ・シエクル サビーヌ・ドゥヴィエル(S) 録音:2021年11月/セーヌ・ミュジカルRIFFX第1スタジオ(ブローニュ・ビリヤンクール) |
|
||
| Altus ALTSA-508(1SACD) シングルレイヤー |
INA 秘蔵音源・バーンスタイン&フランス国立管ライヴ ベルリオーズ:「ローマの謝肉祭」序曲 作品9 シューマン:交響曲第2番ハ長調 作品61 ショスタコーヴィチ:交響曲第5番ニ短調 作品47 |
レナード・バーンスタイン(指) フランス国立放送O ライヴ録音:1966年11月30日パリ、シャンゼリゼ劇場(ステレオ) |
|
||
 EUROARTS 20-72119(DVD) |
カラヤン・イン・リハーサル&パフォーマンス (1)シューマン:・交響曲第4番 本番(27分)/リハーサル風景 (62分) (2)ベートーヴェン:交響曲第5番『運命』 本番(31分)/リハーサル風景 (21分) |
ヘルベルト・フォン・カラヤン(指) (1)ウィーンSO 監督:アンリ=ジョルジュ・クルーゾー 撮影:クルト・ユーネック 録音:ギュンター・ヘルマンス 製作年:1965年 (2)BPO 監督:アンリ=ジョルジュ・クルーゾー 撮影:アウグスト・カーニエル、クルト・コーダル 録音:ギュンター・ヘルマンス 収録:1966年1月,2月 ベルリン、ユニオン・スタジオアトリエ 画面:4:3 NTSC、モノクロ 音声:PCMステレオ リージョン:All 字幕:独、英、140分 |
|
||
| EUROARTS 20-72723(Bluray) |
カラヤン~ベートーヴェン:「運命」&「第9」 (1)ベートーヴェン:交響曲第5番『運命』 本番とリハーサル風景 (2)ベートーヴェン:交響曲第9番『合唱』 ■特典映像:『指揮の芸術』 監督:アンリ=ジョルジュ・クルーゾー |
ヘルベルト・フォン・カラヤン(指)BPO (1)ドイツ語 字幕:英、仏 監督:アンリ=ジョルジュ・クルーゾー 収録:1966年1月、2月ベルリン、ユニオン・スタジオアトリエ 画面:モノクロ (2)アンナ・トモワ=シントウ(S)、アグネス・バルツァ(Ms)、ルネ・コロ(T)、ヨセ・ヴァン・ダム(Bs) ベルリン・ドイツ・オペラcho 収録:1977年12月31日ベルリン、フィル 監督:ハンフリー・バートンハーモニー(ライヴ) 画面:Full HD,16:9 音声:PCMステレオ リージョン:All 字幕:英、仏、原語:ドイツ語、119分 |
|
||
| REFERENCE FR-747SACD(1SACD) |
ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」 スティーヴン・スタッキー(1949-2016):「沈黙の春」* |
ピッツバーグSO マンフレート・ホーネック(指) 録音:ハインツホール、ピッツバーグ(ライヴ)、2017年6月23,24&25日、2018年4月20,21&22日* |
|
||
| TOCCATA TOCC-0646(1CD) NX-B03 |
デレク・スコット(1950-):管弦楽作品集 第2集 交響曲第1番変イ長調 Op.23(1995/2021管弦楽版) 交響曲第2番ト短調 Op.26(1996?97/2021管弦楽版) 交響詩「シルヴァー・ソード」 Op.39(2021) |
リエパーヤSO ポール・マン(指) 録音:2022年3月22-26日 世界初録音 |
|
||
| Forgotten Records fr-1840(1CDR) |
ハイドン:交響曲第102番変ロ長調 Hob.I:102* ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」# |
ゲオルク・ショルティ(指)*,# フランス国立放送O*、パリ音楽院O# 録音:1959年8月1日ザルツブルク* 、1959年9月3日ブザンソン#、ともに放送用ライヴ |
| Forgotten Records fr-1841B(1CDR) |
セルマー・マイロヴィツ~ SP復刻Vol.1 ベルリオーズ:幻想交響曲* グレトリー:バレエ組曲「共和主義者ロジエール」# |
セルマー・マイロヴィツ(指)大PO 録音:1934年3月14日、16日、21日* 1934年12月12日# ※音源:Pathé PDT 10/15* PD 7# |
| Forgotten Records fr-1839(1CDR) |
ヴァンデルノート~モーツァルト:交響曲集Vol.3 第40番ト短調 K.550* 第41番「ジュピター」# |
アンドレ・ヴァンデルノート(指) パリ音楽院O 録音:1956年10月3日-4日*、1957年2月4日-5日#、12日#、1957年4月15日-16日*、1957年6月7日* ※音源:La Voix de son Maître FALP 470 |
 Treasures TRT-021(1CDR) |
ミトロプーロス/ボロディン、チャイコフスキー他 ボロディン(R=コルサコフ編):だったん人の踊り* イッポリトフ=イワーノフ:「コーカサスの風景」組曲第1番** チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調Op.64# |
ディミトリ・ミトロプーロス(指)NYO 録音:1953年4月20日*、1952年12月1日**、1954年3月27日# (全てモノラル) ※音源:米COLUMBIA CL-751*,** 、英PHILIPS SBL-5205 # ◎収録時間:79:04 |
| “絶頂時のミトロプーロスのだけが可能な壮絶無比な魂の叫び!” | ||
|
||
| DUX DUX-1803(1CD) |
クシシュトフ・メイエル(b.1943):チェロとオーケストラのための室内協奏曲
「Canti Amadei」(1983-1984) 交響曲第5番 Op.44(1978-1979) |
バルトシュ・コジャク(Vc)、 ソポト・ポーランド室内PO、 ラファウ・ヤニャク(指) 録音:2021年8月23日-26日 |
|
||
| BSOrec BSOREC-0002(1CD) NYCX-10324(1CD) 国内盤仕様 税込定価 |
ブレット・ディーン(1961-):TESTAMENT テスタメント- 管弦楽のための音楽(原曲:
12人のヴィオラ奏者のための音楽) ベートーヴェン:交響曲第2番ニ長調Op. 36 |
ウラディーミル・ユロフスキ(指) バイエルン国立O 録音:2020年10月5日&6日ミュンヘン、バイエルン国立歌劇場 ※国内盤には片桐卓也氏による日本語解説付き |
|
||
| Capriccio C-7422(6CD) NX-D03 |
シャーンドル・ヴェーグ&カメラータ・ザルツブルク名演集 【CD1】* ベートーヴェン: 1-7.弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調 Op. 131(弦楽合奏) 8. 大フーガ 変ロ長調 Op. 133(弦楽合奏) 【CD2】 1-9. ハイドン:十字架上のキリストの最後の7つの言葉(弦楽四重奏版) Op. 51Hob. III:50-56(弦楽合奏) 【CD3】 シューベルト: 1-4. 交響曲第5番変ロ長調 D. 485 5-8. 交響曲第6番ハ長調 D. 589 【CD4】 シューベルト: 1-2. 交響曲第8番「未完成」 3-6. 交響曲第9番「ザ・グレート 【CD5】 1-4.ブラームス:弦楽五重奏曲第2番 ト長調 Op. 111(弦楽合奏) 5-9. シェーンベルク:浄められた夜(弦楽合奏版) 【CD6】 1-3. バルトーク:ディヴェルティメント BB 118 4-6. ベルク:抒情組曲からの3つの小品 (弦楽合奏版) 7-16. ストラヴィンスキー:バレエ音楽『ミューズを率いるアポロ』 |
インターナショナル・ミュージシャンズ・セミナー・ソロイスツ* カメラータ・ザルツブルク(モーツァルテウム・カメラータ・アカデミカ,ザルツブルク) シャーンドル・ヴェーグ(指) 録音:1987/89年 St. Buryan Church, Cornwall(UK)…CD1 1992年3月15日 Grosser Saal, Wiener Konzerthaus, Vienna(オーストリア)…CD2 1990年11月 Mozarteum, Salzburg(オーストリア)…CD3:1-4 1993年12月10-12日(ライヴ) Mozarteum, Salzburg(オーストリア)…CD3:5-8 1994年2月25日、27日 Mozarteum, Salzburg(オーストリア)…CD4:1-2 1993年3月26、28日 Mozarteum, Salzburg(オーストリア)…CD4:3-6 1991年10月26-27日、11月1-2日 Mozarteum, Salzburg(オーストリア)…CD5 1988年5月 Alte Aula, Salzburg(オーストリア)…CD6:1-3 1989年3月 Mozarteum, Salzburg(オーストリア)…CD6:4-6 1988年11月 Mozarteum, Salzburg(オーストリア)…CD6:7-16 |
|
||
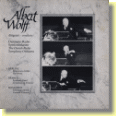 Treasures TRE-254(1CDR) |
アルベール・ヴォルフ~1960年代の貴重ライヴ! (1)ベルリオーズ:序曲「海賊」*、 (2)ベルリオーズ:序曲「ローマの謝肉祭」* (3)ベルリオーズ:「ベンベヌート・チュエルリーニ」序曲 (4)オネゲル:交響詩「夏の牧歌」 (5)フランク:交響曲ニ短調 |
アルベール・ヴォルフ(指) パリ音楽院O*、デンマークRSO 録音:(1)(2)1955年6月20-22日 (3)1962年3月15日ライヴ (4)1962年3月1日ライヴ (5)1965年1月28日ライヴ、全てモノラル ※音源:(1)(2)LONDON LL-1297、(3)-(5)ARTE SYMFONIA ARTE-SYMFONIA-003 ◎収録時間:76:58 |
| “アルベール・ヴォルフの知られざる晩年の完熟至芸!” | ||
|
||
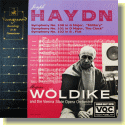 Treasures TRE-265(1CDR) |
ヴェルディケ~ハイドン:交響曲集Vol.1 交響曲第100番ト長調 「軍隊」 Hob.I:100 交響曲第101番ニ長調 「時計」 Hob.I:101 交響曲第102番変ロ長調 Hob.I:102* |
モーゲンス・ヴェルディケ(指) ウィーン国立歌劇場O 録音:1956年6月ウィーン楽友協会小ホール(ステレオ) ※音源:墺amadeo AVRS-12013St*、AVRS-12014St ◎収録時間:74:20 |
| “今こそ聴きたい、永久に光を失わないハイドンの究極形!” | ||
|
||
 GENUIN GEN-22742(4CD) ★ |
ハインツ・レーグナー/ライプツィヒ・ゲヴァントハウスでのライヴ録音集 (1)メンデルスゾーン:序曲「静かな海と楽しい航海」 (2)ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」 (3)シューベルト:交響曲第8番「未完成」 (4)シューベルト(マーラー編):弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」 (5)レーガー:モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ Op.132 (6)ラヴェル:クープランの墓 (7)ブルックナー:交響曲第6番 (8)ガーシュウィン:パリのアメリカ人 |
ハインツ・レーグナー(指) (1)(2)(8)MDR室内PO (3)-(7)MDR響 録音:(1)1999年2月20日、(2)1999年2月28日、(3)1995年8月25日、(4)1997年9月21-22日、(5)1998年10月20日、(6)2001年8月8日、(7)1994年7月12日、(8)1997年12月25日、ライプツィヒ・ゲヴァントハウスにおけるライヴ(全て) |
|
||
| Diapason DIAPCF-024(11CD) ★ |
チャイコフスキー:交響曲、協奏曲&室内楽作品集
~ 仏ディアパゾン誌のジャーナリストの選曲による名録音集 【CD1】 (1)交響曲第1番ト短調 Op.13「冬の日の幻想」 (2)交響曲第2番ハ短調 Op.17「小ロシア」 (3)スラヴ行進曲 Op.31 【CD2】 (1)交響曲第3番ニ長調 Op.29「ポーランド」 (2)幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」Op.32 (3)アレクサンドルⅢ世戴冠式行進曲ニ長調 【CD3】 (1)交響曲第4番ヘ短調 Op.36 (2)幻想序曲「ハムレット」Op.67 (3)幻想序曲「ロメオとジュリエット」 【CD4】 (1)交響曲第5番ホ短調 Op.64 (2)幻想曲「テンペスト」Op.18 (3)序曲「1812年」Op.49 【CD5】 (1)交響曲第6番ロ短調 Op.74「悲愴」 (2)イタリア奇想曲 Op.45 (3)序曲「1812年」Op.49 【CD6】 (1)ロココ風の主題による変奏曲 Op.33 (2)マンフレッド交響曲 Op.58 【CD7】 (1)ピアノ協奏曲第1番変ロ短調 Op.23 (2)ピアノ協奏曲第2番ト長調 Op.44 (3)「四季」~11月「トロイカ」 【CD8】 (1)ピアノ三重奏曲イ短調 Op.50「ある偉大な芸術家の思い出のために」 (2)協奏的幻想曲ト長調 Op.56 【CD9】 (1)ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op.35 (2)ゆううつなセレナード Op.26 (3)弦楽六重奏曲ニ短調 Op.70「フィレンツェの 【CD10】 (1)弦楽セレナード ハ長調 Op.48 (2)弦楽四重奏曲第1番ニ長調 Op.11 (3)ワルツ・スケルツォ Op.34 (4)なつかしい土地の思い出 Op.42 瞑想曲ニ短調 Op.42-1 (5)スケルツォ ハ短調 Op.42-2 (6)メロディ変ホ長調 Op.42-3 【CD11】 弦楽四重奏曲第2番ヘ長調 Op.22 弦楽四重奏曲第3番変ホ短調 Op.30 録音選定:デュック・ムソー、ディディエ・ファン・モエレ、クリストフ・フス、ローラン・ミュラロ、ベルトラン・ボワサール、ジャン=ミシェル・モルコー |
【CD1】 (1)ニコライ・ゴロワノフ(指)モスクワRSO 録音:1948年 (2)ディミトリ・ミトロプーロス(指)ミネアポリスSO 録音:1946年 (3)パウル・ファン・ケンペン(指)アムステルダム・ロイヤルコンセルトヘボウO 録音:1951年 【CD2】 (1)エイドリアン・ボールト(指)ロンドンPO 録音:1956年 (2)イーゴリ・マルケヴィチ(指)LSO 録音:1962年 (3)ヴィアチェスラフ・オフチニコフ(指)モスクワRSO 録音:1979年 【CD3】 (1)アンタル・ドラティ(指)LSO 録音:1960年 (2)エイドリアン・ボールト(指)ロンドンPO 録音:1952年 (3)セルゲイ・クーセヴィツキー(指)ボストンSO 録音:1936年 【CD4】 (1)エフゲニー・ムラヴィンスキー(指)レニングラードPO 録音:1960年 (2)エフゲニー・スヴェトラーノフ(指)ソヴィエト国立SO 録音:1970年 (3)ニコライ・ゴロワノフ(指)モスクワRSO 録音:1948年 【CD5】 (1)イーゴリ・マルケヴィチ(指)LSO 録音:1962年 (2)キリル・コンドラシン(指)ビクターSO 録音:1958年 (3)アンタル・ドラティ(指)ミネアポリスSO、ミネソタ大学吹奏楽団 録音:1958年 【CD6】 (1)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(Vc)、ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー(指)レニングラードPO (2)アレクサンドル・ガウク(指)モスクワRSO 録音:1949年 【CD7】 (1)エミール・ギレリス(P)、カレル・アンチェル(指)チェコPO 録音:1953年 (2)シューラ・チェルカスキー(P)、リヒャルト・クラウス(指)ベルリンPO 録音:1955年 (3)ラフマニノフ(P) 録音:1920年 【CD8】 (1)レオニード・コーガン(Vn)、ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(Vc)、エミール・ギレリス(P) 録音:1952年 (2)タチアナ・ニコラーエワ(P)、キリル・コンドラシン(指)ソヴィエト国立SO 録音:1950年頃 【CD9】 (1)ダヴィド・オイストラフ(Vn)、ユージン・オーマンディ(指)フィラデルフィアO 録音:1959年 (2)ヤッシャ・ハイフェッツ(Vn)、アルフレッド・ウォーレンスタイン(指)ロサンゼルス・フィルハーモニック 録音:1954年 (3)レオニード・コーガン(Vn)、エリーザベト・ギレリス(Vn)、ルドルフ・バルシャイ(Va)、ゲンリフ・タラリアン(Va)、スヴャトスラフ・クヌシェヴィツキ(Vc)、ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(Vc) 録音:1956年 【CD10】 (1)ゲオルク・ショルティ(指)イスラエルPO 録音:1958年 (2)ハリウッドSQ〔フェリックス・スラットキン(Vn)、ポール・シュアー(Vn)、ポール・ロビン(Va)、エリナー・アラー(Vc)〕 録音:1952年 (3)ダヴィド・オイストラフ(Vn)、ウラディーミル・ヤンポルスキ(P) 録音:1956年 (4)ミロン・ポリアキン(Vn)、ウラディーミル・ヤンポルスキ(P) 録音:1939年 (5)ナタン・ミルシテイン(Vn)、レオポルド・ミットマン(P) 録音:1938年 (6)ヨーゼフ・ハシッド(Vn)、ジェラルド・ムーア(P) 録音:1940年 【CD11】 ボロディン・クヮルテット〔ロスティスラフ・ドゥビンスキー(Vn)、ヤロスラフ・アレクサンドロフ(Vn)、ディミトリー・シェバリーン(Va)、ヴァレンティン・ベルリンスキー(Vc)〕 録音:1953年頃 |
|
||
| オクタヴィア OVCL-00777(12CD) 三方背BOX+プラケース仕様 税込定価 2022年1月26日発売 |
ショスタコーヴィチ交響曲全集 at 日比谷公会堂 交響曲第1番ヘ短調Op.10※2種類演奏を収録 交響曲第2番ロ長調Op.14 「十月革命に捧げる」 交響曲第3番変ホ長調Op.20 「メーデー」 交響曲第4番ハ短調Op.43 交響曲第5番ニ短調Op.47 交響曲第6番ロ短調Op.54 交響曲第7番ハ長調Op.60 「レニングラード」 交響曲第8番ハ短調Op.65 交響曲第9番変ホ短調Op.70 交響曲第10番ホ短調Op.93 交響曲第11番ト短調Op.103 「1905年」 交響曲第12番ニ短調Op.112 「1917年」 交響曲第13番変ロ短調Op.113 「バビ・ヤール」 交響曲第14番ト短調Op.135 「死者の歌」 交響曲第15番イ長調Op.141 |
井上道義(指) サンクトペテルブルクSO(第1番-第3番、第5番-第7番、第10番、第13番)、 千葉県少年少女オーケストラ(第1番)、 東京フィルハーモニーSO(第4番)、 新日本フィルハーモニーSO(第8番、第9番、第15番)、 名古屋フィルハーモニーSO(第11番、第12番)、広島SO(第14番) セルゲイ・アレクサーシキン(Br)(第13番、第14番) アンナ・シャファジンスカヤ(S)(第14番) 栗友会(合唱)(第2番、第3番) 東京オペラシンガーズ(男声合唱)(第13番) 録音:2007年11月3日(第1番-第3番)、11月4日(第5番・第6番)、11月10日(第1番・第7番)、11月11日(第10番・第13番)、11月18日(第14番)、12月1日(第4番)、12月5日(第11番・第12番)、12月9日(第8番)、2016年2月13日(第9番・第15番) 日比谷公会堂にてライヴ収録 |
|
||
| Altus ALTL-015(1CD) |
マーラー:交響曲第4番ト長調(エルヴィン・シュタインによる室内楽版) | 中山美紀(S) 青木尚佳 (コンサートマスター) 坂入健司郎(指) 東京ユヴェントス・フィルハーモニー 録音:2020年8月23日/宮地楽器ホール(小金井市文化センター)【東京ユヴェントス・フィルハーモニー特別演奏会】 |
|
||
| GRAND SLAM GS-2257(1CD) |
“フルトヴェングラー・ステレオ・トランスクリプション
2” (1)シューマン:交響曲第4番ニ短調 Op.120 (2)ハイドン:交響曲第88番ト長調 Hob.I:88 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指)BPO 録音:(1)1953年5月14日、(2)1951年12月4&5日/イエス・キリスト教会(ベルリン) 使用音源:(1)ドイツ・グラモフォン 139 971(未刊行テスト・プレスLP) (2)ドイツ・グラモフォン 139 969(未刊行テスト・プレスLP) 録音方式:ステレオ(モノラル録音の電気的ステレオ) |
|
||
| GRAND SLAM GS-2256(1CD) |
“フルトヴェングラー・ステレオ・トランスクリプション 1” ベートーヴェン:交響曲第5番『運命』 『エグモント』序曲 Op.84 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指揮BPO 録音:1947年5月27日ベルリン放送会館、ゼンデザール 使用音源:ドイツ・グラモフォン 139 962(未刊行テスト・プレスLP) 録音方式:ステレオ(モノラル録音の電気的ステレオ) |
|
||
| EUROARTS 20-57373(4Bluray) 20-57379(4DVD) |
ベートーヴェン:交響曲全集 交響曲第1番ハ長調 作品21 交響曲第2番ニ長調 作品36 交響曲第3番変ホ長調 作品55「英雄」 交響曲第4番変ロ長調 作品60 交響曲第5番ハ短調 作品67「運命」 交響曲第6番ヘ長調 作品68「田園」 交響曲第7番イ長調 作品92 交響曲第8番ヘ長調 作品93 交響曲第9番ニ短調 作品125「合唱」 ●ボーナス映像 「インタビュー:クラウディオ・アバド、ベートーヴェンについて語る」(26分) |
クラウディオ・アバド(指)BPO 収録:2001年2月 ローマ,サンタ・チェチーリア音楽院、2000年5月1日 ベルリン,フィルハーモニーザール(第9番) ◆Bluray 画面:16:9、Full HD 音声:PCMステレオ、 DTS-HD MA5.1 リージョン:All BD25 字幕:英独仏伊西、413分 ◆DVD 画面:16:9、NTSC 音声:PCMステレオ、DTS5 リージョン:All DVD9 字幕:英独仏伊西、413分 |
|
||
| ONDINE ODE-1388 NX-B04 |
ターリヴァルディス・ケニンシュ(1919-2008):
交響曲集 交響曲第5番(1976) 交響曲第8番「シンフォニア・コンチェルタータ」(1986) - オルガンと管弦楽のための 弦楽のためのアリア(1984)(弦楽オーケストラ編) |
イヴェタ・アプカルナ(Org) ラトヴィア国立SO アンドリス・ポガ(指) 録音:2021年3月15-19日 |
|
||
| Capriccio C-8082(1CD) NX-B05 |
ブルックナー:交響曲第0番ニ短調「Die Nullte」 WAB100 ノーヴァク版 | リンツ・ブルックナーO マルクス・ポシュナー(指) 録音:2021年2月22-24日リンツ・ミュージックシアター、リハーサル・ホール(オーストリア) |
|
||
| ALPHA ALPHA-784(1CD) |
ペルゴレージ:スターバト・マーテル(悲しみの聖母) ~1769年パリ版* ハイドン:交響曲第49番ヘ短調「受難」 Hob.I:49 (1768) |
ジョディ・デヴォス(S) アデル・シャルヴェ(Ms) フランス放送少年少女cho ル・コンセール・ド・ラ・ロージュ(古楽器使用) オーレリアン・ドラージュ(チェンバロ、オルガン) カミーユ・ドラフォルジュ(Org) ジュリアン・ショーヴァン(Vn、指揮) 録音:2021年4月 フランス放送オーディトリアム、パリ* カーン歌劇場、カーン(フランス北部バス=ノルマンディ地方) |
|
||
| Goodies 78CDR-3855(1CDR) |
ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 | ハンス・プフィツナー(指)BPO 仏 POLYDOR 66939/44 1929年ベルリン録音 |
|
||
| Goodies 78CDR-3856(1CDR) |
ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」 交響曲第8番ヘ長調作品93 - 第2楽章* |
ハンス・プフィツナー(指) ベルリン新SO、BPO* 独GRAMOPHONE 69642/7 1923年12月ベルリン録音 |
|
||
 OTTO KLEMPERER FILM FOUNDATION 24-1121(5Bluray) 日本限定盤 数量限定盤 |
ベートーヴェン:交響曲全集 ) ■BD1 交響曲第1番ハ長調Op.21 交響曲第3番変ホ長調Op.55「英雄」 ■BD2 交響曲第4番変ロ長調Op.60 交響曲第5番ハ短調Op.67「運命」 ■BD3 交響曲第2番ニ長調Op.36 交響曲第6番ヘ長調Op.68「田園」 ■BD4 交響曲第8番ヘ長調Op.93 交響曲第7番イ長調Op.92 ■BD5 交響曲第9番ニ短調Op.125「合唱つき」 ◎ボーナス・オーディオ オットー・クレンペラーについて/ガレス・モリスによる回想録(インタビューアー:ジョン・トランスキー) |
オットー・クレンペラー(指) ニュー・フィルハーモニアO ■BD1 収録:1970年5月26日 放映(BBC TV):1970年6月19日(第1番)、6月21日(第2番) ■BD2 収録:1970年6月2日 放映(BBC TV):1970年6月26日 ■BD3 収録:1970年6月9日 放映(BBC TV):1970年6月19日(第2番)、6月28日(第6番) ■BD4 収録:1970年6月21日 放映(BBC TV):1970年7月3日 ■BD5 テレサ・ツィリス=ガラ(S)、ジャネット・ベイカー(Ms)、ジョージ・シャーリー(T) テオ・アダム(Br)、ニュー・フィルハーモニアcho 収録:1970年6月30日 放映(BBC TV):1970年7月5日 全て、ロンドン、ロイヤル・フェスティヴァル・ホール 音声:PCM Mono 画面:4:3 、リージョン:0 50GB ドイツ語(第9のみ)、404'44 mins |
|
||
 Treasures TRE-263(1CDR) |
超厳選!赤盤名演集Vol.6 シューベルト:「ロザムンデ」~序曲/間奏曲第3番/バレエ音楽第2番 マーラー:交響曲第1番「巨人」* |
パウル・クレツキ(指) ロイヤルPO、VPO* 録音:1958年10月27&29日、1961年11月13-15日*(全てステレオ) ※音源:東芝 ASC-5003、AA-7302* ◎収録時間:75:51 |
| “ユダヤ的情念を湛えつつ決してべとつかないクレツキ特有の美意識!” | ||
|
||
| ポマト・プロ POMA-1001(1CD) 税込定価 |
ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 | 浮ヶ谷孝夫(指揮) ブランデンブルグ国立Oフランクフルト 録音:2018 年2 月27-28 日カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ・ホール |
|
||
| Altus ALT-490(1CD) |
スメターチェクの芸術 第4集 ショスタコーヴィチ:交響曲第3番「メーデー」 プロコフィエフ:交響曲第7番「青春」* |
ヴァーツラフ・スメターチェク(指) プラハRSO、プラハ放送cho(チェコ語歌唱) チェコPO* 録音:1974年9月、1970年6月*(ともにステレオ) |
|
||
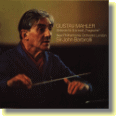 Treasures TRE-252(2CDR) ★ |
マーラー:交響曲第6番「悲劇的」 | ジョン・バルビローリ(指) ニュー・フィルハーモニアO 録音:1967年8月17-19日 ※音源:独ELECTROLA 1C161-01.285 ◎収録時間:83:34 |
| “バルビローリの南欧的感覚によって作品が壮大な愛の讃歌に変貌! | ||
|
||
 Treasures TRE-075r(1CDR) |
ライトナー~モーツァルト:交響曲集 モーツァルト:バレエ音楽「レ・プティ・リアン」序曲+ 交響曲第31番「パリ」K.297* 交響曲第36番「リンツ」K.425# 交響曲第39番変ホ長調K.543 |
フェルディナント・ライトナー(指) バイエルンRSO*,#、バンベルクSO 録音:1959年4月13日+、1959年4月12-13日*、1959年4月11-12日#、1962年11月(全てステレオ) ※音源:独ORBIS HI-FI-73-491+,*,#、独PARNASS 61414 ◎収録時間:74:22 |
| “策を弄せず、作品の底力を信じきるライトナー度量!” | ||
|
||
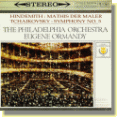 Treasures TRT-017(1CD) |
オーマンディ/「画家マチス」&チャイ5(1959) ヒンデミット:交響曲「画家マチス」 チャイコフスキー:交響曲第5番* |
ユージン・オーマンディ(指) フィラデルフィアO 録音:1962年1月17日、1959年1月25日*(共にステレオ) ※音源:独CBS 61347、COLUMBIA MS-6109* ◎収録時間:74:46 |
| “何度も味わいたい「画家マチス」の温かみに満ちた響き!” | ||
|
||
 OTTO KLEMPERER FILM FOUNDATION KKC-4258(24SACD) |
クレンペラー&コンセルトヘボウ管・録音集 ■Disc1 メンデルスゾーン:序曲「フィンガルの洞窟」 Op. 26 マーラー:.さすらう若人の歌 ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」(1886年版ノヴァーク) ■Disc2 ベートーヴェン:交響曲第8番ヘ長調Op.93 モーツァルト:交響曲第25番ト短調K183* ヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」* ■Disc3 ヤナーチェク:シンフォニエッタOp.60 バルトーク:ヴィオラ協奏曲 ヘンケマンス:.フルート協奏曲* ファリャ:スペインの庭の夜** ■Disc 4 ベートーヴェン:演奏会用アリア「ああ、不実な人よ!」Op.65 交響曲第7番イ長調Op.92 ■Disc5 1951年7月12日(初CDコンサート全収録) モーツァルト:フリーメーソンのための葬送曲 ハ短調 K.477 マーラー:亡き子をしのぶ歌 ■Disc6 マーラー:交響曲第2番「復活」 ■Disc 7 ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」 シェーンベルク:浄夜(1917/1943) ヒンデミット:組曲「気高い幻想」 ■Disc9 メンデルスゾーン:劇付随音楽「真夏の夜の夢」 ■Disc10 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 モーツァルト:セレナード第13番「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」* ■Disc11 モーツァルト:モテット「エクスルターテ・ユビラーテ」K165(158a) マーラー:.交響曲第4番ト長調 ■Disc 12 ベートーヴェン:「プロメテウスの創造物」~.第1曲:序曲/第5曲:アダージョ/終曲:アレグレット ピアノ協奏曲 第3番ハ短調Op.37 ■Disc 13 ベートーヴェン:交響曲第2番ニ長調Op.36 「レオノーレ」第3番序曲Op.72b ■Disc14 ベートーヴェン:交響曲第4番 交響曲第5番「運命」 ■Disc15 ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」 ■Disc16 ベートーヴェン:交響曲第7番イ長調Op.92 交響曲第8番ヘ長調Op.93* ■Disc17 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 ■Disc 18 モーツァルト:交響曲第29番イ長調K201 ピアノ協奏曲第22番変ホ長調K482 ■Disc 19 モーツァルト:オーボエ協奏曲ハ長調K314 交響曲第41番「ジュピター」 ■Disc 20 バッハ:管弦楽組曲第2番 カンタータ第202番「消えよ、悲しみの影」BWV202(結婚カンタータ) モーツァルト:演奏会用アリア「心配しなくともいいのです、愛する人よ」.K505 ■Disc 21 ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 R.シュトラウス:交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」 ●ボーナス・トラック/初正規盤 モーツァルト:「ドン・ジョヴァンニ」序曲* メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調* ■Disc22 メンデルスゾーン:序曲「フィンガルの洞窟」 ストラヴィンスキー:三楽章の交響曲 シューベルト:交響曲第4番ハ短調D417 ワーグナー:「.ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕前奏曲 ■Disc 23 ベートーヴェン:ミサ・ソレニムス ■Disc 24 グルック:シャコンヌ~「オルフェオとエウリディーチェ」 クレンペラー:交響曲第1番(全2楽章) ブルックナー:交響曲第6番イ長調WAB106(1890年ハース版) |
オットー・クレンペラー(指) コンセルトヘボウO ■Disc1 録音:1947年12月4日(初CDコンサート全収録) ヘルマン・シャイ(Br) ■Disc2 録音:1949年5月1日&1951年1月18日* ヤン・ブレッセル(Vn) ■Disc3 録音:1951年1月11日、1951年1月13日*、1951年3月29日** ウィリアム・プリムローズ(Va)、フーベルト・バルワーザー(Fl)、ヴィレム・アンドリーセン(P) ■Disc 4 録音:1951年4月2日(1951年ベートーヴェン・チクルスより) グレ・ブロウエンスティーン(S) ■Disc5 録音:1951年7月12日(初CDコンサート全収録) キャスリーン・フェリアー(C.A) ■Disc6 ヨー・フィンセント(S)、キャスリーン・フェリアー(C.A)、トゥーンクンストcho ) ■Disc 7&8 録音:1955年7月7日(初CDコンサート全収録) ■Disc9 録音:1955年11月3日(正規盤初) コリー・ヴァン・ベックム(S)、ヘレーン・ヴァークレイ(S)、トゥーンクンストchoメンバー ■Disc10 録音:1955年11月6日、1955年11月10日*(初CDコンサート全収録) ■Disc11 録音:1955年11月10日(Disc10の続き) マリア・シュターダー(S) ■Disc 12 録音:1956年5月2日(ベートーヴェン・チクルス~初CDコンサート全収録) ヤン・ヴィッサー(Fl)、クラース・デ・ロック(Cl)、トム・デ・クラーク(Fg)、フィア・ローザ・ベルクハウト(Hp) アニー・フィッシャー(P) ■Disc 13 録音:1956年5月2日(Disc 12の続き) ■Disc14 録音:1956年5月9日(ベートーヴェン・チクルス) ■Disc15 録音:1956年5月13日(ベートーヴェン・チクルス~初CDコンサート全収録) ■Disc16 1956年5月13日(Disc15の続き)、1956年5月17日* ■Disc17 録音:1956年5月17日(Disc16の続き)(ベートーヴェン・チクルス) グレ・ブロウエンスティーン(S)、アニー・ヘルメス(C.A)、エルンスト・ヘフリガー(T)、ハンス・ウィルブリンク(Br) 、トゥーンクンストcho ■Disc 18 録音:1956年7月12日(初CDコンサート全収録) アニー・フィッシャー(P) ■Disc 19 録音:1956年7月12日(Disc18の続き) ホーコン・ストーティン(Ob) ■Disc 20 録音:1957年2月7日(初CDコンサート全収録) フーベルト・バルワーザー(Fl) エリーザベト・シュヴァルツコップ(S)、ヤン・ダーメン(Vn)、ホーコン・ストーティン(Ob) エリーザベト・シュヴァルツコップ(S)、マリア・クルチオ(P) ■Disc 21 録音:1957年2月7日(Disc 20の続き) 1954年6月26日* ヨハンナ・マルツィ(Vn)*、ハーグ・レジデンティO* ■Disc22 録音:1957年2月21日(初CDコンサート全収録) ■Disc 23 録音:1957年5月19日(初正規盤) エリーザベト・シュヴァルツコップ(S)、ナン・メリマン(Ms)、ヨーゼフ・シマンディ(T)、ハインツ・レーフス(Bs-Br)、アムステルダム・トーンクンストcho ■Disc 24 録音:1961年6月22日(初CDコンサート全収録) |
|
||
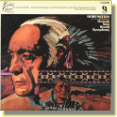 Treasures TRE-250(1CDR) |
ホーレンシュタインの「新世界」 コルンゴルト:歌劇「ヴィオランタ」前奏曲と謝肉祭* ワーグナー:「さまよえるオランダ人」序曲+ 「タンホイザー」~ヴェーヌスベルクの音楽# ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」## |
ヤッシャ・ホーレンシュタイン(指) ロイヤルPO ビーチャム・コラール・ソサエティ** 録音:1965年5月28日&6月2日*、1962年9月30日+,#、1962年1月26&30日##(全てステレオ) ※音源:Quintessence PMC-7047*,+、日Victor GMS-6#、Quintessence PMC-7047## ◎収録時間:73:27 |
| “ビーチャムのオケが豹変!郷愁よりも苦悩が滲む異色の「新世界」!” | ||
|
||
| BSOrec BSOREC-0001 |
マーラー:交響曲第7番「夜の歌」 | キリル・ペトレンコ(指) バイエルン国立O 録音:2018年5月28日&29日 ミュンヘン、バイエルン国立歌劇場(ライヴ) |
|
||
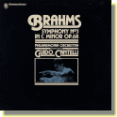 Treasures TRT-237(1CDR) |
カンテルリ~シューマン&ブラームス シューマン:交響曲第4番 ブラームス:交響曲第1番* |
グィド・カンテルリ(指) フィルハーモニアO 録音:1953年5月5月15&21日、1953年5月21-23日* (共にモノラル) ※音源:仏EMI 2905761、W.R.C SH-314* ◎収録時間:68:48 |
| “厳つい鎧を剥ぎ取り、音楽の実像を清らかな感性で刷新!” | ||
|
||
| ベートーヴェン没後250年記念復刻 | ||
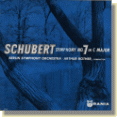 Treasures TRE-241(1CDR) |
ベートーヴェン:交響曲第1番ハ長調Op.21 シューベルト:交響曲第9番「グレート」* |
アルトゥール・ローター(指) BPO、ベルリンRSO* 録音:1951年12月6日ティタニア・パラスト、1950年代中期?(共にモノラル) ※音源:Club Mondial Du Disque CMD-A302、URANIA URLP-7152* ◎収録時間:71:04 |
| “BPOの一時代を支えたローターの恐るべき洞察力!” | ||
|
||
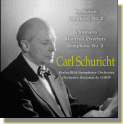 Treasures TRE-242(1CDR) |
ベートーヴェン:交響曲第2番 シューマン:「マンフレッド」序曲* 交響曲第2番ハ長調Op.61# |
カール・シューリヒト(指) ベルリンRIAS響、 フランス国立放送O 録音:1953年11月19日ベルリン、1963年5月14日シャンゼリゼ劇場(ライヴ)、1955年9月(モントルー音楽祭ライヴ)# ※音源:MOVIMENT MUSICA 08-001、ERATO ERL-16009*,# ◎収録時間:78:58 |
| “モーツァルト寄りの解釈でじっくり紡ぎ出すベートーヴェン!” | ||
|
||
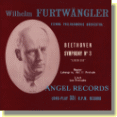 Treasures TRE-243(1CDR) |
超厳選!赤盤名演集Vol.4~フルトヴェングラーの「エロイカ」 ワーグナー:歌劇「ローエングリン」第1幕前奏曲* リスト:交響詩「前奏曲」# ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 |
ウィルヘルム・フルトヴェングラー(指) VPO 録音:1954年3月4日*、1954年3月3日#、1952年11月26,27日ウィーン・ムジークフェラインザール(全てモノラル) ※音源:日TOSHIBA HA-50609*,#、AB-7081 ◎収録時間:77:10 |
| “歴史的名演の真価を最大限まで堪能できる理想の復刻!” | ||
|
||
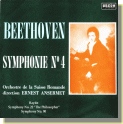 Treasures TRE-244(1CDR) |
ハイドン:交響曲第22番変ホ長調 「哲学者」 Hob.I:22
交響曲第90番ハ長調 Hob.I:90 ベートーヴェン:交響曲第4番* |
エルネスト・アンセルメ(指) スイス・ロマンドO 録音:1965年10月、1958年11月* ※音源:LONDON CS-6481、豪DECCA SDDA-104* ◎収録時間:79:18 |
| “作品への誠実な愛を成就すべくクールな姿勢を堅持” | ||
|
||
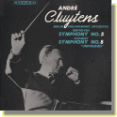 Treasures TRE-245(1CDR) |
超厳選!赤盤名演集Vol.5~クリュイタンスの「運命」&「未完成」 ベートーヴェン:序曲「レオノーレ」第3番 シューベルト:交響曲第8番「未完成」* ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」# |
アンドレ・クリュイタンス(指)BPO 録音:1958年3月10&13日、1960年11月* 、1958年3月10-11&13日# ベルリン・グリューネヴァルト教会 (全てステレオ) ※音源:日TOSHIBA AA-7025、AA-7040*,# ◎収録時間:73:42 |
| “古き佳きBPOの響きを更に美しくブレンドした味わい深いベートーヴェン!!” | ||
|
||
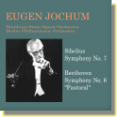 Treasures TRE-246(1CDR) |
ヨッフムのベートーヴェン&シベリウス シベリウス:交響曲第7番 ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」* |
オイゲン・ヨッフム(指) ハンブルク国立歌劇場O、BPO* 録音:1943年(ライヴ?)、1951年3月19日RIASスタジオ* ※音源:Melodiya M10-46747-009、MOVIMENT MUSICA 08-001* ◎収録時間:63:41 |
| “フルトヴェングラーへの尊敬と独自のこだわりを完全一体化した異色の「田園」!” | ||
|
||
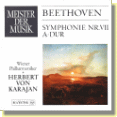 Treasures TRE-247(1CDR) |
ベートーヴェン:交響曲第7番* J・シュトラウス:「こうもり」序曲 アンネン・ポルカ ヨーゼフ・シュトラウス:ワルツ「うわごと」 J・シュトラウス:「ジプシー男爵」序曲 ポルカ「狩り」 ワルツ「ウィーンの森の物語」 |
ヘルベルト・フォン・カラヤン(指) VPO 録音:1959年3月9 - 10日*、1959年4月7-8日(全てステレオ) ※音源:独RCA SMR-8010*、SMR-8012 ◎収録時間:77:36 |
| “作品の生命感とカラヤンの美学がバランスよく共存した名演!” | ||
|
||
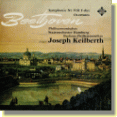 Treasures TRE-248(1CDR) |
メンデルスゾーン:序曲「静かな海と楽しい航海」* 序曲「フィンガルの洞窟」* ベートーヴェン:「エグモント」序曲** 「アテネの廃墟」#~序曲/トルコ行進曲 交響曲第8番ヘ長調 Op. 93+ |
ヨーゼフ・カイルベルト(指) BPO*,**、ハンブルク国立PO 録音:1962年2月9日*、1960年4月11日-5月1日**、1960年4月26日#、1958年2月6-10日+(全てステレオ) ※音源:独TELEFUNKEN SNA-25016*、NT-361#、SNA-25016-T-2**,+ ◎収録時間:64:12 |
| “これぞ「ベト8」演奏史上に輝く偉大なスタンダード解釈!” | ||
|
||
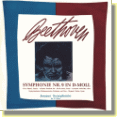 Treasures TRE-249(2CDR) ★ |
ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱つき」* フリードリヒ・ヴィット (1770-1836):イエナ交響曲.ハ長調 |
コリー・ベイステル(S) エリザベス・プリッチャード(C.A) デイヴィッド・ガレン(T) レオナルド・ヴォロフスキ(Bs) ワルター・ゲール(指) ネーデルラントPO&cho 録音:1955年*、1952年(共にモノラル) ※音源:Musical Masterpiece Society MMS-2034*、 MMS-2034F ◎収録時間:67:11*+21:18 |
| “伝統的な演奏スタイルを洗い流すことで顕在化した希望の光!” | ||
|
||
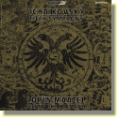 Treasures TRT-016(1CDR) |
R・シュトラウス:交響詩「ドン・ファン」 チャイコフスキー:交響曲第5番* |
ロリン・マゼール(指)VPO 録音:1964年5月4-6日、1963年9月13-14&6-18,20日* (全てステレオ) ※音源:LONDON CS-6376、CS-6376* ◎収録時間:61:48 |
| “ウィーン・フィルの伝統美とマゼールの才気が融合したスパイシーな名演!”” | ||
|
||
| Musicaphon M-56915(1CD) |
マーラー:交響曲第2番ハ短調「復活」(ヘルマン・ベーンによる2台ピアノ版)(1895) | クリスティアーネ・ベーン(P)、マティアス・ウェーバー(P)、ダニエラ・ベヒリー(S)、イリス・フェルミリオン(A)、 クラウス・バンツァー(指)、 ハルヴェステフーデ室内cho 録音(ライヴ):2008年11月、ライスハレ小ホール(ドイツ、ハンブルク) |
|
||
| Musicaphon M-56974(1CD) |
マーラー:交響曲第4番ト長調 (エルヴィン・シュタインによる室内楽版)(1921) |
イザベル・ソコヤ (Ms)、 ダニエル・カフカ(指)、 アンサンブル・オルケストラル・コンタンポラン 録音:2014年12月5日-6日、シャトー・ド・ブテオン(フランス) |
|
||
| MUSICAPHON M-56936(1SACD) |
ブラームスVol.1~後期ロマン主義 ブラームス:交響曲第1番ハ短調 Op.68 R.シュトラウス:死と変容 Op.24 |
ロマン・ブログリ=ザッヒャー(指)、 リューベックPO 録音:2010年9月&2012年6月 |
|
||
| MUSICAPHON M-56947(1SACD) |
ブラームスVol.2~哀愁を帯びたスイス ブラームス:交響曲第2番ニ長調 Op.73 シェック:ヴァイオリン協奏曲変ロ長調「幻想曲風」Op.21(幻想曲風協奏曲) |
ロマン・ブログリ=ザッヒャー(指)、 リューベックPO、カルロス・ジョンソン(Vn) 録音:2011年1月 |
|
||
| MUSICAPHON M-56950(1SACD) |
ブラームスVol.3~交響的な古典主義 ブラームス:交響曲第3番ヘ長調 Op.90 モーツァルト:協奏交響曲変ホ長調 KV.364 |
ロマン・ブログリ=ザッヒャー(指)、 リューベックPO、マユミ・ザイラー(Vn)、 ナオミ・ザイラー(Va) 録音:2012年6月 |
|
||
| MUSICAPHON M-56954(1SACD) |
ブラームスVol.4~ヴィルトゥオーゾ・モダニティ ブラームス:交響曲第4番ホ短調 Op.98 ツィンマーマン:トランペット協奏曲「誰も知らない私の悩み」 |
ロマン・ブログリ=ザッヒャー(指)、 リューベックPO、 ラインホルト・フリードリヒ(Tp) 録音:2012年6月 |
|
||
| MUSICAPHON M-56942(2SACD) ★ |
オネゲル:交響曲全集 交響曲第1番/交響曲第2番* 交響曲第3番「典礼風」 交響曲第4番「バーゼルの喜び」 交響曲第5番「3つのレ」 |
ロマン・ブログリ=ザッヒャー(指)、 リューベックPO、グィド・セゲレス(Tp)* 録音:2008年-2010年 |
|
||
| FUGA LIBERA FUG-764(1CD) |
ヘンドリク・アンドリーセン(1892-1981):苦痛の鏡 ベルリオーズ:幻想交響曲 |
クリスティアンネ・ストーテイン (Ms) ドミトリー・リス(指) 南オランダPO 録音:2017年10月27、28日/2019年4月5、6日 アイントホーフェン音楽堂、フライトホフ劇場(マーストホフ) ライヴ・拍手入り |
|
||
| Velut Luna CVLD-304(1CD) |
マーラー:交響曲第1番「巨人」 | パドヴァ・C・ポッリーニ音楽院SO ジュリアーノ・メデオッシ(指) 録音:2018年3月25日、ライヴ。アウディトリウム・ポッリーニ、パドヴァ、イタリア |
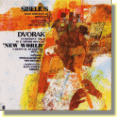 Treasures TRE-221(1CDR) |
A・ギブソン~シベリウス&ドヴォルザーク シベリウス:組曲「クリスティアン2世」 ドヴォルザーク:序曲「謝肉祭」* 交響曲第9番「新世界より」* |
アレクサンダー・ギブソン(指) スコティッシュ・ナショナルO、LPO* 録音:1966年頃、1967年1月27-28日* ※音源:英HMV HQS-1070、World Record Club ST-650* ◎収録時間:72:32 |
| “「ケレン味のなさ」が凡庸と同義ではないことを実証する恰好の名演!” | ||
|
||
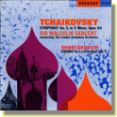 Treasures TRT-015(1CDR) |
サージェント/ショスタコーヴィチ&チャイコフスキー ショスタコーヴィチ:交響曲第9番 チャイコフスキー:交響曲第5番* |
マルコム・サージェント(指)LSO 録音:1959年10月27年、1959年5月20日&6月3日*(共にステレオ) ※音源:米EVEREST_SDBR-3054、日Victor_SRANK-5507* ◎収録時間:71:06 |
|
||
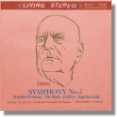 Treasures TRE-219(1CDR) |
A・ギブソン~若き日のシベリウス録音 「カレリア」序曲/交響詩「吟遊詩人」 組曲「歴史的情景」~「祭り」 カレリア組曲* 交響曲第5番変ホ長調Op.82* |
アレクサンダー・ギブソン(指) スコティッシュ・ナショナルO、LSO* 録音:1966年頃、1959年2月9-10日*(全てステレオ) ※音源:英HMV:HQS-1070、英RCA VICS-1016* ◎収録時間:66:00 |
| “自然体の音作りに孕む瑞々しい感性と熱情!” | ||
|
||
 WEITBLICK SSS-0241(1CD) |
ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 | エフゲニ・スヴェトラーノフ(指) エーテボリSO 録音:1992年9月17日エーテボリ・コンサートホール,ライヴ |
| "最晩年の一歩手前で成し遂げた理想のブルックナー" | ||
|
||
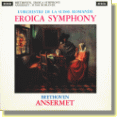 Treasures TRE-207(1CDR) |
アンセルメ~ベートーヴェン厳選名演集Vol.2 ベートーヴェン:序曲「レオノーレ」第2番 交響曲第3番「英雄」* |
エルネスト・アンセルメ(指) スイス・ロマンドO 録音:1960年1月4-17日、1960年4月5-11日*(全てステレオ) ※音源:米LONDON_CS-6184、英DECCA SDD-103* ◎収録時間:62:07 |
| “理性よりも衝動!全身全霊でベートーヴェンの声を代弁!! | ||
|
||
 Treasures TRE-213(1CDR) |
ラインスドルフ/モーツァルト:交響曲集 交響曲第36番「リンツ」 交響曲第41番「ジュピター」* |
エーリヒ・ラインスドルフ(指) ボストンSO 録音:1967年12月22日、1963年1月6日*(ステレオ) ※音源:英RCA CCV-5050、日VICTOR SHP-2307* ◎収録時間:73:33 |
| “音楽における「豊かさ」とは何か?その答えがここに!” | ||
|
||
 NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA NSO-0001(1SACD) |
コープランド:バレエ音楽『ビリー・ザ・キッド』 ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」 |
ジャナンドレア・ノセダ(指) ワシントン・ナショナルSO 録音:2019年6月、J.F.ケネディ・センター・フォー・ザ・パフィーミング・アーツ・コンサート・ホール(ライヴ) |
|
||
 Treasures TRE-209(1CDR) |
クリップス~ベートーヴェン&ブラームス ベートーヴェン:「フィデリオ」序曲 「エグモント」序曲 序曲「献堂式」 ブラームス:交響曲第1番* |
ヨーゼフ・クリップス(指) ウィーン音楽祭O 録音:1962年6月4-5日(ステレオ) ※音源:日Consert Hall SMS-2274、瑞西Consert Hall SMS-2268* ◎収録時間:73:33 |
| “味わい充満!クリップスの意思とオケの意欲が完全調和!” | ||
|
||
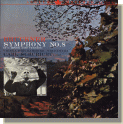 Treasures TRE-208(1CDR) |
超厳選!赤盤名演集Vol.1 ブルックナー:交響曲第8番 |
カール・シューリヒト(指)VPO 録音:1963年12月(ステレオ) ※音源:TOSHIBA AA-7191-92 ◎収録時間:70:48 |
| “芸の極地を極めた人間の手になる壮大なる工芸品!!” | ||
|
||
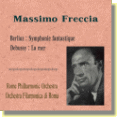 Treasures TRE-206(1CDR) |
フレッチャ~海&幻想交響曲 ドビュッシー:交響詩「海」 ベルリオーズ:幻想交響曲* |
マッシモ・フレッチャ(指) ローマPO、ロイヤルPO* 録音:1959年頃、1962年2月21-22日*(共にステレオ) ※音源:米Reader's Digest RD4-68-7、米CHRSKY_CR-1* ◎収録時間:69:34 |
| “作品を歪めずに自己表現の限りを尽くすフレッチャの芸術家魂!” | ||
|
||
| Caprice CAP-22069 (4CD+BOOK) |
コレクターズ・クラシックス Vol.16~ヴィルヘルム・ステーンハンマル(1871-1927)の遺産 ■Disc1 交響曲第2番ト短調 Op.34-第1楽章「アレグロ・エネルジーコ」、第2楽章「アンダンテ」、第4楽章「終曲」 ■Disc2 (1)交響曲第2番ト短調 Op.34-第1楽章「アレグロ・エネルジーコ」 (2)交響的カンタータ「歌(Sangen)」 Op.44 - 間奏曲(Mellanspel) (3)交響曲第1番ヘ長調 ■Disc3 (1)セレナード(Serenad) ヘ長調 Op.31(管弦楽のための) (2)交響曲第2番ト短調 Op.34 ■Disc4 (1)ピアノ協奏曲第2番ニ短調 Op.23 (2)劇音楽「ロドレッツィは歌う(Lodolezzi sjunger)」 組曲 Op.39 - エレジー(Elegy) (3)交響曲第2番ト短調 Op.34 |
■Disc1 録音:1959年2月23日(リハーサル録音) テープ録音:SR(スウェーデン放送) Ma 59/204:2 ■Disc2 (1)録音:1959年2月25日(総練習録音) テープ録音:SR(スウェーデン放送) Ma 59/204:2 (2)録音:1943年3月4日(レコード録音) ラジオ放送:RA 118(matriser Rtj 886/87) (3)録音:1949年9月25日(公開収録) ラジオ放送:SR LB+ 10.924(ラッカー盤からの復刻) ■Disc3 (1)録音:1938年1月14日(公開収録) ラジオ放送:R 7(未発表)(matriser 142-153) (2)録音:1941年3月13日(公開収録) スチールテープ録音:ラッカー盤(L-B 4.790)に復刻(1943年11月5日) スウェーデン・ラジオRSO(王立ストックホルム・フィルハーモニックO) トゥール・マン(指) エルンスト・トーンクヴィスト(Vn)(「セレナード」第2楽章) 録音場所:ストックホルム・コンサートホール 大ホール(ストックホルム) ■Disc4 (1)録音:1945年12月10日、11日(レコード録音) ラジオ放送:RE 701-04(Matris Rtj 1313-20 A)(78回転レコード) (2)録音:1948年11月15日(レコード録音) ラジオ放送:RE 709(matris Rtj 2904 A)(78回転レコード) (3)録音:1947年12月17日(レコード録音) ラジオ放送:RE 709-14(matris Rtj 2314-24 A)(78回転レコード) ヨーテボリ放送O(ヨーテボリSO) シクステン・エケルベリ(指) ハンス・レイグラーフ(P)(協奏曲) 録音場所:ヨーテボリ・コンサートホール 大ホール(ヨーテボリ) |
|
||
 OTTO KLEMPERER FILM FOUNDATION KKC-9476(5Bluray) |
ベートーヴェン:交響曲全集 ■BD1 交響曲第1番ハ長調Op.21 交響曲第3番変ホ長調Op.55「英雄」 ■BD2 交響曲第4番変ロ長調Op.60 交響曲第5番ハ短調Op.67「運命」 ■BD3 交響曲第2番ニ長調Op.36 交響曲第6番ヘ長調Op.68「田園」 ■BD4 交響曲第8番ヘ長調Op.93 交響曲第7番イ長調Op.92 ■BD5 交響曲第9番「合唱つき」 [ボーナス・オーディオ] オットー・クレンペラーについて/ガレス・モリスによる回想録(インタビューアー:ジョン・トランスキー) |
オットー・クレンペラー(指) ニュー・フィルハーモニアO ■BD1 収録:1970年5月26日 放映(BBC TV):1970年6月19日(第1番)、6月21日(第2番) ■BD2 収録:1970年6月2日 放映(BBC TV):1970年6月26日 ■BD3 収録:1970年6月9日 放映(BBC TV):1970年6月19日(第2番)、6月28日(第6番) ■BD4 収録:1970年6月21日 放映(BBC TV):1970年7月3日 ■BD5 テレサ・ツィリス=ガラ(S) ジャネット・ベイカー(Ms) ジョージ・シャーリー(T) テオ・アダム(Br) ニュー・フィルハーモニアcho 収録:1970年6月30日 放映(BBC TV):1970年7月5日 収録:1970年5、6月、ロンドン、ロイヤル・フェスティヴァル・ホール 音声:PCM MONO リージョン:0 直輸入盤・日本語解説書付 |
|
||
 Treasures TRE-205(1CDR) |
ラインスドルフ/シューマン:交響曲第4番.他 モーツァルト:アイネ・クライネ・ナハトムジーク* ベートーヴェン:序曲「レオノーレ」第3番 シューマン:交響曲第4番(マーラー編) |
エーリヒ・ラインスドルフ(指) ボストンSO 録音:1963年1月6日*、1963年1月5-6日(全てステレオ) ※音源:日VICTOR SHP-2307*、英RCA SB-6582 ◎収録時間:63:04 |
| “ラインスドルフの驚異の耳が制御する作品のあるべき姿!” | ||
|
||
 SILKROAD MUSIC SRM-045SACD (2SACD) |
マーラー:交響曲第3番ニ短調 | ヤッシャ・ホーレンシュタイン(指) LSO ノルマ・プロクター(C.A) アンブロジアン・シンガーズ、 ワンズワース・スクール少年cho ウィリアム・ラング(フリューゲルホルン)、デニス・ウィック(Tb) 録音:1970年7月27-29日/クロイドン(ロンドン) |
|
||
| Caprice CAP-21920 (3CD+Book) ★ |
コレクターズ・クラシックス Vol.15~作曲者の指揮で ■Disc 1 クット・アッテルベリ(1887-1974) 自作を指揮する (1)交響曲第6番ハ長調 Op.31「ドル交響曲(Dollarsymfonin)」 (2)ホルン協奏曲 イ短調 Op.28 - 第2楽章 アダージョ (3)バレエ「愚かなおとめたち(De favitska jungfrurna)」 Op.17(抜粋) (4)交響曲第4番ト短調 Op.14 「シンフォニア・ピッコラ(Sinfonia Piccola)」 - 第1楽章 コン・フォルツァ (5)ピアノ協奏曲 変ロ長調 Op.37 - 第1楽章 ペザンテ・アレグロ (6)組曲第8番「古風な様式の田園組曲」 Op.34 より(第1曲 前奏曲、第2曲 アリア、第5曲 セレナータ、第6曲 ジグ) (7)ヴェルムランド・ラプソディ(En Varmlandsrapsodi) Op.36 (8)バラードとパッサカリア(Ballad och passacaglia) Op.38 ■Disc 2 ラーシュ=エーリク・ラーション(1908-1983) 自作を指揮する (1)ラジオ番組『Dagens stunder(今日の時間)』(「田園組曲」 Op.19) (2)冬物語(En vintersaga)Op.18(4つのヴィニェット) (3)オスティナート Op.17(交響曲第2番終楽章) (4)赤い十字架(Det roda korset) Op.30 [放送未使用作品] ■Disc 3 イングヴァル・リードホルム(1921-2017) 自作を指揮する(オレブルー、ノルショーピング最終コンサート) (1)ラウディ(Laudi)(1947)(混声合唱のための) (2)カント LXXXI(1956)(混声合唱のための)(エズラ・パウンド 詩) (3)ムタンザ(Mutanza)(1959) (4)孤独なナウシカー(Nausikaa ensam)(1963) (5)ハインリヒ・イザークの『インスブルックよ、さようなら』(Heinrich Isaak: Innsbruck, ich muss dich lassen) (6)旧世界からの挨拶(Greetings from an Old World)(1976) |
■Disc 1 (1)BPO、クット・アッテルベリ(指) 録音:1928年10月18日 ベルリン音楽大学 大ホール(シャルロッテンブルク、ドイツ) Polydor/DG 95193-95 (2)アクセル・マルム(Hrn)、ヒルディング・ルーセンベリ(オブリガート・ピアノ)、スウェーデン放送局第一放送O、クット・アッテルベリ(指) 録音:1928年6月 スウェーデン放送第2スタジオ(ストックホルム) Columbia 13603 & 13602 (3)スウェーデン放送局第一放送O クット・アッテルベリ(指) 録音:1928年6月 スウェーデン放送第2スタジオ(ストックホルム) Columbia 13603 & 13602 (4)スウェーデン放送局第一放送O クット・アッテルベリ(指) 録音:1934年5月4日 ストックホルム・コンサートホール 小ホール(ストックホルム)(ヨーロッパコンサート) SR Programarkivet LB 456 (5)オーロフ・ヴィーベリ(P)、 スウェーデン放送局第一放送O、クット・アッテルベリ(指) 録音:1935年1月4日 ストックホルム・コンサートホール 小ホール(ストックホルム)(放送サービス10周年記念) SR Programarkivet LB 715 (6)室内O(王立ストックホルム・フィルハーモニックO員18名)、クット・アッテルベリ(指) 録音:1937年10月21日 ストックホルム・コンサートホール アティックホール(ストックホルム) HMV X 4946-47 (7)スウェーデンRSO、クット・アッテルベリ(指) 録音:1948年4月23日 王立音楽アカデミー 講堂(ストックホルム) Cupol 4119 (8)スウェーデンRSO、クット・アッテルベリ(指) 録音:1950年8月21日、9月9日 王立音楽アカデミー 講堂(ストックホルム) HMV DB 11034-35 ■Disc 2 (1)スウェーデン放送娯楽音楽オーケストラ(王立ストックホルム・フィルハーモニックO員37名)、ラーシュ=エーリク・ラーション(指)、グンナル・ショーベリ(朗読)、グン・ヴォールグレーン(朗読) 録音:1938年10月11日 ストックホルム(2)コンサートホール 小ホール(ストックホルム) SR Programarkivet L-B 2908 (2)スウェーデン放送娯楽音楽オーケストラ(王立ストックホルム・フィルハーモニックO員37名)、ラーシュ=エーリク・ラーション(指) 録音:1938年1月18日 ストックホルム・コンサートホール 小ホール(ストックホルム) SR Programarkivet L-B+2.295 (3)王立ストックホルム・フィルハーモニックO、ラーシュ=エーリク・ラーション(指) 録音:1948年6月7日 ストックホルム・コンサートホール 大ホール(ストックホルム) Cupol 6018 (4)ストックホルム放送O(王立ストックホルム・フィルハーモニックO員64名)、ラーシュ=エーリク・ラーション(指) 録音:1945年5月7日 ストックホルム・コンサートホール 小ホール(ストックホルム) SR Programarkivet LB 9.508 ■Disc 3 (1)スウェーデン放送cho、イングヴァル・リードホルム(指) 録音:1958年10月17日 王立音楽アカデミー 講堂(ストックホルム) SR Programarkivet Ma 58/11997 (2)室内cho、イングヴァル・リードホルム(指)録音:1961年3月10日 (おそらく)第2スタジオ(クングスガータン、ストックホルム) SR Programarkivet Ma 61/M/5180(SR RELP 5002) (3)オレブルーSO、イングヴァル・リードホルム(指)録音:1959年4月26日 オレブルー・コンサートホール(オレブルー、スウェーデン)(オレブルー管弦楽協会50周年記念コンサート) P2(1959年6月25日)放送 私的録音(エアチェック) (4)マッタ・シェーレ(S)、音楽同好会室内cho、ノルショーピングSO、イングヴァル・リードホルム(指) (5)イングヴァル・リードホルム(解説、ピアノ) (6)旧世界からの挨拶(Greetings from an Old World)(1976) マッツ・リードストレム(Vc)、ノルショーピングSO、イングヴァル・リードホルム(指) 録音:1983年6月9日 ノルショーピング講堂(ノルショーピング、スウェーデン)(ライヴ) ノルショーピング管弦楽協会私的録音(24.5.2018) ※Disc 1 に収録トラックの編集ミスがございます。交響曲第6番の第2楽章が、第1楽章(Track 1)の後ではなく、組曲第8番の「第1曲 前奏曲」(ブックレットは Track 8、実際は Track 7)の後、「第2曲 アリア」(Track 9)の前の「Track 8」に収録されています。予めご了承ください。 |
|
||
 Treasures TRE-203(1CDR) |
ワルター~ハイドン/モーツァルト/ドヴォルザーク モーツァルト:フリーメーソンのための葬送音楽 ハイドン:交響曲第100番「軍隊」* ドヴォルザーク:交響曲第8番# |
ブルーノ・ワルター(指) コロンビアSO 録音:1961年3月8日、1961年3月2&4日*、1961年2月8&12日#(全てステレオ) ※音源:日SONY 20AC-1805、日COLUMBIA OS-307*、OS-718-C# ◎収録時間:69:13 |
| “老練の至芸に宿る、青年のような瑞々しい感性” | ||
|
||
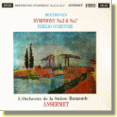 Treasures TRE-201(1CDR) |
アンセルメのベートーヴェンVol.1 ベートーヴェン:「フィデリオ」序曲 交響曲第2番*/交響曲第7番 |
エルネスト・アンセルメ(指) スイス・ロマンドO 録音:1960年1月(ステレオ) ※音源:LONDON CS-6183*、DECCA SDD-102 ◎収録時間:78:33 |
| “知的制御よりも情念を優先させたアンセルメの例外的熱演!” | ||
|
||
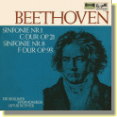 Treasures TRE-202(1CDR) |
A.ローター/ベートーヴェン:交響曲集 グルック:「アウリスのイフィゲニア」序曲# ベートーヴェン:交響曲第1番* 交響曲第8番* フンパーディンク:「ヘンゼルとグレーテル」序曲** 「王子王女」序曲## |
アルトゥール・ローター(指) ベルリンSO* ベルリン国立歌劇場O 録音:1959年頃*、1956年10月10日#、1957年6月18日**、1957年6月24日## (全てステレオ) ※音源:独Opera ST-1911*、独TELEFUNKEN SLT-43011 ◎収録時間:75:29 |
| “世紀の名演「ベト8」に見るローターの飽くなき職人気質!” | ||
|
||
| FUGA LIBERA FUG-754(1CD) NX-B08 |
ワーグナー:楽劇「トリスタンとイゾルデ」~前奏曲と愛の死 チャイコフスキー:交響曲第4番ヘ短調 Op.36 |
ドミトリー・リス (指) 南ネーデルラントPO 録音:2017年3月31日 フライトホフ広場劇場、マーストリヒト 2017年4月1日 アイントホーフェン音楽堂 チャイコフスキー…2017年11月22日 シャッセ劇場、ブレダ、2017年11月23日 アイントホーフェン音楽堂 |
|
||
| EM Records EMRCD-047(1CD) |
コーウェン:交響曲第5番 パーシー・シャーウッド:ヴァイオリン,チェロと管弦楽のための協奏曲 フレデリック・ハイメン・コーウェン:交響曲第5番ヘ短調(全曲世界初録音) |
ルパート・マーシャル=ラック(Vn)、 ジョゼフ・スプーナー(Vc)、 ジョン・アンドルース(指)、 BBCコンサート・オーケストラ 録音:2016年6月20日-22日、ワトフォード・コロッセウム |
|
||
| Cybele 3D-801801(1SACD) |
ヴッパータール交響楽団LIVE Vol.2 ワーグナー:『タンホイザー』~序曲/ヴェーヌスベルクの音楽 ベルリオーズ:幻想交響曲 Op.14 |
ジュリア・ジョーンズ(指) ヴッパータールSO |
|
||
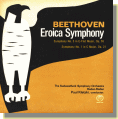 Treasures TRE-197(1CDR) |
クレツキ&南西ドイツ放送響/ベートーヴェン 交響曲第1番ハ長調Op.21 交響曲第3番変ホ長調「英雄」* |
パウル・クレツキ(指) 南西ドイツRSO 録音:1962年(ステレオ) ※音源:瑞西Concert Hall SMSBE-2313(TU)、SMS-2275(TU)* ◎収録時間:75:46 |
| “ユダヤ的感性を隠すことなくベートーヴェンに対峙した確信的解釈!” | ||
|
||
 Treasures TRT-014(1CDR) |
L.ルートヴィヒ/シューベルト&チャイコフスキー シューベルト:交響曲第4番「悲劇的」 チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調Op.64* |
レオポルド・ルートヴィヒ(指) ウィーンSO、 ハンブルク国立PO* 録音:1960年4月18-21日ウィーン・コンツェルトハウス、1960年3月28-30日ハンブルク・クルトゥアラウム*(共にステレオ) ※音源:独Opera St-1995、St-1916* ◎収録時間:76:47 |
| “S・イッセルシュテット以上にドイツの意地を露骨に誇示した熱き名演!” | ||
|
||
 Treasures TRE-194(1CDR) |
クリップス/「未完成」&「悲愴」 シューベルト:交響曲第8番「未完成」 チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」* |
ヨーゼフ・クリップス(指) ウィーン祝祭O、 チューリッヒ・トーンハレO* 録音:1964年、1960年10月* ※音源:仏PRESTIGE_SR-9634、日Concert Hall CHJ-30014* ◎収録時間:65:51 |
| “クリップスの微笑が作品の悲劇性に瑞々しい息吹を注入!” | ||
|
||
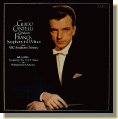 Treasures TRE-196(1CDR) |
カンテッリのステレオ名盤集Vol.2 ブラームス:交響曲第3番 フランク:交響曲ニ短調* |
グィド・カンテッリ(指) フィルハーモニアO NBC響* 録音:1955年8月、1954年4月* ※音源:仏Trianon TRI-33200、英W.R.C SH376* ◎収録時間:70:08 |
| “テンポの変動を抑えて作品の本質を引き出すカンテッリの天才性!” | ||
|
||
 Treasures TRE-200(1CDR) |
ワルター厳選名演集Vol.2 ハイドン:交響曲第88番「V字」 シューベルト:交響曲第9番「グレート」 |
ブルーノ・ワルター(指) コロンビアSO 録音:1961年3月4&8日、1959年1月31日&2月2,4,6日*(共にステレオ) ※音源:日COLUMBIA OS-307、英CBS SRBG-72020* ◎収録時間:74:08 |
| “晩年のワルターの芸術性が奇跡的な次元にまで昇華した2大名演!” | ||
|
||
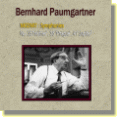 Treasures TreasuresTRE-188(1CDR) |
パウムガルトナー/モーツァルト:交響曲集 交響曲第35番[ハフナー」 交響曲第38番「プラハ」* 交響曲第41番「ジュピター」 |
ベルンハルト・パウムガルトナー(指) ザルツブルク・モーツァルテウム音楽院O 録音:1958年7月*(ステレオ) ※音源:独PARNASS61-415、61-413* ◎収録時間:79:47 |
| “モーツァルトに対する渾身の愛を温かな造形美に凝縮!” | ||
|
||
 OUT OF THE FLAME OUT-082(15CD) |
マーラー:交響曲全集 (1)交響曲第1番「巨人」 (2)交響曲第2番 ハ短調「復活」 (3)交響曲第3番 ニ短調 (4)交響曲第4番ト長調 (5)交響曲第5番 嬰ハ短調 (6)交響曲第6番 イ短調「悲劇的」 (7)交響曲第7番 ホ短調* (8)交響曲第10番 嬰ヘ短調(アダージョ)+ (9)交響曲第8番「千人の交響曲」 (10)交響曲第9番ニ長調 |
チェコ・ナショナルSO リボル・ペシェク(指) (1)録音:2008年1月、ルドルフィヌム、プラハ、チェコ (2)エヴァ・ウルバノヴァー(S) カテジナ・ヤロフツォヴァー(A) ブルノ・チェコ・フィルハーモニーcho 録音:2010年1月、ルドルフィヌム、プラハ、チェコ (3)ダグマル・ペツコヴァー(Ms) ブルノ・チェコ・フィルハーモニーcho キューン児童cho 録音:2012年1月、ライヴ、スメタナ・ホール、市民会館、プラハ、チェコ (4)佐藤美枝子(S) 録音:2009年2月、ルドルフィヌム、プラハ、チェコ (5)録音:2007年3月、ルドルフィヌム、プラハ、チェコ [CD 8-9: OUT 068 (2CD)] (6)録音:2014年1月、ライヴ、スメタナ・ホール、市民会館、プラハ、チェコ (7)(8)録音:2015年1月+、2016年1月*、ライヴ、スメタナ・ホール、市民会館、プラハ、チェコ (9)アンナ・キェリケッティ、ドリアーナ・ミラッツォ、カテジナ・クニェジーコヴァー(S) イヴォナ・シュクヴァーロヴァー、カテジナ・ヤロフツォヴァー(A) マルチェッロ・ナルディス(T) ジャンフランコ・モトレゾル(Br) オンドレイ・ムラース(Bs) ブルノ・チェコ・フィルハーモニーcho カンティレーナ児童cho 録音:2011年1月、ライヴ、スメタナ・ホール、市民会館、プラハ、チェコ (10) 録音:2013年1月、ライヴ、スメタナ・ホール、市民会館、プラハ、チェコ |
|
||
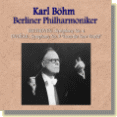 Treasures TRE-189(1CDR) |
ベームのベートーヴェン&ドヴォルザーク ベートーヴェン:交響曲第4番 ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界から」* |
カール・ベーム(指)BPO 録音:1952年4月23日、1951年12月17日* ※音源:伊MOVIMENT MUSICA 08-001、01-024* ◎収録時間:79:40 |
| “作品に対するヴィジョンの違いが際立つ2つの名演!” | ||
|
||
| パスティエル DQC-1581(1CD) 税込定価 |
チャイコフスキー:交響曲第5番 ドヴォルザーク:スケルツォ・カプリチオーソ スメタナ:交響詩「ワレンシュタインの陣営」 |
ラドミル・エリシュカ(指) 札幌SO 録音:2016年10月14~15日 札幌コンサートホールKitara |
|
||
| Cybele D-801702(1SACD) |
ヴッパータール交響楽団LIVE Vol.1 ドホナーニ:交響的瞬間 Op.36、 ピアノ協奏曲第2番 ロ短調 Op.42 ブラームス:交響曲第3番 ヘ長調 Op.90 |
ソフィア・グルバダモーヴァ(P) ドミトリー・ユロフスキ(指) ヴッパータールSO 録音:2017年6月25・26日 |
|
||
 fine NF(N&F) NF-928801(2CD) 税込定価 2017年11月20日発売 |
チャイコフスキー:三大交響曲 交響曲第4番ヘ短調Op.36 交響曲第5番ホ短調Op.64 交響曲第6番 ロ短調「悲愴」Op.74 |
ヴァレリー・ポリャンスキー(指) ロシア国立SO《シンフォニック・カペレ》 録音:2015年7月18日 東京芸術劇場第ホール・ライヴ |
|
||
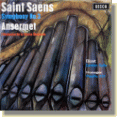 Treasures TRE-187(1CDR) |
アンセルメ~オーディオ・ファイル名演集1 ビゼー:「カルメン」組曲[第1幕前奏曲/アラゴネーズ/間奏曲/アルカラの竜騎兵/密輸入者の行進/ハバネラ/衛兵の交代/ジプシーの踊り] オネゲル:機関車パシフィック231* サン・サーンス:交響曲第3番「オルガン」# |
エルネスト・アンセルメ(指)スイス・ロマンドO ピエール・スゴン(Org)# 録音:1958年4月1-23日&5月12-14日、1963年4月2-8日*、1962年5月3-5日&12-28日#(全てステレオ) ※音源:日KING SLC-1707、SLC-1702*,# ◎収録時間:67:33 |
| “アンセルメ芸術の粋を結集した厳選3曲!” | ||
|
||
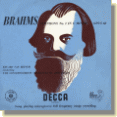 Treasures TRE-181(1CDR) |
ベイヌム/メンデルスゾーン&ブラームス メンデルスゾーン:交響曲第4番「イタリア」 ブラームス:交響曲第1番ハ短調Op.68* |
エドゥアルト・ファン・ベイヌム(指) アムステルダム・コンセルトヘボウO 録音:1955年6月2-4日、1951年9月17日*(共にモノラル) ※音源:PHILIPS 6542-131、英DECC ACL-71* ◎収録時間:68:18 |
| “オケの技術力をそのまま音楽的ニュアンスに変換できるベイヌムの凄さ!” | ||
|
||
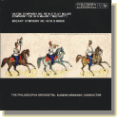 Treasures TRE-183(1CDR) |
オーマンディ/モーツァルト&ハイドン:交響曲集 モーツァルト:交響曲第40番ト短調 ハイドン:交響曲第99番* 交響曲第100番「軍隊」# |
ユージン・オーマンディ(指) フィラデルフィアO 録音:1956年1月10日、1954年4月15日*、1953年12月23日# ※音源:米COLUMBIA ML-5098、ML-5316*,# ◎収録時間:71:20 |
| “深刻な空気を持ち込まないオーマンディのピュアな作品掌握力!” | ||
|
||
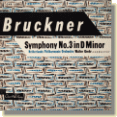 Treasures TRE-182(1CDR) |
ベートーヴェン:12のドイツ舞曲 WoO.8* ブルックナー:交響曲第3番[第3稿=1890年のシャルク改訂版] |
ワルター・ゲール(指) フランクフルトRSO* オランダPO 録音:1950年代中期頃*、1953年11月、ヒルフェルスム 原盤:Concert Hall MMS-2159*、Concert Hall CHS-1195 ◎収録時間:65:32 |
| “クナだけではない!説得力絶大な改訂版による「ブル3」” | ||
|
||
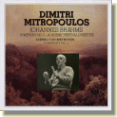 Treasures TRE-185(1CDR) |
ミトロプーロス/ベートーヴェン&ブラームス ベートーヴェン:交響曲第1番ハ長調Op.21* ブラームス:大学祝典序曲 交響曲第3番ヘ長調Op.90 |
ディミトリ・ミトロプーロス(指)NYO 録音:1951年10月15日*、1958年2月9日(共にモノラル・ライヴ) ※音源: MELODRAM 233*、 FONITCETRA DOC-23 ◎収録時間:63:04 |
| “ミトロプーロスの危険な表現とソナタ形式との美しき融和!” | ||
|
||
 Treasures TRT-013(1CDR) |
クーベリック&VPO~ステレオ名演集Vol.1 シューベルト:交響曲第4番「悲劇的」 チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調* |
ラファエル・クーベリック(指)VPO 録音:1960年1月14-20日、11月21-24日* ウィーン・ムジークフェライン大ホール(共にステレオ) ※音源:独ELECTROLA C053-00651、STE-91135* |
|
||
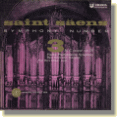 Treasures TRE-180(1CDR) |
スワロフスキー/チャイコフスキー&サン・サーンス チャイコフスキー:交響曲第3番「ポーランド」 サン・サーンス:交響曲第3番「オルガン付き」* |
ハンス・スワロフスキー(指) ウィーン国立歌劇場O フランツ・エイブナー(Org)* ※ウィーン楽友協会ホールのオルガンを使用 録音:1956年6月26-29日(ステレオ) ※音源:URANIA USD-1026、SAGA XID-5283* ◎収録時間:76:14 |
| “色彩の厚塗りを避け、スコアの筆致を信じた実直路線が結実!” | ||
|
||
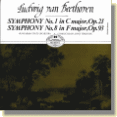 Treasures TRE-178(1CDR) |
フェレンチクのベートーヴェンVol.2 序曲「献堂式」Op.124 交響曲第1番ハ長調Op.21 交響曲第8番ヘ長調Op.93 |
ヤーノシュ・フェレンチク(指) チェコPO*、ハンガリー国立O 録音:1961年1月5日*、1964年7月14-23日(全てステレオ) ※音源:SUPRAPHON SUAST-50025*、HUNGAROTON HLX-90002 ◎収録時間:65:28 |
| “音楽を決して淀ませない、フェレンチク流の指揮の極意!!” | ||
|
||
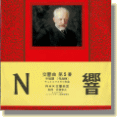 Treasures TRT-012(1CDR) |
岩城宏之&N響~ミュンヘンでの「チャイ5」 リスト:ハンガリー狂詩曲第5番 ハンガリー狂詩曲第4番 チャイコフスキー:交響曲第5番* |
岩城宏之(指) ウィーン国立歌劇場O、NHK響* 録音:1963年4月-5月バイヤリッシャー・ホール、1960年9月26日ミュンヘン・コングレス・ザールでのライヴ*(全てモノラル) ※音源:日Concert Hall M-2381、日Victor JV-2001* ◎収録時間:70:15 |
| “大和魂炸裂!全てを攻めの姿勢でやり尽くしたN響!” | ||
|
||
 Treasures TRE-171(1CDR) |
バルビローリ~「ブラ4」・旧録音 ベートーヴェン:「レオノーレ」序曲第3番 ウェーバー:「オベロン」序曲 ブラームス:交響曲第4番ホ短調* |
ジョン・バルビローリ(指)ハレO 録音:1959年4月、1960年9月* ※音源:英PYE GSGC-2038、GSGC-1*(全てステレオ) ◎収録時間:64:25 |
| “渋味に逃げず果敢に愛をぶつけたバルビローリの代表盤!” | ||
|
||
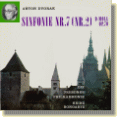 Treasures TRE-168(1CDR) |
ボンガルツのドヴォルザーク バッハ:ブランデンブルク協奏曲第5番* ドヴォルザーク:交響曲第7番 |
ハインツ・ボンガルツ(指) ゲルハルト・ボッセ(Vn)*、 フリーデマン・エルベン(Vc)* ハインツ・ヘルチュ(Fl)*、 ハンス・ピシュナー(Cem)* ライプチヒ・ゲヴァントハウスO* ドレスデンPO 録音:1960年代初頭*、1962年12月17-20日(共にステレオ)、 ※音源:羅ELECTRECORD STM-ECE-0672*、独ELECTROLA STE-91328 ◎収録時間:62:42 |
| “豪華絢爛な響きでは気づかないドヴォルザークの真価!” | ||
|
||
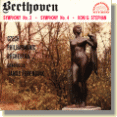 Treasures TRE-165(1CDR) |
フェレンチクのベートーヴェン 「シュテファン王」序曲 交響曲第2番ニ長調Op.36* 交響曲第4番変ロ長調Op.60 |
ヤーノシュ・フェレンチク(指)チェコPO 録音:1961年1月2-5日*、1961年10月14-17日(全てステレオ) ※音源:SUPRAPHON SUAST-50025*、瑞西Zipperling CSLP-6014 ◎収録時間:75:20 |
| “いにしえのチェコ・フィルだけが放つ芳しさと温もり!” | ||
|
||
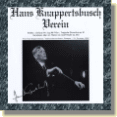 Treasures TRE-161(2CDR) ★ |
クナッパーツブッシュ~ブラームス・プログラム 悲劇的序曲 ハイドンの主題による変奏曲 交響曲第3番 |
ハンス・クナッパーツブッシュ(指) シュトゥットガルトRSO 録音:1963年11月15日(モノラル・ライヴ) ※音源:Private HKV-TY4/5 ◎収録時間:81:48 |
| “いびつな造型の先にある昇華を極めた芸術性!” | ||
|
||
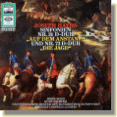 Treasures TRE-160(1CDR) |
レオポルド・ルートヴィヒ/ハイドン:「ホルン信号」他 モーツァルト:「コシ・ファン・トゥッテ」序曲* 「ドン・ジョヴァンニ」序曲* ハイドン:交響曲第31番「ホルン信号」# 交響曲第73番「狩猟」 |
レオポルド・ルートヴィヒ(指) ハンブルク国立歌劇場O*、 バイエルンRSO クルト・リヒター(Hrnソロ)# 録音:1960年代中期*、1966年4月6&8日ビュルガー・ブロイ・ホール(ミュンヘン)全てステレオ ※音源:独EUROPA E-177*、独ELECTRORA SME-91601 ◎収録時間:63:05 |
| “指揮者の存在感を極限まで消して作品の様式美を徹底表出!” | ||
|
||
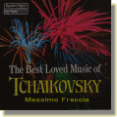 Treasures TRE-159(1CDR) |
フレッチャ~リーダーズ・ダイジェスト名演集1 ロッシーニ:「セミラーミデ」序曲* チャイコフスキー:「エフゲニ・オネーギン」~ワルツ# 弦楽セレナード~ワルツ# 「眠りの森の美女」~ワルツ** スラブ行進曲Op.31## 交響曲第4番ヘ短調Op.36 |
マッシモ・フレッチャ(指) ローマPO、ウィーン国立歌劇場O# 録音:1960年8月4日*、1961年6月23-25日#、1960年8月2日**、1960年8月5日## 1961年12月11,15,21-22日(全てステレオ) ※音源:日Victor SFM-3*.**.##、 米Radars Digest RD4-178-2/4(エフゲニ・オネーギン )、RD4-178-2/5(セレナード)、RD4-178-2/10(交響曲) ◎収録時間:76:19 |
| “イタリアの血と汗と歌で染め尽くした驚異のダイナミズム!” | ||
|
||
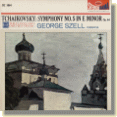 Treasures TRT-011(1CDR) |
セルのチャイコフスキー&R=コルサコフ リムスキー=コルサコフ:スペイン奇想曲 チャイコフスキー:イタリア奇想曲* 交響曲第5番ホ短調Op.64# |
ジョージ・セル(指) クリーヴランドO 録音:1958年2月28日&3月14日、1958年2月28日*、1959年10月23-24日#(全てステレオ) ※音源:米EPIC BC-1002、BC-1064# ◎収録時間:76:07 |
| “セルの美学貫徹により初めて思い知る作品の偉大さ!” | ||
|
||
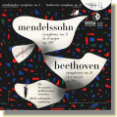 Treasures TRE-158(1CD) |
ウォーレンステイン~ベートーヴェン&メンデルスゾーン他 ベートーヴェン:交響曲第8番 メンデルスゾーン:交響曲第5番「宗教改革」 シャブリエ:ハバネラ* 狂詩曲「スペイン」*/楽しい行進曲* |
アルフレッド・ウォーレンステイン(指) ロスアンジェルスPO 録音:1953年3月、1953年2月*(全てモノラル) ※音源:米DECCA DL-9726、英Brunswick AXTL-1063* ◎収録時間:64:24 |
| “剛毅な進行にも作曲家の息吹を絶やさない「宗教改革」の理想像!” | ||
|
||
 Treasures TRE-154(1CDR) |
ラインスドルフ&ボストン響~厳選名演集Vol.1 マーラー:交響曲第5番 |
エーリヒ・ラインスドルフ(指) ボストンSO ロジャー・ヴォワザン(Tpソロ) ジェームズ・スタグリアーノ(Hrnソロ) 録音:1963年11月17,23,26日(ステレオ) ※音源:英RCA SER-5518 ◎収録時間:64:31 |
| “外面的効果を排し、芸術的な昇華力で勝負した記念碑的名演!!” | ||
|
||
| Les Dissonances LD-009(1CD) ブック仕様(96p) |
ショスタコーヴィチ:チェロ協奏曲第1番 交響曲第5番ニ短調 op.47 |
レ・ディソナンス ダヴィド・グリマル(Vn) グザヴィエ・フィリップス(Vc/マッテオ・ゴフリラー1710年製) 録音:2014年12月2日(協奏曲)、2016年1月23日(交響曲)/ライヴ録音(ディジョン歌劇場) |
|
||
 WEITBLICK SSS-0197(1CD) |
ブラームス:交響曲第1番 ハンガリー舞曲4曲(第1、第3番、第4番、第5番) |
ジョルジュ・プレートル(指) シュトゥットガルトRSO 録音:2000年12月8日リーダーハレ、1997年10月29日~31日リーダーハレ* |
|
||
 WEITBLICK SSS-0198(1CD) |
ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」 マーラー:交響詩「葬礼」 |
ジョルジュ・プレートル(指) シュトゥットガルトRSO 録音:1996年10月14日~28日リーダーハレ、1998年6月28日リーダーハレ* |
|
||
| DACAPO MAR-8.226175(1CD) NX-B06 |
ラスムッセン:交響曲第2番「地球、新たに」(2015)…ソプラノとバリトン独唱、男声合唱、大管弦楽のための | ボー・スコウフス(Br) シンディア・シーデン(S) アカデミスカ・サングフェレニンゲン ムントラ・ムジカンテル ヘルシンキPO ヨーン・ストルゴーズ(指) 録音:2015年9月12-14日ヘルシンキミュージックセンター、コンサート・ホール ※世界初録音 |
|
||
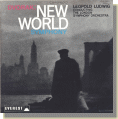 Treasures TRE-148(1CDR) |
L・ルートヴィヒ~「未完成」&「新世界」 モーツァルト:歌劇「イドメネオ」序曲* シューベルト:交響曲第8番「未完成」 ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界から」# |
レオポルド・ルートヴィヒ(指) ハンブルク国立歌劇場O*、LSO 録音:1960年代中期*、1959年11月17日、11月16日#(全てステレオ) ※音源:独EUROPA E-177*、日COLUMBIA MS-1102EV ◎収録時間:68:11 |
| “斜に構えず、誇張せず、音楽の魂をひたむきに追求!” | ||
|
||
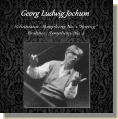 Treasures TRE-147(1CDR) |
G・L・ヨッフム~シューマン&ブラームス シューマン:交響曲第1番「春」Op.38 ブラームス:交響曲第2番ニ長調Op.73* |
ゲオルク・ルートヴィヒ・ヨッフム(指) ベルリンRSO、スウェーデンRSO* 録音:1951年6月10日、1957年7月5日*(共にモノラル) ※音源: RVC RCL-3310、BIS LP-331/333* ◎収録時間:64:52 |
| “高名な兄以上の統率力と高潔な精神力を感じさせる凄演!” | ||
|
||
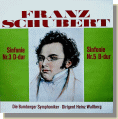 Treasures TRE-152(1CDR) |
ワルベルク~モーツァルト&シューベルト モーツァルト:交響曲第40番ト短調K.550* シューベルト:交響曲第3番ニ長調D.200 交響曲第5番変ロ長調D.485 |
ハインツ・ワルベルク(指) バンベルクSO 録音:1961年3月*、1962年12月(全てステレオ) ※音源:日COLUMBIA MS-4*、独Opera St-1985 ◎収録時間:77:26 |
| “ただの純朴指揮者ではない!ワルベルク流の音楽の息づかせ方!” | ||
|
||
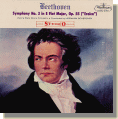 Treasures TRE-150(1CDR) |
シェルヘンの二大過激名演集 ハイドン:交響曲第100番「軍隊」 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」* |
ヘルマン・シェルヘン(指) ウィーン国立歌劇場O 録音:1958年7月、1958年9月18日*(共にステレオ) ※音源:Westminster WST-14044、WST-14045* ◎収録時間:66:58 |
| “伝統美を完全放棄!過激さの裏に迸る絶対に譲れない信条!!” | ||
|
||
| DACAPO MAR-2.110417(6DVD) NX-J01 MAR-2.110423(3Bluray) NX-J01 |
ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴス ■〈DVD1〉 ベートーヴェン:交響曲全集 1.交響曲第1番ハ長調Op.21 2.交響曲第2番ニ長調Op.36 〈DVD2〉 1.交響曲第3番「英雄」Op.55 2.交響曲第4番変ロ長調Op.60 〈DVD3〉 1.交響曲第5番ハ短調Op.67 2.交響曲第6番ヘ長調「田園」 〈DVD4〉 1.交響曲第7番イ長調Op.92 2.交響曲第8番ヘ長調Op.93 〈DVD5〉 1.交響曲第9番ニ短調「合唱」 2.ロドリーゴ:アランフェス協奏曲 〈DVD6〉 1.ベルリオーズ:幻想交響曲 2.R・シュトラウス:アルプス交響曲 〈Blu-ray1〉 ベートーヴェン:交響曲全集 1.交響曲第1番ハ長調Op.21 2.交響曲第2番ニ長調Op.36 3.交響曲第3番「英雄」Op.55 4.交響曲第4番変ロ長調Op.60 〈Blu-ray2〉 1.交響曲第5番ハ短調Op.67 2.交響曲第6番ヘ長調「田園」 3.交響曲第7番イ長調Op.92 4.交響曲第8番ヘ長調Op.93 〈Blu-ray3〉 1.交響曲第9番ニ短調「合唱」 2.ロドリーゴ:アランフェス協奏曲 3.ベルリオーズ:幻想交響曲 4.R・シュトラウス:アルプス交響曲 |
ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴス(指) デンマーク国立SO アルビナ・シャギムラトーヴァ(S) シャルロッテ・ヘレカント(Ms) スコット・マッカリスター(T) ヨハン・ロイター(Bs) デンマーク国立コンサートcho ペペ・ロメロ(G) 収録2012-2014年 収録時間:553分 音声:ステレオ 2.0/DD5.1/DTS5.1 字幕:なし 画面:16:9 REGION All(Code:0) 〈DVD〉片面二層ディスク×6 〈BD〉二層50GB×31080i High Definition |
|
||
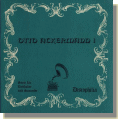 Treasures TRE-139(1CDR) |
オットー・アッカーマン~名演集Vol.1 モーツァルト:交響曲第7番ニ長調K.45 交響曲第8番ニ長調K.48 交響曲第12番ト長調K.110 ハイドン:交響曲第100番「軍隊」* ボロディン:交響曲第2番ロ短調# |
オットー・アッカーマン(指) オランダPO、ケルンRSO*,# 録音:1952年12月10-11日、1955年10月2-3日*、1954年6月8-11日# ※音源:独DISCOPHILIA OAA-101、DIS.OAA-100*,# ◎収録時間:79:02 |
| “アッカーマン知られざる真価の本質を知る交響曲集!” | ||
|
||
 Treasures TRE-140(1CDR) |
オットー・アッカーマン~名演集Vol.2 モーツァルト:交響曲第9番ハ長調 K. 73 交響曲第13番ヘ長調 K. 112 ケルビーニ:歌劇「アナクレオン、またはつかの間の恋」序曲* チャイコフスキー:交響曲第4番ヘ短調* |
オットーアッカーマン(指) オランダPO、 ベルン市立歌劇場O* 録音:1952年12月10-11日、1958年11月18日(ライヴ)* ※音源:独DISCOPHILIA OAA-101、瑞西RELIEF RL-851* ◎収録時間:75:05 |
| “チャイコフスキーの孤独とダイナミズムを高潔な音彩で徹底抽出!” | ||
|
||
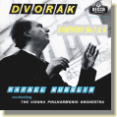 Treasures TRE-136(1CDR) |
クーベリック&VPOのドヴォルザーク 交響曲第7番ニ短調Op.70 交響曲第9番ホ短調「新世界から」* |
ラファエル・クーベリック(指)VPO 録音:1956年10月1-2日、3-4日* (共にモノラル) ※音源:英DECCA LXT-5290、LHT-5291* ◎収録時間:77:05 |
| “「ウィーン・フィルのドヴォルザーク」の頂点をなす感動録音!” | ||
|
||
| DACAPO MAR-8.226098B06 (2CD) |
パウル・フォン・クレナウ:交響曲第9番(1945) | コルネリア・プタセク(S) スサネ・レースマーク(A) ミヒャエル・ヴァイニウス(T) シュテフェン・ブルーン(Bs) デンマーク国立コンサートcho デンマーク国立SO ミハエル・シェンヴァント(指) 録音:2014年3月20-21日コペンハーゲンデンマーク放送,Koncerthuset |
|
||
| DACAPO MAR-8.226110B06 (1CD) |
クリストファー・ラウス:作品集 オーケストラのための「odnazhizn ‐ある一生」(2008) 交響曲第3番(プロコフィエフによる)(2011) 交響曲第4番(2013) オーケストラのための「プロスペロの部屋」(2012) |
アラン・ギルバート(指)NYO 録音:2010年2月20日、2013年6月20日、2014年6月5日 年4月17日 ニューヨーク、リンカーン・センター,デイヴィッド・ゲフィン・ホール/エヴリー・フィッシャー・ホール |
|
||
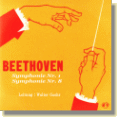 Treasures TRE-133(1CDR) |
ワルター・ゲール~ベートーヴェン他 バッハ:ブランデンブルグ協奏曲第3番 ベートーヴェン:交響曲第1番* 交響曲第8番ヘ長調Op.93** スメタナ:「売られた花嫁」序曲# |
ワルター・ゲール(指) ヴィンタートゥールSO フランクフルト歌劇場O* フランクフルトRSO**,# 録音:1950年代中頃(全てステレオ) ※音源:日Concert Hall SM-6101、仏PRESTIGE DE LA MUSIQUE SA-9653*、日Concert Hall SM-197**、SM-6111# ◎収録時間:66:26 |
| “古典な均整美に活気を与えた、ゲール最高のベートーヴェン!” | ||
|
||
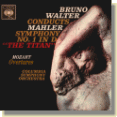 Treasures TRE-125(1CDR) |
マックルーア版/ワルター厳選名演集Vol.2 モーツァルト:歌劇「魔笛」序曲* 歌劇「劇場支配人」* 歌劇「フィガロの結婚」序曲* マーラー:交響曲第1番「巨人」 |
ブルーノ・ワルター(指) コロンビアSO 録音:1961年3月*、1961年1月&2月 ※音源:日SONY 20AC-1805*、20AC-1830 ◎収録時間:68:59 |
| “ワルターの全人生を注いだ「巨人」の不滅の価値!” | ||
|
||
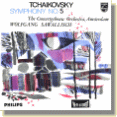 Treasures TRT-010(1CDR) |
サヴァリッシュ~チャイコフスキー チャイコフスキー:バレエ音楽「白鳥の湖」から 第2幕;情景/第1幕:ワルツ 第2幕;小さい白鳥たちの踊り 第2幕;オデットと王子のパ・ダクシオン 第4幕;情景 交響曲第5番ホ短調Op.64* |
ウォルフガング・サヴァリッシュ(指) フィルハーモニアO、 アムステルダム・コンセルトヘボウO* 録音:1957年9月-1958年2月28日、1962年1月*(全てステレオ) ※音源:仏EMI CVD-955、蘭PHILIPS 835116AY* ◎収録時間:62:53 |
| 全盛期のコンセルトヘボウ管の魅力が、意欲満点のサヴァリッシュの棒で大全開!” | ||
|
||
| KLANGLOGO KL-1514(1CD) |
ブラームス:交響曲第3番ヘ長調Op.90 交響曲第4番ホ短調Op.98 |
フランクフルト・ブランデンブルク州立O ハワード・グリフィス(指) 録音:2015年6月22-25日フランクフルト,「カール・フォリップ・エマヌエル・バッハ」コンサート・ホール |
|
||
| DACAPO MAR-2.110416G(DVD) |
ブロムシュテット/シューベルト&ブルックナー シューベルト:交響曲第7番「未完成」 ブルックナー:交響曲第7番(1954年ノーヴァク版) 《ボーナス映像》 ヘルベルト・ブロムシュテットとジョン・フェローの対話(79'54") |
デンマーク国立SO ヘルベルト・ブロムシュテット(指) 収録:2007年10月14日ロスキルデ大聖堂 収録時間:187分/音声:ステレオ 2.0/DD5.1/DTS5.1 字幕:英語/画面:16:9カラー REGION All(Code:0) <DVD>片面2層ディスク |
|
||
| DACAPO MAR-6.220645(1SACD) |
ペア・ノアゴー:交響曲第6番&第2番 交響曲第6番「一日の終わり」(1999) 交響曲第2番(1970/1971改編) |
オスロPO ジョン・ストゥールゴールズ(指) 録音:2015年5月25-28日オスロコンセルトフス、2015年6月1-5日オスロオペラハウスオーケストラ・リハーサル・ルーム |
|
||
| DACAPO MAR-6.220646(1SACD) |
ペア・ノアゴー:交響曲第4番&第5番 交響曲第5番(1987-90/1991改編) 交響曲第4番(1981) |
オスロPO ジョン・ストゥールゴールズ(指) 録音:2015年5月25-28日オスロコンセルトフス、2015年6月1-5日オスロオペラハウスオーケストラ・リハーサル・ルーム |
|
||
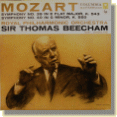 Treasures TRE-103(1CDR) |
ビーチャム~モーツァルト:交響曲集 交響曲第38番「プラハ」K.504* 交響曲第39番変ホ長調K.543** 交響曲第40番ト短調K.550# |
トーマス・ビーチャム(指) ロイヤルPO 録音:1950年4月*、1955年12月**、1954年4月# ※音源:蘭CBS CBS-6020*、英PHILIPS ABL-3094**,# ◎収録時間:74:51 |
| “大きな包容力で魅了する、ビーチャム流の愉しいモーツァルト!” | ||
|
||
| ARTESMON AS-744-2 (2CD+1DVD PAL) |
アンドルー・ダウンズ(1950-): 交響曲第1番(オルガン,金管,打楽器と弦楽の為の)Op.27(1982)* 交響曲第2番(室内管弦楽の為の)Op.30(1984) 演奏会用序曲「コッツウォルズにて」(管弦楽の為の)Op.36(1986) 交響曲第3番「地の精」(拡大された管弦楽の為の)Op.45(1992) 交響曲第4番(吹奏楽の為の)Op.59(1996) 演奏会用序曲「新時代に向かって」(管弦楽の為の)Op.60(1996) ■Bonus DVD 音楽、喜び、望み(レコーディングのドキュメンタリー)[18分8秒] |
アレシュ・バールタ(Org)* オンドジェイ・ヴラベツ(指) チェコPO 録音:2015年3-5月、ドヴォルザーク・ホール、ルドルフィヌム、プラハ、チェコ |
|
||
 ORFEO DOR C901162-B(2CD) |
バックハウス&クナッパーツブッシュ ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番 交響曲第7番イ長調Op.92 序曲「コリオラン」 交響曲第3番「英雄」* |
ヴィルヘルム・バックハウス(P) ハンス・クナッパーツブッシュ(指)VPO 録音:1954年1月17日、1962年2月17日* ウィーン・ムジークフェライン・モノラル・ライブ |
| “血の涙で埋め尽くす「7番」第2楽章は、クナ節の究極形!” | ||
|
||
 Treasures TRE-127(1CDR) |
アンセルメ~1960年代の厳選名演集1~プロコフィエフ他 グリンカ:幻想曲「カマリンスカヤ」 ボロディン:中央アジアの草原にて プロコフィエフ:古典交響曲 交響曲第5番* |
エルネスト・アンセルメ(指) スイス・ロマンドO 録音:1961年2月、1964年4月*(全てステレオ) ※音源:米LONDON CS-6223、CS-6406* ◎収録時間:70:11 |
| “クールなのに作品を突き放さない、アンセルメの絶妙な対峙力!” | ||
|
||
| Les Dissonances LD-008(3CD) |
20世紀の作曲家作品集 (1)ショスタコーヴィチ(バルシャイ編):室内交響曲 ハ短調 Op.110a (2)バルトーク:ディヴェルティメント Sz.113 (3)シェーンベルク:室内交響曲第1番 ホ長調 Op.9 (4)シェーンベルク:室内交響曲第2番 Op.38 (5)バーンスタイン:セレナード (6)シュニトケ:コンチェルト・グロッソ第1番 (7)シュニトケ:モーツァルト・ア・ラ・ハイドン* ■ボーナス:(商品に表記されているURLから記載のパスワードを入力してご覧いただくオンライン映像) ブラームス:交響曲全集(ライヴ録音) |
ダヴィド・グリマル(Vn&コンサートマスター)、レ・ディソナンス、 ハンス・ペーター・ホフマン(Vn)* ライヴ録音:(1)(6)2011年1月7日、(4)2014年10月21日/シテ・ド・ラ・ミュジーク (2)2011年4月6日、(3)2013年2月13日、(5)2010年10月28日、(7)2014年12月2日/ディジョン歌劇場 ※60 ページのブックレット付 |
|
||
| スロヴァキア音楽財団 SF-0087-2(1CD) |
イリヤ・ゼリェンカ(1932-2007):交響曲第1番* 交響曲第2番+ |
チェコスロヴァキアRSO オリヴェル・ドホナーニ(指)* ラディスラフ・スロヴァーク(指)+ 録音:1986年*、1961年+、スロヴァキア放送スタジオ、ブラチスラヴァ、スロヴァキア |
|
||
| スロヴァキア音楽財団 SF-0090-2(1CD) |
ヴラディミール・ボケス(1946-):交響曲第2番 Op.24* 交響曲第3番 Op.36+ |
スロヴァキアPO* ビストリーク・レジュハ(指)* スロヴァキア国立コシツェPO+ リハルト・ジンメル[リヒャルト・ジンマー](指)+ 録音:1980年、ライヴ、スロヴァキア・フィルハーモニー・ホール、ブラチスラヴァ、スロヴァキア*、1989年、ライヴ、スロヴァキア放送、スロヴァキア+ |
|
||
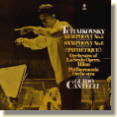 Treasures TRT-009(2CDR) |
カンテッリ~チャイコフスキー:交響曲集 交響曲第5番ホ短調Op.64* 交響曲第6番ロ短調「悲愴」 |
グィド・カンテッリ(指) ミラノ・スカラ座O*、 フィルハーモニアO 録音:1950年9月23-25日*、1952年10月 ※音源:W.R.C SHB-52 ◎収録時間:44:53+42:53 |
| “ストイックなのに柔軟!作品の魅力を再認識させるカンテッリの天才性!” | ||
|
||
 Onyx ONYX-4150(2CD) |
チャイコフスキー:交響曲第1番「冬の日の幻想」 交響曲第2番「小ロシア」 交響曲第5番ホ短調 Op.64 |
ワシリー・ペトレンコ(指) ロイヤル・リヴァプールPO |
| 奇を衒うことなく手垢にまみれたプローチを刷新したペトレンコの快挙!” | ||
|
||
 BERLINER PHIL. KKC-9151 (5CD+3Bluray) 税込定価 |
ベートーヴェン:交響曲全集(ベーレンライター版/ジョナサン・デル・マー校訂版) ■CD1 交響曲第1番ハ長調Op.21[24’42] 交響曲第3番変ホ長調Op.55『英雄』[49’09] ■CD2 交響曲第2番ニ長調Op.36 交響曲第5番ハ短調Op.67『運命』[ ■CD3 交響曲第4番変ロ長調Op.60 交響曲第7番イ長調Op.92 ■CD4 交響曲第6番ヘ長調Op.68『田園』 交響曲第8番ヘ長調Op.93 ■CD5 交響曲第9番ニ短調Op.125『合唱』 ■BD1(ブルーレイディスク・オーディオ) 上記全曲の音声トラックを収録 ■BD2(ブルーレイディスク・ビデオ) 交響曲第1番、第3番『英雄』、第2番、第5番『運命』、第4番、第7番 ■BD3(ブルーレイディスク・ビデオ) 交響曲第8番、第6番『田園』、第9番『合唱』 ■ボーナス(日本語字幕付) ドキュメンタリー『ベートーヴェンと生きる』 (2015年秋、ベルリンにおけるベートーヴェン・ツィクルスの舞台裏)(45分) インタビュー『ラトル、ベートーヴェンの交響曲を語る』(49分) ■ダウンロード・コード このブルーレイ・ディスクには、上記全曲のハイレゾ音源(24bit/192kHz)をダウンロードするためのURLとそのパスワードが封入されています。 ■デジタル・コンサートホール ベルリン・フィルの映像配信サービス「デジタル・コンサートホール」を7日間無料視聴できるチケット・コードが封入されています。 |
全て、サー・サイモン・ラトル(指)BPO ■CD1 録音:2015年10月6&12日ベルリン、フィルハーモニー(ライヴ) ■CD2 録音:2015年10月7&13日ベルリン、フィルハーモニー(ライヴ) ■CD3 録音:2015年10月3、9&15日ベルリン、フィルハーモニー(ライヴ) ■CD4 録音:2015年10月8&14日ベルリン、フィルハーモニー(ライヴ) ■CD5 アンネッテ・ダッシュ(S) エーファ・フォーゲル(A) クリスティアン・エルスナー(T) ディミトリー・イヴァシュシェンコ(Bs) ベルリン放送Cho 録音:2015年10月10&16日ベルリン、フィルハーモニー(ライヴ) 24bit/192kHz録音 ■BD1 2.0PCM Stereo24bit/96kHz 5.1DTS-HDMA24bit/96kHz 収録時間:344分 ■BD2 ■BD3 画面:FullHD1080/60i16:9 音声:2.0PCM Stereo、5.1DTS-HDMasterAudio リージョン:All 収録時間:397分 ★初回特典★ 5枚1組のベルリン・フィル特製ポストカードが封入されています。 日本語帯・解説付 |
|
||
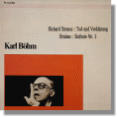 Treasures TRE-113(1CDR) |
ベーム~R・シュトラウス&ブラームス R・シュトラウス:交響詩「死と変容」* ブラームス:交響曲第1番ハ短調Op.68 |
カール・ベーム(指)ベルリンRSO 録音:1950年3月25日*、1950年4月13日ライヴ ※音源:日RVC RCL-3316*、伊Foyer FO-1033 ◎収録時間:69:09 |
| “ベームの芸術のピークを示す2つの名演!” | ||
|
||
| Les Dissonances LD-007(5CD) |
ダヴィド・グリマル / ベートーヴェン、モーツァルト、シューベルト ■CD1 ベートーヴェン:交響曲第2番 ベートーヴェン:交響曲第8番 ■CD2 ベートーヴェン:交響曲第4番 ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ■CD3 ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」Op.67 ベートーヴェン:交響曲第7番 ■CD4 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」Op.55 シューベルト:交響曲第第8番「未完成」 ■CD5 モーツァルト:オーボエ協奏曲ハ長調K.314* モーツァルト:セレナード第10番 変ロ長調「大組曲」K.361 ■ボーナス:(商品に表記されているURLから記載のパスワードを入力してご覧いただくオンライン映像) ブラームス:交響曲全集(ライヴ録音) |
ダヴィド・グリマル(Vn&コンサートマスター) レ・ディソナンス ■CD1 録音:2011年10月18日、2013年10月26日、ディジョン歌劇場(ライヴ) ■CD2 録音:2013年10月26日、2010年5月12日、ディジョン歌劇場(ライヴ) ■CD3 (1)録音:2010年12月9日、2010年5月27日、ディジョン歌劇場(ライヴ) ■CD4 録音:2012年12月20日、ディジョン歌劇場(ライヴ)、2013年12月19日、ミュージック・シティ、フィルハーモニー・ド・パリ(ライヴ) ■CD5 アレクサンドル・ガテ(Ob) 録音:2014年2月19日、2015年4月2日、ディジョン歌劇場(ライヴ) ■ボーナス:(商品に表記されているURLから記載のパスワードを入力してご覧いただくオンライン映像) |
|
||
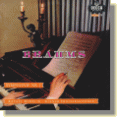 Treasures TRE-102(1CDR) |
クーベリック/ドヴォルザーク&ブラームス ドヴォルザーク:弦楽セレナードOp.22 ブラームス:交響曲第2番ニ長調Op.73* |
ラファエル・クーベリック(指) イスラエルPO、VPO* 録音:1957年3月25日-4月14日、1957年4月4-8日*(共にモノラル) ※音源:米LONDON LL-1720、LL-1699* ◎収録時間:65:14 |
| “ハッタリ無用!クーベリックの底知れぬ才能に再開眼!” | ||
|
||
| CUGATE CLASSICS CGC-010(1CD) |
ラフマニノフ:交響曲第2番ホ短調Op.27 幻想曲「巌」Op.7 |
アレクサンドル・ドミトリエフ(指) サンクトペテルブルグSO 録音:1993年/サンクトペテルブル・フィルハーモニー・ホール |
|
||
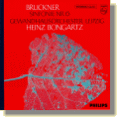 Treasures TRE-111(1CDR) |
ボンガルツ~バッハ&ブルックナー バッハ:ブランデンブルク協奏曲第3番* ブルックナー:交響曲第6番イ長調 |
ハインツ・ボンガルツ(指) ライプチヒ・ゲヴァントハウスO ハンス・ピシュナー(Cem)* 録音:1960年代初頭、1964年12月(共にステレオ)、 ※音源:羅ELECTRECORD STM-ECE-0672*、蘭PHILIPS 835388LY ◎収録時間:72:50 |
| “「ブル6」の命、リズムの意味を体現し尽くした歴史的名演!!” | ||
|
||
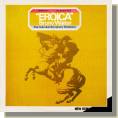 Treasures TRE-108(1CDR) |
マックルーア版/ワルター厳選名演集Vol.1 ベートーヴェン:交響曲第1番Op.21 交響曲第3番「英雄」変ホ長調Op.55* |
ブルーノ・ワルター(指) コロンビアSO 録音:1959年1月5,6,8,.9日、1958年1月20,23,25日*(共にステレオ) ※音源:SONY 20AC1807、20AC1808* ◎収録時間:73:51 |
| “ワルターの正直な感性と楽曲の魅力が完全調和!” | ||
|
||
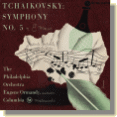 Treasures TRT-008(1CDR) |
オーマンディ没後30年記念~チャイコフスキー&シェーンベルク シェーンベルク:浄められた夜* チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調 |
ユージン・オーマンディ(指) フィラデルフィアO 録音:1950年3月19日アカデミー・オブ・ミュージック(フィラデルフィア)*、1950年11月19日タウン・ホール(フィラデルフィア) ※音源:米COLUMBIA ML-4316*、ML-4400 ◎収録時間:77:00 Cover Art Design By Alex Steinweiss |
| “年々熟成を重ねたオーマンディ・サウンドの原点がここに!” | ||
|
||
 Treasures TRE-099(1CDR) |
レオポルド・ルートヴィヒのマーラー マーラー:交響曲第9番 |
レオポルド・ルートヴィヒ(指)LSO 録音:1959年11月17-20日 ロンドン・ウォルサムストー・アセンブリー・ホール(ステレオ) ※音源:英W.R.C SCM-16~17 ◎収録時間:75:36 |
| “露骨な感情表現から開放した「マラ9」の世界初のステレオ録音!” | ||
|
||
| ORQUESTA Y CORO NACIONALES DE ESPANA 843655-2740033 (1CD) |
コープマンの「宗教改革」&「未完成」 メンデルスゾーン:交響曲第5番「宗教改革」 シューベルト:交響曲第8番「未完成」 |
スペイン国立O トン・コープマン(指) 録音:2014年6月、国立音楽堂、マドリード、スペイン |
|
||
 BERLINER PHIL. KKC-9137 (4CD+2Bluray) 税込定価 |
シベリウス:交響曲全集 ■CD1 1-4. 交響曲第1番(37’39) 5-8.交響曲第2番(43’12) CD2 1-3.交響曲第3番(28’17) 4-7.交響曲第4番(36’50) ■CD3 1-3.交響曲第5番(30’32) ■CD4 1-4.交響曲第6番(29’13) 5-8.交響曲第7番(21’48) ■Disc1 ブルーレイ・ディスク・オーディオ 交響曲第1-7番(24bit/96kHz) 2.0 PCM Stereo 24bit/96kHz 5.0 DTS-HD MA 24bit/96kHz 227 分 ボーナス・ビデオ~サー・サイモン・ラトル、シベリウスを語る(ドイツ語字幕のみ)/58 分 ■Disc2 ブルーレイ・ディスク・ビデオ 交響曲第1-7番(HD Video) 画面:Full HD 1080/60i 16:9 音声:2.0 PCM Stereo、5.0 DTS-HD MA リージョン:All/297 分 ボーナス・ビデオ~ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団のデジタル・コンサート・ホールについて |
サー・サイモン・ラトル(指)BPO 録音:CD & BDA: 2014年12月18-20日(5番) 2015年1月28日~2月6日(1~4番) 2015年2月7~9日(5~7番) VIDEO: 2015年2月6日(1、2番) 2015年2月7日(3、4番) 2015年2月8日(5~7番) 録音場所:フィルハーモニー、ベルリン [24bit/192kHz録音] ■特典 スタジオ・マスター・クオリティーの音源(24bit/192kHz)をダウンロードできる、クーポンコードを封入 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団のデジタル・コンサート・ホールの7日間無料視聴コードを封入 ※日本語帯・解説付 |
|
||
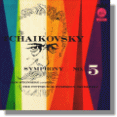 Treasures TRT-006(1CDR) |
スタインバーグのチャイコフスキー チャイコフスキー:弦楽セレナード 交響曲第5番ホ短調Op.64* |
ウィリアム・スタインバーグ(指) ピッツバーグSO 録音:1953年11月30日&1954年4月14日シリア・モスク・ピッツバーグ、1953年頃* ※音源:米Capitol P8290、英mfp MFP-2008* ◎収録時間:75:08 |
| 潔癖でありながら綺麗事ではないフレージングの意味深さ!” | ||
|
||
 Treasures TRE-079(1CDR) |
ル・コント~ラロ&ベルリオーズ ラロ:歌劇「イスの王様」序曲 ベルリオーズ:「ベンヴェート・チェルリーニ」序曲# 「ファウストの劫罰」~ラコッツィ行進曲/妖精の踊り 幻想交響曲Op.14* |
ピエール=ミッシェル・ル・コント(指) パリ・オペラ座O(パリ国立歌歌劇場O) フランクフルトRSO# 録音:1950年代中頃(ステレオ) ※音源:仏Convert Hall SMS-2911、仏Prestige de la Musique SR-9648* ◎収録時間:77:10 |
| “ラロの管弦楽法の凄さを体当たりで表現した奇跡的名演!” | ||
|
||
 BERLINER PHIL. KKC-5461(2SACD) 日本先行販売 税込定価 |
シューマン:交響曲全集 ■デジタル・コンサートホール ベルリン・フィルの映像配信サービス「デジタル・コンサートホール」を48時間無料視聴できるチケット・コードが封入されています。 |
サー・サイモン・ラトル(指)BPO 録音:2013年2月14-16日(第3番)、2月20-22日(第2番)、10月31日-11 月2日(第1&第4番)ベルリン・フィルハーモニー SACDマステリング:オプティマル・メディア デジパック仕様 |
|
||
| SWEDISH SOCIETY SCD-1161(1CD) |
シベリウス:交響曲第1番ホ短調 Op.39 交響曲第7番ハ長調 Op.105 |
ウプサラ室内O パウル・マギ(指) 録音:2010年3月11日、2011年5月12日、ライヴ、ウプサラ・コンサート&コングレス・コンサートホール、ウプサラ、スウェーデン |
|
||
 Treasures TRT-007(1CDR)  ジョージ・ハースト |
ジョージ・ハースト~シューベルト&チャイコフスキー シューベルト:交響曲第8番「未完成」* チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調 |
ジョージ・ハースト(指) デンマーク王立O*、 ハンブルク・プロ・ムジカ 録音:1959年頃(ステレオ) ※音源:英SAGA XID-5029*、STXID-5381 & STXID-5046 ◎収録時間:66:25 |
| “ラトルに指揮者になるきっかけを与えた、ジョージ・ハーストの剛毅な芸風!” | ||
|
||
| DACAPO MAR-6.200003(4SACD) |
ニールセン:交響曲&協奏曲集 《CD1…6.220623》 1-4.交響曲第3番ニ短調「ひろがりの交響曲」Op.27(1910-1911) 5-8.交響曲第2番ロ短調「四つの気質」Op.16(1901-1902) 《CD2…6.220624》 1-4.交響曲第4番「滅ぼし得ざるもの(不滅)」 Op.29(1914-1916) 5-8.交響曲第1番ト短調Op.7(1889-1894) 《CD3… 6.220625》1-6.交響曲第5番Op.50(1920-1922) 7-10.交響曲第6番「素朴な交響曲」(1924-1925) 《CD4…6.220556》 1-3.ヴァイオリン協奏曲Op.33(1911-1912) 4-5.フルート協奏曲(1926) 6-8.クラリネット協奏曲(1928) |
アラン・ギルバート(指)NYO エリン・モーリー(S)…CD1.1-4/ヨシュア・ホプキンス(Br)…CD1.1-4/ロベール・ランジュヴァン(Fl)…CD4/アンソニー・マックギル(Cl)…CD4/ニコライ・ズナイダー(Vn)…CD4 録音:《CD1》2011年6月14-16日…1-4、2011年1月27-29日…5-8 《CD2》2014年3月12-15日 《CD3》2014年10月1-3日 《CD4》2012年10月10-13日…1-5,2015年1月7-10.13日…6-8ニューヨーク,リンカーン・センター,エブリー・フィッシャー・ホール |
|
||
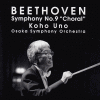 オクタヴィア OVCL-00576(1SACD) 2015年8月21日発売 |
ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 | 宇野功芳(指)大阪SO 神戸市混声Cho 丸山晃子(S)、八木寿子(A) 馬場清孝(T)、藤村匡人(T) 録音:2015年7月4日 いずみホール・ライヴ |
| “宇野氏が悩み続けた「第9」の理想像が遂に結実!” | ||
|
||
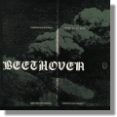 Treasures TRE-073(1CDR) |
スワロフスキーのベートーヴェン ベートーヴェン:「レオノーレ」序曲第3番* 交響曲第8番ヘ長調Op.93 交響曲第2番ニ長調Op.36 |
ハンス・スワロフスキー(指) ウィーン国立歌劇場O 録音:1950年代中期(全てモノラル) ※音源:W.R.C TW-108、ORBIS 21224* ◎収録時間:72:52 |
| “スワロフスキーの指揮者としてのセンスを痛感する二大名演!” | ||
|
||
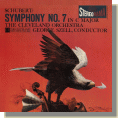 Treasures TRE-072(1CDR) |
ジョージ・セル/エピック録音名盤集1 モーツァルト:ディヴェルティメント第2番K.131 シューベルト:交響曲第9番ハ長調「グレート」* |
ジョージ・セル(指) クリーヴランドO 録音:1963年4月20日、1957年11月1日* 共にステレオ ※音源:米EPIC BC-1273(Blue)、BC-1009(Gold STEREORAMA)* ◎収録時間:72:45 |
| “CDでは伝わらないセルのパッションとスケール感!” | ||
|
||
| BERLINER PHIL. KKC-5445(8CD+Bluray) 国内仕様 税込定価  |
アーノンクール&BPO~シューベルト・エディション(交響曲全曲、ミサ曲、オペラ) 交響曲第1番ニ長調 交響曲第3番ニ長調 交響曲第7番ロ短調 D759『未完成』 交響曲第2番変ロ長調 D125 交響曲第4番ハ短調 D417『悲劇的』 交響曲第5番変ロ長調 D485 交響曲第6番ハ長調 D589 交響曲第8番ハ長調 D944『グレート』 ミサ曲第5番 変イ長調# ミサ曲第6番 変ホ長調* 歌劇「アルフォンソとエストレッラ」 ■Blu-ray アーノンクールのインタビュー映像 |
ルバ・オルゴナソヴァ(S)# ビルギット・レンメルト(A)# クルト・ストライト(シュトライト)(T)# クリスティアン・ゲルハーヘル(Bs)# ドロテア・レッシュマン(S)* ベルナルダ・フィンク(A)* ヨナス・カウフマン(T)* クリスティアン・エルスナー(T)* クリスティアン・ゲルハーヘル(Bs)* ドロテア・レッシュマン(ソプラノ/エストレッラ) クルト・ストライト(シュトライト)(テノール/アルフォンソ) クリスティアン・ゲルハーヘル(バス/フロイラ) ヨッヘン・シュメッケンベッヒャー(バリトン/マウレガート) ハンノ・ミュラー=ブラッハマン(バリトン/アドルフォ) ベルリン放送Cho ニコラウス・アーノンクール(指)BPO 録音:2003年10月23-25日[交響曲第3&4番] 2004年4月22-24日[交響曲第1番、ミサ曲第6番] 2004年12月2-5日[交響曲第6&7番] 2005年4月14-16日[交響曲第2番、ミサ曲第5番] 2005年10月8-9日[アルフォンソとエストレッラ] 2006年3月22-24日[交響曲第5&8番] 録音場所:ベルリン、テルデックス・スタジオ(セッション) ■Blu-ray (2.0 PCMステレオ 24bit/48kHz & 5.0DTS-HD MA 24bit/48kHz) 38分/収録:2014年12月19日、ザンクト・ゲオルゲン、オーストリア 画面:Full HD 1080/60i 16:9 リージョン:All ■ダウンロード・コード ・上記のCD8枚分のハイレゾ音源をダウンロードできる無料チケットコードが封入 (24bir/48kHz) ■デジタル・コンサートホール~7日間無料視聴バウチャー ※日本語字幕付 |
|
||
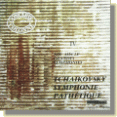 Treasures TRE-067(1CDR) |
デルヴォー/チャイコフスキー:「悲愴」他 グリンカ:歌劇「皇帝に捧げた命 」序曲 チャイコフスキー:「エフゲニ・オネーギン」~ワルツ スラブ行進曲 ボロディン:交響詩「中央アジアの草原にて」 チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」* |
ピエール・デルヴォー(指) アムステルダム・フィルハーモニック協会O コロンヌO* 録音:1959年、1961年12月17日ライヴ*(全てステレオ) ※音源:米Audio Fodelity FCS-50025、DUCRETET-THOMSON SCC-504* ◎収録時間:77:40 |
| “陰鬱さをリセットして壮絶な音のドラマとして描いた驚異の「悲愴!” | ||
|
||
 Treasures TRE-068(1CDR) |
若き日のマゼール/シューベルト&ブラームス シューベルト:交響曲第2番 ブラームス:交響曲第3番* |
ロリン・マゼール(指)BPO 録音:1962年3月、1959年1月* イエス・キリスト教会(共にステレオ) ※音源:独DGG SLPM-138790、独OPERA st-76845* ◎収録時間:61:46 |
| “決して演出ではない、純粋な表現意欲の爆発!” | ||
|
||
 Treasures TRE-069(2CDR) ★ |
スワロフスキー/「運命」&「田園」 ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」 交響曲第6番ヘ長調Op.68「田園」 |
ハンス・スワロフスキー(指) ウィーン国立歌劇場O 録音:1950年代中頃(Disc1=擬似ステレオ、Disc2=モノラル) ※音源:仏VEGA B400 ◎収録時間:75:50 |
| “作為を用いず作品の真価を着実に引き出すスワロフスキーの至芸!” | ||
|
||
.gif) BERLINER PHIL. KKC-8626 (12CD+Book) 限定盤 税込定価  |
ベルリン・フィル/IM TAKT DER ZEIT(時代のタクト) (1)ワーグナー:「パルジファル」からの組曲 リスト:ハンガリー狂詩曲第1番* ベルリオーズ:序曲「ローマの謝肉祭」 * (2)ブルックナー:交響曲第7番 (3)モーツァルト:アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク ウェーバー:「プレツィオーザ」序曲 シューベルト:交響曲第8番「未完成」 リスト:「タランテラ」 R.シュトラウス:「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯」 スッペ:「軽騎兵」序曲 (4)ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」 ラヴェル:「ダフニスとクロエ」第2組曲* ベートーヴェン:交響曲第1番# (5)ドビュッシー:「遊戯」 メンデルスゾーン:交響曲第4番「イタリア」* ミヨー:フランス組曲# (6)ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 (7)チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」 (8)マーラー:交響曲第6番「悲劇的」 (9)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番 交響曲第7番イ長調 (10)モーツァルト:行進曲 ニ長調 K.249 セレナード第7番「ハフナー」 (11)ハイドン:交響曲第82番「熊」 ショスタコーヴィチ:交響曲第15番* (12)バッハ:管弦楽組曲第1番 ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲ニ短調 BWV.1060 管弦楽組曲第3番ニ長調 |
オーケストラは全てBPO (1) アルフレート・ヘルツ(指) 録音:1913年9月12,13,15,16日、ベルリン(モノラル) アルトゥール・ニキシュ(指)* 録音:1920年、ベルリン(モノラル)* (2)ヤッシャ・ホーレンシュタイン(指) 録音:1928年ベルリン(モノラル) (3)エーリヒ・クライバー(指) 録音:1930-35年ベルリン (モノラル) (4)ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) 録音:1943年6月30日ベルリン (モノラル/ライヴ)、1944年3月20-22日、ベルリン(モノラル/ライヴ)*、1954年9月19日、ベルリン(モノラル/ライヴ)# (5)セルジウ・チェリビダッケ(指) 録音:1948年3月20日ベルリン・フィルハーモニー(モノラル)、1950年1月20日ベルリン・フィルハーモニー(モノラル)*、1951年3月31日ベルリン・フィルハーモニー(モノラル)# (6)ヘルベルト・フォン・カラヤン(指) グンドゥラ・ヤノヴィッツ(S)、ジークリンデ・ヴァーグナー(C.A)、ルイジ・アルヴァ(T)、オットー・ヴィーナー(Br)、聖ヘドヴィヒ教会Cho、RIAS室内Cho 録音:1963年10月15日ベルリン、フィルハーモニー(ステレオ/ライヴ) (7)ダヴィッド・オイストラフ(指) 録音:1972年3月16日ベルリン・フィルハーモニー(ステレオ/ライヴ) (8)サイモン・ラトル(指) 録音:1987年11月14,15日ベルリン・フィルハーモニー(ステレオ/ライヴ) (9)ダニエル・バレンボイム(指、P) 録音:1989年11月12日ベルリン・フィルハーモニー(デジタル/ライヴ) (10)クラウディオ・アバド(指) ライナー・クスマウル(Vn) 録音:1996年12月13-15日ベルリン・フィルハーモニー(デジタル/ライヴ) (11)クルト・ザンデルリング(指) 録音:1997年1月9日ベルリン、フィルハーモニー(デジタル/ライヴ)、1999年3月16日ベルリン、フィルハーモニー(デジタル/ライヴ)* (12)ニコラウス・アーノンクール(指) トーマス・ツェートマイヤー(Vn) アルブレヒト・マイヤー(Ob) 録音:2002年10月5日ベルリン・フィルハーモニー(デジタル/ライヴ) ★豪華写真集(全80ページ) ★日本限定特典:ベルリン・フィル・オリジナル刻印付きアーティスト生写真~フルトヴェングラー、カラヤン、アバド、ラトルのいずれかの指揮者の写真が付属します。(種類は選べません) ★商品サイズ:H410mm×W285mm×D16mm |
|
||
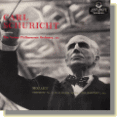 Treasures TRE-059(1CDR) |
シューリヒト~モーツァルトの「ハフナー」 モーツァルト:交響曲第35番「ハフナー」 セレナード第7番ニ長調 K.250「ハフナー」* |
カール・シューリヒト(指) VPO、シュトゥットガルトRSO* 録音:1956年6月3-6日、1962年12月* (全てモノラル) ※音源:KING RECORD LC-4、MOVIMENT MUSICA 01-067* ◎※収録時間:72:19 |
| “神の領域!これこそがシューリヒトの究極の二大名演!” | ||
|
||
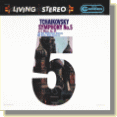 Treasures TRT-005(1CDR) |
グリューナー=ヘッゲ/グリーグ&チャイコフスキー グリーグ:「ペール・ギュント」第1組曲Op.46 「ペール・ギュント」第2組曲Op.55 チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調Op.64* |
オッド・グリューナー=ヘッゲ(指) オスロPO 録音:1959年、1958年6月*(全てステレオ) ※音源:RCA CCV-5019(UK)、Camden SND-5002(UK) ◎※収録時間:78:28 |
| “静かな闘志と確信がセンチメンタルなチャイコフスキーを払拭!” | ||
|
||
 Treasures TRE-053(1CDR) |
ヨッフム/ハイドン&シューベルト ハイドン:交響曲第98番変ロ長調 Hob.I:98 シューベルト:交響曲第9番「グレート」* |
オイゲン・ヨッフム(指) BPO、バイエルンRSO* 録音:1962年5月、1958年2月*(共にステレオ) ※音源:独DG SLPM-138823、英HELIODOR 89511* ◎※収録時間:77:33 |
| “2人の作曲家の人間的な佇まいを生かした名解釈!” | ||
|
||
 Treasures TRE-051(1CDR) |
カンテルリのステレオ名盤集Vol.1 モーツァルト:音楽の冗談K.522 交響曲第29番イ長調 K.201 ベートーヴェン:交響曲第7番イ長調* |
グィド・カンテルリ(指) フィルハーモニアO 録音:1955年8月18日 、1956年6月2日*、1956年5月29-31日 (全てステレオ) ※音源:TRIANON 2C027-03748(FR)、2C027-01214(FR)* ◎※収録時間:75:41 |
| “作品の力を信じるカンテルリの才能と勇気!” | ||
|
||
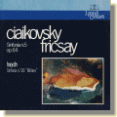 Treasures TRT-004(1CDR) |
ハイドン:交響曲第100番「軍隊」 チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調Op.64* |
フェレンツ・フリッチャイ(指) ベルリンRIAS響、ベルリンRSO* 録音:1954年5月4日、1957年1月24日ライヴ* ※音源:伊LONGANESI PERIODICI GCL-70、GCL-38* ◎※収録時間:66:19 |
| “安定感も燃焼度も申し分なし!フィリッチャイの比類なきロマンチシズム!” | ||
|
||
| DACAPO MAR-6.220625(1SACD) |
ニールセン:交響曲第5番Op.50 交響曲第6番「素朴な交響曲」 |
アラン・ギルバート(指)NYO 録音:2014年10月1-3日ニューヨーク,リンカーン・センター,エイヴリー・フィッシャー・ホール |
|
||
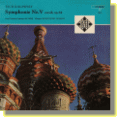 Treasures TRT-003(1CDR) |
チャイコフスキー:フランチェスカ・ダ・リミニ 交響曲第5番ホ短調Op.64* |
コンスタンティン・イワーノフ(指) ソビエト国立SO 録音:1955年、1956年*(共にモノラル) ※音源:Melodiya C-1024221-009、独TELEFUNKEN LT-6624* ◎※収録時間:69:23 |
| “ローカル色に安住せず、入念にニュアンスを注入したイワーノフの知られざる力量!” | ||
|
||
 Treasures TRE-043(1CDR) |
クレンペラー~シューベルト:交響曲集 交響曲第8番「未完成」 交響曲第9番「グレート」* |
オットー・クレンペラー(指) フィルハーモニアO 録音:1963年2月4日-6日、1960年11月16-19日* キングスウェイ・ホール、ロンドン(共にステレオ) ※音源:EMI 29-04604、29-04261* ◎※収録時間:77:25 |
| “自ら歌うことは拒絶し、聴き手の中のシューベルトを覚醒!” | ||
|
||
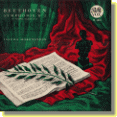 Treasures TRE-042(1CDR) |
ホーレンシュタイン~ベートーヴェン:「英雄」他 ベートーヴェン:「エグモント」序曲 「プロメテウスの創造物」序曲 交響曲第3番変ホ長調「英雄」* |
ヤッシャ・ホーレンシュタイン(指) ウィーン・プロ・ムジカO 録音:1953年 ※音源:仏VOV PL-8020、独Opera 1015* ◎※収録時間:68:06 |
| “異常暴発!苦悶を発散できないホーレンシュタインだからこそ成し得た凄演!” | ||
|
||
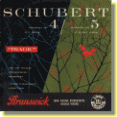 Treasures TRE-036(1CDR) |
ウォーレンステイン~シューベルト他 ベルリオーズ:「ファウストの劫罰」~ラコッツィ行進曲/鬼火のメヌエット/妖精の踊り スメタナ:交響詩「モルダウ」 シューベルト:交響曲第5番* 交響曲第4番ハ短調* |
アルフレッド・ウォーレンステイン(指) ロスアンジェルスPO 録音:1953年頃、1950年代中頃*(全てモノラル) ※音源:英Brunswick AXTL-1063、AXTL-1059* ◎※収録時間:78:47 |
| “シューベルトを堂々たるシンフォニストに引き上げた画期的名演!” | ||
|
||
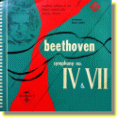 Treasures TRE-038(1CDR) |
フランツ・アンドレのベートーヴェン ベートーヴェン:交響曲第4番 交響曲第7番* |
フランツ・アンドレ(指) ベルギー国立RSO 録音:1953年10月2日、1952年10月3日* ※音源:日KING RECORD MPT-45、英Telefunken GMA-7 ◎※収録時間:64:11 |
| “小品集だけではわからない、フランツ・アンドレの度量の広い芸術力!” | ||
|
||
| MN Records MNRCD-136(1CD) |
マイケル・ナイマン:交響曲第11番「ヒルズボロ・メモリアル」 | キャスリン・ラッジ(Ms) リヴァプール・フィルハーモニック・ユースCho ヨセフ・ヴァンサン(指) ロイヤル・リヴァプールPO 録音:2014 年 |
|
||
| Ai Qualia NKB-105(1SACD) SACD 4.0 Surround ※SACD Hybridのみのアルバム NKB-405 (1SACD+DVD-ROM) |
「運命」と「こうもり」序曲 ●DISC 1 (SACD/CD Hybrid Disc, CD STEREO / SACD STEREO / SACD 4.0 Surround) ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」 J・シュトラウス:「こうもり」序曲 ワルツ「芸術家の生涯」 ●DISC 2 (DVD-ROM Disc) 《FLAC data (24bit/192kHz STEREO》 ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」 J・シュトラウス:「こうもり」序曲 ワルツ「芸術家の生涯」 《DSF data (1bit/5.6MHz STEREO) [ワンポイントマイクによる収録》 J・シュトラウス:喜歌劇「こうもり」序曲 ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」~第4楽章 |
北村憲昭(指)スロバキアPO 録音:2013年2月16-17日/スロバキア・フィルハーモニーホール(ブラチスラヴァ) |
|
||
| BELVEDERE BELVED-10152(2CD) |
カラヤン&ハスキル/モーツァルト作品集 交響曲第39番 変ホ長調 K543 ピアノ協奏曲 ニ短調 KV 466 ディヴェルティメント第15番 変ロ長調「ロードロン・セレナードII」 KV 287[抜粋] |
ヘルベルト・フォン・カラヤン(指) フィルハーモニアO クララ・ハスキル(P) 録音:1956年1月28日/モーツァルト週間音楽祭(モノラル・ライヴ)/ザルツブルク・モーツァルテウム音楽院大ホール |
|
||
| BELVEDERE BELVED-10147(1CD) |
モーツァルト:交響曲第40番 ト短調 KV.550 交響曲第39番 変ホ長調 KV.543 |
シャーンドル・ヴェーグ(指)VPO 録音:1992年1月30日/モーツァルト週間音楽祭(ステレオ・ライヴ)/ザルツブルク・祝祭劇場 |
|
||
 Treasures TRE-031(1CDR) |
ニコライ・マルコ~ボロディン&チャイコフスキー チャイコフスキー:大序曲「1812年」 ボロディン:交響曲第3番(未完)* 交響曲第2番ロ短調# |
ニコライ・マルコ(指) フィルハーモニアO 録音:1953年2月6日、1955年9月24日*、1955年9月23日#(全てモノラル) ※音源:HMV XLP-30010、M.F.P MFP-2034*# ◎※収録時間:61:12 |
| “土俗性を煽らず一途な共感で描き切ったボロディンの素晴らしさ!” | ||
|
||
 Treasures TRE-027(1CDR) |
ホーレンシュタイン~プロコフィエフ作品集 交響曲第1番ニ長調「古典」 交響組曲「キージェ中尉」* 交響曲第5番変ロ長調Op.100 |
ヤッシャ・ホーレンシュタイン(指) コロンヌO、パリPO* 録音:1954年、1955年*(全てモノラル) ※音源:VOX PL-9170、PL-9180* ◎※収録時間:71:24 |
| “ホーレンシュタインの「陰」な性質がプロコフィエフと完全合体!” | ||
|
||
| Intergroove IGC-008-2(1CD) |
プーシキンの音楽 チャイコフスキー:歌劇「エフゲニー・オネーギン」~ポロネーズ/ワルツ ミャスコフスキー:交響曲第10番ヘ短調 「青銅の騎士」 スヴィリードフ:吹雪 |
アレクサンドル・ティトフ(指) サンクトペテルブルク・カメラータ |
|
||
 Treasures TRE-023r(1CDR) |
ベートーヴェン:「エグモント」序曲 ハイドン:交響曲第94番「驚愕」* ベートーヴェン:交響曲第7番# |
レオポルド・ルートヴィヒ(指) バンベルクSO、LSO* 録音:1950年代後半(全てステレオ) ※音源:独PARNASS 61-424、米VOX STPL-512510*、独OPERA ST-1987# ◎※収録時間:69:09 |
| “自然体を通しながら、作品の核心を外さない名人芸!” | ||
|
||
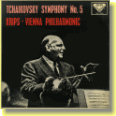 Treasures TRT-001(1CDR) |
ハイドン:交響曲第99番 チャイコフスキー:交響曲第5番* |
ヨーゼフ・クリップス(指)VPO 録音:1957年9月9-14日、1958年9月15-16*(共にステレオ) ※音源:DECCA SXL-2098 , SXL-2109* |
| “宇野功芳氏激賞の意味を真に伝える、極上フラット盤の威力!” | ||
|
||
| DACAPO MAR-6.220624(1SACD) |
ニールセン:交響曲第4番「不滅」 交響曲第1番Op.7 |
アラン・ギルバート(指)NYO 録音:2014年3月12-15日ニューヨーク,リンカーン・センター,エイヴリー・フィッシ ャー・ホール |
|
||
 WEITBLICK SSS-0164(1CD) |
ベルリオーズ:幻想交響曲 デュカス:魔法使いの弟子* |
セルジュ・チェリビダッケ(指) スウェーデンRSO 録音:1969 年11 月23 日ストックホルム・コンサートホール、1968年9月7日ヴェステラス・コンサート・ホール* (共にステレオ・ライヴ) |
| “安易な怪奇趣味とは一線を画すチェリビダッケ美学を完全敢行!” | ||
|
||
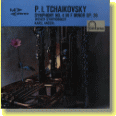 Treasures TRE-022(1CDR) |
アンチェル&ウィーン響~チャイコフスキー チャイコフスキー:スラブ行進曲* 大序曲「1812年」# 交響曲第4番ヘ短調Op.36 弦楽セレナード~ワルツ* |
カレル・アンチェル(指)ウィーンSO 録音:1958年3月29日-4月2日*、1958年11月-12月(*以外) 全てステレオ ※音源:Fomtana 875.011 (SCFL-103)、SFON-7519#、875.002* ◎※収録時間:67:52 |
| “潔癖さの極み!土臭さを排したアンチェル芸術の結晶!” | ||
|
||
 WEITBLICK SSS-0162(1CD) |
スヴェトラーノフのモーツァルト 交響曲第40番ト短調K.550 交響曲第41番ハ長調「ジュピター」* |
エフゲニ・スヴェトラーノフ(指) スウェーデンRSO 録音:1988年9月10日、1993年9月18日(共にライヴ・デジタル) ベルワルド・ホール* ※英語、日本語、ドイツ語によるライナーノート付 |
| “数々のロシア音楽の名演を築いたスヴェトラーノフの音楽性の源がここに!” | ||
|
||
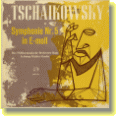 Treasures TRT-002(1CDR) |
チャイコフスキー:弦楽セレナード* 交響曲第5番ホ短調Op.64 |
ワルター・ゲール(指) ローマPO*、フランクフルト室内O 録音:1955頃(ステレオ) ※音源:英CONCERT HALL SMSC-2188*、仏 PRESTIGE DE LA MUSIQUE SR-9629、日CONCERT HALL SM-6108 ◎※収録時間:76:04 |
| “オケのイタリア気質と相まった濃厚な節回しで翻弄する「チャイ5」!” | ||
|
||
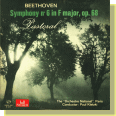 Treasures TRE-013(1CDR) |
パウル・クレツキ~ベートーヴェン:「運命」「田園」 ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」 交響曲第6番「田園」* |
パウル・クレツキ(指) バーデン=バーデン南西ドイツRSO フランス国立放送局O* 録音:1961年頃(全てステレオ) ※音源:英Concert Hall SMS-2341、SMS-2239* ◎※収録時間:72:19 |
| “フランス・オケの起用が大正解!「田園」の魅惑のニュアンス!!” | ||
|
||
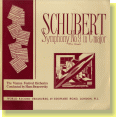 Treasures TRE-014(1CDR) |
シューベルト:「ロザムンデ」~序曲/バレエ曲第1番/間奏曲第3番/バレエ曲第2番 交響曲第9番ハ長調「グレート」* |
ハンス・スワロフスキー(指) ウィーン祝祭O(ウィーン国立歌劇場O) 録音:1950年代中頃、1955年1月*(全てモノラル) ※音源:WORLD RECORD CLUB T-25、TT-17* ◎※収録時間:75:36 |
| “スワロフスキーの穏健なイメージを払拭する、テンポに込めた強い信念!” | ||
|
||
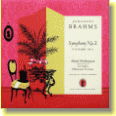 Treasures TRE-020(1CDR) |
モーツァルト:交響曲第35番「ハフナー」 スメタナ:「売られた花嫁」*~序曲/ポルカ/フリアント/道化師の踊り ブラームス:交響曲第2番# |
アルフレッド・ウォーレンステイン(指) ロスアンジェルスPO 録音:1955年頃、1953年頃*(全てモノラル) ※音源:米MUSIC APPRIECIATION RECORDS MAR-5613、英Brunswick AXTL-1063*、英WORLD EECORD CLUB T-6# ◎※収録時間:71:39 |
| “作品の生命力を徹底抽出するウォーレンステインの巧みな棒!” | ||
|
||
 Treasures TRE-012(1CDR) |
J・クリップス~ハイドン&ブラームス ハイドン:交響曲第94番「驚愕」* ブラームス:交響曲第1番ハ短調 |
ヨーゼフ・クリップス(指)VPO 録音:1957年9月9-14日*、1956年10月7-8日(共にステレオ) ※音源:DECCA SXL-2098*、LONDON STS-15144 ◎※収録時間:65:18 |
| “鎧で武装した演奏では味わえない音楽のエッセンス!” | ||
|
||
 BMC BMCCD-188(1CD) |
マーラー:交響曲第1番「巨人」(花の章つき) | ゾルタン・コチシュ(指) ハンガリー国立PO 録音:2004年2月29日/3月30日(フランツ・リスト音楽院コンサート・ホール(ライヴ) |
| “病的ニュアンスを一掃!青春讃歌「巨人」の瑞々しさ!” | ||
|
||
 Linn CKD-450(2SACD) |
シューマン:交響曲全集 交響曲第1番変ロ長調Op.38「春」 交響曲第2番ハ長調Op.61 交響曲第3番変ホ長調Op.97「ライン」 交響曲第4番ニ短調Op.120(1851年版) |
ロビン・ティチアーティ(指) スコットランド室内O 録音:2013年11月25日、26日、30日&12月1日-3日パース・コンサート・ホール(イギリス) |
|
||
 Treasures TRE-003(1CDR) |
ベートーヴェン:序曲「コリオラン」 序曲「レオノーレ」第3番 交響曲第3番「英雄」* |
フランツ・バウアー=トイスル(指) ケルンRSO 録音:1950年代末(ステレオ) ※音源:独PARNASS 75767、61421* ◎収録時間:73:12 |
| “ワインガルトナーへのオマージュとして響く、史上最優美の「英雄」!” | ||
|
||
 Treasures TRE-005(1CDR) |
ベートーヴェン:「プロメテウスの創造物」序曲* 交響曲第9番「合唱付き」 |
アルトゥール・ローター(指) ベルリンSO*、ハンブルクPO ハンブルク・ジングアカデミー エディット・ラング(S)、 マリア・フォン・ロスヴァイ(A) ワルター・ギーズラー(T) フランツ・クラス(Bs) 録音:1960年頃(ステレオ) ※音源:独PARNASS 61-423,424 ◎収録時間:70:38 |
| “音圧ではなく風格で聴かせる高らかなドイツ精神!!” | ||
|
||
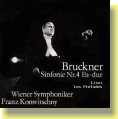 Treasures TRE-007(1CDR) |
リスト:交響詩「前奏曲」 ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」 |
フランツ・コンヴィチュニー(指) ウィーンSO 録音:1961年(ステレオ) ※音源:独PARNASS 61438、70003* ◎収録時間:76:46 |
| “「素朴」の一言で片付けられない、美しい響きの融合!” | ||
|
||
 TRE-009 |
ビゼー:「アルルの女」組曲より 前奏曲/メヌエット/カリヨン/田園曲/間奏曲/ファランドール メンデルスゾーン:「真夏の夜の夢」#~序曲/夜想曲/スケルツォ 交響曲第4番イ長調「イタリア」Op.90* |
ハインツ・ワルベルク(指) フィルハーモニアO 録音:1960年11月29&30日-12月2日、1960年11月28日*、1960年11月29日# (全てステレオ) ※音源:伊EMI SQIMX7003、英EMI SXLP20037#,* ◎収録時間:79:29 |
| “また聴きたくなる魅力!ワルベルクの愚直さが生んだ至純のニュアンス!” | ||
|
||
| Sono Luminus DSL-92177 (CD+Blu-rayAudio) |
モハメド・フェイルーズ:作品集 タハリール 交響曲第3番「詩と祈り」 |
デヴィッド・クラカウアー(Cl) サーシャ・クック(Ms) デイヴィッド・クラヴィッツ(Br) カリフォルニア大学Cho カリフォルニア大学フィルハーモニー ニール・スタルバーグ(指) <BD> 7.1 24-bit/96kHz-MA,5.1 24-bit/192kHz-MA,2.0 24-bit/192kHz LPCM |
|
||
 fine NF(N&F) NF-25802(1CD) 税込定価 |
チャイコフスキー:交響曲第5番 | 西脇義訓(指) デア・リング東京オーケストラ 録音:2013年4月16-18日所沢市文化センター・ミューズ・アークホール |
|
||
 BERLINER PHILHARMONIKER RECORDINGS KKC-9083 (Bluray+2CD) Download Code、 Digital Concert Hall Voucher付 初回特典付 税込定価 |
シューマン:交響曲全集 ■CD1 交響曲第1番《春》 5-8交響曲第4番 ■CD2 交響曲第2番 5-9交響曲第3番7《ライン》 ■ダウンロード・コード 交響曲第1-4番のオリジナル・ハイレゾ音源(192kHz/24bit) をダウンロードするためのURLとそのパスワードが封入されています。 ■Blu-ray 交響曲第1-4番 このBlu-rayディスクには96kHz/24bitの音声トラックとコンサート映像の両方のコンテンツが収録されています。 ■ボーナス・ビデオ *サー・サイモン・ラトル、シューマンを語る *録音製作の舞台裏 *ベルリン・フィルの「デジタル・コンサートホール」について ■デジタル・コンサートホール ベルリン・フィルの映像配信サービス「デジタル・コンサートホール」を7日間無料視聴できるチケット・コードが封入されています。 |
サイモン・ラトル(指)BPO 録音:2013年2月14-16日(第3番)、2月20-22日(第2番)、10月31日-11月2日(第1&第4番) ■Blu-ray ○ブルーレイ・ディスク・オーディオ 96kHz/24bit 2.0 PCM Stereo 5.0 DTS-HD MA /125mm ○ブルーレイ・ディスク・ビデオ 画面:Full HD 1080/60i 16:9 音声:2.0 PCM Stereo 5.0 DTS-HD Master Audio リージョン:All/140mm ■ボーナス・ビデオ 言語:英語・ドイツ語/35mm ※日本語解説付き ★初回特典 初回購入者特典として、商品に貼付されているステッカーを貼って、応募いただくと「ベルリン・フィルの豪華年間プログラム」が抽選で30名様に当たります。(応募期間:2014年7月末日消印まで有効) |
|
||
| Cameo Classics CC-9033CD(1CDR) 【初紹介旧譜】 |
ヤーダースゾーン:交響曲第1番ハ長調 Op.24* パブスト:ピアノ協奏曲変ホ長調 Op.82** ヤーダースゾーン:ピアノ協奏曲第1番ハ短調 Op.89*** |
パナギオティス・トロコプーロス(P)**、 マリウス・ストラヴィンスキー(指)ベラルーシ国立SO*/**、 ワレンティナ・セフェリノワ(P)***、 デニス・ヴラセンコ(指)カレリア国立SO*** 録音:2007年-2008年 ※全曲世界初録音 |
|
||
 Cameo Classics CC-9007CD(1CDR) 【再案内】 |
ストコフスキーの「チャイ5」/プロムス・ライヴ チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調Op.64 同曲のリハーサル風景(約34分) |
レオポルド・ストコフスキー(指) 国際ユース祝祭O 録音年:1973年8月19日 ロイヤル・アルバート・ホール“プロムス” (ステレオ・ライヴ) |
|
||
| Cameo Classics CC-9008CD(1CDR) 【未案内旧譜】 |
バッハ(ストコフスキー編):トッカータとフーガ.ニ短調 ベートーヴェン:交響曲第7番 ムソルグスキー:「ホヴァンシチナ」~第4幕第2場への間奏曲 ストラヴィンスキー:「ペトルーシュカ」組曲 |
レオポルド・ストコフスキー(指) ブカレストRSO 録音:1969年ライヴ |
|
||
 オクタヴィア OVCL-00545(1SACD) 2014年6月25日発売予定 |
小林研一郎&読響/ブラームス交響曲全集シリーズ
Vol.1 ブラームス:交響曲第1番 ハンガリー舞曲集から 第1番、第2番、第4番(ユオン編)、 第5番(シュメリンク編)、 第6番(シュメリンク編)、第10番 |
小林研一郎(指)読売日本SO 録音:2014年4月22、23日 東京芸術劇場 |
|
||
| BOMBA BOMB-033-665(1CD) |
イサーク・シュヴァルツ(1923-2009):交響曲ヘ短調* 映画音楽「カラマーゾフの兄弟」からの組曲+ 3つの正教会聖歌# |
レニングラードPO* アルヴィド・ヤンソンス(指)* ソヴィエト国立映画SO+ エミン・ハチャトゥリアン(指)+ 聖ダニロフ修道院男声cho# 録音:1958年*/1968年(+/#) 発売:2010年 |
|
||
 CRQ Editions CRQCD-080(1CDR) |
ブルックナー:序曲ト短調 交響曲第9番(レーヴェ版) |
チャールズ・アドラー(指) ウィーンSO 録音:1952年 ※音源:米SPA |
| “敬虔さをかなぐり放棄!人間ドラマとして描き切った超激演!!” | ||
|
||
 GRAND SLAM GS-2110(1CD) |
シューベルト:交響曲第9番「ザ・グレート」 「ロザムンデ」序曲 D.644* |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) VPO 録音:1953年8月30日ザルツブルク、フェストシュピールハウス(ライヴ) 1951年1月3、17日ウィーン・ムジークフェラインザール(セッション)* 使用音源:RVC(Japan) RCL 3336、EMI(U.K.) XLP 30097* |
|
||
| OBS PROMETEO OBS-008(1CD) |
イル・マニアティコの肖像 ガエターノ・ブルネッティ(1744-1798):交響曲&アリア集 私にはもう自分がどこにいるのかわからない [Non so piu dov'io sia](ソプラノと管弦楽の為のシーン)L.339* 交響曲第23番ヘ長調 L.312(1783) 聖水曜日の為の第1の哀歌(ソプラノと管弦楽の為の)L.342* 私の宝を盗もうと [Involarmi il mio tesoro] (ソプラノと管弦楽の為のアリア)L.338* チェロ独奏を伴う交響曲第33番ハ短調 |
「イル・マニアティコ」L.322(1780)+ ラケル・アンドゥエサ(S)* セビリャ・バロックO クリストフ・コワン(VC+、指) |
|
||
 GRAND SLAM GS-2109(1CD) |
クレンペラー/本邦初登場1955年ライヴ モーツァルト:交響曲第29番 イ長調 K.201 ベートーヴェン:交響曲第7番 イ長調 Op.92 |
オットー・クレンペラー(指) 北ドイツRSO 録音:1955年9月28日、ハンブルク、ムジークハレ 使用音源:Private archive |
|
||
 Forgotten Records fr-925(1CDR) |
ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 | ハンス・ロスバウト(指) 南西ドイツRSO 録音:1959年6月25日(モノラル放送音源) |
|
||
 WEITBLICK SSS-0150(1CD) |
ベルリオーズ:幻想交響曲 ベートーヴェン:序曲「コリオラン」 |
アルヴィド・ヤンソンス(指) ドレスデンPO 録音:1980年2月28日ドレスデン・クルトゥア・パラスト、ステレオ・ライヴ |
| “主人公の深層心理に徹底的に寄り添った画期的アプローチ!” | ||
|
||
 GEGA NEW GD-380(1CD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲第4番ハ短調Op.43 | エミール・タバコフ(指) ブルガリア国立RSO 録音年月日不詳 STEREO |
|
||
| King International KKC-4014(1SACD) シングルレイヤー 日本語オビ&解説付 ★ |
ブルックナー:交響曲第4番変ホ長調 WAB. 104《ロマンティック》(1878-80年原典版) | ギュンター・ヴァント(指)ミュンヘンPO 録音:2001年9月13、14&15日/ミュンヘン、ガスタイクにおけるライヴ リマスタリング:2013年/ドルマーゲン、THS Studio リマスタリング・エンジニア:ホルガー・ジードラー |
| King International KKC-4015(1SACD) シングルレイヤー 日本語オビ&解説付 ★ |
ブルックナー:交響曲第5番変ロ長調 WAB. 105(1875-78年原典版) | ギュンター・ヴァント(指)ミュンヘンPO 録音:1995年11月29日 & 12月1日/ミュンヘン、ガスタイクにおけるライヴ リマスタリング:2013年/ドルマーゲン、THS Studio リマスタリング・エンジニア:ホルガー・ジードラー |
| King International KKC-4016(1SACD) シングルレイヤー 日本語オビ&解説付 ★ |
ブルックナー:交響曲第6番イ長調 WAB. 106(原典版) | ギュンター・ヴァント(指)ミュンヘンPO 録音:1999年6月24日/ミュンヘン、ガスタイクにおけるライヴ リマスタリング:2013年/ドルマーゲン、THS Studio リマスタリング・エンジニア:ホルガー・ジードラー |
| King International KKC-4017(1SACD) シングルレイヤー 日本語オビ&解説付 ★ |
ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 WAB. 108(1884-90年,ハース版) | ギュンター・ヴァント(指)ミュンヘンPO 録音:2000年9月15日/ミュンヘン、ガスタイクにおけるライヴ リマスタリング:2013年/ドルマーゲン、THS Studio リマスタリング・エンジニア:ホルガー・ジードラー |
 King International KKC-4018(1SACD) シングルレイヤー 日本語オビ&解説付 ★ |
ブルックナー:交響曲第9番ニ短調 WAB. 109(原典版) ハイドン:交響曲第76番変ホ長調 Hob. I:76 |
ギュンター・ヴァント(指)ミュンヘンPO 録音:1998年4月21日(ブルックナー)、1999年6月24日(ハイドン)/ミュンヘン、ガスタイクにおけるライヴ リマスタリング:2013年/ドルマーゲン、THS Studio リマスタリング・エンジニア:ホルガー・ジードラー |
|
||
 オクタヴィア OVCL-00516(2SACD) 2014年2月26日発売 |
マーラー:交響曲第6番「悲劇的」 | エリアフ・インバル(指)東京都SO 録音:2013年11月2日横浜・みなとみらいホール、11月3日東京劇術劇場・ライヴ |
|
||
 Cardellino Record CAR-0001(2CD) |
マーラー:交響曲第2番「復活」 | ガリーナ・コヴァリョーヴァ(S)、 エフゲニヤ・ゴロホフスカヤ(A) ユーリ・テミルカーノフ(指) キーロフ(マリインスキー)劇場O&cho 録音:1980 年 5月(セッション録音)/キーロフ(マリインスキー)劇場(旧レニングラード) |
|
||
 Chandos CHSA-5132(1SACD) |
メンデルスゾーン・イン・バーミンガムVol.1
序曲「フィンガルの洞窟」 交響曲第5番「宗教改革」 交響曲第4番「イタリア」 |
エドワード・ガードナー(指) バーミンガム市SO 録音:2013年10月20日-21日、タウン・ホール(バーミンガム、イギリス) |
|
||
 韓国Nimbus CSM-1034(19CD) |
ハノーヴァー・バンド~Numbus録音集 ■CD1 ベートーヴェン:序曲「コリオラン」 音楽「アテネの廃墟」序曲 音楽「シュテファン王」序曲 6:51 4序曲「レオノーレ」第2番 歌劇「フィデリオ」序曲 6:37 音楽「エグモント」序曲* 8:08 「プロメテウスの創造物」序曲* 随音楽「献堂式」序曲 ■CD2 ベートーヴェン:交響曲第1番 交響曲第2番 ニ長調 op.36 3 ■CD3 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 交響曲第4番 変ロ長調 ■CD4 ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」 交響曲第6番「田園」 ■CD5 ベートーヴェン:交響曲第7番 交響曲第8番ヘ長調 ■CD6 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 ■CD7 モーツァルト:交響曲第40番 バセット・クラリネット協奏曲イ長調 K. 622 アイネ・クライネ・ナハトムジーク K. 525 ■CD8 モーツァルト:交響曲第41番「ジュピター」 ピアノ協奏曲第20番ニ短調 セレナータ・ノットゥルナ.ニ長調 K.239 ■CD9 シューベルト:交響曲第1番ニ長調 D. 82 交響曲第2番 変ロ長調 D. 125 ■CD10 シューベルト:交響曲第8番「未完成」 交響曲第5番変ロ長調 D. 485 交響曲第3番ニ長調 D. 200 ■CD11 シューベルト:交響曲第4番「悲劇的」 交響曲第6番ハ長調 D. 589 ■CD12 シューベルト:交響曲第9番「グレート」 ■CD13 メンデルスゾーン:交響曲第3番「スコットランド」 序曲「フィンガルの洞窟」 序曲「静かな海と楽しい航海」 ■CD14 メンデルスゾーン:交響曲第4番「イタリア」 ピアノ協奏曲第1番ト短調 Op. 25 ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op. 64 ■CD15 ハイドン:ホルン協奏曲第1番ニ長調 ホルン協奏曲ニ長調ハイドン 交響曲第31番ニ長調「ホルン信号」 ■CD16 ハイドン:交響曲第94番「驚愕」 交響曲第95番 ハ短調 L・モーツァルト:おもちゃの交響曲ト長調 ■CD17 ハイドン:交響曲第104番「ロンドン」 交響曲第100番 「軍隊」 ■CD18 ウェーバー:序曲「オイリアンテ」 序曲「オベロン」/序曲「魔弾の射手」 序曲「幽霊の支配者」 舞踏への勧誘 ( ベルリオーズ編) 序曲「アブ・ハッサン」 序曲「ペーター・シュモルとその隣人たち」 ■CD19 ウェーバー:交響曲第1番ハ長調 ホルン小協奏曲 ホ短調 交響曲第2番 ハ長調 |
特記以外、全てロイ・グッドマン(指) ハノーヴァー・バンド ■CD1 モニカ・ハジェット(指)* ■CD2 モニカ・ハジェット(指) ■CD4 モニカ・ハジェット(指)* ■CD6 エイドェン・ハーヒー(S) ジーン・ベイリー(A) アンドルー・マーゲイトロイド(T) マイケル・ジョーン(Bs) オスロ大聖堂聖歌隊 ■CD7 コリン・ローソン(バセットCl) ハノーヴァー・バンド ■CD8 クリストファー・カイト(フォルテ・ピアノ) ■CD14 クリストファー・カイト(フォルテ・ピアノ) ベンジャミン・ハドソン(Vn) ■CD15 アンソニー・ホールステッド(Hrn) |
|
||
 .gif) King International KKC-8014(30CD) ★ |
ORFEO DOR ステレオ名演集 ■CD:1(ORFEOR.100841) ベートーヴェン:交響曲第4番 ■CD:2(ORFEOR.263921) モーツァルト:ピアノ協奏曲第9番 「ジュノーム」 ブラームス:交響曲第1番 ■CD:3(ORFEOR.522991) ベートーヴェン:交響曲第4番 マーラー:さすらう若人の歌 シューマン:交響曲第4番 ■CD:4(ORFEOR.608032) ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 ■CD:5(ORFEOR.608032) チャイコフスキー:交響曲第4番 ■CD:6(ORFEOR.607031) モーツァルト:交響曲第29番 マーラー:亡き子を偲ぶ歌 R.シュトラウス:交響詩「死と変容」 ■CD:7(ORFEOR.264921) シューベルト:交響曲第2番 R.シュトラウス:交響詩「英雄の生涯」 ■CD:8(ORFEOR.587022) モーツァルト:交響曲第41番「ジュピター」 ■CD:9(ORFEOR.587022) ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 ■CD:10(ORFEOR.596031) ドヴォルザーク:弦楽セレナード 交響曲第9番「新世界より」 ■CD:11(ORFEOR.499991) ベルリオーズ:幻想交響曲 序曲「海賊」 ■CD:12(ORFEOR.207891) ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 ■CD:13(ORFEOR.206891) ハイドン:交響曲第99番 モーツァルト:交響曲第25番 交響曲第38番「プラハ」 ■CD:14(ORFEOR.498991) モーツァルト:交響曲第40番 交響曲第41番「ジュピター」 ■CD:15(ORFEOR.550011) ヘンデル:合奏協奏曲ト短調 Op.6-6 ブルックナー:交響曲第9番 ■CD:16(ORFEOR.724071) ブルックナー:交響曲第8番(1890年 第2稿/ハース版) ■CD:17(ORFEOR.553011) モーツァルト:交響曲第40番 ブラームス:交響曲第2番 ■CD:18(ORFEOR.268921) ベートーヴェン:序曲「コリオラン」 交響曲第8番、交響曲第7番 ■CD:19(ORFEOR.654052) モーツァルト:交響曲第40番 ■CD:20(ORFEOR.654052) マーラー:交響曲「大地の歌」 ■CD:21(ORFEOR.867121) ロッシーニ:「セミラーミデ」序曲 シューマン:ピアノ協奏曲 モーツァルト:協奏交響曲変ホ長調 KV364 ■CD:22(ORFEOR.449961) ベートーヴェン:交響曲第8番 チャイコフスキー:交響曲第5番 ■CD:23(ORFEOR.208891) ブルックナー:交響曲第7番 ■CD:24(ORFEOR.484981) ベートーヴェン:「エグモント」序曲 ピアノ協奏曲第3番、 交響曲第5番「運命」 ■CD:25(ORFEOR.265921) ブラームス:交響曲第2番 ヴォーン・ウィリアムズ:交響曲第6番 ■CD:26(ORFEOR.589021) バルトーク:ヴァイオリン協奏曲 モーツァルト:行進曲ヘ長調 KV 248, ディヴェルティメント.ヘ長調 KV247 ■CD:27(ORFEOR.486981) モーツァルト:交響曲第38番 「プラハ」 交響曲第41番「ジュピター」 ■CD:28 (ORFEOR.554011) マーラー:交響曲第6番「悲劇的」 ■CD:29 (ORFEOR.235901) ハイドン:交響曲第103番「太鼓連打」 シューベルト:交響曲第7番「未完成」 アイネム:ブルックナー・ディアローグ Op.39 ■CD:30 (ORFEOR.302921) モーツァルト:アイネ・クライネ・ナハトムジーク チャイコフスキー:交響曲第5番 |
■CD:1(ORFEOR.100841) カルロス・クライバー(指)バイエルン国立O 録音:1982年5月3日ミュンヘン、国立劇場 ■CD:2(ORFEOR.263921) フリードリヒ・グルダ(P)、カール・ベーム(指)バイエルンRSO 録音:1969年9月30日(モーツァルト)、1969年10月2日(ブラームス) ミュンヘン、ヘルクレスザール ■CD:3(ORFEOR.522991) クリスタ・ルートヴィヒ(Ms)、カール・ベーム(指)VPO 録音:1969年8月17日ザルツブルク祝祭大劇場、ザルツブルク音楽祭 ■CD:4&5(ORFEOR.608032) エミール・ギレリス(P)、カール・ベーム(指)チェコPO 録音:1971年8月8日ザルツブルク音楽祭 ■CD:6(ORFEOR.607031) クリスタ・ルートヴィヒ(Ms)、カール・ベーム(指)シュターツカペレ・ドレスデン 録音:1972年8月15日ザルツブルク祝祭大劇場(ステレオ/ライヴ) ■CD:7(ORFEOR.264921) カール・ベーム(指)バイエルンRSO 録音:1973年9月29日ミュンヘン、ヘルクレスザール ■CD:8&9(ORFEOR.587022) ラファエル・クーベリック(指)VPO 録音:1971年8月13日ザルツブルク祝祭大劇場 ■CD:10(ORFEOR.596031) ラファエル・クーベリック(指)バイエルンRSO 録音:1977年5月25日(Op.22)、1980年6月19,20日(Op.95) ミュンヘン、ヘルクレスザール ■CD:11(ORFEOR.499991) ラファエル・クーベリック(指)バイエルンRSO 録音:1962年11月23日(モノラル/ライヴ)、1981年9月25日ミュンヘン、ヘルクレスザール ■CD:12(ORFEOR.207891) ヘレン・ドーナト(S)、ブリギッテ・ファスベンダー(A)、ホルスト・ラウベンタール(T)、ハンス・ゾーティン(Bs)、バイエルン放送cho、ラファエル・クーベリック(指)バイエルンRSO 録音:1982年5月14日ミュンヘン、ヘルクレスザール ■CD:13(ORFEOR.206891) ラファエル・クーベリック(指)バイエルンRSO 録音:1982年5月4日(ハイドン)、1985年5月9日(KV504) ミュンヘン、ヘルクレスザール、1981年6月22日(KV183)ヴェルツブルク、カイザーザール ■CD:14(ORFEOR.498991) ラファエル・クーベリック(指)バイエルンRSO 録音:1985年5月10日ミュンヘン、ヘルクレスザール ■CD:15(ORFEOR.550011) ファエル・クーベリック(指)バイエルンRSO 録音:1985年6月6日ミュンヘン、ヘルクレスザール ■CD:16(ORFEOR.724071) ヨゼフ・カイルベルト(指)ケルンRSO 録音:1966年11月4日ケルン、フンクハウス ■CD:17(ORFEOR.553011) ヨゼフ・カイルベルト(指)バイエルンRSO 録音:1966年12月8日ミュンヘン、ヘルクレスザール ■CD:18(ORFEOR.268921) ヨゼフ・カイルベルト(指)バイエルンRSO 録音:1967年11月30日(コリオラン) 1967年5月5日ミュンヘン、ヘルクレスザール ■CD:19&20(ORFEOR.654052) ブリギッテ・ファスベンダー(A)、フランシスコ・アライサ(T)、カルロ・マリア・ジュリーニ(指)VPO 録音:1987年8月2日、ザルツブルク祝祭大劇場 ■CD:21(ORFEOR.867121) スヴャトスラフ・リヒテル(P)、ゲルハルト・ヘッツェル(Vn)、ルドルフ・シュトレング(Va)、リッカルド・ムーティ(指)VPO 録音:1972年8月17日(ロッシーニ&シューマン)、1974年7月27日(モーツァルト)ザルツブルク音楽祭 ■CD:22(ORFEOR.449961) ルドルフ・ケンペ(指)バイエルンRSO 録音:1975年3月20日ミュンヘン、ヘルクレスザール ■CD:23(ORFEOR.208891) コリン・デイヴィス(指)バイエルンRSO 録音:1987年5月1日ミュンヘン、フィルハーモニー、ガスタイク ■CD:24(ORFEOR.484981) エミール・ギレリス(P)、ジョージ・セル(指)VPO 録音:1969年8月24日ザルツブルク音楽祭 ■CD:25(ORFEOR.265921) ジョン・バルビローリ(指)バイエルンRSO 録音:1970年4月10日ミュンヘン、ヘルクレスザール ■CD:26(ORFEOR.589021) ゲルハルト・ヘッツェル(Vn)、ロリン・マゼール(指)VPO(バルトーク)、ウィーン室内合奏団(モーツァルト) 録音:1984年、1983年ザルツブルク音楽祭 ■CD:27(ORFEOR.486981) シャーンドル・ヴェーグ(指)ザルツブルク・カメラータ・アカデミカ 録音:1989/96年ザルツブルク音楽祭 ■CD:28 (ORFEOR.554011) エーリッヒ・ラインスドルフ(指)バイエルンRSO 録音:1983年6月10日ミュンヘン、ヘルクレスザール ■CD:29 (ORFEOR.235901) ロヴロ・フォン・マタチッチ(指)ウィーンSO 録音:1984年1月7日(ハイドン&シューベルト)、1983年3月13日(フォン・アイネム) ■CD:30 (ORFEOR.302921) ダヴィッド・オイストラフ(指)VPO 録音:1972年8月23日ザルツブルク音楽祭 ※特に表記のないものは全てステレオ・ライヴ |
|
||
 ELECT ERT-1025(1CD) |
シューベルト:交響曲第8番「未完成」 交響曲第9番「ザ・グレート」 |
ジョルジュ・ジョルジェスク(指) ジョルジュ・エネスコPO 録音:1963 年スタジオ(ステレオ)、1963 年ライヴ(モノラル。拍手有り) |
| “高潔でありながら温かいジョルジェスクの芸風が最高に生きたシューベルト” | ||
|
||
| ELECT ERT-1024(1CD) |
ブラームス:交響曲第3番ヘ長調Op.90 ハイドンの主題による変奏曲* |
ジョルジュ・ジョルジェスク(指) ジョルジュ・エネスコPO 録音:1964年5月23 日ライヴ(ステレオ)、1964年2月23日スタジオ(ステレオ)* |
|
||
| ELECT ERT-1026(1CD) |
フランク:交響曲ニ短調 R.シュトラウス:ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら |
ジョルジュ・ジョルジェスク(指) ジョルジュ・エネスコPO 録音:1964 年6 月15 日ライヴ(ステレオ)、1962 年5 月20 日スタジオ(ステレオ) |
|
||
 OTAKEN TKC-352(1CD) |
シューベルト:交響曲第 9 番「グレート」 ウェーバー:「魔弾の射手」序曲* |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指) BPO 録音:1953年9月15日、1952年12月8日* ※原盤:F670.027~8M(疑似ステレオ) |
|
||
| 日本伝統文化振興財団 XRCG-30048 (7XRCD) 完全限定盤 |
NHK交響楽団によるベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」1980年代編 Disc 1 ~R.ワイケルト Disc 2~Z. コシュラー Disc 3 ~スウィトナー Disc 4 ~スウィトナー Disc 5~B.クロブチャール Disc 6~F.ライトナー Disc 7~ 若杉弘 |
Disc 1 ラルフ・ワイケルト(指)、曽我榮子(S)、伊原直子(A)、小林一男(T)、宮原昭吾(Br)/録音:1980/12/22NHKホール Disc 2 ズデニェク・コシュラー(指)、曽我榮子(S)、伊原直子(A)、小林一男(T)、木村俊光(Br)/録音:1981/12/21NHKホール Disc 3 オットマール・スウィトナー(指)、曽我榮子(S)、伊原直子(A)、小林一男(T)、木村俊光(Br)/録音:1982/12/22NHKホール Disc 4 オットマール・スウィトナー(指)、片岡啓子(S)、伊原直子(A)、小林一男(T)、池田直樹(Br)/録音:1986/12/22NHKホール Disc 5 ベリスラフ・クロブチャール(指)、佐藤しのぶ(S)、伊原直子(A)、小林一男(T)、木村俊光(Br)/録音:1987/12/21NHKホール Disc 6 フェルディナント・ライトナー(指)、佐藤しのぶ(S)、伊原直子(A)、小林一男(T)、木村俊光(Br)/1988/12/22NHKホール Disc 7 1989 若杉弘 (指)、佐藤しのぶ(S)、伊原直子(A)、小林一男(T)、多田羅迪夫(Br)/録音:1989/12/22NHKホール 全て、国立音大cho |
|
||
| DACAPO MAR-8.201201(12CD) ★ |
モーツァルト:交響曲全集 <CD1>1-3.交響曲第1番変ホ長調K16/4-6.交響曲第4番ニ長調K19/7-9.交響曲ヘ長調K19a/10-12.交響曲第5番変ロ長調K22/13-16.交響曲ヘ長調K76(42a)/ <CD2>1-4.交響曲第6番ヘ長調K43/5-8.交響曲第7番ニ長調K45/9-11.交響曲ト長調K45a/12-15.交響曲変ロ長調K45b/16-19.交響曲第8番ニ長調K48/ <CD3>1-4.交響曲第9番ハ長調K73(75a)/5-7.交響曲ニ長調K81(73l)/9-11.交響曲ニ長調K97(73m)/12-15.交響曲ニ長調K95(73n)/16-18.交響曲第11番ニ長調K84(73q)/19-21.交響曲第10番ト長調K74/ <CD4>1-4.交響曲第12番ト長調K110(75b)/5-8.交響曲ハ長調K96(111b)/9-12.交響曲第13番ヘ長調K112/13-16.交響曲第14番イ長調K114/ <CD5>1-4.交響曲第15番ト長調K124/5-7.交響曲第16番ハ長調K128/8-10.交響曲第17番ト長調K129/11-14.交響曲第18番ヘ長調K130/<CD6>1-4.交響曲第19番変ホ長調K132/5-8.交響曲第20番ニ長調K133/9-12.交響曲第21番イ長調K134/13-15.交響曲第26番変ホ長調K184(161a)/ <CD7>1-3.交響曲第27番ト長調K199(161b)/4-6.交響曲第22番ハ長調K162/7-9.交響曲第23番ニ長調K181(162b)/10-12.交響曲第24番変ロ長調K182(173da)/13-16.交響曲第25番ト短調K183(173db)/<CD8>1-4.交響曲第29番イ長調K201(186a)/5-8.交響曲第30番ニ長調K202(186b)/9-12.交響曲第28番ハ長調K200(189K)/ <CD9>1-3.交響曲第31番ニ長調「パリ」K297(300a)/4-7.交響曲第33番変ロ長調K319/8-11.交響曲第34番ハ長調K338/11.交響曲第31番ニ長調「パリ」K297(300a)第2楽章:第1稿/ <CD10>1-4.交響曲第35番ニ長調「ハフナー」K385/5-7.交響曲第38番ニ長調「プラハ」K504/ <CD11>1-4.交響曲第36番ハ長調「リンツ」K425/5-8.交響曲第39番変ホ長調K543/ <CD12>1-4.交響曲第40番ト短調K550/5-8.交響曲第41番ハ長調「ジュピター」K551 |
アダム・フィッシャー(指) デンマーク国立室内O 録音:2006年6月-2013年2月 |
|
||
 SCRIBENDUM SC-505(7CD) |
コンヴィチュニーの芸術~ザ・モノラル・レコーディングス ■CD 1 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 ■CD 2 ブルックナー:交響曲第2番(1877年、ハース版) ■CD 3 ブルックナー:交響曲第4番ホ長調WAB104(1881年原典版 ハース版) ■CD 4 ショスタコーヴィッチ:交響曲第10番 ■CD 5 ショスタコーヴィッチ:交響曲第11番「1905年」 ■CD 6 ベートーヴェン:交響曲第4番 交響曲第5番「運命」* ■CD 7 ベートーヴェン:交響曲第番9番「合唱付き」 |
全て、フランツ・コンヴィチュニー(指) ■CD 1 シュターツカペレ・ドレスデン/録音:1955年 ■CD 2 ベルリンRSO/録音:1951年 ■CD 3 チェコPO/録音:1952年 ■CD 4 ライプツィヒ・ゲヴァントハウスO/録音:1954年) ■CD 5 シュターツカペレ・ドレスデン/録音:1959年 ■CD 6 ライプツィヒRSO/録音:1950年、1951年* ■CD 7 ライプツィヒRSO&Cho ハンネ=ローレ・クーゼ(S)、エヴァ・フライシャー(C.A)、ロルフ・アブレック(T)、ハンス・クラーマー(Bs)/録音:1950年 |
| AAM Rscords AAM-1(1CD) |
ヘンデルからハイドンまで ヘンデル:オラトリオ「サウル」~シンフォニア(1738) フランツ・クサヴァー・リヒター(1709-1789):グランド・シンフォニー 第7 番 ハ長調(1740 頃) アントン・シュターミッツ(1717-1757):シンフォニア第4番 ニ長調(1750 頃) モーツァルト:交響曲第1番変ホ長調 K16 ハイドン:交響曲第49番「受難」 |
リチャード・エガー(指&ハープシコード) アカデミー・オブ・エンシェント・ミュージック (エンシェントCO) コンサートマスター:・パヴロ・ベズノシウク(Vn) 録音:2011年9月21-23 日 UK ロンドン セイント・ジュード・オン・ザ・ヒル |
|
||
 WEITBLICK SSS-0147(1CD) |
ショスタコーヴィチ:交響曲第8 番ハ短調 Op.65 | アルヴィド・ヤンソンス(指) ベルリンRSO(旧東独) 録音:1981年11月11日ベルリン放送局大ホール1(ステレオ) ※英語、日本語、ドイツ語によるライナーノート付 |
|
||
 Goodies 33CDR-3461(1CDR) |
ブラームス:交響曲第1番ハ短調Op.68 交響曲第2番ニ長調Op.73* |
ブルーノ・ワルター(指)NYO 米 COLUMBIA SL200(U.S.)(Set) (1953年12月30日、12月28日* ニューヨーク30丁目コロンビア・スタジオ録音) |
| “50年代の最高峰に君臨するブラームス録音!” | ||
|
||
| DACAPO MAR-6.220546 (1SACD) |
モーツァルト:交響曲集第11集(1783&1788) 交響曲第36番ハ長調K425「リンツ」 交響曲第39番変ホ長調K543 |
アダム・フィッシャー(指) デンマーク国立室内O 録音:2012年8-12月,2013年2月コペンハーゲン |
|
||
| DACAPO MAR-6.220639 (1SACD) |
モーツァルト:交響曲集第12集(1788) 交響曲第40番ト短調K550 交響曲第41番ハ長調「ジュピター」K551 |
アダム・フィッシャー(指) デンマーク国立室内O 録音:2013年2月コペンハーゲン |
|
||
 King International KKC-9059 (4Bluray) 日本限定生産 |
サイモン・ラトル来日記念ブルーレイBOX ■Disc1(2056794) 2007年ジルヴェスター・コンサート ボロディン:「イーゴリ公」~「だったん人の踊り」 交響曲第2番ロ短調 ムソルグスキー:「ホヴァンシチナ」前奏曲「モスクワ河の夜明け ムソルグスキー(ラヴェル編):組曲「展覧会の絵」 ショスタコーヴィチ:バレエ音楽「黄金時代」~舞曲(アンコール) ■Disc2(2057754) 2009年ヴァルトビューネ チャイコフスキー:バレエ音楽「くるみ割り人形」~序曲/クリスマス・ツリー/行進曲 ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番 ストラヴィンスキー:バレエ音楽「春の祭典」 リンケ:ベルリンの風(アンコール) ■Disc3 2007年ヨーロッパ・コンサート ワーグナー:「パルジファル」前奏曲 ブラームス:ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 交響曲第4番 ■Disc4 2008年ヨーロッパ・コンサート ストラヴィンスキー:3楽章の交響曲 ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ベートーヴェン:交響曲第7番 |
全て、サイモン・ラトル(指)BPO ■Disc1(2056794) 収録:2007年12月31日ベルリン、フィルハーモニー(ライヴ) ■Disc2(2057754) イエフィム・ブロンフマン(P) 収録:2009年6月21日ベルリン、オリンピックスタジアム(ライヴ) ■Disc3 リサ・バティシアヴィリ(Vn) トルルス・モルク(Vc) 収録:2007年5月1日ベルリン、カーベルヴェルク・オーバーシュプレー(ライヴ) *Blu-ray未発、BOX初発売 ■Disc4 ヴァディム・レーピン(Vn) 収録:2008年5月1日モスクワ音楽院大ホール(ライヴ) *Blu-ray未発、BOX初発売 Disc1:91mm 画面:カラー、16:9、1080i Full HD 音声:PCM2.0、PCM5.1 Disc2:104mm 画面:カラー、16:9、1080i Full HD 音声:PCM2.0、PCM5.1 Disc3:103mm 画面:カラー、16:9、1080i Full HD 音声:PCM2.0、DD5.1、DTS5.1 Disc4:92mm 画面:カラー、16:9、1080i Full HD 音声:PCM2.0、DD5.1、DTS5.1 Region All |
|
||
 Hanssler 98-014(1CD) |
ファイ/ハイドン交響曲集Vol.21 序曲「突然の出会い」ニ長調 Hob.XXVIII:6 交響曲第99番変ホ長調Hob.I:99 交響曲第100番「軍隊」ト長調Hob.I:100 |
トーマス・ファイ(指) ハイデルベルクSO 録音:2013年3月5-8日、パラティン、ヴィースロッホ |
| “クリップスと並ぶ「99番」の名盤誕生!” | ||
|
||
 Audite AU-97677(1CD) |
シューマン:交響曲第1番「春」(初稿) 序曲,スケルツォとフィナーレ* 交響曲4番ニ短調 Op.120(1841年原典版)* |
ハインツ・ホリガー(指) ケルンWDR響 録音:2012年1月23-27日、2012年3月19-23日*、ケルン・フィルハーモニー、ドイツ |
| 「奏でる」ことを忘れない、名手ホリガーの音楽家魂! | ||
|
||
 ICA CLASSICS ICAC-5105B(1CD) |
バルビローリ/ハイドン&ベルリオーズ ハイドン:交響曲第83番ト短調 「めんどり」Hob.1:83 ベルリオーズ:幻想交響曲* |
ジョン・バルビローリ(指) 南西ドイツRSO 録音:1969年2月24日、 1969年2月22-24日* バーデン・バーデン 南西ドイツ放送 ハンス・ロスバウト・スタジオ (共にステレオ) |
| “最晩年のバルビローリ、究極の円熟芸!!” | ||
|
||
 ICA CLASSICS ICAC-5109B(1CD) |
ハンス・ロスバウト ドビュッシー:夜想曲/遊戯* シベリウス:交響曲第6番# |
ハンス・ロスバウト(指) ケルンRSO、ケルン放送Cho 録音:1955年3月7日、1954年4月26日*、1952年4月21日# ケルン放送 第1 ホール |
| “透徹を極めた造形力と表現意欲の完璧なバランス! | ||
|
||
| DACAPO MAR-6.220536 (1SACD) |
モーツァルト:交響曲集第1集 交響曲 第1番 変ホ長調 K16 交響曲 第4番 ニ長調 K19 交響曲 ヘ長調 K19a 交響曲 第6番 変ロ長調 K22 交響曲 ヘ長調 K42a |
アダム・フィッシャー(指) デンマーク国立室内O 録音:2012年2月,8月 コペンハーゲン DR コンチェルトフセット 第2 スタジオ |
|
||
| DACAPO MAR-6.220545 (1SACD) |
モーツァルト:交響曲集第10 集(1782&1786)
交響曲 第35番「ハフナー」 交響曲 第38「プラハ」 |
アダム・フィッシャー(指) デンマーク国立室内O 録音:2012年2月,4月,8月 コペンハーゲン DR コンチェルトフセット 第2スタジオ |
|
||
 Altus ALT-271(1CD) |
マーラー:交響曲第5番 | ミヒャエル・ギーレン(指) ザールブリュッケンRSO (現ザールブリュッケン・カイザースラウテルン・ドイツ放送PO) 録音:1971年2月11,12日、ザールブリュッケン・コングレスハレ(ステレオ・ライヴ) |
|
||
 Guild Historical GHCD-2402(1CD) |
ストコフスキー~ブラームス&ワーグナー1960 ブラームス:交響曲第1番ハ短調 Op.68 ワーグナー(ストコフスキー編):「トリスタンとイゾルデ」~第2幕と第3幕の愛の音楽 |
レオポルド・ストコフスキー(指) フィラデルフィアO ※録音(ライヴ):1960年2月23日(ステレオ)、アカデミー・オヴ・ミュージック(フィラデルフィア) ※リマスタリング:ピーター・レイノルズ&レイノルズ・リマスタリング ※マスター・ソース:エンノ・リエケーナ・コレクション |
|
||
 LEBHAFT LBCDR-1005(1CDR) |
モーツァルト:交響曲第36番「リンツ」 交響曲第38番「プラハ」 |
カレル・アンチェル(指) シュターツカペレ・ドレスデン 録音:1959年6月(モノラル) ※原盤:独Eterna 820099 |
| “渋いだけじゃない!アンチェル&シュターツカペレ・ドレスデンの唯一のモーツァルト” | ||
|
||
 WEITBLICK SSS-0145(2CD) ★ |
マーラー:交響曲第9番 ニ長調 | エフゲニ・スヴェトラーノフ(指) スウェーデンRSO 録音:2000年1月21日ベルワルド・ホール,ライヴ(デジタル) ※英語、日本語、ドイツ語によるライナーノート付 |
| “スヴェトラーノフが最晩年に遂に到達した「愛と悟り」の境地!” | ||
|
||
 コウベレックス KRS-461(1CD) |
ゲルハルト・ボッセ/メンデルスゾーン&ベートーヴェン メンデルスゾーン:交響曲第3番「スコットランド」 ベートーヴェン:交響曲第4番* |
ゲルハルト・ボッセ(指) 神戸市室内合奏団 録音:2011年6月11日(初CD化)、2007年10月13日(初出)*、神戸文化ホール中ホール,ライヴ |
|
||
 GRAND SLAM GS-2095 |
マーラー:交響曲第1番「巨人」 | エイドリアン・ボールト(指)LPO 録音:1958年8月10日-13日、ロンドン、ウォルサムストウ・アッセンブリー・ホール(ステレオ) 使用音源:Everest (U.S.A.) STBR 3005 ( オープンリールテープ、2トラック、19センチ) |
| “名人芸!作り込み過ぎない解釈の背後に宿る強烈な共感” | ||
|
||
| DACAPO MAR-6.220537(1CD) |
モーツァルト:交響曲集第2集 交響曲第6番ヘ長調K43 交響曲第7番ニ長調K45 交響曲ト長調K45A 交響曲変ロ長調K45B 交響曲第8番ニ長調K48 |
アダム・フィッシャー(指) デンマーク国立室内SO 録音:2012年2月コペンハーゲンDRコンサートホール第2スタジオ |
|
||
| DACAPO MAR-8.226147(1CD) |
クヌドーゲ・リーサゲル:交響曲集第2集 T-DOXC(poememecanique…機械的な詩) Op.13(1926) 交響曲第2番Op.14(1927) 管弦楽のための協奏曲Op.24(1931) 演奏会用序曲「春」Op.31(1934) シンフォニア(交響曲第3番)Op.30(1935) |
ボー・ホルテン(指)オーフスSO 録音:2011年6月20-25日オーフス・コンサートホール,シンフォニック・ホール ※世界初録音 |
|
||
 LEBHAFT LBCDR-1004(1CDR) |
メンデルスゾーン:交響曲第3番「スコットランド」 序曲「静かな海と楽しい航海」 |
パウル・クレツキ(指)イスラエルPO 録音:1954年5月 原盤:仏Columbia FCX381 (ジャケット写真は英国盤) |
|
||
BELLA MUSICA~カール・ビュンテの交響曲シリーズ
|
|||
| BELLA MUSICA BM31.2396(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 | カール・アウグスト・ビュンテ(指) 関西PO,大阪アカデミーCho、 T.KOBAYASHI?(S)、岩本敏子(A) 山本裕之(T)、横田浩和(Bs) 録音:1989年12月28日、シンフォニーホール,大阪(ライヴ) |
|
|
|||
| BELLA MUSICA BM31.2414(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 大フーガ変ロ長調 Op.133* |
カール・アウグスト・ビュンテ(指) ベルリンSO 録音:1959年5月2日、1961年5月21日*、ベルリン(モノラル)、74'18 |
|
|
|||
 BELLA MUSICA BM31.2424(1CD) |
チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調 Op.64 ブラームス:セレナード第2番イ長調 Op.16* |
カール・アウグスト・ビュンテ(指) ベルリンSO 録音:1960年4月2日ライヴ(ステレオ)、1960年4月16日ライヴ、ベルリン(擬似ステレオ?)* |
|
| “頑強な造形力を駆使した、野武士的チャイコフスキー!” | |||
|
|||
| BELLA MUSICA BM31.2425(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」 R.シュトラウス:交響詩「ドン・ファン」 |
カール・アウグスト・ビュンテ(指) ベルリンSO 録音:1959年6月6日ライヴ、1954年2月24日(ライヴ)*、ベルリン(モノラル) |
|
|
|||
 BELLA MUSICA BM31.2440(1CD) |
チャイコフスキー:交響曲第6番ロ短調Op.74「悲愴」 チャイコフスキー:弦楽セレナード ハ長調 Op.48 |
カール・アウグスト・ビュンテ(指) ベルリンSO 録音:1962年1月14日、1958年10月 19日、ベルリン音楽大学のコンサートホール(ステレオ・ライヴ) |
|
| “逞しい精神と巨大造形力を土台とした感動的なチャイコフスキー!” | |||
|
|||
| DACAPO MAR-8.226109(1CD) |
セアン・ニルス・アイクベア:交響曲第2番「天の前に、地の前に」(2010) 交響曲第1番「私たちは火の中に身を投じた」(2005) |
クリストフ・ポッペン(指) デンマーク国立SO |
|
||
| STUDIO FONTANA FNCC-005(1CD) 【未案内旧譜】 |
ドヴォルザーク:交響曲第8番ト短調 Op.88* 組曲イ長調「アメリカ」Op.98b+ |
マリオ・クレメンス(指)プラハPO* ヴィラディミール・ヴァーレク(指)プラハRSO+ 録音:2007年12月17日CNSOスタジオ第1「ギャラリー」・プラハ・チェコ*、1995年2月3-5日ドヴォルザーク・ホール+ |
 GRAND SLAM GS-2093(1CD) |
シューベルト:交響曲第9番「グレート」 交響曲第1番ニ長調、D. 82* |
ルネ・レイボヴィッツ(指) ロイヤルPO、パリRSO* 使用音源:Reader's Digest(France) 1579.8, Oceanic(U.S.A.) OCS 33* 録音:1962年1月16-17日ロンドン・ウォルサムストウ・アッセンブリー・ホール(ステレオ)、1952年頃(初出:1953年)モノラル* |
| “時代を先取りし過ぎ!? 楽天的かつ超先鋭的な「グレート」” | ||
|
||
 ELECT ERT-1013(10CD) ★ |
ブルックナー:交響曲全集 (1)交響曲第1番(リンツ稿) (2)交響曲第2番ハ短調 (3)交響曲第3番ニ短調 (4)交響曲第4番変ホ長調 (5)交響曲第5番変ロ長調 (6)交響曲第6番イ長調 (7)交響曲第7番ホ長調 (8)交響曲第8番ハ短調 (9)交響曲第9番ニ短調 |
クリスチャン・マンデアル(指) クルジュ=ナポカPO(現トランシルヴェニア国立PO) 録音: (1)1986年7月、(2)1984年10月、 (3)1984年10月、(4)1989年7月、 (5)1988年6月、(6)1988年7月、 (7)1986年6月、(8)1987年6月、 (9)1988年7月 全曲アナログ・スタジオ録音(ステレオ) ※CD日本プレス。英語、日本語によるライナーノート付 |
| “ブルックナーの純朴さ敬虔さを本当に解する指揮者がまだ存在したのです!” | ||
|
||
 WEITBLICK SSS-0143(1CD) |
シューマン:交響曲第4番 ベートーヴェン:交響曲第2番* |
クルト・ザンデルリング(指) スウェーデンRSO 録音:1990年5月4日デジタル 1997年11月28日デジタル* いずれも、ベルワルドホールに於けるライヴ ※英語、日本語、ドイツ語によるライナーノート付 |
|
||
 Rotterdam Philharmonic KKC-4005(4CD) 900セット完全限定番 |
ゲルギエフ&ロッテルダム・フィル20年の軌跡 (1)チャイコフスキー:交響曲第4番 (2)シベリウス:交響曲第1番ホ短調 op.39 (3)プロコフィエフ:「ロメオとジュリエット」より(全17曲) (4)ストラヴィンスキー:春の祭典 (5)ショスタコーヴィチ:交響曲第11番 (6)ベルリオーズ:「ファウストの劫罰」~「鬼火のメヌエット」「妖精の踊り」「ハンガリー行進曲」 (7)シュニトケ:ヴィオラ協奏曲 (8)デュティユー:ヴァイオリン協奏曲「夢の木」 (9)ティシチェンコ:バレエ「ヤロスラヴナ」より(全6曲) |
(1)録音:1988年11月2日ロッテルダム、デ・ドーレン[NPS] (2)録音:2003年12月13日、アムステルダム・コンセルトヘボウ[NPS AVRO TROS] (3)録音:2004年6月6日ロッテルダム、デ・ドーレン[NPS] (4)録音:1996年5月31日ロッテルダム、デ・ドーレン[NPS] (5)録音:1990年11月17日、アムステルダム・コンセルトヘボウ[VARA] (6)録音:1997年9月25日、ロッテルダム、デ・ドーレン[NPS] (7)ユーリ・バシュメト(Va) 録音:1993年3月13日アムステルダム・コンセルトヘボウ[VARA] (8)レオニダス・カヴァコス(Vn) 録音:2007年9月14日ロッテルダム、デ・ドーレン[KRO] (9)録音:2007年9月15日ロッテルダム、デ・ドーレン[KRO] |
|
||
 Forgotten Records FR-762(1CDR) |
チャイコフスキー:交響曲第5番 弦楽セレナード# |
ワルター・ゲール(指)ローマPO*、 フランクフルト室内O# 録音:1950年代中頃(共にモノラル) 音源:Musical Masterpiece Society & GUILDE INTERNATIONALE DU DISQUE MMS 2155, MMS 2188#, MMS 6013, MMS 6108, MMS 3048# |
|
||
| Forgotten Records FR-770(1CDR) |
オネゲル:交響曲第2番 マルティヌー:ピエロ・デッラ・フランチェスカのフレスコ画 H.352* |
ラファエル・クーベリック(指) フランス国立RSO フランス放送PO* 録音:1956年2月23日ライヴ(初出) 1960年9月9日ブザンソン音楽祭ライヴ(初出)* |
| Forgotten Records FR-704(1CDR) |
チャイコフスキー:交響曲第5番* 幻想序曲「ロメオとジュリエット」# |
ヴィルヘルム・シュヒター(指) 北西ドイツPO 録音:1956年*、1958年# (共にモノラル) 音源:Electrola, JLX 506*, JLP 173# IMPERIAL, J 60594# HMV, XLP 20009* |
|
||
| Forgotten Records FR-521(2CDR) |
チャイコフスキー:交響曲第5番* 交響曲第6番「悲愴」# |
アルトゥール・ロジンスキ(指) ロイヤルPO 録音:1954年10月2日*、3日# 音源:Westminster, XWN 18355*, XWN 18048# HELIODOR, 478608# |
| Forgotten Records FR-463(1CDR) |
ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」* チャイコフスキー:幻想序曲「ロメオとジュリエット」# |
アルチェオ・ガリエラ(指) フィルハーモニアO 録音:1953年10月7日* 1955年3月15日# 音源:Columbia, SX 1025*, FCX 24*, CX 1065# |
|
||
| Forgotten Records FR-339(1CDR) |
チャイコフスキー:交響曲第4番* 幻想序曲「ロメオとジュリエット」# 交響的バラード「ヴォイェヴォーダ」 # サマーリンの栄誉のための悲歌 ト長調# |
ワルター・ゲール(指)オランダPO 録音:1950年代初頭 音源:Musical Masterpiece Society & GUILDE INTERNATIONALE DU DISQUE MMS 16*, MMS 66#, MMS 6013*, MMS 6108*, MMS 3048# |
|
||
 Solo Musica WS-003D(2CD) |
マーラー:交響曲第6番「悲劇的」 | ファビオ・ルイージ(指) ウィーンSO 録音:2011年 ウィーン,ムジークフェライン |
|
||
 読響アーカイブ YASCD-1003(1CD) |
マーラー:交響曲第9番ニ長調 | ハインツ・レークナー(指)読売日本SO 録音:1988年3月8日東京文化会館ライヴ (サウンド・マスタリング:WEITBLICK) |
|
||
 BR KLASSIK BR-900712E(3CD) |
シューベルト:交響曲全集(全8曲) | ロリン・マゼール(指)バイエルンRSO 録音:2001年3月ミュンヘンプリンツレーゲンテンシアター |
| “マゼールのこだわりと円熟!これぞシューベルト交響曲の進化系!!” | ||
|
||
 ICA CLASSICS ICAC-5090B(1CD) |
クラウス・テンシュテット/ブラームス他 ブラームス:交響曲第1番ハ短調Op.68 マルティヌー:交響曲第4番H305* |
クラウス・テンシュテット(指) シュトゥットガルトRSO 録音:1976年9月24日ゲッピンゲン州立劇場、1973年4月26日SDRシュトゥットガルト放送* (共にステレオ) |
|
||
 ICA CLASSICS ICAC-5091B(1CD) |
ハンス・ロスバウトのマーラー マーラー:交響曲第5番嬰ハ短調 |
ハンス・ロスパウト(指)ケルンRSO 録音:1951年10月22日(モノラル) ※初CD化 |
| “比類なき構築と燃焼!冷たいだけではないロスバウトの決死のマーラー” | ||
|
||
 ICA CLASSICS ICAC-5093B(1CD) |
ボールト/ブラームス&メンデルスゾーン ブラームス:交響曲第4番ホ短調Op.98 メンデルスゾーン:交響曲第4番「イタリア」* |
エイドリアン・ボールト(指) BBC響、ロイヤルPO* 録音:1975年8月8日、1972年7月29日 ロイヤル・アルバート・ホール(共にステレオ) ※初CD化 |
|
||
 ICA CLASSICS ICAC-5094D(2CD) |
ヘンヒェン/マーラー:「巨人」他 マーラー:交響曲第1番「巨人」 交響曲第8番「千人の交響曲」* |
リタ・クリス(ソプラノⅠ)…罪深き女 アンジェラ・マリア・ブラシ(ソプラノⅡ)…告白する女 オフェリア・サラ(S)…栄光の聖母 キャスリーン・キーン(メゾ・ソプラノⅠ)…エジプトのマリア ラインヒルド・グンケル(メゾ・ソプラノⅡ)…サマリアの女 グレン・ウィンスラーデ(T)…マリア崇拝の博士 ジョン・ブレヒラー(Br)…法悦の教父 クルト・リドル(Bs)…瞑想する教父 ナショナル・コア・オブ・ザ・ウクライナ「ドゥムカ」 ウクライナ放送Cho ドレスデン・フィルハーモニー少年Cho ハルトムート・ヘンヒェン(指)オランダPO 録音:1999年11月20日、2002年9月10日* アムステルダム・コンセルトヘボウ(共にステレオ) |
|
||
 ICA CLASSICS ICAC-5096D(2CD) |
バルビローリ/シューベルト他 シューベルト:交響曲第4番ハ短調D417 ブリテン:テノール,ホルンと弦楽のための「セレナーデ」Op.31 シベリウス:交響曲第2番ニ長調Op.43 |
ジェラルド・イングリッシュ(T) ヘルマン・バウマン(Hrn) ジョン・バルビローリ(指)ケルンRSO 録音:1969年2月7日ケルン放送第1ホール(ステレオ) ※全て初出 |
| “音盤初登場ブリテンと完全燃焼シベリウスの感動的名演!” | ||
|
||
| ALLEGRO ART SOCIETY AR-001(1CD) |
カレン・ハチャトゥリアン(1920-2011):交響曲第1番(1952-1954/第2版;1963)* 交響曲第2番(1968)+ |
ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー(指)モスクワRSO* アレクサンドル・ラザレフ(指)ソヴィエト国立SO+ 録音:1963年11月*、1980年2月+、モスクワ音楽院大ホール |
 Rotterdam Philharmonic KKC-4003(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 R・シュトラウス:死と変容 op.24 |
ヤニック・ネゼ=セガン(指) ロッテルダムPO 録音:2007年11月8-11日/ロッテルダム、デ・ドーレン演奏・会議センター(ライヴ) |
|
||
 GRAND SLAM GS-2091(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 | エーリッヒ・クライバー(指)VPO 録音:1955年4月11-14日、ウィーン、ムジークフェラインザール 使用音源: Decca/Ace of Clubs (U.K.) ACL-35 |
| “第2楽章必聴!普遍的価値を誇る、エーリッヒ・クライバーの「英雄」” | ||
|
||
 RFP (ロイヤル・フランダース・フィル自主レーベル) RFP-004(1CD) |
マーラー:交響曲第1番ニ長調「巨人」 | エド・デ・ワールト(指)ロイヤル・フランダースPO 録音:2012年6月25-27日ベルギー、アントワープ、デ・シンゲル(セッション) |
|
||
| DUTTON CDLX-7298(1CD) |
ブルーメンフェルト:交響曲ハ短調「愛する故人の記憶に」Op.39(1905-1906頃) ゲオルギー・カトゥアール(1861-1926):交響曲ハ短調 Op.7(1889-1891/管弦楽配置;1895-1898)* |
マーティン・イェーツ(指) ロイヤル・スコティッシュ・ナショナルO 録音:2012年8月22-23日、ロイヤル・コンサートホール、グラスゴー、イギリス *世界初録音と表示されています。 |
| DUTTON CDLX-7299(1CD) |
リチャード・アーネル(1917-2009):番号のない交響曲集 序曲「1940年」Op.6 シンフォニア(1938/マーティン・イェーツ校訂;2012)+ ダゲナム交響曲(映画「Opus 65」からの組曲;1952)* 風景と図 Op.78(1956)* |
キャサリン・エドワーズ(P)* アラン・ダービーシャー(客演首席Ob+) マーティン・イェーツ(指) ロイヤル・スコティッシュ・ナショナルO 録音:2012年8月20-21日、ロイヤル・コンサートホール、グラスゴー、イギリス 世界初録音と表示されています。 |
 Serenade SEDR-5037(1CDR) |
ベートーヴェン:「レオノーレ」序曲第3番 交響曲第5番「運命」* |
ヨゼフ・ローゼンストック(指)マンハイム国立SO フェリックス・プロハスカ(指)ウィーン国立歌劇場O(フォルクスオーパー)* 録音:1955年、1958年5月*(共にステレオ) 音源: Livingston (U.S.A.) 2020 C (2 Track Reel to Reel Tape, 71/2 IPS)、 Vanguard (U.S.A.) VRD 1 (2 Track Reel to Reel Tape, 71/2 IPS)* |
|
||
 Serenade SEDR-5035(1CDR) |
カラヤンのドヴォルザーク&スメタナ ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」 スメタナ:交響詩「モルダウ」* |
ヘルベルト・フォン・カラヤン(指)BPO 録音:(1)1957年11月28-29日、1958年1月5-6日、 1958年5月18-20日 (2)1958年5月18-20日* 全てグリューネヴァルト教会 音源:Angel (U.S.A.) ZS-35615 (4 Track Reel to Reel Tape, 7.5 IPS) |
|
||
 Serenade SEDR-5036(1CDR) |
ハイドン:交響曲第94番「驚愕」 交響曲第99番変ホ長調 |
ヨゼフ・クリップス(指)VPO 録音:1957年9月9-14日ウィーン・ムジークフェライン 音源:London (U.S.A.) LCL-80018 (4 Track Reel to Reel Tape, 7.5 IPS) |
|
||
 東武レコーディングズ TBRCD-0019(1CD) |
シューマン:交響曲第4番 ブラームス:交響曲第1番 |
ペーター・マーク(指)東京都SO 録音:1995年10月17日第416回定期演奏会サントリーホール 1995年10月23日第417 回定期演奏会東京文化会館* (共にデジタル・ライヴ) サウンド・マスタリング:WEITBLICK |
| “マークが最後の来日で見せた真のロマンチストの美学!” | ||
|
||
 フォンテック FOCD-6030(5CD) 2012年11月20日発売 |
チャイコフスキー:交響曲全集(全6曲) | 飯守泰次郎(指) 東京シティPO 録音:2011年7月7日(第3&4番)、2012年1月18日(第1&6番)、2012年3月16日(第2番)以上東京オペラシティ・ライヴ、 2011年11月26日ティアラこうとう・ライヴ(第5番) |
| “世界中の指揮者が模範とすべき、飯守泰次郎の有言実行力!” | ||
|
||
| DACAPO MAR-6.220544(1SACD) |
モーツァルト:交響曲集第9集 交響曲第31番ニ長調K297「パリ」 交響曲第33番変ロ長調K31 交響曲第34番ハ長調K338 交響曲第31番ニ長調K297「パリ」-第2楽章の異稿版(第1版) |
アダム・フィッシャー(指) デンマーク国立室内O 録音:2010年10月4-5日,2011年2月21-23日コペンハーゲンデンマーク放送コンチェルト |
|
||
 King International KKC-10003(1SACD) シングルレイヤー |
シューベルト:交響曲第8番「未完成」 交響曲第9番「グレイト」 |
ウィルヘルム・フルトヴェングラー(指)BPO 録音:1953年9月15日ティタニア・パラスト(Live) 日本語解説付き 美麗デジケース仕様 |
|
||
| King International KKC-10004(1SACD) シングルレイヤー |
ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 | ウィルヘルム・フルトヴェングラー(指)BPO 録音:1949年3月15日ティタニア・パラスト(Live) 日本語解説付き 美麗デジケース仕様 |
|
||
ALTUS創立12周年特別企画
|
|||
| Altus ALTHQ-001(1HQCD) ★ |
ベートーヴェン:交響曲第4番変ロ長調 リャードフ:「バーバ・ヤーガ」 グラズノフ:バレエ音楽「ライモンダ」~第3幕間奏曲 |
エフゲニー・ムラヴィンスキー(指) レニングラードPO 録音:1973年5月26日東京文化会館大ホール(NHKによる実況録音) |
|
| Altus ALTHQ-002(1HQCD) ★ |
ショスタコーヴィチ:交響曲第5番「革命」 | エフゲニー・ムラヴィンスキー(指) レニングラードPO 録音:1973年5月26日東京文化会館、ライヴ |
|
| Altus ALTHQ-003(1HQCD) ★ |
ベルリオーズ:幻想交響曲 ムソルグスキー:「展覧会の絵」~古い城 ビゼー:「アルルの女」~ファランドール |
アンドレ・クリュイタンス(指)パリ音楽院O 録音1964年5月10日、東京文化会館、ライヴ |
|
| Altus ALTHQ-015(2HQCD) ★ |
モーツァルト:交響曲第33番 ブルックナー:交響曲第7番 |
オイゲン・ヨッフム(指) ロイヤル・コンセルトヘボウ感 録音:1986年9月17日人見記念講堂、ライヴ |
|
 Altus ALTHQ-055(2HQCD) ★ |
ベートーヴェン:序曲「エグモント」 交響曲第6番「田園」 交響曲第5番「運命」 バッハ:G線上のアリア |
ヘルベルト・ケーゲル(指)ドレスデンPO 録音:1989年10月18日サントリーホール、ライヴ |
|
|
|||
 ICA CLASSICS ICAC-5087B(1CD) |
アタウルフォ・アルヘンタ ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 スメタナ:歌劇「売られた花嫁」序曲* ■ボーナス・トラック# チャピ:ムジカ・クラシカ-前奏曲 「グラナダの裁判所」~セレナータ(ファンタジア・モリスカ) 「擲弾兵の太鼓」前奏曲 ヒメネス:「ルイ・アロンソの踊り」間奏曲 「ルイ・アロンソの結婚」間奏曲 |
アタウルフォ・アルヘンタ(指) スペイン国立O、スイス・ロマンドO* 録音1957年5月24日マドリッド,パラシコ・デ・ラ・ムジカ 1957年8月29日ジェノヴァ,ヴィクトリア・ホール* 1955-1957年マドリッド,グラン・オルケスタ・シンフォニア# (全てMONO) |
| “シューリヒト譲りのスタイリッシュさと血の熱気との見事な融合!” | ||
|
||
 WEITBLICK SSS-0136(2CD) |
ブラームス:交響曲全集 | エフゲーニ・スヴェトラーノフ(指) スウェーデンRSO 録音:第1番(1984年9月7日)、第2番(1982年1月15日)、第3番(1980年9月6日)、第4番(1985年10月20日) 以上、全てベルワルドホールに於けるステレオ・ライヴ ※英語、日本語、ドイツ語によるライナーノート付 |
|
||
 DACAPO MAR-6.220623 (1SACD) |
ニールセン:交響曲&協奏曲全集第1集 交響曲第3番Op.27「おおらかな交響曲」 交響曲第2番Op.16「4つの気質」* |
エリン・モーリー(S) ジョシュア・ホプキンス(Br) ニューヨーク・フィルハーモニック アラン・ギルバート(指)NYO 録音:2012年6月14-16日、2011年1月27-29日,2月1日* ニューヨーク,リンカーン・センター,エーブリー・フィッシャー・ホール・ライヴ |
|
||
| QUERSTAND VKJK-1214(1SACD) |
ブルックナー:交響曲第2番ハ短調 (1872年稿、キャラガン校訂版) |
ヘルベルト・ブロムシュテット(指) ライプツィヒ・ゲヴァントハウスO 録音:2012年3月8-11日ライプツィヒ・ゲヴァントハウスにおけるライヴ ※日本語オビ・解説付き |
 QUERSTAND VKJK-1215(1SACD) |
ブルックナー:交響曲第9番ニ短調 (コールス校訂版,2000年) |
ヘルベルト・ブロムシュテット(指) ライプツィヒ・ゲヴァントハウスO 録音:2011年11月24-26日ライプツィヒ・ゲヴァントハウスにおけるライヴ |
| “峻厳な第2楽章に象徴される、ブロムシュテットの「ブル9」解釈の集大成!” | ||
|
||
| Columna Musica 1CM-0285(1CD) |
ライヴ・エモーションズ 2 ジョン・アダムズ:ザ・チェアマン・ダンス(管弦楽の為のフォックストロット) チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」 |
ジュゼプ・ビセント(指) ワールド・オーケストラ 録音:2010-2011年、ライヴ |
 ELECT ERT-1001-2(5CD) 国内盤仕様 |
ベートーヴェン:交響曲全集 交響曲第1番(録音:1961年5月) [10:37][7:06][3:21][5:46] 交響曲第7番(録音:1962年1月) [11:55][9:13][8:15][6:35] レオノーレ序曲第3番(録音:1962年1月) [12:47] 交響曲第2番(録音:1961年4月20日) [11:51][13:05][3:26][6:09] 交響曲第6番「田園」(録音:1961年10月) [8:42][14:25][5:15][3:25][9:46] 交響曲第8番(録音:1961年5月) [9:16][3:58][5:05][7:54] 交響曲第3番「英雄」(録音:1961年3月) [14:44][17:34][6:11][12:27] 交響曲第4番(録音:1962年1月) [10:15][11:29][6:05][6:49] 交響曲第5番「運命」(録音:1961年8月 [8:04][10:34][5:55][8:39] 序曲「コリオラン」(録音:1961年8月) [8:23] 交響曲第9番「合唱」(録音:1961年7月) [14:57][11:11][15:06][25:47] 「エグモント」序曲(録音:1962年1月11日) [8:20] |
ジョルジュ・ジョルジェスク(指) ブカレスト・ジョルジュ・エネスコPO エミリャ・ペトレスク(S) マルタ・ケスラー(Ms)、 イオン・ピソ(T)、 マリウス・リンツラー(Bs)、 ジョルジュ・エネスコ・フィルCho ルーマニア放送Cho 録音:1961-62年ルーマニア文化宮殿ホール(スタジオ・ステレオ録音) エンジニア:Ben Bernfeld ※日本プレス マルチケース5枚組 英語、日本語によるライナーノート付 |
|
||
| King International KKC-10001(1SACD) シングルレーヤー |
ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」 交響曲第5番「運命」 |
ウィルヘルム・フルトヴェングラー(指)BPO 録音:1947年5月25日ベルリン・ティタニア・パラストLIVE |
|
||
| King International KKC-10002(1SACD) シングルレーヤー |
ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」 交響曲第5番「運命」 |
ウィルヘルム・フルトヴェングラー(指)BPO 録音:1954年5月23日ベルリン・ティタニア・パラストLIVE |
|
||
| ANALEKTA AN2-9893(1CD) |
ブルックナー:交響曲第7番 | ジャン=フィリップ・トランブレ(指) フランコフォニー・カナディエンヌO 録音:2006 年 8月 |
|
||
 ANALEKTA AN2-9916(1CD) |
ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」(1889年の版&ブルーノ・ワルター、トスカニーニの演奏録音に基づくトランブレ版) | ジャン=フィリップ・トランブレ(指 )フランコフォニー・カナディエンヌO 録音:2008年8月 |
|
||
 LPO LPO-0064(2CD) ★ |
チャイコフスキー:交響曲第4番ヘ短調Op.36 交響曲第5番ホ短調Op.64 |
ウラディーミル・ユロフスキ(指)LPO 録音:2011年3月19日&5月4日ロンドン,ロイヤル・フェスティヴァル・ホール,サウスバンク・センター |
|
||
| DACAPO MAR-6.220621 (1SACD) |
ホルンボー(1909-1996):室内交響曲集 室内交響曲第1番Op.53(1951) 室内交響曲第2番「悲歌」Op.100(1968) 室内交響曲第3番「フリーゼ」Op.103a(1969-70) |
ジョン・ストルゴーズ(指)ラップランド室内O 録音:2011年3月31日-4月1日ロヴァニエミ教会 ※全て世界初録音 |
|
||
 ICA CLASSICS ICAC-5078B(1CD) |
エフゲニー・スヴェトラーノフ ラフマニノフ:交響曲第2番ホ短調Op.44 バーンスタイン:「キャンディード」序曲* |
エフゲニー・スヴェトラーノフ(指) フィルハーモニアO、LSO* 録音:1993年3月15日ロイヤル・フェスティヴァル・ホール、1978年8月28日エディンバラ音楽祭アッシャー・ホール* (共にステレオ) |
| “スヴェトラーノフの円熟味と万全な運動能力が成し得た史上最強の「ラフ2」!” | ||
|
||
 ICA CLASSICS ICAC-5081B(1CD) |
グィド・カンテッリ シューマン:交響曲第4番ニ短調Op.120 ドビュッシー:「聖セバスチャンの殉教」組曲 ドビュッシー:海 |
グィド・カンテッリ(指) フィルハーモニアO 録音:1954年9月9日エディンバラアッシャー・ホール(MONO) |
| “過剰なロマンを排したカンテッリの直截なダイナミズムの勝利!” | ||
|
||
 ANALEKTA AN2-9998(1CD) |
ベルリオーズ:幻想交響曲 | ジャン=フィリップ・トランブレ(指) フランコフォニーO 録音:2011年 8月 |
|
||
 東武レコーディングズ TBRCD-0017(1CD) |
ペーター・マークの「新世界」!! ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」 ワーグナー:楽劇「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死* |
ペーター・マーク(指)東京都SO 録音:1986年3月31日東京文化会館,第232回定期演奏会デジタル・ライヴ 1995年10月17日サントリーホール,第416回定期演奏会デジタル・ライヴ* ※サウンド・マスタリング:WEITBLICK |
| “「新世界」終楽章で咆哮するホルンのトリルの怪!ワーグナーも必聴!!” | ||
|
||
 WEITBLICK SSS-0132-2(1CD) |
スヴェトラーノフのサン・サーンス (1)サン=サーンス:交響曲第3番「オルガン付」* (2)ルーセンベリ:「街のオルフェウス」組曲 |
エフゲニ・スヴェトラーノフ(指) スウェーデンRSO ヴァンサン・ワルニエ(Org)* 録音:1998年9月3日グスタフ・ヴァーサ教会ライヴ* 1983年1月14日ベルワルドホール・ライヴ ※英語、日本語、ドイツ語によるライナーノート付。 |
|
||
| FOK FOK-0005-2(1CD) |
シルヴィエ・ボドロヴァー(1954-):交響曲第1番「鐘と」(2011) R・シュトラウス:交響詩「ドン・ファン」 |
イジー・コウト(指)プラハSO |
|
||
| 日本伝統文化振興財団 SACG-30002 (SACD シングルレイヤー) |
ブラームス:交響曲第1番ハ短調 ベートーヴェン:交響曲第7番イ長調 |
ロヴロ・フォン・マタチッチ(指)NHK響 録音:1984年3月23日N響第927回定期公演ライヴ(NHKホール ) リマスタリング・エンジニア:杉本一家(VCM) 音源提供:NHK/NHKサービスセンター |
|
||
 Altus ALT-234(2CD) |
シューリヒト~奇跡の「エロイカ」 シューマン:「マンフレッド」序曲 メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調* ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 |
カール・シューリヒト(指) フランス国立放送O アルテュール・グリュミオー(Vn)* 録音:1963年5月14日シャンゼリゼ劇場での全演目(ステレオ) ※オリジナル・マスターからの新マスタリング |
| “もはや神の領域!強烈なオーラに溢れた奇蹟の「エロイカ」!!” | ||
|
||
| Ambroisie AM-207(1CD) |
ロマン派のパリ ルベル(1807-1880):交響曲第4番 ト長調 op.33(世界初録音) ベルリオーズ:夢とカプリッチョop.8 リスト:ピアノ協奏曲第1番* |
ベルトラン・シャマユ(P/1837年製エラール(Edwin
Beunkコレクション))* ジュリアン・ショヴァン(Vn) ジェレミー・ロレル(指) ル・セルクル・ドゥラルモニー(管弦楽) 録音:2011年10月16日(メッツ・アルセナル劇場でのライヴ録音) |
|
||
| OBS PROMETEO OBS-005(1CD) |
ハイドン:チェロのオブリガートを伴う交響曲集 交響曲第13番ニ長調 Hob.I:13 交響曲第31番ニ長調 Hob.I:31 交響曲第36番変ホ長調 Hob.I:36 |
クリストフ・コワン(Vc,指) セビリャ・バロックO 録音:2010年10月25-27日、ビリャ文化センター・ホール、サン・ホセ・デ・ラ・リンコナダ、セビリャ県、スペイン |
|
||
 Audite AU-95620(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 | 矢野 滋(S) マルガ・ヘフゲン(A) フリッツ・ヴンダーリヒ(T) テオ・アダム(Bs) ディーン・ディクソン(指) ヘッセンRSO(フランクフルト放送響の旧称) ヘッセン放送Cho, 南ドイツ放送Cho 録音:1962年4月13日、フランクフルト・アム・マイン ヘッセン放送ゼンデザール(ライヴ・モノラル) |
| “今生きていて欲しかった指揮者の筆頭!ディーン・ディクソンの比類なき芸術性” | ||
|
||
 AQUARIUS AQVR-336-2(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」(ロシア語歌唱) | ナタリア・シュピレル(S) ザーラ・ドルハーノヴァ(Ms) ニカンドル・ハナーエフ(T) アレクサンドル・バトゥーリン(Bs) ロシア国立Cho 国立合唱学校少年Cho ヘルマン・アーベントロート(指) ソヴィエト国立SO 録音:1951年2月1日、放送ライヴ、モスクワ音楽院大ホール |
|
||
| WARNER TELDEC-2564663139 (3CD) |
チャイコフスキー:交響曲集、他 チャイコフスキー:交響曲第4番、 幻想序曲「ロメオとジュリエット」 交響曲第5番、序曲「1812年」 交響曲第6番「悲愴」 ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」 |
ダニエル・バレンボイム(指)CSO |
 Signum Classics SIGCD-256(1CD) ★ |
ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」(ハース版) | クリストフ・フォン・ドホナーニ(指) フィルハーモニアO 録音:2008年10月30日、ロイヤル・フェスティヴァル・ホール・ライヴ |
| “自ら主張せず、どこまでもブルックナー自身に語らせた理想の名演! | ||
|
||
 Altus ALT-231(1CD) |
ゲルハルト・ボッセ追悼 シューベルト:「ロザムンデ」序曲 モーツァルト:交響曲第39番変ホ長調K.543 ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」* |
ゲルハルト・ボッセ(指)新日本フィル 録音:2010年4月2,3日*/2011年5月13,14日 すみだトリフォニーホール( ライヴ ) |
|
||
 写影 SHHP-C006(DVD) |
ブラームス:交響曲第1番ハ短調Op.68 ピアノ協奏曲第1番ニ短調Op.15* ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.77# |
伊藤恵(P)、藤川真弓(Vn) 朝比奈 隆(指)新日本フィル 収録:1990年2月5日オーチャードホール(ライヴ)、1990年5月1日オーチャードホール(ライヴ)*、1990年4月3日オーチャードホール(ライヴ) リニアPCMステレオ 152’ カラーNTSC 4 : 3 Region All |
| 写影 SHHP-C007(DVD) |
ブラームス:交響曲第2番ニ長調Op.73 交響曲第3番ヘ長調Op.90* ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲イ短調Op.102# |
豊嶋泰嗣(Vn)、上村昇(Vc) 朝比奈 隆(指)新日本フィル 収録:1990年4月3日オーチャードホール(ライヴ) 1990年5月1日オーチャードホール(ライヴ)*、1990年2月5日オーチャードホール(ライヴ)# リニアPCMステレオ 132’’ カラーNTSC 4 : 3 Region All |
 SUPRAPHON SU-4081(2CD) ★ |
カレル・シェイナの芸術 (1)モーツァルト:歌劇「フィガロの結婚」序曲 (2)交響曲第38番「プラハ」 (3)歌劇「皇帝ティートの慈悲」序曲 (4)ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」 (5)シューベルト:交響曲第8「未完成」 (6)マーラー:交響曲第4番ト長調 |
全てカレル・シェイナ(指)チェコPO (1)録音:1962年11月19日プラハ、ルドルフィヌム(ステレオ) (2)録音:1953年8月7日、9月11日プラハ、ルドルフィヌム(・モノラル) (3)録音:1956年4月5日プラハ、ルドルフィヌム(モノラル) (4)録音:1953年3月6-7日&9日プラハ、ルドルフィヌム(モノラル) (5)録音:1950年5月3日プラハ、ドモヴィナ・スタジオ(モノラル) (6)マリア・タウベロヴァー(S) 録音:1950年4月6、7、29日&5月2日プラハ、ドモヴィナ・スタジオ(モノラル) ※2012年最新リマスタリング(エンジニア:ヤン・ルジチャーシュ) |
|
||
 日本伝統文化振興財団 SACG-30001(1SACD) シングルレイヤー |
ブルックナー:交響曲第8番(ノヴァク版) | ロヴロ・フォン・マタチッチ(指)NH響 録音:1984年3月7日 NHKホール(N響 第925回定期公演ライヴ |
|
||
 MELODIYA MELCD-1001879(2CD) ★ 【値下げ再案内!!】 |
シューマン:交響曲集(ジョージ・セル校訂版) 第1番変ロ長調「春」Op.38 第2番ハ長調Op.61 第3番変ホ長調「ライン」Op.97 第4番ニ短調Op.120 |
ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー(指) エストニアSO 録音:1978年 |
|
||
 Linn CKD-400(1SACD) |
ベルリオーズ:幻想交響曲Op.14 歌劇「ベアトリスとベネディクト」序曲 |
ロビン・ティチアーティ(指) スコットランド室内O 録音:2011年11月 エジンバラ・アッシャー・ホール |
|
||
| DACAPO MAR-8.226545(1CD) |
ニールス・マルティンセン:作品集 交響曲第2番「スナップショット交響曲」 3つのトロンボーンのための協奏曲「こうもりの影に」 白雪姫の鏡 Kongen af Himmelby Demo |
ホーカン・ビョルクマン(Tb) シュテファン・シュルツ(Tb) ヨルゲン・ファン・ライエン(Tb) クリスティアン・リンドベルイ(指) オーフスSO |
|
||
| Gala GSMN-001(1CD) |
マーラー:交響曲第7番「夜の歌」 | エドゥアルド・ヴァン・ベイヌム(指) アムステルダム・コンセルトヘボウO 録音:1958年6月4日 ※初出 |
| HOWE RECORDS HWR-1005(2CD) |
ハワード・ショア:ロード・オブ・ザ・リング・シンフォニー [CD1] ~旅の仲間~ (1)第1楽章(予言-ホビット庄の社会秩序-過去の影-マッシュルームへの近道-古森-闇夜の短剣) (2)第2楽章(数々の出会い-指輪は南へ-暗闇の旅-カザド=ドゥムの橋-ロスロリアン-ガンダルフへの哀悼-ロリアンへの別れ-大河-一行の離散) [CD2] ~二つの塔~ (3)第3楽章(石の基盤-スメアゴルならし-ローハンの騎士たち-黒門不通-夕星姫-白の乗り手-木の鬚-禁断の池) (4)第4楽章(角笛城-進めエオルの家の子ら-アイゼンガルドへの道-ゴラムの歌) ~王の帰還~ (5)第5楽章(望みと想い-白の木-ゴンドールの執政-キリス・ウンゴル-アンドゥリル) (6)第6楽章(全ての終わり-王の帰還-灰色港-イントゥ・ザ・ウェスト) |
ルードヴィッヒ・ヴィッキ(指) ケイトリン・ラスク(S)、 21st センチュリー・オーケストラ、 21st センチュリー・コーラス 録音:2011年2月12日、13日、ルツェルンKKLコンサートホールライブ録音(スイス) |
|
||
| Phaedra DDD-92067(1CD) |
イン・フランダース・フィールズVol.67 イェフ・ファン・ホーフ:序曲「追憶」 序曲「ペルセウス」(世界初録音) 交響曲第2番変イ長調 |
イヴォ・ヴェンコフ(指)ヤナーチェクPO 録音:2010年8月 |
|
||
 Helicon HEL-029656(2CD) |
マーラー:交響曲第9番 | レナード・バーンスタイン(指) イスラエルPO 録音:1985年8月25日テルアビブ、マン・オーディトリアム(ライヴ) |
|
||
| NUMERICA NUM-1216(1CD) |
アントニオ・ヴィクトリノ・ダルメイダ(1940-):善良な男の為の交響曲 Op.146 フルート協奏曲 Op.161* 短い序曲 Op.145 ピアノ・ソナタ第5番 Op.44(フェデリコ・フェリーニに献呈)+ |
パウロ・バロス(Fl)* アントニオ・ロザド(P)+ パウロ・マルティンス(指) サンタ・マリア・ダ・フェイラ青年SO 録音:データ記載なし |
 TAHRA TAH-732(2CD) |
フリッチャイの芸術 (1)モーツァルト:フルートとハープのための協奏曲K.299 (2)チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 (3)ブラームス:交響曲第1番 (4)ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 |
フェレンツ・フリッチャイ(指) (1)ハンス・シュミッツ(Fl)、 イルムガルト・ヘルミス(Hp)、RIAS響 (2)ユーディ・メニューイン(Vn)、ルツェルン祝祭O (3)北ドイツRSO、(4)RIAS響 録音:(1)1952年9月17日 (2)1961年8月16日ルツェルン芸術ハウス (3)1958年2月2-3日ハンブルク・ムジークハレ (4)1953年4月7日 |
|
||
 Altus ALT-224(1CD) |
ウィーン・フィル・ライヴ・エディション~クナッパーツブッシュ R.シュトラウス:交響詩」死と変容」 シューマン:交響曲第4番 |
ハンス・クナッパーツブッシュ(指)VPO 録音:1962年12月16日、ムジークフェラインザール(モノラル・ライヴ) |
|
||
 Altus ALT-225(2CD) |
ウィーン・フィル・ライヴ・エディション~クナッパーツブッシュ ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 |
ハンス・クナッパーツブッシュ(指)VPO 録音:1961年10月29日、ムジークフェラインザール(モノラル・ライヴ) |
| “音楽的な条件の全てを持たす、クナの「ブル8」の最高峰!” | ||
|
||
 Globe GLO-5246(1CD) |
ベートーヴェン:「エグモント」序曲 交響曲第4番変ロ長調Op.60 交響曲第7番イ長調Op.92 |
ヨハネス・レールタウアー(指) ニュー・フィルハーモニー・ユトレヒト 録音:2010年9月ライヴ |
|
||
 WEITBLICK SSS-0126-2(1CD) |
シューベルト:交響曲第8番「未完成」 交響曲第9番「ザ・グレート」* |
エフゲニ・スヴェトラーノフ(指) スウェーデンRSO 録音:1986年9月8日ベルワルドホール・ライヴ(ステレオ) 1990年9月18日ベルワルドホール・ライヴ(ステレオ)* ※英語、日本語、ドイツ語によるライナーノート付。 |
| “過去のどんな名演も引き出し得なかった、シューベルトの未知の魅力!” | ||
|
||
 WEITBLICK SSS-0131-2(1CD) |
ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」 スラヴ舞曲第3番Op.46-3 |
エフゲニ・スヴェトラーノフ(指) スウェーデンRSO 録音:1983年1月14日ベルワルドホール・ライヴ(ステレオ) ※英語、日本語、ドイツ語によるライナーノート付。 |
|
||
 GLOR CLASSICS GC-12471(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第1番ハ長調op.21 交響曲第7番イ長調op.92* |
シルヴァン・カンブルラン(指) バーデン=バーデン&フライブルクSWR響 録音:2011年5月21,24日、2000年3月8日* フライブルク・コンツェルトハウス |
|
||
 CD ACCORD ACD-164(1CD) ● |
チャイコフスキー:交響曲第5番Op.64 | イェジー・セムコフ(指) ポーランド青年SO(シンフォニア・ユヴェントゥス) 録音:2009年 |
| ALLEGRO RPM-29220(1CD) |
チャイコフスキー:交響曲第5番Op.64 交響的バラード「地方長官」Op.78 |
フランク・シップウェイ(指)ロイヤルPO 録音:2007年頃 |
| MARQUIS MAR-81421(1CD) |
チャイコフスキー:交響曲第5番Op.64 | ウラディミール・ランデ(指) サンクトペテルブルクSO 録音:2010年6月 |
|
||
 GRAND SLAM GS-2073(1CD) |
シューマン:交響曲第4番 (1)第1楽章第1部(L2209/WAX3845-2*) (2)第1楽章第2部(L2209/WAX3846-1*) (3)第1楽章第3部(L2210/WAX3847-1*) (4)第2楽章(L2210/WAX3848-1) (5)第3楽章第1部(L2211/WAX3849-1*) (6)第3楽章第2部(L2211/WAX3850-1*) (7)第4楽章第1部(L2212/WAX3851-1*) (8)第4楽章第2部(L2212/WAX3852-1) 未発売テイク(1)(2)(3)(5)(6)(7)(*) チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」* (9)第1楽章 (10)第2楽章 (11)第3楽章 (12)第4楽章 |
ブルーノ・ワルター(指) (1)-(8)パリ・モーツァルト祝祭O、 (9)-(12)ベルリン国立歌劇場O* 録音:(1)-(8)1928年6月19日、(9)-(12)1924/1925年(初発売:1925年3月) 使用音源:(1)-(8)Columbia(U.K.)L2209/2012 (9)-(11)Polydor(Germany)69771/69775(B20493-502/1918as/1634as/1919as/16411/2as/1920as/1921as/1750as/1751as/1642as/1643as) |
|
||
 King International KKC-033(1CD) |
宇野功芳/傘寿記念ライヴ ベートーヴェン:交響曲第7番イ長調Op.92 シューベルト:交響曲第8番「未完成」 |
宇野功芳(指) 宇野功芳傘寿記念日本大学OB管 録音:2011年9月19日上野学園石橋メモリアルホール(ライヴ) |
|
||
| UNIVERSAL ITALY 457-1952(1CD) |
シューベルト:交響曲第3番 交響曲第8番ロ短調「未完成」 |
カルロス・クライバー(指) VPO 録音:1978年、ADD 原盤:Deutsche Grammophon |
|
||
 Avie SFS-0040(22LP) ★ |
マーラー:交響曲全集&管弦楽伴奏付き歌曲集 交響曲第1番ニ長調《巨人》 第2番ハ短調《復活》/第3番ニ短調 亡き子をしのぶ歌/第4番ト長調 第5番嬰ハ短調/第6番イ短調《悲劇的》 第7番ホ短調《夜の歌》 第8番変ホ長調《千人の交響曲》 第10番嬰ヘ短調~ アダージョ 交響曲第9番ニ長調/大地の歌 カンタータ《嘆きの歌》 管弦楽伴奏付き歌曲集(さすらう若人の歌 リュッケルト歌曲集 《子供の魔法の角笛》~塔の中の囚人の歌、少年の鼓手、トランペットが美しく鳴り響くところ、死んだ少年鼓手、原光 リュッケルトによる5つの詩(ボーナス・レコーディング) |
マイケル・ティルソン・トーマス(指) サンフランシスコSO ☆ 180g重量盤LP22枚組 ☆ LP マスタリング:Kevin Gray at Acous Tech Mastering ☆ 録音:2001年-2009年、デイヴィス・シンフォニー・ホール ☆ Originally recorded to DSD, remastered at 96k/24bit |
|
||
| IPPNW IPPNW-74(1CD) |
武満徹:弦楽のためのレクイエム チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」 |
アンドレイ・ボレイコ(指) シュターツカペレ・ベルリン 録音:2011年4月26日、フィルハーモニー、ベルリン(ライヴ) |
| IPPNW IPPNW-1DVD (2DVD) |
■DVD1 ショスタコーヴィチ:弦楽四重奏曲第8番(弦楽合奏版) 朗読 テレーゼ・アッフォルテル&クリスチャン・ブリュックナー(朗読) ■DVD2 武満徹:弦楽のためのレクイエム チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」 アンドレイ・ボレイコ(指揮)、シュターツカペレ・ベルリ |
DVD1 ボグダン・プリッシュ(指)ベルリン・フィル弦楽アンサンブル アレクサンダー・イヴィッチ(コンサートマスター) クレド室内cho、 テレーゼ・アッフォルテル&クリスチャン・ブリュックナー(朗読)* DVD2 アンドレイ・ボレイコ(指) シュターツカペレ・ベルリン 録音:2011年4月26日、フィルハーモニー、ベルリン(ライヴ) |
|
||
| ALLEGLO MUSIC RPM-29220(1CD) |
チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調 交響的バラード「ヴォエヴォーダ」 |
フランク・シップウェイ(指)ロイヤルPO 録音:2007年頃(デジタル) |
 韓国EMI EKC31D-1040(31CD) ★ |
Great Recordings of the Century BOX ■CD1 Wolfgang Amadeus Mozart - Symphony No.41 etc. / Beecham, Royal Philharmonic Orchestra ■CD2 Ludwig van Beethoven - Symphonies Nos.5 & 7 / Klemperer ■CD3 Ludwig Van Beethoven - Symphony No.9 'Choral' / Furtwangler ■CD4 Johannes Brahms - Symphony No.4 / Carlo Maria Giulini ■CD5 Georges Bizet - Symphony In C / L'Arlesienne Suites : Sir Thomas Beecham ■CD6 Gustav Mahler - Symphony No.2 'Resurrection' / Klemperer ■CD7 Gustav Mahler - Symphony No.5 / Barbirolli ■CD8 Richard Wagner - Orchestral Music / Karajan ■CD9 Nikolai Rimsky-Korsakov - Scheherazade / Sir Thomas Beecham ■CD10 Ludwig Van Beethoven / Felix Mendelssohn - Violin Concertos : Menuhin / Furtwangler ■CD11 Johannes Brahms / Jean Sibelius - Violin Concerto : Ginette Neveu ■CD12 Johannes Brahms / Max Bruch - Double Concerto / Violin Concerto No.1 / Oistrakh / Fournier ■CD13 Sibelius, Tchaikovsky Violin Concertos & Glazunov : Violin Sonatas / Jascha Heifetz / Barbirolli ■CD14 Ludwig van Beethoven - Piano Concerto 4 & 5 / Emil Gilels |
■CD15 Frederic Chopin - Piano Concertos
/ Samson Francois ■CD16 Antonin Dvorak - Piano Concerto etc. : Richter / Kleiber ■CD17 Edward Grieg / Robert Schumann - Piano Concerto / Richter ■CD18 Rachmaninov / Saint-Saens / Schostakowitsch - Piano Concertos No.3 Etc / Emil Gilels ■CD19 George Gershwin - Rhapsody In Blue, etc. / Andre Previn ■CD20 Joseph Haydn / Luigi Boccherini - Cello Concerto : Du Pre / Barenboim / Barbirolli ■CD21 Antonin Dvorak / Camille Saint-Saens - Cello Concerto / Rostropovich ■CD22 Ludwig Van Beethoven / Franz Schubert - Piano Trio : Cortot / Thibaud / Casals ■CD23 Schubert : String Quartets No.14 'Death and the Maiden' & No.15 / Busch String Quartet ■CD24 Nicolo Paganini - 24 Capricen / Rabin ■CD25 Frintz Kreisler - Original Compositions & Arrangements / Fritz Kreisler ■CD26 Tartini : Sonata in g "Il Trillo del Diavolo" / David Oistrakh ■CD27 Johann Sebastian Bach / Robert Schumann / Ferruccio Busoni / Johannes Brahms : Michelangeli ■CD28 Ludwig Van Beethoven - Piano Sonatas No.21, 23, 30, 31 / Walter Gieseking ■CD29 Chopin: Etudes Op.10 & Op.25 / Claudio Arrau ■CD30, 31 Johann Sebastian Bach - Cello Suites / Paul Tortelier |
|
||
| Metronome (Magdalen) METCD-8004(1CD) |
マーラー:交響曲第4番ト長調 子供の魔法の角笛より* |
マーガレット・リッチー(S)、 エドゥアルト・ファン・ベイヌム(指)アムステルダム・コンセルトヘボウO、 ロルナ・シドニー(Ms)*、 アルフレート・ペル(Br)*、 フェリックス・プロハスカ(指)ウィーン国立歌劇場O* 録音:1952年4月-5月/1950年* ※原盤:Decca LXT 2718/Vanguard VRS 412/3* |
|
||
 MEMBRAN MEM-223425(52CD) |
マスターピース・オブ・クラシカル・ミュージック ■CD:1 BACH Italian Concerto for Keyboard (Harpsichord) in F major, BWV 971 Rudolf Serkin, piano Concerto for Two Violins and Orchestra in D minor, BWV 1043 Yehudi Menuhin, Gioconda de Vito, violin Philharmonia Orchestra London / Anthony Bernard Brandenburg Concerto No. 2 in F major, BWV 1047 Maurice Andre, trumpet Gyorgy Terebesi, violin Kraft Thorwald Dilloo, flute Horst Schneider, oboe Sudwestdeutsches Kammerorchester / Friedrich Tillegant Brandenburg Concerto No. 5 in D major, BWV 1050 Manoug Parikan, violin Raymond Clark, cello Gareth Morris, flute Philharmonia Orchestra London / Edwin Fischer ■CD:2 BARTOK Concerto for Strings, Percussion and Celesta Irwin Fischer, celesta Allan Graham, Lionel Sayers, Thomas Glenecke, Edward Metzenger, percussion and timpani Chicago Symphony Orchestra / Rafael Kubelik Concerto for Orchestra (1943), SZ 116 Chicago Symphony Orchestra / Fritz Reiner ■CD:3 BEETHOVEN Violin Concerto in D major, op. 61 Gerhard Taschner, violin Berliner Philharmoniker / Georg Solti ■CD:4 BEETHOVEN Piano Concerto No. 1 in C major, op. 15 (Live) Friedrich Gulda, piano Wiener Symphoniker / Friedrich Gulda Sonata No. 26 in E-flat major, op. 81a, “Les Adieux” Friedrich Gulda, piano ■CD:5 BERLIOZ Harold in Italy- Symphony with Viola obbligato, op.16 William Primrose, viola Boston Symphony Orchestra / Sergei Koussevitzky Roman Carnival, op. 9 London Philharmonic Orchestra / Victor de Sabata ■CD:6 LEONARD BERNSTEIN (1918 ? 1990) Facsimile, A Choreographic Essay Sidney Foster, piano RCA Victor Symphony Orchestra / Leonard Bernstein The Age of Anxiety Symphony No. 2 for Piano and Orchestra (after H. W. Auden) Lukas Voss, piano New York Philharmonic Orchestra / Leonard Bernstein ■CD:7 BRAHMS Violin Concerto in D major, op. 77 (Live) (Cadenza: Joseph Joachim) Ginette Neveu, violin Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks / Hans Schmidt-Isserstedt Tragic Overture, op. 81 Wiener Philharmoniker / Hans Knappertsbusch ■CD:8 JOHANNES BRAHMS Piano Concerto No. 2 in B-flat major, op. 83 Arthur Rubinstein, piano Boston Symphony Orchestra / Charles Munch ■CD:9 BRUCH Violin Concerto in G minor, op. 26 Ida Haendel, violin Philharmonia Orchestra London / Rafael Kubelik Scottish Fantasy in E-flat major, op. 46 for Violin, Harp and Orchestra Jascha Heifetz, violin RCA Victor Symphony Orchestra / William Steinberg ■CD:10 FREDERIC CHOPIN (1810 ? 1849) Piano Concerto No. 1 in E minor, op. 11 (Live) Arthur Rubinstein, piano New York Philharmonic Orchestra / Bruno Walter Polonaise No. 7 in A-flat major, op. 61 (”Polonaise Fantasy”) Arthur Rubinstein, piano ■CD:11 DVORAK Cello Concerto No. 2 in B minor, op. 104 Mstislav Rostropovich, cello Czech Philharmonic Orchestra / Vaclav Talich Slavonic Dances, op. 46 Czech Philharmonic Orchestra / Vaclav Talich ■CD:12 GEORGE GERSHWIN (1898 ? 1937) Piano Concerto in F major Rhapsody in Blue Jerome Hanson, piano New York Civic Youth Orchestra / Allan Morton ■CD:13 GRIEG Piano Concerto in A minor, op. 16 Arthur Rubinstein, piano RCA Victor Symphony Orchestra / Antal Dorati From “Peer Gynt”, Suites No. 1, op. 46, and No. 2, op. 55 Statsradiofoniens symfoniorkester / Anders Norquist ■CD:14 HANDEL Organ Concerto No. 8 in A major Organ Concerto No. 16 in D minor, op. 7 No. 4 Geraint Jones, organ Philharmonia Orchestra London / Wilhelm Schuchter The Great Elopment Ballet Suite, arranged by Thomas Beecham The Pump Room The Linleys Hunting Dance London Philharmonic Orchestra / Thomas Beecham ■CD:15 LISZT Piano Concerto No. 1 in E-flat major Geza Anda, piano Philharmonia Orchestra London / Otto Ackermann JOHANNES BRAHMS Hungarian Dance No. 1 in G minor Hungarian Dance No. 2 in D minor Hungarian Dance No. 3 in F major Hungarian Dance No. 5 in G minor Hungarian Dance No. 6 in D major Hungarian Dance No. 7 in A major Hungarian Dance No. 10 in F major Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks / Hans Schmidt-Isserstedt LISZT Les Preludes Symphonic Poem No. 3 Wiener Philharmoniker / Wilhelm Furtwangler ■CD:16 MENDELSSOHN Violin Concerto in D minor, op. 40 (1822) Yehudi Menuhin, violin RCA Victor String Orchestra Violin Concerto in E minor, op. 64 (1844) Yehudi Menuhin, violin Berliner Philharmoniker / Wilhelm Furtwangler ■CD:17 LEOPOLD MOZART (1719 ? 1787) Sinfonia di caccia in G major for Four Horns, Strings, Timpani and Basso continuo Hermann Baumann, Christoph Kohler, Mahir Cakar, Jean-Pierre Lepetit, horn Concerto Amsterdam / Jaap Schroder Sinfonia di Camera in D major for Horn, Violin, Two Violas and Basso continuo Hermann Baumann, horn Jaap Schroder, violin Concerto Amsterdam / Jaap Schroder MOZART Serenade for Thirteen Wind Instruments No. 10 in B-flat major, KV 361 Wiener Philharmoniker Soloists / Wilhelm Furtwangler ■CD:18 MOZART Piano Concerto No. 20 in D minor, KV 466 Piano Concerto No. 23 in A major, KV 488 Arturo Benedetti Michelangeli, piano Orchestra Sinfonica di Roma della RAI / Carlo Maria Giulini ■CD:19 MOZART Clarinet Concerto in A major, KV 622 Benny Goodman, clarinet Boston Symphony Orchestra / Charles Munch (recorded at the Berkshire Festival) Flute Concerto in G major, KV 313 (Cadenzas: Karlheinz Stockhausen) Kathinka Pasveer, flute Radio-Symphonie-Orchester Berlin / Karlheinz Stockhausen ■CD:20 MOZART Horn Concerto No. 1 in D major, KV 412 Dennis Brain, horn Philharmonia Orchestra London / Herbert von Karajan Horn Concerto No. 2 in E-flat major, KV 417 Dennis Brain, horn Philharmonia Orchestra London / Walter Susskind Horn Concerto No. 3 in E-flat major, KV 447 Horn Concerto No. 4 in E-flat major, KV 495 Dennis Brain, horn Philharmonia Orchestra London / Herbert von Karajan ■CD:21 MOZART Violin Concerto No. 4 in D major, KV 218 Yehudi Menuhin, violin Philharmonia Orchestra London / John Pritchard Violin Concerto No. 5 in A major, KV 219 David Oistrakh, violin Radio Symphony Orchestra of the Soviet Union / Kyrill Kondraschin Adagio for Violin and Orchestra in E major, KV 261 Rondo in C major, KV 373 Nathan Milstein, violin RCA Victor Symphony Orchestra / Vladimir Golschmann ■CD:22 NICCOLO PAGANINI (1782 ? 1840) Violin Concerto No. 1 in D major, op. 6 Zino Francescatti, violin Philadelphia Orchestra / Eugene Ormandy Violin Concerto No. 2 in B minor, op. 7 Yehudi Menuhin, violin Philharmonia Orchestra London / Anatole Fistoulari ■CD:23 RACHMANINOV Piano Concerto No. 2 in C minor, op. 18 Svjatoslav Richter, piano Leningrad Philharmonic Orchestra / Kurt Sanderling Prelude in G major, op. 32, No. 5 Prelude in G minor, op. 23, No. 5 Geza Anda, piano ■CD:24 RACHMANINOV Piano Concerto No. 3 in D minor, op. 30 Wladimir Horowitz, piano RCA Victor Symphony Orchestra / Fritz Reiner Vokalise, op. 34, No. 14 (Rachmaninov Version for Solo Orchestra) Philadelphia Orchestra / Sergei Rachmaninov ■CD:25 RAVEL Piano Concerto in G major Leonard Bernstein, piano Philharmonia Orchestra London / Leonard Bernstein MUSSORGSKY (1839-1881) Pictures At An Exhibition (orchestral version by Maurice Ravel) NBC Symphony Orchestra / Arturo Toscanini ■CD:26 RAVEL Piano Concerto for the Left Hand Robert Casadesus, piano Philadelphia Orchestra / Eugene Ormandy La valse, Bolero Pittsburgh Symphony Orchestra / William Steinberg ■CD:27 ROBERT SCHUMANN Piano Concerto in A minor, op. 54 (Live) Dinu Lipatti, piano Orchestre de la Suisse Romande / Ernest Ansermet Introduction and Allegro appassionato for Piano and Orchestra, op. 92 Malcolm Frager, piano Philharmonisches Staatsorchester Hamburg / Marc Andreae ■CD:28 SCHUMANN Cello Concerto in A minor, op. 129 Pierre Fournier, cello Philharmonia Orchestra London / Malcolm Sargent Kreisleriana, Fantasies for the Pianoforte, op. 16 Wladimir Sofronitzki, piano ■CD:29 SHOSTAKOVICH Concerto No. 1 for Piano, Trumpet and String Orchestra in C major, op. 35 (1933) Dimitri Shostakovich, piano Iwan Wolownik, trumpet Symphony Orchestra of the Moscow State Philharmonic / Samuil Samossud Piano Concerto No. 2 in E major, op. 192 (1957) (dedicated to Maxim Shostakovich) Dimitri Shostakovich, piano Soviet Union Great Radio Symphony Orchestra / Alexander Gauk Concertino for Two Pianos, op. 94 (1953) Maxim and Dimitri Shostakovich, piano ■CD:30 SIBELIUS Violin Concerto in D minor, op. 47 Isaac Stern, violin Royal Philharmonic Orchestra / Thomas Beecham Finlandia, op. 26 No. 7 Valse triste, op. 44 The Swan of Tuonela, op. 22 No. 3 Bolero (Festivo) Berliner Philharmoniker / Hans Rosbaud CD31 RICHARD STRAUS Horn Concerto No. 1 in E-flat major Horn Concerto No. 2 in E-flat major Dennis Brain, horn Philharmonia Orchestra London / Wolfgang Sawallisch Waltzes from “Knight of the Rose” Orchestre de la Radiodiffusion Nationale Belge, Bruxelles / Franz Andre ■CD:32 STRAVINSKY Concerto for Orchestra in D major Halle Orchestra / John Barbirolli Jeu de cartes (Card Game) Ballet in Three Deals Berliner Philharmoniker / Igor Stravinsky Duo concertante for Violin and Piano Joseph Szigeti, violin Igor Stravinsky, piano ■CD:33 SZYMANOWSKI Symphony concertante for Piano and Orchestra, op. 60 Arthur Rubinstein, piano Los Angeles Philharmonic / Alfred Wallenstein DEBUSSY Images 1, Images 2 Cloches a travers les feuilles Et la lune descent sur temple quit fu Poissons d’or Walter Gieseking, piano |
■CD:34 TCHAIKOVSKY Piano Concerto No. 1 in B-flat minor, op. 23 Wladimir Horowitz, piano NBC Symphony Orchestra / Arturo Toscanini Overture solennelle “1812”, op. 49 Minneapolis Symphony Orchestra University of Minnesota Brass Band Bells and Bronze Cannon / Antal Dorati ■CD:35 TCHAIKOVSKY Violin Concerto in D major, op. 35 Yehudi Menuhin, violin RIAS Symphony Orchestra / Ferenc Fricsay Slavonic March, op. 31 Royal Philharmonic Orchestra / Yehudi Menuhin Serenade for String Orchestra in C major, op. 48 Boston Symphony Orchestra / Charles Munch ■CD:36 VIVALDI (arr.: Siegfried Behrend) Symphony for Mandolin and Plucked Strings in C major Takashi Ochi, mandolin Das Deutsche Zupforchester / Siegfried Behrend Concerto grosso for Two Mandolins, Two Guitars and Plucked Strings Silvia and Takashi Ochi, mandolin Elfi Germesin and Tadashi Sasaki, guitar Das Deutsche Zupforchester / Siegfried Behrend Concerto for Solo Mandolin and Plucked Strings in C major Takashi Ochi, mandolin Das Deutsche Zupforchester / Siegfried Behrend Concerto for Two Mandolins and Plucked Strings in G major Silvia and Takashi Ochi, mandolin Das Deutsche Zupforchester / Siegfried Behrend Lute Concerto for Plucked Strings Das Deutsche Zupforchester / Siegfried Behrend Concerto for Guitar and Plucked Strings Martin Kruger, guitar Das Deutsche Zupforchester / Siegfried Behrend Concerto for Viola d’amore, Lute and Plucked Strings in D minor Tadashi Sasaki, lute Reimer Peters, viola d’amore Das Deutsche Zupforchester / Siegfried Behrend ■CD:37 HANDEL Concerto for Oboe and String Orchestra in G minor, op. 3 No. 10 Frantisek Hantak, oboe Czech Philharmonic Orchestra / Vaclav Talich Concerto for Oboe and String Orchestra in B-flat major, op. 3 No. 8 Severino Passetti, oboe Camerata sinfonica di Milano GABRIELLI (1659 ? 1690) (arr.: Siegfried Behrend) Concerto for Oboe and Plucked Strings in D major Pierre W. Feit, oboe Das Deutsche Zupforchester / Siegfried Behrend DALL’ ABACO (1675 ? 1742) (arr.: Siegfried Behrend) Concerto for Oboe and Plucked Strings in C major Pierre W. Feit, oboe Das Deutsche Zupforchester / Siegfried Behrend VIVALDI (arr.: Siegfried Behrend) Concerto for Oboe and Plucked Strings in C major Pierre W. Feit, oboe Das Deutsche Zupforchester / Siegfried Behrend Concerto for Two Oboes and Plucked Strings in C major Pierre W. Feit and Diethelm Jonas, oboe Das Deutsche Zupforchester / Siegfried Behrend BENEDETTO MARCELLO (1686 ? 1739) Concerto for Oboe and String Orchestra in D minor Severino Passetti, oboe Camerata sinfonica di Milano ■CD:38 KORNGOLD Violin Concerto in D major, op. 35 Jascha Heifetz, violin Los Angeles Philharmonic / Alfred Wallenstein MIKLOS ROZSA Concerto, op. 24 Jascha Heifetz, violin Dallas Symphony Orchestra / Walter Hendl ■CD:39 BOCCHERINI Cello Concerto No. 9 in B-flat major (arr.: Friedrich Grutzmacher) VIVALDI Cello Concerto in E minor (arr.: Vincent d’Indy, after the Sonata in E minor, RV 40) JOSEPH HAYDN (1732 ? 1809) Cello Concerto No. 2 in D major Pierre Fournier, cello Stuttgarter Kammerorchester / Karl Munchinger ■CD:40 ELGAR Cello Concerto in E minor, op. 85 Pablo Casals, cello BBC Symphony Orchestra / Adrian Boult SAINT-SAENS Cello Concerto No. 1 in A minor, op. 33 Pierre Fournier, cello Philharmonia Orchestra London / Walter Susskind ■CD:41 EDOUARD LALO (1823 ? 1891) Symphony espagnole for Violin and Orchestra, op. 21 David Oistrakh, violin Philharmonia Orchestra London / Jean Martinon FAURE Elegy, op. 24 (1880) Berceuse, op. 16 (1878) Pierre Fournier, cello Ernest Lush, piano SAINT-SAENS The Swan from”Carnival of the Animals” (1886) Pierre Fournier, cello Gerald Moore, piano ■CD:42 SAINT- SAENS Piano Concerto No. 2 in G minor, op. 22 (Live) Arthur Rubinstein, piano Minneapolis Symphony Orchestra / Dimitri Mitropoulos FALLA Noches en los jardines de Espana (Nights in the Gardens of Spain) Arthur Rubinstein, piano San Francisco Symphony Orchestra / Enrique Jorda ■CD:43 HAYDN (1732 ? 1806) Trumpet Concerto in E-flat major L.MOZART Concerto for Solo Trumpet, Two Horns, Strings and Harpsichord in D major HUMMEL Trumpet Concerto in E-flat major Carol Dawn Reinhart, trumpet Munchner Philharmoniker / Marc Andreae TELEMANN Trumpet Concerto in D major JOHANN FRIEDRICH FASCH (1688 ? 1758) Trumpet Concerto in D major ALBINONI (1671 ? 1750) Sonata in C for Trumpet, Strings and Basso continuo PURCELL Sonata in D major for Trumpet, Strings and Basso continuo HANDEL Suite in D major from “Water Music” for Trumpet, Strings and Basso continuo Carole Dawn Reinhart, trumpet Deutsche Bachsolisten / Helmut Winschermann CLARKE (arr.: Wolfgang Ebert) Carole Dawn Reinhart, trumpet Symphony Orchestra Graunke / Heinz Fricke ■CD:44 DANZI Bassoon Concerto in F major Karl Otto Hartmann, bassoon Concerto Amsterdam / Jaap Schroder Sinfonia Concertante in B-flat major for Clarinet, Bassoon and Orchestra Dieter Klocker, clarinet Karl Otto Hartmann, bassoon Concerto Amsterdam / Jaap Schroder FRANZ XAVER RICHTER Concerto in D major for Trumpet, Strings and Basso continuo Joao Costa, trumpet Soloists Ensemble Lisbon ■CD:45 VIVALDI Concerto for Two Trumpets in C major Fred Hausdoerfer, Harry Sevenstern, trumpet Netherlands Philharmonic Orchestra / Otto Ackermann POKORNY (1729 ? 1794) Flute Concerto in D major Frans Vester, flute Concerto Amsterdam / Jaap Schroder MOZART Serenade for Wind Instruments in B-flat major “Gran Partita”, KV 361/370a (Live) Czech Philharmonic Orchestra Wind Society / Vaclav Talich ■CD:46 FRIEDRICH II. VON PREUSSEN (1712 ? 1786) Concerto No. 3 in C major for Flute, Strings and Basso continuo Werner Tast, flute Kammerorchester Berlin / Peter Gulke C.P.E.BACH Concerto in G major for Flute, Strings and Basso continuo Werner Tast, flute Kammerorchester der Staatskapelle Weimar / Wolf-Dieter Hauschild QUANTZ (1697 ? 1773) Concerto in D major “pour Potsdam” for Flute, Strings and Basso continuo Eberhard Grunenthal, flute Kammerorchester Berlin / Heinz Schunk ■CD:47 OFFMEISTER Clarinet Concerto in B-flat major THEODOR BARON VON SCHACHT (1748 ? 1823) Clarinet Concerto in B-flat major JOHANN GEORG HEINRICH BACKOFEN (1768 ? 1830) Sinfonia Concertante for Two Clarinets and Orchestra in A major, op. 10* Dieter Klocker, Waldemar Wandel*, clarinet Concerto Amsterdam / Jaap Schroder ■CD:48 BERG Violin Concerto (Live) (“To the Memory of an Angel”) Joseph Szigeti, violin NBC Symphony Orchestra / Dimitri Mitropoulos SCHONBERG Piano Concerto, op. 42 Glenn Gould, piano CBC Radio Symphony Orchestra / Jean-Marie Beaudet WEBERN Variations for Piano, op. 27 Glenn Gould, piano ■CD:49 DELIUS Piano Concerto (1914 / 16) Benno Moiseiwitsch, piano BBC Symphony Orchestra / Malcolm Sargent ELGAR Introduction & Allegro, op. 47 Boston Symphony Orchestra / Charles Munch BRITTEN Four Interludes, op. 33a from ”Peter Grimes” Concertgebouw-Orchester Amsterdam / Eduard van Beinum ■CD:50 KREISLE Violin Concerto in C major (“In the style of Vivaldi”) Fritz Kreisler, violin RCA Victor String Orchestra / Donald Voorhees Rondino on a Theme by Beethoven Nathan Milstein, violin BEETHOVEN Variations in E-flat major on “Bei Mannern, welche Liebe fuhlen” from “Die Zauberflote” (W. A. Mozart) Variations in F major on “Ein Madchen oder Weibchen” from “Die Zauberflote” (W. A. Mozart) Pablo Casals, cello Rudolf Serkin, piano MOZART Serenade No. 13 in G major, KV 525 “A Little Night Music” Wiener Philharmoniker / Herbert von Karajan ■CD:51 BIZET WAXMAN “Carmen” ? Fantasy Jascha Heifetz, violin RCA Victor Symphony Orchestra / Donald Voorhees DUKAS The Sorcerer’s Apprentice L’Orchestre des Concerts Lamoureux, Paris / Ferenc Fricsay BERLIOZ Overture to ”Benvenuto Cellini” Overture to “Le Corsaire”* Orchestre de la Societe des Concerts du Conservatoire Paris / Charles Munch Hungarian March from “The Damnation of Faust” Berliner Philharmoniker / Ferenc Fricsay ■CD:52 GLASUNOW Violin Concerto in A minor, op. 82 Nathan Milstein, violin RCA Victor Symphony Orchestra / William Steinberg BORODIN(arr.: Alexander Glasunow) Steppes of Central Asia RIAS Symphony Orchestra / Ferenc Fricsay Polovetzian Dances from “Prince Igor” Choeurs et Orchestre National de la Radiodiffusion Francaise / Igor Markevitch MUSSORGSKY Night on the Bare Mountain Orchestre National de la Radiodiffusion Francaise / Igor Markevitch GLIERE Sailors‘Dance from “The Red Poppy”, op. 70 Hollywood Bowl Orchestra / Carmen Dragon KHATCHATURIAN Sabre Dance from “Gayaneh” Hollywood Bowl Orchestra / Carmen DragonHerbert von Karajan, |
|
||
| FHK FHK-001-2(1CD) |
ブルックナー:交響曲第9番(ノヴァーク版) | アンドレアス・セバスティアン・ヴァイザー(指)
フラデツ・クラーロヴェーPO 録音:2008年4月24日、フラデツ・クラーロヴェー・フィルハーモニー・ホール、ライヴ |
|
||
| FHK FHK-002-2(1CD) |
マーラー:交響曲第6番「悲劇的」 | アンドレアス・セバスティアン・ヴァイザー(指)
フラデツ・クラーロヴェーPO 録音:2008年4月24日、フラデツ・クラーロヴェー・フィルハーモニー・ホール、ライヴ |
| DACAPO MAR-8.206002 (CD+SACD+DVD) |
ニールセン:作品集第1集…管弦楽作品集 [CD] 交響曲 第3番 ニ短調「広がり」 Op.27 交響曲 第2番 ロ短調「四つの気質」 交響曲 第4番「滅ばざるもの」 交響曲 第5番 Op.50 交響曲 第1番 ト短調 Op.7 交響曲 第6番「素朴な交響曲」 [SACD] 歌劇「仮面舞踏会」序曲 歌劇「仮面舞踏会」~コッケレルの踊り 劇音楽「領主オールフは馬を駆り」前奏曲 [DVD] メロドラマ「スネフリズ」組曲 FS.17 歌劇「サウルとダヴィデ」第2幕前奏曲 狂詩曲風序曲「フェロー諸島への幻想の旅行」FS.123 劇音楽「ヴィレモエス」第3幕前奏曲 パンとシリンクス~「田園の情景」 劇音楽「アモルと詩人」「序曲」 序曲「ヘリオス」Op.17 ■DVD 交響曲 第1番 交響曲 第2番「四つの気質」 交響曲 第3番「広がり」 交響曲 第4番「滅ばざるもの」 交響曲 第5番 交響曲 第6番「素朴な交響曲」 |
ミハエル・シェンヴァント(指) トマス・ダウスゴー(指) デンマーク国立SO インガー・ダム=イエンセン(S) ポウル・エルミング(T) ニール・トムセン(Cl) トム・ニブエ(スネア・ドラム) 録音:1999年5月~2006年9月 DVD…2000年11月2.4日ライブ |
|
||
 DACAPO DACAPO-912(1CD) |
シューベルト:交響曲第8番「未完成」 ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」 |
マティアス・ゲオルク・ケンドリンガー(指) K&KフィルハーモニーO 録音:2009年5月27日、リューベック |
|
||
| DACAPO DACAPO-917(1CD) |
ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 「エグモント」序曲 |
マティアス・ゲオルク・ケンドリンガー(指) K&KフィルハーモニーO 録音:2009年5月28日、リューベック |
|
||
 MEMBRAN DOC-233373(10CD) |
オットー・クレンペラー名演集 (1)ブラームス:交響曲第1番 (2)ブラームス:交響曲第3番 (3)ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」、第7番、第8番 (4)ベートーヴェン:交響曲全集、 劇音楽「エグモント」(抜粋) (5)ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 (6)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番 |
全て、オットー・クレンペラー(指) (1)ケルンRSO 録音:1955年 (2)フィルハーモニアO 録音:1959年 (3)ケルンRSO、ウィーンSO 録音:1954、1957、1958年(詳細不明) (4)ビルギット・ニルソン、 マリア・シュターダー、グレース・ホフマン、 ヴァルデマール・クメント、ハンス・ホッター ケルンRSO、同cho フィルハーモニアO、 ロイヤル・ストックホルムPO、ケルンRSO 録音:1954,1955,1957,1958,1960年(詳細不明) (5)ゲザ・アンダ(P)、ケルンRSO 録音:1954 (6)レオン・フライシャー(P)、ケルンRSO 録音:1956年 |
| DACAPO MAR-6.220538(1SACD) |
モーツァルト:交響曲集第3集 交響曲第9番ハ長調 K73(K75A) 交響曲ニ長調 K81(K73L) 交響曲ニ長調 K97(K73M) 交響曲ニ長調 K95(K73N) 交響曲第11番ニ長調 K84(K73Q) 交響曲第10番ト長調 K74 |
アダム・フィッシャー(指) デンマーク国立室内O 録音:2010年コペンハーゲン DRコンサートハウス第2スタジオ |
|
||
 写影 SHHP-C005(3DVD) 完全限定盤 税込定価 |
朝比奈隆/ブラームス交響曲全集&協奏曲全集 (1)交響曲第1番ハ短調Op.68 (2)ピアノ協奏曲第1番** (3)ヴァイオリン協奏曲## (4)交響曲第2番ニ長調Op.73 (5)交響曲第3番ヘ長調Op.90 (6)ヴァイオリンとチェロの為の二重協奏曲# (7)ピアノ協奏曲第2番* ■特典映像 インタビュー「実相寺昭雄監督と朝比奈隆先生の思い出」 (8)交響曲第4番ホ短調Op.98 |
朝比奈隆(指) 新日本フィルハーモニーSO 伊藤恵(P)**、藤川真弓(Vn)## 豊嶋泰嗣(Vn)#、上村昇(Vc)# 園田高弘(P)* 収録:(1)1990年2月5日オーチャードホール(ライヴ) (2)1990年5月1日オーチャードホール(ライヴ) (3)1990年4月3日オーチャードホール(ライヴ) (4)1990年4月3日オーチャードホール(ライヴ) (5)1990年5月1日オーチャードホール(ライヴ) (6)1990年2月5日オーチャードホール(ライヴ) (7)1990年6月1日オーチャードホール(ライヴ) (8)1990年6月1日オーチャードホール(ライヴ) |
|
||
| MEMBRAN DOC-233361(10) |
フェレンツ・フリッチャイ名演集 ■CD1: (1)バルトーク:ピアノ協奏曲第2番 (2)バルトーク:ピアノ協奏曲第3番 ■CD2: バルトーク:ピアノのためのラプソディOp.1 弦楽器打楽器とチェレスタのための音楽 ■CD3: (1)モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番 (2)モーツァルト:「後宮からの逃走」序曲、 「魔笛」序曲/「僧侶の行進」、 「フィガロの結婚」序曲 ■CD4: モーツァルト:歌劇「ドン・ジョヴァンニ」(抜粋) ■CD5: (1)ベートーヴェン:交響曲第1番 (2)ベートーヴェン:交響曲第8番 ■CD6: ベートーヴェン:交響曲第7番、 「レオノーレ」序曲第3番 ■CD7: (1)チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 (2)ストラヴィンスキー:ヴァイオリン協奏曲 ■CD8: (1)マーラー:リュッケルトの詩による5つの歌曲 (2)バルトーク:カンタータ・プロファーナ「9匹の魔法にかけられた鹿」 ■CD9: (1)リムスキー=コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 (2)フランク:交響的変奏曲 ■CD10: (1)J・シュトラウス:美しく青きドナウ、 ウィーン気質、「こうもり」序曲、 「ジプシー男爵」序曲 (2)ファリャ:スペインの庭の夜 |
全て、フェレンツ・フリッチャイ(指) ■CD1: (1)ゲザ・アンダ(P)、RIAS響<1953年> (2)ルイス・ケントナー(P)、RIAS響<1950年> ■CD2: アンドール・フォルデス(P)、RIAS響<1951年、1952年> ■CD3: (1)クララ・ハスキル(P)、RIAS響<1954年> (2)RIAS響<1954年> ■CD4: ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(ドン・ジョヴァンニ) セーナ・ユリナッチ(ドンナ・アンナ) マリア・シュターダー(ドンナ・エルヴィラ) カール・クリスティアン・コーン(レポレッロ) エルンスト・ヘフリガー(ドン・オッターヴィオ) イルムガルト・ゼーフリート(ツェルリーナ) イヴァン・サルディ(マゼット) ヴァルター・クレッペル(騎士長) RIAS室内cho、ベルリンRSO<1958年 ステレオ> ■CD5: (1)BPO<1953年> (2)RIAS響<1954年> ■CD6: RIAS響<1953年、1952年> ■CD7: (1)イェフディ・メニューイン(Vn)、 RIAS響<1949年> (2)アルテュール・グリュミオー(Vn)、 ケルンRSO<1951年> ■CD8: (1)モーリン・フォレスター(A) ベルリンRSO<1958年 ステレオ> (2)ヘルムート・クレプス(T) ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(Br) RIAS室内cho、 ベルリン聖ヘドヴィヒ大聖堂cho RIAS響<1951年> ■CD9: (1)ベルリンRSO、ルドルフ・ショルツ(Vn)<1956年> (2)マルグリット・ヴェーバー(P) ベルリンRSO<1957年> ■CD10: (1)RIAS響<1949年、1951年、1952年> (2)マルグリット・ヴェーバー(P)、 ベルリンRSO<1957年> |
|
||
| MEMBRAN DOC-233362(10) |
ジョージ・セル名演集 ■CD1-2: ドヴォルザーク:交響曲第8番*、 交響曲第9番「新世界より」 ブラームス:交響曲第3番* ■CD3: (1)シューマン:交響曲第1番「春」、 (2)ウェーバー:ピアノ小協奏曲 ■CD4 シューマン:交響曲第2番、 「マンフレッド」序曲* ■CD5 モーツァルト:交響曲第33番* ピアノ協奏曲第24番* ■CD6 モーツァルト:ピアノ協奏曲第26番「戴冠式」 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 ■CD7 ハイドン:交響曲第88番「V字」、第97番* ■CD8: ハイドン:第104番「ロンドン」 モーツァルト:ディヴェルティメント第2番* ■CD9: (1)シューベルト:「ロザムンデ」~序曲/バレエ音楽第2番/間奏曲第3番/間奏曲第1番 (2)J・シュトラウス:美しく青きドナウ* ■CD10: (1)メンデルスゾーン:真夏の夜の夢~序曲/スケルツォ/夜想曲/結婚行進曲 (2)スメタナ(セル編):弦楽四重奏曲第1番「わが生涯より」(管弦楽版)* |
■CD1-2: アムステルダム・コンセルトヘボウO<1951年>*、 クリーヴランドO<1958年ステレオ> ■CD3 (1)クリーヴランドO<1958年ステレオ> (2)ロベール・カサドシュ(P)、クリーヴランドO<1952年> ■CD4 クリーヴランドO<1958年*、1957年ステレオ・ライヴ(ルガーノ)> ■CD5 クリーヴランドO<1955年>* ロベール・カサドシュ(P)、コロンビアSO<19547年> ■CD6 ロベール・カサドシュ(P)、コロンビアSO クリフォード・カーゾン(P)*、LPO** <1954年、1949年* > ■CD7 クリーヴランドO<1954年、1957年* > ■CD8: クリーヴランドO<1954年、1955年*> ■CD9: (1)アムステルダム・コンセルトヘボウO<1957年> (2)VPO<1937年> ■CD10: (1)アムステルダム・コンセルトヘボウO<1957年> (2)クリーヴランドO<1949年*> |
|
||
| ARCO DIVA UP-0134-2(1CD) |
マーラー:交響曲第1番ニ長調 アルマ・マーラー:中声と管弦楽の為の7つの歌* |
バルボラ・ポラーシコヴァー(Ms)* ズデニェク・マーツァル(指)プラハSO 録音:データ未詳 |
| MEMBRAN NCA-60234(1CD) |
リスト:ダンテ交響曲、 システィーナ礼拝堂への祈り |
マーティン・ハーゼルベック(指) ウィーン・アカデミーO シネ・ノミネchoウーマン・シンガーズ 録音:2010年10月24-26日 |
| IPPNW IPPNW-72(1CD) |
ハイドン:交響曲第67番ヘ長調 アンタル・ドラティ:交響曲第2番「平和の訴え」 |
アンドレイ・ボレイコ(指)ベルンSO 録音:2010年5月20日ベルン クルトゥア-カジノ大ホール |
|
||
|
| このサイト内の湧々堂オリジナル・コメントは、営利・非営利の目的の有無に関わらず、 これを複写・複製・転載・改変・引用等、一切の二次使用を固く禁じます。 万一、これと類似するものを他でお見かけになりましたら、メールでお知らせ頂ければ幸いです。 |
Copyright (C) 2004 WAKUWAKUDO All Rights
Reserved.

 カール・アウグスト・ビュンテ(CD ではすべてCarl
A. Bunte の表記)は1925年、ベルリン生まれ。ベルリンで学び、四半世紀近くベルリンを拠点として活動してきた名匠。演奏会オーケストラの激戦地ベルリンで長く信頼を勝ち取ってきただけに、ドイツの伝統をしっかりと聞かせてくれます。今回、多くの初出音源を含む若き日の演奏がCD化された(2枚は既に流通済み)。実力に反して録音の極めて少ないビュンテだけに、貴重なものばかりで。ビュンテは、1949年から1967年までベルリン交響楽団(Berliner
Symphonisches Orchester) の首席指揮者。このオーケストラがドイツ交響楽団と合併してベルリン交響楽団(Symphonischen
Orchesters Berlin)になったことで、1967年から1973
年までこの新生ベルリン交響楽団の首席指揮者。その後は各地のオーケストラに客演しつつ、教職に力を入れ、ベルリン芸術大学教授、東京芸術大学名誉教授の称号を持っています。
カール・アウグスト・ビュンテ(CD ではすべてCarl
A. Bunte の表記)は1925年、ベルリン生まれ。ベルリンで学び、四半世紀近くベルリンを拠点として活動してきた名匠。演奏会オーケストラの激戦地ベルリンで長く信頼を勝ち取ってきただけに、ドイツの伝統をしっかりと聞かせてくれます。今回、多くの初出音源を含む若き日の演奏がCD化された(2枚は既に流通済み)。実力に反して録音の極めて少ないビュンテだけに、貴重なものばかりで。ビュンテは、1949年から1967年までベルリン交響楽団(Berliner
Symphonisches Orchester) の首席指揮者。このオーケストラがドイツ交響楽団と合併してベルリン交響楽団(Symphonischen
Orchesters Berlin)になったことで、1967年から1973
年までこの新生ベルリン交響楽団の首席指揮者。その後は各地のオーケストラに客演しつつ、教職に力を入れ、ベルリン芸術大学教授、東京芸術大学名誉教授の称号を持っています。