| 湧々堂HOME | 新譜速報:交響曲 管弦楽曲 協奏曲 器楽曲 室内楽 声楽曲 オペラ バロック 廉価盤 シリーズもの マニア向け | |||
| 殿堂入り:交響曲 管弦楽 協奏曲 器楽曲 室内楽 声楽曲 オペラ バロック | SALE!! | レーベル・カタログ | チャイ5 | |
| Tresures |
| CD音楽業界が売筋至上主義を爆進する中、その反動として、板起こしCDR復刻盤が増えているのは自然な成り行きと言えましょう。しかし、この復刻盤の内容には、首をかしげたくなることが多々あります。「レア音源使用」とか「CD化されていない」とか「資料的価値が高い」といった触れ込みは、音楽的な味わいとは直接関係がないことで、肝心なのは、製作者がその演奏の「どこが魅力的なのか」をきちんと認識し、あえて復刻する意義を聴き手に発信することではないでしょうか。その理想を追い求めるのが“Tresures”です。是非、「ここでしか味わえない感動」を味わってください! ■「王道」も「マニアック」もない! “Tresures”は、決して一部のマニアだけを念頭に置いたレーベルではありません。「マニアックか王道路線か」、「知名度が高いかどうか」、そして「売れるかどうか」…、これらの線引きを極力取り除きたいと考えております。 「この曲はいろいろな演奏で聴いたけど、結局は昔聴いたあの演奏に行き着く」という経験をお持ちの方も多いかと思います。本当に感動した演奏というものは、録音の新旧を問わず、演奏家の知名度にも関係なく、長年聴き手の心に深く刻み込まれるものです。「ヒストリカルはちょっと…」と尻込みされていた方にも、演奏そのものが魅力的であれば、感動に出会える機会が増えるいうことを知っていただきたいのです。 ■専らCDを聴いて育った方々へ 長年音楽を愛されている方には勿論のこと、有名名盤をCDでしか聴いたことのない方々にも、「この演奏の凄さはこんなもんじゃない!」ということを是非して知っていただきたいのです。そのため“Tresures”では、何度もCD化された音源でも、あえて復刻することもあります。レコードをリアルタイムで聴いていない人たちにとっては、CDから出てくる音だけが演奏の良し悪し、好き嫌いの判断材料となるわけですが、その音を聞いても、高評価の理由が全く理解できなかったとしたら、こんな残念なことはありません。フルトヴェングラーやストコフスキー等の強烈な個性を持つ演奏なら、安易な復刻盤でもある程度はその雰囲気は伝わるでしょう。しかし、一見地味でひたひたと染みてくるようなタイプの演奏は、楽音の質感、量感が少しでも損なわれると、平凡な演奏にしか聞こえないことが多々あります。宇野功芳氏の推薦盤として知られるクリップスの「チャイ5」などはその良い例で、過去発売された正規CDは、どれも完敗です。 また、こういったアナログの魅力に気付きつつも、底なし沼にハマるのを恐れている人が結構多い気がします。これまたもったいない話です。実は私自身、レコード盤との関わりを長年避け続けてきました。日々送られてくる新譜CDの魅力をお知らせする仕事が中心である以上、その存在がくすぶっていてはマズいと考えたからです。しかし、上記の通り、そうも言っていられない状況になったのです。 ■制作ポリシー 1) 音源に使用するディスクは、可能な限り複数のディスクを比較視聴し、演奏の魅力を最も強く 感じさせるものを選びます。初期盤絶対主義は取りません。 2) カップリングのオリジナル性を尊重しません。オリジナルを謳い文句にしている復刻盤もありますが、 CD-Rで聴く時点でオリジナルではないのです。 3) 原則的に全て1枚あたり60分以上収録し、通常のコンサートのような曲順(小さい曲から大きい曲へ)に配置。 ■音質処理 音の印象に最も大きな影響を与える要因の一つが、背景ノイズ(チリチリ音)除去のさじ加減。これが過剰なために、実音のニュアンスまで削られている例が少なくありません。そこで“Tresures”では、ノイズカットを最小限に抑えています。そのため、盤質の優れているディスクを探す手間暇は不可欠となります。 また、LPの出現からステレオ初期までは、プレスの不備、ピッチの異常、左右チャンネル逆転、回転ムラ等々により、そのまま再生すると違和感が生じる場合がありますが、そんなことは意に介さないばかりか、「オリジナル性尊重」を持ち出して、全く修正を施さないディスクに出会うことがあります。湧々堂ではそれらは全て「欠陥品」とみなします。万一このような現象が見過ごされていた場合は、必ず修正の上、再出荷いたします。 湧々堂創設以来、心底お薦めするディスクを“殿堂入り”と銘打って、できるだけ丁寧にご紹介してきたつもりですが、気がつけば廃盤だらけ…。“Tresures”が、そんな状態を少しでも解消できればと思っております。 【湧々堂】 |
「チャイコフスキー:交響曲第5番」特集
| 品番 | 内容 | 演奏者 |
|---|---|---|
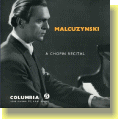 TRE-001 |
マルクジンスキ~ショパン・リサイタル ワルツ第1番Op.18「華麗なる大円舞曲」* 夜想曲第13番Op.48-1*/夜想曲第5番Op.15-2* スケルツォ第3番Op.39*/バラード第2番Op.38 夜想曲第15番Op.55-1/夜想曲第7番Op.70-1 ワルツ第11番Op.64-1/ワルツ第6番Op.54-1「小犬」 マズルカ第21番Op.30-4/マズルカ第45番Op.67-4 マズルカ第25番Op.33-4/即興曲第1番Op.29 スケルツォ第2番Op.31 |
ヴィトルド・マルクジンスキ(P) 録音:1958年3月&5月*、1955年6月-7月 ※音源:英COLOMBIA 33CX-1639*、33CX-1338(全てモノラル) ◎収録時間:67:29 |
| “ステレオ再録音では感じられない漆黒の色彩!” | ||
|
||
 TRE-002 |
メンデルスゾーン:華麗なカプリッチョ.ロ短調Op.22 ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第1番嬰ヘ短調Op.1* ピアノ協奏曲第2番ハ短調Op.18 |
モーラ・リンパニー(P) ニコライ・マルコ(指) フィルハーモニアO 録音:1953年2月2-3日、1954年4月30日* (全てモノラル) ※音源:MFP 2035、HMV CLP-1037* ◎収録時間:66:48 |
| “ラフマニノフの甘美さと一定の距離を保つことで生まれる気品!” | ||
|
||
 TRE-004 |
バッハ:管弦楽組曲集 第1番BWV.1066 第3番BWV.1068* 第4番BWV.1069# |
エドゥアルト・ファン・ベイヌム(指) アムステルダム・コンセルトヘボウO 録音:1955年5月31日~6月2日、1956年4月3日*、1956年4月10日# (全てモノラル) ※音源:仏Philips 700064 - 700055 ◎収録時間:61:43 |
| “香り立つエレガンス!ベイヌムのかけがえのない遺産!!” | ||
|
||
 TRE-005r |
ベートーヴェン:「プロメテウスの創造物」序曲* 交響曲第9番「合唱付き」 |
アルトゥール・ローター(指) ベルリンSO*、ハンブルクPO ハンブルク・ジングアカデミー エディット・ラング(S)、 マリア・フォン・ロスヴァイ(A) ワルター・ギーズラー(T) フランツ・クラス(Bs) 録音:1960年(ステレオ) ※音源:独PARNASS 61-423,424*、日COLUMBIA MS-8-9(全て独Opera原盤) ◎収録時間:70:24 |
| "ただの音圧ではなくドイツ精神の重みで聴かせる古き佳き「第9」!!" | ||
|
||
 TRE-006 |
スメタナ:交響詩「モルダウ」* チャイコフスキー:幻想序曲「ロメオとジュリエット」# ドヴォルザーク:スラブ舞曲Op.46(全8曲)** |
カレル・アンチェル(指) ウィーンSO 録音:1958年2月8-10日*、1958年3月29日&4月2日#、1958年11月5, 6, 26-29日&12月2-4日** 以上ウィーン・ムジークフェライン大ホール(全てステレオ) ※音源:Fontana SFON-7519 、蘭700.158** ◎収録時間:66:18 |
| “チェコのオケのように郷愁を滲ませるウィーン響の佇まい!” | ||
|
||
 TRE-007 |
リスト:交響詩「前奏曲」 ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」 |
フランツ・コンヴィチュニー(指) ウィーンSO 録音:1961年(ステレオ) ※音源:独PARNASS 61438、70003* ◎収録時間:76:46 |
| “「素朴」の一言で片付けられない、美しい響きの融合!” | ||
|
||
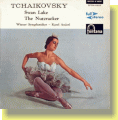 TRE-010 |
アンチェル~チャイコフスキー:バレエ音楽集 組曲「白鳥の湖」~情景(第2幕)/ワルツ(第1幕)/小さい白鳥の踊り(第2幕)/情景(第2幕)/ハンガリー舞曲(第3幕) 組曲「眠りの森の美女」~序奏とリラの精の舞い/バラのアダージョ(第1幕)/長靴をはいた猫と白い猫(第3幕)/パノラマ(第2幕)/ワルツ(第1幕) 組曲「くるみ割り人形」* 「眠りの森の美女」~ワルツ(第1幕)# |
カレル・アンチェル(指) ウィーンSO 録音:1958年2月8-11日、1958年3月27日# 以上、ウィーン・ムジークフェライン・ザール (全てステレオ) ※音源:英Fontana SFL-14054、蘭Fontana 875002CY*,# ◎収録時間:65:18 |
| “実用的なバレエ音楽を超越した、透徹した音彩の追求!!” | ||
|
||
 TRE-012 |
J・クリップス~ハイドン&ブラームス ハイドン:交響曲第94番「驚愕」* ブラームス:交響曲第1番ハ短調 |
ヨーゼフ・クリップス(指)VPO 録音:1957年9月9-14日*、1956年10月7-8日(共にステレオ) ※音源:DECCA SXL-2098*、LONDON STS-15144 ◎※収録時間:65:18 |
| “鎧で武装した演奏では味わえない音楽のエッセンス!” | ||
|
||
 TRE-013 |
パウル・クレツキ~ベートーヴェン:「運命」「田園」 ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」 交響曲第6番「田園」* |
パウル・クレツキ(指) バーデン=バーデン南西ドイツRSO フランス国立放送局O* 録音:1961年頃(全てステレオ) ※音源:英Concert Hall SMS-2341、日Concert Hall SMS-2239* ◎※収録時間:72:19 |
| “フランス・オケの起用が大正解!「田園」の魅惑のニュアンス!!” | ||
|
||
 TRE-014 |
シューベルト:「ロザムンデ」~序曲/バレエ曲第1番/間奏曲第3番/バレエ曲第2番 交響曲第9番ハ長調「グレート」* |
ハンス・スワロフスキー(指) ウィーン祝祭O(ウィーン国立歌劇場O) 録音:1950年代中頃、1955年1月*(全てモノラル) ※音源:WORLD RECORD CLUB TT-17、T-25* ◎※収録時間:75:36 |
| “スワロフスキーの穏健なイメージを払拭する、テンポに込めた強い信念!” | ||
|
||
 TRE-015 |
ワルター・ゲール~グノー、ビゼー、チャイコフスキー グノー:「ファウスト」~バレエ音楽 ビゼー:組曲「美しきパースの娘」~行進曲/セレナード/ジプシーの踊り 「アルルの女」*~前奏曲/メヌエット/アダージェット/メヌエット/ファランドール チャイコフスキー:組曲「くるみ割り人形」# |
ワルター・ゲール(指) コンセール・ド・パリO コンセール・パドルーO* フランクフルト歌劇場O# 録音:1950年代中期 ※音源:独Concert Hall SMS-2146、日Concert Hall SM-6109#(全てステレオ) ◎収録時間:67:48 |
| “クナもびっくり!? ドイツ訛り丸出しの「くるみ割り人形」” | ||
|
||
 TRE-016 |
パリキアン~モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲集 ヴァイオリン協奏曲第1番* ヴァイオリン協奏曲第3番 ヴァイオリン協奏曲第4番 |
マヌーグ・パリキアン(Vn) ワルター・ゲール(指) アムステルダム・フィルハーモニー協会O* ハンブルク室内O 録音:1959年頃(モノラル) ※音源:独CONNCERT HALL MMS-2206*、MMS-2092 ◎※収録時間:68:34 |
| “名コンマス、パリキアンの並々ならぬ音楽への奉仕力!” | ||
|
||
 TRE-017 |
リヒャルト・クラウス~ワーグナー他 グリーグ:「ペール・ギュント」組曲~アニトラの踊り/アラビアの踊り/ソルヴェイグの歌 リスト:ハンガリー狂詩曲第1番/第2番 ワーグナー:「タンホイザー」序曲* 「さまよえるオランダ人」序曲* 「ローエングリン」第1幕前奏曲*/第3幕前奏曲* ワルキューレの騎行* |
リヒャルト・クラウス(指) バンベルクSO、 ベルリン市立歌劇場O* 録音:1958年、1962年頃*(全てステレオ) ※音源:独DGG 136020、独PARNASS 61436* ◎収録時間:77:44 |
| “ワーグナーの真の権威者、リヒャルト・クラウスの無類の共感力!” | ||
|
||
 TRE-018r |
ハンス・リヒター=ハーザー/グリーグ&シューマン他 グリーグ:ピアノ協奏曲* シューマン:ピアノ協奏曲# リスト:愛の夢第3番 グリーグ:抒情小品集第6集~「過ぎ去った日々」Op.57-1 抒情小品集第8集~「トロールハウゲンの婚礼の日」Op.65-6 メンデルスゾーン:無言歌集~「春の歌」Op.62-6 シューマン:子供の情景~トロイメライ |
ハンス・リヒター=ハーザー(P) ルドルフ・モラルト(指)ウィーンSO 録音:1958年1月18-21日*,#(ステレオ)、1958年5月27日-6月1日(モノラル) ※音源:英PHILIPS_SABL-180*,#、EPIC LC-3620 ◎※収録時間:79:18 |
| "構築力だけではない!リヒター=ハーザーの知られざるリリシズム!” | ||
|
||
 TRE-019 |
ヘンリー・クリップス~スッペ&J・シュトラウス J・シュトラウス:ワルツ「芸術家の生活」 ポルカ「雷鳴と電光」 ヴェルディの「仮面舞踏会」によるカドリーユ Op. 272 トリッチ・トラッチ・ポルカ 皇帝円舞曲 スッペ:「軽騎兵」序曲* 「スペードの女王」序曲* 「ウィーンの朝、昼、晩」序曲* 「詩人と農夫」序曲* 「タンタロスの苦悩」序曲* 「幸福への旅路」序曲* |
ヘンリー・クリップス(指) フィルハーモニア・プロムナードO(フィルハーモニアO) 録音:1960年1月14-15日、1956年1月日*(全てステレオ) ※音源:英EMI SXLP-30056、SXLP-30037* ◎※収録時間:78:37 |
| “自らは酔いしれず、聴き手を酔わす望郷の指揮!” | ||
|
||
 TRE-020 |
モーツァルト:交響曲第35番「ハフナー」 スメタナ:「売られた花嫁」*~序曲/ポルカ/フリアント/道化師の踊り ブラームス:交響曲第2番# |
アルフレッド・ウォーレンスタイン(指) ロスアンジェルスPO 録音:1955年頃、1953年頃*(全てモノラル) ※音源:米MUSIC APPRIECIATION RECORDS MAR-5613、英Brunswick AXTL-1063*、英WORLD EECORD CLUB T-6# ◎※収録時間:71:39 |
| “作品の生命力を徹底抽出するウォーレンスタイン の巧みな棒!” | ||
|
||
 TRE-021 |
マルクジンスキ~ショパン&リスト ショパン:ピアノ・ソナタ第3番ロ短調* リスト:ピアノ・ソナタ.ロ短調** ピアノ協奏曲第2番イ長調# |
ヴィトルド・マルクジンスキ(P) ワルター・ジュスキント(指) フィルハーモニアO 録音:1952年1月1日*、1953年3月7-11日**、1953年3月2日&4日#(全てモノラル) ※音源:伊Columbia QCX-194*、仏CLUB NATIONAL DU DISQUE CND-585**,# ◎収録時間:74:20 |
| “詩的ニュアンスを確実に引き出すマルクジンスキの美学貫徹!” | ||
|
||
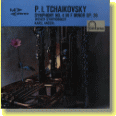 TRE-022 |
アンチェル&ウィーン響~チャイコフスキー チャイコフスキー:スラブ行進曲* 大序曲「1812年」# 交響曲第4番ヘ短調Op.36 弦楽セレナード~ワルツ* |
カレル・アンチェル(指)ウィーンSO 録音:1958年3月29日-4月2日*、1958年11月-12月(*以外) 全てステレオ ※音源:Fomtana 875.011 (SCFL-103)、SFON-7519#、875.002* ◎収録時間:67:52 |
| “潔癖さの極み!土臭さを排したアンチェル芸術の結晶!” | ||
|
||
 TRE-023r |
ベートーヴェン:「エグモント」序曲 ハイドン:交響曲第94番「驚愕」* ベートーヴェン:交響曲第7番# |
レオポルド・ルートヴィヒ(指) バンベルクSO、LSO* 録音:1950年代後半(全てステレオ) ※音源:独PARNASS 61-424、米VOX STPL-512510*、独OPERA ST-1987# ◎収録時間:69:09 |
| “自然体を通しながら、作品の核心を外さない名人芸!” | ||
|
||
 TRE-024 |
デニス・ブレイン/モーツァルト&R・シュトラウス(ブライトクランク版) モーツァルト:ホルン協奏曲第1番~第4番 R・シュトラウス:ホルン協奏曲第1番* |
デニス・ブレイン(Hrn) ヘルベルト・フォン・カラヤン(指) ウォルフガング・サヴァリッシュ(指)* フィルハーモニアO 録音:1953年11月12-23日、1956年9月22日* ※音源:Electrola 1C 0663 00414、HMV HLS-7001*(以上,ブライトクランク擬似ステレオ) ◎収録時間:69:50 |
| “ブライトクランク版で再認識する、D・ブレインが放つ奇跡のニュアンス!” | ||
|
||
 TRE-025r(1CDR) |
音源変更・再復刻 !! 厳選!赤盤名演集Vol.16~サージェントのシューベルト&J・シュトラウス シューベルト:交響曲第8番「未完成」* J・シュトラウス:ワルツ「ウィーンの森の物語」 皇帝円舞曲 ワルツ「美しく青きドナウ」 ワルツ「酒・女・歌」 ワルツ「芸術家の生活」 |
マルコム・サージェント(指) ロイヤルPO 録音:1960年10月26-27日*、1961年5月3-4日(全てステレオ) ※音源:東芝 5SA-5005*、 ASC-5155 (全てステレオ) ◎収録時間:73:13 |
| “サージェントの品格美の中に宿る一途な表現意欲!” | ||
|
||
 TRE-026 |
エゴン・ペトリ~バッハ&ブゾーニ:ピアノ曲集 バッハ(ブゾーニ編):トッカータとフーガ.二短調BWV.565* トッカータ,アダージョとフーガ.ハ長調BWV.564* 前奏曲とフーガ.変ホ長調BWV.552* 前奏曲とフーガ.ニ長調BWV.532* コラール「目覚めよと,われらに呼ばわる物見らの声」BWV.645 コラール「汝にこそ,わが喜びあり」BWV.615 コラール「われ汝に呼ばわる,主イエス・キリストよ」BWV.639 ブゾーニ:対位法的幻想曲 |
エゴン・ペトリ(P) 録音:1956年6月22日(モノラル) ※音源:Westminster XWN-18910*、XWN-18844 ◎収録時間:79:06 |
| “バッハの精神とブゾーニの意思を具現化した、ペトリの圧倒的なピアニズム!” | ||
|
||
 TRE-027 |
ホーレンシュタイン~プロコフィエフ作品集 交響曲第1番ニ長調「古典」 交響組曲「キージェ中尉」* 交響曲第5番変ロ長調Op.100 |
ヤッシャ・ホーレンシュタイン(指) コロンヌO、パリPO* 録音:1954年、1955年*(全てモノラル) ※音源:VOX PL-9170、PL-9180* ◎収録時間:71:24 |
| “ホーレンシュタインの「陰」な性質がプロコフィエフと完全合体!” | ||
|
||
 TRE-029 |
マルクジンスキ~ブラームス&ショパン ブラームス:ヘンデルの主題による変奏曲とフーガOp.24 6つの小品~間奏曲変ホ短調Op.118-6 ラプソディー第2番 ト短調Op.79-2 パデレフスキ:幻想的クラカウ舞曲Op.14-6# シマノフスキ:練習曲変ロ短調Op.4-3# ショパン:マズルカ第47番イ短調Op.68-2# ワルツ第14番(遺作)# ワルツ第7番嬰ハ短調Op.64-2# ピアノ・ソナタ第2番変ロ短調「葬送」* |
ヴィトルド・マルクジンスキ(P) 録音:1954年、1954年6月9-11日#、1953年3月5日*、(全てモノラル) ※音源:米Angel 33549、、日COLUMBIA XL-5229#、伊Columbia 33QCX-194*、 ◎収録時間:77:01 |
| “マルクジンスキによる「葬送ソナタ」の最高名演!” | ||
|
||
 TRE-030 |
O・レヴァント~ショパン、ドビュッシー他 ショパン:夜想曲Op.9-2 /Op.15-2 練習曲Op.10-3,4,5,12 子守唄/軍隊ポロネーズ ワルツOp.70-1 /Op.64-2 ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ* 「クープランの墓」~フォルラーヌ*/メヌエット* ドビュッシー:「子供の領分」~人形のセレナード*/小さな羊飼い#/ゴリーウォーグのケークウォーク# 亜麻色の髪の乙女# 映像第1集~水に映る影# 沈める寺#/月の光#/レントより遅く# |
オスカー・レヴァント(P) 録音:1946年頃(ショパン)、1944-1947年 ※音源:COLUMBIA ML-4147、ML-5324*、CL-1134# ◎収録時間:76:44 |
| “気負わず繊細に歌い上げる、O・レヴァントの知られざる音楽センス!” | ||
|
||
 TRE-031 |
ニコライ・マルコ~ボロディン&チャイコフスキー チャイコフスキー:大序曲「1812年」 ボロディン:交響曲第3番(未完)* 交響曲第2番ロ短調# |
ニコライ・マルコ(指) フィルハーモニアO 録音:1953年2月6日、1955年9月24日*、1955年9月23日#(全てモノラル) ※音源:HMV XLP-30010*#、M.F.P MFP-2034 ◎収録時間:61:12 |
| “土俗性を煽らず一途な共感で描き切ったボロディンの素晴らしさ!” | ||
|
||
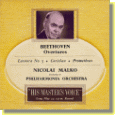 TRE-032 |
ニコライ・マルコ~ベートーヴェン他:序曲集 ベートーヴェン:序曲「コリオラン」 「プロメテウスの創造物」序曲# 序曲「レオノーレ」第3番 スッペ:「詩人と農夫」序曲* メンデルスゾーン:序曲「フィンガルの洞窟」* 序曲「ルイ・ブラス」** エロール:「ザンパ」序曲# |
ニコライ・マルコ(指) フィルハーモニアO 録音:1953年1月28日、1956年2月17-18日* 1956年3月1日**、1953年1月29日#(全てモノラル) ※音源:HMV DLP-1061(ベートーヴェン)、M.F.P MFP-2034 ◎収録時間:60:47 |
| “意地貫徹!品格重視のアプローチが作品の素の姿を再現!” | ||
|
||
 TRE-033 |
ノヴァエス~ショパンのマズルカ&前奏曲集 マズルカ~Op.33-2/Op.41-1 Op.33-4/Op.17-4/Op.24-4 Op.56-2/Op.59-1/Op.33-3 Op.63-1/Op.59-2/Op.24-2 24の前奏曲Op.28* |
ギオマール・ノヴァエス(P) 録音:1954年、1953年*(全てモノラル) ※音源:米VOX PL-7920、独OPERA-PANTHEON XP-2150* ◎収録時間:70:12 |
| “ノヴァエス天性のリズムと色彩感覚が織り成すの豊穣なショパン!” | ||
|
||
 TRE-035 |
モーラ・リンパニー~ベートーヴェン&フランク フランク:交響的変奏曲* ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」 ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 |
モーラ・リンパニー(P) ワルター・ジュスキント(指)フィルハーモニアO* トーマス・シャーマン(指)スタジアム・コンサートSO 録音:1949年6月20日*、1957年ニューヨーク(全てモノラル) ※音源:RCA LHMV-1013*、Music Appreciation Record MAR-5713 ◎収録時間:69:42 |
| “気高い推進力!、リンパニー絶頂期の貴重なベートーヴェン!” | ||
|
||
 TRE-036 |
ウォーレンステイン~シューベルト他 ベルリオーズ:「ファウストの劫罰」~ラコッツィ行進曲/鬼火のメヌエット/妖精の踊り スメタナ:交響詩「モルダウ」 シューベルト:交響曲第5番* 交響曲第4番ハ短調* |
アルフレッド・ウォーレンステイン(指) ロスアンジェルスPO 録音:1953年頃、1950年代中頃*(全てモノラル) ※音源:英Brunswick AXTL-1063、AXTL-1059* ◎収録時間:78:47 |
| “シューベルトを堂々たるシンフォニストに引き上げた画期的名演!” | ||
|
||
 TRE-037 |
パリキアン~バッハ&モーツァルト バッハ:ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 ヴァイオリン・ソナタ ホ短調 BWV 1023# モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」* |
マヌーグ・パリキアン(Vn) アレクサンダー・クランハルス(指)バーデン室内O ワルター・ゲール(指)アムステルダム・フィルハーモニー協会O* アレクサンダー・モルツァン(Vc)#、 ヘルベルト・ホフマン(Cemb)# 録音:1959年頃(全てモノラル) ※音源:独CONCERT HALL MMS-2148、MMS-2206*、 ◎収録時間:77:30 |
| “地味な佇まいから引き出される作品の様式美!” | ||
|
||
 TRE-038 |
フランツ・アンドレのベートーヴェン ベートーヴェン:交響曲第4番 交響曲第7番* |
フランツ・アンドレ(指) ベルギー国立RSO 録音:1953年10月2日、1952年10月3日* ※音源:日KING RECORD MPT-45、英Telefunken GMA-7 ◎収録時間:64:11 |
| “小品集だけではわからない、フランツ・アンドレの度量の広い芸術力!” | ||
|
||
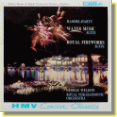 TRE-039 |
ジョージ・ウェルドン~「水上の音楽」 (1)E・コーツ:行進曲「ロンドン・ブリッジ」* (2)グレインジャー:モック・モリス# (3)V=ウィリアムズ:グリーンスリーヴズによる幻想曲# (4)ディーリアス(フェンビー編):歌劇「コアンガ」~ラ・カリンダ# (5)E・ジャーマン:「ジプシー組曲」~メヌエット* (6)V=ウィリアムズ(ジェイコブ編):イギリス民謡組曲~行進曲「サマセットの民謡」# (7)A・コリンズ:「虚栄の市」* (8)R・クィルター:組曲「虹の終わる場所に」~“Rosamund”* (9)F・カーゾン:小序曲「パンチネロ」* (10)ウェールズ民謡(ウェルドン編):Suo-gan# (11)ハーティ:アイルランド交響曲~定期市の日# (12)ヘンデル(ハーティ編):水上の音楽** 王宮の花火の音楽** (13)アイルランド民謡(グレインジャー編):ロンドンデリーの歌# |
ジョージ・ウェルドン(指) (1)(5)(7)(8)(9)プロ・アルテO (2)(3)(4)(6)(10)(11)(13)フィルハーモニアO (12)ロイヤルPO (3)ジョージ・アクロイド(Flソロ) 録音:(1)(5)(7)(8)(9)1963年2月18-19日、 (2)(3)(4)(6)(10)(11)(13)1962年10月、 (12)1960年11月30日(全てステレオ) ※音源:(2)(4)(6)(10)(11)(13)HMV SXLP-30243、 (1)(3)(5)(7)(8)(9)SXLP-20123、 (12)SXLP-20033 ◎収録時間:73:40 |
| “これこそが、個性を誇示しないとう個性の魅力!” | ||
|
||
 TRE-040 |
ヴォイチャッハ他~ドイツ行進曲集 (1)P・ヴィンター:ベルリン・オリンピック・ファンファーレ (2)G・ピーフケ:行進曲「プロシァの栄光」 (3)ヴァルヒ:行進曲「パリ入場」 (4)A・ラインデル:エルファー行進曲 (5)J・フチーク:行進曲「剣士の入場」 (6)C・タイケ:行進曲「旧友」 (7)C・フリーデマン:フリードリヒ大王行進曲 (8)A・ユレックス:ドイツ騎士団行進曲 (9)M・ツィーラー:シェーンフェルト行進曲 (10)H・ニール:行進歌「楽しき兵隊」 (11)H・シュタインベック:」行進曲「連隊の挨拶」 (12)L・フランケンブルク:行進曲「勇躍戦線へ」 (13)O・マイスナー:行進曲「楽しき行軍」 (14)H・フースアーデル:行進曲「リヒトホーフェン爆撃隊」 (15)C・シェスタック:行進曲「ハイル・ヒトラー」 (16)W・ティーレ:行進曲「若き勇士」 (17)C・フリーデマン:提督行進曲 (18)L・ジルヴァール:ドイツ艦隊行進曲 (19)G・フェルスト:行進曲「兵士の歓喜」 (20)A・レオンハルト:アレキサンダー行進曲 (21)H・リヒター:行進曲「ドイツ万歳」 (22)J・フチーク:フローレンス行進曲 (23)ゾンタルク:ニーベルンゲン行進曲 (24)F.V.ブローン:行進曲「戦から勝利へ」 (25)ラウキーン:行進曲「闇から光へ」 |
(1)オリジナル版 (2)-(4)(10)(15)カール・ヴォイチャッハ(指)テレフンケン大吹奏楽団 (5)(6)ベルリン・フィル団員 (7)(13)クーアマルク吹奏楽団 (8)(9)レオポルド・エルトル(指)南オーストリア歩兵隊第14連隊「リンツ」軍楽隊 (11)(14)フリードリヒ・アーラース(指)ベルリン防衛連隊付軍楽隊 (12)ヘルマン・ミュラー・ヨーン(指)アドルフ・ヒトラー親衛隊付軍楽隊 (16)ヴィリー・ティーレ(指)ポツダム騎兵隊付軍楽隊 (17)(18)フリッツ・フーブリヒ(指)海軍第三重砲隊スヴィーデムンデ大隊軍楽隊 (19)ゲオルグ・フェルスト(指)ミュンヘン歩兵隊第19連隊付軍楽隊 (20)(21)ヘルマン・リヒター(指)ベルリン警察隊大吹奏楽団 (22)-(25)アドルフ・ベルディーン(指)ドイツ陸軍軍楽隊 録音:(1)1936年、(2)(15)1933年、(3)1929年、(4)1932年9月、(5)(6)1934年8月、(7)(13)1936年12月、(8)(9)1938年3月、(10)1938年4月、(11)(14)1938年2月、(12)(22)1938年12月、(16)1935年、(17)1934年9月、(18)1934年9月、(19)1934年12月、(20)(21)1933年9月、(23)-(25)1930年11月 ※音源:King Record SLC-2302-2303 ◎収録時間:77:53 |
| “行進曲はかくあるべし!誕生の背景と関係なく心揺さぶる逸品揃い!” | ||
|
||
 TRE-041 |
アルジェオ・クワドリ~エキゾチック・コンサート サン・サーンス:「サムソンとデリラ」~バッカナール 交響詩「死の舞踏」 レブエルタス:センセマヤ# クァウーナウァク# R=コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」* |
アルジェオ・クワドリ(指) ロイヤルPO、ウィーン国立歌劇場O* 録音:1950年代中頃、1953年*(全てモノラル) ※音源:Westminster XWN-18451、W-LAB7004#、仏VEGA C30S124* ◎収録時間:78:29 |
| “作品の内側から歌と色彩を徹底抽出する、名匠クアドリの驚異的センス!” | ||
|
||
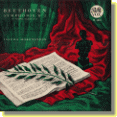 TRE-042 |
ホーレンシュタイン~ベートーヴェン:「英雄」他 ベートーヴェン:「エグモント」序曲 「プロメテウスの創造物」序曲 交響曲第3番変ホ長調「英雄」* |
ヤッシャ・ホーレンシュタイン(指) ウィーン・プロ・ムジカO 録音:1953年 ※音源:仏VOV PL-8020、独Opera 1015* ◎収録時間:68:06 |
| “異常暴発!苦悶を発散できないホーレンシュタインだからこそ成し得た凄演!” | ||
|
||
 TRE-044 |
シューマン:交響的練習曲* ショパン:24の前奏曲集Op.28# ワルツ第3番Op.34-2/第7番Op.64-2/第8番Op.64-3/第9番Op.69-1 |
モーラ・リンパニー(P) 録音:1949年6月16日*、1954年11月18日#、1958年8月15日(全てモノラル) ※音源:RCA,HMV LHMV-1013*、HMV CLP-1051#、CLP-1349 ◎収録時間:74:52 |
| “絶頂期のリンパニーを象徴する二大名演!” | ||
|
||
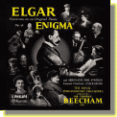 TRE-045 |
ビーチャム他~エルガー:管弦楽曲集 3つのバイエルン舞曲Op.27* 序曲「コケイン」/弦楽セレナード エニグマ変奏曲 |
ローレンス・コリングウッド(指)LSO* トマス・ビーチャム(指)ロイヤルPO 録音:1954年2月11日*、1954年11月-12月(全てモノラル) ※音源:英COLUMBIA 33CX-1030*、PHILIPS ABL-3053 ◎収録時間:70:21 |
| “ビーチャム唯一のエルガー録音で痛感する人間と音楽の大きさ!” | ||
|
||
 TRE-046 |
コンスタンティン・イワーノフ/豪快名演集 チャイコフスキー:スラブ行進曲(改竄版) 大序曲「1812年」(改竄版) プロコフィエフ:スキタイ組曲「アラとロリー」* グラズノフ:交響曲第5番変ロ長調Op.55# |
コンスタンティン・イワーノフ(指) ソビエト国立SO、モスクワRSO# 録音:1964年頃、1964年*、1962年#(全てステレオ) ※音源:Melodiya C-0959-60、C-1024221-009*、DG 2530-509# ◎収録時間:72:56 |
| “改竄版の異常さだけでなく、イワーノフの音作りの御注目!” | ||
|
||
 TRE-048 |
ベートーヴェン:三重協奏曲Op.56* ヴァイオリン協奏曲(カデンツァ;ヨアヒム作) |
マヌーグ・パリキアン(Vn) マッシモ・アンフィテアロフ(Vc)* オルネッラ・サントリクイド(P)* ワルター・ゲール(指)ローマPO* アレキサンダー・クランハルス(指)フランクフルトRSO 録音:1950年代後半(モノラル) ※音源:Concert Hall MMS-2159*、MMS-2124 ◎収録時間:79:57 |
| “個性をひけらかさない表現から漂う作品の魅力!” | ||
|
||
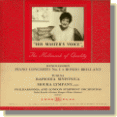 TRE-049 |
メンデルスゾーン:華麗なるロンド ピアノ協奏曲第1番ト短調 Op.25* トゥリーナ:交響的狂詩曲Op.66** グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調Op.16# |
モーラ・リンパニー(P) ハーバート・メンゲス(指)LSO ラファエル・クーベリック(指)フィルハーモニアO* ワルター・ジュスキント(指)フィルハーモニアO** ハーバート・メンゲス(指)フィルハーモニアO# 録音:1952年6月3日、1948年10月3日*、1949年6月20日**、1954年11月4日# ※音源:RCA.HMV LHMV-1025、HMV CLP-1037# ◎収録時間:64:34 |
| “リンパニーの十八番、グリーグにおける結晶化されたタッチ!” | ||
|
||
 TRE-050 |
ベートーヴェン:ミサ・ソレムニス | ワルター・ゲール(指) ハンブルクNDS響、北ドイツ放送Cho ウタ・グラーフ(S)、グレース・ホフマン(A) ヘルムート・クレシュマール(T) エーリヒ・ヴェンク(Bs) 録音:1950年代後半(ステレオ) ※音源:VANGURAD SRV-214-215(コンサートホール原盤) ◎収録時間:71:35 |
| “権威に立ち向かったベートーヴェンの精神が宿る名唱!” | ||
|
||
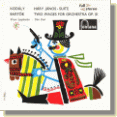 TRE-054  Tibor Paul |
ティボール・パウル~ハンガリー名曲集 リスト:ハンガリー狂詩曲第2番* ブラームス:ハンガリー舞曲集(7曲)# 第5番(パーロウ編)/第6番(パーロウ編) 第7番(ハレン編)/第10番/第1番 第2番(ハレン編)/第3番 バルトーク:2つの映像Op.10 コダーイ:組曲「ハーリ・ヤーノシュ」 |
ティボール・パウル(指) ウィーンSO 録音:1959年11月15-21日*、1959年1月5-8日(*以外) 全てステレオ ※音源:PHILIPS 857-027CY、700-158WGY#、Victor SFON-7521* ◎収録時間:76:10 |
| “厚塗り厳禁!誰も真似できない庶民的なリズムと歌心!” | ||
|
||
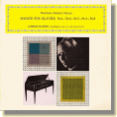 TRE-055 |
コンラート・ハンゼンのモーツァルト ピアノ・ソナタ第1番ハ長調K.279 ピアノ・ソナタ第2番ヘ長調K.280 ピアノ・ソナタ第3番変ロ長調K.281 ピアノ・ソナタ第4変ホ長調K.282 ピアノ・ソナタ第8番イ短調K.310 |
コンラート・ハンゼン(ハンマークラヴィア) 録音:1956~1957年(モノラル) ※音源:DG LPM 18320、日GRAMMOPHON LGM-1136(JP)* ◎収録時間:69:39 |
| “ハンマークラヴィアで弾きたいという音楽的衝動がもたらす説得力!” | ||
|
||
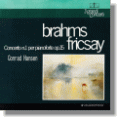 TRE-056 |
コンラート・ハンゼン/モーツァルト&ブラームス モーツァルト:ピアノ・ソナタ第6番ニ長調K.284* ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 |
コンラート・ハンゼン(ハンマークラヴィア*、P) フェレンツ・フリッチャイ(指) ベルリンRIAS響 録音:1956~1957年*、1953年4月19日 ※音源:GRAMMOPHON LGM-1136(JP)*、LONGANESI PERIODICI GCL-50 ◎収録時間:72:29 |
| “ブラームスの第2楽章は、同曲空前の大名演!” | ||
|
||
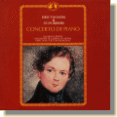 TRE-057r |
L・クラウス~ベートーヴェン&シューマン ベートーヴェン:ロンド変ホ長調(遺作) ピアノ協奏曲第4番 シューマン:ピアノ協奏曲* |
リリー・クラウス(P) ヴィクトル・デザルツェンス(指) ウィーン国立歌劇場O 録音:1962年、1950年代末*(全てステレオ) ※音源:VANGUARD SRV-252SD、Concert Hall SMS-2327* ◎収録時間:73:46 |
| “クラウスの溢れるロマンティシズムが曲想と見事に合致!” | ||
|
||
 TRE-058 |
フォルデス/ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ集 ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」Op.13* ピアノ・ソナタ第19番ト短調Op.49-1 ピアノ・ソナタ第26番「告別」Op.81a* ピアノ・ソナタ第28番イ長調Op.101 ピアノ・ソナタ第30番ホ長調Op.109 |
アンドール・フォルデス(P) 録音:8番:1961年11月2-9日(第8番)、1960年(第19番)、1961年11月3-4, 6, 8-9(第26番)、1960年5月16-17日(第28番)、1960年2月3-4日(第30番) 全てステレオ ※音源:DG 135064(De)*、GRAMMOPHON SLGM-1127 (Jp) ◎収録時間:76:50 |
| デフォルメに頼らずベートーヴェンの精神を表出する透徹のピアニズム! | ||
|
||
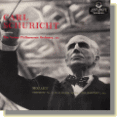 TRE-059 |
シューリヒト~モーツァルトの「ハフナー」 モーツァルト:交響曲第35番「ハフナー」 セレナード第7番ニ長調 K.250「ハフナー」* |
カール・シューリヒト(指) VPO、シュトゥットガルトRSO* 録音:1956年6月3-6日、1962年12月* (全てモノラル) ※音源:KING RECORD LC-4、MOVIMENT MUSICA 01-067* ◎収録時間:72:19 |
| “神の領域!これこそがシューリヒトの究極の二大名演!” | ||
|
||
 TRE-060 |
デゾルミエール&チェコ・フィル名演集 ビゼー:「カルメン」第1組曲~前奏曲/アルカラの竜騎兵/間奏曲/アラゴネーズ 「アルルの女」第1組曲&第2組曲* ドビュッシー:夜想曲(「雲」「祭り」)** ラヴェル:ボレロ# |
ロジェ・デゾルミエール(指)チェコPO 録音:1950年11月15日、1950年5月25-26日*、1950年11月9日**、1950年10月30日# (全てモノラル) ※音源:SUPRAPHON - EURODISC 913-296 ◎収録時間:76:22 |
| “楷書風の筆致から湧き上がる甘美な色彩と香気!” | ||
|
||
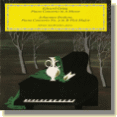 TRE-063 |
エッシュバッハー/グリーグ&ブラームス グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調Op.16 ブラームス:ピアノ協奏曲第2番Op.83* |
アドリアン・エッシュバッハー(P) レオポルド・ルートヴィヒ(指)BPO ウィルヘルム・フルトヴェングラー(指)BPO* ティボール・デ・マヒュラ(Vcソロ)* 録音:1953年3月2-3日、1943年12月12-15日ベルリン・フィル定期公演ライヴ* ※音源:DGG LPE-17143、Melodiya M10-45921-009* ◎収録時間:74:22 |
| “爆撃の危機を乗り切った決死のブラームス!” | ||
|
||
 TRE-064 |
ワルター・ゲール/「展覧会の絵」他 ベートーヴェン:「エグモント」序曲* メンデルスゾーン:交響曲第3番「スコットランド」** ムソルグスキー(ラヴェル編):組曲「展覧会の絵」# |
ワルター・ゲール(指) LSO*、オランダPO 録音:1950年代中期~後期(全てステレオ) ※音源:日Concert Hall SM-6111*、米URANIA USD-1032**、豪Concert Hall SMS-138A(10インチ)# ◎収録時間:77:59 |
| “ワルター・ゲールの超入手困難ステレオ盤!” | ||
|
||
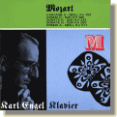 TRE-066 |
カール・エンゲル/モーツァルト他 モーツァルト:幻想曲ニ短調K.397 ロンド.ニ長調K.485* ピアノ・ソナタ第13番K.333 ピアノ・ソナタ第5番K.283 ロンド.イ短調K.511 シューベルト:即興曲Op.142-1&3# |
カール・エンゲル(P) 録音:1959年(全てモノラル) ※音源:独ELECTOROLA E-80461、E-60732*、C-60730# ◎収録時間:78:15 |
| “作曲家の代弁者に徹するカール・エンゲルの信念!” | ||
|
||
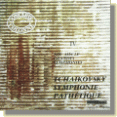 TRE-067 |
デルヴォー/チャイコフスキー:「悲愴」他 グリンカ:歌劇「皇帝に捧げた命 」序曲 チャイコフスキー:「エフゲニ・オネーギン」~ワルツ スラブ行進曲 ボロディン:交響詩「中央アジアの草原にて」 チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」* |
ピエール・デルヴォー(指) アムステルダム・フィルハーモニック協会O コロンヌO* 録音:1959年、1961年12月17日ライヴ*(全てステレオ) ※音源:米Audio Fodelity FCS-50025、DUCRETET-THOMSON SCC-504* ◎収録時間:77:40 |
| “陰鬱さをリセットして壮絶な音のドラマとして描いた驚異の「悲愴!” | ||
|
||
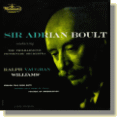 TRE-070 |
ボールト/ヴォーン・ウィリアムズ:管弦楽曲集 バレエ音楽「老いたコール王」* 劇音楽「すずめばち」アリストファネス組曲* グリーンスリーヴス幻想曲 タリスの主題による幻想曲 イギリス民謡組曲(ジェイコブ編) |
エイドリアン・ボールト(指)LPO 録音:1953年9月 ※音源:Westminster WL-5228*、WL-5270 (DEEP GROOVE RED LABEL RIAA high fidelity mono pressing) ◎収録時間:74:48 |
| “ボールトのヴォーン・ウィリアムズ演奏の真髄!” | ||
|
||
 TRE-071 |
ボールト/チャイコフスキー&プロコフィエフ チャイコフスキー:イタリア奇想曲* プロコフィエフ:組曲「キージェ中尉」** チャイコフスキー:組曲第3番# |
エイドリアン・ボールト(指) LPO*、パリ音楽院O**,# 録音:1959年2月*、1955年6月**,#(全てステレオ) ※音源:米PERFECT PS-15001*、DECCA SPA-229**、LONDON CS-6140# ◎収録時間:71:26 |
| “ボールトの虚飾なきアプローチとフランス流儀の麗しい化学反応!” | ||
|
||
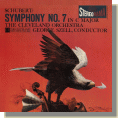 TRE-072 |
ジョージ・セル/エピック録音名盤集1 モーツァルト:ディヴェルティメント第2番K.131 シューベルト:交響曲第9番ハ長調「グレート」* |
ジョージ・セル(指) クリーヴランドO 録音:1963年4月20日、1957年11月1日* 共にステレオ ※音源:米EPIC BC-1273(Blue)、BC-1009(Gold STEREORAMA)* ◎収録時間:72:45 |
| “CDでは伝わらないセルのパッションとスケール感!” | ||
|
||
 TRE-073 |
スワロフスキーのベートーヴェン ベートーヴェン:「レオノーレ」序曲第3番* 交響曲第8番ヘ長調Op.93 交響曲第2番ニ長調Op.36 |
ハンス・スワロフスキー(指) ウィーン国立歌劇場O 録音:1950年代中期(全てモノラル) ※音源:W.R.C TW-108、ORBIS 21224* ◎収録時間:72:52 |
| “スワロフスキーの指揮者としてのセンスを痛感する二大名演!” | ||
|
||
 TRE-074 |
カール・ベーム~2人のシュトラウス R・シュトラウス:交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯」* 交響詩「ドン・ファン」* J・シュトラウス:皇帝円舞曲 ペルシャ行進曲 ピチカート・ポルカ(ヨーゼフとの合作) 常動曲/トリッチ・トラッチ・ポルカ ワルツ「美しく青きドナウ」 「こうもり」序曲 J・シュトラウスⅠ:ラデツキー行進曲 |
カール・ベーム(指) ベルリンRSO*、BPO 録音:1950年3月25日ベルリン*、1954年2月11日ウィーン(全てモノラル・ライヴ) ※音源:RVC RCL-3316*、RCL-3314 ◎収録時間:72:34 |
| “ベームの本性を出しきったJ・シュトラウスの無類の楽しさ!” | ||
|
||
 TRE-075r |
ライトナー~モーツァルト:交響曲集 モーツァルト:バレエ音楽「レ・プティ・リアン」序曲+ 交響曲第31番「パリ」K.297* 交響曲第36番「リンツ」K.425# 交響曲第39番変ホ長調K.543 |
フェルディナント・ライトナー(指) バイエルンRSO*,#、バンベルクSO 録音:1959年4月13日+、1959年4月12-13日*、1959年4月11-12日#、1962年11月(全てステレオ) ※音源:独ORBIS HI-FI-73-491+,*,#、独PARNASS 61414 ◎収録時間:74:22 |
| “策を弄せず、作品の底力を信じきるライトナー度量!” | ||
|
||
 TRE-076 |
バルワーザー~バッハ&モーツァルト バッハ:管弦楽組曲第2番BWV.1067* モーツァルト:アンダンテ.ハ長調K.315# フルート協奏曲第1番ト長調K.313 フルート協奏曲第2番ニ長調K.314 |
フーベルト・バルワーザー(Fl) エドゥアルト・ファン・ベイヌム(指)アムステルダム・コンセルトヘボウO* ベルンハルト・パウムガルトナー(指)ウィーンSO# ジョン・プリッチャード(指)ウィーンSO 録音:1955年5月31日-6月9日*、1954年2月21-22日#、1953年2月28-29日(全てモノラル) ※音源:仏PHILIPS 700064-700055*、仏FONTANA 698094FL ◎収録時間:69:07 |
| “音色美だけではない!愛で語るバルワーザーのフルートの魅力!” | ||
|
||
 TRE-077 |
ヨハネセン~ベートーヴェン:ピアノ曲集 ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」 ピアノ・ソナタ第31番Op.110 ピアノ協奏曲第3番ハ短調* |
グラント・ヨハネセン(P) ワルター・ゲール(指)オランダPO 録音:1950年代初頭、1955年頃*(全てモノラル) ※音源:独Concert Hall MMS-52、MMS-25* ◎収録時間:66:58 |
| “知的な制御の奥底に潜む豊かな情感!” | ||
|
||
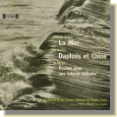 TRE-078 |
ル・コント~フランス管弦楽曲集 アダン:歌劇「我もし王なりせば」序曲 シャブリエ:歌劇「いやいやながらの王様」~ポーランドの祭り 気まぐれなブーレ/狂詩曲「スペイン」 楽しい行進曲 ドビュッシー:交響詩「海」* ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ* 「ダフニスとクロエ」第2組曲* |
ピエール=ミッシェル・ル・コント(指) パリ・オペラ座O(パリ国立歌歌劇場O) 録音:1965年頃、1964年10月*(全てステレオ) ※音源:米QUARANTE-CINQ 45001、日Concert Hall SMS-2119* ◎収録時間:76:07 |
| “ミュンシュ以上の瑞々したを湛えたル・コントの快演!” | ||
|
||
 TRE-079 |
ル・コント~ラロ&ベルリオーズ ラロ:歌劇「イスの王様」序曲 ベルリオーズ:「ベンヴェート・チェルリーニ」序曲# 「ファウストの劫罰」#~ラコッツィ行進曲/妖精の踊り 幻想交響曲Op.14* |
ピエール=ミッシェル・ル・コント(指) コンセール・ド・パリO フランクフルトRSO# パリ・オペラ座O(パリ国立歌歌劇場O)* 録音:1950年代中頃(ステレオ) ※音源:仏Convert Hall SMS-2911、仏Prestige de la Musique SR-9648* ◎収録時間:77:10 |
| “ラロの管弦楽法の凄さを体当たりで表現した奇跡的名演!” | ||
|
||
 TRE-080 |
アニー・フィッシャー/モスクワ・ライヴ集 モーツァルト:ピアノ・ソナタ第10番K.330 シューベルト:即興曲Op.142-3 ショパン:バラード第1番 シューベルト:即興曲Op.142-1* リスト:3つの演奏会用練習曲~ため息** コダーイ:セーケイの嘆き歌# リスト:ハンガリー狂詩曲第14番* バルトーク:2つのルーマニア舞曲Op.8a~第1曲** アレグロ・バルバロ## |
アニー・フィッシャー(P) 録音:1949年7月16日、1951年4月8日*、1951年4月11日**、1951年4月12日#(以上,モスクワ音楽院大ホール)、1955年(会場不明)## ※音源:MELODIYA M10-44183-6 ◎収録時間:65:15 |
| “ロシア・ピアニズムの聖地で叩きつけた自らの信念!!” | ||
|
||
 TRE-082 |
エドゥアルド・デル・プエヨ~フランク&ベートーヴェン フランク:前奏曲,コラールとフーガ* ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第26番「告別」 ピアノ・ソナタ第29番「ハンマークラヴィア」 |
エドゥアルド・デル・プエヨ(P) 録音:1959年10月3-5日アムステルダム・バッハザール*、1958年5月7-15日アムステルダム・コンセルトヘボウ小ホール(共にモノラル) ※音源:蘭fontana 698-042CL*、英fontana CFL-1037 ◎収録時間:79:29 |
| “タッチの色彩力と直感的な構成掌握力の非凡さ!” | ||
|
||
|
||||
 TRE-084r |
《フランツ・アンドレ没後40年記念》 フランツ・アンドレ~イタリア紀行 ベルリオーズ:序曲「ローマの謝肉祭」* チャイコフスキー:イタリア奇想曲# レスピーギ:「交響詩「ローマの噴水」 交響詩「ローマの松」 |
フランツ・アンドレ(指)ベルギー国立RSO 録音:1956年7月15日*、1950年代中期#、1950年代後期 (全てステレオ) ※音源:独TELEFUNKEN SLT-43014*、STW-30006#、英TELEFUNKEN SMA-4 ◎収録時間:61:31 |
||
| “思わず仰け反る、「ローマの松」終曲の脅威的な音の膨張力!” | ||||
|
||||
 TRE-085 |
《フランツ・アンドレ没後40年記念》 フランツ・アンドレ~“ラプソディ” エネスコ:ルーマニア狂詩曲第1番** アウフスト・ドゥ・ブーク:ダホメー狂詩曲* リスト:ハンガリー狂詩曲第1番(ドップラー編) ハンガー狂詩曲第2番(ミュラー=ベルクハウス編) ハンガー狂詩曲第3番(H・オットー編) ハンガー狂詩曲第6番(ドップラー編) 交響詩「前奏曲」 |
フランツ・アンドレ(指)ベルギー国立RSO ソーニャ・アンシュッツ(P)# 録音:1958年4月2-7日*、1959年7月、1950年代後半**(全てステレオ) ※音源:独TELEFUNKEN SLB-12001*、SBT-467、英TELEFUNKEN SMA-14** ◎収録時間:67:47 |
||
| “管弦楽版ハンガリー狂詩曲の突き抜けた楽しさ、豪快さ!” | ||||
|
||||
.gif) TRE-086 |
《フランツ・アンドレ没後40年記念》 フランツ・アンドレ~バレエ音楽集 ポンキエッリ:「ラ・ジョコンダ」~時の踊り ドリーブ:「シルヴィア」*~前奏曲&狩りの女神/間奏曲&緩やかなワルツ(第1幕)/ピチカート(第3幕)/バッカスの行列(第3幕) 「コッペリア」**~前奏曲&マズルカ/ワルツ(第1幕)/人形のワルツ(第2幕)/チャルダッシュ(第1幕) チャイコフスキー:「くるみ割り人形」組曲# ラヴェル:ボレロ## |
フランツ・アンドレ(指)ベルギー国立RSO 録音:1957年4月16日*、1957年4月17日**、1955年10月23日#、1958年4月2-7日##(全てステレオ) ※音源:独TELEFUNKEN ATW-30227、NT-540*,**、NT-200#、SLB-12001## ◎収録時間:75:37 |
||
| “濃厚な色彩で雰囲気を倍増させた「くるみ割り人形」の素晴らしさ!” | ||||
|
||||
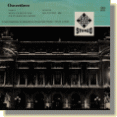 TRE-087 |
《フランツ・アンドレ没後40年記念》 フランツ・アンドレ~序曲・間奏曲集 スッペ:「軽騎兵」序曲/「詩人と農夫」序曲 オッフェンバック:「天国と地獄」序曲 フランツ・シュミット:「ノートル・ダム」間奏曲+ トマ:「ミニョン」序曲## オーベール:「フラ・ディアヴォロ」序曲** エロール:「ザンパ」序曲* アダン:「我もし王なりせば」序曲# オーベール:「ポルティチの唖娘」序曲* |
フランツ・アンドレ(指)ベルギー国立RSO 録音:1950年代中期、1955年10月*、1956年7月15日**、1956年7月19日#、1957年4月17日##(全てステレオ) ※音源:独TELEFUNKEN SLE-14211 、ATW-30227+ 、 SLT-43014*,**,#,## ◎収録時間:64:42 |
||
| “音楽の華を体で知っている、名匠アンドレの棒さばきの妙!” | ||||
|
||||
 TRE-088 |
マルクジンスキ~チャイコフスキー&ラフマニノフ チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番* |
ヴィトルド・マルクジンスキ(P) ヴィトルド・ロヴィツキ(指) ワルシャワPO 録音:1961年(共にステレオ) ※音源:MUZA SX-0123、SX-0124* ◎収録時間:69:54 |
| “謙虚な燃焼が大きく羽ばたく、ラフマニノフの世紀の名演!” | ||
|
||
 TRE-089 |
エッシュバッハー/ベートーヴェン&シューベルト ベートーヴェン:「失われた小銭への怒り」Op.129* エリーゼのために**/ロンドOp.51-1# エコセーズWoO.83## シューベルト:即興曲Op.90/即興曲Op.142 |
アドリアン・エッシュバッハー(P) 録音:1950年9月19日*、1950年頃**、1950年9月20日&5月24日#、1951年8月4日##、1953年4月22&23日 ※音源:独DG 30323、29313(シューベルト) ◎収録時間:75:31 |
| “これぞシューベルトの理想郷!たとえようもない霊妙さ!!” | ||
|
||
 TRE-090 |
ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲全集Vol.1 ピアノ三重奏曲第1番変ホ長調Op.1-1 ピアノ三重奏曲第2番ト長調Op.1-2 ピアノ三重奏曲第3番ハ短調Op.1-3 |
トリオ・サントリクイド [オルネッラ・サントリクイド(P) アリーゴ・ペリッチャ(Vn) マッシモ・アンフィテアトロフ(Vc)] 録音:1957年頃(全てステレオ) ※音源:仏Concert Hall SMS2140~2144 ◎収録時間:79:53(Vol.1)、77:35(Vol.2)、77:43(Vol.3) |
 TRE-091 |
ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲全集Vol.2 ピアノ三重奏曲変ホ長調WoO.38 創作主題による変奏曲Op.44 ピアノ三重奏曲第5番「幽霊」Op.70-1 ピアノ三重奏曲第6番変ホ長調Op.70-2 |
|
 TRE-092 |
ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲全集Vol.3 ピアノ三重奏曲第変ロ長調WoO.39 カカドゥ変奏曲 Op. 121a ピアノ三重奏曲第4番「街の歌」Op.11 ピアノ三重奏曲第7番「大公」Op.97 |
|
| “自然体に徹しながら作品のツボを捉えた、これぞアンサンブルの基本!” | ||
|
||
 TRE-094 |
デゾルミエール/イベール、ドビュッシー他 ドビュッシー:交響詩「海」# ショパン(デゾルミエール編):バレエ音楽「レ・シルフィード」* イベール:ディヴェルティメント |
ロジェ・デゾルミエール(指) チェコPO#、パリ音楽院O 録音:1950年11月13-15日#、1950年2月*、1951年6月 ※音源:SUPRAPHON (EURODISC) 913-296#、LONDON LL-884、 ◎収録時間:61:39 |
| “芳しく小粋なデゾルミエールの至芸を凝縮!!” | ||
|
||
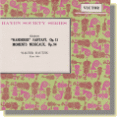 TRE-096 |
ワルター・ハウツィッヒ~シューベルト他 ヘンデル:調子の良い鍛冶屋 ブラームス:ワルツ第15番Op.39-15 リスト:巡礼の年第2年への追加;ヴェネツィアとナポリ~タランテラ シューベルト:即興曲Op.142-2 楽興の時Op.94(全6曲)* 幻想曲ハ長調「さすらい人」Op.15* |
ワルター・ハウツィッヒ(P) 録音:1956年11月28-29ビクター・スタジオ(日本)、1955年ニューヨーク* (全てモノラル) ※音源:Victor LS-2104、 Victor LH-32* ◎収録時間:71:03 |
| “小品専門家ではない!ハウツィッヒの知られざる洞察力と直感力!” | ||
|
||
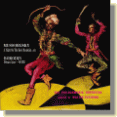 TRE-097 |
ワルター・ジュスキント~ムソルグスキー&ボロディン ムソルグスキー:交響詩「はげ山の一夜」 歌劇「ソロチンスクの定期市」~第1幕序奏/第3幕「ゴパーク」 古典様式による交響的間奏曲ロ短調 歌劇「ホヴァンシチナ」~第1幕前奏曲/ペルシャの女奴隷たちの踊り/第4幕第2場への間奏曲 スケルツォ変ロ長調 荘厳行進曲「カルスの奪還」(トルコ行進曲) ボロディン:歌劇「イーゴリ公」から* 序曲/ダッタン人の行進/ ダッタン人の踊り |
ワルター・ジュスキント(指) フィルハーモニアO 録音:1953年3月、1952年9月* ※音源:英PARLOPHONE PMC-1018、PMD-1023*(共に10インチ) ◎収録時間:79:58 |
| “オケの自発性だけでなく、作品自体の発言力をも引き出す見識力!” | ||
|
||
 TRE-098 |
バレンツェン~ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ他 ブラームス:ワルツ集Op.39~第15番 ウェーバー:ピアノ・ソナタ第1番~第4楽章「無窮動」 メンデルスゾーン:無言歌Op.62-6「春の歌」 無言歌Op.67-4「紡ぎ歌」 ショパン:ワルツ嬰ハ短調Op.64-2 リスト:ハンガリー狂詩曲第2番 愛の夢第3番 ベートーヴェン:エリーゼのために ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」* ピアノ・ソナタ第14番「月光」* ピアノ・ソナタ第23番「熱情」* |
アリーヌ・ヴァン・バレンツェン(P) 録音:1950年代初期(モノラル)、1959年(ステレオ)* ※音源:仏TRIANON TRI-33127、TRI-33190* ◎収録時間:79:15 |
| “冴えわたる技巧と直感を融合させた恐るべきドラマ生成力!” | ||
|
||
|
|
レオポルド・ルートヴィヒのマーラー マーラー:交響曲第9番 |
レオポルド・ルートヴィヒ(指)LSO 録音:1959年11月17-20日 ロンドン・ウォルサムストー・アセンブリー・ホール(ステレオ) ※音源:米EVEREST SDBR-3050-2 ◎収録時間:75:51 |
| “露骨な感情表現から開放した「マラ9」の世界初のステレオ録音!” | ||
|
||
 TRE-100(2CDR) ★ |
ブライロフスキー/リスト:ハンガリー狂詩曲集(全15曲) ●Disc1:第1番嬰ハ短調、第2番嬰ハ短調, 第4番変ホ長調、第14番ヘ短調, 第9番変ホ長調、第6番変ニ長調、 ●Disc2:第13番イ短調、第10番ホ長調, 第3番変ロ長調、第7番ニ短調、 第8番嬰ヘ短調、第12番嬰ハ短調、 第5番ホ短調、第11番イ短調、 第15番イ短調「ラコッツィ行進曲」 (以上、LP収録順と同じ) |
アレクサンダー・ブライロフスキー(P) 録音:1953年-1956年 ※音源:伊RCA B12R-0256/7 ◎収録時間:62:14+62:24 |
| “ふんだんに色気を放ちながら古臭さを感じさせない理想の名演!” | ||
|
||
 TRE-101 |
フランツ・アンドレ~ビゼー、ドビュッシー他 グレトリー(1741-1813):「チェファルとプロクリス」組曲~タンブーラン/メヌエット/ジーグ ラモー:バレエ組曲「プラテ」~メヌエット/リゴードン ベルリオーズ:「ファウストの劫罰」~鬼火のメヌエット シャブリエ:楽しい行進曲 ドビュッシー:管弦楽のための映像~「イベリア」* ビゼー:「アルルの女」第1組曲&第2組曲# |
フランツ・アンドレ(指)ベルギー国立RSO 録音:1954年頃、1950年*、1953年10月1日# ※音源:独TELEFUNKEN PLB-6011、英LGX-66001*、LGX-66021# ◎収録時間:73:03 |
| “クラシック音楽をアカデミックな檻から開放するアンドレの真骨頂!” | ||
|
||
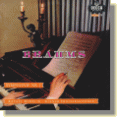 TRE-102 |
クーベリック/ドヴォルザーク&ブラームス ドヴォルザーク:弦楽セレナードOp.22 ブラームス:交響曲第2番ニ長調Op.73* |
ラファエル・クーベリック(指) イスラエルPO、VPO* 録音:1957年3月25日-4月14日、1957年4月4-8日*(共にモノラル) ※音源:米LONDON LL-1720、LL-1699* ◎収録時間:65:14 |
| “ハッタリ無用!クーベリックの底知れぬ才能に再開眼!” | ||
|
||
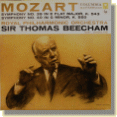 TRE-103 |
ビーチャム~モーツァルト:交響曲集 交響曲第38番「プラハ」K.504* 交響曲第39番変ホ長調K.543** 交響曲第40番ト短調K.550# |
トーマス・ビーチャム(指) ロイヤルPO 録音:1950年4月*、1955年12月**、1954年4月# ※音源:蘭CBS CBS-6020*、英PHILIPS ABL-3094**,# ◎収録時間:74:51 |
| “大きな包容力で魅了する、ビーチャム流の愉しいモーツァルト!” | ||
|
||
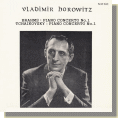 TRE-104 |
ホロヴィッツ~2大激烈ライヴ集 ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番* |
ウラディミール・ホロヴィッツ(P) ブルーノ・ワルター(指)アムステルダム・コンセルトヘボウO ジョージ・セル(指)NYO* 録音:1936年2月20日アムステルダム・コンセルトヘボウ、1953年1月12日カーネギー・ホール(共にモノラル・ライヴ) ※音源:米BRUNO WALTER SOCIETY BWS-728 、Private EV-5007* ◎収録時間:68:53 |
| “似ているようで意味が異なる2つの激烈ライヴ!” | ||
|
||
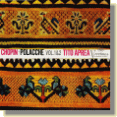 TRE-105(2CDR) ★ |
ティート・アプレア~ショパン:ポロネーズ集 ポロネーズ第9番Op. 71-2 ポロネーズ第1番Op. 26-1 ポロネーズ第3番Op. 40-1「軍隊」 ポロネーズ第4番Op. 40-2 ポロネーズ第13番変イ長調 ポロネーズ第2番Op. 26-2 ポロネーズ第6番「英雄」 ポロネーズ第5番Op. 44 ポロネーズ第8番Op.71-1 ポロネーズ第15番変ロ長調 ポロネーズ第10番Op. 71-3 ポロネーズ第16番変ト長調 ポロネーズ第14番嬰ト短調 |
ティート・アプレア(P) 録音:1960年代初頭(モノラル) ※音源:伊RCA VICTROLA KV-17/18 ◎収録時間:92:35 |
| “ショパンのポロネーズ演奏史上、無類の含蓄を誇る超名盤!” | ||
|
||
 TRE-106(2CDR) ★ |
ヴォイチャッハ~ドイツ名行進曲集 第1巻 ■Disc1 ●歴史的ドイツ行進曲集(エミール・カイザー編)* ○16世紀以前 野戦信号ラッパと軍鼓の大合奏 皇帝領付軍隊の行進曲 騎兵隊のファンファール 鼓笛隊の行進曲 ゴイゼン同盟行進曲(伝承曲) ○17世紀~18世紀へ フィンランド騎兵隊の行進曲 パッペンハイム軍のファンファール 「オイゲン公」行進曲 消燈信号 コーブルク行進曲(伝承曲) ○18世紀 ドイツ海軍礼式行進曲 スワビア地方連隊行進曲 フリードリヒ大王時代の行進曲 行進曲「懐しきデッサウ」 サクソニア選挙候領付連隊行進曲 ヘッセン"クールフェルスト"連隊行進曲 観兵式における騎兵部隊のフアンフアール(伝承曲) クリードリヒ:ホーヘンフリートベルク行進曲 自由戦争における義勇軍の行進曲(伝承曲) ○19世紀 ヴァルヒ:パリ入城行進曲 J.シュトラウス1世:ラデツキー行進曲 G.ピーフケ:行進曲「デュッベルの塹壕」 シェルツァー:バイエルン地方連隊分列行進曲 狩猟の鼓笛行進曲(伝承曲) C.タイケ:行進曲「旧友」 ■ヴォイチャッハ名演集 (1)フリードリヒ:トルガウ行進曲 (2)M.ローランド:行進曲「巨人衛兵の分列式」 (3)リュッベルト:ヘレン行進曲 (4)ノイマン:行進曲「ペピタ」 (5)K.コムツァーク:「バラタリア」行進曲 (6)ウンラート:「カール大王」行進曲 (7)R.ティーレ:行進曲「我等の海軍」 (8)R.ペリオン:行進曲「フェールベルリンの騎士」 (9)0.フェトラス:ヒンデンブルク行進曲 (10)P.キルステン:行進曲「友情」 W.リンデマン:行進曲「グリレンバナーの下に」 (11)H.ブルーメ:鉄兜隊行進曲 (12)D.エルトル:行進曲「ドイツの騎士」 (13)H.ブルーメ:行進曲「祖国の護り」 ■Disc2 (14)C.タイケ:「ツェッペリン伯号」行進曲 (15)R.ヘリオン:ブランデンブルグ行進曲 (16)H.ドスタル:行進曲「大空の勇士」 (17)A.ヴェンデ:行進曲「空の旅」 (18)E.シュティーベルツ:行進曲「ソンムの激戦」 (19)R.ヘルツァー:行進曲「ハイデクスブルク万才」 (20)G.フェルスト:バーデンワイル行涯曲 (21)作者不詳:コーブルク行進曲 (22)C.V.モルトケ:大選帝侯騎兵行進曲 (23)H.ヴェッセル:行進曲「旗を掲げて」 |
カール・ヴォイチャッハ(指) テレフンケン大吹奏楽団 録音:1932年11月*、 (1)1930年6月 (2)1932年11月 (3)1932年9月 (4)1932年7月 (5)1937年4月 (6)1932年7月 (7)1932年6月 (8)1930年6月 (9)1929年11月 (10)1934年7月 (11)1929年11月 (12)1933年2月 (13)1929年4月 (14)1933年2月 (15)1937年4月 (16)1930年6月 (17)1932年7月 (18)1932年8月 (19)1931年1月 (20)1929年7月 (20)1929年7月 (21)1930年頃 (22)1932年9月 (23)1933年頃 ※音源:King Record SLC-2300/2301 ◎収録時間:89:35 |
| “ドイツ行進曲の流儀を確立したヴォイチャッハの大業績!” | ||
|
||
 TRE-107(2CDR) ★ |
フルゴーニ~ショパン:マズルカ全集 第1番Op.6-1~第51番遺作 |
オラツィオ・フルゴーニ(P) 録音:1960年代初頭(ステレオ) ※音源:仏Musidisc RC-887/888 ◎収録時間:105:09 |
| “軽さにこそ意味がある!マズルカの民族色を超えた息吹” | ||
|
||
 TRE-108 |
マックルーア版/ワルター厳選名演集Vol.1 ベートーヴェン:交響曲第1番Op.21 交響曲第3番「英雄」変ホ長調Op.55* |
ブルーノ・ワルター(指) コロンビアSO 録音:1959年1月5,6,8,.9日、1958年1月20,23,25日*(共にステレオ) ※音源:SONY 20AC1807、20AC1808* ◎収録時間:73:51 |
| “ワルターの正直な感性と楽曲の魅力が完全調和!” | ||
|
||
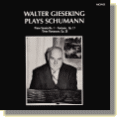 TRE-109 |
ギーゼキング~シューマン:ピアノ曲集 シューマン:3つのロマンスOp.28 ピアノ・ソナタ第1番Op.11* 幻想曲ハ長調Op.17# |
ワルター・ギーゼキング(P) 録音:1951年7月9日ザールブリュッケン、1942年ベルリン*、1947年10月フランクフルト# ※音源:米Discocorp RR-492、露Melodya M10-49335 *,# ◎収録時間:69:27 |
| “ギーゼキングとシューマンとの相性を如実に示す名演集!” | ||
|
||
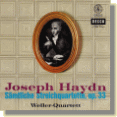 TRE-110(2CDR) ★ |
ウェラーQ/ハイドン:ロシア四重奏曲(全6曲) 弦楽四重奏曲第37番ロ短調Op.33-1 弦楽四重奏曲第38番変ホ長調Op.33-2「冗談」 弦楽四重奏曲第39番ハ長調Op.33-3「鳥」 弦楽四重奏曲第40番変ロ長調Op.33-4 弦楽四重奏曲第41番ト長調Op.33-5 弦楽四重奏曲第42番ニ長調Op.33-6 |
ウェラーQ【ワルター・ウェラー(Vn1)、アルフレート・シュタール(Vn2)、ヘルムート・ヴァイス(Va)、ルードヴィヒ・バインル(Vc)] 録音:1965年2月(ステレオ) ※音源:独ORBIS 92885 ◎収録時間:108:36 |
| “ローカルなウィーン趣味から脱皮したウェラーQの清新スタイル!” | ||
|
||
 TRE-111r |
音源変更・再復刻 !! ボンガルツ~バッハ&ブルックナー バッハ:ブランデンブルク協奏曲第3番* ブルックナー:交響曲第6番イ長調 |
ハインツ・ボンガルツ(指) ライプチヒ・ゲヴァントハウスO ハンス・ピシュナー(Cem)* 録音:1960年代初頭、1964年12月16-16日(共にステレオ)、 ※音源:羅ELECTRECORD STM-ECE-0672*、ETERNA 825540-541 ◎収録時間:72:47 |
| “「ブル6」の命、リズムの意味を体現し尽くした歴史的名演!!” | ||
|
||
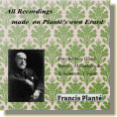 TRE-112 |
フランシス・プランテ~全録音集 ボッケリーニ(プランテ編):メヌエット グルック(プランテ編):ガヴォット ベルリオーズ(ルドン編):メフィストのセレナード メンデルスゾーン:スケルツォ.ホ長調 Op.16-2 無言歌集~Op.19-3「狩の歌」/Op.67-4「紡ぎ歌」/Op.67-6「セレナード」/Op.62-6「春の歌」 シューマン(ドビュッシー編):子供のための12の4手用曲集Op.85~第9曲「噴水にて」 シューマン:4つの小品~ロマンスOp.32-2 3つのロマンス~第2曲Op.28-2 ショパン:練習曲Op.10-4/Op.10-5「黒鍵」 Op.10-7/Op.25-1/Op.25-2 Op.25-9「蝶々」/Op.25-11「木枯らし」 |
フランシス・プランテ(P) 録音:1928年7月3-4日フランス、ランド県モン=ド=マルサン ※音源:Private ZRC-1003 ◎収録時間:44:03 |
| “明瞭な電気録音で遺された老巨匠の奇跡的な妙技!” | ||
|
||
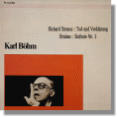 TRE-113 |
ベーム~R・シュトラウス&ブラームス R・シュトラウス:交響詩「死と変容」* ブラームス:交響曲第1番ハ短調Op.68 |
カール・ベーム(指)ベルリンRSO 録音:1950年3月25日*、1950年4月13日ライヴ ※音源:日RVC RCL-3316*、伊Foyer FO-1033 ◎収録時間:69:09 |
| “ベームの芸術のピークを示す2つの名演!” | ||
|
||
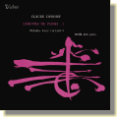 TRE-114 |
ノエル・リー/ドビュッシー:ピアノ曲全集Vol.1 前奏曲集第1巻/前奏曲集第2巻* |
ノエル・リー(P) 録音:1959年、1962年*(共にステレオ) ※音源:日COLUMBIA OS-671VL、OS-672VL*(全てValois原盤) ◎収録時間:73:18 |
| “楽器の魅力と奏者の感性が完全融合した、ドビュッシー録音の金字塔!” | ||
|
||
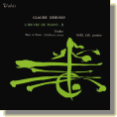 TRE-115 |
ノエル・リー/ドビュッシー:ピアノ曲全集Vol.2 ピアノのために/子供の領分* 12の練習曲集* |
ノエル・リー(P) 録音:1958年頃、1962年#(全てステレオ) ※音源:日COLUMBIA OS-674VL、OS-675VL*、OS-673VL#* (全てValois原盤) ◎収録時間:75:01 |
|
||
| TRE-114-115(2CDR) |
ノエル・リー/ドビュッシー:ピアノ曲全集Vol.1&2 上記2点のセット化 |
ノエル・リー(P) |
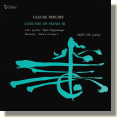 TRE-116 |
ノエル・リー/ドビュッシー:ピアノ曲全集Vol.3 喜びの島 ベルガマスク組曲*/版画# 映像第1巻#/映像第2巻# |
ノエル・リー(P) 録音:1958年頃、1959年*(全てステレオ) ※音源:日COLUMBIA OS-672VL、OS-675VL*、OS-674VL#(全てValois原盤) ◎収録時間:62:55 |
|
||
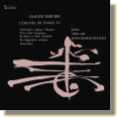 TRE-117 |
ノエル・リー/ドビュッシー:ピアノ曲全集Vol.4 アラベスク第1番&第2番 舞曲(スティリー風タランテラ) スケッチ帳より/仮面# 白と黒で*/リンダラハ* 6つの古代の墓碑銘*/小組曲* |
ノエル・リー(P) ジャン=シャルル・リシャール(P)* 録音:1959年、1962年*(全てステレオ) ※音源:日COLUMBIA OS-675VL、OS-676VL*、OS-671VL# (全てValois原盤) ◎収録時間:64:17 |
|
||
| TRE-116-117(2CDR) |
ノエル・リー/ドビュッシー:ピアノ曲全集Vol.3&4 上記2点のセット化 |
ノエル・リー(P) ジャン=シャルル・リシャール(P)(4手作品) |
 TRE-118r |
フー・ツォン~モーツァルト:ピアノ協奏曲集 モーツァルト:ピアノ協奏曲第25番(カデンツァ=フンメル作) ピアノ協奏曲第27番変ロ長調K.595 |
フー・ツォン(P) ヴィクトル・デザルツェンス(指) ウィーン国立歌劇場O 録音:1962年頃(ステレオ) ※音源:日KING SH-5098 ◎収録時間:62:22 |
| “無類の絶美タッチから溢れ出す無限のニュアンスに絶句!” | ||
|
||
 TRE-119 |
ハリス中佐&グレナディア・ガーズ軍楽隊 ホルスト:吹奏楽のための組曲第1番 フレデリック・ロセ:組曲「ヴェニスの商人」~間奏曲/ヴェニスの総監の行進曲 ジョン・アンセル:3つのアイルランドの絵 アーサー・ウッド:3つの高地の舞曲 スーザ:行進曲集* 星条旗よ永遠なれ/無敵の荒鷲 士官候補生/ピカドーレ/忠誠 エル・キャピタン/マンハッタン・ビーチ キング・コットン/ワシントン・ポスト 自由の鐘 |
フレデリック・J.ハリス中佐(指) グレナディア・ガーズ軍楽隊 録音:1956年11月、1958年4月(共にステレオ) ※音源:米LONDON OS-103、日KING SLC-8* ◎収録時間:62:26 |
| “近衛兵軍楽隊、黄金期のステレオ・サウンド!” | ||
|
||
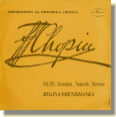 TRE-121 |
レギーナ・スメンジャンカ/ショパン:ワルツ集.他 ショパン:3つのエコセーズOp.72* タランテラOp.43* ワルツ第1番~14番 ワルツ第19番イ短調(遺作)* ワルツ第18番変ホ長調(遺作)* 子守歌Op.57* |
レギーナ・スメンジャンカ(P) 録音:1959-1960年(ステレオ) ※音源:MUZA SX-0068、 SX-0069* ◎収録時間:64:02 |
| “解釈の痕跡を感じさせず、ショパンの心情を余すことなく代弁!” | ||
|
||
 TRE-122 |
レギーナ・スメンジャンカ/ピアノ協奏曲集 バッハ:ピアノ協奏曲イ長調BWV.1055 モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番 ショパン:ピアノ協奏曲第2番* |
レギーナ・スメンジャンカ(P) スタニスラフ・ヴィスロッキ(指) ヴィトルド・ロヴィツキ(指)* ワルシャワ国立PO 録音:1960年頃、1959年*(全てステレオ) ※音源:独CNR FA-402、独TELEFUNKEN NT-459* ◎収録時間:77:28 |
| “タッチの変化の背後にドラマを添える独自のセンス!” | ||
|
||
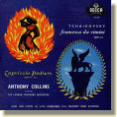 TRE-124 |
A・コリンズ~ファリャ、チャイコフスキー他 ファリャ:「恋は魔術師」~序奏-恐怖の踊り/漁夫の物語/火祭りの踊り/パントマイム-終曲 シベリウス:弦楽のためのロマンスOp.42* 「カレリア」組曲Op.11* チャイコフスキー:イタリア奇想曲# 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」# |
アンソニー・コリンズ(指) LPO、ロイヤルPO*、LSO# 録音:1950年2月4日、1957年*、1956年1月17-18日#(全てモノラル) ※音源:DECCA ACL-124、HMV ALP-1578*、DECCA LXT-5186# ◎収録時間:75:53 |
| “シベリウスだけではない、コリンズの妥協なきダイナミズム!” | ||
|
||
 TRE-125 |
マックルーア版/ワルター厳選名演集Vol.2 モーツァルト:歌劇「魔笛」序曲* 歌劇「劇場支配人」* 歌劇「フィガロの結婚」序曲* マーラー:交響曲第1番「巨人」 |
ブルーノ・ワルター(指) コロンビアSO 録音:1961年3月*、1961年1月&2月(全てステレオ) ※音源:日SONY 20AC-1805*、20AC-1830 ◎収録時間:68:59 |
| “ワルターの全人生を注いだ「巨人」の不滅の価値!” | ||
|
||
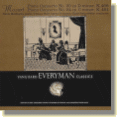 TRE-126 |
デニス・マシューズ~モーツァルト モーツァルト:ピアノ・ソナタ第8番K.310* ピアノ協奏曲第24番(カデンツァ=マシューズ作) ピアノ協奏曲第20番(カデンツァ=ベートーヴェン作) |
デニス・マシューズ(指) ハンス・スワロフスキー(指) ウィーン国立歌劇場O 録音:1959年頃*、1958年(全てステレオ) ※音源:米VANGUARD SRV-196SD*、SRV-142SD ◎収録時間:74:42 |
| “天国のモーツァルトに聴かせることだけを考えた唯一無二の感動作!” | ||
|
||
 TRE-127 |
アンセルメ~1960年代の厳選名演集1~プロコフィエフ他 グリンカ:幻想曲「カマリンスカヤ」 ボロディン:中央アジアの草原にて プロコフィエフ:古典交響曲 交響曲第5番* |
エルネスト・アンセルメ(指) スイス・ロマンドO 録音:1961年2月、1964年4月*(全てステレオ) ※音源:米LONDON CS-6223、CS-6406* ◎収録時間:70:11 |
| “クールなのに作品を突き放さない、アンセルメの絶妙な対峙力!” | ||
|
||
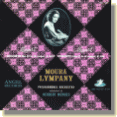 TRE-129 |
リンパニー~モーツァルト:ピアノ協奏曲集 モーツァルト:ピアノ協奏曲第12番(カデンツァ=第1楽章:モーツァルト第2作、第2,3楽章:モーツァルト第1作) ピアノ協奏曲第21番(カデンツァ=第1楽章:ウィンディング作、第3楽章:クレンゲル作)* ブラームス:間奏曲Op.117-2** パガニーニの主題による変奏曲第2巻Op.35-2# ショパン:幻想即興曲Op.66## |
モーラ・リンパニー(P) ハーバート・メンゲス(指) フィルハーモニアO 録音:1954年4月28日、1953年2月17日*、1952年11月3日**、1947年12月19日#、1949年4月26日## ※音源:日Angel HC-1006(モーツァルト)、英Cambridge Records DIMP-2 ◎収録時間:73:33 |
| “英国風の端正さの中に光るリンパニー独自の華やぎ!” | ||
|
||
 TRE-130 |
プエヨ~バッハ&グラナドス バッハ:パルティータ第1番BWV.825* グラナドス:スペイン舞曲集(全12曲) |
エドゥアルト・デル・プエヨ(P) 録音:1959年*、1956年8月29-30日(全てモノラル) ※音源:蘭fontana 698-042CL*、蘭PHILIPS A00388L ◎収録時間:70:36 |
| “打鍵の後の余韻に滲むスペイン情緒と色香!” | ||
|
||
 TRE-131 |
ロジータ・レナルド~カーネギー・ホール・ライヴ バッハ:パルティータ第1番 変ロ長調 モーツァルト:ピアノ・ソナタ第8番 イ短調K.310 メンデルスゾーン:厳格な変奏曲Op.54 モーツァルト:ロンド.ニ長調K.485 ショパン:練習曲~[Op.10-11, 25-5, 10-3, 25-8, 25-4, 10-2] マズルカOp.30-4 メンデルスゾーン:前奏曲 変ロ長調Op.104-1 ショパン:練習曲~[Ops.25-2, 25-3, 10-4] ラヴェル:高雅で感傷的なワルツ ドビュッシー:舞曲 ショパン:マズルカ 嬰へ短調Op.59-3 |
ロジータ・レナルド(P) 録音:1949年1月19日カーネギー・ホール(ライヴ) ※音源:米IPA 120-121 ◎収録時間:79:53 |
| “高度な技巧を聴き手に意識させない天才的閃きの連続!” | ||
|
||
 TRE-132 |
パウムガルトナー/ヘンデル&モーツァルト モーツァルト:コントルダンス付きメヌエット K.463 カッサシオン.ト長調K.63~アンダンテ ディヴェルティメント第12番変ホ長調K.252 ヘンデル:水上の音楽*/王宮の花火の音楽* |
ベルンハルト・パウムガルトナー(指) ザルツブルク・モーツァルテウム・カメラータ・アカデミカ 録音:1965年、1960年* 全てステレオ ※音源:蘭fontana 700438WGY、独Opera ST-92287* ◎収録時間:71:41 |
| “研究者のイメージとは裏腹の心に染みる歌と風格美!” | ||
|
||
 TRE-133 |
ワルター・ゲール~ベートーヴェン他 バッハ:ブランデンブルグ協奏曲第3番 ベートーヴェン:交響曲第1番* 交響曲第8番ヘ長調Op.93** スメタナ:「売られた花嫁」序曲# |
ワルター・ゲール(指) ヴィンタートゥールSO フランクフルト歌劇場O* フランクフルトRSO**,# 録音:1950年代中頃(全てステレオ) ※音源:日Concert Hall SM-6101、仏PRESTIGE DE LA MUSIQUE SA-9653*、日Concert Hall SM-197**、SM-6111# ◎収録時間:66:26 |
| “古典な均整美に活気を与えた、ゲール最高のベートーヴェン!” | ||
|
||
 TRE-134 |
ダヴィドヴィチ~ショパン:ワルツ集.他 マズルカ第7番ヘ短調Op.7-3 マズルカ第36番イ短調Op.59-1 マズルカ第50番イ短調遺作 3つのエコセーズOp.72 ワルツ集(全14曲)* |
ベラ・ダヴィドヴィチ(P) 録音:1950年代中頃、1950年代後期*(全てモノラル) ※音源:Melodiya 06437-6438、011653-54* ◎収録時間:60:45 |
| “気品溢れる造形美で魅了する「ワルツ集」の歴史的名盤!” | ||
|
||
 TRE-135 |
ギーゼキング/シューベルト&ブラームス シューベルト:ピアノ・ソナタ第18番ト長調D894* ブラームス:間奏曲変ロ短調Op.117-2# 6つの小品~第5曲「ロマンス」Op.118-5# ピアノ・ソナタ第3番ヘ短調Op.5** |
ワルター・ギーゼキング(P) 録音:1947年10月12日*、1939年ベルリン#、1948年9月フランクフルト** ※音源:伊MOVIMENT MUSICA 01.063*、Melodiya M10-43395-B ◎収録時間:70:45 |
| “虚飾を排して作品の発言力だけを徹底追求する技巧と直感!” | ||
|
||
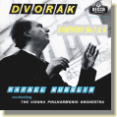 TRE-136 |
クーベリック&VPOのドヴォルザーク 交響曲第7番ニ短調Op.70 交響曲第9番ホ短調「新世界から」* |
ラファエル・クーベリック(指)VPO 録音:1956年10月1-2日、3-4日* (共にモノラル) ※音源:英DECCA LXT-5290、LHT-5291* ◎収録時間:77:05 |
| “「ウィーン・フィルのドヴォルザーク」の頂点をなす感動録音!” | ||
|
||
 TRE-137 |
オーマンディ/米COLUMBIAモノラル名演集1~J・シュトラウス他 ワルトトイフェル:ワルツ「学生楽隊(女学生)」 ワルツ 「スケートをする人々」 レハール:ワルツ「金と銀」 「メリー・ウィドウ」ワルツ J・シュトラウス:「こうもり」序曲* 「女王レースのハンカチーフ」序曲** 「くるまば草」序曲#/皇帝円舞曲## ワルツ「美しく青きドナウ」## ワルツ「南国のバラ」## ポルカ・シュネル「雷鳴と電光」** トリッチ・トラッチ・ポルカ* J・シュトラウスⅠ:ラデツキー行進曲* |
ユージン・オーマンディ(指) フィラデルフィアO 録音:1953年6月26日(ワルトトイフェル&レハール)、1952年5月13日*、1952年12月21日**、1953年4月26日#、1957年12月23日##(全てモノラル) ※音源:蘭PHILIPS S04624L、米 COLUMBIA ML-5238## ◎収録時間:76:52 |
| “ウィーン情緒無用!リズムと色彩の華やぎで聴き手を魅了!!” | ||
|
||
 TRE-138 |
アシュケナージ/ソ連時代のショパン バラード第2番Op.38* 夜想曲第3番Op.9-3* 練習曲集Op.10/練習曲集Op.25 |
ヴラディーミル・アシュケナージ(P) 録音:1959年*、1959-1960年(全てモノラル) ※音源:MELODIYA OS-2101、 OS-2132* ◎収録時間:76:14 |
| “若さだけではない!ソ連時代のアシュケナージの入念な表現力!” | ||
|
||
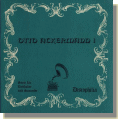 TRE-139 |
オットー・アッカーマン~名演集Vol.1 モーツァルト:交響曲第7番ニ長調K.45 交響曲第8番ニ長調K.48 交響曲第12番ト長調K.110 ハイドン:交響曲第100番「軍隊」* ボロディン:交響曲第2番ロ短調# |
オットー・アッカーマン(指) オランダPO、ケルンRSO*,# 録音:1952年12月10-11日、1955年10月2-3日*、1954年6月8-11日# ※音源:独DISCOPHILIA OAA-101、DIS.OAA-100*,# ◎収録時間:79:02 |
| “アッカーマン知られざる真価の本質を知る交響曲集!” | ||
|
||
 TRE-140 |
オットー・アッカーマン~名演集Vol.2 モーツァルト:交響曲第9番ハ長調 K. 73 交響曲第13番ヘ長調 K. 112 ケルビーニ:歌劇「アナクレオン、またはつかの間の恋」序曲* チャイコフスキー:交響曲第4番ヘ短調* |
オットーアッカーマン(指) オランダPO、 ベルン市立歌劇場O* 録音:1952年12月10-11日、1958年11月18日(ライヴ)* ※音源:独DISCOPHILIA OAA-101、瑞西RELIEF RL-851* ◎収録時間:75:05 |
| “チャイコフスキーの孤独とダイナミズムを高潔な音彩で徹底抽出!” | ||
|
||
 TRE-141 |
マイラ・ヘス~モーツァルト&ブラームス モーツァルト:ピアノ協奏曲第14番K.449 ブラームス:ピアノ協奏曲第2番Op.83* |
マイラ・ヘス(P) ブルーノ・ワルター(指)NYO 録音:1954年1月7日、1951年2月11日*(共にライヴ ※音源:米 Bruno Walter Society PR-36、BWS-736* ◎収録時間:70:21 |
| “ヘスとワルターの親和性が最大に発揮された2大名演!” | ||
|
||
 TRE-142 |
ジャンヌ=マリー・ダルレ/サン・サーンス:ピアノ協奏曲集1 サン・サーンス:七重奏曲Op.65* ピアノ協奏曲第2番** ピアノ協奏曲第5番「エジプト風」# |
ジャンヌ=マリー・ダルレ(P) ルイ・フレスティエ(指) フランス国立放送局O ロジェ・デルモット(Tp)* ガストン・ロジェ(Cb)* パスカルQ団員* 録音:1957年6月*、1957年4月27-28日**、1957年4月15-17日#(全てモノラル) ※音源:仏PATHE DTX-252*、DTX-176 ◎収録時間:68:14 |
| “作曲家直伝という箔を超越したダルレの恐るべき色彩力!” | ||
|
||
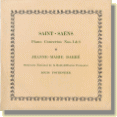 TRE-143 |
ジャンヌ=マリー・ダルレ/サン・サーンス:ピアノ協奏曲集2 ピアノ協奏曲第1番 ピアノ協奏曲第3番 ピアノ協奏曲第4番## |
ジャンヌ=マリー・ダルレ(P) ルイ・フレスティエ(指) フランス国立放送局O 録音:1956年5月、1955年4月##(全てモノラル) ※音源:英HMV ALP-1593、仏PATHE DTX-176## ◎収録時間:74:45 |
|
||
 TRE-142-143(2CDR) |
ジャンヌ=マリー・ダルレ/サン・サーンス:ピアノ協奏曲全集&七重奏曲 TRE-142とTRE=143をセット化したもの |
ジャンヌ=マリー・ダルレ(P) ルイ・フレスティエ(指) フランス国立放送局O ロジェ・デルモット(Tp)* ガストン・ロジェ(Cb)* パスカルQ団員* 録音:1955-1957年 ※音源:仏PATHE DTX-252、DTX-176、英HMV ALP-1593 ◎収録時間:68:14+74:45 |
 TRE-144 |
ヴェルディ:レクイエム | グィド・カンテッリ(指)ボストンSO エルヴァ・ネルリ(S) クララマエ・ターナー(A) ユージン・コンリー(T) ニコラ・モスコーナ(Bs) ニュー・イングランド音楽大学cho 録音:1954年12月17日ライヴ ※音源:米Discocorp IGI-340 ◎収録時間:79:57 |
| “大伽藍に傾かず、歌の力を引き出すカンテッリの統率力!” | ||
|
||
 TRE-145 |
J・B・ポミエ/チャイコフスキー&ベートーヴェン チャイコフスキー:ピアノ・ソナタ.ト長調Op.37 「ドゥムカ」-ロシアの農村風景Op.59* ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」# |
ジャン=ベルナール・ポミエ(P) ディミトリ・コラファス(指) ラムルーO 録音:1964年6月18-25日&10月20-22日&11月4日、1964年10月20-24日&11月4日*、1962年#(全てステレオ) ※音源:東芝 AA-8022、仏Club Francais 2300# ◎収録時間:79:53 |
| “10代から備わっていたポミエの美麗タッチと造形力!” | ||
|
||
 TRE-146 |
カンポーリ~ブルッフ、サン・サーンス&ラロ ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 サン・サーンス:ハバネラ* 序奏とロンド・カプリチオーソ* ラロ:スペイン交響曲# |
アルフレッド・カンポーリ(Vn) ロイヤルトン・キッシュ(指)新交響楽団 アナトール・フィストラーリ(指)LSO* エドゥアルド・ヴァン・ベイヌム(指)LPO# 録音:1951年4月17日、1953年11月10日*、1953年3月3-4日# ※音源:英DECCA ACL-64、ACL-124# ◎収録時間:77:08 |
| “作品の様式美を踏み外さないカンポーリの芳しい歌心!” | ||
|
||
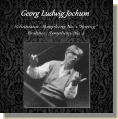 TRE-147 |
G・L・ヨッフム~シューマン&ブラームス シューマン:交響曲第1番「春」Op.38 ブラームス:交響曲第2番ニ長調Op.73* |
ゲオルク・ルートヴィヒ・ヨッフム(指) ベルリンRSO、スウェーデンRSO* 録音:1951年6月10日、1957年7月5日*(共にモノラル) ※音源: RVC RCL-3310、BIS LP-331/333* ◎収録時間:64:52 |
| “高名な兄以上の統率力と高潔な精神力を感じさせる凄演!” | ||
|
||
 TRE-148 |
L・ルートヴィヒ~「未完成」&「新世界」 モーツァルト:歌劇「イドメネオ」序曲* シューベルト:交響曲第8番「未完成」 ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界から」# |
レオポルド・ルートヴィヒ(指) ハンブルク国立歌劇場O*、LSO 録音:1960年代中期*、1959年11月17日、11月16日#(全てステレオ) ※音源:独EUROPA E-177*、日COLUMBIA MS-1102EV ◎収録時間:68:11 |
| “斜に構えず、誇張せず、音楽の魂をひたむきに追求!” | ||
|
||
 TRE-149 |
アルトゥール・ローター~劇付随音楽集 ウェーバー:「オベロン」序曲 「プレチオーザ」序曲* シューベルト:「ロザムンデ」(抜粋)** 序曲/間奏曲第3番/バレエ音楽第2番 メンデルスゾーン:「真夏の夜の夢」(抜粋)# 序曲/スケルツォ/夜想曲/結婚行進曲 |
アルトゥール・ローター(指) ベルリン国立歌劇場O 録音:1956年9月16日、1956年6月16日*、1957年6月20日**、1957年3月27日-4月3日#(全てステレオ) ※音源:独TELEFUNKEN SLT-43011、SLT-43010**,# ◎収録時間:68:58 |
| “聴き手の感性を刺激する究極の音の紡ぎ出し!” | ||
|
||
 TRE-150 |
シェルヘンの二大過激名演集 ハイドン:交響曲第100番「軍隊」 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」* |
ヘルマン・シェルヘン(指) ウィーン国立歌劇場O 録音:1958年7月、1958年9月18日*(共にステレオ) ※音源:Westminster WST-14044、WST-14045* ◎収録時間:66:58 |
| “伝統美を完全放棄!過激さの裏に迸る絶対に譲れない信条!!” | ||
|
||
 TRE-151 |
エフレム・クルツ~マーチの祭典 R=コルサコフ:「皇帝サルタンの物語」組曲* ドゥビーヌシカOp.62* 組曲「雪娘」~道化師たちの踊り* ■行進曲集 ヴェルディ:歌劇「アイーダ」~大行進曲 プロコフィエフ:「3つのオレンジへの恋」~行進曲 R=コルサコフ:組曲「金鶏」~結婚行進曲 マイヤベーア:歌劇「予言者」~戴冠式行進曲 ベルリオーズ:「ファウストの劫罰」~ハンガリー行進曲 スーザ:星条旗よ永遠なれ シューベルト(ギロー編):軍隊行進曲 ベートーヴェン:「アテネの廃墟」~トルコ行進曲 シャブリエ:楽しい行進曲 J・シュトラウス1世(ウィンター編):ラデツキー行進曲 チャイコフスキー:スラヴ行進曲 |
エフレム・クルツ(指) フィルハーモニアO 録音:1963年6月26-29日&7月1-3日*、1959年(全てステレオ) ※音源:HMV SXLP-30076*、東芝 AA-8022 ◎収録時間:75:58 |
| “解釈のスリルではなく、音楽の楽しさをしみじみ感じたい方に!” | ||
|
||
 TRE-152 |
ワルベルク~モーツァルト&シューベルト モーツァルト:交響曲第40番ト短調K.550* シューベルト:交響曲第3番ニ長調D.200 交響曲第5番変ロ長調D.485 |
ハインツ・ワルベルク(指) バンベルクSO 録音:1961年3月*、1962年12月(全てステレオ) ※音源:日COLUMBIA MS-4*、独Opera St-1985 ◎収録時間:77:26 |
| “ただの純朴指揮者ではない!ワルベルク流の音楽の息づかせ方!” | ||
|
||
 TRE-153 |
モーツァルト:レクイエム K.626(ジェスマイヤー版) | ヨーゼフ・クリップス(指) ウィーン宮廷O&cho ヴェルナー・ペック(Boy-S) ハンス・ブライトショップ(Boy-A) ヴァルター・ルートヴィヒ(T) ハラルト・プレーグルヘフ(Bs) 録音:1950年6月 ※音源:KING RECORD ACD-13(Jp) ◎収録時間:55;44 |
| “厳格ではなく厳粛な空気感が心に染みるクリップスの至芸!!” | ||
|
||
 TRE-154 |
ラインスドルフ&ボストン響・厳選名演集Vol.1~マーラー マーラー:交響曲第5番 |
エーリヒ・ラインスドルフ(指) ボストンSO ロジャー・ヴォワザン(Tpソロ) ジェームズ・スタグリアーノ(Hrnソロ) 録音:1963年11月17,23,26日(ステレオ) ※音源:英RCA SER-5518 ◎収録時間:64:31 |
| “外面的効果を排し、芸術的な昇華力で勝負した記念碑的名演!!” | ||
|
||
 TRE-155 |
アルトゥール・ローター/オペラ序曲・合唱曲集 J・シュトラウス:「ジプシー男爵」序曲* 「くるまば草」序曲*/「こうもり」序曲* ニコライ:「ウィンザーの陽気な女房たち」~序曲#/月の出の合唱 ウェーバー:「魔弾の射手」~狩人の合唱/花嫁のために冠を ワーグナー:「タンホイザー」~大行進曲/巡礼の合唱 「さまよえるオランダ人」~水夫の合唱 「ローエングリン」~エルザの大聖堂への入場/婚礼の合唱 「ニュルンベルクのマイスタージンガー」~目覚めよ,夜明けは近いぞ ヴェルディ:「トロヴァトーレ」~朝の光がさしてきた 「ナブッコ」~行けわが思いよ,金色の翼に乗って |
アルトゥール・ローター(指) ベルリン国立歌劇場O*,# ベルリン・ドイツ・オペラO&cho 録音:1958年6月9-10日*、1956年3月5日#、1960年代前半(全てステレオ) ※音源:独TELEFUNKEN SLE-14211*、SLT-43011#、6.42885 ◎収録時間:78:18 |
| “魂の飛翔!劇場叩き上げの本領を発揮した比類なき説得力!” | ||
|
||
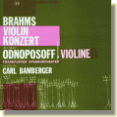 TRE-156 |
オドノポゾフ~ブラームス、サン・サーンス他 サン・サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ ハバネラOp.83 サラサーテ:ツィゴイネルワイゼン ブラームス:ヴァイオリン協奏曲* |
リカルド・オドノポゾフ(Vn) ジャンフランコ・リヴォリ(指)ジュネーヴRSO カール・バンベルガー(指)フランクフルト歌劇場O* 録音:1955年頃、1954年頃*(全てステレオ) ※音源:日Concert Hall SM-2250、仏Prestige de la Musique SR-9653* ◎収録時間:65:49 |
| “甘美な音色と厳しい造形力を駆使した「語り」の妙味!!” | ||
|
||
 TRE-157 |
サージェントの「わが祖国」 スメタナ:連作交響詩「わが祖国」 |
マルコム・サージェント(指)ロイヤルPO 録音:1964年(ステレオ) ※音源:独ELECTROLA SME-80937-38、伊EMI SQIM-6384 ◎収録時間:73:31 |
| “歴史的背景に囚われず純粋な音画描写に徹した潔さ!” | ||
|
||
 TRE-158 |
ウォーレンステイン~ベートーヴェン&メンデルスゾーン他 ベートーヴェン:交響曲第8番 メンデルスゾーン:交響曲第5番「宗教改革」 シャブリエ:ハバネラ* 狂詩曲「スペイン」*/楽しい行進曲* |
アルフレッド・ウォーレンステイン(指) ロスアンジェルスPO 録音:1953年3月、1953年2月*(全てモノラル) ※音源:米DECCA DL-9726、英Brunswick AXTL-1063* ◎収録時間:64:24 |
| “剛毅な進行にも作曲家の息吹を絶やさない「宗教改革」の理想像!” | ||
|
||
 TRE-159 |
フレッチャ~リーダーズ・ダイジェスト名演集1 ロッシーニ:「セミラーミデ」序曲* チャイコフスキー:「エフゲニ・オネーギン」~ワルツ# 弦楽セレナード~ワルツ# 「眠りの森の美女」~ワルツ** スラブ行進曲Op.31## 交響曲第4番ヘ短調Op.36 |
マッシモ・フレッチャ(指) ローマPO、ウィーン国立歌劇場O# 録音:1960年8月4日*、1961年6月23-25日#、1960年8月2日**、1960年8月5日## 1961年12月11,15,21-22日(全てステレオ) ※音源:日Victor SFM-3*.**.##、 米Radars Digest RD4-178-2/4(エフゲニ・オネーギン )、RD4-178-2/5(セレナード)、RD4-178-2/10(交響曲) ◎収録時間:76:19 |
| “イタリアの血と汗と歌で染め尽くした驚異のダイナミズム!” | ||
|
||
 TRE-160 |
レオポルド・ルートヴィヒ/ハイドン:「ホルン信号」他 モーツァルト:「コシ・ファン・トゥッテ」序曲* 「ドン・ジョヴァンニ」序曲* ハイドン:交響曲第31番「ホルン信号」# 交響曲第73番「狩猟」 |
レオポルド・ルートヴィヒ(指) ハンブルク国立歌劇場O*、 バイエルンRSO クルト・リヒター(Hrnソロ)# 録音:1960年代中期*、1966年4月6&8日ビュルガー・ブロイ・ホール(ミュンヘン)全てステレオ ※音源:独EUROPA E-177*、独ELECTRORA SME-91601 ◎収録時間:63:05 |
| “指揮者の存在感を極限まで消して作品の様式美を徹底表出!” | ||
|
||
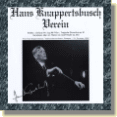 TRE-161(2CDR) |
クナッパーツブッシュ~ブラームス・プログラム 悲劇的序曲 ハイドンの主題による変奏曲 交響曲第3番 |
ハンス・クナッパーツブッシュ(指) シュトゥットガルトRSO 録音:1963年11月15日(モノラル・ライヴ) ※音源:Private HKV-TY4/5 ◎収録時間:81:48 |
| “いびつな造型の先にある昇華を極めた芸術性!” | ||
|
||
 TRE-162 |
デ・ブルゴス~「カルミナ・ブラーナ」 オルフ:カルミナ・ブラーナ |
ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴス(指) ニュー・フィルハーモニアO ルチア・ポップ(S) ゲルハルト・ウンガー(T) レイモンド・ウォランスキー(Br) ジョン・ノーブル(Br) ワンズワース・スクール少年cho 録音:1966年 ※音源:英EMI SAN-162 ◎収録時間:60:51 |
| “人生の光と影に様々な角度から光を当てた画期的なアプローチ!” | ||
|
||
 TRE-163 |
リシャルト・バクスト~ベートーヴェン ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ピアノ・ソナタ第14番「月光」 ピアノ協奏曲第3番ハ短調* |
リシャルト・バクスト(P) スタニスワフ・ヴィスロッキ(指) ワルシャワ国立PO 録音:1963年頃(ステレオ) ※音源:MUZA SXL-0166、SX-0167* ◎収録時間:77:44 |
| “ベートーヴェン弾きとしてのバクストの芸術性を思い知るい一枚!” | ||
|
||
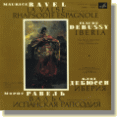 TRE-164 |
コンドラシン~ドビュッシー,ラヴェル、ヒンデミット ドビュッシー:イベリア ラヴェル:スペイン狂詩曲 ラ・ヴァルス ヒンデミット:ウェーバーの主題による交響的変容* |
キリル・コンドラシン(指)モスクワPO 録音:1961年(ステレオ) ※音源:Melodiya C-01783-4、蘭PHILIPS 835264AY* ◎収録時間:67:39 |
| “ロシア音楽以外で堪能するコンドラシンの比類なき洗練美! | ||
|
||
 TRE-165 |
フェレンチクのベートーヴェンVol.1 「シュテファン王」序曲 交響曲第2番ニ長調Op.36* 交響曲第4番変ロ長調Op.60 |
ヤーノシュ・フェレンチク(指)チェコPO 録音:1961年1月2-5日*、1961年10月14-17日(全てステレオ) ※音源:SUPRAPHON SUAST-50025*、瑞西Zipperling CSLP-6014 ◎収録時間:75:20 |
| “いにしえのチェコ・フィルだけが放つ芳しさと温もり!” | ||
|
||
 TRE-166 |
リンパニー/リスト&プロコフィエフ リスト:ピアノ協奏曲第2番* プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第1番 ピアノ協奏曲第3番 |
モーラ・リンパニー(P) マルコム・サージェント(指)ロイヤルPO* ワルター・ジュスキント(指)フィルハーモニアO 録音:1962年10月*、1956年5月2-3日(共にステレオ) ※音源:伊RCA GL-32526*、英WRC T-735 ◎収録時間:61:09 |
| “リンパニーの飾らない気品を堪能する協奏曲集!” | ||
|
||
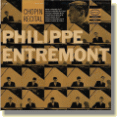 TRE-167 |
アントルモン~ショパン&「展覧会の絵」 ショパン:バラード第3番/夜想曲Op.27-2 即興曲第1番Op.29/タランテラOp.43 スケルツォ第1番/ポロネーズ第5番 軍隊ポロネーズOp.40-1 ムソルグスキー:展覧会の絵* |
フィリップ・アントルモン(P) 録音:1958年(モノラル) ※音源:米EPIC LC-3316、米COLUMBIA ML-5301* ◎収録時間:78:49 |
| “誰も語ってくれないアントルモンの本来の実力!” | ||
|
||
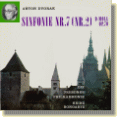 TRE-168 |
ボンガルツのドヴォルザーク バッハ:ブランデンブルク協奏曲第5番* ドヴォルザーク:交響曲第7番 |
ハインツ・ボンガルツ(指) ゲルハルト・ボッセ(Vn)*、 フリーデマン・エルベン(Vc)* ハインツ・ヘルチュ(Fl)*、 ハンス・ピシュナー(Cem)* ライプチヒ・ゲヴァントハウスO* ドレスデンPO 録音:1960年代初頭*、1962年12月17-20日(共にステレオ)、 ※音源:羅ELECTRECORD STM-ECE-0672*、独ELECTROLA STE-91328 ◎収録時間:62:42 |
| “豪華絢爛な響きでは気づかないドヴォルザークの真価!” | ||
|
||
 TRE-169 |
ブランカール~モーツァルト&シューマン モーツァルト:ピアノ・ソナタ第3番変ロ長調 K.281 ピアノ・ソナタ第5番ト長調 K.283 ピアノ・ソナタ第15番ハ長調 K.545 シューマン:ノヴェレッテンOp.21* |
ジャクリーヌ・ブランカール(P) 録音:1951年10月、1955年* ※音源:日King LY-34、英DECCA LXT-5120* ◎収録時間:78:08 |
| “音楽の自律的な推進性を引き出すブランカールの至芸!” | ||
|
||
 TRE-170 |
オドノポゾフ~メンデルスゾーン&パガニーニ他 ショーソン:詩曲* メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調 パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第1番 |
リカルド・オドノポゾフ(Vn) ジャンフランコ・リヴォリ(指) ジュネーヴRSO 録音:1955年頃*、1962年(全てステレオ) ※音源:日Concert Hall SM-2250*、英SMS-2205 ◎収録時間:72:19 |
| “オドノポゾフの「美音の底力」をたっぷり堪能!” | ||
|
||
 TRE-171 |
バルビローリ~「ブラ4」旧録音 ベートーヴェン:「レオノーレ」序曲第3番 ウェーバー:「オベロン」序曲 ブラームス:交響曲第4番ホ短調* |
ジョン・バルビローリ(指)ハレO 録音:1959年4月、1960年9月* ※音源:英PYE GSGC-2038、GSGC-1*(全てステレオ) ◎収録時間:64:25 |
| “渋味に逃げず果敢に愛をぶつけたバルビローリの代表盤!” | ||
|
||
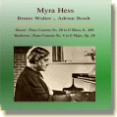 TRE-172 |
マイラ・ヘス~モーツァルト&ベートーヴェン モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番* ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番** ショパン:ワルツOp.18# ブラームス:間奏曲Op.119-3# スカルラッティ:ソナタL.387# |
マイラ・ヘス(P) ブルーノ・ワルター(指)NYO* エイドリアン・ボールト(指)BBC響** 録音:1956年カーネギーホール* 、1953年1月ロンドン**、1949年3月17,18日イリノイ大学# (全てライヴ) ※音源:米 Bruno Walter Society PR-36*、加ROCOCO RR-2041**,# ◎収録時間:74:13 |
| “懐の深さをもって作品を捉えるヘスのピアニズムの大きさ!” | ||
|
||
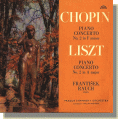 TRE-173 |
チェコのピアニズム~フランティシェク・ラウフ[1]/リスト&ショパン他 ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第30番 アンダンテ・ファヴォリ リスト:ピアノ協奏曲第2番* ショパン:ピアノ協奏曲第2番* |
フランティシェク・ラウフ(P) ヴァーツラフ・スメターチェク(指)プラハSO 録音:1965年11月15,18-19日、1964年6月17-18,20,22日&9月3日*(全てステレオ) ※音源:SUPRAPHON SUAST-50743、SUAST-50603* ◎収録時間:76:16 |
| “真心から紡ぎ出されるタッチに宿る幽玄のニュアンス!!!” | ||
|
||
 TRE-174 |
チェコのピアニズム~フランティシェク・ラウフ[2]/ベートーヴェン&ショパン ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第12番* ショパン:ピアノ・ソナタ第2番「葬送」 ピアノ・ソナタ第3番ロ短調Op.58 |
フランティシェク・ラウフ(P) 録音:1965年11月15,18-19日*、1966年11月-12月(全てステレオ) ※音源:SUPRAPHON SUAST-50743*、SUAST-50893 ◎収録時間:70:13 |
| “ラウフの高貴で敬虔なピアニズムが十二分に生かされた不朽の名演!” | ||
|
||
 TRE-175 |
オーマンディ/米COLUMBIAモノラル名演集2~~「パリの喜び」 ワインベルガー:歌劇「バグパイプ吹きのシュヴァンダ」~ポルカとフーガ ビゼー:交響曲第1番ハ長調* オッフェンバック:バレエ音楽「パリの喜び」(ロザンタール編)# |
ユージン・オーマンディ(指) フィラデルフィアO 録音:1955年12月24日、1955年12月4日*、1954年5月9日#(全てモノラル) ※音源:米COLUMBIA ML-5289、英PHILIPS GBL-5505# ◎収録時間:73:22 |
| “音のお花畑!オーマンディの第一絶頂期を知る痛快名演集!” | ||
|
||
 TRE-176 |
若き日のオスカー・シュムスキー ヴィエニャフスキ:華麗なるポロネーズ第1番 ニ長調 Op. 4* シューベルト:華麗なるロンドOp.70** サン・サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ# ヴュータン:ヴァイオリン協奏曲第22番(ピアノ伴奏版)## モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」+ |
オスカー・シュムスキー(Vn) ピアニスト不明* レオニード・ハンブロ(P)** ミルトン・カティムズ(指)NBC響# ウラディミール・ソコロフ(P)## トーマス・シェルマン(指)小管弦楽協会O+ 録音:1940年8月15日*、1951年6月23日**、1950年4月22日#、1950年##、1956年頃+ (全てモノラル) ※音源:DISCOPEDIA MB-1040、Music Appreciation Records MAR-5613+ ◎収録時間:78:53 |
| “音楽を弄ばず、奉仕者に徹する信念が強固なニュアンスを形成!” | ||
|
||
 TRE-177 |
ロベール・カサドシュ/ベートーヴェン:「皇帝」他 ウェーバー:コンツェルトシュテュック ヘ短調 Op. 79 フランク:交響的変奏曲 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」* |
ロベール・カサドシュ(P) キリル・コンドラシン(指)トリノ放送SO ハンス・ロスバウト(指)アムステルダム・コンセルトヘボウO* 録音:1960年5月6日ライヴ、1961年2月3日* (全てステレオ) ※音源:伊FONIT CETRA LAR-18、独FONO-RING SFGLP-77699* ◎収録時間:66:12 |
| “本質追求ヘの強い意志を分かち合ったカサドシュとロスバウトの強力タッグ!” | ||
|
||
 TRE-178 |
フェレンチクのベートーヴェンVol.2 序曲「献堂式」Op.124* 交響曲第1番ハ長調Op.21 交響曲第8番ヘ長調Op.93 |
ヤーノシュ・フェレンチク(指) チェコPO*、ハンガリー国立O 録音:1961年1月5日*、1964年7月14-23日(全てステレオ) ※音源:SUPRAPHON SUAST-50025*、HUNGAROTON HLX-90002 ◎収録時間:65:28 |
| “音楽を決して淀ませない、フェレンチク流の指揮の極意!!” | ||
|
||
 TRE-179 |
ベラ・シキ/ショパン:スケルツォ&バラード スケルツォ第1番 ロ短調 Op. 20 スケルツォ第2番 変ロ短調 Op. 31 スケルツォ第3番 嬰ハ短調 Op. 39 スケルツォ第4番 ホ長調 Op. 54 バラード第1番 ト短調 Op. 23* バラード第2番 ヘ長調 Op. 38* バラード第3番 変イ長調 Op. 47* バラード第4番 ヘ短調 Op. 52* |
ベラ・シキ(P) 録音:1953年5月、1952年4月* ※音源:英PARLOPHONE PMA-1011、PMA-1008* ◎収録時間:73:50 |
| “明晰なタッチでショパンを哲学する、ベラ・シキ独自のピアニズム!” | ||
|
||
 TRE-180 |
スワロフスキー/チャイコフスキー&サン・サーンス チャイコフスキー:交響曲第3番「ポーランド」 サン・サーンス:交響曲第3番「オルガン付き」* |
ハンス・スワロフスキー(指) ウィーン国立歌劇場O フランツ・エイブナー(Org)* ※ウィーン楽友協会ホールのオルガンを使用 録音:1956年6月26-29日(ステレオ) ※音源:URANIA USD-1026、SAGA XID-5283* ◎収録時間:76:14 |
| “色彩の厚塗りを避け、スコアの筆致を信じた実直路線が結実!” | ||
|
||
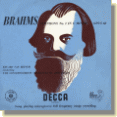 TRE-181 |
ベイヌム/メンデルスゾーン&ブラームス メンデルスゾーン:交響曲第4番「イタリア」 ブラームス:交響曲第1番ハ短調Op.68* |
エドゥアルト・ファン・ベイヌム(指) アムステルダム・コンセルトヘボウO 録音:1955年6月2-4日、1951年9月17日*(共にモノラル) ※音源:PHILIPS 6542-131、英DECC ACL-71* ◎収録時間:68:18 |
| “オケの技術力をそのまま音楽的ニュアンスに変換できるベイヌムの凄さ!” | ||
|
||
 TRE-182 |
ベートーヴェン:12のドイツ舞曲 WoO.8* ブルックナー:交響曲第3番[第3稿=1890年のシャルク改訂版] |
ワルター・ゲール(指) フランクフルトRSO* オランダPO 録音:1950年代中期頃*、1953年11月 原盤:Concert Hall MMS-2159*、CHS-1195 ◎収録時間:65:32 |
| “クナだけではない!説得力絶大な改訂版による「ブル3」” | ||
|
||
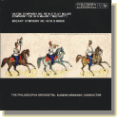 TRE-183 |
オーマンディ/米COLUMBIAモノラル名演集3~モーツァルト&ハイドン:交響曲集 モーツァルト:交響曲第40番ト短調 ハイドン:交響曲第99番* 交響曲第100番「軍隊」# |
ユージン・オーマンディ(指) フィラデルフィアO 録音:1956年1月10日、1954年4月15日*、1953年12月23日# ※音源:米COLUMBIA ML-5098、ML-5316*,# ◎収録時間:71:20 |
| “深刻な空気を持ち込まないオーマンディのピュアな作品掌握力!” | ||
|
||
 TRE-184 |
ラインスドルフ&ボストン響・厳選名演集Vol.2~~R.シュトラウス 歌劇「エジプトのヘレナ」第2幕~第二の新婚の夜 楽劇「サロメ」~サロメの踊り/間奏曲と終曲 交響詩「英雄の生涯」* |
レオンタイン プライス(S) ジョゼフ・シルヴァースタイン(ソロVn)* エーリヒ・ラインスドルフ(指) ボストンSO 録音:1965年4月22,24日、1963年3月9日* ※音源:英RCA SB-6639、日Victor SHP-2290* ◎収録時間:75:10 |
| “虚飾を排して訴えかけるR・シュトラウスの管弦楽法の魅力!” | ||
|
||
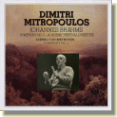 TRE-185 |
ミトロプーロス/ベートーヴェン&ブラームス ベートーヴェン:交響曲第1番ハ長調Op.21* ブラームス:大学祝典序曲 交響曲第3番ヘ長調Op.90 |
ディミトリ・ミトロプーロス(指)NYO 録音:1951年10月15日*、1958年2月9日(共にモノラル・ライヴ) ※音源: MELODRAM 233*、 FONITCETRA DOC-23 ◎収録時間:63:04 |
| “ミトロプーロスの危険な表現とソナタ形式との美しき融和!” | ||
|
||
 TRE-186 |
ドヴォルザーク:スラブ舞曲(全曲) | カレル・シェイナ(指)チェコPO 録音:1959年6月16-18日(ステレオ) ※音源:SUPRAPHON SV-8003-4 ◎収録時間:71:50 |
| “スラブ舞曲の魅力を味わい尽くすための究極名盤!” | ||
|
||
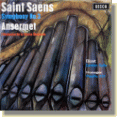 TRE-187 |
アンセルメ~オーディオ・ファイル名演集1 ビゼー:「カルメン」組曲[第1幕前奏曲/アラゴネーズ/間奏曲/アルカラの竜騎兵/密輸入者の行進/ハバネラ/衛兵の交代/ジプシーの踊り] オネゲル:機関車パシフィック231* サン・サーンス:交響曲第3番「オルガン」# |
エルネスト・アンセルメ(指)スイス・ロマンドO ピエール・スゴン(Org)# 録音:1958年4月1-23日&5月12-14日、1963年4月2-8日*、1962年5月3-5日&12-28日#(全てステレオ) ※音源:日KING SLC-1707、SLC-1702*,# ◎収録時間:67:33 |
| “アンセルメ芸術の粋を結集した厳選3曲!” | ||
|
||
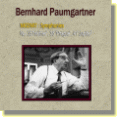 TRE-188 |
パウムガルトナー/モーツァルト:交響曲集 交響曲第35番[ハフナー」 交響曲第38番「プラハ」* 交響曲第41番「ジュピター」 |
ベルンハルト・パウムガルトナー(指) ザルツブルク・モーツァルテウム音楽院O 録音:1958年7月*(ステレオ) ※音源:独PARNASS61-415、61-413* ◎収録時間:79:47 |
| “モーツァルトに対する渾身の愛を温かな造形美に凝縮!” | ||
|
||
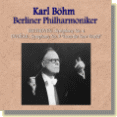 TRE-189 |
ベームのベートーヴェン&ドヴォルザーク ベートーヴェン:交響曲第4番 ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界から」* |
カール・ベーム(指)BPO 録音:1952年4月23日、1951年12月17日* ※音源:伊MOVIMENT MUSICA 08-001、01-024* ◎収録時間:79:40 |
| “作品に対するヴィジョンの違いが際立つ2つの名演!” | ||
|
||
 TRE-190(2CDR) |
イタリアQ/コンサート・ホールヘの全録音 ハイドン:弦楽四重奏曲第62番ハ長調 「皇帝」Op.76-33, Hob.III:77 弦楽四重奏曲第38番 変ホ長調「冗談」Op.33-2, Hob.III:38 シューベルト:弦楽四重奏曲第13番イ短調 「ロザムンデ」 Op.29-1/D. 804 * 弦楽四重奏曲第10番変ホ長調Op.125-1, D. 87* |
イタリアQ [パオロ・ボルチャーニ(Vn)、エリサ・ペグレッフィ(Vn)、ピエロ・ファルッリ(Va)、フランコ・ロッシ(Vc)] 録音:1965年(ステレオ) ※音源:瑞西Concert Hall SMS-2418、日Concert Hall SMS-2417* ◎収録時間:44:52+54:14 |
| “徹底した作曲家への献身によって引き出された作品の内省味!!” | ||
|
||
 TRE-191 |
ノエル・リー/ブラームス&バルトーク ブラームス:ワルツ集Op.39* バルトーク:3つの練習曲Op.18 Sz.72 戸外にて Sz.81/組曲Op.14 Sz.62 ピアノ・ソナタ Sz.80 |
ノエル・リー(P) 録音:1964年3月*、1966年頃 (共にステレオ) ※音源:仏Valois MB-986*、仏chaiers du disque JM-046 ◎収録時間:65:47 |
| “打楽器的アプローチだけでは気づかないバルトークのピアノ曲の本質!” | ||
|
||
 TRE-192 |
カイルベルト/R・シュトラウス:管弦楽曲集 「サロメ」~7つのヴェールの踊り 「インテルメッツオ」~4つの交響的間奏曲 「無口な女」~前奏曲(ポプリ) 交響詩「ドン・ファン」* 交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」* |
ヨーゼフ・カイルベルト(指) バイエルン国立歌劇場O、BPO* 録音:1963年、1961年*(全てステレオ) ※音源:英TELEFUNKEN SMA-106、独TELEFUNKEN SNA-25016 ◎収録時間:68:43 |
| “R・シュトラウスはこうでなければと思わせる無類の説得力!” | ||
|
||
 TRE-193 |
L.ルートヴィヒ/リスト&チャイコフスキー リスト:ハンガリー狂詩曲集より 第2番(ミュラー=ベルクハウス編)* 第4番(リスト&ドップラー編)* チャイコフスキー:「くるみ割り人形」組曲 イタリア奇想曲/スラブ行進曲 |
レオポルド・ルートヴィヒ(指) バイエルンRSO 録音:1966年頃*、1966年4月4-5日(全てステレオ) ※音源:英HMV SXLP-20094*、独ELECTROLA 03-29045 ◎収録時間:73:19 |
| “大衆迎合的な愉しさに傾かない豪然たる快演!” | ||
|
||
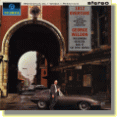 TRE-195 |
ジョージ・ウェルドン・コンサート (1)グリンカ:歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲* (2)バッハ(ウィルヘルミ編):G線上のアリア* (3)スメタナ:「売られた花嫁」~道化師の踊り* (4)ファリャ:火祭の踊り* (5)モーツァルト:歌劇「フィガロの結婚」序曲* (6)プロコフィエフ:「3つのオレンジへの恋」~行進曲* (7)ホルスト:組曲「惑星」~木星* (8)ドヴォルザーク:序曲「謝肉祭」 (9)メンデルスゾーン:「真夏の夜の夢」~スケルツォ (10)ヴェルディ:歌劇「椿姫」第1幕前奏曲 (11)チャイコフスキー:弦楽セレナード~ワルツ (12)チャイコフスキー:祝典序曲「1812年」# |
ジョージ・ウェルドン(指) フィルハーモニアO ロイヤル・マリーンズ・バンド# 録音:1961年5月30日(1)(3)、1961年5月31日(2)(4)-(7)、1963年4月11日(8)-(11)、1963年5月18,21日(12)、全てステレオ ※音源:COLUMBIA SCX-3446*、SCX-3499 ◎収録時間:71:08 |
| “誰にも負けぬ共感が聴き手に確かな味わいを約束!” | ||
|
||
 TRE-196 |
カンテッリのステレオ名盤集Vol.2 ブラームス:交響曲第3番 フランク:交響曲ニ短調* |
グィド・カンテッリ(指) フィルハーモニアO NBC響* 録音:1955年8月、1954年4月* ※音源:仏Trianon TRI-33200、英W.R.C SH376* ◎収録時間:70:08 |
| “テンポの変動を抑えて作品の本質を引き出すカンテッリの天才性!” | ||
|
||
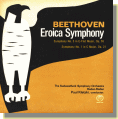 TRE-197 |
クレツキ&南西ドイツ放送響/ベートーヴェン 交響曲第1番ハ長調Op.21 交響曲第3番変ホ長調「英雄」* |
パウル・クレツキ(指) 南西ドイツRSO 録音:1962年(ステレオ) ※音源:瑞西Concert Hall SMSBE-2313(TU)、SMS-2275(TU)* ◎収録時間:75:46 |
| “ユダヤ的感性を隠すことなくベートーヴェンに対峙した確信的解釈!” | ||
|
||
 TRE-198 |
アラウ/ショパン:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲第1番ホ短調Op.11 ピアノ協奏曲第2番ヘ短調Op.21* |
クラウディオ・アラウ(P) オットー・クレンペラー(指)ケルンRSO マッシモ・プラデッラ(指)バイエルンRSO* 録音:1954年10月25日ケルン放送第1ホール、1960年4月12日ミュンヘン・ライヴ*(共にモノラル) ※音源:日KING SLF-5002、伊MOVIMENT MUSICA 01.064* ◎収録時間:73:08 |
| “甘美さ優先のショパンに満足しない方は必聴!” | ||
|
||
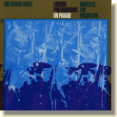 TRE-199 |
エードリアン・ボールト~オーケストラのための行進曲集 チャイコフスキー:スラヴ行進曲* アイアランド:エピック・マーチ** ロジャーズ:ガダルカナル・マーチ# コーツ:ダム・バスターズ スーザ:ワシントン・ポスト J.F.ワーグナー:双頭の鷲の旗の下に タイケ:旧友 トラディショナル(ロビンソン編):ブリティッシュ・グレナディアーズ(近衛歩兵大一連隊行進曲) トラディショナル(アルフォード編):リリーバレロ スーザ:星条旗よ永遠なれ アルフォード:ボギー大佐 スーザ:エル・カピタン H.W.デイヴィス:ロイヤル・エア・フォース・マーチ・パスト(イギリス空軍マーチ) ツィマーマン:錨を上げて スーザ:自由の鐘 ステッフェ:リパブリック賛歌 |
エードリアン・ボールト(指)LPO 録音:1967年8月、1967年1月*、1965年12月**、1967年7月# ※音源:World Record Club ST-750、Odessey 32.16.0238*、Lyrita SRCS.31** ◎収録時間:62:15 |
| “楽しさ無類!ボールト翁が最高にハジけた名行進曲集!” | ||
|
||
 TRE-200 |
ワルター厳選名演集Vol.2 ハイドン:交響曲第88番「V字」 シューベルト:交響曲第9番「グレート」* |
ブルーノ・ワルター(指) コロンビアSO 録音:1961年3月4,8日、1959年1月31日&2月2,4,6日*(共にステレオ) ※音源:日COLUMBIA OS-307、英CBS SRBG-72020* ◎収録時間:74:08 |
| “晩年のワルターの芸術性が奇跡的な次元にまで昇華した2大名演!” | ||
|
||
 TRE-201 |
アンセルメ~ベートーヴェン厳選名演集Vol.1 ベートーヴェン:「フィデリオ」序曲 交響曲第2番*/交響曲第7番 |
エルネスト・アンセルメ(指) スイス・ロマンドO 録音:1960年1月(ステレオ) ※音源:LONDON CS-6183*、DECCA SDD-102 ◎収録時間:78:33 |
| “知的制御よりも情念を優先させたアンセルメの例外的熱演!” | ||
|
||
 TRE-202 |
A.ローター/ベートーヴェン:交響曲集 グルック:「アウリスのイフィゲニア」序曲# ベートーヴェン:交響曲第1番* 交響曲第8番* フンパーディンク:「ヘンゼルとグレーテル」序曲** 「王子王女」序曲## |
アルトゥール・ローター(指) ベルリンSO* ベルリン国立歌劇場O 録音:1959年頃*、1956年10月10日#、1957年6月18日**、1957年6月24日## (全てステレオ) ※音源:独Opera ST-1911*、独TELEFUNKEN SLT-43011 ◎収録時間:75:29 |
| “世紀の名演「ベト8」に見るローターの飽くなき職人気質!” | ||
|
||
 TRE-203 |
ワルター~ハイドン/モーツァルト/ドヴォルザーク モーツァルト:フリーメーソンのための葬送音楽 ハイドン:交響曲第100番「軍隊」* ドヴォルザーク:交響曲第8番# |
ブルーノ・ワルター(指) コロンビアSO 録音:1961年3月8日、1961年3月2&4日*、1961年2月8&12日#(全てステレオ) ※音源:日SONY 20AC-1805、日COLUMBIA OS-307*、OS-718-C# ◎収録時間:69:13 |
| “老練の至芸に宿る、青年のような瑞々しい感性” | ||
|
||
 TRE-205 |
ラインスドルフ&ボストン響・厳選名演集Vol.3~シューマン.他 モーツァルト:アイネ・クライネ・ナハトムジーク* ベートーヴェン:序曲「レオノーレ」第3番 シューマン:交響曲第4番(マーラー編) |
エーリヒ・ラインスドルフ(指) ボストンSO 録音:1963年1月6日*、1963年1月5-6日(全てステレオ) ※音源:日VICTOR SHP-2307*、英RCA SB-6582 ◎収録時間:63:04 |
| “ラインスドルフの驚異の耳が制御する作品のあるべき姿!” | ||
|
||
 TRE-206 |
フレッチャ~海&幻想交響曲 ドビュッシー:交響詩「海」 ベルリオーズ:幻想交響曲* |
マッシモ・フレッチャ(指) ローマPO、ロイヤルPO* 録音:1959年頃、1962年2月21-22日*(共にステレオ) ※音源:米Reader's Digest RD4-68-7、米CHRSKY_CR-1* ◎収録時間:69:34 |
| “作品を歪めずに自己表現の限りを尽くすフレッチャの芸術家魂!” | ||
|
||
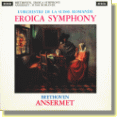 TRE-207 |
アンセルメ~ベートーヴェン厳選名演集Vol.2 ベートーヴェン:序曲「レオノーレ」第2番 交響曲第3番「英雄」* |
エルネスト・アンセルメ(指) スイス・ロマンドO 録音:1960年1月4-17日、1960年4月5-11日*(全てステレオ) ※音源:米LONDON_CS-6184、英DECCA SDD-103* ◎収録時間:62:07 |
| “理性よりも衝動!全身全霊でベートーヴェンの声を代弁!! | ||
|
||
 TRE-208 |
超厳選!赤盤名演集Vol.1 ブルックナー:交響曲第8番 |
カール・シューリヒト(指)VPO 録音:1963年12月(ステレオ) ※音源:TOSHIBA AA-7191-92 ◎収録時間:70:48 |
| “芸の極地を極めた人間の手になる壮大なる工芸品!!” | ||
|
||
 TRE-209 |
クリップス~ベートーヴェン&ブラームス ベートーヴェン:「フィデリオ」序曲 「エグモント」序曲 序曲「献堂式」 ブラームス:交響曲第1番* |
ヨーゼフ・クリップス(指) ウィーン音楽祭O 録音:1962年6月4-5日(ステレオ) ※音源:日Consert Hall SMS-2274、瑞西Consert Hall SMS-2268* ◎収録時間:73:33 |
| “味わい充満!クリップスの意思とオケの意欲が完全調和!” | ||
|
||
 TRE-210 |
バッカウアー/展覧会の絵、ペトルーシュカ他 ムソルグスキー:展覧会の絵* リスト:ハンガリー狂詩曲第12番** ブラームス:パガニーニの主題による変奏曲第2巻Op.35# ストラヴィンスキー:「ペトルーシュカ」からの3章## ショパン(ブゾーニ編):ポロネーズ第6番「英雄」+ |
ジーナ・バッカウアー(P) 録音:1956年6月6-7日*、1963年2月26日**、1963年2月20日#、1963年2月26-27日##、1963年2月25日+(全てステレオ) ※音源:英EMI SXLP-30233*、米MERCURY SR-90349 ◎収録時間:71:25 |
| “強引さ皆無! ロマン溢れる風格美で聴き手を牽引する究極芸!” | ||
|
||
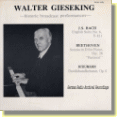 TRE-211 |
ギーゼキング/バッハ~シューマン バッハ:イギリス組曲第6番BWV.811 ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第15番「田園」* シューマン:ダヴィッド同盟舞曲集Op.6# |
ワルター・ギーゼキング(P) 録音:1945年1月23放送録音(ドイツ・ザールブリュッケン)、1949年6月(ドイツ・ザールブリュッケン)*、1947年9月13日放送録音(ドイツ・フランクフルト)# ※音源:米B.W.S_IGI-380、英SAGA_XID-5148# ◎収録時間:73:21 |
| “新即物主義の枠に収まらない閃きとロマン!” | ||
|
||
 TRE-212 |
オーマンディ/米COLUMBIAモノラル名演集4~「白鳥の湖」他 プロコフィエフ:古典交響曲 チャイコフスキー:幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」* バレエ音楽「白鳥の湖」(抜粋)# |
ユージン・オーマンディ(指) フィラデルフィアO 録音:1955年12月18日、1955年1月9日*、1956年19月17日#(全てモノラル) ※音源:米COLUMBIA_ML-5289、英PHILIPS ABL-3228*、米COLUMBIA ML-5201# ◎収録時間:79:42 |
| “1950年代のオーマンディを象徴する色彩とリズムと品格!” | ||
|
||
 TRE-213 |
ラインスドルフ&ボストン響・厳選名演集Vol.4~モーツァルト:交響曲集 交響曲第36番「リンツ」 交響曲第41番「ジュピター」* |
エーリヒ・ラインスドルフ(指) ボストンSO 録音:1967年12月22日、1963年1月6日*(ステレオ) ※音源:英RCA CCV-5050、日VICTOR SHP-2307* ◎収録時間:73:33 |
| “音楽における「豊かさ」とは何か?その答えがここに!” | ||
|
||
 TRE-214 |
バルサム~モーツァルト&ベートーヴェン モーツァルト:ピアノ協奏曲第5番ニ長調K.175* ベートーヴェン:ピアノ協奏曲ニ長調Op.61(原曲:ヴァイオリン協奏曲) |
アルトゥール・バルサム(P) ブロニスラフ・ギンペル(指)交響楽団* クレメンス・ダヒンデン(指)ヴィンタートゥールSO 録音:1951年*、1950年代初頭 ※音源:英NIXA PLP-229*、仏Guilde Internationale Du Disque MMS-3002 ◎収録時間:65:09 |
| “没入しないのに芯は熱い!2つのニ長調の名曲で見せるバルサムの凄い感性!” | ||
|
||
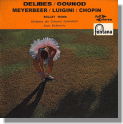 TRE-215(2CDR) |
エチェベリーのバレエ音楽集 ドリーブ:バレエ組曲「シルヴィア」 [前奏曲と狩りの女達/間奏曲と緩やかなワルツ/ピチカーティ/酒神のコルテーズジュ] バレエ組曲「コッペリア」[間奏曲/ワルツ/チャールダーシュ/ハンガリー舞曲/自動人形のワルツ/スラブ主題の変奏] グノー:歌劇「ファウスト」のバレエ音楽 マイヤベーア:歌劇「預言者」~バレエ組曲「スケートをする人々」]* ルイジーニ:バレエ組曲「エジプト舞曲」* ショパン(ダグラス編):レ・シルフィード* |
イェシュス・エチェベリー(指) コンセール・ラムルーO 録音:1958年5月23-24日&6月10-12日(全てステレオ) ※音源:日VICTOR SFON-7506、SFON-7526* ◎収録時間:104:27 |
| “最高の名演奏で堪能するルイジーニ唯一の名曲!” | ||
|
||
 TRE-217(2CDR) |
ノエル・リー~ラヴェル:ピアノ曲選集 鏡/高雅で感傷的なワルツ ソナチネ/夜のガスパール* 亡き王女のためのパヴァーヌ* 水の戯れ*/クープランの墓* |
ノエル・リー(P) ※使用ピアノ:ホルヌンク&メラー(デンマーク) 録音:1966年9月、1967年6月* コペンハーゲン(全てステレオ) ※音源:仏Valois MB-791、MB-792* ◎収録時間:106:40 |
| “ミラクルなタッチで浮かび上がるラヴェル作品の色彩の深部!” | ||
|
||
 TRE-218(2CDR) |
クルト・レーデルのバッハ バッハ:ブランデンブルク協奏曲BWV1046-1051(全6曲) |
クルト・レーデル ミュンヘン・プロ・アルテ室内O ラインホルト・バルヒェット(Vn) ピエール・ピエルロ、レオンハルト・ザイフェルト、ヴィルヘルム・グリム(Ob) クルト・リヒター、ヴィ・ベック(Hrn) カール・コルビンガー(Fg) モーリス・アンドレ(Tp) クルト・レーデル、パウル・マイゼン(Fl) ロベール・ヴェイロン=ラクロワ(クラヴサン) ゲオルク・シュミット、フランツ・ツェッスル(Va) イルミンギルト・ゼーマン、ロルフ・アレクザンダー(gmb) ヴィルヘルム・シュネッラー(Vc) ゲオルク・フェルトナーゲル(Cb) 録音:1962年5月1-6日(ステレオ) ※音源:日COLUMBIA OS-472、OS-473 ◎収録時間:101:20 |
| “親和的なアンサンブルから浮かび上がるバッハの温もり!” | ||
|
||
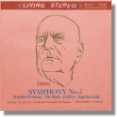 TRE-219 |
A・ギブソン~若き日のシベリウス録音 「カレリア」序曲/交響詩「吟遊詩人」 組曲「歴史的情景」~「祭り」 カレリア組曲* 交響曲第5番変ホ長調Op.82* |
アレクサンダー・ギブソン(指) スコティッシュ・ナショナルO、LSO* 録音:1966年頃、1959年2月9-10日*(全てステレオ) ※音源:英HMV:HQS-1070、英RCA VICS-1016* ◎収録時間:66:00 |
| “自然体の音作りに孕む瑞々しい感性と熱情!” | ||
|
||
 TRE-221 |
A・ギブソン~シベリウス&ドヴォルザーク シベリウス:組曲「クリスティアン2世」 ドヴォルザーク:序曲「謝肉祭」* 交響曲第9番「新世界より」* |
アレクサンダー・ギブソン(指) スコティッシュ・ナショナルO、LPO* 録音:1966年頃、1967年1月27-28日* ※音源:英HMV HQS-1070、World Record Club ST-650* ◎収録時間:72:32 |
| “「ケレン味のなさ」が凡庸と同義ではないことを実証する恰好の名演!” | ||
|
||
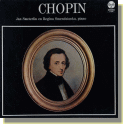 TRE-222(2CDR) |
スメンジャンカ&スメテルリン~ショパン名曲集 ■レギーナ・スメンジャンカ 夜想曲ヘ短調Op.55-1 マズルカ第15番ハ長調Op.24-2 マズルカ第46番ハ長調Op.68-1 マズルカ第42番ト長調Op.67-1 幻想即興曲Op.66 即興曲第1番変イ長調Op.29 練習曲変ト長調Op.10-5 「黒鍵」 夜想曲第9番ロ長調op.32-1 夜想曲第2番変ホ長調op.9-2 夜想曲第10番変イ長調op.32-2 マズルカ.第3番ホ長調Op.6-3 練習曲ホ長調Op.10-3「別れの曲」 ■ヤン・スメテルリン マズルカ第20番変ニ長調Op.30-3 ワルツ第3番イ短調Op.34-2 マズルカ第25番ロ短調Op.33-4 マズルカ第17番変ロ短調Op.24-4 マズルカ第5番変ロ長調Op.7-1 ワルツ第1番変ホ長調Op.18「華麗なる大円舞曲」 ワルツ第6番変ニ長調Op.64-1「小犬のワルツ」 マズルカ第37番変イ長調Op.59-2 ワルツ第5番変イ長調Op.42-5 ワルツ第8番変イ長調Op.64-3 マズルカ第13番イ短調Op.17-4 マズルカ第42番ト長調Op.67-1 マズルカ第15番ハ長調Op.24-2 マズルカ第38番嬰ヘ短調Op.59-3 ワルツ第4番ヘ長調Op.34-3 |
レギーナ・スメンジャンカ(P) ヤン・スメテルリン(P) 録音:全て1960年代初頭(?)。スメテルリンはステレオ。 ※音源:蘭CNR FL-016-017 ◎収録時間:92:28 |
| “気品のスメンジャンカと、幸せオーラのスメテルリン!!” | ||
|
||
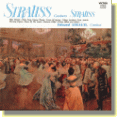 TRE-223(2CDR) |
エドゥアルト・シュトラウスⅡ世/ヨハン&ヨーゼフ・シュトラウスの音楽 ヨーゼフ・シュトラウス:鍛冶屋のポルカ J・シュトラウス:喜歌劇「千一夜物語」間奏曲* ワルツ「ウィーンのボンボン」*/加速度円舞曲* ワルツ「南国のバラ」/ワルツ「ウィーン気質」 ポルカ「ハンガリー万歳」*/常動曲 ヨハン&ヨーゼフ・シュトラウス:ピチカート・ポルカ J・シュトラウス:ワルツ「酒・女・歌」* ヨーゼフ・シュトラウス:ポルカ「風車」 J・シュトラウス:ワルツ「美しく青きドナウ」# ワルツ「春の声」#/「ジプシー男爵」行進曲* ヨーゼフ・シュトラウス:ポルカ「憂いもなく」* J・シュトラウス:ワルツ「ウィーンの森の物語」 ヨーゼフ・シュトラウス:ワルツ「オーストリアの村燕」 J・シュトラウス:ワルツ「朝の新聞」* 喜歌劇「ウィーンのカリオストロ」序曲* ヨーゼフ・シュトラウス:ポルカ「騎手」* J・シュトラウス:皇帝円舞曲# トリッチ・トラッチ・ポルカ ワルツ「芸術家の生涯」 ヨーゼフ・シュトラウス:ポルカ「女心」 ワルツ「わが人生は愛と喜び」 |
エドゥアルト・シュトラウスⅡ世(指) インスブルックSO シュトゥットガルトPO* ウィーン国立歌劇場O# 録音:1960年代初頭(全てステレオ) ※音源:日VICTOR SWK-7501-3 ◎収録時間:156:12 |
| “近年のウィーン・フィルが置き去りにしてきたウィンナ・ワルツの本当の息吹!” | ||
|
||
 TRE-224(2CDR) |
レーヴェングートSQ~フランスの弦楽四重奏曲集 ■Disc1 フォーレ:弦楽四重奏曲Op.121 ルーセル:弦楽四重奏曲 ドビュッシー:弦楽四重奏曲 ■Disc2 フランク:弦楽四重奏曲 ラヴェル:弦楽四重奏曲 |
レーヴェングートSQ 【アルフレッド・レーヴェングート(1Vn)、ジャック・ゴトコフスキー(2Vn)、ロジェ・ローシュ(Va)、ロジェ・レーヴェングート(Vc)】 録音:1965年(ステレオ) ※音源:VOX SVBX-570 ◎収録時間:147:33 |
| “むせ返るほどの芳醇な香りを湛えたレーヴェングートQの至宝!” | ||
|
||
 TRE-225(2CDR) |
超厳選!赤盤名演集Vol.2 クリュイタンス/ラヴェル:管弦楽曲集 (1)ボレロ*/(2)スペイン狂詩曲* (3)ラ・ヴァルス*/(4)マ・メール・ロワ# (5)クープランの墓/(6)古風なメヌエット (7)道化師の朝の歌/(8)海原の小舟 (9)亡き王女の為のパヴァーヌ、 (10)高雅で感傷的なワルツ# |
アンドレ・クリュイタンス(指) パリ音楽院O 録音:1961年11月30日(1)、1961年11月29日(2)、1961年11月27日(3)、1962年4月20&25日(4)、1963年9月26,27日&10月2,3日(5)、1962年10月2日(6)、1962年9月26日(7)、1962年9月27日(8)、1962年10月3日(9)、1964年4月19日(10) ※音源:東芝 AA-9006*、AA-9007#、AA-7281 ◎収録時間:133:33 |
| “色彩の魅力を引き出すためのテンポ設定の妙に改めて覚醒!” | ||
|
||
 TRE-227 |
カイルベルト~J・シュトラウス&R・シュトラウス J・シュトラウス:ポルカ「浮気心」 加速度円舞曲/エジプト行進曲 ワルツ「ウィーン気質」 トリッチ・トラッチ・ポルカ* ワルツ「南国のバラ」*/アンネン・ポルカ ペルシャ行進曲**/常動曲 R.シュトラウス:歌劇「ばらの騎士」より ワルツ第1番#&第2番# |
ヨゼフ・カイルベルト(指) バンベルクSO、 バイエルン国立歌劇場O# 録音:1960年7月11-12日、1959年7月24-25日*、1959年7月25日**、1963年8月5-8日#(全てステレオ) ※音源:独TELEFUNKEN NT-110、英TELEFUNKEN SMA-106# ◎収録時間:63:37 |
| "演出無用!オケとのコンビネーションがそのままニュアンス化したシュトラウス!!" | ||
|
||
 TRE-228 |
ブライロフスキー/ショパン&サン・サーンス:ピアノ協奏曲、他 リスト:メフィスト・ワルツ第1番 愛の夢第3番 2つの演奏会用練習曲~小人の踊り サン・サーンス:ピアノ協奏曲第4番* ショパン:ピアノ協奏曲第2番# |
アレクサンダー・ブライロフスキー(P) シャルル・ミュンシュ(指)ボストンSO 録音:1953年4月18日、1954年11月24日*、1954年11月29日# ※音源:HMV ALP-1110、米RCA LM-1871*,# ◎収録時間:71:56 |
| “華麗な技巧だけで煽らないインスピレーション優先の芸の極み!” | ||
|
||
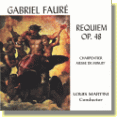 TRE-229 |
ルイ・マルティーニ/シャルパンティエ&フォーレ シャルパンティエ:真夜中のミサ曲* フォーレ:レクイエム |
マルタ・アンジェリシ(S)*、エディト・セリ(S)*、アンドレ・ムーラン(C.T)*、T:ジャン=ジャック・ルジュール(T)*、ジョルジュ・アプドン(Bs)*、ジョスリー・シャモナン(S)、ジョルジュ・アブドアン(Bs) アンヌ=マリー・ベッケンシュタイナー(Org)*、モーリス・デュリュフレ(Org)*-[1][2]、マリー=クレール・アラン(Org)、オリヴィエ・アラン(Org) フランス音楽青少年cho パイヤールO* コンセール・コロンヌO ルイ・マルティーニ(指) 録音:1961年3月8-10日ノートルダム・デュ・リバン教会(パリ)*、1963年11月22日サン・ロック教会(パリ) 全てステレオ ※音源:日COLUMBIA OS-939-R*、VOX STPL-512.720 ◎収録時間:75:34 |
| “「心の故郷」と呼びたいほどの真の安らぎがここに!” | ||
|
||
 TRT-231 |
オーマンディ/米COLUMBIAモノラル名演集5~「英雄の生涯」他 チャイコフスキー:幻想序曲「ロメオとジュリエット」 R・シュトラウス:交響詩「英雄の生涯」* |
ユージン・オーマンディ(指) フィラデルフィアO ジェイコブ・クラチマルニック(ソロVn)* 録音:1953年12月23日、1954年3月14日* ※音源:英PHILIPS ABL-3228、米COLUMBIA ML-4887* ◎収録時間:63:59 |
| “美くしさと迫力を兼ね備えたオーマンディの音作りの凄さ!” | ||
|
||
 TRE-232 |
超厳選!赤盤名演集Vol.3~フランソワ絶頂期のショパン 即興曲集(全4曲)* 練習曲集Op.10/練習曲集Op.25 |
サンソン・フランソワ(P) 録音:1957年11月*、1958年9-10月&1959年2月(全てモノラル) ※音源:TOSHIBA CA-1015*、CA-1016 ◎収録時間:77:58 |
| “技巧を目的ではなく手段として使い切った閃き芸の極北!” | ||
|
||
 TRE-233 |
ヘブラー&ホルライザー/モーツァルト:ピアノ協奏曲集Vol.1 ピアノ協奏曲第8番ハ長調 K. 246 ピアノ協奏曲第15番変ロ長調 K. 450* ピアノ協奏曲第18番変ロ長調 K. 456# |
イングリット・ヘブラー(P) ハインリヒ・ホルライザー(指) ウィーン・プロ・ムジカSO(ウィーンSO) 録音:1955年4月28.30日、1953年*,#(全てモノラル) ※音源:英VOX PL-9290、 PL-8300*,# ◎収録時間:76:48 |
| “「ヘブラーのモーツァルトは甘ったるい」というのは明らかに誤解です!” | ||
|
||
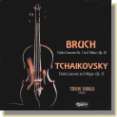 TRE-234 |
ヴァルガ~ブルッフ&チャイコフスキー チャイコフスキー:「懐かしい土地の思い出」Op.42~瞑想曲(グラズノフ編)* ヴァイオリン協奏曲 ニ長調Op.35 ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番Op.26# |
ティボール・ヴァルガ(Vn) ジャン=マリー・オーバーソン(指) ボリス・マーソン(指)* ウィーン祝祭O 録音:1965年(ステレオ) ※音源:Comcert Hall SMS-24110、SMS-2587(TU)# ◎収録時間:74:10 |
| “潔癖かつ鉄壁!造形美への並々ならぬ執着がもたらす凛然たるニュアンス!” | ||
|
||
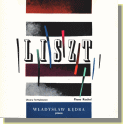 TRE-236 |
ケンドラ~MUZA録音集(リスト&ショパン) ショパン:演奏会用ロンド「クラコヴィアク」Op.14* リスト:ハンガリー狂詩曲第2番 コンソレーション第3番 パガニーニ大練習曲~ラ・カンパネッラ ハンガリー狂詩曲第6番 演奏会用パラフレーズ『リゴレット』 愛の夢第3番/メフィスト・ワルツ第1番 巡礼の年第2年イタリア~ペトラルカのソネット第123番/第104番# 忘れられたワルツ第1番# |
ヴァディスワフ・ケンドラ(P) ヴィトルド・ロヴィツキ(指)* ワルシャワ国立PO* 録音:1960年6月28-29日*、1962年6月18-22日、1965年3月15-18,22日ベルリン、キリスト教会#(全てステレオ) ※音源:MUZA SX-0067*、MUZA SXL-0162、ETERNA 825-554# ◎収録時間:75:34 |
| “ポーランドの名手、ケンドラが繰り広げるコクと香りを込めたリスト!!” | ||
|
||
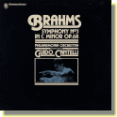 TRT-237 |
カンテルリ~シューマン&ブラームス シューマン:交響曲第4番 ブラームス:交響曲第1番* |
グィド・カンテルリ(指) フィルハーモニアO 録音:1953年5月5月15&21日、1953年5月21-23日* (共にモノラル) ※音源:仏EMI 2905761、W.R.C SH-314* ◎収録時間:68:48 |
| “厳つい鎧を剥ぎ取り、音楽の実像を清らかな感性で刷新!” | ||
|
||
 TRE-238 |
チェコのピアニズム~ジョセフ・ブルヴァ・1 リスト:パガニーニによる大練習曲 S.141* ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第13番Op.27-1 ピアノ・ソナタ24番「テレーゼ」 ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイン」 |
ジョセフ・ブルヴァ(P) 録音:1966年5月23-27,31日*、1967年7月10-14,17日 ※音源:SUPRAPHON SUAST-50891*、SUAST-50929 ◎収録時間:70:29 |
| “音に対するイメージ具現化のために全てをやり尽くす芸術家魂! | ||
|
||
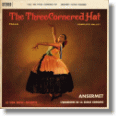 TRE-239 |
アンセルメ~オーディオ・ファイル名演集2~ファリャ&アルベニス アルベニス(アルボス編):組曲「イベリア」* ファリャ:「はかなき人生」~間奏曲/スペイン舞曲 バレエ音楽「三角帽子」# |
エルネスト・アンセルメ(指) スイス・ロマンドO テレサ・ベルガンサ(Ms)# 録音:1960年5月5-20日*、1961年2月12&17日(全てステレオ) ※音源:LONDON CS-6194*、日KING SL-1138 ◎収録時間:79:05 |
| “明晰さを共有するアンセルメとデッカ録音の強力合体が織りなす色彩と迫力!” | ||
|
||
 TRE-240 |
ヘブラー/シューベルト:ピアノ曲集 16のドイツ舞曲D.783 楽興の時D.780 ピアノ・ソナタ第21番D.960* |
イングリット・ヘブラー(P) 録音:1960年4月、1967年10月22-27日*(全てステレオ) ※音源:日Victor SFL-7992、蘭PHILIPS 839700LY* ◎収録時間:73:00 |
| “「いかにも名演」とは一線を画すヘブラーが目指した無垢なシューベルト!” | ||
|
||
| ベートーヴェン没後250年記念復刻 | ||
 TRE-241 |
ベートーヴェン:交響曲第1番ハ長調Op.21 シューベルト:交響曲第9番「グレート」* |
アルトゥール・ローター(指) BPO、ベルリンRSO* 録音:1951年12月6日ティタニア・パラスト、1950年代中期?(共にモノラル) ※音源:Club Mondial Du Disque CMD-A302、URANIA URLP-7152* ◎収録時間:71:04 |
| “BPOの一時代を支えたローターの恐るべき洞察力!” | ||
|
||
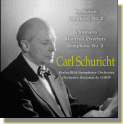 TRE-242 |
ベートーヴェン:交響曲第2番 シューマン:「マンフレッド」序曲* 交響曲第2番ハ長調Op.61# |
カール・シューリヒト(指) ベルリンRIAS響、 フランス国立放送O*,# 録音:1953年11月19日ベルリン、1963年5月14日シャンゼリゼ劇場(ライヴ)*、1955年9月(モントルー音楽祭ライヴ)# ※音源:MOVIMENT MUSICA 08-001、ERATO ERL-16009*,# ◎収録時間:78:58 |
| “モーツァルト寄りの解釈でじっくり紡ぎ出すベートーヴェン!” | ||
|
||
 TRE-243 |
超厳選!赤盤名演集Vol.4~フルトヴェングラーの「エロイカ」 ワーグナー:歌劇「ローエングリン」第1幕前奏曲* リスト:交響詩「前奏曲」# ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」 |
ウィルヘルム・フルトヴェングラー(指) VPO 録音:1954年3月4日*、1954年3月3日#、1952年11月26,27日ウィーン・ムジークフェラインザール(全てモノラル) ※音源:日TOSHIBA HA-50609*,#、AB-7081 ◎収録時間:77:10 |
| “歴史的名演の真価を最大限まで堪能できる理想の復刻!” | ||
|
||
 TRE-244 |
ハイドン:交響曲第22番変ホ長調 「哲学者」 Hob.I:22
交響曲第90番ハ長調 Hob.I:90 ベートーヴェン:交響曲第4番* |
エルネスト・アンセルメ(指) スイス・ロマンドO 録音:1965年10月、1958年11月* ※音源:LONDON CS-6481、豪DECCA SDDA-104* ◎収録時間:79:18 |
| “作品への誠実な愛を成就すべくクールな姿勢を堅持” | ||
|
||
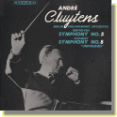 TRE-245 |
超厳選!赤盤名演集Vol.5~クリュイタンスの「運命」&「未完成」 ベートーヴェン:序曲「レオノーレ」第3番 シューベルト:交響曲第8番「未完成」* ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」# |
アンドレ・クリュイタンス(指)BPO 録音:1958年3月10&13日、1960年11月* 、1958年3月10-11&13日# ベルリン・グリューネヴァルト教会 (全てステレオ) ※音源:日TOSHIBA AA-7025、AA-7040*,# ◎収録時間:73:42 |
| “古き佳きBPOの響きを更に美しくブレンドした味わい深いベートーヴェン!!” | ||
|
||
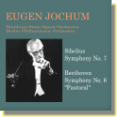 TRE-246 |
ヨッフムのベートーヴェン&シベリウス シベリウス:交響曲第7番 ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」* |
オイゲン・ヨッフム(指) ハンブルク国立歌劇場O、BPO* 録音:1943年(ライヴ?)、1951年3月19日RIASスタジオ* ※音源:Melodiya M10-46747-009、MOVIMENT MUSICA 08-001* ◎収録時間:63:41 |
| “フルトヴェングラーへの尊敬と独自のこだわりを完全一体化した異色の「田園」!” | ||
|
||
 TRE-247 |
カラヤン&VPO/デッカ録音名演集Vol.1 ベートーヴェン:交響曲第7番* J・シュトラウス:「こうもり」序曲 アンネン・ポルカ ヨーゼフ・シュトラウス:ワルツ「うわごと」 J・シュトラウス:「ジプシー男爵」序曲 ポルカ「狩り」 ワルツ「ウィーンの森の物語」 |
ヘルベルト・フォン・カラヤン(指) VPO 録音:1959年3月9 - 10日*、1959年4月7-8日(全てステレオ) ※音源:独RCA SMR-8010*、SMR-8012 ◎収録時間:77:36 |
| “作品の生命感とカラヤンの美学がバランスよく共存した名演!” | ||
|
||
 TRE-248 |
メンデルスゾーン:序曲「静かな海と楽しい航海」* 序曲「フィンガルの洞窟」* ベートーヴェン:「エグモント」序曲** 「アテネの廃墟」序曲#/トルコ行進曲# 交響曲第8番ヘ長調 Op. 93+ |
ヨーゼフ・カイルベルト(指) BPO*,**、ハンブルク国立PO#.+ 録音:1962年2月9日*、1960年4月11日-5月1日**、1960年4月26日#、1958年2月6-10日+(全てステレオ) ※音源:独TELEFUNKEN SNA-25016*、NT-361#、SNA-25016-T-2**,+ ◎収録時間:64:12 |
| “これぞ「ベト8」演奏史上に輝く偉大なスタンダード解釈!” | ||
|
||
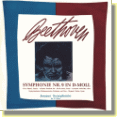 TRE-249(2CDR) |
ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱つき」* フリードリヒ・ヴィット (1770-1836):イエナ交響曲.ハ長調 |
コリー・ベイステル(S) エリザベス・プリッチャード(C.A) デイヴィッド・ガレン(T) レオナルド・ヴォロフスキ(Bs) ワルター・ゲール(指) オランダPO&cho 録音:1955年*、1952年(共にモノラル) ※音源:Musical Masterpiece Society MMS-2034*、 MMS-2034F ◎収録時間:67:11*+21:18 |
| “伝統的な演奏スタイルを洗い流すことで顕在化した希望の光!” | ||
|
||
 TRE-250 |
ホーレンシュタインの「新世界」 コルンゴルト:歌劇「ヴィオランタ」前奏曲と謝肉祭* ワーグナー:「さまよえるオランダ人」序曲+ 「タンホイザー」~ヴェーヌスベルクの音楽# ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」## |
ヤッシャ・ホーレンシュタイン(指) ロイヤルPO ビーチャム・コラール・ソサエティ** 録音:1965年5月28日&6月2日*、1962年9月30日+,#、1962年1月26&30日##(全てステレオ) ※音源:Quintessence PMC-7047*,+、日Victor GMS-6#、Quintessence PMC-7001## ◎収録時間:73:27 |
| “ビーチャムのオケが豹変!郷愁よりも苦悩が滲む異色の「新世界」!” | ||
|
||
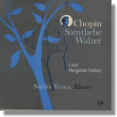 TRT-251 |
ソンドラ・ビアンカ~ショパン&リスト リスト:ハンガリー幻想曲* ショパン:ワルツ集(14曲)【第.2,3,8,6,9,7,11,1,4,10,13,14,12,5番】 |
ソンドラ・ビアンカ(P) カール・バンベルガー(指)北ドイツSO* 録音:1950年代中期?(モノラル) ※音源:Musical Masterpiece Society MMS-166*、MMS-2131 ◎収録時間:61:56 |
| “ワルツ各曲の個性を絞り出した、ソンドラ・ビアンカの筆頭名盤!” | ||
|
||
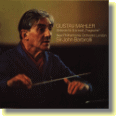 TRE-252(2CDR) |
マーラー:交響曲第6番「悲劇的」 | ジョン・バルビローリ(指) ニュー・フィルハーモニアO 録音:1967年8月17-19日 ※音源:独ELECTROLA 1C161-01.285 ◎収録時間:83:34 |
| “バルビローリの南欧的感覚によって作品が壮大な愛の讃歌に変貌! | ||
|
||
 TRE-253 |
ペナリオのドビュッシー ドビュッシー:前奏曲集(全2巻) |
レナード・ペナリオ(P) 録音:1965年3月15,16,26日(ステレオ) ※音源:日Victor SHP-2495-2496(2LP) ◎収録時間:71:48 |
| “過度な緊張から開放したカラフルな前奏曲集!” | ||
|
||
 TRE-254 |
アルベール・ヴォルフ~1960年代の貴重ライヴ! (1)ベルリオーズ:序曲「海賊」*、 (2)ベルリオーズ:序曲「ローマの謝肉祭」* (3)ベルリオーズ:「ベンベヌート・チュエルリーニ」序曲 (4)オネゲル:交響詩「夏の牧歌」 (5)フランク:交響曲ニ短調 |
アルベール・ヴォルフ(指) パリ音楽院O*、デンマークRSO 録音:(1)(2)1955年6月20-22日 (3)1962年3月15日ライヴ (4)1962年3月1日ライヴ (5)1965年1月28日ライヴ、全てモノラル ※音源:(1)(2)LONDON LL-1297、(3)-(5)ARTE SYMFONIA ARTE-SYMFONIA-003 ◎収録時間:76:58 |
| “アルベール・ヴォルフの知られざる晩年の完熟至芸!” | ||
|
||
 TRE-255 |
モイセイヴィチの十八番協奏曲集 ディーリアス:ピアノ協奏曲 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番「皇帝」* |
ベンノ・モイセイヴィチ(P) マルコム・サージェント(指)BBC響 録音:1955年9月13日プロムス(モノラル・ライヴ)、1963年3月6日ロイヤル・フェスティヴァル・ホール(モノラル・ライヴ)* ※音源:米Discocorp BWS-725 ◎収録時間:56:09 |
| “死の影なし!溢れる生命力を惜しげもなく放射した輝かしい「皇帝」!” | ||
|
||
 TRE-257 |
ノーマン・デロ=ジョイオ(1913-2008):ピアノと管弦楽のための幻想曲と変奏曲* プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第5番ト長調 Op.55# ラヴェル:ピアノ協奏曲ト長調 M.83 |
ロリン・ホランダー(P) エーリヒ・ラインスドルフ(指)ボストSO 録音:1963年2月17日(世界初録音)*、1964年3月28日#、1963年1月16日、ボストン、シンフォニー・ホール(全てステレオ) ※音源:米RCA_LSC-2667、日VICTOR_SHP-2370# ◎収録時間:65:55 |
| “洗練を極めたタッチから紡ぎ出される作品の本質!” | ||
|
||
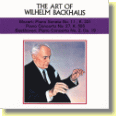 TRE-258 |
バックハウス~珠玉の協奏曲 モーツァルト:ピアノ・ソナタ第11番「トルコ行進曲付き」 ピアノ協奏曲第27番変ロ長調Op.83* ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第2番# |
ウィルヘルム・バックハウス(P) カール・ベーム(指)VPO* ハンス・シュミット=イッセルシュテット(指)VPO# 録音:1955年5月-6月、1955年5月*、1959年6月29-30日#(全てステレオ) ※音源:日KING_SL-1029、SLC-1620# ◎収録時間:71:19 |
| “バックハウスによる協奏曲の二大筆頭名演!” | ||
|
||
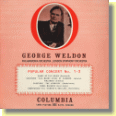 TRE-259(2CDR) |
ウェルドンの「ポピュラー・コンサート」 ■Disc1 (1)ポンキェルリ:時の踊り# (2)ニコライ:「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲# (3)シベリウス:交響詩「フィンランディア」# (4)メンデルスゾーン:序曲「フィンガルの洞窟」# (5)サン・サーンス:交響詩「死の舞踏」# (6)サン・サーンス:「サムソンとデリラ」~バッカナール# (7)ヘンデル(エルガー編):序曲ニ短調* (8)バッハ(ウィルヘルミ編):G線上のアリア* (9)バッハ(ヘンリー・ウッド編):無伴奏バイオリン パルティータ第3番~ガヴォット* (10)ヘンデル:「ソロモン」~シバの女王の入場* (11)ヘンデル:オケイジョナル・オラトリオHWV 62~行進曲* ■Disc2 (1)サリヴァン:序曲「舞踏会で」* (2)エルガー:朝の歌* チャイコフスキー:スラブ行進曲* (3)スッペ:「軽騎兵」序曲+ チャイコフスキー:「眠りの森の美女」~ワルツ+ (4)マスカーニ:「カヴァレリア・ルスティカーナ間奏曲+ (5)バッハ(ウォルトン編):『羊は安らかに草を食み』+ (6)リスト:ハンガリー狂詩曲第2番(ミュラー=ベルクハウス編)+ (7)オッフェンバック:「天国と地獄」序曲+ (8)イッポリトフ・イワーノフ:酋長の行列+ |
ジョージ・ウェルドン(指) フィルハーモニアO#.+、LSO* 録音:1954-1956年#、1953年10月23-29日*、1951-1953年+(全てモノラル) ※音源:英COLUMBIA 33SX-1032+、1045*、1054# ◎収録時間:71:55+67:00 |
| “解釈の痕跡を残さないウェルドンの美学の結晶!” | ||
|
||
 TRE-260 |
フー・ツォン~若き日のショパン録音Vol.1 バラード(全4曲)/子守歌Op.57 夜想曲Op.15-2/ピアノ・ソナタ第3番* |
フー・ツォン(P) 録音:1959年、1959年2月*(全てモノラル) ※音源:英WRC TP-48、英MFP MFP-2026* ◎収録時間:73:49 |
| “歌に必ず詩情が寄り添うフー・ツォン独自のピアニズム!” | ||
|
||
 TRE-261(2CDR) |
A.コリンズ~ディーリアス&V=ウィリアムズ ■ディスク1 ディーリアス:イギリス狂詩曲「ブリッグの定期市」 歌劇「村のロメオとジュリエット」~「楽園への道」 パリ(大都会の歌)* ■ディスク2 ディーリアス:春初めてのカッコウの声を聞いて 川面の夏の夜* 夏の庭で*/夏の歌 ヴォーン=ウィリアムズ:グリーンスリーヴス幻想曲# タリスの主題による幻想曲# |
アンソニー・コリンズ(指) LSO、ロンドン新SO# 録音:1953年2月23-25日、1953年10月20-21日*、1952年3月31日-4月1日# ※音源:英DECCA ACL-245、米LONDON LL-758、英DECCA ACL-144 ◎収録時間:104:29 |
| “ディーリアスの音楽にビーチャムとは異なる光を与えた歴史的名演!” | ||
|
||
 TRE-263 |
超厳選!赤盤名演集Vol.6 シューベルト:「ロザムンデ」~序曲/間奏曲第3番/バレエ音楽第2番 マーラー:交響曲第1番「巨人」* |
パウル・クレツキ(指) ロイヤルPO、VPO* 録音:1958年10月27&29日、1961年11月13-15日*(全てステレオ) ※音源:東芝 ASC-5003、AA-7302* ◎収録時間:75:51 |
| “ユダヤ的情念を湛えつつ決してべとつかないクレツキ特有の美意識!” | ||
|
||
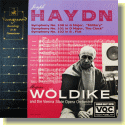 TRE-265 |
ヴェルディケ~ハイドン:交響曲集Vol.1 交響曲第100番ト長調 「軍隊」 Hob.I:100 交響曲第101番ニ長調 「時計」 Hob.I:101 交響曲第102番変ロ長調 Hob.I:102* |
モーゲンス・ヴェルディケ(指) ウィーン国立歌劇場O 録音:1956年6月ウィーン楽友協会小ホール(ステレオ) ※音源:墺amadeo AVRS-12013St*、AVRS-12014St ◎収録時間:74:20 |
| “今こそ聴きたい、永久に光を失わないハイドンの究極形!” | ||
|
||
 TRE-268 |
ワイエンベルク/R.シュトラウス&ガーシュイン R・シュトラウス:ブルレスケ* ガーシュウィン:ラプソディ・イン・ブルー ピアノ協奏曲ヘ調 |
ダニエル・ワイエンベルク(P) クリストフ・フォン・ドホナーニ(指)* フィルハーモニアO* ジョルジュ・プレートル(指) パリ音楽院O 録音:1963年6月16&19日*、1960年頃(全てステレオ) ※音源:蘭CNR SKLP-4145*、蘭EMI 5C045-11656 ◎収録時間:69:03 |
| “リズムと色彩が常に共存する驚異のガーシュウィン!” | ||
|
||
 TRE-269 |
F.ブッシュのベートーヴェン「第9」 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付」 |
フリッツ・ブッシュ(指) デンマーク放送SO&cho シェシュティン・リンドベリ=トルリンド(S) エリセ・イェーナ(Ms) エリク・ショーベリ(T) ホルガー・ビルディン(Bs) 録音:1950年9月7日 ライヴ ※音源:MELODIA M10-46963-003 ◎収録時間:62:08 |
| “理性と直感で一時代先を見通すフリッツ・ブッシュのベートーヴェン!” | ||
|
||
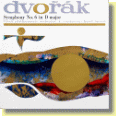 TRE-270(1CDR) |
アンチェル~ヤナーチェク&ドヴォルザーク ヤナーチェク:タラス・ブーリバ ドヴォルザーク:交響曲第6番* |
カレル・アンチェル(指)チェコPO 録音:1963年4月16-20日、1966年1月22-24日*(共にステレオ) ※音源:日COLUMBIA WS-3033、OS-2339* ◎収録時間:64:45 |
| “アンチェルが潔癖な響きに込めた強烈な共感と民族魂!” | ||
|
||
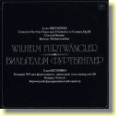 TRE-271 |
ハンゼン~ベルリンでの協奏曲録音 チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番* ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番 |
コンラート・ハンゼン(P) ウィレム・メンゲルベルク(指)BPO* ウィルヘルム・フルトヴェングラー(指)BPO 録音:、1940年7月11日ベルリン*、1943年10月30(31)日(ライヴ)、 共にベルリン、フィルハーモニーホール ※音源:PAST MASTERS_PM-18*、Melodiya M10-460067 ◎収録時間:65:56 |
| “ハンゼンとフルトヴェングラー、双方の強烈なシンパシーが完全融合!” | ||
|
||
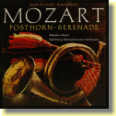 TRE-272 |
ムラデ・バシチのモーツァルト フリーメイソンのための葬送音楽 K. 477* 交響曲第46番ハ長調 K. 96* 交響曲第26番変ホ長調 K. 184* 行進曲ニ長調 K. 335-1 セレナード第9番 「ポストホルン」 行進曲ニ長調 K. 335-2 |
ムラデ・バシチ(指) ザルツブルク・モーツァルテウムO 録音:1964年5月、1960年代後期*(全てステレオ) ※音源: KING RECORD SH-5230、ORBIS 79-271* ◎収録時間:75:44 |
| “笑顔と涙が美しく共存するモーツァルトの中のモーツァルト!” | ||
|
||
 TRE-273(1CDR) |
イッセルシュテット/シューベルト&ワーグナー シューベルト:「ロザムンデ」*~間奏曲第1番/間奏曲第3番/バレエ音楽第1番/バレエ音楽第2番 ワーグナー:「ラインの黄金」~ワルハラへの神々の入城 「ワルキューレ」~ワルキューレの騎行/魔の炎の音楽 「ジークフリート」~森のささやき 「神々の黄昏」~ジークフリートのラインへの旅/ジークフリートの葬送行進曲 |
ハンス・シュミット=インセルシュテット(指) 北ドイツRSO 録音:1955年12月7-15日(モノラル) ※音源:米Capitol P-18021*、仏ODEON XOC-113 ◎収録時間:70:28 |
| “自然な佇まいの中に作品の本質を見出すイッセルシュテットの揺るぎない信念!” | ||
|
||
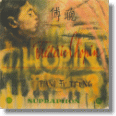 TRE-274 |
フー・ツォン~若き日のショパン録音Vol.2 マズルカ集 Op.6-2/ Op.7-4/ Op.17-2 Op.41-3/ Op.17-4/ Op.24-2 Op.59-1/第58番変イ長調.遺作 第49番ヘ短調Op.68-4.遺作 第52番変ロ長調.遺作 幻想ポロネーズ* マズルカOp.67-2*/ Op.67-4* 夜想曲Op.62-1*/ Op.62-2* マズルカOp.50-3* |
フー・ツォン(P) 録音:1959年2月London, Conway Hall、1956年3月2-6日チェコ* (全てモノラル) ※音源:MFP MFP-2026、PARLIAMENT PLP-159* ◎収録時間:67:40 |
| “身を粉にして心の呟きを吐露するフー・ツォンの独壇場!” | ||
|
||
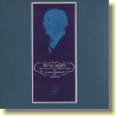 TRE-275 |
超厳選!赤盤名演集Vol.8 ギーゼキングのシューベルト 3つの小品D.946~第2番* 即興曲集Op.90&142(全8曲) |
ワルター・ギーゼキング(P) 録音:1956年10月*、1955年9月(全てモノラル) ※音源:東芝 AB-9047-48 ◎収録時間:70:04 |
| “新即物主義者という縛りを解いて味わいたいギーゼキングの真心の歌!” | ||
|
||
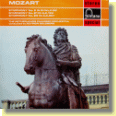 TRE-276 |
S・ゴールドベルク指揮によるモーツァルト アイネ・クライネ・ナハトムジーク* 交響曲第5番K.22 交響曲第21番K.134 交響曲第29番K.201 |
シモン・ゴールドベルク(指) オランダ室内O 録音:1960年12月6-10*、1961年7月6-8日(全てステレオ) ※音源:日VICTOR SFON-10516*、FONTANA SFL-14073 ◎収録時間:65:02 |
| “高潔かつ清新!S.ゴールドベルクの美学がここに凝縮!” | ||
|
||
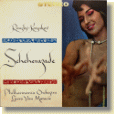 TRE-277 |
マタチッチの「シェエラザード」 ムソルグスキー(R=コルサコフ編):交響詩「禿山の一夜」 R=コルサコフ:序曲「ロシアの復活祭」* 交響組曲「シェエラザード」# |
ロヴロ・フォン・マタチッチ(指) フィルハーモニアO* 録音1958年9月4日、9月5日*、9月1-2日#(全てステレオ) ※音源:仏TRIANON TRI-33114、TRI-33107* ◎収録時間:70:03 |
| “マタチッチの常人離れした色彩力と心理描写力を全投入した空前の名演集!” | ||
|
||
 TRE-278 |
フェラスのシベリウス&チャイコフスキー チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 シベリウス:ヴァイオリン協奏曲* |
クリスチャン・フェラス(Vn) ヘルベルト・フォン・カラヤン(指)BPO 録音:1965年11月6-8日、1964年10月29-30日* イエス・キリスト教会 ※音源:独DG 104-925、独DG 138-961* ◎収録時間:68:49 |
| “カラヤンに従属せず自己表現を貫徹させるフェラスの真の美学!” | ||
|
||
 TRE-279 |
ノイマンのブルックナー グリンカ:幻想曲「カマリンスカヤ」# リスト:交響詩「前奏曲」 ブルックナー:交響曲第1番* |
ヴァーツラフ・ノイマン(指) ライプチヒ・ゲヴァントハウスO 録音:1967年10月17日#、1965年12月13-14日ライプツィヒ救世主教会*、1968年2月22-23日 (全てステレオ) ※音源:独DECCA _SXL-20087*、ETERNA 8-25-847 ◎収録時間:74:34 |
| “ノイマンの端正な造形力にオケの魅力が完全バックアップ!” | ||
|
||
 TRE-280 |
ダイゼンロート/ゴールデン・マーチ集 ●ドイツ・オーストリア編 ハイドン:ドイツ国歌# レオンハルト:アレクサンダー行進曲# マイスナー:故郷をあとに(シュテットル行進曲)# フリーデマン:フリートリヒ大帝行進曲 フチーク:剣士の入場# シュランメル:ウィーンはウィーン# ●イギリス編 アーン:ゴッド・セイブ・ザ・クイーン+ ルール・ブリタニア+ グラハム:勝利者# ●フランス編 リール:ラ・マルセイエーズ* ブランケット:サンブル・エ・ミューズ連隊行進曲* モウガー:金髪美女* ●アメリカ編 スミス:星条旗 ツィンマーマン:錨を上げて クロフォード:アメリカ空軍の歌 グルーバー:アメリカ野砲隊の歌 スーザ:海を越えた握手 闘技士/シカゴの美人 星条旗よ永遠なれ/雷神 士官候補生/ワシントン・ポスト エル・カピタン/忠誠 |
マジョール・ダイゼンロート(指) バッハバタリオン軍楽隊 フランス軍楽隊*、 ドイツ軍楽隊# 英国軍楽隊+ 録音:1950年代末~1960年代初頭(ステレオ) ※音源:日Victor SGW-7020、SGW-7021 ◎収録時間:61:29 |
| “ドイツ魂溢れる強靭なリズムが体の芯から鼓舞!” | ||
|
||
 TRE-281 |
F.レーマン~モーツァルト:作品集1 オペラ序曲集* 後宮からの誘拐/フィガロの結婚、 ドン・ジョヴァンニ/コシ・ファン・トゥッテ、 劇場支配人/魔笛/イドメネオ 交響曲第40番ト短調K.550 |
フリッツ・レーマン(指) BPO*、ウィーンSO 録音:1952年7月9日*、1953年5月3-4日(共にモノラル) ※音源:DGG LPEM-19040*、29311 ◎収録時間:64:20 |
| “今こそ傾聴すべき、楽器や奏法を弄るではない真の原点回帰!” | ||
|
||
 TRE-282 |
スワロフスキー/シューマン&スメタナ スメタナ:歌劇「売られた花嫁」序曲 交響詩「モルダウ」 シューマン:交響曲第1番「春」* 交響曲第3番「ライン」# |
ハンス・スワロフスキー(指) ウィーン祝祭O、 ウィーン国立歌劇場O*、ウィーンSO#、 録音:1958年頃、1959年*、1955年1月19&21日#(全てモノラル) ※音源:W.R.C TT-17、仏ODEON XOC-819*,# ◎収録時間:75:27 |
| “模範解答的な佳演の域を超えるスワロフスキーの熱き表現!” | ||
|
||
 TRE-283 |
カークパトリック/フォルテピアノによるモーツァルト ピアノ・ソナタ第17番 変ロ長調 KV 570 組曲 ハ長調 KV 399 幻想曲とフーガ ハ長調 KV 394 ピアノ協奏曲第17番 ト長調 KV 453* |
ラルフ・カークパトリック(フォルテピアノ) アレクサンダー・シュナイダー(指)* ダンバートン・オークスCO* 録音:1952年、1951年3月* ※音源:W.R.C CM-30、日Victor LH-25* ◎収録時間:71:33 |
| “楽器へのこだわりが音楽表現と不可分であることを証明する最高の実例!” | ||
|
||
 TRE-284 |
超厳選!赤盤名演集Vol.9~_メニューイン/バルトーク&ベートーヴェン バルトーク(シェルイ編):ヴィオラ協奏曲 ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲* |
ユ-ディ・メニューイン(Vn) アンタル・ドラティ(指) オットー・クレンペラー(指)* ニュー フィルハーモニアO 録音:1966年9月28-29日、1966年1月22,22,24,25日*(共にステレオ) ※音源:TOSHIBA AA-8257、HA-1186* ◎収録時間:66:24 |
| “弱音のニュアンスに逃げず呼吸の持久力で作品の精神を徹底音化!” | ||
|
||
 TRE-285 |
ヘブラー/シューマン&シューベルト シューマン:子供の情景Op.15* シューベルト:ピアノ・ソナタ第13番D.664 ピアノ・ソナタ第18番D.894「幻想」 |
イングリット・ヘブラー(P) 録音:1959年8月28-31日*、1960年4月(全てステレオ) ※音源:日Victor SFL-7992*、蘭PHILIPS 835363AY ◎収録時間:67:18 |
| “ヘブラーのピアニズムの品格を支える恐るべき打鍵制御力!” | ||
|
||
 TRE-286 |
超厳選!赤盤名演集Vol.10~シルヴェストリの「幻想」 ファリャ:「はかなき人生」~間奏曲&スペイン舞曲第1番 「恋は魔術師」~火祭りの踊り ベルリオーズ:幻想交響曲* |
コンスタンティン・シルヴェストリ(指) パリ音楽院O 録音:1961年1月31日&2月1日、1961年2月6-8&11日*(全てステレオ) ※音源:東芝 WS-23 、WS-10* ◎収録時間:64:26 |
| “伝統に阿らないシルヴェストリに必死に食らいつくパリ音楽院管!” | ||
|
||
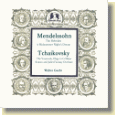 TRE-287 |
ワルター・ゲール/メンデルスゾーン&チャイコフスキー メンデルスゾーン:序曲「フィンガルの洞窟」* 「真夏の夜の夢」~序曲/スケルツォ/夜想曲/結婚行進曲 チャイコフスキー:「地方長官」Op.78# エレジー.ト長調 「イワン・サマーリンの思い出に」# 幻想序曲「ロメオとジュリエット」# |
ワルター・ゲール(指) チューリッヒ・トーンハレO*、オランダPO 録音:1950年、1951年# ※音源:独Concrt Hall MMS-2005、米Concrt Hall MMS-66# ◎収録時間:76:56 |
| “史上最高の「ロメ・ジュリ」に見るゲールの妥協なき心理描写力!” | ||
|
||
 TRE-288 |
若き日のマゼール/モーツァルト 交響曲第38番 ニ長調 「プラハ」 K. 504 交響曲第39番 変ホ長調 K. 543 |
ロリン・マゼール(指) ベルリンRSO 録音:1966年9月23日-9月1日(ステレオ) ※音源:英PHILIPS 6856019 ◎収録時間:62:10 |
| “モーツァルトで浮き彫りになるマゼールの「ケレン味のない」音作り!” | ||
|
||
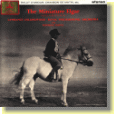 TRE-289 |
コリングウッドのエルガー:小品集 組曲「子供部屋」*/弦楽セレナード* 朝の歌/「伊達男ブランメル」~メヌエット、 「スターライト・エクスプレス」~我が古き調べ#/子供たちへ 愛の挨拶 「子どもの魔法の杖」第2組曲~飼いならされた熊# 3つのバイエルン舞曲 Op. 27~子守歌 夢の子供たち(全2曲) 組曲「子供部屋」~シリアス・ドール 「子どもの魔法の杖」第1組曲~セレナード/太陽の踊り |
フレデリック・ハーヴェイ(Br)# ローレンス・コリングウッド(指) LSO*、ロイヤルPO 録音:1953年11月11日(モノラル)*、1964年3月(ステレオ) ※音源:英COLUMBIA 33CX-1030*、英ODEON PCSD-1555 ◎収録時間:79:23 |
| “エルガーの小品に感覚的な美しさ以上の息遣いを注入した比類なき名演!” | ||
|
||
 TRE-290(2CDR) ★ |
ヴェルディ:レクイエム | レオニー・リザネク(S) レジーナ・レズニック(Ms) デイヴィッド・ロイ(T) ジョルジオ・トッツィ(Bs) フリッツ・ライナー(指) シカゴ・リリック・オペラO&cho 録音:1958年4月3日シカゴ、リリック・オペラ・ライヴ(モノラル) ※音源:Melodram MEL-238 ◎収録時間:95:53 |
| “ライナーのエモーショナルなアプローチが作品の核心に肉薄!” | ||
|
||
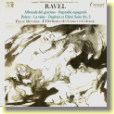 TRE-291 |
デルヴォー/ラヴェル管弦楽曲集(Command録音) 道化師の朝の歌*/スペイン狂詩曲 ボレロ/ラ・ヴァルス* 「ダフニスとクロエ」第2組曲* |
ピエール・デルヴォー(指)コロンヌO 録音:1961年5月17日パリ・サル・ワグラム(ステレオ) ※音源:米Command Classics CC-11005SD*、CC-11007SD ◎収録時間:69:00 |
| “デルヴォー特有の色彩力と官能美がもたらすラヴェル作品の底知れぬ魅力!” | ||
|
||
 TRE-292 |
ストコフスキーのビゼー 「カルメン」組曲【前奏曲/衛兵の交代/アルカラの竜騎兵/ジプシーの踊り/間奏曲/密輸入者たちの行進/アラゴネーズ】* 「アルルの女」組曲第1番【前奏曲/メヌエット/アダージェット/カリヨン】# 「アルルの女」組曲第2番【田園曲/間奏曲/メヌエット/ファランドール】 交響曲第1番ハ長調+ |
レオポルド・ストコフスキー(指) フィラデルフィアO*、ヒズ交響楽団#,+ 録音:1927年4月30日,5月2&10日*、1952年2月29日#、1952年3月20日+ ※音源:日RCA RVC1523*、英RCA VIC1008#,+ ◎収録時間:79:58 |
| “50年代のストコフスキーの本能的な美への執着と妥協なき表現!” | ||
|
||
 TRE-293 |
超厳選!赤盤名演集Vol.11~クレンペラーの「大地の歌」 マーラー:大地の歌 |
フリッツ・ヴンダーリッヒ(T) クリスタ・ルートヴィッヒ(Ms) オットー・クレンペラー(指) フィルハーモニアO、ニュー・フィルハーモニアO 録音:1964年2月&1966年7月(ステレオ) ※音源:東芝 AA-8100 ◎収録時間:63:53 |
| “永遠に光り続ける普遍的芸術の象徴!” | ||
|
||
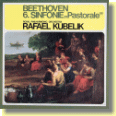 TRE-294 |
超厳選!赤盤名演集Vol.12~クーベリック/田園&ハンガリー舞曲 ブラームス:ハンガリー舞曲集 第1&第3番(以上,ブラームス編) 第5&第6番(以上,シュメリング編) 第17~第21番(以上,ドヴォルザーク編) ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」* |
ラファエル・クーベリック(指) ロイヤルPO 録音:1958年11月20日、1959年1月21-23日*(全てステレオ) ※音源:東芝 ASC-5018、WS-19* ◎収録時間:62:41 |
| “40代半ばにしてクーベリックに備わっていた作品の本質を突く手腕!” | ||
|
||
 TRE-295(2CDR) |
ライナーのモーツァルトVol.1 アイネ・クライネ・ナハトムジーク* ディヴェルティメント第17番K.334# 交響曲第40番K550** 音楽の冗談K.522+ ディヴェルティメント第11番K.251## 交響曲第41番「ジュピター」++ |
フリッツ・ライナー(指) CSO、NBC響団員*,# 録音:1954年12月4日*、1955年4月23&26日#、1955年4月24日**、1954年9月16日+、1954年9月21日##、1954年4月26日++ (全てモノラル) ※音源:米RCA LM-1966*,#、米RCA LM-2114 **,++、独RCA LM-1952-B+,## ◎収録時間:77:33+75:36 |
| “厳格なイメージを超えて愛を燃や尽くしたライナーの特別なモーツァルト!” | ||
|
||
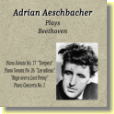 TRE-297 |
エッシュバッハーのベートーヴェン ピアノ・ソナタ第17番Op.31-2「テンペスト」 ピアノ・ソナタ第26番Op.81a「告別」* ロンド・ア・カプリッチョ「なくした小銭への怒り」Op.129 ピアノ協奏曲第1番ハ長調Op.15# |
アドリアン・エッシュバッハー(P) ウィルヘルム・フルトヴェングラー(指)# ルツェルン祝祭O# 録音:1950年9月19日、1951年5月22日*、1947年8月27日# ※音源:独DG LPM-18220、米Discocorp RR-438# ◎収録時間:79:15 |
| “大指揮者と対等に音楽を紡ぎ合った美しき協奏!” | ||
|
||
 TRE-298 |
ヴァーシャリのショパンVol.1 ピアノ・ソナタ第3番Op.58* ワルツ集(全17曲) 第1番変ホ長調Op.18《華麗なる大円舞曲》 第2番変イ長調Op.34-1《華麗なる円舞曲》 第3番イ短調Op.34-2《華麗なる円舞曲》 第4番ヘ長調Op.34-3《華麗なる円舞曲》 第5番変イ長調Op.42《大円舞曲》 第6番変ニ長調Op.64-1《小犬のワルツ》 第7番嬰ハ短調Op.64-2 第8番変イ長調Op.64-3 第9番変イ長調Op.69-1《別れのワルツ》 第10番ロ短調Op.69-2 第11番変ト長調Op.70-1 第12番ヘ短調Op.70-2 第13番変ニ長調Op.70-3 第14番ホ短調遺作 第15番ホ長調遺作 第16番変イ長調遺作 第17番変ホ長調遺作 |
タマーシュ・ヴァーシャリ(P) 録音:1963年5月17-20日*、1965年5月20-30日(全てステレオ) ※音源:DG 136450S-LPEM*、DG 104-367 ◎収録時間:77:50 |
| “激烈さとは無縁のヴァーシャリのショパンの最高峰!” | ||
|
||
 TRE-299(2CDR) |
コンヴィチュニー/ベートーヴェン&ブルックナー ベートーヴェン:交響曲第7番 ブルックナー:交響曲第5番* |
フランツ・コンヴィチュニー(指) ライプチヒ・ゲヴァントハウスO 録音:1959年6月11-19日、1961年6月26-28&30日*(全てステレオ) ※音源:日VICTOR SFON-5506、日COLUMBIA OP-7084* ◎収録時間:63:21+59:40 |
| “攻めの表現にも誇張に傾かない恐るべきバランス感覚!” | ||
|
||
 TRE-300 |
モーリス・ル・ルー/プロコフィエフ&ラヴェル プロコフィエフ:スキタイ組曲* ラヴェル:高雅で感傷的なワルツ 道化師の朝の歌 亡き王女のためのパヴァーヌ ボレロ |
モーリス・ル・ルー(指) フランス公営放送PO*、 フランス国立放送局O 録音:1961年*、1966年(全てステレオ) ※音源:仏VEGA C30ST-20001*、独Concert Hall SMS-2490 ◎収録時間:66:52 |
| “人間味と洗練味が交錯するル・ルーの鮮やかな指揮センス!” | ||
|
||
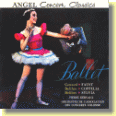 TRE-301 |
厳選!赤盤名演集Vol.13~デルヴォー~序曲&バレエ音楽集 ニコライ:ウィンザーの陽気な女房たち」序曲 ロッシーニ:「セヴィリアの理髪師」序曲 ボワエルデュー:「バグダッドの太守」序曲 スッペ:「軽騎兵」序曲 グノー:歌劇「ファウスト」~バレエ音楽* ドリーブ:バレエ音楽「コッペリア」~[前奏曲とマズルカ/バラード/主題と変奏/ワルツ/ハンガリー舞曲]** バレエ音楽「シルヴィア」~[狩りの女神たち/間奏曲/緩やかなワルツ/ピチカート/バッカスの行進]# |
ピエール・デルヴォー(指) コロンヌO 録音:1958年、1958年7月16&17日*、20&23日**、17&18日#(全てモノラル) ※音源:東芝 HC-1037、XLP-1008*,**,# ◎収録時間:77:45 |
| デルヴォーの粋な棒裁きで浮き彫りとなる作品の未知なる魅力! | ||
|
||
 TRE-303 |
C.デイヴィスのハイドン&モーツァルト ハイドン:交響曲第84番変ホ長調 Hob.I:84* モーツァルト:交響曲第28番 ハ長調 K. 200 交響曲第38番 ニ長調 「プラハ」K.504 |
コリン・デイヴィス(指) イギリスCO 録音:1960年9月30日&10月2日*、1962年12月7-8日(全てステレオ) ※音源:LOISEAU LYRE SOL-60030*、SOL-266 ◎収録時間:74:23 |
| “最後のモーツァルト指揮者、コリン・デイヴィスの真骨頂!” | ||
|
||
 TRE-304 |
ラインスドルフ&ボストン響・厳選名演集Vol.5~ブラームス 交響曲第2番ニ長調 Op. 73 交響曲第4番 ホ短調 Op. 98* |
エーリッヒ・ラインスドルフ(指) ボストンSO 録音:1964年12月14&16日、1966年4月26-27日*(全てステレオ) ※音源:Victor SHP-2383、RCA LSC-3010* ◎収録時間:78:30 |
| “作品によって豹変するラインスドルフの底知れぬ魅力!” | ||
|
||
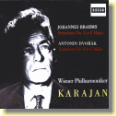 TRE-305 |
カラヤン&VPO/デッカ録音名演集Vol.2 ブラームス:交響曲第3番 ドヴォルザーク:交響曲第8番* |
ヘルベルト・フォン・カラヤン(指)VPO 録音:1961年(ステレオ) ※音源:日KING SLC-1742、SLC-1751* ◎収録時間:69:53 |
| “カラヤンの芸術が「人工的」でも「嘘」でもないということの証明!” | ||
|
||
 TRE-306(1CDR) |
ブルックナー:交響曲第8番ハ短調 WAB 108 (1890年稿・ノヴァーク版) | ヤッシャ・ホーレンシュタイン(指) ウィーン・プロ・ムジカO(ウィーンSO) 録音:1955年(モノラル) ※音源:英VOX PL-9682 ◎収録時間:76:29 |
| “マーラーにもブルックナーにも適応できるホーレンシュタイン独自の音作り!” | ||
|
||
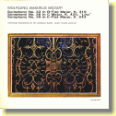 TRE-307 |
ヨッフム&手兵バイエルン放送響とのモーツァルト 交響曲第33番変ロ長調 K. 319 交響曲第36番K.425「リンツ」* 交響曲第39番変ホ長調 K.543# |
オイゲン・ヨッフム(指) バイエルンRSO 録音:1954年11月29-30日*、1955年10月2日#、1954年6月1-2日(全てモノラル) ※音源:英HELIODOR 478-435*,#、DGG 29-307 ◎収録時間:78:52 |
| “おおらかなヨッフムと陽のモーツァルトとの幸福な出会い!” | ||
|
||
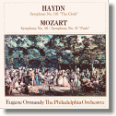 TRE-308 |
オーマンディ~「古典」名演集Vol.1 ハイドン:交響曲第101番「時計」 モーツァルト:交響曲第30番* 交響曲第31番「パリ」# |
ユージン・オーマンディ(指) フィラデルフィアO 録音:1962年1月28日、1962年4月8日*、1961年1月29日#(全てステレオ) ※音源:米COLUMBIA MS-6812、MS-6122*,# ◎収録時間:62:17 |
| “オーマンディと古典的様式美との高い親和性を実証!” | ||
|
||
 TRE-309 |
スメタナ:交響詩「わが祖国」 | ラファエル・クーベリック(指)VPO 録音:1958年4月3-7日 ウィーン、ゾフィエンザール(モノラル・テイク) ※音源:DECCA_LXT-5475(2LP) ◎収録時間:74:51 |
| “貧弱なステレオ・テイクでは感じようのないクーベリックの熱き望郷!” | ||
|
||
 TRE-310 |
赤盤名演集Vol.14~サヴァリッシュ/ワーグナー&ウェーバー ワーグナー:「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕前奏曲* 「神々の黄昏」~夜明けとジークフリートのラインへの旅**/ジークフリートの葬送行進曲** ウェーバー:「魔弾の射手」序曲## 「プレチオーザ」序曲# 「オベロン」序曲++ 「オイリアンテ」序曲+ 「精霊の王」序曲# 「アブ・ハッサン」序曲* 祝典序曲「歓呼」# |
ウォルフガング・サヴァリッシュ(指) フィルハーモニアO 録音:1958年7月29日*、1958年7月28日#、1958年2月26日**、1958年2月25&28日##、1958年2月25日+、1958年2月24-25日++(全てステレオ) ※音源:東芝 AA-7129(ワーグナー)、AA-7128 ◎収録時間:76:55 |
| “惜しげもない愛でウェーバーの魅力を伝えきった若きサヴァリッシュの金字塔!” | ||
|
||
 TRE-311 |
ヘブラー~ソ連ライヴを含む3つの協奏曲 ハイドン:ピアノ協奏曲第11番ニ長調Op.21 Hob.XVIII : 11 モーツァルト:ピアノ協奏曲第12番 イ長調 K. 414 ピアノ協奏曲第17番 ト長調 K. 453* |
イングリット・ヘブラー(P) シモン・ゴールドベルク(指)オランダ室内O ベルンハルト・パウムガルトナー(指)ザルツブルク・モーツァルテウムO* 録音:1960年7月9&14-15日アムステルダム・コンセルトヘボウ、1965年モスクワ音楽院大ホール・ライヴ*(共にステレオ) ※音源:蘭PHILIPS 875-052FY、MELODIYA C90-13051-52* ◎収録時間:73:34 |
| “30代のヘブラーが織りなす気品と生命力溢れる理想のモーツァルト像!” | ||
|
||
 TRE-312 |
ヘブラー~ステレオ初期のPHILIPS録音集 ハイドン:アンダンテと変奏曲.ヘ短調Hob. XVII:6* モーツァルト:ピアノ協奏曲第18番変ロ長調K.456 ピアノ協奏曲第27番変ロ長調K.595 |
イングリット・ヘブラー(P) クリストフ・フォン・ドホナーニ(指)ウィーンSO 録音:1960年7月1-3日*、1959年5月9-11日(全てステレオ) ※音源:蘭PHILIPS 802737DXY*、日Victor SFON-7508 ◎収録時間:69:38 |
| “穏やかなだけではないヘブラーの頑なにブレないピアニズム!” | ||
|
||
 TRE-313 |
ケンプ~シューマン&リスト:ピアノ協奏曲集 シューマン:ピアノ協奏曲イ短調Op.54* リスト:ピアノ協奏曲第1番変ホ長調 ピアノ協奏曲第2番イ長調 |
ウィルヘルム・ケンプ(P) ヨーゼフ・クリップス(指)LSO* アナトゥール・フィストラーリ(指)LSO 録音:1953年5月26-27日*、1964年6月2&4日(全てモノラル) ※音源:英DECCA LW-5337*、独DECCA MD-1043 ◎収録時間:73:03 |
| “芸術的表現に無関係なものを排斥するケンプのピアニズムを象徴!” | ||
|
||
 TRE-314 |
レイボヴィッツ/ベートーヴェン名演集Vol.1 ベートーヴェン:序曲「レオノーレ」第3番* 交響曲第9番「合唱」 |
ルネ・レイボヴィッツ(指)ロイヤルPO インゲ・ボルク(S) 、ルート・ジーヴェルト(A)、リチャード・ルイス(T)、 ルートヴィヒ・ヴェーバー(Bs)、 ビーチャム・コーラル・ソサエティ 録音:1962年2月15日*、1961年5月2-3, 5,7日(共にステレオ) ※音源:英Readers Digest RDS-5013*、日ビクター RBS-6-7 ◎収録時間:74:37 |
| “響きの機能美に隠れがちな作曲家に寄り添ったレイボヴィッツの熱き魂!” | ||
|
||
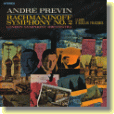 TRE-315 |
プレヴィンの「ラフ2」~第1回録音 リャードフ:8つのロシア民謡 Op.58 ラフマニノフ:交響曲第2番ホ短調 Op.27* |
アンドレ・プレヴィン(指)LSO 録音:1965年8月20-21, 24日ロンドン・ウォルサムストウ・タウン・ホール、1966年4月25日ロンドン・キングズウェイ・ホール*(共にステレオ) ※音源:日ビクター SHP-2439、SHP-2449* ◎収録時間:64:04 |
| “完全完全盤か否かを超越した、伸びやかに歌い上げることの大切さ!” | ||
|
||
 TRE-316 |
ハンゼン/ベートーヴェン:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲第1番ハ長調 Op. 15* ピアノ協奏曲第3番ハ短調 Op. 37 |
コンラート・ハンゼン(P)、 ハインツ・ワルベルク*、イシュトヴァン・ケルテス(指) バンベルクSO、 録音:1960年頃(共にステレオ) ※音源:独OPERA St-3959*、St-3919 ◎収録時間:69:16 |
| “小手先の演出とは無縁のドイツ・ピアニズムの真髄!” | ||
|
||
 TRE-319 |
ブランカ・ムスリン/ショパン:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲第1番ホ短調Op.11* ピアノ協奏曲第2番へ短調Op.21*# 練習曲Op.25-7/Op.25-3 |
ブランカ・ムスリン(P) ハインツ・ワルベルク(指)バンベルクSO* ウィルヘルム・シュヒター(指)ベルリンSO# 録音:1960年代初頭*、1963年7月4-5日#、1964年10月3日(全てステレオ) ※音源:日KING SH-5242*,#、日KING SR-5052# ◎収録時間:77:03 |
| “成熟した精神の昇華力で甘美なショパン像を打破!” | ||
|
||
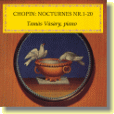 TRE-320(2CDR) ★ |
ヴァーシャリのショパンVol.2 夜想曲集(全20曲) |
タマーシュ・ヴァーシャリ(P) 録音:1965年4月20-24日(Op.9、Op.15、Op.27、Op.32)、5月11-12日(ステレオ) ※音源:独DG 104-369、136-487 ◎収録時間:50:08+51:15 |
| “自然体の歌と呼吸の持久性を兼ね備えた理想のノクターン!” | ||
|
||
 TRE-321 |
ラインスドルフ&ボストン響~厳選名演集Vol.6~ドヴォルザーク他 リムスキー=コルサコフ:組曲「金鶏」* ドヴォルザーク:交響曲第6番ニ長調 Op. 60 スラブ舞曲Op.72-2/Op.72-8 |
エーリヒ・ラインスドルフ(指) ボストンSO 録音:1965年4月23-24*、1967年(全てステレオ) ※音源:日ビクター SHP-2376*、SRA-2527、 ◎収録時間:77:30 |
| “ラインスドルフこだわりの「ドボ6」の比類なき昇華力!” | ||
|
||
 TRE-322 ★ |
ブランカール~ラヴェル&モーツァルト モーツァルト:ピアノ・ソナタ第16番 変ロ長調、K.570 ラヴェル:左手のための協奏曲* ピアノ協奏曲* |
ジャクリーヌ・ブランカール(P) エルネスト・アンセルメ(指)スイス・ロマンドO* 録音:1951年10月、1953年6月* ※音源:日KING LY-34、日KING LY-13* ◎収録時間:54:18 |
| “表面的な雰囲気作りを必要としない明確な音の粒立ちと丁寧な語り口!” | ||
|
||
 TRE-323 |
マツェラート~モーツァルト&チャイコフスキー モーツァルト:交響曲第36番「リンツ」 交響曲第40番ト短調K.440 チャイコフスキー:弦楽セレナード* |
オットー・マツェラート(指) フランクフルトSO、ベルリンSO* 録音:1960年頃、1960年*(全てステレオ) ※音源:米Classica CLA-106、日COLUMBIA MS-134-K* ◎収録時間:79:48 |
| “どんなに激賞しても足りない妥協なき音作りに見るマツェラートの底力!” | ||
|
||
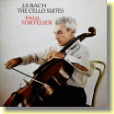 TRE-325(2CDR) ★ |
厳選!赤盤名演集Vol.15~トルトゥリエ~バッハの「無伴奏」 バッハ:無伴奏チェロ組曲(全6曲) |
ポール・トルトゥリエ(Vc) 録音:1960年12月5日&1961年3月20日(第1番)、1960年12月5日&1961年3月20日(第2番)、1960年12月6日(第3番)、1960年12月7日(第4番)、1960年12月5-6日&1961年7月23日(第5番)、1960年12月7-8日&1961年3月20日(第6番) ステレオ ※音源:東芝_ASC-5137-9(赤盤) ◎収録時間:55:07+69:44 |
| “トルトゥリエが格調高く謳い上げる人間讃歌!” | ||
|
||
 TRE-326 |
A.フィッシャー/モーツァルト&シューマン モーツァルト:ピアノ協奏曲第22番変ホ長調 K. 482* シューマン:ピアノ協奏曲イ短調Op.54# メンデルスゾーン:ロンド・カプリッチョーソ ホ長調 Op.14## |
アニー・フィッシャー(P) オットー・クレンペラー(指)* アムステルダム・コンセルトヘボウO* ヨゼフ・カイルベルト(指)# ケルンRSO# 録音:1956年7月12日コンセルトヘボウ*、1958年4月28日 ケルン放送 第1ホール#、1966年モスクワ## (全てモノラル・ライヴ) ※音源:Melodiya M10-44183#,##、Discocorp RR-527* ◎収録時間:70:15 |
| “造形美を確保しつつ確信を持って邁進し続けるA.フィッシャーのピアニズム!” | ||
|
||
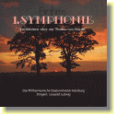 TRE-327 |
ルートヴィヒ/モーツァルト&ブラームス モーツァルト:歌劇「魔笛」序曲* 歌劇「後宮からの逃走」* ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲# 交響曲第1番ハ短調Op.68+ |
レオポルド・ルートヴィヒ(指) ハンブルク国立歌劇場O*、ハンブルク国立PO#,+ 録音:1960年代中期*、1959年頃#,+(全てステレオ) ※音源:独EUROPA E-177*、日COLUMBIA MS-101-K#、独maritim KLASSIK 47473NK+ ◎収録時間:73:37 |
| “質実剛健一辺倒ではないルートヴィヒの人間味豊かな職人芸!” | ||
|
||
 TRE-328 |
スワロフスキー~ベートーヴェン&シューベルト シューベルト:交響曲第8番「未完成」 ベートーヴェン:交響曲第7番イ長調* |
ハンス・スワロフスキー(指) ウィーン国立歌劇場O 録音:1957年(モノラル) ※音源:ORBIS 21224、仏VEGA 30MT-10.107* ◎収録時間:69:51 |
| “品格と内燃エネルギーを共存させるスワロフスキーの知られざる手腕!” | ||
|
||
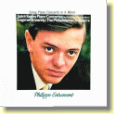 TRE-331 |
アントルモン~グリーグ&サン・サーンス グリーグ:ピアノ協奏曲 イ短調 Op. 16* サン・サーンス:ピアノ協奏曲第2番ト短調 Op. 22# ピアノ協奏曲第4番 ハ短調 Op. 44+ |
フィリップ・アントルモン(P) ユージン・オーマンディ(指) フィラデルフィアO 録音:1958年2月1日*、1964年5月12日#、1961年2月5日+(すべてステレオ) ※音源:蘭PHILIPS OS-592-S*、日COLUMBIA 836404VZ #,+ ◎収録時間:74:40 |
| “ヴィルトウオジティを誇示せず爽快な味わいを湛えるアントルモンの真価!” | ||
|
||
 TRE-333 |
ヘブラー~ステレオ初期のPHILIPS録音集Vol.2 ハイドン:ピアノ・ソナタ第52番 変ホ長調 Hob. XVI:52* モーツァルト:ピアノ協奏曲第19番K.459 ピアノ協奏曲第26番「戴冠式」(カデンツァ:ヘブラー作) |
イングリット・ヘブラー(P) コリン・デイヴィス(指)LSO 録音:1960年7月1-3日*、1961年12月2-5日(全てステレオ) ※音源:蘭PHILIPS 802737DXY*、英PHILIPS SGL-5813 ◎収録時間:78:22 |
| “強い信念があればこそ開花するヘブラーの凛としたピアニズム!” | ||
|
||
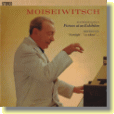 TRE-335 |
モイセイヴィチ/ステレオ名演集1~「展覧会の絵」他 ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 アンダンテ・ファヴォリ ヘ長調 WoO 57 ピアノ・ソナタ第26番「告別」 ムソルグスキー:展覧会の絵* |
ベンノ・モイセイヴィチ(P) 録音:1961年8月、1960年8月29-30日&9月1,2,4日*(全てステレオ) ※音源:米DECCA DL-710067、Brunswick SXA-4006* ◎収録時間:64:06 |
| “作品の内面を色彩豊かに描くモイセイヴィチの破格の名人芸!” | ||
|
||
 TRE-336 |
ケンドラ~MUZA録音集(リスト&ショパンVol.2 ショパン:ポーランド民謡による大幻想曲Op.13 「ドン・ジョヴァンニ」の「お手をどうぞ」による変奏曲Op. 2 リスト:ピアノ協奏曲第1番* ピアノ協奏曲第2番* |
ワディスワフ・ケンドラ(P) ヴィトルド・ロヴィツキ(指) ヤン・クレンツ(指)* ワルシャワ国立PO 録音:1960年6月28-29日、1962年2月10-18日*(全てステレオ) ※音源:MUZA SX-0076、日コロンビア OS-2138PM* ◎収録時間:73:03 |
| “圧倒的な技巧による眩い色彩と丹念な歌心の完全共存!” | ||
|
||
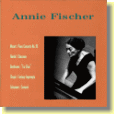 TRE-340 |
アニー・フィッシャーのソ連録音、他 モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番(カデンツァ;フンメル作)* ヘンデル:シャコンヌ.ト長調 HWV435 ベートーヴェン:エリーゼのために ショパン:幻想即興曲 シューマン:謝肉祭Op.9 |
アニー・フィッシャー(P) デイヴィッド・ジンマン(指)オランダ室内O* 録音:1965年*、1951&1955年(全てモノラル) ※音源:Discocorp RR-527*、MELODIA 5289-68 ◎収録時間:73:40 |
| “極限まで練り上げた末に到達した自然体のニュアンス!” | ||
|
||
 TRE-342 |
ラインスドルフ&ボストン響~厳選名演集Vol.7~ベートーヴェン 序曲「コリオラン」 バレエ音楽「プロメテウスの創造物」(抜粋)* 交響曲第7番イ長調Op.92 |
エーリヒ・ラインスドルフ(指) ボストンSO 録音:1967年11月21日、1967年3月6日*(全てステレオ) ※音源:英RCA SB-6733 、英RCA LSC-3032* ◎収録時間:73:40 |
| “セッション録音の丁寧な音作りだから気付かされる「ベト7」の美しさ!” | ||
|
||
 TRE-343 |
マルケヴィチ・イン・モスクワVol.1 ロッシーニ:「チェネレントラ」序曲 シューベルト:交響曲第3番ニ長調D.200* ブラームス:交響曲第4番ホ短調Op.98# |
イーゴリ・マルケヴィチ(指) ソビエト国立SO 録音:1962年5月18日、1964年11月30日*、1960年11月25日# 全てモスクワ音楽院大ホール・ライヴ(モノラル) ※音源:MELODIYA M10-47569、M10-47567# ◎収録時間:70:10 |
| “軽々に「爆演」など呼びたくない壮絶な迫力と造形力!” | ||
|
||
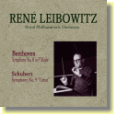 TRE-345 |
レイボヴィッツ~ベートーヴェン&シューベルト ベートーヴェン:交響曲第8番ヘ長調 Op. 93 シューベルト:交響曲第9番「ザ・グレート」D. 944* |
ルネ・レイボヴィッツ(指)ロイヤルPO 録音:1961年4月14日、1962年1月16-17日ウォルサムストウ・アセンブリー・ホール(ロンドン)* 共にステレオ ※音源:日ビクター RBS-6、伊RCA GL-32533* ◎収録時間:69:15 |
| “時代先取り!常識に囚われず音楽の鮮明化を徹底追求!” | ||
|
||
 TRE-346 |
カルロ・ゼッキの芸術Vol.1 ベルリオーズ:序曲「ローマの謝肉祭」 ウェーバー(ベルリオーズ編):舞踏への勧誘 ベルリオーズ:幻想交響曲* |
カレル・アンチェル(指) カルロ・ゼッキ(指)*、チェコPO 録音:1964年12月、1959年8月16-19日* (全てステレオ) ※音源:SUPRAPHON 10-8261-1 、SUAST-50103* ◎収録時間:69:57 |
| “やるべきことを全てやり尽くすカルロ・ゼッキの爆裂表現!” | ||
|
||
 TRE-348 |
デルヴォーのベートーヴェン 交響曲第5番 ハ短調「運命」 交響曲第6番ヘ長調「田園」* |
ピエール・デルヴォー(指)コンセール・コロンヌO 録音:1961年11月5日、1961年12月15日* パリ,サル・ワグラム(共にステレオ・ライヴ) ※音源:仏DUCRETET THOMSON SCC-502、SCC-501* ◎収録時間:70:04 |
| “ドイツ流儀に縛られないデルヴォーの確信的ダイナミズム!” | ||
|
||
 TRE-353 |
ラインスドルフ&ボストン響~厳選名演集Vol.8~ベートーヴェン&ブラームス ベートーヴェン:交響曲第2番 ブラームス:交響曲第1番* |
エーリヒ・ラインスドルフ(指) ボストンSO 録音:1967年3月6日、1963年9月29日*(共にステレオ) ※音源:英RCA LSC-3032、日Victor SHP-2334* ◎収録時間:77:25 |
| “驚異のバランス感覚で造形美を崩さないラインスドルフの執念の名演!” | ||
|
||
| 「チャイコフスキー:交響曲第5番」特集 | ||
 TRT-001 |
ハイドン:交響曲第99番 チャイコフスキー:交響曲第5番* |
ヨーゼフ・クリップス(指)VPO 録音:1957年9月9-14日、1958年9月15-16*(共にステレオ) ※音源:DECCA SXL-2098 , SXL-2109* |
| “宇野功芳氏激賞の意味を真に伝える、極上フラット盤の威力!” | ||
|
||
 TRT-002 |
チャイコフスキー:弦楽セレナード* 交響曲第5番ホ短調Op.64 |
ワルター・ゲール(指) ローマPO*、フランクフルト室内O 録音:1955頃(ステレオ) ※音源:英CONCERT HALL SMSC-2188*、仏 PRESTIGE DE LA MUSIQUE SR-9629、日CONCERT HALL SM-6108 ◎収録時間:76:04 |
| “オケのイタリア気質と相まった濃厚な節回しで翻弄する「チャイ5」!” | ||
|
||
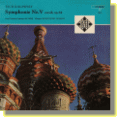 TRT-003 |
チャイコフスキー:フランチェスカ・ダ・リミニ 交響曲第5番ホ短調Op.64* |
コンスタンティン・イワーノフ(指) ソビエト国立SO 録音:1955年、1956年*(共にモノラル) ※音源:Melodiya C-1024221-009、独TELEFUNKEN LT-6624* ◎収録時間:69:23 |
| “ローカル色に安住せず、入念にニュアンスを注入したイワーノフの真価!” | ||
|
||
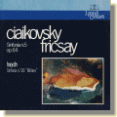 TRT-004 |
ハイドン:交響曲第100番「軍隊」 チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調Op.64* |
フェレンツ・フリッチャイ(指) ベルリンRIAS響、ベルリンRSO* 録音:1954年5月4日、1957年1月24日ライヴ* ※音源:伊LONGANESI PERIODICI GCL-70、GCL-38* ◎収録時間:66:19 |
| “安定感も燃焼度も申し分なし!フィリッチャイの比類なきロマンチシズム!” | ||
|
||
 TRT-005 |
グリューナー=ヘッゲ/グリーグ&チャイコフスキー グリーグ:「ペール・ギュント」第1組曲Op.46 「ペール・ギュント」第2組曲Op.55 チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調Op.64* |
オッド・グリューナー=ヘッゲ(指) オスロPO 録音:1959年、1958年6月*(全てステレオ) ※音源:英RCA CCV-5019、英Camden SND-5002* ◎収録時間:78:28 |
| “静かな闘志と確信がセンチメンタルなチャイコフスキーを払拭!” | ||
|
||
 TRT-006 |
スタインバーグのチャイコフスキー チャイコフスキー:弦楽セレナード 交響曲第5番ホ短調Op.64* |
ウィリアム・スタインバーグ(指) ピッツバーグSO 録音:1953年11月30日&1954年4月14日シリア・モスク・ピッツバーグ、1953年頃* ※音源:米Capitol P8290、英mfp MFP-2008* ◎収録時間:75:08 |
| “潔癖でありながら綺麗事ではないフレージングの意味深さ!” | ||
|
||
 TRT-007  ジョージ・ハースト |
ジョージ・ハースト~シューベルト&チャイコフスキー シューベルト:交響曲第8番「未完成」* チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調 |
ジョージ・ハースト(指) デンマーク王立O*、 ハンブルク・プロ・ムジカ 録音:1959年頃(ステレオ) ※音源:英SAGA XID-5029*、STXID-5381 & STXID-5046 ◎収録時間:66:25 |
| “ラトルに指揮者になるきっかけを与えたジョージ・ハーストの剛毅な芸風!” | ||
|
||
 TRT-008 |
オーマンディ没後30年記念~チャイコフスキー&シェーンベルク シェーンベルク:浄められた夜* チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調 |
ユージン・オーマンディ(指) フィラデルフィアO 録音:1950年3月19日アカデミー・オブ・ミュージック(フィラデルフィア)*、1950年11月19日タウン・ホール(フィラデルフィア) ※音源:米COLUMBIA ML-4316*、ML-4400 ◎収録時間:77:00 Cover Art Design By Alex Steinweiss |
| “年々熟成を重ねたオーマンディ・サウンドの原点がここに!” | ||
|
||
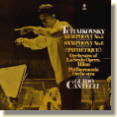 TRT-009(2CDR) |
カンテッリ~チャイコフスキー:交響曲集 交響曲第5番ホ短調Op.64* 交響曲第6番ロ短調「悲愴」 |
グィド・カンテッリ(指) ミラノ・スカラ座O*、 フィルハーモニアO 録音:1950年9月23-25日*、1952年10月 ※音源:W.R.C SHB-52 ◎収録時間:44:53+42:53 |
| “ストイックなのに柔軟!作品の魅力を再認識させるカンテッリの天才性!” | ||
|
||
 TRT-010 |
サヴァリッシュ~チャイコフスキー チャイコフスキー:バレエ音楽「白鳥の湖」から 第2幕;情景/第1幕:ワルツ 第2幕;小さい白鳥たちの踊り 第2幕;オデットと王子のパ・ダクシオン 第4幕;情景 交響曲第5番ホ短調Op.64* |
ウォルフガング・サヴァリッシュ(指) フィルハーモニアO、 アムステルダム・コンセルトヘボウO* 録音:1957年9月-1958年2月28日、1962年1月*(全てステレオ) ※音源:仏EMI CVD-955、蘭PHILIPS 835116AY* ◎収録時間:62:53 |
| 全盛期のコンセルトヘボウ管の魅力が、意欲満点のサヴァリッシュの棒で大全開!” | ||
|
||
 TRT-011 |
セルのチャイコフスキー&R=コルサコフ リムスキー=コルサコフ:スペイン奇想曲 チャイコフスキー:イタリア奇想曲* 交響曲第5番ホ短調Op.64# |
ジョージ・セル(指) クリーヴランドO 録音:1958年2月28日&3月14日、1958年2月28日*、1959年10月23-24日#(全てステレオ) ※音源:米EPIC BC-1002、BC-1064# ◎収録時間:76:07 |
| “セルの美学貫徹により初めて思い知る作品の偉大さ!” | ||
|
||
S.gif) TRT-012 |
岩城宏之&N響~ミュンヘンでの「チャイ5」 リスト:ハンガリー狂詩曲第5番 ハンガリー狂詩曲第4番 チャイコフスキー:交響曲第5番* |
岩城宏之(指) ウィーン国立歌劇場O、NHK響* 録音:1963年4月-5月バイヤリッシャー・ホール、1960年9月26日ミュンヘン・コングレス・ザールでのライヴ*(全てモノラル) ※音源:日Concert Hall M-2381、日Victor JV-2001* ◎収録時間:70:15 |
| “大和魂炸裂!全てを攻めの姿勢でやり尽くしたN響!” | ||
|
||
 TRT-013 |
クーベリック&VPO名演集Vol.1 シューベルト:交響曲第4番「悲劇的」 チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調* |
ラファエル・クーベリック(指)VPO 録音:1960年1月14-20日、11月21-24日* ウィーン・ムジークフェライン大ホール(共にステレオ) ※音源:独ELECTROLA C053-00651、STE-91135* |
|
||
 TRT-014 |
L.ルートヴィヒ/シューベルト&チャイコフスキー シューベルト:交響曲第4番「悲劇的」 チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調Op.64* |
レオポルド・ルートヴィヒ(指) ウィーンSO、 ハンブルク国立PO* 録音:1960年4月18-21日ウィーン・コンツェルトハウス、1960年3月28-30日ハンブルク・クルトゥアラウム*(共にステレオ) ※音源:独Opera St-1995、St-1916* ◎収録時間:76:47 |
| “S・イッセルシュテット以上にドイツの意地を露骨に誇示した熱き名演!” | ||
|
||
 TRT-015 |
サージェント/ショスタコーヴィチ&チャイコフスキー ショスタコーヴィチ:交響曲第9番 チャイコフスキー:交響曲第5番* |
マルコム・サージェント(指)LSO 録音:1959年10月27年、1959年5月20日&6月3日*(共にステレオ) ※音源:米EVEREST_SDBR-3054、日Victor_SRANK-5507* ◎収録時間:71:06 |
|
||
 TRT-016 |
R・シュトラウス:交響詩「ドン・ファン」 チャイコフスキー:交響曲第5番* |
ロリン・マゼール(指)VPO 録音:1964年5月4-6日、1963年9月13-14&6-18,20日* (全てステレオ) 1964 May 4-6、1963 September 13-14+16-18+20* ※音源:LONDON CS-6376、CS-6376* ◎収録時間:61:48 |
| “ウィーン・フィルの伝統美とマゼールの才気が融合したスパイシーな名演!”” | ||
|
||
 TRT-017 |
オーマンディのチャイ5(ステレオ第1回目) ヒンデミット:交響曲「画家マチス」 チャイコフスキー:交響曲第5番* |
ユージン・オーマンディ(指) フィラデルフィアO 録音:1962年1月17日、1959年1月25日*(共にステレオ) ※音源:英CBS 61347、COLUMBIA MS-6109* ◎収録時間:74:46 |
| “何度も味わいたい「画家マチス」の温かみに満ちた響き!” | ||
|
||
 TRT-018 |
マタチッチのロシア音楽1 ボロディン:「イーゴリ公」より 序曲/ダッタン人の行進/だったん人の踊り チャイコフスキー:交響曲第5番* |
ロヴロ・フォン・マタチッチ(指) フィルハーモニアO、チェコPO* 録音:1958年9月、1960年3月12-15日*(全てステレオ) ※音源:仏TRIANON TRI-33114 、独musicaphon BM30SL-1614* ◎収録時間:71:21 |
| ““マタチッチの強力なオーラでチェコ・フィル・サウンドが豹変!” | ||
|
||
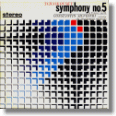 TRT-020 |
超厳選!赤盤名演集Vol.7~シルヴェストリによるスラブ作品集 ボロディン:「イーゴリ公」~だったん人の踊り* ブラームス:ハンガリー舞曲第5番/第6番(シュメリンク編) ドヴォルザーク:スラブ舞曲第1番Op.46-1/第2番Op.46-2 チャイコフスキー:交響曲第5番# |
コンスタンティン・シルヴェストリ(指) パリ音楽院O、フィルハーモニアO# 録音:1961年1月30日-2月1日*、1961年2月2日、1957年2月21-22日#(全てステレオ) ※音源:TOSHIBA WS-23 、WS-20# ◎収録時間:75:31 |
| “実行すべきことをしたに過ぎないシルヴェストリの純粋な狂気!” | ||
|
||
 TRT-021 |
ミトロプーロス/ボロディン、チャイコフスキー他 ボロディン(R=コルサコフ編):だったん人の踊り* イッポリトフ=イワーノフ:「コーカサスの風景」組曲第1番** チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調Op.64# |
ディミトリ・ミトロプーロス(指)NYO 録音:1953年4月20日*、1952年12月1日**、1954年3月27日# (全てモノラル) ※音源:米COLUMBIA CL-751*,** 、英PHILIPS SBL-5205 # ◎収録時間:79:04 |
| “絶頂時のミトロプーロスのだけが可能な壮絶無比な魂の叫び!” | ||
|
||
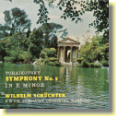 TRT-022 |
シュヒター/チャイコフスキー&シベリウス チャイコフスキー:イタリア奇想曲* シベリウス:交響詩「フィンランディア」** 悲しきワルツ# チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調## |
ヴィルヘルム・シュヒター(指) 北西ドイツPO 録音:1954年11月25日*、1957年8月29日**、1955年2月22日#、1956年10月22-25日##(全てモノラル) ※音源:伊EMIL QUM-6361、HMV XLP-20009## ◎収録時間:72:31 |
| “シュヒターの厳しい制御が活きた品格漂う名演奏!” | ||
|
||
 TRT-023 |
モーツァルト:歌劇「魔笛」序曲 ワーグナー:歌劇「タンホイザー」序曲 チャイコフスキー:スラブ行進曲* 交響曲第5番ホ短調Op.64# |
ジョン・バルビローリ(指)ハレO 録音:1959年3月30日&4月2,5-9日、1959年3月31日*、1959年3月30日-31日#マンチェスター・フリー・トラッド・ホール(全てステレオ) ※音源:Pye GSGC-2038、日TEICHIKU_UDL-3082-Y*,# ◎収録時間:73:42 |
| “敵なし!バルビローリならではの怒涛のロマン!!” | ||
|
||
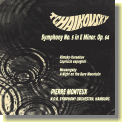 TRT-024 |
モントゥー&NDR響/ロシア音楽集 R=コルサコフ:スペイン奇想曲 ムソルグスキー(R=コルサコフ編):はげ山の一夜 チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調Op.64* |
ピエール・モントゥー(指) 北ドイツRSO 録音:1964年2月6-14日、1963年10月*(全てステレオ) ※音源:豪Concert Hall SMS-2361、米Concert Hall SMS-2333* ◎収録時間:68:20 |
| “90歳目前の老匠とは思えぬ意欲と色彩の大放射!” | ||
|
||
Copyright (C)2004 WAKUWAKUDO All Rights Reserved. |
 フランツ・アンドレ(1893-1975)は、ベルギーの指揮者。ブリュッセル音楽院で最初はヴァイオリンを専攻し、1912年にコンクールで優勝したほどの腕前でしたが、早くから指揮にも興味を示し、ベルリン留学時にはワインガルトナーに師事。1923年にベルギーに放送局が設立された折、そのオーケストラの第2指揮者に抜擢され、1935年にはベルギー国立放送交響楽団を設立。1958年まで。その初代首席指揮者を務めました。このオケは、ベルギー放送フィル、フランダース放送管と変遷し、現在のブリュッセル・フィルに至ります。
フランツ・アンドレ(1893-1975)は、ベルギーの指揮者。ブリュッセル音楽院で最初はヴァイオリンを専攻し、1912年にコンクールで優勝したほどの腕前でしたが、早くから指揮にも興味を示し、ベルリン留学時にはワインガルトナーに師事。1923年にベルギーに放送局が設立された折、そのオーケストラの第2指揮者に抜擢され、1935年にはベルギー国立放送交響楽団を設立。1958年まで。その初代首席指揮者を務めました。このオケは、ベルギー放送フィル、フランダース放送管と変遷し、現在のブリュッセル・フィルに至ります。