| 湧々堂HOME | 新譜速報: 交響曲 管弦楽曲 協奏曲 器楽曲 室内楽 声楽曲 オペラ バロック 廉価盤 シリーズもの マニア向け | |||
| 殿堂入り:交響曲 管弦楽 協奏曲 器楽曲 室内楽 声楽曲 オペラ バロック | SALE!! | レーベル・カタログ | チャイ5 | |
| MIRARE |
 音質のクオリティーもジャケットの装丁も いかにもフランスらしい気品を感じさせるレーベルです。 |
| 品番 | 内容 | 演奏者 |
|---|---|---|
|
MIR-001
|
アリスティド・イニャール(1822-1898):ヴェルヌの詩による歌曲集 全く単純に/春に/私たちの星/子守歌 二つの集団/甘い期待 ダフネ/スコットランドの思い出 スカンジナヴィアの歌/ トルコの歌/、他(全13曲) |
フランソワーズ・マセ(S) エマニュエル・ストロセル(P) |
|
||
|
MIR-002
|
バッハ:カンタータ集 第18番「天より雨下り、雪落ちて」BWV.18 第106番「神の時こそいと良き時」BWV.106 第150番「主よ、われ汝をこがれ望む」BWV.150 |
キャスリーン・フュージ(S) カルロス・メーナ(CT) ヤン・コボウ(T) ステファン・マクラウド(Bs) フィリップ・ピエルロ(指) リチェルカール・コンソート 録音:2004年9月 |
|
||
|
MIR-003
|
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ集 第12番変イ長調Op.26「葬送ソナタ」 第21番ハ長調Op.53「ワルトシュタイン」 第32番ハ短調Op.111 |
ニコラ・アンゲリッシュ(P) |
|
||
|
MIR-004
|
ラフマニノフ:24の前奏曲 | ボリス・ベレゾフスキー(P) 録音:2004年12月、グルノーブル文化会館ホール |
|
||
|
MIR-005
|
F・クープラン:王宮のコンセール~第1,2,7番 趣味の融合(新しいコンセール)~第14番 |
ダニエル・キュイエ(指) アンサンブル・ストラディヴァリア |
|
||
|
MIR-006
|
ペルゴレージ:スターバト・マーテル | ヌリア・リアル(S) カルロス・メーナ(CT) フィリップ・ピエルロ(指) リチェルカール・コンソート |
|
||
|
MIR-007
|
D・スカルラッティ:チェンバロ・ソナタ集 ニ短調 K.213/ニ長調 K.214 ロ短調 K.227/ニ長調 K.511 ト短調 K.8/ハ短調 K.56/ハ短調 K.526 ヘ長調 K.468/ヘ長調 K.525/ヘ短調 K.466 ヘ長調 K.366/ヘ長調 K.276/ヘ長調 K.151 ニ短調 K.517/ロ短調 K.27/ト長調 K.146 |
ピエール・アンタイ(Cemb) 録音:2005年 ※使用楽器:2002年 バルバストにてフィリップ・ユモー製、イタリア式 |
|
||
|
MIR-008
|
ラフマニノフ:ピアノ協奏曲全集Vol.1 ピアノ協奏曲第2番 ピアノ協奏曲第3番 |
ボリス・ベレゾフスキー(P) ドミトリー・リス(指)ウラルPO |
|
||
|
MIR-009
|
バッハ:オーボエ協奏曲 BWV.1055# 結婚カンタータ「今ぞ去れ, 悲しみの影よ」BWV.202* ヘンデル:ハープ協奏曲+ カンタータ「炎の中で」HWV.170* |
ヌリア・リアル(S)* ジョバンナ・ペシ(Hp)+ パトリック・ボージロー(Ob)# フィリップ・ピエルロ(指) リチェルカール・コンソート |
|
||
|
MIR-010
|
ヘンデル:組曲 ホ長調 HWV.430~「調子の良い鍛冶屋」変奏曲の主題 組曲第6番嬰ヘ短調 HWV.431 同第8番ヘ短調 HWV.433 同第3番二短調 HWV.436 同 ト短調 HWV.432~パッサカリアの主題と3つの変奏 シャコンヌ ト長調 HWV.435/プレスト/メヌエット |
アンヌ・ケフェレック(P) |
|
||
|
MIR-011
|
テレマン:組曲 ト長調「ふしだらな女」 オーボエとヴァイオリンの為の協奏曲 ハ短調 ターフェルムジーク 第1集 ヴァイオリンとトランペットの為の協奏曲 ニ長調 |
ダニエル・キュイエ(指) アンサンブル・ストラディヴァリア |
|
||
| MIR-012 |
パーセル:ヴィオールのためのファンタジア集 グランドによる3 声のファンタジア、 パヴァーヌ、3声のファンタジア、 4声のファンタジア、 一音に基づく5声のファンタジア、 6 声のファンタジア「イン・ノミネ」、 7声のファンタジア「イン・ノミネ」 |
リチェルカール・コンソート、 フィリップ・ピエルロ(指&Vn)、 上村かおり、 ライナー・ツィッパリング、 エマニュエル・バルサ、 ミエネケ・ファン・デル・ヴェルデン、 ソフィア・デニズ、 フランソワ・フェルナンデス、 ルイス・オクラビオ・サント、ジョバンナ・ペシ |
|
||
|
MIR-013
|
ハイドン:弦楽四重奏集Op.64-5「ひばり」 Op.33-1/Op.76-1 |
エボニーSQ |
|
||
|
MIR-014
|
ハイドン:ピアノ・ソナタ集 第38番/第39番/第54番/第59番 アンダンテと変奏曲 ヘ短調 |
イド・バル=シャイ(P) |
|
||
| MIR-017 |
バッハ:管弦楽組曲第1番&第4番、 ヴァイオリンとクラヴィーアためのソナタ 第4番 BWV 1017、 カンタータ「われは 憂いに沈みぬ」BWV 21 ~シンフォニア |
ピエール・アンタイ(指) ル・コンセール・フランセ、 アマンディ-ヌ・ベイェ(バロックVn)、 ルフレード・ベルナルディーニ(Ob) |
|
||
|
MIR-018(2CD)
|
フィリップ・ジュジアーノのショパン ショパン: 24の前奏曲集Op.28 24の練習曲集Ops.10 & 25 |
フィリップ・ジュジアーノ(P) |
|
||
|
MIR-019
|
ラフマニノフ:ピアノ協奏曲全集Vol.2 ピアノ協奏曲第1番嬰ヘ短調Op.1 ピアノ協奏曲第4番ト短調Op.40 パガニーニの主題による狂詩曲 |
ボリス・ベレゾフスキー(P) ドミトリー・リス(指)ウラルPO |
|
||
|
MIR-021
|
第26回ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ・フェスティバル公式アルバム (1)ドヴォルザーク:スラヴ舞曲 Op.72~「ドゥムカ」 (2)ムソルグスキー:展覧会の絵~「古城」 (3)ムソルグスキー:涙 (4)グリーグ:抒情小曲集Op.47-3~「メロディ」 (5)グリーグ:抒情小曲集 Op.54-2~「ノルウェーの農民行進曲」 (6)ルービンシュタイン:2つのメロディ~Op.3-1 (7)リャードフ:前奏曲 Op.13-2/ Op.10-1 (8)モーツァルト:ピアノ・ソナタ第14番ハ短調 K.457~第3楽章 (9)ハイドン:ピアノ・ソナタ第39番~第2 楽章 (10)ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイン」~1 楽章 (11)シューベルト:ピアノ・ソナタ第21番より第4 楽章 (12)シューマン:ダヴィッド同盟舞曲集~第14曲 (13)ツェルニー:指使いの技法(50番練習曲)Op.740より3曲 (14)ショパン:練習曲Op.10-3 (15)ムソルグスキー(コルベイニコフ編):「死の歌と踊り」~トレパーク |
(1)クレール・デセール&エマユエル・シュトロッセ(P) (2)ボリス・ベレゾフスキー(P) (3)ブリジット・エンゲラー(P) (4)(5)シャニ・ディリュカ(P) (6)ブリジット・エンゲラー(P) (7)ボリス・ベレゾフスキー(P) (8)アンヌ・ケフェレック(P) (9)イド・バル=シャイ(P) (10)ニコラ・アンゲリッシュ(P) (11)エマユエル・シュトロッセ(P) (12)クレール・デゼール(P) (13)ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) (14)フィリップ・ジュジアーノ(P) (15)アンドレイ・コロベイニコフ(P) 録音:2006年7月20日-8月22日 |
|
||
| MIR-022 |
チャイコフスキー:子供のアルバムOp.39、 ムソルグスキー:涙、 リャードフ:マズルカ、音楽玉手箱Op.32、 グリンカ:夜想曲「別れ」、 アラビエフ:ナイチンゲール、 ショスタコーヴィッチ:人形の踊り-7 つの子供の小品~「踊り」「抒情的なワルツ」「ポルカ」「おどけたワルツ」、 ラフマニノフ:イタリア・ポルカ、 ルービンシュタイン:2 つのメロディOp.3-1、 諸民族の舞曲集~「ポルカ」Op.82-7、 ペテルブルクの夜会~「ロマンス」Op.44-1、 スクリャービン:2 つの左手のための小品~「夜想曲」Op.9 |
リジット・エンゲラー(P) 録音:2006 年6 月6,7 & 8 日フォントヴロー王立大修道院 |
|
||
| MIR-023(2CD) |
ツェルニー:指使いの技法(50番練習曲)Op.740、 リスト:2つの演奏会用練習曲「森のざわめき」「小人の踊り」、 3つの演奏会用練習曲より「軽やかさ」、 ヘラー:4つの練習曲 |
ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) |
|
||
| MIR-024 |
シューマン:ダヴィッド同盟舞曲集Op.6 、 間奏曲Op.4 |
クレール・デゼール(P) |
|
||
| MIR-025 |
シューベルト:ピアノ・ソナタ21番変ロ長調D.960、 3つの小品 |
エマニュエル・シュトロッセ(P) 録音:2005年6月 |
|
||
| MIR-026 |
グリーグ:ピアノ協奏曲、 抒情小曲集 |
シャニ・ディリュカ(P)、 エイヴィン・グルベルグ・イェンセン(指) ボルドー・アキテーヌ国立O |
|
||
| MIR-027 |
F・クープラン:クラヴサン作品集 大殿様、 シャブイの王女またはモナコのミューズ、 軽はずみな女、フロール、メヌエット、 二重生活者、嘆きのほおじろ、 芸術家、おじけた紅ひわ、 キタイロンの鐘、勝利者の歓喜、 プレリュード第6番、機知、 フランスのフォリアまたはドミノ、葦、 プレリュード第8番、 そしらぬ顔であざ笑う女、うなぎ、 交差するメヌエット、手品 |
ピエール・アンタイ(Cemb) |
|
||
|
MIR-028
|
コルボのフォーレ「レクイエム」 フォーレ:レクイエム(1893年版)Op.48 アヴェ・ヴェルム・コルプスOp.65-1 アヴェ・マリアOp.67-2 タントゥム・エルゴOp.55 フォーレ(メサジェ編):ヴレヴィユの漁師達のミサ |
アナ・クインタンス(S) ペーター・ハーヴィー(Br) ミシェル・コルボ(指) シンフォニア・ヴァルソヴィア ローザンヌ声楽アンサンブル |
| MIR-029 |
バルトーク:弦楽四重奏第1番~第3番 | エベーヌSQ |
|
||
| MIR-030 |
ポーランド女王のためのトンボー バッハ:ミサ イ長調BWV.234、 カンタータ第198番「候妃よさらに一条の光を(追悼頌歌)」 BWV.198、 前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544、 コラール・プレリュード「我心よりこがれ望む」BWV.727 |
フィリップ・ピエルロ(指) リチェルカール・コンソート、 キャサリン・フーグ(S)、 カルロス・メーナ(A)、 ヤン・コボウ(T)、 ステファン・マクラウド(Bs)、 フランシス・ヤコブ(Org: ゴットフリート・ジルバーマン製作/1737 ポニッツ教会) 録音:2006年10月 |
|
||
| MIR-033 |
パーセル:わずらわしき世の中よ~歌曲、室内楽曲集 わずらわしき世の中よCease, anxious World/ 新しいアイルランドの歌 ト長調 Z.646 A new irishtune/ 優しき音と美しい調べSoft Notes, and gently rais’d/ 新しいグラウンド ホ短調 Z.T682 Anew Ground/日陰の冷たく心地よき流れの中でA midst the Shades/王子 A Prince/アミンタスが初めて口づけを求めし時When first Aminta’s su’d for a kiss/ ここに神がHere the deities/ プレリュード Prelude/ トリオ・ソナタ Z.780 Trio sonata/ 薔薇より甘く Sweet than roses/ グラウンドZD.221 Ground/ひとときの音楽 Music for a while/愛らしい素敵な人 Dear pretty youth/ソナタ(G . フィンガー作曲)/ 嘆きの歌 O let me weep |
ラ・レヴーズ 【ジュリー・ハスラー(S)、 ステファン・デュデルメル(Vn)、 フローレンス・ボルトン(ヴィオール)、 アンジェリーク・モイヨン(Hp)、 ベルトラン・キュイエ(Clavcin)、 バンジャマン・ペロー(テオルボ&指)】 録音:2007年 |
|
||
| MIR-034 |
ファリャ:歌劇「恋は魔術師」(1915年版) | J.F. エッセール(指) ポワトゥ=シャラントO、 アントニア・コントラレス(フラメンコ歌手)、 ジェローム・コレアス(Bs)、 シャンタール・ペロー(S)、 エリック・ウシエ(T) |
|
||
| MIR-036 |
ビゼー:交響曲第1番、 組曲「子供の遊び」、 シャブリエ:田園組曲 |
フランソワ=グザヴィエ・ロス(指) レ・シエクル |
|
||
| MIR-038 |
J.S.バッハ:フルート・ソナタ集 フルートと通奏低音のためのソナタ.ト短調BWV1034、 フルートと通奏低音のためのソナタ.ハ長調BWV1033、 フルートとチェンバロのための組曲.ニ短調BWV997、 フルートと通奏低音のためのソナタ.ホ長調BWV1035、 フルートと通奏低音のためのソナタ.ト短調BWV1030b |
ヒューゴ・レーヌ(フラウト・トラヴェルソ)、 ピエール・アンタイ(Cemb) エマニュエル・ギゲス(Gamb) 録音:2006年12月5-7日、2007年4月21-23日 ルールマラン城(フランス) |
|
||
|
MIR-040
|
フランソワ・クープラン:ヴィオール作品集 ヴィオール組曲第1番/組曲第2番 コンセール第1番/コンセール第2番 |
フィリップ・ピエルロ、 エマニュエル・バルサ(ヴィオール) エドゥアルド・エグエス(テオルボ/G) ピエール・アンタイ(Cemb) 録音:2007年2月13日-15日、ルールマラン、フランス |
| MIR-041 |
ニコラウス・ブルーンス:深き淵より、主は天に御座を堅く据え ディートリヒ・ベッカー:パヴァーヌ第5番、ソナタ第3番 フランツ・トゥンダー:最愛のイエス、我に与えたまえ ブクスデフーデ:我はシャロンの花 ヨハン・クリストフ・バッハ:ラメント「神よなぜわたしに怒りたもうか」 |
フィリップ・ピエルロ(指) リチェルカール・コンソート、 ステファン・マクラウド(Bs) 録音:2007年3月 |
|
||
|
MIR-042
|
ドヴォルザーク:スラヴ舞曲集第1集&第2集 (全曲;ピアノ4手連弾) |
クレール・デセール&エマユエル・シュトロッセ(P) |
| MIR-043 |
シューベルト:即興曲第3番変ト長調D.899:Op.90、 クッペルヴィーザー・ワルツ、 ハンガリー風のメロディロ短調D.817、 さすらい人幻想曲D760:Op.15、 シューベルト(リスト編):影法師、 都会、海辺に、て、すみか、 セレナーデ、春の想い、連祷、 水車小屋と小川、さすらい |
ブリジット・エンゲラー(P) 録音:2007年9月 |
|
||
| MIR-044(2CD) |
バッハ:平均律クラヴィーア曲集第2巻 | シャオ・メイ・シュ(P) |
|
||
| MIR-045 |
シューベルト:交響曲第9番「グレート」 | クワメ・ライアン(指) ボルドー・アキテーヌ国立O |
|
||
| MIR-046 |
ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ・フェスティバルVol.2 (1)ドヴォルザーク:スラヴ舞曲 Op.72~“ドゥムカ” (2)ムソルグスキー:展覧会の絵~“古城” (3)ムソルグスキー:涙 (4)グリーグ:抒情小曲集Op.47-3~“メロディ” (5)グリーグ:抒情小曲集Op.54-2~“ノルウェーの農民行進曲” (6)ルービンシュタイン:2つのメロディ~Op.3-1 (7)(8)リャードフ:前奏曲 Op.13-2, Op.10-1 (9)モーツァルト:ピアノ・ソナタ 第14番~第3楽章 (10)ハイドン:ピアノ・ソナタ第39番~第2楽章 (11)ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイン」~第1楽章 (12)シューベルト:ピアノ・ソナタ第21番~第4楽章 (13)シューマン:ダヴィッド同盟舞曲集~第14曲 (14)(15)(18)カール・ツェルニー:指使いの技法(50番練習曲)Op.740 より (16)ショパン:エチュードOp.10-3 (17)ムソルグスキー(コルベイニコフ編):トレパーク歌曲集「死の歌と踊り」より |
(1)クレール・デセール&エマユエル・シュトロッセ(P)、 (2)ボリス・ベレゾフスキー(P)、 (3)ブリジット・エンゲラー(P)、 (4)(5)シャニ・ディリュカ(P)、 (6)ブリジット・エンゲラー(P)、 (7)(8)ボリス・ベレゾフスキー(P)、 (9)アンヌ・ケフェレック(P)、 (10)イド・バル=シャイ(P)、 (11)ニコラ・アンゲリッシュ(P)、 (12)エマユエル・シュトロッセ(P)、 (13)クレール・デゼール(P)、 (14)(15)(18)ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P)、 (16)フィリップ・ジュジアーノ(P) (17)アンドレイ・コロベイニコフ(P) |
|
||
 MIR-047 |
ショパン:ピアノ協奏曲第1番&第2番 | ボリス・ベレゾフスキー(P)、 ジョン・ネルソン(指)パリ室内O |
|
||
| MIR-048 |
バッハ:ゴルトベルク変奏曲 | シャオ・メイ・シュ(P) |
|
||
| MIR-049 |
ショーソン:ピアノ三重奏曲ト短調Op.3、 ラヴェル:ピアノ三重奏曲 |
ショーソン・トリオ [フィリップ・タレク(Vn)、 アントワーヌ・ランドウスキ(Vc)、 ボリス・ド・ラロシェランベール(P)] |
| MIR-050 |
スターバト・マーテル 作者不詳:サルヴェ・レジーナ、 ベルターリ:ソナタ第4番ニ短調、 フックス:アヴェ・マリア K151、 レオポルドⅠ世:レジナ・チェリ、 サンチェス:スターバト・マーテル、 シュメルツァー:ソナタ第4/9/11/12番、 ジアーニ:アルマ・レデンプトリス・マーテル |
カルロス・メーナ(C-T)、 フィリップ・ピエルロ(指&ヴィオラ・ダ・ガンバ)、 リチェルカーレ・コンソート [フランシス・フェルナンデス(Vn)、 ルイス・オターヴィオ・サントス(Vn)、 上村かおり(ヴィオラ・ダ・ガンバ)、 ミーネケ・ヴァン・デル・ヴェルデン(ヴィオラ・ダ・ガンバ) フランク・コピエテルス(Vn) ジョバンナ・ペシ(ハープ) ルカ・グリエルミ] |
|
||
| MIR-051 |
シューベルト:ミサ第6番D.950 | ミシェル・コルボ(指) ローザンヌCO&cho、 リジット・フルニエ(S)、 ジャッキー・カーン(A)、 イェルク・デュルミュラー(T)、 アンドレアス・カラシアク(T)、 ガストン・シスター(Bs) 録音:2007年10月29、30日 |
|
||
| MIR-052 |
シューベルト:弦楽五重奏Op.114「ます」、 ピアノ三重奏第2番Op.100 |
トリオ・ショーソン、 ペネロペ・ポアンシュヴァル(Cb)、 井上典子(Va) |
|
||
| MIR-057 |
バッハ:カンタータ第131番「深き淵より、我、主よ、汝に呼ばわる」BWV131、 カンタータ第182番「天の王よ汝を迎えまつらん」BWV182、 カンタータ第4番「キリストは死の縄目につながれたり」BWV4 |
フィリップ・ピエルロ(指) リチェルカール・コンソート、 キャサリン・フュージュ(S)、 カルロス・メーナ(C-T)、 ハンス=イェルク・マンメル(T)、 ステファン・マクラウド(Bs) 録音:2007年11月 |
|
||
| MIR-058(2CD) |
フランソワ・フランクール&フランソワ・ルベル:叙情悲劇「ピラムとティスベ」 | トーマス・ドイル(ピラム)、 ユディット・ヴァン・ワンロイ(ティスペ)他 ダニエル・キュイエ(指) アンサンブル・ストラディヴァリア 録音:2007年5月(ナント) |
|
||
| MIR-059 |
メトネル:作品集 3つのロマンスOp.3~のぞみの日々も流れ去り(プーシキン)*、 4つのおとぎ話Op.34~第2曲ホ短調、 プーシキンの7つの詩Op.29~第4曲「馬」*、 3つのおとぎ話Op.42~第1曲ヘ短調、8つの詩Op.24~なぜ水の上に柳は垂れる(チュッチェフ)#、 プーシキンの詩による7つの歌Op.52~第2曲「カラス」#、 フェート,ブリューソフ,チュッチェフによる7つの詩Op.28~第5曲「春の静けさ」(ウーラント/チュッチェフ)*、 2つのおとぎ話Op.14~ヘ短調「オフィーリアの歌」/ホ短調「騎士の行進」、 4つのおとぎ話Op.35~第4曲ニ短調、2つのおとぎ話Op.48~第2曲ト短調(妖精のおとぎ話)、 ゲーテの詩による9つの歌Op.6~第3曲「妖精の歌」#、 ハイネの3つの詩Op.12~第1曲「いとしい恋人君の手を」*、 ゲーテの詩による9つの歌Op.6~第5曲「可愛い子供よ」*、 8つの詩Op.24~第1曲「昼と夜(チュッチェフ)」#、3つのロマンスOp.3~第1曲「聖なる僧院の門の傍らに(レールモントフ)」*、 8つの詩Op.24~第4曲夕暮(チュッチェフ)」#、8つの詩Op.24~第7曲「ささやき、微かな吐息(フェート)」*、 プーシキンの6つの詩Op.36~第2曲「花」#、チュッチェフとフェートによる5つの詩Op.37~第4曲ヘ短調#、 4つのおとぎ話Op.26~第2曲変ホ長調、チュッチェフとフェートによる5つの詩Op.37~第1曲「眠れずに(チュッチェフ)」#、 プーシキンの7つの詩Op.29~第7曲「呪文」*、2つの詩Op.13~第1曲「冬の夕べ(プーシキン)」*/2つのおとぎ話Op.20~第2曲ロ短調「鐘」 |
ボリス・ベレゾフスキー(P)、 イヤナ・イヴァニロヴァ(S)#、 ヴァシリー・サヴェンコ(Bs)* 録音:2007年12月 |
|
||
| MIR-060(2CD) |
バッハ:イギリス組曲第2番、 ショパン:バラード第2番、夜想曲Op.15-1、 ラヴェル:ラ・ヴァルス、 リスト:ピアノ・ソナタロ短調、 ラヴェル:古風なメヌエット、 ストラヴィンスキー:練習曲ヘ長調Op.7-4、 ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ:バガテル、 バッハ(フェインベルグ編):オルガンのためのソナタ第5番より「ラルゴ」 |
ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) 録音:2007年11月17日 サントリーホール |
|
||
| MIR-061 |
スクリャービン:ピアノ・ソナタ第4番、 2つの詩曲op.32、ピアノ・ソナタ第5番、 2つの詩曲op.69、ピアノ・ソナタ第8番、 2つの詩曲op.71、 ピアノ・ソナタ第9番「黒ミサ」、 詩曲「炎に向かって」op.72 |
アンドレイ・コロベイニコフ(P) |
|
||
| MIR-062 |
メンデルスゾーン:ピアノ曲集 無言歌集第1巻~ホ長調「甘い思い出」Op.19-1、 無言歌集第6巻~嬰ヘ短調「失われた幻影」Op.67-2/変ホ長調「瞑想」Op.67-1/ハ長調「紡ぎ歌」Op.67-4、 無言歌集第7巻~ニ長調「悲歌」Op.85-4、 無言歌集第8巻~ホ短調「寄る辺なく」Op.102-1/ト短調「そよぐ風」Op.102-4/イ長調「楽しき農夫」Op.102-5、 舟歌Op.102-7(遺作)、厳格な変奏Op.54、ピアノ三重奏曲第1番Op.49、 幻想曲嬰ヘ短調「スコットランド・ソナタ」Op.28 |
シャニ・ディリュカ(P) |
|
||
|
MIR-064
|
Stella Matutina ~朝の星 | ヴォクス・クラマンティス ウィークエンド・ギター・トリオ |
| MIR-065 |
ハイドン:弦楽四重奏曲ト長調Op.54-1、 ト短調「騎手」Op.74-3、 変ロ長調「日の出」Op.76-4 |
モディリアーニSQ [フィリップ・ベルナール(Vn)、 ロイック・リオ(Vn)、 フランソワ・キエフェル(Vc) ローラン・マルフェング(Va)] |
|
||
| MIR-070 |
ラフマニノフ:2台のピアノのための組曲第1番Op.5「幻想的絵画」、2台のピアノのための組曲第2番Op.17* チャイコフスキー:組曲「眠れる森の美女」(4手版=ラフマニノフ編) |
ブリジット・エンゲラー(P)、 ボリス・ベレゾフスキー(P) 録音:2006年7月、2007年12月* 言語:フランス語、字幕:英語 DVDトータル・タイム:18分 |
|
||
| MIR-072 |
フォーレ:ピアノ作品全集Vol.1 バラードOp.19/マズルカOp.32 ヴァルス・カプリス(全4曲) 前奏曲Op.103 |
ジャン=クロード・ペネティエ(P) 録音:2008年1月 |
|
||
| MIR-073 |
シューベルト(レネゲイズ編):3つの軍隊行進曲D733より、 楽興のときD.780より、 セレナードより、即興曲より、 スケルツォD593より、 弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」より、 交響曲「未完成」より、 「魔王」D328、アヴェ・マリアD839 |
レネゲイズ・スティール・バンド・オーケストラ 録音:2008年2月、ナントにおけるラ・フォル・ジュルネ音楽祭のライヴ |
|
||
| MIR-074 |
ラインケン:トリオ・ソナタ集「音楽の園」より第1番イ短調、 第4番ニ短調 ブクステフーデ:ソナタ第1番ト長調BuxWV271、 ソナタハ長調BusWV266、ソナタヘ長調BuxWV269、 シャコンヌハ短調BuxWV159(2台のオルガン用編曲) |
ラ・レヴーズ バンジャマン・ペロー(テオルボ&指) 録音:2008年7月 |
|
||
|
MIR-075
|
ショパン:マズルカ集(30曲) 第47番イ短調/第7番ヘ短調/第10番変ロ長調/ 第11番ホ短調/第12番変イ長調/第13番イ短調/ 第56番変ロ長調/第14番ト短調/第15番ハ長調/ 第16番変イ長調/第17番変ロ短調/第42番ト長調/ 第44番ハ長調/第18番ハ短調/第19番ロ短調/ 第20番変ニ長調/第21番嬰ハ短調/第22番嬰ト短調/ 第23番ニ長調/第24番ハ長調/第25番ロ短調/ 第26番嬰ハ短調/第29番変イ長調/ 第42番イ短調「エミール・ガイヤール」/ 第32番嬰ハ短調/第45番イ短調/第43番ト短調/ 第40番ヘ短調/第41番嬰ハ短調/第49番ヘ短調 |
イド・バル=シャイ(P) |
| MIR-076 |
ハイドン:ピアノ・ソナタ第38番ヘ長調Hob.XVI..23、ソナタ第53番ホ短調Hob.XVI..34、 アンダンテと変奏曲ヘ短調Hob.XVII..6、 ソナタ第50番ハ長調Hob.XVI..50、 ソナタ第62番変ホ長調Hob.XVI..52 |
シャオ・メイ・シュ(P) 録音:2008年6月パリ |
|
||
| MIR-078 |
08年ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ・フェスティバル公式CD (1)ラフマニノフ:2台のピアノのための組曲第1番Op.5「幻想的絵画」~バルカローレ (2)メンデルスゾーン:無言歌第6巻~嬰ヘ短調「失われた幻影」Op.67-2 (3)バッハ:前奏曲第3番ハ長調BWV872 (4)フォーレ:前奏曲第7番イ長調Op.103 (5)スクリャービン:2つの詩曲Op.32~アンダンテ・カンタービレ (6)ショパン:夜想曲ヘ長調Op.15-1 (7)ショパン:バラード第2番 (8)メンデルスゾーン:無言歌第1巻~ホ長調「甘い思い出」 Op.19-1 (9)ヘンデル:組曲ト短調 HWV432~パッサカリアの主題と3つの変奏より第1変奏 (10)シューベルト0(リスト編):セレナーデ (11)リスト:巡礼の年第2年補遺「ヴェネツィアとナポリ」-舟歌 (12)スクリャービン:詩曲「炎に向かって」Op.72 (13)メトネル:4つのおとぎ話Op.34~第2曲ホ短調 (14)チャイコフスキー:組曲「眠れる森の美女」(4手版=ラフマニノフ編) (15)ドヴォルザーク:スラヴ舞曲Op.46 (16)メトネル:2つのおとぎ話Op.20~第2曲ロ短調「鐘」 |
(1)(10)(14)ブリジット・エンゲラー、 (1)(13)(14)(16)ボリス・ベレゾフスキー、 (2)(8)シャニ・ディリュカ、 (3)シャオ・メイ・シュ、 (4)ジャン=クロード・ペネティエ、 (5)(12)アンドレイ・コロベイニコフ、 (6)(7)ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ、 (9)アンヌ・ケフェレック、 (11)ニコラ・アンゲリッシュ、 (15)クレール・デセール&エマユエル・シュトロッセ(P) |
|
||
| MIR-079 |
サン=サーンス:ピアノ協奏曲第2番、 ピアノ協奏曲第5番「エジプト風」 |
ブリジット・エンゲラー(P)、 アンドレア・クイン(指)パリCO 録音:2008年6月ルヴァロワ・ペレ(フランス) |
|
||
| MIR-080(1CD+DVD) |
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ集 第29番「ハンマークラヴィーア」、 第19番ト短調Op.49-1、 第20番ト長調Op.49-2、 エリーゼのためにイ短調WoO59 ■特典DVD ハンマークラヴィーアの真髄へ迫る旅(ルネ・マルタン出演) |
ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) |
|
||
| MIR-081(2CD) |
バッハ:ミサ曲ロ短調BWV.232 | 谷村由美子(S)、 ヴァレリー・ボナール(Ms)、 セバスチャン・ドロイ(T)、 クリスチャン・イムラー(Bs)、 ミシェル・コルボ(指) ローザンヌ声楽&器楽アンサンブル 録音:2008年8月 La Fermede Villefavard(仏リムザン地方) |
|
||
| MIR-082 |
バッハ~CONTEMPLATION(瞑想) 「主イエス・キリストよ、われ汝に呼ばわる」BWV639(ブゾーニ編) カプリッチョ「最愛の兄の旅立ちにあたって」変ロBWV992 平均律クラヴィーア曲集第1巻~プレリュード第4番 嬰ハ短調BWV849 平均律クラヴィーア曲集第1巻~プレリュード第22番 変ロ長調BWV867 カンタータ第22番「イエスは十二使徒をひき寄せたまえり」BWV22(コーエン編) 平均律クラヴィーア曲集第1巻~プレリュード第8番 変ホ短調BWV853 トッカータ,アダージョとフーガBWV564(ブゾーニ編) イギリス組曲第2番~サラバンドBWV807 オルガン協奏曲ニ短調BWV596(原曲:ヴィヴァルディ) フランス組曲第1番~サラバンドBWV812、イタリア協奏曲ヘ長調BWV971 オーボエ協奏曲~アダージョ(原曲:マルチェッロ) 平均律クラヴィーア曲集 第2巻よりプレリュード第14番 嬰ヘ短調BWV883 プレリュード.ロ短調BWV855a、プレリュード.ホ短調(以上シロティ編) ゴルトベルク変奏曲~アリア、「主よ人の望みの喜びよ」BWV147(ヘス編) イギリス組曲第3番~サラバンドBWV808、シチリアーノ変ホ長調BWV1031(ケンプ編) 「来たれ、異教徒の救い主よ」BWV659a(ブゾーニ編) 「神の時は最上の時なり」(哀悼行事のソナティナ)BWV106(クルターク編/連弾* |
アンヌ・ケフェレック(P)、 ガスパール・デヘヌ(P)* 録音:2008年9月 La Ferme de Villefavard(仏リムザン地方) |
|
||
| MIR-084 |
リスト:詩的で宗教的な調べ(全10曲) | ブリジット・エンゲラー(P) 録音:2010年4月 |
|
||
| MIR-085 |
バッハ:チェンバロ協奏曲第1番ニ短調BWV1052、 チェンバロ協奏曲第7番ト短調BWV1058 チェンバロ協奏曲第5番ヘ短調BWV1056、 チェンバロ協奏曲第4番イ長調BWV1055 |
ダニエル・キュイエ(Vn&指) ストラディヴァリア、 ベルトラン・キュイエ(Cemb) 録音:2008年12日1-4日 |
|
||
| MIR-086(2CD) ★ |
バッハ:無伴奏チェロ組曲(全6曲) | タチアナ・ヴァシリエヴァ(Vc) 録音:2008年11月(シオン、スイス) |
|
||
| MIR-087 |
ラフマニノフ:交響曲第2番 | クワメ・ライアン(指) ボルドー・アキテーヌ国立O 録音:2008年10月 |
|
||
| MIR-088 |
W.F.バッハ:幻想曲、ソナタ、フーガ、ポロネーズ ポロネーズ第1番ハ長調、 フーガ第1番ハ長調、 ソナタ.ト長調FK7、 フーガ第2番ハ短調、 幻想曲ハ短調FKnv2*、 ポロネーズ第10番ヘ短調*、 フーガ第3番ニ短調、 幻想曲ニ短調FK19、 ソナタ.ニ長調FK3、 ポロネーズ第11番ト長調、 ポロネーズ第7番ホ長調、 ポロネーズ第8番ホ短調*、 フーガ第6番ホ短調、 幻想曲イ短調FK23 |
モード・グラットン(Cemb、クラヴィコード*) |
|
||
| MIR-089 |
ショパン:ピアノ三重奏曲ト短調Op.8 序奏と華麗なポロネーズOp.3 リスト:「オーベルマンの谷」~トリスティア |
トリオ・ショーソン |
| MIR-090 |
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第30番 6つのバガテル ピアノ・ソナタ第24番/第17番 |
アンドレイ・コロベイニコフ(P) 録音:2009年5月 |
| MIR-091 |
ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ・フェスティバル公式アルバムVol.3 (1)バッハ(ジロティ編):プレリュード ロ短調 BWV855a (2)ソレル:第87番ト短調R.416 (3)ハイドン:ソナタ第62番変ホ長調 Hob. XVI:52より (4)ハイドン:ソナタ第38番ヘ長調 Hob.XVI..23より (5)シューベルト(リスト編):水車小屋と小川 (6)ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第19番より (7)リスト:巡礼の年第2年「イタリア」~第2曲「物思いに沈む人」 (8)メンデルスゾーン:幻想曲嬰ヘ短調「スコットランド・ソナタ」Op.28より (9)ショパン:マズルカ ロ短調Op.33 (10)ショパン:マズルカ 変ロ短調Op.24 (11)フォーレ:ロマンスOp.17 (12)メトネル:2つのおとぎ話 Op.48~第2曲ト短調(妖精のおとぎ話) (13)スクリャービン:ピアノ・ソナタ第4番より (14)ボロディン:小組曲より (15)ドヴォルザーク:スラヴ舞曲集 Op.72より (16)チャイコフスキー:組曲「眠れる森の美女」(4手版=ラフマニノフ編) |
(1)アンヌ・ケフェレック(P) (2)ルイス・フェルナンド・ペレス(P) (3)アンヌ・ケフェレック(P) (4)シャオ・メイ・シュ(P) (5)ブリジット・エンゲラー(P) (6)ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) (7)ニコラ・アンゲリッシュ(P) (8)シャニ・デュリカ(P) (9)イド・バル=シャイ(P) (10)イド・バル=シャイ(P) (11)ジャン・クロード・ペネティエ(P) (12)ボリス・ベレゾフスキー(P) (13)アンドレイ・コロベイニコフ(P) (14)ボリス・ベレゾフスキー(P) (15)クレール・デセール&エマユエル・シュトロッセ(P) (16)ブリジット・エンゲラー&ボリス・ベレゾフスキー(P) |
|
||
 MIR-096 |
アンヌ・ケフェレック~ショパン ショパン:ポロネーズ. 変ロ長調KK.IV/1(1817) ポロネーズ.ト短調S1/1(1817) ポロネーズ.変イ長調KK.IV/a2(1821) マズルカ.イ短調Op.7-4 ポロネーズ.ヘ短調Op.71-1 ソステヌート.変ホ長調(1840) カンタービレ.変ロ長調(1834) ノクターン嬰ハ短調遺作(1830) 幻想即興曲/ワルツOp.70-2 マズルカOp.50-3/子守歌/舟歌 スケルツォ第4番 ワルツイ短調KK.IVb/11,P2/11 バラード第4番Op.52(1842) マズルカOp.67-4(1848) |
アンヌ・ケフェレック(P) 録音:2009年11月フランス・リモージュ |
|
||
| MIR-099 |
リスト:ピアノ・ソナタロ短調* 巡礼の年第2年補遺「ヴェネツィアとナポリ」 メフィスト・ワルツ第1番 超絶技巧練習曲~第11番「夕べの調べ」# ショパン:ワルツ第5番変イ長調Op.42「大円舞曲」 |
ボリス・ベレゾフスキー(P) 録音:2009年3月15日ロイヤル・フェスティヴァル・ホール・ライヴ* 2009年6月26日フェスティヴァル・デ・ラ・グランデ・メレ・ライヴ |
| MIR-100 |
フォーレ:ピアノ作品集vol.2 3つの無言歌Op.17(全3曲) 3つの夜想曲op.33(全3曲) 即興曲第1番変ホ長調Op.25 舟歌第1番イ短調op.26 夜想曲第4番変イ長調op.36 夜想曲第5番変ロ長調Op.37 舟歌第2番ト長調Op.41 舟歌第3番変ロ長調op.42 |
ジャン=クロード・ペヌティエ(P) 録音:2009年10月 |
|
||
| MIR-101 |
アントニオ・ソレル:ソナタ集 第129番R.451ホ短調/前奏曲第2番ト短調 第87番R.416 ト短調/第42番R.377ト短調 第18番R.353ハ短調//第19番R.354ハ短調 第24番R.359ニ短調/第25番R.360ニ短調 第54番R.389ニ短調/第15番R.350ニ短調 第85番R.414嬰ヘ短調/第90番R.419嬰ヘ長調 第154番R.472変ニ長調/第88番R.417変ニ長調 第86番R.415ニ長調/第84番R.413ニ長調 |
ルイス・フェルナンド・ペレス(P) 録音:2008年5月27-30日(マドリッド) |
|
||
| MIR-102(1CD+DVD) |
バッハ:マニフィカト マニフィカトBWV243、 マニフィカト「わが心は主をあがめ」にもとづくフーガBWV733、 ミサ曲ト短調BWV235、 プレリュードとフーガ ト長調BWV541 特典DVD:マニフィカト 監督:ピエール=ユベール・マルタン NTSC43mm言語:仏、英 |
フィリップ・ピエルロ(指) リチェルカーレ・コンソート 録音:2009年4月 |
|
||
| MIR-103(2CD) |
バッハ:平均律クラヴィーア曲集第1巻 | シャオメイ・シュ(P) 録音:2009年4、5月ノートルダム・ド・ボン・スクール教会(パリ |
|
||
| MIR-104 |
ハイドン:ピアノ・ソナタ&変奏曲集 ピアノ・ソナタ第62番変ホ長調Hob.XVI:52 変奏曲ヘ短調 Hob.XVII:6 ピアノ・ソナタ第53番ホ短調Hob.XVI:34 ピアノ・ソナタ第54番ト長調 Hob.XVI:40 |
アンヌ・ケフェレック(P) 録音:2001年9月30日、10月1日 |
|
||
| MIR-105 |
エリザベト・クロード・ジャケ・ド・ラ・ゲール(1665-1729):ヴァイオリン、ヴィオールと通奏低音のためのソナタ集 ソナタ第1~4番、 レ・シルヴァン(クープラン/テオルボ編)、 プレリュード(モレル/ヴィオール) |
ラ・レヴーズ【ステファン・デュデルメル(Vn)、フローレンス・ボルトン(ヴィオール)、アンジェリーク・モイヨン(Hrp)、ベルトラン・キュイエ(Clavcin)、バンジャマン・ペロー(テオルボ、バロックG&指)】 録音:2009年9月 |
|
||
| MIR-106 |
フランク(ジョリス・ルジューヌ編):十字架上のキリストの最後の7つの言葉 グノー:十字架上のキリストの最後の7つの言葉 |
ミシェル・コルボ(指) ローザンヌ声楽アンサンブル ソフィー・グラフ(S)、 ヴァレリー・ボナール(A) マティアス・ロイサー(T)、 ヴァレリーオ・コンタルド(T) ファブリス・エヨーズ(Bs)、 ロール・エルマコラ(Hp) マルチェロ・ジャンニーニ(Org) 録音:2009年8月7&8日ラ・フェルム・ド・ヴィルファヴァール |
|
||
| MIR-107 |
ショパン:チェロ・ソナタOp.65、 序奏と華麗なポロネーズ Op. 3 アルカン:演奏会用ソナタ ホ長調 Op. 47 |
タチアナ・ヴァシリエヴァ(Vc) ジャン・フレデリック・ヌーブルジェ(P) 録音:2009 年9 月 |
|
||
| MIR-108 |
サン=サーンス:チェロ協奏曲第1番イ短調Op.33 チェロ・ソナタ第1番ハ短調Op.32*、 ロマンスへ長調Op.36#、 チェロとピアノのための組曲Op.16#、 動物の謝肉祭 |
アンリ・ドマルケット(Vc) ボリス・ベレゾフスキー(P)* ブリジット・エンゲラー(P)# ジョセフ・スウェンセン(指)パリ室内O 録音:2009年11月 |
|
||
| MIR-109 |
ブロウとパーセルのオードとソング集 ジョン・ブロウ:ヘンリー・パーセルの死を悼む頌歌 パーセル:もしより多くの富を望むならばZ.544 目覚めよ我がムーサよZ.320(メアリー2世の誕生日) フルートのためのシンフォニー 来たれ芸術の子よZ.323(メアリー2世の誕生日) 天上の音楽は神々を動かしZ.32(2メイドウェル学校で演奏) シャコンヌ 歌劇「予言者」~第2幕アリア「罠と危険から」 フルートのためのシンフォニー 乙女の最後の祈り(または失敗するくらいなら)Z.601~ダメよ抵抗してもだめ 私は美しいチェリアに恋をした 愛の女神は盲目Z.331 |
フィリップ・ピエルロ(指&Gamb) リチェルカーレ・コンソート カルロス・メーナ(CT) ダミアン・ギヨン(CT) 録音:2009年10月 |
|
||
| MIR-110 |
ショパン:バラード(全4曲) 夜想曲op.15-1/op.15-2/op.9-2/op.48-1 幻想曲ヘ短調op.49 |
広瀬悦子(P) 録音:2009年11月9-11日 フランス・リモージュ |
|
||
| MIR-111 |
ショパン:ノクターン集Vol.1 変ホ長調作品9-2、へ長調作品15-1、 嬰ヘ長調作品15-2、嬰ハ短調作品27-1、 変ニ長調作品27-2、 変イ長調作品32-2、ト長調作品37-2、 嬰ヘ短調作品48-2、ハ短調作品48-1、 「遺作」嬰ハ短調 |
ルイス・フェルナンド・ペレス(P) |
|
||
| MIR-112 |
フランスのチェリストたち~メディテイションズ ブロッホ:祈り/カザルス:鳥の歌 ラフマニノフ:ヴォカリーズ ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界」より」~第2楽章 オフェンバック:ジャクリーヌの涙 Op.76-2 フォーレ:夢のあとに シューマン:古いリュートOp.35-12、 異郷にてOp.39-1、月の夜Op.39-5、 古城にてOp.39-7 ワーグナー:タンホイザー~「おお、おまえ、いとしい夕星よ」 ヴェルディ:ドン・カルロ~「彼女は私を愛したことが無い」 チャイコフスキー:弦楽四重奏曲第3番変ホ短調Op.30~第3楽章 |
レ・ヴィオロンチェレス・フランセ [エマニュエル・ベルトラン、エリク-マリア・クトゥリエ、エマニュエル・ゴーゲ、ハヴィエル・ピドゥ、ラファエル・ピドゥ、 ローラン・ピドゥ、ナディヌ・ピエール、フランソワ・サルク] 録音:2009年12月7-9日 |
|
||
|
MIR-114
|
ショパンの音楽日記 1817年/ポロネーズ.ト短調 S1-1* 1827年/夜想曲.ホ短調Op.72-1# 1829年-1830年/練習曲[Op.10 -1, 2, 3]+ 1832年-1833年/2つのマズルカOp.17** 1838年-1839年/夜想曲ヘ長調Op.15-1## 1837年/スケルツォ第2番変ロ短調Op.31 ++ 1836年-1839年/バラード第2番ヘ長調Op.38## 1831年-1839年/前奏曲第15番変ニ長調 + 1845年-1846年/舟歌.嬰ヘ長調Op.60# 1845年-1846年/幻想ポロネーズOp.61* 1846年/マズルカ.嬰ハ短調Op.63** 1849年/マズルカ.ヘ短調Op.68** |
アブデル・ラーマン・エル=バシャ(P)* アンヌ・ケフェレック(P)# フィリップ・ジュジアーノ(P)+ イド・バル=シャイ(P)** ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P)## 児玉桃(P)++ 録音:2009年11月、La Ferme de Villefavard(仏リムザン地方) ※日本語解説付 |
| MIR-115 |
アーベントムジーク「夕べの音楽」 シューマン:色とりどりの小品Op.99 クララ・シューマン:ロベルト・シューマンの主題による変奏曲Op.20 ブラームス:シューマンの主題による変奏曲Op.9 |
クレール・デゼール(P) 録音:2009年11月 La Ferme de Villefavard (仏リムザン地方) |
|
||
| MIR-116 |
シャブリエ:10の絵画風小品、 即興曲ハ長調、5つの遺作、 幻想的なブレー ラヴェル:シャブリエ風に |
エマニュエル・シュトロッセ(P) 録音:2009年11月リモージュ、フランス |
|
||
| MIR-119(2CD) |
シューベルト:ピアノ・ソナタ集 ピアノ・ソナタ第18番ト長調Op.78D.894「幻想ソナタ」 ピアノ・ソナタ第20番イ長調D.959 |
ジャン=クロード・ペヌティエ(P) 録音:2009年11月リモージュ、フランス |
|
||
| MIR-120 |
メンデルスゾーン:弦楽四重奏曲第2番イ短調Op.13、 弦楽四重奏曲第6番へ短調Op.80、 カプリッチョ ホ短調 |
モディリアーニSQ 【フィリップ・ベルナール(Vn)、 ロイック・リョー(Vn)、 ローラン・マルフェング(Va)、 フランソワ・キエフェル(Vc)】 |
|
||
| MIR-124 |
第30回ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ・フェスティバル公式アルバム (1)ラフマニノフ:2台のピアノのための組曲第1番Op.5「幻想的絵画」~夜と愛 (2)リスト:巡礼の年第1年「スイス」S160~泉のほとりで (3)シューベルト(リスト編):住処 (4)ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第30番~第1楽章 (5)エリーゼのために/ピアノ・ソナタ第20番~第2楽章 (6)シューマン:色とりどりの小品Op.99より (7)メンデルスゾーン:無言歌集Op.85-4~春の歌 (8)バッハ:平均律クラヴィーア曲集第1集~前奏曲〔第8番BWV853/第6番BWV851〕 (9)ショパン:マズルカ〔嬰ハ短調Op.63-3/ト短調Op.67-2/イ短調Op.17-4 (10)ワルツイ短調KK.IVb-11/幻想即興曲嬰ハ短調Op.66 (11)シャブリエ:絵画的小曲集~牧歌/5つの小品~アルバムの綴り (12)メトネル:2つのおとぎ話Op.14~第1曲ホ短調 (13)シューベルト:ハンガリー風のメロディロ短調D.817 シューマン:子供の情景~見知らぬ国と人々から (14)フォーレ:前奏曲第4曲ヘ長調Op.103-4 (15)ショパン:夜想曲ヘ長調Op.15-1 (16)メトネル:4つのおとぎ話Op.26~第2曲変ホ長調 |
(1)ブリジット・エンゲラー、ボリス・ベレゾフスキー(P) (2)ニコラ・アンゲリッシュ(P) (3)ブリジット・エンゲラー(P)] (4)アンドレイ・コロベイニコフ(P) (5)ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) (6)クレール・デゼール(P) (7)シャニ・ディリュカ(P) (8)シャオメイ・シュ(P) (9)イド・バルシャイ(P (10)アンヌ・ケフェレック(P) (11)エマニュエル・シュトロッセ(P) (12)ボリス・ベレゾフスキー(P) (13)ブリジット・エンゲラー(P) (14)ジャン=クロード・ペヌティエ(P) (15)ルイス・フェルナンド・ペレス(P) (16)ボリス・ベレゾフスキー(P) |
| MIR-125 |
セバスティアン・ド・ブロサール(1655-1730):オラトリオ「無原罪の聖マリア」SDB.56、 ソナタ.ハ長調SDB.224、 カンタータ「レアンドロ」SDB.77、 「悔い改めた魂と神との対話」SDB.55 |
ラ・レヴーズ シャルタン・サントン・ジェフリー(S) ウジェニー・ヴァルニエ(S) イザベル・ドリュエ(A) ジェフリー・トンプソン(CT) ヴァンサン・ブーショ(T) ベノワ・アルヌール(Bs) 録音:2010年6月28日-7月1日 |
|
||
| MIR-126 |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第2番 ピアノ協奏曲第1番 |
シャニ・ディリュカ(P) クワメ・ライアン(指) ボルドー・アキテーヌ国立O 録音:2010年4月 |
|
||
| MIR-127 |
エロール:ピアノ協奏曲第2番変ホ長調、 第3番イ長調、第4番ホ短調 |
ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) エルヴェ・ニケ(指) シンフォニア・ヴァルソヴィア 録音:2010年5月16-18日 |
|
||
 MIR-128(2CD) ★ |
バッハ&レーガー:無伴奏ヴァイオリン作品集 レーガー:前奏曲とフーガト短調Op.117-2 バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第1番ト短調BWV1001 レーガー:前奏曲とフーガロ短調Op.117-1 バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第1番ロ短調BWV1002 レーガー:シャコンヌ ト短調 Op.117-4 バッハ:無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ短調BWV1004 |
庄司紗矢香(Vn) 録音:2010年8月ランファン・ジェジュ教会、パリ ※日本語解説付き |
|
||
| MIR-129 |
グノー:レクイエム.ハ長調 ミサ曲.ト短調 |
ミシェル・コルボ(指) ローザンヌ声楽アンサンブル シャルロット・ミュラー=ペリエ(S) ヴァレリー・ボナール(A) クリストフ・アインホルン(T) クリスティアン・イムラー(Bs) 録音:2010年8月 |
|
||
| MIR-130 |
ブラームス:ピアノ五重奏曲ヘ短調Op.34、 2つの歌曲Op.91(ヴィオラ、メゾソプラノ、ピアノのための) |
ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) アンドレア・ヒル(Ms) モディリアニSQ 録音:2010年9月12-15日 |
|
||
| MIR-131 |
ブラームス:ピアノ作品集 創作主題による変奏曲Op.21-1、 8つのピアノ小品Op.76、 2つのラプソディーOp.79、 3つのインテルメッツォOp.117 |
アダム・ラルーム(P) 録音:2010年11月2-5日 |
|
||
| MIR-132 |
ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 パガニーニの主題による変奏曲Op.35*、 ハンガリー舞曲第1番/第2番/第4番 |
ボリス・ベレゾフスキー(P) ドミトリー・リス(指)ウラルPO 録音:2010年11月エカテリンブルグ(ライヴ、*は除く |
|
||
| MIR-133 |
ウィーン 1925年 ベルク:室内協奏曲(ピアノとヴァイオリン、13管楽器のための) J・シュトラウス(ヴェーベルン編):宝のワルツ J・シュトラウス(シェーンベルク編):南国のバラ |
マリー=ジョゼフ・ジュド(P) フランソワ=マリー・ドリュー(Vn) ジャン=フランソワ・エッセール(指) ポワトゥ=シャラントO 録音:2010年10月 |
|
||
| MIR-134 |
ブラームス:ワルツ集「愛の歌」Op.52a(4手のための) ハンガリー舞曲集~第1、2、4、5、6、8、11、16、17、21番(4手のための) |
ブリジット・エンゲラー(P) ボリス・ベレゾフスキー(P) 録音:2011年ラ・フォル・ジュルネ・ドゥ・ナント |
|
||
| MIR-135 |
シューマン:序奏とアレグロ・アパッショナートOp.92、 ピアノ協奏曲イ短調Op.54 リスト:ピアノ協奏曲第2番イ長調 |
広瀬悦子(P) フェイサル・カルイ(指)ベアルン地方ポーO 録音:2010年11月 ※日本語解説付き |
|
||
| MIR-136(2CD) |
バッハ:ヨハネ受難曲BWV245(1724/1725) | フィリップ・ピエルロ(指) リチェルカール・コンソート マリア・キーオヘイン(ケオハーン)(S) ヘレーナ・エーク(S)、カルロス・メーナ(A) ヤン・ヴェルナー(A) ハンス・イェルク・マンメル(T/エヴァンゲリスト) ヤン・コボウ(T)、 マティアス・ヴィーヴェグ(Bs/イエス) ステファン・マクラウド(Bs/ペテロ、ピラト) 録音:2010年9月27-30日リエージュ・フィルハーモニー・ホール |
|
||
| MIR-137 |
トムキンズ氏の《価値のレッスン》 ■イ調の作品 ジョン・ブル:半音階的パヴァン、 半音階的ガリアード トムキンズ:奉献唱 ■ト調の作品 不詳(トマス・トムキンズ?):ロビン・フッド バード:ウィリアム・ピーター卿のパヴァン、 ウィリアム・ピーター卿のガリアード タリス:あなたは幸いな方 トムキンズ:初心者のための「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラで」 ■二調の作品 ブル:イン・ノミネ トムキンズ:グラウンドMB40 ブル:ファンタジアMB11 |
ベルトラン・キュイエ(Cemb) 録音:2010年10月28-31日、クセイ城 |
|
||
| MIR-138 |
グラナドス:詩的なワルツ集(全8曲) ゴイェスカス(全6曲) 歌劇「ゴイェスカス」間奏曲(作曲者編) |
ルイス・フェルナンド・ペレス(P) 録音:2011年5月23-25日 |
|
||
| MIR-141 |
テオドール・デュボワ(1837-1924):協奏曲集 チェロと管弦楽のためのファンタジー・シュトック チェロ,ピアノと管弦楽のためのコンチェルタンテ組曲 ピアノと管弦楽のためのコンチェルト・カプリチオーソ 死者のための追悼~悲しい歌 チェロと管弦楽のためのアンダンテ・カンタービレ |
マルク・コペイ(Vc:マッテオ・ゴフリラー1711) ジャン=フランソワ・エッセール(P&指) ポワトゥ・シャラントO 録音:2010年10月 |
|
||
| MIR-145 |
ピアノ・リサイタル・イン・パリ リスト:詩的で宗教的な調べ~「葬儀」 ヌーブルジェ:マルドロール J.バラケ:ピアノ・ソナタ(全2楽章) ドビュッシー:映像第2集~「そして月は荒れた寺院に落ちる」 |
ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) 録音:2011年1月14日、ラ・シテ・ドゥ・ラ・ムジークライブ録音(パリ) |
|
||
| MIR-149 |
第31回ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ・フェスティバル公式アルバム (1)アリャビエフ(リスト編):夜鳴き鶯 (2)ブラームス:ハンガリー舞曲集第4番 (3)リスト:巡礼の年第1年~ワレンシュタットの湖畔で (4)ブラームス:インテルメッツォOp.117-1 (5)メンデルスゾーン:無言歌Op.102-4 (6)ブラームス:愛のワルツOp.52a-6 (7)シューベルト:ピアノ・ソナタ第22番D.959~スケルツォ (8)ショパン:練習曲Op.25-1 (9)リスト:暗い雲S.199 (10)ショパン:ノクターン ハ短調Op48-1 (11)ラヴェル:シャブリエ風に (12)シューマン:色とりどりの小品よりOp.99 (13)ベートーヴェン:バガテルOp.126-5 (14)モーツァルト:幻想曲ハ短調K.396 (15)ソレル:ソナタ ハ短調 (16)ハイドン:ピアノ・ソナタ変ロ長調Hob.XVI/49 (17)バッハ(クルターグ編):「神の時は最上の時なり」(哀悼行事のソナティナ)BWV106 (18)バッハ:イタリア組曲第2番BWV807より (19)メトネル:2つのおとぎ話Op.14「騎士の行進」 |
(1)ブリジット・エンゲラー(P) (2)ボリス・ベレゾフスキー、ブリジット・エンゲラー(P) (3)ニコラ・アンゲリッシュ(P) (4)アダム・ラルーム(P) (5)シャニ・ディリュカ(P) (6)ボリス・ベレゾフスキー、ブリジット・エンゲラー(P) (7)ジャン=クロード・ペヌティエ(P) (8)フィリップ・ジュジアーノ(P) (9)ブリジット・エンゲラー(P) (10)広瀬悦子(P) (11)エマニュエル・シュトロッセ(P) (12)クレール・デゼール(P) (13)アンドレイ・コロベイニコフ(P) (14)シュ・シャオ・メイ(P) (15)ルイス・フェルナンド・ペレス(P) (16)イド・バルシャイ(P) (17)アンヌ・ケフェレック ガスパール・デヘヌ(P) (18)ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) (19)ボリス・ベレゾフスキー(P) |
|
||
| MIR-150 |
F.クープラン:パルナッソス山、またはコレッリ賛 ルベル:リュリ氏のトンボー F.クープラン:リュリ賛 |
フィリップ・ピエルロ(指,ヴィオラ・ダ・ガンバ) リチェルカーレ・コンソート 録音:2010年9月、ボーフェ(ベルギー) |
|
||
| MIR-152 |
モーツァルト:ピアノ作品集 きらきら星変奏曲K.265、 ピアノ・ソナタ.ハ長調K.330、 幻想曲ハ短調K.396、 アダージョ.ロ短調K.540、 デュポールのメヌエットによる9つの変奏曲ニ長調K.573、 ピアノ・ソナタ.ニ長調K.576、 アンダンテ.ヘ長調K.616 |
シュ・シャオメイ(P) 録音:2011年3月17-20日ポワチエ・オーディトリアム劇場 |
|
||
| MIR-154 |
ブラームス:祭典と記念の格言~「われらの父は汝に望む」Op.109-1 祭典と記念の格言~「栄光の民はいずこに」Op.109-3 2つのモテット~「なにゆえに悩み苦しむ人に光が賜られたか」Op.74-1 レーガー:8つの宗教的歌曲~「アニュス・デイ」Op138-6 8つの宗教的歌曲~「われらみな唯一なる神を信ず」Op.138-8 ブルックナー:モテット「この場所は神が作り給う」Op.92 モテット「正しい者の口は知恵を語り」 ブラームス:祭典と記念の格言~「強き盾にて武装する人、その城を守らば」Op.109-2 ブルックナー:モテット「エサイの枝は芽を出し」 ブラームス:子守歌Op.49-4 |
ヴォーチェス8 (ディングル、ポール、ロバート、チャールズ、バーニー、クリス、アンドレア、エミリー) 録音:2011年ラ・フォル・ジュルネ・ドゥ・ナント |
|
||
 MIR-155 |
ショスタコーヴィチ:ピアノ協奏曲第1番ハ短調Op.35 24の前奏曲Op.34 ピアノ協奏曲第2番ヘ長調Op.102 |
アンドレイ・コロベイニコフ(P) ミハイル・ガイドゥーク(Tp)、 オッコ・カム(指)ラハティSO 録音:2011年5月26/28日 シベリウス・ホール(ラハティ) |
|
||
| MIR-156(2CD) |
バッハ:6つのパルティータBWV825-830 | シャオ・メイ・シュ(P) 録音:1999年9月(MANDALA録音) |
|
||
| MIR-157 |
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第32番ハ短調op.111 シューベルト:ピアノ・ソナタ第21番変ロ長調D.960 |
シャオ・メイ・シュ(P) 録音:2004年(MANDALA音源) |
|
||
 MIR-158 |
シューマン:ダヴィッド同盟舞曲集op.6 子供の情景op.15 |
シャオ・メイ・シュ(P) 録音:2002年6月(MANDALA録音) |
|
||
| MIR-160 |
アンドレ・カプレ(1878-1925):オラトリオ「イエスの鏡」~ロザリオの神秘 | マリー・クロード・シャピュイ(Ms) シネ・ノミネQ 【パトリック・ジュネ(Vn)、 フランソワ・ゴトロー(Vn)、 ハンス・エジディ(Va)、 マルク・ジェルマン(Vc)】 アンヌ・バッサン(Hrp) マルク=アントワーヌ・ボナノミ(Cb) ローザンヌ声楽アンサンブル ジャン=クロード・ファゼル(指) 録音:2011年6月3-5日ラ・ショー=ド=フォン、スイス |
|
||
| MIR-162 |
ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハ(1710 ~1784):クラヴサンと弦楽合奏のための協奏曲集 弦楽合奏とクラヴサンのための協奏曲 イ短調 Falck 45 シンフォニア.ヘ長調 Falck 67 弦楽合奏とクラヴサンのための協奏曲 ニ長調 Falck 41 アレグロ・エ・フォルテ.ニ短調 Falck 65 弦楽合奏とクラヴサンのための協奏曲 ホ短調 Falck 43 |
イル・コンヴィート モード・グラットン(クラヴサン・指) ステファニー・ポーレ(Vn) ソフィー・ジェント(Vn) ガブリエル・グロスバール(Va) エマニュエル・ジャック(Vc) ジョセフ・カーヴァー(Cb) 録音:2012年5月 |
|
||
 MIR-163 |
シャミナード:ピアノ三重奏曲第2番 イ短調 op.34-2 ドビュッシー:ピアノ三重奏曲 ト長調 ルネ・ルノルマン(1846-1932):ピアノ三重奏曲 ト短調 op.30 |
トリオ・ショーソン 録音:2011年7月 |
|
||
| MIR-164 |
2台のクラヴサンによるラモーの歌劇音楽集 ラモー:歌劇「優雅なインド」~序曲、ミュゼット、メヌエット、タンブーラン、ポーランド人たちのエール、アフリカの奴隷たちのエール、ガヴォット、シャコンヌ、未開人たち 歌劇「ダルダニュス」~シャコンヌ、プレリュード、優美なエール、タンブラン、 歌劇「プラテ」~ミュゼット、ヴィエール風のメヌエット、 歌劇「ゾロアスター」~メヌエット、サラバンド 歌劇「ピュグマリオン」~序曲 歌劇「遍歴騎士」~とても陽気なエール、少しゆるやかなガヴォット 歌劇「イポリトとアリシー」~メヌエット 歌劇「エベの祭」~タンブラン コンセール用のクラヴサン曲集軽はずみ、パントマイム、おしゃべり、内気、マレー |
ピエール・アンタイ(クラヴサン)、 スキップ・センペ(クラヴサン) 録音:2011年7&12月、アラス劇場(フランス) |
|
||
 MIR-165 |
プロコフィエフ:トッカータop.11 10の小品op.12 ピアノ・ソナタ第2番ニ短調op.14 風刺op.17/つかの間の幻影op.22 |
アブデル・ラーマン・エル・バシャ(P) 録音:2011年7月12-15日、ヴィルファヴァール農場(リムザン、フランス) |
|
||
 MIR-166 |
ショスタコーヴィチ:ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調Op.77 ヴァイオリン協奏曲第2番嬰ハ短調Op.129 |
庄司紗矢香(Vn)、 ドミトリー・リス(指)ウラルPO ジャケット写真:篠山紀信 ※日本語解説書付き 録音:2011年8月エカテリンブルク・フィルハーモニー(ロシア) |
|
||
| MIR-167 |
リスト:「詩的で宗教的な調べ」~パーテル・ノステル 昇階曲「キリストは我らのために」 前奏曲「泣き、嘆き、悲しみ、おののき」S.179 讃歌「王の御旗は進み」 十字架への道 |
ヴォックス・クラマンティス ヤーン= エイク トゥルヴェ(指) ジャン=クロード・ペネティエ(P) |
|
||
 MIR-168 |
アリアーガ:弦楽四重奏曲第3番変ホ長調 モーツァルト:弦楽四重奏曲第6番変ロ長調 KV 159 シューベルト:弦楽四重奏曲第4番ハ長調 D46 |
モディリアーニSQ 録音:2011年9月/サル・コロンヌ(パリ) |
|
||
| MIR-169 |
ロシアのピアノ小品集 リムスキー=コルサコフ:熊蜂の飛行 スクリャービン:左手のための前奏曲嬰ハ短調Op.9-1 ラフマニノフ:絵画的練習曲変ホ短調op.39-5 スクリャービン:前奏曲ホ長調op.15-4 練習曲嬰ハ短調op.2-1 ボロディン:スケルツォ.変ロ長調 ラフマニノフ:「ひな菊」op.38-3 チャイコフスキー:無言歌イ短調op.40-6 スクリャービン:練習曲嬰ニ短調「悲愴」op.8-12 チャイコフスキー:無言歌ヘ長調op.2-3 ラフマニノフ:前奏曲嬰ハ短調 op.3 スクリャービン:マズルカ変ニ短調op.3-5 チャイコフスキー:ワルツ・スケルツォop.7 スクリャービン:前奏曲変ロ短調op.16-4 ラフマニノフ:前奏曲ト短調op.23-5 ムソルグスキー:子供の遊び/涙 スクリャービン:詩曲「炎に向かって」 op.72 |
クレール・マリ=ル・ゲ(P) 録音:2011 年10 月11-14 日、Le Temple de l’Annonciacion(パリ) |
|
||
 MIR-170 |
ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」 メトネル:追憶のソナタ.イ短調op.38-1(忘れられた調べ)第1集より タニェエフ:前奏曲とフーガ.嬰ト短調op.29 |
ダヴィッド・カドゥシュ(P) 録音:2011 年10 月28-28 日、Le Temple de l’Annonciation(パリ) |
|
||
| MIR-171 |
ストラヴィンスキー:春の祭典 ペトルーシュカ 5つのやさしい小品 3つのやさしい小品 |
リディヤ・ビジャック(P) サーニャ・ビジャック(P) 録音:2007年11月、パリ国立高等音楽院 |
|
||
| MIR-172 |
エンゲラー&コセ グラズノフ:エレジー.ト短調Op.44 チャイコフスキー:夜想曲嬰ハ短調Op.19-4 なつかしい土地の思い出~メロディ変ホ長調 Op.42-3 6つの小品~感傷的なワルツ.イ短調Op.51-6 ラフマニノフ:ヴォカリーズOp.34-14 ショスタコーヴィチ:ヴィオラ・ソナタOp.147 |
ブリジット・エンゲラー(P)、 ジェラール・コセ(Va) 録音:2011年9月、la Fondation Singer-Polignac |
|
||
 MIR-174 |
ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ音楽祭ライヴ録音集 (1)バッハ:ゴルトベルク変奏曲~アリア (2)スクリャービン:2つの左手のための小品~前奏曲嬰ハ短調 Op.9-1 (3)ショパン:マズルカ.ヘ短調Op.68-4 (4)グラナドス:ゴイェスカス~嘆き,またはマハとナイチンゲール (5)シューマン:色とりどりの小品~5つのアルバムの綴り Op.99 (6)メンデルスゾーン:無言歌集第6巻~変ホ長調「瞑想」 Op.67-1 (7)バッハ:平均律クラヴィア曲集第1集~第8番変ホ短調 BWV 853 (8)ショスタコーヴィチ:24の前奏曲第4番 変ホ短調Op.34-4 (9)ショパン:12の練習曲第6番変ホ短調Op.10-6 (10)ドビュッシー:映像第2集~そして月は荒れた寺院に落ちる (11)シャブリエ:10の絵画風小品~森で 変ト長調 (12)シューベルト:即興曲集第4番変イ長調Op.90-4 (13)バラキレフ:園にて変ニ短調 (14)フォーレ:3つの無言歌第3番Op.17-3 (15)ブラームス:8つの小品第3番間奏曲変イ長調Op.76-3 (16)ストラヴィンスキー:3つのやさしい小品 (17)リスト:巡礼の年報第1年スイス~牧歌 (18)ムソルグスキー:展覧会の絵~古城 (19)アルベニス:スペイン組曲~グラナダOp.47-1 (20)プロコフィエフ:10の小品~スケルツォOp.12-10 (21)ブラームス:ハンガリー舞曲集第17番 |
(1)シュ・シャオメイ(P) (2)クレール=マリ・ル・ゲ(P) (3)イド・バル=シャイ(P) (4)ルイス・フェルナンド・ペレス(P) (5)クレール・デゼール(P) (6)シャニ・ディリュカ(P) (7)/アンヌ・ケフェレック(P) (8)アンドレイ・コロベイニコフ(P) (9)フィリップ・ジュジアーノ(P) (10)ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) (11)エマニュエル・シュトロッセ(P) (12)ブリジット・エンゲラー(P) (13)広瀬悦子(P) (14)ジャン=クロード・ペヌティエ(P) (15)アダム・ラルーム(P) (16)リディヤ・ビジャーク(P)、サンヤ・ビジャーク(P) (17)ニコラ・アンゲリッシュ(P) (18)ダヴィッド・カドゥシュ(P) (19)ボリス・ベレゾフスキー(P) (20)アブデル・ラーマン・エル・バシャ(P) (21)ボリス・ベレゾフスキー(P)、ブリジット・エンゲラー(P) |
|
||
| MIR-177 |
ヘンリー・ローズ:歌曲集 朝日を見たことがあるか? ゆるやかに流れよ、銀色の川 ただ生きよと命じて下さい グラウンドによるディヴィジョン(フンシス・ウィシィ?) 前奏曲(ダニエル・バチェラー?) 私は起き上がり、深く悲しむ あなたか私か、罪を犯した ため息も 涙も 悲しみもなく(ニコラス・ラニアー?) 2つのリュートのためのアルマイン[クーラントⅠ/クーラントⅡ(ウィリアム・ローズ?)] Whither are all her false oaths blown ? 私は恋の病(ウィリアム・ローズ?) 草原はもはや花に覆われるこ となく(ニコラス・ラニアー?) トレギアンのグラウンド あわれにも愛の喜びから追放された君が 穏やかに眠れ 離せ、愛していた クーラント(ジャック・ゴーティエ アングレテールのゴーティエ) ゴーティエ氏の鐘(ジャック・ゴーティエ アングレテールのゴーティエ) きみよ まだ帰らないでおくれ おお、愛を教えて!おお、運命を教えて! ディヴィジョン:ジョン、今すぐ私にキスして(クリストファー・シンプソン?) Wert thou yet fairer than thou art ・なぜそう青白く暗いのか、盲目 的に恋する者よ(ウィリアム・ロ ーズ?) |
ラ・レヴーズ フローレンス・ボルトン(指、Va) ベンジャミン・ペロー(指、Lute、テオルボ&バロックG) ジェフリー・トンプソン(T) ベルトラン・キュイエ(ハープシコード) |
|
||
 MIR-181 |
バラキレフ:ピアノ作品集 グリンカ(バラキレフ編):皇帝に捧げた命 バラキレフ:庭園にて(1884) トッカータ(1902) ピアノ・ソナタ 変ロ短調 グリンカ(バラキレフ編):ひばり バラキレフ:イスラメイ |
広瀬悦子(P) 録音:2012年2月 |
|
||
| MIR-183 |
モーツァルト:クラリネット協奏曲イ長調K.622 クラリネット五重奏イ長調K.581 |
ロマン・ギュイヨ(Cl) ヨーロッパCO ロレンツァ・ボラーニ(Vn) マッツ・セッテルクヴィスト(Vn) パスカル・シフェール(Va) リチャード・レスター(Vc) 録音:2012年3月 |
|
||
| MIR-184 ★ |
ルネ・マルタンのル・ク・ド・クールCD~2012年ナントでのLFJ音楽祭ライヴ (1)パベル・チェスノコフ:「お告げ」 (2)ボロディン:だったん人の踊り (3)グリンカ:大六重奏曲 (4)ラフマニノフ:エレジー変ホ短調 op.3-1、 前奏曲嬰ハ短調 op.3-2 (5)ロシア民謡「12人の盗賊」(V.ブリン編) ロシア民謡「鐘の音は単調に鳴る」(A.スヴェシュニコフ編) ロシア民謡「The Boss」 (6)チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番~第3楽章 (7)ロシア民謡「おお!冬よ!」 |
(1)アナトリー・グリンデンコ(指) モスクワ大司教座cho (2)ボドミトリー・リス(指)ウラルPO (3)アンヌ・ケフェレック(P)、 プラジャークQ (4)広瀬悦子(P) (5)ヴラディスラフ・チェルヌチェンコ(指) カペラ・サンクトペテルブルク (6)ボリス・ベレゾフスキー(P)、 ドミトリー・リス(指)ウラルPO (7)アナトリー・グリンデンコ(指) ロモスクワ大司教座cho、 録音:2012年ラ・フォル・ジュルネ音楽祭(ナント)ライヴ |
|
||
 MIR-185 |
ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」 | ユーリ・テミルカーノフ(指)サンクトペテルブルグPO 録音:2011年3月/サンクトペテルブルグ・フィルハーモニア(ライヴ) |
|
||
 MIR-187(10CD) |
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ全集(全32曲) | アブデル・ラーマン・エル=バシャ(P) 録音:2012年4月、2013年1月ヴィルファヴァール農場、フランス |
|
||
 MIR-188(2CD) |
フランス近代弦楽四重奏曲集 ドビュッシー:弦楽四重奏曲ト短調 サン=サーンス:弦楽四重奏曲第1番 ラヴェル:弦楽四重奏曲ヘ長調 |
モディリアーニSQ 【フィリップ・ベルナール(Vn) ロイック・リョー(Vn) ローラン・マルフェング(Va) フランソワ・キエフェル(Vc)】 録音:2012年4月、9月 |
|
||
 MIR-189 |
ケフェレック/ドビュッシー、ラヴェル他 サティ:グノシェンヌ第1番、ピカデリー ジムノペディ第1番 セヴラック:休暇の日々から第1集~「古いオルゴールが聞こえるとき」 プーランク:ジャンヌの扇~「田園」 ドビュッシー:夢 ラヴェル:ファンファーレ* サティ:ジムノペディ第 3 番 ピエール=オクターヴ・フェルー:モンソー公園で~「のんびりと」 サティ:風変わりな美女~「眼の中の意味ありげなキス」のワルツ*、 グノシェンヌ第3番 アーン:当惑したナイチンゲール~「長椅子の夢見る人」 サティ:グノシェンヌ第4番、 ジムノペディ第2番、 ひからびた胎児~「ナマコの胎児」、 風変わりな美女~「上流階級用のカンカン」*、 ジムノペディ第2番 ラヴェル:シャブリエ風に ドビュッシー:小さな黒人 アーン:口絵 デュポン:憂鬱な時間~「日曜日の午後」 ドビュッシー:ベルガマスク組曲~「月の光」 サティ:グノシェンヌ第6番、 梨の形をした3つの小品~第1番&第2番、 グノシェンヌ第5番 ケクラン:陸景と海景~「漁夫の歌」 アーン:冬 フローラン・シュミット:秘められた音楽第2集~「グラス」 |
アンヌ・ケフェレック(P) ガスパール・ドゥアンヌ(P)* 録音:2012年 6月TAP、ポアチエ、フランス |
|
||
| MIR-190 |
子ども時代 フォーレ:組曲「ドリー」Op.56 ビゼー:子供の遊びOp.22 ドビュッシー:小組曲 ラヴェル:マ・メール・ロワ |
クレール・デセール(P) エマニュエル・シュトロッセ(P) 録音:2012年6月16-18日TAP、ポアチエ、フランス |
|
||
 MIR-191 (1CD+DVD) |
シェーンベルク:ピアノ作品集 3つのピアノ曲Op.11、 6つの小さなピアノ曲Op.19 5つのピアノ曲Op.23、 組曲Op.25/ピアノ曲Op.33a,b、 3つのピアノ曲(1894) ■DVD ボッファールが語るシェーンベルク |
フローラン・ボッファール(P) 録音:2012年 6月 |
|
||
| MIR-192 |
オンスロウ:チェロ・ソナタ第2番ハ短調Op16の2 第1番ヘ長調Op.16の1 第3番イ長調Op.16の3 |
エマニュエル・ジャック(Vc)、 モード・グラットン(フォルテピアノ) 録音:2012 年 7 月ヴィルファヴァール |
|
||
 MIR-193 |
フォーレ&サン=サーンス:ヴァイオリンと管弦楽のための作品集 サン=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ ヴァイオリン協奏曲第1番イ長調Op.20 ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンス.ハ長調Op.48 フォーレ:組曲「ペレアスとメリザンド」 子守歌Op.16 |
デボラ・ネムタヌ(Vn) トーマス・ツェトマイアー(指)パリCO 録音:2012年9月サンキャトル、パリ |
|
||
| MIR-194 |
シューマン:ピアノ曲集 フモレスケ変ロ長調Op.20、 ピアノ・ソナタ第1番嬰ヘ短調Op.11 |
アダム・ラルーム(P) 録音:2012年9月2-5日サル・ガヴォー、パリ |
|
||
| MIR-195 |
F.クープラン:クラヴサン曲集 さまよう亡霊たち/修道女モニク/ティクトクショック、またはオリーヴしぼり機/プラチナ色の髪のミューズ/恋のナイチンゲール/ナイチンゲールの変奏/子供時代-ミューズの誕生-幼年期/タンブラン/神秘的な女/小さな皮肉/ロジヴィエール/子守歌、またはゆりかごの中のいとし子/おしゃべり女/心地よい恋やつれ/花咲く果樹園/葦/胸飾りのリボン/煉獄の魂/収穫をする人びと/髪の油/嘆きのほおじろ/騒がしさ/クープラン/神秘なバリケード |
イド・バル=シャイ(P) |
|
||
 MIR-196 |
ショスタコーヴィチ:交響曲第5番ニ短調Op.47 | ユーリ・テミルカーノフ(指)サンクトペテルブルグPO 録音:2012年3月/サンクトペテルブルグ・フィルハーモニア(ライヴ) |
|
||
 MIR-197(3CD) ★ |
アンヌ・ケフェレック~special BOX ■CD1 モーツァルト:ピアノ作品集 ロンド.イ短調K.511, デュポールのメヌエットによる変奏曲K.573 幻想曲ハ短調K.475, ピアノ・ソナタ.短調K.457, 幻想曲ニ短調K.397 ■CD2 ショパン:ピアノ作品集 ポロネーズ変ロ長調KK.IV/1(1817), ポロネーズ.ト短調S1/1(1817), ポロネーズ変イ長調KK.IV/a2(1821), マズルカ変イ長調Op.7-4(1824), ポロネーズ.ヘ短調Op.71-3(1828), ソステヌート変ホ長調(1840), カンタービレ変ロ長調(1834), ノクターン嬰ハ短調 遺作(1830), 幻想即興曲嬰ハ短調Op.66(1834), ワルツ.ヘ短調 Op.70-2(1841) マズルカ嬰ハ短調 Op.50-3(1841-1842) 子守歌変ニ長調Op.57(1843), 舟歌嬰ヘ長調Op.60(1845-1846), スケルツォ第4番ホ長調Op.54(1842), ワルツ.イ短調KK.IVb/11,P2/11, バラード第4番ヘ短調Op.52(1842), マズルカ.イ短調Op.67-4(1848) ■CD3 ハイドン:ソナタと変奏曲集 ソナタ第62番変ホ長調 Hob. XVI:52, 変奏曲ヘ短調Hob.XVII:6, ソナタ第53番ホ短調Hob. XVI:34, ソナタ第54番ト長調 Hob. XVI:40 |
アンヌ・ケフェレック(P) ■CD1(原盤: MIR 9913) 録音:2001年9月30日ー10月1日、シオン(スイス) ティボール・ヴァルガ・ホール ■CD2(原盤:MIR 096) 録音:2009年11月フランス・リモージュ ■CD3(原盤:MIR 104) 録音:2001年9月30日、10月1日 |
|
||
 MIR-198(3CD) ★ |
ブリジット・エンゲラー~special BOX ■CD1 サン=サーンス:ピアノ協奏曲第2番 ピアノ協奏曲第5番「エジプト風」 ■CD2 シューベルト:即興曲第3番.899 クッペルヴィーザー・ワルツ、 ハンガリー風のメロディ.ロ短調D.817 さすらい人幻想曲ハ長調 リスト=シューベルト:歌曲トランスクリプション~影法師、都会、海辺にて、すみか、セレナーデ、春の想い、連祷、水車小屋と小川、さすらい ■CD3 チャイコフスキー:子供のアルバムOp.39 ムソルグスキー:涙, リャードフ:マズルカ、音楽玉手箱Op.32 グリンカ:夜想曲「別れ」, アラビエフ:ナイチンゲール, ショスタコーヴィッチ:人形の踊り-7つの子供の小品より「踊り」「抒情的なワルツ」「ポルカ」「おどけたワルツ」, ラフマニノフ:イタリア・ポルカ, ルービンシュタイン:2つのメロディよりOp.3-1、 諸民族の舞曲集~ポルカOp.82-7 ペテルブルクの夜会~ロマンスOp.44-1 スクリャービン:2つの左手のための小品~夜想曲Op.9 |
ブリジット・エンゲラー(P) ■CD1 アンドレア・クイン(指)パリCO 録音:2008年6月ルヴァロワ・ペレ(フランス) ■CD2 録音:2007年9月 ■CD3 録音:2006年6月6,7&8日フォントヴロー王立大修道院 |
|
||
| MIR-200 |
チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第2番(オリジナル版)* 主題と変奏曲Op.19-6 悲しき歌Op.40-2/マズルカOp.40の5 無言歌Op.40-6/村にてOp.40-7 ワルツOp.40-8 感傷的なワルツOp.51(クバツキー編VcとPf版)* アンダンテ・カンタービレOp.11(ゲリンガス編VcとPf版)* |
ボリス・ベレゾフスキー (P)、 アンリ・ドマルケット(Vc) 、 アレクサンドル・ヴェデルニコフ(指) シンフォニア・ヴァルソヴィア 録音:2012年9月ワルシャワ(ライヴ)*、 2013年4月サル・ガヴォー(パリ) |
|
||
| MIR-204 |
マティアス・ヴェックマン(1621-1674):宗教曲集~コンユラティオ 教会コンチェルト第1番「泣くな、ユダ族の獅子、ダヴィデの若枝は勝てり」 教会コンチェルト第2番「シオンは言う、主は割れを見捨てられたと」 教会コンチェルト第3番「主よ、我汝だけをもち得るなら」 教会コンチェルト第4番「町はなんと荒れ果てていることか」 コラール「いざや喜べ、愛するキリストの徒よ」 コラール「すべて重荷を負うて苦労している者は、私のものにきなさい」 コラール「主がシオンの捕虜を放たれた時」 第1旋法によるプレルーディウム 第2旋法によるマニフィカト |
リチェルカール・コンソート フィリップ・ピエルロ(指) |
|
||
 MIR-213 |
マタン・ポラト~MIRAREデビュー/カルラッティの主題による変奏曲 スカルラッティ:ソナタ.ニ短調K.32 クープラン:クラウザン曲集~「プラチナ色の髪のミューズ 」 No.19-6 ヤナーチェク:ないしょのスケッチ~「ただ先の見えない運命なのか?」 メンデルスゾーン:無言歌集Op.62-1より グリーグ:抒情小曲集Op.12-1 バルトーク:ミクロコスモス~「ハエの日記」 ブラームス:間奏曲ホ短調Op.116-5 ショパン:マズルカ.ホ短調Op.17-2 ブーレーズ:ノタシオン第11番 シューマン:森の情景~「予言の鳥」 サティ:グノシエンヌ第2番 ドビュッシー:前奏曲集第1集~「雪の上の足跡」 バッハ:パルティータ第1番BWV825~ジーグ ショスタコーヴィチ:抒情的なワルツ(人形の舞曲)Op.91b アンタイル:トッカータ第1番 チャイコフスキー:18の小品よりOp.72~「やさしい非難」 ベートーヴェン:バガテル変イ長調Op.33-7 ブーレーズ:ノタシオン第4番 モーツァルト:ジーグ.ト長調K574 リスト:オーベルマンの谷 リゲティ:ムジカ・リチェルカータ~第5番ルバート、ラメントーゾ ブーレーズ:ノタシオン第8番 スクリャービン:炎にむかってOp.72 ポラート:インプロヴィゼーション スカルラッティ:ソナタ.ニ短調K.32 |
マタン・ポラト(P) 録音:2013年1月28-30日ラ・シテ・ナント・イベント・センター |
|
||
| MIR-214 |
ジョバンニ・バッティスタ・フォンタナ(1571-1630):ソナタ集 ソナタ第11番(2Vn) ソナタ第4番(Vnソロ) ソナタ第1番(Flソロ) ソナタ第5番(Vnソロ) ソナタ第8番(2Vn) ソナタ第2番(Vn) ソナタ第3番(Flソロ) ソナタ第6番(Vnソロ) ソナタ第7番(2Vn) |
ダニエル・キュイエ(指、Vn) アンサンブル・ストラディヴァリア【アンヌ・シュヴァレロー(Vn) マリー・ノエル・ヴィセ・シュヴェルツ(Fl) ベルトラン・キュイエ(Cemb) ジョスリーヌ・キュイエ(Cemb)】 ブノワ・ヴァンデン・ベムデン(Vn) 録音:2011年11月29日、12月2日聖母教会、ナント |
|
||
| MIR-215 |
ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ音楽祭公式CD・2013 (1)クープラン:さまよう亡霊たち (2)バッハ:パルティータ第4番~アルマンド (3)ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第21番ハ長調Op53~第2楽章 (4)ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第2番イ長調Op2~第2楽章 (5)フォーレ:3つの無言歌~ロマンスOp.17-1 (6)ブラームス:ハンガリー舞曲第4 (7)シューマン:フモレスケOp.20より (8)ショパン:前奏曲第17番変イ長調アレグレット (9)メデンルスゾーン:無言歌集第3集「夕べの星」変ホ長調Op.38-1 (10)ヌーブルジェ:バガテル (11)スカルラッティ:ソナタ.イ短調K32 (12)ソレル:第24番R.359ニ短調 (13)グリンカ(バラキレフ編):ひばり (14)チャイコフスキー:無言歌ヘ長調Op2-3 (15)シェーンベルク:3つのピアノ曲~アンダンティーノ (16)ショスタコーヴィチ:前奏曲第10番Op34~ (17)ストラヴィンスキー:5つのやさしい小品 (18)メトネル:追憶のソナタ.イ短調 op.38-1(忘れられた調べ)第1集~ (19)フォーレ:ドリー組曲~子守歌 (20)サティ:ジムノペディ第1番 |
(1)イド・バルシャイ (2)シュ・シャ (3ニコラス・アンゲリッシュ (4)アブデル・ラーマン・エル・バシャ (5)ジャン=クロード・ペヌティエ (6)ボリス・ベレゾフスキー (7)アダム・ラルーム (8フィリップ・ジュジアーノ (9)(10)ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ (11)マタン・ポラト (12)ルイス・フェルナンド・ペレス (13)広瀬悦子 (14)クレール・マリ=ル・ゲ (15)フローラン・ボファール (16)アンドレイ・コロベイニコフ (17)リディヤ&サーニャ・ビジャーク (18)ダヴィッド・カドゥシュ (19)クレール・デゼール&エマニュエル・シュトロッセ (20)アンヌ・ケフェレック |
|
||
| MIR-217 ★ |
ルネ・マルタンのレ・ク・ドゥ・クール 2013 (1)ビゼー:「カルメン」 第2組曲 (2)ロドリーゴ:アランフェス協奏曲 (3)ラヴェル:ボレロ (4)ヒメネス:「ルイス・アロンソの結婚式」より(カスタネットとオーケストラのための) (5)ビゼー:「カルメン」第1組曲~ 闘牛士 (6)即興演奏 |
(1)ジャン=ジャック・カントロフ(指) シンフォニア・ヴァルソヴィア (2)フアン・マヌエル・カニサレス(G) ジャン=ジャック・カントロフ(指) シンフォニア・ヴァルソヴィア (3)フェイサル ・カルイ(指)ラムルーO (4)ルセロ・テナ(カスタネット) フェイサル ・カルイ(指)ラムルーO (5)ルセロ・テナ(カスタネット) フェイサル ・カルイ(指)ラムルーO (6)ルセロ・テナ(カスタネット) 録音:2013年2月にナントでおこなわれたラ・フォル・ジュルネ音楽祭のライヴ |
|
||
 MIR-218 |
スクリャービン:練習曲集(全曲) 練習曲嬰ハ短調Op.2-1、 12の練習曲Op.8、8つの練習曲Op.42、 練習曲変ホ長調Op.49-1、 練習曲変ホ長調Op.56-4、 3つの練習曲Op.65、 ピアノ・ソナタ第7番「白ミサ」Op.64 |
アンドレイ・コロベイニコフ(P) 録音:2013年5月21-23日:ミュンヘン、バイエルン放送局第1スタジオ |
|
||
 MIR-219 |
ルイス・フェルナンド・ペレス/ファリャ:作品集 交響的印象「スペインの庭の夜」* 「三角帽子」~隣人たちの踊り/粉屋の女房の踊り/粉屋の踊り アンダルシア幻想曲 「恋は魔術師」~きつね火の踊り/恐怖の踊り/魔法の輪/火祭りの踊り |
ルイス・フェルナンド・ペレス(P) カルロ・リッツィ(指)バスク国立O 録音:2013年4月11-12日ボルドー・オーディトリウム* 6月15-17日アルカラ・デ・エナーレス音楽室 |
|
||
 MIR-220 |
ハイドン:チェロ協奏曲第1番ハ長調、第2番ニ長調 モーツァルト:交響曲第29番イ長調K201 |
タチアナ・ヴァシリエヴァ(Vc) オーギュスタン・デュメイ(指) ワロニー王立CO |
|
||
| MIR-231 |
ハイドン:弦楽四重奏曲集 弦楽四重奏曲第75番ト長調Op.76-1 Hob.Ⅲ.75 、 弦楽四重奏曲第44番 変ロ長調Op.50-1 Hob.Ⅲ.44、 弦楽四重奏曲第81番ト長調Op.77-1 Hob.Ⅲ.81 |
モディリアーニSQ 【フィリップ・ベルナール、 ロイック・リョー(Vn) ローラン・マルフェング(Va) フランソワ・キエフェル(Vc)】 録音:2013年 4月21-24日ラ・グランジュ、エヴィアン=レ=バン |
|
||
| MIR-232 |
ラヴェル:ピアノ作品集 夜のガスパール 高雅にして感傷的なワルツ クープランの墓 |
ジャン=フレデリック・ヌーブル ジェ(P) 録音:2013 年 5月/フェルム・ドゥ・ヴィユファヴァール |
|
||
| MIR-235(4CD) ★ |
バッハ:平均律クラヴィーア曲集(全2巻) | シュ・シャオメイ(P) 録音: 2009年5月ノートルダム・ド・ボン・スクール教会、パリ(第1集) 2007年4月, 2009年4ヴィルファヴァール農場、リムザン、フランス(第2集) |
|
||
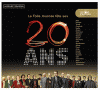 MIR-236(3CD) ★ |
ラ・フォル・ジュルネ音楽祭20周年記念アルバム ■CD1 1. バッハ:マニフィカトBWV243~マニフィカト *2009年「シュッツからバッハまで」 2. バッハ:オーボエ・ダモーレ協奏曲~第1楽章アレグロ *2006年「国々のハーモニー」 3. バッハ:カンタータ第106番「神の時こそ、いと良き時」BWV106 *2000年「ヨハン・ゼバスチャン・バッハ」 4.ヴィヴァルディ:詩篇第126番「ニシ・ドミヌス」RV608 *2009年「シュッツからバッハまで」 5. バッハ:マニフィカト BWV243~「エト・ミゼリコルディア(その憐れみは世々に限りなく)」 *2009年「シュッツからバッハまで」 6.ヘンデル:カンタータ「炎の中で」HWV170~アリア「翼をもつ者は空を飛ぶがよい」 *2006年「国々のハーモニー」 7. D.スカルラッティ:ソナタ.ト短調K.27 *2003年「モンテヴェルディとヴィヴァルディ」 8. バッハ/ジロティ編:前奏曲ト短調BWV855a 9. バッハ:前奏曲ハ長調BWV846 *2000年「ヨハン・ゼバスチャン・バッハ」 10.ソレル:ソナタ第129番ホ短調R.451 *2006年「国々のハーモニー」 11.ヘンデル:ハープ協奏曲第1番Op.4-6~第1楽章アンダンテ・アレグロ *2006年「国々のハーモニー」 12.パーセル:ディドとエネアスより *2006年「国々のハーモニー」 13.パーセル:しばし楽の音に *2006年「国々のハーモニー」 14.ペルゴレージ:スターバト・マーテルより「ドロローサ」 *2003年「モンテヴェルディとヴィヴァルディ」 15. バッハ:ミサ・ブレヴィスBWV234より「クイ・トリス」 *2009年「シュッツからバッハまで」 16. バッハ:ミサ曲ロ短調BWV232より「アニュス・デイ」 *2009年「シュッツからバッハまで」 17. バッハ:カンタータ150番「主よ、われ汝をあおぎ望む」BWV150より「チャコーナ」 *2000年「ヨハン・ゼバスチャン・バッハ」 18.ヴィヴァルディ:四季より「冬」 *2003年「モンテヴェルディとヴィヴァルディ」 ■CD2 1.ハイドン:チェロ協奏曲第1番より第2楽章 *2002年「ハイドン&モーツァルト」 2.モーツァルト:クラリネット協奏曲イ長調K.622より第2楽章 *1995年「モーツァルト」 3.シューベルト:ピアノ五重奏曲「ます」より第4楽章 *2008年「シューベルト、その生涯と境遇」 4.モーツァルト:ピアノ・ソナタ第10番ハ長調K.330より第1楽章 *1995年「モーツァルト」 5.ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第17番ニ短調Op.31-2「テンペスト」 より第3楽章 *2005年「ベートーヴェンと仲間たち」 6.ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第2番変ロ長調Op.19より第3楽章 *1996年「ベートーヴェン」 7.ベートーヴェン:エリーゼのためにWoO.59 *2005年「ベートーヴェンと仲間たち」 8.シューマン:予言の鳥 *2004年「1810年ロマン派音楽時代」 9.リスト:コンソレーション第3番 ブリジット・エンゲラー(P) *2004年「1810年ロマン派音楽時代」 10.ショパン:練習曲変ホ長調作品10-3 *2010年「ショパンの宇宙」 11.メンデルスゾーン:無言歌集より第6巻作品67-2「失われた幻影」 *2004年「1810年ロマン派音楽時代」 12.シューベルト:ピアノ三重奏曲第2番変ホ長調D929より第2楽章 *1997年「シューベルト」 13.ショパン:ピアノ協奏曲第2番より第2楽章 *2010年「ショパンの宇宙」 14.シューベルト:アヴェ・マリア *2008年「シューベルトその生涯と境遇」 ■CD3 1. R.シュトラウス:「ツァラトゥストラはかく語りき」より導入部 *2011年後期ロマン主義タイタンたち 2.ブラームス:ハンガリー舞曲第4番(ポール・ジュオン編) *2011年後期ロマン主義タイタンたち 3.ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番より第2楽章 *2001年熱狂の日イヴァン・イリイチ 4.ボロディン:だったん人の踊りより *2007年民族のハーモニー 5. ガヴリーリン :交響古劇「鐘の鳴る音」より<夕べの調べ> *2012年サクル・リュス(ロシアの祭典) 6.フォーレ:レクイエムよりサンクトゥス *1999年ヘクトル・ガブリエル・マウリキウス 7.アルベニス:アストゥリアス *2013年パリ、至福の時 8.ラヴェル:クープランの墓よりトッカータ *1999年ヘクトル・ガブリエル・マウリキウス 9.ドビュッシー:小さな黒人 *1999年ヘクトル・ガブリエル・マウリキウス 10.サティ:ジムノペディ第1番 *2013年パリ、至福の時 11.バーバー:パ・ドゥ・ドゥ *2014年峡谷から星たちへ 12.ドヴォルザーク:スラヴ舞曲ホ短調作品72-2 *2008年「シューベルトその生涯と境遇」 13.リムスキー=コルサコフ:熊蜂の飛行 *2001年熱狂の日イヴァン・イリイチ |
■CD1 1. フィリップ・ピエルロ(指) リチェルカール・コンソート 2. パトリック・ボージロー(Ob) フィリップ・ピエルロ(指) リチェルカール・コンソート 3. フィリップ・ピエルロ(指) リチェルカール・コンソート 4.カルロス・メーナ(CT)、 ハンス・イェルク・マンメル(T) フィリップ・ピエルロ(指) リチェルカール・コンソート 5. フィリップ・ピエルロ(指) リチェルカール・コンソート 6.ヌリア・リアル(S) 、 フィリップ・ピエルロ(指) リチェルカール・コンソート 7. ピエール・アンタイ(Cemb) 8. アンヌ・ケフェレック(P) 9. シュ・シャオ・メイ(P) 10.ルイス・フェルナンド・ペレス(P) 11.ジョヴァンナ・ペッシ(バッロクHrp) フィリップ・ピエルロ(指) リチェルカール・コンソート 12.ヌリア・リアル(S)、 セリーヌ・シェーン(S)、 リチェルカール・コンソート、 フィリップ・ピエルロ(指) 13.ジュリー・ヘスラー(S)、 ラ・レヴーズ ベンヤミン・ペロー&フローレンス・ボルトン(指) 14.ヌリア・リアル(S)、 カルロス・メーナ(CT) 、 フィリップ・ピエルロ(指) リチェルカール・コンソート 15. キャサリン・ フーグ(S)、 フィリップ・ピエルロ(指) リチェルカール・コンソート 16. ヴァレリー・ボナール(A)、 ローザンヌ器楽アンサンブル、 ミシェル・コルボ(指) 17. キャサリン・ フーグ(S)、 カルロス・メーナ(CT) ヤン・コボウ(T) ステファン・マクラウド(Bs)、 フィリップ・ピエルロ(指) リチェルカール・コンソート 18.ジル・コリャール(Vn)、 アンサンブル・バルバロック ■CD2 1.タチアナ・ヴァシリエヴァ(Vc) オーギュスタン・デュメイ(指) ワロニー王立室内O 2.ロマン・ギュイヨ(Cl) ヨーロッパ室内O 3.トリオ・ショーソン、 ペネロペ・ポアンシュヴァル(Cb)、 井上典子(Va) 4.シュ・シャオ・メイ(P) 5.アンドレイ・コロベイニコフ(P) 6.シャニ・ディリュカ(P) クワメ・ライアン(指) ボルドー・アキテーヌ国立O 7.ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) 8.ブリジット・エンゲラー(P) 9.ブリジット・エンゲラー(P) 10.フィリップ・ジュジアーノ(P) 11.シャニ・ディリュカ(P) 12.トリオ・ショーソン 13.ボリス・ベレゾフスキー(P) パリO、ジョン・ネルソン(指) 14.シレネゲイズ・スティール・バンド・オーケストラ ■CD3 1. ドミトリー・リス(指)ウラルPO 2.山田和樹(指)ウラルPO 3.ボリス・ベレゾフスキー(P) ドミトリー・リス(指)ウラルPO 4.ドミトリー・リス(指)ウラルPO、Cho 5. カペラ・サンクトペテルブルクCho ヴラディスラフ・チェルヌチェンコ(指) 6.ミシェル・コルボ(指) シンフォニア・ヴァルソヴィア ローザンヌ声楽アンサンブル、 7.アルベニス:アストゥリアス エマニュエル・ロスフェルダー(G) 8.ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) 9.アンヌ・ケフェレック(P) 10.アンヌ・ケフェレック(P) 11.シャニ・ディリュカ(P) 12.クレール・デゼール(P)、 エマニュエル・シュトロッセ(P) 13.クレール=マリ・ルゲ(P) |
|
||
| MIR-237 |
J.S.バッハ:音楽の捧げものBWV1079 3声のリチェルカーレ 王の主題による無窮カノン トリオ・ソナタ/無限カノン 王の主題による各種のカノン 上方5度のカノン風フーガ 6声のリチェルカーレ/謎のカノン |
リチェルカーレ・コンソート モード・グラットン(Cemb) マルク・アンタイ(Fl) フランソワ・フェルナンデス(Vn) フィリップ・ピエルロ(ヴィオラ・ダ・ガンバ) 録音:2011年11月、フランス、ルールマラン教会 |
|
||
| MIR-238 |
ガブリエル・デュポン:作品集 詩曲~ピアノと弦楽四重奏 「療養の時」~墓碑銘/陽をあびる庭日曜日の午後/友が花を持って来る 思わせぶり/庭で遊ぶ子供たち 平穏 「砂丘の家」~思い出の家 幸せの憂鬱 春の日~ヴァイオリンとピアノ |
マリー=カトリーヌ・ジロー(P)、 プラジャークSQ 録音:2013年8月マルティネク・スタジオ(プラハ) |
|
||
| MIR-239 |
ルート66~アメリカ音楽ピアノ作品集 ジョン・アダムズ:中国の門 キース・ジャレット:マイ・ワイルド・アイリッシュ・ローズ グレインジャー:子守唄 バーバー:パ・ドゥ・ドゥ エイミー・ビーチ:ヤング・バーチズ ビル・エヴァンス:ワルツ・フォー・デビイ フィリップ・グラス:エチュード第9番 バーンスタイン:フェリシア・モンテアレグレのために ジョン・ケージ:イン・ア・ランドスケープ ガーシュウィン(キース・ジャレット編):愛するポーギー バーンスタイン:間奏曲 ヒャン-キ・ジュー:シャンデルアーズ ヒナステラ:優雅な乙女の踊り バーンスタイン:アーロン・コープランドのために コープランド:ピアノ・ブルース第1番「レオ・スミットのために」 ビル・エヴァンス:ピース・ピース ガーシュウィン(グレインジャー編):愛が訪れた時 コール・ポーター(ラファエル・メルラン編):恋とはなんでしょう* |
シャニ・ディリュカ(P) ナタリー・デセイ* 録音:2013 年11月 |
|
||
 MIR-240 |
シューベルト:ピアノ作品集~星のかけら 感傷的なワルツD.779~第13番 16のドイツ舞曲 D.783~第5番、第14番、第15番、第10番 12のワルツD.145~第2番、第8番 12のドイツ舞曲D.790~第5番、第11番、第3番 高貴なワルツD.969~第10番 オリジナル舞曲集D.365~第1番 ハンガリー風のメロディ D.817 ピアノ・ソナタ第21番変ロ長調D.960 |
シャニ・ディリュカ(P) 録音:2013年9月 フランス、ナンテール芸術文化センター |
|
||
 MIR-241 |
ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲第6番変ホ長調Op.70-2 シューマン:ピアノ三重奏曲第3番ト短調Op.110 |
トリオ・レ・ゼスプリ 【アダム・ラルーム(P) 梁 美沙(ヤン・ミサ)(Vn) ヴィクトル・ジュリアン=ラフェリエール(Vc)】 録音:2013年4月28-30日サル・ガヴォー、パリ |
|
||
| MIR-242 |
デュカス:ピアノ曲全集 牧神のはるかなる嘆き ピアノ・ソナタ変ホ短調 ラモーの主題による変奏曲、間奏曲と終曲 ハイドンの名による悲歌的前奏曲 |
エルヴェ・ビヨー(P) 録音:2013年9月16-18日/ロシュボン城教会 |
|
||
| MIR-243 |
J.S.バッハ:待降節&クリスマスのカンタータ集 カンタータ第110番「われらの口を笑いで満たし」BWV110 カンタータ第151番「甘き慰め。わがイエスは来ませり」BWV151 カンタータ第63番「キリストの徒よ、この日を彫り刻め」BWV63 |
リチェルカール・コンソート マリア・コヘイン(S) カルロス・メーナ(A) ユリアン・プレガルディエン(T) ステファン・マクラウド(Bs) フィリップ・ピエルロ(指) 録音:2012年11月ベルギー |
|
||
| MIR-244 |
アメリカン・ジャーニー バーンスタイン:セレナード(プラトンの「饗宴」による) バーバー:弦楽のためのアダージョ バーナード・ハーマン:弦楽のための「サイコ」組曲 ガーシュウィン:3つの前奏曲(ピアノ独奏) アイヴス:答えのない質問 |
タイ・マレイ(Vn)、 ジャン=フランソワ・エッセール(P、指 ) ポワトゥー=シャラントO 録音:2013 年 10 月/ポワチエ・オードトリウム劇場 |
|
||
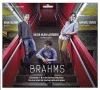 MIR-250 |
ブラームス:クラリネットのための作品集 クラリネット三重奏曲イ短調Op.114 クラリネット・ソナタ ヘ短調Op.120-1、 クラリネット・ソナタ 変ロ長調Op.120-2 |
ラファエル・セヴェール(Cl) アダム・ラルーム(P) ヴィクトル・ジュリアン=ラファリエール(Vc) 録音:2014年1月6-8日パリ、サル・ガヴォー |
|
||
| MIR-251 |
バッハ:コラール「ただ愛する神の摂理にまかす者」BWV691 幻想曲とフーガ.イ短調BWV944 イギリス組曲第2番イ短調BWV807 コラール「ただ、愛する神のみ旨に従うものは」BWV690 コラール「わが確信たるイエスは」BWV728 イタリア協奏曲BWV971 イギリス組曲第6番ニ短調BWV811 |
ピエール・アンタイ(Cemb) [使用楽器]ミヒャエル・ミートケ、ベルリン1702年製、ウィリアム・ダウド、パリ1984年製、ブルース・ケネディ、アムステルダム1994年製 録音:2014年4月ハールレム、オランダ |
|
||
 MIR-252(2CD) ★ |
アヴデーエワ/本格CDデヴュー シューベルト:3つのピアノ曲(第1曲変ホ短調、第2曲変ホ長調、第3曲ハ長調) プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第7番Op.83 ショパン:24の前奏曲Op.28 |
ユリアンナ・アヴデ ーエワ(P) 録音:2014年2月10-13日レ・ヴィンチ、コンベンションセンター、ピエール・ド・ロンサール・オーディトリウム |
|
||
| MIR-254 |
ラインハルト・カイザー(1674-1739):マルコ受難曲 | アマンディーヌ・ベイエ(Vn) アンサンブル・リ・インコーニティ ジャック・モデルヌ・アンサンブル ジョエ ル ・スュユビエット(指) ヤン・コボウ(テノール/ 福音史家) トーマス・E・バウアー(バス/イエス) 録音:2014 年 4月 |
|
||
| MIR-255 |
テレマン:四重奏曲集 ソナタ イ長調TWV43:A1、 ソナタ ト短調TWV43:g1、 協奏曲 ト長調TWV43:G1、 「6つの組曲からなる新四重奏曲集 」~四重奏曲第6番 ホ短調 TWV 43:e4 |
レ・ゾンブル シルヴァン・サルトル(フラウト・トラヴェルソ) マルゴー・ブランシャール(ヴィオラ・ダ・ガンバ) ジョナサン・ペシェク(Vc) ナディア・ルソニエ(Cemb) 録音:2013 年 |
|
||
| MIR-259 |
ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ・フェスティヴァル2014公式CD~プラタナスの木の下に佇むピアノ (1)ソレル:ソナタ.ホ短調第129番R.451 (2)バッハ:前奏曲変ロ短調BWV853 (3)クープラン:神秘のバリケード (4)モーツァルト:ピアノ・ソナタ.ハ短調K.457 (5)ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第17番「テンペスト」~第3楽章 (6)シューマン:森の情景~予言の鳥 (7)リスト:巡礼の年第1年~泉のほとりで (8)シューマン:ピアノ・ソナタ第1番嬰ヘ短調Op.11 (9)ショパン:前奏曲変ニ長調「雨だれ」Op.28-15 (10)ラフマニノフ:前奏曲嬰ト短調Op.32-12 (11)チャイコフスキー:中程度の12の小品Op.40-8 (12)ラフマニノフ:ひなぎくOp.40-8 (13)ビゼー:子供の遊びOp.22「小さい旦那様、小さい奥様」 (14)ドビュッシー:月の光 (15)ラヴェル:夜のガスパール~オンディーヌ (16)ヒナステラ:優雅な乙女の踊り (17)ガーシュウィン:3つの前奏曲 (18)アーン:冬 |
(1)ルイ・フェルナンド・ペレス(P) (2)シュ・シャオメイ(P) (3)イド・バル=シャイ(P) (4)アンヌ・ケフェレック(P) (5)アブデル・ラーマン・エル=バシャ(P) (6)マタン・ポラト(P) (7)ニコラ・アンゲリッシュ(P) (8)アダム・ラルーム(P) (9)フィリップ・ジュジアーノ(P) (10)ボリス・ベレゾフスキー(P) (11)ボリス・ベレゾフスキー(P) (12)クレール=マリ・ルゲ(P) (13)クレール・デゼール&エマニュエル・シュトロッセ(P) (14)アンヌ・ケフェレック(P) (15)ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) (16)シャニ・デュリカ(P) (17)ジャン=フランソワ・エッセール(P) (18)アンヌ・ケフェレック(P) |
|
||
| MIR-260 |
セメレ マラン・マレ:音楽悲劇「セメレ」(抜粋) デトゥーシュ:シンフォニーとソロのためのカンタータ「セメレ」 ヘンデル:音楽劇「セメレ」(抜粋)、 オラトリオ「テオドーラ」(抜粋)、 合奏協奏曲ヘ長調 Op. 3 NO 4, HWV 315、 オラトリオ「快活の人、沈思の人、温和の人」~愛らしい鳥、カンタータ「炎の中で」 |
シャンタル・サントン=ジェフェリー(S) メロディ・ルヴィオ(A) レ・ゾンブル マルゴー・ブランシャール&シルヴァン・サルトル.(音楽監督) 録音:2013 年 6 月フランス、ジュジュリュー、ボネ絹博物館 |
|
||
| MIR-261 |
ピアノ・デュオ作品集 ボロディン(ソコロフ編):だったん人の踊り ラヴェル(作曲者編):スペイン狂詩曲 グリーグ:ヴァルス=カプリスOp.37 ノルウェー舞曲集Op.35 バーバー:スーヴェニールOp.28 |
デュオ・ヤーテーコク【アデライード・パナジェ&ナイリ・バダル(ピアノ・デュオ)】 録音:2013年8月27-30日/コーク音楽学校公会堂(アイルランド) |
|
||
| MIR-262 |
スコラ・エテルナ~聖母マリアへの聖歌 フランク:パニス・アンジェリカス/天使の糧(ソプラノ)、 主よ、私たちを罰しないでください、 アヴェ・マリア、このお方はどなたか、 主の右手は、 パニス・アンジェリカス/天使の糧(テノール) ラドミロー:古いブルターニュの頌歌集 ベルティエ:諸聖人の日の奉納唱、 アヴェ・マリス・ステラ、 タントゥム・エルゴ、アヴェ・マリア ロパルツ:3声のミサ アラン:旋法的なミサ |
ローザンヌ声楽アンサンブル ミシェル・コルボ(指) 録音:2014年8月18,19日ヴィルファヴァール |
|
||
 MIR-264 |
バッハ:イタリア協奏曲BWV971 カプリッチョ「最愛の兄の旅立ちに寄せて」BWV992 シンフォニア第11番ホ短調BWV797 パルティータ第1番変ロ長調BWV825 インヴェンション第14番変ロ長調 半音階的幻想曲とフーガ.ニ短調BWV903 |
クレール=マリ・ル・ゲ(P) 録音:2014年6月ヴィルファヴァール農場 エンジニア:セシル・ルノアール |
|
||
| MIR-265 |
D・スカルラッティ:鍵盤のための18のソナタ集 ハ長調K.420/イ短調K.54/イ短調149/ト長調K.103/ト長調K.425/ホ短調K.147/ト長調K.144/ト長調K.260/イ短調K109/イ長調K.279/ニ長調K145/ヘ短調K.481/変ロ長調K.551/ニ短調K.32/ニ短調K.517/嬰ハ短調K.246/嬰ヘ長調K.318/ロ短調K.27 影と光~Ombre et lumiere |
アンヌ・ケフェレック(P) 録音:2014 年 9 月ポワティエ・オーディトリアム・シアター エンジニア:ユーグ・デショー |
|
||
| MIR-266(2CD) |
ラモー:クラヴサン曲集 クラヴサン曲集第1巻(1706)、 クラヴサン曲集(1724)、 王太子妃(1747)、 新クラヴサン曲集(1726-1727)、 コンセール用クラヴサン曲集(1741) |
ベルトラン・キュイエ(クラヴサン:フィリップ・ユモー
1977 年製) 録音:2014年1月3&6日、5月19&20日ロワイヨモン修道院 |
|
||
| MIR-267 |
テレマン:三重奏と四重奏曲集 ソナタ第2番ト短調TWV.43g1(クァドリ/1730年ハンブルク)、 三重奏曲第5番ト短調TWV.42g1(1718年フランクフルト)、 ソナタト長調TWV43:G12、ソナタイ短調TWV42:a7、三重奏曲第2番ト長調TWV42:G6(音楽の練習帳/1727年ハンブルク)、 『シャコンヌ(モデレ)』(パリ四重奏曲第6番より/1738年) |
ラ・レヴーズ 【フローレンス・ボルトン(ガンバ)、 ステファン・デュデルメル(Vn) セルジュ・サイッタ(トラヴェルソ) エミリー・オドゥワン(ガンバ) カルステン・ローフ(クラヴサン) ベンジャミン・ペロー(テオルボ)】 録音:2013 年9月サンセール教会 |
|
||
 MIR-268 |
バッハ:パルティータ第4番ニ長調BWV828 カプリッチョ変ロ長調「最愛の兄の旅立ちにあたって」BWV992 イギリス組曲第1番イ長調BWV806 トッカータ ハ短調BWV911 |
レミ・ジュニエ(P) 録音:2014 年 9 月ポワティエ・オーディトリアム・シアター(TAP) エンジニア:ユーグ・デショー |
|
||
| MIR-269 |
ドヴォルザーク:弦楽四重奏曲第12番ヘ長調『アメリカ』Op.96 バルトーク:弦楽四重奏曲第2番 ドホナーニ:弦楽四重奏曲第3番イ短調Op.33 |
モディリアーニSQ [フィリップ・ベルナール(ヴァイオリン:1780年製G.B.ガダニーニ) ロイック・リョー(ヴァイオリン:1734年製ガリアーノ) ローラン・マルフェング(ヴィオラ:1734年製ガリアーノ) フランソワ・キエフェル(チェロ:1706年ゴフリラー「ヴァールブルク」)] 録音:2015年3月サレ・コロンヌ、パリ |
|
||
| MIR-270 |
ブラームス:チェロ・ソナタ集 チェロ・ソナタ第1番ホ短調Op.38 チェロ・ソナタ第2番ヘ長調Op.99 ヴァイオリン・ソナタ第3番 ニ短調Op.108(チェロのための編曲版) |
アレクサンドル・クニャーゼフ(Vc) アンドレイ・コロベイニコフ(P) 録音:2014年10月/バイエルン放送スタジオ2(ミュンヘン) |
|
||
 MIR-271 |
トリオ・ショーソン~ハイドン&フンメル ハイドン:ピアノ三重奏曲第43番ハ長調Hob.XV:27、 ピアノ三重奏曲第5番ト短調Hob.XV:1、 ピアノ三重奏曲第25番ホ短調Hob.XV:12 フンメル:ピアノ三重奏曲第2番ヘ長調Op.22 |
トリオ・ショーソン 【フィリップ・タレク(Vn) アントワーヌ・ランドウスキ(Vc) ボリス・ド・ラロシェランベール(P)】 録音:2014年7月、アンギャン=レ=バン・アートセンター |
|
||
 MIR-273(3CD) |
スカルラッティ:チェンバロ・ソナタ集(50曲) ■CD1(MIR-9918) ソナタ.ニ長調K.535/ソナタ.イ短調K.3/ソナタ.イ短調K.175/ソナタ.イ短調K.208/ソナタ.イ短調K.54 / ソナタ.ヘ短調K.185/ソナタ.変ロ長調K.248/ソナタ.変ロ長調K.249/ソナタ.変ロ長調K.310/ソナタ.ニ長調 K.299 /ソナタ.ニ長調K.484 /ソナタ.ホ長調K.162/ソナタ.ハ長調K.199/ソナタ.ニ長調K.145/ソナタ.ニ短 調K.141/ソナタ.ホ短調K.531/ソナタ.ニ長調K.177/ソナタ.ニ長調K.492 ■CD2(MIR-9920) ソナタ.ハ短調 K.58/ソナタ.ヘ短調 K.239/ソナタ.変ホ長調 K.370/ソナタ.変ホ長調 K.371/ソナタ.ホ長調 K.135 /ソナタ.ホ長調 K.215/ソナタ.ホ長調 K.216/ソナタ.嬰ヘ短調 K.25/ソナタ.ロ長調 K.261/ソナタ.ロ長調 K.262 /ソナタ.ホ短調 K.263/ソナタ.ホ長調 K.264/ソナタ.ト長調 K.314/ソナタ.ト長調 K.259/ソナタ.ト長調 K.260 /ソナタ.ハ短調 K.84 ■CD3(MIR-007) ソナタ.ニ短調K.213/L.108/ソナタ.ニ長調K.214/L.165/ソナタ.ロ短調K.227/L.347/ソナタ.ニ長調K.511/L.314 /ソナタ.ト短調K.8/L.488/ソナタ.ハ短調K.56/G 356/ソナタ.ハ長調K.357/L.456/ソナタ.ヘ長調K.468/L.226 /ソナタ.ヘ長調K.525/L.188/ソナタ.ヘ短調K.466/L.118/ソナタ.ヘ長調K.366/L.119/ソナタ.ヘ長調K.276/L.S20 /ソナタ.ヘ長調 K.151/L.330/ソナタ.ニ短調 K.517/L.266/ソナタ.ロ短調 K.27/L.449/ソナタ.ト長調 K.146/L.349 |
ピエール・アンタイ(Cemb) [使用楽器]CD1:1999年テューリンゲン、ユルゲン・アンマー復元、1720年モデル製作者不明 CD2,3:2002年バルバスト、フィリップ・ユモー製作(イタリア式) CD1:録音:2002年 CD2:録音:2003年 CD3:録音:2005年 |
|
||
| MIR-274 |
バッハ:カプリッチョ「最愛の兄の旅立ちに寄せて」BWV992 シューマン:森の情景Op.82 ヤナーチェク:霧の中で バルトーク:戸外にて |
ダヴィッド・カドゥシュ(P) 録音:2014年10月24-26日 パリ、サル・ガヴォー |
|
||
 MIR-275 |
フォーレ:ピアノ作品集第3集 8つの小品Op.84 主題と変奏Op.73、 舟歌第4番変イ長調Op.44、 舟歌第5番嬰ヘ短調Op.66、 舟歌第6番変ホ長調Op.70、 ノクターン第6番変ニ長調 |
ジャン=クロード・ペヌティエ(P) 録音:2014 年12月 |
|
||
 MIR-277(2CD) ★ |
パシオン~魂と心 ■CD1【魂PASSION DE L'AME】 1.バッハ:ヨハネ受難曲~コラール「主よ、我らを治めたまう主よ」 2.ペルゴレージ:スターバト・マーテル~「肉体は死んで朽ち果てるとも」 3.ヴィヴァルディ:スターバト・マーテル~「悲しみに沈める聖母は」 4. ヴィヴァルディ:スターバト・マーテル~「いざ、愛の泉である聖母よ」 5.バッハ:カンタータ「我がうちに憂いは満ちぬ」BWV21~シンフォニア 6.テレマン:ソナタ ト短調 TWV43:g1~ラルゴ 7.J.M.バッハ:「ああ、いかにこの時を待ち望んでいたことか」 8.バッハ:チェンバロ協奏曲第5番ヘ短調BWV1056~ラルゴ 9.F.クープラン:王宮のコンセール第2番 10.パーセル:ここに神々はよしとし給う ラ・レヴーズ 11. バッハ:オーボエ協奏曲BWV1055a~ラルゲット 12.バッハ:ロ短調ミサ曲BWV232~われらのために十字架に架けられ 13.バッハ:カンタータ第198番「候妃よ、さらに一条の光を」BWV198(追悼頌歌) 14.バッハ:カンタータ第4番「キリストは死の縄目につながれたり」BWV4 15.バッハ:マニフィカトBWV243~僕イスラエルを 16.バッハ:ヨハネ受難曲~憩え安らけかに,聖なる御からだよ ■CD2【心PASSION DU COEUR】 1.ショパン:ピアノ協奏曲第2番~第1楽章 2.チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」~第2楽章 3.ボロディン:弦楽四重奏曲第2番~第3楽章 4.ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲ニ長調Op.70-1「幽霊」~第2楽章 5.ラフマニノフ:組曲第1番「幻想的絵画」~舟歌 6.グラナドス:ゴイェスカス第1部~第4曲「嘆き、またはマハと夜鳴きう ぐいす」 7.シューマン:ダヴィッド同盟舞曲集Op6~第2部第18番速くなく 8.ショパン:前奏曲Op.28第4番ホ短調 9.ショパン:前奏曲Op.28第8番嬰ヘ短調 10.シューマン:ピアノ協奏曲~第2楽章 11.フォーレ:組曲「ペレアスとメリザンド」Op.80~前奏曲 |
■CD1 1.リチェルカーレ・コンソート、フィリップ・ピエルロ(指) 2.リチェルカーレ・コンソート、フィリップ・ピエルロ(指)、ヌリア・リアル(S)、カルロス・メーナ(C.T) 3.リチェルカーレ・コンソート、フィリップ・ピエルロ(指)、カルロス・メーナ(C.T) 4. リチェルカーレ・コンソート フィリップ・ピエルロ(指)、カルロス・メーナ(C.T) 5.ル・コンセール・フランセ、ピエール・アンタイ(指)、アマンディーヌ・ベイエ(Vn)、アルフレート・ベルナルディーニ(Ob) 6.アンサンブル・レ・ゾンブル、マルゴー・ブランシャール&シルヴァン・サルトル(指) 7.リチェルカーレ・コンソート フィリップ・ピエルロ(指)、カルロス・メーナ(C.T) 8.ベルトラン・キュイエ(Cemb)、アンサンブル・ストラディヴァリア、ダニエル・キュイエ(指) 9フィリップ・ピエルロ(ヴィオール)、エマニュエル・バルサ(ヴィオール)、エドゥアルド・エグエス(テオルボ、ギター)、ピエール・アンタイ(クラヴサン) 10.ジュリー・ハスラー(S)、フローレンス・ボルトン(ヴィオール&指)、バンジャマン・ペロー(テオルボ&指) 11. フィリップ・ピエルロ(指)リチェルカーレ・コンソート、パトリック・ボージロー(Ob) 12.ローザンヌ声楽・器楽アンサンブル、ミシェル・コルボ(指) 13.フィリップ・ピエルロ(指)リチェルカーレ・コンソート、キャサリン・フュージュ(S)、カルロス・メーナ(C.T)、ハンス=イェルク・マンメル(T)、ステファン・マクラウド(Bs) 14.フィリップ・ピエルロ(指)リチェルカーレ・コンソート、キャサリン・フュージュ(S)、カルロス・メーナ(C.T) 15.フィリップ・ピエルロ(指)リチェルカーレ・コンソート、マリア・ケオハネ(S)、アンナ・ツァンダー(S)、カルロス・メーナ(C.T) 16.チェルカーレ・コンソート、フィリップ・ピエルロ(指) ■CD2 1.リス・ベレゾフスキー(P)、パリ室内O、ジョン・ネルソン(指) 2.シンフォニア・ヴァルソヴィア、イェジー・セムコフ(指) 3.プラジャークQ 4.プラハ・グァルネリ・トリオ 5.ボリス・ベレゾフスキー&ブリジット・エンゲラー(P) 6.ルイス・フェルナンド・ペレス(P) 7.クレール・デゼール(P) 8.9.ユリアンナ・アヴデーエワ(P) 10.広瀬悦子(P)、フェイサル・カルイ(指)ベアルン地方ポーO 11.パリ室内O、トーマス・ツェートマイアー(指) |
|
||
| MIR-280 |
シューベルト:幻想曲 ヘ短調 Op.103,D.940 創作主題による8つの変奏曲 変イ長調 Op.35,D.813 アレグロ イ短調「人生の嵐」Op.144,D.947 フランスのモティーフによるディヴェルティメント ホ短調D.823~アンダンティーノと変奏曲 ロ短調 Op.84 |
クレール・デゼール(P) エマニュエル・シュトロッセ(P) 録音:2015年1月/サン=ルイ劇場 |
|
||
| MIR-282 |
ブラームス:クラリネット五重奏曲ロ短調op.115 ヒンデミット:クラリネット五重奏曲 op.30 |
ラファエル・セヴェール(Cl) プラジャークSQ 録音:2015年5月 |
|
||
| MIR-283 |
ヘンリー・パーセル:賛歌とアンセム ゴットフリート・フィンガー(1660年頃~1730):ソナタとディヴィジョン |
ジェフリー・トンプソン(T) マルク・モイヨン(T) ジェフロワ・ビュフィエ(Bs) フローレンス・ボルトン(バス・ヴィオラ・ダ・ガンバ) ピエール・ガロン(クラヴサン・オルガン) バンジャマン・ペロ(テオルボ) ラ・レヴーズ 録音:2014年11月 |
|
||
| MIR-285 |
D・スカルラッティ:ソナタ集VOL.4 ソナタ.イ長調 K.212/ソナタ.ニ短調 K.247 ソナタ.ト長調 K.144/ソナタ.ハ長調 K.133 ソナタ.ヘ短調 K.204a/ソナタ.イ長調 K279 ソナタ.イ長調 K.533/ソナタ.イ長調 K.405 ソナタ.ホ短調 K.402/ソナタ.ホ長調 K.403 ソナタ.ホ長調 K.381/ソナタ.イ長調 K.208 ソナタ.イ長調 K.456/ソナタ.イ長調 K.457 ソナタ.ハ短調 K.302/ソナタ.ト長調 K.201 ソナタ.ニ長調 K.45 |
ピエール・アンタイ(Cemb:Jonte Knif2004年製) 録音:2015年6月、オランダ、ハールレム |
|
||
| MIR-286 |
第35回ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ音楽祭 (1)J.S.バッハ:カプリッチョ変ロ長調「最愛の兄の旅立ちに寄せて」BWV992 (2)スカルラッティ:ソナタ.ニ短調 K.32~アリア (3)クープラン:プラチナ色の髪のミューズ (4)J.S.バッハ:シンフォニア第11番ト短調BWV797 (5)グリーグ:ピアノ抒情小品集Op.12-1 (6)ボロディン:ダッタン人の踊り (7)バラキレフ:ソナタ 変ロ短調~間奏曲 (8)ショパン:前奏曲第15番変ニ長調Op.28~ソステヌー (9)スクリャービン:練習曲Op.2-1 (10)ラヴェル:高貴で感傷的なワルツ~レント (11)ドビュッシー:小組曲~小舟にて (12)チャイコフスキー:12の小品~シャンソン・トリエステ (13)デュポン:砂丘にある家~思い出の家 (14)フォーレ:夜想曲変ニ長調 (15)リスト:巡礼の年第2年イタリア~サルヴァトール・ローザのカンツォネッタ (16)シェーンベルク:ピアノ小曲集~アンダンテ・グラツィオーゾ (17)デュカス:牧神のはるかなる嘆き (18)ストラヴィンスキー:5つのやさしい小品~ナポリ風 (19)シューマン:森の情景~別れ (20)シューマン:フモレスケ~第2曲性急に-アダージョ (21)ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第19番ト短調Op.49~第1楽章 (22)キース・ジャレット:マイ・ワイルド・アイリッシュ・ローズ |
(1)レミ・ジュニエ (2)アンヌ・ケフェレック (3)イド・バルシャイ (4)クレール=マリ・ル・ゲ (5)マタン・ポラト (6)/デュオ・ヤーテーコク (7)広瀬悦子 (8)ユリアンナ・アヴデーエワ (9)アンドレイ・コロベイニコフ (10)ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ (11)クレール・デゼール&エマニュエル・シュトロッセ (12)ボリス・ベレゾフスキー (13)マリー=カトリーヌ・ジロー (14)ジャン=クロード・ペヌティエ (15)ニコラ・アンゲリッシュ (16)フローラン・ボッファール (17)エルヴェ・ビヨー (18)リディヤ・ビジャーク&サーニャ・ビジャーク (19)ダヴィッド・カドゥシュ (20)アダム・ラルーム (21)アブデル・ラーマン・エル=バシャ (22)シャニ・ディリュカ |
|
||
| MIR-287(2CD) |
シャニ・ディリュカBOX ■CD1(MIR126) ベートーヴェン:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲第2番 ピアノ協奏曲第1番 ■CD2(MIR062) メンデルスゾーン:作品集 無言歌集第1巻よりホ長調「甘い思い出」Op.19-1、第6巻より嬰ヘ短調「失われた幻影」Op.67-2/変ホ長調「瞑想」Op.67-1/ハ長調「紡ぎ歌」Op.67-4、第7巻よりニ長調「悲歌」Op.85-4、第8巻よりホ短調「寄る辺なく」Op.102-1/ト短調「そよぐ風」Op.102-4/イ長調「楽しき農夫」Op.102-5/舟歌Op.102-7(遺作) 厳格な変奏曲Op.54、 ピアノ三重奏曲第1番Op.49~アンダンテ・コン・モート・トランクィロ(シャニ・ディリュカ自身によるピアノ独奏用編曲)、 幻想曲嬰ヘ短調「スコットランド・ソナタ」Op.28 |
■CD1(MIR126) シャニ・ディリュカ(P) クワメ・ライアン(指)ボルドー・アキテーヌ国立感 録音:2010年4月 ■CD2(MIR062) シャニ・ディリュカ(P) |
| MIR-288(2CD) |
タチアナ・ヴァシリエヴァBOX ■CD1(MIR107) ショパン:チェロ・ソナタ.ト短調Op.65 序奏と華麗なるポロネーズハ長調Op.3 アルカン:演奏会用ソナタホ長調Op.47 ■CD2(MIR220) ハイドン:チェロ協奏曲第1番ハ長調、 チェロ協奏曲第2番ニ長調, モーツァルト:交響曲第29番イ長調K201 |
■CD1(MIR107) タチアナ・ヴァシリエヴァ(Vc) ジャン・フレデリック・ヌーブルジェ(P) 録音:2009年9月 ■CD2(MIR220) タチアナ・ヴァシリエヴァ(Vc) オーギュスタン・デュメイ(指)ワロニー王立CO |
| MIR-289(2CD) |
ピエール・アンタイBOX~バッハ、ラモー ■CD1(MIR017) J.S.バッハ:管弦楽組曲第1BWV1069、第4番BWV1066 ヴァイオリンとクラヴィーアためのソナタ第4番BWV1017 カンタータ<われは憂いに沈みぬ>BWV21~シンフォニア ■CD2(MIR164) ラモー:歌劇『優雅なインド』より(序曲、ミュゼット、メヌエット、タンブーラン、ポーランド人たちのエール、アフリカの奴隷たちのエール、ガヴォット、シャコンヌ、未開人たち) 歌劇『ダルダニュス』より(シャコンヌ、プレリュード、優美なエール、タンブラン) 歌劇『プラテ』より(ミュゼット、ヴィエール風のメヌエット) 歌劇『ゾロアスター』より(メヌエット、サラバンド) 歌劇『ピュグマリオン』より(序曲) 歌劇『遍歴騎士』より(とても陽気なエール、少しゆるやかなガヴォット) 歌劇『イポリトとアリシー』より(メヌエット) 歌劇『エベの祭』より(タンブラン) コンセール用のクラヴサン曲集より(軽はずみ、パントマイム、おしゃべり、内気、マレー) |
■CD1(MIR017) ピエール・アンタイ(指) ル・コンセール・フランセ アマンディーヌ・ベイェ(バロックVn) アルフレード・ベルナルディーニ(Ob) 録音:2006年1月 ■CD2(MIR164) ピエール・アンタイ(クラヴサン) スキップ・センペ(クラヴサン) 録音:2011年7月、12月フランス、アラス劇場 |
 MIR-290(3CD) |
ボリス・ベレゾフスキーBOX~ブラームス、メトネル、チャイコフスキー ■CD1(MIR059) メトネル:作品集 3つのロマンスOp.3~第2曲のぞみの日々も流れ去り(プーシキン)* 4つのおとぎ話Op.34~第2曲ホ短調 プーシキンの7つの詩Op.29~第4曲「馬」* 3つのおとぎ話Op.42~第1曲ヘ短調 8つの詩Op.24~なぜ水の上に柳は垂れる(チュッチェフ)# プーシキンの詩による7つの歌Op.52~第2曲カラス# フェート、ブリューソフ、チュッチェフによる7つの詩Op.28~第5曲「春の静けさ」(ウーラント/チュッチェフ)* 2つのおとぎ話Op.14~ヘ短調「オフィーリアの歌」、ホ短調「騎士の行進」 4つのおとぎ話Op.35~第4曲ニ短調 2つのおとぎ話Op.48~第2曲ト短調(妖精のおとぎ話) ゲーテの詩による9つの歌Op.6~第3曲妖精の歌# ハイネの3つの詩Op.12~第1曲いとしい恋人、君の手を* ゲーテの詩による9つの歌Op.6~第5曲可愛い子供よ* 8つの詩Op.24~第1曲「昼と夜」(チュッチェフ)# 3つのロマンスOp.3~第1曲聖なる僧院の門の傍らに(レールモントフ)* 8つの詩Op.24~第4曲「夕暮」(チュッチェフ)# 8つの詩Op.24~第7曲ささやき、微かな吐息(フェート)* プーシキンの6つの詩Op.36~第2曲「花」# チュッチェフとフェートによる5つの詩Op.37~第4曲ヘ短調# 4つのおとぎ話Op.26~第2曲変ホ長調 チュッチェフとフェートによる5つの詩Op.37~第1曲眠れずに(チュッチェフ)# プーシキンの7つの詩Op.29~第7曲呪文* 2つの詩Op.13~第1曲冬の夕べ(プーシキン)* 2つのおとぎ話Op.20~第2曲ロ短調「鐘」 ■CD2(MIR132) ブラームス:アノ協奏曲第2番 パガニーニの主題による変奏曲* ハンガリー舞曲第1番/第2番/4番 ■CD3(MIR200) チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第2番(オリジナル版)* 主題と変奏曲Op.19の6 悲しき歌Op.40の2/マズルカOp.40の5 無言歌Op.40の6/村にてOp.40の7 ワルツOp.40の8 感傷的なワルツOp.51(クバツキー編VcとPf版) アンダンテ・カンタービレOp.11(ゲリンガス編VcとPf版) |
■CD1(MIR059) ボリス・ベレゾフスキー(P) イヤナ・イヴァニロヴァ(S)# ヴァシリー・サヴェンコ(B)* 録音:2007年12月 ■CD2(MIR132) ボリス・ベレゾフスキー(P) ドミトリー・リス(指)ウラルPO 録音:2010年11月エカテリンブルグ(ライヴ、*は除く) ■CD3(MIR200) チャイコフスキー: ボリス・ベレゾフスキー(P) アンリ・ドマルケット(Vc) アレクサンドル・ヴェデルニコフ(指) シンフォニア・ヴァルソヴィア [録音:2012年9月ワルシャワ(ライヴ)*、2013年4月サル・ガヴォー(パリ) |
| MIR-291(3CD) |
アンドレイ・コロベイニコフBOX~スクリャービン他 ■CD1(MIR061) スクリャービン:ピアノ・ソナタ第4番嬰ヘ長調Op.30、 2つの詩曲Op.32、 ピアノ・ソナタ第5番Op.53、 2つの詩曲Op.69、 ピアノ・ソナタ第8番Op.66、 2つの詩曲Op.71、 ピアノ・ソナタ第9番「黒ミサ」Op.68、 詩曲「炎に向かって」Op.72 ■CD2(MIR090) ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第30番 6つのバガテル、 ピアノ・ソナタ第24番、 ピアノ・ソナタ第17番 ■CD3(MIR155) ショスタコーヴィチ:ピアノ協奏曲第1番*、 24の前奏曲Op.34、 ピアノ協奏曲第2番 |
■CD1(MIR061) アンドレイ・コロベイニコフ(P) 録音:2008年1月 ■CD2(MIR090) アンドレイ・コロベイニコフ(P) 録音:2009年5月フランス・リモージュ ■CD3(MIR155) アンドレイ・コロベイニコフ(P) ミハイル・ガイドゥーク(Tp)* オッコ・カム(指)ラハティSO 録音:2011年5月26/28/シベリウス・ホール(ラハティ) |
| MIR-292(3CD) |
イド・バル=シャイBOX ■CD1(MIR014) ハイドン:ピアノ・ソナタ集 第24(39)番ニ長調Hob.XVI-24 第23(38)番ヘ長調Hob.XVI-23 第40(54)番ト長調Hob.XVI-40 第49(59)番ニ長調Hob.XVI-49 アンダンテと変奏曲ヘ短調Hob.XVII-6 ■CD2(MIR075) ショパン:マズルカ集 マズルカ第47番イ短調 マズルカ第7番ヘ短調 4つのマズルカOp.17〔第10番変ロ長調、第11番ホ短調、第12番変イ長調、第13番イ短調〕 マズルカ第56番変ロ長調 4つのマズルカOp.24〔第14番ト短調、第15番ハ長調、第16番変イ長調、第17番変ロ短調〕 マズルカ第42番ト長調 マズルカ第44番ハ長調 4つのマズルカOp.30〔第18番ハ短調、第19番ロ短調、第20番変ニ長調、第21番嬰ハ短調〕 4つのマズルカOp.33〔第22番嬰ト短調、第23番ニ長調、第24番ハ長調、第25番ロ短調〕 マズルカ第26番嬰ハ短調 マズルカ第29番変イ長調 マズルカ第42番イ短調「エミール・ガイヤール」 マズルカ第32番嬰ハ短調 マズルカ第45番イ短調 マズルカ第43番ト短調 マズルカ第40番ヘ短調 マズルカ第41番嬰ハ短調 マズルカ第49番ヘ短調 ■CD3(MIR195) フランソワ・クープラン:クラヴサン曲集 さまよう亡霊たち/修道女モニク/ティクトクショック、またはオリーヴしぼり機/プラチナ色の髪のミューズ/恋のナイチンゲール/ナイチンゲールの変奏/子供時代-ミューズの誕生-幼年期/タンブラン/神秘的な女/小さな皮肉/ロジヴィエール/子守歌、またはゆりかごの中のいとし子/おしゃべり女/心地よい恋やつれ/花咲く果樹園/葦/胸飾りのリボン/煉獄の魂/収穫をする人びと/髪の油/嘆きのほおじろ/騒がしさ/クープラン/神秘なバリケード |
■CD1(MIR014) イド・バル=シャイ(P) 録音:2006年1月 ■CD2(MIR075) イド・バル=シャイ(P) 録音:2008年9月 ■CD3(MIR195) イド・バル=シャイ(P) |
 MIR-293(3CD) |
リチェルカール・コンソートBOX~Instrumental ■CD1(MIR9969) アントニオ・ベルターリ、ヴァロローゾ(腕のよいヴァイオリニスト) アントニオ・ベルターリ:2,3,5,6声のためのソナタ(7曲) シャコンヌ,レオポルド1世:「天の女王」(ベルターリ作曲:ヴィオール伴奏部) 作曲者不詳(クロムニェジーシュ写本):ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナティナ フィリップ・ピエルロ(指&ヴィオラ・ダ・ガンバ) ■CD2(MIR012) パーセル:ヴィオールのためのファンタジア集 グランドによる3声のファンタジア,パヴァーヌ,3声のファンタジア,4声のファンタジア,一音に基づく5声のファンタジア,6声のファンタジア「イン・ノミネ」,7声のファンタジア「イン・ノミネ」 ■CD3(MIR150) フランソワ・クープラン:パルナッソス山、またはコレッリ賛 ルベル:リュリ氏のトンボー クープラン:リュリ賛 |
■CD1(MIR9969) フィリップ・ピエルロ(指&ヴィオラ・ダ・ガンバ) リチェルカール・コンソート,フランソワ・フェルナンデス(Vn)、カルロス・メーナ(C.T) 録音:2003年9月21-24日ベルギー、ブラ=スュル=リエンヌ教会 ■CD2(MIR012) リチェルカール・コンソート フィリップ・ピエルロ(指) 上村かおり,ライナー・ツィッパリング,エマニュエル・バルサ,ミエネケ・ファン・デル・ヴェルデン,ソフィア・デニズ,フランソワ・フェルナンデス, ルイス・オクラビオ・サント,ジョバンナ・ペシ 録音:2005年7月 ■CD3(MIR150) フィリップ・ピエルロ(指&ヴィオラ・ダ・ガンバ)、リチェルカール・コンソート 録音:2010年9月、ボーフェ(ベルギー) |
| MIR-294(3CD) |
リチェルカール・コンソートBOX~Vocal ■CD1(MIR009) J.S.バッハ:オーボエ協奏曲BWV.1055、 結婚カンタータ『今ぞ去れ、悲しみの影よ』BWV.202 ヘンデル:ハープ協奏曲、 カンタータ『炎の中で』HWV.170 ■CD2(MIR204) マティアス・ヴェックマン(1621-1674):宗教曲集~コンユラティオ 教会コンチェルト第1番「泣くな、ユダ族の獅子、ダヴィデの若枝は勝てり」 教会コンチェルト第2番「シオンは言う、主は割れを見捨てられたと」 教会コンチェルト第3番「主よ、我汝だけをもち得るなら」 教会コンチェルト第4番「町はなんと荒れ果てていることか」 コラール「いざや喜べ、愛するキリストの徒よ」 コラール「すべて重荷を負うて苦労している者は、私のものにきなさい」 コラール「主がシオンの捕虜を放たれた時」 第1旋法によるプレルーディウム, 第2旋法によるマニフィカト ■CD3(MIR243) J.S.バッハ:待降節&クリスマスのカンタータ集 カンタータ第110番「われらの口を笑いで満たし」BWV110 カンタータ第151番「甘き慰め。わがイエスは来ませり」BWV151 カンタータ第63番「キリストの徒よ、この日を彫り刻め」BWV63 |
■CD1(MIR009) ヌリア・リアル(S)、ジョバンナ・ペシ(Hp)、パトリック・ボージロー(Ob)、リチェルカール・コンソート フィリップ・ピエルロ(指) ■CD2(MIR204) マリア・ケオハネ(S)、カルロス・メーナ(C.T)、ハンス=イェルク・マンメル(T)、ステファン・マクラウド(Bs)、モード・グラットン(Org)、リチェルカール・コンソートフィリップ・ピエルロ(指) ■CD3(MIR243) マリア・コヘイン(S)、カルロス・メーナ(A)、ユリアン・プレガルディエン(T)、ステファン・マクラウド(Bs)、リチェルカール・コンソート フィリップ・ピエルロ(指) 録音:2012年11月ベルギー |
| MIR-295(3CD) |
ラ・レヴーズBOX ■CD1(MIR033) ヘンリー・パーセル:わずらわしき世の中よ~歌曲、室内楽曲集 わずらわしき世の中よ Cease, anxious World 新しいアイルランドの歌 ト長調 Z.646 A new irish tune 優しき音と美しい調べ Soft Notes, and gently rais'd 新しいグラウンド ホ短調 Z.T682 A new Ground 日陰の冷たく心地よき流れの中で A midst the Shades 王子 A Prince アミンタスが初めて口づけを求めし時 When first Aminta's su'd for a kiss ここに神が Here the deities プレリュード Prelude トリオ・ソナタ Z.780 Trio sonata 薔薇より甘く Sweet than roses グラウンド ZD.221 Ground ひとときの音楽 Music for a while 愛らしい素敵な人 Dear pretty youth ソナタ(G . フィンガー作曲) 嘆きの歌 O let me weep ■CD2(MIR125) セバスティアン・ド・ブロサール(1655-1730):オラトリオ「無原罪の聖マリア」SDB.56 ソナタハ長調SDB.224 カンタータ「レアンドロ」SDB.77 「悔い改めた魂と神との対話」SDB.55 ■CD3(MIR177) ヘンリー・ローズ:歌曲集 朝日を見たことがあるか? ゆるやかに流れよ、銀色の川 ただ生きよと命じて下さい グラウンドによるディヴィジョン(フランシス・ウィシィ?) 前奏曲(ダニエル・バチェラー?) 私は起き上がり、深く悲しむ あなたか私か、罪を犯した ため息も涙も悲しみもなく(ニコラス・ラニアー?) 2つのリュートのためのアルマイン/クーラントⅠ/クーラントⅡ(ウィリアム・ローズ?)/Whither are all her false oaths blown ? 私は恋の病(ウィリアム・ローズ?) 草原はもはや花に覆われることなく(ニコラス・ラニアー?) トレギアンのグラウンド あわれにも愛の喜びから追放された君が 穏やかに眠れ/・離せ、愛していた クーラント(ジャック・ゴーティエ/アングレテールのゴーティエ) ゴーティエ氏の鐘(ジャック・ゴーティエ/アングレテールのゴーティエ) きみよまだ帰らないでおくれ おお、愛を教えて!おお、運命を教えて! ディヴィジョン:ジョン、今すぐ私にキスして(クリストファー・シンプソン?)/Wert thou yet fairer than thou art なぜそう青白く暗いのか、盲目的に恋する者よ(ウィリアム・ローズ?) |
■CD1(MIR033) ラ・レヴーズ ジュリー・ハスラー(S) ステファン・デュデルメル(Vn)フ ローレンス・ボルトン(ヴィオール) アンジェリーク・モイヨン(Hp) ベルトラン・キュイエ(Clavcin) バンジャマン・ペロー(テオルボ&指) 録音:2007年2月 ■CD2(MIR125) ラ・レヴーズ シャルタン・サントン・ジェフリー(S) ウジェニー・ヴァルニエ(S) イザベル・ドリュエ(A) ジェフリー・トンプソン(CT) ヴァンサン・ブーショ(T)ベノワ・アルヌール(B) 録音:2010年6月28日-7月1日 ■CD3(MIR177) ラ・レヴーズ, フローレンス・ボルトン(指、Va) ベンジャミン・ペロー(指、Lute、テオルボ&バロック・ギター) ジェフリー・トンプソン(T) ベルトラン・キュイエ(ハープシコード) |
| MIR-296(6CD) |
ジャン=フレデリック・ヌーブルジェBOX ■CD1、2(MIR023) カール・ツェルニー:指使いの技法(50番練習曲)Op.740, リスト:2つの演奏会用練習曲「森のざわめき」「小人の踊り」、3つの演奏会用練習曲より「軽やかさ」, ステファン・ヘラー:4つの練習曲 ■CD3、4(MIR060) ライヴ・アット・サントリーホール J.S.バッハ:イギリス組曲第2番イ短調BWV.807, ショパン:バラード第2番Op.38、 ノクターンヘ長調Op.15-1, ラヴェル:ラ・ヴァルス リスト:ロ短調ソナタ, ラヴェル:古風なメヌエット, ストラヴィンスキー:練習曲嬰ヘ長調Op.7-4, ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ:バガテル, J.S.バッハ(S.フェインベルグ編):オルガンのためのソナタ第5番より「ラルゴ」 ■CD5(MIR145) ピアノ・リサイタルinパリ リスト:詩的で宗教的な調べより「葬儀」 ヌーブルジェ:マルドロール J.バラケ:ピアノ・ソナタ(全2楽章) ドビュッシー:映像第2集~「そして月は荒れた寺院に落ちる」 ■CD6(MIR232) ラヴェル:ピアノ作品集 夜のガスパール、 高雅にして感傷的なワルツ 、クープランの墓 |
■CD1、2(MIR023) ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) 録音:2006年9月 ■CD3.4(MIR060) ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) 録音:2007年11月17日サントリーホール ■CD5(MIR145) ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) 録音:2011年1月14日、ラ・シテ・ドゥ・ラ・ムジークライブ録音(パリ) ■CD6(MIR232) ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) 録音:2013年5月/フェルム・ドゥ・ヴィユファヴァール |
| MIR-298 |
サンーサーンス:組曲「動物の謝肉祭」 | ボリス・ベレゾフスキー(P) ブリジット・エンゲラー(P) ミシェル・ギュイヨ(Vn) デボラ・ネムタヌ(Vn) セルジュ・スフラール(Va) アンリ・ドマルケット(Vc) エックハルト・ルドルフ(Cb) マリーナ・シャモー=ルゲ(Fl) リシャール・ヴィエイユ(Cl) ナタリー・ジュジョン=ガンティエ (パーカッション) イオネラ・クリストゥ(パーカッション) |
|
||
 MIR-299 |
シューマン:ダヴィッド同盟舞曲集Op.6 シューベルト:ピアノ・ソナタ第21番変ロ長調D960 |
アダム・ラルーム(P) 録音:2015年7月21-23日パリ、サル・ガヴォー |
|
||
 MIR-301 |
ショパン:幻想曲 ヘ短調 作品49 モーツァルト:ピアノ・ソナタ第6番ニ長調K.284 リスト:巡礼の年第2年「イタリア」~ダンテを読んで-ソナタ風幻想曲 ヴェルディ(リスト編):「アイーダ」~神前の踊りと終幕の二重唱S.436 |
ユリアンナ・アヴデーエワ(P) 録音:2015年、ノイマルクト、ライツターデル ※日本語解説帯付 |
|
||
| MIR-302 |
ビーバー、シュメルツァー、ポリエッティ、ケルル作品集~標題音楽と幻想様式 ビーバー:5声のセレナード*、4声の嘆きのバレット、ソナタ6番、戦い シュメルツァー:ソナタ・レプレゼンタティヴァ、ヴィオールとヴィオラのためのソナタ、古いアリアによるセレナータ アレッサンドロ・ポリエッティ: 「ハンガリーの反乱」によるトッカッティーナ ケルル:シュタイアーの羊飼い、ソナタA.3.ex.G.B mol ** |
リチェルカール・コンソート ソフィー・ジェント、トゥオモ・スニ(Vn)、フィリップ・ピエルロ(バス・ド・ヴィオール、ヴィオール・アルト)、上村かおり、ライナー・ツィパーリング(バス・ド・ヴィオール)、フランク・コピーテルス(ヴィオローネ)、マウデ・グラットン(クラヴサン)、ジュリアン・ウォルフス(オルガン・クラヴサン)、 マティアス・フィーヴェク(バス)*、サラ・クイケン(Vn)** フレデリック・ヒルデブランド(ヴィオール)**、サンネ・デプレッテーレ(ヴィオローネ)** 録音:2014年12月 |
|
||
| MIR-303 |
ラ・レヴーズによるブクスデフーデ ブクステフーデ:ヴァイオリン,ヴィオラ・ダ・ガンバと通奏低音のためのソナタ イ短調 BuxWV272* トリオ・ソナタ集 op.2より第3番ト短調 BuxWV261(ハンブルク1696) ヴィオラ・ダ・ガンバ,ヴィオローネと通奏低音のためのソナタニ長調 BuxWV267* ヴァイオリン,ヴィオラ・ダ・ガンバと通奏低音のためのソナタと組曲変ロ長調 BuxWV273* ディートリヒ・ベッカー:ソナタと組曲ニ長調(ハンブルク1674) 作曲者不詳:無伴奏ヴィオラ・ダ・ガンバのためのソナタ.ニ短調(リューベック) |
ラ・レヴーズ ステファン・デュデルメル((Vn) フローレンス・ボルトン(ヴィオール) バンジャマン・ペロー(テオルボ) エミリー・オードワン(ヴィオラ・ダ・ガンバ) カスティン・ローフ(クラヴサン) セバスティアン・ウォナー(Org)] 録音:2015年10月パリ *=ウプサラ大学所蔵手稿譜より |
|
||
| MIR-305(2CD) 限定盤 |
ラ・フォル・ジュルネ 「la nature ナチュール」ナント公式CD ■CD1 (1)ヴィヴァルディ:『四季』op.8 第4番「冬」~第1楽章 (2)ヴィヴァルディ:『四季』op.8 第4番「冬」~第2楽章 (3)ハイドン:弦楽四重奏作品64-5「ひばり」~第4楽章 (4)シューベルト:ピアノ五重奏曲「ます」~第4楽章 (5)ベートーヴェン:交響曲第6番「田園」~第2楽章 (6)サン=サーンス:「動物の謝肉祭」~「森の奥のカッコウ」 (7)サン=サーンス:「動物の謝肉祭」~「白鳥」 (8)シューベルト:ピアノ三重奏第2番Op.100~第2楽章 (9)ドヴォルザーク:弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」~第1楽章 (10)グリーグ:ピアノ協奏曲~第2楽章 (11)サン=サーンス:ピアノ協奏曲第5番「エジプト風」~第2楽章 (12)ボロディン:交響詩「中央アジアの草原にて」 ■CD2 (1)チャイコフスキー:四季‐~「舟歌」 (2)ショパン:前奏曲第15番変ニ長調Op.28 (3)リスト:巡礼の年第3年~「エステ荘の噴水」 (4)ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第17番「テンペスト」~第3楽章 (5)アリャビエフ(リスト編):夜鳴き鶯 (6)リムスキー=コルサコフ(ラフマニノフ編):熊蜂の飛行 (7)シューマン:森の情景~「予言鳥」 (8)シューベルト(リスト編):春の想い (9)リスト:超絶技巧練習曲~第11番「夕べの調べ」 (10)ドビュッシー:ベルガマスク組曲~「月の光」 (11)バルトーク:ミクロコスモス~「ハエの日記」 (12)グラナドス:ゴイェスカス~ 嘆き、またはマハとナイチンゲール (13)ドビュッシー:前奏曲集第1集~「雪の上の足跡」 |
■CD1 (1)(2)オリヴィエ・シャルリエ(Vn)、 オーヴェルニュO (3)エベーヌQ (4)トリオ・ショーソン、井上典子(Va)、 ペネロペ・ポアンシュヴァル(Cb) (5)シンフォニア・ヴァルソヴィア、 ユーディ・メニューイン(指) (6)アンリ・ドマルケット(Vc) 、 ボリス・ベレゾフスキー(P)、 ブリジット・エンゲラー(P)、パリ室内O (7)アンリ・ドマルケット(Vc)、 ブリジット・エンゲラー(P) (8)トリオ・ショーソン (9)モディリアーニSQ (10)シャニ・ディリュカ(P)、 エイヴィン・グルベルグ・イェンセン(指) フランス国立ボルドー・アキテーヌO (11)ブリジット・エンゲラー(P)、 アンドレア・クイン(指)パリ室内O (12)ドミトリー・リス(指)ウラルPO ■CD2 (1)ジョナス・ヴィトー(P) (2)フィリップ・ジュジアーノ(P) (3)ニコラ・アンゲリッシュ(P) (4)アブデル・ラーマン・エル=バシャ(P) (5)ブリジット・エンゲラー(P) (6)クレール・マリ=ル・ゲ(P) (7)ダヴィッド・カドゥシュ(P) (8)ブリジット・エンゲラー(P) (9)ボリス・ベレゾフスキー(P) (10)アンヌ・ケフェレック(P) (11)マタン・ポラト(P) (12)ルイス・フェルナンド・ペレス(P) (13)アンドレイ・コロベイニコフ(P) |
|
||
| MIR-308 |
チャイコフスキー:四季Op.37b グランド・ソナタ.ト長調Op.37 |
ジョナス・ヴィトー(P) 録音:2013年12月31日 |
|
||
| MIR-310 |
ブラームス:チェロ・ソナタ第1番 ホ短調 Op.38 フランク:チェロ・ソナタ.イ長調(原曲:ヴァイオリン・ソナタ) ドビュッシー:チェロ・ソナタ.ニ短調 |
ヴィクトル・ジュリアン=ラフェリエール(Vc) アダム・ラルーム(P) 録音:2015年12月21-23日/ボン・セクール寺院(パリ) |
|
||
| MIR-311 |
シューマン:ピアノ三重奏曲第1番、第2番 | トリオ・カレニーヌ |
|
||
| MIR-312 |
イレーヌ・ドゥヴァル~ポエム プーランク:ヴァイオリン・ソナタ シマノフスキ:「神話」Op.30~アレトゥーザの泉 ショーソン:詩曲Op.25 フォーレ:ヴァイオリン・ソナタ第1番イ長調Op.13 エルンスト:シューベルトの「魔王」による大奇想曲Op.26 |
イレーヌ・ドゥヴァル(Vn) ピ エ ー ル=イヴ・オ ディク(P) 録音:2015年11月10-12日/サル・ヴァンサン=メイエ(パリ) |
|
||
| MIR-313 |
第36回ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ・フェスティヴァル (1)バッハ:パルティータ第1番変ロ長調BWV.825よりPraeludium (2)バッハ:イギリス組曲第1番イ長調BWV.806よりAllemande (3)スカルラッティ:ソナタイ長調K.27 (4)モーツァルト:ピアノ・ソナタ第6番ニ長調K.284より第2楽章 (5)クープラン:小さな皮肉 (6)シューベルト:ワルツ第10番D.783 (7)シューベルト:創作主題による8つの変奏曲変イ長調D.813より第5変奏 (8)ショパン:夜想曲第5番嬰へ長調Op.15-2 (9)リスト:巡礼の年第1年「スイス」S.160よりパストラーレ (10)ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第28番イ長調Op.101より第1楽章 (11)ブラームス:インテルメッツォ変ロ長調Op.76-4 (12)チャイコフスキー:四季Op.37aより「6月舟歌」 (13)グリーグ:ノルウェー舞曲Op.35より第2番 (14)チャイコフスキー:無言歌Op.40-6 (15)フォーレ:舟歌第4番変イ長調Op.44 (16)デュカス:ハイドンの名による悲歌的前奏曲 (17)スクリャービン:前奏曲ホ長調Op.15-4 (18)デュポン:砂丘の家より「幸せの憂鬱」 (19)ファリャ:恋は魔術師より「魔法の輪」 (20)サティ:グノシエンヌ第2番 (21)ヤナーチェク:霧の中でよりAndantino (22)ラヴェル:高雅にして感傷的なワルツよりPresquelent (23)スクリャービン:練習曲ロ長調Op.8-4 (24)シェーンベルク:6つの小さなピアノ曲Op.19よりLangsam |
(1)シュ・シャオ=メイ(P) (2)レミ・ジュニエ(P) (3)アンヌ・ケフェレック(P) (4)ユリアンナ・アヴデーエワ(P) (5)イド・バル=シャイ(P) (6)シャニ・ディリュカ(P) (7)クレール・デセール&エマニュエル・シュトロッセ(P) (8)広瀬悦子(P) (9)ニコラ・アンゲリッシュ(P) (10)アブデル・ラーマン・エル=バシャ(P) (11)アダム・ラルーム(P) (12)ジョナス・ヴィトー(P) (13)デュオ・ヤーテーコク(P) (14)ボリス・ベレゾフスキー(P) (15)ジャン=クロード・ペネティエ(P) (16)エルヴェ・ビヨー(P) (17)クレール=マリ・ル・ゲ(P) (18)マリー=カトリーヌ・ジロー(P) (19)ルイス・フェルナンド・ペレス(P) (20)マタン・ポラト(P) (21)ダヴィッド・カドゥシュ(P) (22)ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) (23)アンドレイ・コロベイニコフ(P) (24)フローラン・ボッファール(P) |
|
||
| MIR-316 |
モーツァルト:ピアノ協奏曲集 ピアノ協奏曲第21番 ハ長調 K467 ピアノ協奏曲第24番 ハ短調 K491 |
ジャン=クロード・ペヌティエ(P) クリストフ・ポッペン(指) フランス放送PO 録音:2016 年 2 月 20日、オーディトリウム・ド・ラ・メゾン・ド・ラ・ラディオ(ライヴ) |
|
||
| MIR-318 |
オネゲル:「ダヴィデ王」 | ローザンヌ声楽アンサンブル スイス・ロマンドO ダニエル・ロイス(指) クリストフ・バリッサ(語り手) アテナ・ポウロス(巫女) リュシー・シャルタン(S) マリアンヌ・ベアート・キールランド(Ms) トーマス・ウォーカー(T) 録音:2016年9月、スイス、ジュネーヴ、OSRスタジオ |
|
||
 MIR-320 KKC-5705 日本語帯・解説付 税込定価 |
ダンスに加わって モンポウ:歌と踊り第4番 ラヴェル:なき王女のためのパヴァーヌ 優雅で感傷的なワルツ~第2曲 ドビュッシー:雪が踊っている~「子供の領分」 シャブリエ:アルバムの一葉 ロパルツ:ロンド~「山の日陰で」 アーン:愛と倦怠の踊り~「うぐいす狂乱」 フロラン・シュミット:石板に書かれた文字のロンド~「眠りの精の一週間」* プーランク:シャンパーニュのブランル~「フランス組曲」 マスネ:狂ったワルツ プーランク:パヴァーヌ~「フランス組曲」 ドビュッシー:バレエ~「小組曲」* ラヴェル:古風なメヌエット ドビュッシー:舞曲~「カンマ」 サン=サーンス:のんきなワルツOp.110 サティ:ゆがんだ舞曲~「逃げ出したくなる歌」 ピエルネ:即興的なワルツOp.27* 愛と悪の踊り~「うぐいす狂乱」 プーランク:幽霊の舞踏会~「夜想曲集」 フォーレ:スペインの踊り~「ドリー」* フランク:ゆるやかな舞曲 ドビュッシー:クロタルを持つ舞姫のための~「6つの古代の墓碑銘」 プーランク:シシリエンヌ~「フランス組曲」 ショーソン:パヴァーヌ~「いくつの舞曲」 |
アンヌ・ケフェレック(P) ガスパール・ドゥアンヌ(連弾)* 録音:2016年10月/アルセナル(メッツ) |
|
||
 MIR-321 |
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ集 ピアノ・ソナタ第2番イ長調Op.2-2 ピアノ・ソナタ第9番ホ長調Op.14-1 ピアノ・ソナタ第14番「月光」嬰ハ長調Op.27-2 ピアノ・ソナタ第31番変イ長調Op.110 |
レミ・ジュニ エ(P) 録音:2016年9月 |
|
||
| MIR-322 |
ブラームス:ピアノ三重奏曲第1番 ロ長調 op.8 ドヴォルザーク:ピアノ三重奏曲第4番 ホ短調 op.90「ドゥムキー」 |
トリオ・レ・ゼスプリ 【アダム・ラルーム(P) 梁美沙(ヤン・ミサ)(Vn) ヴィクトル・ジュリアン=ラフェリエール(Vc)】 録音:2016年4月11-13日、ボン=セクール寺院 |
|
||
| MIR-324 |
シューベルト:アルペジオーネ・ソナタ イ短調 D821 セレナーデ D957 水車職人と小川(歌曲集「美しき水車小屋の娘」 D795/ 第19曲) 連祷 D343/嘆きの歌 D23 君は憩い D776/涙の賛美 D711 朝の挨拶(歌曲集「美しき水車小屋の娘」 D795/ 第8曲) さすらい人の夜の歌 D224 さすらい人 D489/夜と夢 D827 エレンの歌 第3番 D839 |
フランソワ・サルク(Vc) クレール=マリ・ル・ゲ(P) 録音:2016年6月26-28日、TAP、ポワティエ(フランス) |
|
||
| MIR-326 |
ドメニコ・スカルラッティ:ソナタ集vol.5 変ロ長調K551、変ホ長調 K474、変ホ長調 K475、変ホ長調K252、変ホ長調 K253、ト長調 K547、変ロ短調 K87、ホ長調 K28、イ長調 K211、ニ長調 K401、ニ長調 K388、ニ長調 K277、ト長調 K124、ハ長調 K157、ヘ短調 K238、ヘ長調 K205 |
ピエール・アンタイ(Cmeb/2004年Jonte Knif製作の、18
世紀ドイツ・モデル・チェンバロ) 録音:2016年6月、ハーレム(オランダ) |
|
||
| MIR-327 |
鳥のシンフォニー ドヴォルザーク:ボヘミアの森より「森の静けさ」Op.68-5 シューマン:森の情景より「予言の鳥」Op.82-7 サン=サーンス:動物の謝肉祭より「白鳥」 グラナドス:ゴイェスカスより「嘆き、またはマハと夜鳴きうぐいす」 モーツァルト:魔笛より「私は鳥刺し」 セリン(カナリア属)の鳴き声 ヴォーン=ウィリアムズ:揚げひばり グリーグ:抒情小品集より「小鳥」Op.43-4 鶏小屋 ラモー:新クラヴサン組曲集より「めんどり」 ジョージ・パールマン:小鳥は歌う チャイコフスキー:白鳥の湖より「小さな白鳥たちのおどり」 ストラヴィンスキー:火の鳥より「子守歌」 リスト:伝説より「小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ」 カザルス:鳥の歌 クロウタドリの鳴き声 オリヴィエ・メシアンと「救世主の鳥」 |
シャニ・ディリュカ(P) ジュヌヴィエーヴ・ロランソー(Vn) ジョニー・ラス&ジャン・ブコー(鳥のさえずり) 録音:2016年10月、カルクフー、ナント、フランス |
|
||
 MIR-328 |
バッハ:イギリス組曲第2番 イ短調 BWV 807 トッカータ ニ長調 BWV 912 フランス風序曲 ロ短調 BWV 831 |
ユリアンナ・アヴデーエワ(P) 録音:2017年3月8-10日/ライツターデル(ノイマルクト/ドイツ) |
|
||
| MIR-332 |
J.S.バッハ:カンタータ集 カンタータ第75番「乏しき者は食らいて飽くことを得」BWV 75 カンタータ第22番「イエス十二弟子を召寄せて」BWV 22 カンタータ第127番「主イエス・キリスト、真の人にして神よ」 |
リチェルカール・コンソート フィリップ・ピエルロ(指) ハンナ・モリソン(S) カル ロ ス・メー ナ(A) ハンス=イェルク・マンメル(T) マティアス・ヴィーヴェク(Bs) 録音:2016年5月 |
|
||
| MIR-334 |
トーマス・アデス(b.1971):「テンペスト」よりコート・スタディーズ(2005) メシアン:世の終わりのための四重奏曲 |
ラヴァエル・セヴェール(Cl) トリオ・メシアン【ダヴィッド・ペトルリック(Vn)、ヴォロディア・ファン・クーレン(Vc)、テオ・フシュネレ(P)】 録音:2017年12月20-22日、ベルギー |
|
||
| MIR-336 |
ムッシュ・ド・サント=コロンブと息子たち ●ニ調作品 (1)サント=コロンブ:コンセール第41番「再会」 (2)同:コンセール第25番「カリジエ」 (3)ルイ・クープラン:3本のヴィオールのための組曲 (4)サント=コロンブ:コンセール第27番「気まぐれ」 ●ト調作品 (5)サント=コロンブ:コンセール第48番「親愛」 (6)シャンボニエール:パヴァーヌ「神々の話」 (7)サント=コロンブ:コンセール第44番「悲しみのトンボー」 (8)シャンボニエール:サラバンド「若きゼフィールたち」 ●ハ調作品 (9)サント=コロンブ:コンセール第66番「不貞」 (10)ロベール・ド・ヴィゼ:ヴィゼ嬢たちのトンボー (11)サント=コロンブ:コンセール第54番「デュボワ」 |
リチェルカール・コンソート 【フィリップ・ピエルロ(トレブル&バス・ヴィオール)、リュシル・ブーランジェ、ミリアム・リニョル(バス・ヴィオール)、ロルフ・リスレヴァン(テオルボ)】 録音:2016年12月7-10日/無原罪御宿り礼拝堂(ナント) |
|
||
 MIR-337(1LP+CD) |
CARNETS DE VOYAGE(旅へのチケット)~ボヤージュ
旅から生まれた音楽(ものがたり) [A面] (1)ファリャ:スペイン舞曲第1番(はかなき人生より) (2)フリアン・プラサ:ブエノスアイレス~東京 (3)タレガ:グラン・ホタ・アラゴネーサ (4)アラン・ウルマン/アマリア・ロドリゲス:Meu amor(私の愛) [B面] (1)ピアソラ(ビジェーナ&ロスフェルダー編):アヴェ・マリア (2)ルペルト・チャピ:セベデオの娘たちよりカルセレラス (3)ロドリーゴ:3つのスペイン民謡よりアデーラ (4)ペドロ・ピナル/ペロド・アシス・コインブラ:Se eu adivinhasse que sem ti |
全て、エマニュアル・ロスフェルダー(G) [A面] (1)モディリアーニSQ、ギュイ=ルー・ボワノー(カスタネット) (2)クトル・ウーゴ・ビジェーナ(バンドネオン) (4)ラケル・カマリーナ(S) [B面] (1)ビクトル・ウーゴ・ビジェーナ(バンドネオン) (2)ラケル・カマリーナ(S)、ヨアン・エロー(P) (3)ラケル・カマリーナ(S) (4)ペドロ・ピナル/ペロド・アシス・コインブラ:Se eu adivinhasse que sem ti ラケル・カマリーナ(S)、ヨアン・エロー(P) 録音:2018年9月 |
|
||
| MIR-340 |
ブラームス:ピアノ協奏曲第1番ニ短調Op.15 ストラヴィンスキー:ピアノと管楽オーケストラのための協奏曲 |
ボリス・ベレゾフスキー(P) スヴェトラーノフ記念ロシア国立SO 録音:2017年 4月8日/モスクワ音楽院大ホール(ライヴ) |
|
||
| MIR-344 |
イベリア~ルネッサンスから現代のスペインとポルトガルの多声音楽集 アルフォンソ10世:サンタ・マリアのカンティガ ウエルガス写本より女声のための作品 トマス・ルイス・デ・ヴィクトリア(1548-1611):Alma Redemptoris mater, Super Flumina Babylonis, O Magnum Mysterium イヴァン・ソラノ(b.1973):Cielo Arterial フランシスコ・ゲレーロ(1528-1599):Canciones y villanescas espirituales ドゥアルテ・ローボ(1563-1646):Audivi vocem de caelo アントニオ・カガス・ローサ(b.1960):Lumine Clarescet マヌエル・カルドーソ(1566-1650):Lamentatio |
レ・ゼレマン ジョエル・スユビエット(指) 録音:2017年6月27-30日、トゥールーズ |
|
||
| MIR-346 |
シューマン:弦楽四重奏曲集 第1番 イ短調 op.41-1 第2番 ヘ長調 op.41-2 第3番 イ長調 op.41-3 |
モディリアーニSQ アムリ・コエイトー(Vn/1733年製グァダニーニ) ロイック・リョー(Vn/1734年製アレッサンドロ・ガリアーノ) ローラン・マルフェング(Va/1660年製マリアーニ) フランソワ・キエフェル(Vc/1706年製マッテオ・ゴフリラー”ex=Warburg”) 録音:2017年4月、フランス |
|
||
| MIR-348 |
アラベスク~エル=バシャ作品集 3つの東洋的小品【祭礼舞曲/エジプトの歌による変奏曲/バッカス】 子供の世界【子守歌第2番/童謡/森の小兵隊の夢/クリスマス・ツリーの前で/子供らしさ/思春期】 前奏曲と歌【アンダルシア前奏曲/アンダルシアの歌/東洋前奏曲/レバノンの歌/葬送前奏曲/ マリー、または子供の死/ロマンス第2番】 10のロマンティックな小品【モデラート・カンタービレ/儚いワルツ/シューマンを讃えて/カンツォネッタ/蝶々/メストⅠ/メストⅡ/コラール/デュオ/間奏曲 若者の作品【子守歌第1番/悲しい歌/砂漠の騎士/愛の歌/前奏曲】 ショパン(エル=バシャ編):ワルツもしくはマズルカ(遺作) |
アブデル・ラーマン・エル = バシャ(P) 録音:2017年7月/フラジェ(ブリュッセル) |
|
||
| MIR-350 |
プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第4番ハ短調Op.29(1917) 10の小品Op.12(1906-13) トッカータOp.11(1916) ラヴェル:クープランの墓(全曲)(1914-7) |
ナターリヤ・ミルシテイン(P) 録音:2016 年9月1-3日/ベートーヴェン・ザール(ハノーファー) |
|
||
| MIR-352 |
第37回ラ・ロック・ダンテロン・ピアノフェスティバル公式CD (1)クープラン:恋のナイチンゲール (2)シューマン:ダヴィッド同盟舞曲集~第2曲 (3)シューベルト:ディヴェルティメントD.823~変奏1 (4)同:ハンガリーのメロディD.817 (5)チャイコフスキー:秋の歌 (6)ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第2番~ラルゴ・アパッショナート (7)メンデルスゾーン:5月のそよ風 (8)デュポン:墓碑銘 (9)ショパン:マズルカ第21番嬰ハ短調Op.30の4 (10)モンポウ:庭の乙女たち (11)グラナドス:嘆き、またはマハとナイチンゲール (12)ショパン:前奏曲嬰ヘ長調Op.28の13 (13)フォーレ:即興曲嬰ハ短調Op.84の5 (14)シャブリエ:アルバムの1ページ (15)ラヴェル:優雅で感傷的なワルツ~第2曲 (16)リスト:ペトラルカのソネット第47番 (17)スクリャービン:練習曲変ロ長調Op.8の8 (18)フランク:前奏曲,コラールとフーガ~前奏曲 (19)ショパン:前奏曲ロ短調Op.28の6 (20)チャイコフスキー:田舎でOp.40の7 (21)ラヴェル:クープランの墓~フォルラーヌ |
(1)イド・バル=シャイ(P) (2アダム・ラルーム(P) (3)クレール・デゼール&エマニュエル・シュトロッセ(P) (4)シャニ・ディルカ(P) (5)ジョナス・ヴィトー(P) (6)レミ・ジュニエ(P) (7)マタン・ポラト(P) (8)マリー=カトリーヌ・ジロー(P) (9)イド・バル=シャイ(P) (10)ルイス・フェルナンド・ペレス(P) (11)シャニ・ディルカ(P)と鳥笛 (12)フィリップ・ジュジアーノ(P) (13)フジャン=クロード・ペヌティエ(P) (14)アンヌ・ケフェレック(P) (15)ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) (16)ニコラ・アンゲリッシュ(P) (17)アンドレイ・コロベイニコフ(P) (18)マリー=アンジュ・グッチ(P) (19)ユリアンナ・アヴデーエワ(P) (20)ボリス・ベレゾフスキー(P) (21)ナターリヤ・ミルシテイン(P) |
|
||
 MIR-354 |
リスト:メフィスト・ワルツ第2番 S.515 死者の追憶(「詩的で宗教的な調べ」S.173より) 死の踊り(ピアノ独奏編曲版)S.525 葬送(「詩的で宗教的な調べ」S.173より) 死のチャールダーシュ S.224 グレートヒェンS.513(「ファウスト交響曲」から) |
ナタナエル・グーアン(P) 録音:2016年12月27-29日、ブリュッセル |
|
||
| MIR-356 |
フォーレ:ピアノ作品全集 vol.4 舟歌 第7番 ニ短調 op.90 即興曲 第4番 変ニ長調 op.91 舟歌 第8番 変ニ長調 op.96 ノクターン 第9番 ロ短調 op.97 即興曲 第5番 嬰ヘ短調 op.102 ノクターン 第11番 嬰ヘ短調 op.104-1 舟歌 第10番 イ短調 op.104-2 舟歌 第11番 ト短調 op.105 舟歌 第12番 変ホ長調 op.106bis ノクターン 第12番 ホ短調 op.107 舟歌 第13番 ハ長調 op.116 ノクターン 第13番 ロ短調 op.119 |
ジャン=クロード・ペヌティエ(P) 録音:2017年6月、ボン・セクール・ルター派教会(パリ) |
|
||
| MIR-358 |
F.クープラン:ルソン・ド・テネブル&モテット集 聖水曜日のためのルソン・ド・テネブル[1714,パリ] 詩篇「あなたの定めは驚くべきものです(Mirabilia testimonia tuoa)119.129」による、王の礼拝のために作曲され歌 われた4行[1703,パリ] アニュス・デイ~修道院のためのミサ[1690,パリ] 「主よ、われらを救いたまえ」~モテット(世界初録音)[1705,パリ] |
レ・ゾンブル シャンタル・サントン・ジェフリ(S)、 アンヌ・マグエ(S) ブノワ・アルノー(Br) 録音:2017年 3&12月 |
|
||
| MIR-360 |
ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ集 ソナタ第3番変ホ長調 op.12-3 (1798) ソナタ第7番 ハ短調 op.30-2 (1802) ソナタ第10番 ト長調op.96 (1812) |
バティスト・ロペス(Vn) モード・グラットン(フォルテピアノ) 録音:2014年5月、フランス |
|
||
 MIR-362 |
マリー=アンジュ・ヌグシ フランク:演奏曲,アリアとフィナーレ.ホ長調 FWV 23 ティエリー・エスケシュ:木陰の連祷 フランク:演奏曲,コラールとフーガFWV 21 バッハ(ブゾーニ編):シャコンヌ サン=サーンス:ピアノ協奏曲第5番のフィナーレによるトッカータ op.111-6 |
マリー=アンジュ・ヌグシ(P) 録音:2016年11月22-25、ヴァンサン=メイヤー・ホール(パリ国立高等音楽院) |
|
||
| MIR-364 |
モンポウ(1893-1987):ピアノ作品集 「歌と踊り」(1~12&14番) 「風景」/「子供の情景」 「ひそやかな音楽」第1巻より第3番 |
ルイス・フェルナンド・ペレス(P) 録音:2016年12月1-3日、スペイン |
|
||
| MIR-366 |
デュリュフレ:グレゴリオ聖歌の主題による4つのモテット ギョーム・ド・マショー:Le Lai de Nostre Dame プーランク:悔悟節のための4つのモテット メシアン:おお、聖なる饗宴よ |
ヴォックス・クラマンティス ヤーン= エイク・トゥルヴェ(指) 録音:2014年9月 |
|
||
| MIR-368 |
1700年頃のロンドン~パーセルとその周辺 Vol.1 パーセル:ソナタ第3番 ニ短調 Z792、ソナタ第6番ト短調 Z807 ダニエル・パーセル(1664-1717):ソナタ第3番 ニ短調(2本のリコーダーのための)、ソナタ第6番 ト短調(ヴァイオリンのための) ゴッドフリー・フィンガー(1655/56-1730):グラウンド ニ短調(リコーダーのための)、組曲 ニ短調(リコーダーのための)、 ヴィオラ・ダ・ガンバのためのソナタ第2番ニ調 ジョヴァンニ・バッティスタ・ドラーギ(1640-1708):トリオ・ソナタ ト短調 ジョン・ブロウ(1649-1708):2つのリコーダーのためのグラウンド ト短調 ウィリアム・クロフト(1678-1727):2本のリコーダーと2つのヴァイオリンのためのソナタ ヘ調 |
ラ・レヴーズ 録音:2017年10月、パリ |
|
||
| MIR-370 |
J.S.バッハ:フルート・ソナタ集 フルート・ソナタ ホ長調 BWV 1035 フルート・ソナタ ロ短調 BWV 1030 フルート・ソナタ ホ短調 BWV 1034 パルティータ(無伴奏)イ短調 BWV 1013 フルート・ソナタ イ長調 BWV 1032 |
マルク・アンタイ(Fl/ルドルフ・トゥッツ(2013年)、ロッテンブルク・モデル) ピ エ ー ル・アンタイ(Cemb) 録音:2016年9月19-23日、ハーレム(オランダ) |
|
||
| MIR-372 |
ウェーバー:クラリネット協奏曲 ヘ短調 op.73 クラリネットとピアノのための変奏曲(「シルヴァーナ変奏曲」) op.33 クラリネットとピアノのための協奏的第二重奏曲 op.48 |
ラファエル・セヴェール(Cl) ベルリン・ドイツSO アジス・ショハキモフ(指) ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P) 録音:[協奏曲]2016年2月15,16日ベルリン、フィルハーモニー(ライヴ) [協奏曲以外]2016年2月25-26日、ボン=セクール寺院、パリ |
|
||
| MIR-374(3CD) ★ |
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集 [CD1] ・ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 op.15 ・ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 op.19 [CD2] ・ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 op.37 ・ピアノ協奏曲第4番 ト長調 op.58 [CD3] ・ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調「皇帝」op.73 |
ジャン=フランソワ・エッセール(P&指) 新アキテーヌCO 録音:2014年11月&2015年3月 |
|
||
| MIR-376 |
フォーレ:ピアノ三重奏曲 ニ短調 op.120 ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調 タイユフェール:ピアノ三重奏曲 |
トリオ・カレニーヌ パロマ・クイデール(P) ファニー・ロビヤール(Vn) ルイ・ロッド(Vc) 録音:2017年 6月22-24日 |
|
||
| MIR-378 |
ロシアの祈り ラフマニノフ:晩祷Op.37~来たれ、我らが王、神に チャイコフスキー:聖金口イオアン聖体礼儀Op.41~クレド 我らが父 ラフマニノフ:聖金口イオアン聖体礼儀Op.31~我ら汝のために歌う グレチャニノフ:正教受難週の聖歌~花婿を見よ タネーエフ:セレナード グリンカ:ヴェネツィアの夜 ダルゴムイシスキー:嵐は霞で空を覆う ロシア民謡(スヴェシニコフ編)「果てもなき荒野原」「暗い森にて」「おお、広き野よ」「鐘」 (ルプツォフ編)「箒」 スヴィリドフ:プーシキンの花束~起床ラッパ 祖国への讃歌~広野の悲哀 アリャビエフ(ペトレンコ編):ナイチンゲール ガヴリーリン:鐘~夜の音楽 ティ・リ・リ |
アンドレイ・ペトレンコ(指) エカテリンブルグ・フィルハーモニーcho 録音:2017年4月28日-5月3日/スヴェルトロフスク国立フィル・コンサート大ホール |
|
||
| MIR-380(2CD) ★ |
ベートーヴェン:チェロとピアノのための作品全集 チェロ・ソナタ第1番 ヘ長調 op.5-1 チェロ・ソナタ第2番 ト短調 op.5-2 ヘンデルの『ユダ・マカベア』の「見よ勇者は帰る」の主題による12の変奏曲 ト長調WoO.45 チェロ・ソナタ第4番 ハ長調 op.102-1 チェロ・ソナタ第3番 イ長調 op.69 モーツァルトの『魔笛』の「娘か女か」の主題による12の変奏曲 ヘ長調 op.66 モーツァルトの『魔笛』の「恋を知る男たちは」の主題による7つの変奏曲 変ホ長調 WoO.46 チェロ・ソナタ第5番 ニ長調 op.102-2 |
ヴァレンティン・エルベン(Vc/1720年製マッテオ・ゴフリラー) シャニ・ディリュカ(P) 録音:2016年3月7-19日 |
|
||
| MIR-382(2CD) ★ |
リスト: ワーグナーのオペラ・楽劇からの全編曲作品集・トリスタンとイゾルデの前奏曲*(タンギ・ド・ヴィリアンクールによる編曲) イゾルデの愛の死~「トリスタンとイゾルデ」より ヴァルハラ~「ニーベルングの指環」より リエンツィの主題による変奏曲 つむぎ歌~「さまよえるオランダ人」より ゼンタのバラード~「さまよえるオランダ人」より 静かな炉辺で~「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より 聖杯への厳かな行進曲~「パルジファル」より リヒャルト・ワーグナーの墓に*(リスト作曲) タンホイザー序曲 エルザの夢~「ローエングリン」より エルザの結婚の行進~「ローエングリン」より 祝典と結婚式の歌~「ローエングリン」より ローエングリンの非難~「ローエングリン」より ヴァルトブルク城への客人の入場~「タンホイザー」より レチタティーヴォと夕星の歌~「タンホイザー」より 巡礼の合唱~「タンホイザー」より ・ワーグナー:エレジー トリスタンとイゾルデの前奏曲、およびリスト作の「リヒャルト・ワーグナーの墓に」、ワーグナー作の「エレジー」以外はすべてワーグナー原曲/フランツ・リスト編曲です。 |
タンギ・ド・ヴィリアンクール(P) 録音:2016年4月19-22日、2017年3月31日&4月2日/エスパス・モーリス・フルレ(パリ音楽院) |
|
||
| MIR-386 |
マラン・マレ:作品集~ヴィオール組曲より ・プレリュード-バドミントン遊び-小さな諧謔-ヴィルヌーヴのロンドー -トロワルール氏のロンドー ・プレリュード-風変りなガヴォット-ビジュー氏のロンドー -村祭り-ビスカイヤの女 ・いたずら ・パラザ ・ル・タクト ・猫なで声のロンドー ・プロヴァンスの女」 ・夢想家(La Reveuse) F.クープラン:「神秘的なバリケード」「子守歌、またはゆりかごの中のいとし子」(テオルボ編曲/バンジャマン・ペロー) |
ラ・レヴーズ〔フロランス・ボルトン(バス・ド・ヴィオール)、バンジャマン・ペロー(テオルボ、バロック・ギタ
ー )、カスルテン・ローフ(Cemb)、ロビン・ファロ(バス・ド・ヴィオール)〕 録音:2016年9月、2017年6月 |
|
||
| MIR-388 |
ハイドン:弦楽四重奏曲 ハ長調 op.20-2 Hob.III:32 モーツァルト:弦楽四重奏曲第14番ト短調 KV 387 シューベルト:弦楽四重奏曲 第12番「四重奏断章」ハ短調 D703 |
アキロン・クァルテット [エムリン・コンセ(Vn)、エリーズ・ドゥ= ベンドゥラック(Vn)、ルイーズ・デジャルダン(Va)、ルーシー・メァカット(Vc)] 録音:2017年10月30日-11月3日、パリ音楽院 |
|
||
| MIR-390 |
リャプノフ:12の超絶技巧練習曲Op.11 【子守歌/幽霊の踊り/鐘/テレク河/夏の夜/嵐/牧歌/ブィリーナ/エオリアン・ハープ/レズギンカ/妖精の踊り/リスト追悼のエレジー】 |
広瀬悦子(P) 録音:2017年10月29日-11月2日/聖マルセル福音教会(パリ) ※日本語解説付 |
|
||
| MIR-392(2CD) ★ |
ドビュッシー:若き日の作品集 ベルガマスク組曲/マズルカ 忘れられた映像 アラベスク第2番 ピアノとオーケストラのための幻想曲 小組曲(1台4手のための)* 忘れられたアリエッタ(T) ビリティスの3つの歌(Ms) 牧神の午後への前奏曲(ヴィトーによるピアノ独奏編曲版) |
ジョナ ス・ヴィトー(P) ルステム・サイトクロフ(P)* カリーヌ・デエ(Ms) セバスティアン・ドロワ(T) セセッション・オーケストラ クレマン・マオ=タカク((指)音楽監督) 録音:2017年9月(幻想曲のみ2017年12月) |
|
||
| MIR-394 |
ジャン=ルイ・デュポール(1749-1819):チェロ協奏曲集 チェロ協奏曲 第4番ホ短調 チェロ協奏曲 第1番イ長調 チェロ協奏曲 第5番ニ長調 |
ラファエル・ピドゥ(Vc) ストラディヴァリア ダニエル・キュイエ(ヴァイオリンと指揮) 録音:2017年10月 |
|
||
| MIR-400 |
「LUX」 グレゴリオ聖歌「Introitus Lux fulgebit」 シューマン:暁の歌op.133より第1曲’落ち着いたテンポで’ ドビュッシー:沈める寺(前奏曲集第1巻より) ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第21番ハ長調 op.53「ワルトシュタイン」より第3楽章 マティアス・ピンチャー:Whirling tissue of light (2013) ※世界初録音 スクリャービン:ピアノ・ソナタ第4番op.30 ドビュッシー(ポラト編):牧神の午後への前奏曲※世界初録音 リスト:夕べの調べ(超絶技巧練習曲より) トマス・アデス:Darknesse Visible バルトーク:夜の音楽(戸外にてより) グレゴリオ聖歌「Exortum est in tebebris」 ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第14番「月光ソナタ」より第1楽章 |
マタン・ポラト(P) 録音:2018 年1月 |
|
||
| MIR-408 |
シューマン:ピアノ作品集 幻想曲 op.17(1836-38) 3つのロマンスop.28(1839) 森の情景op.82(1848) |
クレール・デゼール(P) 録音:2018 年1月 |
|
||
| MIR-410 |
バルトーク~根 2つのルーマニア舞曲Op.8a ハンガリー農民の歌による即興曲Op.20(全8曲) 野外にて(全5曲) 14のバガテルOp.6 |
フロラン・ボファール(P) 録音:2018 年1月/グルノーブルMC2 |
|
||
| MIR-412 |
プロコフィエフ:ピアノ曲集 )ピアノ・ソナタ第2番ニ短調Op.14 ピアノ・ソナタ第5番ハ長調Op.135(改訂版) 10の小品Op.12 |
ルーカス・ゲニューシャス(P) |
|
||
| MIR-414 |
PORTRAITS- QUATUOR MODIGLIANI~ポートレイツ/モディリアーニSQ メンデルスゾーン:カプリッチョ(弦楽四重奏のための小品 op.81-3) ラフマニノフ:スケルツォ(弦楽四重奏曲第1番より) プッチーニ:菊 .コルンゴルト:間奏曲(弦楽四重奏第2番 変ホ長調 op.26より) クライスラー:スケルツォ(弦楽四重奏曲 イ短調より) バーバー:アダージョ(弦楽四重奏曲 ロ短調 op.111より) シューベルト:メヌエットとトリオ(弦楽四重奏曲 D.89-3より) ボロディン:スペイン風セレナータ(ベリャーエフの名前による四重奏曲) ショスタコーヴィチ:ポルカ(弦楽四重奏のための2つの小品より) ウェーベルン:弦楽四重奏のための緩楽章 ホフシュテッター:アンダンテ・カンタービレ(セレナーデ)(弦楽四重奏曲 ヘ長調より) モーツァルト:プレスト(ディヴェルティメント ヘ長調 K.138) ルロイ・アンダーソン:プリンク・プランク・プランク! |
アムリ・コエイトー(ヴァイオリン/グァダニーニ(1773)) ロイック・リョー(ヴァイオイン/グァダニーニ(1780)) ローラン・マルフェング(ヴィオラ/マリアーニ(1660)) フランソワ・キエフェル(チェロ/ゴフリラー“ex-Warburg”(1706)) 録音:2018年4月、フラゲイ、スタジオ1(ベルギー) |
|
||
| MIR-416 |
ラヴェル:作品集 ヴァイオリン・ソナタ(1897) 5つのギリシア民謡(マリヤ・ミルシテイン編) フォーレの名による子守歌 ヴァイオリン・ソナタ(1923-27) 「カディッシュ」(2 つのヘブライの歌より/ルシアン・ギャルバン編) ツィガーヌ ハバネラ形式の小品 |
マリヤ・ミルシテイン(Vn) ナターリヤ・ミルシテイン(P) 録音:2018年11月24-28日 |
|
||
| MIR-418 |
ガブリエル・デュポン:砂丘の家 サマズイユ:海の歌 |
マリー=カトリーヌ・ジロー(P) 録音:1997年 1月/サン・ピエール教会(パリ) |
|
||
| MIR-420 |
モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ集 ヴァイオリン・ソナタ ト長調K.379 ヴァイオリン・ソナタ 変ホ長調K.380 ヴァイオリン・ソナタ ホ短調K.304 ヴァイオリン・ソナタ ニ長調K.306 |
梁美沙(Vn)、 ジョナス・ヴィトー(P) 録音:2018年6月27-29日/ラベイ・エコール・ドゥ・ソレーズ |
|
||
| MIR-422 |
D.スカルラッティ:ソナタ集 VOL.6 ニ長調 K.119、ト短調 K.179、ト短調 K.234、ハ長調 K.501、ハ長調 K.502、ヘ短調 K.69、ト短調 K.43、ハ長調 K.384、ハ長調 K.487、ハ長調 K.170、ヘ長調 K.6、変ロ長調 K.550、ニ短調 K.18、変ロ長調 K.544、変ロ長調 K.273、ニ長調 K.161、ト長調 K.477 |
ピエール・アンタイ(Cemb) 録音:2018年6月、オランダ |
|
||
 MIR-426 |
モーツァルト:ピアノ・ソナタ集 ソナタ第13番変ロ長調 KV 333 ソナタ第12番ヘ長調 KV 332 ソナタ第11番イ長調 KV 331「トルコ行進曲つき」 |
アンヌ・ケフェレック(P) |
|
||
| MIR-428 |
REVOLUTION デュシーク(デュセック)(1760-1812):フランス王妃の受難 ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第26番「告別」 ショパン:練習曲 ハ短調 op.10-12「革命」 スケルツォ第1番 op.20 リスト:「葬送」(『詩的で宗教的な調べ』より) ヤナーチェク:ピアノ・ソナタ「1905年10月1日の街角で」 ドビュッシー:燃える炭火に照らされた夕べ、「花火」(前奏曲第2集より) ジェフスキ(b.1938):ウィンスボロ綿工場のブルース(ノース・アメリカン・バラード第4曲) |
ダヴィッド・カドゥシュ(P) 録音:2018年12月、ベルギー |
|
||
| MIR-430 |
第38回ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ・フェスティヴァル公式CD 1. バッハ:イタリア協奏曲 BWV 971よりアンダンテ 2. F.クープラン:子供の時代~幼年期(クラヴサン曲集第2巻第7組曲 3. バッハ:イギリス組曲第2番イ短調よりアルマンド 4. ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第14番op.27-2「月光」より第1楽章 5. シューベルト:フランスのモティーフによるディヴェルティメント D823 ホ短調より変奏4 6. シューベルト:16の舞曲と2つのエコセーズ D783より第5番 7. アブデル・ラーマン・エル=バシャ:思春期 8. シューベルト:ワルツ第2番op.18 D145 9. シューマン:森の情景op.82より寂しい花 10. シューマン:ダヴィッド同盟舞曲より第14曲やさしく歌いなが 11. フランク:プレリュード、コラールとフーガ FWV21よりプレリュード 12. フォーレ:舟歌 第13番ハ長調 op.116 13. フランク:ゆるやかな舞曲 14. モンポウ:歌と踊り第1曲 15. リャプノフ:超絶技巧練習曲 op.11より子守歌 16. ワーグナー(リスト編):ローエングリンよりエルザの夢 17. チャイコフスキー:四季より3月ひばりの歌 18. ラフマニノフ:前奏曲op.23-10 変ト長調 19. スクリャービン:練習曲 op.42-4 20. ヤナーチェク:霧の中でよりアンダンテ 21. スクリャービン:ソナタ第4番op.30よりアンダンテ 22. デュポン:砂丘の家より星の光 |
1. クレール・マリ=ル・ゲ 2. Fイド・バル=シャイ 3. ユリアンナ・アヴデーエワ 4. レミ・ジュニエ 5. クレール・デゼール&エマニュエル・シュトロッセ 6. シャニ・ディリュカ 7. エル=バシャ 8. シャニ・ディリュカ 9. クレール・デゼール 10. アダム・ラルーム 11. マリー=アンジュ・グッチ 12. ジャン=クロード・ペヌティエ 13. アンヌ・ケフェレック 14. モルイス・フェルナンド・ペレス 15. 広瀬悦子 16. タンギ・ド・ヴィリアンクール 17. チジョナス・ヴィトー 18. ボリス・ベレゾフスキー 19. アンドレイ・コロベイニコフ 20. ヤダヴィッド・カドゥシュ 21. マタン・ポラト 22. デマリー=カトリーヌ・ジロー |
|
||
| MIR-434 |
TEMPERAMENTS~C.P.E.バッハとモーツァルト作品集 C.P.E.バッハ:アンダンテ・コン・テネレッツァ(Andante con tenerezza) Wq.65/32 (H.135) ソルフェッジオSolfeggio ハ短調 H.220 スペインのラ・フォリアにもとづく12の変奏曲 H.263 ピアノ協奏曲 ニ短調 Wq.23 わがジルバーマン・ピアノへの別れ Wq.66(H.272) モーツァルト:ピアノ・ソナタ第8番イ短調 KV310/300d 幻想曲 ニ短調 K.397/385g * C.P.E.バッハ:アンダンテ・コン・テネレッツァ Wq.65/32 (H.135)* |
シャニ・ディリュカ(P/*は1790年アントン・ヴァルターのピアノフォルテ(コピー)を使用) パリ室内O ベン・グラスバーグ(指) 録音:2018年7月、8月 |
|
||
| MIR-436 |
フランス風アコーディオン (1)ティボー・ペリーヌ:ミュゼット組曲(全5曲) (2)プロコフィエフ(ティボー・ペリーヌ編):ユダヤ主題による序曲 (3)ガーシュウィン(ティボー・ペリーヌ編):パリのアメリカ人 (4)ピアソラ(ティボー・ペリーヌ編):天使のミロンガ (5)リシャール・ガリアーノ:小フランス組曲(全5曲) (6)ギュス・ヴィズール(ティボー・ペリーヌ編):モントーバンの火 |
ル・パリ・デ・ブルッテル【フェリシアン・ブリュ(アコーディオン)、エルメスSQ、エドゥアール・マカレ(Cb)】 録音:2018年9月/四季劇場(グラディニャン) |
|
||
| MIR-438 |
シューベルト:八重奏曲ヘ長調 D.803 | モディリアーニSQ【アムリ・コエイトー(ヴァイオリン/グァダニーニ(1773))、ロイック・リョー(ヴァイオイン/グァダニーニ(1780))、ローラン・マルフェング(ヴィオラ/マリアーニ(1660))、フランソワ・キエフェル(チェロ/ゴフリラー"ex-Warburg"(1706))】 ザビーネ・マイヤー(Cl) ブルーノ・シュナイダー(Hrn) ダグ・イェンセン(Fg) クヌート・エリック・サンドクイスト(Cb) 録音:2018年9月 |
|
||
| MIR-440 |
民謡から生まれたピアノ曲 デシャトニコフ:ブコヴィナの歌(24の前奏曲) バルトーク:15のハンガリー農民歌Sz.71 チャイコフスキー:ドゥムカOp.59 |
ルーカス・ゲニューシャス(P) |
|
||
| MIR-442 |
ブクステフーデ:独唱のためのカンタータ集(および同時代人たちの作品集) フランツ・トゥンダー(1614-1667):Ach Herr, lass deine lieben Engelein ブクステフーデ:主は言われた BuxWV 17、ソナタ第6番ニ短調 op.1- BuxWV 257、Sicut Moses、 Herr, wenn ich nur dich hab - BuxWV 38 作曲者不詳:3つのヴィオラ・ダ・ガンバのためのソナタ ヨハン・フィリップ・フェルチュ(1652-1732):深き淵より われ汝に呼ばわる 主よ ガブリエル・シュッツ(1633-1710/11):2つのヴィオラ・ダ・ガンバのためのソナタ クリスティアン・ガイスト(ca.1650-1711):Resurrexi adhuc tecum sum |
ラ・レヴーズ マイイ・ド・ヴィルトレイ(S) 録音:2018年10月、パリ |
|
||
| MIR-444 |
ブクステフーデ(1637頃-1707):われらがイエスの御体(四肢)
BuxWV 75 神よ、われを助けたまえ! BuxWV 34 |
フィリップ・ピエルロ(指) リチェルカール・コンソート マリア・ケオハネ、ハンナ・バトディ=ヒルト(S) カルロス・メーナ(C.T) ジェフリー・トンプソン(T) マティアス・フィーヴェグ(Bs) 録音:2018年9月 |
|
||
| MIR-446 |
ロワール川に沿って~流域の音楽的描写 序唱~“Exultantes in partu virgins 処女の誕生を喜ぶ”より(12-16世紀の山間部の手稿譜に基づく) オケゲム:キリエ(ミサ「 Fors seulement 」より)/Intemerata Dei Mater ジャン・ムトン(1459-1522):グローリア(ミサ「 Quem dicunt homines 」より)/Nesciens mater virgo virum/Quis dabit oculis nostris クレマン・ジャヌカン:Quand contremont verras/Herbes et fleurs/Bel aubepin verdissant/Le rossignol/ Etans assis aux rives aquatiques/サンクトゥス(ミサ「 La bataille 」より) ファブリス・カイエタン(1540-1578):La terre va les eaux boivant ピエール・セルトン(1515-1572):Vignon, vignette アントワーヌ・ド・フェヴァン(1470-1512):序唱~ミサ「 Pro fidelibus defunctis 」より ギョーム・ファギュ(1442-1475):アニュス・デイ~ミサ「 Je suis en la mer 」より 作曲者不詳:Dedans la mer |
アンサンブル・ジャック・モデルヌ ジョエル・シュビエット(指) 録音:2018年10月 |
|
||
| MIR-448 |
ショパン:19の歌曲(ポーランド語歌唱) シューベルト(ゲーテ詩):あこがれD.359/ミニヨンの歌ⅠD.726/ミニヨンの歌ⅡD.727/ 「ヴィルヘルム・マイスター」からの歌D.877(全4曲)(ドイツ語歌唱) |
ラケル・カマリーナ(S)、 ヨアン・エロー(P) 録音:2019年1月14-20日/モンス、アルソニク大劇場(ベルギー) |
|
||
| MIR-450 豪華仕様 |
シューベルト:冬の旅 | エドウィン・クロスリー=メルセル(Br) ヨアン・エロー(P) 録音:2019年1月14-20日、ベルギー 美麗ブックCD(縦216ミリ、横157ミリ、厚さ12ミリ) |
|
||
| MIR-452 |
ビゼー:ピアノ作品集~無言歌 ラインの歌(6っつの無言歌)〔1.夜明け 2.出発 3.夢 4.ジプシー女 5.打ち明け話 6.帰還〕 『真珠とり』よりナディールのロマンス”耳に残るは君の歌声”(グーアン編) 半音階的変奏曲 メヌエット(「アルルの女」第1組曲より)(ラフマニノフ編) サン=サーンス(ビゼー編):ピアノ協奏曲第2番(ビゼー編曲によるピアノ独奏版) |
ナタナエル・グーアン(P) 録音:2019年7月3-5日 |
|
||
| MIR-454 |
ベートーヴェン&コルンゴルト:初期ピアノ三重奏曲集 ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲第1番変ホ長調 op.1-1 コルンゴルト:ピアノ三重奏曲 op.1 ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲第3番ハ短調 op.1-3 |
ナタナエル・グーアン(P) ギョーム・シルム(Vn) ヤン・ル ヴィノワ(Vc) 録音:2019年2月22-24日 |
|
||
| MIR-456 |
モーツァルト&ハイドン:ピアノ・ソナタ集 モーツァルト:ピアノ・ソナタ 第12番ヘ長調 K332 ハイドン:ピアノ・ソナタ ハ長調 第36番Hob.XVI:21(1773) モーツァルト:ピアノ・ソナタ 第4番変ホ長調 K282(1774) ハイドン:ピアノ・ソナタ 第44番ヘ長調 Hob.XVI:29(1776) ハイドン:ピアノ・ソナタ 変ホ長調 第51番 Hob.XVI:38(1780) |
ジェローム・アンタイ(フォルテピアノ/18世紀後半、ドイツ製) 録音:2017年7月 |
|
||
| ”FUTUR”シリーズ MIR-464 |
シューマン:ヴァイオリン・ソナタ第1番イ短調 op.105 間奏曲(動きをもって、しかし速すぎずに)~F.A.E.ソナタ第2楽章 ブラームス:スケルツォ(アレグロ)~F.A.E.ソナタ第3楽章 クララ・シューマン:ヴァイオリンとピアノのための3つのロマンス op.22 ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第1番ト長調 op.78 |
岡田修一(Vn) クレマン・ルフヴュル(P) 録音:2017年12月 |
|
||
| MIR-472 |
(1)ショスタコーヴィチ:ピアノ三重奏曲第1番ハ短調Op.8 (2)ドヴォルザーク:ピアノ三重奏曲第4番ホ短調Op.90「ドゥムキー」 (3)ヴァインベルク:ピアノ三重奏曲Op.24 |
トリオ・カレニーヌ【パロマ・クイデール(P)、ファニー・ロビヤール(Vn)、ルイ・ロッド(Vc)】 録音:2019年5月24-17日/サン=ラザール・サナトリウム(ボーヴェ) |
|
||
| MIR-474 |
ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ集 ソナタ 第5番ヘ長調 op.24「春」 ソナタ第6番イ長調 op.30 ソナタ第10番ト長調 op.96 |
オリヴィエ・シャルリエ(Vn) エマニュエル・シュトロッセ(P) 録音:2019年8月28-30日、音楽院オーディトリウム(パリ17区) |
|
||
| MIR-476 |
ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ペトリス・ヴァスクス(b.1946):「遠き光」ヴァイオリンと弦楽のための協奏曲 |
ファニー・クラマジラン(Vn/マッテオ・ゴフリラー(1700年) ケン=デイヴィッド・マズア(指) イギリス室内O 録音:2016年3月9-11日 |
|
||
| MIR-478 |
「FOLK」 クライスラー:ラ・ヒターナ、序奏とアレグロ、中国の太鼓 ファリャ:はかなき人生 バルトーク:ルーマニア民俗舞曲 Sz.56 ファリャ:7つのスペイン民謡より‘ポーロ’‘アストゥーリアス地方の歌’‘ホタ’ サラサーテ:ボヘミアの歌 マスネ:タイスの瞑想曲 スコット・ジョプリン:エリート・シンコペーションズ(プレヴィン&パールマン編) ドヴォルザーク(クライスラー編):スラヴ幻想曲 ブロッホ:ニーグン サン=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ ラヴェル:ツィガーヌ |
トマ・ルフォー(Vn) ピエール=イヴ・オディク(P) 録音:2018年10月1-5日 |
|
||
| MIR-480 |
ヘンデル:クラヴサン組曲第1巻より第1~4番 (1)クラヴサン組曲第1番イ長調 HWV426 (2)クラヴサン組曲第2番ヘ長調 HWV427 (3)クラヴサン組曲第3番ニ短調 HWV428 (4)6つのフーガより第6番ハ短調 HWV610 (5)クラヴサン組曲第4番ホ短調 HWV429 |
ピエール・アンタイ(Cemb) 録音:2020年1月/ハールレム(オランダ) |
|
||
| MIR-486 |
「SON」~夢 ムソルグスキー:歌曲集「子供部屋」(全曲) リスト:‘愛って何’、‘若き日の幸せ’、‘漁師の少年’、‘ローレライ’、 ‘「どうやって」彼らは尋ねた’、‘すべての山の頂きに安らぎが’ ラフマニノフ:6つの歌曲op.38(全曲) |
イリーナ・キシリャルク(S) チェン・ユン=ホ(P) 録音:2018年9月 |
|
||
| MIR-488 |
ベートーヴェン:変奏曲集 創作主題による32の変奏曲 ハ短調 WoO 80 「森のおとめ」のロシア舞曲の主題による12の変奏曲 WoO 71 創作主題による15の変奏曲とフーガ 変ホ長調(エロイカ変奏曲) op.35 創作主題による6つの変奏曲 ヘ長調 op.34 |
セリム・マザリ(P) 録音:2019年6月6-7日、サル・モリエール(リヨン) |
|
||
| MIR-490 |
バッハ~ただ神の栄光のために カンタータ第21番「われは 憂いに沈みぬ」BWV 21 カンタータ 第76番「もろもろの天は神の栄光を語り」 BWV76 「主イエス・キリストよ、われ汝に呼ばわる」BWV639 「いと高きところには神にのみ栄光あれ」BWV663 「主なる神よ、いざ天の扉を開きたまえ」BWV617 「いと高きところにいます神にのみ栄光あれ」 BWV 715 |
コレギウム・ヴォカーレ・ゲント、 リチェルカール・コンソート、 フィリップ・ピエルロ(指) マリア・コヘイン(S) カルロス・メーナ(A) ユリアン・プレガルディエン(T) マティアス・フィーヴェク(Bs) ベルナール・フォクルール(Org) |
|
||
| MIR-492 |
ベートーヴェン:バガテル全曲集 7つのバガテル op.33 アレグレット WoO.53 バガテル「楽しい―悲しい」WoO.54 バガテル WoO.52 バガテル WoO.56 11のバガテル op.119 バガテル WoO.59(エリーゼのために) やや生き生きと WoO.60 アレグレット WoO.61 バガテル WoO.61a 6つのバガテル op.126 |
タンギ・ド・ヴィリアンクー ル(P) 録音:2019年10月24-26日、グスタフ・マーラー・コンサートーホール(イタリア) |
|
||
| MIR-496 |
ルイ13世の宮廷のスペイン歌曲 ・Gaspar Sanz (1640/1710) : Clarin de los Mosqueteros del Rey de Francia、Zarabanda Francesca ・Etienne Moulinie (1599/1676) : Repicavan las campanillas、Ojos si quiereis vivir、Si matais quando mirais、Si me nacen colores morena、Si negra tengo la mano ・Gabriel Bataille (1575/1630) : Quien quiere entrar conmigo、Pues que me das a escoger、Passava amor、Si suffro por ti morena、Claros ojos bellos、De mi mal nace mi bien、Dezid como puede ser、Vuestros ojos tienen d’Amor ・Santiago de Murcia (1673/1739) : Las Bacas、Las Penas、Tarentelas、Jacaras Francesca ・Gabriel Bataille : Rio de Sevilla、En el valle, Ynes la tope riendo、El baxel esta en la playa、Aver mil damas ・Henri de Bailly (158?/1637) : Yo soy la Locura |
アンサンブル・エル・ソル クロエ・セヴェール(Cemb、指) 録音:2019年4月 |
|
||
| MIR-498 |
ツアー中 ルトスワフスキ:舞踏前奏曲 プーランク:クラリネット・ソナタ ヴェイネル:ペレグの踊り/2つの楽章 バルトーク:ルーマニア民俗舞曲 バーンスタイン:クラリネット・ソナタ ラファエル・セヴェール:絆の始まり |
ラファエル・セヴェール(Cl)、 ポール・モンタグ(P) 録音:2019年10月1-4日/ボン・セクール教会(パリ) |
|
||
| MIR-500 |
ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲集 第5番ニ長調 op.70-1 「幽霊」 第7番変ロ長調 op.97「大公」 |
トリオ・ショーソン〔マテュー・ハントシェヴェルケル(Vn/ジャック・フスティエ、2001年製)、 アントワーヌ・ラントフスキ(Vc/ギュスターヴ・ベルナルデル、1848年製)、ボリス・ド・ラロシュランベール(P)〕 録音:2019年9月19-22日 |
|
||
| MIR-502 |
シューマンの謝肉祭をメインとしたリサイタル 1. Carnaval:1. 前口上 2. ラロ先生(Master Raro):前口上 3. Carnaval:2. ピエロ 4. ヴィラ=ロボス:ピエレットの気まぐれ(「ブラジルの子供の謝肉祭」より) 5. Carnaval:3. アルルカン 6. ラッヘンマン:Akiko (「子供の遊び」より第3曲) 7. F.クープラン:道化(L'Arlequine) 8. ストラヴィンスキー:ワルツ 9. Carnaval:4. 高貴なワルツ 10. スクリャービン:アルバムの綴りop. 45より第1曲 11. Carnaval:5. オイゼビウス Eusebius 12. シューマン:Frisch (ダヴィッド同盟舞曲 op.6より第15曲) 13. Carnaval:6. フロレスタン Florestan 14. Carnaval:7. コケット Coquette 15. ヴィトマン:間奏曲(妖精のユモレスクより) 16. Carnaval:8. 返事 Replique 17. シューマン:蝶々 op.2より第2曲 18. プーランク:少女の舞踏会(8つのノクターンより第2曲) 19. Carnaval:9. 蝶々 20. ブラームス:間奏曲(ピアノ小品集 op.76より) 21. シューマン:間奏曲(ウィーンの謝肉祭の道化 op.26より) 22. ラロ先生(Master Raro):A.S.C.H-S.C.H.A 23. Carnaval:10. 踊る文字~A.S.C.H-S.C.H.A 24. グリーグ:シルフィード(叙情小曲集 op.62より) 25. Carnaval:11. キアリーナ 26. クララ・シューマン:マズルカ(音楽の夜会 op.6より) 27. Carnaval:12. ショパン 28. ショパン:練習曲第2番変イ長調 遺作 29. Carnaval:13. エストレラ 30. クルターク:頑固 変イ長調(ヤーテーコクより) 31. Carnaval:14. 再会 32. バッハ:前奏曲 ハ短調(平均律第1巻より) 33. Carnaval:15. パンタロンとコロンビーヌ 34. ヴェーベルン:変奏曲 op.27より第2番 35. Carnaval:16. ワルツ・アルマンド(ドイツ風ワルツ) 36. シューマン:パガニーニの奇想曲による6つの演奏会用練習曲 Op.10 より第1番 37. Carnaval:17. パガニーニ 38. シュトックハウゼン:ピアノ小品第3番 39. Carnaval:18. 告白 40. チャイコフスキー:少しシューマン風に(18の小品 op.72より) 41. Carnaval:19. プロムナード 42. Carnaval:20. 休憩 43. マスター・ラロ(Master Raro):休憩Pause 44. Carnaval:21. フェリシテ人と闘う「ダヴィッド同盟」の行進 |
マタン・ポラト(P) 録音:2019年12月9-11日、ノイマルクト、ドイツ |
|
||
| MIR-504 |
ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ 第7番ハ短調 op.30-2、 ソナタ第8番ト長調 op.30-3 ブリテン:組曲 op.6 バーバー:ヴァイオリン・ソナタ ヘ短調「Lost movement」 |
リヤ・ペトロワ(Vn) ボリス・クズ ネツォフ(P) 録音:2019年9月19-22日 |
|
||
| MIR-506 |
モディリアーニQ~ハイドン、バルトーク、モーツァルト ハイドン:弦楽四重奏曲第76番ニ短調 op.76-2(Hob.III-76)『五度』 バルトーク:弦楽四重奏曲第3番ハ短調Sz. 85 モーツァルト:弦楽四重奏曲第19番ハ長調K.465『不協和音』 |
モディリアーニSQ〔アムリ・コエイトー(Vn)、ロイック・リョー(ヴァイオイン)、ローラン・マルフェング(Va)、フランソワ・キエフェル(Vc)〕 録音:2019年12月14-17日、スイス、ラ・ショー=ド=フォン、市民劇場 |
|
||
| MIR-508 |
ショパン:マズルカ&ソナタ (1)マズルカ第3番ホ長調Op.6の3 (2)マズルカ第7番ヘ短調Op.7の3 (3)マズルカ第10番変ロ長調Op.17の1 (4)マズルカ第21番嬰ハ短調Op.30の4 (5)マズルカ第22番嬰ト短調Op.33の1 (6)マズルカ第23番ニ長調Op.33の2 (7)マズルカ第24番ハ長調Op.33の3 (8)マズルカ第39番ロ長調Op.63の1 (9)マズルカ第40番ヘ短調Op.63の2 (10)マズルカ第41番嬰ハ短調Op.63の3 (11)マズルカ第47番イ短調Op.68の2 (12)ピアノ・ソナタ第3番ロ短調Op.58 |
ルーカス・ゲニューシャス(P) 録音:2019年9月20-23日/グスタフ・マーラー・ザール(ドッビャーコ、イタリア) |
|
||
| MIR-510 |
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ベルク:ピアノ・ソナタ Op.1 ロ短調 ブーレーズ:ピアノ・ソナタ 第3番 |
フローラン・ボファール (P) 録音:2020年8月、ベルギー |
|
||
| MIR-512 |
リスト:ピアノ曲集 (1)メフィスト・ワルツ第1番 (2)愛の夢 (3)イゾルデの愛の死(ワーグナー原曲) (4)詩的で宗教的な調べ~愛の賛歌 (5)詩的で宗教的な調べ~葬送1849年10月 (6)巡礼の年第1年「スイス」~泉のほとりで (7)コンソレーション(全3曲) 魂の喜び~リスト作品集 |
クレール=マリ・ル・ゲ(P) ※ベーゼンドルファー使用 |
|
||
| MIR-514 |
ショパンの「バラード&スケルツォ」 スケルツォ第1番ロ短調Op.20 バラード第1番ト短調Op.23 スケルツォ第2番変ロ短調Op.31 バラード第2番ヘ長調Op.38 スケルツォ第3番嬰ハ短調Op.39 バラード第3番変イ長調Op.47 スケルツォ第4番ホ長調Op.54 バラード第4番ヘ短調Op.52 |
アブデル=ラーマン・エル=バシャ(P) |
|
||
| MIR-518 |
シュトックハウゼン:マントラ | ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ&ジャン=フランソワ・エッセール(2台ピアノ) セルジュ・ルムトン(エレクトロニクス) |
|
||
| MIR-520 |
シューマン:ピアノ曲集 交響的練習曲Op.13(1837年版) 交響的練習曲~遺作の5つの変奏 ベートーヴェンの主題による自由な変奏形式の練習曲 天使の主題による変奏曲 |
クレール・デゼール(P) 録音:2020年8月17-19日/フラジェ・スタジオ4(ブリュッセル) |
|
||
| MIR-522 |
ピアノ・トリオNo.1 ショスタコーヴィチ:ピアノ三重奏曲第1番ハ短調Op.8 ニ短調Op.32 メンデルスゾーン:ピアノ三重奏曲第1番ニ短調Op.49 |
トリオ・ゼリハ【ホルヘ・ゴンザレス=ブアハサン(P)、マノン・ガリ(Vn)、マクシム・クネルソン(Vc)】 録音::2019年9月9-13日/パリ音楽院 |
|
||
| MIR-524 |
マドリードの一夜 ボッケリーニ:フルート五重奏曲ト短調(G426) ギター五重奏曲第7番ホ短調(G451) フルート五重奏曲変ロ長調(G429) フルート五重奏曲ニ長調(G428) ギター五重奏曲第4番ニ長調「ファンダンゴ」(G448) |
レ・ゾンブル【シルヴァン・サルトル(トラヴェルソ)、ロマリック・マルタン(G)、 テオティム・ラングロワ・ドゥ・スワルト、ソフィ・ド・バルドネシュ(Vn)、マルタ・パラーモ(Va)、 ハンナ・ザルツェンシュタイン(Vc)、マリ=アンジュ・プティ(打楽器)】 録音:2020年1月/サン=ピエール教会(パリ)、6月/レザール・フロリサン集会所(ティレ) |
|
||
| MIR-526 |
エル=バシャ・プレイズ・ショパン (1)24の前奏曲Op.28 (2)幻想曲ヘ短調Op.49 (3)子守歌Op.57 (4)舟歌Op.60 |
アブデル・ラーマン・エル=バシャ(P、ベヒシュタイン282) 録音:2020年1月8-12日/ヴィルファヴァール農場 |
|
||
| MIR-532 |
ボヴァリー夫人の音楽 ファニー・メンデルスゾーン:1年~5月「春の歌」 ポリーヌ・ヴィアルド:セレナード ショパン:3つのノクターンOp.9 ファニー・メンデルスゾーン:1年~9月「川辺で」 ドリーブ(ドホナーニ編):コッペリアのワルツ ルイーズ・ファランク:ロシアの歌変奏曲 ファニー・メンデルスゾーン:1年~6月「セレナード」 リスト:「ルチア」の回想 クララ・シューマン:ローベルト・シューマンの主題による変奏曲 ファニー・メンデルスゾーン:1年~3月「アジタート」 夜曲ト短調/メロディ |
ダヴィッド・カドゥシュ(P) 録音:2021年7月12-16日/ポワチエ公会堂) |
|
||
| MIR-534 |
ベートーヴェン(カルクブレンナー編):交響曲第9番「合唱」 (フランス語歌唱) |
広瀬悦子(P) セシール・アシーユ(S)、コルネリア・オンキオイウ(Ms)、サミー・カンプス(T)、ティモテ・ヴァロン(Bs) エカテリンブルグ・フィルハーモニーcho アンドレイ・ペトレンコ(終楽章の指揮) 録音:2020年1月29日-2月1日/ナント市イヴェント・センター 日本語帯・解説・歌詞対訳付 |
|
||
| MIR-540 |
ベートーヴェン:アイルランドの歌 1. アイルランド男の胸は高鳴る WoO 154-4 2. リラよ、私をなぐさめて WoO 153-7 3. 朝の空気が私の顔にたわむれ WoO.152-4 4. My bonny laddie has my heart(わたしのボニーが心をうばった) 5. En midsommarafton(真夏の夜に) 6. カールちゃん WoO 158-17 7. 古老が教えてくれてから WoO.153-4 8. あなたの船は出て行く WoO 153-20 9. Open the door softly(ドアをやさしく開けて) 10. シャノン川のほとりで WoO 157-8 11. The Miller o' drone; St. Kilda wedding; Port-a-Beul 12. グレンコウの虐殺でWoO 152-5 13. 楽しきわが故郷ガリオンから WoO 154-7 14. 小人の妖精たち WoO 154-1 15. Gu ma maith thig an crun dha Tearlach (Well may Charlie wear the crown) 16. Di-moladh an Uisge-bheatha(In dispraise of whisky) 17. The parting glass ※4, 5, 9, 11, 15, 16は器楽曲 |
マリア・ケオハネ(S) リチェルカール・コンソート、 フィリップ・ピエルロ(指) サラ=ジェーンズ・サマーズ(フィドル)、 ゾフィー・ゲント(Vn)、 ジョヴァンナ・ペッシ(ケルト・ハープ)、 ダニエル・ザピコ(G)、 ブノワ・ヴァンデン・ベンデン(Cb)、 フィリップ・ピエルロ(Br) 録音:2020年3月7-9日、ベルギー |
|
||
| MIR-542 |
(ヌフ)~ベートーヴェンとアコーディオンと今日9人の作曲家の出会い (1)ステファヌ・デルプラス:嫌なフーガ(交響曲第9番から触発) (2)ファビアン・ワクスマン:暗い牢獄(交響曲第5番から触発) (3)パトリス・ドローヌ:和解(交響曲第6番から触発) (4)ティボー・ペリーヌ:イン・メモリアム(交響曲第7番から触発) (5)ドミ・エモリーヌ:パラホの嵐(テンペスト・ソナタから触発) (6)コランタン・アパレイー:影より(月光ソナタから触発) (7)ジャン=フランソワ・ジジェル:彼はそこにいる(様々な主題から触発) (8)シリユ・レーン:クロイツェルへのタランテラ(クロイツェル・ソナタから触発) (9)トーマス・エンコ:嵐の後に(ピアノ・ソナタ第32番から触発) |
フェリシアン・ブリュ(アコーディオン) エルメスSQ、 エドゥアール・マカレス(Cb) 録音:2020年5月/サン=マルセル |
|
||
| MIR-548 |
ナターリヤ・ミルシテイン (1)バルトーク:野外にて(全5曲) (2)リスト:忘れられたワルツ第1番 (3)プロコフィエフ:つかの間の幻影Op.22(全20曲) (4)リスト:忘れられたワルツ第2番 (5)アルズマノフ:ピアニスティックな世界第12巻Op.100 ~大気中/競争/ヴァルセット/見えない寺院 (6)同:ピアニスティックな世界第13巻Op.107 ~こんにちは! /柔軟な/消えるコラール (7)同:ユーモアの境でOp.237~行進曲 (8)同:7つの民謡調Op.201~あるロシアの歌の思い出 (9)リスト:忘れられたワルツ第3番 (10)ショパン:3つのマズルカOp.63 (11)リスト:忘れられたワルツ第4番 |
ナターリヤ・ミルシテイン(P) Yamaha CFX使用 録音:2020年7月20-24日/ザーンダム音楽ホール(オランダ) |
|
||
| MIR-550 |
ベートーヴェン:弦楽三重奏曲第2番ト長調 op.9-1 弦楽三重奏曲第3番ニ長調 op.9-2 弦楽三重奏曲第4番ハ短調 op.9-3 |
トリオ・アーノルド 岡田修一(Vn) マニュエル・ヴィオック = ジュード(Va) キム・ボムジュン(Vc) 録音:2020年7月11-14日、ベルギー |
|
||
| MIR-552 |
ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第7番ニ長調(K.271a(271i))(カデンツァ:ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ) |
リヤ・ペトロワ(Vn) 使用楽器:1735年カルロ・ベルゴンツィ‘Helios’ ジャン=ジャック・カントロフ(指) シンフォニア・ヴァルソヴィア 録音:2020年9月14-18日、ワルシャワ |
|
||
| MIR-554 |
リスト:トリスティア ~「オーベルマンの谷」より シューマン:6つのカノン風小品 Op.56(テオドール・キルヒナー編) シェーンベルク:浄められた夜 Op.4(エドゥアルト・シュトイアーマンによるピアノ三重奏曲版) |
トリオ・カレニーヌ パロマ・クイデール(P)、 ファニー・ロビヤール(Vn) ルイ・ロッド(Vc) 録音:2020年8月18-21日、ベルギー |
|
||
| MIR-556 |
ベートーヴェン:チェロとピアノのための作品集 ヴァイオリン・ソナタ 第9番「クロイツェル」 Op.47 イ長調(チェルニーによるチェロ編曲版) モーツァルトの「魔笛」から「恋を知る殿方には」の主題による7の変奏曲 WoO 46 変ホ長調 チェロ・ソナタ 第3番Op.69 イ長調 |
イヴァン・カリズナ(Vc) ヴァシリス・ヴァルヴァレソス(P) 録音:2019年12月2-6日、パリ国立高等音楽院 - Salle Remy Pflimlin |
|
||
| MIR-560 |
ヘンデル&スカルラッティ ヘンデル:「忠実な羊飼い序曲」 HWV 8aより序曲(アンタイ編) 組曲 ニ短調(アルマンド HWV 436 クーラント HWV 437、 サラバンド HWV 438、 メヌエットと変奏 HWV 436、ジーグ HWV 438) 組曲第5番ホ長調 HWV 430 D.スカルラッティ:ソナタ ホ短調 K147、ソナタ イ長調 K24、ソナタ イ長調 K 429、ソナタ ニ長調 K443、ソナタ と短調 K12、ソナタ ト短調 K546、ソナタ 変ロ長調 K16 |
ピエール・アンタイ(Cemb) |
|
||
| MIR-562 |
ベートーヴェン~1802年、ハイリゲンシュタット 「エロイカ変奏曲」(創作主題による15の変奏曲とフーガ) 変ホ長調 op.35 7つのバガテル op.33 ピアノ・ソナタ第17番ニ短調 「テンペスト」op.31-2 創作主題による6つの変奏曲 ヘ長調 op.34 |
ジョナス・ヴィトー(P) 録音:2020年8月31日-9月3日(フランス) |
|
||
| MIR-564 |
フランスのピアノ三重奏曲 サン=サーンス:ピアノ三重奏曲第1番ヘ長調Op.18 ラヴェル:ピアノ三重奏曲イ短調 リリ・ブーランジェ:悲しみの夕べに 春の朝に |
トリオ・エリオス【カミーユ・フォントゥノ(Vn)、ラファエル・ジュアン(Vc)、アレクシス・グルネール(P)】 |
|
||
| MIR-568 |
チェンバロとヴィオラ・ダ・ガンバによるバッハ ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタト短調BWV1029、シンフォニアト短調BWV797、 ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタト長調BWV1027、前奏曲ニ長調BWV1006(無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番)、 ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタニ長調BWV1028、「御身がともにあるならば」BWV508 |
マルゴー・ブランシャール(ヴィオラ・ダ・ガンバ)
ディエゴ・アレス(Cemb) 録音:2022年4月21-24日 |
|
||
| MIR-570 |
親密な言葉 シューマン:3つの幻想的小曲Op.111 クララ・シューマン:3つのロマンスOp.21 ブラームス:アルブムブラット(遺作) ブラームス:ピアノ・ソナタ第3番ヘ短調Op.5 シューマン:暁の歌Op.133の5 シューマン(クララ・シューマン編):献呈 ブラームス:間奏曲変ホ短調Op.118の6 |
プラメナ・マンゴーヴァ(P) 録音:2020年11月28、29日、12月11、12日/フラジェ・スタジオ4(ブリュッセル) |
|
||
| MIR-572 |
ドビュッシー、アーン、ストラヴィンスキー ドビュッシー:ヴァイオリン・ソナタ レイナルド・アーン:ヴァイオリン・ソナタ ハ長調 ストラヴィンスキー:協奏的二重奏曲 |
アイレン・プリッチン(Vn) ルーカス・ゲニューシャス(P) 録音:2021年12月1-3日/サンクトペテルブルグ放送局 |
|
||
| MIR-574 |
女性視線 ルイーズ・ファランク:「ノルマ」のカヴァティーナによる変奏曲Op.14の1 エレーヌ・ド・モンジュルー:ソナタ ヘ短調Op.5~フィナーレ アンナ・ボン・ディ・ヴェネツィア:チェンバロ・ソナタ ト短調Op.2の1 エイミー・ビーチ:舞う木の葉Op.102の2/スコットランドの伝説Op.54の1 アガーテ・バッケル=グロンダール:小品Op.19の2 クララ・シューマン:ロマンスOp.21の1 ファニー・メンデルスゾーン=ヘンゼル:さすらいの歌Op.8の4 エセル・スマイス:自作主題(とてつもなく陰気な)による変奏曲 メル・ボニ:伝説の女たち~メリザンド ジャンヌ・バルビヨン:プロヴァンス(1.海辺。夕暮れ 2.太陽祭) リリー・ブーランジェ:古い庭園 ヘンリエッテ・ボスマンス:6つの前奏曲 ジュルメーヌ・タイユフェール:即興曲 セシル・シャミナード:トッカータOp.39 マリア・エステル・パルク:ソナタOp.4の1~メヌエット エミーリエ・ツムシュテーク:ポロネーズ第3番 クララ・ゴットシャルク=ピーターソン:スタッカート・ポルカ |
マリー=カトリーヌ・ジロー(P) 録音:2020年12月21-23日/エコール・ノルマル・サル・コルトー |
|
||
| MIR-576 |
ラフマニノフ・ピアノ曲集 楽興の時Op.16(全6曲) 前奏曲嬰ハ短調Op.3の2「鐘」 前奏曲ニ長調Op.23の4 前奏曲ト短調Op.23の5 前奏曲変ホ長調Op.23の6 前奏曲変ロ長調Op.23の2 |
ルイス・フェルナンド・ペレス(P)スタインウェイD使用 録音:2019年12月26-30日/マドリード |
|
||
| MIR-578 |
夜への頌歌 (1)ビゼー:耳に残るは君の歌声(「真珠採り」より) (2)オーギュスタ・オルメス:夜と愛(「ルードゥス・プロ・パトリア」より) (3)フォーレ:月の光Op.46の2 (4)シューベルト:セレナードD.957の4 (5)同:君こそわが憩いD.776 (6)同:夜D.983の4 (7)同:森の中の夜の歌D.913 (8)ドヴォルザーク:月に寄せる歌(「ルサルカ」より) (9)グノー:輝かしい夜(「サン=マール」より) (10)ブラームス:静かな夜にWoO34の8 (11)同:森の夜Op.62の3 (12)同:夜警「静かな胸の音」Op.104の1 (13)同:夜警「あなたは眠っているか」Op.104の2 (14)サン=サーンス:夜の静けさOp.68の1 (15)R・シュトラウス:夢の光Op.123の2 (16)ドビュッシー:雲(「夜想曲」より) (17)同:祭(「夜想曲」より) ※編曲:ロラン・ピドゥー(1)-(15)、ルノー・ギウ(16)(17) |
チェロ8【ロラン・ピドゥー、ラファエル・アッレギーニ、ヤニス・ブドリス、アルベリク・ブルノワ、ノエ・ドレダク、レオ・イスピル、エリオット・レリドン、ソニ・シェチンスキ】 録音:2022年10月9-13日 サル・コロンヌ |
|
||
| MIR-582 |
錬金術師ラヴェル ラヴェル:ピアノ協奏曲 ト長調 マ・メール・ロワ クープランの墓(管弦楽組曲) 亡き王女のためのパヴァーヌ(管弦楽版) |
ジャン=フランソワ・エッセール(P、指揮) ヌーヴェル=アキテーヌ室内O 録音:2020年12月11日~13日、2021年1月2,3日 |
|
||
| MIR-584 |
バッハ=アーベル・ソサエティ J.C.バッハ:四重奏曲第2番ニ長調 WKO 194(6つの四重奏曲 op.8より) プレリュード ニ短調 WK205(バス・ヴィオールのための27の小品より) 四重奏曲 ト長調(WKO 227) カール・フリードリヒ・アーベル(1723-1787):プレリュード(バス・ヴィオールのための27の小品より) ソナタ ハ短調(通奏低音とヴィオラ・ダ・ガンバのための10のソナタより) 四重奏曲 ト長調 2本のフルート、2つのヴァイオリンとチェロのためのソナタ op.3-1 ハイドン:スコットランド歌曲集より「メアリーの夢」「私はいとしい人を内緒で愛す」 ヨハン・ザミュエル・シュレーター(1753-1788):チェンバロ五重奏曲 ハ長調 op.1、ソナタ第6番(6つのソナタ op.6より) |
レ・ゾンブル〔マルゴー・ブランシャール(ヴィオラ・ダ・ガンバ)、シルヴァン・サルトル(Fl)、フィオナ・マガウン(Ms)、テオティム・ラングロワ・ド・スワルテ(Vn
)、ジュスタン・テイラー(Pフォルテ)、ハンナ・サルツェンシュタイン(Vc)〕 録音:2021年2月 |
|
||
| MIR-586 |
プーランク:ヴァイオリン・ソナタ FP.119(1943) プロコフィエフ:ヴァイオリンとピアノのための5つのメロディ op.35bis(1921/1925年編) ストラヴィンスキー:ディヴェルティメント(1928/1932年編) ドビュッシー:ヴァイオリン・ソナタ(1917) |
梁美沙(ヤン・ミサ)(Vn)、 アダム・ラルーム(P) 録音:2022年4月2-5日、ベルギー |
|
||
| MIR-588(5CD) |
シューベルト:弦楽四重奏曲全集 [CD1]~ハーモニー 弦楽四重奏曲第1番D18 弦楽四重奏曲第4番ハ長調 D46 弦楽四重奏曲第13番イ短調 D804「ロザムンデ」 [CD2]~歌の技法 弦楽四重奏曲第2番ハ長調 D32 弦楽四重奏曲第6番ニ長調 D74 弦楽四重奏曲第10番変ホ長調 D87 [CD3]~古典派の精神 弦楽四重奏曲第3番変ロ長調 D36 弦楽四重奏曲第8番変ロ長調 D112 弦楽四重奏曲第11番ホ長調 D353 [CD4]~魂の感傷 弦楽四重奏曲第5番変ロ長調 D68 弦楽四重奏曲第9番ト短調 D173 弦楽四重奏曲第14番ニ短調 D810「死と乙女」 [CD5]~光と影 弦楽四重奏曲第12番ハ短調 D703「四重奏断章」 弦楽四重奏曲第7番ニ長調 D94 弦楽四重奏曲第15番ト長調 D887 |
モディリアーニSQ【アムリ・コエイトー(Vn/1773年製グァダニーニ)、ロイック・リョー(ヴァイオイン/1780年製グァダニーニ)、 ローラン・マルフェング(ヴィオラ/1660年製マリアーニ)、フランソワ・キエフェル(Vc/1706年製マッテオ・ゴフリラー”ex-Warburg”)】 録音:第1,2,3,5,6,11番/2021年2,3月、第4,8,9,10番/2021年10月、第12,13,14,15番/2021年9月 |
|
||
| MIR-590 |
モーツァルト:ピアノ協奏曲第14番変ホ長調K.449 ピアノと管弦楽のためのロンド ニ長調K.382 ピアノ協奏曲第12番イ長調K.414 |
セリム・マザリ(P) ポール・メイエ(指) マンハイム・プファルツ選帝侯室内O(マンハイム・チェンバー・オーケストラ) 録音:2021年3月16-19日/マンハイム・エピファニー教会 |
|
||
| MIR-594 |
ファニー&フェリックス・メンデルスゾーン ファニー・メンデルスゾーン=ヘンゼル(1805-1847):ピアノ三重奏曲 ニ短調 op.11 メンデルスゾーン:ピアノ三重奏曲 ニ短調 op.49 |
トリオ・ショーソン 録音:2021年4月 |
|
||
| MIR-596 |
リスト:超絶技巧練習曲 S.139 | ガブリエル・スターン(P) 録音:2021年5月14-17日、スイス |
|
||
| MIR-598 |
ヴィリアンクール・プレイズ・フランク 交響詩「ジン」 前奏曲,コラールとフーガ 交響的変奏曲 前奏曲、アリアとフィナーレ |
タンギ・ド・ヴィリアンクール(P) クリスティーナ・ポスカ(指)フランダースSO 録音:2021年4月26-29日/ブルージュ・コンセルトヘボウ |
|
||
| MIR-600 |
ヴラディゲロフ:作品集 (1)10の印象Op.9【慕情/抱擁/ワルツ・カプリス/愛撫/優雅/告白/笑い/情熱/驚き/諦め(エレジー)】 (2)ブルガリア組曲Op.21【行進曲風に/歌/チェーンダンス/ラチェニッツァ】 (3)前奏曲Op.15 |
広瀬悦子(P) ※ベヒシュタイン使用 録音:2021年4月5-7日/サンマルセル教会(パリ) |
|
||
| MIR-602 |
ローマの晩祷 ピエトロ・パオロ・ベンチーニ:神よ、わが保護に心を向けたまえ1. めでたし、海の星よ(アヴェ・マリス・ステラ) その方の左手が、わが頭の下に 詩篇第109篇「主は言われた」 王が宴におられる間 詩篇第111篇「主を信ずる者は幸いなり」(ベアトゥス・ヴィル) 私は黒い アレッサンドロ・スカルラッティ:主の僕たちよ、主をほめたたえよ マニフィカト |
ジョエル・スービエ(指)アンサンブル・ジャック・モデルヌ ソプラノ:セシル・ディボン=ラファルジュ、シプリール・メイエル、ジュリエット・ペレ、ユリア・ヴィシニェフスキ アルト:マルゴ・メルーリ、ギレーム・テライユ テノール:マルク・マノドリッタ、ギヨーム・ザベ バス:ディディエ・シュヴァリエ、マチュー・ル・ルヴルール 録音:2021年5月20-23日サン・フロラン・ル・ヴィエイユ修道院 |
|
||
| MIR-604 |
Ellipses~円 ジョヴァンニ・ソッリマ(b.1962)/ボッケリーニ:ファンダンゴ ドビュッシー:チェロ・ソナタ ヴィラ=ロボス:ブラジル風バッハ第5番「アリア」~チェロとギターのための編曲版 ヴィレム・デ・フェッシュ(1687-1761):シシリエンヌ(バロック・チェロとチェンバロ) フォーレ:シシリエンヌ op.78(Vcとピアノ) マリア・テレジア・フォン・パラディス(1759-1824):シシリエンヌ(Vcとピアノ版) ヨハン・エルンスト・ガリアルド(1687-1747):シシリエンヌ(バロック・チェロとチェナロ) マラン・マレ:スペインのフォリア(Vcとチェンバロ版、セルバン・ニキフォルによる) ティエリー・エスケシュ:ラ・フォリア(無伴奏チェロのための) ジュール・マットン(b.1988):Detail(細部)~バロック・チェロとチェンバロのための(世界初録音) コベーキン:ハヤルド(Vcとタンブーランのための) |
アナスタシヤ・コベキナ(Vc/1698年製ストラディヴァリウス)
ヴァンサン・ボッカドーロ(P)エマニュエル・アラケリアン(Cemb)、ティヴォー・コヴァン(G)、トリスタン・ペレイラ(パーカッション) 録音:2021年5月3-6日 |
|
||
| MIR-606 |
ラ・ファヴォリート(お気に入り) ジャック・デュフリ(1715-1789):クラヴサン曲集第3巻 ジャン=バティスト・カルドンヌ(1730-1792):”ラ・ファヴォリート”(ソナタ第4番~ヴァイオリンをともなうクラヴサンのためのソナタ集第1巻より~ドーフィーヌ夫人に捧ぐ) モンドンヴィル:通奏低音をともなうヴァオリン・ソロのためのソナタ第5番~ラ・カシア(狩) ルイ・クープラン(1727-1789):ソナタ第3番随意にヴァイオリンをともなう、クラヴサンの小品の形式の6つのソナタ集~ボーヴォー嬢に捧ぐ カルドンヌ:ソナタ第6番~ヴァイオリンをともなうクラヴサンのためのソナタ集第1巻より~ドーフィーヌ夫人に捧ぐ ショーベルト(1735-1767):ソナタ第4番ニ短調 |
ジョスリン・キュイエ(Cemb)、 ダイエル・キュイエ(Vn) 録音:2021年10月2-4日 |
|
||
| MIR-608 |
スウェーデン歌曲集 1. トール・アウリン(1866-1914):ばらに(Till en ros) ヴィルヘルム・ステーンハンマル(1871-1927): 2. メロディ(Melodi)3. 彼方を船はゆく(Det far ett skepp) 4. Fylgia(フュリア) 5. テューレ・ラングストレム:ただひととき(Den Enda Stunden) 6. ステーンハンマル:楓の木陰で(I lonnens skymning) ヴィルヘルム・ペッテション=ベリエル: 7. 山羊よ、坊やのところまで(Kom bukken til gutten) 8. 収穫後の歌(Sang efter skordeanden) 9. テューレ・ラングストレム:別れ(Avskedet) 10. ステーンハンマル:森で(I skogen) ボー・リンデ(1933-1970): 11. リンゴの木と洋梨の木(Appeltrad och parontrad) 12. あなたが私に口づけをした草原で(Den angen dar du kysste mig) 13. シグルド・フォン・コック(1879-1919):シャイトラの月に(I manaden Tjaitra) トゥーレ・ラングストレム:14. 夜の翼(Vingar i natten) 15. 夜への祈り(Bon till natten) 16. ラーシュ=エリク・ラーション:草はさまよえる足の下で歌う(For vilsna fotter sjunger graset) 17. ヴィルヘルム・ペッテション=ベリエル:待つは楽しい(Intet ar som vantanstider) 18. トール・アウリン:そして騎士は聖地に向かった(Och riddaren for uti osterland) 19. トゥーレ・ラングストレム:セレナード(Serenad) 20. グスタフ・ノルドクビスト(1886-1949):海で(Till havs) 21. ヴィルヘルム・ステーンハンマル:海辺の歌(En strandvisa) 22. グンナル・デ・フルメリー(1908-1987):あなたが私の目をとじるとき(Nar du sluter mina ogon) 23. ヴィルヘルム・ペッテション=ベリエル:Boljeby Waltz(Boljeby-vals) |
マリーヌ・シャニョン(Ms) ジョセフィー ヌ・アンブロセッリ(P) |
|
||
| MIR-610 |
GEISTER DUO シューマン:東洋の絵 op.66 ブラームス:シューマンの主題による変奏曲 op.23 ドヴォルザーク:ボヘミアの森より op.68 |
ガイスター・デュオ ダヴィド・サルモン&マニュエル・ヴィエイヤール(P) 使用楽器:ヤマハ 録音:2021年5月21-24日 |
|
||
| MIR-612 |
ブルターニュのエレノアのグラドゥアーレ集~フォントヴローのクリスマス ・真夜中のミサ ・夜明けのミサ ・日中のミサ |
ヴォックス・クラマンティス、 ヤーン=エイク・トゥルヴェ(指) 録音:2021年11月22-28日、フォントヴロー修道院 |
|
||
| MIR-616 |
ショーソン・サン=サーンス ショーソン:ピアノ三重奏曲ト短調Op.3 サン=サーンス:ピアノ三重奏曲第2番ホ短調Op.92 |
ネーベルメーア・トリオ【ロアン・フルマンタル(P)、アルトゥー
ル・ドゥカリス(Vn )、アルベリック・ブルノワ(
チェロ)】 録音:2021年10月27-31日/カーン音楽院 |
|
||
| MIR-620 |
Muses eternelles~永遠のミューズたち ラフマニノフ:「春の洪水」 op.14-11、「リラの花」 op.21-5 ラヴェル:マダガスカル島民の歌(「ナアンドーヴ」、「おーい(呼び声)」、「休息-それは甘く」) デュパルク:「戦のある国へ」、「前世」 ワーグナー:「天使」、「温室にて」(ヴェーゼンドンク歌曲集より) ショーソン:「温室」(歌曲集「温室」op.24より第1曲) R.シュトラウス:「あした!」op.27-4 ジェイク・ヘギー(b.1961):アニマル・パッション(ナチュラル・セレクションより) |
シリー ル・ンジキ(S)、カオリ・オノ(P)、イリス・シャロン(Vn
/シュトラウス)、サラ・ファン・デア・ヴリスト(フルート/ラヴェル)、アルベリク・ブルノワ(Vc/ラヴェル) 録音:2020年9月21-25日、パリ国立高等音楽院 |
|
||
| MIR-622(2CD) ★ |
メシアン:峡谷から星たちへ・・・(全12曲)(1970-74) | ジャン=フランソワ・エッセール(指)、 ヌーヴェル=アキテーヌ室内O ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ(P)、 根本雄伯(Hrn)、 アデライーデ・フェリエール(シロリンバ)、 フロラン・ヨデレ(グロッケンシュピール) 録音:2021年5月20-23日 |
|
||
| MIR-624 |
レシ 組曲ニ調 (1)ジャック・ボワヴァン:レシ・グラーヴェ (2)アンリ・デュモン:アルマンド (3)マラン・マレ:鐘あるいはカリヨン (4)同:人間の声 (5)アンリ・デュモン:デュモン氏のパヴァーヌ 組曲ホ調またはト長 (6)ジャン=アダム・ギラン:ティルセによるレシ (7)同:トリオ (8)マラン・マレ:ジグ「もめごと」 (9)同:嘆き (10)同:シャコンヌ (11)ジャン=アダム・ギラン:ディアローグ (12)マラン・マレ:昔のリュート作曲家の流儀によるパヴァーヌ 組曲イ調 (13)ダンドリュー:ティルセによるレシ (14)アンリ・デュモン:オルガン・タブラチュアによるアルマンド (15)ルイ・クープラン:ピエモンテ人 (16)マラン・マレ:サラバンド (17)同:花嫁 (18)同:ファンタジー 組曲ニ調 (19)ルイ・マルシャン:レシ (20)ピエール・デュ・マージュ:バス・ド・トロンペット (21)ルイ・クープラン:クープラン氏のサラバンド (22)ピエール・デュ・マージュ:プラン・ジュ |
サロメ・ガセラン(ヴィオラ・ダ・ガンバ) エマニュエル・アラケリヤン(Org)、 マティアス・フェレ、アンドレアス・リノス、コリンナ・メッツ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)、 ジャスティン・テイラー(Cemb) 録音:2021年9月 聖アポリネール・ド・ボラン教会(ベルギー)、12月 サン・トゥルザンヌ教会(スイス) |
|
||
| MIR-626 |
モーツァルト:クラリネット作品集 (1)クラリネット協奏曲イ長調K.622 (2)クラリネット五重奏曲イ長調K.581 |
ラファエル・セヴェール(Cl) ラルス・フォークト(指)パリ室内O(1) モディリアーニSQ(2) 録音2021年10月6-8日フィラルモニ・ド・パリ(1) 2022年2月1-2日サル・コロンヌ(2) |
|
||
| MIR-630 |
Un monde fantastique~幻想的世界 リスト:グノーのファウストのワルツにもとづくパラフレーズ シューマン(リスト編):「春の夜」(リーダークライス op.39-12) シューマン:クライスレリアーナ op.16 シューマン(リスト編):献呈 op.25-1 リスト:ダンテを読んで―ソナタ風幻想曲 ジャン=バティスト・ドゥルセ:エンディミオン(2021, キーツの詩による) |
ジャン=バティスト・ドゥルセ(P) 録音:2021年12月 |
|
||
| MIR-632 |
ヴェネツィアの天才を祝う~カルダーラとヴィヴァルディ ヴィヴァルディ:『グローリア』 RV 589、 協奏曲 ハ長調 RV 443、 協奏曲 ト短調 RV 156、 協奏曲 ニ長調 RV 781 カルダーラ:シンフォニア(セレナーデ 1709年より)、 モテット「Caro mea vere est cibus」、 シャコンヌ(op.2より)、 シンフォニア(オラトリオ「アベルの死」より) |
アマリリス(エロイーズ・ガイヤール/音楽監督、リコーダー、バロック・オーボエ;セルジュ・チザク/トランペット他)
ペイ・ド・ラ・ロワール児童合唱団(合唱指揮:マリアナ・デルガディッロ・エスピノーザ) 録音:2021年2月 |
|
||
 MIR-634 |
ベートーヴェン:後期3大ソナタ ピアノ・ソナタ第30番ホ長調Op.109 ピアノ・ソナタ第31番変イ長調Op.110 ピアノ・ソナタ第32番ハ短調Op.111 |
アンヌ・ケフェレック(P) 録音:2022年2月5-8日ポワチエ劇場講堂 |
|
||
| MIR-636 |
ハイドン:ピアノ三重奏曲集 ピアノ三重奏曲 ト長調 Hob.XV:15(フルート、チェロとピアノ) ピアノ三重奏曲 ヘ長調 Hob.XV:16(Vn、チェロとピアノ) ピアノ三重奏曲 ニ長調 Hob.XV:16(フルート、チェロとピアノ) ピアノ三重奏曲 ホ短調 Hob.XV:12(Vn、チェロとピアノ) |
ジェローム・アンタイ(フォルテピアノ)、 マルク・アンタイ(Fl) アレッサンドロ・モッチア(Vn) アリクス・ヴェルジエ(Vc) 録音:2020年2月 |
|
||
| MIR-642 |
ゾーイのためのダンス集 ブラームス:ワルツOp.39~第1番ロ長調/第11番ロ短調/第6番嬰ハ長調/第3番嬰ト短調/第14番嬰ト短調/第15番変イ長調 スクリャービン:マズルカOp.25の2 トーマス・アデス:マズルカOp.27の2 (4)ラヴェル:メヌエット~「クープランの墓」 C.P.E.バッハ:メヌエット マタン・ポラト:ワルツ・フォー・ビル ビル・エヴァンス:ワルツ・フォー・デビイ ストラヴィンスキー:タンゴ ナンカロウ(ポラト編):練習曲第6番「タンゴ」 ラモー:サラバンド~組曲イ短調 サティ:サラバンド第3番 スクリャービン:ワルツOp.38 クープラン:フォルラーヌ~王宮コンセール第4番 ラヴェル:フォルラーヌ~「クープランの墓」 ラッヘンマン:影踊り~「子供の遊び」 ショスタコーヴィチ:ワルツ・スケルツォ~「人形の踊り」 |
マタン・ポラト(P) 録音:2022年5月23-25日/ノイマルクト・ライツターデル(ドイツ) |
|
||
| MIR-646 |
スーク&ドヴォルザーク スーク:ピアノ三重奏曲 ハ短調 op.2、 エレジーop.23 ドヴォルザーク:ピアノ三重奏曲 第3番ヘ短調 op.65 |
トリオ・カレニーヌ【シャルロッテ・ジュイヤール(Vn)、ルイ・ロッド(Vc)、パロマ・クイデール(P)】 録音:2022年 |
|
||
| MIR-650 |
冬のセレナード (1)ドビュッシー:冬は嫌いだ(「シャルル・ドルレアンの3つの歌」より) (2)ドリーブ:寒気の合唱 (3)フランス民謡::新しいノエル (4)クロード・グディメル:精霊たち、聖なる夜に歌おう (5)ウスタシュ・デュ・コロワ:ようこそ、栄光なる聖母 (6)プーランク:クリスマスのための4つのモテット (7)パトリック・ブルガン:雪の夜 (8)サン=サーンス:冬のセレナード (9)プーランク:白雪 (10)同:雪の夜 (11)ザド・ムルタカ:フランマ (12)バスク民謡::若き乙女がいた (13)アントワーヌ・ビュノワ:ノエル、ノエル、ノエル (14)アントワーヌ・ブリュメル:ノエ、ノエ、ノエ (15)フランス民謡::聖母よ、われらに歌いたまえ(クリストフ・バラールによる) (16)ニコラ・サボリ:カンボが私を傷つける (17)クローダン・ド・セルミジ:声のかぎりノエと叫ぼう (18)アンリ・マルティネ:プチ・パパ・ノエル ※(2)(3)(15)(16)(18)ピエール・ジャノ編 |
ジョエル・シュービエット(指) レ・ゼレマン 録音:2022年2月28日-3月5日 サン・ピエール・デ・キュイジーヌ教会(トゥールーズ) |
|
||
| MIR-656 |
ドビュッシー:6つの古代墓碑銘 牧神の午後への前奏曲【ラヴェルによる4手連弾版、1910年】 ストラヴィンスキー:ペトルーシュカ(作曲者自身による4手連弾版) |
ガイスター・デュオ〈マニュエル・ヴィエイヤール(プリモ)、ダヴィド・サルモン(セコンド)〉 録音:2022年4月26-28日、ベルリン、エルベルク教会・トーンストゥディオ、ドイツ |
|
||
| MIR-660 |
ブラームス:セレナード集 セレナード第2番イ長調Op.16 セレナード第1番ニ長調Op.11 |
ヴィクトル・ジュリアン=ラフェリエール(指) コンスエロO 録音:2022年9月30日-10月3日/ヴァンセンヌ・メディアセンター |
|
||
| MIR-662 |
ボヘミアのピアノ三重奏曲 ノヴァーク:ピアノ三重奏曲第2番ニ短調Op.27「バラード風」 フィビヒ:ピアノ三重奏曲ヘ短調 スメタナ:ピアノ三重奏曲ト短調Op.15 |
トリオ・エリオス【カミーユ・フォントゥノ(Vn)、ラファエル・ジュアン(Vc)、アレクシス・グルネー
ル(P)】 録音:2022年7月8-12日/アルセナル=メス |
|
||
| MIR-664 |
カプリス ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲* バッハ:カプリッチョ「最愛の兄の旅立ちにあたって」BWV992 ブラームス:カプリッチョ嬰ヘ短調Op.76の1 パガニーニの主題による変奏曲第1集Op.35 レイナルド・アーン:ミニュミネク フォーレ:ヴァルス・カプリス第2番変ニ長調Op.38 モーリス・オアナ:カプリス第1番「埋めて黙れ」 アルカン:イソップの饗宴Op.39の12 |
ナタナエル・グーアン(P) アレクサンダル・マルコヴィチ(指) シンフォニア・ヴァルソヴィア 録音:2022年12月20-21日ポーランド放送コンサート・スタジオ(ワルシャワ)*、10月24-27日シテ・ド・ソレーズ(2)-(8) |
|
||
| MIR-668 |
ブクステフーデ:救世主~受難と復活のカンタータ集 1. Jesu, meines Lebens Leben(イエスは我が生命の生命) BuxWV62 2. Furwahr, er trug unsere Krankheit(げに彼は我らの病を負い)BuxWV 31 3. Ich bin die Auferstehung(我は蘇りなり) BuxWV44 4. Laudate pueri(主をほめたたえよ)BuxWV 69 5. Befiel dem Engel, das er komm(来たれと天使に告げて言え) BuxWV10 6. Quemadmodum desiderat cervus(鹿の谷川を慕いあえぐがごとく) BuxWV92 7. Herr, ich lasse dich nicht(主よ、我汝を去らじ) BuxWV36 8. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr(心より我汝を愛す、おお主よ) BuxWV41 |
リチェルカール・コンソート フィリップ・ピエルロ(指&ヴィオラ・ダ・ガンバ) ハンナ・バヨディ=ヒルト、イェツァベル・アリアス(S) ダヴィド・サガストゥム(A) ユーゴ・イマ(T) マティアス・ヴィエヴェグ(Bs) 録音:2022年10月10-15日 |
|
||
| MIR-670 |
Momentum1 ウォルトン:ヴァイオリン協奏曲(ロ短調) レスピーギ:ヴァイオリン・ソナタ(ロ短調) |
リヤ・ペトロワ(Vn/Helios、1735年カルロ・ベルゴンツィ製) ロイヤルPO ダンカン・ウォード(指) アダム・ラルーム(P) 録音:[ウォルトン]2022年9月5日、ロンドン/[レスピーギ]2023年1月28-29日 |
|
||
| MIR-672 |
ハンガリー風狂詩曲集 バルトーク:ピアノ・ソナタ Sz.80、野外にて コダーイ:マロシュセーク舞曲集 リスト:ハンガリー狂詩曲第5番ホ短調 「悲しい英雄物語」、第16番 イ短調、第10番ホ長調 「前奏曲」 |
ロドルフ・メンギ(P) |
|
||
| MIR-674 |
ラヴェル:弦楽四重奏曲 ヘ長調 シューマン:弦楽四重奏曲第3番イ長調 op.41 |
レオンコロSQ【〔ヨナタン・昌貴・シュヴァルツ
(1st Vn)、アメリー・コジマ・ヴァルナー(2nd
Vn)、近衞麻由 (Va)、ルカス・実(ミノル)・シュヴァルツ
(vc)】 録音:2022年12月14-17日、テルデックス・スタジオ |
|
||
| MIR-682 |
グリーグ:弦楽四重奏曲 第1番 ト短調 op.27(1878年) スメタナ:弦楽四重奏曲 第1番 ホ短調 「わが生涯より」(1876年) |
モディリアーニSQ【アモリ・コエイトー(Vn):1773年ジョヴァンニ・バッティスタ・グアダニーニ、ロイック・リョー(Vn):1734年製ガリアーノ
、ローラン・マルフェング(Va):1660年製ルイジ・マリアーニ
、フランソワ・キエフェル(Vc):1706年ゴフリラー「ヴァールブルク」】 録音:2022年12月6-9日、シューベルティアーデ、オーストリア |
|
||
| MIR-684 |
Chants de l’Isole~孤立の歌 フィリップ・エルサン(b.1947):Chants de l’Isole(孤立の歌)(P、ヴァイオリン、チェロ、弦楽オーケストラとパーカッションのための)(2014) ブノワ・ムニュ(b.1977):Les Allees Sombres(暗い通り)(Vn、チェロとピアノのための三重奏曲第2番)(2013) フィリップ・エルサン:ザッハーの名によるファンタジー(弦楽オーケストラのための)(2008初演) ブノワ・ムニュ:岸辺から(P、パーカッション、弦楽オーケストラのための詩曲)(2022) |
トリオ・カレニーヌ、ワロニー室内王立O、 ヴァハン・マルディロシアン(指) 録音:2022年3月31日-4月1日 |
|
||
 MIR-686 |
モーツァルト:ピアノ協奏曲 第20番ニ短調 KV466 ピアノ協奏曲 第27番変ロ長調 KV595 |
アンヌ・ケフェレック(P) リオ・クオクマン(指)パリ室内O 録音:2023年2月21-24日、フィルハーモニー・ド・パリ |
|
||
| MIR-688 |
デュール (Duelles) (1)ヘンリエッテ・ボスマンス:ヴァイオリン・ソナタ(1918) (2)グラジーナ・バツェヴィチ:カプリス第3番(1930) (3)ドラ・ペヤチェヴィチ:スラヴ・ソナタOp.43(1917) (4)バツェヴィチ:オベレク第1番(1951) (5)マルグリット・カナル:ヴァイオリン・ソナタ(1925) |
ラファエル・モロー(Vn) セリア・オヌト・ベンサイド(P;YAMAHA CFX) 録音:2023年2月17日~3月2日/ヴィルファヴァール農園 |
|
||
| MIR-690 |
Momentum2~コルンゴルト&シュトラウス コルンゴルト:ヴァイオリン協奏曲 op.35 R. シュトラウス:ヴァイオリン・ソナタ 変ホ長調 op.18* |
リヤ・ペトロワ(Vn) ロイヤルPO ダンカン・ワード(指) アレクサンドル・カントロフ(P) 録音:2022年9月6日聖ヨハネ・スミス・スクエア(イギリス) 、2023年9月、TAP(フランス)* |
|
||
| MIR-698 |
E IL VIOLONCELLO SUONO~そしてチェロは奏でられる 1. ジュリオ・タリエッティ(1660-1718):チェロと、スピネットあるいはヴィオローネで弾くアリア・ダ・スオナーレ19番よりアダージョ 2. ジューリオ・デ・ルヴォ(c.1650-c.1716):シャコンヌ 3. ヴィヴァルディ:チェロと通奏低音のためのソナタ ホ短調 RV40 4. ジュゼッペ・マリア・ダッラーバコ(1710-1805):独奏チェロのためのカプリッチョI ハ短調 5. ヴィヴァルディ:チェロと通奏低音のためのソナタ 変ロ長調 RV46より「ラルゴ」 6. プラッティ(1607-1763):チェロと通奏低音のためのソナタ第3番/イ長調より「ラルゴ」 7. ジョルジョ・アントニオット(1681-1776):チェロと通奏低音のためのソナタ第4番 ニ短調 作品1より「ラルゴ」 8. ダッラーバコ:無伴奏チェロのためのカプリッチョ第4番ニ短調 9. マルチェッロ:チェロと通奏低音のためのソナタ第3番 ト短調より「ラルゴ」 10. ガスパロ・ガラヴァリア(18世紀):チェロと通奏低音のためのソナタ ト短調 11. ダッラーバコ:無伴奏チェロのためのカプリッチョ第4番ホ短調 12. ヴィヴァルディ:トリオ・ソナタ(Vn、チェロと通奏低音)ト長調 RV820 13. ジューリオ・デ・ルヴォ:タランテラ |
ハンナ・ザルツェンシュタイン(Vc)、 ジュスタイン・テイラー(Cemb)、 ティボー・ルーセル(アーチリュート)、 アルベリク・ブ ルノワ(Vc)、 テオティム・ラングロワ・ド・スワルテ(Vn)、 マリー=アンジュ・プティ(パーカッション ) 録音:2023年10月9-13日、パリ、ドイツ福音主義教会 |
|
||
| MIR-704 |
チャイコフスキー:四季 (1)チャイコフスキー:四季Op.37a(全12曲) (2)グリンカ:ノクターン「別れ」 (3)キュイ:セレナード~アルジャントーにてOp.40より (4)バラキレフ:ノクターン第3番 (5)グリンカ(バラキレフ編):ひばり (6)ムソルグスキー(チェルノフ編):禿山の一夜 |
ドミートリー・マスレエフ(P) 録音:2022年6月17-18日、2023年6月28-29日モスフィルム・スタジオ1 |
|
||
| MIR-708 |
禁じられた愛 プーランク:エディット・ピアフへのオマージュ(「15の即興」より第15番) チャイコフスキー:花のワルツ(「くるみ割り人形」op.71より)パーシー・グレインジャー編 エセル・スマイス(スミス)(1858-1944):ノクターン/ハ長調の小品/若き日より レイナルド・アーン(1874-1947):ほどけたリボン(カドゥシュ編)/画家の肖像 アンソニー・ファン・ ダイク/黄昏時の別れ(当惑したナイチンゲールより)/ワルツ「ニネット」 ワンダ・ランドフスカ(1879-1959):秋の夜/ワルツ ホ短調/鬼火(Feu follet) プーランク:メランコリー/プレスト シマノフスキ:ポーランド民謡のテーマに基づく変奏曲 op.10[テーマ/ヴァリエーション I-VII /ヴァリエーション VIII-IX /フィナーレ] チャイコフスキー:四羽の白鳥の踊り(「白鳥の湖」op.20より)アール・ワイルド編 シャルル・トレネ(1913-2001)/アレクシス・ワイセンベルク(1929-2012):パリの四月 |
ダヴィド・カドゥシュ(P) 録音:2024年9月23-26日、ポワティエ |
|
||
| MIR-714(3CD) |
リスト:「巡礼の年」 [CD1] ・巡礼の年第1年『スイス』 「ウィリアム・テルの礼拝堂」、「ワレンシュタット湖畔で」、「牧歌」(パストラール)、「泉のほとりで」、「夕立」、「オーベルマンの谷」、「牧歌」(エグローグ)、「郷愁」、「ジュネーヴの鐘」 [CD2] ・巡礼の年第2年『イタリア』 「婚礼」、「物思いに沈む人」、「サルヴァトール・ローザのカンツォネッタ」、「ペトラルカのソネット 第47番」、「ペトラルカのソネット 第104番」、「ペトラルカのソネット 第123番」、「ダンテを読んで-ソナタ風幻想曲」 ・巡礼の年第2年補遺『ヴェネツィアとナポリ』 「ゴンドラを漕ぐ女」、「カンツォーネ」、「タランテッラ」 [CD3] ・巡礼の年第3年 「夕べの鐘、守護天使への祈り」、「エステ荘の糸杉に寄せて-葬送歌(第1)」、「エステ荘の糸杉に寄せて-葬送歌(第2)」、「エステ荘の噴水」、「哀れならずや-ハンガリー風に」、「葬送行進曲」、「心を高めよ」 |
ニコラ・アンゲリッシュ(ピアノ) 録音:2003年 |
|
||
| MIR-720(6CD) |
D.スカルラッティ:100のソナタ集/ピエール・アンタイ [Disc1] ソナタ ニ長調 K.535/イ短調 K.3/イ短調 K.175/イ短調 K.208/イ短調 K.54/ヘ短調 K.185/変ロ長調 K.248/変ロ長調 K.249/変ロ長調 K.310/ニ長調 K.299/ニ長調 K.484/ホ長調 K.162/ハ長調 K.199/ニ長調 K.145/ニ短調 K.141/ホ短調 K.531/ニ長調 K.177/ニ長調 K.492 [Disc2] フーガ ニ短調 K.58/ヘ短調 K.239、変ホ長調 K.370、変ホ長調 K.371、ホ長調 K.135、ホ長調 K.215、ホ長調 K.216、嬰へ短調 K.25、ロ長調 K.261、ロ長調 K.262、ホ短調 K.263、ホ長調 K.264、ト長調 K.314、ト長調 K.259、ト長調 K.260、ハ短調 K.84 [Disc3] ニ短調 K.213、ニ長調 K.214、ロ短調 K.227、ニ長調 K.511、ト短調 K.8、ハ短調 K.56、ハ短調 K.526、ヘ長調 K.468、ヘ長調 K.525、ヘ短調 K.466、ヘ長調 K.366、ヘ長調 K.276、ヘ長調 K.151、ニ短調 K.517、ロ短調 K.27、ト長調 K.146 [Disc4] イ長調 K.212、ニ短調 K.247、ト長調 K.144、ハ長調 K.133、ヘ短調 K.204a、イ長調 K.279、イ長調 K.533、イ長調 K.405、ホ短調 K.402、ホ長調 K.403、ホ長調 K.381、イ長調 K.208、イ長調 K.456、イ長調 K.457、ハ短調 K.302、ト長調 K.201、ニ長調 K.45 [Disc5] 変ロ長調 K.551、変ホ長調 K.474、変ホ長調 K.475、変ホ長調 K.252、変ホ長調 K.253、ト長調 K.547、ロ短調 K.87、ホ長調 K.28、 イ長調 K.211、ニ長調 K.401、ニ長調 K.388、ニ長調 K.277、ト長調 K.124、ハ長調 K.157、ヘ短調 K.238、ヘ長調 K.205 [Disc6] ニ長調 K.119、ト短調 K.179、ト短調 K.234、ハ長調 K.501、ハ長調 K.502、ヘ短調 K.69、ト短調 K.43、ハ長調 K.384、ハ長調 K.487、ハ長調 K.170、ヘ長調 K.6、変ロ長調 K.550、ニ短調 K.18、変ロ長調 K.544、変ロ長調 K.273、ニ長調 K.161、ト長調 K.477 |
ピエール・アンタイ(Cemb) [Disc1] 録音:2002年 [Disc2] 録音:2004年 [Disc3] 録音:2005年 [Disc4] 録音:2015年 [Disc5] 録音:2016年 [Disc6] 録音:2003年 |
|
||
| MIR-724 |
ORIGINES~オリジン/レ・ズィティネラント [Creation~創造] 1. ビッグ・バン/複数の借用(引用)による作品 編曲:マノン・クサン、エロディー・ポン、ミヒャエル・マグリン [Earth~土] 2. トゥンカ・ロワンピ(Tunka Lowampi)/ラコタ(スー族)の伝統音楽 編曲:エロディー・ポン 3. ウォーキング・ソング(Waulking Song)/スコットランド、アイルランドの伝統音楽 編曲:ポーリーヌ・ラングロワ・ド・スワルテ 4. オロヴェラ(OROVELA)/ギリシアの伝統音楽 5. 愛の神に讃美あれ(ACK LOVA GUD)/スウェーデンの伝統音楽 編曲:マノン・クサン [Fire~火] 6. 女戦士たちのダール(DAHR SAELLI)/リリアン語(ド・スワルテが造った言語)による 作詞・編曲:ポーリーヌ・ラングロワ・ド・スワルテ 7. アデス・キリイ(ADES KIRIJ)/ムンハリ語(マノン・クサンが造った言語)の作品 作詞・編曲:マノン・クサン 8. ドラゴ(DRAGO)/リトアニアの伝統歌~エルダリ語(エロディー・ポンが造った言語)の作品 9. カテル(KATELL)/迷子のカテリーヌ(ブルターニュ伝承の物語)~フレン(Fulenn) 作曲:アレクシス・モルヴァン=ロジウ、詞:マリーヌ・ラヴィーニュ、編曲:エロディー・ポン [Water~水] 10. 水の月(MIZU NO TSUKI)~日本の歌にインスパイアされた作品 編曲、作曲:エロディー・ポン 11. プーランク:かわいい小さなお姫様(C’EST LA PETIT’ FILLE DU PRINCE) 編曲:マノン・クサン 12. 古池や(FUUR IKE YA)~日本の歌にインスパイアされた作品 編曲・作曲:エロディー・ポン 13. ドビュッシー:亜麻色の髪の乙女 詞と編曲:ポーリーヌ・ラングロワ・ド・スワルテ [Air~空気] 14. 空気は飛んでいく(AER ENIM)~ヒルデガルト・フォン・ビンゲンの作品 15. ULETAY(イーゴリ公)~だったん人のおどり 編曲:マノン・クサン 16. AESTAS~夏はきたりぬ(中世イングランド)~Amor Potest Conqueri ~Ad Amorem et Alle Psallite Cum Luya 編曲:ポーリーヌ・ラングロワ・ド・スワルテ 17. LOOMINE~エストニア 編曲:エロディー・ポン [Ether~エーテル] 18. TERRA MATER*~ヒルデガルト・フォン・ビンゲンのテキストによる作曲およびポーリーヌ・ラングロワ・ド・スワルテの音楽 |
レ・ズィティネラント〔マノン・クサン(声 )、ポーリーヌ・ラングロワ・ド・スワルテ(声
)、エロディー・ポン(声 )〕 ティエリー・ゴマル(パーカッション) Irvem聖歌隊*(トラック18のみ参加) 録音:2023年9月1-5日、サン=ローラン教会 |
|
||
| MIR-756 |
月と炎 / アリエル・ベック シューマン:フモレスケ 変ロ長調 op.20 ブラームス:8つのピアノ小品 op.76 アリエル・ベック:シューマンの主題による変奏曲 |
アリエル・ベック(P/ Shigeru Kawai SK-EX)
録音:2024年10月21-24日、フェルム・ド・ヴィルファヴァール |
|
||
| MIR-774 |
シューマン風に チャイコフスキー:6つの小品〔1. 夕べの夢想 2. ユーモラスなスケルツォ 3. アルバムの綴り 4. 夜想曲 5. カプリッチョーソ 6. 創作主題と変奏〕 シューマン(ナターリヤ・ミルシテイン編):オラトリオ「楽園とペリ」より 合唱曲「ああ、ああ、彼は目標を達成できなかった)」 シューマン:幻想曲 ハ長調 op.17 |
ナターリヤ・ミルシテイン(P) 録音:2025年2月3-7日 |
|
||
| MIR-9911 |
17世紀後半ドイツの独唱曲集 J.C.バッハ:哀歌, ああ、たっぷり水があったなら、 C.ベルンハルト:なにがおまえを悩ませるのかわが魂よ、 C.ガイスト:だがそれはあの方が十字架につけられていた場所のそばだった、悲しみよ!心の痛みよ!、 J.M. バッハ:ああどんなにそのときを待ち焦がれているでしょう、 J.A.ラインケン:ソナタイ短調、 N.ハッセ:永遠について、 J.フィッシャー:嘆きの詩 |
カルロス・メーナ(CT) リチェルカール・コンソート [フランソワ・フェルナンデス(Vn)、 マヤ・ジンルバーシュタイン(Vn)、 ドメン・マリンチッチ(Va)、 ギズレン・ヴァウターズ(ヴィオール/Vn/Va)、 ライナー・ツィパリング(ヴィオール/チェロ)、 上村かおり(ガンバ)、 ブライアン・フィーハン(テオルボ)、 フランシス・ジャコブ(Org/Cemb)、 フィリップ・ピエルロ(ヴィオール/ディレクター)] 録音:2000年1月、ブラ教会、ベルギー |
| MIR-9913 |
モーツァルト:ピアノ・ソナタ第14番、 ロンドイ短調K.511、 デュポールのメヌエットによる変奏曲、 幻想曲ニ短調K.397/ハ短調K.475 |
アンヌ・ケフェレック(P) 録音:2001年 |
|
||
| MIR-9918 |
D・スカルラッティ チェンバロ・ソナタ集 K535 ニ長調/K3 イ短調,K175 イ短調/K208 イ短調,K54 イ短調/K185 ヘ短調,K248 変ロ長調/K249 変ロ長調,K310 変ロ長調/K299 ニ長調,K484 ニ長調/K162 ホ長調,K199 ハ長調/K145 ニ長調,K141 ニ短調/K531 ホ短調,K177 ニ長調/K492 ニ長調 |
ピエール・アンタイ(Cemb) 録音:2002年 ハールレム ※使用楽器:1720年無名製をモデルに、1999年テューリンゲのユルゲン・アマー複製 |
|
MIR-9920
|
D.スカルラッティ:チェンバロ・ソナタ集Vol.2 フーガ ハ短調K.58 ソナタ集~ヘ短調K.239/変ホ長調K.370 変ホ長調K.371/ホ長調K.135 ホ長調K.215/ホ長調K.216 嬰へ短調K.25/ロ長調K.261/ロ長調K.262 ホ短調K.263/ホ長調K.264/ト長調K.314 ト長調K.259/ト長調K.260/ハ短調K.84 |
ピエール・アンタイ(Cemb) |
| MIR-9930(2CD) |
バッハ:平均律クラヴィーア曲集第1巻 | ピエール・アンタイ(Cemb) 録音:2001年&2002年 ハールレム ※使用楽器:ユルゲン・アンマー製作、1999年(1720年 テューリンゲンの無名氏制作による楽器のコピー) |
| MIR-9931 |
17世紀イタリアとスペインの音楽 マラッツォーリ:「薔薇について」、 ジョヴァンニ・バッティスタ・ヴィターリ:カプリッチォ「イル・モルツァ」、 マラッツォーリ:カンタータ「おお、死すべき定めの者よ」、 マラッツォーリ:チャコーナ、 フアン・ナバス:「草茂る野を統べる薔薇よ」、 ファルコニエーロ:フォリアス、 マラッツォーリ:「ごきげんよう、新しい四月よ」 |
アリアンナ・サバール(S) リチェルカール・コンソート 録音:2002年10月20ー24日、ベルギー、ブラ=シュル=リエンヌ教会 |
| MIR-9941(3CD) ★ |
リスト:巡礼の年(全曲) | ニコラ・アンゲリッシュ(P) 録音:2003年 |
|
||
| MIR-9945 |
バッハ:ゴルトベルク変奏曲 | ピエール・アンタイ(Cemb) 録音:2003年 洗礼派教会、ハーレム、オランダ。使用楽器:ヨンテ・クニフ&アルノ・ペルト制作(2002) |
|
MIR-9955
|
愛の夢 リスト:愛の夢 シューマン:謝肉祭~キアリーナ/ショパン ショパン:夜想曲(遺作) シューマン:火の鳥 クララ・シューマン(リスト編):ひめごと リスト:コンソレーション 第3番 ショパン:練習曲 ハ短調「革命」Op.10-12 メンデルスゾーン:ヴェネツィアの舟歌 ト短調Op.19-6 嬰ヘ短調Op.30-6 リスト:悲しみのゴンドラ 第2番 シューマン:謝肉祭~間奏曲 シューベルト:セレナード メンデルスゾーン:春の歌 シューマン:子供の情景~見知らぬ国と人々から ショパン:夜想曲Op.15-2 ワルツ イ短調(遺作) シューマン:トロイメライ モーツァルト:コンフタティスとラクリモサ リスト:暗い雲 |
ブリジット・エンゲラー(P) |
| MIR-9968 |
ヴィヴァルディ:独唱のための宗教作品集 サルヴェ・レジーナ RV.616 スターバト・マーテル ヘ短調 RV.621 ヴィオラ・ダモーレ協奏曲 ニ短調 FII-2 独唱,ヴィオラ・ダモーレ,弦楽合奏と通奏低音の為の「ニジ・ドミヌス」RV.608 ■ボーナストラック:「ニジ・ドミヌス」の第7曲「父と子、聖霊に栄光あれ」の為の差し替え異稿版 |
カルロス・メーナ(CT) フランソワ・フェルナンデス(ヴィオラ・ダモーレ) フィリップ・ピエルロ(ヴィオラ・ダ・ガンバ) リチェルカール・コンソート |
|
||
|
MIR-9969
|
アントニオ・ベルターリ:ヴァロローゾ(腕のよいヴァイオリニスト) アントニオ・ベルターリ(1605-1669):2、3、5、6声の為のソナタ(7曲)/シャコンヌ レオポルト1世:「天の女王」(ベルターリ作曲:ヴィオール伴奏部) 作曲者不詳(クロムニェジーシュ写本):ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナティナ |
フランソワ・フェルナンデス(Vn) カルロス・メーナ(CT) フィリップ・ピエルロ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)(指) リチェルカール・コンソート 録音:2003年9月21-24日ベルギー、ブラ=スュル=リエンヌ教会 |
|
||
|
MIR-9972
|
ベートーヴェン:珠玉の名曲集 エリーゼのために ゴッド・セイヴ・ザ・キングによる7つの変奏曲 WoO.78 アンダンテ・ファヴォリ WoO.57 ピアノ・ソナタ第14番「月光」 バガテルOp.33-1/Op.119-1/Op.119-3 Op.119-11/ なくした小銭への怒り 創作主題による6つの変奏曲 ヘ長調Op.34 |
アンヌ・ケフェレック(P) |
|
||
| MR-301147 |
グラント・フォスター:ピアノ曲集 ロマンス嬰ハ短調/ロマンス.ハ長調 ピアノ・ソナタ/エレジー ブィドロ/6つの前奏曲/バラード |
グラント・フォスター(P) 録音:2015年9月19-20日/イワキ・オーディトリアム(メルボルン) |
|
||
Copyright (C)2004 WAKUWAKUDO All Rights Reserved. |